2025年08月の記事
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その64): Dublin市内散策(3/)・トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)~College Green(カレッジ・グリーン)
DUBLIN市内の観光は、このアイルランド旅行の初日、旅友Yさんと訪ねた👈️リンクが、残りの旅友・SさんとHさんは、初日のホテル到着が深夜であったため、二人は、この日が初めてのDublin市内観光なのであった。左手には、初日に訪ねたトリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)の正面玄関(Front Squareに面した建物)が現れた。トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)👈️リンクは・創設:1592年、イングランド女王エリザベス1世により設立。・アイルランド最古かつ最も有名な大学であり、現在も国際的な研究拠点。・校舎や広場は17世紀〜19世紀の建築を中心に構成され、学問都市ダブリンの中心地に位置。正面に廻り込んで。Trinity College Front Arch(フロント・アーチ)。ジョージ王朝時代の新古典主義建築(ネオクラシカル)。正面には4本のドーリア式円柱が並び、三角破風(ペディメント)には時計が取り付けられていた。中央には大きな木製アーチ扉(訪問者の出入り口)。この扉の奥には、石畳の中庭「Front Square」が広がっており、キャンベル鐘楼(Campanile)、図書館(Old Library)、そしてケルズの書(Book of Kells)展示室があった。観光客はこの正門から入り、チケット売り場と展示エリアへ向かうのであった。トリニティ・カレッジは1592年創立、アイルランド最古の大学。卒業生には、ジョナサン・スウィフト、オスカー・ワイルド、サミュエル・ベケットそして我が友O氏など著名な人物がいるのであった。トリニティ・カレッジの学内構造案内図(地図の数字とは一致しない)。1.正門・フロントゲート(Front Gate / Regent House Entrance) 位置:カレッジ・グリーン(College Green)に面した南側、キャンパスの主入口 内容・特徴: ・トリニティ・カレッジの象徴的な正面玄関。重厚な石造ファサードに時計塔がある ・上階の「リージェント・ハウス(Regent House)」は、かつて学長の執務室だった ・鉄柵前には、エドマンド・バーク像とオリヴァー・ゴールドスミス像が左右対称に立つ ・観光客の多くがここから入場。書の間(Book of Kells)への入口もこの先にある2.フロント・スクエア(Front Square) 位置:正門をくぐった中心広場 内容・特徴: ・カレッジ内の中核となる石畳の広場。多くの歴史的建築が四方に並ぶ ・学生・観光客が集まる開放的な空間で、芝生と整った動線が特徴 ・中央キャンパナイル(鐘楼)が立つ ・学生の間では「試験前にキャンパナイルの下をくぐると落第する」という迷信がある3.キャンパナイル(Campanile) 位置:Front Squareの中央 内容・特徴: ・高さ約30mの石造鐘楼。1853年にチャールズ・ラニヨン卿の設計で建設 ・建築様式はネオクラシカル。下部はアーチ状で通り抜け可能 ・学内のランドマークであり、写真撮影スポット ・象徴的建築として、時間・伝統・静寂を表す存在4.旧図書館・ロングルーム(Old Library / The Long Room) 位置:Front Squareの南側(正門と向かい合う位置) 内容・特徴: ・ケルズの書(Book of Kells)を展示する最も有名な建物 ・ロングルームは、幅約12m・長さ65m・高さ約15mの2階建てバレルヴォールト空間で、 蔵書20万冊以上 ・アイルランドの文化的至宝として世界的に知られる ・学術・観光両面でトリニティ最大の見どころ5.ニュー・スクエア(New Square) 位置:Old Libraryの北東側(フロントスクエアの東隣) 内容・特徴: ・18世紀後半に整備された第2の中庭(広場) ・四辺を囲むように、学術系建物(特に理系学部やオフィス棟)が並ぶ ・広々とした芝生が広がり、静かな雰囲気 ・キャンパス南東部と理学系施設をつなぐ学術ゾーンの玄関口6.ルブリックス(Rubrics) 位置:Front Square 北側、チャペルの背後(北東側) 内容・特徴: ・トリニティ・カレッジで最も古い現存建築(1710年代) ・赤レンガ造りの長屋風建物で、均整のとれたファサードが特徴 ・かつては学生と教員の住居、現在は研究室・管理部門として使用 ・フロントスクエアにおける「古きトリニティ」の象徴 7.卒業生記念館(Graduates Memorial Building, GMB) 位置:Rubricsの西隣、図書館広場の北端に面する位置 内容・特徴: ・建築:1899年完成、ヴィクトリアン・ゴシック様式 ・学生ディベート協会の本拠: - 「The Phil」(Philosophical Society/哲学協会) - 「The Hist」(Historical Society/歴史協会) ・トリニティの弁論・議論文化の中心 ・彫像や塔屋がある荘厳な外観が特徴8.講堂・ダイニングホール(Public Theatre / Dining Hall) 位置:チャペルの東側(Front Square北東部) 内容・特徴: ・式典・表彰式・招待講演などの公式行事に使用 ・食堂部分はスタッフや公式ゲスト用。天井は高く、歴代学長の肖像画などが並ぶ ・木造梁と歴史的調度品に囲まれた荘厳な雰囲気 ・フロントスクエアの儀礼ともてなしの空間9.ミュージアム・ビルディング(Museum Building) 位置:New Square の南西隅(Library Squareの東隣) 内容・特徴: ・建築:1857年完成、ロマネスク・リヴァイヴァル様式 ・使用学部:建築学、工学、地質学などの拠点 ・外壁:アイルランド産の石灰岩とポルトガル産大理石の装飾 ・内部には見事な柱頭彫刻やタイルモザイクがあり、アイルランドで最も美しい大学建築の 一つとされる10.ダグラス・ハイド・ギャラリー(Douglas Hyde Gallery) 位置:Front Gate(正門)を入って右手すぐ、アートスクール近接 内容・特徴: ・1978年開設の現代美術ギャラリー ・アイルランド内外の現代アーティストによる展示を開催 ・無料公開され、学生・市民・観光客に開かれた芸術空間 ・現代文化と大学の知性の交差点を象徴トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)の全景の航空写真をネットから。特徴と主要建物・広さ 約47エーカー(約19ヘクタール、190,000㎡)、東京ドーム(約4.7万㎡)のおよそ 4個分。・中央広場(Front Square) 真ん中に「キャンパナイル(Campanile, 鐘楼)」がそびえています。トリニティ・カレッジの シンボルです。・右手奥の大きなクラシック建築群 ・図書館広場(Library Square)に面した建物群。 ・オールド・ライブラリー(Old Library) には有名な「ロング・ルーム」や 「ケルズの書(Book of Kells)」が収められています。・緑の芝生の広場 校舎に囲まれて複数の芝生広場があり、学生たちが集う憩いの場です。・南西部のモダン建築 白い屋根の現代的な建物群は、学術施設や管理棟です。・南側(写真下側)に沿って走る通り ダブリン市内を走る路面電車「ルアス(Luas)」のグリーンラインが見え、黄色いトラムが 通過している。詳細案内。ここからは、既にブログにアップ済み👈️リンク ですが、より詳しく説明したいと思います。トリニティ・カレッジ(Trinity College Dublin)正門の手前左側にあったのが、エドマンド・バーク(Edmund Burke, 1729–1797)の像。エドマンド・バークとは:・出身:アイルランド・ダブリン・学歴:トリニティ・カレッジ卒業(1744年入学)・職業:政治家・哲学者・演説家・作家・主な活動: ・イギリス議会で活躍(ホイッグ党) ・アメリカ独立戦争ではアメリカ側に理解を示す ・フランス革命には強く反対し、保守思想の先駆とされる・代表作: ・『フランス革命の省察(Reflections on the Revolution in France)』(1790年) ・近代保守主義の父とされ、後世の政治思想に大きな影響を与えました正面から。左手に書類(もしくは書物)を持ち、理性的知性を象徴。右側の像はオリヴァー・ゴールドスミス(Oliver Goldsmith, 1728?–1774)の銅像。ズームして。・生没年: 約1728年 – 1774年・出身: アイルランド、ロングフォード県(またはウェストミーズ県)・職業: 作家、詩人、劇作家・トリニティとの関係: トリニティ・カレッジの卒業生(1744年入学)・主な作品: 小説『ウェイクフィールドの牧師(The Vicar of Wakefield)』、 詩『田園の僧侶(The Deserted Village)』、戯曲『気まぐれ女房(She Stoops to Conquer)』などゴールドスミス像は本を手に持つ姿勢で、思索的に視線を落としている。これは学識と創造性の象徴であり、詩人・作家としての彼の業績を表現している。一方、エドマンド・バーク像は演説的で前方を指すポーズで、政治・哲学的影響を象徴する と。トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)の構内「フロント・スクエア(Front Square)」から、キャンパスの象徴的建造物であるキャンパナイル(Campanile)を正面に見る。中央の塔:キャンパナイル(Campanile)・名称:Campanile of Trinity College・建立年:1853年・設計者:Sir Charles Lanyon・建築様式:ヴィクトリアン・ネオクラシカル様式・高さ:約30メートル・構造:石造、アーチ型基礎部の上に塔状構造・用途:実際の鐘楼というよりは象徴的な建造物(鐘はあるが時報としては使用されていない)学生の間では、「試験に落ちる」という迷信があり、「試験前にキャンパナイルの下を通ると不合格になる」とされている と。そのため、期末試験前になると、多くの学生がこの塔の下を避けて通る姿が見られるのだ と。 構内「フロント・スクエア(Front Square)」の左・北側に位置する建物。左手前の堂々たる円柱建築は、Exam Hall(試験ホール)、その奥に連なる建物群はChapel(礼拝堂)やDining Hall(食堂)。卒業生記念館・Graduates Memorial Building(GMB)トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)構内のFront Square(フロント・スクエア)北側に位置する壮麗な建物。 内容・特徴: ・建築様式:ヴィクトリア朝ゴシック・リヴァイヴァル様式 ※尖塔状の屋根、石造の装飾、ファサードのリズム感が特徴 ・建築年:1899年完成 ・設計者:Thomas Drew(トマス・ドリュー)Old Library(オールド・ライブラリー、旧図書館)トリニティ・カレッジ・ダブリン(Trinity College Dublin)の構内にある、世界的にも有名な図書館建築であり、観光のハイライト。内容・特徴: ・建築年:1712年着工、1732年完成 ・設計者:Thomas Burgh(同時代の著名建築家) ・建築様式:ジョージ王朝様式(Georgian) ・構造:3階建ての石造建築で、1階はアーケード状主な内部構成: ◾ Book of Kells(ケルズの書)展示室 ・世界的に有名な9世紀の装飾写本 ・アイルランドの文化・宗教・芸術を象徴 ・観光客の最大の目的地のひとつ ◾ The Long Room(ロングルーム) ・2階にある巨大な閲覧室:全長65m、バレル・ヴォールト天井 ・蔵書20万冊以上(主に17〜19世紀の貴重本) ・両側の書架と歴代学者の胸像が並ぶ荘厳な空間象徴性と重要性: ・アイルランド最大の学術図書館の一部 ・「デポジット・ライブラリー」として、アイルランド・英国の全出版物を収蔵 ・映画やゲームでもモデルにされる幻想的な空間(例:『スター・ウォーズ』風の内観に 影響を与えたとされる)講堂・ダイニングホールのうち、試験ホール(Public Theatre / Examination Hall)内容・特徴: ・建築年:1784年竣工 ・建築様式:ネオクラシカル様式(古代ローマ神殿風) ・設計者:サー・ウィリアム・チェンバーズ(Sir William Chambers)建築的特徴: ・ファサード中央には4本のコリント式円柱と三角破風(ペディメント) ・アーチ型の玄関3つ(左右対称) ・上部には大きな窓とバルコニー手すり(balustrade)用途と意義: ・かつての大学公開講義(Public Theatre)の場 ・現在も使用されている主要な試験会場 ・入学式・表彰式など儀礼的な公式行事も行われる ・トリニティの学問と格式の中心的象徴中心に立つ象徴的な建物、キャンパナイル(Campanile)をクローズアップ。建築的要素: ・下層部はアーチ型通路で、通り抜け可能 ・上層部は八角形の鐘楼(オクタゴン)、繊細な石の格子窓 ・ドーム型屋根の上に風向計が載る ・四隅に座す彫像(寓意像)は学問や精神を象徴しているとされる象徴と伝説: ・トリニティ・カレッジの精神的中心・象徴的ランドマーク ・「試験前にキャンパナイルの下を通ると落第する」という学生間の有名なジンクスがある ・入学式、卒業式などで学生や家族が記念撮影を行う定番スポットトリニティ・カレッジ・ダブリンのキャンパナイル(Campanile)上層に置かれた4体の彫像は、建物の象徴性を高めるために配置された寓意像(allegorical figures)です。それぞれはアカデミア(学術)に関係する抽象概念を表しており、以下のように分類されます。 ◾北東角 象徴する概念:Science(科学) ・書物や巻物、望遠鏡などを持って表現されることが多く、「観察と法則性の探求」を象徴。 ◾北西角 象徴する概念:Literature(文学) ・ペンや本を持つ女性像が一般的で、「表現と言語の力」を象徴。詩や演劇、哲学への 敬意を示す。 ◾南東角 象徴する概念:Divinity(神学) ・聖書や十字架を持ち、霊的・倫理的知の追求を表す。大学の歴史的ルーツである 神学部を象徴。 ◾南西角 象徴する概念:Law(法学) ・天秤や律法の書を持ち、「正義と秩序」の原理を象徴。学問における論理とルールの 基盤を表す。この像が象徴する概念はScience(科学) または Medicine(医学) ・杖に巻きつく一匹の蛇は、しばしば治癒・医学・生命の探求を象徴します。 ・医学に限らず、自然科学(biology / physiology)全般を象徴する場合もあります。 ・トリニティ・カレッジでは、この像は伝統的に"Science"(科学)を代表する像と されています。これが、「Literature(文学)」を象徴していると考えられる像。(前回の写真)特徴的な持ち物:・像の右手には、巻物または装飾的な書物を模した細長い物体が握られています。・この形状は古代の書板(タブレット)や詩篇集を表現している可能性があり、書くこと・読む ことの象徴。・衣装はギリシャ風のドレーパリー(長衣)で、静かな威厳を備えた座像です。これが「Law(法学)」を象徴する像特徴的な持ち物・姿勢:・像は左手に、束ねた棒状のもの(ファスケス)のようなものを持っています。・ファスケス(fasces)は、古代ローマにおいて執政官の権威を象徴した「権威と統治」の 道具であり、今日でも法・統治・正義の象徴として多用されます。・右手は膝に置かれ、冷静で威厳ある姿勢。・衣装は重厚なドレーパリーで、厳格な印象を与える構図です。「Divinity(神学)」を象徴する像。特徴的な持ち物:・像は右手を高く掲げて十字架を持っています。・左手には書物(聖書)と思われる物を抱えています。・視線は斜め上、天を仰ぐような姿勢です。旧図書館(Old Library)付近の芝生エリア(Library Square)にあったのがウィリアム・エドワード・ハートポール・レッキー(William Edward Hartpole Lecky, 1838–1903)の像。像の台座には「LECKY」という刻印。レッキーは椅子に座りながら、手には開いた書物を持ち、思索的な姿勢。肩からアカデミックガウンを羽織っており、知識人としての威厳を表現。像の様式は19世紀末〜20世紀初頭の伝統的記念彫刻スタイルで、写実的で穏やかな造形。W. E. H. Lecky・生没年:1838–1903・出身:アイルランド、ダブリン出身・職業:歴史家・哲学者・政治評論家・教育:トリニティ・カレッジ・ダブリン卒業・主な業績: ・『ヨーロッパの道徳の歴史(History of European Morals)』 ・『イングランドにおける合理主義の歴史』 ・宗教、倫理、自由主義政治に関する批評を多く著した・政治活動: ・晩年はイギリス自由党に所属し、1902年には貴族に列せられた。「The Examination Hall(試験ホール)」。・建設年代:18世紀(1780年代)・正面は対称的なファサード(正面構造)を持ち、三角破風(ペディメント)と古典的な オーダーの柱が特徴。・上階の窓下には小さなバルコニー風の装飾(バラスター)があり、格式を感じさせます。・屋根上の小さな塔は換気口(ヴェンティレーター)です。通常は学生の試験会場として使われており、年間を通して重要な大学行事にも利用されていると。ジョージ・サーモン(George Salmon)像。生没年:1819年9月25日 – 1904年1月22日職業・業績:・アイルランドの数学者・神学者。・若いころは純粋数学の研究で知られ、とくに代数学や射影幾何学で名声を得ました。・後年は宗教的関心を深め、アイルランド国教会の聖職者としても活躍。・1888年から1904年までトリニティ・カレッジの学長(Provost)を務めました。 女性入学への反対 ・サーモン学長は、女性のトリニティ・カレッジ入学に強く反対したことで知られています。 ・彼の反対にもかかわらず、彼の死後すぐの1904年に女性の入学が許可されました。 ・皮肉を込めて、「彼が女性の入学を阻止できたのは彼の死までだった」と語られる こともあります と。「Public Theatre(パブリック・シアター)」 ・名称:Public Theatre(別名:The Examination Theatre / College Chapelの向かい) ・所在地:Front Square の東側、Examination Hallのすぐ隣 ・建築様式:ジョージアン様式(Georgian architecture) ・設計者:Sir William Chambers ・完成:18世紀後半(主に1780年代)この建物は、・卒業式や大学の重要式典(トリニティ・カレッジでは「Commencements」)・公的講義(Public Lectures)や演奏会・一部の大学行事での集会所 で使われて来た と。構内にあった案内標識の一つ。英語とアイルランド語(アイルランド・ゲール語)の併記形式で、構内施設の方向を示していた。上から、正門(フロントゲート)宿泊事務所(学生寮オフィス)礼拝堂(チャペル)寮(建物)6〜10号棟学生会館(学生組合) の方向を示していた。Trinity College Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン)構内で提供されている見学ツアーや展示のチケット料金案内。とくに有名な「ケルズの書(Book of Kells)」関連展示のチケットも示されていた。「ケルズの書(Book of Kells)」とは?■ 概要制作年代:おおよそ 800年頃(8〜9世紀)言語:ラテン語内容:新約聖書の4つの福音書(マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ)制作地: スコットランドのアイオナ修道院で着手され、 アイルランドの**ケルズ修道院(County Meath)**で完成したと考えられています。所蔵場所:現在はトリニティ・カレッジ・ダブリンの旧図書館(Old Library)内で、 特設の「Book of Kells Exhibition」として常設展示。 ケルズの書・The Book of Kells👈️リンク写真はネットから。写真をネットから。「ケルズの書」は、紀元800年・8世紀頃に修道士が作成した4つの福音書。その本にはケルトの渦巻き模様や、人、動物などが描かれ、ケルト美術の最高峰と言われ、アイルランドの国宝である装飾写本。聖書、特に福音書をラテン語で記したもので、その装飾の美しさから「世界一美しい本」とも称される。ダブリン大学トリニティ・カレッジ図書館に所蔵されているのだ。「Book of Kells Exhibition」👈️リンク。学内をガイド付きで巡るツアーや「ケルズの書」鑑賞を組み合わせたプランも用意されており、参加すればより深くトリニティ・カレッジの魅力に触れられるのであったが・・・。ダブリン市内中心部のトリニティ・カレッジ正門(Front Gate)前の風景。ダブリンの路面電車「Luas(ルアス)」。紫がかった銀色 → Luas Green Line(緑線)。写真左手の建物には「TOURISM OFFICE(観光案内所)」の表示が見えた。ここはダブリンの「Visit Dublin」オフィスがあるエリアで、観光パンフレットや地図をもらえるのであった。アイルランドの作曲家として知られる「トマス・ムーア(Thomas Moore, 1779–1852)」の像。アイルランドの民族的アイデンティティを詩と歌で表現したことで、国民的詩人とも称されている作曲家 と。1795年にダブリン大学トリニティ・カレッジに入学し、母親の意向に従って法学を学んだ と。ムーアは片手を高く掲げ、もう一方の手は胸にあてるポーズを取っており、詩人または演説者としての姿を象徴的に表現していた。銅像のスタイルは19世紀風の衣装(フロックコート、タイツ)を再現。そして右側にあったのが「旧アイルランド銀行本店(Bank of Ireland, College Green)」。建設年 1729年(18世紀前半)建築様式 新古典主義建築(Neoclassical)設計者 Edward Lovett Pearce ほか用途 現在は一部が銀行として使用されているが、歴史的建築物として公開部分もある と。アイルランド議会議事堂(旧用途)この建物はもともと、アイルランド王国の議会(Parliament of Ireland)の議事堂として使用されていた と。世界初の特別に設計された議会用建築物(Purpose-built Parliament House)として知られる。1801年、イギリスとの合同法(Act of Union)によってアイルランド議会が解散されると、建物はアイルランド銀行に売却されたのだ と。Trinity College Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン)正門(Front Gate) の正面を振り返って。今回参加できなかった学友Oさんからの依頼が、『1年間留学していたこのTrinity College Dublin(トリニティ・カレッジ・ダブリン)正門(Front Gate)を背景に路面電車Luas(ルアス)の写真を土産に欲しい』とのことで撮影したのであった。移動して。ダブリン市内の装飾的街灯柱(ヴィクトリア朝様式のガス灯柱)。イルカ型の彫刻装飾(実際は神話的海獣)が特徴的なもの。背後にはトマス・ムーア像の台座の一部が。そしてここにもトマス・ムーア(Thomas Moore, 1779–1852)像が。この像はトリニティ・カレッジの卒業生像ではなくアイルランドの詩人としての市民的顕彰像なのであろう。台座には「Moore」とのみ刻まれていた。ダブリン中心部のO'Connell Street(オコンネル・ストリート)南端から北方向を見る。手前は歩道とLuas(ルアス)・グリーンラインの軌道が並走しており、ダブリン市内でも最も賑やかな大通りの一つ。ダブリンのO'Connell Street(オコンネル・ストリート)を南方向(川方面)から北方向(市街中心)に向かって見た光景。ここはダブリンの目抜き通りであり、観光・交通の中心地。121m高さのThe Spire(スパイア)とオコンネル像(Daniel O’Connell Statue)が見えた。左の緑の旗は「Ireland Green Flag」。アイルランド海軍のジャック。ジャックとは船の舳先につける船首旗の事であり、正しくはユニオン・フラッグ(Union Flag)と言うと。ダブリン中心部のオコンネル橋(O'Connell Bridge)南側から北方向を見る。オコンネル橋はダブリンを南北に分けるリフィー川に架かる橋。特徴的なのは、「幅より長さが短い橋」としても知られている と(幅約50m、長さ45mほど)。ズームして。ダブリンの象徴的なオコンネル通り(O'Connell Street)とそこに建つダニエル・オコンネル像、スパイア(The Spire)がほぼ一直線に並んで見える場所なのであった。ダブリン市街を東西に貫流し、ダブリン湾へ流れ込む主要河川・リフィー川(River Liffey)とその下流に架かるButt Bridge(バット・ブリッジ)を見る。Butt Bridge は鉄道の Loopline Bridge のすぐ隣に位置します。ループライン橋はダブリン郊外からの通勤電車(DARTやIntercity)が通るアーチ型の鉄道橋です。Butt Bridge はもともと1880年に開通し、1932年に再建されました。橋の名は、アイルランドの政治家 Isaac Butt(アイザック・バット) に由来しています。アイルランドの政治家・弁護士・オラトリスト(雄弁家)である ダニエル・オコンネル(Daniel O'Connell, 1775–1847)像を再びズームして。写真のように、しばしば頭上にカモメが留まっているのも「ダブリンらしい」光景なのであった。リフィー川(River Liffey)に架かるButt Bridge(バット橋)とその先にLoopline Bridge(ループライン鉄道橋)を見る。Butt Bridge(バット橋)・開通:1879年(現行の橋は1932年再建)・名前の由来:第3代アルタモント侯爵(William Butt)・通る道路:R802・自動車・歩行者・Luasトラム(東側トラック)も利用Loopline Bridge(ループライン鉄道橋)・建設:1891年・設計:ジョージ・ウィルキンソン(鉄道建築家)・役割:ダブリンのコンノリー駅(Connolly Station)とパールマウント駅を結ぶ鉄道路線の一部・特徴:鋼鉄の格子梁構造で、川をまたぐ低めの橋・旅客列車が頻繁に通過しますオコンネル橋を渡り直ぐに右折してリフイー川に沿ってR105を下流方向に進む。オコンネル橋を振り返って。三連のアーチ構造で石造の親柱には装飾の彫刻があった。左手に見える高い建物は「O'Connell Bridge House(オコンネル・ブリッジ・ハウス)」。現在の橋は 1880年に再建(旧称は Carlisle Bridge)。名の由来はダニエル・オコンネル(Daniel O'Connell)に由来し、橋の南端には彼の大きな像があるのであった。Rosie Hackett Bridge(ロージー・ハケット橋)を見る。ダブリン中心部、リフィー川を横断、アビー通り下(Abbey St Lower)とバーチャー通り(Bachelors Walk)を結ぶ。2014年5月20日開通の比較的新しい橋。労働運動家・1916年蜂起にも参加した女性 Rosie Hackett(ロージー・ハケット) にちなんで命名。Rosie Hackett Bridge(ロージー・ハケット橋)を正面から。中央に見えるのは Luas(ルアス)グリーンラインの路面電車(Green Line)。この橋は、自動車の通行は限定的(バスとトラム中心)で、主にLuas Green Lineのトラム軌道と歩道から構成されており、2014年に開通した比較的新しいインフラ。Loopline Bridge(ループライン橋)。・アイルランド語名:Droichead na Loice・建設:1891年完成・用途:鉄道専用橋(Irish Rail / Iarnród Éireann のダブリン通過路線)・構造:鉄製のトラス橋(格子状の梁が特徴的)・所在地:リフィー川上、カスタムハウスとタラ・ストリート駅の間左奥に見えたのが「The Custom House(カスタム・ハウス)」の緑のドームLoopline Bridge(ループライン橋)を斜めから。橋の側面が「X」形状の鉄骨構造で覆われており、Loopline Bridgeの特徴そのもの。写真中央部に見える丸い装飾柱は、Loopline Bridge特有の意匠で、かつてのDublin & Drogheda Railway Companyの「D」のエンブレムがデザインされている と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.31
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その63): Dublin市内散策(2/)・O'Connell Street Upper-2
O'Connell St (オコンネル通り)からLUASトラム(路面電車)を見る。色はシルバーに黄のライン(これはグリーンラインの車両)LUASはダブリン市内を走る電車で、現在2路線(Red LineとGreen Line)があるのだ。観光にもビジネスにも便利な交通手段。行き先表示には「Brides Glen」とあり、南方面の終点行き。路線は2つ「Green Line」と「Red Line」がある。An PostーGeneral Post Office(GPO)・中央郵便局の屋上に立つ彫像。この建物の屋上正面(ペディメントの上)には、3体の古典的彫像が配されていた。正面から左:マーキュリー(Mercury)商業・通信・旅行の神。郵便と通じる。杖(カドゥケウス)を持つ。中央:ヒベルニア(Hibernia)アイルランドの擬人化像。盾と槍を持ち、守護の象徴。右:フィデス(Fides)忠誠・信義の象徴。古代ローマの徳の女神。TATTOO・タトゥースタジオ(刺青店)の店舗。様々なタトゥーのデザイン原画が多数貼られていた。多くの図案が展示されていた。図案例として: ・ケルト模様(Celtic Knotやトリケトラ Triquetra) ・生命の樹(Tree of Life) ・蝶や花、動物など ・目、ハート、トカゲ、ドクロなどのモチーフ ・ポートレート風・手描き風のアートもありアイルランドではタトゥーは近年とても人気があり、伝統的ケルト模様を取り入れたデザインが特に人気である と。ダブリンの中心部にある「ザ・スパイア(The Spire)」を再び。・正式名称:Monument of Light(光の記念碑)・通称:The Spire(スパイア)、The Needle(針)とも呼ばれる・高さ:120メートル(世界最大級のステンレス製モニュメント)・完成:2003年・設計者:Ian Ritchie Architects(英国)・場所:ダブリン市中心部・オコンネル通り(O’Connell Street)の中央 旧ネルソン柱があった場所(IRAにより1966年に破壊された)・素材:鏡面仕上げのステンレススチール特徴: ・下部は直径3メートル、上部は直径15センチに細くなるテーパー形状 ・夜間は先端が発光し、ダブリン市内のランドマークとなる ・雲に溶け込むように見える姿が印象的下部は直径3メートル と。An PostーGeneral Post Office(GPO)・中央郵便局を背景にしたライトアップをネットから。ダブリン中心部のO'Connell Street(オコンネル通り)沿いにあるフランシスコ会修道士・セオバルド・マシュー神父(Father Theobald Mathew)の像。ズームして。名前:Theobald Mathew(セオバルド・マシュー、1790–1856)職業:アイルランドのカトリック司祭・フランシスコ会修道士功績: ・禁酒運動(Temperance Movement)の指導者として有名。 ・1838年にコーク市で禁酒誓約運動(Total Abstinence Society)を開始し、数百万人の アイルランド人が「禁酒の誓い(pledge)」を結んだ。 ・「Apostle of Temperance(禁酒の使徒)」と呼ばれた。 ・像の設置:ダブリン市のオコンネル通り中央分離帯の北側に設置移動して。アイルランドの社会改革運動や宗教指導者の影響力を象徴するランドマーク。この像は、明らかに「指導者」または「布教者(説教者)」のポーズをとっている。右手は神や真理の象徴として空を指し、左手は地上の人々に向けた慈愛や導きの表現である と。ダブリン市内を走る2階建て(上部は屋根なし=オープントップバス)の観光用の「BIG BUS(ビッグ・バス)」。「Hop-On Hop-Off(乗り降り自由)」の観光バス。主要観光地で自由に乗り降り可能。えんじ色とクリーム色のツートンカラー、側面に「BIG BUS.COM」の大きな文字。車内には多言語対応の音声ガイドあり(日本語も選択可)ヘッドホンを通じて、ダブリンの歴史や建築、人物などを解説してくれるのだ と。「GPO(General Post Office/中央郵便局)」の正面ファサードを見上げて。建築年:1814年完成建築様式:新古典主義(Neoclassical) ・写真に見える柱は、古代ギリシャ・ローマ建築に基づいたコリント式の円柱 (柱頭はアカンサスの葉で装飾) ・正面の三角破風(ペディメント)と列柱(ポルチコ)が特徴とのこと。中央郵便局(General Post Office, GPO)正面中央出入口。アーチの上には、円形の時計(アナログ時計)が。時計の上には英国王室の紋章(王冠とライオン、ユニコーン)があしらわれていた。これは、GPOが1814年にイギリス統治下で建てられた建物であることの名残、現在もこの意匠は残されており、歴史的建築物の一部として保護されている と。オコンネル・ストリート(O’Connell Street)に面した「Clerys(クレリーズ)」百貨店。・創業:1853年(「The New Mart」として開業、後にClerysに改名)・所在地:O’Connell Street Lower, Dublin 1・アイルランドの最も歴史あるデパートの一つ。アイルランドの労働運動家・社会主義者として知られる ジム・ラーキン(Jim Larkin) の彫像。労働運動の指導者:・1909年にアイルランド交通労働組合(ITGWU)を創設。・1913年の「ダブリン・ロックアウト(Dublin Lockout)」という歴史的な労働争議を主導。社会正義と連帯の象徴:・労働者階級の権利向上を求め、ストライキや演説で市民を鼓舞。・「労働者に教育を!平和を!団結を!」(Educate, Agitate, Organise)という スローガンでも有名 と。この像の背後には、先ほどの「Clerys百貨店」が見えていた。つまりこの像は、ダブリン市民生活の中心における「労働の声」として、極めて象徴的な場所に立っているのであった。中央に見えたのは、ジョン・グレイ記念像(John Gray Monument)。サー・ジョン・グレイ(Sir John Gray, 1815–1875)は政治家、新聞編集者、ダブリンの給水整備に尽力。ダブリン市民に清潔な水を届けるため、Vartry貯水池プロジェクトを推進し、都市衛生に貢献。背景中央の円塔のある建物は、「Imperial Hotel」として知られていた(現:ショッピング施設などに転用)。Sir John Gray(サー・ジョン・グレイ、1815年–1875年)は、アイルランドの医師・新聞経営者・政治家として知られ、特にダブリン市への清潔な水の供給を実現した功績によって称えられています。ズームして。ダブリンの近代水道整備(Vartry Water Scheme)ダブリン市では19世紀前半まで安全な水の供給が困難であり、コレラやチフスがしばしば流行していた。ジョン・グレイはダブリン市議会のDublin Corporation Water Works Committee(ダブリン水道事業委員会)の議長を務め、ヴァートリー湖(Vartry Reservoir)からの水を引く水道計画を主導した。1863年10月1日に水道が開通。このプロジェクトは、近代都市インフラとして画期的な成功例と評価され、今日のダブリンの水道供給の原型となっている。グレイはその尽力によって、「ダブリンに清潔な水をもたらした人物」として市民の間で広く称賛されている と。「ERECTED BY PUBLIC SUBSCRIPTION TO SIR JOHN GRAY, KNT. MD. JP PROPRIETOR OF THE FREEMAN’S JOURNAL A CITIZEN OF DUBLIN CITY CHAIRMAN OF THE DUBLIN CORPORATION WATER WORKS COMMITTEE TO WHOSE EXERTIONS THE CITY IS PRIMARILY INDEBTED FOR THE INTRODUCTION OF THE VARTRY WATER SUPPLY INAUGURATED 1st OCTOBER 1863 DIED APRIL 9th 1875」【公共の寄付により建立された サー・ジョン・グレイ卿 医学博士・治安判事へ 『フリーマンズ・ジャーナル』新聞社の経営者 ダブリン市の市民 ダブリン市水道事業委員会 議長 その尽力により この市は主として ヴァートリー水道の導入を得た 1863年10月1日 開通 1875年4月9日 没】 William Smith O'Brien(ウィリアム・スミス・オブライエン)像左奥の緑のドーム屋根の建物は旧「ナショナル・ウォール・バンク」。腕を組むWilliam Smith O'Brien 。・アイルランドの政治家・民族主義者(1803–1864)・1848年に「ヤング・アイルランド」運動を指導し、反乱(Young Irelander Rebellion)を 起こした・反乱失敗後に逮捕され、タスマニアへ流刑となるも、後に恩赦で帰国。・議会制の枠内でアイルランド独立を目指した穏健派の象徴的存在。Daniel O'Connell Monument(ダニエル・オコンネル記念碑)を後方から。・設置年:1882年完成・場所:ダブリン中心部、オコンネル橋北詰(オコンネル通りの起点)・作者:John Henry Foley(彫刻家)、死後はThomas Brockが完成・高さ:約12メートル以上近づいて。最上部:ダニエル・オコンネル像(マント姿、右手に巻物)中段のレリーフ帯:ダブリン市民など、多くの支持者の姿の浮き彫り(オコンネルの社会的支持を表現)下段の4人の女性像:アイルランドの4州を象徴(Ulster, Munster, Leinster, Connacht)台座正面の銘板:Daniel O'Connell”と刻まれている廻り込んで。・人物:ダニエル・オコンネル(Daniel O'Connell)・服装:マントを羽織り、手には巻物(憲法・請願書を象徴)・姿勢:俯きながら威厳ある表情で群衆を見下ろす ・非暴力の政治運動と道徳的指導力を象徴中央の浮き彫り(レリーフ)部分・登場人物:さまざまな市民階層の男女(農民・商人・聖職者・兵士など)・中心の女性像: ・片手を掲げて人々を導く姿 ・アイルランドの擬人化(エリン女神)とも解釈される意味:オコンネルが民衆と共に歩んだ「平和的改革」の精神を表現建物との位置関係 ・左奥:銅緑色の屋根がある建物(貯蓄銀行旧館) ・中央奥:Sir John Gray像がある角の建物ズームして。左手:胸に置き、忠誠心や誠実さを象徴右手:書物を握っており、法や知識を象徴衣装:クラシカルなコートとショール。威厳ある姿勢中央の浮き彫り(レリーフ)部分を追う。アイルランドの各州を象徴する人物像と、群像(民衆)を配置。オコンネル・モニュメント(Daniel O'Connell Monument)の下部に配置された4体の有翼女性像のうちの2体。正面が「Winged Victory(勝利の女神)」。右手が「Justice(正義)」を象徴すると解釈されている像。「ハーフペニー橋(Ha'penny Bridge)」を中心にしたリフィー川(River Liffey)沿いの風景。中央の橋がハーフペニー橋(Ha'penny Bridge)。 ・1816年に完成した鋳鉄製の歩行者専用橋。もともと通行料が「ハーフペニー(半ペニー)」 だったためこの名前が付けられた。 ・ダブリンの象徴的なランドマークで、多くの観光客が写真を撮る人気スポット。背景の建物群: ・リフィー川北岸と南岸の歴史的な建物や店舗が並んでおり、ダブリンの街並みの雰囲気を よく表していた。 ・特に左側奥には、クリスチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)の尖塔が見えた。 ・右側奥には、セント・オードンズ教会(St. Audoen's Church)の尖塔も見えた。The National Wax Museum Plus・国立蝋人形館。右面のスーパーマン像を含め、同じビルの他の窓にもバットマンやその他のキャラクターの人形が配置されているのであった。ダブリン中心部にあるビルの上階窓辺に設置された「スーパーマンの立体像」。ダブリン市内中心部、オコンネル・ストリート(O'Connell Street)とヘンリー・ストリート(Henry Street)の交差点近くの歴史的ビルの上階窓辺に。通りに面した建物の2階部分の窓から突き出すように設置。この建物はかつて「Ned's of Town」というバーやカフェ、あるいは観光客向けの展示・ショップなどに利用されており、装飾としてこのようなフィギュアが配置されていた。現在も定期的にデコレーションが変わるユニークなスポットである と。左から順に:1.死神(グリム・リーパー / Grim Reaper) ・黒いローブを着て、右手に大鎌(Scythe)を持った姿。 ・死の象徴的キャラクターで、ハロウィンやホラー系装飾で頻出。2.ドラキュラ伯爵(Count Dracula) ・吸血鬼の典型的な姿:黒いスーツに赤裏地のマント、白塗りの顔と牙。 ・ゴシック建築との相性も良く、建物の雰囲気を引き立てています。3.バットマン(Batman) ・アメリカのDCコミックスに登場するヒーロー。 ・グレーと黒のクラシックなスーツ、黄色いユーティリティベルト。 ・前回のスーパーマン像と同様、アメリカン・ポップカルチャーの象徴。 「Bank of Ireland 本店(旧アイルランド議会議事堂)」が右手前方に。・建築様式:ジョージアン様式とネオクラシカル様式の融合・ファサード(正面): ・6本のコリント式円柱 ・上部のペディメント(切妻)には彫刻装飾と3体の像(女神像) ・中央ドア:訪問者用の入口(かつての議場ホールへの導入路) ・左翼・右翼:半円状のウィングを持つ優雅な対称構造正面から3体の像(女神像)を。以下3枚は5月30日に撮った写真。中央 像の名称:Hibernia(ハイバーニア) 象徴する理念:アイルランドの擬人化 特徴・持ち物:槍、盾(またはハープ) 解説:「Hibernia」は古代ローマでのアイルランドの呼称。女性像は国家の精神を体現し、 槍は守護、盾は誇りまたはハープによって文化を表す。堂々たる立ち姿で建物の中心に 置かれている。向かって左(西) 像の名称:Commerce(商業) 象徴する理念:交易・繁栄・経済活動 特徴・持ち物:商業の杖(カドゥケウス)、コイン、貨物など 解説:アイルランド経済の発展や国際貿易の重要性を象徴。カドゥケウス(2匹の蛇と翼の杖)は 伝統的に商業と交渉の象徴。向かって右(東) 像の名称:Justice(正義) 象徴する理念:法の支配、公平性、国家の秩序 特徴・持ち物:剣、天秤(この像では剣のみが明確)解説:剣は法の執行力を、天秤は公平な判断を象徴。司法制度の中立性と国家の安定を示す。 視線を前方に据え、威厳を保つ姿勢で表現される。そしてトーマス・ムーア(Thomas Moore)の銅像。・人物名:Thomas Moore(トーマス・ムーア)・職業:詩人・作曲家・歌手・生没年:1779年 – 1852年・銅像の位置:ダブリン市内、トリニティ・カレッジ正門近く(College Green)・像の特徴: ・ムーアはクローク(マント)を羽織り、楽譜の如き書類を持つ。 ・台座に "MOORE" とのみ刻まれています。 非常にシンプルな表記で、ごく控えめな銘文。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.30
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その62): Killarney~Dublinへ戻る、そしてDublin市内散策(1/)・O'Connell Street Upper-1
この日は6月5日(木)、アイルランド旅行7日目。アイルランドの西部地区、西海岸の観光を終わり首都ダブリンに戻る日。時間は7:55。2泊した「Flesk River Apartments Killarney」をチェックアウト。 ズームして。我々が利用したレンタカーの写真を記念に。BMW(ビー・エム・ダブリュー、ベー・エム・ヴェー、ドイツ語: Bayerische Motoren Werke AG」 は、ドイツのバイエルン州ミュンヘンを拠点とする自動車。エンジンメーカーでもあり、ドイツのプレミアムブランド御三家の1つ。ロゴマークは、黒く縁取った円に白抜きの「BMW」を配し、中央の円の中を十字によって4等分し、点対称に青と白とに塗り分けたデザイン。アイルランドで車は日本と同じの左側通行なので、このレンタカーは右ハンドルで日本と同じ。ナンバー「231-D-40974」の構成をネットで調べて見ました。YYX-CCC-NNNNNでは下記の如くであると。項目 内容 例(231-D-40974)YYX 登録年+半期コード(1月〜6月なら"1"、7月〜12月なら"2") 231C 登録地コード(地域略号) D(ダブリン)NNNNN 連番(その年・地域での登録順) 40974よって●231:2023年・前半期に登録 ・23 = 西暦2023年 ・1 = 1月~6月に登録された車両 以前は「12」(2012年)などで始まるのみで、年に1回の更新であった。 その後、2013年から、年2回の更新制(前半=1、後半=2)を導入●D = ダブリン(Dublin)で登録 アイルランド各地には地域コードがあります。例: D = Dublin(ダブリン) G = Galway(ゴールウェイ) C = Cork(コーク) L = Limerick(リムリック) WD = Waterford(ウォーターフォード)●40974 = その地域での登録番号(連番) ダブリン地域での2023年上半期に登録された40,974台目という意味。●プレート上の補足情報: BAILE ÁTHA CLIATH:ダブリンのアイルランド語表記(英語名:Dublin) 点線の◯:ヨーロッパ連合(EU)シンボルと国コード、12個の金色の星が円形に並び、 統一と協調を象徴。 「12」は西洋文化において調和・完全性・円満を象徴する象徴的な数字。 IRL:国コード(アイルランド) JDonohueBMW.ie:販売ディーラーのドメイン(ここではBMWの販売店)アイルランド・ダブリンに来て最初に宿泊したホテルがこの日の宿泊ホテル。ひたすら北東に向かってダブリンへとR877を北上する。前日の最後に訪ねステンドグラスの美しさを堪能したた「St Mary’s Cathedral」とも今生の別れ。 N22に入り、Lemnaguilla・レムナギーラに向かって進む。右手には羊の牧場が拡がっていた。N23に入る。右手にあったのが「Kerry Airport・ケリー・エアポート」 。Kerry Airport(ケリー空港)は、アイルランドのケリー県ファランフォーにある国際空港。通称はファランフォー空港。県都トラリーの南東約15kmに位置する。「Castleisland」の手前でN21に入る。 この日も空いている国道N21。アイルランド南西部の都市・Luimneach(リムリック)に向かって進む。ひたすら続く田園風景。ケリー県とリムリック県との県境がこの先に。Abbeyfeale・アビーフェールの街に入る。アビーフェール(アイルランド語: Mainistir na Féile 、「フェールの修道院」の意)は、アイルランドのリムリック州にある歴史的な市場町で、ケリー州との境界付近にあった。町はリムリックからトラリーに向かうN21道路沿いにあり、ニューカッスル・ウェストの南西約21キロメートル(13マイル) 、リストウェルの南東約16キロメートル(10マイル) 、トラリー の北東約38キロメートル(24マイル)に位置する。 Abbeyfeale(アビーフィール)の街中・メインストリートの横にあったこの像は、「ウィリアム・オブライエン(William O'Brien)の記念像」と。地元住民の土地保有の権利を擁護し、農民の生活改善に尽力した功績を称えるものと。オブライエンは1890年代にこの地域の貧困農民を支援し、イギリス政府と交渉して土地を買い取らせ、農民へ売り渡す「土地購入計画(Land Purchase Acts)」を推進したのだと。 先ほどのウィリアム・オブライエン像があるThe Square(中央広場)のすぐ先を。Ringmoylan・リングモイラン手前の緑あふれる田園風景。そして、2日前に訪ねたAdareの街まで戻る。この先を右折するとメインストリートへ。駐車所に入り一時休憩。Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)が左手に。Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)内に設置されたノルマン騎士と兵士のジオラマ展示。そして暫しの散策。先日に訪ねた「Trinitarian Abbey」を「Adare Heritage Centre」側から見る。 ケルト十字(Celtic Cross)を冠した記念碑・戦没者慰霊碑(War Memorial)を再び。正式名称はAdare War Memorial Cross(アデア戦争記念十字)と。第一次世界大戦(1914–1918)で戦死したアデア出身の兵士たち、後に第二次世界大戦(1939–1945)の戦没者名も加えられた と。「Trinitarian Abbey」を西側から再び。Adare War Memorial Cross(アデア戦争記念十字)越しに。引き返して。北側部分にあたる構造の一部を。聖心のイエス像(Sacred Heart of Jesus)。背後の建物は、修道院敷地内に後世建てられた20世紀の施設棟か?そしてM20を走りLimerickを通過し、M7をひたすらダブリンに向かって北西を車を進めた。青空も見えて来た。Doonane・ドゥーネインの村には風力発電装置が数機。そしてM7からN7へ。Naas(ナース)方面およびDublin(ダブリン)への案内標識。M7(Motorway 7)はアイルランド南西部のリムリック(Limerick)と首都ダブリン(Dublin)を結ぶ主要幹線道路。中央分離帯と6車線の構造になり、ダブリン寄りの交通量の多い区間に入った。そして4時間弱で、この日のホテル「Maldron Hotel Parnell Square・マルドロン ホテル パーネル スクエア 」に到着したのであった。全ての荷物をレンタカーから降ろし、Yさんと二人でレンタカーの返却に向かう。無事にレンタカー屋に到着。走行距離は約1300km。GPS電波の強度不足によるナビの不調以外は何事もなく無事に返却できたことに安堵!!運転手のYさん、Hさん 安全運転、お疲れ様でした。そしてホテルに徒歩で戻り、部屋で40分ほどの暫しの休憩後にダブリン市内の散策に4人で。まだまだ合計300歳の旅友は元気なのであった。ホテルからリフィー川に向かってO'Connell street Upper(オコネル・ストリート・アッパー)を歩く。今回の旅友のHさん、Sさんは翌日早朝便でアイルランド離れる予定であり、この日が最後のアイルランド・ダブリン観光なのであった。O'Connell street Upper(オコネル・ストリート・アッパー)沿いにあったFlanagan’s Restaurant & Bar(フラナガンズ)で遅い昼食を。早速、ビール、ワインで無事にDUBLINに戻って来られたことを4人で乾杯。そして私も昼食を。Hさんは、フィッシュ・アンド・チップス(fish-and-chips)を注文。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.29
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その61):St Mary’s Cathedral・カトリック大聖堂
そしてこの日の最後に、St Mary’s Cathedral・カトリック大聖堂を訪ねた。所在地: Killarney, County Kerry, Ireland アイルランド・ケリー州の都市キラーニー(Killarney)に位置。宗派: カトリック教会(Roman Catholic)設計者: Augustus Welby Northmore Pugin(ゴシック・リバイバル建築の代表的建築家)建設期間: 1842年着工(19世紀中盤)外観の主塔(スパイア)が空に突き出るように聳えており、典型的な尖塔型ゴシック建築のデザイン。大きな縦長のランセット窓(細長い尖頭アーチの窓)が前面に並ぶ。左側に写る巨大な針葉樹(恐らくセコイア類)がランドマークのように寄り添っている。ファサードのバラ窓(ローズウィンドウ)が確認でき、バットレス(控え壁)も含めて縦方向の強調が印象的。両脇のミニスパイア付きの塔や縦長窓の反復性から、ゴシック・リバイバルの典型スタイルを継承している。教会堂の両翼(側廊)と後方のトランセプト(翼廊)もはっきり見える構図で、ラテン十字型平面(クロス型)の構成がわかる。St. Mary's Cathedral(聖マリア大聖堂)を北西側(または北側)から仰ぎ見るアングルで。高くそびえる尖塔は高さ約86メートルで、キラーニーのランドマークとなっている。塔基部には4連の鐘楼窓(louvered belfry openings)がある と。ゴシック建築を象徴する縦長の尖頭アーチ窓・ランセット窓で、内部のステンドグラスがここに設置されているのだ。上空からの写真をネットから。建物全体が十字架型(クルシフォーム)の平面構造になっていることも、垂直性と対称性の統一美を示している。Mary's Cathedral(聖マリア大聖堂 の内陣(chancel)東側にあるステンドグラス群。①上部:バラ窓(Rose Window) ・形式:放射状に花びらのように開いた「円形のステンドグラス」。 ・象徴: ・中央の光を放つ様子は 神の栄光 や 天上のエルサレム を象徴。 ・バラは 聖母マリアの象徴 ともされます(「Mystical Rose」=神秘の薔薇)。 ・様式:このバラ窓は、フランスのゴシック様式に倣いながらも、19世紀末のアイルランド的な 装飾(鮮やかな色調と幾何学的花弁)を備えています。 ・図像:中央に描かれているのは、旗を持つ子羊(Agnus Dei)。 ・意味: ・中央:神の子羊(Agnus Dei) ・中央に描かれているのは、旗を持つ子羊(Agnus Dei)。 ・「神の子羊」は、イエス・キリストの犠牲と贖いの象徴。 ・白い子羊が十字旗を掲げている姿は、「世の罪を取り除く神の子羊」としての キリストを示す。 ・この図像はヨハネの黙示録(Rev. 5:6)や洗礼者ヨハネの言葉(ヨハネ1:29)に 基づいている。 ・放射状の12枚の細長いパネル:天使(Seraphim)たち ・各パネルには、赤い翼と白い衣をまとった天使たちが描かれています。 ・各天使は祈りや楽器、巻物などを持ち、神への賛美や祈願を表現しているように 見えます。 ・12という数は、新約の12使徒や旧約のイスラエル12部族に対応し、教会の普遍性と 完全性を象徴しています。 ・外周:装飾的なフローラル型のパネル(8枚) ・これらのパネルは、幾何学的な花模様(quatrefoil)や星形で構成されており、 抽象的な天上の秩序を示しています。 ・青・赤・金の配色は、聖性(青)、犠牲(赤)、神の栄光(金)を表しています。 ・8という数は復活や永遠を象徴し、バプテスマ(洗礼)後の新生とも関係しています。② 下部:縦長の3連ステンドグラス ・典型的なランセット窓(lancet windows)と呼ばれる、ゴシック建築の象徴的な 尖頭アーチ型窓。 ・中央の窓が最も大きく、キリストの姿が確認できます。 ・各窓は3層に区切られており、次のような内容が描かれている可能性があります 窓位置 推定される図像 主な意味 左側 預言者や聖人 旧約の預言、教会の基礎 中央 イエス・キリストの受難・復活 救いの中心 右側 使徒や聖母マリア 教会の創設、信仰の模範St Mary’s Cathedral(キラーニー)の内陣にある三連ランセット窓の中央パネルの下部に位置する場面。・上方の人物:白い衣をまとい、右手を挙げ、左手には十字の旗(復活の象徴)を持つ人物 → これは復活のキリストです。・下方の人物:膝をついて、キリストの傷に触れている → これは「トマスの不信(Incredulity of Thomas)」の場面です。「トマスの不信」とは?新約聖書『ヨハネによる福音書 20章24〜29節』トマスは、復活したイエスに会えなかったため、「私はその手に釘の跡を見、この指をその釘跡に入れてみなければ、決して信じない」と言った。八日後、イエスは現れ、トマスに「あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい」と言い、トマスは信じて跪いた。この場面は、信仰とは「見ずに信じること」を示す象徴的なエピソードです。窓は ゴシック様式の三連窓で、上部に三つの円形装飾(ローズウィンドウ様)を持ち、下部に碑文と紋章が見えます。中央2枚のランセット(縦長)部分に人物が描かれ、左右のランセットには天使のような姿が。・上部円形パネル 最上部の丸窓には3人の人物が描かれています。 左右に白衣の人物、中央に冠を戴いた人物(キリストまたは天の父)と思われ、 聖三位一体を象徴している可能性があります。 下に見える2つの小さな円形パネルは、六芒星または花模様で装飾的意匠に見えます。・中央ランセット2面(人物が描かれていた)。 この写真はネットから。・左の中央パネル ・青と赤の衣をまとった人物が、ひざまずいて礼拝しています(おそらく聖母マリア 大天使ガブリエル)。 ・「受胎告知」の場面と考えられます。・右の中央パネル ・赤い衣と巻物を持った人物(おそらく預言者イザヤまたは聖ヨセフ)。 ・靴を脱いで立っているようにも見え、神殿での啓示または聖家族の一場面かもしれません。この窓は、2つのランセット(縦長パネル)と、上部に四葉型の小窓(クアトレフォイル)を持つ構成。・上部小窓(クアトレフォイル) 花模様と星を組み合わせたような幾何学的装飾で、象徴的・装飾的意味合いが強いです。・左側パネル 上部には白と青の衣をまとう女性が座して幼児を抱いています。 → 聖母マリアと幼子イエスを示す伝統的な描写です。 下部には緑の衣をまとう人物(跪いている)が祈りを捧げている様子。 → 女性聖人、または寄進者(ドナー)として描かれた信徒の可能性もあります。 解釈: これは「玉座の聖母子(The Virgin and Child Enthroned)」という図像です。 聖母子の慈愛と、信仰を捧げる人間の姿が対照的に描かれています。・右側パネル 頭に司教冠(ミトラ)を戴いた人物が立っています。 手に司牧の杖(クロシエ)を持ち、足元に白い塔状の建築物が描かれています。 解釈: アイルランドの聖人(聖ブレンダン)、地元ケリー州の守護聖人として、土地と信仰の 結びつきを象徴東端の内陣(sanctuary)。東端の内陣(sanctuary)にある三連ランセット窓の全体像。それぞれの窓に複数の場面が縦に積み重なるように配置されており、全体で9段×3列=27場面から構成されていた。この窓は、キリスト教の聖餐(ユーカリスト)と復活信仰を主題として、旧約と新約の物語を対応づけながら展開している と。伝統的にステンドグラスの物語順は:左→右(西洋の読字方向)、下→上(地から天へ=人間から神へ)の順に構成されることが多いとのことです。よって、以下も物語の順に従って書きます。このステンドグラスは、アイルランドの守護聖人・聖パトリックの霊的使命と信仰の勇気、そしてそれに先立つキリストの誕生という救済の始まりを描いた4場面から構成されています。物語は、まず左側下段において、聖パトリックが神の導きを夢で受ける場面から始まり、その使命に従って火を灯す決意と行動(右下)、続いて王たちの前での宣教(左上)、そしてキリストの降誕(右上)という順に、人間の応答と神の救いの交差が強調されています。①左下:聖パトリック、捕囚中に神の幻視を受ける◉場面:・夢の中で神からの使命を受ける聖パトリック ◉図像:・聖パトリックがベッドに横たわって眠る。 ・上空に天使が現れ、巻物(啓示の象徴)を持って指し示す。 ・もう一人の天使が伴っており、霊的世界の使者として描かれる。◉意味:・捕囚中の聖パトリックが神から幻視を通じて「アイルランドへ戻り、布教せよ」との召命を 受けた瞬間。 ・福音宣教の根本動機としての「神の呼びかけ」を象徴。 ・修道的ヴィジョン、祈りのうちに聞く神の声。 ◉銘文: ST. PATRICK DURING HIS CAPTIVITY SAW IN A DREAM (聖パトリックは捕囚中に夢を見た)②右下:聖パトリック、タラの丘で火を灯す ◉場面: ・復活祭の火を灯すことで信仰を宣言する聖パトリック◉図像:・聖パトリックが祭壇のような場所に火を灯す。・炎が赤々と燃え上がり、巻物や器、壺がそばに置かれている。・背後は青い装飾と建築的な背景(神殿・聖域)を思わせる。◉意味:・キリスト教の信仰の光を象徴する「復活祭の火」を、異教の権威下にあるタラの丘で あえて灯した象徴的行為。・キリスト教がアイルランドに根付く決定的瞬間を示す。・聖パトリックの大胆な信仰告白と実践。◉銘文: FIRE ON THE HILL OF TARA(タラの丘の火)③左上:聖パトリック、王たちに福音を語る ◉場面: ・ 聖パトリックによる王族層への宣教 ◉図像: ・聖パトリックが2人の男性(王族や貴族)に向かって語る。 ・彼らは落ち着いた表情で話を聞いており、受容的な姿勢。 ・背景には赤と金を基調とした意匠があり、王権の象徴。 ◉意味: ・聖パトリックがキリスト教を王たちに説いた象徴的場面。 ・支配層の改宗を通じて信仰が国土に広がっていく重要な局面。 ・キリスト教の普遍性と統治との結びつきを強調。 ◉銘文: (この場面自体には銘文は明示されていません)④右上:キリストの誕生(降誕) ◉場面: ・イエス・キリストの誕生の場面 ◉図像: ・聖母マリアが青衣でひざまずき、幼子イエスを見守る。 ・イエスは飼い葉桶の中に眠り、背景にはヨセフと天使または羊飼い。 ・上部には十字と光に彩られた神聖な空間が広がる。◉意味: ・神の救いの計画の始まり、イエスの誕生。 ・神が人間の世界に来られた出来事としてのインカルネーション(受肉)。 ・他の3場面で描かれる宣教の根源的な意味を担保する中心的出来事。◉銘文: GLORIA IN EXCELSIS DEO (天のいと高きところには神に栄光)このステンドグラスは、聖パトリックの召命、殉教者への祈り、布教活動、信仰の継承という4つの場面で構成され、アイルランドにおけるキリスト教の始まりと、その信仰を伝え守る人々の姿を描いています。捕囚中に夢で神の啓示を受けるパトリック(左下)に始まり、殉教者にひざまずく祈り(右下)、王たちへの布教(左上)、そして子どもたちへの教導(右上)と続くこの窓は、「信仰の使命 → 殉教の継承 → 福音の宣言 → 教えの伝播」という、信仰の流れと霊的成長の物語を体現しています。①左下:捕囚中の聖パトリック、神からの召命を夢で受ける ◉場面: 聖パトリック、捕囚中の幻視 ◉図像: ・ベッドに横たわるパトリック。 ・上空に2人の天使が現れ、一人は巻物を指差す。 ・天使たちは白と金の衣をまとい、神からの使者を象徴。 ◉意味: ・神が聖パトリックにアイルランド布教の使命を与えた象徴的瞬間。 ・捕囚という苦しみの中で召命を受ける「逆境の中の啓示」。 ・彼の生涯と布教活動の出発点。◉銘文: ST. PATRICK DURING HIS CAPTIVITY SAW IN A DREAM(聖パトリックは捕囚中に夢を見た)②右下:殉教者たちの血の上にひざまずく聖パトリック ◉場面: 信仰のために倒れた者たちへの祈り ◉図像: ・殉教者の亡骸にひざまずき、手を当てて祈る聖パトリック。 ・背後に暗い装束の兵士たちが無言で立つ。 ・地には血を流した殉教者の遺体。 ◉意味: ・キリスト教信仰の広がりは、殉教者たちの犠牲のうえにあるという認識。 ・パトリックの使命が彼らの霊に支えられていることの象徴。 ・信仰とは「受け継がれた犠牲の記憶の上に立つもの」であることを表現。 ◉銘文: SHED FOR HIS MASTER (主のために流された)③左上:聖パトリック、王族に宣教する ◉場面: 支配層へのキリスト教布教 ◉図像: ・聖パトリックが巻物を手にして語りかけている。 ・向かって右には王族風の人物2人が、深く聞き入っている。 ・落ち着いた尊敬の態度でパトリックの言葉を受け入れている。 ◉意味: ・キリスト教が社会の中枢、王族階層にも届いた歴史的展開。 ・パトリックの雄弁と人格が王の心を動かす。 ・支配者たちの改宗が人々に大きな影響を与えた象徴的場面。 ◉銘文: (銘文なし)④右上:パトリック、子どもたちへ信仰を教え導く◉場面: 信仰の継承と教育◉図像: ・赤い服の少年がパトリックの前に立ち、導きを受ける。 ・白い衣の女性や子どもが傍らで見守る。 ・背景には自然と草地、教えを受ける場としての平穏な空気が漂う。◉意味: ・若い世代に信仰を伝えることの重要性。 ・教育と福音宣教の融合。 ・次の時代に信仰が絶えず継がれていく希望の場面。◉銘文: (銘文なし)この2連のステンドグラスは、日々の労働・奉仕・家庭・信仰の営みの尊さを主題にしており、神の御子イエスが家庭内で働く姿や、修道士たちの労働と祈り、死に臨む者への慈しみが描かれています物語は、左下の修道士たちの共同作業に始まり、右下での終末期への奉仕と祈りへと続き、上段では幼子イエスの家庭生活(左上)、そして成長したイエスの大工としての姿(右上)へと展開し、日常と信仰、労働と祈りの一致を示しています。①左下:修道士たちの労働 ◉場面: 修道士たちが木工などの作業を行っている場面 ◉図像: ・3人の修道士が協力して木槌や道具を使って作業。 ・背景にはアーチ状の装飾と教会建築風の意匠。 ・互いに声を掛け合っている様子から、協働の精神がうかがえる。 ◉意味: ・「祈り、働け(Ora et Labora)」という修道会のモットーを具現化。 ・労働は神への奉仕であり、共同生活の重要な一部。 ・地道な手仕事もまた神聖な務めであることの象徴。◉銘文: SI HIC ESSET ADIUVARET(もし彼がここにいたなら、助けてくれただろう) ※少し意訳的な銘文で、「神の助けがあれば…」という文脈の可能性もあります。◉寄進銘文: ERECTED BY ANDREW & MARIA SHEEHAN IN MEMORIAM (アンドリューとマリア・シーハンが記念に建立)②右下:死に臨む者の手を取る修道士 ◉場面: 修道士が病者または死者に聖油などを授ける場面 ◉図像: ・座っている人物(病者または臨終者)に、もう一人の修道士が両手で触れて祈っている。 ・周囲の背景は静かな礼拝堂を思わせ、儀式的な場面。 ・頭には輪(聖性の象徴)があり、魂の準備が行われている印象。◉意味: ・臨終者への終油または霊的交わりを象徴する場面。 ・修道士の奉仕が、死の瞬間にも寄り添うものであることを示す。 ・肉体の終わりに際し、魂のために祈る行為としての「慈愛の業」。◉銘文: DE MORTE ORATIO(死に際しての祈り)◉寄進銘文: ERECTED BY DANIEL & MARGARET SHEEHAN IN LOVING MEMORY (ダニエルとマーガレット・シーハンが愛を込めて建立)③左上:幼子イエスと聖母マリア、家庭での労働◉場面: 聖母マリアとイエスが家庭で働く場面◉図像: ・リアが糸車を扱い、幼子イエスが木工作業をしている。 ・家庭内での労働に集中する様子。 ・足元には子羊もおり、犠牲や純潔を象徴。◉意味: ・イエスも人間の家庭に育ち、労働に親しんだという人間性の強調。 ・家庭の中に神聖が宿るという思想。・労働と日常における聖性の表現。◉銘文: ET ERAT SUBDITUS ILLIS(彼は彼らに従っていた) → ルカ2:51、イエスが両親に従順であったことを示す④右上:成長したイエスの労働◉場面: 若きイエスが大工として働く姿◉図像: ・イエスが木材を削る姿。 ・木片や道具が足元にあり、職人としての生活を送っていたことを示す。 ・周囲の色合いは素朴ながらも神聖さを醸し出している。◉意味: ・キリストが人として働いたという事実に込められた謙遜と尊厳。 ・労働そのものが神に仕える手段であることの象徴。 ・地上的労働と霊的使命が調和していたイエスの人生を映す。◉銘文: ET LABORAVIT(そして彼は働いた)このステンドグラスは、キリスト教における洗礼の重要性とその始まり・継承・拡がりを主題としています。物語は、左下に描かれる王の洗礼(アイルランドの指導者層の改宗)から始まり、右下では聖パトリックによる布教と洗礼の儀式、続く右上ではイエス・キリスト自身が洗礼を受けた場面(ヨルダン川)、そして左上では天使たちがこの神秘の出来事を礼拝する様子が描かれ、「洗礼」という行為が神から始まり、人々へと伝えられていく過程が視覚的に展開されています。①左下:王の洗礼(アイルランドの支配者層の改宗)◉場面: アイルランド王または貴族の洗礼を受ける場面◉図像: ・白い衣をまとった人物がひざまずき、聖職者から洗礼を受けている。 ・背後には立会人たちと馬を連れた従者が控えており、王的身分を暗示。 ・洗礼者は器から水を注ぎ、典礼的な所作。◉意味: ・支配層の改宗によりキリスト教がアイルランド全体に広がるきっかけを示す。 ・聖パトリックの布教の成果の象徴。 ・信仰が社会的階層を超えて根付くプロセス。◉銘文: THE BAPTISM OF THE KING (王の洗礼)②右下:聖パトリック、Armagh(アーマー)で洗礼を施す◉場面: 聖パトリックによる洗礼の実施◉図像: ・聖パトリックが緑の外套をまとい、ひざまずく人物に水を注いでいる。 ・洗礼を受ける人物は白い衣で清められた魂を象徴。 ・背景は教会的空間を思わせる意匠。◉意味: ・聖パトリックがアイルランドにおけるキリスト教の洗礼儀式を確立したことを示す。 ・Armagh(アーマー)はアイルランド教会の中心地としての象徴性を持つ。 ・伝道者としての聖パトリックの中心的役割。◉銘文: BY ST. PATRICK AT ARMAGH (アーマーにおける聖パトリックによる)③右上:主イエスの洗礼(ヨルダン川)◉場面: イエス・キリストがヨハネから洗礼を受ける場面◉図像: ・洗礼者ヨハネが赤い衣をまとい、イエスに水を注いでいる。 ・イエスは白い布をまとい、両手を組んで受洗の姿勢。 ・頭上には聖霊の象徴である鳩が描かれ、天の光が差し込む。◉意味: ・洗礼という儀式の起源を示す中心的場面。 ・神の子が人間として神に従ったことを象徴。 ・洗礼が信仰生活の出発点であることを示す。◉銘文: OF OUR LORD (主の洗礼)④左上:天使たちが洗礼を礼拝する◉場面: イエスの洗礼を見守り、崇める天使たち◉図像: ・左に金と赤の衣をまとう天使、右に白とピンクの天使。 ・祈りの姿勢、巻物または花を持つ。 ・背景はブルーの意匠で天上の雰囲気を表現。◉意味: ・イエスの洗礼が天上界でも重要な出来事であることを示す。 ・神の救済計画の始まりとして、天使が敬意を表している。 ・洗礼の神秘性と祝福の象徴。◉銘文: GOD’S BAPTISM (神の洗礼)この2連のステンドグラスは、聖パトリックの布教と奇跡、そして王たちとの対話と宣言という4場面で構成されています。物語は、下段左で聖パトリックが異教の儀式を打ち破る祈りを行い、続いて下段右で王たちの前に立ち、キリスト教の真理を語る場面へと進みます。上段右では、王たちや群衆がその教えを受け入れる様子が描かれ、最後に上段左で、聖パトリックが癒しと祝福を与える奇跡的な場面が示され、アイルランドにおけるキリスト教の確立と、聖パトリックの霊的権威が強調されています。①下段左:聖パトリック、異教の儀式に立ち向かう◉場面: 聖パトリックが異教の火を祈りによって打ち砕く場面◉図像: ・聖パトリックが赤と白の祭服をまとい、祈りの手を掲げている。 ・左には火を焚く異教の儀式が描かれ、背を向けた人物(ドルイド司祭)が見える。 ・青衣の人物が見守る中、信仰と儀式の衝突を象徴する構図。◉意味: ・聖パトリックが異教の慣習に公然と挑み、キリスト教の真理と力を示した場面。 ・信仰の力による「闇に対する光」の象徴。・アイルランドにおける宗教的転換の始まり。◉銘文: ST. PATRICK PRAYING (祈る聖パトリック)②下段右:王たちの前で語る聖パトリック◉場面: 王族にキリスト教を宣言する聖パトリック◉図像:・聖パトリックが緑のマントをまとい、2人の王(または長官)に向かって語っている。・王たちは座して聞き入っており、背後に従者の姿も見える。・パトリックの手には巻物や十字架はなく、言葉による説得の場面。◉意味:・キリスト教が支配者層に対して宣言された決定的瞬間。・言葉の力、信仰の確信による布教の核心。・権威と霊的指導の対話の象徴。◉銘文: BEFORE THE KINGS (王たちの前で)③上段右:王たちと群衆が福音に耳を傾ける◉場面: 聖パトリックの教えを受け入れる王と民衆◉図像: ・群衆が前方に押し寄せ、複数の王(王冠付き)がパトリックを中心に向かって立つ。 ・人々は手を伸ばし、言葉を受け止めようとしている。 ・祭服の赤が中央人物の視線を集め、パトリックの霊的中心性を強調。◉意味: ・キリスト教が王と民に広く受け入れられていく段階。 ・信仰が個人から共同体へと広がる。 ・群衆の表情や姿勢により、教えの威力が視覚的に表現される。◉銘文: TO THE KINGS AND PEOPLE (王と民に)④上段左:聖パトリック、祝福と癒しを与える◉場面: 聖パトリックが癒しの奇跡を行う場面◉図像: ・聖パトリックが片手を上げ、祝福を与えている。 ・足元にひざまずく人物(病人または改宗者)が癒し を求める姿。 ・背後の青と赤の装飾が霊的力と神秘を強調。◉意味: ・聖パトリックが神の力によって癒しと救いを人々にもたらしたことの象徴。 ・宣教の言葉だけでなく、行動・奇跡によって信仰が裏打ちされたことを示す。 ・アイルランドの聖人としての力と慈愛の象徴的場面。◉銘文: LAY HANDS ON THE SICK AND THEY SHALL RECOVER (病人に手を置けば彼らは癒される)このステンドグラスは、聖パトリックによる王族や貴族への教化と洗礼の物語が展開されています。信仰と権力の交差点における劇的な布教の瞬間が4場面に分けて描かれ、異教の王が跪いて洗礼を受け、キリスト教への改宗が社会的に拡大していく過程が視覚化されています。①下段左:聖パトリック、王を前に福音を語る◉場面: 異教の王に福音を説く聖パトリック◉図像: ・パトリックは白衣に赤いマント、司教帽を被り、右手に福音書を持ち、語りかける。 ・王は王冠をかぶり、玉座に座し、剣を持つ従者たちと共にいる。 ・白衣の人物が跪いている(求道者か洗礼志願者)。◉意味: ・聖パトリックが王権の前で信仰を明確に語る決定的瞬間。 ・信仰と世俗権力の対峙と交渉の象徴。 ・アイルランド社会における宗教的転換点。◉銘文: HE PREACHED TO THE HIGH KING OF TARA②下段右:異教からの転向・洗礼の前段階◉場面: 高位聖職者たちの前で洗礼を受ける改宗者◉図像: ・聖パトリック(中央)と2人の司教が赤い帽子をかぶって立ち、聖油または水の器を持つ。 ・白衣の人物(改宗者)がひざまずき、頭を垂れる。 ・背後には神殿風の建築モチーフ。◉意味: ・洗礼前の儀礼、または赦しと受け入れの場面。 ・教会制度が整えられた布教の段階。 ・異教からの霊的転向の完成。◉銘文: BAPTIZED BY ST. PATRICK WITH MANY OTHERS INTO THE CHRISTIAN FAITH (聖パトリックにより他の者たちと共にキリスト教へと洗礼された)③上段右:異教の神殿に背を向ける者たち◉場面: 改宗者が異教の偶像を離れ、キリストへと向かう◉図像: ・中央の人物(おそらく王子か貴族)は背後に異教の像や偶像を背にして、前方へ歩き出す。 ・その背中を支えるように従者が付き添う。 ・奥には石像や神殿のようなものが見える。◉意味: ・異教との決別、キリスト教への回心を象徴。 ・改宗の内面の選択と、社会的転換の表現。 ・光に向かって進む構図は信仰の希望を象徴。◉銘文: THE KING WENT OUT TO WORSHIP (王は外へ出て礼拝へと向かった)④上段左:王の洗礼◉場面: 跪く王に洗礼を授ける聖パトリック◉図像:・聖パトリックは赤の祭服をまとい、片手で水を注ぐ仕草。・王冠を脱いだ人物(王)がひざまずき、謙虚に洗礼を受ける。・背景は天と聖霊の輝きで満たされる神秘的構図。◉意味:・社会秩序の頂点にある人物がキリスト教に従う劇的瞬間。・謙遜と信仰の象徴的融合。・パトリックの布教の頂点を示す場面。◉銘文: KING LAOGHAIRE'S SUBMISSION TO FAITH (ロイリー王の信仰への服従) (彼はタラの高王に説教した)この新しいステンドグラスは、聖パトリックの昇天(または栄光)と彼を記念する祈りを中心とした三連窓です。聖パトリックの崇拝・顕彰・永遠の平和を象徴する宗教的ビジョンの場面と理解されます。この三連ステンドグラスは、聖パトリックの死後の栄光・天上での勝利・記念祈祷を主題としています。中央には聖パトリックが白衣で輝く姿として表され、彼の使命が天に受け入れられたことを象徴します。両脇には、祈り・感謝・悔い改めの姿勢で跪く人々が描かれており、アイルランドの民衆が彼の遺産を敬い続ける構成になっています。中央パネル:聖パトリックの栄光または昇天◉図像: ・聖パトリックは白いローブをまとい、手を広げて天に向かって立つ。 ・足元には跪く男性(悔悛者または信者)、天使の顔、赤い天上の背景。◉意味: ・聖パトリックの聖性と天上での永遠の命を象徴。 ・彼が「アイルランドの守護聖人」として受け入れられていることの可視的表現。 ・足元に跪く人物は、後世の信者の悔い改めまたは祈りを代表する可能性。左パネル:信徒たちの祈りと悔い改め◉図像: ・女性を含む複数の人物が、苦悩・祈り・悔い改めの姿勢で跪く。 ・頭に手を置く、手を合わせる、深く頭を下げるなどのジェスチャー。◉意味: ・聖人に対する嘆願と感謝。 ・罪の赦しを願う悔い改めの場面。 ・社会全体がパトリックの功績を称え、平和を祈る構図。◉銘文(一部): PRAY FOR THE SOULS OF THOSE WHO... (以下省略)右パネル:感謝と平安を求める信徒たち◉図像:・若い女性と天使、または女性信者が穏やかに祈る姿。・柔らかな赤と緑の色調が用いられ、平安と信仰の静けさを演出。◉意味:・聖パトリックへの感謝の祈り。・個人レベルでの信仰の継承と、心の平和の象徴。◉銘文(一部): OF KERRY, 1899–1904... (これは記念献納者の情報。キラーニー司教 Henry の名が見られます)この2連窓は、聖パトリックの晩年の祈り・最後の瞬間・天への召しを描いています。左側は群衆に見守られた祈りと説教、右側は天の使者に迎えられての永眠が中心的なテーマです。①下段左:聖パトリック、民衆に最後の祈りを捧げる◉場面: 人々に囲まれて祈る聖パトリック◉図像: ・緑のローブをまとった聖パトリックが座り、両手を広げて祈りを捧げている。 ・背後には複数の聖職者と民衆が集まり、涙や崇敬の表情で見守っている。 ・背景のアーチと赤い意匠が、教会空間であることを示す。◉意味: ・パトリックの最後の説教や祈りを象徴。 ・教えを弟子たちや民衆に遺し、信仰共同体を託す場面。 ・彼の生涯が「祈りで始まり祈りで終わる」ことを示す。◉銘文: ST. PATRICK SPEAKS TO HIS PEOPLE BEFORE HIS DEATH (死の前に民に語る聖パトリック)②下段右:聖パトリックの永眠と天使たち◉場面: 聖パトリックの死(永眠)◉図像: ・白い衣をまとった聖パトリックが床に横たわり、天使が彼の魂を天に迎えている。 ・一人の天使が手を取り、もう一人が天を指し示している。 ・周囲は赤い祭服の聖職者たちが祈りを捧げる姿。◉意味: ・天国への召しと、聖人としての完成。 ・人々の祈りの中で穏やかに息を引き取ったことを示唆。 ・死が終わりではなく、神の懐に迎えられる新たな始まりであるという信仰表現。◉銘文: SAINT PATRICK ENTERS ETERNAL REST (聖パトリック、永遠の安息に入る)③上段右:晩年の祈りと天の幻視◉場面: 聖パトリックが晩年に神の啓示を受ける◉図像: ・赤いマントをまとい、岩場でひざまずき祈るパトリック。 ・天には光が差し込み、神の象徴として天使や聖霊が現れる。 ・背景の青が深い霊的静寂を表す。◉意味: ・死を前にした深い祈りと、天国の幻視。 ・神との最後の交わり。 ・苦悩と希望の融合。◉銘文: ST. PATRICK'S FINAL PRAYER (聖パトリックの最後の祈り)④上段左:天国の喜びに迎えられる魂◉場面: 天使たちが聖パトリックを迎える◉図像: ・天使たちが空から降り、パトリックの魂を抱き上げるようにして天に向かう。 ・下では弟子たちが涙を流し、祈る姿。 ・背景には光に満ちた青空が描かれる。◉意味: ・死の瞬間、聖人の魂が天使に導かれるという伝統的な象徴。 ・残された人々の悲しみと、天上での喜びの対比。 ・聖人が「天国の仲間入り」をする教会的理解の表現。◉銘文: (この場面には明示的な銘文は見られません)St. Mary’s Cathedral(聖マリア大聖堂)の内陣(chancel)から身廊(nave)方向を。主祭壇前(内陣)から西面の入口側に向けて撮影。側壁にはステンドグラスが多くはめ込まれており、本体よりも信徒席寄り(中廊の左右)に連続配置されているのであった。左側上段。・図像:半裸の人物(イエスと思しき人物)が鞭打たれている場面。周囲に赤衣の司祭や 衛兵らしき人物。・主題:「鞭打ちの刑」(The Scourging at the Pillar)・意味:キリストの受難の始まり、彼の苦しみによる贖罪。右側上段。・図像:白衣姿のキリストが手に器を持ち、弟子たちの足を洗っている場面。・主題:「弟子の足を洗う」(The Washing of the Disciples' Feet)・意味:謙遜と奉仕の象徴。最後の晩餐の直前、イエスが自ら弟子の足を洗うことで、 愛と仕え合う教えを体現。左側下段。・図像:捕らえられ、屈服させられる人物。兵士に囲まれた様子。・主題:「イエスの逮捕」(The Arrest of Jesus)・意味:ゲツセマネの園での裏切りと捕縛の場面。人類の罪を背負う決意の瞬間。右側下段。・図像:白衣の女性(聖母マリア?)に向かって語る男性と、もう一人の証人。・主題:「ピラトの前のイエス」(Jesus Before Pilate)あるいは「ユダの裏切りの報告」・意味:無実のイエスが裁判にかけられ、不正と誤解の中で処刑へ導かれていく様子。左窓上段 キリストが祭司の前で尋問を受けている。 →「Our Lord before Pilate」(ピラトの前に立つ主)と関係。左窓下段 キリストがローマの法廷で裁きを受ける様子。 → ピラトによる尋問・裁判を受けている描写。右窓上段 キリストが手を縛られ、ローマ兵に引かれている。 →「Condemned to death」(死刑判決)に至る場面。右窓下段 キリストが正式に死刑宣告を受けた場面。衛兵に囲まれた裁きの瞬間。左窓上段:イエス・キリストのゲッセマネの祈り キリストが岩にひざまずき祈る姿。天使が現れ励ます(ルカ22:41-43)。 ラテン語枠:“God strengthened him.”下段:聖パトリックの遺体を運ぶ場面(St. Brigid brings the Bishop’s Staff) 女性たち(中央の人物は聖ブリジット)が、司教の杖を携えて移送する様子。 「St. Brigid bringing the Bishop’s Staff」右窓上段:キリストの復活(Resurrection) 輝く白い衣の復活のキリストが現れる。 ラテン語枠:“He showed himself alive.”下段:聖パトリックの死後の場面(The Dead Body of St. Patrick) 人々が聖パトリックの亡骸を丁寧に扱っている。 → アイルランドの守護聖人としての崇敬が示される場面。このステンドグラスは、キリストの救済史(祈り〜復活)と、アイルランドにおけるキリスト教布教の完成(パトリックの死とブリジットの継承)という、二重の物語構造になっています。ステンドグラスの典型的な「物語順(左上→左下→右上→右下)」の型を保っていますが、左右を通じて時系列が交差して進むため、教会内での位置や意味合いによって観客が読み解く形になります と。左窓上段:エマオの食事(The Supper at Emmaus) 復活したキリストが、エマオの村で弟子たちと食事をする場面。 弟子たちは彼を識別できなかったが、パンを裂く姿を見て気づく(ルカ24:30–31)。下段:聖者(プリンス)たちが聖体拝領を受ける場面(Prince and retainers Holy Communion) この場面はアイルランドの王または貴族とその随行者が聖体拝領を受けている様子であり、 初期のキリスト教受容を示しています。右窓上段:復活のキリストと弟子たちの夕食(同上・エマオの場面の続き) 左窓の続きと考えられる構成。パンを裂く動作の直前または直後を描写。下段:St. Columba(聖コルンバ)が子どもに教えを授ける場面 アイルランドにキリスト教を広めた重要な聖人の一人。 St. Columba and a boy from St. Columba’s School(聖コルンバと弟子)と 考えられます。St Mary’s Cathedral(セント・メアリーズ大聖堂)内の側廊に面した一角。この空間は、洗礼式(Baptism)が行われる神聖な場所。・構造 ・アーチ状の石組みの出入口。 ・両脇に装飾鉄製の扉(Wrought Iron Gates)。 ・床面は美しい幾何学模様のタイル張り。 ・中央に洗礼盤(Baptismal Font)が据えられ、後方に椅子が並ぶ。 ・背後には三連窓のステンドグラス。洗礼堂のステンドグラス。中央場面(主パネル) 主題:イエスの洗礼(Baptism of Christ) ・中央に立つ人物はヨハネ(洗礼者ヨハネ)、その左に跪いて水を受けているのが イエス・キリスト。 ・頭上には聖霊の象徴である白い鳩と、光輪の放射、天からの光が描かれている。 ・周囲に弟子たちや群衆が見守っている様子。左パネル ・祈る人物:青い衣をまとった人物(おそらくマリア)、あるいは洗礼の証人。・ ・複数の人物がイエスの洗礼を見守る場面の一部として描かれているようです。右パネル ・群衆の中で跪く人物や、祈りを捧げる姿。 ・イエスが神の子であることを見出した瞬間を称える描写か。丸窓(上部3つ) ・天上の天使たち(Cherubs or Seraphs)がラッパやハープなどの楽器を奏でている。 ・最上部の丸窓には、神の目や栄光の象徴(十字架と王冠)が描かれている可能性があります。このステンドグラスは、おそらく1931年に逝去したケリー司教アンドリュー・ヒギンズ(Andrew Higgins)師の追悼として奉納されたものである と。ステンドグラス窓(2連)で、復活後のイエスと弟子たちへの教えの場面が描かれていた。左パネル上段:復活後のイエスが現れる場面 ・白い衣のキリストが弟子たちの前に現れ、一人が膝をついてひれ伏している。 ・背後に天使2人が控える。 ・キリストの手には磔刑の傷跡が見える。右パネル上段:キリストの昇天直前、最後の教え ・白いローブ姿のイエスが右手を挙げ、弟子たちに語っている。 ・場面としては「最後の命令(大宣教命令)」の一部か、あるいは昇天直前。左パネル下段:イエスの言葉を聴く群衆 ・多くの弟子たち(または聴衆)が立ち並び、話に耳を傾けている。 ・背後の赤い背景と建築は、教会内や天国的空間の象徴。右パネル下段:バプテスマ(洗礼)を授ける場面 ・司教の装束を纏った人物が手前の若者に洗礼を授けている。 ・「あなたがたはキリストの体の一部である」という教えと一致。左パネル上段:聖パトリック、少年に教えを授ける ・赤い衣の聖パトリックが立ち、巻物(または書物)を持って説いている。 ・少年が足元に跪いており、聴衆が周囲にいる。左パネル下段:聖パトリックが病人を癒やす ・聖パトリックが白衣をまとい、病人に手をかざしている。 ・傍らには看護する者たちの姿。右パネル上段:聖パトリック、弟子と共に旅をする ・2人の人物(パトリックと弟子)がローブ姿で前を向いて歩いている。 ・巻物と杖を持つ、宣教の象徴。右パネル下段:パトリック、少女に洗礼を授ける ・若い女性が白い衣を纏い、前に立つ司教姿のパトリックが手をかざしている。 ・後方に修道女のような姿の人物。左パネル上段:聖パトリックが説教する ・パトリックが聴衆に向かって説教している場面 ・傍らには聖書を持つ人物も見られる左パネル下段:聖パトリックが聖水を授ける ・パトリックが白衣の人物に聖水を注いでいる様子(洗礼) ・背後に見守る人々右パネル上段:旅するパトリックと同行者たち ・2人の人物が並んで歩いており、杖と巻物を所持 ・宣教の旅を表す典型的構図右パネル下段:若き修道女を導く聖パトリック ・聖パトリックが修道服を着た少女を導いている ・背後に教会らしき建物、司教杖などが見える左パネル上段:聖パトリック、病者に祝福(または癒し)を与える ・横たわる人物に手を差し伸べるパトリック ・周囲には心配そうに見守る家族や従者左パネル下段:聖パトリック、弟子たちと共に教えを説く ・複数人の弟子たちに囲まれ、座って語るパトリック ・落ち着いた学びの場面右パネル上段:聖パトリック、復活または霊的啓示を受ける姿 ・輝く白衣姿、腕を広げて立つ ・背後には十字架、足元には蛇(悪の象徴)右パネル下段:聖パトリック、書物を記す晩年の姿 ・老年のパトリックが杖を持ち、書を記している ・静かな時間の中で黙想している印象祭壇周辺を再び。西端(入口側)から東の祭壇方向を振り返って。ズームして。さらに。中央のパネル解説(上から下へ)1.最上部:神を象徴する存在(白髭の御父またはキリスト昇天後のイコン)2.中段最下部:立像の聖人(緑・紫のローブ、巻物または剣を持つ) ・この人物はおそらく聖パウロ(St. Paul) ・剣は彼の殉教(斬首)の象徴 ・巻物は彼の手紙(新約聖書の使徒書簡)を示す3.背景装飾:花紋、蔦模様、ラテン十字左右のパネルの意味・天使、聖人、預言者などの象徴的図像・赤系の衣装やハープ、書物、リュートのようなものを持つ姿も見える・時系列の物語というよりは「永遠の賛美」「聖人列伝」など象徴的な配置の可能性祈祷用の小礼拝堂(Chapel of Repose)。ズームして。St Mary’s Cathedral(キラーニー)の南側側廊の南端部(左側通路の一番奥)。St Mary’s Cathedral の南側礼拝堂)にあるステンドグラスのクローズアップ(ズーム)。左パネル(向かって左)・登場人物:聖母マリアと幼子イエス・主題:聖母子像(The Madonna and Child) ・マリアがイエスを抱きかかえ、母性的なまなざしを向けている。 ・背景の鮮やかな赤と青の装飾が神聖さを際立たせています。🔹 右パネル(向かって右)・登場人物: ・上部の司教冠をかぶった人物:聖パトリックと思われます(白い尖塔と緑のマント、 アイルランドの守護聖人に典型的)。 ・下部の人物が跪き祈る姿も見えます。・主題:アイルランドの守護聖人・聖パトリックの加護 ・マリアと子イエスの隣に配置されていることから、信仰とアイルランドの守護という 二重の意味を持つと思われます。St Mary’s Cathedral(キラーニー)東端の高窓部をズームして。聖ヤコブ(St. James the Greater) ・新約聖書の使徒の一人で、ゼベダイの子、ヨハネの兄弟。 ・巡礼者の守護聖人(例:スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ)。 ・よく「貝殻(ホタテ)」や「巡礼杖」「書物」を持って描かれます。 ・赤い衣装は殉教の象徴でもあります。St Mary’s Cathedral(キラーニー)の内陣(高窓部)の右側パネル群の一つをズームして。聖シモン・ゼロテス(Simon the Zealot)聖シモン・ゼロテス(Simon the Zealot)は、イエスの十二使徒の一人で、「熱心党のシモン」とも呼ばれます。伝承ではペルシャやエジプトなどで布教し、のこぎりで殉教したとされ、その道具が象徴として描かれます。記念日は10月28日で、信仰と情熱の象徴的存在です。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.28
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その60):ディングル半島(Dingle Peninsula)(3/3)
ディングル半島北部・大西洋側に位置する絶壁の近くから、絶景をひたすら楽しむ。何故かといえば、我が人生でこの目で大西洋を地上から直接見るのはこれが最後であると感じていたのであった。Ballydavid Head(ベリーデイヴィッド岬)付近の無名??の岩峰を見る。標高はおおよそ300〜400メートル?。・岩がむき出しの丘陵状の山容。・植生は低い草地中心で、山頂部は岩だらけ。・海岸線からすぐ近く、断崖地帯に連なる一部 であったが。Ballydavid Head(ベリーデイヴィッド岬)。Ballydavid Head(ベリーデイヴィッド岬)の付け根方向。青と白、緑の絶景のカオスをカメラで追う。白い波頭が岩礁に砕け散るたび、刻一刻と海の姿が変わるのであった。ズームして。透明感を帯びたエメラルドグリーンから群青、そして灰青へと、海の色は空と光を映して刻々と移ろうのであった。吹きすさぶ潮風と荒々しい波が、切り立つ崖を絶え間なく打ち続ける。一方で、打ち寄せた波が静かに引く瞬間、海面は絹のような柔らかさを帯びる。緑の草地と黒褐色の岩肌、そこに白い波が絡みつき、色と質感の対比が視覚的な調和を。波が岩壁にぶつかるたびに生まれる泡のしぶきは、まるで海の息吹そのもの。激しく跳ねる水飛沫が、逆光に照らされて宝石のように輝くのであった。崖の縁に立つと、眼下に広がる海は果てしなく、どこか異世界のような静謐さを感じさせるのであった。ズームして。人の気配のない絶壁の風景は、太古の自然そのものを思わせるのであった。右奥の三角形状の3つの山は、アイルランド・ケリー州のディングル半島北岸にあるThree Sisters(三姉妹) と呼ばれる特徴的な連峰。各山の名前(東から西へ) 通称 アイルランド語名(英語表記) 説明① Binn Diarmada(ビン・ディアマダ) Diarmuid’s Peak 最も東側。三姉妹の中で最も緩やかな山② Binn Hanrai(ビン・ハンライ) Henry’s Peak 真ん中のピーク③ Binn Meanach(ビン・マーナフ) Middle Peak(最も西で鋭角な山。最も目立つ三角形)前景の海岸は Clogher Strand または Clogher Beach(クロガー・ストランド)。この四角い穴は自然の産物であろうか?自然の浸食作用によって形成された海食洞(sea cave)!?ディングル半島は、頁岩(シェール)や砂岩、堆積岩などの層状の堅い地質を持つため、風化と波の作用によって垂直や直線的な割れ目が生じやすい地形である と。アイルランドのディングル半島北岸に位置する Ceann Sraithe(ケアン・スラーまたはストラヘ・ヘッド) に設置された看板。Ceann Sraithe はゲール語で「草地の岬(Headland of the Strand)」を意味し、アイルランド語圏のケリー県の西端に位置。「Welcome to Ceann SraitheWelcome to Ceann Sratha where seabirds such as puffins and cormorants as well as whales and sharks can sometimes be seen.Cast an eye towards Sybil Head (1) – a major location (2016) for Star Wars VIII.The promontory is noted for its Napoleonic watch tower and Ferriter's Castle or Fort (2) is near at hand.The famed 'Three Sisters' (3, 4 & 5) are to the North and beyond them the headland at Baile Dháith (6) situated at the mouth of Smerwick Harbour.」 【ケアン・スラーへようこそ。ここでは、パフィン(ニシツノメドリ)や鵜(ウ)などの海鳥のほか、クジラやサメが見られることもあります。シビル・ヘッド(Sybil Head)(①)に目を向けてみてください。ここは2016年に映画『スター・ウォーズ エピソード8/最後のジェダイ』の主要なロケ地の一つとなりました。この岬は、ナポレオン時代の見張り塔で知られており、近くにはフェリター城(または砦)(②)もあります。有名な「スリー・シスターズ(三姉妹)」の丘々(③、④、⑤)は北に位置し、それを越えると、スマーウィック湾の入口にあるベール・ダーフ(Baile Dháith)(⑥)の岬が見えてきます。】①Ceann Sibéal(ケアン・シビール) → 有名な映画『スター・ウォーズ』の撮影地②Cathair na gPiaras(キャハー・ナ・ピアラス) → 古代の石の要塞跡、ピアス氏族の居城跡とされる③An Áird → 岬の突端部分(Headland)④An Bhinn Mhéanach(アン・ヴィン・ヴェーニャハ) → 「中間の峰」の意味の丘⑤Binn Dáimeas → 「敬意の丘」と訳されることもある地形⑥Ceann Bhéal Dúin → 「砦の口の岬」の意味(古代の防衛施設があったとされる)⑦Gallarus(ガラルス) → 有名な「Gallarus Oratory(ガラルス礼拝堂)」がある地域⑧Tráigh Chloichí → 小石の浜辺この岩は、ザトウクジラ(Humpback Whale)の尾びれ(fluke)を想起させる形である!? と。ザトウクジラ(Humpback Whale)の尾びれ(フルーク)。この地域(スマーウィック湾周辺)では、運が良ければクジラが見られるということを視覚的に示しているだと。特に写っているのは、クジラが潜る直前に尾びれを海上に持ち上げる瞬間であり、これはホエールウォッチングでよく知られるシーン と。左右に広がったシルエットが、海面から尾びれを持ち上げた瞬間の姿に似ている と。Ceann Sraithe(草地の岬)を後にしてR559を進む。「放牧中の羊たち」の姿を車窓から。ピントが金網に邪魔されて。3つ星ホテル・Ceann Sibéal Hotel。その先、右側には「カトリック教会・Séipéal Uinsinn Naofa(St. Vincent's Church / 聖ヴィンセント教会)」。 さらにR559の山道を上って行った。R560の右側にあったパネル。ケリー県西部(West Kerry)における氷河時代の地形と地質を解説するパネル。「The Ice Age at Pedler’s LakeDuring the last 2 million years Ireland has been subjected to various glacial periods.In West Kerry, ice collected mainly on the north-east side of mountains.There it produced deepened corries (cwm, cirques) which fed ice to valley glaciers.Pedler’s Lake is in a typical corrie.」 【ペドラーズ湖の氷河時代約2万5千年前の最終氷期の頃、アイルランドのほぼ全域はスコットランドから南下した巨大な氷床に覆われていました。氷河は谷を下りながら地形を削り、深めていきました。ペドラーズ湖は、山の北側にある氷河のすり鉢状の窪地(カリー)に氷河が削って形成されたものです。急な後壁と平らな湖底を持つ、氷河地形の好例として残っています。「In 1837 the Swiss geologist Louis Agassiz said for the firsttime, that ice formerly covered much of Northern Europe. Thefirst evidence in Ireland for the ice Age was discovered in 1848at Pedler’s Lake by John Ball (1818–89), a Dublin-born civilservant and mountaineer.」 【1837年、スイスの地質学者ルイ・アガシーが初めて、かつて氷が北ヨーロッパの大部分を覆っていたと述べました。アイルランドにおける氷河時代の最初の証拠は、1848年にペドラーズ湖でジョン・ボール(1818–1889)によって発見されました。彼はダブリン生まれの官僚であり登山家でもありました。】「During the Ordovician and Silurian Ireland was south of the equator; and under an ocean between two continents. Mud and sand deposited into it eventually became the rocks seen near Annascaul. In the Silurian, volcanic islands erupted lavas and ash, now found at Clogher Head. Muddy sediments trapped animals preserved as fossilsnear Dún Chaoin and on Caherconree Mountain. Younger sandy sediments produced the sandstones near An Daingean and Slea Head.By the Devonian, the ocean had disappeared, forming a large continent with deserts. The sand formed Old Red Sandstone, the backbone of the Slieve Mish Mountains, while coarser sediments produced rocks called conglomerates, seen now at Lough Slat and at Inch.At the beginning of the Carboniferous period the land was flooded by shallow tropical seas where shellfish and corals thrived. These are preserved in the limestones on the Magharees.During the last 2 million years to 10,000 years ago, ice on mountainsides formed depressions called corries many of which now contain lakes. Glaciers moved downslopealong river valleys, and when they melted boulder clay containing many different rock types was deposited.」 【オルドビス紀およびシルル紀の間、アイルランドは赤道の南に位置し、2つの大陸の間の海の下にありました。泥や砂が堆積し、やがてアンナスカウル付近で見られるような岩石となりました。シルル紀には火山島が噴火し、現在クロガー・ヘッドで見られる溶岩や火山灰を生じました。泥の堆積物は動物を閉じ込め、ドゥーン・カオインやカハーコンリー山で化石として保存されています。より新しい砂質の堆積物は、アン・ダンガンやスレア・ヘッド付近の砂岩を形成しました。デボン紀になると、海は消失し、砂漠を伴う大陸が形成されました。この砂がオールド・レッド・サンドストーン(赤色砂岩)を形成し、これはスリーヴ・ミッシュ山地の基盤となっています。より粗い堆積物は、現在ラフ・スラットやインチで見られる礫岩を形成しました。石炭紀の初めには、陸地は浅い熱帯の海に覆われ、貝やサンゴが繁殖しました。これらはマガリーズの石灰岩の中に保存されています。最後の200万年から1万年前までの間、山腹に氷が溜まり、コリー(氷河圏谷)と呼ばれるくぼ地を形成しました。その多くは現在湖になっています。氷河は川の谷を下って移動し、溶けるときにさまざまな種類の岩石を含む粘土質の堆積物(ボルダー・クレイ)を残しました。】右手に小さな滝が流れていた。近づいて。「Old Red Sandstone」(古赤色砂岩)で、これは氷河による擦痕(グレージング striations)で、氷河が通過した際に岩の破片で削られた痕跡であると。眼下左にはいくつかの沼の姿が。Pedler’s Lake(Loch an Pheidléara)周辺の氷河地形を。この風景は、典型的な氷河圏谷(カール、corrieまたはcwm)地形を示しています。写真の注目点:1.中央やや下の小さな池: ・これは「カール湖(tarn)」と呼ばれ、氷河が山腹に深い窪地を削り取った後に、 そこへ水が溜まって形成されたものです。2.奥に広がる湿地帯と2つの湖: ・複数の湖が点在しており、かつて氷河によって形成された小盆地に水が残っていることを 示しています。 ・一部は氷河が後退したときに残した「モレーン(堆積物)」で囲まれた形になっている 可能性があります。3.全体に広がる丸みを帯びた丘陵地: ・氷河によって滑らかに削られた地形で、植物が生えて湿原化しています。 ・氷河の重さや流れにより、こうした地形が生まれたことが案内板にも記されています と。Connor Pass(コナー峠)近くにあるPedler’s Lake(ペドラーズ湖)付近の断崖地形。これは氷河圏谷(corrie、cwm、cirque)の背後にある断崖で、氷河が山の斜面を削り取って形成した典型的なU字型地形の一部です。ペドラーズ湖(Loch an Pheidléara)**はこの崖のすぐ奥の斜面下に位置しており、まさにこの崖が氷河の発祥地点(氷河源)だったとされています と。移動して小滝を。正面にBrandon Bay(ブランドン湾)。リー川に架かる「Blennerville Bridge」を渡る。N70をひたすら進む。真っ赤な路線バスが前方を。バス名:Expresswayはアイルランド国営の長距離高速バスブランド)バス と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.27
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その59):ディングル半島(Dingle Peninsula)(2/3)
昼食を終え、「Dingle Port」を後にして、さらに岬に向かって西に進む。リバー・ミルタウンの対岸には瀟洒な白壁の民家が並ぶ。雨雲が上空にあったが、雨は止んで。再び「Dingle Harbour」を左に見ながら。 R559をひたすらに。山の裾野にポツンと一軒。そしてR559を更に走り、「スリー・ヘッド・ドライブ」の「展望台・Ceann Sléibhe」で車を止めた。大西洋に浮かぶ「グレート・ブラスケット島・Great Blasket Island」が姿を現した。 東方向の海岸線を振り返って。そして西方向の、大西洋に浮かぶ「グレート・ブラスケット島・Great Blasket Island」方向を。真下を覗き込んで。岩場をズームして。ヨーロッパカモメ(European Herring Gull)。白い頭部と体、灰色の背中・翼、太くがっしりした黄色のくちばし、くちばしの先端に赤い斑点(ゴニスポット)があるのが特徴。淡黄色の目と白いアイリング、脚は薄いピンク色。「Birds of the Siea Head area(スレイヘッド地域の鳥たち)」案内板。 「Slea Head area(スレイ・ヘッド地域)」は、アイルランド南西部のケリー県ディングル半島(Dingle Peninsula)の最西端に位置する、風光明媚な海岸エリア。アイルランド語では「Ceann Sléibhe(キャウン・シュレーヴァ)」と呼ばれている と。右下にはメッセージ:"Please! Take only photos. Leave only footprints."(お願い:写真だけを持ち帰り、足跡だけを残してください) と。放牧された羊の姿も。そして、アイルランド・ケリー県のスレイ・ヘッド(Slea Head)沿いにある有名な宗教モニュメントに到着。「磔刑(たっけい)のキリスト像(Crucifixion scene)」。1.中央:十字架上のキリスト(Jesus Christ) ・十字架に磔にされた姿。頭には茨の冠。 右脚からは血が流れているがごとくに。2.左側:聖母マリア(Virgin Mary) ・キリストの母。悲しみに満ちた表情で祈っている。3.中央下:マグダラのマリア(Mary Magdalene) ・キリストの足元にひざまずいて涙を流している姿。4.右側:聖ヨハネ(St. John the Apostle) ・最も若い使徒で、イエスのそばに残った弟子。手を組んで祈っている。この像は単なる観光オブジェではなく、カトリック信仰に基づく巡礼的モニュメント!?。地元民や信仰者が祈りを捧げるためにも使われているのだと。「アイルランドのキリスト教的風景(sacred landscape)」の象徴の一つ であると。経緯となぜこの場所に?・明確な建立年や寄贈者情報は定かではないが、20世紀前半〜中盤の可能性が高い と。・おそらくは地元のカトリック教会、あるいは巡礼者団体による寄贈であり、スレイ・ヘッド 周辺を巡る人々の祈りと記憶の場として設置された と。・自然と神の創造の偉大さを感じられる断崖絶壁と大西洋の絶景・キリストの受難の象徴としての「孤高・静寂」が強調される場所である とネットから。ヨーロッパカモメ(European Herring Gull)をスマホで撮る観光の女性。私も。「磔刑(たっけい)のキリスト像(Crucifixion scene)」を後にして、北方向に進む。「Coumeenoole Beach」をズームして。 「Coumeenoole Beach」をネットから。「Dunmore Head」の先端の島々が左手奥に見えた。「Dunmore Head・ダンモア・ヘッド」は、アイルランドのディングル半島の西端に位置する岬。アイルランド本島の最西端であり、ヨーロッパ最西端の地点の一つとしても知られている と。以前に訪ねたポルトガルの「ロカ岬」👈️リンクは「ヨーロッパ大陸最西端の岬」であったが、この場所は「ヨーロッパ最西端の地点の一つ」であり、ここが「ヨーロッパ最西端(島を除く)」!?。 移動してズーム。後方の島が「Great Blasket Island・グレート・ブラスケット島」。 緑に覆われた丘には多くの羊の姿が。左手奥に「Beginish・ベジニッシュ」島。 スレイ・ヘッド・ドライブ(R559号)沿い、断崖が続く荒々しい海岸。アイルランドの西海岸の絶景を楽しみながらカメラに収めながら北上。屋根の南面にはソーラーパネルが。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.26
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その58):ディングル半島(Dingle Peninsula)(1/3)
「Muckross House・マックロス・ハウス」を後にして、この日の次の目的地である大西洋に向かって南西に突き出ている「ディングル半島(Dingle Peninsula)」の西端を目指す。この場所は、アイルランドで最も西に位置すると共にヨーロッパの最西端でもある。N71・マックロスロードを北に進む。写真右の緑の丸に白い「a」、これは Applegreen社のロゴマーク。アイルランド国内で広く展開している燃料供給・コンビニ型のサービスステーション。数字(159.8 / 169.8):これは燃料のリッター単価(ユーロセント)を表している。アイルランドでは、燃料価格は1リットルあたりのユーロ単位で小数第1位まで表示されるのが一般的である と。おそらく上段が無鉛ガソリン(Unleaded)、下段がディーゼル燃料(Diesel)であろう。無鉛ガソリンは1ユーロ = 170円として1.598ユーロ × 170円 = 約271.66円/リットル。日本よりは1.5倍以上の高価なのであった。St Mary’s Cathedralの尖塔が見えて来た。St Mary’s Cathedralをズームして。Ballydowney Roundabout(ラウンドアバウト)を通過。N72の方向に左折して進む。N72を西に進むと、右手にあったのが「The Golden Nugget Bar & Restaurant」大型の(液体糞尿貯蔵・散布用タンク)車が前方に。日本では、牛馬等の糞尿は農地に散布は出来ないが、ここアイルランドでは散布場所は制限されているが、牧場緑地等への散布が可能なのであろう。突然の雨。教会の名は??Castlemaine・キャッスルメインを通過し、R561に入ると左側にDingle Bay(ディングル湾)が見えて来た。Dingle Bay(ディングル湾)はアイルランド南西部ケリー県に位置する美しい湾で、風景・自然・文化・歴史が豊かに融合した地域。大西洋からアイルランド内陸部へ深く入り込むフィヨルド状の湾である。長さはおよそ 40km に及び、湾の両岸にはなだらかな丘や牧草地、断崖が広がる。湾の最奥部にはCastlemaine Harbour(キャッスルメイン湾)があり、ここは汽水域で、干潟と湿地が発達しており、渡り鳥や水鳥の生息地として重要 とのこと。道路工事の信号は、人力で。R561は海岸線に出る。湾に向かって、なだらかな丘や牧草地、断崖が広がる。大西洋からアイルランド内陸部へ深く入り込むフィヨルド状の湾。小雨の降る中、再び海岸線を離れN86の山道を西に向かって進む。植栽で仕切られた牧草地が拡がっていた。Dingle・ディングルの街に入り「THE BOATYARD RESTAULAND」で昼食を。 地元ディングルやケリー産の新鮮な魚介類を中心に、ロブスター、カキ、ムール貝、ハクセイ(鱈の一種)、クラムなどを提供する店であった。「THE BOATYARD RESTAULAND & BAR」と。MENU。シーフードプラッター(フィッシュ&チップス、カラマリ、クラブクロー、ムール貝、チャウダー、自家製ギネスパンなど)やシグネチャーディッシュも人気 と。ムール貝を注文。バケツに似た容器一杯に盛られたムールマリニエール(ムール貝のワイン蒸し)を楽しんだのであった。ムール貝の日本での養殖は、一部地域でカキ養殖の副産物として行われていたり、新たな特産品として養殖に取り組む地域も出てきていると。特に、宮城県石巻市の雄勝湾で養殖される「三陸ムール貝」はブランド化されている。また、北海道余市町でも養殖が行われているとのこと。最初に1個食べた後、その貝殻を指でパクパクさせ、2個目からはその貝殻で、身が入った別のムール貝の身を挟んで、口の中にヒョイ、ヒョイヒョイと放り込みながら、バケツが空になるまで一心不乱に味わったのであった。水槽の中にいたのが、アイルランドやヨーロッパ近海で見られるヨーロッパロブスター(European Lobster)。体色は、深い藍色や青紫色を基調とし、白い斑点模様があるのが特徴的。熱を加えると赤くなるのだ。はさみは左右で形状や大きさが異なり、「クラッシャー(砕く側)」と「カッター(切る側)」に分かれてるのだ。アイルランドでは特にここ西海岸(ディングル、ゴールウェイなど)でローカルシーフードとして人気 と。食べたかったが・・・・・。アイルランド・ケリー県のディングル(Dingle)港にあった「スピリット・オブ・ディングル(The Wishing Needle / Spirit of Dingle)」と呼ばれる彫刻作品。素材はステンレススチールとガラス繊維のようであった。高さは約4メートルほどの先端が鋭く尖った彫刻作品。色彩は下部は銀色、上部がエメラルドグリーンに彩色されているのが特徴的。制作者は地元アーティストにより設計(詳細不明)と。このモニュメントは「願いを託す針(The Wishing Needle)」という愛称で知られており、港町ディングルの海と空を貫く祈りの象徴とされている。尖塔形状と色彩はアイルランドの自然や文化(エメラルド色はアイルランドの象徴色)を反映しており、「海と空、そして希望をつなぐもの」と解釈されているとのこと。そしてディングルのマリーナを見る。後方の山の上には塔らしきものが見えた。ネットで調べてみると「Eask Tower」と。(写真はネットから)。ディングル湾の航行安全のために建てられた航行標識(ナビゲーション・マーカー)であると。入港してくる船が安全に港へ進入できるよう、塔の上部には木製の「矢印型のフィンガー」が取り付けられているとのこと。これは船がHarbour Rock(航路上の暗礁)を避け、安全にディングル港に進入する方向を示すためのもの と。観光船であっただろうか?湾内や沖合を回って、イルカ、アザラシ、海鳥、時にクジラなどを観察するツアーがあるとのこと。防波堤上の通路から。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.25
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その57):Muckross House・マックロス・ハウス(4/4)
内部の見学を終え、Muckross House(マックロス・ハウス)を裏手から見る。この区域は、19世紀の使用人たちの生活・労働空間であると。・中央の大きな建物 使用人の居住区またはキッチン、ランドリー・右側の小さな建物 パントリー(食品庫)、木炭庫など・左奥の窓の多い建物(上階) 使用人の寝室、縫製部屋・複数の煙突 各部屋の暖炉。居住・調理・洗濯用・小さな扉と低い天井の部屋 食料庫、下働きの出入口 と。マックロス・ハウス(Muckross House)の裏手の中庭(サービス・ヤード/Servants' Courtyard)の別角度からの様子。右:南側の大きな建物 使用人の寝室、裁縫部屋、アイロン室、食器室など中央:北側の小さな部屋 パントリー(食品・皿の収納)、下働きの脱衣室、 燃料置き場など左:角の突き出た構造 火の気のある作業空間:ベーカリー、洗濯炉、キッチン可能性ズームして。観光客向けには「Muckross Traditional Farms」や「Servants’ Quarters」見学の出入り口ともなっている場所。マックロス・ハウス正面の芝生エリアと庭園との中間地点にあった巨木。大きなツツジ属(Rhododendron)または西洋イチイ(Yew)の一種か??この建物は、マックロス・クラフトセンター(Muckross Craft Centre)およびガーデン・レストラン(Garden Restaurant)で、マックロス・ハウス観光の拠点のひとつ。内部の様子。クラフトショップ:アイルランド伝統工芸品、マックロス製ツイード製品、手織りスカーフ、陶器、ぬいぐるみなどが販売されていた。「Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)」の案内看板。上記案内板に従って進む。「Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)」の見学を4人で行うこととした。「Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)」の位置は下記写真中央左側に。アイルランドの1930~40年代の農村生活を忠実に再現した野外博物館で、Killarney National Park(キラーニー国立公園)内のMuckross House(マックロス・ハウス)敷地の南西部に位置。徒歩にても、1~2時間で可能とのことであったが、シャトルカート(13€/人)を利用。途中、シャトルカートから様々な品種のニワトリの姿が。循環運行しているシャトルカートを下りて農村民家(コテージ)の見学を。Muckross Traditional Farms内に再現された典型的なアイルランドの農村民家(コテージ)のひとつ。このような建物は、1930年代から1950年代にかけての小作農民(smallholders)や自作農の住居を再現したもので、アイルランドの田園生活を伝える重要な展示物。農村民家(コテージ)の内部に入る。左側の黒い箱状のものは飼槽。干し草や飼料(オート麦など)を入れるためのトラフ。3つに仕切られており、複数の動物が同時に食べられるようになっていた。右側の木の棒は家畜、特に牛や馬を繋ぐための棒。縄や革帯で結びつける と。伝統的な農家の暖炉(Hearth)。19世紀アイルランドの農家における生活の中心となる場所で、調理・暖房・団らんがここで行われていたのだ。鉄製の吊り鍋。スープやポリッジ(粥)、煮物、ジャガイモなどを調理。また、パン(soda bread)は鉄板(griddle)またはこの鍋で焼かれていた と。写真上部のチェック柄の布に洗濯物が干されているように、衣類の乾燥や保存食品の燻製にも使われた。再現されている農家の寝室(ベッドルーム)。再現されている農家のキッチン/食器棚(dresser)。「セトルベッド(settle bed)」または「ボックスベッド(box bed)」と呼ばれる、19世紀から20世紀前半にかけてのアイルランドやスコットランドの農村家庭に見られた伝統的な多機能家具。昼はベンチや収納箱として使い、夜はベッドとして使用。使用者は主に召使いや子ども、時に家族の年長者や農場の手伝い人 と。Muckross Traditional Farms内の伝統的なジャガイモ畑(Potato Plot)。18〜19世紀のアイルランドの農村民の主な栄養源・主食はジャガイモであった と。再び、シャトルカートに乗り移動。Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファームズ)にあるSchoolhouse(田舎の小学校)を見る。石灰を塗って消毒・防湿した典型的なアイルランドの建築。煙跡が残る暖炉。農家の納屋(barn, outhouse)。典型的なアイルランドの茅葺き農家(thatch cottage)。1930年代ごろの農村中流家庭の典型的な生活空間が再現されているのだと。この空間は「キッチン兼居間(Kitchen/Living Room)」として機能していた場所。アイルランドの伝統家屋では、この1部屋が家庭生活の中心であった。暖炉上の額縁には、宗教的な絵(聖人など)が飾られており、信仰心が生活に深く根付いていたことがわかるのであった。この農家の奥にも伝統的なジャガイモ畑(Potato Plot)があった。アイルランドの伝統的な山羊(ヤギ)。Old Irish Goat(オールド・アイリッシュ・ゴート)か?かつてのアイルランド農村における作業場や納屋(Barns and Outbuildings)が並ぶエリアへ。Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファーム)に展示されている19世紀末から20世紀初頭の馬車(ホースドローン・カート/キャリッジ)のコレクション。左側:黒い馬車(幌付き)・ヴィクトリアン・キャリッジ(Victorian Carriage)の一種・前部に御者席(ドライバー用)があり、背面は屋根付きの客室スタイル・社交用・移動用の上流階級の乗り物・赤い車輪、装飾されたシート、黒光りするボディは高級感を表現右側:緑とピンクの馬車(キャンバス幌付き) スプリング・トラップ(Spring Trap)またはシャンドリー(Shandry)*と呼ばれる実用的な馬車 ・軽量設計で、荷物の運搬や市場への移動に使用 ・幌(ほろ)は雨除けの簡易布カバーで、農家の日常生活向け ・車輪やシャフト部分は木製で、鉄枠が補強されている構造19世紀末から20世紀初頭の脱穀機(Threshing Machine)。アイルランドの農村地域における穀物収穫後の処理作業に不可欠な大型農機具。・麦、オート麦、小麦などの穀物の脱穀・脱穀とは、収穫した穀物の穂から粒を分離する作業のことアイルランドの伝統的な農家における屋内の馬小屋(厩舎/stabling area)に繋がれたロバ(donkey)。伝統的な農家または労働者住宅(labourer's cottage)。農家労働者や小作人の家族が住んでいた建物であろう。ゲーリックフットボール(Gaelic Football)👈️リンク用のH型ゴールポスト。ゲーリックフットボールは、アイルランド発祥の手も足も使えるサッカーのようなスポーツ。400年以上の歴史があり、アイルランドで最も人気のある伝統的なスポーツ。ゲーリックフットボールのルール・ボールは手に持って移動できる。その際の移動範囲は4歩までと決まっており、ボールを バウンドさせることにより更に4歩進むことが出来る。ただしこれが許されるのは1回まで。・上記規定の移動範囲内で、ボールを蹴るかフィスト・パス(ボールを掌か拳で打つパス)に よって味方プレイヤーにパスが出来る。・このパスは自分自身に対しても有効である。これを行うことでプレイヤーはボールを持った まま9歩まで進むことができる。・サッカーのオフサイドのような制度はない。・相手が持っているボールを手ではじいたり、ショルダータックルは認められるが、ラグビーの ように体全体でタックルすることは認められない。ラグビーのようなスクラムも存在しない。・得点はH型ゴール(ラグビーのゴールポストにほぼ同じ)の上の空間にボールを蹴り通すか、 ゴールポストの下のゴールネット(サッカーのゴールネットにほぼ同じ)の部分にボールを 入れることで得点となる。ゴールポストを超えて得点すれば1ポイント、ゴールネットに ボールを入れるとゴールとなり3ポイントが得られるが、サッカーのようにゴールキーパーが ゴールマウスを守っている。下記写真はネットから。アイルランドの伝統的な農村家屋(ファームハウス)がここにも。アイルランドの伝統的な農家の居間を再現した展示。「小作農の家(Cottier’s House)」の台所。寝室。寝室内にある鏡付きドレッサー(化粧台)の上をズームして。ここには、カトリック信仰と家庭文化の象徴的なアイテムが集められていた。・赤いガラスのランプ 石油ランプ(オイルランプ)で、電気が普及する前の照明器具。赤いシェードは暖かみの ある光を演出し、室内の雰囲気を柔らかくします。・イエス・キリスト像 衣を開いて聖心(Sacred Heart)を示す姿のキリスト像。これはカトリック信仰で 「イエスの愛と慈しみ」を象徴する重要なモチーフで、特に家庭内での信仰の証として 飾られました。・ガラスの花瓶と花 家庭の愛情や日常の美を表現するため、野花や庭の花がこうして飾られていたことも多く あります。清潔さや迎える心の象徴でもあります。・鏡に映る部屋 鏡にはベッド、暖炉、そして壁に掛けられた十字架や聖母子像らしき額縁が映り込み、 部屋全体が信仰心と家庭の温もりに包まれている様子が見て取れます。中流農家の居間(Parlour / Dining Room)。庭にはカラーの白き花が。そして再びシャトルカートに乗り込み帰路に。Muckross Traditional Farms(マックロス・トラディショナル・ファーム)の敷地内にある鍛冶屋(Blacksmith's Forge)を振り返る。石造りの納屋(barn)を振り返って。そしてビジターセンター(受付・案内所)まで戻りシャトルカートを下りる。ビジターセンター(受付・案内所)の前庭にあった農具(スピット=spade)を手にした農夫の像 を再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.24
コメント(0)
-
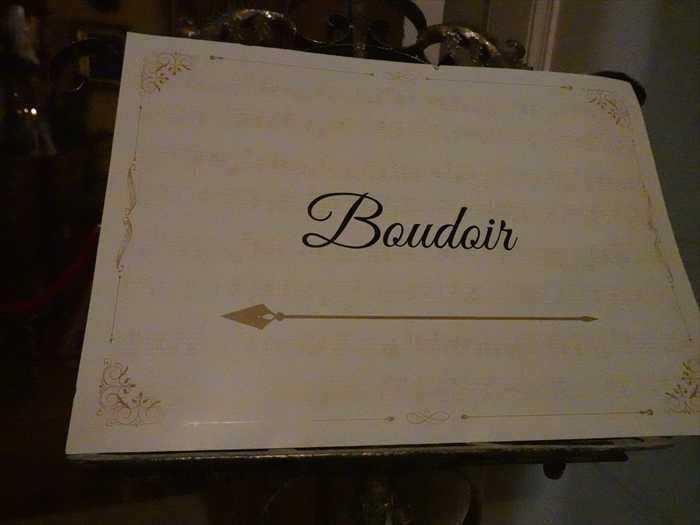
アイルランド・ロンドンへの旅(その56):Muckross House・マックロス・ハウス(3/4)
「Muckross House・マックロス・ハウス」内の散策を続ける。案内板には 「Boudoir(ブドワール)」 と.「Boudoir(ブドワール)」とは、特に18世紀から19世紀のヨーロッパ貴族・上流階級の女性たちの私室・化粧室・控えの間を意味するとのこと。マックロス・ハウスの「Boudoir(ブドワール)」内部の様子。中央の丸テーブル:文机あるいはティーテーブルとして使われていた。 開かれた本は客間の装飾でもあり、家の「教養」を示すものでもある。テーブル上の花とティーセット:ブドワールでは客人(親しい女性など)とのお茶会も行われた。 花は当時の「花言葉」や季節感を大切にした文化の象徴でも あります。左奥のハーブ:上流階級の女性が習うべき教養の象徴。ピアノやハープはよくブドワールに 置かれていた。肘掛け椅子と張地の刺繍:小さな社交や読書、刺繍などのための椅子。柔らかく豪華な布地は 女性のための空間を演出します。食器棚(中央奥)と小机:陶器やガラス器の展示用であり、持ち主の趣味と品位を誇示する家具 でもあった。カーテン(左):重厚で豪華なドレープが特徴。外界からのプライバシーを守るだけでなく、 部屋全体の格式を高めている。このブドワールは、おそらく やMaud Bourn Vincent の時代(19世紀末〜20世紀初頭)のもの。左:ヴィクトリア女王(Queen Victoria)右:アルバート公(Prince Albert)天蓋付きベッド(Canopy Bed) : カーテンがかかっており、冬の寒気や虫除け、プライバシー確保のために使われました。 木製のヘッドボードとフットボードは彫刻入りで高級感があります。ラウンドテーブルと椅子セット : 手紙を書いたり、朝食・ティータイムなどに使われたもの。 上流家庭では主寝室にもこうした社交用の机が置かれていました。天蓋付きベッド(Canopy Bed) に近づいて。ベッド上に置かれたいたのはとげのついた金属製の道具。この金属製のとげ道具は、「ベッドテスター(bed tester)」または「夜具検査用トゲ」と呼ばれる再現された展示物。想定される目的は・召使いによる「ノミ・シラミ」チェック: 19世紀の富裕層の寝室では、召使いがベッドに「とげ」や「硬いブラシ」などを用いて、 寝具に害虫(ノミ、シラミなど)がいないか確認していました。 とげはリネンの上を軽く押し当てて、害虫の有無を検査する手段の一つ。・「鉄のとげ」による目印や見張り: 一部の展示では、ベッドが使用中ではないことを示すために置かれている場合もあり、 「手を触れないでください」の注意喚起の意味合いを含む。 ・19世紀の「プランクベッド」や「ノブ付きマットレス」用装飾具: ある時代には、病院や上流階級の寝具に、患者や主人の寝位置のマーキングとして「突起」や 「くぼみ」付きの器具が用いられたこともあった と。マックロス・ハウス(Muckross House)主寝室の暖炉周辺。暖炉(マントルピース)素材は黒い大理石またはペイントされた木製で、ヴィクトリア時代の上流階級住宅によく見られるデザイン。上部には、金色の装飾が施された楕円形の鏡が取り付けられており、部屋を広く明るく見せる意図があったと考えられる。「ガラスケースに収められた「装飾扇子(ファン)」 。ビクトリア朝時代の陶器類。「メイドや使用人のための控えの部屋(Servants’ Sitting Room / Housekeeper’s Room)」「召使い呼び出しベル(servants’ bell system)」 。右にはNORTH EAST BED ROOM(北東寝室)と。この部屋から紐を引くと、対応するベルが鳴る仕組み。ワインセラー(wine cellar)。アーチ型の天井で、石造りで湿度が保たれるように設計されており、ワイン貯蔵に適した環境。断熱性と温度安定性の高い地下構造。ヴィクトリア朝時代の火災警報ベル(Fire Alarm Bell)あるいは召使い呼び出し用ホーン(Servant’s Call Horn)の一種。主人が部屋のボタンや引き紐を引くと、各部屋に対応したベルが鳴る仕組み。使用人用の食堂(Servants’ Dining Room)。召使い階層の中でも上級の使用人(HousekeeperやButler)とその下のスタッフたちが出入りする部屋であろう。鋳鉄製の調理レンジ(Cast Iron Kitchen Range)燃料は石炭(coal)を主に使用し、下部の焚き口で火をおこす。煉瓦でアーチ状に囲まれた開口部にレンジがはめ込まれており、暖炉と調理機能を兼ねた特徴的な構造。ヴィクトリア朝時代の台所で日常的に使われていた鋳鉄や銅製の調理器具。ヴィクトリア朝末期~エドワード朝初期(おそらく1890~1910年代)のスポーツ用具を展示したキャビネットであり、マックロス・ハウスのような邸宅の使用人階層や家族のレクリエーション活動を示すもの。左上:ラクロススティック メッシュ付きのフレームで、ボールを受けたり投げたりするためのもの。 ラクロスはカナダの先住民に起源をもち、19世紀末に英国貴族社会で人気となった。左下:ペタンクまたはボッチャ的な道具 棒付きの金属的ディスク → 距離測定か、クロッケーのピン類似品?右下:ゴルフクラブとゴルフボール クラブは木製シャフト、金属ヘッド。20世紀初頭の形状。 アイルランドでは19世紀後半から貴族階級でゴルフが盛んだった。 フラッグ「5」「8」が添えられており、邸宅敷地内のホール番号を示すマーカーか。アーチェリー(弓術)の的。クラシックなアーチェリーターゲット色の構成:黄色(中心)→赤→青→黒→白という5色同心円は、イギリス式ターゲットに典型的。材質:中心のマットは、ワラ(藁)またはシュロ繊維を巻いた円形構造に布を被せた伝統的な仕様。ヴィクトリア朝〜エドワード朝時代の油ランプ(オイルランプ)のコレクション展示さまざまな形・色・素材のランプが並べられており、当時の生活や美意識を垣間見ることができるのであった。電気が普及する以前、照明は家庭の中で非常に重要なインフラであり、ランプは用途や場所によって使い分けられていたのであろう。クロッケット(Croquet)の用具が展示されているガラスケース。ヴィクトリア朝時代の上流階級の家庭で人気だった屋外娯楽スポーツに使われていた本物の用具。調理台の上に並べられた野菜の模型。セロリ(celery)、小玉キャベツ(cabbage)、レタス(lettuce)またはロメインレタスに似た野菜、ブロッコリー(broccoli)と思われる濃緑の野菜マックロス・ハウス(Muckross House)のキッチン(厨房)展示室の一部であり、ヴィクトリア時代の大邸宅の厨房の様子を忠実に再現したもの。壁の棚にずらりと並ぶのは銅鍋・銅やかん・銅ボウルなどの 銅製の調理器具。銅製の大鍋(copper cauldron or copper jam pan)に近づいて。素材は純銅、内側は錫メッキされているのであろうか?中央の作業台には・回転式のスライサー(手回し式):チーズ、リンゴ、じゃがいもなどを薄くカット。・陶磁器製の器やカバー付き皿:料理の保温と衛生管理に使用。・アイアン製フードカバー(ドーム型):調理済みの料理を保温する蓋で、虫除けや冷却防止などが展示されていた。パントリー(食品貯蔵室)の一角には保存容器類が並ぶ。棚の上段に並ぶ透明なガラス瓶は、ジャム、果物、ピクルス、乾燥ハーブなどを保存するためのもの。棚の中段に並ぶ茶色とベージュの二色使いの容器は、イギリスやアイルランドでよく見られたストーンウェア(石器陶器)ジャーで、内容物はバター、塩、ラード、ピクルス、シロップ漬け果物、ビネガー、麦芽エキス、マスタード など・・・・と。ドーム型の金属製フードカバー(food domes / meat covers)。温かい料理や煮込み料理などをテーブルに出す際、温度を保つため、埃や虫を避けるためのものであろう。19世紀〜20世紀初頭の陶製ドリンクボトル。銘柄:Wheatley’s Old Style Brewed Ginger Beerジンジャービールは19世紀に英国で人気だった炭酸飲料で、ノンアルコールまたは低アルコールの発酵飲料。このような陶器製ボトルは、炭酸を逃さないために使われていたのであろう。19世紀末から20世紀初頭にかけて使用されていた「手回し式洗濯機(ロータリー式洗濯ドラム)」手動式ローラー脱水機(mangle または wringer)。左側に写っているのは、おそらく大型の洗濯用ボイラー(copper boiler)。「Muckross Weavers(マックロス織工房)」の看板。「Muckross Weavers(マックロス織工房)」は、アイルランドの伝統的な手織物(ハンドウィーブ)の技術を守りながら、マックロス・ハウス(Muckross House)の敷地内で営業している工房兼ショップ。奥の壁一面(左)には、様々なデザインの帽子がずらりと並んでいた。ツイード素材のフラットキャップ(ハンチング帽)やバケットハットなど、男女問わず人気のあるスタイルが並んでいた。手前のテーブルには、手編み風のニット帽やカラフルなスカーフもあり、季節に応じた商品展示。手前には、カラフルなウールスカーフやマフラーが積まれており、紫系・青系・チェック柄など、アイルランドの伝統的な色使いが目立っていた。かごの中にはぬいぐるみ(羊モチーフやアルパカのようなデザイン)が多数並び、観光客向けの土産にも人気。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.23
コメント(0)
-
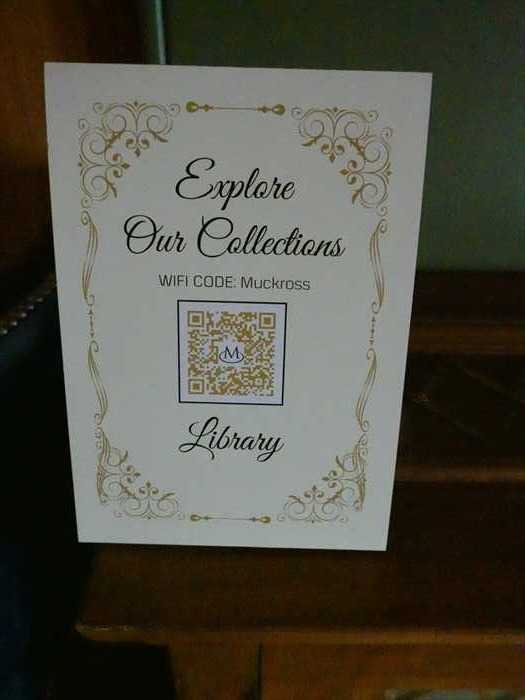
アイルランド・ロンドンへの旅(その55):Muckross House・マックロス・ハウス(2/4)
さらに、Muckross House・マックロス・ハウス内の散策を続ける。「Explore Our Collections(私たちのコレクションを探訪してください)」という案内。マックロス・ハウス(Muckross House)内の「Library(図書室)」。壁一面の本棚。背の高い木製の書棚が部屋の壁を覆い、色とりどりの古書がずらりと並んでいた。19世紀の英国貴族の典型的な書斎のような様式で、学術的・装飾的両面で重厚感が。手前にあるクラシックなソファは、英国スタイルを象徴するチェスターフィールド型で、格式高い雰囲気を醸し出していた。約2,000冊以上の本が革装・金箔装飾・布装丁で並び、主に以下のジャンルをカバー。・古典文学(英・仏・ラテン語)・歴史書(イギリス史、アイルランド史、ローマ史など)・宗教書(聖書、説教集、教父文献など)・自然科学(博物学、植物、天文学)・旅行記や地理書(当時の探検記も含む)・美術・建築に関する図録・版画集この図書室は、Muckross House(マックロス・ハウス)の内部にある展示室の一つ。ビクトリア時代に建てられたこの屋敷は、現在は博物館として公開されており、当時の上流階級の生活様式を再現した内装・家具・蔵書などがそのまま保存されていたのであった。天井は格子状の装飾パネル(コファード天井)となっており、ビクトリア時代の上流階級建築に典型的な意匠であると。天井と壁の境界にはスタッコ(漆喰)による細かい葉模様の装飾が施され、豪奢(ごうしゃ)な印象を与えてくれたのであった。「Mr. William Bowers Bourn(ウィリアム・バワーズ・ボーン)」の肖像画。アメリカ・カリフォルニア州の大富豪で、ボーン・ヴィンセント家(Bourn Vincent family)の当主。ボーン氏はカリフォルニア州のEmpire Mine(金鉱山)の所有者として知られ、莫大な富を築いた人物 と。1911年、マックロス・ハウスを娘マウドと娘婿アーサー・ヴィンセント(Arthur Rose Vincent)夫妻のために購入。その後、家族の悲劇(娘マウドの若年死)を経て、1932年にマックロス・エステートをアイルランド政府に寄贈した と。マックロス・ハウスのこの図書室は、19世紀中頃のアイルランド貴族の邸宅における知的・社交的中心空間として設計された。この部屋は単なる読書スペースではなく、「学問・芸術・人付き合い」の場でもあったとのこと。図書室(Library)を別の角度から。左側に大理石の暖炉と金色鏡(オーバーマントルミラー)、暖炉上には花瓶・燭台・陶器などが展示され、花束も飾られていた。キャンドルが2本灯されているクラシカルな燭台があり、その中心には片腕を上げたブロンズ風の人形彫刻が配置されていた。その右には、おそらく歴代の所有者や家族の肖像画などが。右側の燭台とディスプレイ。King Charles II(チャールズ2世)の文字が。チャールズ2世(Charles II, 1630–1685)とは?・イングランド、スコットランド、アイルランドの王(在位:1660年~1685年)。・ピューリタン革命(清教徒革命)後、父チャールズ1世の処刑を経て、王政復古によって即位。・宮廷文化の復興、科学アカデミーの支援(王立協会の設立)などで知られる と。次の部屋は「Billiard Room」。壁面の装飾は鹿の角(トロフィー)。壁の高い位置に立派な鹿の角を2対掲げており、これは狩猟の戦利品(ハンティング・トロフィー)。こうした飾りは、ヴィクトリア朝以降の貴族的アウトドア趣味の象徴であり、特に「Game Room(猟の部屋)」や「Dining Room(食堂)」に多く見られる と。中央には大きな装飾壺、周囲には絵付けされたプレート(皿)が美しく配置されていた。釣りの戦利品としての魚の剥製(サーモン)が下部に飾られていた。別の展示棚であり、さらに豪華で細密な木彫装飾が。そして、青白磁の皿(デルフト風)、伊万里様式風の皿、東洋・洋風を融合させた様々な図柄のプレートが。この展示棚下部のガラスケースにも中型の魚(ブラウントラウト?)の剥製が。左の壁面には18世紀〜19世紀の海戦画、帆船画が4枚飾られており、これは英国貴族の男性的趣味「戦史・軍艦・征服・植民地支配」の象徴であったのだろう。そいて中央にビリヤード台が。移動して。右の額には大きく 「BILLIARDS」 の文字が。これはビリヤードに関する解説文またはルール説明??他の額縁もすべて文章形式で、ビリヤードのルール、マナー、歴史などが解説されている??William Bowers Bourn(ウィリアム・バワーズ・ボーン)の肖像画。・アメリカ・カリフォルニアの鉱山王(Empire Mine所有者)・娘モード・ボーン(Maud Bourn)のために1911年、マックロス・ハウスを購入・娘の早逝(1929年)をきっかけに、1932年にマックロス・エステートを アイルランド政府に寄贈・現在のマックロス・ハウス博物館化の礎を築いた人物そして「メインホール(Great Hall / Entrance Hall)」来館者がまず足を踏み入れる場所であり、建物全体の格式と上流階級の生活様式を象徴する空間。このホールは、建物内での中心的な交差点 ・正面奥右手 → ビリヤードルーム ・階段上 → 主寝室階・展示ギャラリー ・左側 → 図書室、朝食室、ドローイングルーム等カーペットは赤地に金の菱模様の絨毯=格式の象徴。階段にも同柄が続く。木製の壮麗な階段は2階ギャラリーへと通じており、光の入る大窓が設置されていた。天井中央に大型のクリスタルシャンデリア。「Stairs(階段)」案内。メイン階段(Main Staircase)を見上げて。直線+踊り場+直線というL字型の典型的な大邸宅スタイルで、登りながら階下全体を見渡せるようになっていた。手すり部分はツイスト(ねじり)状の挽物(ひきもの)細工で装飾された重厚な木製バラスター(欄干柱)。2階にあったのが「Master Bedroom(主寝室)」。廻り込んで。壁には格式高い服装をした人物の肖像が飾られ、部屋の由緒ある性格を示していた。。豪華な陶磁器の壺(花瓶)は「ドイツのマイセン様式やフランスのセーヴル磁器の影響を受けたものか!?。鹿の頭部の壁飾りにあった。ヴィクトリア朝時代特有の重厚で華やかな柄の絨毯(カーペット)。ベッドの上部には立派な天蓋(キャノピー)があり、側面に美しいカーテンが付いていた。寒さや虫から身を守るためだけでなく、プライバシーの確保や装飾的要素としても重視された。ベッド左側にある3連の衝立(スクリーン)は、着替えやプライベートな作業時に目隠しとして使われたのせあろう。「主寝室(Master Bedroom)」内の窓際に設けられたティーセット付きの小卓。足元のカーペットは、ヴィクトリア朝の「Axminster(アクスミンスター)スタイル」に似た幾何学文様。木製のヘッドボードとフットボードを持ち、青緑色のダマスク柄の布で囲われた天蓋(キャノピー)が特徴的。二脚のアームチェアと一つの足置き(オットマン)が。そして、隣接するNursery(子ども部屋・育児室)へ。写真右手前には小型のベッドが。サイズや高さから見て子供用ベッドであり、幼少期の子どもたちが使用していたもの。白を基調とした軽やかな装飾とシンプルなアイアンまたは木製の構造が特徴。写真左中央には、長方形の小さな角テーブルと、背の低い子供用の椅子が4脚ほど並べられて。手前の白木ベッド(シングル)子ども用。中央にはダークウッドの乳幼児用の柵付きベビーベッド。このような部屋の構成から見て、この空間は単なる「子どもが寝る場所」ではなく、育児・教育・日常生活がすべて行われるNursery(ナーサリー)として設計されていた と。19世紀のアイルランドやイギリスの大邸宅では、上流階級の子どもたちは専用の部屋(Nursery)でナニー(乳母)やガヴァネス(家庭教師)と過ごすことが一般的であった と。「Master Bedroom(主寝室)」に付随するドレッシングルーム(更衣室・洗面室)。左手前には木製の便器チェア(commode chair)。実用的な家具付きトイレ。蓋つき椅子に陶器製のポット(便器)が組み込まれていたのだと。現代の水洗トイレ普及以前に上流階級の室内用として使用された と。中央左には、白い楕円形のバスタブ。ポータブルな寝室用バス(hip bath)。給仕人が湯を運び入れて使用した と。木製の便器チェア(commode chair)に近づいて。左端の肖像画は女性の胸像で、当時のドレスと髪型からヴィクトリア朝中期〜後期の人物か?マックロス・ハウスの歴代の住人の女性の一人か?。中央の風景画2点は湖や山、森を描いたアイルランドの風景画と思われ、ケリー州周辺の景勝地を描いた作品か?。「Emily Julia Keane(エミリー・ジュリア・キーン)」 この女性は、マックロス・ハウスの初代当主ヘンリー・アーサー・ハーバート(1815–1866)の息子、ヘンリー(ハリー)・アーサー・ハーバート(1840–1901)の妻です。すなわち、マックロス・ハウスにおける第2世代の女性当主にあたります と。「Emily Julia Keane (1848 – 1911)wife of Captain Henry (Harry) Arthur Herbert(1840–1901,by John Butler Yeats.」 【エミリー・ジュリア・キーン(1848年–1911年)ヘンリー(ハリー)・アーサー・ハーバート大尉(1840年–1901年)の妻ジョン・バトラー・イェイツによる作品】「The Herberts of MuckrossLarge areas of Munster were seized by the English Crown following the collapse of the Desmond Rebellion in 1583.Three years later Queen Elizabeth I granted lands at Castlelough, near Killarney,to the Welshman Sir William Herbert of St. Julians.By the early eighteenth century members of the Herbert family had settled at Muckross.Henry Arthur HerbertHe was the eldest son of Charles John Herbert (1785-1823) and his wife Louisa Middleton (1796-1828).Henry Arthur Herbert was born at Muckross.By the time Henry was thirteen years of age his parents and younger brother, Charles, had died. Having spent much of his early years in England, Henry inherited the Muckrossestate in 1837 and immediately set about improving the estate. He built new farmbuildings, school and a church in Cloghereen (Muckross) village.Cloghereen (Muckross) July 1833」 【マックロスのハーバート家1583年、デスモンドの反乱の崩壊後、イングランド王室はマンスター地方の広大な土地を接収しました。その3年後、エリザベス1世はキラーニー近郊のキャッスルローの土地を、セント・ジュリアン出身のウェールズ人、サー・ウィリアム・ハーバートに与えました。18世紀初頭までには、ハーバート家の一族がマックロスに定住していました。ヘンリー・アーサー・ハーバートはマックロスで1815年に生まれました。彼はチャールズ・ジョン・ハーバート(1785–1823)とその妻ルイーザ・ミドルトン(1796–1828)の長男として生まれました。ヘンリーが13歳になるまでに、両親と弟チャールズはすでに他界していました。若年期の多くをイングランドで過ごした彼は、1837年にマックロスの領地を相続し、直ちにその改良に取り組みました。彼は新しい農場の建物、学校、そしてクロヒリーン(マックロス)村に教会を建設しました。クロヒリーン(マックロス) 1833年7月】「Mary Balfour & Henry Arthur HerbertMary (1817–1893), daughter of James Balfour and Lady Eleanor Maitland of East Lothian, Scotland was a talented writer and artist.She met Henry Arthur Herbert (1815–1866), while holidaying in Rome with her familyduring the winter of 1835.Charles Balfour had helped to educate Henry at Cambridge University and was thenenjoying a European tour.James Balfour agreed to the marriage of his daughter Mary to Henry as he consideredthe latter to be a responsible, intelligent and admirably wealthy young man.The young couple were married by William Gladstone at the Balfour family home,on the 25th of September 1837.Upon their return to Muckross, Henry and Mary lived in Torc Cottage, before moving into a house that stood at the foot of Torc Mountain.Soon afterwards, William Burn, the Scottish architect, was engaged to design the present Muckross House, which was completed in 1843.」 【メアリー・バルフォアとヘンリー・アーサー・ハーバートメアリー(1817年–1893年)は、スコットランドのイースト・ロージアン出身のジェームズ・バルフォアとレディ・エレノア・メイトランドの娘で、才能ある作家・芸術家でした。彼女は1835年の冬、家族と共にローマで休暇を過ごしていた際に、ヘンリー・アーサー・ハーバート(1815年–1866年)と出会いました。チャールズ・バルフォアはケンブリッジ大学でのヘンリーの教育を助けた人物で、そのときはヨーロッパ旅行中でした。ジェームズ・バルフォアは、ヘンリーのことを責任感があり、知的で、非常に裕福な若者だと考え、娘メアリーとの結婚を承諾しました。若い2人は1837年9月25日、バルフォア家の邸宅でウィリアム・グラッドストン(※後の英国首相)によって結婚式を挙げました。マックロスに戻った後、ヘンリーとメアリーはまずトーク・コテージに住み、その後、トーク山の麓にあった邸宅に移り住みました。その後まもなく、スコットランド人建築家ウィリアム・バーンが現在のマックロス・ハウスの設計を依頼され、1843年に完成しました。】「Muckross – the mid-19th CenturyHenry and Mary enjoyed a high social profile.Henry was elected to the Irish Parliament in 1847 and briefly occupied the position ofChief Secretary for Ireland in 1857.The high point of the Herberts' ownership of Muckross was the visit of Queen Victoria, with members of her family, in August 1861.Thereafter, Henry appears to have suffered from ill-health and he died in February 1866.Mary and Henry had four surviving children.Their eldest son, the so-called Harry, but whose real name was Henry Arthur Herbert(1840–1901), inherited Muckross.Soon after his father's death, Harry married Emily Keane, in 1868, and his mother Maryalso settled in London.Harry and Emily had three children together but were divorced in 1882.」 【マックロス ― 19世紀中頃ヘンリーとメアリーは非常に高い社会的地位を享受していました。ヘンリーは1847年にアイルランド議会の議員に選出され、1857年には短期間ながらアイルランド主席秘書官の職にも就きました。ハーバート家によるマックロス所有の最高潮は、1861年8月にビクトリア女王とその家族が訪問したことでした。その後、ヘンリーは健康を害し、1866年2月に亡くなったとされています。メアリーとヘンリーには4人の子どもが生き残りました。長男は「ハリー」と呼ばれましたが、本名はヘンリー・アーサー・ハーバート(1840–1901)で、マックロスを相続しました。父の死後すぐの1868年、ハリーはエミリー・キーンと結婚し、母メアリーもロンドンに居を構えました。ハリーとエミリーは3人の子どもをもうけましたが、1882年に離婚しました。】この肖像画の人物は「EDWARD AMPHLETT 1824~1887」。ネットから。マックロス・ハウスとは深い結びつきがある人物であるとのこと。「Muckross: the late 19th CenturyFrom the 1870s onwards the Muckross Estate was heavily mortgaged to the Standard Life Assurance Company of Scotland.Following his divorce, Mary Herbert spent time in America and Muckross was let out for its hunting, shooting and fishing.Retired Captain Edward Amphlett periodically leased the estate for this purpose in the late 1870s and 1880s.So too did Mr. Ralph Sneyd, who left the estate in the late 1890s.The Standard Life Assurance Company foreclosed on the Herbert mortgage in 1898. A year later, following another auction that gave rise to Lord Ardilaun, of the Guinness brewing family.He, in turn, sold it in 1911 to Mr. and his wife Agnes. They presented Muckross as a wedding present to their daughter Maud, upon her marriage to Arthur Rose Vincent of CooIanla, County Clare.Following Maud’s early death her parents gifted Muckross to the Irish people.」 【マックロス:19世紀後半1870年代以降、マックロス・エステートはスコットランドのスタンダード生命保険会社に対して多額の抵当権が設定されていました。メアリー・ハーバートが離婚した後、アメリカに滞在することが多くなり、その間マックロスは狩猟・射撃・釣りの目的で貸し出されました。退役大尉エドワード・アンフレット(Edward Amphlett)は、この目的で1870年代後半から1880年代にかけてこの地所を借りていました。その後、ラルフ・スニード氏(Ralph Sneyd)も利用し、1890年代後半に退去しています。1898年、スタンダード生命保険会社はハーバート家の抵当権を差し押さえました。翌年のオークションでは、ギネス醸造家一族のロード・アーディローン(Lord Ardilaun)が購入しました。彼はその後、1911年にマックロスをボーン氏とその妻アグネス(Agnes)に売却しました。夫妻はこれを娘モード(Maud)への結婚祝いとして贈り、彼女はクレア州クーランラのアーサー・ローズ・ヴィンセント(Arthur Rose Vincent)と結婚しました。モードが若くして亡くなった後、両親はこの地所をアイルランド国民へ寄贈しました。】マックロス・ハウス(Muckross House)内の「Children's Staircase(子どもたちの階段)」と呼ばれる階段の上部の様子この階段はおそらく、子ども部屋やナーサリー(nursery)に通じる使用人階段的な役割を果たしていたと考えられます。階段を下る。「Children's Staircase(子どもたちの階段)」の下り方向を撮る。マックロス・ハウス(Muckross House)内に復元・展示されているヴィクトリア時代のトイレ(化粧室)の一室。白い陶製の基礎台(pedestal)の上に、木製の便座と蓋が載せられていた。背後には木製のタンクがあり、内部に水を蓄える構造 と。(early flushing toilet の初期型)。このタイプの便器は19世紀後半~20世紀初頭にかけて広く使用され、上流階級の邸宅に多く見られたのだ と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.22
コメント(0)
-
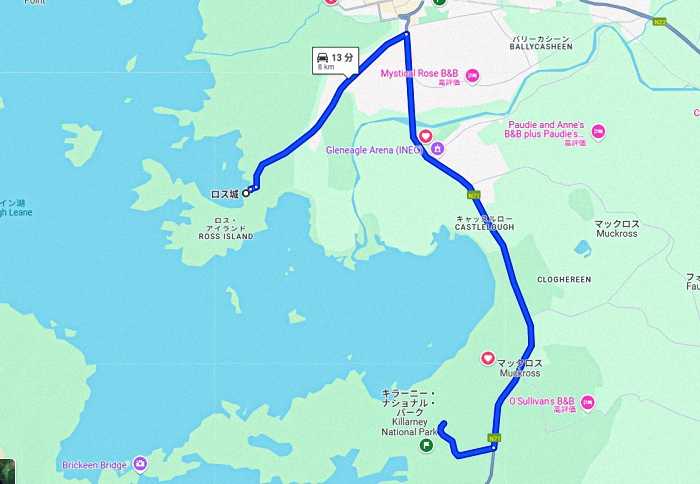
アイルランド・ロンドンへの旅(その54):Muckross House・マックロス・ハウス(1/4)
次に訪ねたのは「キラーニー国立公園内」にある「Muckross House・マックロス・ハウス」。ROSS城から「ロス・ロード」そしてN71・リンダ・オブ・ケリーを利用して13knm、約15分で到着。「キラーニー国立公園内」にある「Muckross House・マックロス・ハウス」の正門。キラーニー国立公園内にある「真ん中の湖」湖畔にある広大な邸宅で、19世紀に領主のヘンリー・ヒューバートがヴィクトリア女王を邸宅に招待し、爵位を貰おうと造らせたのだが、女王が夫の急病のため途中で帰ったので爵位を貰えなかったというエピソードがある。緑が多い周囲の風景に溶け込んだヴィクトリア朝の建物。現在では邸宅内の公開、庭園内の散策などが出来、ミュージアムショップやレストランなどが併設された複合施設になっていた。 正門から、駐車場まで約1kmくらいの森林が続いていた。そして駐車場に車を駐め散策開始。ビジターセンター(受付・案内所)が左側に。前庭にはシャベルを手にした農夫の姿が。ビジターセンター(受付・案内所)で13€/人≒2200円/人のチケットを購入。やや高価な入園料なのであった。Muckross Traditional FarmsまたはMuckross Houseの敷地内に設置された「インフォメーション・キオスク(案内小屋)」であっただろうか!? Killarney National Park /Muckross House & Gardens の公式マップ(観光案内板)。番号 名称 内容1 Muckross House 邸宅(本館)2 Entrance to House ハウスの入口3 Gift Shop / Restaurant ギフトショップ・レストラン4 Traditional Farms Entrance トラディショナル・ファームズ入口5 Coach Park 観光バス駐車場6 Craft Workshops クラフト体験工房7 Camper Van Park キャンピングカー駐車場8 Jarvey Stand 馬車乗り場(ジャーヴィー)9 Gardens 庭園エリア10 Rockery 岩園風の造園(ロックガーデン)11 Arboretum 樹木園(植物園)12 Boat House 湖畔のボートハウスMuckross House(マックロス・ハウス)本館の芝生庭園に設置された現代彫刻作品。黒く変色・風化していたが、木製のようであった。タイトル「Echoes(反響、残響)」。作者のJoseph Sloan(ジョセフ・スローン)は、アイルランドまたは英国で活動した現代彫刻家で、自然素材や抽象フォルムを用いた作品で知られていると。。彫刻作品「Echoes(反響、残響)」の先から見た「Muckross House(マックロス・ハウス)本館」。 ・建築様式:チューダー・リヴァイヴァル(Tudor Revival)様式 ・19世紀中頃の流行建築で、石造の重厚な造りと高い煙突群が特徴。・屋根:切妻と急勾配の屋根が組み合わさり、複雑な構造・煙突:高くそびえる複数の石造煙突は、ヴィクトリア時代の邸宅の象徴的意匠・窓:複層構造で装飾の少ない石枠のサッシュ窓・入口周辺:中央に見える淡緑色のドアがサブエントランスまたはスタッフ用入口・背景:マグリリカディ山脈(MacGillycuddy's Reeks)などキラーニー国立公園の自然が広がる移動して。・建設年:1843–1849年・建築家:William Burn(スコットランドの著名建築家)による設計・所有者:もとはヘンリー家(Henry family)、その後ヴィンセント・トワーム家を経て、 1932年にアイルランド政府へ寄贈・特記事項:1861年、ヴィクトリア女王が訪問し、その滞在に備えて大改装が施された と。サービス棟への通用門.Muckross House(マックロス・ハウス)開館60周年(1964–2024)を記念する展示パネル。・1964年 Dr. Frank Mitchell and the Trustees open Muckross House to the public. (フランク・ミッチェル博士と管理団体により、マックロス・ハウスが一般公開される。)・1970年代 Development of craft & stable exhibits (クラフト展示(手工芸)と馬屋の展示の整備が進められる。)・1980年代 Restoration of Muckross House (マックロス・ハウスの修復工事が行われる。)・1990年代 Opening of Muckross Traditional Farms (マックロス・トラディショナル・ファームズ(伝統農場)の開園)・2000年代 Addition of the Garden Restaurant, craft workshops, gift shop & Muckross Archival Centre (ガーデンレストラン、クラフト工房、ギフトショップ、資料アーカイブセンターが 追加整備される。)Muckross House(マックロス・ハウス)受付とチケット売場の案内標識。アイルランドの公式標識は、母国語であるアイルランド語(Gaeilge)を上段・英語を下段に表記することが法律で義務付けられているとのこと。本館のチケット受付棟。緑の扉の右側が入場受付(チケットカウンター)の入り口であり、観光客はここでチケットを購入して館内見学へ進むのであった。Muckross House(マックロス・ハウス)本館の中庭(Courtyard)に面した一角。来訪者の受付・案内機能や展示室、ギフトショップ等が設けられている場所。Muckross House(マックロス・ハウス)の館内見学ルートの出入口付近に設けられた撮影スポット兼入退出案内エリア。Muckross House(マックロス・ハウス)の正面全景写真。Muckross House(マックロス・ハウス)内部のダイニングルーム(Dining Room)を写したパネル。この後に訪ねたのであった。壁紙:深紅のダマスク柄(織物風の高級壁紙) → ヴィクトリア時代中〜後期に流行した豪華装飾スタイル天井:漆喰装飾による幾何学的なモールディング → 吊るされたシャンデリア(クリスタル)との調和が美しい照明:キャンドルスタンド型のランプとシャンデリア → 現代的照明に改装されているが、19世紀の雰囲気を再現Muckross House(マックロス・ハウス)内部の「ハンティング・ホール(Hunting Hall / Trophy Room)」または「玄関ホール(Entrance Hall)」に相当する空間のパネル写真。壁の装飾 鹿の角や剥製が多数掲げられており、狩猟文化(ハンティング・ロッジ)を象徴額装 風景画や肖像画が複数飾られ、邸宅の格式と趣味を示す家具 大型のキャビネット(飾り棚)やアームチェア、丸テーブルなど天井 モールディングで装飾された幾何学天井と中央の大型シャンデリア床 赤地に白のパターンを持つ厚手のカーペット(絨毯)Muckross House & Gardens(マックロス・ハウスと庭園) の由来と所有の変遷を説明する壁面レリーフの一部「Muckross House & GardensCompleted in 1843 for Henry Arthur Herbert and his wife Mary Balfour.Purchased by Lord Ardilaun, of the Guinness family, 1899.Purchased by William and Agnes Bowers Bournas a wedding present for their daughter Maud, 1911.Presented to the Irish People in memory of Maud byher parents and husband, Arthur Rose Vincent, 1932.」【マックロス・ハウスと庭園1843年、ヘンリー・アーサー・ハーバートとその妻メアリー・バルフォアのために完成。その後、ギネス家のアーディローン卿により1899年に購入。さらに1911年、ウィリアム&アグネス・バワーズ・ボーン夫妻が娘モードの結婚祝いとしてこの邸宅を購入。そして1932年、娘モードの追悼として、彼女の両親と夫アーサー・ローズ・ヴィンセントにより、アイルランド国民に寄贈された。】と。大理石製胸像。「Arthur Edward Guinness(アーサー・エドワード・ギネス)初代アーディローン男爵(1st Baron Ardilaun)(1840–1915)」 近づいて。・アイルランドのビール醸造王ギネス家の一族・慈善活動家、政治家、地主として活動・1899年にMuckross Houseを購入・ダブリンのSt. Stephen’s Green 公園を整備して市民に開放した功績でも知られる・タイトル「Baron Ardilaun(アーディローン男爵)」は1880年に与えられたもの「Arthur Edward Guinness1st Baron Ardilaun(1840 – 1915)By Sir Thomas Farrell, R.H.A.」 【アーサー・エドワード・ギネス初代アーディローン男爵(1840年 – 1915年)制作:サー・トマス・ファレル(アイルランド王立美術アカデミー会員)】「Muckross House(マックロス・ハウス)」の歴史を年代順に説明した年表。近づいて。「The Muckross House Story(マックロス・ハウスの物語)1843BUILT BY THE HERBERT FAMILYハーバート家によって建設される1861VISIT OF QUEEN VICTORIAヴィクトリア女王の訪問1866DEATH OF HENRY ARTHUR HERBERTヘンリー・アーサー・ハーバード死去1898FORECLOSURE ON HERBERT MORTGACEハーバード家の抵当権が差し押さえられる1899PURCHASED BY LORD ARDILAUNアーディローン卿が購入1911PURCHASED BY BOURN VINCENT FAMILYボーン・ヴィンセント家が購入1929DEATH OF MAUD BOURN VINCENTモード・ボーン・ヴィンセント死去1933IRELAND'S VERY FIRST NATIONAL PARKアイルランド初の国立公園となる1964MUCKROSS HOUSE OPENS AS A MUSEUMマックロス・ハウス、博物館として開館2024CELEBRATING 60 YEARS OF MUCKROSS HOUSE AS A MUSEUM博物館としてのマックロス・ハウス60周年を祝う」 Muckross House(マックロス・ハウス)内部の展示ケースの一部で、ヴィクトリア朝時代の子ども用おもちゃやミニチュア家具が収められたコレクション。左:三輪型の子ども用ペダル車(ペダル・トライシクル)右:19世紀~20世紀初頭の大型算盤(アバカス) このサイズは特に「デモンストレーション用(教育者が使う大型モデル)」である可能性が高い と。アンティークの子ども用ベビーカー(ドール・プラム/ドール・キャリッジ)とその中のビスクドール(磁器人形)。Muckross House(マックロス・ハウス)が取得したミュージアム認証証明書(Museum Standards Programme for Ireland)。Muckross HouseMuseum Standards Programme for Ireland(アイルランド博物館標準化プログラム)Administered byThe Heritage Council(主管:アイルランド遺産評議会)Date of Accreditation:13 July 2023(認証日:2023年7月13日)Muckross House Research Library(マックロス・ハウス調査図書館)が取得したミュージアム認証証明書。Muckross House Research LibraryMuseum Standards Programme for Ireland(マックロス・ハウス調査図書館)(アイルランド博物館標準化プログラム)認証日:13 July 2023(2023年7月13日)展示ケースの中には、上流階級のピクニック装備やアウトドア用品をテーマにしたコレクションが収められていた。「Gun Room」と。この部屋は?ヴィクトリア朝時代らしい重厚な木製テーブル。机上の黒い箱は銃器ケース?散弾銃の道具類(銃身ブラシ、オイル等)が入っていた?暖炉(ファイヤープレイス)と鏡(マントルミラー)。白鳥(おそらくコブハクチョウ / Mute Swan)の剥製(はくせい)標本。「Gun Room(ガン・ルーム)」 を写したもの。典型的な19世紀上流階級の狩猟文化と自然史趣味を反映した空間 と。中央上部:巨大な角(Irish Elk または Giant Deer のレプリカ) ・絶滅した「アイルランドヘラジカ(Megaloceros giganteus)」の角 ・多くのカントリーハウスで飾られる象徴的アイテム(特にアイルランド)右上:赤鹿の首掛け剥製(Red Deer) ・アイルランド最大の現存野生動物 ・キラーニー国立公園周辺で見られた種と一致 ・狩猟の成果=名誉とされ、ガンルームに飾られている と。こちらの壁にも。右:Irish (Kerry) Mountain Goat / アイリッシュ(ケリー)・マウンテン・ゴートの剥製左:Red Deer Stag(アカシカ雄)の角。「Gun Room(ガン・ルーム)」内を移動して。Muckross House(マックロス・ハウス)の中でも特に豪華な部屋の一つ、「ヴィクトリア朝様式のダイニング・ルーム(Dining Room)」濃紅色のダマスク柄の壁紙が空間に重厚さと格式を与えていた。壁には肖像画(おそらく歴代の家主や貴族、軍人)が多数飾られており、系譜・権威・伝統を強調しているのであった。ダイニング・ルームの壁面の装飾と暖炉まわりの様子。様々な絵画が飾られていた。イングランド国王・ジェームズ1世(James I, 1566–1625) の有名な戴冠肖像画(coronation portrait)。・生没年:1566年 – 1625年・統治: ・スコットランド王(ジェームズ6世)として:1567年〜1625年 ・イングランド王・アイルランド王(ジェームズ1世)として:1603年〜1625年・王朝:ステュアート朝の初代イングランド王サイドボード(sideboard)と銀器類(Silverplate / Electroplated Silverware)そしてその上部に飾られた肖像画。この絵画は、アイルランド・ケリー州のキラーニー周辺、とくにマックロス・ハウス(Muckross House)のある地域の風景を描いたものである と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.21
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その53):Ross Castle・ロス城 へ(2/2)
そして9:30になり入城。受付にて入城料金€4/人を支払う。ロス城に併設された小さな展示室のみ見学可能であった。。左側パネル。「PREVENTING COLLAPSE — Searching For DetailsNarrow Escape in Dangerous SiteROSS CASTLE came into State ownership in 1970. Over the years, work had been doneto stabilise it. The northwest corner had been heavily buttressed with stone. A steel andconcrete roof had been put on, and the Georgian windows had been filled in. An internal wall had been built to support the upper vault. Much of this was causing more damage.The heavy buttressing of the northwest corner was falling away, causing cracks on eitherside of it, running all the way to the top of the walls. The east wall was falling outwards. The steel beams holding the roof up had almost rusted away, and the upper vault was collapsing. In fact, the building was about to fall down.Raking shores were used to support three of the walls on the outside (see main photo), fixed to a steel frame inside. All cracks in the building were constantly monitored, but not all the dangers were visible. On two occasions, staff narrowly escaped injury when large sections of apparently sound masonry collapsed.Vital Traces SurviveThe spiral staircase had survived intact, with the doors to each floor (see photo) still inplace. From the surviving foundations and close inspection of the inner faces of the walls,it was possible to accurately reconstruct the internal walls. This greatly preserved the structural integrity of the building. On the south wall, the curved outline of the lowervault survived, sothat it too could be accurately replaced.With the lower floor greatly strengthened, the buttress against the northeast corner wasremoved. This revealed that the rock outcrop on which the castle sat had been cut awaywhen a house was built here in the 1800s. When the house was demolished, the corner hadbegun to slip. A steel and concrete 'corset' was inserted to prevent further movement(frozen into place).Enough traces were discovered to show the exact positions of missing windows. It was thusclear that these were identical to surviving windows.」 【崩壊防止 — 詳細の調査危険な場所での間一髪の回避ロス城 は1970年に国家の所有となりました。その後、安定化のために様々な作業が施されました。北西の角は石材で大きく控え壁(バットレス)が築かれ、鋼鉄とコンクリート製の屋根が取り付けられ、ジョージアン様式の窓は塞がれていました。上部のヴォールト(穹窿天井)を支えるための内壁も建てられていました。しかし、これらの多くはむしろさらなる損傷を引き起こしていたのです。北西角の重い控え壁は崩れかけており、その両側の壁には上部まで達する亀裂が入っていました。東側の壁は外側へ倒れかけ、屋根を支える鋼鉄製の梁はほとんど腐食しており、上部のヴォールトも崩壊していました。実際、建物はまさに倒壊寸前の状態だったのです。外壁3面を支えるために、傾斜支柱(レイキングショア)が外側に設置され(中央の写真参照)、内側の鋼鉄フレームに固定されました。建物にできた亀裂は常に監視されていましたが、すべての危険を事前に把握することはできませんでした。実際、2度にわたって、大きな石造部分が突然崩れ落ち、スタッフが負傷寸前の状況に遭遇しました。重要な痕跡の保存螺旋階段は完全な状態で残っており、各階への扉も(写真参照)まだ元の位置にありました。また、残された基礎と壁の内側の詳細な観察により、内部の壁を正確に復元することが可能でした。これにより、建物の構造的な安定性が大きく保たれました。南側の壁には、下層のヴォールト(アーチ型天井)の湾曲した輪郭も残っていたため、こちらも正確に復元することができました。下層階の強化が完了すると、北東隅の控え壁(バットレス)が撤去されました。これにより、この城が建つ岩盤が1800年代に家を建てるために削られていたことが判明しました。その家が取り壊された後、城の角がずれ始めていたのです。そこで、鋼鉄とコンクリート製の「コルセット」が設置され、それ以上の構造の動きを防止する措置が取られました(固定された状態です)。さらに、失われた窓の正確な位置を示す痕跡も発見されました。これにより、残されていた窓と同一のものであることが確認されたのです。】右側パネル。「CAREFUL RESTORATION — Learning Medieval TechniquesMatching Ancient MaterialsWhat started as a limited project to conserve and repair the castle, developed into full restoration. The later stages were greatly assisted by EU funding. The restored castle was opened to the public in 1993.Careful study of the surviving building meant that there was very little guess workinvolved in the reconstruction. The same was true of materials. The original mortar and plasters were carefully analysed. The plaster had been applied in several layers, all but the last strengthened with cow hair to prevent it from cracking. This was difficult to come by, but faithfully reproduced (see photo on left).Craftsmen learned how to weave wicker ‘centring’ (see photo on left) to rebuild the vaults accurately. Wicker mats were woven in place, and curved to the shape of the arch. On top of these, the stones of the arch were bedded in mortar. Trial pieces of wicker were pressed into sand, to check that the pattern matched fragments of the original.」【慎重な修復 — 中世の技術を学ぶ歴史を越えての作業古代の材料との整合この修復は、もともと城を保存・修理するための限定的なプロジェクトとして始まりましたが、最終的には本格的な修復事業へと発展しました。後期の段階ではEUの資金援助が大きな助けとなり、修復されたロス城は1993年に一般公開されました。現存する建造物の綿密な調査により、再建においてほとんど推測を必要とせずに済みました。使用された材料についても同様です。元のモルタルや漆喰は詳細に分析されました。漆喰は複数の層にわたって塗布されており、最後の層以外すべてに牛の毛が加えられていました。これはひび割れ防止のためでした。この牛毛は入手困難でしたが、忠実に再現されました(左の写真参照)。職人たちは、アーチ型天井を正確に再構築するための柳の枝で編んだ型枠(セントリング)の作り方を学びました。柳で編まれたマットはその場で形成され、アーチの形に合わせて湾曲させられました。その上にアーチの石材がモルタルで固定されました。試作品の柳を砂に押し当て、模様が元の断片と一致するかを確認する作業も行われました。】 「THE ROMANCING OF ROSSTHE CASTLE CRUMBLESCreating a RuinDuring the military occupation of Ross Castle the interior was altered to create bigger rooms. The lower stone vault was removed. The internal walls were removed to createone large room on each floor. In the east wall, six Georgian sash windows were inserted.All these changes had seriously weakened the structure.When the military left in 1825, it was returned to the Earl of Kenmare. He made it into a decorative feature in the landscape, a venerable ruin with the lake lapping at its feet, surrounded by wild mountains. Generations of tourists have come in jaunting cars toadmire the result.With its roof removed, the weakened building was exposed to the weather. Beneath a cloak of ivy, it gently crumbled. Some work was done to keep it standing, but this created more problems. By the time it came into State ownership in 1970, the building was dangerously unstable.Changing Ways of Seeing The CastleEven before the castle ceased to be a military barracks, it appears as a focal pointin romantic illustrations of Killarney. Many of these representations are very inaccurate. Theartists are more interested in portraying the idea of a medieval castle than the real Castle. Thebuilding itself was treated in the same way. When it was returned to theEarl of Kenmare, he did not wish to conserve it as a monument, indeed he had the rooftaken off to avoid rates. He did,however, want it to 'look right'. The functional block of the barracks (which you are in)did not fit in, so he had it changed into a mock medievalruin. The windows were reducedto narrow arrow loops.Approaches to the treatment ofancient buildings have changed over the years.In the 1900s, many of our medieval buildings were very heavily restored and muchof the original fabric was lost. Today we treat the fabric as a document of the past,conserving as much of it as possible. Restoration is always problematic, because old buildingsbecome what they are through continual change. To what point in the story ofa building do you restore it?Ross Castle became a vital element in the landscape of Killarney. This influencedthe intervention that was undertaken to prevent it from falling down. In the process,a remarkable amount of evidence for the original form of the building was recorded.Over a number of years, the project evolved into the restoration you see today.」【廃墟をつくるロス城が軍に占拠されていた間、その内部はより大きな部屋を作るために改造されました。下層の石造アーチ天井は撤去され、内部の壁も取り払われて、各階に一つの大部屋が作られました。東側の壁にはジョージアン様式の上げ下げ窓が6つ取り付けられました。こうしたすべての改造により、構造は著しく弱体化してしまいました。1825年に軍が撤退すると、城はケンメア伯爵に返還されました。伯爵はこの城を風景の中の装飾的な遺構として利用し、湖の水が足元に寄せる中、荒々しい山々に囲まれた由緒ある廃墟を演出しました。以来、多くの観光客がジャウンティングカー(観光馬車)に乗ってこの風景を楽しみにやって来たのです。屋根が取り除かれたことで、弱体化した建物は風雨にさらされるようになり、ツタに覆われたまま、ゆっくりと崩れていきました。倒壊を防ぐために一部の補修は行われましたが、それが逆にさらなる問題を引き起こしました。そして1970年に国の所有となった時には、この建物は極めて不安定な状態にあったのです。城の見方の変遷ロス城が軍の兵舎としての役割を終える以前から、キラーニーのロマンチックな挿絵ではすでにこの城が中心的な存在として描かれていました。しかし、これらの多くは実際には非常に不正確な表現であり、画家たちは本物の城ではなく、「中世の城のイメージ」を描くことに関心を持っていたのです。そのため、建物自体もその「イメージ」に合わせて扱われてしまいました。城がケンメア伯爵に返還された際、彼はこれを記念碑として保存しようとはせず、むしろ税金逃れのために屋根を取り払ってしまいました。ただし、「見た目がそれらしくあること」は求めたのです。現在あなたがいる兵舎部分の機能的な建物はその雰囲気にそぐわなかったため、伯爵はそれを中世風の廃墟に改造し、窓も細い矢狭間(arrow loops)へと変更させました。】 「DRAWN AFTER THE QVICKE(生き写しに描かれた または そのまま描かれた)」 アイルランドの「傭兵歩兵カーン(Kern または Cearnaigh)」の様子が描かれているのだ と。※"QVICKE" は「QUICK(生者・現実のもの)」の古綴り と。「Drawing from the 1600s of Kern or Cearnaigh.These were bands of lightly armed mercenary foot soldiers.They went barefoot and carried Irish swordsand the Irish scian or dagger.Reproduced courtesy of The Ashmolean Museum, Oxford.」 【1600年代のカーン(Kern または Cearnaigh)の姿を描いた絵。彼らは軽装の傭兵歩兵団であり、裸足で歩き、アイルランドの剣や、スキアン(scian)と呼ばれる短剣を携えていた。オックスフォードのアシュモレアン博物館所蔵・複製提供】1594年に描かれた「サー・トーマス・リー(Sir Thomas Lee)の肖像画」。彼はアイルランドの傭兵部隊「カーン(Kern)」の総指揮官であった。「SIR THOMAS LEECAPTAIN GENERAL OF THE KERNMarcus Gheeraerts, 1594Lee, an English officer, is shown bare legged like his men and carrying an Irish lance. English officials were worried that servants of the Crown would ‘lapse into barbarism’ by adopting Gaelic ways.Courtesy of The Tate Gallery」 【サー・トーマス・リーカーン(アイルランド軽歩兵)の総司令官マーカス・ヘラールツ画、1594年リーはイングランド人の将校であり、彼の部下たちと同様に裸足で、アイルランドの槍(ランス)を持って描かれています。イングランド政府の役人たちは、王室の従者たちがゲール文化に染まり「野蛮化」してしまうのではないかと憂慮していました。作品所蔵:テート・ギャラリー(ロンドン)】ドイツ・ルネサンスの巨匠「アルブレヒト・デューラー(Albrecht Dürer)」によって描かれた有名な素描の複製 と。16世紀初頭のアイルランド人傭兵たちの姿を描いている と。「HERE GO THE PEASANTS IN IRELANDFacsimile of a drawing by Albrecht Dürer. 1521Dürer must have seen these men in Germany, where they were hiring themselves out as mercenaries.Reproduced courtesy of The National Gallery of Ireland」 【アイルランドの農民たち、ここに行くアルブレヒト・デューラーによる素描の複製(1521年)デューラーは、これらの男たちをドイツで見たに違いありません。彼らは傭兵として雇われるために自らを売り込んでいたのです。提供:アイルランド国立美術館のご厚意による複製】「15世紀(1400年代)のロス城(Ross Castle)の復元想像図」。・この図は、ロス城が最初に築かれた時代の姿を描いている。・オドノヒュー家(O'Donoghue clan)は、ケリー県一帯を支配していたゲール系アイルランド 貴族であり、この城の創建者とされている。・この時代のロス城は、塔(タワーハウス)と囲郭(バウンダリーウォール)を持つ典型的な 防衛型居城であり、湖に面しており、木製の桟橋(左手前)、内部に家畜用の囲いや副次的な 建物(長屋)を含んでいる様子が分かる。・角に丸塔(bartizanまたはturret)を持ち、監視や防衛に使用されていたことがうかがえる。「1400s Ross Castle as the O'Donoghues first built it」【1400年代 オドノヒュー家がロス城を最初に建てた】 17世紀(1600年代)におけるロス城(Ross Castle)の復元想像図。・この鳥瞰図は、ロス城が17世紀初頭に私邸として使われていた様子を描いています。・テキストの「the house the Brownes built」は、ブラウン家(Browne family)によって 建てられた住宅部分を指している。・ブラウン家はこの地の有力なカトリック家系であり、ロス城を居城として利用していた。・西側の城壁に接して屋敷が建てられている様子が描かれており、これは城が純粋な 防衛施設から居住空間としても利用されるようになったことを示している。「1600sWith the house the Brownes built against the west wall」 【1600年代:ブラウン家が西壁に沿って建てた家屋】「18世紀(1700年代)におけるロス城(Ross Castle)の様子を示した復元イラスト」・この鳥瞰図は、1700年代のロス城が兵舎(バラック)として使用されていた時代の様子を 描いたもの。・城の南側の外壁に沿って長い建物(兵舎)が追加されており、煙突から煙が上がっている。 これは実際に居住・使用されていたことを示す。・中庭や門構えのような要素もあり、軍事施設としての機能を果たしていたことが分かる。・周囲には塀や土塁が整備され、外部からの接近に対して防御的な構造が見て取れる。「1700sWith the barracks attached to the south wall」 【南側の壁に兵舎が接続された1700年代)】「GAELIC ORDER PASSESCASTLE BECOMES A BARRACKSThe Brownes Recover EstatesWITH THE DEFEAT OF James II, most of the old Gaelic aristocrats lost everything.Many fled to Spain and France. An Act of the Irish Parliament in 1717 assignedRoss Castle for use 'as a garrison forever'. The Brownes’ house was demolished andthe barracks you are now in was built. Backed by a network of such barracks, central authority and the rule of English law were established throughout Ireland.When Nicholas Browne died in exile in 1720, the family managed yet another come back. His son Valentine (see picture left) recovered the estate with the sponsorship of his Protestant relatives, the Butlers of Kilkenny. He also received a pension of £100 in compensation for the loss of his house attached to the castle. When the military leftin 1825, it was restored to his descendant, the Earl of Kenmare.By now, the castle was weakened by alterations and in poor condition. The Earl had the roofs removed to avoid taxes. He also disguised the barracks as a medieval ruin, by narrowing the windows to mock arrow loops. A symbol of power in the landscapewas transformed into a romantic ruin. It became an icon of the tourism that has thrived in Killarney since the 1750s. It remained in the family until the death of the last Earl of Kenmare in 1956.Five Hundred Years Of ContinuityThe Brownes managed to cling on to their lands, in unbroken succession, for 500 years. Remaining Catholics, they survived the campaigns against Catholic land ownershipin the 1600s and 1700s, becoming Earls of Kenmare at the time of the Act of Unionin 1800. They continued to prosper, playing an important role in the development of Killarney.A letter, written by Sir Thomas Browne in 1757, reveals the family's sense of historical continuity. He writes of lands to be leased at Gorravullane:“besides a small part let to O Donoghue of Ross in charity to help maintain him.”The O'Donoghues of Ross had lost everything in 1583, yet almost two hundred years later, they were still acknowledged by the Brownes.」 【ブラウン家、領地を回復すジェームズ2世の敗北により、古いゲール系貴族の多くは全てを失いました。多くはスペインやフランスに亡命しました。1717年のアイルランド議会の法により、ロス城は「永遠に駐屯地として使用する」と定められました。ブラウン家の邸宅は取り壊され、現在あなたがいる兵舎が建てられました。このような兵舎のネットワークを背景に、アイルランド全土に中央集権とイングランド法の支配が確立されました。1720年、ニコラス・ブラウンが亡命先で亡くなると、家族は再び復帰の機会を得ます。彼の息子バレンタイン(左の肖像画参照)は、キルケニーのプロテスタント系親族バトラー家の支援を受けて、領地を回復しました。また、彼は城に付属していた邸宅を失った補償として100ポンドの年金も受け取りました。1825年に軍が撤退すると、領地はその子孫であるケンメア伯に返還されました。この頃には、城は改造によって弱体化し、状態も悪化していました。伯爵は税金を避けるために屋根を取り外しました。また、兵舎を中世の廃墟に見せかけるために、窓を狭くし「矢狭間」に似せて改造しました。かつては権力の象徴だったこの建物は、ロマンティックな廃墟へと変貌し、1750年代以降観光業が栄えるキラーニーの象徴となったのです。ロス城は1956年に最後のケンメア伯が亡くなるまで、ブラウン家が所有し続けました。500年にわたる継続性ブラウン家は、500年もの間、代々土地を保持し続けてきました。カトリック信徒でありながら、17世紀と18世紀のカトリック土地所有者への弾圧をくぐり抜け、1800年の合同法(イングランド・アイルランド統一)当時にはケンメア伯爵の地位を得ていました。彼らはその後も栄え続け、キラーニーの発展に重要な役割を果たしました。1757年にサー・トーマス・ブラウンが書いた手紙は、彼らの「歴史的継続性」への意識を示しています。その中で彼は、Gorravullaneに貸し出される土地について記しています。「ロスのオドノヒュー家には、生活の支援として小さな区画を慈善的に貸与している。」ロスのオドノヒュー家は1583年に全てを失いましたが、そのおよそ200年後にも、ブラウン家はその存在を認めていたのです。】「COLONISATION CONTINUES Brownes Prosper but Join JacobitesSurviving Difficult TimesThe story of the 1600s in Ireland is of campaigns of land seizure against Catholiclandowners and their struggle to survive. The resettlement of seized lands by Protestant immigrants from Britain created a lasting bitterness.The Brownes avoided the conflict and prospered. In 1620 they were granted a patent to their lands by King James I (detail reproduced here). On the other hand, they continued to intermarry with the MacCarthys and other Gaelic aristocrats, at some point becoming Catholics.In 1652, Cromwellian forces took Ross Castle and seized the lands of the 14-year-old Sir Valentine Browne. As an innocent Catholic Royalist, he was given back his estate after the restoration of the monarchy.Sir Valentine was made Viscount Kenmare for his service to King James II as Privy Counsellor. When James was defeated in the 1690s, Valentine and his son, Nicholas, were declared traitors and the estate was seized once more. During the fighting, the castle was taken over as a military barracks, which it remained for over a century.The Backdrop of Colonisation and RebellionAs the plantations progressed, the divisions in Ireland became increasingly defined by religion. With the Restoration of the Monarchy, the hopes of Catholic landowners were raised, only to be dashed when James II was defeated by William of Orangein the 1690s.Success and SeizuresIn the Browne family, three Sir Valentines succeeded one another in the 17th century. The first two married two MacCarthy sisters, Sheely and Mary, daughters of Viscount Muskerry.It was the third Sir Valentine who lost the estate to the Cromwellians in 1652. He was probably not here at the time, but in France where he was educated. It happened when Irish forces under his uncle, Lord Muskerry, retreated to Ross Castle after a battle at Knocknriclashy in Cork. Muskerry surrendered when the Cromwellians brought artillery across Lough Leane by boat. This allegedly fulfilled a local legend that Ross Castle would never be taken ‘until a ship should swim on the lake’.」 【植民地化は続くブラウン家は繁栄するが、ジャコバイトに加わる困難な時代を生き抜く1600年代のアイルランドでは、カトリック地主に対する土地の強制収奪と、彼らの生き残りをかけた闘いが繰り広げられました。これらの没収された土地にイギリスから移住してきたプロテスタントたちが再定住したことにより、長きにわたる怨恨が生まれました。ブラウン家はこの紛争を回避して繁栄し、1620年にはジェームズ1世から土地に関する特許状(正式な所有権)を授与されました。一方で、彼らはマッカーシー家や他のゲール系貴族と婚姻関係を結び、やがてカトリックに改宗していきました。1652年、クロムウェル軍がロス城を占領し、当時14歳だったサー・ヴァレンタイン・ブラウンの土地を没収しました。彼は無実のカトリック王党派だったため、王政復古後に土地を返還されました。その後、ヴァレンタインはジェームズ2世への忠誠が認められ、ケンメア子爵(Viscount Kenmare)に叙せられ、枢密顧問官にも任命されました。しかし、1690年代にジェームズ2世が敗北すると、ヴァレンタインと息子のニコラスは反逆者とされて再び土地を没収されました。戦闘中、ロス城は軍用の兵舎として接収され、その状態は100年以上続きました。】「The Struggle for MunsterThe Munster Plantation did not go according to plan. The ‘Seignories’ held by Undertakers were made up of scattered parcels of land, and the settlers were fewand isolated. Many Catholic landowners managed to recover their lands in the courts.The Brownes’ claim to Ross Castle and the O’Donoghue Lands was contested by the MacCarthys, who successfully appealed to the Queen. Browne arranged for his son Nicholas to lease back the estate and to marry MacCarthy’s daughter and sole heir. In the event, she married her cousin Florence MacCarthy. The tussle betweenthe families lasted for generations.When the plantation collapsed in 1598, Nicholas Browne’s house was occupied by Florence MacCarthy. At the Battle of Kinsale in 1601, the tide was turned.Sir Nicholas Browne returned from the battle and evicted MacCarthy.Plantation TroublesMANY SEIGNORIES were so fragmented, that Undertakers had difficulty working outwhich land was theirs. Worse still, officials soon realised that there was not enoughland to go around. The survey, which Browne had worked on, failed to distinguishbetween lands where the Desmonds received payments from the crown in the Gaelic manner and those they owned under English law. Only the latter could be seized. This led to many Gaelic landowners winning back their lands in the courts.The Struggle for Ross in Courts, Beds, and BattlefieldsQUEEN ELIZABETH I accepted title claims to the O’Donoghue estate by rights ofovertantry. Coll Donagh MacCarthy More, the Earl of Clancar, A deal was brokered in Court, that Clancar would mortgage the estate to Browne’s son Nicholas, who would then marry the Earl’s daughter and sole heir. To keep the lands in the family, however, the Earl later secretly married his daughter to her cousin, Florence MacCarthy. The English settlers in the area harassed Florence MacCarthy and made sure he neverhad enough money to pay off the mortgage. In 1598, the Brownes obtained a grantfrom the Queen to lands described as “late in the tenure of Rory O’Donochue aliasO’Dono more”.Sir Nicholas secured his position by marrying Sheely O’Sullivan, daughter of the clan chieftain of Sullivan Beare. When Nicholas returned after the Battle of Kinsale, Munster was in ruins and much of the population starving. The plantation effort had been broken by the settlers’ individual efforts than by central planning.」【マンスターの争奪戦マンスター植民地化政策は計画通りには進みませんでした。「シニョリー」と呼ばれる領地はアンダーテイカー(植民地主導者)によって保持されていましたが、それらは分散した小区画から成り、入植者の数も少なく孤立していました。多くのカトリック系地主たちは、法廷で土地を取り戻すことに成功しました。ブラウン家によるロス城とオドノヒュー家の土地への請求権は、マッカーシー家によって争われ、女王に対する訴えが成功しました。ブラウンは息子ニコラスがこの地所を借り戻し、マッカーシー家の一人娘で相続人と結婚するよう手配しました。しかし実際には、彼女は従兄であるフローレンス・マッカーシーと結婚してしまいました。こうして両家の争いは数世代にわたって続くこととなります。1598年に植民地化政策が崩壊すると、ニコラス・ブラウンの家はフローレンス・マッカーシーに占拠されました。1601年のキンセールの戦いで情勢が逆転し、サー・ニコラス・ブラウンは戦から戻ってマッカーシーを追放しました。プランテーションの問題点多くの領地(シニョリー)は非常に断片化されていたため、アンダーテイカー(植民地主導者)は自分の領地がどこなのかを把握するのに苦労しました。さらに悪いことに、当局はすぐに土地が十分にないことに気付きました。ブラウンが関わった調査では、デズモンド家がゲール式に王室から支払いを受けていた土地と、英法に基づいて所有していた土地とを区別できていませんでした。差し押さえが可能だったのは後者のみだったため、多くのゲール人地主が法廷で土地を取り戻すことに成功しました。ロスをめぐる争い ― 法廷、寝室、そして戦場でエリザベス1世女王は、オドノヒュー家の土地に対する請求権をオーバーロード(封建的主権者)の権利に基づいて認めました。コール・ドナフ・マッカーシー・モア、すなわちクランカー伯爵が裁判所で取引をまとめ、伯爵は地所をニコラス・ブラウンに抵当に入れ、彼が伯爵の娘で唯一の相続人と結婚するというものでした。しかし、土地を家族内に留めるため、伯爵はその後、密かに娘を従兄のフローレンス・マッカーシーと結婚させました。地域のイングランド系入植者たちはフローレンス・マッカーシーを妨害し、彼が抵当を返済できないようにしました。1598年には、ブラウン家がエリザベス女王から、「かつてロリー・オドノヒュー(別名オドノモア)の名義であった」土地に対する許可証を得ました。ニコラス卿は、スリーブン・ベアの族長の娘シーリー・オサリバンと結婚することで、自らの地位を確保しました。キンセールの戦いの後、ニコラスが帰還したときには、マンスター地方は荒廃し、多くの住民が飢えていました。プランテーション(植民地化)事業は、入植者たちの個々の努力によって支えられ、中央の計画はほぼ機能していなかったのです。】 「MUNSTER PLANTATION –ROSS CASTLE CHANGES HANDSWhat to do with DesmondBy the late 1500s, the O'Donoghues of Ross were subject to the 'Old English' Earls of Desmond, who controlled much of Munster. They remained Catholic after the Reformation and had connections with England's enemies in Spain. Queen Elizabeth Iwas determined to break them.The Earl of Desmond was provoked into rebellion in 1579 and eventually defeated. Ruairidhe O'Donoghue of Ross Castle joined the rebellion and was killed in 1583. Ross Castle and the O'Donoghue lands were seized along with the lands of Desmond.The Crown planned to create a Protestant bulwark against Spain by ‘planting’ Munster with English settlers. The ‘Munster Plantation’ was led by well-known figures such as Sir Walter Raleigh. These ‘Undertakers’ undertook to populate the land with English tenants.Ross Castle and the O'Donoghue lands came into the hands of Sir Valentine Browne. He had been sent to Munster in 1585, as one of the Crown Surveyors, to plan the plantation.The Big PlanFollowing his survey, Sir Valentine Browne declared that 574,645 acres were available for settlement, in counties Cork, Kerry and Limerick. Implying that there was now plenty ofroom for settlers, he reported that:"The towns and villages are ruined and not one out of thirty persons leftand those for the most part starvelings"The ‘Undertakers’, such as Sir Walter Raleigh and Sir Christopher Hatton, were to receive ‘Seignories’ of 12,000 acres (4856 hectares) of good land. Of this they were to occupy 1000 acres (405 hectares) for themselves. The rest they were to rent out, according toa detailed plan (see seignory plan down left), which included building villages for theirtenants.It envisaged that 11,375 settlers would establish 2,375 English households. In the event the seignories varied considerably. The Queen’s then favourite, Sir Walter Raleigh, was granted an enormous estate of 42,000 acres.Sir Valentine Browne was allotted lands near Dingle and Killorglin, but swapped these for the O’Donoghue lands. He was a powerful figure, with a commission to lease all crown land in Munster and 120 horse to enforce order. Weaknesses in the survey he had worked on, however, were to create problems for him and for the entire plantation.」【マンスター植民地化計画 ロス城の所有者交代デズモンド家をどうするか1500年代後半、ロスのオドノヒュー家は、マンスターの大部分を支配していた「オールド・イングリッシュ(古イングランド系)」のデズモンド伯爵家の支配下にありました。彼らは宗教改革後もカトリックを保持し、スペインのイングランド敵勢力と関係を持っていたため、エリザベス1世女王は彼らを打破しようと決意しました。1579年、デズモンド伯は反乱を扇動され、最終的には鎮圧されました。ロス城のルアリデ・オドノヒューもこの反乱に加担し、1583年に殺されました。その後、ロス城とオドノヒュー家の土地は、デズモンド伯の領地とともに没収されました。イングランド王室は、マンスターにイングランド人入植者を「植え付ける」ことで、スペインへの防波堤となるプロテスタントの砦を築くことを計画しました。「マンスター植民計画(Munster Plantation)」は、ウォルター・ローリー卿など著名な人物によって主導されました。これらの「アンダーテイカー(入植責任者)」たちは、イングランドの小作人で土地を満たすという任務を請け負いました。こうしてロス城とオドノヒューの土地は、サー・ヴァレンタイン・ブラウンの手に渡りました。彼は1585年に王室の土地調査官の一人としてマンスターに派遣され、植民計画の策定に携わっていたのです。大計画土地調査の後、サー・ヴァレンタイン・ブラウンは、コーク、ケリー、リムリック各州において57万4,645エーカーの土地が入植に適していると宣言しました。彼は入植者にとって十分な余地があると述べ、次のように報告しています:「町や村は廃墟と化し、30人に1人も残っていない。そして、残っている者のほとんどは飢えた者たちである。」「アンダーテイカー(入植請負人)」たち――例えばウォルター・ローリー卿やクリストファー・ハットン卿など――は、1万2,000エーカー(約4,856ヘクタール)の良質な土地をそれぞれに与えられる予定でした。そのうち1,000エーカー(約405ヘクタール)は自分たちで占有し、残りは小作人に貸し出す計画でした。(左下にある「領地計画図」参照)その計画には、入植者のための村の建設も含まれていました。この計画では、1万1,375人の入植者が、2,375戸のイングランド人家族として定着することが見込まれていました。実際には、領地の規模は大きく異なりました。女王の寵臣であったローリー卿は、4万2,000エーカーという広大な土地を与えられました。サー・ヴァレンタイン・ブラウンは、当初ディングルやキロルグリン近郊の土地を与えられましたが、それらをオドノヒュー家の土地と交換しました。彼は強大な権限を持つ人物であり、マンスターにおける王室所有地の貸与を統括する任命を受け、治安維持のために120騎の兵も指揮していました。しかし、彼自身が関わった土地調査には不備があり、それが彼自身とこの植民事業全体に問題を引き起こすこととなったのです。】 「ROSS CASTLE A MIRROR TO ITS TIMESRoss Castle was built by the O’Donoghues in the mid 1400s.It reflects the troubled times when it was built. As you travel through the Irishcountryside you will see the ruins of many of these ‘Tower Houses’. Up to 3,500 were built in the 1400s and 1500s.For two hundred and fifty years, the history of Ross Castle closely reflected the wider current of Irish history. It is a story of England’s struggle for control over the lordshipsin Ireland.What Are Tower Houses?They are rectangular defensive towers, with stepped battlements. The windows on thelower floors are narrow defensive slits or ‘arrow loops’. Tower Houses often haveprojecting machicolations overhanging the corners or the door, allowing defenders tofire straight down. The photograph shows the two machicolations here, at opposite corners. These were added fifty years after the castle was first built and were fitted with gun loops.On the inside, stone vaults over the basement and under the upper floor protected against fire. The main room, or hall, was located on the top floor, where it was safeto have larger windows.Many Tower Houses were surrounded by an outer defensive wall. This enclosure, or bawn, probably protected livestock as well as outbuildings. In the photograph you can see the sections of bawn wall that survives here and the two corner towers.Where And Why Were They Built?Most are found in areas where central authority was weak during the 1400s and 1500s.Constant skirmishing between the great lords often took the form of cattle raiding.The lesser chieftains took the brunt of this and built tower houses to protect themselves.They in turn raided their neighbours when they could. The O'Donoghues of Ross Castlewere no exception, a document from 1567 tells us that:"Lord Roche complained to the MacCarthy Mor that the O'Donoghue Mor and others,with 6 or 7 banners displayed had taken 1500 cattle, 7000 sheep and had burned his corn."What Is The Main Difference Between Tower Houses And Other Castles?Tower Houses are quite varied. Because they were built for local conflicts, defencewas compromised for convenience. For example, the entrance door is on the ground floor.In earlier castles it was on the first floor, where it was harder to attack, but moreawkwardfor everyday use. The surviving section of the bawn wall here has impressivelooking corner towers,but the gate itself is very simple, as you can see in the photograph—in earlier castles an outer tower or “barbican” would have defendedsuch a gate.The word bawn is derived from the Irish bábhún, meaning a cattle fort.In troubled times,it is safer to defend cattle than field crops. This may have caused an increase in stock farmingand a decrease in tillage in this period.」【ロス城 時代を映す鏡ロス城(Ross Castle) は、1400年代半ばに オドノヒュー一族によって建てられました。この城は、その建設時の不安定な時代を反映しています。アイルランドの田園地帯を旅すると、多くの「塔屋(タワーハウス)」の廃墟を目にすることでしょう。1400年代から1500年代にかけて、最大3,500棟が建てられました。ロス城の歴史は、250年にわたりアイルランド全体の歴史の流れを反映してきました。それは、イングランドがアイルランドの領主権を掌握しようとする闘争の物語です。どこに、なぜ塔屋は建てられたのか?ほとんどの塔屋は、1400年代から1500年代にかけて中央政府の権力が弱かった地域に見られます。当時、有力な領主たちの間では、小競り合いとして家畜の略奪が頻発していました。下位の酋長たちはこうした争いの矢面に立たされ、自らの身を守るために塔屋を建てました。彼らもまた、機会を見ては隣人を襲いました。ロス城のオドノヒュー一族も例外ではありません。1567年の文書には、以下のような記録があります:「ロッシュ卿がマッカーシー・モアに訴えたところによれば、オドノヒュー・モアらが6〜7の旗を掲げて襲来し、牛1500頭、羊7000頭を奪い、穀物を焼き払った」と。塔屋と他の城との主な違いは?塔屋には多様な形がありますが、局地的な争いのために建てられたため、防衛よりも利便性が優先されていました。 たとえば、入口が地上階にある点が特徴です。それ以前の城では、1階(日本の2階相当)に入口があり、攻撃されにくい反面、日常生活では不便でした。現存するバウン(防御壁)の一部には立派な角塔がありますが、門自体は非常に簡素です。写真にも見られるように、かつての城ならばこのような門には外塔や「バービカン(防衛門)」が設けられていたはずです。「バウン(bawn)」という言葉は、アイルランド語の「bábhún(牛囲い)」に由来し、不安定な時代には農作物よりも家畜を守る方が安全とされました。これがこの時代における畜産の増加と耕作の減少につながった可能性があります。】 「A CATTLE RAID 500 YEARS AGOBy Ed Miliano15 things in this picture are from the wrong time. Can you find them?There are 12 black cats in this picture. Can you find them?」 【500年前の家畜略奪エド・ミリアーノ 作①この絵の中には時代に合わないものが15個あります。見つけられますか?②この絵の中には黒猫が12匹います。見つけられますか?】この画像が「A CATTLE RAID 500 YEARS AGO(500年前の家畜略奪)」というイラスト作品。現代のもの・時代が合わないものが15個番号 時代錯誤と思われるもの 備考1 エアロバイク 城の左上、屋上にあります2 傘(パラソル) 中央やや左上、屋上3 野球のバット 城の周辺の人物が手に4 サングラス 城の左中ほどの人物5 モダンな椅子 左側、オレンジの屋根の付近6 ゴルフクラブとバッグ 城の前庭に7 ラジカセ 城の手前の人物が肩に8 ノートパソコン 建物の上の人物が操作しているような姿9 電球 建物上部からぶら下がっているように見える10 マイク(演説用) 焚火のそばの人物が持っている11 サッカーボール 左下の広場あたりに見える黒白の球体12 ジェット機 空の右上の鳥と並んでいる細長い飛行体13 時計(腕時計) 拡大で手首に見える(確定には至らず)14 ギター 左下あたりで演奏しているような人物15 カメラ 背負っている人物が一人(または手持ち)以下のような場所に黒猫が確認できます1.城の屋上(左上)の人物のそば2.城壁中央上の門の前3.火の手前4.城の右側の外壁の上5.手前(画面中央下)の人物の肩に6.左下の広場7.建物の屋根の上(手前)8.城壁の間に挟まっているような場所9.城の左側の中庭の小道10.牛の群れの中に混ざって11.柵の内側(左下)の羊舎周辺12.城壁左下の隅展示室の様子を再び。ロス城(Ross Castle)👈️リンク の内部構造を示す精巧な模型(カットモデル)が中央に。・塔の構造: ロス城は15世紀中頃にオドノヒュー家によって建設された**アイリッシュ・タワーハウス (Irish Tower House)**の典型であり、防御性を重視した建築様式が特徴です。・階層: 模型からは最低でも4階層があり、それぞれに異なる機能の部屋が設けられていたことが わかります。 ・地上階: 玄関、倉庫、兵士の詰所など。 ・中層階: 生活空間、居住部屋。 ・上層階: 宴会や主の私室。 ・屋上: 見張り・防御用のマチコレーション(murder holes)と防御のための胸壁 (battlements)。・階段: 中央や隅には螺旋階段があり、急勾配で敵の侵入を妨げる設計になっているのがわかります。・防御設備: 窓は非常に小さく、矢狭間(arrow slits)として利用されたもの。模型にもそうしたスリットが 反映されています。この模型は、ロス城の戦乱の歴史や、当時のアイリッシュ・タワーハウスの建築様式を理解するうえで貴重な資料であり、館内展示のハイライトの一つといえるでしょう。「Living in a Tower HouseIN OUR MODEL we are trying to give some idea of how the O’Donoghues lived in Ross Castle in the 1500s.By modern standards it was extremely cramped. There was little privacy, even for the Lord. It was also damp and smelly.Some first-hand accounts survive. In 1644, Boullaye le Gouz from France wrote:‘The castles of the nobility consist of four walls extremely high... square towers withoutwindows,or at least having small apertures as to give no more light than a prison. They have little furniture ...put rushes a foot deep on their floors and on their windows,and many ornament their ceilings with branches’The fact that so many people needed to protect themselves by living in tower houses,tells us that life was very tough.An agent of Phillip II of Spain reported:‘Every petty gentleman lives in a stone tower, where he gathers into his service all therascals of the neighbourhood(and of these towers there are an infinite number)’In his account of travels in Ireland in the 1600s, Luke Gernon gives a more positive account of Irish hospitality:‘We are come to the castle al...ady. The castles are built very strong with narrow stayres for security.The hall is in the uppermost room, let us go up, you shall not come down agayne till tomorrow...you shall be presented with all the drinks in the house... you must not refuse it.The fyre is prepared in the middle of the hall where you may solace yourself till supper time,you shall not want sacke (wine) and tobacco.By this time the table is spread and plentifully furnished with a variety of meates...they feast together with great jollity and healths around; towards the middle of the supper the harper begins to tune and singeth Irish rymes of auncient making...’」【塔屋での暮らし私たちの模型では、1500年代にオドノヒュー家がロス城でどのように暮らしていたかを伝えようとしています。現代の基準から見ると、当時の暮らしは非常に窮屈でした。主(領主)でさえプライバシーはほとんどなく、湿気が多く臭気もありました。当時の第一級資料がいくつか残っています。1644年、フランスのブーレイ・ル・グーはこう記しています。「貴族の城は非常に高い四つの壁から成り立っており……窓のない四角い塔であるか、あっても光の入らない小さな開口部しかない。家具はほとんどなく……床や窓には足の深さまでイグサが敷かれ、天井には枝などで装飾が施されている」これほど多くの人々が塔屋に住んで身を守っていたという事実は、当時の生活がいかに過酷だったかを物語っています。スペイン王フェリペ2世の使節はこう報告しました。「すべての小領主は石造りの塔に住み、近隣の悪党どもを召し抱えている。(そしてこのような塔は無数に存在する)」1600年代にアイルランドを旅行したルーク・ガーノンは、もっと好意的な記述を残しています。「われわれはすでに城に着いた。城は非常に堅牢に建てられており、防御のために階段は狭い。大広間は最上階にあり、上がってしまえば明日まで降りられない。屋敷中の酒が出され、断ってはならない。暖炉の火が大広間の中央に焚かれ、夕食までの間くつろげる。ワインやタバコも不足しない。やがて食卓には様々な料理が並び、陽気に杯を交わす。夕食の中ほどになると、ハープ奏者が古いアイルランドの歌を奏で始める……」】 この展示パネルは、ロス城(Ross Castle)の各階の用途を説明したもの。Top FloorThe Hall was located at the top of the castle. This was the safest place, high abovethe ground and at the top of the narrow spiral staircase. This room would be used for all grand occasions.Second FloorThis was the main bedroom. There was little privacy in a tower house. Not only the lord would have slept here, but most of his family and many of their servants.First FloorThe main room on this floor was a parlour for domestic use.Ground FloorThe ground floor was often used for storage, but the large fireplace here showsthat it was also used for living in. The guards and servants probably cookedtheir food on this fire.【最上階(Top Floor) 大広間(ホール)は城の最上階にありました。ここは地上から高く離れた場所で、狭い 螺旋階段の頂上に位置し、最も安全な場所でした。この部屋は、重要な催しや式典に 使用されました。3階(Second Floor)主寝室がありました。塔屋ではプライバシーがほとんどなく、領主だけでなく、その家族や多くの召使いもこの階で眠っていました。2階(First Floor)この階の主な部屋は、日常の家庭的な用途のための居間として使われていました。地上階(Ground Floor)この階は主に物置として使われていましたが、大きな暖炉があったことから、生活の場としても使用されていたと考えられます。警備兵や召使いたちは、この暖炉で食事を作っていたと思われます。】「復元されたロス城(Ross Castle)の断面図」 Cap House above the spiral stairs→ 「螺旋階段の上の小屋(キャップハウス)」 ※塔の最上部にある小さな屋根付き構造物で、見張りや通気の役割も担っていたと 考えられます。Corner Machicolation→ 「隅のマシコレーション(石落とし)」 ※敵が城壁に近づいたときに真下へ石や熱湯を落とすための開口部。防御機能の一つです。Great Hall→ 「大広間」 ※城の中で最も重要な公共空間で、式典や宴会、会議などが行われました。Musician’s Gallery→ 「楽師のギャラリー」 ※大広間の上部にあるバルコニー状の構造で、音楽家が演奏するスペースです。Bed Chamber→ 「寝室」 ※領主や家族が休息するための私的空間。Parlour→ 「居間・談話室」 ※日常の食事や会話、家庭的な用途に使われる部屋。Store Room→ 「貯蔵室」 ※食料、薪、武器などを保管する部屋。しばしば召使いや兵士もこの階で生活していたと されています。「ロス城(Ross Castle)」の構造断面を描いた復元イラストをネットから。下から順に。① 1階:貯蔵庫・厨房・下働きの空間 ・使用目的:食料の保存、台所、火の管理など ・見どころ: ・わら敷きの床と、保存食品(肉の燻製・樽など) ・外からの荷物の搬入出(右下の外壁に通じる通路)② 2階:家畜や労働者の部屋 ・使用目的:農作業後の作業や、召使・家畜の居住空間 ・見どころ: ・馬を繋いだり、手工業的な作業をする様子 ・簡易的な間仕切りしかなく、生活は質素③ 3階:寝室(主に家族や高位の使用人) ・特徴: ・アーチ天井と石壁、居住に最適な安定した環境 ・ここからが「主家族の居住域」④ 4階:ホール(Great Hall/食堂兼応接室) ・使用目的:食事、来客応対、談話、政治の場 ・見どころ: ・暖炉とテーブル、居心地の良い空間 ・窓辺の席(window seat)、外を見渡す守備機能も⑤ 屋上(屋根裏階):見張り台・防御拠点 ・特徴: ・城壁上部の胸壁(クレネレーション)と見張り小屋 ・敵襲時にはここから矢や石を落とす(殺人孔:machicolation) ・屋根には雨樋も見られる(雨水排出)ロス城(Ross Castle)の塔屋(タワーハウス)の南面。1.スリット状の狭い窓(Arrow Loops/射撃用スリット)・この面には、縦に3つ並ぶスリット状の細長い窓が見えます。これは「アローループ」または 「ディフェンススリット」と呼ばれ、弓矢やクロスボウを用いた防衛のために設置されて いました。・敵に内部を見せず、こちらからは攻撃できる構造です。2.マシコレーション(Machicolation)・上部右側に突き出している部分が「マシコレーション」と呼ばれる構造で、真下に向かって石や熱湯、 排泄物などを落とすことができる開口部です。・これは敵が城壁に取り付いたときの防御手段として非常に重要でした。3.城壁上部のバトルメント(Battlements)・上部には交互に突き出した「胸壁(クレネレーション)」が見られます。・これは攻撃と防御を繰り返しながら身を隠せるようにするための構造です。4.「Cap House(キャップハウス)」・上部中央に見える小さな屋根構造は「キャップハウス」と呼ばれ、螺旋階段の最上部に 位置する見張り小屋です。「The South WallThe barracks building you are now in was attached to this wall in the 1700s. You can see an artist’s impression of this on the wall behind you.The window at the bottom of this wall was converted into a door, linking the barracks to the castle, which is still in use.」 【南側の壁現在あなたがいる兵舎の建物は、1700年代にこの壁に接続されました。これについての画家の想像図があなたの後ろの壁に展示されています。この壁の下部にあった窓は扉に改造され、兵舎と城を結ぶ通路として、現在も使用されています。】窓の数・位置が非常に限定されており、防御を優先した設計になっていた。模型の正面(西面)には:・地階の小さな明かり取り用スリット・中層階に3つの縦スリット窓(矢狭間)・上層に1つのやや大きな窓(ホール階の窓)・屋上には防壁(クレネレーション)と、左隅に小塔・Machicolation(マチコレーション) (角塔・見張り塔)があった。 「Machicolation Over the Northwest Corner」 【北西角上部のマチコレーション】「Gun Loops(銃眼)」というラベルが示されているように、防衛用の開口部も確認できます。Machicolation(マチコレーション) とは、城壁や塔の上部に設けられた石造の張り出し部分で、床に穴があり、そこから敵に向かって石・熱湯・油などを落とす防御構造です。Gun Loops(銃眼) は、火器(マスケット銃など)を撃つための小さな開口部で、防御側が内部から敵を狙撃できるようになっています。こんな感じであったのでしょうか?「The West WallA MACHICOLATION overhangs the top left hand corner of this wall, allowing defendersto fire down on attackers from the roof level wall walk. The two machicolations, at opposite corners, were added about fifty years after the castle was built. As well as protecting the base of the walls, they were fitted with gun loops, providing wider cover.At the top of this wall is the largest window in the castle, lighting the hall. The hall is so high up, that it was safe to insert a large window here, allowing in more light. Lower down, the windows are reduced to narrow arrow loops.At the bottom left of the wall is the end of the garderobe (toilet) chute, which runs down the inside of the wall from the first floor.」 【西の壁この壁の左上隅にはマチコレーション(防御用の石造張り出し構造)が張り出しており、屋上の歩道から攻撃者に向かって下方へ攻撃を加えることができました。このマチコレーションは、城が建設された約50年後に反対の隅とあわせて追加されたものです。これらは壁の基部を防御する役割を果たしただけでなく、銃眼(Gun Loops)も備えられており、より広い範囲を射撃できるようになっていました。この壁の最上部には、城内で最大の窓があります。この窓はホールを照らすためのもので、ホールが非常に高い位置にあるため、大きな窓を設けても安全だったのです。下の階に行くほど、窓は矢狭間(arrow loops)と呼ばれる狭い開口部に変わっていきます。壁の左下には、1階から壁の内側を通って下に伸びるガーダローブ(トイレ)の排出用シュートの出口があります。】「The North WallAt the top of the north wall is a heavy wooden ‘shutter’, hung from stone brackets.This hinged outwards, protecting defenders on the roof while they fired on attackers at the door below. This is a unique feature in Ireland, though known from castles in Europe.The larger windows in this wall were inserted in the 1500s.」【北の壁北の壁の最上部には、重い木製の「シャッター」が石製のブラケットに吊るされた状態で設置されています。このシャッターは外側に開閉する構造で、屋上の防御側が下の扉を攻撃する敵に向かって矢や銃を放つ際に身を守るためのものです。この構造はアイルランドでは珍しいものですが、ヨーロッパの城には類似例が見られます。】 ロス城(Ross Castle)の塔屋の模型を南西方向から。ロス城(Ross Castle)を描いた歴史的な18世紀末~19世紀初頭の風景画。右下に「Courtesy of the National Library of Ireland」とあり、国立アイルランド図書館の所蔵作品。絵の中央の塔がロス城の主塔(タワーハウス)、その左の斜め屋根建物が後に説明された「兵舎」にあたる。湖の広がりと山の連なりが背景にあるため、位置的には現在の遊覧船桟橋側からの視点に近いであろうか。ロス城(Ross Castle)の南側の城壁を外から。石造りの城壁 この分厚い石壁は、攻撃に耐えるために建設されたもので、当時の典型的なタワーハウス 防衛構造です。上部には**防御用の胸壁(battlements)**が見えます。左端の小塔(角の部分) この小塔の上部は「マシコレーション(machicolation)」と呼ばれる防御構造が付け 加えられていた場所です。敵が城壁のすぐ下に接近した際に、上から石や熱湯などを 落とすための構造です。ロス城(Ross Castle)の北壁(The North Wall)を下から。ROSS城(ロス城)北側の芝生エリアのカモたち。その先に木橋。木々の間に、観光用の馬車(ジャウンティーカー jaunting car)が見えた。マガモ(Mallard)たち。ほとんどがオスのマガモ。オスは鮮やかな緑色の頭部、白い首輪、灰色の胴体、黒い尾と、尾の横に白い羽が。ROSS城(ロス城)付近に設置された観光案内板で、「Ciar's Quest(キアの冒険)」という自然探索プログラムを紹介していた。「Download the free Ciar’s Quest app, seek special symbols on the marked trail andhelp Ciar on his quest to find iconic Kerry wildlife & hidden gems.」 【無料の “Ciar’s Quest” アプリをダウンロードして、指定されたトレイル上の特別なシンボルを探し、キアと一緒にケリー州の象徴的な野生動物や隠された名所を発見しよう!】と。そしてROSS城(ロス城)の見学を終え、駐車場に戻り、次の目的地へと。 観光用の馬車(ジャウンティーカー jaunting car)が車の前方に。アイルランドの観光都市キラーニー(Killarney)で運行されている観光用2階建てバス(ダブルデッカー)。いわゆる乗り降り自由の周遊シャトルバスのようであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.20
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その52):Ross Castle・ロス城 へ(1/2)
この日は6月4日(水)、まずは「Ross Castle(ロス城)」に向かったのであった。宿泊場所のAPARTMENTSの内部の居間の写真を撮影。台所。台所横のテーブル。キッチンルームの全体を。テレビのニュースでは、日本野球界のレジェンド・長嶋茂雄氏が89歳で逝去されたと。大谷翔平の活躍のニュースも。そして、この日の朝の最初の訪問場所「Ross Castle」への走行ルート。「Lough Leane・レイン湖」に面した「Ross Castle・ロス城」はここ。 Ross Castle(ロス城)近くにある「Garden Café(ガーデン・カフェ)」への案内看板。そして正面に「Ross Castle・ロス城」👈️リンク の姿が現れた。湖面に映る城のリフレクションが非常に美しく、晴れでも曇りでも絵になる風景なのであった。 「Ross Castle・ロス城・築城時期:15世紀後半・築城者 :オドノフー家(O'Donoghue clan)・所在地 :キラーニー国立公園(Killarney National Park)内、 ロッホ・レーン(Lough Leane)湖畔・建築様式:中世の塔屋(Tower House)形式・特徴: ・厚い石壁と狭間(はざま=矢を射るための小窓) ・湖に面した立地で、戦略的・防衛的に重要な城であった ・アイルランド伝説では、この城の主「O’Donoghue」が湖の底に住み、霧の日には馬に 乗って現れるとされます。」 「Ross CastleBuilt for the O’Donoghue Chieftains during the first half of the 15th century, Ross Castlehas a typical tower house layout, with a banqueting hall and minstrel’s gallery on the topfloor.It was battlemented in the Irish fashion, and was surrounded by a bawn wall withflanking towers at each corner, two of which now remain.」【ロス城15世紀前(約1440年頃)にオドノフー族の族長たち(O’Donoghue Chieftains)によって建てられた。この城は、以下のような典型的な塔屋式レイアウトを持っています:・宴会場(バンケットホール)・最上階には吟遊詩人(ミンストレル)のギャラリーまた、この城はアイルランド式の防御構造(battlemented in the Irish fashion)を採用しており、四隅に防御用の塔(flanking towers)が設けられた防壁(bawn wall)に囲まれていました。現在、そのうちの2つの塔が現存しています。開館時間(Opening Hours) 3月〜11月(March to November) 9:30 – 17:00最終入場:閉館の1時間前】左手に「Ross Catle」絵入り案内板。 「Ross CatleRoss Catle is tower, built sometimes in the late 15th century by the O'Donoghue familywho ruled the Killarney area at the time.【ロス城ロス城は「塔屋式(タワーハウス)」の城で、15世紀後半ごろに当時キラーニー一帯を支配していたオドノフー一族によって建てられました。】「About 1500The castle was originary continued inside a strong stone bawn wall。Outside this ,there was probably an earthen bank and wooden palisade whichi enclosed an area calledthe bailey.The thatched houses insaide this were the homes at O'Donoghus's retainersor possibly of hired soldeiers.」 【1500年頃この城は、もともと頑丈な石造りの防御壁(バウン)の内側にありました。その外側には、おそらく土塁と木製の柵(パリセード)が築かれ、「バウン」と呼ばれる区域を囲っていたと考えられます。その内部には藁葺き屋根の家々があり、これらはオドノヒュー家に仕える家臣たち、あるいは雇われた兵士たちの住居であった可能性があります。】ロス城(Ross Castle)の建設当初(約1500年頃)の復元図.この時代のロス城は、オドノヒュー家(O'Donoghue family)によって建てられたもので、アイルランドの伝統的な塔型住宅(Tower House)として、防御機能を重視した構造になっている と。① タワーハウス(中央の高い塔) ・ 居住と防御を兼ねた主建造物。通常4〜5階建てで、最上部には防御用の胸壁(パラペット)。 ・ 小さな窓と厚い石壁により、攻撃への防備が強化されています。② バウン・ウォール(城壁)・主塔の周囲を囲む堅牢な石壁。四隅に**小塔(タレット)**があり、見張りと防衛に使用。 ・外敵の侵入を防ぐため、壁内は一つの閉じた防衛区域になっています。③ 内部の茅葺き家屋群(内部の建物)・城主の家臣や使用人の住居、倉庫、厨房など。・中庭(バリー)には、木造または石造の建物が複数建ち並んでいました。④ 外周の木製柵と堀・石壁の外側には、おそらく木製の柵(パリセード)や堀が設けられ、さらに防衛を強化。・図の下部(入口側)に橋が描かれており、跳ね橋や門番小屋の存在が示唆されます。About 1700By 1700 the castle had changed hands twice. The O'Donoghues were alliedwith the Earl of Desmond during his failed rebellion and so the castle fell intothe hands of the McCarthy Mor family. This was probably when the larger windowsand bartizans were added. The castle was subsequently granted to an English landsurveyor Sir Valentine Browne who, in 1688, built the fortified house against theside of the castle. To do this he demolished the west section of the bawn wall.【1700年頃1700年までに、この城は2度にわたって所有者が変わっていた。オドノヒュー家は反乱に失敗したデズモンド伯爵と同盟を結んでいたため、城はマッカーシー・モア家の手に渡った。おそらくこのとき、大きな窓やバーティザン(張り出し小塔)が追加されたと思われる。その後、この城はイングランドの土地測量技師であるサー・ヴァレンタイン・ブラウンに与えられた。彼は1688年に城の側に要塞化された邸宅を建設したが、そのために城の西側にあった城壁(ボーン・ウォール)の一部を取り壊した。】「ロス城(Ross Castle)」の1700年ごろの姿を再現したイラスト。この時代は、ロス城がオドノヒュー家(O'Donoghue)からイングランドの地図測量官バレンタイン・ブラウン(Valentine Browne)に渡った後の状態を描いている と。① 主塔(タワーハウス) ・中央の高くそびえる塔が、15世紀後半に建てられたオリジナルの要塞です。 ・防衛に優れた構造で、上部にはマーダーホール(殺人孔)や胸壁(パラペット)が見られます。② バウン・ウォール(外壁) ・城の敷地を囲む頑丈な石壁で、角には見張り用の小塔(タレット)が設けられています。 ・攻撃に備えて外部と内部を区画し、守備力を高める設計。③ 居住棟(長屋) ・手前の長い建物は、ブラウン卿(Sir Valentine Browne)によって1688年に建てられたもの。 ・居住空間または管理施設として使用されていたと考えられます。④ 馬や荷車のある中庭 ・中庭には馬や荷車、作業用の人々が描かれており、生活や管理機能の拠点だった様子がわかります。 ・城の防衛だけでなく、経済や生活の中心としての役割も果たしていたことを示しています。⑤ 通路と堀 ・図の左側には、城へ続く道や橋が見られます。堀があった可能性もあります。歴史的背景 ・オドノヒュー家は、デズモンド伯の反乱に加担して敗北し、城を失いました。 ・その後、城はマッカーシー・モー家(McCarthy Mór)を経て、1688年にブラウン卿へ 譲渡されました。 ・ブラウン卿は、城の西側に自らの居住棟を建設し、そのために西側のバウンウォールを 取り壊したと記録されています。About 1800By the mid-18th century the castle had become a garrison. Most of the bawn walls hadbeen removed, Valentine Browne's house had been demolished, and it had beennecessary to support the north-west corner of the castle with a substantial buttress.A new barrack block was built, as well as additional accommodation on the west side.This drawing shows the castle shortly after the 1798 rising at a time when the Englishwere expecting a French invasion.」 【1800年頃18世紀中頃までに、この城は駐屯地(ガリソン)として使われるようになっていた。ボーン・ウォール(防御用の外壁)のほとんどが取り壊され、ヴァレンタイン・ブラウンが建てた家屋も撤去されていた。その結果、城の北西角を支えるために大きな控え壁(バットレス)を設置する必要があった。さらに、新たな兵舎棟と、西側には追加の宿泊施設が建設された。この図は、1798年の蜂起直後、イギリス側がフランスの侵攻を予期していた時代の城の様子を示している。】この図は、ロス城(Ross Castle)の1800年頃の様子を再現したイラスト。このイラストは、1798年のアイルランド蜂起直後、フランス軍の侵攻が懸念された時期のロス城を描いている。18世紀後半の軍事施設(ガリソン)としての様子を示しており、追加の兵舎や防衛施設が見られるのだ。主な構造と説明① ロス城の本体(中央の高い塔) ・15世紀にオドノヒュー(O'Donoghue)一族が建てた塔屋(タワーハウス)。 ・石造の高い主塔(keep)で、かつての領主の居住・防衛の中心。② 煙突のある長い建物(兵舎・バラック) ・18世紀に建てられた兵舎棟(Barrack block)。 ・兵士の宿泊施設として使われていた。 ・城の南側(イラストの左)に延びるように設置。③ 外壁(バウン・ウォール:Bawn Wall) ・城を取り囲んでいた石の外壁。 ・この時期にはほとんどが撤去されているが、一部が残されている。④ 控え壁(バットレス) ・城の北西角を支えるための補強壁(buttress)。 ・土台が弱くなっていた箇所を補強している。⑤ 西側の追加施設(小屋や補助建物) ・西側には炊事場や倉庫、衛生施設などが追加されていた。 ・軍の駐屯に伴う生活機能が強化されている。⑥ 川(湖)沿いの護岸と上陸場 ・城の周辺にはロッシ湖(Lough Leane)が広がっており、船着き場や護岸も描かれている。 ・水路による補給や移動も考慮されていた。図は D. Tietzsch-Tyler 氏によって描かれたもの。下部のキャプションに「Ross Castle — from Caisleán an Rois (Castle of the Promontory)」とあり、城の正式な意味が記されている と(Caisleán an Rois は「岬の城」)。ここにも「ROSS CASTLE」案内板。 「ROSS CASTLE・ロス城」前に広がる「Lough Leane・レイン湖」。レイン湖(Lough Leane, アイルランド語: Loch Léin)は、アイルランド南西部のケリー県(County Kerry)に位置するキラーニー国立公園(Killarney National Park)の中心的な湖。 多くの野鳥が羽を休めていた。マガモ(Mallard)のオス(雄)であっただろうか?・頭部が緑色の光沢(金属光沢のある濃緑)・くちばしが黄色・胸は栗色、腹は灰色、尾は白黒・翼の中央に「青紫色の翼鏡(よくきょう)」があり、白い縁取りがある・脚は橙色(オレンジ)高さ約5階建ての塔屋式天守(Tower House)を正面に。ズームして。・四隅に見張り塔を備えた「バウン・ウォール(防御壁)」が城を取り囲んでいた。 (現在は部分的に残存)・最上階には出窓式のミンストレルギャラリー(楽師の間)が設置されていた。・頑丈な石造りで、敵の侵入を防ぐための狭間(arrow slits)や防御的な出入口が見られる。再び「Lough Leane・レイン湖」を。面積 約 19.6 km²(平方キロメートル)最大長 約 8 km(南北方向)最大幅 約 3 km(東西方向)最大水深 約 60 m(推定)標高 約 20 m(海抜) と。現在の関係者通用門であっただろうか?写真の門は主門(大きな正面の出入口)ではなく、側面の壁に設けられた小規模な出入口。アーチ型の石積みで、上部には監視・防御目的の窓(または射撃口)が設けられていた。ロス城(Ross Castle)の主塔(タワーハウス/keep)を真下から見上げて。壁面に多数ある縦長の細いスリット状の開口部は、「矢狭間」または「銃眼」と呼ばれる。中世の初期には弓やクロスボウ、後期には火縄銃(アーキバスなど)で攻撃するためのもので、内部から外部へ射撃可能、外部からはほぼ攻撃不可能な構造である と。マーダーホール(Murder Hole)※上部最上部の出っ張った部分には、石や熱湯、油などを下に落とす穴(マーダーホール)が設けられていた可能性がある と。①主門や通路の上に設けられ、侵入者に対して上から攻撃できる防御機能。②バトルメント(Battlements)とマシュクリレーション(Machicolation) 最上部のギザギザのような部分(城塞の縁)は、「バトルメント(胸壁)」と呼ばれ、 兵士が隠れながら反撃できる構造です。 一部の部分が張り出し、その下に開口部がある構造は「マシュクリレーション」といい、 ここからも石や矢を落とせるようになっている。③窓(格子付き)や換気用スリット 中央部のやや幅の広い開口部は、後世に追加された格子付きの窓である可能性がある と。レイン湖遊覧船(Lake Cruise Boat)。廻り込んで、ロス城(Ross Castle)のタワーハウス(Tower House)・主塔を西側から。写真のこの面には窓が少なく狭いのがわかります。これは防御性を高める設計。左側の建物(角楼・砲塔)は城の主塔(タワーハウス)や城壁の隅を防御するための見張りおよび砲撃用の施設。特にこの塔は海や湖側からの侵入に備える構造。「Killarney National Park(キラーニー国立公園)Killarney National Park, 10,289 hectares in extent, comprises the mountains andwoodlands which surround the world famous Lakes of Killarney, as well as the three Lakes themselves. The Park includes the peaks of Mangerton, Torc, Shehy and the Purplemountains. Just to the west of the Park rises MacGillycuddy's Reeks, the highestmountain range in Ireland.The nucleus of the National Park is the 4,000 hectare Bourn Vincent Memorial Park,formerly known as the Muckross Estate, which was presented to the State in 1932by Mr. and Mrs. W. Bowers Bourn and their son-in-law Senator Arthur Vincent to beIreland’s first National Park.In 1981, the Park was designated as a Biosphere Reserve under the UNESCO Man andthe Biosphere Programme. It is therefore a part of a world network of natural areaswhich have conservation, research, education and training as major objectives.Killarney National Park is part of the largest candidate Special Area of Conservation(SAC) in the country under the EU Habitats Directive as well as being an SpecialProtection Area (SPA) under the EU Birds directive.」 【キラーニー国立公園キラーニー国立公園は、10,289ヘクタールにおよび、世界的に有名なキラーニー湖群とそれを囲む山々や森林を含んでいます。公園には、マンガートン山、トーク山、シーヒー山、パープルマウンテンズ(紫の山々)の山頂が含まれています。公園の西側には、アイルランド最高峰の山岳地帯「マクギリカディ・リークス」がそびえ立ちます。国立公園の中心は、かつてマックロス・エステートとして知られていた4,000ヘクタールのボーン・ヴィンセント記念公園であり、1932年にW.・バワーズ・ボーン夫妻およびその娘婿アーサー・ヴィンセント上院議員から国家に寄贈され、アイルランド初の国立公園となりました。近年では、旧ケンメア領地の土地と水域が加わり、今日の規模とアイルランドを代表する国立公園としての地位を確立しました。1981年には、UNESCOの「人間と生物圏計画」の下で生物圏保護区に指定され、保全・研究・教育・訓練を主要目的とする世界的な自然保護ネットワークの一部となっています。キラーニー国立公園は、EUの「生息地指令」に基づく最大規模の特別保護区域(SAC)候補地であり、また「鳥類指令」に基づく特別保護地域(SPA)でもあります。】「Innisfallen IslandInnisfallen Island (Inis Faithleann) once the home of a monastery, dating back to640 AD.Founded by St. Finian the Leper.The Island was a place of solitude for the monks to reflect and pray.Located in Killarney National Park, Lower Lake, Lough Lein, just 1.5 km from Ross Castle.The monks were great scholars, and the High King of Ireland Brian Boru was said tohave studied on Innisfallen Island.Over a three hundred years period 39 monks wrote what is now known as the Annals of Innisfallen, a history of Ireland written in Irish and Latin. The Annals are considered ofmajor importance to historians.The Annals are currently housed in the Bodleian Library, in Oxford, but there is hopethey will return to Killarney in the not too distant future.On the island you will see the ruins of a 12th century Augustinian priory, as well as a Romanesque church, which are the remarkable remains of this early Christian period.The Island was gifted to the Irish Nation by the late John and Mary McShain,of Killarney House and Philadelphia, USA in 1972.It is cared for by the National Parks and Wildlife Service.Páirc Náisiúnta Chill AirneKillarney National Park」 【イニスファレン島イニスファレン島(アイルランド語: Inis Faithleann)は、かつて修道院のあった島で、西暦640年にまで遡る歴史を持ちます。創設者はハンセン病の聖フィニアン(St. Finian the Leper)です。この島は、修道士たちにとって祈りと内省の静かな場でした。場所はキラーニー国立公園のレイン湖(Lough Leane)下湖部(Lower Lake)にあり、ロス城(Ross Castle)から約1.5kmのところにあります。修道士たちは高い学識を持ち、アイルランドの大王ブライアン・ボル(Brian Boru)もここで学んだと伝えられています。約300年の間に、39人の修道士がアイルランドの歴史を記した『イニスファレン年代記(Annals of Innisfallen)』をアイルランド語とラテン語で著しました。これは歴史的に極めて重要な史料とされています。この『年代記』は現在、イギリス・オックスフォードのボドリアン図書館に所蔵されていますが、将来的にはキラーニーへの返還も期待されています。島には、12世紀のアウグスティノ会の修道院跡や、ロマネスク様式の教会の遺構があり、初期キリスト教時代の貴重な名残を見ることができます。この島は、1972年にジョン&メアリー・マクシェイン夫妻(米フィラデルフィア/キラーニー・ハウス)よりアイルランド国家へ寄贈されました。現在は国立公園・野生動物庁により管理されています。】「Innisfallen Island・イニスファレン島」をネットから。さらに「Ross Castle・ロス城」周囲を南に向かって歩く。ロス城(Ross Castle)の敷地内にある屋外ピクニックエリアの軽食・カフェ施設。西側の主塔(タワーハウス)を見上げて。「Ross Castle Garden Café(ロス城ガーデンカフェ)」。 吊り下げられた花籠や白い窓枠が印象的。一周して東側に戻る。大砲。ロス城は15世紀後半にO'Donoghue Mór一族によって建てられた塔屋式城館(Tower House)。1652年、クロムウェル軍に包囲され、湖から砲艦で攻撃され降伏。このときの伝説では「湖から砲撃されるまでロス城は陥落しない」と信じられていた。この大砲はその歴史的場面を再現する展示物と。ロス城の周囲を1周して観光客用入口まで戻る。観光客用入口。時間は9:27。開館時間は9:30~。左側の角の部分には小型の見張り塔が設置され、監視・防御の拠点となっている と。廻り込んで。ここにも角塔(タレット:turret)が。城壁の角や出隅に取り付けられた小さな塔で、通常は円形か八角形。この部分は見張り台(watchtower)や防御用の射撃位置(defensive turret)として使用された と ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.19
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その51): Adare・Trinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)(3/3)~Desmond Castle Adare(デズモンド城)~ホテルへ
そしてN21・メイン・ストリートを更に進み、River Maigue(メイグ川)に架かる「14 Arch Bridge(1400)」を渡る。 右手奥、River Maigue(マイグ川)の川岸に建っていたのが「Desmond Castle Adare(デズモンド城)」。 手前の野花と草地が美しく、川越しに城がそびえ立つ構図は、アデア村の風景の中でも特に絵になる一枚なのであった。「デズモンド城(Adare Castle / Desmond Castle)・所在地: アイルランド共和国リムリック県アデア村(Adare, Co. Limerick)・築城時期: 約1226年、ノルマン人による建設・主要使用時期: 13〜16世紀・主な所有者: ・オドノバン家(原初の支配者) ・フィッツジェラルド家(Kildare伯) ・ジェラルディン家(デズモンド伯、Earl of Desmond)」 「遺構と現況 ・保存状況: 城壁、塔、門、内部構造の一部が比較的良好に保存。 ・修復: アイルランド政府によって1990年代に部分修復。 ・(予約推奨)。 ・敷地内には現在も堀の跡や野草の群生地が見られ、歴史と自然が融合した雰囲気を楽しめます。」 『見学はアデア・ヘリテージセンターからのガイドツアーのみで内部見学可』!!。しかし、我々4人はそれを知らずに、ひたすら入口を探して歩いていたのであった。「構造と間取りデズモンド城は典型的なノルマン型河畔城郭であり、以下のような構成が確認されています:1. 曲輪(Curtilage / Bawn) ・厚い石壁で囲まれた中庭空間。 ・城の中心であり、居住や軍事活動の拠点。 ・壁の上には歩哨路(wall-walk)と胸壁(crenellation)。2. 主塔(Keep / Great Tower) ・城内で最も堅固な建物。 ・多層構造で、最上階には見張り台。 ・下層は倉庫や兵舎、上層は居住区。3. 防衛用塔(Corner Towers / Bastions) ・四隅に配された円筒型または角塔。 ・弓兵やクロスボウ兵による十字砲火が可能な構造。 ・下部に矢狭間(arrow slits)あり。4. 城門・ポータル(Gatehouse) ・主出入口には厚い木製扉と鉄格子(ポートカリス)。 ・侵入者を狭所で迎撃する仕掛け(死の落とし戸=murder hole)。5. 居住区画(Hall / Living Quarters) ・士官や家族、召使が住んでいた木造または石造の建物。 ・暖炉、窓、簡易な床材などが残る。6. 聖堂跡(Chapel) ・小規模なゴシック様式のチャペル跡が確認されている。 ・城主および兵の宗教儀礼の場。」 「軍事的役割◎ 防衛機能(13世紀〜16世紀)1.戦略的立地: ・リバー・マイグ(River Maigue)の西岸に位置し、水運と交通の監視が可能。 ・アデア地方の支配拠点として機能。2.封建防衛: ・ノルマン=アングロ支配者が、ゲール系アイルランド人勢力に対抗するための砦。 ・16世紀のデズモンド反乱(Desmond Rebellions)では重要な前線基地となる。3.城塞構造: ・高い石壁と塔で囲まれ、攻囲戦に耐えうる設計。 ・内部には弾薬・食糧の備蓄倉庫もあったとされる。4.中世後期には儀礼的役割も: ・軍事的重要性の低下とともに、貴族の威信の象徴へ。 ・城のホールは宴会や裁判、徴税などに使われた。」 上空からの写真をネットから。デズモンド城(Desmond Castle)の見学入口に設けられた金属製ゲートは閉まっていたのであった。 左側の白い標識には「Access to this OPW site isstrictly with a guide from theAdare Heritage Centre.Your co-operation is appreciated.」 【このOPW(公共事業庁)管理地への立ち入りは、アデア・ヘリテージセンターのガイド同伴に限られます。ご協力に感謝いたします。】ここで初めて、見学は予約、ガイド同伴が必要 を知ったのであった。その先にあったのがゴルフ場入口「ADARE MONOR GOLF CLUB EST 1900」。 ここまでとして引き返す。「デズモンド城(Desmond Castle, Adare)」の天守(キープ)部分を、西側から望んで。「14 Arch Bridge(1400)」から再び「Desmond Castle Adare(デズモンド城)」を。「Desmond Castle Adare(デズモンド城)」👈️リンクをズームして。アデア(Adare)村の入り口に設置されているウェルカム標識。アデア(Adare)の歴史的遺産地区(Heritage Town)を訪れる観光客向けの案内板。 施設名(英語) 創建年 内容Augustinian Abbey 1315年 アウグスチノ会修道院。アデア中心部の北東に位置。Franciscan Abbey 1464年 フランシスコ会修道院。現在は廃墟、保存状態良好。Trinitarian Abbey 1230年 トリニタリアン修道院。世界でも稀な修道会の跡。現在教会 として使用。Desmond Castle 1202年 デズモンド家の城。川沿いに建つ軍事拠点。OPW管理下。この標識は、アイルランドのアデア(Adare)村が「Tidy Towns(タウンズ美化運動)」において、3年連続ゴールドメダルを受賞したことを示していた。帰路にも、「藁葺き屋根のコテージ群(Thatched Cottages)」を再び。「Adare Manor(アデア・マナー)の正門ゲート」も。そして「Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)」まで戻り内部へと。歴史的な衣装と場面を再現した蝋人形の展示がされていた。馬に乗った女性の蝋人形・19世紀またはそれ以前のアイルランドの農村女性または巡礼者を表現していた。・フード付きマントと粗布の衣服で、雨や風から身を守っていた。・黒い馬に乗っており、移動手段としての馬が一般的だった時代を示唆。 廻り込んで。馬を引いている男性 は、農民あるいは従者の姿。素朴な衣服をまとい、主に仕えている様子がうかがえるのであった。背景に貼られたパネル には「PICTURESQUE ADARE(絵のように美しいアデア)」の文字があり、アデアの町並みを紹介するパネル展示が。デズモンド城(Desmond Castle)の模型(復元ジオラマ)。模型の構造解説以下は模型に基づく主な建造物とその機能:1. ゲートハウス(正門) 城の正面中央に位置し、頑丈な木製の門が取り付けられています。 通常は跳ね橋が設けられ、堀と連携して防衛線を構成。 門塔(左右の高い塔)は門への侵入を監視・防御する役割。2. カーテンウォール(城壁) 高い石壁が城内を囲んでおり、外敵からの防御を目的としています。 上部には胸壁(battlements)があり、兵士が身を隠しながら弓や矢を射つことができます。3. コーナータワー(円塔・角塔) 四隅や要所に配置され、敵の接近を高所から監視する目的。 円形塔は死角が少なく防御に有利。 階上は弓兵や見張り台として活用。4. キープ(主塔 / 大広間) 城内中央に建つ大きな建物。 領主の住居や行政・儀式の中心。 外敵が侵入しても最後の拠点となる「最終防衛施設」。5. 小道・通路 各塔や建物を結ぶ通路が再現されており、連携した防衛行動が可能であることを示します。事前に知りたかった内容が書かれていたのであった。「Desmond Castle ToursDaily Guided Castle Tours:10:00am, 12:00pm, 2:00pm, 3:30pmAsk at reception, call 061 396 666 or book online:www.adareheritagecentre.ie/tour-bookings/」 【デズモンド城ツアー毎日開催のガイド付き城内ツアー: ・午前10時 ・正午12時 ・午後2時 ・午後3時30分受付にてお尋ねいただくか、以下の電話番号にお電話ください:☎ 061 396 666または、下記ウェブサイトからオンライン予約が可能です:🌐 www.adareheritagecentre.ie/tour-bookings/】そしてレンタカーに戻り、この日の宿泊場所の Killarneyに向かって進む。帰路のルートはひたすらN21を南西方向に。アイルランドの高速道路は、この日に限らず比較的空いていた。Croagh・クロアーの街に向かって進む。屋根にはソーラーパネル?が。テンプルグランティーン近くから見た風力発電装置。アイルランドの西海岸方向の風力発電装置の普及率はまだまだ少なかった。Abbeyfeale・アビーフェールの街に入り「Convent Rd・コンベント・ロード」を走る。右手には教会があったが名前は「Saint Mary's Convert ・聖マリア修道院、付属礼拝堂」 。Limerick県からKerry県に入る。事故?故障トラックか?Kerry県の草原地帯を南下。Kerry Airport・ケリー・エアポートが前方に姿を現した。N22に入り進む。Lough Leane・レイン湖を囲む山々の姿。Killarneyの街に入る。アイルランド、ケリー県にある町 キラーニー(Killarney/アイルランド語名:Cill Airne、「スズランの教会」の意) は、人口約14,400人(2022年)で、観光が盛んな美しい地方都市。キラーニー国立公園(102.9 km²)はアイルランド初の国立公園で、湖、水辺の森、山岳地帯、野生のレッドディア(アイルランド本土唯一)を含む多様な生態系を有していると。1981年にはユネスコの生物圏保護区に指定された。公園内の三つの湖(Lough Leane, Muckross Lake, Upper Lake)や観光名所の Ross Castle、Muckross House & Gardens は歴史・景観共に見応えがあったのだ。N71・East Avenには観光用の馬車の姿があった。この後にMuckross RdのFlesk Riverを渡った後にこの日の宿泊場所のApartmentsへの道に迷い、しばしの迷走。そして何とかこの日の宿泊場所に到着したのであった。2連泊の宿泊場所「Flesk River Apartments」。そしてこの日の夕食は宿から徒歩5分程の場所にあった4つ星ホテル「The Brehon Hotel & Spa」。ネットからホテルの航空写真を。ホテルの裏の奥が我々の宿泊場所「Flesk River Apartments」。正面から。夕食の写真はこのスープのみで、他の料理やホテル内部の写真や旅友の写真は撮り忘れていました。 ・・・もどる・・・ ・・・・つづく・・・
2025.08.18
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その50):Adare Trinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)(2/3)
N21道路沿いのカトリック教会の境内に設置された祈念碑が右手前に。再びTrinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)の敷地内を散策する。「聖母マリア像(Our Lady / Virgin Mary)」の石像。近づいて。合掌して祈りを捧げる姿。これはマリア像の典型的なポーズで、信仰と謙虚さ、慈愛の象徴。ローブには繊細な植物文様や十字架のような装飾が浮き彫りされ、非常に細密な彫刻。これはマリアの「純潔」「神聖さ」を視覚的に伝える工夫 と。手から下がるロザリオは、祈りと瞑想を意味し、マリア信仰に深く関わる象徴。再び塔を見上げて。塔は四角い形状で、要塞建築のように頑丈に見えた。胸壁(バトルメント):上部には切り欠きのある石の防壁(クレネレーション)があり、 これは中世の防御建築によく見られるスタイル。スリット状の銃眼(ループホール):塔の壁に縦長の狭いスリットがあり、これはかつて 弓や銃での防御のために用いられたものです。石の外壁には苔や草が生えており、中世以来の長い歴史を感じさせたのであった。トリニタリアン修道会は12世紀末に設立されたカトリック修道会で、このアデアの修道院は13世紀初頭にノルマン系の領主により創建されたと。アデア村は3つの修道院遺跡(フランシスコ会、オーガスチン会、トリニタリアン会)で知られており、特にこのトリニタリアン修道院はアイルランドで唯一残る同会の修道院建築。ゴシック・リヴァイヴァル様式(Gothic Revival)様式の教会の入口。こちらは脇門?脇門の正面に移動して。・尖頭アーチ(ポインテッドアーチ)の入口。・アーチ上部の小尖塔(ピナクル)・壁上部には、ここにも胸壁(クレネレーション)が残されており、これは中世の要塞的建築を 模していた。・十字架が正面の三角破風の上に掲げられており、キリスト教会堂であることが明示されていた。・ゴシック窓も側面に見られ、細い尖頭アーチ形のステンドグラス窓が設置されていた。「AdareÁTH DARATRINITARIAN MONASTERYMainistir Ord na TríonóideFounded in 1230, this is the only monastery of the Trinitarian order known in Ireland. It is now Holy Trinity Abbey, Adare’s Roman Catholic church.The Trinitarian order – or the Order of the Redemption of Captives – was founded in France at the end of the 12th century. Their purpose was to rescue hostages takenduring the Crusades in the Holy Land. The monasteries in Northern Europe were set up to recruit monks and collect ransom money, though some were hospitals for rescued captives. The Trinitarians may have come to Adare from Scotland.After the Crusades, the monks gradually assumed a way of life little different from other orders.」 【トリニタリアン修道院Mainistir Ord na Tríonóide(アイルランド語名)1230年に創設されたこの修道院は、アイルランドで唯一知られているトリニタリアン会の修道院です。現在はホーリー・トリニティ・アビー(Holy Trinity Abbey)として、アデアのローマ・カトリック教会となっています。トリニタリアン会(捕虜救済の修道会)は、12世紀末にフランスで設立されました。彼らの目的は、十字軍遠征中に聖地で捕らえられた人々を救出することでした。北ヨーロッパに設けられた修道院では、修道士を募り、身代金を集める活動が行われていました。一部の施設は救出された捕虜のための病院でもありました。アデアの修道士たちは、スコットランドからやってきた可能性があります。十字軍の終結後、修道士たちの生活様式は次第に他の修道会とほとんど変わらないものになっていきました。】(右側小テキスト)「A panel from the stained-glass window above the altar shows a monk in chains about to redeem a hostage.」【祭壇上部のステンドグラスの一枚のパネルには、捕虜を救おうとして鎖につながれた修道士が描かれています。】 西面を見る。こちらが「西正面ファサード」であっただろうか? 大きな入口扉と壮麗なトレーサリー付きの窓が。さらに奥に進んで。教会の西側敷地内を見る。西面と南面の接合部を斜めから捉えた構図で。道路沿いにあった「記念十字架(Memorial Cross)」。十字架の上部はケルト風の装飾が施された石のクロスで、アイルランドの伝統的なハイクロス(High Cross)を模した様式。柱の上部には編み込み模様(interlace)が見られ、装飾的意味と象徴的意味(信仰の堅固さや永遠性)を併せ持っているとのこと。台座は4面構成で、中央に十字のレリーフと水飲み場のような突起があり、おそらくかつては噴水機能があったのでは。左右に碑文が刻まれた「戦争記念碑(War Memorial)」。 Holy Trinity Abbey Church(旧トリニタリアン修道院)境内にあった歴史的な噴水(fountain)の修復記念碑。「Unveiled 5th November 2021byCouncillor Daniel Butler, Mayor of theCity & County of Limerickto mark the restoration of this historicfountain by Limerick City and County Council.」 【2021年11月5日 除幕リムリック市および郡の市長、ダニエル・バトラー市議によってこの歴史的な噴水の修復を記念して、リムリック市・郡議会により建立された。】Trinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)を背景に。ズームして。Trinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)の内部へ。祭壇を正面から。写真中央の大アーチ(尖頭アーチ)はゴシック建築の典型。アーチの上部に描かれた金文字のラテン語文が視線を引きつけたのであった。「QUAM DILECTA TABERNACULA TUA DOMINE VIRTUTUM」【あなたの住まいはいかに愛されていることか、万軍の主よ】これは典型的な教会の祭壇上部に掲げられる句で、聖堂が神の住まいであることを讃えているのだ と。奥のステンドグラス窓。キリストや聖人の姿が色鮮やかに描かれていた。特に中央には、イエス・キリストの昇天または聖三位一体(Trinity)がテーマに。中央の白衣をまとい、光輪(nimbus)を持つ人物はキリスト。頭上から神の光が降り注ぐ様子が放射状のラインで描かれていた。キリストは両手を広げ、両側には跪く人々が配置される典型的な「裁き主」としての姿に近い。左側第2パネル:キリストの受難を示すような衣をまとった男性が登場(おそらくペテロ またはパウロ)右側第4パネル:ひざまずく女性と子どもを祝福するキリスト(慈愛の象徴)左右端パネル:説教や施しを行う聖人(福音記者または使徒たち)<小型の三連ランセット窓(three-light lancet window)主に聖母マリアと幼子イエスに焦点を当てた図像構成となっており、母性・慈愛・信仰のテーマが前面に描かれているのだ と。中央:聖母マリアが玉座に座り、幼子イエスを抱く場面左 :上部に聖歌隊の天使たち、下部には巻物を持った聖人(おそらく旧約の預言者)右 :聖歌隊の天使たち。部には若い母親と子どものような姿(マリアの母アンナ)各パネルの下部にはそれぞれ紋章が描かれていた。中央:王冠とユリ(純潔)のモチーフ → 聖母マリアの象徴左右:ダンレイヴン伯爵家の家紋である可能性(この教会の庇護者)右:赤と青の衣に身を包んだ栄光のキリスト(Christ in Majesty)が玉座に座っており、 威厳ある姿で右手を挙げ祝福。足元には地球を象徴する青い球体。左:白衣をまとった復活のキリストが、手に十字架と勝利の旗(白地に赤十字)を掲げて登場。 足元には倒れる兵士の姿。これはキリストの墓を守っていたローマ兵が驚いて倒れ伏す様子。さらにステンドグラスをカメラで追ったのであった。ステンドグラスを短い時間で慌ただしく楽しんで外に出る。道路沿いの案内標識。アイルランド・リムリック県の「リムリック・グリーンウェイ(Limerick Greenway)」の観光案内看板。これは、かつての鉄道路線を活用したサイクリング・ウォーキング用の全長40km以上の緑道(greenway)とのこと。そしてアデア村の中心部、Main Street沿いにあった「Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)」。Adare Tourist Information Point(アデア観光案内所)。上部にはおなじみの緑地に白の "i" マークがあり、これは国際的に認知されている「インフォメーション(案内所)」の標識。「Adare Heritage Centre(アデア・ヘリテージ・センター)」の内部には後ほどに と。引き返して、再びTrinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)を背景に記念十字架(Memorial Cross)を。戦争犠牲者の慰霊を目的に建立されたもの。先ほど訪ねた「藁葺き屋根のコテージ群(Thatched Cottages)」を道路越しに。ズームして。道路の右側前方に見てきたのが、「Adare Manor(アデア・マナー)の正門ゲート」。・19世紀に建てられたネオ・ゴシック様式のマナーハウス(大邸宅)・現在は5つ星の高級リゾートホテル&ゴルフ場・Adare Manor Golf Club。・広大な敷地には、ゴルフコース、スパ、ファインダイニング、乗馬施設などが整備・2027年のライダーカップ(Ryder Cup)開催地にも決定されており、世界的に注目されている 上空からの写真をネットから。手前に巨大なゴルフ場・Adare Manor Golf Club。Adare Manor(アデア・マナー)。その先にあったのは、Adare Manor(アデア・マナー)のもう一つのメインゲート(セキュリティゲートハウス)。Adare Manorの敷地の出入口にあたるが、こちらはより厳格な管理用の入り口としての性格が強いもののようだ。宿泊ゲスト、関係者、スタッフなどの出入りを管理する受付・警備所。石造りでゴシック調のデザインが施されており、本邸と統一された建築様式になっている。屋根はスレート葺きで、尖塔や煙突、尖頭アーチ窓が中世風の雰囲気を醸し出していた。N21を「Desmond Castle Adare」の見学に向かって徒歩にてさらに北上する。 左手奥にあったのが「アウグスチノ会修道院跡(Augustinian Priory / Abbey)」。1315年頃、ジョン・フィッツトーマス・フィッツジェラルド(John FitzThomas FitzGerald, 1st Earl of Kildare)によって創設 された と。修道士の服の色から「ブラック・アビー」と呼ばれていた。宗教活動は約200年間続きましたが、16世紀半ばにコミュニティは廃止されたとのこと。「アウグスチノ会修道院跡(Augustinian Priory / Abbey)」入口ゲートにあった看板。「St. Nicholas’ National School(セント・ニコラス国立学校)」の2025年度入学案内。アイルランドの大学の新学期(学年度の開始)はイギリスと同様に一般的に9月から。「St. Nicholas’ National School(セント・ニコラス国立学校)は、男女共学の小規模な国立小学校で、3人の担任教師と2人のサポート教師が在籍しています。学校はアデアの郊外、マイグ川(River Maigue)のほとりに位置し、アデア・マナー(Adare Manor)の門の向かいにあります。ダンレイヴン伯爵夫人(Countess of Dunraven)がパトロン(後援者)を務めています。この学校はアイルランド国教会(Church of Ireland)の理念に基づいて運営されていますが、すべての宗教、または無宗教の子どもたちを歓迎しています。」 と。St. Nicholas’ National School(セント・ニコラス国立学校)の案内看板。アウグスチノ会修道院(Augustinian Priory / Abbey)の正面(東面)から見た全景。観光案内板「Adare Nature Trail & Heritage Sites(アデア自然散策路と文化遺産地)」。「Adare (Desmond) Castle (c.1226)Adare Castle was built and owned by the O'Donovan family until the arrival of theNormans in the 12th century. In 1226, the lands and castle were granted to theFitzGerald family, Earls of Kildare.The castle was rebuilt and enlarged during the 13th and 14th centuries and was used by the Earls of Kildare until 1536 when it was confiscated by the Crown after the rebellion of Silken Thomas against Henry VIII. It then passed into the ownership ofthe Earls of Desmond who held it for over 100 years.The castle fell into ruin after the Desmond Rebellion of 1580 and remained unoccupieduntil restoration work in the 20th century. Guided tours of the castle commence at the Adare Heritage Centre.」【Adare(Desmond)Castle(1226年)アデア城は元々ノルマン人のディ・ブルゴ(De Burgo)家によって築かれました。1233年、ヘンリー3世によって没収され、リチャード・ド・クレア(ストロングボウの孫)に与えられました。およそ300年にわたり、アデア城はリムリック伯爵(Earl of Kildare)によって占拠されていましたが、1536年、トマス・フィッツジェラルド(通称「シルバートン卿」)がヘンリー8世に反旗を翻したため没収されました。その後、城は第1代サー・ジョン・フィッツジェラルドに譲渡され、彼の家系が19世紀まで城を保持しました。20世紀初頭に修復が行われ、現在はガイド付き見学が可能です(出発点はアデア・ヘリテージセンター)。】「Franciscan Friary (1464)The Franciscans arrived in Dublin around 1230. During the next century the Catholic Church was reformed by Henry VIII and the monasteries dissolved. The Adare Franciscan Friary was built in 1464 by Thomas Earl of Kildare and was used by the Franciscan Friars for over 100 years. In 1540, it was suppressed by Henry VIII and passed into the hands of lay owners.It remained in use by the Franciscans in the 17th and 18th centuries and was restored by the Earl of Dunraven in the 19th century. Today the friary is used as a school (St. Nicholas National School) and as a venue for cultural and community events.」 【Franciscan Friary(1464年)フランシスコ会修道士がアデアに最初に到着したのは13世紀でした。16世紀初頭にカトリック信仰の改革の一環として再建され、第7代ダンレイヴン伯爵が支援しました。宗教改革の影響を受けた1540年、修道院は**ヘンリー8世によって解散(Dissolution of Monasteries)**させられましたが、地元の人々の手で保持され、再建も進められました。修道院にはプレバンダル・ハウス(教会の財務官の館)や墓地跡も残っており、歴史的にも建築的にも貴重な遺産です。現在、聖ニコラス国立小学校が隣接しています。】「14 Arch Bridge (1400)Originally built by Gerald the 1st Earl of Desmond in 1400, this bridge was widened in 1836 by Windham Quin the 2nd Earl of Dunraven who added the pedestrian refuges.」 【14アーチ橋(1400年頃)この橋は14世紀初頭、第1代デスモンド伯ジェラルド卿によって建造されました。その後、1836年に第3代ダンレイヴン伯によって歩道が追加され、現在の姿となりました。】MAPをズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.17
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その49):Bunratty Castle and Folk Park・ボンラッティ城と民芸村(6/6)~Adare・Trinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)(1/3)
Bunratty Folk Park(バンラッティ民俗公園)の散策を更に続ける。「The Woodland Stag(森の牡鹿)」という童話的な案内板で、Bunratty Folk Park(バンラッティ民俗公園)内の子供向けネイチャートレイルの一部。「The Woodland StagAs Ella ventured deeper into the woods, she stumbled upon a magnificent Woodland Stag hiding behind the trees.“Why are you hiding?” asked Ella, concerned.“A young troll just passed by and scared me,” replied the Stag.“Don’t worry. I’ll go find him and use my cheerful spirit to cheer him up,” exclaimed Ella.」 【森の牡鹿エラが森の奥へと進んでいくと、木々の陰に隠れる立派な森の牡鹿を見つけました。「なぜ隠れているの?」と心配そうにエラが尋ねました。「さっき若いトロールが通りかかって、僕を驚かせたんだ」と牡鹿は答えました。「心配しないで。私がその子を探して、明るい気持ちで元気づけてあげるわ!」とエラは言いました。】「Bunratty Folk Park(バンラッティ民俗公園)」内の「Fairy Trail(妖精の小道)」に設置された木製の彫刻作品「Woodland Stag(森の牡鹿)」。様々な質感の木材を組み合わせて作られており、胴体部分は滑らかな流線形の木材、胸から首にかけては粗い樹皮状のパーツで構成。その先にあったのが「Water Mill(小型水車製粉小屋)」。 「小型の水車式製粉小屋(water-powered mill)」中央の円形の石臼が粉挽き用の「ミルストーン(millstone)」。下部の固定石(bedstone)と、上部の回転石(runner stone)から構成。上部の木製ホッパーは穀物を落とし込む「ホッパー」。粉砕石の中心に穀物を送り込む役割。壁際の車輪型構造は、水車の回転部またはギア連結装置。木製歯車で回転エネルギーを伝達。「The Helpful FoxElla happily walked over to the Helpful Fox, Freddy.He was busy picking up the berries that the birds had dropped from the trees.Ella kindly offered to help, making the task even more enjoyable.They shared laughter and playful moments while working together.」【親切なキツネエラは喜んで「親切なキツネ」フレディのところへ歩いて行きました。フレディは木から落ちた実を拾い集めるのに夢中でした。エラはその手伝いを申し出て、作業をより楽しいものにしました。ふたりは一緒に働きながら、笑い声と楽しいひとときを分かち合いました。】 先ほどの「The Helpful Fox(親切なキツネ)」に登場したキツネのフレディ(Freddy the Fox)をかたどった彫刻。「The Wise OwlFlying round a tree, Ella discovered The Wise Old Owl.With his round glasses perched on his beak,he shared riddles and stories that made Ella gasp.」【賢いフクロウ木のまわりを飛んでいると、エラは「賢い年老いたフクロウ」を見つけました。そのフクロウは丸いメガネをくちばしの上にちょこんとかけ、エラが思わず息をのむようななぞなぞや物語を語ってくれました。】 ロバ(Donkey)が木陰に沿った柵の内側に。プレイグラウンド(遊び場)。この遊具エリアは、Bunratty Folk Parkの東側エントランス付近に位置していた。ズームして。複数の塔や橋で構成されたアスレチック風遊具。滑り台やクライミングウォールなどが確認できた。動物飼育エリアにはインドクジャク(Indian Peafowl,)のオスの姿が。見事な大きさと色彩の羽根。羽を広げて。アイルランド伝統の茅葺き屋根(thatched roof)を持つ農家風建物。「Tea Room(ティールーム)またはカフェ」として利用されていた。Bunratty Castle & Folk Park(バンラッティ城と民俗公園)で行われる夜の特別イベント「Medieval Banquet(中世の宴)」の宣伝ポスター。「LEGENDARY NIGHTS BEGIN AT BUNRATTY!Experience the Magic of Medieval Ireland at Bunratty Castle and Folk Park.Join us for an unforgettable evening in the majestic 15th-century Bunratty Castle, where the Great Hall comes alive with music, song, and dance performedby the renowned Bunratty Castle Singers.Your Evening Includes:・A delightful pre-dinner reception・A sumptuous 4-course feast accompanied by house wine・Performances by the world-famous Bunratty Castle Entertainers」【バンラッティの伝説の夜中世アイルランドの魅力を体験する特別な晩餐イベント。場所: 15世紀の壮麗なバンラッティ城・大広間内容:・中世風の衣装を着た演者による音楽・歌・踊りのショー・ワイン付きの豪華な4コースディナー・開宴前のウェルカムレセプション】 そして「Bunratty Castle & Folk Park(バンラッティ城と民俗公園)」の見学を終えて出口にあったエントランスマットを再び。 そして「Bunratty Castle and Folk Park」を後にして、ADARE村にある「Trinitarian Abbey」に向かって車を走らせた。N18~M20~N21を利用して、渋滞もあって約40分ほどで到着。道路脇の駐車場に車を駐め散策開始。アイルランド、カウンティ・リムリック県Adare(アデア)村にあった「Trinitarian Abbey(トリニタリアン修道院)」 現在は「Holy Trinity Abbey Church、聖三位一体教会」と。Adare(アデア)村にはリムリックの南西、マイグ川沿いに位置。創建は1226年頃(Geoffrey de Mariscoの勅許により)または1230年頃に創設されたとされ、アイルランド唯一のトリニタリアン修道院です。1811年:第1代ダンレイヴン伯爵により、修道院廃墟がカトリック教会として修復。1852–53年:さらに拡張と修復が行われたと。修道院の塔・中堂・身廊・合唱席の一部が現存、塔の構造は15世紀に付加された防御的な構造で、高さ約67フィート(約20 m)。約20m高さの修道院の塔。Adare(アデア)村は 19世紀初頭(1820年代) にダンラヴェン伯爵によって町並みが整えられ、その際、 邸宅(Adare Manor)の従業員や農場労働者のために建てられた藁葺きコテージ(thatched cottages)がMain Streetや周辺に数多く建設された。これらは現在も保存され、商店やカフェ、宿泊施設として使われていることが多く、アデア村の観光的風景を形成しているのであった。乳牛の姿の像も。藁葺き屋根(thatch roof):アイルランドの伝統的建築。主に麦わらや水辺の葦などを 材料とし、断熱・防水に優れている。白壁に赤い窓枠:アデアのコテージは、保存修復される際にカラフルな窓枠やドアが特徴。バラや庭の手入れが行き届いている:多くの建物が現在も居住用またはカフェ・店舗などに 活用されており、庭先も整備されていた。そしてAdare Village(アデア村)中心部のメインストリート沿いに位置している店でこの日の昼食を。アイルランド・アデア村(Adare)にある 「OAK & APPLE(オーク・アンド・アップル)」というカフェ・ビストロ・ワインバー。正面から。店内へ。ラテアートも美しく。ラテアートとは、エスプレッソにミルクを注ぎ、カップの表面に絵柄や模様などのアートを描くことや、アートが施されたカフェラテのこと。カフェラテとは、エスプレッソコーヒーに蒸気で温めたスチームドミルクや、蒸気でふわふわに泡立てたフォームドミルクなどを注いで作る飲み物。軽い!?昼食を。店の前のベンチにも多くの観光客の姿が。昼食を終えて、「藁葺き屋根のコテージ群(Thatched Cottages)」を再び。Restraunt「1826 Adare」。 藁葺き屋根の店が続く。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.16
コメント(0)
-

平塚・花菜ガーデンへ(その4)
そして「ハス田」に到着。 「ハス田」の場所はここ◯。蓮の種類は「舞妃蓮」であろう。 ほんのりピンク色が儚く美しい舞妃蓮(まいひれん)。舞妃蓮(まいひれん)は、和歌山県御坊市生まれのハスの品種で、1966年に阪本祐二氏が「王子蓮」と「大賀蓮」を交配して作出しました。花弁は黄色味がかった白地に桃色の爪紅(先端がピンクまたは緑)が乗り、風に舞うような姿から「舞妃蓮」と名付けられた と。ズームして。日本人が蓮(はす)の花を好む理由をChatGPTに訊ねて見ました。丁寧な回答は以下のごとし。『1. 仏教との深い関わり ・蓮は仏教の象徴のひとつで、「清浄」「悟り」「極楽浄土」を表します。 ・泥水の中から茎を伸ばし、濁りに染まらず清らかな花を咲かせる姿が、煩悩の世界に 生きながらも清らかな心を保つ理想の人間像と重ねられます。 ・仏像や曼荼羅では、釈迦や菩薩が「蓮華座(れんげざ)」に座る姿が多く描かれます。2. 四季の情緒と観賞文化 ・夏の早朝に咲き、昼には閉じるという独特の開花リズムが、儚さや一瞬の美を感じさせます。 ・奈良の薬師寺や上野の不忍池など、日本各地で「蓮見(はすみ)」が夏の風物詩として 定着しています。 ・朝の静けさの中、花が開く際にわずかに響く「ポン」という音を聞こうとする愛好家もいます (科学的には諸説あり)。3. 日本文化・美意識との親和性 ・「泥中の蓮」という表現は、困難や俗世にあっても清らかに生きることの象徴。 ・茎や葉の造形美、葉の撥水性(ロータス効果)なども、工芸・文様・着物柄に 取り入れられています。 ・花・葉・種・根(蓮根)まで利用できる実用性も、古くから生活文化に浸透。4. 文学・芸術での表現 ・和歌や俳句では、蓮は「夏」「仏」「静寂」といった季語やモチーフとして用いられます。 例:蓮咲いて 露をこぼせる 池の面(正岡子規) ・日本画や浮世絵にも蓮池の風景が多く描かれています。』こちらは蒲の穂。上部から覗いて。蓮の花の特徴。蓮の花は、中央の平らな部分が花托(かたく)で、その上に雌しべが並んでいます。花托の周囲には多数の雄しべがあり、雌しべには届かない構造で自家受粉を防いでいます。花が終わると、花托が成長して果托となり、その中に蓮の実が入ります。蓮の花の構造の詳細:・花托 (かたく):花の中心にある平らな部分で、花が終わると果托に変化します。 蜂の巣のような形状から「はちす」と呼ばれ、それが変化して「はす」になったという説が あります。・雌しべ:花托の上に等間隔に並んでいます。・雄しべ:雌しべの周囲を囲むように多数存在し、雌しべには届かない構造です。・果托:花托が成長した部分で、蓮の実を包み込みます。・蓮の実:果托の中にある黒い実で、成熟すると種子が抜け落ちます。その他:・蓮の葉は、表面が水をはじく特殊な構造を持っています。・地下茎はレンコンとして食用にされます。・蓮の花は、泥水の中から茎を伸ばし、清らかさの象徴とされています。キャプションは不要!!大きな立派なカメラを持って。静けさに包まれた「ハス田」、水面に浮かぶ大きな葉の間から、白く淡紅の花がそっと顔を上げていた。澄んだ空気に香りが混じり、心の奥に溜まっていた澱が一枚ずつ剥がれ落ちていくのであった。ただ見つめるだけで、心は清らかな水に浸されるが如くに。総合案内。「みはらしデッキ」に向かって進む。右手にあったのが「富士山ベンチ」。 こちらが「みはらしデッキ」。「富士山」案内図。大山、丹沢山塊を見る。その左の富士山は雲に隠れていた。こんな光景が(写真はネットから)。「関秉の富士見百景富士山の見えるまちづくり地点名 平塚市からの富士 平成17年11月 国土交通省関東整備局 寄贈(社)関東建設弘済会」。 ノウゼンカズラ(凌霄花)。1.5時間ほどの滞在であったが、百日紅、スイレン、タイタンビカス、蓮の花等を楽しんだのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.08.15
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その48):Bunratty Castle and Folk Park・ボンラッティ城と民芸村(5/6)
広い牧草地には、動物の姿が。金網の柵越しに茶色のヤギが。角が後ろに湾曲しており、毛はやや長め。草の上でくつろいでいる仔ヤギ?仔羊たち?。「Fairy HousesThe path led to a collection of Fairy Houses, where tiny fairy friends lived in acorn homes and toadstool cottages. They invited Ella to tea, and she delighted in their cosy dwellings.」 【妖精の家その小道は妖精の家々へと続いていました。そこには、小さな妖精たちがドングリの家やキノコのコテージに住んでいました。妖精たちはエラをお茶に招待し、彼女はその居心地のよい住まいを楽しみました。】と。草原にくつろぐ子牛たち(calves)。白黒や茶色などさまざまな毛色をしており、アイルランドやイギリスで一般的に見られるヘレフォード種やフリージアン種の雑種であると。このような放牧風景は、アイルランドの伝統的な酪農文化を体感できる場所なのであった。「Church of Ireland, Ardchoney(アードコニーのアイルランド国教会)」が姿を現した。「Church of Ireland ARDCRONEY CONGOR」 【アイルランド国教会 アードクローニー教会 コングー地区 礼拝案内】この教会は、19世紀初頭に建てられたゴシック・リバイバル様式の教会で、アイルランドの農村部に多く見られる典型的な国教会建築。現在の建物は1998年、Bunratty Folk Park(バンラッティ民俗公園)に再建・移築されたものである。1820年代〜1830年代初頭に最初に建築されたものと。建築様式は ゴシック・リバイバル(ネオゴシック) 採用で、丁寧な石積みと尖頭窓が特徴。Ardcroney Church(アードクローニー教会)の内部、祭壇(altar)。ステンドグラスのパネルは、キリスト教の聖パトリック(Saint Patrick)像。長い白髪と豊かな顎ひげをたくわえ、青い光輪(ニンブス)を背にしていた。左手には金色の十字架付きの司教杖(クロス・スタッフ)を。教会内部の屋根構造(トラス)を見上げて。木彫の記念銘板(メモリアル・プレート)。「SACREDto the MEMORY ofANNIS BIDDULPHDied September 28th, 1891」 【聖なる記憶にアニス・ビドゥルフを偲んで1891年9月28日 逝去】「Annis Biddulph」はイギリス系貴族または地主階層の家系「Biddulph家」の一員であった。この銘板は、教会への献金・奉仕に対する追悼記念として設置された と。1891年という年は、アイルランドでは土地改革や英国からの自治運動が進む時期であったと。案内標識も丁寧に。アイルランドの伝統的な農村景観を象徴する石積みの塀(ドライストーンウォール)と、木々に囲まれた放牧地または農耕地が拡がっていた。手前の石垣は積層型のドライストーンウォールで、以下のような特徴があるのだと:・平らな板状の石を水平に積み重ねる方式。・アイルランドの中でもクレア県特有の石灰岩質地層を利用。・通気性と排水性が高く、長期耐久性に優れる。前方に見えて来たのが「アイリッシュ・ストーン・コテージ(石造り農家)」。 ・素材:地元産の石灰岩(limestone)を積み上げて作られたドライストーン構法 (モルタルを使わない)。・屋根:石板葺き(スレート)またはかつては茅葺きであったものを現代の耐候性重視で改装。・壁厚:60cm〜90cm以上にもなり、断熱性と蓄熱性を確保。・開口部:窓は小さく、光は少なめだが防風・防寒性を優先。英国統治下での土地制度により、土地は地主(Landlord)から借り受ける形。1840年代のジャガイモ飢饉(Great Famine)以前は多数存在していたが、その後多くが廃屋化または荒廃した と。そして前方に見えて来た「Bunratty House(バンラッティ・ハウス)」を訪ねることに。 項目 内容建築年 1804年建築様式 ジョージアン様式(Georgian style)建設者 Studdart家(バンラッティ城の最後の居住者)所在地 バンラッティ城敷地内、Folk Parkの一部用途 領主邸宅 → 20世紀初頭まで居住 → 1970年代より復元・公開Studdart家は、18世紀から19世紀にかけてこの地方の地主として力を持っていた。バンラッティ城が廃城同然になった後、より現代的で快適な住まいとしてこのBunratty Houseを建設。住居としては約150年使われ、Folk Park設立後に博物館的保存と展示対象になった。「Bunratty House(バンラッティ・ハウス)」の敷地内にあった「Walled Garden(囲い庭園)」18世紀〜19世紀のレージェンシー様式に見られる特徴。貴族や地主の邸宅では庭園を囲って外部と隔てていた。レンガと石灰岩の組み合わせの石塀。「Bunratty House(バンラッティ・ハウス)」内に入る。エントランスホールまたは廊下部分。左右のドアは書斎や寝室、ダイニングルームなどへの入り口。17世紀中頃〜18世紀初頭の上流階級女性の絵画。胸元を大きく露出したドレス、サテン(絹)のような質感。これは17世紀ヨーロッパの貴婦人のファッション様式。かつての住人やその親族の肖像画であろうか?ダイニングルーム(食堂)。深紅(赤ワイン色)のダマスク模様の壁紙は、19世紀中〜後期のビクトリア様式によく見られる装飾。長方形のダイニングテーブルとマホガニー製の椅子は、ジョージ王朝後期~ヴィクトリア朝のスタイル。背もたれの曲線が美しいのであった。客間(ドローイングルーム / Drawing Room)。来客をもてなしたり、婦人たちが午後を過ごす空間として使われた。特に19世紀は「婦人用サロン」としての性格が強い。主にビクトリア朝時代(1837〜1901)の様式が色濃く反映されており、家具や装飾品は18〜19世紀の混合。Nursery ・子供部屋。クマのぬいぐるみや木馬型の三輪車、手押し車などが見られる。手前にあるレトロな乳母車。金属製のフレームと幌つき構造は19世紀の典型。中にはぬいぐるみが座っていた。女性の寝室(Bedchamber / Lady’s Bedroom)。キャノピーベッド(天蓋付きベッド)は花柄の布張りが施された大きな四柱式のベッド。天蓋(キャノピー)は防寒・防虫と装飾の両面を兼ねる。着替え・化粧・祈りなど、女性の日常的な活動がすべてこの部屋で行われていたのであろう。黒のドレスと白の襟元・ボンネットの女性像。未亡人や敬虔な女性の象徴的な服装。この家の母・祖母など「家の礎となった女性」であろうか?この大理石像は、西洋美術における有名な主題の一つ 「とげを抜く少年(Spinario, Boy with Thorn)」 に類似しているのだ と。ヴィクトリア時代に流行した陶製の装飾柱(pedestal or plant stand)。鮮やかな 緑青(ターコイズ)と紺色の釉薬仕上げは、19世紀中期〜後期に流行したマジョリカ焼(Majolica ware)と考えられる と。談話室(study / drawing room)。暖炉(マントルピース)は石製(おそらく黒大理石風)、暖炉内に薪が入っていた。上には置き時計、燭台(キャンドルホルダー)が見えた。18〜19世紀のジョージアン様式(Georgian style)の住宅の正面玄関を振り返って。「Bunratty House(バンラッティ・ハウス)」の前庭を見る。見事に手入れされている庭園。「サービス棟」または「ガーデン・アウトビルディング(付属建物)」を見る。「ウォールド・ガーデン(Walled Garden)」石造の高い囲い壁、中央の芝生とそれを取り囲む花壇、通路の配置から見て、装飾的なビクトリア時代風のフォーマル・ガーデンとなっていた。「ワイナリー・Bunratty Mead & Liqueur Company Limited」の建物の裏側。創業:1970年代特産品:アイルランドの伝統的な蜂蜜酒「Mead(ミード)」、ハーブリキュールなど。ひまわりの花に近づいて。再び「ウォールド・ガーデン(囲い庭園 / Walled Garden)」を振り返って。大きな木は、「モントレー・パイン(Monterey Pine)」?? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.15
コメント(0)
-

平塚・花菜ガーデンへ(その3)
そしてその先にあったのが真っ赤なフヨウの花。近づいて。「タイタンビカス(アオイ科)耐寒性・耐暑性のある、宿根性の種物で特定のアメリカフョウとモミジアオイの交配選抜種です。タイタンビカスは、株式会社 赤塚植物園が作出したオリジナル植物で、一度見たら忘れられないインパクトのある大きな花(直径15~25cm)が特長タイタンビカスは宿根草で、多年草。冬には地上部が枯れますが、根は残り、翌春に再び芽を出して生育する。そのため、寿命は特に定められていません。」と。 花菜ガーデンの入口にあったポスターの写真。圧倒的な存在感と驚異的な強さ、ハイビスカスのような花姿から『巨神タイタン』にちなんで、『タイタンビカス』と名づけられたのだ と。大きなものでは花径25cmにもなるという『タイタンビカス』。強い日ざしのなかでしおれもせずに元気に育つ強健さが身上。草丈も2mを超え、ギリシャ神話に出てくる巨神タイタンの名に恥じない存在感で、庭を飾るのだ と。「タイタンビカス プレアデス」。 真っ赤な「タイタンビカス フレア」。非常に鮮明な緋赤色の大輪花と、2m以上になる草丈で、とても目を引きます。中心部の隙間が目立つことと、ややネオン(花弁の裏側の中心部が白くなる裏白)タイプで、中心部が光って見えます。7月中旬ごろから開花し始めます。花持ちがとても良く、6時過ぎまで萎れません と。 「タイタンビカス イリス」。さわやかなブラッシュピンクと白のバイカラーが美しい、中輪タイプのタイタンビカス。 「タイタンビカス ヘルメス」。白い花弁にくっきりとした赤い目が入るショートタイプの花で、配色としてはピーチホワイトに似ていますが、ほぼ純白といえる花色が新鮮で、赤い目が鮮やかに目立ちます。花はやや小さめですが多花性で次々と花を咲かせます と。 純白の「タイタンビカス エルフ」。花の中心部分の「目」がないタイプ。クリアな白色が一層引き立つ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.14
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その47):Bunratty Castle and Folk Park・ボンラッティ城と民芸村(4/6)
さらに「Bunratty Castle & Folk Park」の散策を続ける。 聖母子像(マドンナとチャイルド / Madonna and Child)の石像、近づいて。「Bothán Scóir(ボーハン・スコール)」、つまり貧しい農業労働者の小屋(労働者用の最下層住宅)。「BUNRATTY CASTLE & FOLK PARKBothán ScórThis little dwelling of a poor labourer is in utter contrast to that of the rich farmernearby. It is a typical example of the type of dwelling inhabited by the labourers of the strong farmers in the 18th and 19th centuries. The farmer would let a small piece of ground, about half an acre, to the labourer, who would pay off the rent inlabour; about eighty days in the year. For the rest of the time the labourer could work for himself or for wages.The house is of the simplest kind, only one room with a bare hearth and a floor ofpacked earth. The simplicity of the furniture and of the few household goods speaksfor itself. Their only livestock would be a few hens or ducks.Such a labourer, if permanently employed on the same farm, would have some milk,vegetables and occasionally a piece of salt beef or bacon from the farmhouse, and his wife would also be employed there in the house or farmyard. Such a family would bewell off among labourers. Most, it is to be feared, were less lucky. Once numerous, these houses almost completely disappeared, when the class of landless labourers was greatly reduced in numbers by starvation and emigration, during the great famine of the 1840’s.」 【バンラッティ城と民俗公園ボーハン・スコール(労働者小屋)この小さな労働者の住まいは、近くの裕福な農民の住まいとはまったく対照的です。これは18~19世紀に、富裕な農家で働いていた日雇い労働者が住んでいた典型的な住宅の例です。農場主は約半エーカー(約2000㎡)ほどの小さな土地を労働者に貸し、労働者はその地代を労働で支払いました(年に約80日ほど)。それ以外の期間は、自分自身のため、あるいは賃金を得るために働くことができました。この家は最も簡素な造りで、一部屋のみ、暖炉がむき出しで、床は固く踏み固めた土です。家具やわずかな家財の質素さが、その生活ぶりを物語っています。飼っている家畜といえば、数羽の鶏やアヒル程度でした。このような労働者が特定の農場に常雇いされていた場合、ミルクや野菜、時には塩漬けの牛肉やベーコンなどを農家から分けてもらえたほか、妻も家事や農作業として雇われることがありました。こうした家族は労働者の中では「恵まれた層」に入ります。しかし、ほとんどの者はそれほど幸運ではなかったと考えられます。かつてはこのような小屋は数多く存在しましたが、1840年代の大飢饉の際に、無土地労働者階級は飢餓や移民によって大きく数を減らし、こうした家屋もほとんど姿を消しました。】貧しい農業労働者の住まいの内部再現の一部であり、非常に簡素な生活ぶりを象徴する展示。寝床(ベッド)は簡素な木製の枠に藁や詰め物を入れたマットレスを置いたもの。ヘッドボードも最低限。アイルランドの貧しい農業労働者の家の生活空間を再現。左壁の棚(プレートラック)は木製の「dresser shelf」または「plate rack」と呼ばれるもので、家庭の陶器を並べて収納・乾燥・装飾を兼ねていた。貧しい家でも数枚の皿を誇りにして壁に飾った と。暖炉の煙突フード(チムニーフード)を見上げて。白く塗られたチムニーフード(煙突フード)は暖炉の上部に設置され、煙を天井から屋外へ導くための構造物。粘土や藁、土、石を混ぜて作られた粗い表面が石灰で白く塗装されていた。中流階層の農家(または職人の家)を見る。茅葺き屋根(Thatch Roof)には厚みがあり、雨風を防ぎつつ断熱効果を持つ。アイルランドでは麦わらやアシ(リード)などが用いられる。滑らかで丸みを帯びた形状が美しく、職人技が光る部分。白い石造の壁は石灰岩を積み、外側を白い石灰で塗装したもの。防虫・防カビ・衛生面に優れ、視覚的にも清潔感を演出。伝統的な品種のニワトリ(鶏)で、アイルランドの民俗公園や農家でよく見られる古来種(ヘリテージブリード)。バンラッティ民俗公園(Bunratty Folk Park) 内に設置された案内標識。飼育されていると思われるアイリッシュ・ウルフハウンド(Irish Wolfhounds) 。非常に大柄で穏やかな性格を持つ、アイルランド原産の犬種。スチール製の簡易ベッドの上で、2頭とも丸くなって休んでいた。「IRISH WOLFHOUNDSMeet Rian and Mide, our majestic Irish Wolfhounds. These gentle giants are a living link to Ireland’s past, as they once played a vital role in the country’s history.Bred for their imposing stature and strength, Irish Wolfhounds were historically used in hunting and to serve and protect the ancient Celts. In medieval times, ownership of Irish Wolfhounds was a symbol of status and nobility, and they feature in folklore in stories ofheroism, chivalry and companionship. Highly prized and often gifted to kings and foreign dignitaries, these dogs were symbols of loyalty and courage. Rian and Mide are both descendants of an ancient and noble bloodline and now reside here in Bunratty Folk Park.Don’t be deceived by their size – these dogs are known for their gentle and friendlynature. They love attention and are very sociable with adults and children alike.Known in Irish as Cu Faoil (meaning hound or wolf dog), they are the stuff of legends. Records of heroic Irish Wolfhounds can be found throughout Irish mythology. Beloved fortheir loyalty, friendliness & very intelligent, they hold the distinction of being the tallest breed of dog in the world.Irish Wolfhounds have a long and distinguished history and have existed for over 4,000 years in Celtic Ireland. They were originally bred to hunt wolves and are depicted in Celtic artwork dating back to the 5th & 6th centuries. The Great Hall at Bunratty Castle Medieval Banquet illustrates this tradition.Wolfhounds were regular guests at meals & would have been the companions to medieval nobles.」 【アイリッシュ・ウルフハウンドバンラッティ民俗公園の誇るアイリッシュ・ウルフハウンド、リアン(Rian)とミーデ(Mide) に会いましょう。この穏やかな巨犬たちは、アイルランドの過去と現代をつなぐ「生きた証人」です。かつてはアイルランド史において重要な役割を果たしていました。威厳ある体格と強さを持つウルフハウンドは、古代ケルト人により狩猟や護衛用に飼育されてきました。中世になると、この犬種は地位と貴族の象徴となり、英雄譚や騎士道、忠誠と友情の物語に登場します。しばしば国王や外国の賓客に贈られた彼らは、「忠誠」と「勇気」の象徴でもありました。リアンとミーデは、この古く高貴な血統を受け継ぐ子孫であり、現在はバンラッティ民俗公園で静かに暮らしています。見た目に反して、彼らはとても穏やかで人懐っこい性格を持ち、大人にも子どもにも社交的です。アイルランド語では 「Cú Faoil(クー・フォイル)」、つまり「猟犬」「狼犬」と呼ばれ、数々の神話に登場する伝説の存在です。忠誠心・友好性・知性に優れ、世界で最も背の高い犬種としても知られています。アイリッシュ・ウルフハウンドは、ケルト時代から4,000年以上の歴史を誇り、もともとはオオカミ狩りのために飼育されました。5〜6世紀のケルト美術にもその姿が描かれています。バンラッティ城の「グレート・ホール」にも、彼らの伝統を示す描写があります。かつて中世の貴族たちは、食卓にもウルフハウンドを同席させ、常に身近な伴侶として大切にしていたのです。】「Doctor's House(町医者の家)」。白壁、切妻屋根、2本の赤レンガ煙突、そして中央の尖った破風(ガブル)が特徴的。Doctor's House は「中流以上の専門職家庭の暮らし」を示す建物として、住宅と診療所が一体化された形で展示されています。バンラッティ民俗公園では非常に人気のある展示のひとつ。正面から。番号15案内。「Doctor's House(町医者の家)」の内部展示。右奥のテーブルにはカラフルな薬瓶類が。処方薬や調剤道具。茶色や青のガラス瓶は光から薬を守るため。すり鉢やガラス棒も見える。中央左の机上には医療器具・金属製トレイが。注射器やピンセット、消毒用アルコール瓶などを載せる。こちらは医師の書斎兼診察室を再現した部屋。左手前:診察用ベッド(白いシーツ)患者の身体検査・診察・応急処置などに用いられた簡易ベッド。Doctorの写真か?「Doctor’s House(町医者の家)」の屋根裏部屋?の寝室の一室。こちらも屋根裏部屋の女性用の寝室・更衣室・化粧室!?左には乳母車または揺りかご(ベビーベッド)もあることから、育児や看護の場でもあったようだ。「National School(国民学校)」アイボリー色の漆喰壁とスレート屋根、そして左右対称のデザインで、両側に出入口。窓枠は格子入り、装飾的な石灰岩(ライムストーン)風の縁取りあり正面中央の石板には「National School」の文字が彫られていた。復元された教室。19世紀末〜20世紀初頭のアイルランドの田舎の小学校を再現。「National School」の教室内で、実際に再現授業が行われている様子。農産物販売所(小売店)。玄関の看板には「O'NEILL'SPotato Market"Where the Best are Found"」【オニールのポテト市場「最高のじゃがいもはここで見つかる」】と。 「No. 21:S. SEAN O'FARRELL 3(オファレルの店)」写真スタジオ兼記念品屋、水色と濃紺で彩られた印象的な外壁。建物の角や柱の装飾が目を引く意匠そして窓枠に花が飾られており、ヴィクトリア朝風の愛らしい外観。この建物がある一帯は、バンラッティ民俗公園の「ビレッジ・ストリート(Village Street)」と呼ばれる区域で、19世紀のアイルランドの町並みがリアルに再現されていた。銀行・パブ・郵便局・食料品店・薬局などが軒を連ねており、見学者は当時の生活を追体験できたのであった。その先、隣りにあったのが「John Foster 印刷所」。No.17「J.J. CORRY」パブまたは酒販店を模した再現。「18 Browne's Traditional Hairdresser(ブラウンズ 伝統的理髪店)」近づいて。「12 McInerney & Sons(マクイナーニー商会)」。 上部の看板には「STORESSCQsREPAIRS OF ALL KINDSCOPPER & ZINCTIN PLATE WORKOVENSREPAIRED & REMODELED」 【あらゆる種類の修理銅および亜鉛製品 ブリキ細工(ブリキ加工)オーブン類 修理および改造】郵便局(Post Office)。「POST OFFICEMONEY ORDER, SAVINGS BANKPARCEL POST & INSURANCE – MONEY SERVICES」 【郵便局為替・貯蓄銀行小包郵便・保険・金融サービス】と。壁には伝統的な赤い郵便ポストが設置され、窓越しには制服姿の職員や郵便関連の展示も。建物番号「19」は右下に表示されていた。この建物は、おそらく19〜20世紀初頭のアイルランドの郵便局の様子を再現した展示施設です。内部には当時の郵便用品や業務風景の再現がされていたのであった。先生?に連れられた子供たちの姿も。この美しい花はフクシア(Fuchsia)。アイルランドでは庭木や垣根、鉢植えとしてよく見られ、「愛国の花」として知られるFuchsia magellanica(マゼランフクシア)は、特にアイルランド西部で自生に近い状態でよく咲いているとのこと。茅葺き屋根(Thatch Roof)用の資材等の保管場所。左側の大きな円筒形:これは圧縮された干し草(hay)や藁(straw)のロール。 農業用として家畜の餌や、建材の一部として使われることがあります。右側の束になった細長い草:これは典型的な屋根葺き用のリード(葦)やストロー(麦わら)。 特にアイルランドでは、伝統的な茅葺き(thatching)屋根の材料 として使用 と。可愛らしい妖精のイラストとともに、まるで童話の一場面のような案内板。「Wishing WellAs Ella’s adventure was coming to an end, she felt a strong urge to visit the Wishing Well. She stumbled upon a beautiful well with a thatched roof and colourful flowers under the shade of a graceful tree.Ella was curious, so she leaned over and whispered her heartfelt wish into the well. To her surprise, a twinkling mist rose from the well, bringing her wishes to life.」 【願いの井戸エラの冒険が終わりに近づいたとき、彼女は「願いの井戸」を訪れたいという強い衝動に駆られました。彼女は、優雅な木の陰にある、色とりどりの花に囲まれた茅葺き屋根を持つ美しい井戸を見つけました。エラは好奇心にかられ、井戸に身を乗り出して、心からの願いをそっとささやきました。すると驚いたことに、井戸からきらめく霧が立ち上り、その願いが現実となったのです。】井戸は何処にあったのだろうか? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.14
コメント(0)
-

平塚・花菜ガーデンへ(その2)
そしてこの日の目的地の一つのスイレン(睡蓮)の池・尾根見の池に到着。「尾根見の池で咲いているこの花の名前は何?」 睡蓮(スイレン)と蓮(ハス)は、どちらも水辺に生える植物ですが、いくつかの違いがある。主な違いは、葉の形、花の咲き方、そして花の開花時間。睡蓮は葉に切れ込みがあり、水面に浮かぶように咲き、日中に花を咲かせます。一方、蓮は葉に切れ込みがなく、水面から高く伸びて咲き、早朝から咲き始めます と。なるほど、睡蓮(スイレン)の葉には切れ込みが。様々な色のスイレン(睡蓮)の花が。「日本には古くから ヒツジグサ(未草) という在来のスイレンが存在します。夏から秋にかけて白い花を咲かせ、午前中から昼過ぎまで開花して夕方には閉じる性質を持ちます。『万葉集』にも詠まれ、古くから日本人の自然観に組み込まれていました。ヒツジグサの学名は「Nymphaea tetragona」で、属名はギリシア神話の水の精に由来します。植物学上の名称はヒツジグサですが、「スイレン」とも呼ばれます。日本の在来種は1種だけですが、スイレン属は温帯から熱帯にかけて、世界に約40種が自生しています。明治時代に外国産のスイレンが日本に輸入されるようになると、その花の美しさから一般に広まりました。その際、輸入種が日本在来種と同じ「スイレン」の名称で呼ばれたことから、ヒツジグサとスイレンが混同される原因になったようです。本来なら「西洋スイレン」と呼ぶか、英名の「Water Lily」「Pond Lily」にちなんで「水生百合」と呼ぶべきだったのかもしれません。」と。 薄いピンクのスイレン(睡蓮)。実は、スイレンは日中花を咲かせ、夜になると閉じるという行動を、約3日間繰り返します。そのため、あたかも夜になると睡っているような状態になる花なので、睡る蓮の葉に似た植物ということから「睡蓮」という名前が付けられたのです。黄色。スイレン(睡蓮)の地下茎はまるでワサビのような形をしていて、ハスのように大きな穴が開いていないのだ と。黄色とピンク。濃いピンク。ピンボケですが、ウッドデッキに俯せになって何かをカメラで追う青年の姿が。この池のスイレン(睡蓮)は熱帯性スイレンなのであろうか?花茎が長く、水面から10〜15cmほど持ち上がって咲いている花が多かったのです。このため、横から見ると「水に浮いている」というより「水上に咲いている」印象に。花をズームして。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.13
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その46):Bunratty Castle and Folk Park・ボンラッティ城と民芸村(3/6)
木製の浮き彫りパネル(レリーフ)。上部:騎馬武者や狩猟の様子、城塞のような建物中央:人物同士のやりとりや儀式的な動き、あるいは戦闘の場面下部:捕らわれた人や犬と人との絡み、異国風の服装をした人物など旧約聖書「創世記」に登場するアダムとイヴ(Adam and Eve)の場面の絵画。絵画の左は男性(アダム)が林檎のような果実を手に持っている。絵画の右は女性(イヴ)がもう一方の手でアダムに果実を渡している。これは「原罪(The Fall of Man)」と呼ばれる場面で、イヴが蛇にそそのかされ禁断の果実を取り、アダムに渡して二人がそれを食べてしまう瞬間、もしくはその直後を描いている。装飾タペストリー。緑や青を基調とした背景に、花・葉・果実(ぶどうなど)・鳥類が描かれており、生命や豊穣の象徴的な意味を持つパターン。キリスト教の聖人たちの神秘体験や隠遁生活を描いたと考えられる作品。暖炉(ファイアプレース)。貴族階級または高官を描いた絵画。この人物は誰?イギリス王室の紋章(Royal Coat of Arms of the United Kingdom)の木彫版。イングランドの支配がアイルランドに及んでいた時代の象徴。重厚な木製家具の上、壁に取り付けられた鹿の剥製(または装飾角)。ルネサンス様式またはジャコビアン様式の木製キャビネット。貴族もしくは高位の軍人・政治家を描いたものか?中世から近世初期の鉄製の機械式時計(塔時計/タレット・クロック)の機構部(ムーブメント)。中世から近世の厨房(キッチン)や食料準備室の再現展示。狩猟で捕れた野ウサギなどを調理する前の状態を再現。古代の鹿(おそらくアイルランドヘラジカ:Irish Elk または Giant Deer)と思われる頭骨と角の標本。バンラッティ城(Bunratty Castle)から東方向に見下ろして。手前に見える川は Ratlty River(ラッティ川)。防衛用の胸壁とマーダーホールが見える城の石造りの塔を見る。ラッティ川に架かるN18号線の橋が下方に。その先には、Shannon Estuary(シャノン河口)が見えた。バンラッティ城(Bunratty Castle)の塔の一角から突き出したポールに掲げられたアイルランド国旗(緑・白・橙)。Bunratty Castle(バンラッティ城)の屋根部分。中央の八角形の尖塔屋根(ルーバー付き換気塔)。おそらく煙の換気や鐘楼(bellcote)としての役割を果たすもので、木製のルーバー(羽板)が特徴。再び、バンラッティ城(Bunratty Castle)から北東方向を見る。蛇行している川は Owenogarney River(別名RatltooまたはOwengarney川)で、Shannon河の支流。左手前の舗装路は、Low Road (R462)。ズームして。バンラッティ城(Bunratty Castle)の内部に掛けられていたタペストリー(壁掛け布)の一部。大型のタペストリー(壁掛け織物)とその前に配置された装飾盾(飾り盾)。「グレートホール(Great Hall)」まで下ると、地元の学校などからの見学グループと思しき子どもたちが整然と並んで、ガイドの説明を聴いていた。バンラッティ城(Bunratty Castle)内部の、人工的に石を刳り貫いた狭くて急な螺旋階段。そしてバンラッティ城(Bunratty Castle)の外に出て、城の西面を見上げる。ローズガーデン(薔薇園)の花々。紫の花は、茎が非常に長く、先端に直径10〜15cmほどの紫の球状花序をつけるアリウム(Allium)。ウロコタケ(鱗茸)またはシャグマタケであったか?移動して、バンラッティ城(Bunratty Castle)の西面を再び。左:北面、右:西面 を見る。Bunratty Castle の北面には、中世の防御構造に由来する大アーチ(木造の外部階段またはバルコニー跡)が見られます。このアーチはGreat Hall(大広間)の外側に面しており、室内からも目立つ形で露出している。写真右側には北西角と北東角の塔が見えた。中世の野外調理場または厨房を再現した展示であっただろうか?ここも。軍事・砲兵展示エリアを再び。木製台座に据え付けられた大砲が4門ほど確認できた。そして、見納めにBunratty Castle(バンラッティ城)北面の外観を。中央に見える巨大なアーチ型のくぼみは、旧来の引き込み式木製階段(drawbridge)の付け根部分であり、建築上の重要な特徴。大アーチのある面は北側で、そこに見学者入口・チケットブース・橋・フォークパーク入口などが集中しているのであった。Bunratty Castle(バンラッティ城)を後にして、振り返る。そして、帰路は再びアイルランド・バンラッティ民俗公園(Bunratty Folk Park)内の展示品の見学を。案内図。再現されていたジプシー・ワゴン(Gypsy Caravan)、別名「ヴァルド(Vardo)」と呼ばれる移動式住居を見る。赤と緑の装飾ワゴン(Vardo)は伝統的なロマ(ジプシー)民族のワゴン住居で、「Bow-Top Vardo(ボウトップ・ヴァルド)」と呼ばれる型。アイルランドの伝統的な茅葺き農家(thatch cottage)・「Mountain Farmhouse(マウンテン農家)」建物の外観は黄色い漆喰、茅葺き、花が植えられた窓、石垣が特徴。 2部屋構造の伝統的中級農家(母屋+納屋が連結)。隣りにあった黄色く塗られた木造の建物は「昔のリムリックのレモネード屋(製造所)」を再現した建物。看板には「LIM’L OLD LIMERICK LEMONADE of Bunratty」と記載。【リムリック風 昔ながらのレモネード 〜バンラッティにて〜】と。さらに進むと美しい白いクジャクが羽根を広げ出迎えてくれた。中央:白色クジャク正確には 「白変種(leucistic)」のインドクジャクのオス通常のクジャクと同じく長い尾羽を持ち、扇形に広げて誇示白い羽でも目玉模様(オクルス)はかすかに見えることがある左はインドクジャク(メス)とのこと。オスが、尾羽を全開に広げて誇示しているのであった。インドクジャク(オス)の顔をズームして。インドクジャク(メス)は羽根を広げてくれなかった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.13
コメント(0)
-

平塚・花菜ガーデンへ(その1)
アイルランド旅行記が延々と続いていますが、このブログアップ中も、様々な場所を訪ねていますので、かなり時間遅れですが、順不同でアップしたいと思います。この日は、7月22日、平塚での仕事の打ち合わせの帰りに平塚市寺縄にある神奈川県立花と緑のふれあいセンター・「花菜ガーデン」を訪ねた。この日の目的は、タイタンビカス、睡蓮、そして蓮の花の鑑賞。駐車場に車を駐め入口へと向かう。ポスター「花菜さんぽ 涼を感じる7月の花たち」。 「花菜ガーデン 入園口」案内ボード。 鉢に植えられたバラの花は既に終わっていた。3種の旗が掲げられていた。日本国旗、神奈川県旗、そしてブルーの神奈川県鳥旗。「花菜ガーデン」案内図。「花菜ガーデン」の広さは約92,000平方メートル。これは横浜スタジアムの約3.5倍の広さに相当すると。「花菜ガーデンの見どころ情報」。 入園料金は、この時期はシニア・500円。客の数は少なく。花菜ガーデン 15周年記念のアルバムコーナー。数多くの応募作品が紹介展示されていた。「花菜ガーデン」正面のモニュメント。名称:神奈川県立花と緑のふれあいセンター愛称:花菜ガーデン住所:神奈川県平塚市寺田縄496-1 花菜ガーデンの名称は、公募によって選ばれた愛称で、正式名称は「神奈川県立花と緑のふれあいセンター」です。愛称の「花菜」は、神奈川県の「かな」と、花や菜の花(野菜)を連想させる「菜」を組み合わせたもの と。既に終わっているのは解かっていたが、「花菜ガーデン」👈️リンク のピーク時は1,300品種に及ぶバラが咲き乱れるバラ園に向かってみた。緑の紫陽花の花。緑色の紫陽花の花は、主に「アナベル」という品種。アナベルは、咲き始めは緑色で、その後白く変化していくのが特徴。ルドベキア・タカオ?美しい色合いの薔薇の花。「ホリデー アイランド ピオニー」と。 赤い小さな花のバラ。「薔薇の轍(ばらのわだち)ローズ・コレクションEvolution of RosesRose Collection歴史上の人物たちも愛してやまなかった花、「薔薇」。長く深い歴史を持つバラの"進化の軌跡”がここにあります。古代ぺルシア時代にすでに栽培されていたバラは、西洋と東洋で別々に園芸化が進みました。やがて、東洋のバラが西洋へと持ち込まれることで大いなる変革が起こり、私たちがよく知るモダン・ローズが誕生します。ここでは、野生種から将来のバラまで、悠遠の歴史をたどることができます。」と。 女郎花(おみなえし)。「おみな」は「女」の意、「えし」は古語の 「へし(圧)」で、美女を圧倒する美しさから 名づけられた と。トランプカードのオブジェが。「A」から「Z」までのアルファベットと、あなたと花菜ガーデンを結ぶ「&」マークの合計27文字のフォトスポット であると。「ご自分のイニシャルや、大切な方へのメッセージを撮って、SNSにアップしましょう」と。 こちらは、前回訪ねた時の写真。アルファベットの文字が。蔓薔薇のアーチには花はなく。園内の女性像をカメラに。鹿の子百合。近づいて。香りの薔薇の花は僅かに。「風ぐるま迷図クレマチス・コレクションPinwheel MazeClematis Collection風ぐるまのような花を咲かせるクレマチス。色彩や種類豊かなクレマチスの世界に迷い込んでみてはいかがですか。クレマチスは世界に約300種、日本に約20種が自生し、花色や花型、花期、草姿などに幅広いバリエーションがあります。迷路のようなこのエリアでは、クレマチスを系統ごとに植栽しています。迷路をつくるツバキやクリスマスローズ、サルビア、マンサクなど季節の花々とのコラボレーションをお楽しみくたさい。」 オレンジ色のカンナの花。そして黄色に淡いピンクの縁取りのある薔薇の花。こちらは純白。再び「アナベル」。 近づいて。真っ赤な花のサルスベリ(百日紅)の木。サルスベリは漢字で「百日紅」と書きます。これは、夏から秋にかけて長く咲き続ける花の様子を表しています。また、和名の「サルスベリ」は、木の幹がツルツルしていて、猿でも滑って登れないほどだということに由来しているのです。鮮やかな赤い花。濃いピンクの(百日紅)の花も。「紅葉重ねのほとり(もみじがさねのほとり)カエデ・コレクションLakeside Maple TreesMaple Collection水辺に積もる木の葉の絨毯が、秋の深まりを静かに伝えます。染まりゆく葉の美しさを堪能ください。葉の形がカエルの掌に似ていることからその名がついたカエデは、日本の秋を代表する紅葉の美しい樹木です。こでは紅葉に焦点をあて、イロハモミジとオオモミシ、ヤマモミジを中心に国内外の野生種と園芸品種を展示しています。また、尾根見の池では円沢・大山を背景に、スイレンのコレクションもお楽しみください。」 ・・・つづく・・・
2025.08.12
コメント(0)
-
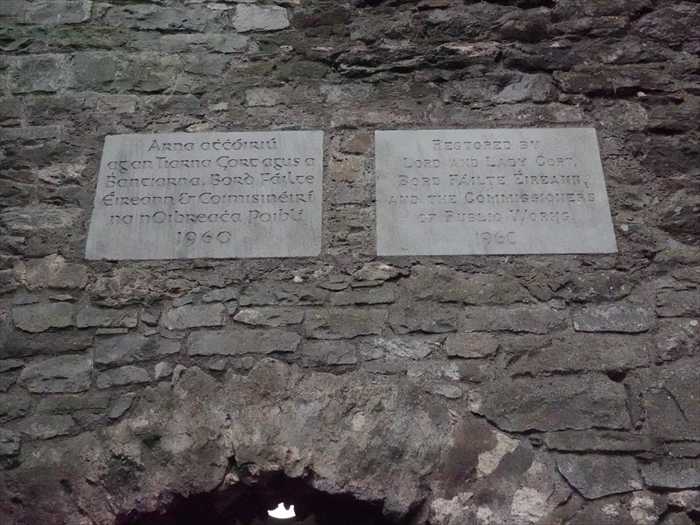
アイルランド・ロンドンへの旅(その45):Bunratty Castle and Folk Park・ボンラッティ城と民芸村(2/6)
Bunratty Castle(バンラッティ城)の入口上部に設置された2枚の記念銘板。それぞれアイルランド語(左)と英語(右)で、修復事業について刻まれていた。「Restored byLord and Lady GortBord Fáilte Éireann,and the Commissionersof Public Works1960」【この城はゴート卿およびゴート夫人、アイルランド観光局(Bord Fáilte Éireann)、公共事業委員会(Commissioners of Public Works)によって1960年に修復された】 案内板のアイルランド語版(Gaeilge)。「CAISLEÁN BHUN RAITHETÚR ADHMAID AR MHÓTA NÓ TULACH AN CHÉAD DHAINGEAN A TÓGADHAG BUN RAITE (1251). INA DHIAIDH SIN THÓG AN CLÁRACHCAISLEÁN CLOICHE (1277) AGUS THÓG DE ROKEBY CAISLEÁN (1353).BA IAD NA BRIANAIGH (1425) A THÓG AN CAISLEÁN ATÁ ANN ANOIS,AGUS CUIREADH CUID MHAITH ATHRUITHE AIR SNA 400 BLIANA ARAIBH SÉ DA ÁITIÚ. NUAR A BHÍ SÉ DA ATHCHÓIRIÚ (1956/58)CUIREADH DEIREADH LE HAON LEASÚ BA DEIREANNAÍ NA 1619 (DÁTANA SÍLEÁL ORNÁIDI SA SÉIPÉAL) AGUS HATÓGADH CÍOR LÁMHAGHNA 15ú AOIS.RINNEADH LÉIGEAR ANSEO 1646 AR AN AIMAIRÉAL PENN, AGUSCEAPTAR GO RAIBH A MHAC, WILLIAM PENN, BUNAITHEOIRPENNSYLVANIA, SA CHAISLEÁN INA NAÓNÁN.」 ネットで翻訳して【バンラッティ城最初の要塞は1251年に木造の塔として築かれ、堀または小高い丘の上に建てられました。その後、1277年にクレア人によって石造りの城が建てられ、1353年にはロクビーによって再建されました。現在の城は1425年にオブライエン家によって建てられたもので、400年間にわたり居住される中で大幅な改築が行われました。1956年から58年にかけての修復の際には、1619年以降の全ての増築部分(礼拝堂の装飾天井の日付)を撤去し、15世紀当時の胸壁(城壁上部のギザギザ)が再現されました。1646年にはこの城でアドミラル・ペンが包囲され、その息子であり、ペンシルベニア州の創設者ウィリアム・ペンが、幼少期にこの城にいたと考えられています。】「見張り台(あるいは射撃狭間)」の再現展示。黒い人形(背中を見せてしゃがんでいる)は、城を防衛する兵士を再現した模型。視線の先には、外を監視する狭間(射撃口)があった。ゴート子爵(Viscount Gort)とその夫人(Viscountess Gort)について説明。近づいて。「The restoration of Bunratty Castle commenced in 1954 when the 7th Viscount Gort purchased the ruin from local land owner R.H. Russell.Viscount Gort was a member of an Anglo-Irish family with a seat at Lough Cutra in Gort,County Galway. In 1921 he married Bessy Surtees who belonged to an aristocratic Northof England family whose lineage went back to Norman times.Prior to his death in 1976, Viscount Gort bequeathed the castle and its furnishingsto the people of Ireland.The castle is now managed by Shannon Development Company on behalf of Trustees.」 【バンラッティ城の修復は1954年に始まりました。第7代ゴート子爵が、この城の廃墟を地元の地主R.H.ラッセルから購入したのです。ゴート子爵は、ゴールウェイ州ゴートにあるロック・クトラを本拠とするアングロ・アイリッシュ(英系アイルランド人)の家系の一員でした。1921年には、ノルマン時代まで系譜を遡ることのできる、イングランド北部の貴族階級出身のベシー・サーティーズと結婚しました。1976年に死去する前に、ゴート子爵は城とその調度品一式をアイルランド国民に遺贈しました。現在、城は信託団体を代表してシャノン開発公社(Shannon Development Company)によって管理されています。】バンラッティ城(Bunratty Castle)内部では、子供達へのガイドツアーが行われていた。展示「The Changing Castle」 この写真は、バンラッティ城(Bunratty Castle)の展示室にある歴史解説パネルの一部で、13世紀のバンラッティの町と城の発展を描いたものです。左下に「1250」、右下に「1275」と記されており、城と集落の変遷が視覚的に説明されていた。「The first Bunratty Castle was a wooden structure built on high ground by the Norman adventurer Robert de Muscegros (near the site now occupied by the Shannon Shamrock).」【1250年最初のバンラッティ城は、ノルマン系の冒険者ロバート・デ・ミューセグロスによって高台に築かれた木造の要塞でした(現在のシャノン・シャムロックのある場所に近い地点】「In the late 13th century the lands were granted by King Edward I to Thomas de Clare who built the first stone fortress.」 【1275年13世紀後半、エドワード1世がこの土地をトマス・デ・クレアに与え、彼が最初の石造の要塞(石の城)を築きました。】「1450The O'Briens and MacNamaras continued to attack the castle and eventually drove out the Norman settlers.The present stone castle was built by the MacNamara family in the middle of the 15th century and later taken over by the O’Briens.The castle remained an important stronghold during the Confederate and Williamite wars until the 1700s when it declined.」【1450年オブライエン家とマクナマラ家は城への攻撃を続け、最終的にノルマン系の入植者を追い出した。現在の石造りの城は15世紀中頃にマクナマラ家によって建てられ、その後オブライエン家の所有となった。この城は、アイルランド連盟戦争やウィリアマイト戦争の間も重要な拠点であり続けたが、1700年代になると衰退した。】中央に描かれているのが現在のバンラッティ城の原型となる15世紀の石造りの城。周囲には川と村があり、城壁で囲まれた構造が当時の防衛的機能を表している。小舟が川を行き来しており、交易や物資の補給があったことも想像される。丘の上や平地には農民の住居や集落が描かれ、封建領主の支配下にある中世的な村の様子が伺える。バンラッティ城の軍事的・政治的な重要性の変遷を、視覚的・時間軸的に解説。「The Earls of ThomondBunratty Castle spent most of its early life in the hands of the O’Brien family –the Earls of Thomond – who eventually moved to nearby Dromoland Castle.Portraits (left to right):Donough O’Brien, Baron of Ibrickan (d. 1634)Henry Fifth Earl, Bunratty, Sixth Earl (?), Henry O’Brien」 【トモンド伯爵家バンラッティ城は、その初期の歴史のほとんどをオブライエン家(トモンド伯爵家)の支配下で過ごしました。彼らは最終的に、近くのドロモランド城(Dromoland Castle)へ移りました。肖像画(左から順に):ドナフ・オブライエン(イブリッカン男爵、1634年没)第五代伯爵ヘンリー、バンラッティ在住。第六代伯爵(?)、ヘンリー・オブライエン】オブライエン家(O'Brien family) はアイルランドの著名な王族の末裔で、中世から近世にかけてのトモンド(Thomond)地方(現在のクレア県)を支配していた。トモンド伯爵は、イギリスによるアイルランド統治の中で与えられた称号。ドロモランド城は現在では高級ホテルとして使われているが、元はこの一族の居城。展示されている肖像画は、17世紀初頭のオブライエン家の有力者を描いたものと考えられる と。ここにも、狭い通路に設置された中世の兵士の甲冑を着た人物像(マネキン)が。バンラッティ城(Bunratty Castle)の地下部分(ベースメント)に関する展示パネル。「The Castle BasementThis is a fine long vaulted room with narrow windows. It was most likely used as a store or stable. Weapons and armour may also have been repaired andstored here. A murder hole over the entrance protected the inside door.A similar murder hole can be seen over the drawbridge protecting the main doorto the castle. Defenders could pour boiling water down on their attackers to keepthem away from the drawbridge and the main door. A second murder hole is situatedon the ceiling just inside the main door and could be controlled from the drawbridgechamber. This room also houses the drawbridge mechanism.A narrow stone stairs leads up from the basement to the Main Guard Hall, throughthe wall under the drawbridge, but this is far too narrow for everyday use. Modern visitors have to use the drawbridge to reach the Main Guard Hall.The castle walls are more than three metres thick at ground level.They may even conceal secret rooms and stairs that have yet to be discovered.The castle foundations are even wider and contain dungeons.These are located under each corner tower below ground level.One dungeon is open for viewing on the next floor.ATTACKING THE BASEMENTThe basement door could be attacked with a battering-ram but getting into the basement was not much use as it was difficult to reach the floor above.The openings were very narrow and defenders could keep the enemy・・・・?【城の地下室これは、細い窓のある立派な長いアーチ型天井の部屋です。おそらく物置や馬小屋として使われていたと思われます。武器や鎧が修理され、保管されていた可能性もあります。入口の上にある「殺人孔(murder hole)」は、内側の扉を守っていました。同様の殺人孔が、城の正面玄関を守る跳ね橋の上にも見られます。守備側はこの穴から攻撃者に向けて熱湯を注ぐことで、跳ね橋や正門から遠ざけることができました。2つ目の殺人孔は、正門のすぐ内側の天井に設置されており、跳ね橋室から操作可能でした。この部屋には跳ね橋の機構も収納されています。地下室から主警備室(Main Guard Hall)へは、跳ね橋の下の壁を通って狭い石造りの階段が続いていますが、日常的に使うには非常に狭すぎます。現代の訪問者は主警備室へ行くために、跳ね橋を利用する必要があります。城の壁は地上部分で厚さ3メートル以上あります。未発見の秘密の部屋や階段が隠されている可能性もあります。城の基礎部分はさらに広く、地下牢が含まれています。これらの地下牢は、四隅の塔の地下に位置しています。1つの地下牢は、次の階で見学可能です。地下室への攻撃地下室の扉は破城槌(バッテリング・ラム)で攻撃されることもありましたが、地下室に入っても上階へ到達するのが困難だったため、あまり意味がありませんでした。開口部が非常に狭く、防御側が敵を・・・】「Bunratty Castle(バンラッティ城)」の修復作業に関する展示パネル「1954 to 1960」、この期間にわたって、バンラッティ城の修復が行われたことを示していた。「SKIPS LUNCH WITH QUEEN」(女王との昼食を断って)ある著名な人物(おそらく修復資金の支援者または当時の文化関係者)が、女王との昼食の予定をキャンセルしてアイルランドの遺跡保存活動に専念したという内容の記事。当時の新聞切り抜きとともに、修復前の荒廃したバンラッティ城の写真も掲載されていた。「OIBRE」 は、アイルランド語で「作業」「事業」「工事」を意味。ここでは、修復作業の技術的概要や工期の詳細が説明されていると考えられる。バンラッティ城(Bunratty Castle)の主入口(メインドア)。吊り橋(Drawbridge)を渡って入る構造に。両脇には鎖(チェーン)があり、引き上げ可能な典型的な中世の防御機構。正面のアーチ型石造りの玄関口が、メインガードホール(Main Guard Hall)へとつながる通路。出入口の上部はやや張り出しており、かつてマーダーホール(murder hole)があった場所と一致していた。Great Hall(グレートホール/大広間)。奥の窓の両側に甲冑・武具(Armor & Weapons)が展示。左手奥の暖炉(fireplace)上にも装飾が。天井中央には枝角を模したシャンデリア。右奥上部のバルコニー風構造は “Minstrel’s Gallery”(吟遊詩人のバルコニー)で、演奏者が上から音楽を奏でるための場所であると。18世紀前後の貴婦人の肖像画。名前は??中世風のシャンデリア(天井吊り燭台)。髪を波打たせ、胸元を開いたローブをまとった女性像。両手を構え、祝福や祈りを表すポーズを取っていた。おそらく聖母マリア(Virgin Mary)を象徴した像。人物像の両脇には、左右に広がる2本の鹿の角(もしくはそれを模した木の枝)のような装飾。角(枝)には6つの燭台(計6本)を支える台座が付いていた。中世またはそれに倣ったデザインの「ロイヤル・ボックス(Laird's Gallery / Minstrel's Gallery / Lord's Balcony)」暖炉(fireplace)。移動して。ステンドグラスのあるゴシック様式の窓。左上と右上の壁に兜付きの胸甲(キュイラス cuirass)が壁に掛けられていた。飾りではなく、16~17世紀頃の実戦用であったもの。現地では「trophy armor(記念装備)」と呼ばれることも。左の壁にかけられた大きな銃(火縄銃または火打ち石式)も。長い銃身は、城の防衛用あるいは狩猟用。兜付きの胸甲(キュイラス cuirass)。大きな銃(火縄銃または火打ち石式)。見事な彫刻が施された木製のキャビネット(もしくはワードローブ)。左右開きの両開き扉を持つ大型の収納家具。扉面が格子状に分割されており、それぞれに彫刻が施されていた。石造建築の内部天井(アーチ構造)部分をクローズアップで。表面は白く塗られており、おそらく石やレンガに漆喰(プラスター)仕上げが施されていた。再び「大広間(Great Hall)」を。正面中央:主席(領主の座)窓の前に見える大きな椅子は、おそらく城主または支配者の玉座(主椅子)であり、左右に家臣などの席が配置されていた。壁に掛けられた鹿の角(スタッグ・ヘッド)もあった。大広間(Great Hall)を移動して。左の壁に掛けられている巨大なタペストリーは、中世・ルネサンス期によく見られる織物の装飾。騎士や貴婦人、宗教・神話的場面などが描かれていた。木製の棚(サイドボードまたはダレル棚 / credenza / court cupboard)厨房(キッチン)の暖炉であっただろうか?多くの暖炉内の器具(調理用鉄器)も。フィアドッグ(Firedog) 鍋をかける鉄製の支柱。火の上に鍋や串を渡す。ポットフック 鎖や鉤で鍋を吊るして火の強さを調整。スピット(Spit) 肉を串刺しにして回転させながら焼く回転器具。トリベット(Trivet) 熱源の上に鍋を載せるための三脚 等々が。厨房(キッチン)の「調理準備台(スラブ)」奥の小窓から自然光が入る、調理用の石造カウンターが壁際に設置されていた。吊るされた獣肉・鳥類(フェザント=キジ類)の姿も。羽付きのまま吊るされており、中世では熟成(aging)や血抜きのために数日吊るすのが常であったと。現在も同じ!?手前にはホタテ貝(Scallop shell)も。巡礼の象徴(サンティアゴの道)である一方、料理の容器としても使用されたのであろう。(グラタン風の焼き料理など)。壁上部には皿(木皿)が。上部の木製棚には、素朴な木製の丸皿(トレンチャー)が並べられていた。食卓用というより準備や運搬用の皿かも?非常に精緻な彫刻が施された大型の木製キャビネット(箪笥・収納棚)。主に貴族の大広間(Great Hall)や応接室に設置される、見せるための家具のようだ。タペストリー(壁掛け織物)。左右の壁に掛けられている2枚の織物は、室内装飾と断熱効果を兼ねた貴族文化の象徴。歴史や神話的場面が織り込まれていたのであった。そして 鹿の角(剥製)も。中世や近世ヨーロッパでは、狩猟は貴族階級の象徴 と。鹿の角を壁に飾るのは、地位・武勇・狩猟の誇りを表すのだ と。ここにも大きなタペストリーが。左側にはアーチと奥の空間が見えた。奥に見えるのは小礼拝堂か、別室の展示スペース。中央に十字架と祭壇のような物が見え、宗教的な用途が示唆されたのであった。反対側の壁面上部にも巨大タペストリーが。このような大広間の構造は、以下の目的を持っていたのだと・権威の象徴:高い天井、厚い石壁、狩猟戦利品の展示・実用性:防寒のためのタペストリー、防衛的構造・社交の場:祝宴、裁判、宗教儀式、結婚などの開催特にこの写真の壁面は、演出・象徴性に特化したデザインで、部屋の中心的な位置にあったのであろう。城館の大広間(Great Hall)の一部で、入り口近くの壁面の彫像と出入口の構造を。騎馬像(Equestrian Statue)。このような騎馬像は、以下のような象徴を持つのだと1.封建領主または城主の顕彰 ・建物を築いた者、または軍事的に功績のあった人物の姿を模した可能性2.宗教的または民話的英雄像 ・聖人(例:聖ゲオルギウス)、あるいは地方の伝説的守護者である場合3.ヨーロッパ中世の「騎士道美学」の象徴・名誉、忠誠、保護を象徴する空間演出 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.12
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その44):Bunratty Castle and Folk Park・ボンラッティ城と民芸村(1/6)
そして3連泊したGEATA NA CATHRACH APARTMENTSともお別れ。3連泊したAPARTMENTSの奥にあったのが四つ星ホテル「The Galmont Hotel & Spa・ザ ガルモント ホテル & スパ」。 この日の最初の目的地の「Bunratty Castle・ボンラッティ城」に向かって進む。 R339~R338~N67を使って南下する。「Bunratty Castle・ボンラッティ城」へのこの日の走行ルート。今にも雨が降りそうな天気。アイルランドの西海岸の気候は毎日こんな感じなのであった。そして約1時間で「ボンラッティ城&フォーク・パーク(Bunratty Castle & Folk Park)」入口に到着。「Welcome BUNRATTY CASTLE & FOLK PARK」 のロゴと名称中央のイラストはバンラッティ城の門とシカ(フォーク・パーク内で飼育)を表していた。「Bunratty Castle & Folk Park(バンラッティ城と民族公園)」の玄関マットFáilte(ファールチェ)とはアイルランド語(ゲール語)で「ようこそ!」という意味。Bunratty Castle & Folk Park(バンラッティ城とフォークパーク)の年間パスを紹介するポスター。「A GIFT OF MAGIC AND ADVENTURE AWAITS」【魔法と冒険の贈り物があなたを待っています】 「WITH YOUR ANNUAL MEMBERSHIP PASSImagine a year filled with magic andadventure for you and your loved ones!With an annual pass to Bunratty Castle& Folk Park, you can experience theenchantment and historical wonders ofthis unique destination.」 【年間メンバーシップ・パスのご案内あなたとご家族・ご友人にとって、魔法と冒険に満ちた一年をお届けします。バンラッティ城&フォークパークの年間パスがあれば、このユニークな場所で、魅力的で歴史ある体験を何度でもお楽しみいただけます。】「MEMBERSHIP INCLUDES:★ Day Visit Admission to Bunratty Castle and Folk Park★ 10% Discount at Admissions to Experience Stores★ 10% Discount on Evening Entertainment Shows★ Free Parking★ Newsletter Subscription for all events:Festivals, Educational Programmes and Christmas Events」 【メンバーシップに含まれる特典★ バンラッティ城とフォークパークへの日中入場(回数制限なし)★ 体験型ショップでの10%割引★ 夜間エンターテインメント・ショーの10%割引<★ 無料駐車場の利用★ 年間を通じて開催されるイベント情報(フェスティバル、教育プログラム、 クリスマス行事など)のニュースレター配信】「Bunratty Castle & Folk ParkMembership Terms & ConditionsIf you are a Family Membership Pass Holder, your pass gives you day admission to visit Bunratty Castle and Folk Park with one of the following combinations:Passholder + 3 AdultsPassholder + 2 Adults + 2 Children*Passholder + 1 Adult + 4 Children*If you are an Individual Pass Holder, your pass gives you day admission to visit Bunratty Castle and Folk Park with one of the following combinations:Passholder + 1 AdultPassholder + 2 Children*(*Children must be under 16 years)Named Passholder must be present and provide ID to gain admission at all times.Any card that is being used by someone other than the passholder is in breach of membership terms and conditions and the card will be retained by Shannon Heritage.Shannon Heritage may have to restrict the number of tickets that can gain access toBunratty Castle and Folk Park from time to time for circumstances outside of ourcontrol e.g. extreme weather conditions, in line with public health restrictions andguidance.Shannon Heritage will contact you via email in relation to priority booking for events.Admission is not included on capacity controlled event days such as Easter, Halloween and Christmas.EXPLORE MOREwww.bunrattycastle.ie/membership」【バンラッティ城&フォークパーク 年間メンバーシップ 利用規約【ファミリーメンバーシップ・パスをお持ちの方】下記のいずれかの組み合わせで、日中入場が可能です:パス保持者 + 大人3名パス保持者 + 大人2名 + 子ども2名*パス保持者 + 大人1名 + 子ども4名*【個人メンバーシップ・パスをお持ちの方】下記のいずれかの組み合わせで、日中入場が可能です:パス保持者 + 大人1名パス保持者 + 子ども2名**子どもは16歳未満に限ります。■ 注意事項・指名されたパス保持者ご本人が必ず同伴し、身分証明書を提示する必要があります。・他人によるパスの使用は利用規約違反とみなされ、カードはシャノン・ヘリテージにより 回収されます。・天候や公衆衛生の制限など、管理不能な状況により、入場者数が制限される場合があります。・イベントの優先予約については、メールでご案内いたします。・イースター、ハロウィン、クリスマスなど、入場制限のある特別イベント日はパスに 含まれません。】 受付にあった案内板。「BUNRATTY CASTLE & FOLK PARKWELCOME TO BUNRATTY CASTLE & FOLK PARKPlease note last admissionsto the Castle is 4.00 p.m. due topreparation for Medieval Banquet.Castle closes at 4.30 p.m.Please note last admissionsto Folk Park is 5.00 p.m.Folk Park closes at 5.30 p.m.」 【バンラッティ城 & フォークパークバンラッティ城 & フォークパークへようこそ 城への最終入場時間は午後4時です。 (中世の晩餐会の準備のため) ※城は午後4時30分に閉館します。フォークパークの最終入場時間は午後5時です。 ※フォークパークは午後5時30分に閉園します。】Bunratty Castle(バンラッティ城)内の受付デスク!?「Bunratty Castle Medieval Banquet BOOK TODAY or ONLINE WWW.BUNRATTYCASTLE.IE 」 【バンラッティ城 中世の饗宴ご予約は本日またはオンラインにてwww.bunrattycastle.ie】カフェや軽食レストラン「Mr. O'Regan’s Café」の内部。アイルランドの観光名所 Bunratty Castle(バンラッティ城) で行われている名物イベント、「Bunratty Castle Medieval Banquet(中世バンケット)」 を宣伝するポスター。中世の雰囲気を再現した晩餐会で、観光客にとって非常に人気の高い体験イベント とのこと。「Bunratty Castle・ボンラッティ城」に向かって進みながら、「Folk Park・フォーク・パーク」の見学へ。アイルランド西部の伝統的な漁船「クラック(Currach)」と、漁に使う網や籠などの漁具が展示されていた。Currach(アイルランド語:Curach)は、アイルランドの沿岸地域、とくに西部やアラン諸島で使われてきた伝統的な帆・櫂の漁船である と。茅葺き農家(Thatched Cottage)。建物の構造:白い石造りの壁に、厚い茅(藁)を葺いた屋根用途:主屋(左)には居住スペースや暖炉、納屋(右)には農具や動物の収容場所屋根の材質:小麦やライ麦などの麦わらを乾燥させ、厚く重ねて雨風を防ぐ煙突:暖炉の煙突が中央に見え、生活の中心が暖炉であることを示す建築年代:19世紀〜20世紀初頭にかけての農村生活の典型的住居農業用の古い機械(耕作・牧草作業用)。写真位置名称 名称(推定) 用途・特徴左側(青と赤) テッダー(Tedder) 用途:乾草を広げたり、裏返して乾燥を早めるき または 特徴:回転アームで草をま上げ、通気性を高める レーキ(Rake) 右側(緑と赤) ロータリーレーキ 用途:牧草を整列させて集める・土壌をならす (Rotary Rake) または 特徴:回転する爪で草や土をかき集める構造 ハロー(Harrow) アイルランド司祭館・医師の家か?鍛冶屋の作業小屋(Blacksmith’s Forge)。荒く切り出した石積み造りの壁には、複数の鉄製車輪が立てかけられていた。自然エリアで飼育されている鳥たち(家禽)。白い体で尾が長い鳥(写真右)は白色インドクジャク(White Indian Peafowl)。「カシェン川の漁師の家(The Cashen Fisherman’s House)」。 外壁が鮮やかな青色に塗られた建物。アイルランドの農村部では、家の外壁を青や白で塗ることがよくあった。特に青色は、魔除けや幸運の象徴とされ、家の中に「妖精(fairy)」や邪悪なものが入り込まないようにする信仰的意味合いがあったのだ と。「The Cashen Fisherman’s HouseThis simple two-roomed house is a replica of a salmon fisherman’s house from the Cashen river, which is located on the south side of the mouth of the Shannon.In the old days of wooden sailing ships, and ship wrecks, shore dwellers dependedlargely on flotsam and jetsam for their timber. Most of the timbering of this house and its like would have been of driftwood, which often came in huge planks and beams. This is evident in the wooden chimney canopy and the solid bedroom furniture, made by a local carpenter-boat builder. The ceiling is of whitewashed canvas to coverthe bare roof inside.Smuggling was a feature of life for these fishermen in the old days and many of the hardy fishermen were familiar with the ports of north western France and the Channel Islands. Claret and brandy were the local drinks, rather than beer and whiskey.The garden is meagre but potatoes and vegetables were grown for family consumption.」 【カシェン川の漁師の家この質素な2部屋の家は、シャノン川河口の南側に位置するカシェン川のサケ漁師の家を再現したレプリカです。木造帆船が使われていた時代、海難事故などで流れ着いた木材(漂流物)に、沿岸の人々は大きく依存していました。この家の木材の多くも、巨大な板や梁として打ち上げられた流木だったと考えられます。それは、木製の煙突フードや、地元の船大工によって作られたしっかりとした寝室の家具からも見て取れます。天井には、むき出しの屋根を覆うために石灰で白く塗られたキャンバス布が使われています。当時の漁師たちの生活には密輸がつきもので、たくましい彼らの多くは、フランス北西部やチャンネル諸島の港をよく知っていました。地元で飲まれていたのは、ビールやウィスキーではなく、クラレットワインやブランデーでした。庭は貧弱ですが、家族で食べるためのジャガイモや野菜が育てられていました。】「カシェン川の漁師の家(The Cashen Fisherman’s House)」の内部中央に黒い暖炉(open hearth)。寝室内部。壁には宗教画や家族写真と思われる額縁が3点掲げられており、アイルランド人家庭の深いカトリック信仰と家族への愛情を象徴していた。キッチン・ダイニングスペースに見られる典型的な「ドレッサー(dresser)」の様子。案内地図をネットから。そして石門を入ると「Bunratty Castle(バンラッティ城)」の正面、北面が現れた。バンラッティ城は非常に堂々とした建造物で、地面からそびえ立つ巨大な石柱のごとし。ノルマン様式のモット・アンド・ベイリー構造は、1250年に木造の天守閣と共に初めて建設された。その後、1276年にこの土地は別のノルマン人(トーマス・デ・クレア)に与えられ、防御力を高めるため、木造の天守閣は石造に建て替えられました。しかし、1287年、デ・クレアがイングランドに滞在していた際にアイルランド軍が攻撃し、バンラッティは破壊された。デ・クレアは再び城に戻り、再建と要塞の増築を行った。城はデ・クレアの息子リチャードの手に渡ったが、彼は1318年の戦死を喫した。リチャードの妻は彼の死を知るとバンラッティから逃亡し、城(と町全体)を焼き払った。この地はリムリックへの水路に近い戦略的な立地であったため、1353年にはこの地域の守護を任された別のノルマン人の領主によって3つ目の城が築かれましたが、完成後まもなくアイルランド人に占領されました。この城が破壊されたのか、それとも改築されただけなのかは記録に残っていないが、現在の城は1450年頃にマクナマラ一族の族長によって築かれたことは分かっていると。城は(おそらく政略結婚を通じて)所有者を変え、数百年にわたりオブライエン家の邸宅として使われた。19世紀初頭、数百年にわたり所有していたスタッダード家は、当時の流行に従い、より快適なマナーハウスへと移転した。その後、城跡は荒廃するまま放置されていたが、1950年代に民間人が購入し、公共事業局が修復作業を行い、1960年代に一般公開された と。西側にあった中世〜近世の砲台(大砲)展示エリア。中〜後期の鋳鉄製カノン砲(Cannon)で、木製砲架(gun carriage)に搭載された状態で展示されていた。長く細身の砲身は、17世紀〜18世紀の「ロングガン(long gun)」に近い形式。丸い鉄輪付きの移動式砲台である点が、城や要塞の防御に加え、場合によっては港湾防衛にも転用されていたことを示唆か。現在の 観光客の入場口(仮設の木製階段がある箇所)は、北側に。アーチ状の場所が城内入口。バンラッティ城(Bunratty Castle)の正面(北側)を見上げて。中央の大きく張り出した構造物は、「マッショリオン(machicolation)」と呼ばれるもので、敵が城壁に接近したときに上から石や熱湯を落とすための開口部。窓の配置や壁面の防御構造も、15世紀後半の塔型城(tower house)の典型的な特徴。左右の上部には防御用の胸壁(バトルメント / crenellations)が見える。正面(北側)の木製階段をズームして。この木製階段は、現代の来城者が安全に館内へ入るために設置された構造物。中央の踊り場から左右に階段が分かれており、上部の入口ポーチ部分(マッショリオン下)へと導いています。右手のアーチ型の石造入口からはおそらく地下または1階部分に入れますが、通常見学ルートは階段上から入るよう案内されていた。手前にある緑色の看板には「Last admission to castle 4:15pm」と。「BUNRATTY CASTLEThe earliest fortress at Bunratty (1251) was a “bretesche” or wooden tower erected on a moat. This was followed in turn by De Clare’s stone castle (1277) andDe Rokeby’s castle (1353).The present O’Brien castle, built 1425, had undergone many alterations during four centuries of occupation, but in the restoration works (1956/58) all additions later than 1619 (the date of the decorated ceiling in the chapel) were removed and the 15th century crenellations restored.Admiral Penn was besieged here in 1646 and it is generally believed that his son, William Penn, founder of Pennsylvania, then an infant, was at the castle.」 【バンラッティ城バンラッティにおける最初の要塞は1251年に築かれた「ブレテシュ」(堀に建てられた木製の塔)でした。その後、1277年にデ・クレア卿による石造りの城、1353年にデ・ロクビー卿の城が続きました。現在のオブライエン家の城(1425年築)は、約400年にわたる使用の間に数多くの改築を受けました。しかし1956〜58年の修復工事において、礼拝堂の装飾天井が設けられた1619年以降のすべての増築部分は取り除かれ、15世紀当時の胸壁(城壁の上部のギザギザした構造)が復元されました。1646年にはペン提督がこの城で包囲されており、後にペンシルベニア州の創設者となるその息子ウィリアム・ペン(当時はまだ幼児だった)が、この城にいたと一般に信じられています。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.11
コメント(0)
-

座間のひまわり畑へ-2
県道42号線、相模川に架かる「座架依橋(ざかえばし)」へ移動して、展望台代わりに。神奈川県座間市と神奈川県厚木市にあり、相模川にかかる道路橋。座間市座間(ざま)と厚木市依知(えち)に架かることから座架依橋(ざかえばし)と名付けられたのだ と。県道42号線は、3連休前からであろうか、貨物車両等で混雑していた。「相模川」のモニュメントには鮎の姿が。近づいて。道路に反対側には、この橋の下の相模川河川敷が「座間大凧まつり会場」でもあることから、大凧の姿が。こちらには「座架依橋」と。 残念ながら多くの落書きが。「座架依橋」の上を歩く。「座間市」の案内板がこの位置に。昔はこの下にも相模川の流れがあり、この下が相模川の中央なのであろう。眼下の「ひまわり畑」。 ここも「PHOT SPOT」 。スマホの設置台が置かれていた。「ひまわり畑」越しに海老名市方面の高層ビルを見る。分譲ツインタワーマンションの姿も。黄金野 風にそよぎて 波ひかる「座架依橋」と。夏の道 影を落とさぬ 花の群れ黄金波 風が子守の 歌をうたう平和とは 種蒔くひとと 花の列「座架依橋 Zakae Bridge」と。 咲き尽くし 種を残して 次の夏そして再び「座架依橋」のモニュメントを大山を背景に。そして、帰宅して我が部屋から昨夜の月をカメラに。農家のガラス温室の屋根に映る月光。ズームして。8月の満月は、昨日2025年8月9日(土)の午後4時55分と。この満月は「スタージェンムーン」とも呼ばれると。「スタージェンムーン」 (Sturgeon Moon) とは、8月の満月を指すアメリカ先住民の呼び名で、チョウザメの漁獲が盛んになる時期であることに由来 と。よってこの日は満月の1日前の写真で99% と。パーセントの数字は輝面率といい、月の光っている部分の面積率を表しています。新月が0%、満月が100%です。夜19:00時点の輝面率で計算しているのだと。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.08.10
コメント(0)
-
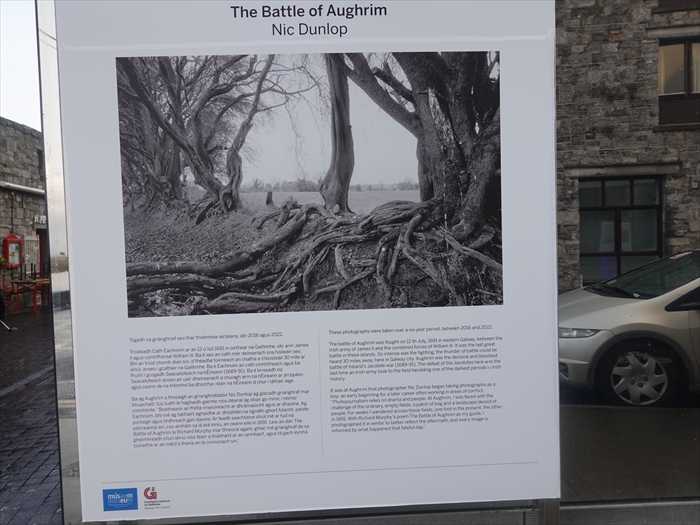
アイルランド・ロンドンへの旅(その43):GALWAY早朝散歩(4/4)
観光案内所「Galway Tourist Information Centre」のフェンスに掲げられていたアイルランドの写真をカメラで追う。「The Battle of Aughrim Nic DunlopThese photographs were taken over a six year period, between 2016 and 2022.The Battle of Aughrim was fought on 12 July, 1691 in eastern Galway, betweenthe Jacobite army under the command of James II and the combined forces ofWilliam III. It was the last great battle on Irish soil. Estimates of the dead runto 7,000. Sometimes who was fighting, the thunder of battle could be heard as far as Galway city. Aughrim was one of the decisive and bloodiest battles in Irish history, one which sealed William’s takeover (1690–91) of the throne of James II. For the defeated, the Irish army took to the field, signalling one of thedarkest periods in Irish history.It was at Aughrim that photographer Nic Dunlop began taking photographs as ameditation on the passage of time after war, often working in areas of conflict himself. The series highlights different markers of man and place at Aughrim and in landscapewest of the Shannon. As with all Dunlop’s documentary works, ordinary faces, a footpath, a tree, the bend of the road, form part of the terrain of memory. The Battle of Aughrimwas my guide. The Irish author Richard Murphy’s poem “The Battle of Aughrim” isused as the title. I began photographing the field in winter to better reflect the aftermath, and every image is haunted by the need to narrate not only what happened, but why it happened that fateful day.【これらの写真は2016年から2022年にかけて6年間撮影されたものです。アスリムの戦いは1691年7月12日にゴールウェイ東部で行われました。ジェームズ2世に忠誠を誓うジャコバイト軍と、ウィリアム3世の連合軍との間で戦われたこの戦いは、アイルランドの地で行われた最後の大規模な戦いでした。死者は7,000人に達したとも言われます。戦の轟音は、遠くゴールウェイ市にまで届いたとされています。この戦いは、アイルランド史上最も決定的で流血の多い戦闘の一つであり、ジェームズ2世に対するウィリアムの王位奪取(1690–91)を決定づけたものでした。敗北したアイルランド軍が戦場に身を投じたことは、アイルランド史の中でも最も暗い時代の始まりを象徴しています。写真家ニック・ダンロップは、このアスリムの地で戦後の時間の経過を見つめる瞑想的な作品作りを始めました。彼自身も多くの紛争地で活動してきた経験があり、このシリーズではアスリムやシャノン川以西の風景にある人間と場所の痕跡を強調しています。彼の他のドキュメンタリー作品と同様に、普通の顔、道、木々、曲がりくねった道が記憶の地形の一部を成しています。このプロジェクトの指針となったのはアイルランド人作家リチャード・マーフィーの詩「The Battle of Aughrim」でした。私は戦いの余韻をより鮮明に映し出すために冬に撮影を始めました。そしてすべての写真には、あの日何が起こったのか、そしてなぜそれが起こったのかを語り継ぐ必要性が宿っています。】「"At the very top of the hill, cavalry were mixed with infantry. The firing was so intensethat the ridges seemed to be ablaze. As dusk fell, the cavalry began to move away andtake flight, abandoning the infantry, who, in turn threw down their arms, left their colours and ran."— A Danish eyewitness account」 【丘の頂上では、騎兵と歩兵が入り混じっていた。銃撃は非常に激しく、尾根がまるで燃えているように見えた。夕暮れが迫ると、騎兵は後退して逃げ始め、歩兵を見捨てた。歩兵は次々と武器を投げ捨て、軍旗を置き去りにして逃走した。」― あるデンマーク人の目撃証言】「And a rook tied by the leg to scare flocks of birds /Croaks as I dismount at the deathcairn of St Ruth:Le jour est à nous, mes enfants, his last words: /A cannonball beheaded him andsowed a myth.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」 【そして群れをなす鳥たちを追い払うため、足を縛られたミヤマガラスが /私がセント・ルースの死のケルンに降り立つと鳴き声を上げる:「今日は我らのものだ、子らよ(Le jour est à nous, mes enfants)」と、彼の最期の言葉: /砲弾が彼の首を跳ね、そして神話が蒔かれた。— 『アスリムの戦い』リチャード・マーフィー著(リリパット・プレス刊)】「“The blood from the dead so covered the ground that one could hardly take a step without slipping. This grisly scene of slaughter remained untouched and unchanged for several days, the horror of which cannot be imagined except by those who saw it.”— A Danish eyewitness account」【死者の血が地面を覆い尽くし、一歩踏み出すことさえ滑らずにはできなかった。この凄惨な虐殺の光景は、数日間手つかずのまま変わることなく残り、その恐ろしさはそれを目にした者にしか想像できない。」― あるデンマーク人の目撃証言】この証言は、1691年7月12日のアスリムの戦いの結果として広がった戦場の阿鼻叫喚と死の光景を非常に生々しく描写しています。当時、戦死者は推定7,000人にのぼり、その多くが戦場に放置されたままだったとされています。血にまみれた地面という描写は、戦闘の激しさと死の密度を物語っており、単なる数字では捉えきれない「戦争の現実」が伝わって来るのであった。「Behind the dog-rose ditch, defended with pikes, /A tractor sprays a rood of flowering potatoes: /Morning fog is lifting, and summer hikers /Bathe in a stream passed by cavalry traitors.」【ドッグローズ(野バラ)の生け垣の裏側、かつて槍で守られた塹壕の向こうに、トラクターが一反の花咲くジャガイモ畑に薬剤を散布している。朝もやは晴れゆき、夏のハイカーたちがかつて裏切りの騎兵たちが渡った小川で水浴びをしている。】 「Aughrim’s great disaster /Made him two hundred years my Penal master /Raparees, whiteboys, volunteers, ribbonmen,Where have they gone? /Coerced into exile, scattered /Leaving a burnt gable and a field of ragwort.」 【アスリムの大災厄があの男を200年にわたる私の刑罰の主としたラパリー(義賊)、ホワイトボーイズ、義勇兵、リボン党たちよ彼らはどこへ行った?追放され、散り散りにされ焼け落ちた妻壁(切妻)と、キオンの野にそれを残して。】「“The Irish laid so close in their ditches, that several were doubtful whether they had any men at that place or not: but they were convinced of it at last; for no sooner were the French, and the rest, within twenty yards, or less, of the ditches, the Irish fired most furiously upon them; which our men bravely sustained, and pressed forwards, though they could scarce see one another for smoke.”— The Reverend George Story An Impartial History」 【アイルランド兵は自軍の塹壕の中に極めて身を潜めていたため、多くの者が本当にそこに兵がいるのか疑うほどだった。しかしついにそれが事実であることを思い知った。なぜなら、フランス兵や他の兵がその塹壕に20ヤード(約18メートル)以内に近づいたとたん、アイルランド兵たちは猛烈な銃撃を浴びせたからである。我が軍の兵士たちはこれを勇敢に耐え、前進を続けたが、煙のせいで互いの姿をほとんど見分けることができなかった。— ジョージ・ストーリー牧師『公正なる歴史』より】「He sees men run to the skyline /Throwing away muskets and pikes, /Then horsemen with sabres drawn /Cutting them down.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」【彼は、男たちが地平線へと逃げ走るのを見た。マスケット銃や槍を投げ捨てながらその後、サーベルを抜いた騎兵たちが彼らを斬り伏せていった。ーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)】 「Deep red bogs divided / Aughrim, the horse’s ridge /Of garland hedgerows and the summer dance, /Ireland’s defence / From the colonialist’s advance: /Twenty thousand soldiers on each side, /Between them a morass /Of godly bigotry and pride of race, /With a causeway two abreast could pass.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」 【深紅の泥炭地がアスリムを隔てた/馬の背のような尾根には/花輪の生垣と夏の踊りがあり、それはアイルランドの防壁となって/植民地支配者の進軍を拒んだ:二万の兵が両陣に並び、その間に広がるのは泥沼——敬虔なる偏狭と人種の誇りの泥沼、二人並んで通れるほどの狭い道しかなかった。ーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)】「Who owns the land where musket-balls are buried /In blackthorn roots on the eskar, the drained bogs /Where sheep browse, and credal war miscarried? /Names in the rival churches are written on plaques.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」 【マスケット弾が埋もれたこの土地は誰のものかエスカー(砂礫丘)に根を張るスピノサ(ブラックソーン)、排水された泥炭地には羊が草を食み、信仰の戦争は失敗に終わったーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)】「I dream of a headless man /Sitting on a charger, chiselled stone. /A woman is reading from an old lesson: /‘…who died in the famine.’ /Royal bulls on my land, I starved to feed the absentee landlord with rent.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」 【私は首を失った男の夢を見る軍馬にまたがり、刻まれた石の上に座る男。女が古い教科書を読み上げている:「……飢饉で命を落とした者について」王の牡牛が私の土地を歩き回り、私は地代を払うために飢えた――それも、そこにいない地主のために。ーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)】「Flies gyrate in their galaxy above my horse’s head /As he ambles and shies close to the National School – /Bullets under glass, Patrick Sarsfield’s /Would to God… /And jolts me bareback on the road for battle hill— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」 【蠅が銀河のように、馬の頭の上を旋回する馬がのんびり歩きながら、ナショナル・スクールの近くで身をすくめる ガラスの下にある銃弾、パトリック・サースフィールドの「神よ、かくあれかし……」そして私は鞍もなく、戦の丘へと向かう道で跳ね上がる。ーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)】「In opposite camps our ancestors /Ten marriages ago, /Caught in a feud of absent kings /Who used war like a basset tableGambling to settle verbal things, /Decide if bread be God / Or God a parable, /Lit matches, foddered horses, thirsted, marched, /Halted, and marched to battle.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」【敵対する陣営に分かれていた我らの祖先十代前の婚姻の時代、いずれもその場にいない王たちの争いに巻き込まれ戦争をバセット(賭博)テーブルのように使い言葉の問題を賭けで片付けようとしたパンが神か、それとも神はたとえ話かを決めようとしながら火を灯し、馬に飼葉を与え、喉を渇かせ、行軍し立ち止まり、そして戦場へと進んだ。ーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)】 「The story I have to tell /Was told to me by a teacher /Who read it in a poem /Written in a language that has died.Two hundred and fifty years ago /The poet recalled /Meeting a soldier who had heard /From veterans of the warThe story I have to tell.— The Battle of Aughrim, Richard Murphy © Lilliput Press」【私が語らねばならぬ物語はある教師から聞いたものでその教師はそれを一篇の詩で読んだ今は死に絶えた言語で書かれた詩だった250年前に詩人は語っていたある兵士に出会ったことをその兵士は、戦争の古老たちからこの物語を聞いたのだとーアイルランドの詩人 リチャード・マーフィー(Richard Murphy, 1927–2018) による詩集『The Battle of Aughrim(アスリムの戦い)』からの引用であり、出版元はダブリンのLilliput Press(リリパット・プレス)――私が語らねばならぬ物語を。】 「Dillon-Leetch & Company Solicitors Estd,1889」のビルの前にあった 「金属片を溶接?して製作された彫刻」。地元アーティストによる小規模なパブリックアートであろうか??正面を道なりに左折。R336とDock Street・ドックストリートとの交差点角にあったあった建物・「Steamship House(スチームシップ・ハウス)」。かつての蒸気船関連の倉庫や事務所として使われていた歴史的建築です。地元で長い歴史を持つ建物であり、象徴的な産業遺産として現在は改装され、さまざまなオフィスや事業所が入居。前方右手にマリーナ・Port of Galwayが姿を現した。この建物の壁にあった青い記念プレート(ブルー・プラーク)は、アイルランド・ゴールウェイの文筆家 Pádraic Ó Conaire(パードリック・オ・コナーラ) を讃えるもの。この建物は、ジェームズ・コノリーが1868年に生まれた場所とされており、ゴールウェイにおける歴史的スポットの一つ。現代では飲食店となっていますが、歴史的建築物としての記憶がこのブループラークに刻まれているのだと。「GALWAY LIONS CLUBPÁDRAIC Ó CONAIRE1882–1923AIT BHREITHE AN SCRÍBHNEORACHLIÚITIGH AS GAILLIMH AD'FHOILSIGH FORMHÓR ACHUID SAOTHAIR ASGAEILGEDÚCHAS NA GAILLIMHE - GALWAY CIVIC TRUST」 【ゴールウェイ・ライオンズ・クラブパードリック・オ・コナーラ(1882–1923)ゴールウェイ出身の著名な作家の生誕地。彼の作品の大半はアイルランド語で出版された。ゴールウェイ市民信託】朝のゴールウェイ港(Galway Harbour)のドックエリア(Galway Docks)を見る。このゴールウェイ港(Galway Harbour)の先端にマリーナ・Port of Galwayがあり、アイルランド3日目の6月2日(月)に楽しんだAran Islands(アラン諸島)・Inishmore(イニシュモア)島への観光フェリー👈️リンク、はここから出港したのであった。中世以来、ゴールウェイはアイルランド西部の重要な港湾都市で、スペインとの交易などにより繁栄して来た。正面に見える建物群は、旧倉庫を改装した港湾関連施設で、一部はまだ現役の業務用建物(貨物、漁業、港湾機械管理)として使用されているとのこと。様々な船舶が停泊中。停泊している船舶の中には、作業船(タグボートや浚渫船)も含まれており、港湾整備に関与しているのであろう。「United Presbyterian and Methodist Church」(合同長老・メソジスト教会)」。プロテスタント系のメソジストおよび長老派合同教会であり、現在も現役の礼拝施設である。 「United Presbyterian & Methodist Church, GalwaySunday Worship 11:15 a.m.(and other information about congregation)」と。「Eyre Square Centre(エア・スクエア・センター)」の西側入り口と、その隣接する歴史的石造建築。左側の建物(石造3階建て)は19世紀風のジョージアン様式またはネオクラシカル様式。ゴールウェイの「旧鉄道駅構内(Eyre Square / Ceannt Station)付近」にある特徴的な建物群。中央~右の「空中に浮いた建物」は「Celtic Gateway Building」または「Córas Iompair Éireann(CIÉ)オフィスビル」として知られる建物。近代的なプレキャスト・コンクリート構造で、ピロティ(1階が開いている柱構造)形式の珍しいデザイン。「Ceannt Station(ケアント駅)」前を通過。アイルランド国鉄(Iarnród Éireann)のゴールウェイ駅(Galway Railway Station)の正式名称であると。「To commemorate the 1916 Rising this building was namedÉamonn Ceannt Station in honour of Éamonn Ceannt」 【1916年の蜂起を記念して、この建物はエーモン・ケアントに敬意を表し、「エーモン・ケアント駅」と名付けられました。】約1.5時間の早朝散歩であった。Corrib川に沿ったGalwayの街の中にあった教会、史跡等を訪ねることが出来たのであった。そして3連泊したアパートメントに無事到着。時間は7:34。「eata na Cathrach - Galway Lakeside Apartments」 アパートメントに入るためのパスワード入力端末がこれ。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.10
コメント(0)
-

座間のひまわり畑へ-1
昨日、8月8日(金)の午後に車で45分程の場所にある「座間のひまわり畑」を訪ねてみました。相模川の川岸にある「座間大凧まつり会場」でもある駐車場に車を駐め、「座間のひまわり畑」に向けて歩く。相模川に架かる「座架依橋 (ざかえばし)」越しの大山を見る。 そしてこちらは、途中、角にあった「土地改良の碑」と「本多菊近翁之像」「土地改良の碑」には、神奈川県知事 長洲一二 と。ズームして。区画整理記念碑 座間市長 星野勝司本地域は、古くから相模第一の美田と称せられた水田と、畑地が連らなる相模川左岸耕地の北部に位置するが、水田地域に於ける用水不足や農道用排水路の不備。また狭小かつ不整形な圃場区画による農作業の非効率性解消は、関係耕作者永年の願望であった。昭和26年に国が農業基本法を制定されたのを契機に、関係者相諮り既に区画整理完了済の○○○○第一区とし主水路の改良、未整理地区〇第二区として区画整理の実施を目的に土地改良区を設立、昭和33年・・・・・・・(後略) 平成四年三月吉日 座間市新田宿土地改良区「本多菊近翁之像」。お顔をズームして。場所は県道42号線 座架依橋の下(相模川)。建立年月日:1989年5月(平成元年)。本多菊近翁之像の後ろ側に「勲五等瑞○○○○」。そして2025年の「座間ひまわりまつり」は翌日・今日8月9日(土)~8月10日(日)の3連休に開催されるのであった。まつり開催日には道路、駐車場が混むことが予想されるため、開催日前日に訪ねることにしたのであった。別の「座間ひまわりまつり」のポスター。55万本のひまわりが輝く と。そして5分ほど歩くとひまわり畑が姿を現した。無数の花が連なる畑が作る黄金の海原。「太陽を追う花」という物語性のひまわりの花。夏祭りのように一斉に同じ方向を向く統一感。花弁の縁に光が透ける透明感ある黄の輝き。仮設展望台が所々に設置されていたが、まつり開催の前日のため、階段は閉鎖され展望台に上ることは出来なかった。背伸びし、手を伸ばしカメラのシャッターを押す。携帯用の踏み台を持参するカメラマンの姿もあった。準備万端!!どこか懐かしさを感じさせる昭和の夏休みの記憶。翌日の出番を待つテント村。子どもたちの背丈を超える圧倒的な存在感。開花した瞬間のぱっと開く花火のような印象。大山を背にして。花芯の複雑な模様が持つ幾何学的な美しさ。白いベンチが準備された「PHOT SPOT」。 ひまわり畑へ誘うアーチも。こちらでは仮設駐車場の最終準備を。再び大山を背景に。田園の緑との調和が生む日本的な pastoral beauty(田園美)。ズームして。風に揺れるたびにこぼれる光のしずくのような輝き。一方では、ひまわりを見るたびに映画「ひまわり」を想いだし、戦火の「ウクライナ」に想いを寄せるのであった。ひまわりの列が未来へと歩みを進める行進のよう。 風にそよぐ音が平和のささやきに聞こえる。テント村に入り込んで。ウクライナの避難キャンプ場がふと・・・。青空と黄色の対比が生み出す国旗のような誇りの色彩。強くまっすぐ太陽を仰ぐ姿に揺るがぬ信念を感じるテント村の上には真っ白な入道雲一本一本が立ち上がる民衆のように誇らしい黄金の花畑の中に立つと、自分も一輪のひまわりになったような錯覚展望台も明日の出番を今や遅しと待つ。長く伸びる影が夏の午後の時間感覚を呼び起こして黄金の大地に降り注ぐ陽光をそのまま宿した花空に向かって開くその姿は、「負けない」という宣言のよう強くまっすぐ太陽を仰ぐ姿に揺るがぬ信念を感じるひまわりの瞳(花芯)が空の青を映しているように見えるそして県道42号線の下を潜り、次のひまわり畑へと。夏空を押し上げる黄金の太陽のような花姿青空とのコントラストが際立つ鮮やかな黄色花びらが寄り添い合って作る仲間の輪母子が花の陰で遊ぶ姿に平和な日常の尊さを思うそしてヒマワリに訪花するミツバチを追う。 ・・・つづく・・・
2025.08.09
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その42):GALWAY早朝散歩(3/4)
アイルランド旅行4日目、GALWAYの早朝散歩を続ける。Galway Cathedral・ゴールウェイ大聖堂を後にして、橋・Droiched an Dóchaisを渡りながらCorrib川の下流方向を見る。Galway Cathedral・ゴールウェイ大聖堂を振り返って。「Cross street Upper」にあったゴールウェイ(Galway)市内の有名な飲食店街「Latin Quarter(ラテン・クォーター)」の一角。左に見えるパブはTigh Neachtain(タイ・ノクタン)、アイルランド語で「ネクタン家の家」。伝統的なアイリッシュパブで、音楽イベントも行われている。右に見えるのがBusker Brownes(バスカー・ブラウンズ)複数の部屋とバーを持つ広いパブ/レストランで人気スポッ と。青い壁の建物は「Quay Street(キー・ストリート)」にあった有名なパブ「The Quays Bar(ザ・キーズ・バー)」。建物の上部にはアイルランドやアメリカ、ユニオンジャックなどの多国旗と、ニシツノメドリ(puffin)やイルカの絵が描かれたユニークな壁画。伝統的なアイリッシュ音楽とパブ文化の拠点で、観光客にも地元民にも人気 と。写真右手の緑と赤の外壁が印象的なファストフードレストラン・The Charcoal Grill。ケバブやバーガーなどのテイクアウトで人気。その隣に、HEART IN HANDS。アイルランド伝統のクラダリング(Claddagh Ring)を象徴する名。ジュエリーショップやアイリッシュギフトを扱う店 と。The Quays Bar(ザ・キーズ・バー)の正面に設置されている像で、名前は「The Galway Girl(ゴールウェイ・ガール)」像。女性は伝統的なアラン模様の服やスカーフを身にまとっており、ゴールウェイの歴史と文化を感じさせるのであった。ベンチに座っており、観光客が隣に腰かけて写真を撮ることができる「インタラクティブ型彫刻」。両手と膝が金色に輝いているのは、多くの人が触れたり写真を撮ったりすることで磨かれたため。いわゆる「幸運スポット」現象か。 店の名は「THE QUAYS BAR GALWAYGALWAYGALWAY GIRL」 「ラテン・クォーター(Latin Quarter)」の壁画。左側の壁画は魚売りの女性。年配の裸足の女性。緑のショールに茶色の服、青い前掛け。片手に魚、もう片手にバスケットを持つ。右側の壁画は「THE LATIN QUARTER」。「WELCOME TO THE LATIN QUARTER GALWAY(ラテン・クォーターへようこそ)」下にはアイルランド語で「Fáilte go Gaillimh!(ゴールウェイへようこそ)」と。アイルランド・ゴールウェイ市中心部にあるWolfe Tone Bridge・ウルフ・トーン橋のたもとにあった記念碑群。アイルランドの飢饉(The Great Famine, 1845–1852)を記念したモニュメントである と。Great Irish Famine(大飢饉):1845〜1852年のアイルランドを襲った壊滅的な飢饉。当時の主食であったジャガイモが疫病により壊滅し、約100万人が死亡、さらに100万人以上が国外に移民したのだ と。石碑には、青銅の銘板(英文とアイルランド語の碑文)が設置されていた。「TO THE MEMORY OF THE GREAT IRISH FAMINE AND OF THE SCULPTOR JOHN BEHAN SEAMEN'S GROUP WHOSE MEMORIAL SCULPTURE WAS DONATED TO THIS SITE」 【大飢饉の記憶に そして 彫刻家ジョン・ビーハンによる 「船乗りたちの群像」に捧ぐ その記念彫刻は この場所に寄贈されたものである】と。そしてこちらは抽象的な黒い花弁のような彫刻。「帆船の帆」または「海鳥」を象徴しており、コロンブスの航海と探検精神を表現していると。近づいて。「FRANCO COLOMBOS T E F A N O M I R A L L A C HJ A V I E RB O N M I R K A L L O C HC R I S T O F O R OC O L O M B OCITTÀ DI GENOVA1492-1992」 【フランコ・コロンボステファノ・ミララックハビエルボン・ミルカロッククリストフォロ・コロンボ(コロンブス)ジェノヴァ市1492年 - 1992年】「Colombo(コロンブス)」という名前と「Città di Genova(ジェノヴァ市)」は、コロンブスの出生地を指しています。「1992年」は、コロンブスのアメリカ大陸“発見”から500年(1492年〜1992年)を記念する年。ゴールウェイとイタリア・ジェノヴァ市の友好関係、もしくは大航海時代のコロンブスを通じた歴史的つながりを記念した碑文である と。2人の肖像画風のステッカーが貼られていた。いわゆるストリートアートや政治風刺・都市芸術の一種か?Wolfe Tone Bridge・ウルフ・トーン橋のたもとから、Corrib川の河口方向を見る。Wolfe Tone Bridge・ウルフ・トーン橋を振り返って。次の目的地「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」に向かってCorrib川の流れに沿って進む。 「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」。「The Spanish ArchAn Póirse CaochThe Spanish Arch is a bulwark constructed as an extension to the medieval town wall. Completed in 1584, it was built to protect an extended quays area from attack.Originally known as Ceann an Bhalla (Head of the Wall), the arch eventually became better known by its Spanish name, though the exact origin of the name is unknown. It is widely assumed that the name reflects Galway’s strong historical trade connectionswith Spain and Spanish merchants.A picture of the Spanish Arch and the town bulwark with two arches, of which only onesurvives today, dates from the early 19th century. Both arches can be seen along thestretch of the old town wall extending to the banks of the River Corrib. The surviving arch is thought to be one of the last remaining features of the medieval town wall. The site of the Spanish Arch has been designated as a protected structureand is maintained by Galway City Council.The Spanish Arch is today one of Galway’s most recognizable landmarks andbears testimony to its importance as a medieval seaport.」 【スパニッシュ・アーチ(スペインのアーチ)アイルランド語:An Póirse Caoch(アン・ポールシュ・キーホ) スパニッシュ・アーチは、中世の城壁を延長する形で築かれた防御のための建造物です。1584年に完成し、波止場の拡張区域を外敵から守る目的で建設されました。もともとはCeann an Bhalla(壁の端)というアイルランド語で知られていましたが、後に「スパニッシュ・アーチ」の名で広く知られるようになりました。その由来は明確ではありませんが、ゴールウェイがスペインと強い交易関係を持っていたことを反映していると考えられています。スパニッシュ・アーチと、その隣にあった2つのアーチ(現在は1つだけが残存)を描いた19世紀初頭の絵が残されています。これらのアーチは、コリブ川(River Corrib)へと伸びる旧城壁の一部として存在していました。現在残っているアーチは、中世の町の城壁の最後の遺構のひとつと考えられています。スパニッシュ・アーチの場所は、現在保護構造物(Protected Structure)として指定され、ゴールウェイ市議会により維持管理されています。今日、スパニッシュ・アーチはゴールウェイで最も有名なランドマークのひとつであり、中世の港町としてのゴールウェイの重要性を今に伝えています。】1838年にウィリアム・エヴァンス・オブ・イートン(William Evans of Eton)によって描かれた水彩画。この作品は、19世紀前半のゴールウェイの港の様子を生き生きと描いた歴史的なビジュアル資料。・左側には、スペインのアーチ(Spanish Arch)の2つのアーチ門が描かれています (現在は1つだけ現存)。・アーチの前では、女性や子どもたちが談笑・作業しており、漁師町の賑わいを感じさせます。・中央から右側にかけては、帆を張った小舟が着岸しており、荷物の積み下ろしや魚の取引が 行われている様子。・背景の遠景(Claddagh)には、クラダ地区(Claddagh)の漁村家屋が描かれており、当時の クラダ漁村の生活圏がうかがえます。気候変動による海面上昇の予測と、それを可視化するアートインスタレーションについての案内板。Línte na Farraige – A light InstallationPredicted Sea Level Rise 2150(リンテ・ナ・ファラガ:光のインスタレーション/2150年の海面上昇予測)「Línte na Farraige(アイルランド語で『海の線』の意)」は、将来的な海面上昇の予測を視覚化するための光のインスタレーション。このプロジェクトでは、2150年までに予測される海面上昇の高さに光の線を投影。スペイン・アーチ(Spanish Arch, Galway)を含む、アイルランド各地の歴史的・象徴的な場所で実施。目的:気候変動への理解と行動を促す。コミュニティ、自治体、政策決定者にインフラ強化の必要性を訴える。中央の夜景写真では、スペイン・アーチの壁に光の線が投影されている様子が見らた。これは、2150年にはこの高さまで海面が上昇する可能性があるという警告 と。移動して、「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」を見る。川岸からCorrib川に架かるWolfe Tone Bridge・ウルフ・トーン橋を振り返って。「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」のアーチ部。Corrib川に架かるWolfe Tone Bridge・ウルフ・トーン橋方向を見る。「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」の右側を海側から。「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」とは?・建設:1584年(拡張は18世紀)・ゴールウェイ港を防御するための町の外壁の一部。・アーチは町と港をつなぐ通路として機能していました。・「スペイン・アーチ」という呼び名は後世に付いたもので、スペインとの貿易の関係を示唆。・現在はゴールウェイを代表する観光名所の一つ。ゴールウェイ(Galway)の「Long Walk」沿いの石壁に取り付けられた銘板(プレート)。アイルランドの作家 Ken Bruen(ケン・ブルーエン)の小説 「Priest」(2006年)の一節を引用したもので、Long Walkの魅力を詩的に語っているのだ と。「LONG WALKLong Walk is among my favourite routes. You pass under the Spanish Arch andthen along by the water, the Claddagh right across. Nimmo’s Pier marks the point. Before you lies Galway Bay, you can almost see the Aran Islands. If I ever get lucky orseriously rich, that’s where I’m headed, as a base if nothing else. The sound of seagulls, the smell of the ocean, you gulp deep breaths and want to mouth a rosary of gratitude.It should be mandatory for artists to live here, an oasis of the soul. And if it’s a bright day,Sweet Jesus, you are elated. from *Priest* by Ken Bruen」 【ロング・ウォークロング・ウォークは、私のお気に入りの散歩道のひとつです。スペイン・アーチをくぐり、水辺沿いに歩きます。対岸にはクラダフが広がっています。ニンモの桟橋がその先端を示しています。目の前にはゴールウェイ湾が広がり、アラン諸島がほとんど見えそうです。もし運よく、あるいは本当に裕福になれたら、私はきっとそこへ向かうでしょう。せめて拠点にするだけでも価値があります。カモメの鳴き声、海の匂い、深く息を吸い込み、思わず感謝の祈りを口にしたくなるのです。芸術家はここに住むことを義務づけられるべきでしょう。心のオアシスなのです。そして、もし晴れた日なら──おお、主よ、まさに天に昇る気分です。ケン・ブルーエン著『プリースト』より】Corrib川の河口方向を再び。前方の道が「The Long Walk」。「The Long Walk(ロング・ウォーク)」は、アイルランド・ゴールウェイ市の中心部、スペイン・アーチ(Spanish Arch)のすぐ西側から始まり、ゴールウェイ湾(Galway Bay)に沿って続く短いが非常に風光明媚な海辺の遊歩道。ゴールウェイを代表する散策スポットとして、地元の人々や観光客に愛されているのだ と。 T字路の角から「Spanish Arch・スパニッシュ・アーチ」を振り返る。そして、T字路の角にあったのが観光案内所「Galway Tourist Information Centre」。観光案内所のフェンスにはアイルランドの写真が数多く並んでいた。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.09
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その41):GALWAY早朝散歩(2/4)
「Saint Nicholas' Collegiate Church・英国国教会」を後にして、次の目的地の「Galway Cathedral・ゴールウェー大聖堂」に向かって「コリヴ川」に沿って歩く「Friars River Abhainn na mBráthar」と書かれていた。Abhainn na mBráthar(アウィン・ナ・ヴラーアハル) =「修道士たちの川」 - Abhainn = 川 - na mBráthar = 修道士たちの と。「Friars River」は、Corrib川から分かれる小さな流れで、かつてドミニコ会修道士(Dominican friars)が住んでいた場所の近くを流れていた。この川は、修道士たちがかつてこの地にいたことから「Friars’ River(修道士の川)」と呼ばれているのだと。 「Friars River」の清流には川藻が。この教会風の建物は?。橋「Droiched an Dóchais」の袂にあったが。The Galway City Museum(旧教会建築部分)または旧「St. Vincent de Paul Catholic Church」であろう。 橋「Droiched an Dóchais」の上から振り返って。前方に見えて来たのが「Galway Cathedral・ゴールウェー大聖堂」。手前の川が「Corrib川」。 ゴールウェー大聖堂(Galway Cathedral)は、アイルランド西部ゴールウェー市のランドマークであり、宗教的・歴史的・建築的に非常に重要な建物 と。正式名称:Cathedral of Our Lady Assumed into Heaven and St. Nicholas(聖母被昇天および聖ニコラス大聖堂)。 項目 内容・建設期間 1958年着工、1965年完成・設計者 J.J. Robinson(アイルランド人建築家)・建設地 旧ゴールウェー市刑務所(The Galway Gaol)跡地・建築様式 ローマ・ルネサンス様式+ビザンチン様式+ゴシック要素の折衷・緑青色の大ドーム:遠方からもよく見えるランドマーク的存在・石造りの重厚な壁面:アイルランド産石材を使用・二本の鐘塔(右側)と八角形のドラム型ドーム(中央)・ファサード中央の彫刻:キリストと天使の浮き彫り(聖母の被昇天を象徴)朝の陽光に照らされた「Salmon Weir Bridge・サーモン・ウィア橋」。 橋の上から「Salmon Weir・サーモン・ウィア堰/魚道」を見る。これは「可動式の堰(ウィア)」で、Corrib川の水量や流速を制御する目的で設置されている と。中央部分の一部に、サケの遡上を助ける「魚道(フィッシュパス)」が見られる と(小さく水が逆流している部分)。右岸側をズームして。更に。ネットから航空写真を。再び「旧St. Vincent de Paul Catholic Church」を振り返って。橋の上から先ほど訪ねた「Collegiate Church of St. Nicholas(聖ニコラス教会)の尖塔」が見えた。 正面にGalway Cathedralの巨大な中央ドーム。そしてファサード中央の花型ローズウィンドウ(バラ窓)。ファサード中央の花型ローズウィンドウ(バラ窓)をズームして。さらに。内部からの写真をネットから。Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)の鐘楼(ベルタワー)を西側から見上げて。Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)とSalmon Weir Bridgeの間の緑地帯(川沿い)にあったのが「Statue of Máirin de Valéra(マーリン・デ・ヴァレラの記念碑)」 近づいて。「リバー・ガール(River Girl)」や「ニンフ像」などと呼ばれることもある と。これは「Máirin de Valéra」博士(1912–1984)の記念碑の一部である と。Máirin de Valéra 博士はアイルランドの有名な植物学者であり、アイルランド大統領Éamon de Valéra の娘。アイルランド西部の自然、とくに藻類(海藻類)研究の第一人者。Galwayの自然と教育に大きく貢献した人物 と。「Equality Emerging –The PeopleThis John Behan sculpture unveiled in 2001 by Mr. Des Geraghty, General President ofSIPTU and Professor Iognáid O'Muircheartaigh, President of NUI Galway and Convenor of Líonra, was inspired by an idea of Eddie Higgins of SIPTU and Nuala Keher ofNUI Galway.It was part funded by the European Social Fund and presented throughGalway's Mayor, Councillor Donal Lyons, to the people of Galway City.“Equality Is But Difference – Respected and Celebrated”KILMAINHAM ART FOUNDRY」【平等の顕現 ― 人々このジョン・ビーハンによる彫刻作品は、2001年にSIPTU(アイルランド労働組合)会長デス・ゲラフティ氏と、NUIゴールウェイ学長でLíonra(高等教育ネットワーク)代表のイオグナイド・オ・ムルケルタ教授によって除幕されました。この作品は、SIPTUのエディ・ヒギンズ氏とNUIゴールウェイのヌーラ・キーハー氏のアイデアに触発されたものです。制作費の一部は欧州社会基金(European Social Fund)によって支援され、ゴールウェイ市長ドナル・ライオンズ市議を通じて、ゴールウェイ市民に贈られました。「平等とは違いである ― 尊重され、そして称賛されるべきもの」(鋳造:キルメイナム・アート・ファウンドリー)】 Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)の鐘楼(Bell Tower)。八角形ベースの塔屋(タレット)が四隅にあるロマネスク風デザイン。中央のアーチ内には実際の鐘(ベル)と、それを補助するように取り付けられた複数のラウドスピーカー(拡声装置)が見えた。中央ドーム(main dome)を斜めから。銅板葺き(緑青に変化)の大きなドーム。上部に金色の像(おそらく大天使ミカエルか、聖母マリアの象徴)が飾られていた。Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)の西正面(西側ファサード)を正面方向から。Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)西正面ファサードの全景を正面から。ズームして。ローズウィンドウ(Rose Window・バラ窓)石のトレーサリー(枠)で構成された花形の装飾窓。ガラス部分は控えめですが、内側にはステンドグラスが組み込まれており、内観から見ると光を受けて鮮やかに輝きます。このデザインは、「聖母マリアの象徴(薔薇)」を表していると。「聖母マリアと幼子イエス(The Virgin Mary and Child」 聖母マリアは直立した姿で、腕に幼子イエスを抱いていた。像の背景にある文字「M」と「R」は、→ Maria Regina"(マリア・レジーナ=「女王マリア」)の略と。縦に長く流れるローブ状の造形は、マリアの荘厳さと霊的象徴性を表しているのだ と。Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)の歴代司教の紋章。カトリック教会において、緑の広縁帽(galero)と両脇の房(タッセル)は階級を示す伝統的記号であるとのこと。・緑色+6段の房(左右12個) → 大司教(Archbishop)・緑色+5段の房(左右10個) → 司教(Bishop)このレリーフでは、5段の房があるため、これは通常の司教の紋章であると。教皇パウロ6世(Pope Paul VI)の紋章(在位:1963年~1978年)上部に描かれた3段構成の王冠・三重冠(ティアラ)は、伝統的なローマ教皇の象徴である「ティアラ(Tiara)」。University Roadの西側を望む。 Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂)の周囲を1周することに。アイルランド・ゴールウェイにある Galway Cathedral(ゴールウェイ大聖堂) の南側から見た外観。1周して東側手前からの外観。再び東側のローズウィンドウ(バラ窓)を。振り返って。鐘楼(ベルタワー)が右手に見えた。ゴールウェイ大聖堂の方位構成まとめ:方角 内容東側 正面ファサード、ガラス扉、ローズウィンドウ、鐘楼(右手に)西側 主祭壇、後陣(apse)、聖具室や事務棟のある裏側構造南側 側廊・身廊の窓が並ぶ長辺、駐車場にも接している北側 通常は通路・河川(Corrib川)に面する遊歩道あり早朝の為、内部を見学できなかったのでネットから写真をいくつか。4箇所のローズウィンドウ(バラ窓)の絵柄(デザイン・ステンドグラス)はすべて異なるとのこと。●東側正面(入口上部) 石の花形トレーサリーあり、ガラス越しに明るく見える 外から見て目立つが、内部からのステンドグラスはシンプル (象徴モチーフ)●西側(主祭壇上部) 最も荘厳で色彩豊か キリストの栄光と復活を中心とした宗教画様式 (Patrick Pollen 作)●北側(横壁高所) 色調は寒色系中心、抽象的構成 旧約の象徴や神秘的なモチーフが多い●南側(横壁高所) 色調は暖色系、動きのある構成 新約、福音書記者の象徴 (獅子・鷲など)や聖霊の鳩など ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.08
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その40):GALWAY早朝散歩(1/4)
この日は6月3日(火)、アイルランド4日目、3連泊のアパートをチェックアウトする日の朝。6時前の起床し、我が部屋の窓からの朝の陽光を見る。そして6時過ぎに、1人で1時間ほどの朝の散策に出かける。「GALWAY」駅前を通過。 「GALWAY」駅の到着時間案内の電光掲示板。ズームして。「GALWAY」駅は終着駅。時間は06:17。Tickets売場。更に進むと、雨が降って来たので傘を差しての早朝散策に。Eyre Square・エア広場に到着。正面に銅像があった。「Pádraic Ó Conaire Statue・パトリック・オカハンの記念像」。座っている像はオカハン本人の姿を写実的に表したもので、帽子とスカーフ姿の物憂げな表情が印象的。パトリック・オカハン(Pádraic Ó Conaire)とは?・1875年〜1928年・アイルランド語での文学・詩作の先駆者であり、小説家、評論家、ジャーナリストとしても活躍。・彼の作品は、アイルランド語復興運動と文化的ナショナリズムを支えるものとして高く 評価されました。・主にゴールウェイ出身で、生涯に渡って西部アイルランドの風土や人々を作品に取り入れました。横にある、ライトアップされた石碑には「PÁDRAIC(パドリック)Ó CONAIRE(オカハン)SCRÍBHNEOIR(作家)1882 – 1928」 と。「Pádraic Ó Conaire(パドリック・オカハン)」について詳しく紹介するバイリンガル解説板「Pádraic Ó Conaire (1882–1928)Born Patrick Joseph Conroy in Galway in February 1882, Pádraic Ó Conaire was raised in Irish-speaking Conamara. Following the untimely deaths of his parents, he was raised by relatives. Educated at Rockwell and Blackrock colleges, he joined the CivilService in London in 1901 and became a member of the Gaelic League. Inspired by Russian, French, and Scandinavian literature, he began to write short stories andplays in the Irish language under his Irish name, Pádraic Ó Conaire. His work won multiple awards and was published in newspapers and magazines.He returned to Ireland in 1915 and spent his final years in Galway. He died in Dublin in October 1928 and was buried in Bohermore Cemetery, Galway. A limestone memorial statue by sculptor Albert Power was unveiled in Eyre Square in June 1935 by Irishleader Éamon de Valera. The first statue in Ireland to honour an Irish-language writer,it became a beloved Galway landmark. It was decapitated in 1999 and subsequently repaired and moved for safekeeping. This bronze replica was unveiled by Irish President Michael D. Higgins in November 2017. The original may be seen atGalway City Museum.」 【パドリック・オカハン(1882年 – 1928年)1882年2月、ゴールウェイでパトリック・ジョセフ・コンロイとして生まれたパドリック・オカハンは、アイルランド語を話すコネマラ地方で育ちました。両親の早すぎる死を受け、親族に引き取られて成長します。ロックウェル校とブラックロック校で教育を受けた後、1901年にロンドンの官吏(公務員)となり、ゲール語連盟(Gaelic League)に加入しました。ロシア、フランス、スカンジナビアの文学に影響を受け、アイルランド語で短編小説や戯曲を書き始めます。その作品は複数の賞を受賞し、新聞や雑誌にも掲載されました。1915年にアイルランドへ戻り、晩年はゴールウェイで過ごしました。1928年10月にダブリンで亡くなり、ゴールウェイのボホーモア墓地に埋葬されました。1935年6月、彫刻家アルバート・パワーによる石灰岩の記念像が、アイルランドの指導者エイモン・デ・ヴァレラの手でアイア・スクエア(ゴールウェイ中心部)にて除幕されました。これはアイルランド語作家を讃える国内初の銅像であり、以来ゴールウェイの人々に親しまれるランドマークとなりました。1999年に頭部を破壊される事件が発生したため、修復後は安全のため移設されました。現在のブロンズ製レプリカ像は、2017年11月にアイルランド大統領マイケル・D・ヒギンズによって」除幕されました。オリジナルの像はゴールウェイ市立博物館で展示されています。】正面にあったのが、5月31日(土)の夜に訪ねた「クインセンティニアル ファウンテン(Quincentennial Fountain )」👈️リンク。(旧): Bank of Ireland, Eyre Square branch(アイルランド銀行・エア広場支店、現在は閉鎖・賃貸中)と。19世紀中期のジョージ王朝様式(Georgian)を基にした石造建築。特徴:・2階部分のアーチ型窓と、1階入口上部の重厚な庇(ひさし)。・3階屋根裏部分のドーマー窓(屋根から突き出た半円アーチの小窓)。・灰色の石材を使用した外観は、官公庁建築にも似た重厚な雰囲気を持ちます。Eyre Square・エア広場前の街並みを振り返って。Eyre Square・エア広場の道路沿いには「リアム・メロウズの像(Liam O'Maoiliosa Statue)」、「クインセンティニアル ファウンテン(Quincentennial Fountain )」や「ブラウン・ドアウェイ(The Browne Doorway)」の史跡があった。いずれも先日に訪ねた史跡。 デパート・Brown Thomas Galway。正面にあったのが「Statue of Oscar Wilde and Eduard Vilde」 「Conversation Piece」とも呼ばれていると。近づいて。・制作者:彫刻家サーヴィ・ジーグル(Seamus Connolly)とジョアナ・ジーグル (Joanna Zieger)。・設置年:1997年(ゴールウェイとエストニアのタルトゥ市の姉妹都市関係を記念)。両者が対話しているようなポーズでベンチに腰掛けており、実際に観光客が間に座って記念写真を撮ることができる人気スポット。彫像はエストニア共和国からの寄贈であり、文学と国際交流を象徴している と。 左:オスカー・ワイルド(Oscar Wilde, 1854–1900)・アイルランドを代表する詩人・劇作家・小説家。・『ドリアン・グレイの肖像』や戯曲『ウィンダミア卿夫人の扇』などで知られる。・鋭いウィットと美への愛、社会批判的な風刺で知られる人物。・彫像では、杖と帽子を手にしている姿で表現されている。右:エドゥアルド・ヴィルジリオ・ヴィルモラン(Eduardo Vilde, 1836–1913)・アルゼンチンの作家・政治家・医師。・偶然にも同じ「Wilde(ワイルド)」という姓を持ち、オスカーと対話する設定で この彫像が制作された。「IRISH WRITER OSCAR WILDE」 “It is only by contact with the art of foreign nations that the art of a country gainsthat individual and separate life that we call nationality”」【一国の芸術が“国民性”と呼ばれる独自で独立した生命を得るのは、外国の芸術と触れ合うことによってのみである。】 この碑文は、オスカー・ワイルドと同姓であるエストニアのEduard Vildeとの彫刻「Conversation Piece」に付随するもので、アイルランドとエストニアの文化的友好関係を象徴しているのだ と。歴史的建物 「Teach an Linseach(リンチ家の家)」。この建物は16世紀初頭に建てられた。1930年に修復され、マンスター&レンスター銀行の支店として使用された。ゴールウェイをアイルランドで最も優れた都市建築の町にした壮麗な建物群の、最後に残された例である と。彫刻装飾の中には、ヘンリー7世、リンチ家、キルデアのフィッツジェラルド家の紋章が含まれている と。「Teach an LinseachBuilt early 16th century. Renovated 1930 when it was adapted as a branch of the Munster & Leinster Bank.The last surviving example of the stately buildings which made Galway one of the bestbuilt of Irish towns.Among its sculptured decorations are the arms of Henry VII, the Lynches, and the Fitzgeralds of Kildare.」 【リンチ家の家16世紀初頭に建てられた。1930年に修復され、マンスター&レンスター銀行の支店として使用された。この建物は、ゴールウェイをアイルランドで最も優れた都市建築の町にした壮麗な建物群の、最後に残された例である。彫刻装飾の中には、ヘンリー7世リンチ家、キルデアのフィッツジェラルド家の紋章が含まれている。】移動して。そして正面に見えて来たのが「Saint Nicholas' Collegiate Church・英国国教会」。 セント・ニコラス・カレジエイト・チャーチ(Saint Nicholas' Collegiate Church)は、アイルランドのゴールウェイに位置する、英国国教会の教会です。1320年に設立され、アイルランド最大の現役の中世の教会。セント・ニコラス・カレジエイト・チャーチは、700年以上にわたり、ゴールウェイの中心で活動を続けています。教会では、聖歌隊「セント・ニコラス・スコラ・カントールム」が音楽活動を支えています。また、教会の構造と文化を未来世代のために守るためのプロジェクトが進行中です。教会は、その歴史を学ぶためのツアーも提供しています と。ロンバート・ストリートに面した正門から中に入る。創建: 1320年頃(14世紀初頭)宗派: アイルランド聖公会(Church of Ireland)特徴: ・アイルランドで現在も使われている最大の中世の教会のひとつ ・名称の「Collegiate」は、1485年に集会聖職者団(collegiate church)となったことに由来。・中央の赤い扉: ゴシック様式のアーチに囲まれた主玄関の一部。色鮮やかな赤いドアが印象的で、 訪問者を迎える入口として機能。・三連の尖塔型窓(ゴシック様式): 上部に見える大きなアーチ型のステンドグラス窓は、ゴシック建築の特徴である 頭アーチ(Pointed Arch)を示しています。 現在はガラスが透明または半透明で装飾は控えめですが、かつては彩色されたステンドグラスが はめられていた可能性もあります。・石造りの壁: 灰色の石材による堅固な壁面が教会の歴史的な重厚さを物語っています。 長い年月の風雨による石の変色や劣化も、教会の長い歴史の証です。・排水管: 窓と窓の間に見える縦の黒いパイプは雨水の排水用のもので、伝統的な建物に現代の機能を 加えた形です。・右下の小さな標識:「RECTOR PARKING」 教会の主祭司(Rector)が車を駐車できる場所を示している。この石碑は?「IN MEMORY OF REV. JOHN [姓] RECTOR OF THIS PARISH WHO DIED [日付] 18[年号]」の文字が・・・??? 時計塔部分をクローズアップ。この教会は15世紀のゴシック建築様式を基に建てられており、後の時代(19世紀末〜20世紀初頭)に時計塔などが増築されたと考えられる。尖塔は銅板で覆われており、長年の風雨により緑青(ろくしょう)を帯びた美しい緑色になっていた(酸化銅の自然な変化)。教会本体の南側の付属構造(チャペルまたは側廊)。前景の建物は、おそらく後世に付け加えられた小礼拝堂(side chapel)。手前の建物(付属棟)にも、本体と同じような尖頭アーチ型のゴシック様式の窓が見られた。窓ガラスはダイヤ型のリード線(格子状)で組まれたステンドグラス(透明~半透明)。北側の教会墓地(Churchyard)。「Welcome to St. Nicholas’ Collegiate Church and GroundsThe Church is open dailyPlease take care and watch for moving trafficChildren must be supervised at all timesDo not litterDo not feed the pigeonsDrinking alcohol & antisocial behaviour is forbiddenBy Order of the Select Vestry」 【聖ニコラス・コレギエート教会および敷地へようこそこの教会は毎日開いています通行する車両に注意してください子どもは常に保護者の監督下に置いてくださいごみを捨てないでくださいハトに餌を与えないでください飲酒および反社会的行動は禁止されています選任聖職者委員会の命による】建物のファサード(正面壁)には、尖頭アーチ(ゴシック・アーチ)の大きな窓が複数見られます。これは中世ゴシック建築の代表的な特徴で、教会建築では定番。窓枠には石造のトレーサリー(透かし模様)が施されており、繊細な印象を与えます。教会の南側を斜めから見上げて。尖頭アーチ型の高窓で、石造のトレーサリー(透かし模様)が特徴。ガラスには鉄の格子(リードケイム)が組まれており、ステンドグラス風の構造。「St. Nicholas' Collegiate Church(聖ニコラス・カレッジエイト教会)」 の公式案内板Church of IrelandAnglican / EpiscopalSt. Nicholas' Collegiate ChurchSUNDAY SERVICES:9:00AM HOLY COMMUNION11:00AM EUCHARIST (SUNG)(SEE SOUTH DOOR NOTICE BOARDS FOR DIARY)This Church is Open DailyVisitors most WelcomeRECTOR: VERY REV. LYNDA PEILOWTEL: 091 521914Website: www.stnicholas.ie」 【アイルランド聖公会(Church of Ireland)英国国教会 / エピスコパル教会聖ニコラス・カレッジエイト教会日曜礼拝:午前9時:聖餐式(Holy Communion)午前11時:聖餐式(歌付き)(Eucharist, Sung)※日程については南扉の掲示板をご覧ください当教会は毎日開いておりますご訪問の皆様を心より歓迎いたします主任司祭:リンダ・ピーロウ首席司祭電話:091 521914ウェブサイト:www.stnicholas.ie】「Church of IrelandAnglican/EpiscopalianSt. Nicholas’ Collegiate ChurchThis Church is open daily and Visitors are most welcomeWebsite: ウェブサイトhref="http://www.stnicholas.ie">www.stnicholas.ieCirca 1320 A.D.」 【アイルランド聖公会(Church of Ireland)英国国教会 / エピスコパル教会聖ニコラス・カレッジエイト教会この教会は毎日開かれており、訪問者の皆さまを心より歓迎しますウェブサイト:href="http://www.stnicholas.ie">www.stnicholas.ieおおよそ西暦1320年建立】早朝につき、教会の内部には入れなかったが、ステンドグラスの写真をネットから。キリストの生涯や聖書の場面、および象徴的な聖人や記号が色鮮やかに描かれていた。下部の5つの縦パネルでは、新約聖書の場面が描かれていた。左端:復活したキリストが現れる場面か、もしくは「よみがえりのラザロ」に言及する場面。左から2番目:足を洗う場面か、「マリアの油注ぎ(罪の女の悔い改め)」を描いている 可能性があります。中央:キリストが祈っている姿(おそらく「ゲッセマネの園」の祈り)。右から2番目:キリストが子どもたちと接する場面(「子どもをわたしのところに来させなさい」 マルコ10章14節)。右端:キリストが盲人の目を癒す奇跡か、もしくは群衆への教え。上部(ティンパヌム部分)中央最上段:キリストが玉座に座り、右手で祝福を与え、左手に書物(おそらく福音書)を 持っています。「栄光のキリスト(Christ in Majesty)」の典型的な表現。その左右には楽器を奏でる天使たちが配置され、天上の礼拝を象徴しています。下段(地上での奇跡・教えの場面)左から順に:1.幼子の祝福(Let the Children Come to Me): ・キリストが子どもを抱いて祝福している場面(マルコ10:14)。2.祈るキリストと弟子たち(ゲッセマネの園か): ・緑の服の人物がキリストに祈る様子は弟子ペテロや女性信者を表すか。3.癒しの奇跡: ・病人や目の見えない人を癒しているキリスト(マルコ10:46-52など)。4.最後の審判を連想させる場面(右下):・右側の人物は杖を持ち頭に布を巻いており、律法学者または預言者を示唆?Market Street・マーケット・ストリート側から見た「Saint Nicholas' Collegiate Church・英国国教会」「Lynch Memorial Window(リンチ記念窓)」。St. Nicholas’ Collegiate Church(聖ニコラス協同教会)の南側、Market Street に面した場所にありました。石造の壁だけが残された廃墟の一部で、この構造物全体が「Lynch's Memorial Window」として知られている。残された壁に、ゴシック様式の尖頭アーチの窓が取り付けられており、それが「メモリアル・ウィンドウ(記念窓)」である と。窓の周囲には、家族の紋章やレリーフ装飾が施されており、歴史的・芸術的価値があるのだと。1.二連の尖頭アーチ窓(Gothic style) ・石柱で区切られた細長い窓で、ゴシック建築の特徴です。 ・この窓の裏手が「息子が処刑された」という伝説の場所とされています。2.中央の石碑プレート ・プレートにはおそらく銘文が刻まれていますが、風化により読み取り困難です。 ・古い記録によれば、これは James Lynch FitzStephen(ジェームズ・リンチ・ フィッツスティーブン) にまつわる碑文だった可能性があります。3.頭蓋骨と交差骨(スカル&クロスボーン) ・これは死と正義の象徴で、中世・近世ヨーロッパで墓標や処刑台跡などにしばしば 使われた意匠です。 ・息子の処刑(あるいは伝説)を記念した厳粛な象徴として配置されたと考えられます。「Lynch Memorial Window(リンチ記念窓)」を正面から。セント・ニコラス教会(St. Nicholas' Collegiate Church)鐘楼(Bell Tower)をズームして。・建築様式: ・元はゴシック様式ですが、写真の塔部分は後年の補強・改築を経ており、やや要塞的な 外観となっています。 ・角のクレネレーション(胸壁)が特徴的で、まるで城塞の見張り塔のような印象を与えます。・屋根: ・急傾斜の銅板屋根で、典型的な中世の教会塔の形状(ピラミッド型)をしています。 ・緑青(ろくしょう)によって青緑色になっており、経年による銅の酸化作用の証です。・塔上部の窓: ・通風用のルーバー付き開口部(鐘音を外に響かせるため)があります。 ・時計も設置されており、地域社会の時刻標としても機能していたことがわかります。廻り込んで。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.07
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その39):Ashford Castle・アシュフォード城
「Ashford Castle Front Gate」から「Ashford Castle・アシュフォード城」の敷地内に入り広大な敷地を道なりに進むと、正面に「Ashford Castle・アシュフォード城」の建物が姿を現した。 手前の道の両脇はゴルフのミニコース?になっているようであった。アッシュフォード城 (Ashford Castle) は、何世紀にもわたって拡張され、メイヨー県とゴールウェイ県の境界のコングの近くで5つ星高級ホテルとなった中世の城であり、アイルランドにあるコリブ湖のほとりに建てられている。建設: 元は1228年、アンガロウ家(Anglo-Norman de Burgo family)によって建てられた 中世の城が起源。拡張・改築: 19世紀後半にギネス家(Guinness family)によって拡張・整備され、現在のような 壮麗な姿に。現在: 「レッド・カーネーション・ホテルズ(Red Carnation Hotels)」という高級ホテル グループが所有・運営。完全なラグジュアリー体験を提供する5つ星ホテル。正門の橋周辺まで歩いて行き、写真撮影することにする。城の裏側に広がる「Lough Corrib(コリブ湖)」沿いの遊歩道やGuinness Tower方面の散策ルートを利用することも可能なようであった。Cong Abbey(コング修道院)から続く森林トレイルもおすすめです と。Ashford Castle・アシュフォード城の上空からの写真をネットから。右奥に見えたのが、「Mrs Tea's on the Ashford Estate」。旬の食材、焼きたての菓子、温かい飲み物、パティオ、そして土産物等を用意した店。近づいて。店の入口。「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」。 土産物。正門の石橋に向かって歩く。アッシュフォード城は、正門の石橋(城門の手前にある橋)を渡った先が私有地になっており、基本的には宿泊者またはレストラン・アフタヌーンティーなどを予約したゲストのみが橋を渡って内部に入ることができるとのこと。一般の立ち入り制限について: 条件 橋を渡れるか 説明・宿泊予約がある ✅ 可能 ホテルゲストとしてフルアクセス可能・レストラン・ アフタヌーンティー等を予約 ✅ 可能 時間制限付きの立ち入りが許可される・観光目的のみ(予約なし) ❌ 原則不可 橋の手前のゲートで止められます・敷地周辺を散策 ✅ 一部可能 コング村側の湖畔や森(公道・遊歩道) は自由に散策可能石橋の手前からアッシュフォード城 (Ashford Castle) を。アッシュフォード城 (Ashford Castle) の塔の上にはアイルランド国旗がはためいていた。1. 中世の城塞風のデザイン ・13世紀に創建され、元々はアングロ・ノルマンのデ・バーク家が築いた防衛用の要塞でした。 ・厚い灰色の石造りの壁と高い塔、狭間(さま)付きの胸壁(防御用のギザギザした上部)が、 中世の風格を今に伝えています。2. ビクトリア朝の増築 ・19世紀後半、ギネス家(ビールで有名な家系)が大規模に改築。 ・ゴシック・リバイバル様式の要素を取り入れ、現在のようなロマンチックな外観に。 ・大きな窓、尖塔、時計塔などもこの時期の特徴です。3. 美しい湖畔の立地 ・アシュフォード城は**ロッホ・コリブ湖(Lough Corrib)**の湖畔に立ち、湖面に映る 城の姿が非常に美しいです。 ・湖を望むテラスや庭園も整備されており、建物の荘厳さと自然の静けさが融合しています。4. 入口の石橋と門塔 ・城の敷地にはアーチ型の石橋がかかっており、その橋を渡ると警備付きのゲートハウス(門塔) があります。 ・ゲートをくぐらないと本館の全景は見えません。前述のように、予約なしでは進入できません。アイルランド国旗をズームして。さらに。アイルランドの国旗は、緑、白、オレンジの縦三色旗です。緑色はカトリック教徒、オレンジ色はプロテスタント教徒を表し、白色は両者の平和と友情を表しています。アイルランドの国旗は、1922年にアイルランド自由国の国旗として採用され、1937年に新憲法で国旗として定められました。国旗の由来と意味:緑色:ケルトの伝統とカトリック教徒を表します。オレンジ色:プロテスタント教徒を表します。白色:カトリック教徒とプロテスタント教徒の平和と友情を表します。アイルランドの国旗は、異なる宗教間の調和と平和を象徴する、アイルランドのアイデンティティを象徴する重要な旗です と。五つ星ホテルの部屋をネットから。石橋を横から。・材質:石造り(切り石)・構造:7つのアーチからなる多連アーチ橋・用途:アシュフォード城の正門へと続く唯一の車道/歩道橋・建設年代:19世紀(城の拡張期)に現在の姿に整備されたと考えられます構造と特徴アーチ型: 水の流れを妨げず、重さを均等に分散するために最適な構造。石材 : 現地産の石灰岩を使用していると推定され、城と調和した灰色の外観。防衛性: 観光目的で設計されたわけではないが、橋の両端に小さな塔を配置し「城門風」に 演出されている。中世の城塞風の美観を意識した意匠です。修復歴 : 近年では観光施設としての維持管理のために補修されているが、橋の原型は 19世紀の拡張工事に基づくものです。7つのアーチからなる多連アーチ橋。橋の両端に小さな塔を配置し「城門風」に。入口には警備員の姿が。そして、アシュフォード城の石造りの門の前には、伝統的なアイルランドの衣装(黒のローブ、緑の帽子、白いソックス)を着たバグパイプ奏者の姿が。宿泊客の歓迎セレモニーや結婚式、イベントの一環として登場するのであろう。この写真の船は、アイルランド西部のコリブ湖(Lough Corrib)をクルーズする観光船 「ISLE OF INISHFREE(イニシュフリー島号)」。船体の側面にその名前が見えた。ズームして。クルーズ内容:・Lough Corrib(コリブ湖)を遊覧・美しい湖の景色や野鳥観察、歴史の紹介など・しばしばアシュフォード城近くから出発し、湖に浮かぶ島々(Inchagoill など)を巡る と。クルージング客の姿はなかったが、次の出発時間は?。そして、駐車場所に戻る。再び「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」の看板を。「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」。こちらもレストラン「Cullen's at the Cottage」。 植栽の中央にあった「ケルト十字(Celtic Cross)」。精巧に加工された花崗岩または石灰岩が使用されており、風化にも耐える重厚な造り。周囲には噴水が。ゴルフコース案内。小規模ながら高級感のある9ホールのコース と。宿泊客専用または予約制のプライベートコースであることが多いようだ。再び「MRS TEA’S BOUTIQUE & BAKERY ON THE ASHFORD ESTATE」を見る。そしてレンタカーに戻り、「アシュフォード・キャッスルST」を利用して帰路に。 敷地内にあった「St Mary's, Church of Ireland・英国国教会」が右手に現れた。・ネオ・ゴシック建築:尖塔(スパイア)と尖頭アーチの窓が特徴的で、19世紀に流行した ネオ・ゴシック様式。・尖塔の高さ:非常に高く、遠くからでも視認可能。・石造りの重厚感:アイルランド西部でよく見られる灰色の石材(おそらく地元産)。Cong Abbey・コング修道院の横を再び通過し、Cong Abbeyの見学時に駐めていた駐車場手前にも入口表示があった。一般観光客のメインエントランスとは別のサービスゲートもしくは関係者専用ゲートのようであったが。そして「Ashford Castle Front Gate」が右手に。先程、探し回って入った正門・メインゲートがこれ。 一時停止してもらって。・構造様式: 厚い灰色の石造りで、2つの塔とアーチ状の門からなる堂々たるゲート。 これは中世の城郭の防御門を模したゴシック・リバイバル様式。・門の上部には防御用の「マシコレーション(machicolation)」風の張り出しがあり、 まさに要塞のような外観。・中央の小さな紋章: アシュフォード城の旧家の紋章、あるいはギネス家時代の装飾の一部と思われます (19世紀、ギネス・ビールの創業者の一族が所有していました)。・門の奥には観光バスが見えたが、これは宿泊者やレストラン利用者を迎え入れる際に使用される 正式なエントランスであることが確認できたのであった。振り返って。そして3連泊のGALWAYのアパートに戻ったルート。R346~R334をひたすら走る。私は助手席でナビっていたが。この日は、部屋での夕食とすることとし、途中のスーパーマーケット・「DUNNES TERRYLAND HEADFORD ROAD」で4人で買い出し。そして部屋にて長い1日であった、この日の反省会を。生ハムはあっという間に無くなったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.06
コメント(0)
-
アイルランド・ロンドンへの旅(その68):Dublin市内散策(7/)
ああああああああああああああああああああああああああああ
2025.08.06
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その38):Cong Abbey(コング修道院)(2/2)
さらに、Cong川沿いの公園を散策する。自然素材(おそらく柳や何かの蔓)で作られた鳥のオブジェ。「Curlew – An Crotach“Hearing his voice, a god who …… the curlew would almost …… had made the … remake himself,… instantly want to be made …… as the thing he had made.”John Moriarty」 と。【「ダイシャクシギ ― アン・クロハ(アイルランド語で“Curlew”)その声を聞いた神は、ダイシャクシギの姿に心を奪われ、自ら創造したものによって自分を作り変え、ついにはその創造物そのものになりたいと願った。」― ジョン・モリアーティ】Cong川にかかる木橋を渡りながら、上流を見る。橋をわたる旅友。下流側。下流側にあった「Monks’ Fishing House(修道士の釣り小屋)」を橋の上から見る。移動して。入口に近づいて川の中央側をズーム。「Monk’s Fishing HouseWe owe our knowledge for this rare monument to an anonymous writer who visitedCong Abbey and its surroundings in 1855.Cong is unique in that the River Cong flows both above and below ground. This is due toits location on an esker ridge – a narrow, winding ridge formed by glacial meltwater streams – between Lough Mask and Lough Corrib.The fast-flowing River Cong is an ideal place to glimpse a salmon leaping or a herondive to bring a fish to the riverbank.The building before you, called the Monk’s Fishing House, is believed to have been constructed in the 15th or 16th century. The monks are thought to have sat inside, dry and sheltered, while fishing through an opening in the floor. A fireplace provided warmth in cold weather.Fish was a staple in the diet of a medieval monastery. It was an invaluable protein,particularly for the 110 days of the year when the eating of meat was forbidden. The Fishing House is built on piers at the confluence of a small stream and the River Cong, and it is part of the stone wall and arch which forms the boundary of the river terrace.A square hole in the floor allowed a net to be lowered into the water. The building isbelieved to have been connected by a line to a bell in the monastery kitchen to letthe cook know that there was fresh fish available.」 【修道士の釣り小屋この珍しい建造物に関する知識は、1855年にコング修道院とその周辺を訪れた匿名の旅行者の記録によって伝えられています。コングは、川が地上と地下の両方を流れるという、非常に珍しい地形を持っています。これは、ロッホ・マスク湖とロッホ・コリブ湖の間に位置するエスカー地形(氷河の融水によって形成された細長い丘)によるものです。急流のコン川では、跳ねるサケや、魚を捕えるサギの姿が見られることもあります。この前にある建物「修道士の釣り小屋」は、15~16世紀に建てられたと考えられています。修道士たちは、この小屋の中で、床に開けられた穴から釣りをしながら、雨風をしのいで座っていたとされています。小屋内には暖炉があり、寒い季節にも暖を取ることができました。魚は、中世の修道院の食事において重要なタンパク源でした。特に年間110日間の「肉の摂取が禁じられた日(斎日)」には、魚が欠かせない食材でした。この釣り小屋は、小さな支流とコング川の合流地点にある石造りの土台の上に建てられており、川沿いのテラスを囲む石の壁とアーチの一部でもあります。床に開けられた四角い穴から網を下ろして川に垂らすことができました。また、修道院の厨房にはベルがつながっていて、魚が獲れたら鳴らして知らせたとも言われています。】「Monks’ Fishing House(修道士の釣り小屋)」の絵に近づいて。再びLough Corrib・コリブ湖に繋がる下流側を。引き返して、「Cong Abbey(コング修道院)」の墓地まで戻る。背景には石造りの小礼拝堂または納骨堂?が見え、墓石には典型的なケルト十字(Celtic Cross)が数多く並んでいた。中央奥に見えた三連アーチの窓はCong Abbeyの教会堂の東壁(祭壇側)。「Cong Dry Canal(コング・ドライ・キャナル/コングの乾いた運河)」案内板。「The Cong Dry CanalThe Cong Canal was begun in the 1840s in an attempt to link Lough Mask and Lough Corrib by a navigable waterway.However, because of the porous nature of the limestone bedrock, water leaked away, and the canal was never completed.Today the canal is dry and has become a beautiful woodland walk with a wide variety offlora and fauna.」 【コングの乾いた運河(Cong Dry Canal)コング運河は、ラフ・マスク湖(Lough Mask)とラフ・コリブ湖(Lough Corrib)を航行可能な水路で結ぶために、1840年代に建設が始められました。しかし、石灰岩の地盤が多孔質であったため、水が漏れ出し、運河は完成しませんでした。現在ではこの運河跡は美しい森林の散策路となっており、多種多様な植物や動物の生息地となっています。】「For five years both skilled and unskilled workers were paid 4p per day to blast their way through 4 miles of solid limestone rock.Because of the porous nature of the limestone this was to become an engineering disaster because the bed of the canal proved too polous and was unable to retain water.The government would not provide money to concrete the canal as by this time canals were going out of fashion and railway were in operation in many parts of Ireland.」 【5年間にわたり、熟練工も未熟練工も、1日あたりわずか4ペンスの賃金で、4マイル(約6.4km)に及ぶ堅固な石灰岩を爆破しながら掘り進みました。しかし、石灰岩が多孔質だったため、これはやがて技術的な大失敗へとつながります。というのも、運河の底があまりにも穴だらけで、水を保持することができなかったのです。さらに悪いことに、当時すでに運河は時代遅れとなりつつあり、アイルランド各地では鉄道が普及し始めていたため、政府はこの運河をコンクリートで補修するための資金を出そうとはしませんでした。】「In April 1854 the commissioners directed that work on the navigational aspect of the canal be discontinued;drainage work was to continue to enable the level of lough mask to be regulated. This artificial waterway so elaborately finished with sluice-gates, substantial locks of cut stone and arched bridges has become known as the dry canal.」 【1854年4月、委員会(※公共事業委員会)は、運河の航行目的に関する工事を中止するよう命じました。ただし、ラフ・マスク湖の水位を調整できるようにするための排水工事は続けられることになりました。この人工の水路は、水門(スルースゲート)、切石で造られた頑丈な閘門(ロック)、アーチ型の橋などが精巧に仕上げられていたにもかかわらず、「乾いた運河(ドライ・キャナル)」として知られるようになったのです。】「The locksThe main works include three locks two stone bridges (one at Cong and one at Drumsheel) and aqueduct between locks 2 and 3. The purpose of th locks was to lift the boats up orlower them down as Lough Mask is about 36ft higher than Lough Corrib.The firstt lockwhich is located closest to Ashford castte and is sometimes referred to as the Strandfordlock.The lock now has a roof and is used as a boathouse.The second lock was referred to the Cong lock and is located right in the village. This lock was never completed and there is no trace of it today as Lord Ardilaun bought the land in 1876 and closed the section from the first to the second lock.The building of the canal meant the direction of the road from Cong to Ballinrobe had to be changed and a new bridge had to be built over this road for the canal.」【閘門主要な構造物には、3つの閘門(ロック)、2つの石橋(1つはコング、もう1つはドラムシール)、および第2と第3のロックの間にある水路橋(アクアダクト)が含まれています。ラフ・マスク湖はラフ・コリブ湖より約36フィート(約11メートル)高いため、船を昇降させるためにロック(閘門)が設置されました。第1のロックはアシュフォード城に最も近い場所にあり、ストランドフォード・ロック(Strandford Lock)とも呼ばれることがあります。このロックには現在屋根がかけられており、ボートハウスとして使用されています。第2のロックは「コング・ロック(Cong Lock)」と呼ばれ、村の中心部に位置していました。このロックは完成することはなく、現在では跡形も残っていません。というのも、1876年にアーディローン卿(Lord Ardilaun)がその土地を買い取り、第1と第2のロックの区間を閉鎖したためです。この運河の建設により、コングからバリンローブへ向かう道路の方向が変更され、その道路の上に運河を通すための新しい橋を建設する必要が生じました。】「The aqueduct was built to allow the river form from the rising water below Cong toflow under the new canal.This all that remains today of the aqueduct.The third lock is located close to the Cong pubiic car park,on the Galway road and was completed except for the gates.」 【このアクアダクト(水路橋)は、コングの下から湧き出す水が「フォーム川(River Form)」となって流れるために、その川が新たに建設された運河の下を通れるように造られたものでした。今日では、このアクアダクトの名残はこの部分だけが残っています。第3のロック(閘門)は、ゴールウェイ方面道路沿い、コングの公共駐車場のすぐ近くに位置しており、ゲート(門扉)を除けば完成していました。】「Dry Canal Loop Walk. 40minsStarting from the Cong public car park, and walking North,down to the old lock gate, it ispossible to walk the old canal bed to the bridge at Drumsheel,Walk the length of the canal until you reach large cut stone bridge over thead.After walking under the Drumsheel bridge there is stone steps on your right totake youup the road.」【 ドライ・キャナル・ループ・ウォーク(所要時間:約40分)コングの公共駐車場からスタートし、北方向へ歩いていくと、旧ロックゲート(閘門)に下りる道があります。そこから古い運河の底(運河跡)をたどって、ドラムシール(Drumsheel)の橋まで歩くことができます。運河の全長を歩いていくと、頭上に切石で造られた大きな橋が見えてきます。このドラムシール橋の下をくぐったあと、右手に石段があり、そこを登ると車道(道路)に出ることができます。】「Turn back towards the bridge and cross it, returning back in to Cong village in a loop walk. You will arrive down School Hill to the duck pond at 0 ' Connor's supermarket.permarket.Please do not litter Cong and LEAVE NO TRACE on your walks.Thankyou、Cong Village Tidy Towns Committee」【橋の方へ引き返して渡り、ループ状にコング村へ戻ってください。やがてスクール・ヒル(School Hill)を下って、オコナー・スーパーマーケット(O'Connor's Supermarket)前のカモの池に到着します。コングの自然を汚さず、「痕跡を残さない行動(LEAVE NO TRACE)」を心がけてください。ご協力ありがとうございます。コング村 環境美化委員会(Cong Village Tidy Towns Committee)】 この案内板は「Trailhead 31 – Cong, Co. Mayo(トレイルヘッド31 – メイヨー県コング村)」のナショナル・ループ・ウォーク(National Looped Walk)。・Loop 131a:Nature Loop・Loop 131b:igeon Hole Loop「 The Guinness Tower(or locally known as Leonard's Tower and also the Keeper's Tower)Built in 1864 by Benjamin Lee GuinnessIt was built in 1864 by Benjamin Lee Guinness so he could view all of his estate for thetop of the tower.There was once great views from the tower, Lough Corrib Lough Mask and the partryMountains.」【ギネス塔(地元では「レナードの塔」または「番人の塔」とも呼ばれる)1864年、ベンジャミン・リー・ギネスによって建設されたこの塔は、ベンジャミン・リー・ギネスが自身の領地全体を見渡せるように、1864年に建てられました。かつては、塔の上からコリブ湖、マスク湖、そしてパートリー山脈を一望できる絶景が広がっていました。】 「Today with some of the trees over 60 feet tall fhey now reach higher than the toweritself.Apart from it's usefulness as a viewing tower for Ashford castle's gamekeeper, it is nothing more than a rich man's folly,but the stonework is incredibly good.The tower is unusual in that there is practically nothing inside except a stone spiralstairway and small octagonal room below the loof. There are 83 steps in the spiralstairway up to the rooftop of Cong woods.」【現在では、高さ60フィート(約18メートル)を超える木々がいくつもあり、それらはすでに塔の高さを超えています。アシュフォード城の狩猟管理人が眺望に利用する以外は、この塔は裕福な男の「気まぐれな建築物(フォリー)」にすぎませんが、石細工の仕上がりは驚くほど見事です。この塔の内部は非常に珍しく、石造りの螺旋階段と屋根の下にある小さな八角形の部屋しかほとんど存在しません。コンウッズの頂上にある屋上まで、螺旋階段には83段の階段があります。】 「Continue straight on past this green gate on your left and follow walkway in to thewood.You will after 5 minutes walking passTeach Aille Cave on your right. Keep walkingstraight and follow pathway.The pathway soon starts to turn right,at this point you will see a small pass on yourleft leading to the GuinnessTower.Remember to mind the little children on the stairway up and also to leave no litter in our woods on your walk.Leave no Trace,Thank you.」 【左手にある緑の門を通り過ぎ、そのまま真っすぐ小道に沿って森の中へ進んでください。約5分ほど歩くと、右手に「ティーチ・アイル洞窟(Teach Aille Cave)」が見えてきます。そのまま道なりにまっすぐ進みましょう。まもなく道は右にカーブし始めますが、その地点で左側に小道があり、それが「ギネス・タワー(Guinness Tower)」へと続いています。タワーの階段では、小さなお子様に十分ご注意いただき、また、森の中ではゴミを絶対に捨てないようお願いいたします。「痕跡を残さない(Leave no Trace)」を守りましょう。ありがとうございました。】「The Heritage of CongWelcome to Cong or Cunga Feichin — the narrow isthmus of St. Fechin.Cong and the area around the village is rich in historical sites spanning over 5,500 years.Looking around you, there is the Abbey which dates from the 12th century, the oldChurch of Ireland which originally dates from the 18th century, and the Court House which dates from 1867.Evidence of early settlement in the local area is still visible. Dating from around 3500 BC are the Court Tombs at Killimor and Toberbiroge. From the later Neolithic and earlyBronze Age are the Hilltop Cairns at Ballymagibbon and the Glebe Stone Circles at Nymphsfield. Evidence of settlement during the later Bronze Age and Iron Age can beseen in the Crannogs at Lisloughrey and burial sites at Aghalahard.From the 5th century onwards the local area became an important Christian centre.Early Christian structures dating from this time can be found on the island of Inchagoillin Lough Corrib. The Abbey was originally founded in the 7th century although most ofthe buildings that can be seen today date from the 13th century to the 16th century. Ruaidri Ua Conchobair — the last High King of Ireland — spent the last years of his lifeat the Abbey and died here in 1198. The Abbey was also home to important Irish artefacts like the Cross of Cong, which today can be seen in the National Museum ofIreland in Dublin.The Abbey was suppressed in 1542, but Cong remained an important strategic locationand was garrisoned by Sir Richard Bingham in the late 16th century. The ruins of castles dating from the 15th and 16th century can be found at Aghalahard and Ballykine between Cong and Clonbur.The ruins and caves became the focus of interest for many visitors to the West of Irelandin the 19th century, and the filming of “The Quiet Man” in the village in 1951 ensuredthat the village continues to attract visitors from around the world in the 21st century.」 「Hidden Cong」 The Abbey GraveyardThe grounds and interior of the Abbey have been the final resting place of the people ofCong and its neighbourhood for many centuries. Some gravestone memorials datingback to the early eighteenth century can still be deciphered. For example, in the centreof the chancel, on your left as you enter through the archway, is a beautifully carved slab stone commemorating James Lynch, Abbot of Cong, who died in 1703. Close by, part of a family crest — a right-angled arm with the hand holding a cross — identifies the gravestone of members of the McDonnell family of Ahalard Castle.George McNamara, a legendary local "Robin Hood" character who died in 1760, was buried close to the east-facing chancel window, while members of his daughter’s family, the Jenings of Fountainhill, lie close to the sedilia — their name just legible still. In a small annexe next to the nearby doorway lies the gravestone of Thomas Bermingham of Rosshill, who died on 23 December 1705 aged seven. He was a grandson of John Browne, who founded thetown of Westport.A short distance away, diagonally opposite the chancel window, is a large Celtic crossmarking the grave of Michael O’Brien, killed on the Partry Mountains during the War of Independence. His gravestone inscription is in the Irish language. Translated it reads as follows:“In fond and proud remembrance of the brave and noble freedom fighter, Michael O’Brien,volunteer of the West Mayo Brigade of the Irish Republican Army.He willingly and bravely gave up his life in the heat of battlefor the green sod of his country, fighting against the Englishon the slopes of Tourmakeady on the 3rd of May 1921 at the age of 22.God be with you, true Irish hero, you were never overcome and you did not yield in the hour of need.”His mother erected this monument.A white marble plaque, on the high wall in the lower part of the graveyard, remembersMary Burke, who for fifty years worked at Moytura House, the home of Sir William Wilde, father of Oscar. Dr. Edward Murphy, who served the medical needs of the people of Cong from 1925 to 1954, rests with his wife in a grave in the next section of the graveyard— as do many others who lived and worshipped in this small village over the years.Explore their epitaphs.Stained Glass Window in Saint Mary of the Rosary Roman Catholic Church, CongThe light stained glass window of native Irish Art is situated behind the altar. The window contains a central figure of Christ the King. Insets illustrate events in the lifeof the Holy Family. The window was designed by the Irish stained glass artist Harry Clarke.In 1931 it was installed in the church which stood on the site of the present church.When the building of the present church was completed in 1973 the Harry Clarke window was re-erected behind the altar.Harry Clarke, Ireland's most famous stained glass artist, was born in Dublin in 1889. His father established a decorating business which included a stained glass division. Harry left school at the age of 14 and became apprenticed to his father. He studied stained glass at Dublin Metropolitan School of Art and won gold medals at National Competitions for his stained glass panels and was awarded a scholarship. Following this he toured Europe gaining inspiration for his work while visiting medieval cathedrals and churches.After the death of his father, Harry continued to work in the family business with his brother Walter. Following the sudden death of Walter, the decorating business terminatedin 1930. The business was renamed Harry Clarke Stained Glass Studios Ltd.Harry had suffered from a “weak chest” for most of his life. He was diagnosed with tuberculosis in 1929 and travelled to a sanatorium in Davos on two occasions for treatment without improvement in his condition. He left Davos planning to return to Dublin in 1931 but passed away in his sleep in Switzerland, aged 41 years. He was laid to restin Switzerland.Guinness SeatThis circular stone seat by the entrance of Cong Abbey was put in place on the orders of Sir Benjamin Lee Guinness, Irish brewer and philanthropist and one time Lord Mayor of Dublin, at the site of the old market square in Cong.It is described simply as a rest in texts of the time and was originally shaded by trees.The Rising of the WatersCong is situated on an isthmus between Lough Mask and Lough Corrib.Streams flow underground from the Mask to the Corrib and rise again in Cong in what is known locally as “The Rising of the Waters.”The main risings are Poll Tuathail (Polltoothil), Poll an Chuairteil (Pollacuarleale), Poll Leibin, and Corr na Buinnighe (Cornabany).To view these wonders of nature, go to the bridge at the northern end of the village on the road to Clonbur.On the western side of the bridge (i.e. on your left if facing away from the village), you can see a mild disturbance in the water which marks Poll Tuathail, also referred toas The Pool of the Turning Waters or The Northern Pool.If you look further west, closer to the old sawmill (now the Salmon Hatchery), you will notice the more turbulent Poll an Chuairteil, also referred to as The Whirlpool.The waters that rise from here flow into what is now called Cong River, which then joins Lough Corrib near Ashford Castle.To the right of the bridge, just a short stroll down the path beside the garage, Poll Leibin is a very significant rising.Its waters divide into two streams that encircle the village and join Cong River south of the Abbey.They are supplemented with a major flow from the spring at Corr na Buinnighe(The Round Hill of the Oozing Water).Industry and Commerce in CongIt is difficult to imagine small villages like Cong being centres of industry and commerce, but before the industrialisation of the 19th century, industry and commerce were located close to markets and energy.Because Cong is located on an island surrounded by fast-flowing rivers, it soon becamethe site for water-powered mills.The first mill is mentioned in a grant of lands in 1568.By the late 18th century, two grain mills were in operation at The Rising of the Waters.By the mid-19th century, Cong boasted four millsーtwo Grain Mills,a Tuck Mill (forprocessing wool) and a Saw Mill.The last mill in the village closed in the 20th century.To the east of the village is the site of another industrial development — the dry canal.Work on the canal began in 1848 and was halted before completion in 1854.Efforts to regulate the levels of Lough Mask and ensure power to the mills continued until 1856.The canal workings — including locks, bridges, and an aqueduct — can still be seen around the entrance to the car park on the Galway road.The right to hold a market in Cong has existed since the beginning of the 17th century.Traditionally, Cong also held a fair day on the 1st of August each year.By the 19th century, fairs were also held at Funshinogh in May and September.Cong CavesThe geology of Cong is mainly limestone, and a series of underground rivers flow through this limestone bedrock.Caves have formed as the waters dissolved the limestone beneath, and subsequently the roofs of these caves collapsed to expose them to us.The caves are a natural habitat for a wide variety of fauna in the area, especially bats.There are many local legends associated with the caves around Cong.The Pigeon HoleThe Pigeon Hole (Poll na gColum) cave is the most famous cave in Cong and is easily accessible from the village by walking through the wood by the Abbey or by car out the Clonbur Road.It got its name from pigeons nesting in the ivy growing on the walls of the cave.The deep cavern was made accessible by the construction of 61 stone steps descending to the underground passage.Water flows through the cave on its underground way to Lough Corrib, though in summer it can dry up.The local legend of the “Fairy Trout” or “White Trout” originates from this cave,where it isI thought that a pair of trout living in the cave were actually young tragic lovers fromthe area.One of them, a white trout with gridiron burn marks on her side, was caught byan English soldier caught her to trying to dismiss the legend that the pair was inseparable and proceeded to cook her.Upon being left on the hot gridiron, the trout turned into a grief stricken beautiful young maiden begging to be returned to the cave.Teach AilleTeach-Aille Cave, meaning “House of the Cliff”, is found in Cong Wood near the Abbey.It is a fine example of a natural grotto.From the wide entrance, steps can be seen downinto the water-filled chamber, where it is thought that the monks from the Abbey tookadvantage of the cool freshness of the water as their drinking supply.Kelly’s Cave is situated on the left after the national school on the Galway Road from the village.It is easily accessible by a pathway from a stile in the wall.The cave is partnatural and part man-made.The entrance has been built up to resemble a souterrain.Five steps lead to the ground floor.The cave contains two rectangular compartments, and at the end of the cave four steps lead down to a water source.A hole in the roofnear the end of the cave acts as a natural skylight.Kelly is thought to have been an outlaw who used the cave to hide from the authorities,or in other stories, a fugitive who used the cave as a place of refuge after the 1798 rebellion.」【コングの遺産コングへようこそ。 アイルランド語では Cunga Feichin — 聖フェイキンの「狭い地峡」と呼ばれます。コングおよびその周辺地域には、5,500年以上にわたる歴史的遺跡が数多く存在します。周囲を見渡せば、12世紀に築かれた修道院、18世紀にさかのぼるアイルランド国教会の古い教会、そして1867年建造の裁判所などがあります。この地域には、紀元前3500年ごろのものとされるキリモーやトバーブリッジのコート・トゥーム(墓)が現存し、定住の痕跡が見られます。さらに、後期新石器時代および初期青銅器時代のものとされるバリーマギボンの丘上ケルン(石塚)やニンフスフィールドのストーンサークルも残っています。後期青銅器時代や鉄器時代の定住の証拠は、リスラフリーのクラノグ(人工島)やアガラハードの埋葬地に見ることができます。5世紀以降、この地域はキリスト教の重要な中心地となりました。この時期の初期キリスト教建築は、ロッホ・コリブ湖内のインチャゴイル島に今も残っています。コング修道院は7世紀に創設されたと伝えられますが、現在見られる建物の大部分は13~16世紀にかけてのものです。アイルランド最後の上王ルアドリ・ウア・コンホバールは晩年をこの修道院で過ごし、1198年にここで亡くなりました。修道院はまた、「コングの十字架(Cross of Cong)」のようなアイルランドの重要な聖遺物の保管場所でもありました。十字架は現在、ダブリンの国立博物館に所蔵されています。修道院は1542年に解散されましたが、コングは戦略的に重要な場所として存続し、16世紀後半にはリチャード・ビンガム卿によって駐屯地とされました。15~16世紀に築かれた城の遺構が、コングとクロンバーの間にあるアガラハードとバリキーンに今も残っています。これらの廃墟や洞窟は、19世紀には西アイルランドを訪れる観光客の関心を集めました。そして1951年に映画『静かなる男(The Quiet Man)』がこの村で撮影されたことで、21世紀に入っても世界中から観光客を惹きつけ続けています。隠されたコングコング修道院墓地 修道院の敷地および内部は、長年にわたってコングとその周辺地域の人々の終の住処となってきました。墓石の中には、18世紀初頭にさかのぼるものもあり、今なお読み取ることができます。たとえば、内陣(祭壇部)の中央、アーチをくぐって左側には、美しく彫られた石板があり、1703年に亡くなったコング修道院長ジェームズ・リンチを記念しています。その近くには、家紋の一部とみられる「十字を握った右腕」の彫刻があり、アハラード城のマクドネル家の墓石であることが示されています。1760年に亡くなった伝説の「ロビン・フッド」的存在であった地元のジョージ・マクナマラは、東向きの内陣窓の近くに埋葬されており、彼の娘の家族であるジェニングス家(ファウンテンヒル出身)は、セディリア(礼拝者用座席)のそばに葬られています。その名はかろうじて判別可能です。近くの小さな別室には、1705年12月23日に7歳で亡くなったロスヒルのトーマス・バーミンガムの墓石があります。彼は、ウエストポートの町を創設したジョン・ブラウンの孫にあたります。少し離れた場所、内陣窓の斜め向かいには、独立戦争中にパートリー山地で戦死したマイケル・オブライエンの墓を示す大きなケルト十字が建っています。墓碑銘はアイルランド語で書かれており、訳文は次のとおりです:「勇敢で高潔な自由の戦士マイケル・オブライエンを、誇りと敬愛を込めて追悼する。彼はアイルランド共和国軍西メイヨー旅団の志願兵であった。彼は喜んで、そして勇敢に、自国の緑の大地のために戦い、1921年5月3日、トゥアマケイディの山腹で22歳の若さで命を捧げた。真のアイルランドの英雄よ、あなたは決して屈せず、緊急の時にも信念を貫いた。神があなたと共にありますように。」※この記念碑は彼の母親によって建てられました。墓地の下部、高い石垣には、白い大理石のプレートがあります。そこには、サー・ウィリアム・ワイルド(オスカー・ワイルドの父)の邸宅「モイチュラ・ハウス」で50年間勤務したメアリー・バークが記念されています。また、1925年から1954年までコングの人々の医療を担ったエドワード・マーフィー医師は、妻とともにその隣の区画に眠っています。小さな村で信仰とともに生きた多くの人々が、そこに埋葬されています。彼らの墓碑銘をぜひ辿ってみてください。コングのロザリオ聖マリア・カトリック教会にあるステンドグラスアイルランド独自の芸術による明るい色調のステンドグラスが、教会の祭壇の背後に設置されています。この窓には「キリスト王」の中央像が描かれており、周囲の小窓には聖家族の生涯に関する場面が描かれています。この作品は、アイルランドのステンドグラス作家ハリー・クラークによってデザインされました。1931年、このステンドグラスは、現在の教会が建てられる前の教会に設置されました。1973年に現在の教会が完成した際、このハリー・クラークのステンドグラスは祭壇の背後に再設置されました。ハリー・クラークは、アイルランドで最も有名なステンドグラス作家であり、1889年にダブリンで生まれました。父親は装飾業を営んでおり、その中にステンドグラス部門もありました。ハリーは14歳で学校を中退し、父親の元で見習いとなりました。彼はダブリン美術学校でステンドグラスを学び、全国コンクールで金賞を受賞し、奨学金も得ました。その後、ヨーロッパ中を旅して中世の大聖堂や教会を訪れ、創作のインスピレーションを得ました。父親の死後、ハリーは兄のウォルターとともに家業を継ぎました。しかし、1930年にウォルターが急逝したことで、装飾業は終了し、会社は「ハリー・クラーク・ステンドグラス・スタジオ株式会社」として再出発します。ハリーは長年「胸の弱さ(=呼吸器系疾患)」に苦しんでおり、1929年には結核と診断されました。彼は2度にわたりスイス・ダボスの療養所で治療を受けましたが、病状は改善しませんでした。1931年にダブリンへの帰国を計画していた矢先、スイスで眠るように亡くなりました。享年41歳。彼はその地に埋葬されました。このステンドグラス作品は、ハリー・クラークの卓越した芸術性と、アイルランドの信仰の象徴として、現在も教会を訪れる多くの人々を魅了し続けています。ギネス・シートこの円形の石のベンチは、コング修道院の入口付近にあり、かつての旧市場広場の跡地に設置されました。設置を命じたのは、アイルランドの醸造家で慈善家、またかつてのダブリン市長であったサー・ベンジャミン・リー・ギネスです。当時の記録では、このベンチは単に「休憩所(rest)」として記されており、もとは木陰に覆われていたとされています。水が湧き上がる場所コング村は、ロッホ・マスク湖とロッホ・コリブ湖の間の地峡(isthmus)に位置しています。水流は地下を通ってマスク湖からコリブ湖へと流れ、その途中、コング村の地下から湧き上がる現象があり、地元ではこれを「ザ・ライジング・オブ・ザ・ウォーターズ(水の湧出地)」と呼んでいます。主要な湧水地点には以下があります:ポル・トゥアハル(Poll Tuathail)、ポル・アン・クアルテイル(Poll an Chuairteil)、ポル・リービン(Poll Leibin)、コール・ナ・ブインニエ(Corr na Buinnighe)この自然現象を観察するには、村の北端、クロンバー方面へ向かう橋まで行ってみてください。橋の西側(村の外向きに立ったとき左側)には、水面のわずかな揺らぎがあり、これが「ポル・トゥアハル(転じる水の池/北の池)」と呼ばれる湧き出し口です。さらに西側、旧製材所(現在のサーモン・ハッチャリー:鮭の孵化場)付近には、より激しい湧出である「ポル・アン・クアルテイル(渦の池)」があります。ここから湧いた水はコング川に流れ込み、やがてアッシュフォード城付近でロッホ・コリブに合流します。橋の右手、小道を少し下ると「ポル・リービン」と呼ばれる重要な湧水があります。この水流は村を取り囲む2本の川に分かれ、修道院の南側でコング川に合流します。さらに、コール・ナ・ブインニエ(「にじみ出る水の丘」)の湧水も加わっています。コング村における産業と商業今日では想像しにくいですが、コングのような小さな村も、19世紀の産業革命以前には産業と商業の中心地の一つでした。当時の産業や商業は、市場やエネルギー源の近くに立地していたのです。コング村は急流に囲まれた島のような地形であったため、まもなく水力を利用した製粉所(ミル)の適地となりました。最初の水車小屋の記録は1568年に土地の文書に登場します。18世紀末には2つの穀物製粉所が、「ザ・ライジング・オブ・ザ・ウォーターズ」の地点で稼働していました。19世紀半ばまでには、村には4つの製粉施設が存在しました:穀物製粉所 ×2、羊毛処理用のタック・ミル、製材所村内の最後の製粉所は20世紀に閉鎖されました。村の東側には、別の産業遺構である「ドライ・キャナル(乾いた運河)」があります。この運河の建設は1848年に開始されましたが、1854年に未完成のまま中止されました。その後もロッホ・マスク湖の水位調整や、製粉所への水力供給を目的とした整備が1856年まで続きました。現在でも、閘門(こうもん)や橋、水道橋などの構造物は、ゴールウェイ道路沿いの駐車場入口付近で見ることができます。また、コングでの市場開催の権利は、17世紀初頭から存在しており、伝統的に8月1日には大規模な定期市(フェア)が開催されてきました。19世紀には、5月と9月にフンシノー(Funshinogh)でも市が開かれるようになりました。コングの洞窟コング村の地質は主に石灰岩で構成されており、地下河川がこの石灰岩層を貫いて流れています。長年にわたって地下水が石灰岩を溶かしたことで、洞窟が形成され、やがてその天井部分が崩れて地表に現れました。これらの洞窟は、特にコウモリをはじめとするさまざまな野生動物の生息地にもなっています。また、これらの洞窟には多くの地元伝承が結びついています。ピジョン・ホール洞窟この「ピジョン・ホール(ハトの穴)」は、コングで最も有名な洞窟であり、村の修道院裏の森を歩くか、クロンバー方面への道路を車で進むと簡単にアクセスできます。洞窟の名は、壁のツタに巣を作っていたハトたちに由来しています。内部へは、地下への61段の石段を降りて入ることができます。この洞窟を通って流れる水は、地下でロッホ・コリブ湖へと続いています。ただし夏季には水が干上がることもあります。この洞窟には、「妖精のマス(Fairy Trout)」または「白いマス(White Trout)」と呼ばれる伝説の魚が住んでいたという話があります。地元の伝説によれば、この洞窟に住んでいた2匹のマスは、実は悲劇的な恋に落ちた若者の化身であり、そのうちの1匹は、白いマスで体に焼き網の跡があるとされていました。ある時、この白いマスをイギリス兵が捕らえ、その伝説を迷信として無視し、焼いて食べようとしました。ところが、熱い焼き網の上に置かれると、マスは突然、悲しみに暮れる美しい少女の姿に変わり、「元の洞窟へ帰らせて」と懇願したといいます。ティーチ・アーリェティーチ・アーリェ洞窟(Teach-Aille Cave)は、「崖の家」という意味の名を持ち、修道院の近くにあるコングの森(Cong Wood)の中に位置しています。この洞窟は、自然に形成された石室(グロット)の優れた一例です。広い入り口からは、水をたたえた地下室へと続く石段が見えます。ここでは、かつて修道院の僧たちが、その冷たく澄んだ水を飲料水として利用していたと考えられています。ケリーの洞窟ケリーの洞窟は、村からゴールウェイ通り(Galway Road)を進み、国立学校を過ぎて左手側にあります。壁に設けられた小門(スタイル)から続く小道を通って簡単にアクセスできます。この洞窟は、自然にできた部分と人工的に掘られた部分が混在しています。入り口は、スーターリン(地下通路)のような構造に造られています。中へは5段の階段を下って地面に降ります。内部には長方形の区画が2つあり、洞窟の奥には水源に続く4段の階段があります。また、洞窟の奥の天井には自然光が差し込む穴があり、天窓(スカイライト)として機能しています。伝承によると、ケリーという人物はこの洞窟を官憲から逃れるための隠れ家として使っていた無法者であった、あるいは、1798年の反乱の後に逃亡者としてここに潜んだとも言われています。】「Toulist OfficeCong(コング)村の観光案内所として使われている、旧裁判所(Courthouse)の建物。1863年建設の裁判所で、現在は観光インフォメーションセンターとして再利用されています。窓の形状や石造りのゴシック風デザインは、当時の公的建築物に多く見られたスタイル。「Things to See & Do Nearby(近隣の見どころ・体験スポット)」。アイルランド西部・Cong(コング)周辺の観光地を紹介したもの。01.University Of Galway ゴールウェイ大学(見学可能)02.Galway Distillery ゴールウェイ・ウイスキー蒸溜所03.Micil Distillery ミキル蒸溜所(クラフトウイスキー/ポチーン)04.Galway City Museum ゴールウェイ市立博物館05.St. Nicholas Collegiate Church 聖ニコラス教会(アイルランド最古の教区教会)06.Spanish Arch スペイン門(中世の海港防御門)07.Galway Market ゴールウェイ市場(ローカルフード・クラフト)08.Aughnanure Castle アフナニュア城(16世紀の塔城)09.Lough Mask Distillery ロッホ・マスク蒸溜所(クラフトスピリッツ)10.Glenowla Mines & Family Farm Experience グレノーラ鉱山とファーム体験11.Galway Cathedral ゴールウェイ大聖堂12.University Of Galway ゴールウェイ大学(見学可能)13.Galway Distillery ゴールウェイ・ウイスキー蒸溜所14.Micil Distillery ミキル蒸溜所(クラフトウイスキー/ポチーン)15.Galway City Museum ゴールウェイ市立博物館16.St. Nicholas Collegiate Church 聖ニコラス教会(アイルランド最古の教区教会)17.Spanish Arch スペイン門(中世の海港防御門)18.Galway Market ゴールウェイ市場(ローカルフード・クラフト)19.Aughnanure Castle アフナニュア城(16世紀の塔城)20.Lough Mask Distillery ロッホ・マスク蒸溜所(クラフトスピリッツ)21.Glenowla Mines & Family Farm Experience グレノーラ鉱山とファーム体験「Joyce Country & Western Lakes Geopark Project(ジョイス・カントリーと西湖のジオパーク・プロジェクト)」に関する案内パネル。UNESCO Global Geoparks(ユネスコ世界ジオパーク) ・ユネスコ世界ジオパーク(UNESCO Global Geopark, UGGp)**とは、国際的に重要な 地質遺産を持ち、それを教育・保護・持続可能な観光と地域経済に活かす地域です。・現在世界に177のUGGpがあり、46カ国にまたがっています。・このプロジェクトは、アイルランド西部(メイヨー県・ゴールウェイ県)のジョイス・ カントリーと西 部湖沼地 域を対象としています。Cong and its surroundings(コングとその周辺)・コングは、火山活動と氷河作用により形成された特異な地形にあります。・古代から人々がこの土地で暮らし、**Cong Abbey(修道院)や地下水のネットワーク (The Rising & Sinking Rivers)**などが地形と深く関わっています。・アシュフォード城(Ashford Castle)やラフ・コリブ(Lough Corrib)、ラフ・マスク (Lough Mask)なども近隣の見どころです。Our Geodiversity・この地域には、火山岩、堆積岩、変成岩、石灰岩など様々な地質が存在し、地球の形成史を 理解するのに貴重です。・氷河の跡やカルスト地形(溶食地形)も多く、これが湖や洞窟、地下水脈などの形成に 影響しています。Our Biodiversity・ジオパーク内では、自然と人間の営みが調和しており、森林、湖、湿原、牧草地などが 生物多様性を支えています。・動植物の保護にも取り組みが進められており、ヨーロッパレベルで重要な種の生息地も 存在します。Archaeology and history of Cong・コングは古代からの人類の活動の証が豊富に残る地域です。・有名な修道士聖フィンニアンにより建てられた修道院跡、バイキング時代の痕跡、 アングロ・ノルマン様式の石橋などが見られます。・地元の生活や土地利用の歴史を学ぶ上でも重要な場所です。「Toulist Office」を出て再び「Cong Abbey・コング修道院」の遺跡を見る。R345の道路の中央にあった「Cross of Cong」。 この石碑の碑文は古いゲール語(アイルランド語)で刻まれているようであった。十字架には「OR DO NIAHOL AG DO GILLIBERD O'DUBTHAIGH RABIH ABAIDDE AGT CUNGA」と刻まれており、「コングの修道院長であったニアホルとギルバート・オドゥブタイのために祈りなさい」という意味であると。 裏面。そして駐車場に戻ったが、旅友Yさんが、「Cong Abbey」内にガイドブックを忘れて来たことが判明した。旅友Yさんが、直ぐにひきかえたが、幸い見つかりやれやれであった。そしてこの日の最後の訪問場所「Ashford Castle・アッシュフォード城」 への入口に向かって進むが、いろいろな入口があり、車で入門できる場所に辿り着くのに手間取ったのであった。そして漸く、「Ashford Castle Front Gate」から中に入れたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.05
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その37):Cong Abbey(コング修道院)(1/2)
R345をひたすら走り「Cong」の街に到着し、街の北側にあった駐車場に車を駐め散策開始。駐車場の横には、各所に植物が整備された raised beds(盛土式花壇)が見え、鉄製の縁取りが美しくモダンな公園が。この場所は、Cong Abbey(コング修道院)や、映画『静かなる男(The Quiet Man)』のロケ地としても有名な村の中心部に位置する と。この橋は、「The Abbey Bridge(修道院橋)」または単に「Stone Bridge」として地元で知られており、中世から存在している橋。奥に見えるのは、この後訪ねたCong Abbey(コング修道院)の遺構。12世紀に建てられたこの修道院は、アイルランドのロマネスク様式建築の貴重な例とされ、廃墟となった今でも美しい窓の意匠が残っていたのであった。橋の上から清き流れを見る。CongのMAP。現在地は●。名所、レストラン等の案内。Cong Abbey(コング修道院)に向かって進むと、交差点の角にあったのが映画『The Quiet Man(静かなる男)』を記念したブロンズ像「Quiet Man Statue」。 像の人物は、1952年のアメリカ映画『The Quiet Man』の主演 ジョン・ウェイン(John Wayne)と モーリン・オハラ(Maureen O’Hara)を表しているのだ と。ジョン・ウェイン演じる「ショーン・ソーントン」が、結婚後に妻メアリー・ケイトを力強く抱えて家へ向かう有名なシーンを再現したもの。『静かなる男(The Quiet Man)』について:監督:ジョン・フォード公開:1952年内容:アメリカからアイルランドの故郷・イニスフリー村に戻った元ボクサー、ショーン・ ソーントンが、現地の女性メアリー・ケイトと恋に落ち、伝統と現代の狭間での葛藤や 文化の違いを描いたラブロマンス。Cong村がロケ地として多く登場し、映画の舞台である「イニスフリー村」のモデルにもなっている。「記念プレートThis statue is dedicated to all those involved in the 1951production of the filmThe Quiet Manwhich was filmed here in Cong.The statue depicts the characters of Sean Thornton,played by John Wayne and Mary Kate Danaher,played by Maureen O’Hara.」 【この像は、1951年に製作された映画『静かなる男(The Quiet Man)』に携わったすべての人々に捧げられています。この映画はここコング村で撮影されました。像は、ジョン・ウェインが演じたショーン・ソーントンと、モーリン・オハラが演じたメアリー・ケイト・ダナハーの登場人物を描いています。】銘板の下部には「Donations Welcome(寄付歓迎)」、「Make A Wish(願いを込めて)」とあり、訪問者がこの像にちなんだ願い事や寄付を行える仕組みになっていた。おそらく、像の維持やThe Quiet Man Museumの運営支援のためのもの。」 この日は訪ねなかったが、「he Quiet Man Museum」をレンタカーの車窓から。 Cong Abbey(コング修道院)を「Tourist Office」前から。右側:Cong Abbeyの聖堂跡(本堂ファサード) ゴシック様式の尖頭アーチの玄関(西側出入口)が残っており、当時の精緻な石工技術が うかがえる。 壁には細長いランセット型の窓(細い縦長のアーチ窓)も見られ、13世紀以降の建築特徴を 示している。 この修道院はかつて、聖職者の教育や祈りの中心であり、王の埋葬地としても名高い場所 であった と。左奥:鐘楼(もしくは塔の残骸) 一部が崩れているが、上部には開口部(アーチ窓)が残っており、修道院の鐘楼跡または 見張り塔だった可能性が。 この部分は草に覆われ、廃墟化した風情を際立たせていたのであった。中央手前:鮮やかな緑の看板「LOUGH MASK SCENIC DRIVE」 これはロッホ・マスク湖周辺の観光ドライブコースを案内する地図で、Congはこの湖の南端 に位置しているのだ。植栽の中にあったのが「CONG HANDS OF FAME AWARD」のモニュメント。 地球を囲むように広げられた手のシンボルは、人類の団結・感謝・追悼を表しているとのこと。「Cong Hands of Fame Award(コング・ハンズ・オブ・フェイム賞)」に関する説明パネル。PUBLIC NOTICECONG HANDS OF FAME AWARDThe "Cong Hands of Fame Award" is bestowed to those who have done both the land and her people proud — in Ireland and abroad. It is our own boulevard of fame, and recipients have been nominated by you, the public, and receive a CHOFA awardvia the Freedom ducks whenever and wherever in the village.This sculpture is in tribute to all those who served and in memory of all those who died during the Covid pandemic.“About the sky, where that is clear of cloudBrightness remains, a brighter star shoots down.”— W. B. Yeats」 【コング・ハンズ・オブ・フェイム賞「Cong Hands of Fame Award(コング栄誉の手形賞)」は、アイルランド国内外を問わず、この土地とその人々に誇りをもたらした人物に贈られるものです。これはコング村独自の“名声の遊歩道”であり、受賞者はあなた(=市民)によって推薦されます。受賞者には、村のどこかで“フリーダム・ダック(自由のアヒル)”を通じて賞が贈られます。この彫刻は、COVID-19パンデミックに際し奉仕したすべての人々と、亡くなられた方々への追悼として建立されました。「空の彼方、雲のない場所には、明るさが残り、より明るい星が降りてくる。」― ウィリアム・バトラー・イェイツ】受賞者の手形プレート。両手の型(手形)が金属板(ブロンズや青銅系)に鋳造されており、訪問者が触れたり、記念写真を撮ったりできるようになっていた。手形の周囲が摩耗して輝いているのは、多くの人がそこに触れてきた証であり、地元の愛情と観光客の関心の高さを物語っているのであった。「LOUGH MASK SCENIC DRIVE」Congの北西側にあるLOUGH MASK・マスク湖周辺の観光ドライブコースを案内する地図。Cong ST.の前方左にあったのが「鐘楼(Bell Tower)」。 ズームして。石灰岩造りの四角い塔で、3層に分かれているように見えた。各層にアーチ型の開口部(鐘楼窓)が設けられており、最上部はかつて鐘や鐘つき場だったか?円形の小窓(ローズウィンドウの名残のようなもの)も確認できた。壁面の割れ目や、自然に生えた植物が中世遺跡としての古びた風格を際立たせていた。Cong ST.の前方右側にあったのがCong Abbeyの聖堂跡(本堂ファサード)。Cong Abbey(コング修道院) の本堂の壁面と窓部の遺構に近づいて。12世紀初頭に創建、13世紀に大幅な再建が行われた。アイルランド最後の高王「Ruaidrí Ua Conchobair」がこの修道院で晩年を過ごし、ここで亡くなったとされる。教育・祈祷・地域共同体の拠点として機能し、周辺の村とともに栄え と。コング修道院の西側出入口(West Doorway)がここ。入口奥に「鐘楼(Bell Tower)が垣間見えた。正面から。「Cong Abbey(Mainistir Chonga)案内板The monastery of Cong, founded in the early 7th century, was destroyed by fire in the early 12th century.Turlough O'Conor, the High King of Ireland, refounded the abbey around 1135, and his son Rory constructed new buildings.The community adopted the Augustinian rule several years later.Soon after, in 1203, the Norman knight William de Burgo attacked the town, and again the monastery had to be rebuilt.Very little remains of the abbey.The present church and also the fragmentary cloister, where the monks once worked and prayed, belong to the rebuilding of the early 13th century.The north doorway of the church, and the elaborate doorways that open onto the cloister from the east and west, might pre-date the destruction by William de Burgo.The doorway with two fine windows on either side of it belongs to the chapter house, where the monastery’s business was conducted and a chapter of the rule read every day.This was also the place where the monks gathered to confess their sins publicly.The sculpture in the abbey, which suggests links with western France, is some of thefinest in Ireland.」【コング修道院コング修道院は、7世紀初頭に創建されましたが、12世紀初頭に火災で焼失しました。アイルランドの上王トールハ・オコナーが1135年頃に再建し、息子ローリー・オコナーが新たな建物を建設しました。数年後、この修道院はアウグスチノ会の規律(修道ルール)を採用しました。しかし1203年、ノルマン騎士ウィリアム・ド・ブルゴが町を襲撃し、修道院は再び再建を余儀なくされました。現在、修道院の遺構はわずかしか残っていません。現在の教会建物および僧侶たちがかつて働き祈った回廊(クロイスター)の一部は、13世紀初頭の再建によるものです。教会の北側出入口や、回廊に面した東西の精緻な出入口は、ウィリアム・ド・ブルゴの襲撃以前のものかもしれません。両側に美しい二つの窓をもつ出入口は会議室(チャプター・ハウス)に通じており、そこで修道会の業務や日々の戒律の朗読が行われていました。ここはまた、僧たちが公に罪を告白した場所でもあります。修道院に残る彫刻装飾は、フランス西部とのつながりを示しており、アイルランド国内でも最上級のものとされています。】 Cong Abbey(コング修道院)の西側出入口(West Doorway)の見事な石造アーチ。旅友が立っていることで、アーチの壮大さと細部の美しさがより際立っていたのであった。建築の特徴:1. ロマネスク様式の多重アーチ この出入口は、半円形の複数のアーチ(アーチボルト)で構成されていた。 各アーチは、柱頭(キャピタル)の上に繊細に積まれており、柱間の彫刻にも装飾が見られる。 アーチ内側の縁に見られるビーズ状の装飾(ビーディング)や葉・渦巻模様などは、12世紀 ロマネスク様式の典型である と。 2. 扉上部の繊細な彫刻 アーチの要石(中央上部)周辺や、柱の胴部に彫られた模様(蔓草模様や幾何学模様)は、 当時の職人の高度な技術を示しているのだと。 一部には顔のようなレリーフも見られることがあり、宗教的な象徴や守護の意匠が込められて いる。 3. 保存状態の良さ 12~13世紀の石造アーチでこれほど精緻な意匠が残っているのは非常に貴重。苔や風化も見られたが、むしろそれが歴史の重みと風格を引き立てているのであった。西側出入口(West Doorway)の見事な石造アーチを潜り内部へ。修道院跡地にある墓地の一部。古い石造りの壁と、ケルト十字を含む多くの墓石が。写真中央には比較的新しい墓石があり、「In Loving Memory Of James Clarke Died 9th Jan 1964 His Wife Annie Clarke Died 29th Apr 1970 Also His Brother Patrick Clarke Died 26th June 1952 AndHis Sister Mrs. Catherine (née Clarke) Died 10th May 1963 Also Tess Mullins (née Clarke) Died 20th Jan 2020 R.I.P.」と刻まれていた。この碑文からは、クラーク(Clarke)家の複数の人物が埋葬されていることがわかった。年代も1950年代から2020年まで広がっており、家族の代々の墓であろう。Cong Abbey(コング修道院) の遺構の一部、教会堂(聖堂)東側の三連窓を内側から。その先に鐘楼が垣間見えた。三つの縦長の尖頭アーチ型窓を備えたゴシック様式の建築で、教会建築における東側の祭壇背後の窓にあたる と。アーチの形状や石の積み方から、12〜13世紀ごろのアイルランドの修道院建築様式が見て取れるとのこと。「This National Monument is in the care of the Commissioners of Public Works forthe State under the provisions of the National Monuments Acts.The public are requested to aid the Commissioners in preserving it.Injury or defacement is severely punishable by law.」 【この国家記念物は、アイルランド国家の名のもとに公共事業委員会(OPW)の管理下にあります(国家記念物法に基づく)。一般市民の皆様には、この遺産の保存にご協力いただくようお願い申し上げます。損壊または落書きなどの行為は法律により厳しく罰せられます。】Cong Abbey(コング修道院)内にある古い墓碑の一つ。床に平らに設置された石板で、長年の風化により文字は摩耗。「.. mercy on the Soul of Mr. Thos. Viganer [Viganeron?] ofCong, in the County of Mayo, Departed this life on the 4th of January, 1857aged 50 years.His brother Thomas ...」 【「神がこの魂に慈悲を与え給え」メイヨー州コングに住んでいた トーマス・ヴィガナー(あるいはヴィガネロン?)氏彼は 1857年1月4日に亡くなり、享年50歳その弟 トーマスによって(あるいは彼の名もトーマスか)・・・】左手前には大きな「ケルト十字墓碑」 写真奥にはロマネスク様式の柱とアーチが。左手の碑には「IN LOVING MEMORY OF JOHN HOLIAN Died JULY 4-1940 Aged 87 Years ・・・・・・・・・・・・」 鐘楼(Bell Tower)方向を見る。西側出入口(West Doorway)の見事な石造アーチ方向を振り返る。さらに西側の緑の跡地・クロイスター(Cloister)=中庭回廊を見る。四角形または長方形の芝生の中庭で、周囲を屋根付きの柱廊(回廊)が囲んでいた と。修道士たちはここを通って教会・食堂・書写室などを行き来した。中庭では祈りや瞑想、読書、そして時に薬草栽培も行われていた と。現在では、屋根は失われて芝地だけが残り、石の柱列や壁のみが遺構として。ロマネスク様式の石造窓枠。この窓は、ロマネスク様式(Romanesque)に特徴的な半円アーチと分厚い石造構造。12世紀頃の建築に典型的なスタイル。一つの大きなアーチの中に2つの小アーチがあり、これらは柱で仕切られていた。これは「双子窓(twin-light window)」または「ビフォラ窓(bifora)」と呼ばれる形式で、ロマネスク〜初期ゴシック建築に多く見られるのだ と。石の階段がある洞窟状の空間。鉄格子で保護されており、手前には宗教的な小像が奉納?近づいて。この緑地は、修道院の中庭(cloister garth)であり、周囲を柱廊で囲まれた回廊(cloister walk)が残っていた。中央の芝生エリア:ここは本来、修道士たちが祈りや瞑想、読書などを行った静かな空間。中世の修道院ではこの空間が精神的・身体的な中心であった と。奥の壁面に見える彫刻とアーチ:左から順に、ロマネスク様式の出入口、飾りアーチ(blind arcade)、そして最も右の彫刻装飾された主出入口が見えたのであった。移動して。周囲のアーチ型柱列:これが「回廊」の一部で、修道士たちは雨の日でもここを歩きながら祈りを唱えたり、礼拝堂・食堂・寝室へ移動していた。アーチは典型的な12世紀アイルランド=ノルマン様式。現存するクロイスター(回廊)北東部のアーケード構造に近づいて。① 複柱式アーケード(二重列柱) 各アーチは2本1組の円柱(双柱)で支えられ、上部に丸みを帯びたアーチ(ロマネスク様式) が かかっている。 この形式は中世の修道院回廊に典型的で、祈りの道としての静けさと秩序を強調。② 柱頭装飾(キャピタル) 手前左端の柱頭にある葉状の彫刻(アカンサス風)は、自然界のモチーフを取り入れた 典型的なロマネスク装飾。 他の柱頭はやや素朴で、いくつかは摩耗していますが、それが逆に時代の重みを感じさせる。③ 上部構造の崩落痕 手前の石梁の一部が激しく損傷し、石が不均等に突き出しています。 これはかつて屋根の構造がここまで覆っていたことを示唆します。 植物が生えているのも長い歳月の証し。狭間窓(さままど)=スリット状の開口部を内側から撮影。元は修道院が略奪の危険に晒された時代、弓矢を外に射るための防御窓(アロースリット)。壁の厚さが非常に分厚いのだ(1メートル以上)。窓は内側が広く、外側に向かって狭まる「逆ラッパ型」。アーチ上部は丸みを帯び、ロマネスク様式の影響が。クロイスター(中庭回廊)内側から外を見た。柱列アーケード越しに中庭と回廊の反対側の壁面が見えた。まさにこの修道院の最も象徴的な風景のひとつ。アーチを支える柱は一対になっている(複柱式)のが特徴で、それぞれの柱頭(キャピタル)には植物文様や装飾モチーフが施されていた。クロイスター(中庭回廊)を、外側の遊歩道と階段越しに正面から見たもの。これにより修道院の回廊と中庭の全体構成が非常によくわかるのであった。旅友が私の写真を撮ってくれました。<クロイスター(中庭回廊)を後にしてさらに南方向に進む。イチイ(Yew tree)の大木であっただろうか?幹が複数に分かれて曲がりくねる独特の形状で枝が地面すれすれまで広がってアーチ状に垂れていた。常緑で針状の葉を持ち、樹冠が濃い緑色で地面には針葉と茶色の葉が落ちて柔らかい絨毯のようになっていたのであった。川に架かる橋の先にも石の門が見えた。近づいて。「マイヤーズ・ゲート(Myers’ Gate)」Cong Abbey(コング修道院)周辺の公園内にある、印象的なゴシック様式の石造アーチで、19世紀の詩人・作家であるジョージ・マイヤーズ(George Augustus Moore)を記念して建てられたもの と。上部の彫像。アーチの上に顔のレリーフがあったが、これはジョージ・マイヤーズ本人の肖像 と。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.04
コメント(0)
-
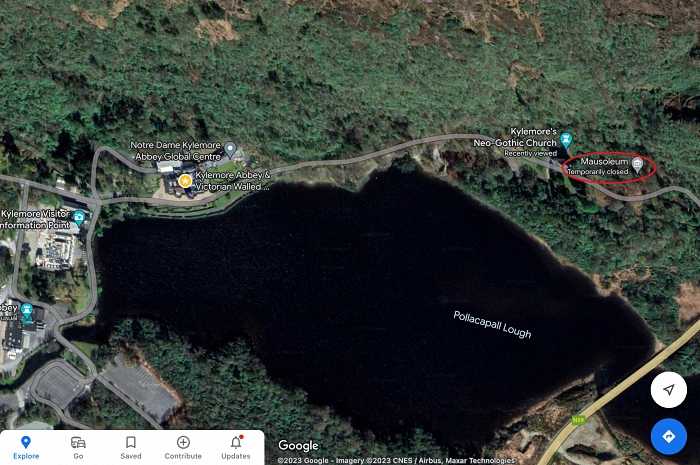
アイルランド・ロンドンへの旅(その36):カイルモア修道院(Kylemore Abbey)を訪ねる(9/9)~「Cong Abbey」へ
「Kylemore’s Neo-Gothic Church」を訪ねたの後に、さらにその先の博物館「Mausoleum」を訪ねる予定であったが、時間の関係上諦めたのであった。 ネットから霊廟(れいびょう)「Mausoleum」の写真を。「Kylemore Abbey & Victorian Walled GardenMausoleumHere lies the remains of Margaret Henry 1829–1874 who died tragically while on holiday in Egypt just 4 years after the castle at Kylemore was constructed.Her body was brought back to Kylemore by her husband Mitchell Henry.Mitchell Henry 1826–1910, who built Kylemore Castle, died in England.His ashes were brought back to Kylemore and laid to rest next to his beloved wife Margaret in accordance with his final wishes.The remains of John Henry, a grandnephew of Mitchell Henry who died 13th February 1989, were laid to rest in the mausoleum.」 【カイルモア修道院 & ヴィクトリア朝の囲い庭園霊廟(れいびょう)ここには、マーガレット・ヘンリー(1829年–1874年)の遺骨が埋葬されています。彼女は、カイルモア城が完成してからわずか4年後、エジプトでの休暇中に悲劇的な死を遂げました。その遺体は、夫であるミッチェル・ヘンリーの手によってカイルモアに運ばれました。ミッチェル・ヘンリー(1826年–1910年)はカイルモア城を建てた人物で、イングランドで亡くなりました。彼の遺灰は遺志によりカイルモアに持ち帰られ、愛する妻マーガレットの隣に安置されました。また、この霊廟には、ミッチェル・ヘンリーの又甥(またおい)にあたるジョン・ヘンリー(1989年2月13日没)の遺骨も共に埋葬されています。】この写真もネットから。よって「Kylemore’s Neo-Gothic Church」迄とし、引き返す。ウィッチ・エルム(ニレの一種)。「MEET THE ELMCommon name – Wych Elm Botanical name – Ulmus glabra Irish name – Leamhán SléibheIreland is home to one species of elm, the Wych elm (Ulmus glabra).The Irish name translates as mountain elm, as Wych elms prefer to grow on hillsides.Elm trees have largely disappeared from the landscape since the 1960s due to Dutch Elm disease.The elm bark beetle spreads a fungus that blocks the vessels transporting nutrientsin the tree.Kylemore’s woodland is fortunate to have several healthy elms.The timber of Wych elm is strong and water-resistant.It was used for cabinet making, construction, boat-building, coffin manufacturing, andwater pipes.Strips of the inner bark once made strong cordage and woven chair seats.The foliage, rich in nutrients, has been used as fodder for livestock since the Neolithic times.」【ニレの木に出会う(Wych Elm)一般名:ウィッチ・エルム(ニレの一種)学名:Ulmus glabraアイルランド語名:Leamhán Sléibhe(山のニレ)アイルランドに自生するニレの木は、この「ウィッチ・エルム(Ulmus glabra)」の1種だけです。アイルランド語名は「山のニレ」という意味で、これはこの木が斜面や丘陵地を好んで生育するためです。1960年代以降、ダッチ・エルム病(オランダニレ病)の影響で、ニレの木は風景の中からほとんど姿を消してしまいました。この病気はエルム樹皮カミキリムシによって広がり、木の内部で栄養を運ぶ導管を菌によって詰まらせることで枯死させてしまいます。しかし、カイルモアの森には幸運にも健康なニレの木が数本生育しています。ウィッチ・エルムの木材は強靭で耐水性があり、古くは家具作り、建築、造船、棺桶製造、そして水道管などに使われてきました。また、内樹皮の繊維は、強い縄や椅子の座面を編む材料としても用いられていました。さらに、栄養価の高い葉は、古代新石器時代から家畜の飼料として利用されてきました。】 「The Boathouse」の建物の遺跡。 「The BoathouseAMPLE OPPORTUNITIES FOR BOATING"...an ornamentally-designed Boat House."– Kylmore Book of Sale 1903While clearing invasive rhododendron, this once beautiful picturesque building was uncovered.It housed the pleasure boats of the Henrys and would originally have beenused for fishing or recreational boating.The Boathouse was built from locally quarried stone, finished with red brick and roofed with terracotta tiles.A mountain stream was cleverly diverted to have continuous fresh water running through the boathouse to prevent algae growth.The small lake in front of the boathouse acts as a “dripping pond” – these fill with heavy rainfall but dry up in sunny weather.Artist impression of the Boat House」【ボートハウスボート遊びに最適な環境「装飾的に設計されたボートハウス」ー『カイルモア売却目録』(1903年)外来種のシャクナゲ(ツツジ科)を伐採していた際、この美しく趣ある建物が再び姿を現しました。この建物は、かつてヘンリー家が所有していた遊覧ボートの格納庫として使われており、釣りや娯楽としてのボート遊びに利用されていたと考えられます。ボートハウスは地元で切り出された石材で建てられ、赤レンガで仕上げられ、屋根にはテラコッタ瓦が葺かれていました。また、山からの小川を巧みに引き込み、建物内に常に新鮮な水が流れるように設計されており、これによって藻類の繁殖が防がれていました。ボートハウス前の小さな池は、「ドリッピング・ポンド(しみ出し池)」として機能しており、大雨の際には水がたまりますが、晴天が続くと自然に乾いていきます。(※図:ボートハウスの復元イメージ)】ポラカパル湖を左に見ながら。「THE Rowan・ナナカマド」。「MEET THE RowanCommon name – Rowan Botanical name – Sorbus aucuparia (bird catcher) Irish name – CaorthannThe rowan is sometimes called the mountain ash. But, despite a similar leaf shape,the rowan is not related to the ash.The “mountain” part of the name is apt however, as the rowan is the only deciduous tree that can grow at high altitude (up to 900m) in the Irish landscape.Because the rowan can grow in remote areas and bears bright red berries, it is a valuablefood source for birds, especially migrating birds.The rowan seed must pass through a bird or animal gut in order to germinate.Rowan berries are too acidic and bitter to eat rawbut once boiled, the acid breaks down, and can beused to make a delicious jelly rich in Vitamin C.」 【ローワンの木(ナナカマド)に出会う一般名:ローワン(ナナカマド)学名:Sorbus aucuparia(鳥を捕まえる=鳥寄せの意)アイルランド語名:Caorthann(カーフラン)ローワンの木は、しばしば「マウンテン・アッシュ(山のトネリコ)」と呼ばれますが、葉の形が似ているだけで、実際にはトネリコとは関係がありません。「山(マウンテン)」という名は適切で、ローワンはアイルランドの風景の中で、標高900メートルまで育つ唯一の落葉樹です。ローワンは人里離れた場所でも育ち、鮮やかな赤い実をつけるため、特に渡り鳥など多くの鳥にとって貴重な食料源となっています。なお、ローワンの種子は、発芽するために一度鳥や動物の消化管を通過しなければなりません。ローワンの実はそのままだと酸味が強く苦いため食用には適しませんが、加熱することで酸が分解され、ビタミンCが豊富な美味しいゼリーに加工できます。】ナナカマドと白樺は、どちらも北国の風景を彩る代表的な木ですが、それぞれ異なる特徴を持っているのだ と。帰路には「カイルモア修道院(Kylemore Abbey)」の前の湖岸の路を引き返す。「Lake WalkWater and Connemara are synonymous.The region is named after an ancient tribe: Conmhaicne Mara, the ‘Con Mhac’ of the sea. The Atlantic Ocean borders its jagged coastline; the land is rich in freshwater bodies andblessed with high annual rainfall.Mountain lakes and streams feed into the three large lakes of Kylemore Valley. The largest lake is Kylemore Lake, followed by Pollacapall (the lake in front of Kylemore Abbey) andLough Maladrolaun. The Victorian Walled Garden is irrigated by Lough Touther, situatedjust above the garden.Lough Touther was used to generate electricity in Kylemore Castle in 1893. Engineersfrom J. G. Howell of London designed and installed the hydro-electrical system in a small powerhouse west of the castle. We hope to reinstate hydropower in the near future toharness sustainable green energy.」【湖の散策路(Lake Walk)カイルモアの谷には三つの大きな湖(カイルモア湖、ポラカパル湖、マラドローラン湖)があり、周囲の山からの小川が注ぎ込んでいます。この地方は古代の部族「コンワイクネ・マーラ(海の民)」にちなんで名付けられ、大西洋に面し、淡水と雨量に恵まれた地域です。中でもラフ・タウザー湖(Lough Touther)は1893年、カイルモア城で水力発電に利用されました。今後、再びこの水力発電を導入し、持続可能な再生エネルギー源として活用する予定です。】 モンテレー・パイン(Monterey Pine / Pinus radiata)であっただろうか?そして再びカイルモア修道院・Kylemore Abbeyを振り返る。いつまでもいたい空間と時間なのであった。そしてレストランにて昼食を。時間は12:30過ぎ。駐車場に戻り、この日の午後の目的地の「Cong Abbey」に向かってN59を西に向かって進む。走行ルート図。Kylemore Lough・カイルモア湖を右に見ながら進む。Kylemore Lough・カイルモア湖の奥にそびえる大きな山の名はドゥールルー(Doughruagh)/デューホルーチ(Dúchruach)であろうか。ズームして。手前にはドゥールルーの北側から続く、なだらかな稜線の連なりが見えた。ガラウン山群(Garraun Complex)の一部で、標高約598 mのガラウン山が代表峰。ガラウン山群(Garraun Complex)を追う。対岸のガラウン山群(Garraun Complex)の山腹の白い場所は石灰岩が剥き出しになっている場所なのであろうか!?Kylemore Lough・カイルモア湖の中央付近の湖岸を走る。更に10分ほど進むと、坂の下、前方に現れたのが、アイルランド唯一のフィヨルド、北大西洋に繋がっている壮大なキラリー港の入江。前方に見えたのは、サーモン?マス?の養殖場であっただろうか。ズームして。Aasleagh・アアズリー方向の山並みを見る。右手に見えたのはアパート?ホテル?ホテルのようであったが?その先の、「leenaun(リーノーン)」のT字路を右折してR336に入る。 山々は牧草に覆われて緑一色。Maumturk Mountains(マウムターク山脈)の山々を見る。この山並みは「lungnabrick SW top 454m」周辺であっただろうか。 R336をひたすら走る。Maumを通過し、R345を更に進む。Lough Corrib・コリブ湖が右手に現れた。ゴールウェイ州コルナモナ近郊、コリブ湖の北岸を進む。R345から、コリブ湖の北岸の景色を楽しむ。コリブ湖の北岸には大小の島々が浮かんでいた。カイルモア修道院(Kylemore Abbey)~Congへのルート図を再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.03
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その35):カイルモア修道院(Kylemore Abbey)を訪ねる(8/9)
カイルモア修道院(Kylemore Abbey)の見学を終え、外に出る。再び目の前に拡がる、Pollacapall Lough・ポラカパル湖を見る。名前の由来:「Pollacapall」はアイルランド語で、おそらく「Poll a' Chapall(馬の穴/水たまり)」に由来すると考えられます。poll=穴や水たまりcapall=馬→ 「馬が水を飲みに来たような場所」という意味が込められている可能性があります と。この湖は自然湖でありながら、19世紀に建設されたカイルモア城(現・修道院)と庭園の一部として、景観整備が加えられているのであった。厚みのある石壁は、まるで時を超えて守られてきた祈りと物語の砦のよう。貴族の私邸として建てられ、修道院として生まれ変わったこの建物には、愛・喪失・再生の歴史が刻まれているのであった。湖(Pollacapall Lough)のほとりにたたずむその姿は、鏡のような湖面に完璧に映り込む白い幻想のような建物。尖塔(せんとう)やアーチ窓、装飾の細部までが19世紀ゴシック・リヴァイヴァル様式(ネオ・ゴシック)を反映。縦に伸びる構造が、空へ祈りを捧げるような精神性を感じさせるのであった。建物の背後にはダイヤモンド山脈(Twelve Bens)の森と山が広がり、灰色の石造りの建物はその自然と一体化しているかのようであった。チリランタンの木(Chilean Lantern Tree)。近づいて。チリランタンツリーはマツ科に属する8種の顕花植物を含む植物属。それらはチリの森林原産の常緑低木または小さな木。敷地内にある祈りの場(マリア像の洞窟)にあったルルドの洞窟を模した聖母マリア像。フランス南部の聖地「ルルド(Lourdes)」にある有名な洞窟にインスピレーションを得て、世界中のカトリック施設ではこのような岩に囲まれたマリア像の祈りの空間を再現している と。白いローブに青い帯をまとった姿は、「無原罪の御宿りの聖母マリア(Our Lady of the Immaculate Conception)」の典型的な表現。対岸の山々をズームして。Kylemore Abbey(カイルモア修道院)の対岸(南側)に広がる山岳地帯。湖の向こうに見える山々は、Duchruach(ドゥクルーア)やその周辺の峰々であろう。山の斜面から水の流れも。ヨーロッパでよく見られるコブハクチョウ(英名:Mute Swan)。ズームして。嘴がオレンジ色で、根元に黒い「コブ」がある(これが名前の由来)。Duchruach(ドゥクルーアク)山(アイルランド語で「暗い尾根」の意味)。標高 :約550メートルwelve Bens(トゥエルブ・ベンズ)山脈の一部。「LAKE WALK」案内板。「LAKE WALKThe community of Benedictine nuns have been stewards of the Kylemore estate for over a century, the longest continuous habitant of the estate.They welcome postulants, students, guests,and visitors from around world to their home.Over a hundred years , the Communiry has managed the estate,farmed the land,supported the local economy, and preserved the historic and natural heritage. The nuns produce susrainable products like skincare products, chocolate, pottery and honey. Discover the handcrafted products in Kylemore Abbey Craft & Design Shop.」 【湖の遊歩道(Lake Walk)ベネディクト会の修道女たちは、100年以上にわたりカイルモアの地を守り続けてきた管理者(スチュワード)であり、この地で最も長く暮らす共同体。彼女たちは志願者(ポスチュラント)や学生、宿泊者、そして世界中からの訪問者を」この「家」へ温かく迎え入れています。この100年の間に、修道女たちは:広大な敷地を管理し、農業を営み、地域経済を支え、歴史的・自然遺産を守ってきました。また、彼女たちは環境に配慮した持続可能な製品も手がけており、スキンケア用品、チョコレート、陶器、はちみつなどを製造しています。こうした手作りの品々は、敷地内の「カイルモア修道院クラフト&デザインショップ」でご覧いただけます。】Letterbreckaun(レターブレカン)山か?ここにも「Lake WalkDid you know that Kylemore's woodland is a temperate rainforest?Ireland is situated at a northern lattitude, only 15 degrees south of the Arctic Circle,the same latitude as Newfoundland in Canada. Yet the lrish climate originating in the Gulf of Mexico, gives Connemara high humidiry, high rainfall, and minor fluctuation in average mild temperatures. This creates perfect conditions for a forest with layered vegetation rich in lichens,mosses,ferns,and epiphytes.These woodlands,associatedwith native species,are confined to western Ireland and Britain and form a uniquehabitat.」【レイク・ウォーク情報:カイルモアの森は温帯雨林?ご存知でしたか?カイルモアの森林は「温帯雨林(テンペレート・レインフォレスト)」なのです。アイルランドは北緯に位置し、北極圏からわずか15度南、カナダのニューファンドランド島と同じ緯度にあります。しかし、メキシコ湾からの暖流(ガルフ・ストリーム)によってもたらされる気候は、コネマラ地方において・高い湿度・豊富な降水量・穏やかで安定した気温を生み出しています。このような気象条件は、以下のような多層的な植生をもつ森を育むのに理想的です:・地衣類(リケン)・苔(モス)・シダ(ファーン)・着生植物(エピファイト)これらの温帯雨林型の森林は、アイルランド西部およびイギリスの一部にのみ分布し、きわめて限られた希少な生態系を形成しています。】「THE Monterey Pine・モントレーパイン」。「 MEET THE Monterey PineCommon name: Monterey PineBotanical name: Pinus radiataIrish name: Péine MontereyThe Monterey pine is unmistakably one of the most imposing trees on the Kylemore estate. This tree is native to only three places: Monterey in California, just south of San Francisco, and the islands of Guadalupe and Cedros off the California Baja Mexican coast.The Monterey pine, like many other American west coast tree species, was “discovered” by David Douglas, a Scottish botanist. The first seeds were sent to the British Isles in 1831. This pine grows well in Kylemore’s mild oceanic climate, growing an incredible one meter a year for up to 30 years.The Monterey pinecones stay on the branches until hot weather, or a forest fire opens them up to free the seeds. In hot summers, the Monterey pines have been known to self-seed on our estate.」 【モントレーパインをご紹介一般名:モントレーパイン学名:Pinus radiata(ピヌス・ラジアータ)アイルランド名:Péine Montereyモントレーパインは、カイルモアの敷地内で最も堂々とした木のひとつとして、ひと目でわかります。この木が自生しているのは、カリフォルニア州モントレー(サンフランシスコ南部)と、メキシコ・バハカリフォルニア沖のグアダルーペ島およびセドロス島の3か所だけです。他のアメリカ西海岸の樹種と同様に、モントレーパインはスコットランドの植物学者デイヴィッド・ダグラスによって「発見」されました。最初の種は1831年にイギリス諸島に送られました。この松はカイルモアの穏やかな海洋性気候によく適しており、最大30年間で年間1メートルも成長することがあります。モントレーパインの松ぼっくりは、暑い気候や山火事が種子を放出するまで枝についたままです。暑い夏には、敷地内で自然に発芽することも知られています。】「Lake Walk」を奥に進む。 「Lake WalkThe Kylemore Valley is rich in geological heritage.Our estate is part of the Joyce Country & Western Lakes aspiring UNESCO Global Geopark (Gleann Uí Dhálaigh agus Lochanna an Iarthair) and the bedrock of Kylemore Valley is of great geological importance of a foreign landmass, and its influence on the local heritage, communities, and biodiversity.The bedrock of Kylemore Valley is mainly metamorphic rocks dating back to 700 million years ago: quartzite for the peaks, schist and marble for the valley floor. The last Ice Agehad a major influence on the landscape.」 【レイク・ウォークカイルモア渓谷は、豊かな地質遺産を有しています。当敷地は、「ジョイス・カントリー & 西部湖沼群」のユネスコ世界ジオパーク申請地域の一部であり(アイルランド語名:Gleann Uí Dhálaigh agus Lochanna an Iarthair)、カイルモア渓谷の基盤岩は、かつての外来の大陸地塊に由来し、地元の文化遺産、地域社会、生物多様性に大きな影響を与えています。カイルモア渓谷の基盤岩は主に変成岩で、約7億年前にさかのぼるものです。山頂部には石英岩、谷底には片岩や大理石が見られます。最終氷期もこの景観に大きな影響を及ぼしました。】そして「Kylemore’s Neo-Gothic Church」に到着。 「Gothic Church THE MINIATURE CATHEDRAL」 【ゴシック教会 小さな大聖堂(ミニチュア・カテドラル)】「Gothic ChurchTHE MINIATURE CATHEDRALIn 1874, Mitchell Henry and his adored wife Margaret went on holiday to Egypt. It was a happy time in their lives. But tragedy struck on the River Nile. Margaret contracted dysentery and sixteen days later, she died. She was only 45, a mother of nine.“It is not our mistress we have lost, but our mother” said one tenant as the distraught Mitchell lovingly brought home the body of his wife to rest in her beloved Kylemore.Mitchell wanted to show his love for Margaret in a way that would last through time, and so he commissioned the architect J.F. Fuller to create a “cathedral in miniature” in her honour. This beautiful Neo-Gothic Church is his tribute to her.」【ゴシック教会小さな大聖堂(ミニチュア・カテドラル)1874年、ミッチェル・ヘンリーは最愛の妻マーガレットと共にエジプトへ休暇に出かけました。それは二人にとって幸せな時でした。ところがナイル川で悲劇が起こります。マーガレットは赤痢にかかり、16日後に亡くなってしまいました。彼女はまだ45歳で、9人の子どもを持つ母でした。「私たちが失ったのは奥様ではなく、母です」と、ある小作人が語ったと伝えられています。打ちひしがれたミッチェルは、妻の遺体を愛するカイルモアへと丁重に連れ帰りました。ミッチェルは、時を超えて妻マーガレットへの愛を示したいと考え、建築家J.F.フラーに「ミニチュアの大聖堂」を設計させました。この美しいネオゴシック様式の教会は、彼女への追悼の証です。】 「The gargoyles on the limestone exteriorare classic marks of cathedral architecture – but these are angelic creatures telling of peace, setting the design apart from some of its more fearsome cousins from Europe. The wolves of Ireland are set against a light-yellow sandstone from the North of France.“The carvings of the interior are breathtaking,” say the experts – graceful and feminine with delicately shaped flowers and birds of beauty incised in the sandstone. The superb stained-glass windows remind us of the Five Virtues of Fortitude, Faith, Charity, Hope and Chastity.Originally, the Gothic Church was a place of Anglican worship. Following the arrival of the Benedictine Nuns to Kylemore in 1920, it was re-dedicated as a Catholic Church. The Mausoleum containing the remains of Margaret and Mitchell Henry is a short distance to the east of the church.」 【石灰岩の外壁に見られるガーゴイル像は、大聖堂建築の典型的な意匠ですが、ここでは平和を象徴する天使的存在として表現されており、ヨーロッパの他の恐ろしげなガーゴイルとは異なる雰囲気を醸し出しています。アイルランドのオオカミは、フランス北部の淡黄色の砂岩を背景に彫刻されています。「内部の彫刻は息を呑むほど美しい」と専門家は評しています。優雅で女性的な様式で、繊細に形づくられた花々や美しい鳥が砂岩に刻まれています。素晴らしいステンドグラスは、「五つの徳」──勇気・信仰・慈善・希望・純潔──を想起させます。もともとこのゴシック教会は、英国国教会(聖公会)の礼拝所として建てられたものでした。1920年にベネディクト会の修道女たちがカイルモアに到着した後、カトリック教会として再奉献されました。マーガレットとミッチェル・ヘンリーの遺骨が納められた霊廟(マウソレウム)は、教会の東側すぐの場所にあります。】「Next to the church lies the cemetery of the Benedictine community of Kylemore Abbey,which is still in use today. You will notice that some of the earlier graves bear names with a French, German or Belgian origin, testament to the nuns of those regions thatfirst arrived in the community when it was re-established at Kylemore. This graveyard isfull of Benedictine nuns – that of a schoolgirl, Ruth Stoker who died of a childhood illnesswhile she was a pupil here in 1923.Today the church is used to host musical recitals, poetry readings and cross-community celebrations. It will always be what it originally was – Margaret’s Memorial, created by her loving husband.」 【この教会のすぐ隣には、カイルモア修道院に属するベネディクト会修道女たちの墓地があります。この墓地は今も現役で使われており、初期の墓石にはフランス語・ドイツ語・ベルギー系の名前が見られます。これは、カイルモアに再定住した初期の修道女たちがこれらの地域から来たことを物語っています。ここには数多くのベネディクト会の修道女たちが眠っており、中には1923年にこの地で病気により亡くなった女学生、ルース・ストーカーの墓もあります。現在この教会は、音楽リサイタルや詩の朗読会、地域を越えた共同の祝祭の場としても利用されています。しかし、何よりも本来の目的──愛する妻マーガレットの追悼の場──として、この教会の本質は今も変わっていません。】尖塔は工事中であったが、カイルモア修道院(Kylemore Abbey)のNeo-Gothic Church(ネオ・ゴシック教会)の外観は、まさに「ミニチュア大聖堂」と呼ばれるにふさわしい荘厳さと繊細さを兼ね備えていたのであった。スコットランドの建築家 J.F. フラー(James Franklin Fuller) によって設計され、1877年に完成した と。以下、2枚の写真はネットから。この教会は19世紀に建てられたゴシック・リヴァイヴァル様式の礼拝堂で、ヘンリー・ミッチェルが亡き妻マーガレットの追悼のために建てた記念教会。ネオ・ゴシック様式(19世紀に流行したゴシック建築の復興様式)で建てられており、本格的なゴシック大聖堂を小型化したような荘厳な造り。地元コネマラ地方の石材を使用しており、色合いの異なる石(灰色の片岩、黄色がかった砂岩など)がバランスよく組み合わされていた。尖塔(せんとう):鋭く天に向かって伸びた塔が印象的で、ゴシック建築の象徴。尖塔アーチの窓:縦長のアーチ状の窓が多く、内部のステンドグラスに自然光を取り込む。バットレス(控え壁):外壁の補強として、教会周囲に飛び出した構造があり、垂直の力を 分散させる役割も。装飾彫刻:外壁の随所に花や鳥の彫刻が施されており、宗教的な象徴性と美を兼ねていた。尖塔は工事用シートに覆われていた。ファザード。教会内部の天井。教会の天井は尖頭ヴォールト(pointed vault)構造で、リブ(梁)が美しく交差し、天へと導くような印象を与えてくれるのであった。ゴシック建築特有の「垂直性」を強調することで、信仰の高みを感じさせる空間構成に。アーチの輪郭にはレース状の石細工(トレサリー:tracery)が施されており、葉の彫刻が精巧に組み込まれていた。各アーチの内部上部にある円形の装飾には、花(おそらくバラかアザミ)を模した彫刻が。これはヴィクトリア朝時代によく見られるモチーフであり、自然と美を象徴 と。正面の祭壇方向を再び。ズームして。左:「The Restoration ProjectConnemara’s climate is not kind to buildings and over the years a process of erosion and decay – driven by storms, wind, and wet – weakened the church, rendering it dangerous and in need of total restoration.In 1992, the Benedictine Community with the help of the National Heritage Council, the Department of the Environment and generous philanthropic and donor support,devised plans and raised the funds to completely restore the church.Today, the church hosts musical performances and liturgies and offers visitors a chanceto enjoy the acoustical quality and experience the wonder of Kylemore’s “cathedral-in-miniature”.Gothic Church during the time of the Henry family.」【コネマラの気候は建物に厳しく、年月とともに嵐、風、湿気による侵食と劣化が進み、教会の構造は弱体化し、危険な状態に陥っていました。完全な修復が必要となったのです。1992年、ベネディクト会の修道女たちは、アイルランド国家遺産評議会、環境省、そして多くの寄付者や支援者の助けを得て、教会の完全修復に向けた計画を立て、資金を集めました。現在、この教会では音楽の演奏や典礼が行われ、訪問者は音響の美しさと「ミニチュアの大聖堂」と称されるカイルモアの教会の魅力を体感することができます。写真はヘンリー家の時代のゴシック教会】右:「Before the restoration started the church was suffering significant damage causedby water ingress under the decayed lead of the copper roof and the external pointing.Internally, the main visible symptoms of this were the extensive mould growth whichcovered much of the interior whenever the weather was wet and stagnant water fallingfrom a water soaked clean stone walls and ceiling.During the restoration work the external stone work was cleaned and repointed.The conservation work involved repairs to:the main roof ,floors and roof of the tower,the leaded windows,conservation and repair of ironworks,rainwater goods and joinery.All marble columns were installed.Restoration works were reprogrammed when it wasfound that the main roof is home to the largest known colony of Natterer's bats inIreland.Great care was taken to ensure that the bats were not disturbed.The colony hassince bred succsessfully every year.」 【修復が始まる前、この教会は深刻な損傷を受けていました。それは、劣化した銅屋根の鉛板や外壁の目地部分から水が浸入していたことによるものでした。内部では、その主な目に見える症状として、雨が降るたびに室内の広い範囲にカビが繁殖し、さらに水を吸った石壁や天井から停滞した水が滴り落ちるという状態が発生していました。修復作業中、外壁の石材は洗浄され、再度目地(リポイント)処理が施されました。保存修復には以下の修繕が含まれていました:・主屋根、床、および塔屋の屋根の修理・鉛ガラス窓の修復・鉄製装飾の保存・修復・雨樋や木工細工(ジョイナリー)の修繕また、すべての大理石製の柱が設置されました。作業の途中で、主屋根がアイルランド最大級のナターレコウモリ(Natterer’s bat)の生息地であることが判明し、工事はそれに配慮して再調整されました。コウモリの邪魔にならないよう、細心の注意が払われました。それ以来、このコロニーは毎年順調に増殖を続けています。】 修復された壁等の写真。「PAX – PeaceA welcome from the Mother AbbessIn 1867 the Mitchell Henry family built Kylemore Castle and subsequently this beautiful Neo-Gothic Church which was used by the family for their term of residence there, terminated by tragic circumstances.In 1920 the Benedictine nuns arriving from Ypres in Belgium bought the property andthe castle became Kylemore Abbey.The Abbey and this church have become a centre of hospitality and admiration for visitorsto the West of Ireland and this exquisite scenic beauty.The church has become a source of joy and satisfaction to all who visit and we are glad toshare with you the pleasure and peace of this architectural treasure.We hope you will enjoy your visit and that our prayers and message of peace and heritagewill bless you.You are most welcome in the name of the Benedictine tradition of Kylemore Abbey.M. Clare Morety O.S.B. (Abbess)」 【PAX – 平和修道院長より皆さまへようこそ1867年、ミッチェル・ヘンリー一家はカイルモア城を建て、その後この美しいネオ・ゴシック様式の教会を建立しました。この教会は家族の滞在期間中、私的な礼拝の場として使われていましたが、不幸な事情によりその使用は終わりを迎えました。1920年、ベルギーのイーペルから到着したベネディクト会の修道女たちがこの地所を取得し、城は「カイルモア修道院」となりました。以来、修道院とこの教会は、西アイルランドを訪れる人々にとってのおもてなしと感嘆の中心となり、周囲の風光明媚な景観とともに多くの人に愛されています。この教会は訪れるすべての人にとって喜びと満足の源となっており、私たちはこの建築的宝物から得られる平和と喜びを皆さまと分かち合えることを嬉しく思っています。あなたの訪問が喜びに満ち、私たちの祈りと平和のメッセージ、そしてこの遺産があなたを祝福しますように。ベネディクト会の伝統に基づき、カイルモア修道院より心から歓迎いたします。M・クレア・モレティ修道院長 O.S.B.(ベネディクト会)】「The Gothic 'Memorial' ChurchAs a tribute to his late wife Margaret, Mitchell Henry commissioned a magnificent neo-gothic church in her memory.The“cathedral-in-miniature.”was designed by J. Fuller and embodies an almost-feminine aspect with its interior of lightCaen sandstone,angel in place of gargoyles,beautiful marble pillars and exquisite stone carvings.The marble pillars come from the four provinces of Ireland:green fron Connemara (Connaught), rose from Cork (Munster),black from Kilkenny (Leinster).and grey from Armagh(Ulster).There is only one stained glass window.Located in the south transept,it depicts the five graces: Fortitude, Faith, Charity, Hope, and Chastity.」 【ゴシック様式の「記念」教会ミッチェル・ヘンリーは、亡き妻マーガレットへの追悼として、壮麗なネオ・ゴシック様式の教会を建てることを依頼しました。彼が「ミニチュアの大聖堂」と呼んだこの教会は、J・フラーによって設計され、内部は明るいカーン石(Caen sandstone)で仕上げられており、全体にどこか女性的な美しさを漂わせています。ガーゴイルの代わりに天使像が配され、美しい大理石の柱と精巧な石の彫刻がその特徴です。柱に使われている大理石は、アイルランドの四つの地方から採取されたもので、それぞれの色が異なります:・緑色:コネマラ(コノート地方)<・バラ色:コーク(マンスター地方)黒色:キルケニー(レンスター地方)・灰色:アーマー(アルスター地方)ステンドグラスはただ一枚だけで、南翼廊(サウス・トランセプト)に設置されています。その窓には「五つの恩恵(グレース)」――勇気(Fortitude)・信仰(Faith)・慈愛(Charity)・希望(Hope)・貞潔(Chastity)が描かれています。】「KYLEMORE ABBEY GOTHIC CHURCH」 1.Nave – the central aisle 2.Side aisle – a passage running parallel to the nave 3.Narthex – entrance or lobby area 4.Choir – where the choir or clergy sits 5.Sanctuary – sacred area around the altar 6.Apse – semicircular or polygonal area at end of choir 7.Transept – arm of the cross-shaped church 8.Vestry – room where vestments and sacred items are kept 9.Tower – architectural feature rising above the church10.Buttresses – exterior supports to strengthen the walls11.Rose window – circular stained glass window12.Confessionals – private spaces for sacrament of confession13.Chapel niches – recessed spaces for devotional altars14.Burial vault – final resting place of Margaret Henry【カイルモア修道院 ゴシック教会 建築図解 1.身廊(ネイブ) – 教会の中央通路 2.側廊(サイド・アイル) – 中央通路と並行する通路 3.ナルテックス – 入口部分またはロビーエリア 4.聖歌隊席(クワイア) – 聖歌隊や聖職者が座る場所< 5.内陣(サンクチュアリ) – 祭壇周囲の神聖な区域 6.アプス – 半円形または多角形の後陣部分 7.翼廊(トランセプト) – 十字形平面の横部分< 8.聖具室(ヴェストリー) – 祭服や聖具を保管する部屋 9.塔(タワー) – 教会の上部にそびえる構造物10.控え壁(バットレス) – 壁の強化用外部支柱11.バラ窓(ローズウィンドウ) – 円形ステンドグラス窓12.告解室(コンフェッショナル) – 告解のための個室13.小礼拝室(チャペル・ニッチ) – 小さな祭壇のあるくぼみ14.納骨室(バリアル・ヴォールト) – マーガレット・ヘンリーの埋葬場所】「CHRIST, 2003, Kylemore Abbey, ConnemaraBronze, 130 cmRowan Fergus Meredith Gillespie is an Irish bronze casting sculptor of international acclaim. Born in Dublin to Irish parents, Gillespie spent his formative years in Cyprus.His singular often exhausting modus operandi involves taking the work through from conception to creation, entirely unassisted in his purpose-built bronze casting foundry at Blackrock, Co. Dublin. This is one of the things that makes him unique among the bronze casting fraternity.Influenced by the sculptor Henry Moore and the painter Edvard Munch, Gillespie uses the lost wax casting process to portray the whole gamut of human emotions. Having worked almost exclusively on site-specific art since 1996, Gillespie’s public works can befound in his native Ireland, Europe, the USA and Canada.Following the restoration of the Gothic Church at Kylemore Abbey, Rowan Gillespie was commissioned to create a sculpture of Christ. The sculpture was completed in 2003.The donor for this work is Martin Hart from the USA.」 【「キリスト」2003年、カイルモア修道院(コネマラ)ブロンズ像、高さ130cmローワン・ファーガス・メレディス・ギレスピーは、国際的に高く評価されているアイルランドのブロンズ鋳造彫刻家です。ダブリンでアイルランド人の両親のもとに生まれ、幼少期はキプロスで過ごしました。彼の独自で、しばしば過酷ともいえる制作手法は、構想から完成に至るまでの全工程を、ダブリン県ブラックロックにある専用のブロンズ鋳造工房で完全に一人で行うという点にあります。これこそが、彼をブロンズ彫刻の世界で唯一無二の存在とする要素のひとつです。彫刻家ヘンリー・ムーアや画家エドヴァルド・ムンクの影響を受けたギレスピーは、人間のあらゆる感情を表現するために「ロストワックス鋳造法」を用いています。1996年以降、彼はほぼすべての作品を特定の場所のために制作するサイトスペシフィック・アートとして取り組んでおり、彼の公共彫刻作品は、アイルランド国内のほか、ヨーロッパ、アメリカ、カナダでも見ることができます。カイルモア修道院のゴシック教会が修復された後、ギレスピーはキリスト像の制作を依頼されました。この彫刻は2003年に完成しました。この作品の寄贈者は、アメリカ合衆国のマーティン・ハート氏】「The Furniture MakerMichael Bell and his team of craftsmen make contemporary furniture using traditional cabinet making techniques, specialising in Irish hardwoods, which are matched for colour and grain pattern.InspirationInspired by the beautifully restored ‘Cathedral in Miniature’, the chancel pieces are simpleand well made, picking up on some of the church’s architectural details.Arched Stretchers span the underframe of the Irish elm altar echoing the ceiling’s vaultedarches; each of the altar’s four legs are composed of a trio of turned maple posts, to reflect the cluster of coloured marble columns of the church.The WoodThe contrasting timbers of maple and Irish elm were chosen for a chiaroscuro effect. As elm is becoming increasingly rare, it was felt that it would be wonderful to use it in a way that would live on.The maple tones in well with the Caen stone walls and accents the richly coloured elm.The rest of the altar furniture pays homage to the Gothic detail. The curves of the Elm candlesticks melt into each other. The celebrant’s chair features a laminated black cross in Elm, a maple frame and sculpted seat.Finally, all of the pieces are finished with six coats of oil. Each coat is buffed to a satiny sheen and allowed to dry before the next coat is applied.」 【家具職人マイケル・ベルと彼の職人チームは、伝統的なキャビネット製作技術を用いて、アイルランド産の広葉樹に特化した現代家具を製作しています。木の色合いや木目のパターンを合わせて使うのが特徴です。インスピレーション美しく修復された「ミニチュアの大聖堂(Cathedral in Miniature)」に着想を得て、内陣の家具はシンプルながら丁寧に作られ、教会建築の装飾ディテールを取り入れています。アイルランド産エルム(ニレ)の祭壇の下部にはアーチ型の補強材(ストレッチャー)が渡され、天井のヴォールト(アーチ状天井)を反映。祭壇の4本の脚は、3本ずつのメープル材の円柱から成り、教会内の色とりどりの大理石柱の束を表現しています。木材についてメープル材とアイルランド産エルム材というコントラストのある木材が、明暗表現(キアロスクーロ)の効果を狙って選ばれました。エルムは今では希少となっており、「永く生き続ける形で使えること」が大切だと考えられました。メープルの明るい色調は、教会のカーン石の壁ともよく調和し、エルムの深みある色合いを引き立てています。祭壇用家具のその他の部分も、ゴシック様式の装飾美に敬意を表しています。たとえばエルム材で作られた燭台の曲線は、互いに溶け合うようにデザインされており、司祭用の椅子にはエルム材による黒い十字の象嵌、メープルの枠、そして彫刻された座面が組み合わされています。最後に、すべての家具には6層のオイル仕上げが施されており、それぞれの層は光沢のあるサテン仕上げになるまで磨かれ、次の層を塗る前に十分に乾燥させられます。】正面には美しいステンドグラス。近づいて。上半円(バラ窓)この部分には象徴的な意匠や紋章があり、中心には子羊(Agnus Dei:神の子羊)が十字架を抱いている場面が描かれています。これはキリストの犠牲を象徴します。周囲の円には天使たちがラッパを吹いているような姿や、IHS(イエス・キリストのギリシャ語頭文字)を表す記号も見られます。近づいて。下部の縦長パネル(5つの人物像)それぞれの人物像は五つの恩恵(グレース)を象徴している。画面右から順に以下のように解釈されます:FORTITUDE(勇気) — 手に剣と盾を持ち、毅然と立つ女性像。勇気・強さ・試練に立ち向かう精神を表します。FAITH(信仰) — 聖書や十字架を掲げ、天を見上げる姿。神への信頼と確信を表す象徴的ポーズです。CHARITY(慈愛) — 子供を抱く女性。キリスト教において最も重要な美徳とされる愛(アガペー)を体現 しています。HOPE(希望) — 錨(アンカー)を手にする姿で描かれることが多く、この作品でも中央に錨のモチーフが ある可能性があります。CHASTITY(貞潔) — 白い衣をまとい、清らかさを象徴する花(たとえばユリ)などを持つ姿。純潔や誠実な 心を表します。各人物の足元にその美徳の名称(例:FORTITUDE、CHARITYなど)が明記されていた。下記写真はネットから。見上げて。<キリストの受難あるいはゲッセマネの祈り(The Agony in the Garden)を描いたもの。イエス・キリストの頭部には後光(ハロー)と十字のニンバス(神性の象徴)が。赤いマントと白い衣、そして金色の縁取りは、王としての栄光と神性、人間性を同時に表しているのだ と。新約聖書に基づく場面・「イエスによる子どもの祝福」(Blessing of the Children)この場面は、以下のような聖書の言葉に基づいているとのこと。「子どもたちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。」― マルコによる福音書 10章14節この言葉は、キリストの無垢な者への愛と、子どもの純粋さの価値を象徴しており、ステンドグラス芸術でもよく取り上げられるテーマである と。キリスト教美術における非常に象徴的なテーマである「良い羊飼い(The Good Shepherd)」を描いたもの。この図像はヨハネによる福音書10章からの引用に基づく と。「わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。」― ヨハネによる福音書 10-11この比喩は、神がすべての信者(=羊)を見守り導く存在であるという福音の核心を成す重要な象徴である と。ステンドグラスの美を満喫して外へと。紅葉時には。ネットから。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.02
コメント(0)
-

アイルランド・ロンドンへの旅(その34):カイルモア修道院(Kylemore Abbey)を訪ねる(7/9)
フォーダム・ホール(Fordham Hall)。アイルランド西部カイルモア修道院の敷地内にある文化・展示・教育のための多目的ホール。アメリカ・ニューヨークのフォーダム大学とのパートナーシップにより設立され、修道院と世界をつなぐ拠点として親しまれている と。19 世紀から 20 世紀初頭のアイルランドの生活を描いた美しい写真展示がされていた。写真中央上部には、ゴシック様式のアーチ型のステンドグラス窓があった。色は淡いパステル調(紫・ピンク・水色など)の格子パターンで、宗教施設特有の荘厳な雰囲気ではなく、柔らかく上品な印象を与えていた。光の加減によってほんのり色づいた光が室内に差し込んでいたのであった。「カラーで見る昔のアイルランド」展・(Old Ireland in Colour at Kylemore Abbey)「Old Ireland in Colourat Kylemore AbbeySpring – Autumn 2023Front HallThis exhibition celebrates the rich history of Ireland through the colourisation of historical black and white photographs from the 19th and 20th centuries.Based on the success of the bestselling book series Old Ireland in Colour by a University of Galway academic, John Breslin and Sarah-Anne Buckley, the exhibition offers a newand poignant way to consider Irish history.The first one hundred years of photography saw some of the most dramatic social, cultural and political changes in Ireland. Using cutting-edge technology to enhance and restore these photographs, a light is shone on this historical era.」【カラーで見る古きアイルランドカイルモア修道院にて2025年 春〜秋正面ホールにてこの展覧会は、19世紀から20世紀の白黒写真に色を付けることで、アイルランドの豊かな歴史を称えるものです。この展示は、ゴールウェイ大学のジョン・ブレスリンとサラ=アン・バックリーによるベストセラー書籍シリーズ『Old Ireland in Colour』の成功に基づいており、アイルランドの歴史を新たな、そして感動的な視点で見つめ直す機会を提供します。写真の歴史の最初の100年間は、アイルランドにおける社会的・文化的・政治的な大きな変化の時代でした。最新の技術を用いてこれらの写真を復元・着色することで、この歴史的時代に新たな光が当てられています。」「<1914 – Inis Mór – Gasúir ag an Gcrois in aice le(Children at Cross near) Teampall BheanainThis image is part of the Clonbrock Photographic Collection in the National Library of Ireland and was taken during a visit to the island. It shows the stub of an ancient cross and the children appear to be viewing the photographer with some wariness. We know it was taken prior to 1914 due to the absence of the twenty-one cottages.【1914年以前 – イニシュ・モア島 – テアンパル・ヴァナン近くの十字架のそばにいる子どもたちこの写真はアイルランド国立図書館のクロンブロック写真コレクションの一部であり、島への訪問中に撮影されたものです。古代の十字架の断片が写っており、子どもたちは写真家を警戒するような様子を見せています。1914年以前に撮影されたとわかっているのは、21戸のコテージがまだ存在していないからです。】「1893–1895 – Inis Mór – A Corner of Cill Éinne VillageThis first Robert John Welch photograph of Cill Éinne shows a collection of neatly thatched stone-built cottages, some of which are whitewashed. Three of the children are in a second photograph of the holy well.」【1893〜1895年 イニシュ・モア島 — キル・エンナ村の一角このロバート・ジョン・ウェルチによるキル・エンナの最初の写真には、整然とした茅葺き屋根の石造りの小屋群が写っており、一部の家は白塗りされています。ここにいる子どもたちのうち3人は、聖なる井戸の別の写真にも登場します。】 イニシュモア島またはアラン諸島の農村で撮影されたもの。上段:石造の壁や十字架のような碑、野草に囲まれた環境 子どもたちは裸足で、農作業か遊びの合間のような自然な姿 女の子たちの服装はパッチワークのようなカラフルな布地(手作りの可能性も) 1910年代ごろ下段:年配の女性が、伝統的なアイルランド西部の衣装を身にまとい座っている姿 鮮やかな赤と金の刺繍が施されたショールやドレス 白いレースのヘッドドレスと黒いボンネット 柔らかくほほえむ表情、背景は石の壁または農家の外壁 1880年代〜1900年代初頭アメリカ南北戦争(1861–1865年)時代の軍人・従軍司祭・支援者たちを写したもの前列右の2人は黒衣の聖職者のように見え、従軍牧師や司祭の可能性も。上段:アラン諸島やアイルランド西部(特にコネマラ地方)に暮らす子どもたちの歴史的な姿 20世紀初頭~中頃のアイルランド農村部の写真であろう。下段:足元を見ると、多くが裸足であることから、当時の生活の厳しさや貧困の中でも教育を 受けていた様子がうかがえます。 服装も非常に質素で、兄弟や親戚のお下がりを着ている可能性があります。「kilronan became the primary port of the island only after its two piers were developedin the late nineteenth century along with the coastguard station,the long building onthe hill in the distance.The photo was taken by Carl Wilhelm von Sydow from the deckof the MV Dun Aengus, which entered service to the islands in 1912.」 【キルロナンが島の主要な港となったのは、19世紀後半にふたつの波止場(ピア)が整備され、さらに沿岸警備隊の詰所(写真奥の丘に見える細長い建物)が建設された後のことでした。この写真は、カール・ヴィルヘルム・フォン・シードウ(Carl Wilhelm von Sydow)によって、1912年に就航したMVダン・エンガス(MV Dun Aengus)のデッキ上から撮影されたものです。】・MV Dun Aengusは、20世紀初頭にアラン諸島への連絡船として活躍した蒸気船。・Carl Wilhelm von Sydow(1881–1952)は、スウェーデン出身の民俗学者・民族誌研究者で、 アイルランドを訪れて文化や暮らしの記録も行いました と。「1883-1885 ーAran Islands ーAran Men Carrying a Canvas CurrachTaken by Robert John Welch,this image from Tra Chill Mhulrbhlgh depics men carring a four-men currach from the shore typically used for fishing.Currachs are wooden framed boats covered in tanned leather,whichi were propelled by oars.They are extremely light and fast. Until the middle of the twntieth century they would have been used mainly for transport and fishing.We can also see four currachs in the background,including the more typical three-man currach.It is part ofthe Balfour Album in the University of Galway.」 【1883–1885年 ― アラン諸島 ― 帆布舟クラカを運ぶアランの男たちロバート・ジョン・ウェルチによって撮影されたこの写真は、Trá Chill Mhulrbhlgh(トラ・キル・ウルブルフ)の浜辺で、漁業用として一般的に使われていた4人乗りのクラカ(currach)を岸から運ぶ男性たちを描いています。クラカとは、木製の骨組みに鞣(なめ)した革を張った船で、オールを使って漕ぎ進めます。非常に軽量かつ高速で、20世紀半ばまでは主に輸送や漁業に使われていました。写真の背景には、より一般的な3人乗りのクラカを含む4隻のクラカも見えます。この写真は、ゴールウェイ大学に所蔵されている「バルフォー・アルバム(Balfour Album)」の一部です】これも、アイルランド西部の伝統的な生活様式や労働の様子を写した歴史的なカラー化写真。20世紀初頭〜中頃に撮影されたもの上段:砂浜のような場所で、大勢の男女が海藻(たぶん「ケルプ」)や薪、荷物を背負うための 大きな籠(クレール/creel)を運んでいる。このような作業は、アラン諸島やコネマラ地方で 見られた海岸労働の一環で、海藻採取や燃料としての利用、また畑への肥料として 用いられたもの。下段:女性たちが海辺に立ってる。全員が伝統的なアイルランドのショール(毛織物)や スカート、エプロンなどを身につけている。 手にしているものは左手前の女性は木の枝束(たぶん燃料用の柴),右下の女性は大きな魚 (たぶんタラ),背景には港町らしき建物がぼんやりと写っており、Galway(ゴールウェイ) 湾周辺の可能性が高い.アイリッシュ・トラベラー(Irish Travellers)の子どもたちを写した写真。子どもたちが花で飾られたワゴンの中に乗っており、非常に装飾的なつくりであることから、これはトラベラー(アイルランドの移動型少数民族)の伝統的な「バード・ワゴン」(Bow-top wagon)と考えらる。中央の湖は、カイルモア修道院の前に広がるPollacapall Lough(ポラカパル湖)。湖の奥に見える白いゴシック風の建物が、Kylemore Abbey(カイルモア修道院)。背景の山はDuchruach山で、カイルモア修道院のすぐ裏にそびえる険しい山。再びフォーダム・ホール(Fordham Hall)を。アイルランド西部コネマラ地方のClifden(クリフデン)近郊にかつて存在した「マルコーニ無線局(Marconi Wireless Station)」を写した歴史的写真。写真中央に見えるのは、広大な草原に建てられたマルコーニ無線通信基地の建物群。背景には複数のアンテナ塔(無線塔)が立ち並んでいる。アイルランドの有名な劇作家・小説家 サミュエル・ベケット(Samuel Beckett, 1906–1989)。戯曲『ゴドーを待ちながら(Waiting for Godot)』、小説『モロイ(Molloy)』『マロウンは死ぬ(Malone Dies)』『名づけえぬもの(The Unnamable)』が代表作。「1940ーInis Mör-Gathering stonesThe image despicts two men and a donkey and cart lifting heavy stones and boulders for stone walls.Heinrich Becker(1907-2001),the photographer,was born in Germany in1907.By 1934 he had written a book on the Ebe boatmen of which he is one himself and had been awarded a doctorate in forkdore.He then moved to Ireland to study theIrish language, and many years to follow on the Aran Islands and in Connemara learningIrish and collecting folklore,His books are in the University's James Hardman Library.」 【1940-イニシュモア島(Inis Mór)石を集めるこの写真には、2人の男性と1頭のロバ、それに荷車が写っており、石垣を築くために大きな石や岩を持ち上げている様子が描かれています。撮影者のハインリヒ・ベッカー(Heinrich Becker, 1907–2001)は、1907年にドイツで生まれました。1934年までに、自身も属していたエーベ川の舟人(エーベ・ボートマン)についての著書を執筆し、民俗学の博士号を取得しています。その後、彼はアイルランド語を学ぶためにアイルランドへ移住し、アラン諸島やコネマラ地方で長年にわたって滞在しました。彼は現地でアイルランド語を習得するとともに、口承伝承や民間伝承(フォークロア)を数多く収集しました。ベッカーの著作は、大学のジェームズ・ハードマン図書館(James Hardman Library)に所蔵されています。】「1930-50 Inis Meain Waiting for Masshis image of a group of men waiting for mass was taken by Tomás Ó Muircheartaigh,who was a prolific and talented amateur photographer best remembered for capturing the everyday life of ordinary people living in rural Ireland, especially in Gaeltacht districts.He worked for the Department of Education for much of his life and his love of hill walking and Irish culture/language is reflected in his photographic work. A selection of his work was published posthumously in 1987 in a book titled An Muircheartach. Thank you to Deirdre Ní Chonghaile for her recommendation on the read of thewoman’s shawl and skirt.」 【1930-50 ミサを待つ男たちこの「ミサを待つ男たち」の写真は、トマス・オ・ムルヒェアルタ(Tomás Ó Muircheartaigh)によって撮影されました。彼は多作で才能あるアマチュア写真家であり、特にアイルランドの農村部に住む一般市民の日常生活を捉えた作品で知られています。とくにゲール語圏(Gaeltacht)地域を中心に活動しました。彼は生涯の多くをアイルランド教育省(Department of Education)に勤務し、山歩きやアイルランド文化・言語への愛情が彼の写真作品に表れています。彼の作品のセレクションは、彼の死後の1987年に『An Muircheartach』という書籍にまとめられ、出版されました。また、女性のショールとスカートの色の再現にあたり、ディアドラ・ニー・コンガイル(Deirdre Ní Chonghaile)の助言に感謝が記されています。】初の大西洋無着陸横断飛行を成功させた2人の英雄、ジョン・オールコック(John Alcock)とアーサー・ブラウン(Arthur Whitten Brown)を撮影した、非常に有名な歴史的記念写真。左:ジョン・オールコック(John Alcock) イギリス空軍出身のパイロット、手には飛行機の模型を持っています。右:アーサー・ブラウン(Arthur Brown)、航法士(ナビゲーター) 膝に黒い猫のぬいぐるみを抱いています(この「猫」は彼らのマスコットだったとも 言われています)。20世紀初頭のアイルランドにおける政治運動・独立運動・女性の参政権運動などを象徴する貴重な歴史的瞬間をとらえたもの。上:著名なアイルランドの英雄の葬儀や記念行事であろう。 多くの軍服姿の男性たちは、おそらくIRA(アイルランド共和国軍)または ナショナリスト部隊で、国家の独立を目指す運動であろう。下:団体名:「IRISH WOMEN WORKERS’ UNION(アイルランド女性労働者組合)」の 横断幕が掲げられています。 20世紀初頭に結成された女性による労働者運動団体で、特にダブリンの1913年ロックアウト などで重要な役割を果たしました。写真に写る女性たちは、労働運動、参政権運動、社会正義 運動に関わる勇敢な人々の姿。 上段「1962 – Inis Oírr – Bailiú ag an Stáisiún Tarrthála / Assembly at the Rescue StationFrom photographer Harold Strong: “There is a sense of purpose, of camaraderie and trust among the islanders as they gather outside the Rescue Station. These are menused to the hardships of island life, and they know that in any emergency, they mustall rely on one another.”」 【1962年 – イニシュイア島 – 救助所前での集まり写真家ハロルド・ストロングの言葉:「島民たちが救助所の外に集まる様子には、目的意識、仲間意識、信頼が感じられます。彼らは島での厳しい生活に慣れており、緊急時には互いに頼らざるを得ないことを理解しています。】下段「1962 – Inis Oírr – Húicéirí le Móin ag an gCé / 1962 – Inis Oírr – Hookers with Turf at the Pier.From photographer Harold Strong: There is no source of fuel on the island. Here the winter fuel, turf (peat)、is brought from the mainland by the traditional Galway Bay Hookers as was done for generations.This trade died out with the arrival of bottled gas.」 【1962年 – イニシュイア島 – 桟橋に着いたターフ(泥炭)を運ぶフッカー船写真家ハロルド・ストロングの言葉:「この島には燃料となる資源がありません。ここでは、冬の燃料であるターフ(泥炭)が、伝統的なゴールウェイ湾のフッカー船によって本土から運ばれてきていました。何世代にもわたって続けられた習慣です。この輸送手段は、ボンベ入りガスの登場とともに廃れました。】アイルランド西部・沿岸部における人々の生活と信仰、そして海とのかかわりを象徴的に伝えるもの。上段 子どもたちや女性たちが一堂に会してカメラに向かっている集合写真。 背景には、を中心とした宗教的な祭壇が壁に組まれており、装飾や絵画、植物 などで美しく飾られている。これはアイルランドにおける「祈りの窓(holy grotto)」や 「マリア様の家内礼拝所」の一種で、各家庭や村の路地などにしばしば設けられてきたもの。下段 伝統的な木製の小舟(カラフなど)を操る漁師たちが、荒波を越えて海から帰還している様子。 背景には汽船が見え、時代が19世紀末~20世紀初頭の過渡期であろう。 「1896 Athens agus 1906 James Brendan ConnollyThe first medal of the first modern Olympic Games in 1896 was in the hop. skip and jump (or triple jump)in track and field and was taken by a young lrish-American,James Brendan Connolly with a jump Of 44ft11.in.He would also win a silve rmedal in the high jump andbronze in the long jump. ConnoIIy was born in South Boston to parents who had emigratedfrom lnis Mor.His father worked on the Boston docks and after leaving school, moved to Savannah,where he worked in the engineering corps of the Marines before returning toBoston and enrolling at Harvard where he focused his attention on athletics. After the Olympics, he volunteered to fight in the American-Spanish Civil War and was one of thefirst ever war correspondents. He would go on to be a famous writer. His life is the subJect of a documentary An Chéad Laoch narrated by Seosamh O Cuaig.In the TV miniseries First Olympics,he was portrayed by David Caruso.」 【1896年アテネ大会と1906年 ― ジェームズ・ブレンダン・コノリー1896年の近代オリンピック最初の大会で最初に授与されたメダルは、陸上競技のホップ・ステップ・ジャンプ(三段跳び)でのものでした。このメダルを獲得したのは、アイルランド系アメリカ人の若者ジェームズ・ブレンダン・コノリー(James Brendan Connolly)で、記録は44フィート11インチ(約13.7メートル)でした。彼はこの大会でさらに、走高跳で銀メダル、走幅跳で銅メダルも獲得しています。コノリーは、アラン諸島のイニシュモア(Inis Mór)から移民した両親のもと、ボストン南部で生まれました。父親はボストンの港湾で働いており、彼自身は学校を中退したのちサバンナ(ジョージア州)に移り、海兵隊の工兵隊で働いていました。その後ボストンに戻り、ハーバード大学に入学し、陸上競技に専念しました。オリンピック後、彼は米西戦争(アメリカ・スペイン戦争)に志願兵として参加し、史上初期の戦争特派員の一人となりました。その後、彼は著名な作家として活躍しました。彼の人生は、『An Chéad Laoch(最初の英雄)』というドキュメンタリーで取り上げられ、セオサム・オ・クアイグ(Seosamh Ó Cuaig)がナレーションを務めました。また、テレビのミニシリーズ『ファースト・オリンピックス』では、デヴィッド・カルーソ(David Caruso)が彼を演じました。】「1893ー1895 Inis Mor The Young Firbolgs」 「1893ー1895 Inis Mor The Young FirbolgsA large gloup of children. both boys angirls, mostly facing the camera. They are standingin front of a cottage whose partially whitewashed gable is visible. Many of the girls are wearing white of the boys are wearing traditional Aran knittedclothing. PhotographerRObert Welch's use of word 'Firbolgs' reflects antiquarian ieas of the ancestry of islanders.」【1893–1895年 イニシュモア島「若きフィルボルグたちたくさんの子どもたち(男女)が写っており、その多くがカメラの方を向いています。彼らは、部分的に白く漆喰が塗られた切妻壁のあるコテージの前に立っています。多くの女の子は白い服を着ており、男の子の多くはアラン諸島伝統の編み物衣装を身にまとっています。写真家ロバート・ウェルチ(Robert Welch)がこの写真に「フィルボルグ(Firbolgs)」という言葉を用いたのは、当時の古代史観(antiquarian ideas)において、アラン諸島の住民が古代ケルトの部族「フィルボルグ族」の末裔であるという見方を反映したものでした。】 暖炉(マントルピース)。彫刻が施された重厚な木製パネル 暖炉を囲むこの壁面装飾は、ヴィクトリア朝時代のゴシック・リバイバル様式を色濃く反映。中央に掲げられた鹿の剥製(トロフィー) 狩猟が貴族のたしなみとされていた時代の名残で、こうしたトロフィーはイギリス・ アイルランドの邸宅では定番の装飾。乾燥草(パンパスグラス)による装飾反対側から。2種類の案内が。「Owns Beautiful Kylemore Castle ... But will live in America and learn the duties of a Railway Clerk"WILLIAM ANGUS DROGO MONTAGUE NINTH DUKE OF MANCHESTERLord of Kimbolton Castle and Tandragee Castle is to become a railway clerk in Detroit,USA.This decision was announced by President Eugene Zimmerman of the Cincinnati,Dayton and joint lines. Mr. Zimmerman went further into his plans for his SON-IN-LAW and let it be known that the duke is to be trained for the great responsibilities of the management of a large railway.IRISH INDEPENDENT NEWSPAPER, THURSDAY 4 MAY 1905This was just one of Mr. Zimmerman’s failed attempts to curb the duke’s reckless ways in the hopes that he would be a loyal and useful husband to his daughter Helena, the Duchess of Manchester.」【「美しきカイルモア城の所有者... だがアメリカに渡り、鉄道事務員としての職務を学ぶ予定」ウィリアム・アンガス・ドローゴ・モンタギュー 第9代マンチェスター公爵キンボルトン城とタンドラギー城の領主である彼は、アメリカ・デトロイトで鉄道事務員(レールウェイ・クラーク)になる予定でした。この決定は、シンシナティ、デイトンおよび共同鉄道のユージーン・ジマーマン社長によって発表されたものです。ジマーマン氏はさらに計画を進め、自らの義理の息子(=公爵)が、大規模鉄道の経営に関わる重大な責務を担うよう訓練されることを明らかにしました。『アイリッシュ・インディペンデント』紙 1905年5月4日(木)付この一件は、ジマーマン氏が放蕩者であった公爵を更生させ、彼を忠実で有能な夫にしようとした試みのひとつでした。彼の娘であるヘレナ(マンチェスター公爵夫人)にとって、良き伴侶となることを願ってのことでした。】 「KYLEMORE CASTLEFROM THE MANCHESTERS TO THE BENEDICTINE NUNS1900MARRIAGE in London of the DUKE OF MANCHESTER to American heiress, HELENA ZIMMERMAN1903The Duke and Duchess PURCHASE KYLEMORE CASTLE FOR £63,000. They begin major refurbishments1910EUGENE ZIMMERMAN, Helena’s father takes over the mortgage to relieve the couple’s money problems1914The Duke and Duchess leave Kylemore and the castle is sold to property speculator Earnest Fawkes who sells it seven years later in 1920 to the Benedictine Nuns for a cost of £45,0001920With the arrival of the nuns KYLEMORE CASTLE becomes KYLEMORE ABBEY」 【カイルモア城マンチェスター公爵家からベネディクト会修道女たちへ1900年マンチェスター公爵がアメリカ人大富豪の娘、ヘレナ・ジマーマンとロンドンで結婚。1903年公爵夫妻がカイルモア城を6万3,000ポンドで購入。大規模な改装に着手。1910年ヘレナの父ユージーン・ジマーマンが、夫妻の金銭問題を救うため住宅ローンを肩代わり。1914年公爵夫妻はカイルモアを離れ、不動産投機家アーネスト・フォークスに城が売却される。フォークスは7年後の1920年に、ベネディクト会の修道女たちに4万5,000ポンドで売却。1920年修道女たちの到着とともに、カイルモア城は「カイルモア修道院(Kylemore Abbey)」へと生まれ変わる。】このプレートは、カイルモア城の所有者がどのように移り変わり、修道院となったかを簡潔に「The Manchester Family’s Coronation and Parliamentary RobesLate 19th centuryCoronetThis coronet has been worn by members of the Manchester family at coronations,such as that of King Edward VII in 1902, King George V in 1911, and Queen Elizabeth II in 1953.While members of the British nobility were given standardised robes to wear to coronations, their title or rank was indicated by their coronet. A Duke’s coronet has eight strawberry leaves set on top of a silver-gilt band, fitted round a red velvet cap. The coronet is trimmed with ermine, which is the winter coat of a stoat. At the top of the cap is a tassel made of fine gold wire.Parliamentary RobesThe robes were made by Ede & Son (renamed Ede & Ravenscroft), thought to be the oldest tailor in London. This business developed a relationship with the Royal Family, providing robes and tailoring for coronations, as well as making robes for clergy, government officials, and legal and academic professionals.Parliamentary robes, such as this one, were made of a scarlet wool material and trimmed with bands of miniver (a generic term for squirrel fur used in this period). The high band came from the winter coat of a northern European red squirrel. Each band of fur is3 inches (7.62 cm) wide and 5 inches (12.7 cm) long and square-shaped.Similar to the coronet, parliamentary robes indicate the rank of the wearer. This robe wasmade for a Duke, whose title was shown through the number of fur bands and the spacing between them: the highest number possible. Those made for those of lesser rank, such as Marquess, Earl, or Viscount, have fewer bands of fur.ProvenanceThe robes and coronet went missing in the mid-1950s following the death of the 10thDuke of Manchester. They were rediscovered by Lord Nicholas Monckton, a younger son of the Manchester family, stored in the attic of a cottage in Hampshire. He undertook conservation work and gave them on long-term loan to Kylemore Abbey. They are now on display for the first time in decades.Lord Nicholas requested the help of Kylemore Abbey in obtaining and preserving these robes and coronet, and the Abbey is honoured to have these objects on permanent exhibition for the next six years.【マンチェスター家の戴冠式・議会用礼服19世紀後半冠(コロネット)についてこの冠は、マンチェスター家の人々が以下のような戴冠式で着用したものです:1902年のエドワード7世、1911年のジョージ5世、1953年のエリザベス2世。イギリス貴族が戴冠式に着用する礼服には共通仕様がありますが、冠(coronet)によって身分が示されました。公爵(Duke)の冠には、銀鍍金の帯の上にイチゴの葉が8枚飾られ、その下に赤いビロードの帽子があり、毛皮(白鼬の冬毛)で縁取られています。帽子のてっぺんには、金の糸で作られた房飾りがついています。議会用礼服についてこの礼服はロンドン最古の仕立て屋とされる「Ede & Son(後にEde & Ravenscroft)」によって製作されたものです。同店は王室との関係を築き、戴冠式用の衣装や、聖職者・官僚・法曹・学術関係者のための礼服を手掛けてきました。このような議会用礼服は、スカーレット(深紅)のウール地に、ミニヴァー(この時代にはリスの毛皮を意味)で縁取られています。使用されている毛皮の帯は、北ヨーロッパのアカリスの冬毛で、各帯は約7.6cm幅・12.7cm長の正方形です。冠と同様に、礼服の毛皮の帯の本数と間隔によって身分が示されます。この礼服は「公爵(Duke)」用で、可能な限り多くの帯が使われています。侯爵(Marquess)、伯爵(Earl)、子爵(Viscount)などの下位の貴族用では、帯の数が少なくなります。来歴この礼服と冠は、マンチェスター公爵第10代の死後、1950年代中頃に所在不明となっていましたが、後にマンチェスター家の一員であるニコラス・モンクトン卿によって、ハンプシャーのコテージの屋根裏で再発見されました。彼は保存修復を行い、これらをカイルモア修道院に長期貸与しました。ニコラス卿の要請により、カイルモア修道院はこれらの保存と展示に協力し、今後6年間の常設展示として展示されることになっています。】アンティークのガラス扉付きキャビネット(飾り棚)。彼らは19世紀末から20世紀初頭頃の服装(スーツ、蝶ネクタイ、ボーラーハット)をしており、1人は釣り竿を持っていることから、おそらく釣りや狩猟に関わるスタッフまたは地主と従者という構図だと考えられます。背景の木製ドアや蔦の絡む外壁は、カイルモア修道院(元邸宅)の敷地内にあった建物の一部かもしれません。このような写真は、ヴィクトリア朝~エドワード朝時代のレジャー文化や、貴族のアウトドア活動(釣り、狩猟)の一端を伝えるものです。「When Mitchell Henry purchased the land at KYLEMORE, he also gained extensive FISHING and SHOOTING rights. Members of the OUTDOOR STAFF included the gamekeeper, beaters and ghillies.」 【ミッチェル・ヘンリーがカイルモアの土地を購入したとき、彼は広大な漁業権と狩猟権も同時に得ました。屋外業務のスタッフには、ゲームキーパー(狩猟管理人)、ビーター(獲物を追い出す係)、ギリー(釣りや狩猟の手伝いをする従者)などが含まれていました。】右:Mother Magdalena FitzGibbon 左:Mother Abbess Maire Hickey ともに20〜21世紀の修道院長(アッベス)で、修道院の精神的・運営的リーダーを務めた人物。聖ベネディクトゥス(Saint Benedict)をかたどった木彫りの像。ズームして。右手には司牧杖(パストラル・スタッフ)を持ち、教会の指導者であることを象徴。足元には書物とカラスが彫られており、これは聖ベネディクトゥスの伝説に基づくシンボル。書物=「聖ベネディクトの戒律(Rule of Saint Benedict)」カラス=彼が毒を盛られたパンをカラスに持ち去らせたという逸話を象徴。「Explore the Estate」のMAPを再び。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.08.01
コメント(0)
全38件 (38件中 1-38件目)
1
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- ついでの2泊3日・6県ぐるっと旅 …
- (2025-11-19 12:00:07)
-
-
-

- あなたの旅行記はどんな感じ??
- 帰路へ 楽しい旅ももうおしまい
- (2025-11-16 22:43:16)
-
-
-

- ヨーロッパ旅行
- ヨーロッパ土産の小物を見て、フラン…
- (2025-10-28 17:31:03)
-







