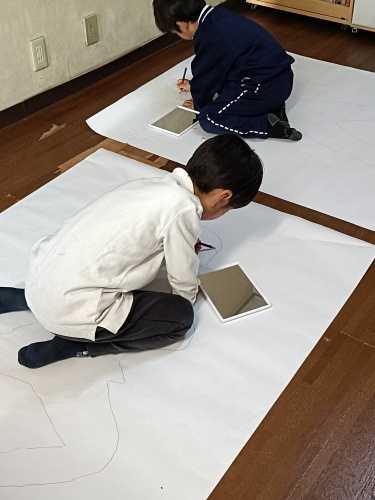2020年03月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-

【休校期間お役立ち情報】その8 自宅で取り組む「未来への投資」
長らくこのブログで書いてきた「休校期間お役立ち情報」。今日が年度末の3月31日ということで、ひとまず今日を区切りとしたいと思います。そういうわけで、突然ですが、最終回。室内でできることで、まだ書いていなかったオススメを書いていきます。 これまでの記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて ▼【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない ▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう ▼【休校期間お役立ち情報】その4 ゲームから現実へつなげよう ▼【休校期間お役立ち情報】その5 やっていいこと、悪いこと ▼【休校期間お役立ち情報】その6 録音・録画したものをネットや放送で発信する ▼【休校期間お役立ち情報】その7 自宅で楽しく長時間取り組める教材 ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ これまでの記事では意図的に、漢字や計算のドリル学習のようなものは取り上げてきませんでした。今回が最終回ですが、やっぱり取り上げません。(^^;)というのも、想定外の長期休みでしかも行動制限がかかる中、子どもたちには「ダカラコソ、デキルコト」に取り組んでほしいと思っているからです。学校で毎日やっていたようなことと同じことをやるのもいいのですが、せっかくだから、全然違うことをやってみたら?というふうに思っています。想定外のことは長い人生、これからも起こると思います。そんなとき、どうするか。時間ができたなら、腰を据えて、これまでにはできなかったチャレンジをしてほしい。マイナスをプラスに変える。ダカラコソ、デキルコトを探して、取り組む。それは、未来の自分への投資であり、未来の社会への投資です。大人だったら、どうでしょう。「時間があったら、やりたいなあ」と思っていることには、何があるでしょう。弾けなかった楽器を弾けるようにする、とか、ステキですね。観たかったけど観れていなかった映画を観る、というのも、いいかもしれません。(今はAmazon Prime Videoなどで、名作がとても観やすくなってますし。。。) 読書にふけるのも、いいと思います。何をやりたいかは、人によって違います。自分で、見つける。普段だったら、自分で見つけなくても、言われたことをやっていれば、済んでいたわけです。それが、やるべきことが、一気になくなる。何をしていいか、わからない。暇だ。・・・人生には、そういう時間も必要です。自分で探して、自分で取り組む。うちの子は、今日は、ウクレレを弾いていました。調弦が狂っていたので、ピアノの音と聴き比べながら合わせる方法を教えてあげました。フレット1つ分がピアノの半音にあたることも教えて、ドレミの弾き方も教えてあげました。ただ、それをふまえて、これからも練習するかどうかは、本人次第です。時間をどう使うか。大人にとっては大問題であるこのことを、子どもたちも考えることができたのは、チャンスかもしれません。この時間を、ぜひ、生かしてほしいと思います。・・・自分で見つけることが大事、なんてことを書いておいて、前回の最後には「他の教材の紹介は、また次回!」と予告していたので、矛盾してますね。一応、参考までに、「こんなんあるよ」というのを、最後に書いておきます。基本的には、うちの子にさせたものを中心に紹介していきます。もしもやってみたいものがあれば、やってみても、いいかもしれない。(1)認知トレーニング系『わざわざ買いたい!!! てんつなぎ』(ワニのあそび知能本シリーズ)(わざわざ買うほどうつくしいてんつなぎ制作委員会、878円、2020/2/27)「点つなぎ」というのは、どういうわけか、子どもに大人気です。無料のものをネットでとってきてもいいのですが、タイトルに「わざわざ買いたい」とあったので、買ってみました。タイトルの付け方がうまいです。(笑)最初が20までの点つなぎ、最後は200までの点つなぎなので、難易度は低め。小学校低学年が取り組むのにはベストでしょうか。うちの子は思いっきり小学校中学年ですが、それでも、夢中でやっていました。やる前に予想して、やっていくうちに予想が覆るのが、面白かったようです。オールカラーで背景が凝っていて、無料で印刷できるネット上の点つなぎとは、確かに違います。初歩の点つなぎとしては、おすすめ!『漢字てんつなぎ』4月号(マイウェイ出版、662円、2020/2/19)これも夢中で取り組んだ点つなぎ。大人用の点つなぎ雑誌ですが、点をつないでいるうちに漢字熟語が出てくる。子どもが習っていない漢字が出てくる可能性もありますが、ノープロブレム。習っていない漢字が出てくるくらいの方が、挑戦意欲が刺激されるようです。点をつないだ後は、漢字を丁寧に書いて、懸賞に応募します。当たれば現金がもらえるとあって、嬉々として取り組みます。山ほど問題が入っているので、たくさんやれば、もしかすると、当たるかもしれません。『大きくて見やすい数独初級編 目にやさしいからサラサラ解ける!』数独も、子どもが夢中になるパズル。推理力も鍛えられて、いいんじゃないでしょうか。1つできると、次もやりたくなるという、中毒性があるようです。やめられない止まらないのかっぱえびせんのようです。気づけば、時間が、あっという間に過ぎているかも?『算数と国語を同時に伸ばすパズル(入門編) 考える力試行錯誤する力が身につく 小学校全学年用』 [ 宮本哲也 ]推理問題や数独など、考える力を鍛える教材。考えることが好きな子が、さらに考える力を伸ばすことになる禁断の本。ただ、もともと「勉強好き」な子でないと、厳しいかもしれない。これらのほかにも・・・DSなどでできる「脳トレ」「英語トレーニング」も、ゲームを通して楽しくトレーニングできるので、僕は、好きです。(2)楽器演奏系音楽は一生の趣味になりますので、この機会にやってみると、いいんじゃないでしょうか。学校で使っている鍵盤ハーモニカやリコーダーを家で練習すれば?と思わないでもないですが、子どもは学校で習っていない楽器をやりたがります。♪ウクレレ安くて取り組みやすい。ギターと違って指が痛くならない。適当に弾いていても、なんか楽しい。(笑)というわけで、オススメです。今から買う方は、下のサイト様などが参考になります。▼子供用の可愛いウクレレおすすめ5選!独学でも弾けるようになるの? (「ウクレレ初心者のすすめ」様)教則本は、たとえば、以下のようなものがあります。コード2つで弾けるようなのが、簡単でいいです。『「コード2つ」から弾けるやさしい曲がいっぱい!ウクレレで一緒に歌おう♪こどものうた』ただ、要注意なのは、コード1つやコード2つの曲は、収録曲の中でも、かなり少ない。コードをいっぱい使う曲も、けっこう載っているので、ほとんどの曲は、弾くのがわりと大変です。 ♪キーボード(ピアノ)楽器の王様と言えば、やはり、ピアノでしょうか。うちの子たちは、ピアノを習ってますが、やはり、遊びで弾く方が、楽しいようです。カシオ 電子キーボード ブラック/グリーン SA-46 [SA46](税込3259円)安いのに使い勝手がいいという、スグレモノ。一家に一台!カシオ計算機 電子キーボード LK-512(32,780円)カシオの電子キーボードは、光ナビゲーションがついていて、弾く鍵盤を教えてくれます。いろんな曲が弾けるようになるスモールステップが工夫されていて、素晴らしい。次の記事も参考になります。▼実は37年間進化してきた! カシオ「鍵盤が光るキーボード」の楽しさ大解剖 (価格.comマガジン2018/12/3)なんか、かなりかたよった紹介だったように思いますが、このへんでおわります。僕と趣味が似通った人には、「おっ♪」と思えるものも、あったかもしれません。では、毎回恒例の、最後のメッセージを。今回が、本当の、最後になります。 悪い点にばかり過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 今の世の中、いろんな手段でいろんなことが可能ですよね。 ダカラコソ、デキルコトのほんの少しの例を示させてもらいました。何かしら、参考にしていただけるところがあったなら、幸いです。
2020.03.31
コメント(0)
-

【休校期間お役立ち情報】その7 自宅で楽しく長時間取り組める教材
「休校期間お役立ち情報」の続きです。今回は、第6回で予告したとおり、室内でできることを取り上げていきます。 これまでの記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて ▼【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない ▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう ▼【休校期間お役立ち情報】その4 ゲームから現実へつなげよう ▼【休校期間お役立ち情報】その5 やっていいこと、悪いこと ▼【休校期間お役立ち情報】その6 録音・録画したものをネットや放送で発信する ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ 東京、大阪、神戸など、大都市を中心に自粛要請が出ています。人口密集地の場合、普段はどこに行っても人がいるので、こういう場合、行動制限がハードにかかるので、つらいですね。では、自宅で過ごす場合、どんな工夫ができるか。第4回「その4 ゲームから現実へつなげよう」で、少しゲームのことを取り上げました。基本的にはゲームの中でも、長時間かけて創意工夫できるものや、時間をかけて思考力や粘り強さを伸ばしていけるものをオススメします。マインクラフトやドラゴンクエストビルダーズ、将棋や囲碁ですね。ネット対戦については、将棋や囲碁のネット対戦なら、個人情報の流出をさほど気にすることはありません。チャットができるものもありますが、しなくてもいいわけですし・・・。ネットとはいえ、対人戦は、やはりやりがいが違います。身近に遊び相手がいない場合、コミュニケーション主体ではなくあくまでも一緒にゲームをすることが主体のネットゲームであれば、いいのではないか、と思っています。インターネットを利用する場合、やはり子どもであれば子ども用のサイトを利用したい。代表的なのは、Yahoo!きっず。▼https://kids.yahoo.co.jp/教科の学習もできるし、ゲームもできるし、調べ物もできる。漢字にふりがなをつける機能があるのも、うれしい。教科学習は、NHK for School と連携。ハイクオリティな教育番組の動画にすぐにアクセスできます。ネットを使わせたくない家庭も多いと思います。その気持ちは、よく分かります。そこで、ネットを子どもに使わせない場合も考えてみます。大きく分けて2つあります。(1)テレビやパソコンは使うけど、ネットは使わせない場合(2)テレビも含め、デジタル機器自体を使わせない場合では、いってみよう♪(1)テレビやパソコンは使うけど、ネットは使わせない場合運動不足解消もかねて、運動系ゲームとか、いかがでしょう。ゲームの中で運動するのではなく、実際に体を動かすタイプのゲーム。実は、そういうジャンルがあることが、あまり知られていない。(^^;)たとえば、エポック社の「エキサイトピンポン」。▼エポック社 卓球やろうぜ! エキサイト ピンポン 体感ゲーム - アマゾンちょっと古いんですが、小学校の特別支援学級の教材として活用されていた例もあります。ホントにラケットを振らないといけないので、いい運動になります。注意集中や反射神経も鍛えられますよ。エポック社の体感ゲームは、卓球以外にも、いろいろ出ています。▼体感ゲーム (エポック社)(Wikipedia)ただ、かなり以前の商品なので、今は中古でないと買えないと思います。特別なゲームを買わなくても、今あるゲーム機のソフトでも、いわゆる「フィットネス系ゲーム」というのがあります。任天堂のゲーム機 Wii や Switch でいくつかのソフトが出ています。その分野の先駆けとしては『Wii Fit』が有名ですね。中古市場価格は暴落しており、楽天で調べたら72円からとビックリ価格でした。Wiiをすでに持っているなら、この機会に買ってもいいかもしれません。【中古】【表紙説明書なし】[Wii]Wii Fit(ウィーフィット)(ソフト単品)(2)テレビも含め、デジタル機器自体を使わせない場合マインクラフトみたいにでっかい建物をゲームの世界上に作る代わりに、レゴとか紙工作で作る方が、手先も器用になって、いいかもしれません。(^^)レゴはいろいろ出ていますし、マニュアル通りに組み立てた後は、崩してオリジナルのものを作ることができるので、オススメです。「ピタゴラスイッチ」が好きなら、この機会にピタゴラ装置を作るなんて、考えただけでワクワクしちゃいますね!レゴでピタゴラ装置的なものを作るには、次のようなものがあります。▼カラコロピタン! レゴブロックで作るからくり装置(ポプラ社) ▼【送料無料】Lego Chain Reactions レゴ チェーンリアクションズ(完全日本語マニュアル付き) 【レゴ ギミック カラコロピタン 自作 ピタゴラスイッチ 本 連鎖 装置 LEGO 作り方】(すでにレゴブロックを持っている人向け。上の商品だけですべての装置が作れるわけではありません。)紙工作も、なかなかすごいのが作れたりします。「ペーパークラフト」で検索すると、ネット上でデータがとれるので、自宅のプリンターで印刷すれば安上がりです。(^^;)以下のようなまとめサイトもあります。▼休校のお供に。ペーパークラフトが無料ダウンロードできるサイト50 有料の場合、有名どころで人気なのが、「小学館の図鑑NEOのクラフトぶっく」シリーズ。うちの子どもたちも、2年くらい前(小学校低学年の頃)はかなり熱中して作っていました。公式サイトの対象年齢は、3歳から中学年向けとなっています。確かに、それくらいの年齢層を幅広くカバーしているかな、という気がします。簡単なものはかなり簡単だけど、難しいものはかなり作りがいがあります。 ちなみに、うちの息子は、折り紙でスゴイ作品を作り続けています。今は、ゴジラを折るために超巨大折り紙をほしがっています。仕方ないのでネットで注文してあげたところです。世の中には1辺が60cmという巨大折り紙が売っているって、皆さん知ってました?折るのにとんでもなく時間がかかりそうですが、とんでもなくスゴイものができそうです。もっと大きな教育折り紙60cm6色組(1) 暖色7-801【松田商店】一方で、娘は折り鶴オンリーで、なぜか千羽鶴を作っています。まあ、千羽鶴も、時間をかけて取り組まないといけないという意味では、いいのかもしれません。何のために千羽鶴を折っているのかが、謎なのですが。(笑) さて、僕が最後に書くことは、毎回同じです。 臨時休校等の悪い点にばかり過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 デメリットばかりでもないですし、今の世の中、いろんな手段でいろんなことが可能ですよね。 今回は、室内でできるいろいろなことを紹介しました。 皆さんのお役に立つところが少しでもあれば、うれしいです。長くなったので、他の教材の紹介は、また次回!
2020.03.30
コメント(0)
-

【休校期間 特別編2】 卒業式で歌えなくなった歌を動画配信
昨日のブログ記事で【休校期間お役立ち情報】その6 録音・録画したものをネットや放送で発信する<と書きました。そして今日、自分でも実際にやってみました。明日の卒業式で歌うはずだった合唱曲「大切なもの」。6年生が大好きだったこの歌を、1人で歌ってYouTubeで公開しました。勤務校だけでなく、卒業式で合唱が歌えなくなったすべての学校の子どもたちに、気持ちが届けばいいな、と思います。
2020.03.22
コメント(0)
-

【休校期間お役立ち情報】その6 録音・録画したものをネットや放送で発信する
「休校期間お役立ち情報」の続きです。 これまでこのブログで取り上げてきた「休校中の外遊びの保障」は、ずいぶん世間で行われるようになってきたように思います。今回からは、室内でできることを取り上げていきます。 これまでの記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて ▼【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない ▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう ▼【休校期間お役立ち情報】その4 ゲームから現実へつなげよう ▼【休校期間お役立ち情報】その5 やっていいこと、悪いこと ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ 僕は音楽教育に関心があるので、たまに『教育音楽』という学校の音楽の先生向け月刊誌を買っています。最新刊の4月号(3月18日発売)を読むと、なんと!今回の長い休校をふまえて、新年度の最初にどうするか2ページだけですが、そんな内容が、書かれていました。「かつてない春を迎えて」(東京都府中市立府中第四中学校 横田純子主幹教諭、 『教育音楽 中学・高校版』2020年4月号 p56-57)『教育音楽 中学・高校版 2020年4月号』 音楽之友社休校は2月末に突然決まったので、それを踏まえて原稿を書いて4月号の印刷締め切りに間に合わせるとは、すごい。雑誌印刷前に急遽原稿を書き直して差し替えられたのだと思います。今回、全国の先生たちが一番気にしているのは、まさに、このこと。よくぞタイムリーに4月号に間に合わせて載せていただいた!と感動しました。その文章の中で横田先生は、「卒業式や入学式で歌うはずだった曲を歌って、それを録音して昼休みの放送で流せたらいいな、と思っています。」と書かれています。飛沫感染のおそれから、式の中で歌を歌うのをとりやめる学校が頻発している現在、子どもたちの「届けるはずだった思いのやり場」はどうしたらいいのか・・・と思っていただけに、このアイデアには、なるほど!と思いました。歌えなかった歌がある子どもたちの思いに寄り添った、横田先生の愛を感じました。横田先生はその後、「人と人が接触できないのであれば、ネットや放送、何らかを介して伝えるしかない」というご自身の考えを書かれています。僕も、同じことを思っていました。というわけで、今回はネットや放送の利用についてです。前回紹介した文部科学省の休校期間特設サイト▼新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応についてには、全国の取組事例も掲載されています。その中には、次のような取組事例が載っていました。「在校生による合唱や吹奏楽部による演奏は、休業に入る前に事前に録音し、卒業式で流すことで卒業生を祝福。」(学校の臨時休業の実施状況、取組事例等について【令和2年3月19日時点】 スライドp4より)これは、卒業式の事後ではなく事前に録音する取組ですね。そういう学校もあったようです。ただ、卒業式前に在校生が登校できたとしても、未履修の授業をするだけで時間がかかった学校が多く、卒業式前に在校生の歌を録音できた学校は少数派ではないかという気がしています。文科省の取組事例報告には、先生たちによる放送の例もありました。「箕面市のコミュニティFM放送に、市立小学校の先生が出演し、メッセージやアドバイスを生放送で伝える。放送した音声は、放送後2日以内にYouTubeチャンネルにアップされるので、聴き逃した場合やもう一度聴きたい場合でも改めて聴くことが可能。」(学校の臨時休業の実施状況、取組事例等について【令和2年3月19日時点】 スライドp5より)箕面市の先生方からのメッセージは、YouTube上で、たとえばこんなふうに公開されています。このご時世、すでにあるインフラを使って、思いを伝えられるというのは、かなりありがたいですね。ただ、公共のインフラだと、一部の人しか思いを伝えられないと思うので、全員に保障しようとなると、一人一人が一人一人に電話で話す、ということになるのかな、と思います。学校のホームページに各担任から児童生徒向けのメッセージを載せている学校もあるようです。メール連絡網が整備されている学校であれば、メールでメッセージを送っているところもあるでしょうね。事例としては大人から子どもへ、というものが多くなりますが、中には、子どもの側からの発信もあります。▼子ども対話教室Y&B (YouTubeチャンネル)上のリンク先の各動画では、小学生が先生役になったり、本の紹介をしたりしています。臨時休校でできた時間を使って社会に発信をするというのは、もしかすると有意義な時間の使い方かもしれません。不特定多数へのネット配信については、大人が管理・監督するべきだと思いますが、学校ではどうしても受け身になりがちだった子どもたちが、自主的に取り組んだ成果を、広く世の中に知らせる活動をするというのは、非常に有意義だと思います。僕は以前、国語の教科書の朗読をYouTubeで公開したことがあります。こんなふうに、著作権の切れた教科書教材の音読を録音してYouTubeで公開することも、いいかもしれませんね。ネットや放送の利用については、個人情報の漏洩や、気づかずに他者の権利を侵害するおそれなど、いろいろなことに気をつけなければいけません。しかし、うまく使えば、出会えないけどつながれる、という大きなメリットも期待できます。YouTubeは不特定多数向けだけでなく、限定範囲での公開もできるようです。時間をかけて完成させた動画をネットを通じて他の人に見てもらえれば、休校による不全感解消にかなり役立てるかも!?僕が最後に書くことは、毎回同じです。 臨時休校等の悪い点にばかり過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 デメリットばかりでもないですし、今の世の中、いろんな手段でいろんなことが可能ですよね。 今回は、「できることをしよう」と意欲的に取り組んでおられる事例を紹介しました。皆さんのお役に立つところが少しでもあれば、うれしいです。
2020.03.21
コメント(0)
-
【休校期間お役立ち情報】その5 やっていいこと、悪いこと
「休校期間お役立ち情報」というシリーズ(?)の続きです。 前回からかなり久しぶりの更新。その間に、学校が再開されたところもあり、休校期間中に登校日があったところもあります。そしてもうすぐ春休み!休みから休みへという・・・学校に行かない日が続く状況になっています。状況は変わってきているところもあるし、変わっていないところもあります。今だからこそ、「やっていいこと、悪いこと」というテーマで、休み中の行動基準みたいなものを確認していけたら、と思います。 これまでの記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて ▼【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない ▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう ▼【休校期間お役立ち情報】その4 ゲームから現実へつなげよう★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ ★ ~ 文部科学省は、休校期間に「Q&A」を随時更新しています。以下に記載する内容は、基本的には文部科学省の▼新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応についてに通知関係のリンクがまとめてありますので、そこからの情報になります。このシリーズの第3回の時のコメント欄に書きましたが、最初、文部科学省は次のように言っていました。「新型コロナウイルスの感染の拡大を防止するための臨時休業の措置であるという趣旨を児童生徒に理解させ,人の集まる場所等への外出を避け,基本的に自宅で過ごすよう指導すること」(2月28日付の文部科学省の通知)これをふまえ、おそらく全国のほとんどの学校で、「外出禁止」に近い指導があって、休校期間を迎えたものと思います。ただ、3月4日の時点で「一斉臨時休業中の児童生徒の外出について」の通知が新しく出ました。休校中の子どもたちの「外出」について、どう指導するか について。(1)軽い風邪症状(のどの痛みだけ,咳だけ,発熱だけなど)でも外出を控えること。(2)規模の大小に関わらず,風通しの悪い空間で人と人が至近距離で会話する場所やイベントにできるだけ行かないこと。以上の2点が示されました。この時点で、外出自体を控えるように指導するわけではない、というふうに変わってきていました。「Q&A」の項目で言うと、「問2 学校が臨時休業でも、児童生徒が外出したら効果がないのではないか。」がこれに当たります。3月4日の通知が回答に含まれたほか、追記として次のようなことも書かれています。「児童生徒の健康維持のために屋外で適度な運動をしたり散歩をしたりすること等について妨げるものではなく、感染リスクを極力減らしながら適切な行動をとっていただくことが重要であると考えています。」他の子と混じって一緒に遊ぶことも含めて、健康な子どもが外で遊ぶことについては、特に問題ないということが、周知され始めたと言えます。そして3月17日、「Q&A」には春休みの子どもたちへの指導内容が掲載されました。基本的には3月4日の内容と同じです。問57 春季休業期間中の過ごし方として児童生徒にどのように指導すればよいか。指導内容は、以下の3点。・咳エチケットや手洗いなどの基本的な感染症対策を徹底すること。 ・風邪症状がある場合には外出を控え、やむを得ず外出する場合には、マスクを着用すること。 ・集団感染の共通点は、特に、「換気が悪く」、「人が密に集まって過ごすような空間」、「不特定多数の人が接触するおそれが高い場所」であるため、換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることを避けること。僕が赤字にしたところが、特に重要なところではないかと思います。つまり、健康な子どもにずっと家の中で過ごせということはなく、外で運動することはOKということです。校庭や体育館を運動のために開放することについても別のQ&Aで示されました。(問45 春季休業中に学校の校庭や体育館、公共スポーツ施設を開放して運動の機会を提供すること )文部科学省のQ&Aは更新も頻繁でとってもありがたいのですが、項目がどんどん増えてきて、目的のものを探すのが少々大変になってきているのが難点です。世間は相変わらずコロナ騒ぎが続いており、外国でもすごいことになっています。ただ、次の丹波新聞(3月12日付)の記事のように、恐れすぎず、気をつけるべきことを知りつつ、過剰反応をしないことが大事です。▼専門医「感染者も被害者」 風評と差別懸念「検査する人出なくなる」 勇気出した検査に感謝 新型コロナ初確認受け兵庫県丹波市の医療センター長は症状が出ないのに受診して感染確認をしてくれた市内初めての感染者に感謝し、過剰に感染者を怖がることが検査を受けようとしなくなることにつながることを戒めています。僕が最後に書くことは、毎回同じです。 悪い点に過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 ウイルスよりも風評被害のほうがよっぽど怖い、ということもよく聞きます。ウイルスを過剰に怖がって子どもたちを外に出さないこともいけないし、確証のないことで怖がったり、感染者を犯罪者のように見てしまうこともいけない。良識ある大人としての対応をし、落ちついて過ごしましょう。 冷静さを失って、パニックになるのが、一番おそろしいです。 まわりが落ち着きを失っているときこそ、どうか落ち着いて行動してくださいね。
2020.03.20
コメント(0)
-

【休校期間 特別編】 3.11をむかえるにあたって
日本中のほとんどの学校が休校中の中、9年目の3.11を迎えます。 自分の子には、前日の晩の今日、 「明日は震災の番組をテレビでするだろうから、観てみたら?」 「明日の14時46分には黙祷をしたらどうか」 という提案をしました。 あまり気乗りしない感じだったので、どうするかは分かりませんが・・・ ただ、やはり特別な日だと思いますので、できればこの日ぐらいは、9年前の震災に思いをはせてもらいたいと思います。 昨年、初めて東北を訪れました。 被害の大きかった大川小学校にも行きました。 2020年3月10日の今日、 産経新聞さんが大川小学校の映像記録をYouTubeで公開されています。 ご遺族のお話を聞いたり、当時の詳しい話が載っている本を読んだりしていたので、映像を見ながら、胸が詰まりそうになりました。 まともに観ることができませんでした。 子どもたちの学校生活の跡が、そこかしこに感じられました。 震災は、楽しかった学校生活を、突然に断ち切ってしまったんだな、と思いました。 多くの子どもたちの命が失われました。 本当に残念でなりません。 現在、新型コロナウイルスが猛威を振るっています。 その中で、感染者はどこの誰か、という情報が、とびかっています。 震災後、福島から避難した子どもたちが「放射能がうつる」などと周りに言われて差別されることが起こりました。 今、同じようなことが起きていないか、と大変心配しています。 非常事態という意味では、今も9年前も同じです。 冷静さを失い、思いやりを忘れて、軽率な言動をとってしまわないように、 風評被害を広めたり、感染してしまった方の人権を無視してしまったりすることのないように、 みんなで気をつけていきたい、と思っています。 震災後に、被災地に向けて、多くの歌が作られました。 学校で歌われる歌の中に、「一つの明かりで」という曲があります。 「COSMOS」「地球星歌」で知られるミマスさんが作曲されました。 YouTubeの動画に、この曲ができるまでの経緯を子どもたちが説明し、その後みんなで合唱するものがあります。 これは、全国の子どもたちにぜひ観てほしいと思います。 僕はこの曲が好きで、自分が受け持った子どもに、授業中に歌って聞かせたこともありました。 歌詞も、曲も、本当に、じんと、心にしみます。 動画の再生数がまださほど多くないのですが、もっともっと多くの人に観てもらいたいです!! (2020/3/10時点での再生数は384回でした。公開日は2019/10/7。 こんな素敵な動画を公開していただいたことに感謝します!) 3.11については、過去のブログでも少しふれています。 以前僕がブログで取り上げたのは被災地小学生の作った「ファイト新聞」です。 小学生が震災のことを知るのに、同じ小学生の目線からのメッセージはすごくよく伝わるだろう、と思いました。 この本には僕の住んでいる町の図書館で出会いました。 もし図書館で借りることができたら、この機会にぜひご家庭で読んでほしいと思います。 ▼東日本大震災の避難所で小学生が始めた壁新聞『ファイト新聞』 (2019/3/31の日記より) 『宮城県気仙沼発!ファイト新聞』 [ ファイト新聞社 ] 本来なら3.11の日に各学校で震災に関する学習や追悼式などが予定されていたと思います。 休校でそれらが全くなくなってしまい、代わりのものも何もないとなると、大変残念なことだと感じています。 休校でも、休校だからこそ、 この日には子どもたちに、改めて3.11について、自分なりに学んでほしいと思っています。 身近な大人の方々、もしよかったら、お子さんにここで書いた内容の一部でも紹介していただき、東日本大震災についての話を、一緒にしていただけたら、うれしいです。
2020.03.10
コメント(0)
-

【休校期間お役立ち情報】その4 ゲームから現実へつなげよう
最近、「休校期間お役立ち情報」というテーマで、記事を書いています。 今回が、第4回。内容は第3回からつながっています。 (これまでの記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて ▼【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない ▼【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう) 第3回で、「普段外に出ていないうちの子たち。 休日は無人の場所を探して遊ばせています。」という話をしました。先週は川に行ったので、昨日は山に行きました。場所は、綾部市の天文館パオの横。大きなローラー滑り台と、山小屋のような休憩所があり、トイレは天文館のトイレが使えます。あまり知られていない穴場です。ここのローラー滑り台はとても素晴らしい!それ以外にも、「野山で遊ぶ」というのがお手軽にできるのがおすすめポイントです。うちの子どもたちは何回か来たことがありますが、今回はすべり台よりも、木の枝を拾ったり、自然のもので遊ぶ方が、面白かったようです。で、こっからが本題です。3月になってから、うちの子どもたちには、あるゲームをさせていました。テレビゲームは平日はできないので、休日だけですが、ソフトは僕が「これがいい」と思ったものを買っています。3月から導入したゲームソフトとは、マインクラフト(マイクラ)のドラクエ版『ドラゴンクエストビルダーズ』。【中古】 ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ /PS3▼メーカー公式サイトこのゲームの中で、主人公が「ひのきのぼう」を装備し、地面を壊して素材を集めます。そして、使いすぎた「ひのきのぼう」は、やがて壊れてしまいます。子どもたちは昨日、実際の野山の中で、同じことをしていました。棒を拾って、「ひのきのぼうやー」。棒で地面をほじくって、「石炭でてきたー」「ここは粘土やー」ゲームでやっていたことを、現実でも、楽しそうに、やっていました。「子どもがゲームにハマってる」っていうのは、普段は悪い意味で使われることが多いですよね。ゲームにハマると、ゲームの世界だけでなく、現実の世界でも、同じことをやってみようとします。これは、悪い影響を受けて実際にやっちゃう場合もありますが、いい影響を受けることも、少なからずあります。ゲームの世界で家を建てていると、現実世界でも特製ノートにオリジナルの家の設計図を描いたりします。それって、かなり素敵なことだと思います。(だからこそ、たとえゲームの世界であっても、人を傷つけるようなゲームはさせたくない、と思っています。)僕はゲーム大好きなので、ゲームを子どもたちにさせるのは悪いと思っていないのですが、いろんなゲームが世の中にはあるので、何を選ぶかは、かなり気にしています。個人的な考えですが、教育的効果が高いゲームというのは、次のようなものだと思っています。(1)学習ゲーム(お勉強をそのままゲームにしたもの)(2)脳トレ系ゲーム(認知トレーニングを含む)(3)頭の中で作戦を考えるもの(囲碁、将棋、パズル等)(4)自由に考えて創作できるもの(プログラミング系、マインクラフト等)あまり学習が前面に出たものは子どもが嫌がることが多いのですが、「マインクラフト」だったら今子どもたちに大流行しているということもあり、食いつきがいいだろう、と思いました。本家マイクラではなくドラクエ版を買ったのは、僕の趣味ですが・・・。休校期間中のおすすめゲームとしては、囲碁・将棋もおすすめです。「どうぶつしょうぎ」はスマホアプリ版が無料でできますし、ルールも簡単なので、小さい子にもおすすめ。大きい子には、この機会にぜひ本将棋のルールを覚えて、ネット上でいろんな人と対戦してみてほしい、と思っています。「将棋倶楽部24」という老舗のネット将棋サイトがあり、これも無料で使えます。レーティングという本人の成績の数値が上下するので、やりがいがあります。囲碁・将棋の場合も、コンピュータ対戦でルールを覚えたら、対人戦で駆け引きとかコミュニケーションも覚えてほしいと思います。ゲームの世界から次第に現実の世界に広げていく。ゲームが「きっかけ」になって、現実の豊かな体験につながれば、と思います。 僕が最後に書くことは、毎回同じです。 悪い点に過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 ウイルスのことも、しかり、ゲームのことも、しかり。「ゲームばっかりしてる」というのを悪いふうに捉えるだけでなく、いい方に捉えることも、できるかもしれませんよ。日常生活で、できる範囲で気をつけてさえいれば、過剰にウイルスを恐れる必要はありません。 冷静さを失って、パニックになるのが、一番おそろしいです。 まわりが落ち着きを失っているときこそ、どうか落ち着いて行動してくださいね。
2020.03.08
コメント(0)
-

【休校期間お役立ち情報】その3 子どもたちの外遊びを保障しよう
このところ、「休校期間お役立ち情報」というテーマで、記事を書いていきます。今回が第3回です。(これまでの記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて ▼【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない)「恐れすぎない」の続きですが、具体的にしていきたいと思います。つまり、どこまでならOKなのか?ということです。基準が明確でないと、際限なく恐れすぎることにつながってしまいます。たとえば、今回の休校に際し、各学校は子どもたちにこんな話をしているようです。「夏休みや冬休みとは違います。不要不急の外出をしてはいけません。 友だちとは遊べません。家で過ごしてください」これは、果たして、家に閉じこもれということでしょうか?家に閉じ困らないと、ウイルスに感染するのでしょうか?外に出ただけで?・・・そんなわけは、ないはずです。前回引用した情報の中にも、「空気感染はしない」というものがありました。換気しない室内にいる方が危ないのです。僕は、自分の子には「散歩には出てもいい」と言っています。「健康な者が、家の中に閉じこもっている方が、病気になる」と話をしました。考え方は人それぞれですが・・・。ただ、実際には散歩に行っておらず、家の中で暴れているようです。せめて、親が付き添える休日には、親の責任で一緒に外へ出て、運動させてやりたいと思っています。僕は普段から、土日のうち1日は、クルマで田舎の方へ出かけ、誰もいない広いところを見つけて遊ばせるようにしています。別に誰もいない必要はないのですが、田舎住まいなので、クルマで少し行けば、誰もいないところはいっぱいあります。都会住まいの人は、少人数で屋外で遊ぶ分には、それでもOKだと思います。子どもを家の中に閉じ込めておいたときの子どもたちのストレスは、容易に想像がつきます。子どもは元来、動きたがるものです。平日の親がいないときに我慢しているなら、その分はどこかで発散させてやりたいと思います。先週の週末は、誰もいない田舎の公園に行ってきました。田舎であれば、誰もいない公園というのは、わりとあります。駐車場に全くクルマがないのを確認してからとめて、川べりを走ったり歩いたり木切れを拾ったり、岩の上をぴょんぴょん跳んだり。 先週行った場所は丹波篠山市の遠方、ふるさとの川公園。駐車場と公衆トイレがあるところから、川と野原と展望台にすぐ行けて、手軽に自然が満喫できました。川沿いを歩くと、向こう岸に大きな竹林が広がっていて、鳥のさえずりが聞こえました。少し行くと、飛び石を使って向こう岸に渡れるようになっていました。渡った先は、とっても広くて、高いところには、展望台までありました。初めて行きましたが、とてもいいところでした。子育て歴10年の経験からいうと、田舎であっても人工の遊具が整備された公園は、他の子と一緒になる確率が高いです。狙い目は自然に近い公園。川沿いは特に狙い目で、田舎の川はところどころ下りられるようになっています。ただし子どもだけの川遊びは危ないので、保護者の見守りは必要です。僕はいろいろ探検するのが好きなので、子どもを連れて誰もいない自然の中で遊ばせることがたまにあります。地図にも載ってないような穴場で言うと、丹波市の下滝駅の近くに、川のそばに下りれるところがあり、そこもめったに人が来ないところでした。名前は、一応、太田井堰というのが名前かな。行ったのは2ヶ月くらい前ですが。田舎の川沿いを歩くと、上の写真のように、たまに下りられるところがあります。上の写真の右側に映っている階段を降りると、下のようなところに出ます。丹波竜の化石が出たところのすぐ近くです。この場所からも、化石が出たのかも知れません。太古の恐竜時代から続く、ロマンを感じました。感染症にかかるかかからないかでいうと、少しくらい人がいても、屋外で距離1m以上離れていれば、大丈夫でしょう。そこまで「誰もいない」にこだわらなくてもいいと思っています。冒頭にも言いましたが、室内よりも屋外の方が、感染しにくいのですから。僕は神戸市に住んでいた経験も長いですが、阪神間の場合はわりと山が近くにあるので、山の方がおすすめかもしれません。六甲山の山歩きとかは、ほとんど人に出会わなかった記憶があります。ちょこっとだけ散歩するにしても、おすすめです。休校中の外遊びの保障は、都会の方がニーズが高いと思います。神戸市では、外遊びをさせてくれる団体に助成金が出るそうです。▼休校中の子どもの外遊び支援 神戸市、活動団体に助成(神戸新聞NEXT) リンク先の記事にある神戸市長の意見「感染拡大に配慮した上で、健康な子どもが少人数で屋外で過ごせる環境を提供することが重要ではないか」という意見に、僕は賛成です。というか、子どもたちが黙ってずっと家の中や屋内施設の中でおとなしくしていられるのは、限界があります。外遊び支援は、これからどんどんニーズが高まってくるでしょうね・・・。今回の記事はこれで終わりです。あくまでも個人のブログの個人の見解なので、事情によっては変わってくると思います。子どもたちの外遊びをどう保障するかは、それぞれでまた考えていただければと思います。「普通の公園で、子どもが集団で遊具で遊ぶのは、OKなのか?」ということについては、僕はOKだと思っていますが、地域の実情によっても、変わってくるかと思います。基準はいろいろな要素で変わってきますが、神経質になりすぎるのもどうか、と思っています。 僕が最後に書くことは、毎回同じです。 過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 できる範囲で気をつけてさえいれば、過剰にウイルスを恐れる必要はありません。 冷静さを失って、パニックになるのが、一番おそろしいです。 まわりが落ち着きを失っているときこそ、どうか落ち着いて行動してくださいね。
2020.03.07
コメント(2)
-

【休校期間お役立ち情報】その2 恐れすぎない
昨日に続き、「休校期間お役立ち情報」というテーマで、記事を書いていきます。(昨日の記事は、こちら↓ ▼【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて) 第2回目は、恐れすぎないことについてです。僕は、これが一番大事なことだと思っています。リスクに備えることは大事です。しかし、恐れすぎる必要はありません。自己啓発の名著に、カーネギーの『道は開ける』があります。イライラしたり怒ったり、悲しくなったり、やるせなくなったり・・・そういった心理状況から、冷静に落ち着いて行動できるよう、導いてくれる好著です。『道は開ける 文庫版』(デール・カーネギー著、香山晶訳、創元社、2016、700円+税)この中に、次のような記述があります。====================・平均値の法則に照らして、自分の悩みが正当なものかどうかを判断し、いつまでもくよくよしている態度を改めれば、悩みの9割は解消できるに違いない。(p104より)・世界で最も著名な保険会社――ロンドンのロイズ保険組合――は、まれにしか起こらない出来事を気に病むという人間の性質を利用して莫大な富を築き上げた。(p105より)====================「平均値の法則に照らして」というのは、つまり、それが実際にどの程度の割合で起こりうるのか、データにあたってみなさい、ということです。頭の中だけで考え始めると、心配の種が、どんどん膨らんでしまいます。人間は、「まれにしか起こらない出来事を気に病む」という性質があるのです。私たちは、そのようにできているのです。それが本当にどこまで気に病むに値するものかは、しっかりと調べておかなくてはいけません。本書の中に、小児麻痺が大流行したときの実際のエピソードがでてきます。この状況は、今とかなりよく似ています。長くなりますが、以下に引用します。====================・私たちは万全の用心だけはしました。 子供たちを人込みから遠ざけ、学校や映画館へは行かせませんでした。 衛生局に問い合わせて過去の記録を調べると、カリフォルニアで小児麻痺が最も猛威をふるった時でさえ、それに冒された子供は州全体で1835人にすぎないとわかりました。普通の場合は2、300人とのことでした。 これは悲しい記録には変わりありませんが、平均値の法則に当てはめてみると、子供がそれに冒される確率はごく小さなものでしかないという気になりました。 『平均値の法則から見て、まず起こりえない』。 この言葉によって私の悩みの90%は消え去りました。 (p108より)====================カーネギーは、人間は心配すぎる傾向があるので、冷静になるよう呼びかけています。もちろん、今回のコロナウイルスについては、未知のことがたくさんあるので、現時点のデータだけで、楽観視することはできません。ただ、専門家は過去に感染症が大流行したときのデータも含めて、根拠に基づいた予想をしているはずです。私たちはそういった情報を受けながら、現実的にどう行動するか、冷静に考えなければなりません。 カーネギーが『道は開ける』の原著を出したのは1948年ですから、普遍的な人間の性質を扱っているとはいえ、現代を生きる我々には古すぎると思われるかもしれません。そこで、今回のコロナウイルスについての「恐れすぎない」対応について、僕の地元の新聞が取り上げていた内容も、紹介したいと思います。最近は全国紙の多くのページがコロナウイルス関連の記事に費やされています。しかし、僕はこの件については地域によって対応策が違うと思っています。そのため、地域密着型の地元の地域新聞の記事が、かなり参考になりました。以下は「丹波新聞」(2020年3月5日)の記事です。====================・今回のコロナウイルスは、症状のない人でも感染源になるという厄介な特徴を持つ。しかし一方、空中感染はしない。肺炎で死亡する高齢者もいるが、ほとんどの患者は回復する。(具体例略)感染者が広がると言っても、累積していくわけではない。 普段から十分注意自重しつつ、過剰に恐れはすまい。(一面の「丹波春秋」より)====================僕はこれを読んで大変安心しました。引用からはカットしましたが、途中の具体例に説得力があり、感染者が出ても収束に向かっているところの数字を見せられたことが大きかったです。丹波新聞そのものにWeb版はありませんが、一部の記事はWebでも読めます。Web上で読める記事として、専門医の見解も載せています。▼感染症専門医「そう怖くない」 新型コロナ、8割は「風邪かなぁ」 最新情報触れても評価変わらず (「丹波新聞」公式サイト)丹波市内に新しくできた県立丹波医療センターの専門医の見解。僕は、信用できると思います。 前回の最後に書いたことを、もう一度書きます。 過剰反応をせず、落ち着いて行動してください。 できる範囲で気をつけてさえいれば、過剰にウイルスを恐れる必要はありません。 冷静さを失って、パニックになるのが、一番おそろしいです。 まわりが落ち着きを失っているときこそ、どうか落ち着いて行動してくださいね。
2020.03.06
コメント(0)
-

【休校期間お役立ち情報】その1 マスクについて
新型コロナウイルスによる突然の休校で、現場は大変混乱しています。子どもたちが、少しでも安心・安全に過ごせたら、と思います。たくさんの情報があり、それらを整理して提供するサービスもあちこちで見かけます。このブログも、少しでもお役に立てたらと思います。休校期間が解除されるまでは、「休校期間お役立ち情報」というテーマで、記事を書いていきます。なお、記載する情報については、「自分で実際にやってみた。その結果、いいと思った」という基準で掲載します。正しいか正しくないか、自分もやってみるかみないかは、それぞれの判断でお願いします。あくまでも個人のブログですので、「ホントかな?」と思ったら、ご自身でも調べてみてくださいね。では、今回の第1回目は、マスクについてです。(1)マスクの付け方Facebookで教えてもらったのですが、僕はマスク、長年間違ってつけてました。ゴムの継ぎ目を口の側にしていたのですが、逆だったようです。それを知ってからは、ゴムの継ぎ目がある面を外にしています。そして、ワイヤーのところを、外側に折っています。そうすると、ちょうど薄紙のところが鼻の頭にきます。こうすることで、つけたときに、メガネがくもりにくくなるのです。マスクをしているとメガネがしょっちゅうくもるのですが、少しでも対策ができてよかったです。(関連リンクその1)▼【マジかよ】マスクの正しい着け方は? メーカーに聞いてみた結果 → ずっと “逆” に着けてた疑惑が浮上(ロケットニュース24)(関連リンクその2)▼【検証】マスクの上部を折るとメガネがくもらないのは本当なのかやってみた(youpouch.com 田端あんじさんの記事)(2) マスクの効力全国的にマスクが品薄ですね。マスクはかけないよりはかけたほうが安心ですが・・・人混みの中に行かない限り、ウイルスにかからないための効果は、さほどでもないらしいです。田舎暮らしで人混みに行かずに普通に生活できる人は、そこまで必要ではない気がします。もちろん、せきやくしゃみなどが出る人が、病気を他の人にうつさないようにするためには、マスクは効果あり。花粉症の人も、マスクがいりますね。必要な人にマスクが行き渡るようになれば、と思います。(関連リンクその3)▼【マスクの正しい着用方法】付け方と外し方、手順が大事です(ハフポスト 中崎太郎さんの記事)※19:30の予約投稿でいったん公開しましたが、1つだけリンクを追加します。(関連リンクその4)▼感染予防にマスク着用不要 過度の使用控えてとWHO (日本経済新聞)このシリーズの最後には、毎回同じことを書こうと思います。それは、過剰反応をせず、落ち着いて行動してくださいということ。できる範囲で気をつけてさえいれば、過剰にウイルスを恐れる必要はありません。冷静さを失って、パニックになるのが、一番おそろしいです。まわりが落ち着きを失っているときこそ、どうか落ち着いて行動してくださいね。また明日の19:30に第2回を公開します。
2020.03.05
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1