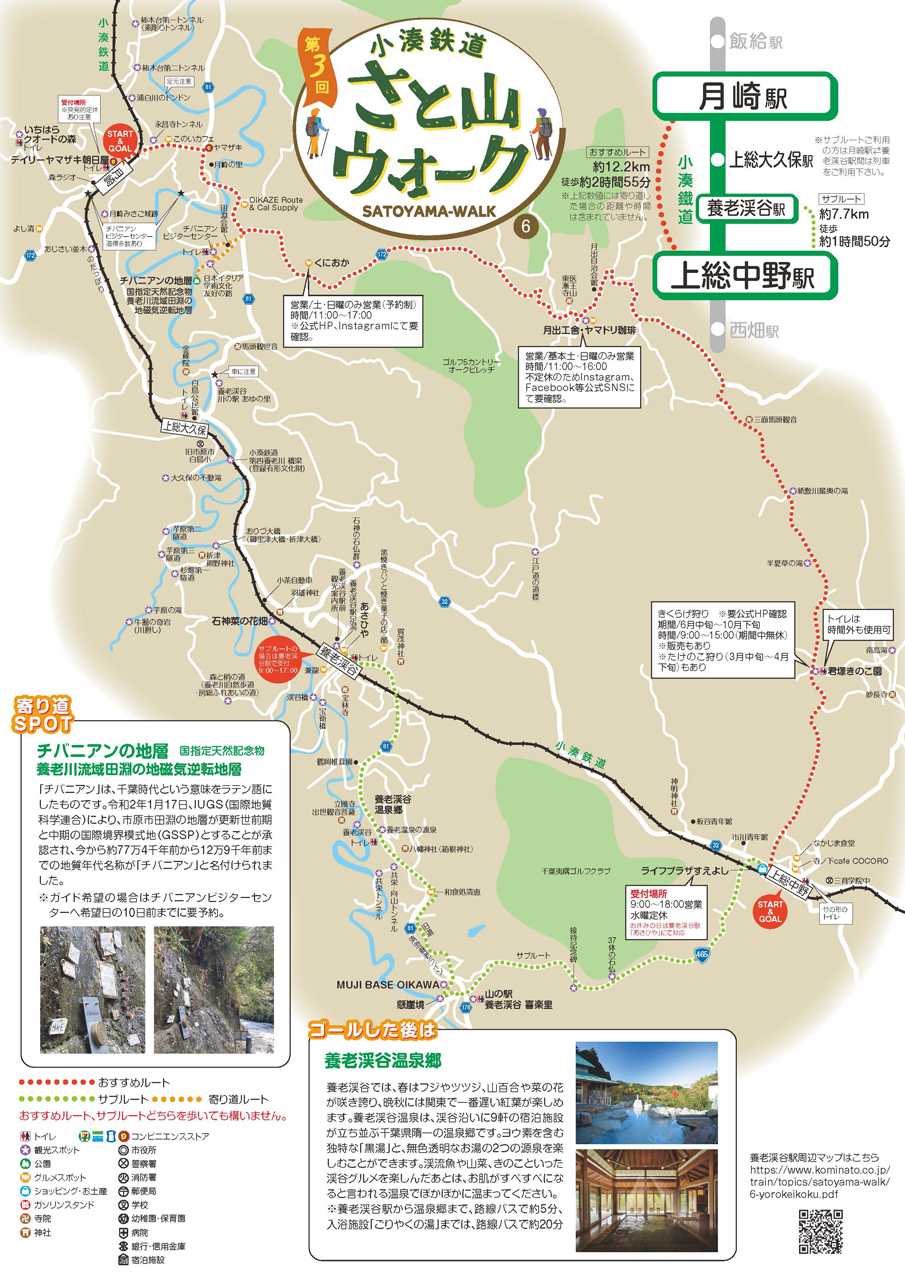2003年09月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
好きなことは国境を越える
教会での式は久しぶりだった。改めて聞く生の賛美歌はとても心に響いてジーンときた。きっと参加者全員が同じ想いだったに違いない。そのせいもあってか、披露宴も楽しくも感動的なもので、出席できた喜びが込み上げて来た。「唄っていいなぁ」とシミジミ。皆で聞き入れば、なんか共通体験をしたような感覚になる。ちょうど、アーティストのコンサートはその典型だろう。以前、北京に行った時、「滝沢くんって知っている?」「宇多田ヒカルは聞いている?」…と、現地のスタッフから聞かれてビックリした。思い出すのは、北京での休日に王府井(東京で言えば銀座)をブラブラして楽器屋を見つけて入った。大きな楽器屋さんで様々な国のギターがあった。「弾いてもいいよ」とスタッフが声をかけてくれたので、学生時代の記憶を頼りにちょっとだけ弾いた。すると、さっきのスタッフたちが飛んできて「今のはカシオペアだろ?朝焼けっていう曲だよね、確か…」と声をかけられてビックリした記憶がある。「知っているの?」「もちろんだよ。凄くうまいよね。日本のフュージョンは最高だね」と。その晩、近くの居酒屋でスタッフ3名と飲んで語り合った。語り合ったと言っても韓国人、北京人、東京人、なので、共通語はない。片言の中国語、英語、日本語のつぎはぎの会話。「朝焼けという曲は、イントロのギターがいいね。チャラララッスチャッチャチャチャーン…とね」などで、「チャ」とか「ウンチャ」とか擬音が飛び交う会話になる。けれど、話題が音楽だとそれでも通じるから不思議だ。そう言えば、ピカチュウも、「ピカチュウ」「ピカッチュウ」とかで、基本的にはピカチュウで世界をまたにかけている。そう考えると凄い存在である。世界中の子供達が「ピカチュウ」で遊んでいると思うと、世界共通語を作ったのはピカチュウだ。英語を話せない子供達もピカチュウはわかる。これはもう「ノーベル平和賞」でもあげて頂きたい。そういう子供対たちが大人になった近い将来の外交では、多少難しい局面には「ピカチューの精神で話し合おう」でお互いに席につけるようになるかもしれない。21世紀は文化産業の世紀で、それはどのくらい人類に影響を与えていくのか?興味が尽きない。明日はいよいよ北京。今度はどんな体験があるのか?楽しみです。インターネットがつながりますように!
2003/09/28
コメント(3)
-
上海@ランチのフライングディナーIN池袋
楽天が再会のツールになるとは思っていなかった。ので、素晴らしい広場だなぁと噛み締めた一日だった。その中で考えたこと。思い出したこと。●世界中で好きなことを仕事にできる人数は何人くらいいるのだろう?ma-meitさんの仕事も僕の仕事も世界中では100万人もいないかもしれない…。アジア諸国ではどうか?お隣韓国では…、中国では…、北朝鮮では…、多分、僕たち日本人の方が選択肢多いのだろう。「職業は自由に選んでいいよ…」という国に生まれたのだからやっぱり選んで生きていこう。●日本は素晴らしい国だこれだけ世界(特にアメリカから)しゃぶられても、国民は普通に生活できる。90年代に金融で相当しゃぶられたが、それでも皆生きている。自動車も持っているし、マンションも買える。(まぁ、貧血は起こしたが…)戦後、諸外国への借金を完済した唯一の国で、その後はただひたすら貸している。首相がかわっても関係ない(あんまり)。他国ではトップがかわるとお国の事情が相当かわるが、日本は誰が首相になっても淡々と生きていく。自動販売機でタップリ商売ができる。これは凄い。誰も盗む人がいないからできるビジネスだ。しかも24h営業で稼げる。この分野ではダントツである。実際は、世界でもっとも学歴の関係ないビジネス社会が完成した。他国はまだまだごく一部である。などなど、たくさんある。●起業しようとする人たちの熱意と気迫は凄い。…ということは、人は起業しようとすると本気を出すのではないか?でも、もし今いる企業の中で同じくらいの本気を出したらどうなったのであろう?ひょっとして、好きなことをやらせてくれたのではないか?そう考えると、企業家精神というのは真の自立心のことであって、会社を辞めることとイコールではない…。なんでもかんでもアメリカの真似ではいけない。事情が全く違うから。ということで、日本経済復活のポイントは2つあると思った。一つは、才能ある人々が新たな事業を起こしていくこと。もう一つは、皆、社内企業家モードで本気になること。そして、より強い企業になること。どっちか向いている方を選べばよい。本気であればどっちでもきっと楽しい。●セミナーは面白いが、1:1は楽しい僕の場合は、セミナーや研修に参加するのは好きというか趣味みたいなところがある。しかし、せっかく楽天で知り合った人と1:1で会うのも楽しい。(ランチではなくディナーオフ会?でした)「みなさん、はじめまして」ではなく「所長さん、こんにちは」になる。お互いが主役だ。最近、セミナー講師の仕事が多かったので、とても新鮮な感じがした。<接近戦>の醍醐味というやつだろう。これからも少数の接近戦をしたいなぁと。積極的に。(どなたか…やりましょう…接近戦を…気軽にね!)●上海を舞台にやりたいこと宣言!…をma-meitさんに言ってしまった。本当は「上海@ランチ」で言おうと思っていたんだけど…。(のむてつさん、フライングしてしまいました。今度ちゃんとお話しします)とても素敵なお店を予約してくれて…さすがフードコーディネーターですね。ma-meitさん。謝謝!!
2003/09/27
コメント(2)
-
好きなことを仕事にしよう!
好きなことを仕事にする場合、起業するあるいは独立するのがよいのか?社員のままでいいのか?の論議になりがちだ。しかし、実は会社にいた方ができる場合もたくさんあるし、独立しした方がいい場合もある。これは人ぞれぞれだし、やりたい仕事による。つまり、社長がいいか?社員がいいか?はやりたい仕事次第…という見方もある。仕事によって決まるもので、どっちが正しいとというのはない。ただし、経営の仕事がしたければ起業するべき…となる。僕の場合は、好きなこと優先だったからどっちでもよい。約10年前、やりたい仕事が明確だったから、偶然お誘いがあった時にすぐに引き受けて入社した。もしなかったら、自分でやっていたかもしれない。だからあまりお金にならないことも多々あって、会社の経営が苦しい時は、その仕事に関わる経費を全部自分で払って(立替えて)でも仕事をやった。(しかし、実際は数百万円だから結構度胸がいる)そういう時はすぐに「独立すれば?」とアドバイスを頂く。知人友人からは「おかしいんじゃないの?」と言われたが、まぁ本人がやりたかったんだから大目にみて頂きたい…と。この場合の報酬は、まさに「体験を買った」ということになる。一般的には、投資はお金を出して働くのは別の人だが、この場合は、お金も自分で出して仕事も自分でやる。そして、体験も丸々自分のもの。そういう意味では大きな投資である。しかし、その体験のお陰で次があるのも事実で、本人が了解なら何も問題はない。そういうのが、中国の仕事まで広がって行ったから、そろそろ回収に入っているのかもしれない。今にして思えば、完全に社内企業家だった。ようするに、企業でも通用するし、いざとなれば独立もできる、起業もできるだけの「その道での実力」を磨いて行きたい…といことでいいんじゃないかなぁと思っている。何しろ、実力があればどっちにころんでもあまり痛くないし…。僕の場合は、好きなこと最優先できたし、これからもそうするつもり。このプロジェクトの期間はある企業の業務契約社員で、次のこの仕事は自営で受けている…という人も周りに出てきた。しかし、これはあくまでも「実力がある人」の話。それに、好きなことを仕事にしたらもう一切の言い訳はきかない。そのジャンルで生きていく覚悟が必要で、10年も20年もやってから他のジャンルに手を出せるはずもない。「あれもできます」「これもできます」では生きていけない。天才は別として、凡人はニッチの達人を目指すしかない…と思う。起業を目指すのもいいが、肝心なのは実力のはずで、実力があれば、起業したり、契約したり、あるいは大手に引き抜かれたり巨大な仕事ができたり…と選択肢が無限に広がって、楽しい人生が待っている。「好きなことを仕事にする」場合の人生設計はこうなる。つまり、本当の意味でネットワーク社会に対応できる人になろうということで、僕もそれを目指していますよ…というのが本音。目指すは「七人の侍」に選ばれるような人になること!たまにはお金を払ってでもやりたい仕事、好きな仕事をしよう!
2003/09/26
コメント(6)
-
リピーター97%の先の世界とは…
リピーター率が90%を超えるとどんな変化が起きるのか?を見ていくと大変面白い。働いていた側の目線から見ていくと、これまた色々な発見がある。近年、ディズニーランドのサービスが「下がった」というようなコラムやHPを見かける。その点も注意して見てみることもテーマだった。結果として、昔と比べて特に下がっていませんよ…と判定!心配しないで頂きたい。別にヒイキ目には見ていません。ただ、何度か訪れたゲストがそう感じることはあるだろうなというのも理解できる。なぜか?というと、最初の10周年くらいまでは、ゲストが初めて、あるいは2~3回目くらいの方々が多いので、「すみません、○○はどこですか?」「これはどこで食べられるんですか?」「パレードは何時から?」「フィルムはどこで売ってますか?」とわからないことだらけであった。だから、従業員はいつもフル稼働で、忙しかった。いつもゲストの役に立っている感触を毎日十分に実感できた。ところが、リピート率97%の世界に突入すると、もうあまり困っている人はいない。明らかに激減した。かつてのように「写真をお撮りしましょうか?」はもう必殺技ではなくなってしまった。園内のガイドマップを広げているゲストがいたら、すかさず「どちらかお探しでしょうか?」も使う機会がない。トイレの場所も聞かれない。正確には圧倒的に少ない。そういうことがないと、従業員もサービスの実感を噛み締めるような感触を味わう機会が少なくなっていることは確かである。反対に以前は多過ぎたのかもしれない。ゲストも園内のことが自分で全てわかってくると、余裕ができてくるから、段々と目線が厳しくなってくる。困っていないから当然助けてもらうこともない。従業員もお役に立てなくなる。それで、なんとなく以前より目が肥えてきて「下がったな」と感じて、もう来場しなくなるゲストもいる。それは仕方ない。それは、ただ入れ替りが行われるだけで、新たに「リーピーター新人」がデビューして2回、3回と訪れることになる。つまり、来なくなる人3%。リピーターになる人3%で交替しましょうということ。偶然かどうか別として、民間企業も毎年3%くらいの入替えがよいと言われる。3%くらいは卒業して別の企業に移ったり、あるいは起業して新たな事業を起こして雇用を作る。そして、また3%の人々がデビューすることになる。つまり、97%というのは、新陳代謝状態に入ったことを意味する。では、この先はどうなるのか?「いやーもう厳しいと思うよ」「ここからのマーケティング展開では…」などと、アメリカ帰りのコンサルが理論をこねくり回して色々とそれらしいことを言おうとするが、ここから先の経済学はもう教科書に載っていない。経済学では袖を振っても、もう何も出てこない。だから、もうわからないというのが正解。先端商品、知識産業、高付加価値産業はわからないことだらけで、今度のアニメが売れるのか?新曲は何枚売れるか?などもう完全嗜好商品の領域である。当然、ムダが多くなってくる。ハズレも出て来る。せっかく作ったバンダナが大量に売れ残ったり、一方で、「アリエルの油絵」が20万円で売れてしまう。そうなると、客単価も変わってくる。また、舞浜周辺のユニークな傾向として、定年退職した家族が引っ越して来る。おばあちゃんに年間パスポートを買ってあげるらしい。するとおばあちゃんは足腰のために毎日ディズニーランドへ行く園内は20年前からとっくに「バリアフリー」化されていて歩きやすい。極端にうるさい音楽もない。園内は日本一きれいで清潔。特にスペースマウンテンに乗るでもなく、ベンチに腰掛けて園内で知り合った仲間とベンチでおしゃべりをしている。おなかが空いたら食事で、その後にお茶。気が向いたらショーを見る。仮に一人でも、スタッフは顔見知りで挨拶してくれるし、話し掛けてくれる。家族からしたら、ヘンな所に行くよりディズニーランドの方がよほど安心で、何かあればすぐにスタッフが飛んでくる。救護室もある。ナースもいる。医者もいる。自宅に連絡してくれる…と。このように、リピーター新人の中には、実はおばあちゃんも入ってくる。客層も変わる。すると、そういうサービスを提供しつつ、いつかディズニーランドの横に老人介護施設ができてしまうかもしれない。人を楽しませる、癒す、楽しませるノウハウはふんだんにある。そうなると、スタッフは昔のようなサービスではなく、「おばあちゃんと一緒に遊んであげるサービス」になっていく。それはそれで好きな人たちがやってくれるからきっとまた繁盛する。…などなど97%の世界は前例がない分、あれこれ考えていくと大変面白い。夢と魔法の王国ではすでに未知への挑戦が始まっていた。--------------------リベンジのセミナーは大変充実していた。全国から集まった参加者の方々は、斜に構えている人なんかはいなかった。何か盗んでやろう!と虎視眈々。でも、「ここで笑ってね」という時は気持ちいいくらい「ワッハッハ」。中小企業の経営者あるいは幹部の方々で、とても気さくで楽しいセミナーになった。これもひとえに主催側の担当者の熱意によるもの。何があっても諦めない。地に足が付いた企画立案、実施、運営は見ていて気持ちが良い。仕事は熱意ある人とやると幸せな気分になる。大変有意義な一日を送ることができました。ということで、リベンジの第1ラウンドは終了。第2ラウンドは11月の予定!
2003/09/25
コメント(3)
-
ディズニーランドでリベンジ!
夢と魔法の王国はとても楽しくて厳しくて、充実した日々だった。小学生の頃から遊園地で働くことが夢だったから、迷うことなく就職できた。ところが、数年たったある日、突然、家と財産を失うことになった。父が保証人になっていた借金。見事にやられ、身包みはがされた一家は、再度全員が肩を寄せ合って暮らすしかなかった。やっと借りることができた借家からはディズニーランドは遠すぎた。早番、遅番が務まらない…。出社できないし帰れない。それでも何とか…の悪あがきの期間経て、去ることになった。その後、一連の苦労がたたって、母が発ガン。5年間の入退院と手術を繰り返して他界。僕から母とディズニーランドを奪った借金を憎んだ。レジャーサービスの楽しさと厳しさのたくさんの教訓と「好きなことができてよかったね」の母の遺言を胸に10年間走り続けた。そして、ようやくリベンジが始まった。「世界一大繁盛テーマパークに学ぶ、最高の演出・商品・接客」のセミナーのゲスト講師に呼んで頂いた。入社以来、20年の時を経て、堂々と凱旋できる。好きなことをしてきて、本当によかった。
2003/09/24
コメント(6)
-
新しいパートナーの募集!
☆トップページを見て下さい!今日は札幌へ出張。準備していつものスクーターで羽田へ…と思いきや、ライトがまったくつかない。メーターのライトも。そのまま近くのバイク屋に駆け込む。20分くらいして「これはもう電気系がダメですね。配線が焼きいれてます。全部交換すると結構かかりますよ。どうします?」と。とうとう買い換える時が来た。思えばよく走ってくれた。何しろ都内では、中型スクーターは大変便利で、渋滞もすり抜けるし、高速も乗れる。多少の雨も気にならない。荷物も結構積める。駐車場所に困らない。燃費がいい…と、都市生活には欠かせないもの。僕は車よりもスクーターの方がよく使う。「ただの道具」と割り切ってはいても、5年間も一緒だと、何となく愛着がわいてしまう。「一緒に写真とっておけばよかたな…」と。バイクは機械の固まりで、ボルトとナットと配線とプラスチックの固まりに過ぎないが、何年も乗っていると「馬」のような気がして来るから不思議だ。コンディションが微妙に伝わってくる。PCやデジカメなど、新しいものも好きだし、物欲が強い方かもしれないが、いったん気に入ったものは長く使ってしまう。今、日記を入力してるノートPCのVAIOも4年目で、そろそろ限界か?けれどなかなか買い換えられない。結局は完全に壊れて諦めがつかないと難しいのかもしれない。オフィスで働いているより、移動している、出張している時間の方が圧倒的に長いから、身の回りのモノは生活必需品であり、パートナーのような存在になってくる。ということで、新しいパートナーを至急探さなければならない。今度はどんな相棒(スクーター)を手に入れるか?しばらくは検索合戦の日々が続く。-------------------地下鉄を乗り換えて、羽田空港に到着。ギリギリ。スクーターなら首都高で20分なのに…。新千歳空港でエアポートライナーに乗り換える。15分くらいあるので、待合室でメールチャックと思いきや、旧型VAIOのバッテリーはもう30%の表示。これでは多分10分も持たない。待合室周辺を隈なく探すと、以外にもたくさんコンセントがあった。助かる。JR札幌駅到着。やはり夜は寒い。舐めていたことを反省。GAPを見つけて飛び込み、折りたたみの「アノラック」を買う。防水で折りたたみというのがいい。その後、南2条の「炭おやじ」というお店で、クライアントの方々と打ち合せ件食事件懇親会。明日は研修なので、飲み過ぎない程度に切り上げて、ホテルサンルートニュー札幌へチェックイン。食事しながらヒアリングしたことを思い出しながら、明日のスクリプトを作成中…。うまくいきますように!
2003/09/23
コメント(5)
-
北京でのサービス研修の舞台裏
周到な準備で乗り込んだつもりでも、やはり初めての土地、国では予想もつかないことが日々起こって翻弄される。北京のレジャー施設を担当した時も…。まずは、余裕をもったカリキュラムとスケジュールを作成したつもりでも、全く思うように行かなかった。つまり、時間が足らないのである。なぜか?まずは、「通訳によるタイムロス」である。僕が話す→通訳する→スタッフが理解する→質問が出る→通訳する→質問に答える→通訳する→スタッフが納得する…という工程は予想より長くかかってしまった。日本で同じ内容をやる場合の約3倍はかかる。とはいっても、これは誰が悪いというわけでもないから仕方ないことだ。それと、日本のスタッフとの大きな違いもあった。それは「何か質問がある人?」と聞くと、「ハイ!」と十数名が手をあげる。これにはまいった。無意識に「質問のある人?」と聞く癖がついていた。なぜならば、日本ではたいていの場合「ない」からである。そういうペースが体に染み込んでいたと言える。ところがこっちではわからないことはちゃんと聞いてくる。だから、その質疑応答に時間ととられることになる。もう一つは、通訳さんとのリレーションというか、「息が合う合わない」というのが大きい。原因の一つに、最初のうちは、派遣会社からやってくる通訳さんが毎日違った。だから毎朝「はじめまして…。この施設の特徴は…。日本のサービスの考え方は…。昨日までの内容は…。僕の主なキャリアは…」と説明しなければならない。そしてようやく授業となるが、午前中は息が合わない。午後になってようやく…という感じである。そして、一日が終了すると「なるほど。あなたのいうサービスの考え方が少しわかってきました。ちょっとおもしろいです」となる。「謝謝」といって別れると、次の日にまた違う通訳さんが…。これでは、スタッフよりも通訳さんの教育に手間を取られて進まない。ということで、かなり強力に交渉して、担当者を固定してもらった。そこからは段々と遅れを取り戻せる…はずだった。ところが2日目にして、授業中にスタッフがざわつき出す。いつもと違う。ヘンなことを言ってしまったか?気になった。休憩時間、あるスタッフが英語を使って僕に直接訴えかけてくる。ようするに、あの通訳さんはダメだ。ちゃんと訳してくれていないように思う。皆そう思っている。言葉はわからないけど勘でわかる…と。彼は北京大学出身の秀才なので、当たっているのかも?と。しかし、確かめようにも中国語がわからないのだから打つ手がない。そこで、後半の授業は「復習」にした。今日の午前中に教わったことをパートごとにスタッフに発表してもらう。僕はスタッフの発表内容をただひたすら聞く。つまり逆通訳してもらうことにした。すると…思っていた通りで、ちゃんと通訳してないから、まともな答えが返ってこない。ここで怒っても仕方ないから、どのくらいわかっていないのか?を懸命に把握することに終始した。すると、ほとんどいい加減だったことが判明した。すぐに本社に連絡してまた通訳さんを替えて頂く手配をした。一日の授業が終了すると、スタッフたちが僕の周りに集まってきた。今日のところはもう一度やってくれるのか?と。僕は「もちろん」と答えた。彼ら彼女達の熱心さにちょっと感動した。(日本の施設では滅多に見られない光景で、授業なんかない方が皆うれしがる)次の日教室に行くと、日本語で「先生、昨日はごめんなさい!」と書いてあった。ジーンときた。それでまた少し北京が好きになった。
2003/09/22
コメント(6)
-
クライアントVS業者
「この車いいよね~。欲しいと思わない?」「このデジカメさぁ~」とカタログを広げながら物色していると、友人が「このメーカーのは絶対に買わない。それとこのメーカーも絶対に嫌だ。死んでも買わない!」といきり立つようにモードが突然変化した。「来年度は一律15%カットを~」というかけ声はどこにでも木霊していて、別に珍しいことではない。しかし、その内容や取り組む姿勢には雲泥と言ってよい差がある。そして、そこに「品格」「人格」が透けて見えてしまうから要注意である。友人彼女は、コストカットの矛盾の渦に巻き込まれて、体を悪くしたらしい。現在、休職中だ。相当悪いらしい。レジャー産業でも、ハード系の企業の場合と、設計、デザイン、コンサルティングなどのソフト分野の企業ではダメージが全く違ってくる。極端な話、部品などのコストダウンの場合、工程や仕様などの再検討で、製造過程そのものの簡略化や材料を世界中でもっと安い企業に求める。あるいは、輸送費を飛行機から船に変える…などのある程度、明確な手法で可能である。ところが、ソフト系の場合、単純に「コストを下げろ」「だけど、品質は落とすな」「納期をもっと早くしろ」の場合、建前論としては最もらしい項目もいくつかあがるが、基本的には「泣いてね」である。もうちょっと義理人情のある場合、「頑張ったら次のプロジェクトでは必ずお返しするからさぁ。僕を信じてよ。ねっ!」くらいなもの。しかし、次のプロジェクトになればなったで「悪い。こういうご時勢だから~ねっ。わかってもらえるね」となる。個人的には、こういう場合、手間を簡略することを双方で約束するようにしている。打合せ→作成→担当者へ提出→赤入れ→修正作業→再提出→担当者から課長へ→赤入れ→修正作業→課長から部長へ→赤入れ→修正作業→取締役へ→…と、果てしなく続く「スタンプラリー」の回数減らすことである。これだけで、コストは3割どころか半分にもなる。新幹線代、飛行機代だけでも凄い金額になる。だいたい、「担当者」というからには最後まで担当してくれないと困る。担当者の変わりに課長に提案し、部長提案し、役員用のプレゼン資料に修正…となると、それらを見越した見積になる。けれど、コストはダウンしたいとなると、実作業をカットしないで下げるにはそれしかない。今までの経験から業界内を見渡すと、特にデザイン業者さんなどは見ていて気の毒なことが多い。(まぁ、皆大変だが)担当者と再三打合せをして、「うーん、うちの会社では~というのが基本だからそこは修正してもらなわないと…」などとやっておいて、修正後、自分で課長に説明したら撃沈されてしまう。だから、デザイン会社をもう一度呼ぶ。飛行機で来る。それで説明する。すると、課長は課長なりの考えがあって、色々と修正が入る。それで、飛行機で帰ってやってくる。もちろん土日はない。「週明けまでに頼むよ。早いところ部長の決裁を取りたいでしょう」の一言があるから、猛烈に頑張る。週明けに新しいデザインがアップする。月曜の朝一の飛行機で乗り込んで渡す。すると課長が「いやー部長は今日、会議が目白押しで会えないらしいから、僕の方で説明しておくよ」とのこと。それでまた飛行機で帰る。すると担当者から電話で「金もう曜日に部長が空いています。来て下さい」となる。ここまで来ると「ねぇねぇ」という感じである。これを役員に通るまで繰り返せば見積は高くなるに決まっている。傍で見ていても十分にそう思う。コストダウンをするには、担当者のスキルを5倍くらいにUPするか、事前の社内調整をきちんとするしかない。さらに言えば、「社内調整の達人」を雇うなど。会う人ごとに「うちの会社はねぇ~」と会社の代表としてあっているのだから、代表らしくして頂きたい。そうでなければ「私は単なる窓口の総合案内所です」と言って頂きたい。デザイン会社に社内調整までしてもらうようでは、コストダウンへの道は厳しい。それでも強引に進めるところが後を絶たない。すると、デザイン会社の若いスタッフが「犠牲者」となる。「月曜の朝一で頼むよ」という仕事ばかりになってくるから、毎日終電、あるいは深夜タクシーである。自宅が遠いこともあって、深夜タクシーが半年で100万円を超えてしまった。しかも「自腹」である。(という人が現実にいる)「なぜ、そんなバカなことになるの?と聞くと、ようは、「お前がクライアントを一発で満足できるようなデザインができないからいけない。よって、何時間残業しようが、何キロタクシーに乗ろうがお前の責任である」ということらしい。まぁなんともメチャメチャな話になっていく。こうして、あるデザインのコストダウン「200万円」は達成されて、おじさんたち同士は夜の街に繰り出して、お姉ちゃんを触ってはしゃぐことになる。しかし、コストダウンの実態は、若いスタッフの「自腹深夜タクシー代100万円」と、本来ならば間に合わないから外注に出す仕事も自分で残業と休日出勤でやった「サービス残業代100万円」だった。ちなみに、友人の彼女も、ほぼこのパターンだったらしい。そして、恐ろしいのが、こういう目にあった人たちの間では、実はしっかり非買運動の輪ができいる。これがどんどん大きくなってくると、メーカーが力をいれたCMや宣伝をやっても「おかしいな?売れないな?」が出てくる。いくつかの事例を聞いて鳥肌が立った。個人を舐めてはいけない。僕も、仕事柄、業者の立場とクライアントの立場をちょうど「5:5」くらいあるから、身が引き締まる思いがした。考えてみれば、人は皆、ある人からみれば下請け業者であり、クライアントであり、お客様であって、どれか一つだけの役割の人などいない。それを勘違いすると恐ろしいことになる。強引なものは、何の解決にもなっていない…という教訓である。
2003/09/21
コメント(3)
-
日中合作映画制作への道①
「私、日中合作映画を制作しようと思ってるんだ」と久しぶりにあったK’さんは言った。「日中合作って共同で制作するっていうこと?」「そうよ」その頃、レジャー産業に関わっていても、映画を制作しようなどとは思ったこともなかった。シネコンの仕事は経験があったが…。だから、どういう経緯で動機でそうなったのか?に非常に興味津々だった。貪るように質問攻めにした。「そう言えば、僕も秋になったら北京に行くんだ」「何をしに?」「子供向けの科学館の立上げの仕事で、研修したりOJTしたり…」「そうなの。お互いに中国に縁があるのね…」それから約8ヶ月後、僕は北京にいた。半年間くらい、日本と北京を行ったり来たりしながらようやくオープンに漕ぎ着けてホッとしていた時だった。施設の中を巡回していると、ショップのスタッフが、「先生、チケットカウンターに友達がきているみたいよ」と教えてくれた。しかし、北京に僕の友人はいないので躊躇していると、「本当だよ。早く…」と、今度はチケットカウンタ-のスタッフが僕を呼びに来た。「?????」と半信半疑に一緒に向かう。「ニーハオ!素晴らしい施設ね。おめでとう!」と、そこにはK’さんがいた。「ヘッ?なんで…?ここに…?どうやって…?」と、あまりの驚きにうまく応対できなかった。なんでそこまで驚いたかと言うと、彼女には「北京」とだけしか伝えていなかったから。具他的な場所も、施設名も伝えていなかった。ちょっとボーっとした僕を尻目に、「勘が働いたんだ。へへッ」とさらっと笑顔だった。それにしても、よくこの広い北京で、しかも日にちまでピタリと当てて…。なぞは深まるばかりだった。中国で舞台公演をしたことのある彼女は、中国語でスタッフにあいさつをする。そして、なにやら色々と話してい笑ったりしていた。「何話しているの?」「うん、この先生はどうだった?って、聞いてたのよ。楽しかったって」なんだかこそばゆい。「でも、本当にやったんだね。先を越されたけど今度は私の番よ。応援してね!」…それが、日中合作映画のお手伝いをすることになった初めのきっかけである。
2003/09/20
コメント(1)
-
(株)=カッコカブ?
あるお店で「領収証下さい」とお願いしたら、「えーっと、ハイ」と言って何やらレジのシートキーを探し始める。「あっこれかぁ」とシートキーを押す。通常のレシートの他に、領収証が出てきた。その瞬間にこちらも習慣で「(株)でお願いします」と告げ、社名を言おうとすると、「はい?なんですか?」とレジバイト君が質問をしてくる。「宛名は(株)○○で…」と再度告げる。「なるほど…」とレジバイト君。レジ横にある、大福に目を奪われつつ「そろそろ書いてくれたかな?」と領収証に目を移すと…なななんと、「カッコカブ」とカタカタで書いてあった。「社名はカタカナでお願いします…」とは言ったが…。世の中、コスト削減を大号令に突っ走った結果、サービス業の現場のほとんどがアルバイト化が加速している。月給25万円より、時給800円で働かせようということである。その際に、月給25万円時代と変わらないサービスが受けられるなら、顧客に迷惑をかけていることになはならないが、明らかにアルバイト君の顔には「だって、オレ、時給800円のバイトだもん」と書いてある。コスト削減で企業の収益を確保して、残っている社員たちは以前と変わらないだけの給与をもらおうということらしいが、時給800円は立派に時給800円分しかやってくれないから、しわ寄せはお客さまに行く。月給25万円時代のサービスを時給800円でも実現するための「仕組み」をきちんと考えないところは、当然こうなる。仕組みにもお金や手間をかけたくないなら、サービス業はやらない方が良い。そんなに調子よくはいかない。考えてみれば「領収証」なんか全く関係ない18才のバイト君には、「(株)(有)(資)」など、言われてもピンと来るわけがない。こういうのもマニュアルに書いてあるところとないところ。トレーニングの中で3分でもいいから教えているところとそうでないところの違いが出る。そういう意味では、当たり前、常識と思っていることをきちんと教えているだけでも、「あそこはやるな」と差をつけるのも簡単な時代なのかもしれない。
2003/09/19
コメント(3)
-
道場六三郎のような講師とは…
昨晩、研修の準備に手間取り(大いに悩み)AM3:00過ぎまで「あーでもない」「こーでもない」と久しぶりにグジグジした。講演会の時と違って、サービスマインドの研修では、テーマとなる<材料>はあっても、その店舗、その施設、そこのスタッフのコンディションに噛み合うように材料を料理しなくてはならないから「今回はどんな料理にしようか?」が毎回違うので講師と言えども半分はシェフみたいなもの。この「チームはイタリアンがいいな」とか「いや、中華だ」などと色々と考える。そして、これまた料理と同じで、前菜は○○で~デザートは杏仁豆腐で~と一連のコースメニューでなければならい。同じ中華でも、食べる相手に合わせて塩加減も変えなければならない。しかも、オープンキッチンで、オーダーしたお客さまの顔を見ながら料理するようなもの。シェフの腕次第で、多少苦手なことも吸収してもらえるかどうか?差がつくリアルな世界。小さな頃、トマトが大嫌いだった。小学2年生の夏休み、田舎で過ごしてから食べられるようになった。縁側で<蟻いじり>をして遊んでいた僕に、祖母が「ほれ、トマトさ食え」とお皿に持ってきた。「いらない」と答えると、「このトマトはなぁ、ちょっと違うんだ。ほれ」と。それでちょっとだけ食べてみると、よく冷えたトマトに砂糖がついていた。ただそれだけである。しかし、「こんなに美味しいものを今まで食べないで損した」と思ったほど美味しかった。それ以来小学生時代は<砂糖つきトマト>ばかり食べていた。まぁ大人になるにつれて別に砂糖なんかつけなくても食べるようになるのだが、キッカケはそんなものである。砂糖ひと振りだから、料理と呼べるほどではないが、子供心にはなんとなく<魔法の粉>くらいに思った。それからというもの、なぜか祖母の作る料理は全部美味しく感じて、何でも食べた。まさに子供心は<魔法使い=おばあちゃん>なのである。いまだに、とても魔法使いには慣れないが、こちらの分野(レジャーサービス業)の中では、道場六三郎氏や三国清三氏のような料理人になれたら…と。そのせいか、料理人の方々の本はとても参考になる。(しかし、本当の料理はそんなにうまくはなっていない)だから、研修をやる前には美味しいものを食べるべき…と、まことに都合のいい勝手な理念をこしらえて、今日はお昼にお寿司を食べた。すると、やはり調子がよい。落ち着いていい料理ができた?ような気がするが、そればかりは受講した人に聞いてみないとわからない。食べ残しはありませんように!
2003/09/18
コメント(1)
-
「5の評価」と「1の評価」
社会人になると人を評価する機会がある。反対に評価されることもある。自分の部下だったりチーム全体だったり他の企業だったり…と、職業柄、評価は避けて通ることはできない。。ディズニーランドで働いていた頃、アルバイトスタッフの評価表が定期的に回ってくる。評価者研修なるものも受けているのだが、それでも何となく苦手だった。なぜなら、その時に、実は自分と直面することがあるからだ。自分の反省も交えて例えるならば、(仮に5段階評価だとして)「大変良い=5」に○をつける時はいいのだが、本当は「1」に○をつけようと思った時に葛藤みたいなものが起こる。そのひとつは、その人が嫌いで、その感情までもが混ざってしまい非常に厳しくなって「1」をつけてしまう場合。後で冷静に考えると、多少感情のはけ口になっていたり、何かの「仕返し」なんかも混ざってくる。こうなるともう仕事の評価の枠をはみ出てしまう。多少寛大で、コミュニケーションのスキルの余裕のある人は「2」をつけていることがる。もっと積極的に指導すればすぐに「3」になるはず…と思っているので余白が多少あるし、実際に、その後は「2」の人を浮上させる。なぜなら、特に人間関係は正常だから。つまり「1」をつけた時は、つけた側にも大いに問題がある(余裕がないなど)場合が多いということ。それほどになるまでに放っておいたことが問題である。例え相手が上司であれ同僚であれ部下であれ「1=最低」をつけるほどまでに放っておいて、あるいは真剣に関わらないでおいて、そこそこのつき合いだけはしておきながら、すました顔で「1」をつける。こういう場合もあるから、評価者は「1」の人間をマークするだけではなく、「1」をつけた方にも十分に注意を払わなければならない時がある。反対に、自分が「5」の評価をもらった場合は…、実は相当プレッシャーにもなることがわかる。「次も5を維持しなければ…」と。もう誰が見ていようと絶対に手抜きはできないし、5で当たり前のような感じで見られることになる。半年後に、自分としては同じレベル(5くらい)はキープしたつもりでも、周囲の期待は、前回の5が自然に(半分無意識で)今回の評価では「3」になっていたりするから、たまらない。5をもらうとそこが「最高点」と思われがちだが、そうではなくて、「次のステージへどうぞ!」という意味がある。A面クリア…みたいなものだ。ということは、5をもらうと「また次のステージでスタートを切って下さい」と言われているようでもあり、「先に次のステージへ行ってみてください」と受けっとれたりで、うれしかったり恐かったりと、ここでも多少混ざってくる。細かくみていけば「3」をつける時の心理は「適当に…」なのか、「評価したくない…」の表現なのか?「4」の評価は、最高得点はあげるのは嫌だから「少しだけ足を引っ張やれ…」かもしれないから、どの段階にも色んな心理戦が混ざってくる。いずれにしろ、評価をしたりされたり…というのは、非常に奥が深い。社会人は常に様々なシーンで両方の立場にさらされているのだから、職場の中で、評価制度があるというのは良いことだと思う。少なくとも、世間の中の無言の評価よりも気持ちがいい。何と言っても評価の免疫もできる。色んなことを考えながら成長していくよい機会である。良い評価も悪い評価も、それが自分という人間の全て(評価)ではないけれど、評価の一部であることも認められるようになる。
2003/09/17
コメント(2)
-
全日本あいさつ検定一級
ミスターチルドレンのCDを鞄につめて、福岡に。昨日は、最終便の飛行に間に合わず、朝一で羽田空港に向かう。しかし、寝坊意味で結局はバイクで羽田に向かう。目線は完全にケビン・シュワンツ(元2輪のGPチャンピオン)。福岡空港で地下鉄に乗り換え、楽天王国?の天神に到着。せっかくだから、ベンチャー大学の栢野さんに接近戦を申し込みたい衝動に駆られたが、時間に余裕が無いのでおとなしく研修会場へ直行。ショールームを運営するスタッフの方々は、ほぼ99%の企業経営者が羨ましがるほどに、レベルが高い。研修の始める前の挨拶「よろしくお願い致します!」だけで、絶対にそのポテンシャルが体験できる。心境としては、こちらの方がお金を払いたくなる…ほどで、挨拶だけでもここまで磨けば、一生食べていけるのかもしれない…と。もし、「全日本あいさつ検定」があったら、間違いなく「一級」。段があれば…5段くらいか。始めての時は、「この人たちに一体なにを研修すればよいのか?」と真剣に考える日々が続いた。研修会や講演会などで目にする光景の多くは(少数の方々を除けば)、○机にヒジをつく○足を組む○さらに腕を組む○加えて目を瞑っている、あるいは本当に寝ている○別の仕事をしている…などである。(自分も気を抜くと、すぐにこうなる)それと比較してはなんだが、○両手はメモをとるかひざの上○足はきちんと揃えている○わからないことがあれば質問する○人の話の最中に、重ねて話さないそれと、とどめで、○イスの背もたれに寄りかからない…などなど、あげればキリがないほどで、「日本人でよかった」というほどの気持ちいいマナーのシャワーを浴びることができる。「なんとか美女軍団」で舞い上がっている場合じゃない。あんな支配的教育の賜物のマナーなど勝負にならない。誰にも強制されずに、自分で選んで飛び込んできた世界でトレーニングを積んでいる。ヤワラちゃんが世界柔道選手権の連覇を達成しているが、もし、仮に「世界あいさつ選手権」「世界ナレーション選手権」「世界インフォメーション選手権」があれば、こちらも望むところだ…などと想像は果てしなく膨らんでいく。まじめな話し、ご本人たちに「もし、九州○○選手権があったとしたら出たいですか?」と聞くと、(控えめな態度ではあるが)「出たい」と言っているから、相当の自信がうかがえた。それは、まさに「練習して身につけた迫力」である。サービス業の多くは入社してしまえば、年に一回くらいの申し訳ない程度の研修会などに行くくらいで、柔道家のように練習するという習慣が非常に少ない。なんだかんだ言っても「ブッツケ本番」ばかりである。または「自称本番に強い」という人で、それは「生まれつき」の正確や才能、あるいは外見に頼った所が多くて「向いている」くらいなものだ。しかし、彼女たちは違う。「練習→本番」の毎日である。もちろん、外見も素晴らしいが、体系から身だしなみにも最新の注意と研究を怠らない。その上で、モチベーションを保つのに色々と苦労してたりしているが、それはとてもレベルの高い「悩み」となって発言される。講師としては、本物のプロスポーツ選手でも何でも見て参考にして頂きたい…しか言えない。女子マラソンのQちゃんは、こうやって…と。せめて、「全日本あいさつ選手権大会」でもなんでもいいから見てみたいものだ。(実況は古館さんにお願いしたい。そんな風にしゃべるのか?考えると眠れなくなる)でも、今のままでは福岡の圧勝かも?まったく天神は奥が深い!中国で言えば、少林寺なのかもしれない。(まさに少林寺のごとく訓練しているから)P.S.2次会のカラオケでは、もちろんミスターチルドレンのナンバーを大合唱?だった。それとちょっと今井美樹。
2003/09/16
コメント(0)
-
本当にマーケティングできんの?
こういう業界だから、関係業者もオッペケペーが結構いる。何がオッペケか?というと、自称「何でも知っている、出来る人」ばかりだ。(けれど、極少数のプロ、天才もいるのであしからず)先日も、ある施設内にあるレストランのリニュアル計画の業者プレゼンに立ち会った。案の定、皆、何でも屋さんで、一通りのデザインや商品計画、店舗デザインの説明が終わると質疑応答に入る。「なるほど、だいたいわかりました。ところで、これが出来たら、店舗と商品に合わせたトレーニングなんかはどうするんでしょう?誰に頼むの?」とクライアントの部長。「ええぅえ?部長。僕らはトータルコンサルタントって言うことをお聞きでないんですか?トレーニングはもちろんウチでやりますよぉー!」とブレゼン社長。部長「トレーニングって例えば?」社長「ですから、キッチンからホールまで…です。接遇もビシッとやりますんで」部長「じゃあ、そこまできちんと明示してよ。でないとわからないよ」社長「了解です。来週月曜日にはトレーニング計画を提出しますんで…」と、一連の質疑応答がなんとか終わった。その後の座談?で、部長がぼそっとつぶやく(身内に対して)。「けどさぁ、これだけの費用をかけて仕上げても広告宣伝やら大丈夫なのかなぁ?ハードばかりに金かけすぎじゃない?」などと、急に冷静モードになる。すると部下たちは、「うーん、マーケティングについては、今のところ社内でやるしかありませんねぇ」とちょっと弱気というか慎重な答え。その会話を、5m近く離れているはずの会議室の端にいたプレゼン社長が、別の人と話している振りしながら、耳だけはダンボ、いやデビルイヤーのごとく、体中の全神経とついでに全エネルギーを文字通り総動員させて聞いていた。「あのー部長。ちょっと聞こえちったんですけどぉー」と言いながら一目散に駆け寄ってくる。レストランの店舗転のマーケティングこそはウチの本業ですよ。相談してくれれば良かったのになぁ。別料金にはありますけど、相談にのりますよぉ」とまくし立てる。「へぇ、マーケティングもやるの?トレーニングも?デザインも?大丈夫なの?」と部長。「だって、ウチの実績は○○リゾートでしょう。デズ○○ラ○ドのプロジェクトでは~。それとお台場の○○も。業界では…」と果てしなく続く。その辺で周囲の人々が「また、始まった…」と心の中でつぶやきまくっている音が聞こえた(ような気がした)。いつもはこの調子で「あと、○○やった△△さん知ってますよ。仲間です。それと…」と続くのだが、その日は相手が悪かった。日本を代表する企業からの出向で、これまた大変優秀な方で(普段は大人しい)、実績が素晴らしい。最初は「へぇー」とか「そんなもんかねぇ」などとつぶやいてばかりいる。しかし、矛盾点は絶対に見逃さないし、見逃してくれない。その部長の右耳がピクンと動いた。(きっと試合開始の合図だ)「ちょっと待ってよ。本当にそんな人たち知っているの?本当にやったの?プレゼンで意気込み見せるのは結構だけど、ウソはダメだよ。全部調べるよ?いいね」…と、一発目から手加減なしに左ミドルが炸裂。「それに、マーケティングが専門というなら、あんた自分の会社のマーケティングはどうなの?うまくいっているの?いってるよね?でないと、人様の会社のマーケを手伝うなんてとんでもない話だよ。本当にマーケティングできんの?決算書見せてよ。そのくらい平気でしょう」これは間違いなく、レバー(肝臓)に入ったようなもの。さらにとどめで、「トレーニングだって本当にできんの?ウチはさ。サービス業なんだよ。接客業だよ。あんた説明ばっかりで人の話全然聞いていないじゃないか?人の話が聞けない奴にサービス業のトレーニングなんてできないでしょう。自分の会社の教育計画はちゃんとあるの?それ通りやってる?さっきのお茶の飲み方を見てると不安になるんだよなぁ」(ズズーッと音を立てまくっていた)…最後は重たい右ストレートで撃沈!!それでもなんとか立ち上がろうとするプレ前社長に「結局さぁ、自分の社内でもできないようなことまで手出ししない方がいいよ。火傷するよきっと。わかりやすく言えば、この仕事を取ると赤字になるってこと。だいたい、何でも出来るやつなんかいないんだから、そんなに気張らないで、本当に得意なこと、我々の力になれることだけをしっかり提案してよ、ねっ!」ここで、タオルが投げ込まれ、試合終了。改めて部長の発言を思い出すと、ここ会議室でも、ほのかにランチェスター経営の香が漂っていた。…ということで、試合結果<部長○ VS プレゼン社長×>(ランチェスター原爆固め)
2003/09/15
コメント(1)
-

ミスターチルドレンの研修とは…
いったん東京に戻り来週の研修の用意。今回は音楽を聞きながらの研修で、音楽、特に歌詞が重要。研修のストーリーにあっていなければならない。先日選んだものに自信がなくなり、再度CDを聞きまくる。そういうことをしていると、選んでいるはずが、曲を聴いていた頃のことを思い出したりで、一曲ずつ聞き入ってしまい、なかなかはかどらない。それでもなんとかいい曲が選ぶことができた。今回はミスターチルドレンのナンバーが中心。歌詞カードを見ながら聞くと、本当にいい。素晴らしい歌詞だ。まさにジャストヒットだ。そういった意味では、ミスターチルドレンは研修ソングの宝庫だ。「なんで音楽ばかり使うの?」聞かれることがある。あるいは映画…。やはり、天才たちが作ったものはよい。良いものはいい。講義を2時間やっても伝わらない、理解できないことが、たった4分くらいで伝わることもある。開業の頃のディズニーランドのトレーニングの時、「星に願いを」を歌詞を見ながら聞かされた時、言葉には言い表せないけど、自分がどういう場所で働くのか?何をゲストに提供しなくてはならないのか?が漠然とわかったような記憶がある。とても鳥肌が立った。しかし、ものの3分である。これもディズニーマジックというべきか。これが、部長かなんかが、「あー、ううん(少し痰がからまったりする)。我々の使命は~。であるから~。にしてからにして~。よって諸君も~。誠心誠意をもって~。お客さまの笑顔のために~」では、あそこまでのモチベーションは沸いてこなかったはず。絵で伝えられるものは絵を見せた方がいいし、音楽で伝わるものは音楽を聞かせるし、語りかけた方がいいものは語りかける…。(「話す」ではなく、「語りかける」というのがミソ!ですね。ちょっと読み聞かせに近い感じが漂います)この原則は今も変わらない(自分の中では)。教育やトレーニングでは、こうしたことが効果的であるという事例はいくつもある。僕と同年代の人たちの最も印象深い例で言えば、「8時だよ全員集合!」である。番組の最後の「ババンバ バン バン バン ハッビバのんのん~」と始まると、加藤茶が「お風呂は入れよ」「宿題やれよ」「歯を磨けよ」と子供達に毎週語りかけてくれた。ちなみに僕は毎週それをやっていたマジメな少年だった。散々楽しんだ後に、楽しませてくれた加藤茶にあの笑顔で言われると、妙に「そうだな、宿題をやろう」と納得したりした。仮に50分間、ひたすら母親が風呂だ宿題だ歯磨きだと言ったとしても、せいぜい一つくらいしかやらないかったかもしれないが、加藤茶が言えば、手前50分で笑わせておいて、最後の一分の指示だけで子供達は一気に3つも言うことを聞く。しかも瞬く間にやり終える。そういうことは、大人になっても実はあまり変わらない。研修会場に入ってくる時の30代40代の中堅社員は、もう頭の中がパンパンで言いたいこと、訴えたいことで溢れている。今にもこぼれそうで、始めって間もなく本当にこぼしてしまう(愚痴など)ことも珍しくはない。なので、実はもう何も新しいモノが入る余地は残されていない。なのに、「では、始めます。近年のマネジメントスタイルは大きく変わりました~」と講義が始まっても、水が溢れているバケツに水を入れるようなものだから、垂れ流し状態である。 なので、水を少し抜いてからやりましょう…というのは正しい。いい歌詞を聞いて、心を落ち着けてからでもよい。少しだけ水が減ってスペースができる。その分だけ用意して来た新しい水を注ぐ…。場合によっては、水抜きに2時間くらいはかけても良い。その分、後でたくさん入るから。ということで、今週の僕のテーマは「ミスターチルドレンに、オンブにダッコに肩車」である。
2003/09/14
コメント(0)
-
中国進出への準備第一弾とは…
「そろそろ私たちがやっている中国での仕事を一緒にやりましょうよ」とお誘いを受けた。その時、心の中のリベンジ魂に火がついた(ような気がした)。実は、2000年~2001年にかけて、北京で仕事をさせて頂いたことがある。行ったり来たりで約半年間。業務内容は、施設のスタッフの採用から、座学からOJT…そして、実際のグランドオープンまでの指導だった。しかし、「天安門事件」の映像は思い出せても、それ以外はブルースリーの映画やアグネスチャンが結構好きだったことくらいで、あまりに寂しい中国への知識。何しろ、日本よりも30年遅れている…だの、基本的には人民服を着ているから君も向こうでは着なくてはダメだよ…などといった、メチャメチャなで曖昧な情報しか知らなかったから、何をどう準備していいやらわからなかった。しかも、仕事内容がスタッフに運営サービスを指導する仕事で、特に「サービスマインドは会社の命ですから、徹底的にお願いします」とのオーダー。事前のやり取りはインターネットで済ませ、いざ北京へ…。ところが、北京空港について王府井(ワンフージン)に向かうと腰が抜けるほど驚いた。王府井は東京で言えば銀座で、都会のど真ん中。しかし、もう銀座どころの話ではない。その周辺を含めて、お台場や汐留、六本木ヒルズを合わせたようなたたずまいに圧倒される。(それから、悪戦苦闘で、楽しくほろ苦い日々が続くことになるが、この辺はこれから連載させて頂きたい)海外と言えば欧米の旅行が中心だったせいで、何ともエキサイティングだったが、同時にじれったさもこの上ない。というのも、中国はいわば日本の漢字文化のお師匠さんである。だから、漢字を見かけるとなんとなくわかような気がする。つまり、意味がわかったような、わからないような…この感覚が何日も続くと非常にじれったくなる。多分、日本人は皆そうなるのでは?例えば、ドイツ語やスペイン語は諦めもつく。けれど中国語は非常に似ていし、中には同じ漢字も多々あるから、非常に悔しい。けれど、同じ意味であるか?というと微妙に違う。これもまたじれったさの原因だ。そして、話すともうチンプンカンプンの世界で、カタカナ英語しかわからないといっても、まだ英語圏の方がはるかに通じるし、意味もわかる。店員さんとも多少のやり取りはできる。しかし、中国語は文字を見るとわかりそうでも話していることは全くわからない…ことギャップが堪らない(今となっては)。そこで、当時は秋葉原でSONYのディスクマンなどを買ったり、辞書を持参したりで何とか楽しい日々を送ろうとしたが、結局、聞く話すについてはダメで、つまるところ「筆談」が多くなる。当然、仕事の時は常に通訳さんがいる。しかし、夜、スタッフの皆さんに「食事に行こう」と誘ってもらって現場に行くと、気がつけばというか当然ながら通訳さんはいない。そうなると、お互いが片言の英語を交えて、ディスクマンで日中、あるいは中日で訳しながらの会話。それが何度かあると、本当に悔しくなる。話せたら聞きたいことはたくさんあるし、話したいこともある。帰国後は、NHKテレビ中国語会話をビデオに録画して、テキスト片手に勉強したものだが、必要性がなくなると必然的に遠のいて行った。…そうしてたまにみる中国映画が趣味になった頃、またまた中国の話が舞い込んで来た。「そういえば、中国語はわかりますか?それか英語でもいいけど」(さも当然そうに)「へ?中国語はほんのちょっとしか…」「じゃあ英語はどうですか?通訳要りますか?」「両方できないとダメなんですか?」(いるに決まってるじゃないですか!とつぶやきながら)「いやそんなことありませんよ。ただ、あちらのスタッフは英語も話せますからどっちか話せれば通訳要りませんけど」「会議レベルですか?」「もちろん」「無理です。通訳をお願いします」「わかりました。でも日常生活もあるんで勉強した方がいいですね」(ちなみにこのお方、4ヶ国語を自在に操る)「中国語は難しいですよね。どんな風に勉強すればいいですか?」「中国語はもう発音命でしょう。英語はカタカナ発音でも通じることがありますけど、中国語はそうはいかない。もう、ヒアリングですね。片時も…」あれ依頼その言葉が頭の中を走馬灯のように駆け巡るので、○片時も聞いているにはどうしたらいいか?○やっぱりMDウォークマン系が必要なはず。などを考える日々が続いた。それで、元研究員魂が疼いて、片っ端からカタログを収集。そしてついに、<Rio-SU30>を買った。MP3プレーヤーでは現在No1の人気商品らしい。買ってみてわかるのが、○重さわずかに37g(だから、胸ポケットにも入るし、重たさを感じない)○ネックストラップにイヤフォンがついた<ネックレス型イヤフォン>(だから、クビからぶら下げて聞けるし、イヤフォンも邪魔にならない。100g代の商品だと、カバンに入れたり、ストラップでベルトにつけたりでかっこ悪い)○PCのUSBにそのままコードを使わずに接続ができる。(すると勝手につながるようになる)○MP3をマウスでドラックしてファイルを移動できる。(どこぞの有名メーカーの商品だと、様々なセキュリティや保護がかかっていて、ドラック&ドロップではできないものが多数)○PCにつないでいると自動的にUSBから充電してくれる。(これは出張族にはたまらない。充電アダプターを別に持ち歩くと、カバンの中が携帯やらデジカメやら、なにしろアダプターだらけになっていく)○おまけにFMラジオまで聞ける。全国どころか海外でも。(これも大事。出張中はテレビをみる機会が極端に少ないので)「こんな商品があったらなぁ…」と思っていたら、その通りのモノが売っているとビックリして感動して、当然買ってしまう。このメーカーの凄いところは、基本的にはMP3プレーヤーなどのポータブルプレーヤーが専門で、その分野においては、他の有名巨大メーカーを寄せつけない。なんとなくランチェスター的な匂いを感じた。それにしても、またまたモノから入る癖が全開になってしまった。明日から、中国語のヒアリングの日々が始まる…(予定)。
2003/09/13
コメント(2)
-
“一握りの勇気”検定とは…
しばらくぶりにあるクライアント先に訪れると、何とも重たい空気が漂っていることを察した。毎日働いているとわからないが、たまに行く方はよくわかる。外部業者の特権だ。だたし、逆もしかりで、気をつけないと「元気ないですね?大丈夫ですか?」なんてことになるから要注意である。重たい空気の原因には、たいてい1~2名の主人公がいる。その主人公が「黒いリンゴ、あるいはガンだから…それが原因です」という展開。その主人公は、何しろ上司には大変気を使うし食事や飲み会にもきちんと登場する。幹部は皆、主人公をよい社員だと思っている(実際にその様子)。しかし、一緒に働いている人は、幹部がいない時の<正体><素顔>の方も知っているから、なおさら許せないらしい。その正体は、「現場に出ない症候群」である。最近は、どこの現場でも裏の事務所には1人1台のPCがあるから、ほとんどの時間をPCに向かって過ごしているらしい。朝礼だけして、あとは「私は忙しいから…」と。クレームの際に呼んでも「何でいちいち呼ぶの?クレーム対応をしっかりしなさい」と。「しっかりできなかったから呼んでいるんですけど…」と呟くスタッフたち。そんな日々が続いたから、No2やNo3が辞めていく。職場の定着率が著しく悪い。採用コストも教育費用もかさんできた。本人曰く「いろいろな書類が溜まっていて…」ということ。でも、すでに1年と4ヶ月くらい同じセリフだから、きっとオフィスワークが好きなんだと思って聞くと、「私はお客さまの笑顔のために働きたいんです」と。つまり、本部などの勤務や嫌ですということを間接的に訴えている。理想と行動のギャップが大きいから問題は問題なので、上司に確認しにいく。すると「いやー何回も言ってるんですけどねぇ…」「ほう、何回も?それで?」「何回言ってもダメなんですよ」「ダメ?」「はい、もう言う方が疲れちゃって…、だから様子をみてます」…とのこと。でも、ダメの様子をみて何になるのだろう?そこで、主人公に何度注意されたのか?聞いてみた。「注意ですか?私に?えー?そんなこと言われてませんよ」と。ズバリこの上司は言ってないか、ちゃんと言っていないか、いずれにしろ何も改善できていないことがわかった。本人が受取っていないなら言ったことにはならない。それで、「全く直ってないし、気づいていませんよ。どうするつもりですか?」「うーん、しばらくは放っておこうと思ってるんですよ」「???」放っておいて、早1年4ヶ月。こっからまだ先送りにするつもりである。何だか、政治の世界もレジャー施設のいちセクションも大して変わらない…。こういう小さな現場からして「先送り合戦」をしているのだから、もう日本は「先送り国家宣言」でもするしかないか。起こった問題は将来に先送りにします。だから僕を責めないで欲しい。次の世代がきっと何とかしますんで…と声を高らかに…。それなりに仕事をきちんとやる上司だと思いきや、放っておくでは話にならない。「それは、上司に相談しましたか?」と聞くと、「いやーそれほどのことでもないでしょう…」つまり、していない。「国立大学を出て、就職して以来毎月購読しているハーバード・ビジネス・レビューは、一体なんのために?」と聞きたくなった。そして、これが問題であるという自覚がない。そうでなければ1人で「問題倉庫部」でも作るつもりなのだろうか?時にはギブアップもしなくてはいけない。「僕には彼女の指導ができません。アドバイスをお願いします…」でもなんでも上司に相談するべき。相談することで、上司に責任が移行する。それで、少し軽くなる。すると少し冷静に考えられるようにもなる。また、そうやって、何人かの知恵が混ざれば、意外と何とか解決できるもの。このように小さくても大事な問題が放っておかれるのだから、どんなに社長や経営幹部がセミナーで勉強しても、肝心の「正確な情報」が無ければどうにもならない。経営幹部が真っ先にしなければならないのは、正確な情報が上がってくるような組織にすることだ。ノウハウはその先。ノウハウを身に付けるのもいいが、気をつけないと身につけたものを教えたくて、あるはい伝えたくて「下り」の指示ばかりになって、肝心の「上り」の情報が入ってこなくなる危険がある。何ごともバランスが大事。武沢さんの「がんばれ社長」に続いて、「がんばれ部長」「がんばれマネージャー」などが必要なはず。人数では新入社員と社長以外は皆中間管理職みたいなものだから、多分4000万人くらいいるはずだ。毎日4000万の人々が問題を先送りをしたら、それこそ日本経済は足腰も立たないくらいメチャメチャになってしまうであろう。といことで、現場の責任者、あるいはマネージャーは、得意不得意を超えてスタッフに接することのできる「一握りの勇気」がなければつとまらない。どんなにマネジメントスキルを勉強しても宝の持ち腐れ。発酵して本人まで腐ってしまう。だから、マネジメントスキルの分野にも「一握りの勇気検定」でもなんでも設定して、で3級を取らないとマネージャーではありませんよ、といった、超実践的な内容にしていくべきと考える。そうすれば、その先には心が軽くなった元気な中間管理職がイキイキと働く、新しい日本が待っている。
2003/09/12
コメント(3)
-
名刺でわかるプロジェクトの行方とは…
先日、机回りの整理をして、ついでに名刺ホルダーの中身も整理した。すると「おおー懐かしい、この名刺。○○村の時だっけ?」「こっちは○○館だったね」と、メンバーから感嘆が上がった。なぜ上がるのか?というと、プロジェクトの常?で、「今回の仕事はうちの会社の人間としてやってね」「名刺も作っておいたから。先方に絶対にしゃべっちゃダメだよ」というのがよくあった(最近は若造でなくなってきたせいか、メッキリ減った)そういうのが何枚も出てくる。そして、ある飲み会で「偽物名刺何枚持ってる?」と聞いたら、平均5枚だった。少なくとも過去3年間以内で…。ゼネコンや代理店などが主導のプロジェクトでは特に多い。なので、プロジェクトメンバーと名刺交換しても、実態はどうなのか?本当は誰がどの会社なのか?よくわからないことが多い。別のプロジェクトで偶然に会うと、同じ人物から、これまた違う名刺をもらったりするから尚更よくわからない。ところが、近年はわかりやすくなってきた。それは<Eメールアドレス>が登場したからである。会社名や電話番号、FAX番号、部署名、それに、ありそうでなさそうな架空の役職名はなんとかなるとしても、Eメールアドレスはいきなり取得できない。仮に取得できても、当人は違う会社の人間だから自分のPCにいちいち設定しなければならない。4つ掛け持ちの場合はもう、どれがどれ経由のメールなのか?わからなくなってしまう。かと言ってHotmailのアドレスでは、50億円のプロジェクトマネージャーとしてはどう考えてもウソっぽい。Yahooでも同じこと。そういうことがあって、段々と「偽物名刺」が減ってくる傾向にあるようだ。しかし、それでも大型プロジェクトの時にはまだまだあって、今も大型が控えているから花盛りなはずだ。そう考えると、ある分野の専門家は実は4分の1~5分の1くらいしかいない…ということになる。あとは複数掛け持ちの幽霊社員ごっこだらけである。偽物名刺を持つようになるとある症状が出てくる。それは、携帯に出るときに、個人名しか名乗らなくなることだ。または、「ハイ」とだけ返事をする。そして、相手が話すまでしゃべらない。相手の声や名前を伺うってから「ああー○○さんですか」とホッとしたりする。また、出張時も要注意で、仙台で仕事して、翌日は福岡だからそのまま飛行機で移動しようとした時に、福岡用の名刺(偽物)を持っていないことに気がつく。結局、たかが名刺2~3枚のせいでいったん東京に戻って名刺を浜松町まで届けてもらって、カプセルに泊まって、翌朝一便で福岡へ…という、何とも涙ぐましい日々もあった。夜くらいは、天神で美味しいものをゆっくり味わって、美味しいお酒を飲もう…という、ささやかなレジャーが木端微塵になる。30代半ばくらいは、「いつかきっと自分の名刺だけを使える身分になってやる…」とコブシを握り締めながらカプセルに寝ていたことを思い出した。社会人になって、初めて自分の名刺をもらった時の感動が懐かしすぎる。名刺を渡すのも、もらうのも、いちいち嬉しかった。万事そんな風だから、ロクな仕事ができない。あくまでもある会社の下請けだから会議の前でも「その資料は出すな」「そのページはカット」「余計なこと言わないで頷いていろ」などなど。最後にはただの作業者、資料作成者、付き添い総務…になっていく。名刺を眺めながら冷静に振り返ってみると、偽物名刺が数多く出回ったプロジェクトほどよく破綻する。あるいは、大きく傾いた。失敗の教訓はこんな所にもあった。偽物名刺はもうしばらく、思い出(教訓)の品としてコレクションしておこう。
2003/09/11
コメント(3)
-
職場のレギュレーション
「我が社では人材こそが~」「我が社の財産は人材である」「我が社は人材の育成に~」というスローガンは、まるであいさつ代わりのようにどこでも聞くことができる。しかし、実施際にはどうか?と言えば、「本当は掛け声のために作っているんでしょう」という企業が多い。本当に人材の育成に力を入れている…、あるいは、企業の生き残りを賭けて…というなら、経営陣からスタートするべきなはず。そうでなければ、「我が社は人材育成にはそんなには積極的ではない。自分で頑張って勉強して欲しい」と正直に言った方が気持ちが良い。あるいは「邪魔だけはしません」でもよい。ところが、依頼の多くは、「うーん、この部長研修というのは、今回は外しましょう。決済を取るのに難しい。その代わり課長以下をお願いしますよ」と。それで課長のところに行くと「そーですねぇ。うちはの課長は忙しくて時間が取れないから今年は主任研修と新入社員をお願いします」となり、ゴールはズバリ新入社員で、「とりあえず新入社員研修で行きましょう。しっかり頼みますよ。厳しくビシッとやって下さい。手加減は無用です」となる。なので、多分、「我が社は~」とやっている所では、新入社員研修がなくなることはない。本当は、いつまで経っても「忙しい。あー忙しい。私こそは忙しい」とやっている課長が能力を磨いて、今よりも効率よく仕事ができるようにするために色んな講師を紹介しているのだが、「忙しいのが大好きだから取り上げないで欲しい…」ということかもしれない。ただし、部下からみればたまったものではない。自分たちを含めて、仕事が忙しいのは、指示の出し方がメチャクチャだから…という声が圧倒的多数な会社なのに、コミュニケーションの勉強もしてもらえないのなら、自分たちはこのまま無駄な<指示ミスによるやり直し残業>をあと何年続ければいいんだ?といううめき声が聞こえてくる。「おい。アレどうなった?」「あっちの方はよろしくな」「なんで今頃持ってくるんだ。俺はもう帰るところだぞ。明日にしろ!」「クライアントとはうまく行っているんだろうな」「うちのチームをもっとビシッとさせておけ!」「そっちからやつに投げておけ」…など、「そっちがアレで、投げて…よろしく…」と、まぁこれを社内の専門用語であると言い切るならもう打つ手はない。新入社員研修で、元アナウンサーやスチュワーデスの方々に「正しい日本語」や「正確なコミュニケーション」を一週間もかけて教わって「よし、頑張る!」と配属になったら職場の上司がこれでは貧血になったり5月病にもかかっても仕方ないような気がしてくる。オフィスでは、散々こうした「投げつけ言葉」でメチャメチャな指示をされていながら、現場では笑顔で「いしゃっしゃいませ!」でなければならない。毎日「おい」「おまえ」で呼ばれながら、現場では「お客さま~」とやわらかく応対しなければならない。「我がホテルは一流であるから、我々従業員のマナーも…」と新入社員研修で2時間もの演説をしておいて(予定は45分だった)、ホテルのロビーで自分の携帯電話の着メロが鳴ってしまう支配人に「よう!元気にやっているか?」と言われても心からの元気が回復するのは至難の業だ。こういう支配人ごっこをしていたホテルは、2001年を無事通過できていない。2001年になった瞬間に、世の中の職場のレギュレーション(F-1風に言えば)がどんどん進化しているから、予選を通過できなくなってしまった(よって、よい社員が辞めていく)(または、PC用語でいえば、WINDOWS 95のままで、ブロードバンドに対応できない…など)。経営陣を入替えて、予備予選から再スタートを切ることになる。一方で、90年代後半から21世紀型の新レギュレーションを積極的に導入して、すでに他のホテルを<周回遅れ>にしてしまう所もある。今日、CSマインド研修を担当した企業はまさに後者で、時には悔し涙を流しながらも、必死にうまくなろうとするチームだった。「プロとは?」の質問に、参加したフタッフから様々な答えがあった。「結果を出す人」「コンディションを整えられる人」「同じことを常に新鮮に繰り返せる人」「本番に強い人」「練習に自信のある人」「失敗しても次に行ける人」…などなど、こういう答えは聞いていて気持ちいい。それに何と言っても、それを答えている時の表情がなんとも素敵に、逞しく思えたりする。実際には、そういう自分ではないのだろう。しかし、そういう自分になりたい…ということが伝わってくる。<なりたい自分像>の輪郭が少し見え隠れするのだと思う。その後で、「現在の自分のプロ度は?」と質問を続ける。途端に、教室のトーンが深くなる。「65%くらいだと思います」それに続くように50%、45%、55%…と半分前後の<%>が続く。そして、「30%くらいです。なぜなら~」と話す彼女の瞳は悔し涙でいっぱいだった。今にも泣き崩れそう…な気配。それでも少しシャクリながら必死にその理由を答える。そのシャクリあげているスタッフをひたすら見守り励まし、勇気づける支配人。思う存分に働かせて、失敗もたくさんさせているらしい。その失敗はマネージャと支配人で全部フォローしてしまう。そういうシーンを見ている方も目頭が熱くなってしまう。現代のサービス業はこうした矛盾の中で、葛藤の真っ最中である。頑張れ新入社員。ようやく5ヶ月経過だ。
2003/09/10
コメント(1)
-
サービスの異種格闘技
TDLツアーの今日は、うれしさを通り越して残暑全開の蒸し暑く、十分に体にキツイ天候だった。改めて視察すると新たな発見のオンパレードで、別にエレクトリカルパレードを見なくても済む…わけがない。何しろ、年がいにもなく楽しい。仕事柄、各地でサービスについての議論を交わすことがあるが、そうすると必ず、ディズニーランドのサービスは「よい」「いや大したことない」「まぁそれなり」など色んな意見がある。それは当人にとっては事実である。見方によっては、どうとでも取れるはず。仮に「接客」だけをとれば、一流ホテルのコンシェルジェにはかなわないかもしれない。スチュワーデスもしかり…。スターバックスも舐めてはいけない。(PRIDEで言えば、ダン・ヘンダーソン級)これは、異種格闘技みたいなもので、同じ仕事を「一斉のせっ!」とやってみなければわからない。だからどこが一番というのはなかなか決めづらい。裁けるレフリーがいない。それでも何とか部門別で決めましょう…となれば、いくつか方法がある。例えば、ディズニーランドがサービス業で日本一に輝くことの一つには、ズバリ「キッチン」がある。これは、他の追従を許さない。ファーストフードの店に入ってちらっとのぞくとよくわかるが、キッチンでポテトを揚げたりハンバーガーを作っているスタッフのユニフォームが他とは違う。髪の毛を隠すように深くかぶる帽子。そしてマスク。キッチンから出るたびに使い捨てにする手袋…などである。一見すると、NHKで放映中のTVドラマ緊急救命室「ER」をみているよう。グリーン先生にベントン先生のような様相で、そのまま手術室にエキストラとして入れそうである。ファーストフードでここまで衛生に気を使っている所は、ほとんど見かけることがない。いや、ホテルの厨房でも意外にここまでは衛生的ではない。そこまでやるべきかどうかの議論は別にして、「衛生で日本一」を目指す姿勢を20年間継続しているのには頭が下がる。その他、日本一、電球切れのない施設…というのも面白いかも。つまり、サービスと言っても「個人戦」では判断しづらいが、「チームプレー部門」では、圧倒的に強いことがわかる。(スタバも強敵)こうした小さな日本一がパークの中にはたくさんある。その積み重ねが魔法のような効果を生む。働く者のモチベーションになる。誇りにもなる。これが重要で、これを徹底しないでおいて、スタッフに<焼肉>を何度奢ってみても遠く及ばない。焼肉のモチベーションはだいたい3日間くらしか持たないが、誇りは長く続く。いちいち上司にせっつかれなくても、自力で元気になろうと努力する。同業の視点に立てば、最も脅威なのが「時給900円~」くらいのアルバイトで、現場のほとんどを運営してしまうことだ。これはとても真似できない。よく様々な同業者と一緒に視察すると、「まぁまぁだね」「うちのホテルのフロントの方がいいんじゃない?」などと言う人たちもいるが、正社員で年収450万円なら勝っても当然である。勝ってくれなければ困る。年収200万円クラスと争っている場合じゃないですよ…と。逆にTDLのアルバイトスタッフ全員が、年収450万円になったらどんなサービスをするのか…?あのホテルが時給900円だったら…?スタバがホテルを経営したら…?など、考える楽しみは尽きない。【主な行動】○寝坊につき、バイクでTDLへ。合流。○カフェ・オーリンズでコーラ。○プラザ・パビリオンで昼食(パスタとサラダ)。○アドベンチャーランドのワゴンでパイナップルとお茶。○乗ったアトラクションは、ウェスタンリバー鉄道だけ。(だけど、買ったのはパスポートとホルダー)○ディズニーギャラリーで懐かしの<ワンマンズ・ドリーム>を見る。(涙腺が大きくゆるむ)○<ヒストリー・オブ・ナイトタイムエンターテイメント>のCD2枚組みを買う。ようするに、夜の花火やレザーショーEパレードなどの20年間の集大成版。(聞きながら日記を書いている)○夕方、オフィスに戻る。(首都高をバイクで)○明日のCSマインド研修の準備。○六本木へ。アジアでの仕事の依頼を受ける。○毎朝ドイツから空輸される生ビールを飲ませてくれる店に案内される。(ドイツ人ばっかり)○終電ギリギリで帰宅。
2003/09/09
コメント(1)
-
小さな地方都市★レジャー施設開発のルール
昨晩は数日振りに<小さな会社★儲けのルール>を読み返した。いい本は2度3度読んでも面白い。前回とは違う所にヒットしたりする。1度目に読む時は、シャーペンで線を引く。2度目は黒のボールペン。3度目は赤。それで改めてダブっているところ、そうでない所を見るのも楽しい。何人もの自分がいるような気がしてくる。これはレジャー施設にも大いに当てはまることばかりだった。例えば「わが県にもリゾートを!」「テーマパークを!」と大騒ぎして200億円くらいの投資をしようとする。かつて(90年代)は、これをそれこそ一箇所に注ぎ込んで、そこれそ立派なものを造ろうと「全国一斉工事!」と言えるほどに建築ラッシュがあった。その場合の多くは、建物を立てる設計、デザイン、施工…なにしろハードに195億円注ぎ込んだ。それでもまだいい方で、150%予算オーバーなんてザラだった。それこそ、もう「おかわり!」と元気良く?追加投資を要求したものである。それで残った10%に満たないようなお金で、ソフトを考え用意していた。これは何もレジャー施設に限らず、公民館や芸術劇場などがそれである。その結果をパソコンに例えるなら、ペンティアム4、3.06GでHDが180GB、メモリーが2GBのパソコンができるわけだが、肝心のソフトはと言うと<WINDOWS95>だった…みたいなものである。明らかに過剰スペックである。ハードとソフトの絶妙なバランスで成立つレジャー産業なのにで、WINDOWS95型施設が乱立してしまった。なぜ、そうなるのか?答えは簡単で、計画の当初はハード屋さんしか関わっていないからである。そこで予算配分をやってしまう。だから、後にソフト屋さんが登場してもWINDOWS95くらいしか買えなかった…というのが正直な実態。ただし、予算が豊富にあれば年間100万人が楽しめるようなソフトを考え付くか?というと、これまた疑問である。仮に予算があっても「若い女性のマーケティング状態」になってしまう。そうなると、方法は大きく2つ。1つ目は、200億円の内の100億円で映画と制作する。もちろん外注。本来ならば依頼する監督は、スピルバーグさんやルーカスさんと行きたいところだが、少し足りないなら、ジョン・ウーさんでもアジアの巨匠、チャン・イー・モーさんでもよい。「外国人に~わかるのか?」と言う声もあるが、ここはひとつ天才にお願いする。そして、わが県、わが町にまつわる伝説や風習などつぶさに調べてもらって脚本を書いてもらい…で、映画を制作してもらう。撮影は、もちろんできる限り現地でお願いする。それが大ヒットするか?中ヒットか?赤字か?はわからない。ソフトビジネスで絶対はない。しかし、自分たちで100万人サイズの企画をするくらいなら、シロートがやるよりも確立ははるかに高い。それで、公開に合わせて残りの100億円で、テーマパークでもホテルでも造る。もちろん「あの映画の舞台」の登場である。そうなれば、施設内のアトラクションでもショップでも、ストーリーにまつわるモノがふんだんにあるから、企画に困ることは無い。企画会議も短くなるはず。200億円で造るよりはハードは小さくなるが、ストーリーのぎゅっと詰まった「小粒でピリッと辛い」施設の誕生である。もう1つは、200億円あるなら、20億円ずつ10箇所(町ごと)に造る。あまり離れすぎない程度の感覚で市全体を包み込むように。20億円サイズなら、頑張ればなんとかなるサイズである。中身のぎゅっと詰まった小型パソコンをネットでつなぐ…感覚。(一部の地域で繋ぎかけで「惜しい」所はある)そして、この場合は、天才に頼まず自前で企画するから、「頑張る」ことが条件。そのため、プロジェクトに関わる全ての人々に対して、竹田先生のセミナーやかやのさんの講演会の参加は必須で、年間と通じて定期的に実施する。黒字になるまでやる。予算200億円のプロジェクトから見れば2億円くらいの教育費は仕方が無い。安いものである。(ちなみにディズニーランドはもっと…である)それにプラスして、失敗の教訓を活かすなら、従業員は、男女比は「5:5」が原則とする。ということで、「小さな地方都市★レジャー施設開発のルール」などと、色々と考えてみた。明日は、某協会の方々とTDLツアー。晴れますように!
2003/09/08
コメント(0)
-

マニュアルに頼るとダメなんですか?
近年「マニュアル教育に頼っているからダメなんだ…」と言うような意見やら評論にお目にかかることが多くなってきた。そういうことはアッという間に伝染するから、セミナーや研修会でも同様の質問が必ずと言って良いほど飛び交うことになる。その時の僕の応えは逆で、マニュアルすら徹底していないからダメなんです、と言うことにしている。これは本心。中途半端にやっているところは、何かしらポカがあって、そうすると、マニュアルなんかいらいない…と、すぐにマニュアルの方に行く。マニュアルに責任はないはずで、作る人、使う人の問題。一方で、マニュアルのお陰で大成功している施設やチェーン店もある。その両方を経験するとよくわかることがある。成功しているところは、マニュアル一つとっても、気合が違う。内容が本当にきちんとしている。入社したてのパートさんが、一週間で一人前の仕事ができるようになっている。それは見る人が見れば宝物みたいなモノで、何十回のリニュアルを繰り返した迫力見たいなものが滲み出ている。マニュアル通りにやっていて、クレームが出たり失敗した際には、すぐにマニュアルの内容の方を点検する。それですぐに修正して全員に徹底する。だから、職場に悪人やいじめられっ子が少ない。反対の所は、2年前に誰かが作ったままの状態で、なるほど、いくら読んでも、もうすでに使い物にならない。現場の実態とかけ離れてしまっている。さらに、教え方にも大きな違いがあって、マニュアルを使わないで、自分の言葉で話す方がカッコイイと勘違いしてしまし、研修中、延々とサービスに関する想いや持論を語り続けていたりする。話している方はさぞかし気持ちいいかもしれないが、聞いていいる方は堪らない。それでもその時間も時給がもらえるなら…と頑張る。しかし、それで現場に出てで何もわからない。できない。すると、先輩スタッフに「何やってんだよ」「邪魔だよ」などと言われて萎縮して働くことになる。数ヶ月間頑張って、何とか仕事に自信がついたところで、人事評価が「中」だったりする。本人は頑張ったつもりだが、教えた上司は「まだ、あまい!」の一言。言われた方は、一体何があまいのか?わからないから腑に落ちない。マニュアルでしっかり「仕事のストライクゾーン」あるいは、そのお店なりの「サービスのストライクゾーン」を教えてもらい、それで、「ボール!」「ストライク!」と言われるなら納得が行くが、ストライクゾーンもロクに教えないで、気まぐれに「ボール!」とやられても、ちゃんとしたプレー(仕事)はできない。大体、ストライクゾーンがわからなければ、頑張りようもない。そして、だんだんとビクビクした仕事あるいはサービスになってくる。そうなると「トロイ」だの「気が利かない」だのと言われて、ますます仕事が嫌いになる。スポーツでも、ルールがきちんと整備されて、審判の実力がついてくると、大いに盛り上がりをみせるスポーツへと進化する。レジャーサービス業の世界の課題は、マニュアルだけではなく、「審判=トレーナーあるいは上司」の育成である。そうすれば「まったくトロイやつだなぁ」などと思っていたスタッフが、突然「盗塁」を決めるようになる。
2003/09/07
コメント(1)
-
ディズニーマジックの正体とは?
「ディズニーランドは何が凄いんですか?」と若いスタッフに聞かれた。ほんの少しの時間、僕と2人で帰り際のお客さんと見送っている時だった。「誰にでもできる当たり前のことを、どこにも負けないくらい徹底的にやっているからだよ」と応えた。入社前の研修からよくディズニーランドのことを聞いてくる子だった。その時は応えるたびに「えっえええ!?」などと、とても大きなリアクションでビックリしたり、感激したり…、なにしろそんな感じだった。ところが、今は、実際に現場に立って1年と4ヶ月。上司とアルバイトスタッフの間に挟まれながら日々悩んだり、喜んだり、泣いたり、笑ったり…喜怒哀楽の毎日を過ごしてきたせいだろうか、「なるほど…そういうことなんですね。やっとわかってきた気がします」と。「来週の公休に行ってきます。ディズニーランドに…。ディズニーマジックの正体を見てきます」と、僕の目をビシッと見つめてそう言った。サービス業の現場は、いくら講義しても、本を100冊読んでも、レポートを1000ページまとめても、うまくならない。文字通り「何でもあり」の世界で、格闘技なら「バーリトゥード」であり、PRIDEだ。戦ってみないとわからない。テーマパークの場合、もちろん直接戦うなどということはないが、お客さんは両方を知っている人ばかりである。お客さんを通しての壮絶なる戦いがある戦ってみて初めて相手の本当の強さや凄さがわかる。この業界であれば、ディズニーランドの他の追従を許さない運営とサービスの前に「タップ(ギブアップ)」することになる。しかし、こうしたやりとりはどこの施設でも若い社員とのことで、幹部社員は、「大体、うちはディズニーランドを造っているんじゃない」となる。こちらからすれば、その時点でタップ、いや試合放棄も同然で、こういう台詞が出る時というのは、「あのメニューは汚れていますよ。清掃しましょう」「電球が切れているものがあいます。すぐに交換しましょう」「幹部社員も現場に出る時はちゃんと名札をつけてください」「ポケットに手を入れるのは止めて下さい」…など、運営やサービスのモラルのことに触れる時だ。つまり、このくらいでキレているうちはこの業界に参入しない方がいいですよ、ということである。予選すら通過できませんよ、いいんですか?と。そうは言ったところで、プライドがどうのこうの…と言い訳が続く。500億円も投資して始めたビジネスなのに、ポケットに手を入れない、名札をつけることくらいなんてことはないはず。ポケットに手を入れたいなら、ポケットに手を入れた方が成功するようなビジネスをするべきであって、JALのパイロットになって、コックピットでっビールが飲みたい…と言っているようなものである。一方で、ディズニーランドに視察に行くと決めた彼女は、もちろん自腹である。なぜ、あのような質問をしてきたのか?と言うと、彼女が販売した商品を買った親子が、「~でも、ディズニーランドの方がやっぱり楽しいね…」と言いながら、彼女が包装した袋から商品を出して、事前に持参したと思われる、ディズニーランドの袋に入替えた。彼女が包んだ袋はそのまま捨てられた。そのシーンが脳裏に焼きついた(その親子には悪気はない)。精一杯の笑顔で応対していた彼女にとって、そのシーンは、突然、プロフェッショナルへのドアが開いたことを意味する。4回戦デビューはもうすぐだ。がんばれ!
2003/09/06
コメント(4)
-
顧客動向調査:10年前との比較は…
レジャー施設での動向調査をかれこれ10年やっている。かっこつけないで言えば尾行のようなもので、どういうルートで回って、どの店に入って、何時間くらい滞在したのか?などなど、調べていく。とても地味な業務である。だから、心中では「オレは探偵物語の工藤ちゃんなんだ…」と言い聞かせながら頑張る。今年の夏も、様々なところでやってみたが、改めて10年前と比べると、とても大きく変わったことがある。それは、ファミリーで来場したお客さんが、二手に別れて行動する頻度が高くなったこと。最も、10年前もそうしたファミリーはいたが、その数が多くなった。家族一緒に来場して、少し一緒に遊ぶ。しばらくすると、お父さんとお兄ちゃん、お母さんと妹のペアに別れて遊んでいるシーンが目についた。そういうことが重なるとメンバーも「最近の家族は、絆が薄いから…」「両親の不仲率が上がっているのかなぁ…」などと、無責任はことをつぶやいていた。しかし、改めて良く見ていくと、原因は「ケータイ」であった。これは年の功である者にしかわからなかった。10年前は、ケータイを持っている人は稀だった。ケータイがないと、はぐれたら再会するのが大変だから、よほどしっかり「12:00にここで待っててね」などの約束をかわさないと、うかうか別行動ができなかった。ところが、現代は、約束自体も結構ゆるめで、「夕方になったら連絡するから…」で、自由に別れる。それで、きちんと再会する。その傾向は、インフォメーションセンターにいるとさらに良くわかる。かつてのテーマパークや博覧会では、「迷子センター」や「呼び出し」「捜索」という業務が溢れんばかりで、多忙を極めた。ところが、近年では、メッキリ減った。ケータイで連絡が取れるからである。ところが、施設によっては、昔、博覧会でならした先生が設計していたりするから、卓球場ができるほどの広く豪華な迷子センターになっていたりする。当然、迷子センターまでもが閑古鳥状態で、プチ不良債権と化す。考えてみると、ケータイの普及で、施設の運営やサービスは相当変わったし、これからもどんどん変えて行かなければならない。ただし、ケータイは便利と言えば便利だが、せっかく家族で来ているのに、「いつでも連絡が取れるから」ということで、家族が別行動…というのには、少し寂しいものを感じる。せっかくの休日、親子で目一杯楽しんで頂きたい。パークに来て、園内の親子同士でメールのやり取りをしているシーンを見るとそう思う。コミュニケーションツールなんだけど、ヘタすると「離れているためのツール」にもなりかねない…のでは?と。
2003/09/05
コメント(4)
-
部長の販売促進策とは…?
夏休みの終わったテーマパークは、ゆったりしている。晴天で抜けるような青空の中、ウォーターパークを回ると、平日の女神たちがいる(業界のおじさん用語)。幼児を連れた若い主婦である。とはいっても、僕と同年代の頃の「お母さん」とはわけが違う。まったく違う人種である。コンサルの仕事だから…と心の中で言い聞かせても、あまり凝視できない。なぜか?きれいだからである。なんとなく気が引ける。皆、かっこいいのである。小さな浮き輪の子供をあやしていなければ、相当多くの男性たちは、「ロックオン」状態になるはずだ。もう、トップガンの世界である。マーケティングの会議で「ファミリー」とか「主婦層」で語られる人々を目の当たりにすると、改めて会議室での議論や資料の空しさを増す。主婦もこれまた相当に幅が広いことを思い知る。ある意味で一番広い領域かもしれない。40歳過ぎても黒木瞳さんがいる。かっこいいのは、ベッカムの妻ビクトリアだけではない。日本にもたくさんいる。主婦と言えば「主婦の友」を読んでいる…と思っている人たちに、現在の主婦を喜ばせたり満足させるのは、タイソンとヒクソン・グレーシーを戦わせるくらい難しい。ある施設で、「この夏は販売促進を強化する」「夏はファミリー、つまり主婦が多い」「主婦のためのお弁当でも用意しておいたらどうか?」と店舗に置かれた<幕ノ内弁当>は、見事に売れ残った。「主婦=幕ノ内弁当」というのも、あまりに乱暴な企画である。高校生の学園祭実行委員でもこんなことは考えないはず。自分の奥さんやお母さんをタブらせて考えるからこんなことになる。「時代は動いているんだ!」と月例会議で演説を打ったところで、現実に自分で考えると「主婦=幕ノ内弁当」である。本来であれば、「主婦=幕ノ内弁当」と起案した部長は、マーケティング部には向かないから自分で異動願いを書いて頂きたい…と思った。年収1000万円ももらっているのだから、それだけの仕事をしてもらわなければ、会社も割に合わない。それでもさらに、「売れなかった原因は、から揚げが小さかったから…」という分析。から揚げに責任を押付けるのか!と、参加したスタッフは怒りを通り越して、力が抜けてしまった様子。そのお陰で売上目標に届かなかったのだから…「部長っていったいなんなんだ?」「アメリカに留学してたって本当か?」「銀行系のシンクタンク出身なんじゃないの?」などの不信感の嵐が吹く。一方で、ロックオン状態になってばかりではなく、そのような主婦のパートを積極的に採用している施設もある。始めのうちは「えー主婦を採用するんですか?」と、納得いかない独身男性社員たちも、採用して一緒に働き出すと、思ったよりもきれいで、しかも小さなことではへこたれないタフさを持っていて、おまけに面倒見もいい。若い社員の愚痴まで受け止めてくれたりするから、大変喜んでいる。若いだけで、髪の毛とケータイばかりいじくり回してわがままな20前後の女性よりもいい…という意見もあったりする。「主婦=幕ノ内弁当」と言い放ったところでは、相変わらず主婦の採用は消極的。そんなことを言っているうちに、主婦の応募どころか、お客さんまで激減してしまい、平日は閑古鳥状態になってしまった。今日、あるパークでお話した主婦でパートIさんは、4200ccの4WDで通勤している。女子大生にもテキパキと指示を出す。社員にも改善案をチャキチャキ出す。20歳のギャルと一緒にカラオケも行く。Ayuのナンバーも唄う。けれどキャンディーズも唄える。振りまでつく。英語も話す…と、大変奥行きが深い人だった。そういう人に「休日に幕の内弁当が食べたいですか?」と聞いたら「レジャー施設で幕ノ内弁当が売れると言うことは、他にろくな食事が無いか、お店のサービスが遅くて並んでばかりいるからよ。食べたいと思って食べているわけではないと思うけど」と。「結局は、非常食なの」と一蹴された。失敗の教訓である。
2003/09/04
コメント(2)
-
@リゾート
ヨットハーバーを眺めるボードウォークで、パラソルの下でアイスコーヒーを飲む…。昨晩からコンサル先のリゾートに出張中。打合せの間に時間ができたので、ちょっと一息。次の打合せの内容をノートを広げておさらいすることに。これだけ天気のいい日に、こうしたロケーションで1人で考えごとができるのはありがたいシチュエーションだ。打合せの内容が多少ヘビーなものであっても、精神が落ち着いてきて自然にポジティブになっていくのがわかる。近年、自己啓発的な書物が数多く出版されているが、難しいこと考えなくても、こうした環境に身を置くことでも安らぎが手に入る。東京でも、二ヶ月に一回は、ディズニーランドでメンバーとミーティングをするようにしている。会議室では大激論になったり、なかなかまとまらなかった「持ち越し議題」をパーク内のレストランで話し合う。すると、やっぱり、よい結論、満足いく結論に至ることが多い。圧倒的に。そして、ようやく結論にいたってスッキリした頃、タイミングよく、エレクトリカルパレードが始まったりすれば、もう言うことはなし。大変贅沢なご褒美(インセンティブ)のように思えてくる。リゾートというと、何だかとても構えてしまい、周到な準備をしてから行くようなイメージが強いが、普段はできるだけ生活の一部として使うべきものだと思う。日本全国きちんと見渡せば、どの県にも大小さまざまなリゾート、あるいはプチリゾートがある。自宅やオフィスにこもらないで、外で人にあったり話し合ったり…。そういう場所にもっと活用したらよいのだと痛感している。PCに向かっての時間が多い分、こうした時間は今まで以上に大事にしていきたい。「若い女性…」の話も、せめてこうした環境で話せばもう少し中身のある案が生まれるような気がする。美人秘書の入れてくれたコーヒーもいいが、太陽の下で飲むアイスコーヒーにはかなわない。
2003/09/03
コメント(0)
-
若い女性たちのマーケティングとは?
レジャー施設の仕事をしていると、様々な打合せで「最近の若い女性たちは~な感じでしょう」「それに若い女性は~的傾向がある」「そうは言っても若い女性は~もあるはず」と、若い女性というターゲットの議論に事欠かない。ざっと考えただけでも、毎月、そのような打合せに計15時間くらい出席しているような気がする。さっき、その会議の様子をデジカメで撮った写真をPCに移して眺めてみた(ホワイトボードの記録を撮影するためのもの)。それをみていて気がついたことは、そのマーケティング会議に出席しているメンバーは100%の純度で40代、50代のオヤジ軍団である…ということ。しかも、天然で良質な油ギッシュな面々。こういうフォーメーションは、どこでもあまり変わらない。大抵はこうなる。そうした結果の集大成がこの十年間のリゾートやテーマパークの結果にきちんと反映されているから市場の評価は正直だ。だいたい「若い女性」とは、●何歳~何歳なのか?●25歳くらいで二児の母だけど、松たか子級の主婦の場合はどうなのか?●学生と社会人と家事手伝い…の場合は?●銀座のクラブで年収5000万円の24歳はどうするのか?…など、あまりに広いジャンルの議論であることを忘れて会議が進行する。「若い女性」をターゲットに、あれほど多くの雑誌が発売されているわけだから、もう好みは多種多様であることはすぐにわかる。我々おじさんたちの手におえる議論ではないはず…。しかも、参加者が約20名で、役員から代理店の幹部社員までの会議の実費は2時間で100万円は下らないはず。そういう立派?な会議に、「若い女性」たち(秘書か総務部と思われる)が、30分ごとに、お茶、コーヒー、ウーロン茶、ミネラルウォーターを会議室に運んで、配膳してくれている。20人に4回も配膳しているから、ほとんど議題や内容は聞いているはずだし、聞こえている。彼女たちは一体どう思っているのか?聞いてみたくなった。そういう会議で生まれた企画で、過去にビックリしたものは、●イタリアンフェア●カレーフェア●ビアガーデン●ハロウィンパーティ●スペシャル・クリスマス●おしゃれなガーデン●アメリカン・フェスティバル●カウントダウン・スペシャル・ディナー…など、思い出すのも大変なほど、特に会議をするまでもないようなものがたくさんある。これに、その打合せや会議と、それに伴う書類の作成や、業者の出張(飛行機、新幹線、ホテルなど)があったから、それらにかかる経費だけでも自爆行為であった。涙ぐましい努力では済まされないかもしれない。そうやって、企画会議ごっこではしゃいでいたら…ディズニーランドの1人勝ちの世の中になってしまった。ディズニーランドは確かに凄いが、逆に、追いかける方が上記のようなありさまだから、違う業界の出来事のような気がしてくる。中野区の高校生空手選手権で勝ったからといって、PRIDEに出ようとしているようなもの。もしくは、公民館で5年間、「早朝太極拳教室」に通っていた人が、K-1に出る…など。そのくらいレベルが違う。そうして、当時(90年代)、若い女性と言われて、お茶汲みをしていたスタッフたちが、いつか、ミルコやヒョードル(TDLやUSJなど)に向かっていく時(または、企画を任された時)の日本のレジャー産業が楽しみでしかたがない。
2003/09/02
コメント(1)
-
焼肉強化月間
久しぶりの丸一日のオフィスワークday。午前中に<デパ地下視察>のレポートをまとめる。メモとデジカメに撮影した写真を眺めながらPCに向かう。昼近くになると、写真が辛い。急激にお腹が空いてきた。ので、出張から戻ったスタッフとランチミーティングに。思わず<ステーキランチ>を注文する。食事をしながら、出張の報告をヒアリング。どこの施設でも人のことからおかしくなってくる。良い人が辞めていく。もしくは、トーンダウンしてくる。ただし、サービス業は意外に人間関係に弱い人が多い(と思う)。瞬間的な接客サービスは皆喜んでやるが、組織的な人間関係については、持久力がなかったり、コミュニケーション力が貧しかったりするから、現場の問題は尽きない。そんなことを考えながら、午後はサービスマインド研修の報告書と、参加者へのフィードバックメールを作成。久々の長時間のキーボード入力で、指が言うことをきかない。誤字脱字の修正に追われる。その後、レジャー施設のケータイコンテンツの打合せに参加。まさに日進月歩のケータイとはよく言ったもので、ちょっと学習していないと、新しい機能の話についていけなくなる。夕方から、月末の講演会の原稿案の作成に取りかかる。題材はディズニーランド。成功のノウハウが満載して溢れている。20年前の写真より今の方がきれいだから恐れ入る。まったく、他の追従を許さない。いくら研究しても飽きない不思議な場所である。久しぶりに、メンバーで食事をしよう!と。「何がいい?」「焼肉!」が圧倒的だった。ステーキランチを食べたことを後悔した。さらに許せないことに、冷静に記録を辿ると、昨晩も焼肉だった。こうなったら、今月は<焼肉の研究月間>にするしかない。
2003/09/01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1