2008年11月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-

本と共に~オバマ政権誕生
新聞の広告で目にして、先日来、『オバマ演説集』を探しているのですが、姫路のジュンク堂(ただいま引越準備中)では売り切れでした。探してくださったお姉さん曰く「今朝は、このあたりに並べてあったんですけどねぇ。」「売り切れかなぁ…私も、今日だけで2,3冊扱いましたからねぇ。」-----ならば仕方ないと、今日は最近近所に出来た大型書店「フタバ書店」に。コンピューターを叩いてくれた店員さん曰く「在庫がないですね。お取り寄せになります。」うーん、じゃ、いいです、と、次はイトーヨーカ堂内にある「くまざわ書店」へ。担当のお兄さんは、「新刊書」「語学」「話題書」と棚から棚へと走り回って「すいません。在庫がないみたいです。お取り寄せされますか?」-----すげー。すげー人気だ。大型書店をこれだけ本気で回って、どこでも売り切れって。 代わりに、父から言われていた『ブラック・ケネディ』を購入。これが、内容もさることながら、執筆者が面白い。元は、ドイツの「ターゲスシュピーゲル」という新聞社のワシントン支局記者がドイツ語で書いた本を、日本語に翻訳。さすが、世界中で注目されていた候補者だけあります。=====ここからは、少しだけ、この悪夢の8年間について。-----彼の演説を聞いて興奮し「そうだよ、あんた、ブッシュ以上だ!」と叫んだ聴衆の一人に対し、「大丈夫。君でも、ブッシュ以上の大統領候補にはなれるさ。」といなしたオバマ次期大統領に、私も同意見です。-----21世紀が始まり、9.11テロのあった、2001年。年末に、その年を振り返って「今年は最高の一年だったよ!」と言い放った、自称「神の代理人」。-----小泉政権にとって最大の不幸は、同盟国であるアメリカのカウンターパートがクズのチンパンジーだったことに尽きます。しかも、4年で終わらず、8年も!-----チンパンジーの悪口は書くと長いので自制しますが、平たく言えば、あんなのを大統領にして恥じないアメリカ人をアホでクズで品がない生物として軽蔑した8年間でもありました。今回の選挙で、ようやく、アメリカ人の知性と理性の回復を垣間見ることが出来ました。-----メディアは言います。「ブッシュの唯一の功績は、その政権運営によって、オバマを大統領に導いたことだ。」そうか。それならば、世界中にテロと恐怖と武器をばら撒いたクズにも存在価値があったと言えるか。まぁ、兵器産業とオイル産業にとっての神だったんでしょうが。殺す価値もない以上に、生きている価値がない、大統領史に汚点として永遠に刻まれる最低最悪の大統領。彼がキリスト教徒であることを踏まえて、敢えて言いたい。「自殺しやがれ、クソ野郎!(Kill yourself,Bush!)」-----そう、新年から、ようやく21世紀が始まります。願わくば、平和と対話の国際関係が築かれますように。=====寺山修司 『花嫁化鳥』新刊文庫で並んでいたので、なんとなく気になって手に取りましたが、想像以上にすごい。寺山修司が、地方の風習やら「ヒバゴン」やらを訪ねた論考なのですが、流暢な語り口の中が、「現実」と「知識」「自分の体験」を自然に結びつけ、ふっと「物語」の深淵を垣間見せてくれるのです。-----日本の歴史には、暗い部分があります。それは、「教科書に書かれない歴史」が切り捨てて顧みない真の意味での「教科書に書かれない歴史」。民俗学などがつまびらかにする、渦巻く呪詛、怨念、怨嗟、差別、死、殺し、人身売買…歴史の裂け目から垣間見える闇黒面(ダークサイド)-----それを、厭うのでも、距離を取るのでも、見ない振りをするのでもなく、「あるがまま」に受け入れ、さらりと文章にしてしまう、寺山修司。優しさ、というより、強さ、なのか。いや、さすがと言うか、何と言うか。=====重森三玲 『枯山水』ワタリウムさんの旅行や何やで、重森三玲先生のお名前は良く聞き、また、関西のカルチャースクールでは、血縁の方が講座を開かれたり、(日が合わなくて、行ったことないのが残念(>_
November 29, 2008
コメント(2)
-

【ラストチャンス!】「姫路城」四季折々
姫路城が「平成の大修理」に入るというお話は、皆様ご存知かと思います。今日、姫路で、この詳しい情報を頂いてきました。-----工期は平成21年秋から5年間を予定。とは言え、平成22年の3月までは、外観はそのまま、天守閣の見学も影響はないそうです。-----しかし、年が明ければ、平成21年。次の1年間が、四季の好きな時に姫路城を見ることが出来る、最後のチャンスとも言えます。-----私にとって、平成20年は、お正月に、初日の出に照らされる姫路城を見たことから始まって、姫路市立美術館のボランティアに登録したことで、ほぼ毎月の姫路行きとなりました。今回は、この一年で撮った写真を紹介。=====お正月の空気は特別で、初日の出のオレンジ色の光に照り映える白鷺城の姿は、夕日が映すのとは違う、荘厳な空気をまといます。 =====そして、春。姫路城は、絶好のお花見スポットでもあります。 淡く色づいた桜越しに眺める真っ白な城の姿の美しさ。=====夏。お城は、濃い緑に囲まれ、濃い青空の下、白が映える季節を迎えます。とは言え、僕が行ったのが、雨の日ばかりだったため、良い写真がないのが残念。=====秋。真っ赤に色づいた桜の葉。赤く黄色く燃える木々。 姫路城も美しいですけど、姫路には、書写山という紅葉スポットもあり、あわせて行くとより紅葉を楽しめるでしょう。※書写山:http://www.shosha.or.jp/=====そして、お城の隣に作られた日本庭園「好古園」も、10周年を過ぎて、木々も育ち、落ち着いた風情をかもしています。※好古園:http://www.city.himeji.lg.jp/koukoen/-----もちろん、駅からそぞろ歩く「みゆき通り」も楽しいですし、駅からは、100円で乗れるレトロ調のループバスも出ていて便利。※ループバス:http://www.shinkibus.co.jp/roopbus/roopbus.html-----また、最近では、おろし生姜醤油であっさり食べる「姫路おでん」や「カレー鍋」など、姫路発祥のB級グルメも有名です。-----さて、いつ姫路に来るか、予定は決まりましたか?お声をかけて頂ければ、出来る限りのご案内はさせて頂きますので、是非、この機会に、姫路へ!!お待ち申し上げております。※姫路観光協会:http://himeji-kanko.jp/
November 23, 2008
コメント(2)
-

in 『赤毛のアン展』 @高島屋大阪店
名作と言われて、しかし、読んでない作品って、たくさんあるのですが、残念なことに、『赤毛のアン』もその一つです。しかし、原作を読んでなくても感動できる、密度の濃い展覧会でした。=====もともとの、アンのストーリーに立脚した企画自体も魅力的なのですが、この展覧会では、それに加えて、 作者 モンゴメリの魅力 訳者 村岡花子の魅力 舞台 プリンス・エドワード島の魅力が語られます。=====【モンゴメリの魅力】1874年、プリンスエドワード島で生まれたモンゴメリの人生は、決して平担なものではありませんでした-----母は生後20ヶ月で亡くなり、父は西部へ行き再婚します。彼女は、母方の祖父母に引き取られ、厳格に躾られます。幼い頃から、文学を志し、教師を夢見ますが、女性が学歴を得ることは、大変難しい時代でもあり、それを説得するのも、容易ではありませんでした。父の元から通ったハイスクールには、義母から家事を押し付けられ、ほとんど行けず、1年足らずで、父の元から戻り、教員免許を取得、さらに大学へと進学し、小学校教師の職を得ます。-----「老夫婦が孤児院に男の子を申し込んだら、間違えて女の子が送られてきた」という新聞記事からヒントを得て、彼女は『赤毛のアン』を書き始めます。1年足らずで書き綴られた作品を出版社に送るも、4社から断わられます。そして、この作品は、そっと仕舞われてしまったのですが、しばらくして、再びこの作品を手にとって、面白さを確信した彼女は、もう一度別の出版社に作品を送ります。こうした経緯をたどって、作品が日の目を見たのは、1908年のこと。そう、今年は、「赤毛のアン」出版100周年なのです。出版された「アン」の評判は、大変良いものでした。-----作家としては成功したモンゴメリでしたが、その裏で、私生活では苦労をしていました。祖父の急死を受け、祖母の面倒を見るようになり、祖母の死の後は、長年住み慣れた家を離れざるを得なくなります。その時に5年前から婚約していた牧師と結婚するのですが、これが、36歳の時。その後も、牧師の妻として、地域活動に貢献し、夫の精神的支えとなり、母として子を育て(死産も経験します)そんな中で、数々の小説が書かれていったのです。=====さてさて、展覧会では、小説の中にも登場する犬の置物や、フルーツ籠、そして、直筆原稿が展示され、モンゴメリの足跡が紹介されます。-----面白かったのは、彼女が作っていたスクラップ帖のコピー展示。固定台に置かれたのを、自由にめくれるようになっているのですが、興味や関心、趣味が伺えて興味深い。モンゴメリって、自分の感じたたくさんの「素敵」を昇華して、「アン」という物語を綴っていったんだろうなぁ、と。=====【村岡花子の魅力】訳者 村岡花子の人生も、波瀾に満ちたものでした。関東大震災では、夫の経営する印刷会社が倒産。33歳の時には、長男を病気で亡くし、戦争では、多くの友人との別れを体験します。-----東洋英和女学校で学んだ彼女は、カナダ人教師から英語を学びました。その後、山梨英和女学校で英語教師をし、教文館で本の編集に携わります。「王様と乞食」の翻訳や、家庭雑誌「青蘭」発行。また、NHKラジオでの子供向けニュース担当として、「ラジオのおばさん」として親しまれますが、これも、太平洋戦争が始まるまでのことでした。親しかったカナダ人宣教師たちは、戦争が始まる前に、日本から去っていかざるをえませんでした。その時に、彼女へと託された本の一冊が、「赤毛のアン」でした。戦後、彼女の手になる翻訳が、三笠書房より出版されます。今現在、新潮文庫から出ている文庫版も彼女の訳です。-----カナダ人宣教師から贈られたアンの物語は、村岡花子さんの手によって、日本の子供達への素敵なプレゼントとなったのです。=====展覧会では、彼女の生涯の紹介と、ゆかりの品々が展示されています。面白かったのは、ラジオの子供ニュースが聞けること。落ち着いた、ゆっくりとした語り口は、さすが「ラジオのおばさん」だなぁ、と。=====【アンの世界の魅力】続いて、シリーズ第1作「赤毛のアン」の作品世界が展示されています。所々のエピソードは、聞いた覚えがあるなぁ…新潮文庫の新装版の表紙となっている丁寧で端正な、ガッシュ水彩画の原画が並びます。再現された物語中の料理。プリンスエドワード島で演じられているミュージカルのポスターと衣裳。-----アンを原作とした、映画とアニメの紹介。「世界名作劇場」の「赤毛のアン」おお~。懐かしい!たしかに、そんなのやってた覚えはあります。ちゃんとは覚えてないですけどね。当然、当時は、高畑勲さんが監督だとか、宮崎駿さんが作画スタッフだとか、知りませんでしたけど。映画版も美しい。=====【プリンスエドワード島の魅力】当時のプリンス・エドワード島で使われていた生活用品の展示。洗濯機とか、アイロンとか、ちょっと懐かし面白い感じ。今の生活に関わる展示として、巨大なキルト作品、刺繍作品。そして、モニターには、吉村和敏さんが撮られた、プリンスエドワード島の四季が映されます。 何と言うか、手の届く幸せって、良いなぁ、と。本当の意味で、豊かだなぁ、と。=====いやはや、ものすごく豊かで盛りだくさんな内容で、お土産物(タイアップグッズ。意外と好きだったり。)も充実していて、大満足でした。家を探したら、本がある、と思ったんだけど、2巻しか見つからないんだよなぁ。ちょっと読んでみたら、いや、面白い。とは言え、まだ読み終えてないですけど。新装版(訳は村岡花子さんのまま)も出たそうだし、ちょっとちゃんと読んでみますか。=====『赤毛のアン』展 @高島屋大阪店 (難波)展覧会(出版100周年記念企画)公式サイト:http://www.anne100th.com/[会期]2008.09/04(木)~2008.09/15(月) [開館]10:00-20:00[料金] 一般 800円 / 大学・高校生 600円 / 中学生以下無料東京、名古屋、広島、大阪では終わりましたが、年明けには福岡、仙台、札幌、そして京都、大分、横浜とまだまだ巡回は続くようですね。お近くで開催された際には、是非。
November 22, 2008
コメント(0)
-

▼Movie▼『L change the WorLd』
こんなアホな「L」がおってたまるかいッ!ワシが探偵でも、もうちょっとちゃんとするわッ、ボケッ!という関西のおっちゃんなつっこみを可能としてしまう、グダグダ・ムービーでした。-----『アフター・スクール』とか、『ジャージの二人』とか、ちゃんとしてて面白い日本映画は、大劇場で公開されないのに、こういう「お金をかけた駄作」が「好評」とか報道されるのは、まったくもって、いったいどうなんだろう。ああ、お金のかけどころが、宣伝費なんだなぁ…。=====えっと、まぁ、ストーリーは、ウィルス・テロのあったタイの村から、なんだかんだ逃げ出してきた男の子と、命を狙われている研究者の娘さんを、「L」が頑張って助けました。というものです。-----おお。今までで一番短くて分かりやすい無いよう紹介だ。あ。変換ミスだ。内容です。うーん。この映画に関して言えば、あまり違いないですけど(>_
November 19, 2008
コメント(0)
-

♪Movie♪ 『デトロイト・メタル・シティ』
しばらく前から、神戸三ノ宮のジュンク堂のマンガが置かれている階で、「DMC」のテーマが、ミニ映像と共に流され、気になっていました。で、原作を読んでみると、いやはや、なんとも。というわけで、予習を済ませて、映画に臨みました。=====田舎から出てきて、大学の軽音サークルで、カジヒデキ的音楽を奏で、それなりに尊敬される先輩であった根岸は、音楽の世界へと進みます。「NO MUSIC NO DREAM !!!」しかし、その音楽会社で、今、彼が演っているバンドは、「デトロイト・メタル・シティ(DMC)」。問答無用のデス・メタル・バンド&サウンド。「僕が演りたかったのは、こんなバンドじゃない!」という彼の叫びも虚しく、彼は「ヨハネ・クラウザー二世」と名乗り、デス・メタル・ヴォーカリストとしての才能を開花させます。-----それでも、プライベートでは、路上で甘い恋の歌など唄ってみるのですが、聞いてくれるのは犬くらい。運命の再会を果たした相川さんとのデートで、オシャレカフェで舞台に立つチャンスを得るも、「お遊戯じゃないんだ」と貶められる始末。-----本人の思惑とは裏腹に、DMCはインディーズ界を席巻していきます。全てに嫌気がさし、何もかも捨てて故郷に帰る彼。そこで再発見する自分自身の「才能」。文字通り、地獄から甦った「ヨハネ・クラウザー二世」が、今、信者どもを引き連れて、最終決戦の舞台へと走り出す!=====主人公より、ヒロインより、何をおいても拍手を送りたいのが、我らが大倉孝二大先生!『ピンポン』のアクマでも、『新撰組!』でも、『スウィング・ガール』でも、この人の曲者ぶりは、腹が立つほど素晴らしかったですけど、正直、この映画、この人のお芝居なしでは、成立しません(断言)役柄としては、ただの「ファン代表」ではあるのですが、彼が「解説」することによって、「ヨハネ・クラウザー二世」の行動が、「信者たち」に意味を持って伝えられていくという、まさに、伝道師役。この役を説得力を持って演じられる、というのは、奇跡に近い。-----音楽会社の社長役を演じて魅せる、松雪泰子さん。彼女の歪んだ「愛」が、物語を導くわけですが、役に負けないスーパーハイテンション。セリフが下品あることすら忘れさせられるくらいの、ぶっちぎり演技。-----そして、帝王ジャック・イル・ダーク役に、KISSヴォーカル、ジーン・シモンズさん。音楽には素人の僕でさえ、ゾクゾクしてしまう、あまりに、あまりに、圧倒的な存在感。正直、あまりにも存在感がありすぎて、物語のバランスを崩してしまってます。「ヨハネ・クラウザー二世」役の松山ケンイチさんがいかに頑張ろうと、いかに上手かろうと、貫禄負けは仕方ない。-----主役に、松山ケンイチさん。うーん。5年前なら、きっと窪塚さんだったよなぁ。ヒロイン役に、加藤ローサさん。可愛い。=====マンガの世界観を、強引に実写に持っていったことで、違う形での笑いになっているのが、面白い。例えば、マンガの、メイクを落として、クラウザーメイクして、を繰り返す、というギャグは、マンガだから成り立つ早替えの笑いなのに、それを、本当に実写にしてしまう、なんてのは、その度胸も含めて、身体を張ったギャグ。「本当にやっちゃいますか!」となると、笑うしかないでしょう。-----あるいは、決戦の場に向かう、ヨハネ・クラウザー二世。必要ないのに、走って会場に向かう、それだけだと、物語の破綻ですが、必要以上に、ずっと走り続ける、それを延々と見せられると、もう笑うしかない。-----相川さんに嫌われた、とガラスを叩くヨハネ・クラウザー二世。叩いているのが、楽器屋さんの窓というのは出来すぎなんですけど、このギャグ的世界観なら、このシーンで泣き出しちゃった女の子が、クラウザーさんが「乱入」する遊園地にもいる、というのも、むしろ、アリ。-----帝王ジャック・イル・ダークが、既に音楽対決ではなくなった激しい戦いの末、どう考えても、音楽的には勝ててないクラウザーさんに勝ちを譲る、という無茶も、「いや、それはないだろ~」と心の中で突っ込んでしまってることを思えば、しまった、そういうギャグか、と。=====ギャグ映画としては、それなりに面白いし楽しいと思います。ああ、ああ、しかし、しかし。確かに「物語」としては、お母さんとのやり取りのくだりや、相川さんとのアイデンティティに関わるやり取りなど、ヒューマンなドラマはあってもおかしくないのですが、そこまでちゃんと「物語」しなくても良いのになぁ、というのが、正直な感想。ぶっちゃけ、ぶっ飛びギャグ映画で通しても良いのに、と。もちろん、これだけの豪華キャストを揃えた以上、商業的には、そうやって丸めないと成り立たないのでしょうが。-----現実問題として、「面舵…(胸をつかむ)」のギャグとか「悪魔玉(相手の口に痰を吐く)」とかを、実写で加藤ローサさん(じゃなくても、可愛い女の子)相手にやれたら、正直、不愉快だし、犯罪な気がするから、「ひよこ(スカートめくり)」で十分なんですけどね。-----破壊的なギャグは、それだけで魅力なんだけど…。という気持ちは、スタッフも同じのようで、深夜アニメでは、その破壊性が全壊…全開のようです。うちの地区では放送されないので、そして、さすがにビデオを借りる気はないので、どうなのかは分かりませんが。-----音楽的なことは良く分からないので、そちらの観点では、あまり突っ込んだ話はできませんが、ギャグ映画と商業映画の両方の要件を十分に充たした作品だったと思います。=====『デトロイト・メタル・シティ』2008年 日本 104分http://www.go-to-dmc.jp/index.html監督:李闘士男 出演:松山ケンイチ / 加藤ローサ / 松雪泰子 / ジーン・シモンズ / 大倉孝二 / 細田よしひこ / 秋山竜次 他★★★☆☆原作:若杉公徳
November 18, 2008
コメント(0)
-
▼Movie▼『少林少女』
CMで見た、柴咲コウさんのカンフー・ラクロスがカッコ良かったので、映画館に観に行きました騙されました。いや、カンフー・ラクロス映画で良かったのに。めちゃな敵とか出て、すごい必殺技とか出すんだけど、カンフーで逆転みたいな、そういうのを期待していたので、なんともかんとも。あー。ストーリーを略すのも面倒だ。=====中国で少林拳の修行を終えて日本に帰ってきた少女が、なんか知らんけど、大学に入ってラクロスをやることになって、練習を通じて、友情とか育んで、メンバーに少林寺拳法を教えたりするようになるんだけど、なんか知らんけど、彼女を狙う悪い組織、というか人がいて、それが彼女の実家の道場を潰した犯人でもあって、なんか知らんけど、そいつが塔の高い所にいて悪いことしてるから、塔で順番に雑魚とか倒していって、そいつと戦って勝つ、と。エンディングでようやく、ラクロスで活躍する姿が見れます。これはカッコ良い。短いけど。-----えーっと、突っ込みどころが多過ぎて…。「お前と戦ってみたかった」みたいなこと言うなら、雑魚をいっぱいけしかけるなよ、とか、中国人留学生が、柴咲コウさんからカンフーを習うのは、日本人留学生が、ベルリンでドイツ人に寿司の握り方を教えてもらうようなものじゃねーか、とかいや、なんか、もう良いや。=====主演は、柴咲コウさん。問答無用でカッコ良いし、上手い。本当素敵です。-----彼女の兄弟子に、江口洋介さん。これまた、カッコ良く頼りがいある「兄貴」を演じています。-----ジョーカーな役に、ナインティナインの岡村隆史さん。普通のシーンでも、さりげなくカンフーアクションを取り入れた動きを見せつつ、最後には大活躍を見せてくれます。この人の身体能力も、本当に高い。-----すごく偉い役に、仲村トオルさん。鍛えている肉体と言い、すごいしカッコ良いのですが、いかんせん、私の中では「あぶない刑事」のいじめられ役のイメージが強くて、どうしても、「そんな偉そうなこと言ったら、館さんに怒られるよ…」とか、「柴咲コウさんじゃなく、木の実ナナさん相手なら…」とか思ってしまって、どうにもイメージがついてこない。いや、カッコ良いのですよ?=====いやはや、役者もアクションも素晴らしいのですが、ストーリーが許しがたい程にダメダメ。ギャグならギャグなりの、ハチャメチャならハチャメチャなりの、「物語の中のリアリティ」があれば、それなりに楽しみますけど、(「インディ・ジョーンズ」でも「パイレーツ・オブ・カリビアン」でも何でも良いや)そんなの皆無で、しかも最後は「愛」みたいな、サイテーな脚本。これだけマンガ文化の発達した国で、こんなにストーリーの破綻した作品が書けるなんて、赦しがたいというより、理解不能です。ジャンプなら、2週で打ち切りくらいの勢いですよ。役者が素晴らしいだけに、なおもったいない。てか、1年かけて特訓した柴咲さんをはじめ、絶対めっちゃ頑張ったはずなのに、活躍のシーンがほとんどない、ラクロスメンバーの女の子たち、頑張った岡村さん、江口さん、仲村さん、名前を貸してしまったチャウ・シンチーさん、みんな可哀想。-----「チーム・アメリカ」という、ぶっとんだ映画がありましたが、その製作チームが常に意識していたのが、「ブラッカイマーならどうするか」だったそうです。『アルマゲドン』やら『パイレーツ・オブ・カリビアン』やら、ヒット作連発の辣腕プロデューサーの「ハリウッド臭さ」を笑い飛ばすため、その手法をわざと真似て、それを人形劇でやってみせたわけですが、笑いなり、ドラマなりを、大きなレベルでやりたいのなら、それくらいの確信犯をやっても良いし、せめて研究はしよう。-----つまらないオリジナリティなんていりません。どうせそういう映画だと思って、楽しみに観に来ているんだから。非日常で面白い、ストレスなんてぶっ飛ばしてくれるそんな作品を期待していたのになぁ。残念です。=====『少林少女』2008年 日本 107分http://www.shaolingirl.jp/blog/監督:本広克行出演:柴咲コウ / 江口洋介 / 岡村隆史 / 仲村トオル 他★☆☆☆☆
November 15, 2008
コメント(0)
-

in 『生活と芸術-アーツ&クラフツ』展 @京都国立近代美術館
楽しみにしていたのですが、期待以上に素晴らしい展覧会でした。別の機会に行った、父や友人から「期待してなかったのに、素晴らしかった」という評価を耳にしていたので、是非とも、と。ちょうど京都は紅葉がはじまるシーズンで、まだ「見頃」には遠かったものの、夜間拝観も始まり、素晴らしい行楽になりました。=====さて、アーツ&クラフツ運動は、なんと言ってもウィリアム・モリスなしには語れません。2005年に汐留ミュージアムで「ウィリアム・モリス」展に行きましたが、その時は、あくまで、「モリスのデザイン」が中心だったので、その後の展開、系譜をたどれるというのは、なかなか興味深い体験でした。-----最初の部屋で目に付くのは、大きな大きなタペストリー。堂々たる獅子を真ん中に、その姿を見返る狐、警戒と畏怖をもって背中を向ける兎。背景には、生命力溢れる緑の木々と、カラフルなのに控えめな色彩の花々。その背景に溶け込むように、左右のそれぞれの端には、立派な孔雀と、烏。-----私自身は、その視点には気付いていなかったのですが、モリスの功績として挙げられるのは、「アーツ&クラフツ運動」を通じて、工業化が進む中で、手仕事の良さを見直したこと」だけでなく、それによって、「工業化の中で失われつつあった、手仕事による伝統技法を復活させ、新しい息吹を与えたこと」という指摘には、はっとさせられました。もしかしたら、私がモリスに惹かれる根本にも、この「伝統への眼差し」という意識はあるのかも知れません。-----モリスの住んでいた「レッド・ハウス」そして「ケルムスコット・マナーの家」。写真や、調度品の展示から伺われる、モリス・センスの生活。それは、例えば、一時期流行ったデザイナーズマンションなどがもっていた「クールさ」とは対極の、温かみのある、家自体が息づいているかのような、居心地良い空間演出。=====アーツ&クラフツ運動は、時代も国境も越えて、広がりを見せます。都市に展開した例として挙げられるのが、「アーツ&クラフツ展協会」の活動。協会は、装飾芸術を対象とした展覧会を開き、担い手たちに活躍の舞台を与え、また、その成果を商業と結びつける役割を果たしました。-----例えば、ベンソンの暖炉用衝立は、幾何学的なデザインが、面白い一品。自らの工房で扱うだけでなく、モリス商会を通じて、販売されました。あるいは、第一回の展覧会で出品されたルイス・F・デイのキャビネット。「家具にデザイナーの名前を入れる」方針に、大手家具メーカーは当初難色を示していたそうですが、第3回を迎える頃には、参加するメーカーも増えて行ったそうです。-----本の飾り文字に見られるカリグラフィ(西洋書道)。これも、アーツ&クラフツ運動が復興させた「デザイン」の一つです。文字の装飾、本の装丁、文字組みのデザイン、それらは確かに、渾然一体となって、一つの芸術世界を提示します。-----商業化と共に、運動は、美術学校としても結実していきます。レニー・マッキントッシュを輩出したグラスゴー美術学校。洗練されたデザインの椅子や家具の数々。-----そう、こうやって時代を下ると、段々、デザインが洗練されていき、気がつけば、それは、モリスのデザインよりお洒落でありながら、何か完成されてしまったような寂しさを感じさせないでもありません。それは、アール・ヌーヴォーそしてアール・デコへと繋がる、デザインの萌芽。=====さて、目を田園地方に転じると、アーツ&クラフツ運動は、別の力を持ちます。それは「地域伝統技術の再発見と再興」という役割であり、力です。C.R.アシュビーは「アーツ&クラフツの本来の場所は田園」として、工房をチッピング・キャムデンに移し、自身のデザインと、伝統技術の融合した、ギルド作品を世に出していきます。=====アーツ&クラフツ運動の影響は、イギリス国内のみにとどまるものではありませんでした。-----当時の文化の都の一つであったウィーンでは、クリムトなどが所属するウィーン分離派が装飾芸術を礼賛し、グラスゴー美術学校のメンバーの作品を集めた展覧会が開かれ、C.R.アシュビーの影響を受けて、ウィーン工房が設立されました。このメンバーの中には、「芸術は必要にのみ従う」と語った建築家オットー・ワーグナーも含まれています。展覧会では、彼がデザインした椅子などが展示され、その主張の通り、機能性とデザイン性が融合した、美しい姿を見せてくれています。ウィーン美術工芸学校で教鞭をとっていたヨーゼフ・ホフマンがデザインしたカトラリー(フォーク・スプーン・ナイフなど)の洗練されたフォルムも、息をのむほど美しい。あるいは、ウィーン工房が成功した部門の一つである、ファッション部門。モリス調のデザインが、プリントされた生地で作られた洋服のお洒落なこと。-----ロシアやデンマーク、ノルウェーにも、運動は波及します。もともと、「安くて品質もデザインも悪い大量生産」へのアンチテーゼとして始まったアーツ&クラフツ運動は、しかし、まだ手工業が中心だったこれらの地方では、ナショナリズム=自分たちの足元の文化の見直し、として作用しました。伝統のデザインを見直し、今のセンスにマッチさせて、世界に問う、アーツ&クラフツ運動はそういう意味を担っていたのです。-----さて、目をドイツに向けると、ドイツでは、工業へのアンチテーゼではなく、うまく工業と連携する形で、工業デザインとしてのアーツ&クラフツの展開がありました。一連の「製品」のセンスを見ていると、思い出すのは、そう、バウハウス。この展覧会の中では触れられていませんでしたが、「最終的に建築を目指す姿勢」や「芸術は必要にのみ従う」という思想、それに加えて、この工業との連携、工業にデザインを取り戻す姿勢は、まさにバウハウスの姿勢そのものです。=====ここまででも、十分に満足のいく内容だったのに、この先にもすごいのが待っていました。日本のアーツ&クラフツとして、「民藝運動」が紹介されているのですが、この質も量も、共に素晴らしくて、これだけでも十分に美術展が開けるほど。-----出迎えは、木喰作の地蔵菩薩像。「柔和」を体現したような丸く優しい笑顔は、心を和ませてくれます。大胆な大津絵。雷様が落とした太鼓を拾おうとするユーモラスな画題は、日本における、神様と民衆のかかわりの一端を感じさせてくれます。刺し子に片口、霰釜、お盆に背負子。生活に根付いたデザインの豊かで温かなこと。今なお語り継がれる「YANAGI」柳宗悦の眼の鋭どさ、ではなく、温かさと確かさが偲ばれます。-----そしてそして、再現された三國荘の十全なる美しさ。華美ではない、質素ではない、心を満たす豊かさに充ちた贅沢な空間。その空間を充たすのは、河井寛次郎、富本憲吉、バーナード・リーチといった温故知新の体現者達の陶芸作品。-----紅型に触発された染織作家、芹沢けい介の「沖縄絵図六曲屏風」は、ようやく沖縄へと渡り、過ごした時期の作品。沖縄の地図の上に、風景と文物を文字通り「織り込んだ」この作品は、朱が目を引く島の彩り、鮮やかな青の海の色、紅型特有の味わいが、沖縄の地図に収斂されていく、なんとも不思議な魅力があります。-----そして、この展覧会の最後を飾るのは、棟方志功の「十大第子」です。この素朴さと大胆さが一体となった迫力。しかも、この大作が1週間で仕上られたという伝説。すごい、の一言に尽きます。=====いやはや、楽しませて頂きました。見事で素晴らしい、この秋の大収穫、な展覧会でした。=====『生活と芸術-アーツ&クラフツ展 ウィリアム・モリスから民芸まで』展 @京都国立近代美術館 (京都)[会期]2008.09/13(土)~2008.11/09(日) [開館]10:30-17:00[料金] 一般 1,300円 / 大学生 1,000円 / 高校生 500円 / 中学生以下無料作者: ウィリアム・モリス [William Morris] (1834-1896) レニー・マッキントッシュ [Charles Rennie Mackintosh] (1868-1928) C.R.アシュビー [C.R.Ashbee] (1863-1942) オットー・ワーグナー [Otto Wagner] (1841-1918) 柳宗悦 [YANAGI Muneyoshi] (1889-1961) 河井寛次郎 [KAWAI Kanjoro] (1890-1966) 富本憲吉 [TOMIMOTO Kenkichi] (1886-1963) バーナード・リーチ [Bernard Howell Leach] (1887-1979) 芹沢けい介 [SERIZAWA Keisuke] (1895-1984) 棟方志功 [MUNAKATA Shiko] (1903-1975)この展覧会、次は東京!東京都美術館で、2009年 01/24-04/05開催。そして愛知県美術館へと回りますので、お楽しみに♪
November 12, 2008
コメント(2)
-

♪Movie♪『ジャージの二人』
題名からして、不思議感が漂ってますけど、「なんかこう~」なんとも味のある、不思議な作品でした。======久しぶりに、軽井沢の「別荘」と呼ぶにはちょっとくたびれたおうちに、二人で向かった父と息子。そこでの、何も起こらない、でも何か不思議な日常が綴られます。-----グラビアカメラマンの父は、息子の母とは離婚して、別な人と結婚しているんだけど、ちょっと最近仲が良くないらしい。息子は、最近仕事を辞めて、現在フリーター。父には語らないのだけれども、妻との間に、問題を抱えてる。こういったことが、多く語られるわけではなく、ジャージで過ごす、「なんかこう~」な普通の日常が描かれる中で、なんとなく理解されます。なんてことのない日常の出来事が、笑いをもたらす、トマトのくだりは秀逸。-----一年後、息子は妻を連れて、今度は三人で「別荘生活」が始まります。妻と歩くキャベツ畑。語られない言葉が物語る妻への思い。それぞれの態度が物語る二人の関係。仕事のために帰る妻と、それを見送る親子。-----かわって、やってくる父の後妻の娘、花ちゃん。明るく振る舞う彼女の姿も、父には心配。三人で過ごす「なんかこう~」な時間。-----花ちゃんも、父も帰り、一人になって、息子は、ずっと抱えたままだった白紙の原稿と向かい合います。嵐の中、書き上げられる物語。-----ラストのワンシーンは、何と言うか、リアル。何ともつらい、というか、やるせない時、ふっと、面白いこと、そして、それを伝えることに、喜びを見出して現実逃避してしまうこと、ってあると思うのです。======主人公である「息子」役に、堺雅人さん。悩みを抱えても表に出さない主人公。その微妙な心の動きを「体現」してしまう演技力は、正に役者。「父」役に、シーナ&ロケッツの鮎川誠さん。「なんかこう~」寡黙で自然体な存在感ある父親を自然体で演ってしまうのは、いや、すごい。下手な役者気取りの俳優より、よっぽど素晴らしい「役者さん」でした。それにしても、二人がジャージ姿で並ぶのは「なんかこう~」卑怯な気がします。「妻」役に、水野美紀さん。ダンナを裏切って甘えて悪びれない(彼女を主人公にすれば一昔前の「純愛」になるんでしょうが)「汚れ」役に、説得力ある息吹を与えています。謎のご近所さん「遠山さん」役に、大楠道代さん。つかみどころのない、どことなく暖かで不思議な存在感で、物語に不安感と安心感を同時に与えます。======この物語で、重要な役割を担うのが携帯。携帯の通じない「別荘」という非日常の空間だからこそ、「携帯が繋がる」ことの特別さが際立ちます。それは、「家の電話で話す」とは違う特別な「繋がり」。-----たくさん、家族それぞれ、個人個人の問題は抱えているんだけれど、それを真面目に相談するわけではないし、全く語らないわけでもない。そこに「何か」が投げかけられることで、「ドラマ」になるわけですが、何も投げかけられない、「日常」を切り取ることで、静かな「なんかこう~」時間がゆっくり流れている感覚を与えてくれる、のんびりムービーでした。-----『猛スピードで母は』で芥川賞を受賞した長嶋有さんの原作は読んでいないのですけど、原作も「なんかこう~」な感じなのかしら。また、先々読んでみたいものですね。======『ジャージの二人』2008年 日本 93分http://www.ja-zi2.jp/監督:中村義洋出演:堺雅人 / 鮎川誠 / 水野美紀 / 田中あさみ / 大楠道代 / ダンカン 他★★★★☆原作:長嶋有
November 2, 2008
コメント(490)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- 芸能ニュース
- 水上恒司(26)『中学聖日記』から7…
- (2025-11-19 17:50:25)
-
-
-
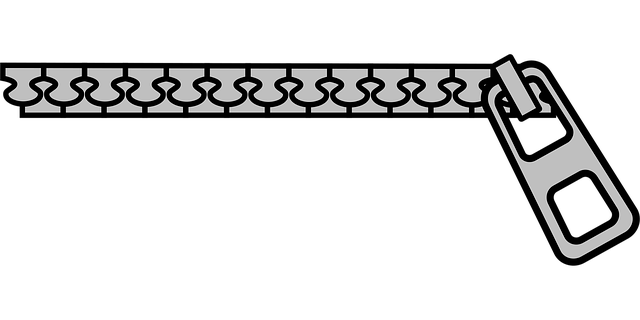
- どんなテレビを見ました?
- ソーイング・ビー8 (7) キルティン…
- (2025-11-20 12:20:11)
-
-
-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…
- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…
- (2025-04-26 15:25:48)
-






