2007年12月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
来年のオペラ鑑賞は
2008年の主なオペラ劇場来日公演は5月~6月 ウィーン・フォルクスオーパー 「こうもり」、「ボッカチオ」、「マルタ」7月パリ・オペラ座公演 「アリアーヌと青ひげ」 「トリスタンとイゾルデ」 「青ひげ公の城/消えた男の日記」10~11月ウィーン国立歌劇場 「コシ・ファン・トゥッテ」R.ムーティ指揮、 「フィデリオ」小澤征爾指揮 「ロベルト・デヴェリュー」【演奏会形式】F.ハイダー指揮 ウィーン・フォルクスオーパーは1月にソフィア国立オペレッタ劇場「こうもり」へ行くこともありオペレッタはパス。パリ・オペラ座は初来日公演とのことだが最安価席でも2万と高額なためパス。ウィーン国立歌劇場は「フィデリオ」が小澤征爾指揮・神奈川県民ホールなのでぜひ行きたいところだが安価席の入手は困難か。新国立3月「アイーダ」は会員先行でチケットを入手。一般発売は即完売だったようで。アイーダ役ノルマ・ファンティーニと豪華な演出が楽しみ。(最近恒例のキャスト変更が無ければ良いが)当方のオペラ合唱出演も既に3公演が決まっており、来年も忙しい年になりそうだ。End
2007.12.30
コメント(2)
-
年末は「第九」とともに
今年は2回の合唱出演あり。1つは300人の小規模ホール、ピアノ伴奏でベートーヴェンをテーマにした音楽劇の中で第四楽章を歌うもので、あと一つは2000人超大規模ホール、プロのフルオーケストラで全楽章+合唱幻想曲のコンサート。好対照の演奏会であるが、改めて本曲の素晴らしさと難しさを認識することになった。音楽劇冒頭でベートーヴェン役が「シラーの詩に『おお友よ、このような音ではない!我々はもっと心地よい、もっと歓喜に満ち溢れる歌を歌おうではないか』を付け加えた」との台詞があり、神に感謝し、兄弟達と歓びを歌う詩であり、どんなに高い音でもけして苦痛ではなく?、歓びとして歌うべきことを再認識出来た。ただ合唱としては高音部がやたらに多く歌うのはけして容易ではない。管弦楽としても難しく、ソリスト含め全てを上手く合わせるのは困難な曲であり、今回も色々とあったが舞台裏話なので省略。なぜ「第九」を年末に演奏するかについては『1937年にヨーゼフ・ローゼンシュトックが新交響楽団(現在のNHK交響楽団)の音楽総監督に就任した際、「ドイツでは習慣として大晦日に第九を演奏している」と紹介し、年末の演奏が始まった。実際に年末に第九を演奏しているドイツのオーケストラとして、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団が挙げられる(出典Wikipedia)。』となっているが、ウィーンフィルやベルリンフィルでは恒例ではなく、その後に書かれている、『戦後オーケストラの収入が少なく、楽団員の年末年始の生活に困る現状を改善するため、「必ず(客が)入る曲目」であった第九を日本交響楽団が年末に演奏するようになり、それを定例としたことが発端。』が正しいのでしょう。そう言えばベートーヴェンの誕生日12月16日に因んでとの話も聞いたような。『Webぶらあぼ』情報によれば12月だけで155回とのことで何とも驚くべき数。TVでも大阪城ホールの1万人の第九の放送をしていたっけ。それだけ多くの人々を引きつける魅力がこの曲にはあるのでしょう。来年2月に立川志の輔原作の『歓喜の歌』の映画があるようで、こちらも楽しみ。End
2007.12.23
コメント(5)
-
レニングラード歌劇場のカルメンはバレエが素晴らしい
鑑賞日:2007年12月9日(日)16:00開演入場料:¥5,000 D席2階(16列38番)主催:光藍社、神奈川芸術協会レニングラード国立歌劇場来日公演歌劇「カルメン」ビゼー作曲全2幕4場 原語上演・日本語字幕付会場:グリーンホール相模大野指 揮:ミハイル・パブージン 管弦楽:レニングラード歌劇場管弦楽団合 唱:レニングラード歌劇場合唱団バレエ:レニングラード歌劇場バレエ演 出:スタニスラフ・ガウダシンスキー 出演カルメン:エカテリーナ・エゴロワドン・ホセ:ミハイル・マカロフエシカミーリョ:アレクサンドル・クズネツォフミカエラ:マリア・リトケスニガ:アレクサンドル・マトヴェーエフモラレス:ドミトリー・ネラソフダンカイロ:アレクダンドル・ペトロフレメンダード:ヴァレンチン・シェヴェレフフラスキータ:オリガ・シャニーナメルセデス:ヴァレンチナ・サラプロワ感想カルメンは今年既に小澤征爾音楽塾のオペラ鑑賞、鎌倉での演奏会形式のオペラに合唱出演をしており今回で3度目。今回のチケットは1月に既に予約しており、その当時は3回も聴くことになるとは想いもしていなかったのだが。本公演を選んだのは、会場のグリーンホール相模大野が未経験であることと、昨年のキエフ・オペラ(ウクライナ国立歌劇場)『トゥーランドット』が思いの外良かったので、またロシア歌劇場のオペラをと。なおレニングラードは既にサンクトペテルブルクとの名前に代わっており、当国立劇場も「ムソルグスキー記念 サンクトペテルブルク国立アカデミックオペラ・バレエ劇場」が正式名称とのこと。今回も言葉がフランス語、舞台はスペイン、演奏者はロシア人、観客のほとんどは日本人との摩訶不思議な組み合わせ。序曲の途中から幕が上がりさっそくバレエが入る。カルメン役の女性の周りに男性が数人入っての踊りは鮮やか。これから始まるオペラのストーリーが見えて来る内容で、ダンサーは容姿と言い、踊り自身やその揃い具合は、普段見ている日本人のバレエとは全く異なったレベル。4幕ではバレエ用の音楽場面も入っており素晴らしかった。年末から始まる当歌劇場のバレエの公演も観てみたくなった。舞台装置は1幕から4幕まで舞台中央を取り囲む様に、舞台上部までつながる茶色の壁が設けられ、それを斜めにしたり、門や橋、牛の頭の像等を加え、照明を変えることでそれなりに場面を作っていた。1幕兵隊達の合唱から始まるのだが、結構バラバラな印象。どうもピッタリと合わせることを余り重要視していないようで、NHK等の海外オペラ放送番組を観てもよく感じる。1幕と4幕の子供達の合唱は省略。出演者の中では主役二人の歌声が良かった。カルメン役エゴロワは若干ビブラートが入るが低音部まで良く聞こえており、場面に合わせ歌声の表情を変え良かった。ドン・ホセ役マカロフは2幕アリアの「花の歌」は頑張って歌い、その後少しダウン気味だったが、4幕はまた持ち直しなかなか良かった。二人の4幕の演技は、エスカミーリョの投げた赤いマントを上手く使い、やり取り表現し、最後の刺殺場面は赤い照明とともに最高潮に。ここまで盛り上げたのは管弦楽の力も効いている。序曲から1幕当たりは音の乱れやズレが少々気になったが、4幕の盛り上がりは素晴らしく、昨年のウクライナ国立歌劇場よりは随分と上手い。指揮者はレニングラード歌劇場の公演チラシ等に載っているアフロヘアーの音楽監督アンドレイ・アニハーノフではなく、七三分けのミハイル・パブージン。若そうだが音楽のためやうねり、強弱を上手く出しており、この当たりは同歌劇場指揮者の強みか。ただエスカミーリョの「闘牛士の歌」が少しテンポが早すぎて違和感有り。声の調子は良さそうだったが。ミカエラ役リトケは声が大きいだけで、役柄もう少し透明感のある声質の方が良いが、もちろん聞こえなくなるよりは良い。今回2階席奥の天井桟敷だったが、このホールは2階奥でも舞台を近く感じることが出来、音響もいつもの東京文化会館や神奈川県民ホールより良く、オペラ向きと感じた。また相模大野の駅からは商店街を通り、更に伊勢丹デパートの店舗の中を通って行くのだが、伊勢丹は何と夜の10時まで営業しておりコンサート帰りにも立ち寄れるようになっている。デパート、商店街はすっかりクリスマスの風景となっていた。End
2007.12.09
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- 70年代サブカルチャー URC, ELEC, …
- まんだらけの優待のまんだらけZEM…
- (2023-06-24 23:18:46)
-
-
-
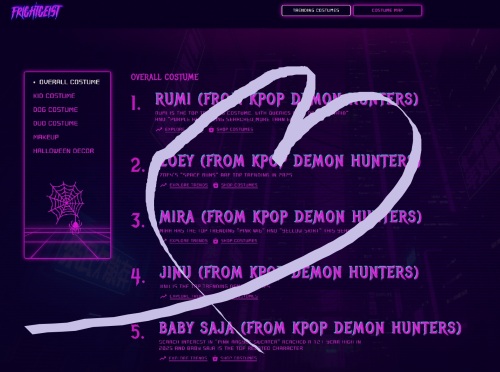
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- The moment Prog Rock went too far
- (2025-11-17 01:31:07)
-







