2007年03月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
真央ちゃんはハバネラなのだ
昨日は「ラ・ボエーム」第2幕の児童合唱と合同練習。子供達への指導はその集中力を持続させるために、大人への指導より一層のハイテンションが要求され指揮者は本当にご苦労様でした。段々と全体の形が見えて来た段階で、面白くなってきた。本日は色々都合があり、チケットを取っていたオペラには行けず。夜はTVで世界フィギアのエキビジションを観た。メダルを争う本選も確かに緊張感があって良いのだが、その緊張感から解放されたエキビジションは自由な音楽の選曲と合間って、より音楽と合わせてのショーとの意味合いが高まってより楽しい。今大会SPで出遅れ銀メダルだった浅田真央の選曲はオペラ「カルメン」のハバネラ。その曲に合わせたドラマチックな演技で、大人の雰囲気も出て、大変良かった。(当方は安藤美姫のファンなので、今回の金メダルは満足)なお「ハバネラ」とは正確にはスペイン舞曲ではなくキューバの大衆舞曲とのこと。先週の世界水泳シンクロナイズスイミングの日本代表チームで音楽にカルミナブラーナが使われており改めてその劇的な音楽性を再認識した。11月の演奏会では如何にその音楽性を表現出来るのか。と言うことで音楽を使ったスポーツに取ってクラシック音楽とは大変重要な部分を占めていることを認識することが出来た。End
2007.03.25
コメント(0)
-
ヴェルディもやはり歌い手で決まる
鑑賞日:2007年3月18日(日) 14:00開演入場料:\5,670 4階席(1列18番)主催:新国立劇場オペラ「運命の力」G.ヴェルディ作曲全4幕【イタリア語上演/字幕付】会場:新国立劇場オペラ劇場【原作】リヴァス公爵ドン・アンヘル・デ・サーヴェドラ【台本】フランチェスコ・マリア・ピアーヴェ (改訂版:アントーニオ・ギスランツォーニ)指 揮: マウリツィオ・バルバチーニ演 出: エミリオ・サージ美術・衣裳:ローレンス・コルベッラ照 明: 磯野 睦再演演出: 田尾下 哲舞台監督: 大仁田 雅彦合唱指揮: 三澤 洋史合 唱: 新国立劇場合唱団管弦楽: 東京交響楽団出演:レオノーラ: インドラ・トーマスドン・アルヴァーロ: 水口 聡ドン・カルロ: ウラディーミル・チェルノフプレツィオジッラ: 林 美智子グァルディアーノ神父:妻屋 秀和フラ・メリトーネ: 晴 雅彦カラトラーヴァ侯爵: 小野 和彦クッラ: 鈴木 涼子マストロ・トラブーコ:加茂下 稔村 長: タン・ジュンボ軍 医: 大久保 光哉感想昨日ブリテン「戦争レクイエム」の合唱本番が終了(児童合唱が素晴らしかった)し、その足で夜は「ラ・ボエーム」の合唱練習。今日は朝から草刈りのボランティア活動に参加し、3週間連続で新国立劇場へ(ヘトヘトで書き込み中)。本日の公演はヴェルディ中期作品の「運命の力」。ロシアのサンクト・ペテルブルク帝室歌劇場の依頼で作曲された作品で舞台は18世紀のスペインのセリビアなのだが、今日の舞台設定は20世紀で第1次対戦頃の設定となっている。お話しは、混血のアルヴァーロ(本当はインカ王族の血筋)が公爵の娘レオノーラと駆け落ちをする所を公爵に見つかり、投げ出した拳銃が不発し公爵に当たり、娘も恨み亡くなる。息子のカルロが敵討ちをするため探し周り、遂にアルヴァーロを見つけ決闘をしたが返り討ちに、それを聞いたレオノーラが見に行ってカルロに最後の力で刺され兄妹が亡くなる場面で幕。いかに運命に翻弄される人々となるかは、歌い手の技量にかかっている割合が多い作品。歌手の中ではドン・カルロ役ウラディーミル・チェルノフとプレツィオジッラ役林美智子が良かった。林美智子は「フィガロの結婚」のケルビーノ役の印象が強いのだが、本日のジプシー女役もなかなか様になっており、ラタプランの合唱も良かった。(合唱を歌ったことがあるが早口言葉的な所があり結構難しい)レオノーラ役インドラ・トーマスはMET他アメリカで注目のソプラノ歌手とのことだが、ビブラートが多く音程が不安定で好きな声質でない。ドン・アルヴァーロ役は高音部が多く大変なのだが水口聡が最後までがんばっていた。管弦楽は音量の大小が旨く表現されていおり、4幕最後の消え入りそうな弦楽器は良かった。今日からSuicaが私鉄、地下鉄共通で使用出来るようになり、スムーズに移動できた。End
2007.03.18
コメント(0)
-
イギリス人ブリテンは皮肉・風刺屋だ
鑑賞日:2007年3月11日(日) 14:00開演入場料:\3,600 1階席(6列38番)主催:新国立劇場オペラ研修所 研修公演オペラ「アルバート・ヘリング」ベンジャミン・ブリテン作曲全3幕【原語(英語)上演/字幕付】会場:新国立劇場中劇場原作:ギー・ド・モーパッサン (短編小説「ユッソン夫人のばらの樹」)台本:エリック・クロージャー作曲:ベンジャミン・ブリテン指揮・音楽指導:アンドリュー・グリーンウッド演出・演技指導:デイヴィッド・エドワーズヘッド・コーチ:ブライアン・マスダ美術・衣裳:コリン・メイズ管弦楽:東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団出演:レディ・ビロウズ: エレン・ファン・ハーレン(賛助出演)フローレンス・パイク:小林紗季子(第9期生)ミス・ワーズワース: 田島千愛(第8期生)ゲッジ牧師: 青山貴(第4期生・賛助出演)アップフォールド市長:河野知久(第7期生)バッド警察署長: 森雅史(第8期生)シド: 近藤圭(第9期生)アルバート・ヘリング:中川正崇(第8期生)ナンシー: マーサ・ブレディン(賛助出演)ヘリング夫人: 増田弥生(第4期生・賛助出演)エミー: 山口清子(第9期生)シス: 鷲尾麻衣(第7期生)ハリー: 前嶋のぞみ(第8期生)感想今回名前を聞くのも初めての作品でだが、現在ブリテン作曲の戦争レクイエムの合唱練習をしており、不協和音が多発する作曲者のオペラ作品を一度聴いてみたかったことと、オペラ研修所研修生が出演とのことで若さ溢れる元気な声を聴きたいとの思いで先週に引き続き新国立劇場へ出かけた。お話しはイギリスの小さな村で貞操を尽くす清純な「5月の女王」を選ぼうとするのだが、村中の若い女性の生活態度から該当者がなく、青果屋の息子がアルバート・ヘリングが親に従い女性とも付き合ったことがない品行方正な生活態度から「5月の王」に選ばれる。その5月祭の表彰式で悪友から酒入りレモネードをのまされ、その夜から行方不明になる。翌日村中懸命の捜査でも見つけられず「自殺か?」となったところで登場。実は賞金を手に初めて夜遊びをして戻ったことで、母親の干渉・拘束から抜けだし、自分自身を見いだしたと高らかに歌うと言うホームドラマの様な内容。ところが無料パンフレットによると「1947年度グラインドボーン音楽祭」の委託作品として作られたとなると意味は大きく異なってくる。イギリスのグラインドボーン音楽祭は、ロンドンから100キロ離れたイーストサセックス州グラインドボーンに住む大富豪ジョン・クリスティーが、自分の屋敷に増築して約300人が入れる劇場を建て、1934年からオペラを上演したもの。現在は800人位のホールになっているのだが、上演内容の素晴らしさからプレミアチケットとなるとともに、観客は全て第一正装を要求されるらしい。つまりは音楽祭主催者や観客が5月の(女)王を押しつける社会的立場の人たちであり、それを強烈に批判する作品となるわけで、確かに当時主催者は眉をひそめただろう。アルバート・ヘリングが最後に「この機会を与えてくれてありがとう」と歌うのだが、正しくブリテンが主催者側や観客達をからかっているようであり、本当にブリテンはイギリス人らしく皮肉屋で風刺屋なのだ。実は戦前に日本の皇紀2600年記念祝典のために依頼されシンフォニア・ダ・レクイエムを作曲したが皇室のための祝典曲にレクイエム(死者のためのミサ)は不敬であるとして日本政府は演奏を禁止したいわくもある(これは軍国日本を批判したためか、純粋に音楽として作ったかは不明)。と話は尽きないものの、音楽の方は不協和音の混沌とした中から美しい旋律が突如歌われたり、4、5重唱では全員異なった言葉をぶつけるように歌いその中から一つの言葉が現れたり、旋律の終わりでベルや鐘が鳴ったりと、戦争レクイエムと同じく、いかにもブリテン作品との印象。管弦楽はピアノも含め良くその特徴が生かされ演奏されていた。イギリス人指揮者の功績か。歌手では若手研修生が元気に歌っている印象。その中ではタイトルロール、アルバート・ヘリング役の中川正崇が柔らかい声でも表現もあり良かった。レディ・ビロウズ役エレン・ファン・ハーレンはさすがの存在感ある声と演技だった。今回全席同一料金なので6列目(実質3列目?)中央と絶好の席を確保でき、チケットの値段分は十分に楽しめた。またぜひ研修生オペラを観てみたい気になった。End
2007.03.11
コメント(2)
-
ワーグナーは歌い手が重要
鑑賞日:2007年3月4日(日) 14:00開演入場料:\5,670 4階席(1列14番)主催:新国立劇場さまよえるオランダ人R.ワーグナー作曲全3幕【ドイツ語上演/字幕付】会場:新国立劇場オペラ劇場指 揮: ミヒャエル・ボーダー演 出: マティアス・フォン・シュテークマン美 術: 堀尾 幸男衣 裳: ひびの こづえ照 明: 磯野 睦舞台監督:菅原 多敢弘管弦楽: 東京交響楽団合 唱: 新国立劇場合唱団出演:ダーラント:松位 浩ゼンタ: アニヤ・カンペエリック: エンドリック・ヴォトリッヒマリー: 竹本 節子舵手: 高橋 淳オランダ人:ユハ・ウーシタロ感想本日は遂に日本オペラの殿堂、新国立劇場オペラ劇場での初めての鑑賞。とは言えいつもの天井桟敷の最上階だが、変な手すりもなく、傾斜もあり、どの席からも舞台が見えやすく座席も十分ではないが我慢できるスペースが確保されている印象。音の方は、最上階でも良く聞こえてくる。ワーグナー作品を丸々通して生で聴くのは初めての経験で、途中で眠くならないかと心配したが、今回初期の作品でそれほど難解でもなく、長さも休憩入れて丁度3時間と適当な長さだったため、楽しめて観ることが出来た。お話しの方は、さまよえるオランダ人=幽霊船船長が7年に一度陸に上がれる際に一人の乙女が永遠の愛を捧げられれば呪いが解かれる話しなのだが、個人的な恋愛よりも救済の愛との意味合いであり、その部分は理解が難しい。演出は第1幕で船の甲板の部分が嵐の中現れたり、闇の中から赤い光とともに幽霊船が現れたりと照明を旨く使って表現されている。先ずはオーケストラが大音量と音無しの部分差が旨く演奏されていた。そして合唱は有名な「水夫の合唱」では50人の男声合唱で迫力があり良かった。後半掛け合いとなる幽霊船からの合唱はPAを使っていたようで録音かな。歌手ではゼンタ役アニヤ・カンペが、Pの部分から最期のFまで表情豊かに歌いきり良かった。タイトルロールのオランダ人役ユハ・ウーシタロ(フィンランド人でフルート奏者出身と異色)大変存在感があった。本役はウィーン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座でも歌われており得意役なのでしょう。ちらしに挟まっていたが、劇場内レストラン「マエストロ」ではその日のオペラにちなんだ、幕間、ディナーが用意されており、一度はゆっくりと食べてみたいものだが、今日もカーテンコールそこそこに駅へダッシュとなった。End
2007.03.04
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- KAN 全39曲をCD3枚に収録した『KAN …
- (2025-11-11 22:53:08)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-
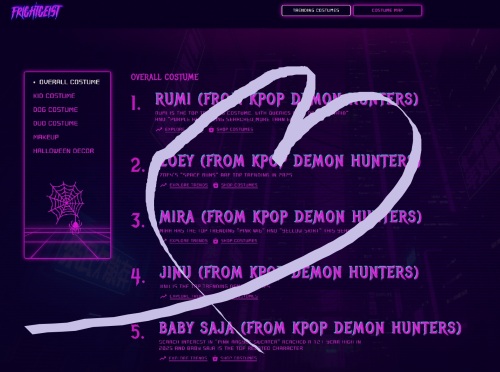
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-







