2013年08月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

8月のおしゃれ手紙:異常気象
猛暑!今年の暑さは異常で・・・。でも、異常気象って毎年言っているような・・・。1992年ブラジル・リオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットでは、「今年が地球を救う最後の年・・・」といわれていて、私たちも何とかしなければと思ってイベントを開いたものだった。あれから20年以上。毎年の暑さは、人類への罰だ。でも、これから産まれてくる子どもたちのためになんとかしないと・・・。■映画2013年8月見た映画■■冒険者たち■2013.8.7■ローン・レンジャー■2013.8.7■タイピスト!■2013.8.20■少年H■2013.8.27■書き残したネタ■*終活「身軽に暮らす」*白虎隊の歌*さすけねぇ*「君をだいて」*友人の100か日。*「とっさの方言」*消えゆく職業:「猫のしっぽカエルの手」*「最高の離婚」*湿布薬の効果*探偵!ナイトスクープ*からほり御屋敷再生複合ショップ「練」*桜*近つ飛鳥*近つ、遠つ*多肉植物*悲しみや苦しみを見つめること。*排熱エネルギー*東京駅の特別な出口*領土問題*「二年間の休暇」の難点。*土人、女性は家事をすることが好き。*キラキラネーム*和泉市の美術館*もっと緑が欲しいのだ!(駐車場)*「清貧の思想」*橋元大阪市長 *みどり学*ファーストレディ *「小石川の家」*あさぶら*小説「アーレンガート」*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月29日*器歳時記:金魚の絵皿 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.31
コメント(0)
-

奈良のカフェ「くるみの木」
11時半の開店にそなえて10時過ぎから人が並び始める、奈良の超人気カフェ、「くるみの木」。ていねいに作られた滋味豊かな味わいのランチを求めて、関西圏はもちろん東京や、遠くは北海道や沖縄からも毎日たくさんの人が訪れています。東京にさえ、カフェや雑貨店が少なかった25年前。奈良のはずれに「くるみの木」は生まれた-。 そんな奈良の名所ともいうべきカフェ「くるみの木」に8月27日(火)行ってきた。近鉄なんば駅から近鉄奈良駅までは、40分かからない。林の中にあるような素敵なカフェ。「くるみの木」に着いたのは、10時半ごろだった。火曜日だし、空いているかもと思ったのが大違い。すでに多くの人が、順番を書いて待っていた。関西だけでなく多くのファンがいて、関西に来た時には、奈良の大仏は見なくてもここに来ようというくらいの人気だ。11時に併設の雑貨店が開店すると、そこで雑貨を見ながら待つ。それを観終わると、外に出て、周りを散策。薪を積んだ壁と大きな木、鉢植えのイチジクの木が素敵。この薪は、冬の暖をとるためのストーブの薪だがアクセントになっている。ストーブの煙突もかっこいい!!スタッフが庭の木の枝や花を切っていたが、店内に入るとその枝があちこちに飾ってあった。 カフェについて待つこと2時間。やっと席に着くことができたのは、12時半を過ぎていた。どこをとっても、隙のないかっこいいカフェで、有名になるはず。 ■くるみの木一条店■■住所:〒630-8113 奈良県奈良市法蓮町567-1■TEL/FAX 0742-23-8286 ■休みは■ここ■■アクセス近鉄奈良駅orJR奈良駅より奈良交通バス「西大寺行」または「航空自衛隊行き」に乗車。「教育大附属中学校前」下車。踏切方向に徒歩3分。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月29日* 器歳時記:金魚の絵皿 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.29
コメント(0)
-

少年H★妹尾河童
■少年H:あらすじ■すべてを失ったあの夏、我が家の未来が始まった。昭和初期の神戸。Hこと妹尾肇(吉岡竜輝)は、好奇心に満ちた少年だった。洋服の仕立屋を営む父・盛夫(水谷豊)、優しい母・敏子(伊藤蘭)に温かく見守られながら、妹の好子(花田優里音)とともにのびのびと育った。幸せいっぱいに過ごす妹尾一家だったが、近所のうどん屋の兄ちゃん(小栗旬)が政治犯として逮捕されたり、召集されたおとこ姉ちゃん(早乙女太一)が脱走したりと、一家の周囲にも次第に戦争の足音が忍び寄ってきた。 べストセラーとなった 妹尾河童・原作「少年H」を読んだのは、もう10数年前。まだ元気だった父に会いに、老人ホームに行った時、「『少年H』を読んだか?」と聞かれた。私がまだだと答えると、「そりゃあ、いけん。読まれぇ(読んで)」と渡されたのが今持っている2冊の文庫本。さっそく読んだら面白くて、あっという間に読んでしまった。妹尾河童の少年時代の戦争体験だけれど、辛さの中にユーモアがある。あたたかい家庭が描かれている。まっとうな父と母。のびのびを育ったH少年。仲間との野球や裸で海で泳ぐこと。今の子どもたちが失った、子ども本来の姿が小説には書かれていた。だから、悲惨なはずの戦争体験がどこか楽しい。もちろん、「うどん屋のにいちゃん」が「アカ」というだけで警察にとらわれたり、「おとこ姉ちゃん」が脱走兵としていなくなり、クビつり自殺するなど悲惨な事がおこる。H少年の家はクリスチャンで、父がテーラーなので外人からの注文も多かったので、目をつけられ、嫌がらせを受ける。戦争を賛美していた大人たちも戦後は手のひらを返したようにアメリカを賛美する。何事もなかったかのように振る舞う戦争に加担した大人たちに腹がたつ。原発大賛成だった人が、3.11以来、何のためらいもなく、原発は怖いというのに似ている。日本人は、忘れやすい民族なのか。原作者の妹尾河童氏が先日「徹子の部屋」に出て「少年H」について語っていた。それによると、「少年H」の映画化の話は小説が発表以来沢山あったそうだ。しかし、これまでは断ってきたという。しかし、監督が降旗康男というので、今回は受けたのだそうだ。少年の目を通して描かれた戦争の問題を提起した「少年H」は、父から私に、そして今年の夏、10歳の孫が読んだ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月26日*父の麦わら帽子:目次 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.28
コメント(0)
-

昔語り:花同じからず
私の子ども頃は、ガーデニングなどという言葉はなかった。けれども、夏になるといろんな花を見かけた。■朝顔■私の子どもの頃の夏の花の代表は、なんといっても朝顔だ。村に疎開をして来ている家族があったが、その家の朝顔を見るのがラジオ体操の帰り道の楽しみだった。■:朝顔の思い出 ■■ノコギリソウ■ピンクの小さな花が寄り集まって咲いている花。うちの家の前の家族が作っていた。のこぎりの様なギザギザの葉っぱは、その名前の由来なのだなと思っていた。葉は歯痛、偏頭痛対策に使われる他、乾燥して粉にし、タバコの代用品にすることもあったというが、使っているのを見たことがない。■アメリカ草■おなじく、うちの前の家に毎年咲くのがこの花。1m足らずの高さに黄色い花を咲かせていた。私も植えたことがある■キクイモ■の花に似て、キクイモのことを「アメリカイモ」というらしいから、これだったのだろうか?「アメリカ草」と呼んでいたあの植物の本当の名前はなんというのだろう?最近、黄色い花を見たが「アメリカ草」はこれだったのだろうか。■アオイ■アオイもよく見た。ゼニアオイという花が小さい地味なアオイばかりだったが・・・。ゼニアオイは、ハーブティとして使われるらしいが、ハーブという言葉を知ったのは20代になってからだった。■ケイトウ■近所に植えている家があった。この花は、墓参りの際、供えていた。日本でも食用植物として栽培されていた時期があるというが、食べたことはない。■ネムノキ■ネムノキも懐かしい夏の花だ。夏休みの間中、毎日、川で泳いでいたが疲れるとあお向けに川の中に漂った。その時、 目に映ったのが、薄紅色の花と優しげな葉っぱ、花咲く合歓の木・・・。■川遊び・・・花咲く、合歓(ねむ)の木の下で ■山が川まで迫っている大きなネムノキの花の咲くあの場所は、今は車が通れるようになって、変わってしまった。年年歳歳花あい似たり歳歳年年人同じからず毎年美しい花は同じように咲くが、この花を見る人々は毎年変わっているのだ。という詩があるが、現代では、半世紀以上たつと、花同じからずだ。最近、見かけなくなった昔の夏を彩った花は、今も心にしっかりと咲いている。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月26日*父の麦わら帽子:目次 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.26
コメント(0)
-
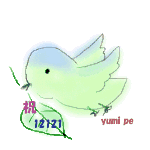
天然生活:特集「本棚は親友」
雑誌「天然生活」を京都の大好きな本屋さん「恵文社」で買った。●特集は、「本棚は親友」で雅姫さん、吉本由美さん、赤木明登さん、岸 朝子さん私をつくる、8冊の教科書を興味深く読んだ。 デザイナーでモデルの雅姫さんの8冊は、ライフスタイルのビジュアルブックが多いが中に「はらぺこあおむし」と「イリスの庭」は、私も持っている。(「はらぺこあおむし」は孫にやったから、正確には、もっていた。) 「チープ・シック」、「すてきなあなたに」など私と同世代の文筆家の吉本由美さんがもっている本は全て気になる。なかでも、■【送料無料】独り居の日記 [ メー・サートン ]同性愛者であることをカミングアウトし、世間から非難を受けた著者がどん底から立ち直る内容。 吉本さんの著書 「かっこよく年をとりたい」を書く参考になった」そうだ。■《立風書房》稲垣足穂月球儀少年 極美についての一考察 【中古】afb 少年愛を描いた作品集。吉本さんは、「ダンディズムに満ちた硬い石のような文章に憧れました。とくに原稿書きにいき詰まったときに読むと刺激をもらえるんです。」私は読んだことがないが、著者は稲垣足穂という本読みの間では有名な人。吉本さんの8冊はどれも気になるが手に入りにくそう。他に塗師の赤木明登さんや料理記者の岸 朝子さんの8冊もその人らしさがあらわれていて面白い。よその家の本棚をのぞくような気分で楽しい。「必要な本は自然と手元に集まって来る。」塗師の赤木明登さんの言葉。私を作る8冊の教科書を考えてみよう。■◎キリバン鳥◎NYヤンキースのイチローは4000本ヒット。「おしゃれ手紙」は。もうすぐ「876543」ヒット。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月24日*北国(ほっこく)の雷 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.24
コメント(0)
-

タイピスト!★キュート
■タイピスト!:あらすじ■♪音が出ます!マドモアゼルのド根性を見せてあげる。1950年代のフランスでは、社会進出しようとする女性たちの間で一番花形の職業は秘書だった。田舎から出てきたローズ(デボラ・フランソワ)もそんな一人で、保険会社を経営するルイ(ロマン・デュリス)の秘書となる。ドジで不器用すぎるため1週間でクビを宣告されるが、ローズにタイピングの才能を見出したルイは、彼女にある提案をする。当時秘書の中で、タイプライター早打ち大会で優勝することはステイタスとなっており、一大競技として人気を誇っていた。ルイはローズと組んで、タイプライター早打ちの世界大会で優勝を目論んでいた。地方予選に出場したローズは、初めて触れる試合の空気に飲み込まれあえなく敗退。ルイは1本指ではなく10本の指を使ったタイピングをするよう矯正し、難解な文学書のタイプやジョギングなどのハードなメニューを課して、ローズを特訓する。その甲斐あって地方予選を1位通過したローズだが、全仏大会には2連覇中の最強の女王が待ち構えていた……。 キュートな映画だ。冒頭の味気ない雑貨店に置かれた、タイプライター。ころんとした形がキュート!車のラインもころんとしたまるみをおびていて、キュート!若い女性のファッションもかわいい!1950年代って戦争が終わって、少したってからだから、世の中も落ち着いている。女性は戦時中には出来なかったおしゃれをする。そのおしゃれがかわいいのだ。スカートは、フレアスカートで膝下。全時代で比べても、この時代のファッションが一番かわいいかも。映画は水色やピンクなどの淡い色が沢山使われていて、乙女チック。 ところで、ローズの働く事務所では、シュレッダーが使われていた。1950年代には、シュレッダーがあったのだろうか?またタイプライターの指を乗せる部分がカラフルなのにも驚いた。どの指を使うかを色分けしているのだったら、タイプの練習にいいな。もうひとつ、ローズのマニキュアのカラフルなこと。当時は、赤かピンクだと思っていたのに、本当にあったころだろうか。■アーティスト■、■オーケストラ!■の製作陣が作った映画。 私の高校生時代、英語の時間に英文タイプライターを習ったことがある。苦手だったが、当時は、必須だった。和文タイプも会社に入ってから使った。当時はパソコンなどなかったから、和文タイプで打って、それを謄写版で印刷したような記憶がある。その次に使ったのは、ワープロ。これは、90年代に、環境保全団体の通信を作るために、けっこう使った。1997年にパソコンをかって今にいたるが、どこまで進歩するのだろう。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月20日*里山の旬だより:お天気話 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.20
コメント(0)
-

デジカメ、キボンヌ
■2003年4月3日に産まれた孫も■はや10歳。■2歳ですでに電車の形を覚え異常なくらいに電車に興味を覚えていた。■そんな孫、ちゅん太が今興味があるのは、カメラ。今年の誕生日プレゼントに「ipad」をもらって、そのカメラで写しまくっているらしい。 先日、長女と孫・ちゅん太を私で出かけた時のこと。「今、動画が撮れるカメラが欲しいんや」とちゅん太。「動画を撮ってYou tubeにアップするのが夢やねん。友達の○○ちゃんは、やってるんや、ハンドルネームをつけて」と続けた。今どきの10歳はスゴイな。夫なんか、未だに私のipadにさえ触ることが出来ないのに・・・。アルバイト先の冷蔵庫に寝転んだ姿をアップする若者が話題になり、その店は閉店を余儀なくされているというニュースをテレビで何度も見た。彼らにとって、ネットは、産まれた時からあるのだから、いたづらを友人に知らせるために軽い気持ちでネットを使ったのだろう。結果、アルバイト先の店や自分自身がどれほど傷つくかも知らないで・・・。ネット社会といわれて久しいが、カメラ、*キボンヌ*の10歳の孫が動画をアップする日も近いだろう。*キボンヌ「希望する」という意味。2チャンネルでよく使われている。 シドニーオリンピックの100mハードルで、 日本代表に金沢イボンヌという選手がいました。で、なかなかインパクトのある名前であったため、 誰かが 希望すると書くところを、語呂合わせで「キボンヌ」と書いた所、これが受けて現在でも使われている訳です。 ■Yahoo!知恵袋■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月15日*なぜ、お盆に墓参りなのか? *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.15
コメント(0)
-

方言:じぇじぇ
NHKの朝ドラ■「あまちゃん」■が大人気で私もはまっている。特に、「じぇ」という方言が今年の流行語大賞の有力候補という勢い。「じぇ」とは、驚きの時に発する岩手県久慈市小袖地区の言葉。「じぇ」、「じぇじぇ」、「じぇじぇじぇ」と驚きの大きさによって変わる。「じぇ」という言葉を使うのは、ほんの少しの集落だけらしい。しかし、近くには、「じゃ」や、「じゃ」、「ざー」、「ば」という言葉があるというから「じぇじぇじぇ!」である。「じぇ」は「じゃ」から変化したものだそうだ。 「じぇ」は、室町時代には、京都で使われていた言葉だそうだ。「じぇ」という言葉の残る久慈市小袖地区は、リアス式海岸で、かつては人の往来が少なかった。そこで新しい言葉が入って来ることなく、「じぇ」が使われていたのだそうだ。東北弁といえばマイナーなイメージがあるが、「じぇ」と同じように言葉の全ては京都から始まったのだから自信をもって方言を使ってもらいたいと思う。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月12日*ヨウネンコウ*・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.13
コメント(0)
-

ローン・レンジャー★お笑い西部劇
■ローン・レンジャー:あらすじ■友(キモサベ)よ、マスクをつけるのだ・・・復讐のために。少年時代のある忌まわしい事件のせいで復讐に燃える戦士となった悪霊ハンター、トント(ジョニー・デップ)は、その悲願のために、不思議な白馬シルバーの導きと自らの聖なる力によって、瀕死の状態にあった検事のジョン・リード(アーミー・ハマー)を甦らせる。レンジャー部隊の英雄である兄ダンを何者かに殺された過去があるジョンは、兄の敵を探すためにトントと手を組む。しかし、法に基づく正義の執行を求めるジョンと、復讐のためなら手段を選ばないトントはまったく噛み合わない。しかし、愛する者に再び魔の手が迫り、マスクをつけた謎のヒーロー“ローン・レンジャー”として生きる覚悟を決めたジョンは、白馬シルバーを従え、無敵の相棒トントと共に巨悪に立ち向かう……。 ハリウッド映画では、今や「西部劇」というジャンルはなくなったのでは・・・と思うほど、「西部劇」がない。一番ちかくでは2011年にみた■トゥルー・グリット■くらい。かつては、西部劇はけっこうあった。「駅馬車」や■大いなる西部■そして「ローン・レンジャー」も人気西部劇だった。ディズニーがつくった「ローン・レンジャー」も派手な撃ち合いやインディアンの襲撃、騎兵隊の攻撃などなど西部劇の要素たっぷり。しかし、それ以上に、お笑いの要素たっぷりでツッコミどころ満載の映画だった。しかし、昔なら悪役として描かれる、インディアンも白人に迫害を受ける人々として描かれている。呼び名もインディアンという呼称は使わなかった。(日本語吹き替えでみたのだが)西部劇も20~30年くらいで変わった。しかし、悪人を懲らしめるためにローン・レンジャーがあらわれる時の、♪パーンパカパンパン~、パーンパカパンパン・・・という音楽は健在!・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月10日*大阪しぐれ:八月のやり *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.10
コメント(0)
-

冒険者たち★男女3人友情物語
■冒険者たち:あらすじ■命知らずのパイロット・マヌー(アラン・ドロン)と、自動車技師ローラン(リノ・バンチュラ)は、ある日、美しい前衛彫刻家レティシア(ジョアンナ・シムカス)と出会う。厚い友情で結ばれていた男二人に女一人。この三人の間には、いつしか不思議な三角関係が生まれていく。そしてある日、三人はどん底の生活から這い上がるために、アフリカ沖に沈む財宝を積んだ船を探すという、一獲千金の旅に出る。この船出が、彼らの運命を変えていくとも知らずに……。 アクロバット飛行をしているマヌーと元レーサーのローランの男の友情。その中にひとりの若くて美しい芸術家の卵のレテェシアという女性が入ってくる。マヌーとローランは、お互いに、レティシアを好きなのに、まったくそんなそぶりを見せない。それは、お互いの友情を壊さないため。3人は奇妙な友情で結ばれていた。夢を追う彼らは、海底に眠る財宝を引き上げるため、アフリカのコンゴ沖にオンボロ船でやってきた。しかし、みごと財宝を引き上げたとき、ギャングが襲ってきて、流れ弾に当たったレティシアは死んでしまう。この映画、音楽がすばらしく、死んだレティシアを水葬する時のスキャットや大空を飛ぶシーン、口笛のもすばらしい。この映画の結末を描くかのような、もの悲しいさがよかった。「冒険者たち」というタイトルだけれど、冒険よりも友情を強く感じたすばらしい映画だった。この映画に出てくる要塞島、■写真はここ■は、まったく知らなかった。ボイヤール要塞という名前の要塞で、大金を手に入れたら島を買うといっていたレティシアの島だ。軍艦のようなビルのようなこんな島があるなんて、じぇじぇじぇじぇじぇ!!!物語後半の舞台となる要塞島(ボイヤール要塞)。これは映画のセットではなく、実在する島である。1801年、フランス本土のラ・ロシェルを守るために要塞の建設が始まるも、完成したのは56年後の1857年。しかし、その間に大砲の性能もアップして必要性がなくなってしまったのだ。その後、刑務所として使われたこともあったという。なお、この要塞島は現在、フランスのテレビ局が所有していて、テレビ番組のアトラクションの舞台となっている。残念ながら一般観光客は上陸できないようだ。■冒険者たち:動画■■新・午前十時の映画祭■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月7日*七日盆 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.08
コメント(0)
-

ごちそうさん歌:さんまとネバネバ野菜の酢の物
♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・(某国営放送の料理番組の音楽)みなさん、こんばんわ。天地 はるなの「ごちそうさん歌」の時間がやって来ました。暑い夏!料理をして、部屋の中が暑くなるのはイヤですよね。そんな時は、火を使わない料理がいい!!ということで、今日は「さんまとネバネバ野菜の酢の物」を作りましょう。まず材料から。 <材料> (4人分) ●刺身さんま、一袋(袋に入れて売ってあるもの) ●オクラ 6本●長いも 100g ◎純米酢、大さじ 2◎砂糖 小さじ 1◎醤油 小さじ 2◎塩 小さじ 11/4 <作り方>1. さんまは小骨を取り、皮をむいて、削ぎ切りにする。2.オクラは、塩をふって板ずりして洗い、さっと塩ゆでし、1cmの輪切りにする。 長いもは、皮をむきポリ袋などに入れて、綿棒で、粗くたたく。 (私は、すりこぎを使用)3. ◎印の調味料を混ぜ合せる。4.サンマ、オクラ、長いもを混ぜ、<3>の調味料を加え、和える。もし、ミョウガがあれば、千切りにして添えるといいですね。暑さはこれからば本番。くれぐれも、夏バテにご注意くださいね。それでは、また、お会いしましょう・・・。♪チャンチャカ、チャカチャカ、チャンチャンチャン・・・。 一晩の時間オクラのふとりかな 松田秀一「健康のためなら死んでもいい」というほどの健康オタクの夫が今度はネバネバ野菜にはまりました。(ノД`)これなら、簡単で火を使わないから、これからの季節にピッタリ。なによりも、美味!!■ごちそうさん歌:牛肉とじゃがいものバルサミコ酢煮 ■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月6日*父の麦わら帽子:カワニナ *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.06
コメント(0)
-

京都:バレエ・マンガ展
バレエ・マンガ~永遠なる美しさ~少女マンガは、戦後より一気に花開いた文化ですが、そうした中で、最も描かれたテーマの一つに「バレエ」があります。日本人が、「バレエ」と聞いて思い浮かべる「白いチュチュにトウシューズ」というイメージも、マンガによって広まり、定着したと言っても過言ではないでしょう。また、他の国と比べると日本では、バレエがお稽古ごととして定着し、鑑賞するより、自らが行うものとして独特な発展を遂げてきたと言えます。 本展は、バレエ・マンガを描いた代表的な作家12名の作品を中心にした展覧会です。原画を中心としたおよそ120点の額装品、当時の貴重な雑誌資料などが2会期に分けて公開されます。少女マンガの発展とバレエとの関係、日本において実際のバレエ受容とマンガがいかにリンクしてきたかを垣間見るべく、バレエ・マンガの歴史を源流から現在まで時系列にたどっていきます。1.バレエ・マンガの源流(大正時代~昭和初期) 日本にバレエが入ってきたのはいつだったのか。戦前日本のバレエ受容を探るとともに、バレエ・マンガの源流に迫ります。兵庫県立芸術文化センター所蔵の薄井憲二バレエ・コレクションより、古くは18世紀後半頃のロマンティック・バレエ時代から描かれてきたバレエにまつわる資料など、貴重な資料が展示されます。また、大正時代の少女雑誌、高畠華宵のバレエ抒情画のパネルなども展示されます。 2.バレエ・マンガの創世期(1950~1970年代) 戦後からすさまじい勢いで広がったバレエブームは、時期をほぼ同じくして少女マンガにも起こりました。当時のバレエブームを、少女マンガ誌やパネルなどでも紹介。また、1950~1970年代にいたるまで、バレエ作品で人気を博した高橋真琴、牧美也子、北島洋子、上原きみ子の原画も展示されます。出展作品例 高橋真琴「プチ・ラ」、牧美也子「マキの口笛」、北島洋子「ふたりのエリカ」、上原きみ子「まりちゃんシリーズ」など 3.バレエ・マンガの変革期(1970年代) 1971年連載開始の山岸凉子の「アラベスク」は、バレエの芸術性や身体表現に目を向け一石を投じたエポックメイキングな作品です。そんな作者のバレエ・マンガの魅力に注目します。出展作品例 山岸凉子「アラベスク」「テレプシコーラ/舞姫」など4.バレエ・マンガの編成期(1970年代~現在) 1970年代以降は、深遠なドラマとしてのバレエ・マンガが次々と誕生していきます。バレエ・マンガの進展を、有吉京子、萩尾望都、槇村さとる、水沢めぐみ、曽田正人の作品から探っていきます。 出展作品例有吉京子「SWAN」、萩尾望都「フラワーフェスティバル」、槇村さとる「Do Da Dancin´ヴェネチア国際編」、水沢めぐみ「トウ・シューズ」、曽田正人「昴」など5.バレエ・マンガはどこへ行く? マンガ家達にとって、バレエとは一体何か?また、バレエはマンガの中で描き尽くされたものなのか?バレエ・マンガの今後について考えます。出展作品例水野英子「ルジマトフのバレエ画」、魔夜峰央「パタリロ!(『バレエ入門』『バレエあれこれ』)」など ■主催 京都精華大学国際マンガ研究センター、 京都国際マンガミュージアム■■会場 京都国際マンガミュージアム 2階 ギャラリー1・2・3 ■期間 2013年7月13日(土)~9月23日(月・祝) ◇午前10時~午後6時(最終入館は午後5時30分)◇休館日:水曜 ※ただし7/11(木)~9/3(火)は無休■展示替 第一期:7月13日(土)~8月19日(月)※8/19(月)は、展示入替えのため午後4時終了 第二期:8月20日(火)~9月23日(月・祝) 8月1日(木)■復刻版「マキ口笛」■を持っているくらい、漫画オタクの妹と一緒に行った。「マキの口笛」などバレエ漫画の創世記に私と妹は子ども時代を送った。私は早々と漫画は卒業したけれど、妹は今も漫画オタク。大満足の展示だった。京都国際マンガミュージアムの職員さんって羨ましい。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年8月4日*◎日本ちょっと昔話◎始まります。 *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.04
コメント(0)
-

里山の旬だより:「川」を食べる。
里山で夏の訪れを知らせてくれるのは、ホタル。ホタルは幼虫のとき、川の中で過ごし、餌にしているのがカワニナです。県北では、このカワニナを食べる習慣があります。茹でたり、汁に入れたり。カワニナは、昔なつかし庄原の夏の味。 私は、子どもの頃、夏になるとカワニナも食べたし、蛍の飛ぶのを見ていた。庄原では、現在、ホタルのために食べることをやめている。そのおかげで、沢山の蛍が群れ飛ぶのを見た。しかし、人もホタルもカワニナが食べられる川がいいな・・・。■里山の旬だより■広島県の庄原という所に行った時、「道の駅」で偶然見つけた、「しょうばら里山の旬だより」という小冊子。 伝統の食事や諺の数々・・・。 小粒ながらにピリリと辛いこの冊子、気に入りました。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2013年7月31日*禊ぞ夏のしるしなりける *・・・・・・・・・・・・・・
2013.08.01
コメント(0)
全13件 (13件中 1-13件目)
1









