PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(84)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(35)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(62)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(94)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(26)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(90)読書案内「映画館で出会った本」
(18)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(52)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(23)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(52)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(27)読書案内「現代の作家」
(98)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(65)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(85)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(48)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(78)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(30)読書案内「近・現代詩歌」
(54)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(22)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(18)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(2)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(13)映画「パルシネマ」でお昼寝
(31)読書案内「昭和の文学」
(25)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(5)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(9)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(34)週刊マンガ便「鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(19)ベランダだより
(149)徘徊日記 団地界隈
(112)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(26)徘徊日記 須磨区あたり
(28)徘徊日記 西区・北区あたり
(10)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(41)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(5)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(11)読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」
(14)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(11)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(25)映画 香港・中国・台湾の監督
(37)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(52)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(26)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(16)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(41)映画 イタリアの監督
(21)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(20)映画 ソビエト・ロシアの監督
(11)映画 アメリカの監督
(97)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(3)読書案内「旅行・冒険」
(4)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(13)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(5)映画 フランスの監督
(47)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(5)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(14)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(7)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(6)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(10)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(6)映画 トルコ・イラン・カザフスタンあたりの映画監督
(12)映画 ギリシアの監督
(3)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルー・チリの監督
(6)映画 ハンガリー・ルーマニアの監督
(5)映画 アフリカの監督
(3)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5)週刊マンガ便「小林まこと」
(9)読書案内「野口武彦・前田愛・橋川文三・藤井貞和」
(2)映画 インド・ネパール・ブータン・アフガニスタン・タイ・ベトナム あたりの監督
(5)週刊マンガ便 キングダム 原泰久・佐藤信介
(17)読書案内「川上弘美・小川洋子・佐伯一麦」
(9)読書案内「立花隆・松岡正剛」
(2) 週刊 読書案内 岸田奈美「もうあかんわ日記」(ライツ社)
想田和宏「五香宮の猫」元町映画館no263
小松莊一良「恋するピアニスト フジコ・ヘミング」キノシネマ神戸国際no15
ベランダだより 2024年10月5日(土)「宵の夕顔」 ベランダあたり
空音央「HAPPYEND」シネリーブル神戸no275
ベランダだより 2024年10月26日(土)「酔芙蓉、酔った時(笑)。」団地あたり
閆非・彭大魔「抓娃娃(じゅあわわ) ―後継者養成計画」シネリーブル神戸no276
徘徊日記 2024年10月24日(木)「高倉台の夕焼け!」須磨あたり
週刊 読書案内 岸田奈美「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館)
ヌリ・ビルゲ・ジェイラン「二つの季節しかない村」シネリーブル神戸no274
想田和宏「五香宮の猫」元町映画館no263
小松莊一良「恋するピアニスト フジコ・ヘミング」キノシネマ神戸国際no15
ベランダだより 2024年10月5日(土)「宵の夕顔」 ベランダあたり
空音央「HAPPYEND」シネリーブル神戸no275
ベランダだより 2024年10月26日(土)「酔芙蓉、酔った時(笑)。」団地あたり
閆非・彭大魔「抓娃娃(じゅあわわ) ―後継者養成計画」シネリーブル神戸no276
徘徊日記 2024年10月24日(木)「高倉台の夕焼け!」須磨あたり
週刊 読書案内 岸田奈美「家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だった」(小学館)
ヌリ・ビルゲ・ジェイラン「二つの季節しかない村」シネリーブル神戸no274
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「近・現代詩歌」
遠藤豊吉編「日本の詩」(全10巻)小峰書店
遠藤豊吉 は 1924年生まれ 。幼年時代に生母を亡くし継母に育てられたが、師範学校卒業と同時に出征し、特攻隊員となったそうです。出撃の機会なく生き延びて敗戦。戦後、小学校の教員として生き、のちに数学者の 遠山啓 とともに 「ひと」 という雑誌を主宰した人です。
実は、この方の教育実践を読んだことはありました。しかし、こんなふうに詩を語る手法と、経歴、そして、その人柄にあらためて心が動きました。
紹介されている詩はどれも子供向けなどではなく日本の近現代詩の傑作です。詩を読むということの原点に帰らせてくれる名アンソロジーといえるでしょう。こんな出版が可能だった時代があったのだと、一人でため息をつきました。
のちに、調べてみると 昨年(2017) シリーズ が復刊されていることがわかりました。今が最悪というわけでもなさそうだと、ちょっと嬉しくなりました。
最近出会っている大学生の皆さんが、単なる教養としてではなく、こんなアンソロジーの中の一つ一つの詩を受け止めてくれると嬉しいと思いました。2018/06/09
追記 2019・04・22
今となっては、数年前の出来事になっていまいましたが、高校に入学したばかりの一年生の少女が、文字通り埃まみれの図書館再生作業を手伝ってくれたことがありました。彼女が何故、図書館のじーさんのところに通うようになったのか、それは今でもわかりません。
百人近い職員の中で、たった一人、
この春、大学を卒業した彼女が市内の公立中学に教員として採用されたと報告してくれました。新採用の気遣いと不安に涙をこぼす日もあるようです。高校生だった彼女が、定年を迎えんとしていた老教員を、三年間にわたって励まして続けてくれたことを思い返しながら、心の中でエールを送り続けています。
中学校の教員になった、新卒の一学期はどうも大変だったようです。学校現場の労働時間に対する無頓着な 「異常さ」 は、ぼくらの頃からありました。夕刻の7時、8時を過ぎた職員室で、昼の2時、3時のように働いている教員が一人や二人ではなかったりするのです。毎日の疲労が積み重なっていく結果は目に見えません。そのうえ、土・日には、若い教員にはクラブ活動の付き添い・引率が、必ずあります。
で、「若さ」が終わるころ、ようやく気付くんです。
思い切って、自由にふるまうことには勇気がいりますが、せめて6時くらいには帰宅して、家族とおしゃべりしたり、仕事とは離れた本の一つも読むことを選ぶ勇気を持ってほしいと、いまさらながらに思います。なんか説教臭いですね。うまくいえません。
追記2020・04・27
中学校の教員になって一年がたった彼女から久しぶりの便りがありました。 「図書室」 の係になったそうです。
「中学校の図書室に置く、いい本はありますか?」
なんというか、聞かれそうなことが書いてあります。答えは簡単ですね。
「これがいい!なんていいきれる本なんてありません。」
こう書くと、困ってしまうかもしれませんね。いい本は図書の係の人が自分で探すよりほかに方法はないと思います。一冊一冊の本には、結局良いも悪いもないのです。ぼくが 「いい」 と思った本があるだけです。だから、学校の図書館の仕事を始めた人に言えることは、たった一つです。
「『これは面白いよ!』あなたがそう言える本を、一冊づつ探し出してください。」
簡単そうですが、思いのほか大変ですよ。よく一年間に何冊とか、目標にして本を読む人がいますが、何かを調べる参考に読む場合は少し違いますが、純粋に本を読むという作業は結構手間がかかります。
ぼくは読んだ本の感想をノートに書いていたことがあって気付きましたが、仕事をしながら、好きな本を読んで、一年間、何冊くらいかと調べてみるとせいぜい150冊くらいなものです。150冊を30年続けると4500冊です。あなたの卒業した高校の、あの頃ぼくがいた、あの小さな図書館でも、うろ覚えですが、3万冊くらいは並んでいましたからね。
150冊とか、4500冊とか、大した数ではないのです。でも、一年間に100冊くらい読むと、これは面白いよといえる本に何冊か出会えることは確かです。それを紹介すればいいのです。
あなたが面白かったり好きだった理由は何でもいいのです。そのうち、真っ当そうな理由も見つかりますよ。さあ、本を読んでください。あっという間に60歳を越えてしまいますよ(笑)。
ボタン押してね!

にほんブログ村







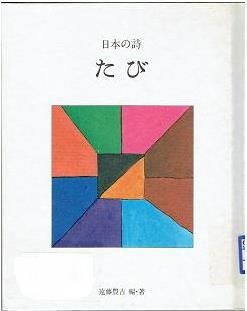 夏休みの午後。5年がかりで片づけてきた職場の図書館の書庫。
夏休みの午後。5年がかりで片づけてきた職場の図書館の書庫。
カビだらけの汚い本は捨てる!
と腹を決めた仕事が終わりに差し掛かっていました。汗まみれになって段ボール箱に廃棄する本を詰めながら、目の前の棚にあった薄汚くよごれた小冊子のシリーズが、ふと目に入りました。ビニールカバーをカッターナイフで切り裂き、茶ばんだ表紙カバーもひきはがしてみると、なかなかしゃれた詩集が出てきました。
「日本の詩(全10巻)」 (小峰書店)
、1970年代の終わりころ 小峰書店
という出版社から出された現代詩のアンソロジーです。
一冊に二十篇ほどの詩が紹介されていて、 全10巻
。 遠藤豊吉
という小学校の先生だった人の個人編集です。
「へー」と思いながら、中の一冊の詩集 「たび」
を読み始めて、やめられなくなりました。
出さない絵葉書 新川和江 詩の解説のようにして、編者 遠藤豊吉 のことばが添えられています。
遠く
来てしまいました
春は
たけなわですけれど・・・・・・・
このさびしさには
もう
散りしく 花びらがない
つかまる 手摺りがない
通す 袖がない
まぶす 粉砂糖がない
梳く 櫛がない
まわす ノッブが
つき刺す フォークが
いれる袋が ない
遠く
来てしまいました
もう、帰らないでしょう
帰れないでしょう
〔編者の言葉〕 その日の午後、ぼくは、一編一編の詩と、その詩の後ろに書きつけられている 遠藤豊吉 の 「編者の言葉」 を蒸し風呂のような書庫で、汗だくになって読みながら過ごしました。
特別攻撃隊員になって一か月ほどたったある日、二泊三日の帰郷が許された。
梅雨でぬれた故郷の町はなつかしかったが、特別攻撃隊員として〈死〉の世界にあゆみはじめている心には、もはや無縁、という思いのほうが強かった。
二夜とも、父と継母とわたしと三人で、一つの部屋に寝た。町は無縁の風景と見えても、両親はやはり無縁ではなかった。父はほとんど何もしゃべらなかったが、継母は夜半すぎても、私にむかってしゃべることをやめなかった。
わたしは、自分が特別攻撃隊員になったことを告げずに故郷を去るのだが、ふたりともわたしの身の上に重大な変化がおこったことを感じとったにちがいない。
故郷を去る日、継母は駅まで送ってくれた。目にいっぱい涙をため、彼女は車窓に手をつきだし、せいいっぱいわたしの手を握ってくれたが、その手は雨にしとどにぬれて、つめたかった。
遠藤豊吉 は 1924年生まれ 。幼年時代に生母を亡くし継母に育てられたが、師範学校卒業と同時に出征し、特攻隊員となったそうです。出撃の機会なく生き延びて敗戦。戦後、小学校の教員として生き、のちに数学者の 遠山啓 とともに 「ひと」 という雑誌を主宰した人です。
実は、この方の教育実践を読んだことはありました。しかし、こんなふうに詩を語る手法と、経歴、そして、その人柄にあらためて心が動きました。
紹介されている詩はどれも子供向けなどではなく日本の近現代詩の傑作です。詩を読むということの原点に帰らせてくれる名アンソロジーといえるでしょう。こんな出版が可能だった時代があったのだと、一人でため息をつきました。
のちに、調べてみると 昨年(2017) シリーズ が復刊されていることがわかりました。今が最悪というわけでもなさそうだと、ちょっと嬉しくなりました。
最近出会っている大学生の皆さんが、単なる教養としてではなく、こんなアンソロジーの中の一つ一つの詩を受け止めてくれると嬉しいと思いました。2018/06/09
追記 2019・04・22
今となっては、数年前の出来事になっていまいましたが、高校に入学したばかりの一年生の少女が、文字通り埃まみれの図書館再生作業を手伝ってくれたことがありました。彼女が何故、図書館のじーさんのところに通うようになったのか、それは今でもわかりません。
百人近い職員の中で、たった一人、
生徒が本を借りる図書館にしたい。 と意地になって、放課後、勤務時間もとうに過ぎた図書館の、薄暗がりでうろついていると、運動部のマネージャーの仕事をおえた彼女がやってきて雑巾がけ手伝ってくれた日々を、徘徊しながら思い浮かべることがあります。人は何に励まされ、何を励ましているかなんて、その時にはわからないものですね。
この春、大学を卒業した彼女が市内の公立中学に教員として採用されたと報告してくれました。新採用の気遣いと不安に涙をこぼす日もあるようです。高校生だった彼女が、定年を迎えんとしていた老教員を、三年間にわたって励まして続けてくれたことを思い返しながら、心の中でエールを送り続けています。
「あなたなら大丈夫ですよ、心配しなさんな。」 追記 2019・08・02
中学校の教員になった、新卒の一学期はどうも大変だったようです。学校現場の労働時間に対する無頓着な 「異常さ」 は、ぼくらの頃からありました。夕刻の7時、8時を過ぎた職員室で、昼の2時、3時のように働いている教員が一人や二人ではなかったりするのです。毎日の疲労が積み重なっていく結果は目に見えません。そのうえ、土・日には、若い教員にはクラブ活動の付き添い・引率が、必ずあります。
で、「若さ」が終わるころ、ようやく気付くんです。
「これはおかしい。」 って。そういう仕事ぶりが、かえってルーティーンに枠づけられた、狭い思考しか育てないってことに。そんな、教員に育てられる子供たちはやはり不幸です。
思い切って、自由にふるまうことには勇気がいりますが、せめて6時くらいには帰宅して、家族とおしゃべりしたり、仕事とは離れた本の一つも読むことを選ぶ勇気を持ってほしいと、いまさらながらに思います。なんか説教臭いですね。うまくいえません。
追記2020・04・27
中学校の教員になって一年がたった彼女から久しぶりの便りがありました。 「図書室」 の係になったそうです。
「中学校の図書室に置く、いい本はありますか?」
なんというか、聞かれそうなことが書いてあります。答えは簡単ですね。
「これがいい!なんていいきれる本なんてありません。」
こう書くと、困ってしまうかもしれませんね。いい本は図書の係の人が自分で探すよりほかに方法はないと思います。一冊一冊の本には、結局良いも悪いもないのです。ぼくが 「いい」 と思った本があるだけです。だから、学校の図書館の仕事を始めた人に言えることは、たった一つです。
「『これは面白いよ!』あなたがそう言える本を、一冊づつ探し出してください。」
簡単そうですが、思いのほか大変ですよ。よく一年間に何冊とか、目標にして本を読む人がいますが、何かを調べる参考に読む場合は少し違いますが、純粋に本を読むという作業は結構手間がかかります。
ぼくは読んだ本の感想をノートに書いていたことがあって気付きましたが、仕事をしながら、好きな本を読んで、一年間、何冊くらいかと調べてみるとせいぜい150冊くらいなものです。150冊を30年続けると4500冊です。あなたの卒業した高校の、あの頃ぼくがいた、あの小さな図書館でも、うろ覚えですが、3万冊くらいは並んでいましたからね。
150冊とか、4500冊とか、大した数ではないのです。でも、一年間に100冊くらい読むと、これは面白いよといえる本に何冊か出会えることは確かです。それを紹介すればいいのです。
あなたが面白かったり好きだった理由は何でもいいのです。そのうち、真っ当そうな理由も見つかりますよ。さあ、本を読んでください。あっという間に60歳を越えてしまいますよ(笑)。

追記
ところで、このブログをご覧いただいた皆様で 楽天ID
をお持ちの方は、まあ、なくても大丈夫かもですが、ページの一番下の、多分、楽天のイイネボタンを押してみてくださいね。ポイントがたまるんだそうです(笑)
ボタン押してね!
にほんブログ村



お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「近・現代詩歌」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 朝倉裕子「雷がなってい… 2024.09.16
-
週刊 読書案内 朝倉裕子「母の眉」(編集… 2024.08.23
-
週刊 読書案内 宗左近「長編詩 炎える… 2024.07.09
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










