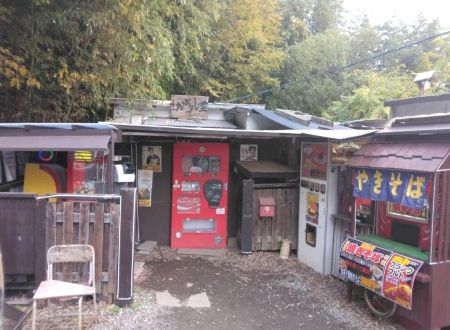2010年10月の記事
全53件 (53件中 1-50件目)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
布施というと、今ではお寺へのお礼のことのように思いがちだが、元々はお釈迦様の大切な教えの一つです。布施とは、人に自分が大切にしているモノを差し出すことです。モノといっても品物とは限りません。笑顔や優しい言葉など目に見えない気持ちでもいいのです。電車で青年に席を譲られたお婆さんが、「ありがとうございます。立たせてしまってすみませんね」と言いました。青年を立たせてしまったことへの思いが素直に伝わってきて、席を譲った青年も嬉しそうでした。周りの人の顔も、心なしか爽やかになりました。(席を譲られて怒る人は自分本位なエゴイスト)このように、たった一つの思いや言葉が、人々の心を温かくしてくれます。でも、何か善いことをしたとき、ふと我に返ってみると、相手の人への労りの気持ちよりも、善いことをしたという自己満足の方が強いことがよくあります。憐憫の気持ちや優越感からの好意では、本当の布施にはなりません。そんな自分の小さな心を離れて、人と心から喜びを分かち合う気持ちが大切なのです。自己満足の気持ちを離れて、どんな小さいものでも分かち合うことができたら、どんなに素晴らしく清々しいことでしょう。
2010.10.31
コメント(0)
-
若い女性たちの頑張りに感激
昨日は毎月最終金曜日の集まりで、japanheart「海を越える看護団」の大原さんと「スマイルプロジェクトin京都」の中田医師の話を聞きました。お二人とも若い女性で、知性と行動力に溢れています。大原さんはお寺生まれで法名もお持ちだが、「坊主はあかん」と看護士になって慈悲喜捨の実践をされています。「人の幸せを、自分の幸せと思える」女性たちが、活動費の不足分を自分達で補いながら、ミャンマーやカンボジア、離島や僻地の医療に携わっている姿にはガツンとやられた思いです。ミャンマーやカンボジアへ1回出かけると約50万円の費用が掛かるが、それで50~70人の手術ができるそうです。中田さんは小児ガンの患者などを診られていて、写真を拝見すると無邪気な子供の患者姿につい涙を誘われます。暗い話が多いこの頃、お酒を片手の集まりで申し訳ないような話でした。ついでに、私の本も紹介されたが持っていった10冊も無くなりました。有り難いことです。合掌
2010.10.30
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
知識のある人が誰かに教えたり、時間のある人がそれを使って誰かの役に立つなど、誰かに何かを与えること総てが布施で、人は他人に何かをしてあげることによって社会の中で役に立つ存在となり、その生き方が意味のあるものとなります。布施の心を、ひろさちやさんは次のような例話で説明されています。姉がケーキをもらってきたので、お母さんが「弟と半分ずつ食べなさい」と教え、食べ終わってから「なぜ分けないといけないのか分かる」と聞きました。姉が「分けてあげないと弟が可哀相でしょう」と答えると、弟は「僕がもらってきたときは半分お姉ちゃんにあげるから、お姉ちゃんが半分くれたのだね」と答えた。姉のように「相手が可哀想だから分けてあげる」というのはお恵みでしかなく、喧嘩しているようなときなどは分けてあげないとなります。弟のような気持では、お返しをくれそうにない人にはあげる気持ちが起きません。「あなたが一緒に食べてくださったので、美味しくいただくことができました。ありがとう」と思えるようになると、ケーキは一層美味しくなるはずです。「1つのケーキを2人で分けて食べた方がおいしい」と思える心、つまり、人のためだけではなく、自分も共に楽しく生きるための智慧と言えます。
2010.10.30
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
この世の中には悪い人間はいない。自分と気が合う人間と、気が合わない人間がいるだけだと斉藤茂太さんはおっしゃいます。誰にだって、気が合わない人はいます。でも、この世の中は、いろんな人がいて、いろんな意見があるから面白いのです。要は接し方です。最初から話が合いそうにもないと思ってしまえば、相手もそれを何となく感じてきっとそう思うから、気が合わない人ほどほめてみることです。何事も、自分が正しくて相手が全部間違っていることなどありえないし、相手の考え方が一方的に正しいということもありません。だから、自分の考えだけが正しいと思い込んで、相手を一方的にやっつけても問題は解決しません。また、人は欠点ばかりではなく長所もあります。欠点も見方を変えれば長所にもなります。まず、相手の意見を認めたりほめたりすることです。そうしているうちに、気が合うようになってくるものです。すると、だんだんと相手の良いところが見えてくるから不思議です。敵は好んで作るものではありません。敵と思われている人を、どう自分の中で消化するかです。そうすれば、人生も仕事も楽しいものになってきます。
2010.10.29
コメント(0)
-

大台ヶ原は初雪でした
先週末に、フッと大台ヶ原に行ってこようと思い立ちました。天気予報では今週はあまり良い日が無く、昨日がかろうじて昼前後から晴れそうでした。そこで、5時頃は小雨がぱらついていたが、思い切って5時46分のJRに乗り、近鉄を乗り継いで8時28分大和上市まで来ると太陽が顔を出し始めました。日に1往復の登山バスがスカイライン(といっても、途中は車1台がやっと通れるような道)にかかるころには快晴になり、駐車場に着くと雲一つ無い青空。お天気男健在なり。下界の雨が上では雪だったようで、パウダースノーで木々は雪帽子。紅葉とのコントラストは何とも言えず、ガイドの人も今年最後で最高の眺めですと言ってみえました。さっそく、東大台から西大台を一周すべく歩き始める。大台ヶ原に来たのは、もう50年も前に大杉谷へと降りたとき以来で記憶も定かでないが、鹿の害が目立ち、丸坊主の原っぱや山が目立ちます。その代わり眺望は良く、真下に熊野灘が見え、「エッ こんなに海が近かったの」と驚きです。樹氷の中を歩くのも久しぶりで楽しく、出だしは快調です。西大台に入ると状況は一変、厳しいアップダウンの連続で膝が痛くなり、歳を痛感させられました。10数キロの行程を4時間程度で歩き通しはしたものの、明日以降に足にみがはいろのではと心配です。3時過ぎにはガスが出て天候も一変、さすが雨の多い大台ヶ原です。15時45分発のバスで下へ降りるともう真っ暗、20時27分に嵐山に帰り着きました。9時間ばかりの乗り物と、5時間半ばかりの登山。駆け足でしたが思いでの1日でした。
2010.10.28
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
人は自分のことだけで精いっぱいで、実に自己中心的な動物です。だから、逆に自分に関心や好意を持ってくれる人を求め歓迎します。1.人は自分のことに最も関心があるから、自分のことを聞いてくれる人には好意を待ちます。だから、上司や営業マンにとって大切なことは、話すことではなく、部下やお客様の話を聴くことです。質問や相談するのも効果的です。2.出会った時に一声かける挨拶は、相手を無視していないことの証です。挨拶は、人間関係の出発点であり生活のケジメです。出会いの挨拶は「仲良くやりましょう」という平和宣言、別れの挨拶は「今後ともよろしく」という友好宣言、挨拶をしないのは相手への無視宣言あるいは敵対宣言です。朗らかに元気良く先手で挨拶すれば、自分の気持ちもよく、周りも明るくなります。3.誰でも、知り合いからの手紙や葉書をもらったときの喜び、心のときめきを経験したことがあるはずです。でも、自分からはなかなか書こうとしません。メールでも良いから、写真を添付するなりチョット工夫して出してみませんか。4.相手が興味を持っていることに関連する情報を提供すれば、自分のことに関心を持っていてくれたのかと好意を持ち、感謝もするはずです。
2010.10.28
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
山田恵諦天台座主は、「最近は自己主張が盛んで、そうでないと損するばかりと思っている。しかし、自分を出したら真実はかすんで見えてこない。つまりは、自分を出すことでは決して賢くはなれない。少し長い目で見れば、自分を出して損するのは自分である。大愚であることだ。大愚とは、自分を第二に置いて、まず相手の言うことを聞いて相手の立場で考え、それにどう調和しうるかを探し求める。そこに初めて思案が生まれてくる。『自分が、自分が』ということが先にくると、相手が応えてくれればいいけれども、お互いに『自分や』ということになると、どうにも調和が取れなくなる」と言う。自分を生かそう生かそうと思うと、どうしても自我が出てきて真実が見えにくくなり、その場に最も適した対応を取れなくなりがちです。その時、自分一人が喜ぶよりも、できるだけ沢山の人が一番喜ぶ方法考え、そのように行動することです。その方が、自分の歓びもずっと大きくなるはずです。仕事でもそうです。仕事を巧く進めるには、コラボレーションする能力、もっと言えば「周りの人のパフォーマンスを高める能力」が一番求められます。 いくら仕事ができても、この能力に欠ける人に大きな成果は期待できません。
2010.10.27
コメント(0)
-
ガンバレ! 「快老力」
不良老人ガンバレ! アマゾンのランキングを見ると、小さな出版社で露出率が低い割には頑張っているのではないでしょうか。発売以来、ここ1週間ばかりでランキングを1千番くらい駆け上がりました。もう少し頑張ってくれて、書店で置いてくれるところが増えると嬉しいのですがね。この本を書いて良かったことは、私もこんなことをしているという元気なリタイヤ組のメールが届くことです。団塊の世代も定年を迎え、それぞれに頑張っているようです。ガンバレ! アラカン(還暦前後)!さて、今年は紅葉が綺麗と言うことで大台ヶ原に行こうと思っているが、天候が良くありません。明日くらいは晴れないかなと願っています。
2010.10.26
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
コピーショップで前の人が大量のコピーが一段楽して座って整理をしていたので、私は一枚のこともあり「お借りします」と言ったところ、「私が使っているのです。君は割込むのか」とえらい剣幕で言われたことがあります。タクシー乗り場で待っていたら、チケットが使える車がやってきました。次々と車が来るので、前の人に事情を話してお願いしたら、「先に乗るなんて、チョット図々しいんじゃない」と言われてしまいました。「あの人は付き合いにくい」などと言われる人は、「自分が、自分の」という部分が出過ぎたり、自分の中に意地っ張りな部分があるからだと思います。「自分のして欲しいことを、まず他人にせよ」と聖書にあるように、自己中心の心を抑制し、一歩下がる心のゆとりが大切です。「相手こそ、私の欲しいモノを私以上に必要としているのでは」と考えることのできるゆとりは、自分中心に生きていては生まれません。自己中心的で、互いに奪いあったり押しつけたりすることに終始して、相手を受け入れようとしないところに人間関係の難しい原因があります。自分の心が、どれほど他人に開かれているか、他人を入れるゆとりがあるかにかかっています。
2010.10.26
コメント(0)
-
長生きの秘訣
「快老力」を読んで、6歳上の兄からメールがありました。肩も凝らず気軽に読めて、内容もなる程と楽しくて良い本が出来ましたね。3分程度の一小節で区切りがつくのも読みやすいですね。家内(保健活動推進員)も活用させてもらえそうだと言っていました。 おじいちゃん(義姉方)に長寿の秘訣を聞いたことがありますが、全く同じですね。97歳までゴルフを年間100ラウンド以上プレイしていました。ダンデイで幾つになっても若々しさを失わず、気遣いの出来る人でした。・好奇心を持つこと・おしゃれをすること・色気を失わないことの三つでした。中々難しいことですが、私も最後に「生れてきてよかった」「楽しかった」「ありがとう」と言う言葉を残せる人生を目指して、「今日と言う一日を精一杯生きる」ことを心掛けたいと思います。取り敢えず、5冊送って下さい。
2010.10.25
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
誰でも、その人自身の人生という舞台では自分が主役です。だから、自分の人生に登場する他人は皆、それぞれの場面で自分を引き立ててくれる脇役でしかありません。そこで、自分勝手に振る舞いがちです。だがよく考えてみると、自分の人生では主役の私も、他人の人生では脇役にしかすぎません。全く当たり前のことだが、このことに思いがいたらない人が意外に多い。人間関係がうまくいかないのは、このことを忘れているからです。たとえば、家庭でも、夫は妻を自分の脇役と思い、妻は夫を自分の脇役でしかないと思いがちです。親子の間でも同じです。相手にとっては自分は脇役でしかすぎないのに、お互いに自分が主役面をして振る舞うところから諍いが起きることになります。会社でも、国家間でも、諍いが起きるのは同じ原理です。従って、人間関係をよくするコツは、お互いが相手にとっては自分は脇役でしかないことをよくわきまえ、相手を主役として立てることです。でも、頭では分かっていてもなかなか実行できないのが人間です。手始めに、大したことのないところでは少し相手に花を持たせてみませんか? すると、以外に大きなお返しがあるかもしれませんよ。
2010.10.25
コメント(0)
-
後輩たちも頑張っているようです
「快老力」を読んだ大学ワンゲルの後輩たちからも、こんなことをやっているという知らせが入ってきます。本にも少し紹介した小沢君からはこんあメールがありました。60歳で退職後、何をするという当ても無くボランティアを始めました。 最初に行ったのが老人ホームです。 お年寄りに楽しんでいただきたい、何の芸も持たない自分にできることは何か? マジックしかない。そう確信し、地元のマジックサークルに参加。 覚えたネタをすぐに披露。 4回目(1ヶ月後)に初めて拍手をもらいました。 思った通り安直に楽しんでもらえる芸事でした。 5年計画を作り、やるからにはアマトップクラスになろう。 目標は「500回のマジックショー、レパートリー1000、コンテスト入賞」です。 昨年12月(5年目の最後の月)にコンテストでグランプリをいただき、約束が果たせました。 次の5年計画です。 「翻訳叢書を作る、自分は20冊を翻訳する、日本マジック学会を立ち上げる」です。 日本は技術はトップクラスであるが、歴史を繋いでいるものが少なく、和妻を除けばオリジナルは全て輸入。 文献は殆どが英語で書かれており、過去翻訳されたものは10数件しかない。 世界最古のマジック文献(1584年)を翻訳したところ、 日本の権威と尊敬していた人の引用している3件が全て間違っていた。 「原書を読んでいない」ことが明白、ショックです。 現在所属しているクラブの会長(荒木一郎)の指導を得て文献翻訳を開始しました。 調査したところ重要なもの270冊があり、特に重要なもの50冊を選びました。 古い順に翻訳することとし、現在5冊完了したところです。 一般向けには販売せず、クラブ内の希望者のみ限定の予定です。 午前中はヘルパーの仕事、午後はマジックショーなどで朝の2時間が翻訳時間です。 2ページ/日ですので年間800ページ、3冊程度かな。 仲間を募っていますがクラブ(500人)内にはまだ戦力になる人は出ていません。 命のあるかぎり、目の見える間は続けたいと思っています。また、機械工学専攻だったエンジニアは、定年後「からくり」の開発に挑戦し、着々と成果を上げているようです。嬉しいかぎりです。
2010.10.24
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
さて、食べるときが問題です。地獄では、自分の箸でうどんをつかむが早いか、自分の側にあるつけ汁につけます。でも、箸が長すぎて自分の口には入りません。反対側からは、こいつに食われてたまるかというので、人の取ったうどんを箸で引っ張ります。こうして阿鼻叫喚の図が出現し、釜の周辺にはせっかくのうどんが飛び散って、結局誰も一口も食べることができず、人は餓鬼道に走ってしまいます。ところが、極楽には思いやりにあふれた人たちだけが住んでいます。「うどんができましたよ。みなさん、一緒に食べましょう」と言い、箸で釜の中のうどんを取り、つけ汁につけて、「はい、あなたからどうぞ」と箸を伸ばして向こう側の人に食べさせてあげます。すると、前の人は「ああ、おいしゅうございました。今度はあなたがどうぞ」と言って、その人にうどんを取ってあげます。うどんは少しもこぼれないし、誰もが穏やかに食べることができます。そして、人々は手を合わせて感謝しながら食べています。「これこそが極楽なんだよ。しかし、外見は地獄と何も変わらない」と老師が雲水に教えたと孔子の話にあります。「わたし」にこだわるから、争いが生じ、苦が生じるのです。
2010.10.24
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
自分ほど可愛い者はいない」「自分がまず幸せになりたい」と願うのは誰もが同じです。でも、自分本位で「自愛」と「我欲」の心が先に立つと、相手には面白くないことが多く、諍いが起きがちです。そこで、自分が可愛ければ可愛いほど、自利の気持ちをグッと抑えて「あなたからどうぞ」と対応してみると、相手も善いことを返してくれ、結果として自分の本来の願いが叶えられ「明るく、楽しく、心安らかに」過ごすことができます。地獄も極楽も自分の心が創り出すもので、自分の相手への対応次第です。こんな例え話があります。部屋の真ん中に置いている大きな釜においしいうどんが煮えていて、つけ汁も置いてあります。だが、食べ方のルールが決まっていて、三尺三寸(約1m)の長い箸で、しかもその端を持って食べなければなりません。地獄も極楽も、部屋の大きさも、釜の大きさも、釜を囲んでいる人数もまったく一緒です。違っているのは、そこに住んでいる人の心だけで、地獄には自分のことしか考えない利己的な人が住んでおり、極楽には思いやりにあふれた利他の心を持っている人が住んでいます。さあどうするか?
2010.10.23
コメント(0)
-
アマゾンで発注して下さい
今日は時代祭です。ついでに書店を廻ってきましたが、やはり小さな出版社の悲哀で、取扱店が少ないですね。友人たちからにも、「小さな出版社なので無いときはメール下さい」と案内を送ったら、送ってくれと言うメールが何通か来ました。でも、送金問題が面倒なので、アマゾンを勧めています。アマゾンのランクが上がれば置く店が増えるそうですからご協力いただければ嬉しいですね。読んで下さった人の評判は良いので、なんとか1人でも多くの人に読んで欲しいと願っています。「快老力」太田典生で検索いただけば、アマゾン他に接続できます。
2010.10.22
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
私たちは、自分の周りの誰かが仕事で成功したり、大金を手に入れたり、美人の恋人を持ったりすると素直には喜べず、嫉妬という感情に苦しめられ、心安らかに過ごすことができません。そこで、気持を切り替えて、人が成功したならば「ああ、よかった、よかった」と共に喜ぶ、それが「喜」の心です。 私たちは、人に善いことをしてあげても、その一方で「~をしてやったのに」という気持が生じ、恩着せがましくなりがちです。そして、「あいつは恩知らずだ」と怒ったりしがちです。それでは心安らかに過ごせないので、そんな恩や恨みの感情に流されないよう戒める心、それが「捨」の心です。 人間は誰でも自分が一番愛しいものだが、辛い経験の中で人の情けが身に染みたときに始めて、人に喜んでもらうことの大切さも分かってきます。大事な人に喜んでもらうことは何よりも嬉しいものだし、自分自身が励まされる面もあります。子供のころ、正月前になると寒い中を障子洗いをさせられたものだが、おふくろは「お陰でこんなにきれいに張り替えられた」と言って喜んでくれました。それが嬉しくて、心にポッと灯がともるような気がしました。このように、人の喜びを自分の喜びとして単純に喜べばいいのです。
2010.10.22
コメント(0)
-
やっと身内にも喜ばれる本(快老力)が書けました
12人兄弟の末っ子の私だから甥や姪も多く、姪などは一つ違いで曾孫までいます。兄や姉だけでなく、姪や甥などからも「本屋にありましたよ」と電話があり、友達に贈りたいのでまとめて送ってくれという電話もあり嬉しいかぎりです。生まれ故郷(三重県四日市市)の甥からは、岡田さん(民主党の岡田さんの生家は四日市です)の本の横にあったと言ってきました。姉などは、「お父さんと読んでいる」と何度も感想の電話があります。私は、田舎の親族からは「口先だけで良く生きてきたね」と言われてきたが、今回の本でやっと喜んでもらうことができ認められました。妻からも、本にも書いた「いてくれてよかった」という言葉を初めて聞きました。これで、やっと身内にも認められたかなと喜んでいます。
2010.10.21
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
誰でも自分を喜ばせることには熱心だが、他人を喜ばせることのない人は長く喜びを持続することはできません。なぜなら、自分が喜びたいという意識が強くなると、大概の場合、それは自分本位になって相手には面白くないことが多いものです。すると応報の法則で、相手はその感情をこちらに返してきます。それでは、結局は自分を楽しませることはできません。(敵対的買収も同じ)私たちは自利ばかりを求めがちだが、逆に、まず人が喜ぶことをしてあげると、相手も良いことを返してくるので自分も楽しむことができます。「してあげる幸せ」により、人を喜ばせることで自分の命が輝くことを知りたいものです。つまり、自分が明るく、楽しく生きるためには慈悲喜捨を実践することです。「慈」とは、簡単に言えばみんな仲良くしましようという感情で、大勢の人と仲良くしたい、みんなで楽しく暮らしたいと思う感情です。「悲」とは、悲しんでいる人を助けてあげたい、苦しみの渦中にある人を救ってあげたいと思う感情です。誰かが困っていればすぐ助けに行ってあげる、そのときの助けに行く自分も気持がいいはずです。例えば、阪神大震災のときも日本中の人々が何とかしてあげたいと立ちあがりました。その心です。
2010.10.21
コメント(0)
-
老獪に快老やろうと思います
「快老力」が書店に並びだして、懐かしい人たちから次々と便りがあります。・女子大教授のヤイコパパからは、来年3月で定年です。老獪に快老しようと思います。・私も喉頭ガンの手術をしました。貴兄の本を読んで元気もらいました。・今年、子供が就職しました。これからは快老見習います。・長年連れ添った自分も知らないことを君には話していたんだね。何と言っていいか?確かに、家族への気遣いから、周りの人にはなかなか言えないことも、他人になら話せることがあります。そして、苦しさを話してしまえば楽になることも多いものです。いま、傾聴塾があちらこちらにでき、傾聴ボランティアも増えているようです。直接人の話を聞くとなると大変だが、メールで人に打ち明けるのも一つの手だと思います。私は、できるだけそんな受け手になろうと思っています。介護予防のための暮らしのしゃっきり度チェックリスト1□バスや電車に乗って1人で外出している□日用品の買い物を自分でしている□預貯金の出し入れを自分でしている□友人の家などを訪ねる□家族や友人の相談に乗ることがある□階段を手すりや壁を伝わらずに登っている□椅子に座った状態から何も掴まずに立ち上がれる□15分以上続けて歩いている
2010.10.20
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
正法眼蔵に「仏道をならうというは、自己をならう也。自己をならうというは、自己をわするる也。自己をわするるというは、万法に証せらるる也」とあるが、「自分というものを徹底的に見つめ考えてみると、自分の未熟さ加減、不完全さ、無力さがわかってくる。これが“自己をわするるなり”である。自分が未熟者だとわかったとき、まさに“「万法に証せられた”自分が発見できるのです、と荒崎良徳住職は言う。みな自分が賢いと思うからダメなのです。例えば、お嫁さんが「私ほど未熟な者はいません。何も知らない不束者ですが、一生懸命に勉強しますから、どうか教えてください」と心からお姑さんに頭を下げれば、「うちの嫁はできた嫁だ。なんと可愛い嫁だろう」と息子よりも大切にするはずです。お姑さんが「私は昔人間で、何も知らない。いろんな新しいことをどんどん教えてね。あなたに教えてもらって、私も若返りたいの」とお嫁さんの手を握ってごらんなさい。嫁さんは、「私なんて幸せなんだろう。もし離婚するようなことがあっても、この姑さんも連れて出ていっちゃうわ」と思うはずです。これは、全ての人間関係に言えることです。
2010.10.20
コメント(0)
-
「快老力」 まだ並んでない店が多いですね
昨日は、街に出たついでに何店かの大型書店を除いてみましたが、未だ並んでいませんでした。読売新聞の広告が21日だが、その辺りにならぶのでしょうか?老人性うつ病度チェックリスト(幾つか思い当たれば病院へ)□寝起きの体調が悪い □午前中より午後のほうが体調が良い □寝ても疲れがなかなか取れない □些細なことで気分が沈む □「自分なんていないほうがいい」と思う □よく頭が痛くなる □将来に希望が持てない □自分を責める □言いたいことがあるのに言えない □寝つきが悪い □喜怒哀楽が無く表情に乏しい □自分は独りぼっちだと思う □何もしたくなくなる □元気が出ない □自分は何の面白みも無い人間だと思う □以前好きだったことにも何に対しても興味が沸かない □常に頭がボーっとしてスッキリしない □過去の失敗をいつまでもうじうじ悩んでいる □ぼんやりと考え込んでしまうことが良くある □よくため息をつく □食欲が無い □性欲が無い □悩みを人に打ち明けない □死を考えることがある □自分を情けないと思う □悪夢を見ることがある □ついつい「いい人」になってしまってNOと言えない □脅迫的な責任感に襲われ、逃げ出したくなることがある □人に悪く見られるくらいなら死んだほうがましだと思う □「自殺」と打ってインターネット検索をすることがよくある
2010.10.19
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
もしあなたが、誰かに期待した微笑みが得られなかったら、不愉快になる代わりに、あなたの方から微笑みかけてごらんなさい。実際、微笑みを忘れた人ほど、あなたからのそれを必要としている人はいないのだから。不愉快になって貰えなかっただけでも損なのに、こちらが与えるなんてダブルの損と思えるかも知れないが、ダブルに損をすると得になるから不思議です。「相手が悪いのだから相手が態度を変えるべきだ」とか、「上司(あるいは部下)はなぜあんなに物分かりが悪いのだ」などと思うこともあるが、そう思っている間は、現実を少しも変えることはできません。何故なら、自分には自分の言い分があるように、相手にも相手の言い分があるのですから。あなたの考えだけが正しく、相手が自分の思う通りに動いてくれれば、これほど楽なことはありません。でも、自分を変えることは大変で面倒だから、他人に文句を言って相手が変わってくれることを期待していませんか?人間関係を良くして明るく楽しく生きていくためには、例え原因の90%が相手側にあったとしても、まず自分の側の10%を変えることでしか解決できません。それには、自分は未熟者で、直すところばかりだと思うことです。
2010.10.19
コメント(0)
-
「快老力」 マニュアル化をと
先週末に発売された「快老力」の出足が気になります。これから必要な本、マニュアル化をという意見もありました。こんな「おじさん度チェック」というのがありました。□昔の苦労話を良くする□愚痴をこぼすことが多い□怒りっぽくなった□涙もろくなった□疑い深くなった□他人に邪魔されず独りでいたいと思う□流行語が分からない□騒がしいことが妙に気になる□知らない人と付き合うのは億劫だ□自分自身の感情に囚われやすくなった□外出が少なくなった気をつけたいものです
2010.10.18
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
相手の気持ちになって行動するというのは、簡単なようで難しいものです。あるお医者さんが痔の手術を受けて、そこでいろんなことを学んだと言う。まず、うつ伏せになって看護婦さんの前にお尻を曝し、浣腸されるあの気持。「ああ、患者というのは、こんなに惨めな思いをしているんだ」と分かった。回診してくる担当医の問診を受けるときも、向こうは立っていて、こちらを見下ろしながら口をきく。相手が若い医者であっても、見下ろされると威圧感があって、射すくめられるような気がする。医学部教授の自分さえそうなのだから、普通の患者はもっと威圧感を受け、医師に聞きたいこと、訴えたいことがあっても、何も言えなくなってしまうのではないだろうかと反省した。退院してからは、患者に話しかける時には必ず椅子に腰を降ろすことにした。すると患者は落ち着き、安心した表情になって、問診にもハキハキと答えるようになった。こちらを信頼している様子が、態度にも見えるようになってきた。相手の気持ちを知るには、自分がその身になってみないとなかなかわからないものです。だから、いろんな体験をすることも大切です。私も30代後半に挫折し、どん底に落ちたことで人間心理を少し理解できるようになりました。
2010.10.18
コメント(0)
-
秋の1日をジャズでも如何?
昨日は琵琶湖畔の大津まで行ってきました。大津ジャズフェスチバルが行われていて、街のあちらこちら十数カ所で演奏が行われています。知人の若い娘がピアノ演奏をするので出かけた次第です。飲み物片手に午後の一時ジャズを聴くのもいいものですよ。ついでに、大津絵を見て歩きました。江戸時代初期から名産としてきた民俗絵画で、さまざまな画題を扱っており、東海道を旅する旅人たちの間の土産物・護符として知られていたようです。それと、大津祭も有名で、カラクリ屋台は高山ほど有名ではないが素晴らしいものです。今日も、ジャズフェスチバルは開かれています。出かけられては如何ですか?私の本「快老力」も本屋に並び始めました。83歳のお元気な女性から、「怪老力」じゃないのと言われました。嬉しいかぎりです。怪人を調べてみると、「素性の知れない人間・常人離れした行動力を持つ人間を指して呼ぶことがあり、博物学者の南方熊楠や雑誌編集者の大伴昌司などプライバシーを明らかにせず広範な知識と活動を行った先人で怪人扱いされるものも多い」とありました。そう言えば、「怪人二十面相」とか「オペラ座の怪人」なんてのもありましたね。
2010.10.17
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
昭和56年にローマ法王ヨハネ・パウロ二世が日本の各宗教の代表者を集めた懇談会の席で最澄の言葉を引用され、「この言葉こそが世界宗教の最も大切な理念と宗教行為を示すのであり、世界中の宗教者がこの精神を用いて、世界平和実現のため協力していこうではありませんか」と挨拶されたが、「忘己利他」の教えこそが、すべての世界に通用ずる自然の道理=真理といえます。仏教でいう利行とは、ビジネスでいえば『忘己利他=お客様第一』『自利利他=共存共栄』に尽きると思います。しかし、煩悩や欲望の塵が、この道理を覆い隠してしまいます。苦しみも悩みも、すべてこの欲望のなせる業といえます。自分を全ての出発点にすると、何事も行き詰まり上手くいきません。自分のために相手を利用するのではなく、相手を生かすことをまず考えることです。困っていない自分にとってはたいした負担ではなくても、その時困っている人にとっては、そのチョットした助けや情が非常に大きく身にしみるものです。そのことは、自分が困ったときによくわかります。自分の特徴や特技などを通じて人様のために何らかのお役に立って喜んで戴き、そうやって周囲の人たちと共存していくことが、自分が生きたという証ではないでしょうか?
2010.10.17
コメント(0)
-
改めて知る手紙の良さ
昔の葉書を整理していたら、こんな葉書が出てきました。04年、44歳の若さで亡くなった忘れられない女性から戴いた97年のハガキです。1通のハガキにどれほど勇気づけられた人がいるでしょう。心がしおれそうになっているとき、何だかホロホロしてくる。そういう気持ちを持った人がいるだけで、意味があるのではないでしょうか。たとえ本として出版されなくとも、この空の下で先生の文に今まで気づかなかった自分を見つけ出せた人がいるだけで、作家としては命輝くことではないかと思います。これからも続けて下さることを祈っています。パソコンを始める前は、一人ひとりを思い浮かべながら最適の文章を選び、ハガキ通信を出していました。相手からは、「どうして今の私にピッタリの文章が来るの」とよく言われたことがあるが、相手のことを思っていると、何気なく選んだ文章がピタリとはまるから不思議です。そんな気持ちを、ブログで発信するようになってから忘れていました。これからは初心に返ろうと思います。いま毎日5本書いているブログやメルマガを来年は整理し、もう一度ハガキの良さを見直したいと思います。
2010.10.16
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
終戦後間もない頃、三愛の市村氏は銀座四丁目の土地を入手するため奔走したが、皇后様の足袋も造ったという足袋屋の老舗の老未亡人が頑として聞き入れない。ある大雪の日、こんな日にお願いに行ったら誠意も通ずるかと思い出かけたが、娘さんに「母は売らないと言っています」と門前払いだった。翌日、老未亡人は、折角来てくれたのに会いもしないで追いかえしたことに気がとがめ、「今日はこちらから出向いて、きっぱりお断りしよう」 と、雪の中を出かけた。愛想よく迎えた受付嬢が、「この大雪の中、大変だったでしょう」と言葉をかけ(愛語)、着物の裾の雪を払ってあげ(利行)、自分のはいていた暖かいスリッパを脱いではかせ(布施)、抱きかかえるようにして(同事)二階の社長室に案内するのに、未亡人はいたく感動して涙ぐんだ。未亡人は市村氏の顔を見るなり「こんな立派なお嬢さんのいる会社は、きっと立派な仕事をなさる会社でしょう。私は社長さんを見込んで、土地を譲るのですからお金はいりません」と言う。市村さんも、相手の誠意にはそれに倍する誠意を以ってこたえるべきだと考え、鑑定価格に2割プラスしてようやく受け取ってもらったという。自然な心からの対応は、頑な心さえ開かせます。
2010.10.16
コメント(0)
-
「快老力」いけそうな気がしています
昨日は本屋を覗いてみたが、未だ店頭には出ていないようですね。先行配布の方々からは読後の感想が来ています。出版社の編集長(三笠書房の元副社長)から小生も担当させていただきながら、これからの生き筋の勉強をさせていただきました。取り上げもした高校時代のマドンナからまだ読み切っておりませんが、易しく書いてありますが深く心に響きます。友人に是非薦めたい本です。 私のこと過分なおほめを頂き恥じ入ります。ただただ楽しんできただけですのにめったにいただけないすごい美味なお菓子をいただいた気がいたします。有難う。昭和一桁生まれの先輩から正直な感想は、「20年前に読ませてもらって、仕事オフの人生を、もっと楽しませてもらうべきだった!」です。もうすぐ喜寿なんて年齢になってしまうと、「さあ今から」なんてモメンタムは沸いてこないし、「面倒くさいことはやらんとこう!!」なんてのが、全てを支配してしまうので、「好きなこと」だけやって、飛ぶような速さに過ぎていくようになった1年間を過ごしている次第です。そう今年も残り75日のみ!!皆様も、お手に入りましたら是非感想をお聞かせ下さい。
2010.10.15
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
荒れ果てた小さなお堂に、身動きもできない重い病気で独り捨て置かれているお坊さんが気になっていたお釈迦様は、彼を見舞って「何故、誰も看病してくれないのかね」と問うと、「私は今まで、他の人々の世話をしてあげたことがなかったからです」と答えた。お釈迦様は、自分のこれまでの冷たい心の姿がわかり始めて懺悔の様子が見て取れたので、優しくうなずかれ介護された。あくる日、お釈迦様は精舎で修行する僧たちを集めて、「小さなお堂に、一人の僧が病気で寝ていることを皆は知っているだろう。なぜ看病してあげないのかね」と問うと、「彼は、自分のことばかり考えていて、誰にも親切にしてくれたことがありません。だから見舞ってやる気にもならないのです」と答えた。すると、「それ見ろ、そうなるのが平生の振る舞いの報いなんだと言って、平気でいていいのかね。仏さまのお恵みとは、してくれたから返すというものではなく、してくれようがくれまいが、してあげずにはおられないという、清らかで優しい心なのですよ。それがわからないのかね」と諭されました。私たちの日頃はまさにこの通りで、見返りを求めずに慈悲を実践することは難しいが、「情けは人の為ならず」で何時か巡り巡って自分に還ってきます。
2010.10.15
コメント(0)
-
今日は2001日目です
ブログを書き始めて2000日が立ちました。我ながら、休むことなく良く続いたと思っています。また、こんな硬い内容のものをよく読んでいただいたと思っています。延べ約30万人ということは、1日平均約150人の人に読んでいただいているわけです。エミリー・ディキンソンは「一羽の小鳥を癒しなば、我が人生に悔いあらじ」と言ったが、私も、暗い世の中だからこそ、たった一人でも良いから、私の文章を読んで「明るく、楽しく、自分らしく」生きるための手がかりを掴んでいただければと思って書いてきました。幸いにも、この文章を読んで、自殺までしようと思った娘さんが心を癒してくれたこともあり、私の願いは通じたと思っています。新たな1歩を踏み出すにあたり、どうしようかと考えています。「釈迦の智慧」があと1ヶ月ばかりで終わるので、その後に考えてみたいと思います。ご意見、ご感想を戴ければ幸いです。
2010.10.14
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
「自分が変われば相手が変わる。相手が変われば態度が変わる。態度が変われば行動が変わる」とヒンズー教の一節にもあるように、その究極は「四無量心(慈悲喜捨)」を持って見返りを求めず「四摂法」を実践することです。最澄は『己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり』と言ったが、「慈悲」とは「私も他の生命も皆、幸福になりたい。互いに仲良くしなければ幸せに生きることはできない」、この生きる基本を忘れてはならないという教えです。つまり、何事にも偏らない優しい心を育て、慈しみあうこと、人と悲しみを分かち合うこと、一緒に喜ぶこと、過分な欲望を捨てて持てるエネルギーを人々のために尽くそうということが大切だという教えと私は解釈しています。「四摂法」の本質は「あなたからどうぞ」と相手を先にする心で、「布施(精神的、物質的な恵みを人に与える)・愛語(人に優しい言葉をかける)・利行(相手の利益になることをする)・同事(相手と同じ気持ちになって考える)」の四つを心がけて行動すれば、心安らかに生きていくことができるという教えです。ある人が、「他人さまのお役に立つことは人生を2倍生きることだ」と言いました。あなたも、人生を2倍生きてみませんか?
2010.10.14
コメント(0)
-
書評が届き始めました
著書はまだ少数の人にお渡ししただけだが、読書感想メールが入ってきます。僕の母親も読ませていただいたのですが、「この手の本は内容が難しいことが多く、また、読んでいるうちに叱られているような気分になったりするが、先生の本はわかりやすくて面白く、とても元気づけられた」と申しておりました。嫁の親にもプレゼントしようと思います。老年について書かれたものは数多いが、その大部分が私に言わせれば50代終わりから60代初めのまだまだ少年少女 たちが書いたものである。年老いた人間の本当の気持というものが、こういう人たちに未だわかる筈がない。80うん歳の誕生日が間近に迫っている私には、もちろん老人の気持がよくわかる。君は未だ70だが、老いに対する優しさに溢れ、「あれするな、これするな」という説教調が無く勇気づけてくれるのがいい。困ったのは涙したことだ。ずるいぞ。気持ちが伝わり嬉しいですね。自分のために書いたのだから、老いに対する愛しさを感じていただけたのだと思います。私自身、優等生ではなく、失敗ばっかりしてきた落ちこぼれだから、かえって賛同していただけるのかな?私は、サラリーマン時代には新規事業を企画提案したが失敗して30代に早くも窓際を経験し、退職して最初に興した会社では取り込み詐欺的な被害に遭って長女の幼稚園代にも困り、コンサルタントになってからも公私にわたる挫折と失望を繰り返す悩み多い半生でした。その間、「生き甲斐とは」、「働き甲斐とは」、「幸せとは」ということをずっと考え続けてきました。皆さんもよくご存じのカール・ブッセ「山のあなた」の詩ではないが、幸せは自分の外にあるものと思って求め続けてきました。山のあなたの空遠く、「幸」住むと人のいふ。ああ、われひとと尋(と)めゆきて、涙さしぐみ、かへりきぬ。山のあなたになほ遠く、「幸」住むと人のいふ。でも、60代を前に、あるとき「幸せは外に求めるものではなく、自分の心の中に棲んでいるもので、自分の心の持ち方を変えればいいのだ」と豁然と悟りました。その途端に心は穏やかになり、「何時も笑顔が素適ですね。太田さんを見るとホッとします」と言われるようになりました。そんな気持ちの延長線上で書いたのが、今回の「快老力」です。週末をお楽しみに。◆ネット予約の場合は「快老力」太田典生で検索下さい
2010.10.13
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
絵本『きつねのおきゃくさま』(あまんきみこ:二俣英五郎)をご存じですか?腹ぺこの狐が痩せた雛に出会い、ガブリとやろうと思ったが、太らせてから食べようと考えた。雛が「狐さんどこかに良い住む処はない」と聞くと、狐は心の中でニヤリと笑い自分の家に連れて行きます。「狐さんは優しいね」と雛が言うと、狐はボウッとなります。狐は雛に優しく食べさせました。ある日、散歩に行った雛が痩せたアヒルに出会い、「狐さんとっても親切なの」と言うのでアヒルもまた狐の家に行きます。狐は親切という言葉にうっとりし、雛とアヒルにそれは親切にしました。またある日、散歩の途中で痩せた兎に出会った雛が、「狐さんは神様みたいなんだよ」と言うのを聞いて、狐はうっとりとして気絶しそうになります。雛とアヒルと兎を、狐は神様のように育てました。そんなある日、山から下りてきた狼と勇敢に戦います。狼は逃げていくが、その晩、狐は恥ずかしそうに笑って死んでいきます。たとえ誤解であっても雛の肯定的な対応が、狐の心の中に元々あった優しくて親切な心を引き出し、神様みたいな存在にしたという話です。相手がどういう行動をとるかは、実は自分の相手に対する心の持ち方次第なのです。
2010.10.13
コメント(0)
-
著書への反応は上々
休みの間に、今週末に発売される自著の案内メールを80名ばかりの方に送りました。ビックリしたのは、今までにない反応です。「是非読みたい、振り込むから直ぐ送れ」とか、友達にも勧めたいというメールが1日で1割を超え、30冊を超えるオーダーを戴きました。それだけ老いに対する不安が強いのでしょうね。出版社が「これほどまでに美しい老いへの準備」と帯に書いたが、ごく普通の高齢者自身が自分のために書いたものがなかったこともあるのでしょうね。専門家や50代や60代の人が書いた本は多いが、それは実際に老いの実感がない人が想像で書いたもので、実際に老いの真ただ中にある人の実感から見ると、「何か違うよな」ということが多いものです。また、専門家が書いたものは、身体や健康、介護などについて書いたものが多いですね。でも、本当に知りたいのは心の問題で、どう若々しく、イキイキと生きるかということだと思います。その点、私の本は「自分がこうありたい」という視点から出発しているので、章立ての案内だけでそれを嗅ぎ分けてくれたのかなと思っています。今週末にはお送りできると思いますので、楽しみにしていて下さい。
2010.10.12
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
釈迦仏法においては、苦しみの原因は煩悩にあるゆえに、煩悩を完全に滅すれば一切の苦悩は消滅し、ただちに成仏の境地を得ることができると説いています。この煩悩の数は8万4千あるが、見惑・思惑・塵沙惑という三惑に分かれます。見惑(道理や理屈に於ける迷い)と思惑(感情や感覚的な迷い)は、自己の内面の問題だから自己を覚知することで断てるかもしれないが、人間関係などから生まれる塵や砂ほどもある無数の塵沙惑は難しいと思います。人間関係においては、いかに善意を持って誠意を尽くしたとしても、必ずしも理解には結びつかず、誤解、矛盾、対立、葛藤、嫉妬、妬み、中傷などがつきものです。たとえそうであっても、それを乗り越える努力をし、他者に語り続け、誠心誠意、慈悲の心を貫き通す利他の精神を実践するしかありません。他者に対して語るということは、同時に自らにも語り続けるということでもある。人間関係の場を鏡とし、自分の生き方、思想を相手にぶつけて、そこで返ってくるもの、反応に自らの姿を見、自ら反省し、自己を磨き、また他者に係わり続けることです。つまり、「慈悲の心=忘己利他・自利利他」の実践によって、自他共に妙法に目覚めていくしかありません。
2010.10.12
コメント(0)
-
偶然か必然か
出版のご案内に、「この春我が家に泊まられた方のご縁で日の目を見ました」と書いたら、縁というものは偶然か必然かというメールを戴き、次のような返信を送りました。今回の出版は、「情けは人のためならず」と「縁=運」(成功=能力×努力×運)の賜だと思っています。 たった1回会っただけの人でも、困っていれば手を差し伸べるのが私の生き方です。 そして、手を差し伸べたからには、心から歓待するように心掛けています。 そこから縁が生まれてきます。 今回は、たった1回会っただけの人(それも顔を合わせた程度)でしたが、春のシーズンで宿が取れなくて困っていると言うことで我が家に泊め、行きつけの祇園の店で一緒に飲みました。 そのときに、「三笠の前副社長が定年で当社にきたんですよ」という話が出て、「彼なら昔私の担当でした」という話しになり、帰られてから「いま、彼の所にいるから電話を替わります」となり、「では、名刺代わりに書きためた原稿を送りますので見て下さい」と袖すりあう縁をたぐり寄せました。 前半のお泊めしたのは偶然であり、それから生まれた縁の糸をたぐり寄せて出版にこぎ着けた後半は必然だと思います。「いや、そうですか」とか「お久しぶりです」で終わればそれまでだが、「原稿を送りますので」と積極的に縁を生かす行動に出たからこそ実を結んだと言えます。 柳生家家訓に「小才は縁に出会って、その縁に気づかず。中才は縁に気付いて、その縁を生かさず。大才は袖すりあう縁をも生かす」とあるが、一つひとつの縁を大切に生かし、縁に感謝することから運が向いてくるのだと思っています。 袖すりあう縁をも生かすには、何にでも食いついてみる好奇心と行動力、普段からの努力と蓄積が大切だとも思っています。すると運が向いてきます。 私は若い人たちに良く縁の糸口を提供するようにしているが、その縁=運を生かす努力をしない人が殆どです。つまり、中才なわけです。若い間は「これやってみない」というチャンス=縁をもらっても、実力が無くてその縁を生かせない場合も多々あります。若いから実力が足りないのは致し方のないことだが、「次は期待に応えるように頑張ります」とそれをきっかけに努力する姿勢が見えず、黙って疎遠になっていく人が殆どなのは寂しい限りです。 私は「これは」と思った人には何回かは面倒を見るが、生かす努力をしない人は、厳しいようだがそこで見限ります。 すると、自分のことは棚に上げて私を悪者にする人もいるが、そんなのはほっておけばいいのです。良きにつけ悪しきにつけ、結果を甘受するのは自分自身なのですから。でも、それを聞いたいい大人が、真偽も確かめもせずに鵜呑みにして、私を遠ざける人もいて寂しい思いをすることもあるが、その程度の信頼関係の人ならこちらもお付き合いする価値はないと割り切っています。「来る人はこばまず、去る人は追わず」「来る人には安らぎを、去る人には幸せを」をモットーに、偶然の縁を必然に変えていく努力をこれからもしていきたいと思っています。
2010.10.11
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
私たちは独りで生きているのではなく、互いに助け合って共存して生きています。だから、自分だけが上手くいくということはまずありません。相手もまた、あなたと同じように自分が上手くいくことを必死に考えているのですから。ところが、自分だけが上手く行くことばかりを考えていませんか?自分が幸せを手に入れるために、自分の安全を確保するために、相手を自分の思う通りに操作したいという気持ちがほんのちょっぴりでもありませんか?そこから、人間関係やコミュニケーションのさまざまな問題が起きます。相手が委縮していたり、攻撃的だったり、素直でなかったり、上の空だったりするのは、あなたのコミュニケーションや行動そのものに対する反応です。人様から戴く縁によって自分の世界が変わるために、誰もが「できるだけ善い縁に巡り合いたいな。できることなら悪い縁は遠慮願いたい」と思って生きています。しかし、考えてみると、他人から縁を戴くという受け身だけでなく、自分そのものが他人にとっては縁になっているわけです。これを忘れてはならないと思います。人に対して、自分が善い縁にならなければなりません。そうすることによって、人様からお返しを戴いているのではないでしょうか?
2010.10.11
コメント(0)
-
やっと著書の見本が届きました
『快老力』は15日頃に店頭に並ぶ予定です。昨日見本が10冊届き、早速誌面にご登場いただいた方々にお届けに上がりました。私は縁というモノを大切にしているが、この本の誕生ははまさに縁の賜で、皆様に厚く感謝しています。書き手にとって本は子供のようで、その誕生は嬉しいものです。ついつい祝い酒を重ね、家に帰ったのが12時過ぎでした。難産であればあるほど、ホッともしますどう育っていくかは、読者の皆様の応援次第ですが、皆様に可愛がられて長生きして欲しいモノと願っています。不如意(生老病死)をも笑い飛ばして、「明るく、楽しく、自分らしく」心豊かに熟年以降を過ごすための自分用のメモを原稿にしたものです。老年社会の今日、皆様が「楽しく、笑いつつ」死を迎えるためのヒントになればと願っています。
2010.10.10
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
バブル期に成功した青年経営者が「自分は高卒だけれども、人よりも一生懸命に努力したから成功した。大卒の大会社の皆さんよりも良い生活をしている。それは皆さんよりも努力したからだ。成功するか否かは99%以上が努力で、運は1%以下もない」と得意げに話していたが、私はその話を聞きながら危険なものを感じました。案の定、バブル崩壊と共に会社は潰れてしまいました。努力したから成功したという一面も確かにあるだろうが、努力するだけで成功するならことは簡単です。努力したという原因と成功したという結果の間に、多くの善い縁があったことを知り(=知恩)、それに感謝する心が大切です。西濃運輸を興した田口利八は郷土の代議士大野伴睦から「人生ではいろいろな人から恩を受ける。恩を受けたことは絶対に忘れてはならん。これだけは守ってくれ。そうすれば君は必ず志を達することができる」と言われたそうだが、この世は自分一人では何もできません。出会いの恩を忘れないことです。柳生家家訓に「小才は縁に出会って、その縁に気づかず。中才は縁に気付いて、その縁を生かさず。大才は袖すりあう縁をも生かす」とあるが、成功者は一つひとつの縁を大切に生かし、縁に感謝するから長続きするのだと思います。
2010.10.10
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
この世の総てのものは、相互に支え合い、関わり合い、助け合って存在しています。人と出会い、ものと出会い、さまざまな状態との出会いによって私どもの一生は織りなされ、その巡り合わせによって人生が展開していきます。ある経済界の重鎮が、「人の生涯は誰と出会ったかで決まる。若い頃は人生に恐いものはなく、自分の力で何でもやれると思い込んでいる。それは若さの特権でもある。そんな若者も結婚し、子供ができると、だんだんと考え方も変わってくる。世の中、自分の言いたいことを言っていたのでは生きられないことが分かってくる。私は、そこからが本当の人生だと思う」と言われました。その志すものや仕事が何であれ、自分一人だけの力で大成することは不可能です。大成するには、個人の能力や努力はもちろん大切だが、それだけでは不十分で運が大きく左右します。松下幸之助は、運が9割だと言っています。運というのは棚からぼた餅的な僥倖ではなく、人との良い巡り合わせだと思います。例えば、「これやってみないか」とか「この人に会ってみない」などと紹介してくれたり、困っているときにアイデアや援助の手をさしのべてくれたりなど色んな縁があるが、その巡り会いこそが運の実態ではないでしょうか。
2010.10.09
コメント(0)
-
裁判への国民参加
私も法学部出身で刑事法をゼミで専攻した身だが、「疑わしきは罰せず」は刑事裁判における原則です。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負い、事実の存否が判然としない場合には被告人に対して有利に事実認定をすることで、推定無罪と同じ意味です。これは、冤罪を防ぎ、嫌疑を掛けられた人が被る不利益を守るためのものです。近年、日本ではこの疑わしきは罰せずの原則に反して、性犯罪やセクハラに関係する裁判では、警察や検察などが被害を受けたと訴えた女性側の言い分を鵜呑みにして(検証が難しい)証拠無しで立件し、加害者と見なされた男性側の言い分が十分考慮されないことが原因となっています。憎むべき犯罪ではあるが、無実なのに裁かれた人のその後の人生は無惨です。いま問題になっている郵便不正の問題でもそうですが、このために村木さんは貴重な人生を犠牲にされました。死刑囚にされて、人生をぼうにふった人もいます。そんなことを避けるために、集団ヒステリーを起こす危険性のある制度はよく考えるべきです。検察審査会の問題もクローズアップされているが、ある意味では魔女裁判の危険性を含んでいます。私たち一般人に与えられているのは、マスコミによる偏った見方による一方的な情報だけです。感情だけで告発され、一生を左右される人の身になって考えることも大切だと思います。小沢さんの問題にしても、証拠書類などを読み込んだのかも疑わしく、法律的な質問はほとんど無く、被疑者が悪いという感情論が出る程度で、「取り敢えず裁判所に投げて判断してもらったらいいじゃないか」という雰囲気だったようです。まさに魔女裁判で、被告にされた人はたまったものではありません。「自分がもし被告になったら」と少しでも考えたことがあるのでしょうか?中世末期から近代にかけてのヨーロッパや北アメリカにおいてみられた魔女裁判は、心理学的な観点から集団ヒステリーの産物とみなされています。セイラム魔女裁判(アメリカのセイラム村で1692年にはじまる一連の裁判)では、200名近い村人が魔女として告発され、19名が処刑され、1名が拷問中に圧死、5名が獄死しました。無実の人々が次々と告発され、裁判にかけられたその経緯は、集団心理の暴走の例として著名です。現代においても、魔女狩りに類した行為が行われることがあります。民衆が参加する制度には反対しがたい雰囲気もあるが、愚衆政治という言葉もあります。もう一度、あらゆる面から裁判制度を真剣に見直してみる必要があると思います。
2010.10.08
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
天台宗座主山田恵諦師は「与えられた自分の仕事に本命をもって打ち込む人は、必ずその場に無くてはならない人になる。それが一隅を照らす人です。その道を究めようとする心を持って生活しようじゃないですか。その道に打ち込み、直向きに生きていけば、生活が成り立たないはずがない」と言われた。綺麗な水でも停滞した途端に腐敗し、悪臭を放つようになります。人間も同じで、進歩が無くなると愚痴ばかりが目立つようになります。愚痴をこぼしている人は、年齢に関わりなく先に進もうとする意欲を失っている証拠です。困難な仕事を命じられて「自分の手に余ります」と逃げていては、いつまで経っても進歩しません。人間は、手に余るほどの問題にチャレンジすることで成長していきます。苦労は、後で大きな花を咲かせるための肥料といえます。・大きな理想を絶えず頭の中に描いて現状に満足せずに問題を創り出し、・その実現のために広い視野から問題点を洗い出し、・自部門の利害や立場だけでなく全体的な見地から真因を明らかにし、・業界や社内の常識に囚われずに新鮮な対策を考え、・その集団を背負って立つという気概で自己責任で対応していくことです。
2010.10.08
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
サラリーマンの一生の中で、「やりたいこと」をやれる割合は低く、「やりたくないこと」「面白くないこと」をやらされる割合の方が多いかもしれません。でも、「嫌だ」と思えば思うほど、苦しさばかりがドンドンと募ってきます。そこで、「あばたもえくぼ」ではないが、自分から惚れ込んでみることです。営業マンでも「あのお得意さんは嫌だな」と思えば、やっぱり足が遠のきがちです。そんな気持は相手にも自然と伝わるもので、事態は益々悪くなってくるのが普通です。そんなときは、心の中で「あなたが好きだ」とそっと繰り返してみて下さい。すると、悪いこと嫌な面ばかりでなく、良い面も少しずつ見えてくるはずです。そんな気持は相手にも以心伝心で伝わり、段々と良くなってくるはずです。このことは、仕事への取り組み姿勢にも当てはまります。郵便局勤めのA子さんは、窓口での単純作業の繰り返しが嫌になり、司書になろうと通信教育を受け始めたが続かない。転職を諦め、毎日が楽しくない原因を考えてみた。事務手続を機械的にこなしているだけの自分を反省し、お客様に笑顔で接し積極的に声を掛けることにした。するとお客様からの相談も増えてきて窓口に座るのが楽しくなり、研修にも身が入るようなってきたという。
2010.10.07
コメント(0)
-
日本語を学ぶ中国の人も多い
昨日は中国大連大学教授で、阪大博士課程(言語文化研究科)に留学している李さん(女性)が訪れてくれました。奨学金が16万円で授業料も無料と言うことで、アルバイトをしなくてもなんとか勉学に励むことができるとか。でも、奨学金は3年間しか出ないので3年で博士号を取る予定とか。その意気込みがいいですね。日本語を書くのは未だ多少おぼつかないところがあるが、日本語を教えて見えると言うことで話すのは流ちょうです。各国の若者たちの話題の特徴性を研究して見えるそうで興味が湧いてきました。コミュニケーションの原稿を差し上げたが、お役に立てば嬉しいですね。大連は100万人都市で、日本の進出企業も多く、1万人が日本語を学んでいるとか。就職に有利と言うこともあるようだが、1%が日本語を学んでいるというのは素晴らしいことですね。中国との関係がギクシャクしている現在、もっと民間同士のコミュニケーションを密にしていくことが大切だと思います。
2010.10.06
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
人は誰でも、少しでも人のために役立っていると思えば、やり甲斐も出てくるし楽しいものです。実は、仕事を通して人を楽しませたり喜ばせたりすることによって、自分自身も楽しませてもらっているのです。昔、瀬戸内海を汚染した工場があり、漁民たちは「魚が売れない」と補償を要求し、海がきれいになるまで魚は魚市場の卸値で引きとられることになった。翌日から、漁民たちは、捕った魚を工場に運んで穴の中に捨て、お金をもらって帰りました。最初のうちは満足していたが、1週間経ち、2週間経つうちに漁民の顔に生気がなくなり笑顔が消えてきました。いくら収入が保証されても、意味のない仕事をしていることは虚しいものです。今までは、魚を美味しいと言って食べてくれる人がいたからこそ、苦しい仕事も楽しかったのです。労働が生活の手段となり、労働対価として給料をもらうという考えでは、労働は苦痛となるだけです。心ある仕事とは、相手を思うチョットとした心の込め方の問題で、このチョットが欠けたら金儲けだけの仕事になってしまいます。仕事に誇りが持てないという人もいるが、仕事自体に貴賤があるわけでなく、役立ち意識と人を喜ばせようという心の欠如にあるように思います。
2010.10.06
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
人間というものは、不思議な生き物で、犬猫のように目的もなく生きていると、生き甲斐がなくなってしまいます。すると、イライラがつのってきます。現代人にイライラする人が増えているのは、目的喪失症が影響しているのかもしれません。ですから、自分なりの生きる目的を持つことが大切になります。「はたらく」とは、「はた」を「らく」にさせることだと思いませんか?つまり、慈悲の実践です。自分は、仕事を通して「どんなことで人を楽にさせてやりたいのか」を考えてみることです。人間が働くということは、自分のためだけではなくて、他のために働いている、それを通して他のために生きている、そういう面を意識することが本当の生き甲斐に繋がるのだと思います。仏教に自利利他という言葉があるが、自利というのは自分自身が安心立命することです。自分自身が安心立命していないのに、他人を安心させることなどできません。だが、自分が安心立命するだけでは、本当の安心立命は得られないと思います。一人でも多くの人に手を差し伸べて安心立命をしてもらうために手を尽くす、そうすることによって自分自身の安心立命も確固たるものになるのではないでしょうか? そんな生き様の表現が仕事だと思います。
2010.10.05
コメント(0)
-
ブログがとりもつ見知らぬ人に会う楽しみ
昨日は、中国から大阪大学に留学している若者から、『小さな感動のおすそわけ』やブログ(若者向けの方だと思う)を読んでいるが一度お会いしたいとメールが入りました。そこで、自著の「まえがき」を読み返してみたら、こんなことを書いていました。人間の本性である「自分ほど可愛い者はいない、自分が先ず幸せになりたい」ということに固執しすぎては、何事もうまく解決できません。「自利」と「自利」がぶつかりあえば、そこに生まれるのは「対立」です。この対立が前面に出すぎては、政治・経済はもちろん、ビジネスも、仕事の人間関係も、友人や家族とのコミュニケーションも、すべてがうまくいかなくなるのは当然でしょう。京都の知恩院の掲示板で、「立場が違えば重いが違う。違う思いを話しあい、違う立場で手を握る」という言葉を見つけました。まさに、この言葉の通りだと思います。新聞を見れば、尖閣列島問題から検事による改ざん問題、家族問題まで「自利」を求めるあまりの記事で溢れています。そんなこともあって、「釈迦に学ぶ」のブログを書いているのだが、「自利」を求める心を冷まして、忘己利他や自利利他の心を養うことはなかなかできることではありません。ほんの少しでも、そんな心を持ちたいものです。若者とは明日会うことにしたが、どんな話しで盛り上がるか楽しみです。◆今月は時代祭があります。同じ日の夜、鞍馬では火祭りがあります。
2010.10.04
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
では、「何のために働くの」→「生きるため」→「何のために生きるの」と追究していくと、答えに詰まります。結局、私たちは、「良い人生」を送るためには「良い会社」に入る必要がある、それには「良い学校」に入れる必要があると、「いま」を楽しむこともなく子供の頃から塾に追われてきても、最終的な「何のために生きるのか」という、最も大切なことを考えてこなかったことに思い当たるはずです。恐らくは、そんなことも考えたこともないのが多くの人の実感だと思います。つまり、目標はあっても目的がないことになります。それで、満足する人生が送れるのでしょうか?この世の中にあるものはすべて、何か目的があって、その目的のために存在しています。だが、肝心の我々だけが、何のために生きているのか、何の目的もない。(「人間は生きているために生きている」といったお坊さんもいるが)だから、「誰でもいいから殺したかった」というよう事件が多発したり、「生きていてもしようがない」と毎年3万人以上の人(奈良市・豊橋市・長野市などの人口に相当)が自殺をしています。
2010.10.04
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
職場での重圧から心や体を病む人が増え、とくに30代(心の病で労災認定を受けた人の4割が30代)や課長職に多く、過労死ラインを越す長時間残業をしている人が男性の2割強もいるそうです。それほどまでして、私たちは、毎日、毎日、生きて働いています。でも、朝早くから出勤して、嫌な目もしながら、夜は夜で遅くまで働いていると、フッと「一体、私は何のためにこんなに一生懸命に働いているのだろうか」と思うことはないでしょうか?「会社のために働く」・・・でも、社長だろと部長、課長だろうと、自分が辞めたり死んだりしたとしても、すぐに別の人が後窯を努めて何も無かったように仕事はまわっていきます。いや、かえって良くなるかもしれません。「家族のために働く」・・・女房や子供にしても、親父が死んだって、親はなくても子供は育つし、結構、女房もイキイキと楽しそうに生きていきます。かえって、ノビノビと人生を楽しんでいる奥さん連中は多いものです。「食うために働いているのだ」と自問自答してみる。でも、三度三度、飯を食っていても、やっぱり死ぬときは死にます。そうすると、遅かれ早かれ差はあるかもしれないが、食っても死ぬし、食わなくても死ぬわけです。
2010.10.03
コメント(0)
全53件 (53件中 1-50件目)