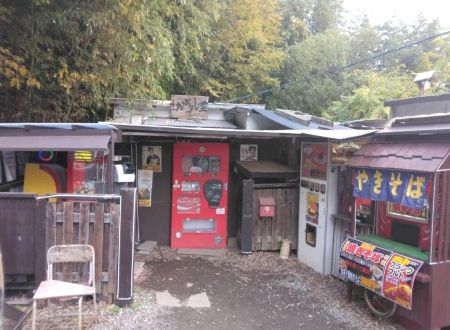2010年03月の記事
全47件 (47件中 1-47件目)
1
-
寒い日が続きます
相変わらず寒い日が続きます。昨日の春の雪は日の出と共に溶けてしまいましたが、寒いと花見をする気にもなりませんね。花見が浮き浮きするのは、春が来たことが実感できるポカポカ陽気を伴ってこそと実感しています。今朝のNHKでは天龍寺の枝垂れ桜を放映していたが、明日辺りからは気温も高くなるとのこと、週末は花見を心から楽しむことができそうですね。一度、お時間のある方は、公園前から保津川展望台に登り、その先の方から小倉山に登ってみて下さい。ここから眺める天龍寺の庭や洛中の景色もいいですよ。◆昨日朝6時過ぎの展望台からの眺めです
2010.03.31
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
お釈迦様は、最後に次のように弟子たちに言われたそうです。(大般涅槃経)弟子たちよ、これまでお前たちのために説いた私の教えの要は、心を修めることである。欲を抑えて己に克つことに努めよ。身を正し、心を正し、言葉を真あるものにしなければならない。貪ることをやめ、欲を無くし、悪を遠ざけ、常に無常を忘れてはならない。もし心が邪悪にひかれ、欲にとらわれようとするなれば、それを抑えねばならない。心に従わず心の主となれ。心は人を佛にし、また畜生にする。迷って鬼となり、悟って佛となる。弟子たちよ、この教えのもとに相和し、相敬い、争いを起こすことなく、水と乳のように和合せよ。水と油の如くはじきあわざれ。この教えの通りに行わないものは、私に会っていながら私に会わず、私と一緒にいながら遠く離れている人である。この教えの通りを行う者は、たとえ遠く離れていても、私とともにある人である・・・。「無欲になれば涅槃の境地に立てますよ」と言われたが、無欲になっては人間は生きてはいけません。「無欲の教えは、悪しき欲望の営みを捨てなさい」、つまり少欲知足の精神、欲をより良く生かす道を無欲の教えで導いて下さっているのです。「今日だけは控えよう」程度から始めればいいのです。
2010.03.31
コメント(0)
-

嵯峨野の桜は真っ白な綿帽子を被っています
今朝起きたらこの冬一番の積雪。嵐山から小倉山、愛宕山・・・一面雪に覆われています。咲きかけた桜の花も綿帽子を被って寒そうです。
2010.03.30
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
ある大学の教授がキャンパスを歩いていると、ベンチに学生が座っており、その前にゴミが落ちていました。そこで、学生に「目の前にゴミが落ちているんだから、拾ったらどうだ」と言いました。すると学生は、まったく心外だという顔で、「僕が捨てたんじゃありません」と答えました。「そんなことは分かっているが、ここは君の大学だろう。自分を“よそ者”であるかのように考えるのは、全くもったいないことじゃないか。大学の校舎も庭も“自分のもの”だと思えば、愛着がわき、きれいに使おうと思えるのではないか。“私は○○大学の学生である”という誇りがあれば、自然にそう思えるようになれるはずだ」と言ったが反応がなかったそうです。車の窓から平気でタバコの吸い殻を投げ捨てる人でも、まさか自分の部屋の中で同じことはしないはずです。自分の車の中、自分の部屋の中さえきれいになればいいという考え方は、とても貧しく、ちっぽけな欲です。「自分さえよければいい」というのでは、かえって自分の生き方を窮屈にしてしまいます。「この町、この国、地球すべてが自分のもの」と大きな欲を抱けば、どれだけ心は豊かになるでしょう。そんな大欲を育てて欲しいと思います。
2010.03.30
コメント(0)
-
嵯峨野は雪が舞っています
今年の花は早いと思ったら、寒い日が続き、咲き始めた花が縮こまっています。今日の午後は、雪が激しく舞っています。何か変な陽気ですね。例年4月の始めに一般公開される平和郷(広沢の池端 世界救世教内)の桜はいつになるのでしょうか? 円山公園の垂れが衰えたこの頃では、京都一番の枝垂れ桜かな? ここの桜はいいですよ。
2010.03.29
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
人間は欲望によって苦しむが、仏法では「小欲を捨て、大欲に立つ」ことを説きます。ちっぽけな我欲を捨て、それらすべてを超越するような大きな欲をもてば、煩悩に煩わされることもなく、かえって謙虚になれると諭します。他人をうらやんだり、憎んだりするのは、「自分のもの」と「他人のもの」を分けて考えるからです。「自分の幸せ」よりも「他人の幸せ」のほうが大きく見える。「自分の心」が「他人の心」によって傷つけられた。「自分だけが幸せになりたい」と思うから苦しむのです。それが「小欲」です。人は誰でも幸せになりたいと願うものであり、それ自体は悪いことではないのだが、他人と自分を比較して落ち込んでしまうようでは苦しいだけです。「他人のもの」も「自分のもの」だと思って大切に扱えば、他人の幸せまでも自分の幸せと感じることができるようになります。「他人のもの」を「自分のもの」にすると言っても、何かを他人から奪い取るわけではありません。我が物顔で振る舞うというのでもありません。「奪う」という発想は、「他人のもの」と「自分のもの」を分けているからこそ起こるのです。他人と自分の垣根を取り払い、すべてを共有すると考えればよいのです。
2010.03.29
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
中卒後プロボクサーを志したが、内蔵の病で新人王の夢を断念した小笹公也さんは、アルバイト先の塗装屋で修行して21歳で独立した。今では社員1500人を抱えるリホーム会社の社長だが、38歳の時に大検に合格して大学の商学部に週4日は通い、パソコンで決済をしたり指示を出したりしています。宝塚花組主演娘役として活躍し、退団後はテレビドラマのヒロイン役などを演じていた枡谷多紀子さんは、30代半ばに芸能界を去り、自宅でピアノと歌を教えながら歯科医師を目指して予備校に通い、2度目の受験で歯科大学に合格した。歳を取ってからの勉強は、やっと頭に入れたことがあっと言う間に抜けていく。学校は卒業できたものの、国家試験にはなかなか受からない。母親の看病と家事も重なり、やっと4度目の挑戦で合格しました。現実の社会や生身の人間に直接関わりたいという思いを抱いて、挑戦した歯科医の夢の実現に10年を費やしたが、「投げ出さなかったのは宝塚で鍛えられたおかげ」と笑う。夢への挑戦には、人それぞれのドラマがあります。早咲きの花もあれば、遅咲きの花もあります。何歳になっても、前向きに挑戦し続ければ成就しないことはないはずです。あなたに、『頑張れ』というエールを送ります。
2010.03.28
コメント(0)
-
京は快晴
今日は快晴だが肌寒いですね。朝の散歩は展望台まで行ってきました。山ツツジも咲き始め、保津川沿いの嵐山斜面も咲き始めました。京都の桜スポットで5分咲き以上の所は次の通りです。地蔵禅寺・法金剛院・醍醐寺・高台寺・あとは咲き始め程度です。
2010.03.27
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
今の若者にとっては国境も県境のようなもので、国にこだわることはありません。大切なのは、「やりたいことがやれる自分の居場所」で、それがたまたま外国だったという日本人もこれからは増えてくると思います。また、仕事と趣味の両立を図るのも良いでしょう。医師でピアニストの上杉春雄さんは、4歳でピアノを始め、小中学校の時には数々の音楽コンクールで優勝や準優勝もしました。北大医学生の時にはCDデビューもし、将来を期待されたものの、医学の修行に専念したくて卒業と同時に表舞台から退きました。でも、研修医時代も、忙しい合間を縫って何時間も鍵盤に向かい、まるで野戦病院のような環境の中で疲れた心を癒やしていました。あるとき、パーキンソン病の患者グループにピアノを披露したところ、「演奏の間、初めて病気のことを忘れました」と言われ、「音楽活動を通して私自身が豊かに生きることで、患者さんや世の中にお返しができることがきっとあるはず」と医者と音楽活動との両立を決意しアルバムも発表しました。「これ」といった定型に拘らず、自分なりの道を見つければいいのです。
2010.03.27
コメント(0)
-

花冷えです
昨夜は祇園からの帰りに寒いと思ったら、今朝は愛宕山さがうっすらと雪化粧です。円山公園の枝垂れ桜は年老いて無惨な姿ですが、開花しました。(夜桜の写真)今朝は広沢の池向かいの佐野造園まで散歩しましたが、綺麗に咲いています。(下の写真)嵐山の斜面も咲き始めています。見頃は、この2,3日の寒さで来週末頃かと思われます。
2010.03.26
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
タイ初の日本人歌手といわれる俳優あおい輝彦さんの長女青井英里奈さんは、タイのヒットチャート1位になり、象の調教師を目指すヒロイン役でテレビドラマにも出演した。英語の腕を磨き通訳を目指していた彼女は、日本で何度もスカウトを受けたが断った。大学2年の時にタイを旅し、季候、街のにおい、食べ物、言葉、そして温かい人々、すべてが「私に一番ピッタリくる」と感じられた。タイに恋に落ち、迷わずタイ王立大学院に進んだ。「誘われて芸能活動を始めたが、それ自体が目的ではない。タイ文化を机上の勉強以上に知ることができると思ったからである」と語っています。韓国で大人気の女優「ユミン」こと笛木優子さんは、日本人として初めて韓国のテレビドラマに主演し、生放送の超人気歌謡番組の司会者まで射止めた。日本でも新進女優として順調だったが、21歳の時にヒロインがイキイキと魅力的に描かれている韓国映画に魅了され、「良い作品ならどこへでも行きたいし、人と違う目標も良いかな」とソウルで一人暮らしを始めて3年で開花した。二人に共通するのは、「目に見える成功よりも、一日一日、自分の信念を貫いて好きなものに接していたい」ということです。
2010.03.26
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
人目につかない地味な仕事、あるいは決して特殊ではないありふれた仕事であろうと、それだけで働き甲斐がないと早とちりしないでください。どんな仕事であろうと、ひたすら自分の人生を投入しても惜しくないという意気込みで打ち込めば、そこに工夫が生まれ、張り合いが生まれ、無常の生き甲斐を感じることができるはずです。そうやって一つのことに打ち込んで、それを極めることによって、初めて総ての物事に共通する真理に到達することもできます。結局、人間としての本当の幸せは、それが、仕事であれ、ボランティア活動であれ、自分の能力を十分に発揮でき、自己実現欲求が満たされたときです。だから、職選びに当たって大切なことは、1.自分の価値観から見て役割意識を満たすことができるか?2.自分の適正からみて一隅を照らすような存在になれるか?が基本で、これが満たされれば張り合いを持って働くことができるはずです。間違った職選びをすると、一生ストレスを抱えて不愉快に過ごさなければなりません。この世には、生計を立てる方法は2万以上あるといいます。その中には、自分に合った好きな仕事は幾つもあるはずです。
2010.03.25
コメント(0)
-
京の花見は来週辺り
昨日からの雨で気温も下がり、垂れ桜をのぞいては2分咲き程度で来週明け頃からが見頃と思われます。明日からの客には、佐野造園など早咲きの所を選んで案内しようと思っています。ところで、私たちの政治への期待を見ていると面白いですね。(今朝の朝日世論調査)みな、直ぐの効果や目先対応ばかり望んでいるようです。レーガン元大統領は「皆さんが必要なものを何でも与えられる強力な政府は、皆さんから何でも取り去ってしまう強力な政府と言うことになります」と言ったが、皆何かをしてもらうことばかり望んでいた結果が、1000兆円にもおよぶ借金を後世に残しています。ケネディーの言葉が思い出されます。「あなたの国家があなたのために何をしてくれるかではなく、あなたがあなたの国家のために何ができるかを問おうではないか。わが同胞の世界の市民よ、アメリカがあなたのために何をしてくれるかではなく、われわれと共に人類の自由のために何ができるかを問おうではないか」という言葉です。それと、富士通の秋草さんが辞任に追い込まれたという記事もスッとしました。いつまでも権力(幻想にしか過ぎないが)を振り回すのは見苦しいものです。そんなのは我欲にしか過ぎません。いつまでも欲を捨てられない人は憐れです。まあ、政治家たちも同じですがね。
2010.03.24
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
野球のイチローや松井、サッカーの中田などが若者たちに支持されているが、それは彼らが富や名声(名聞・名利)を得たことよりも、自分らしい生き方をしているからだと思います。イチロー選手がアメリカ大リーグに挑戦するとき、「僕はロングヒッターではないので、ヒットを量産し、足を生かす一番打者こそ天職だと思っている。トップ・バッターとしてのイチローを完成させたい。『生きる、生かされる、生かす』、これができる選手です。大リーグの道を選んだのは、まず自分を生かすためです。そして、自分の存在が他の選手との関係に広がって、お互いに生き生かされるようになることです。それがベンチの采配の幅を広げさせ、チームを生かすことになれば最高です」と言いました。彼はまさに、究極の一番打者こそが自分が一隅を照らす存在になれる場だと確信して働く場を選択したのです。その選択に間違いはなく、彼はいまイキイキと輝いています。みなさんも、自分の特性をよく見極めて、自分にとって「生きる、生かされる、生かす」仕事の場は何かを見極める努力をして欲しいと思います。
2010.03.24
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
やり甲斐はコインの裏表のように、生き甲斐と働き甲斐が背中合わせになっています。表が生を楽しむ人生の顔なら、裏は喰うために働く生活の顔です。ほんのこの間まで、大部分の人にとって生き甲斐とか働き甲斐などとは無縁に、生活のために働いてお金を稼ぐのが人生の全てでした。そんな時代には、労働は苦役以外のなにものでもありませんでした。だが、物質的に豊かになった今日の日本では、働くことにどんな意味があるのでしょうか?プロ野球の新庄選手が日本での5年間12億円という高額の年俸を蹴って20万ドルを提示したメッツに夢を求めたように、現代においては仕事はその人をその人たらしめ、自分の生き様を表現する一つの手段だと思います。そもそも、私たちの一番貴重な時期の大部分を仕事に費やすのだから、仕事を自分の夢の実現や価値観の表現手段として生かすことで、働き甲斐の中に生き甲斐を見つけていかないと、なかなか心豊かで日々充実した人生を歩いていくことは難しいと思います。だから、好きなことやよくできることを見極めて、それを天職として励み、一隅を照らす存在となって自己実現を図ることが大切なのです。
2010.03.23
コメント(0)
-
花も咲き始めました
朝から作務衣を着て(着物姿は交通機関が無料ですから)西大谷にお参りに行ってきました。鴨川の五条大橋の下流は早咲きの桜が綺麗でした。上流はまだ蕾。この差がいいですね。両親のお墓に(墓のマンションですが)お参りし、清水寺に出るとさすがに彼岸の翌日、連休最後の観光客で一杯でした。清水三年坂の桜が綺麗でした。飲食店のガラス窓に映る桜がまた絶景。散歩がてらに歩いて久しぶりに二条城へ。桜はまだですね。週末から週明けかな?この週末には嵯峨野にもお運び下さい。京の桜守佐野造園の庭が穴場です。
2010.03.22
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
あくる朝会社に行って、数十人の社員を集めて、「今まで自分はどうして銭を儲けようか、どうしてこの会社を大きくしようかと焦っていたが、今日から考えを変えた。今日からは、どうしたら世の中のみなさんが喜んでくださるか、ということに全力をあげる会社にする。みなさんの欲しがるもの、必要なもの、便利なものを、なるべく安く提供すれば、社会のみなさんが喜んでくださる。社会のみなさんが喜べば、会社に金がはいるのは当たり前だ。銭もうけなどは考えないで、今日から社会に奉仕していくことをこの会社の目的とする。みんな賛成か」といったところ、みんなもこれに賛成した。これが、家内工業から松下電器へと発展する精神的な礎となったことは疑いの余地もありません。 要するに、自分のことだけ考えていく人生は、うまくいってプラスマイナスゼロで、あとにはなんにも残りません。しかし、たとえささやかでも、毎日の生活を人に喜んでもらうために送るならば、それこそすべてがプラスとなり、自分も幸せになれば周囲も幸せになる、ほんとうの人生というものがそこに味わえるはずです。その精神を守って、幸せな人生、明るい人生を開かれることを、一人でも多くの人に分かって頂きたいと思います。
2010.03.22
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
松下幸之助『道をひらく』という本の中にもこんな話がありました。松下さんが事業を始めて15年ほど経った頃、ある宗教の本部へ連れて行かれたが、そこには素晴らしい本殿が建ち、信徒の宿泊のための建物がずらっと並んでいてびっくりしたそうです。たいしたものを建てたものだ、この新しい宗教がこんなものを建てたが、財源はどこにあったのか、どうして建てられたのだろう。経済人として、まずそのことが頭を離れなかった。電車の中でも考え、うちに帰っても考え、考え抜いて結論が出た。あれはなんでもない。その宗教の教えで社会の大勢の人を喜ばせたのだ。喜んだ人が大勢なら、わずかな金を持ち寄ってもあれができるのだ。大勢の人を喜ばせたということ、それだけが資本だ。私は今まで、どうして銭をもうけようか、どうして自分の会社を大きくしようかと焦ってきたが、それは間違っていた。銭儲けなんぞは考えんでもいい。世の中の大勢を喜ばせさえすれば、金は自然に入ってくるのだ。これからは、自分の電器事業を通して、社会の大勢のみなさんに喜んでもらえる会社にならねばならぬ。それが自分の一生の事業だと気付かれたそうです。それが、松下さんにとって一大転機をもたらしました。
2010.03.21
コメント(0)
-
京都に開花宣言
昨日、桜の開花宣言がでました。観測史上2番目の早さとか。来週末には見頃になるのですかね?醍醐寺の桜は今週末でも見られるようですよ。花の咲くのを今か、今かと待つ今の季節が好きです。
2010.03.20
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
朝日新聞『ひととき欄』に、「私はぼんやり学校を卒業して、人にすすめられて平凡な結婚をし、毎日変化の無い生活をしているつまらない女です。人生とか生き甲斐なんてことさえ、考えてみたこともありませんでした。ところが、子供ができて赤ちゃんに乳をふくませたとき、私ははじめて生き甲斐を感じました。この赤ちゃんは私がおらなければ育たない。育つかも知れないが幸せにはなれない。私と言う人間はつまらないが、この赤ちゃんにとっては日本一大切な、なくてはならない人間だなと感じましたとき、はじめて自分の値打ちがわかりました。私はこの赤ちゃんのために健康で長命してやらねばならぬと考えました」という投書が掲載されていました。 この一文を読んで、生き甲斐とはそういうものだなとうなづきました。この世の中に、「あなたがいてくれるから」といってくれる人が一人でもあってこその生き甲斐です。家庭においても社会においても職場においても、自分の存在に価値観を持ってくれる人が多ければ多いほど生き甲斐が大きいわけです。 もう一歩進んで、よりよい世界をつくるために、自分なりにできる一生を貫く仕事の持てることは人生最大の喜びです。それが、本当の幸せです。
2010.03.20
コメント(0)
-
自然は凄いですね
NASAの写真分析によると、奈良県と同じくらいの大きさの氷山が南極にぶつかり、新に大阪の1.6倍くらいの大きさの氷山が誕生し、ペンギンを載せたままオーストラリアに向けて動き始めたとのこと。地震といい、地球の営みは凄いですね。人間界の欲や煩悩にもとづいた諍いなど小さい小さい。政治家や官僚、経営者の皆さん、もっと大きく考えて下さい。富士通の経営陣の争いも見苦しいですね。その後ろに秋草相談役の影も見えるが、秋草さんは社長時代に「経営の目的は利益で、人は手段」(私は逆だと思う)と言った御仁、やんぬるかな。まあ、それはそれとして、今日は植物園でも行って心を静めてこようと思います。22日まで、京都では着物で出かけるとバスや地下鉄、ライトアップが始まった二条城も無料になります。作務衣も着物として扱ってもらえるので、南禅寺末寺の住職に戴いた丹後縮緬の作務衣を着て出かけようと思います。皆さんも、この週末には、たまには着物で如何ですか? レンタルもやっているようですし。◆氷山の衝突写真
2010.03.19
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
人生は、自分の幸福だけをつかめばいいというものではありません。自分一人の幸福などというものは、泡のごとくたちまち消えてしまう儚いものです。いわゆる幸福とは、欲望というマイナスを何かで満たしていくものです。その欲望というマイナスは無限で、埋めても、埋めても、埋め尽くされることはありません。もし埋めることが出来たとしても、それは単に欲望というマイナスを何か物でプラスにしただけだから、その人生はプラスマイナスゼロです。しかし、人のために働くことはすべてプラスになります。家族だけでご馳走を食べることは楽しく生き甲斐かもしれないが、そんな楽しみは半日ももたない生き甲斐です。ところが、難民の人たちにその分を差し上げたなら、相手に喜ばれるだけでなく、自分にも長い喜びとなって消えることはありません。自分のことよりも人のために働いたことは、すべてプラスになります。しかも自分と他人の区別のない心境がわかるならばなおさらです。 人の幸福が私の幸福であり、あなたの幸せだとわかる、そのことが実は最上の幸せです。『人のことばかり考えたら自分が成り立たないではないか』といわれそうだが、まずその常識的疑念から解放されなければなりません。
2010.03.19
コメント(0)
-
もう春はすぐそこまで
昨夜は、田舎から届いたタケノコをおすそ分けするために祇園界隈を徘徊。白川の早咲きの桜が1本(吉井勇の句碑の近く)花を付けていました。野原の一本桜は好きだが、巷の灯りに交じる一本桜はなにか寂しいですね。かにかくに 祇園はこひし寝るときも 枕のしたを水のながるる「かにかくに」は「ともかく」というような意味だが、東山連峰をもした形の石に刻まれた吉井勇の句です。一度、舞妓さんの膝枕で横になり、白川の水の流れる音でも聞いてみたいものですね。来週辺りになれば、あちこちで花も開き始めるのでしょうね。心が騒ぎます。
2010.03.18
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
これら当たり前のように思っていることも、実は大変幸せなことなのです。体が不自由になってみて、自分で「できる幸せ」が初めて分かります。できて当たり前の「今」に感謝したいものです。人間の本性は自愛と我欲だから、人から何かをしてもらったり、自分が何かができるようになると嬉しくなります。でも、この二つは、自分の欲望を満たすだけの幸せです。では、他人に何かをしてあげて心から喜ばれた時、あなたはどんな気持ちがしましたか? きっと、何とも言えない喜びを感じたはずです。人は共に喜ぶ時、喜びは二倍にも三倍にも膨らみます。喜びが人の数だけ増幅され、感動を呼び起こします。「してあげる幸せ」です。でも、人に何かをしてあげても、決して「してあげた」と思わないで、自分自身がさせていただける境遇にあることに感謝することです。つまり、「させて戴ける」幸せです。「してあげた」という気持ちを持つと、ついつい「~をしてあげたのに」と「のに」が出てきます。「のに」には、何かお返しを期待した打算が見え隠れします。そうすると相手も、素直に喜ばなくなります。何かをしてあげても、スッパリと忘れてしまうことのできる人は心の達人です。
2010.03.18
コメント(0)
-
早くもタケノコが届く
今朝、三重の兄からタケノコが届きました。例年は4月の10日前後なのに、随分と今年は早いようです。「タケノコの本場京都に送ってきて」と何時も冗談を言っているが、78になる兄がわざわざ掘って送ってくれる気持が嬉しく、今日は土佐煮を楽しむつもりです。このところ春の便りを載せるようになって、今日も東京から来週の金曜日に泊めてというメールも入っています。京都の桜守佐野さんの庭なら咲いているだろうなと今から楽しみです。ガンと闘っている高校時代にのマドンナからも、春ですねというメールが届きました。今月の末は、親しい友人が逝ってから2年目の春にもなります。それこそ「さまざまのこと思い出す桜かな」(芭蕉)ですね◆広沢の池端 今朝の桜のつぼみ
2010.03.17
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
ところで、私たちには三つの幸せがあります。赤ちゃんの時には、泣けば、お母さんがお乳をくれたり、おしめを替えたりしてくれました。それは、父母の愛に守られた「してもらう幸せ」です。社会人になっても、仕事をくれたり、何かプレゼントをもらえば嬉しくなります。年をとって子供たちに面倒を見てもらい、何不自由なく暮らせるのは幸せなことです。他人から何かをしてもらうのは、いくつになっても嬉しいものです。当たり前のように思っているが、「してもらう幸せ」のなんと多いことでしょう。大きくなるにつれて、自分でいろんなことができるようになると嬉しくなります。「できる幸せ」です。ハイハイができ、やがて歩けるようになる。一人で服が着られたり、ご飯が食べられたり、トイレに行ったり、風呂に入ったりすることができるようになる。遊びやスポーツができ、絵や字が書けるようになる。達成感は人間を成長させ、生きている幸せを感じさせてくれます。さらに、大人になっても、欲しい物が買える、贅沢ができる、綺麗な家に住んで美味しいものが食べられる、仕事がうまくできる、ゴルフがうまくなるなど、「できる幸せ」をいっぱい味わっています。
2010.03.17
コメント(0)
-
昨日は春一番が吹きました
昨日は20度近い暖かさになり、近畿地方にも春一番が吹きました。春一番は、立春から春分までの間に、その年に初めて吹く南寄り(東南東から西南西)の強い風です。おおむね、日本海を進む低気圧に向かって、南側の高気圧から10分間平均で風速8m/s以上の風が吹き込み、前日に比べて気温が上昇することで発生するようです。春一番は必ずしも毎年発生する訳ではなく、気象台の認定基準にあてはまらず、「春一番の観測なし」とされる年もあるそうです。気象庁は「春一番」の語源について、石川県能登地方や三重県志摩地方以西で昔から用いられたという例を挙げ、諸説があるとしつつ、安政6年(1859年)2月13日、長崎県壱岐郡郷ノ浦町(現・壱岐市)の漁師が出漁中、おりからの強風によって船が転覆し、53人の死者を出して以降、漁師らがこの強い南風を「春一」または「春一番」と呼ぶようになったと紹介しています。私の好きな桜ももうすぐですね。この春は第2期5年計画の最後の年 いかがなりますや?願はくは 花のしたにて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃 西行願ひおきし 花のしたにて をはりけり 蓮の上も たがはざるらん 俊成◆100名山NO8幌尻岳
2010.03.16
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
若い2人が「私を幸せにしてくれる」「君を一生幸せにするから」と言いあうが、そんなことはありえません。幸せは外に求めるもの(形ある物)ではなく、自分の心の中に求めるものだからです。幸せな人生とか不幸な人生という定型はなく、その瞬間、瞬間に自分の心が感じていくものだと思います。例えば、恋人と一緒にいるときは心もウキウキとして幸せだと感じるが、喧嘩して恋人が帰ってしまうと、気持ちは沈んで不幸な気分になってきます。だから、ずっと幸せな人生だったという人もいなければ、ずっと不幸な人生だったという人もいないはずです。それは境遇にしても同じです。薬害エイズを日本で始めて公表した川田龍平さんは「投げやりになった時期もあったけれど、自分の今の状態は不幸だけれども幸せだ。薬害で自分は命を脅かされている。この状態は不幸としか言いようがない。しかし命あるかぎり胸を張って生きていきたいと思い、二度とこういう問題の起きない社会にしたいと決心して一歩を踏み出したら、前には考えられなかったような多くの人たちと深い結びつきを持てるようになった。これは幸せ以外の何物でもない。今の自分は、不幸だけれども幸せという不思議な気持ちだ」と言いました。
2010.03.16
コメント(0)
-

今日はお松明です
何とか雨にもならずにもっています。午前中にお松明が立てられ、屋台が準備に追われています。河津桜も綺麗に咲いています。20:30頃に点火されますので関西の方は今からでもお出かけ下さい。ところで、「釈迦の智慧」 若い人にも読んでいただいているようで嬉しく思います。人間の心理は3千年の昔から変わっていません。その変わらぬものが真理だと思います。まだまだ1年ばかり続きますので宜しく。
2010.03.15
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
健康だけが幸せなのではありません。不治の病にかかったとき、私たちはそれだけで不幸と思い、絶望してしまいがちです。だが、どんな状態であっても、心の持ち方次第で幸せになれます。なってしまったことやできないことを不幸に思うのではなく、今のままで幸せに生きることを考えることが大切です。それが、お釈迦様の本当の教えでもあると思います。肺がんで12歳の子供を亡くしたお母さんは、「心残りはもちろんありますが、仕方がありません。あの子と12年間も一緒に暮らせたのを、何よりの幸せだと思うようにしました」と語るように、どんな場合でも、それが自分たちにとってどういう意味があるのかを考えて、自分なりに納得する答を見いだすことが大切です。日々の生活には、面白くないこと、納得できないこと、つらいこと、悲しいこと、理不尽なことがたくさんあります。しかし、それに意味付けをしていって、自分の人生の一番根本のところで満足が得られれば、きっと幸せに生きていけると思います。幸福を見出し、味わう能力こそが人類をここまで発展させた重要な要素です。生きるための前向きな姿勢が、社会性や冒険心、創造性を高め、免疫力も強めてきました。
2010.03.15
コメント(0)
-
今日は快晴も
昨日はJR嵯峨野線が複線化し、途中での待避もなくなり少し便利になりそうです。明日は雨模様の天気予想だが、清涼寺でお松明と狂言があります。嵯峨野線に乗っていらっしゃいませんか?ところで、チョット真面目な話。【国債+借入金】は11年3月末予想で973兆円(政府短期借入などを含むと現在で1100兆円) 約37兆円の税収だが、歳出を10兆円抑えても返済に100年掛かる。それなのに、新年度予算の歳出は92兆円で、益々借金を積みますことになる。国民は要求するだけ、政府は人気取りのために後先を考えずに「ばらまき」をするだけ、官吏は税金を食い荒らし・・・。その先に来るのは、夕張市ではないが日本国の破産です。(収入の2.5倍も使えば破産は当たり前)高福祉を享受する我々世代と、借金返済のためだけに働かなければならない孫・子世代。我々が使ってしまったお金を、孫・子は馬車馬のように働いて返すしかない。財政問題の深刻さに、国民も政治家も官僚も気づかなければならないときです。◆日本100名山 NO7十勝岳
2010.03.14
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
自分自身の良かったときや、他人の良い状況と比べないことも大切です。戦争の後遺症で両足を切断し、右肩も動かない僧侶は「良かった時や他人と比べるから苦しくなる。今ある状態をそのまま受け入れれば苦はなくなり、なんのてらいもなくなり、素敵な笑顔でいられるようになる」と言われました。私たちは長生きする、五体満足である、財貨が沢山ある、高い地位に就くといった良い状態だけが幸せだと考えて、それだけを求めすぎて不幸な気持ちに陥りがちです。でも、不満足な状態と不幸とは同じではありません。現状を素直に受け入れ、全身全霊をかけて目の前のことに前向きに取り組んだとき、自ずとこだわる心は消え、生きていることの本当の喜びを知ることができるはずです。人生を明るく楽しく生きていくには、どんなにひどい状況の中でも、何かしら良いこと楽しいことを見つけ出し、希望を見いだしていくポジティブな思考が大切だと思います。乙武さんも「五体不満足は不便ではあるが不幸ではない」というように、どんな状況に置かれても、自分の心と折り合いをつけて、「いま」という状況の中で自分なりの満足を見つけていくことは可能です。
2010.03.14
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
生きているうちには、この世は一切皆苦だから悪いことも起きます。そういう時にこそ、身近な中に「楽しいもの、嬉しいこと」を見つけ、それを繋いでいくことで、穏やかな心を保てるように心がけることが大切です。一つの幸福感は短くても、いろんな幸せ感を繋いでいくことができれば幸福感を継続することができます。「幸せな一日」とは、心穏やかな時間の中に、ほんの少し心楽しめる時間がいくつかあり、その他にもちょっぴり幸せを感じられることがいろいろある、という感じなのではないでしょうか?「幸せな人生」とは、そんなささやかな幸せを感じる日々を積み重ねつつ、時々中ぐらいの幸せを感じ、たまに大きな幸せを感じられる可能性のある人生といえるのではないでしょうか?心が穏やかだと、他の幸せも感じやすく、幸せになれる行動もしやすいと思います。つまり、「穏やかな心」を基本として、その合間にいろんな幸せを感じられるようになれたら一番いいような気がします。ですから、第一に「穏やかな心」を心がけ(貪欲な心を制御する)、その中で幸せに暮らす努力を続けていけたらいいのではないでしょうか。
2010.03.13
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
「使っても減らぬ金百両」 人間は貪欲なもので、お金お金と無理して貯めて、貯まった途端に息が切れ。地獄か極楽か、貯めたお金を道ずれにできますか。 「死んでも命があるように」 誰しも永遠の命を望むようだが、生まれたら死ぬのが道理。「此の世は所詮四苦八苦。カッポレ、カッポレ。死んで花実の咲くものか」とこの世をおもしろ・おかしく生きるに限ります。 沢山のお金を儲ける、豪邸に住む、高い地位に就く、健康である、確かに表面的には幸せです。だが、そんな人が本当に幸せな生活をしているかというと、必ずしもそうではありません。裏では、ドロドロした人間関係に悩んだり、醜い闘争に明け暮れて暗い気持ちになったり、もっともっとと求めて欲求不満の人も多いはずです。私たち人間は、よい状態でなくても、たとえ逆境にあっても、それでも幸せを得られるということをしっかりと知っておきたいものです。「少女ポリアンナ」のように、どんなにひどい状況の中でも、何かしら良いこと楽しいことを見つけ出し、希望を見いだしていくポジティブな思考が大切です。それは、別の角度から言えば、自分の心と折り合いをつけることです。
2010.03.12
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
上記の歌のように良い状態だけを幸せだと考えて良い状態を求めすぎ、それが得られないといって不幸な気持ちになっている人が多いような気がします。「弥生三月花の頃」 暑からず寒からず、心地良い季節が弥生の頃、花咲き匂う頃ばかりではなく、この世には雨や雪の日もあり、嵐や台風も来ます。心浮き浮きする好きな季節だけを選ぶ訳にはいきません。「おまえ十九で、わしゃ二十歳」 「娘十八、番茶もでばな」ではないが、若くて一番いい頃といっても、若さを持続させることは出来ないのがこの世の定め。美しく老いる事が如何に避け難いものか、しみじみと味わうこの頃です。「死なぬ子三人、親孝行」 親に先立つ逆縁ほど哀しいものはありません。何も気にせずスクスクと育つのが一番の親孝行です。だが、この頃では引きこもりや自殺など心配の種の尽きることがなく、何かと一喜一憂させられます。期待し過ぎて、子供を駄目にすることもよくあります。「親孝行したい時には、親はなし」とは子の常です。「親孝行し尽くしたから、親も満足だろう」と言い切れる子が何人いることか。「親孝行したくないのに、親がおり」が普通ではないでしょうか。とかく此の世は儘ならないものです。
2010.03.11
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
人間には、財の蔵、名利の蔵、心の蔵の三つがあるといいます。財や名利の蔵に蓄えることばかりを考えていると心の平安は難しくなります。目に見えるものを過度に追いかけることを止め、ほどほどの現在をあるがままに受け入れ、穏やかな心でいられるようになれば、身のまわりの幸せに気づくことも、生活の中で多くのことを楽しむことも、心静かなワクワク感をも得ることができるようになるだけでなく、他の人の幸せをも応援したくなるはずです。どんなときでも心の平安を心掛けてみると、驚くほどいろいろなストレスも消えていくはずです。心の平安を基準に生きると、どんなことがあっても落ち着いていられるようになります。善いことがあっても大げさに喜んだり見せびらかすこともせず、静かに「よかった」と感謝できるはずです。逆に、よくないと思うことが起きても「命まで取られたわけではない、大丈夫だよ。この状態が何時までも続くわけでもない」と静かに対処できるようになるはずです。どのような状況に直面しても、この世は諸行無常、いかに快晴であるとも夜の来ない日もなければ、いかに暗黒の闇であろうとも朝の来ない日もないと、感情が揺れなくなります。
2010.03.10
コメント(0)
-
愛宕の山は雪化粧
昨日は女性3人に囲まれて楽しい食事会だったが、帰りに冷えてきたなと思ったら、今朝は愛宕山が雪化粧です。まさに「早春賦」の世界ですね。春は名のみの 風の寒さや 谷の鶯(うぐいす) 歌は思えど 時にあらずと 声も立てず時にあらずと 声も立てず氷解け去り 葦(あし)は角(つの)ぐむさては時ぞと 思うあやにく今日もきのうも 雪の空 今日もきのうも 雪の空 春と聞かねば 知らでありしを 聞けば急かるる(せかるる)胸の思(おもい)をいかにせよとの この頃か いかにせよとの この頃http://classic-midi.com/midi_player/uta/uta_sosyun.htm◆百名山NO6 トムラウシ
2010.03.09
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
恒常ドル価格で測ると、1950年以降に世界の人々が消費した財とサービスは、それ以前のすべての世代が消費したものの総計に匹敵し、40年以降のアメリカ人だけで、それまでに全世界で全人類が使ったのと同じだけの鉱物資源を使ったことになるそうです。だが、シカゴ大学が1950年代から定期的に行っている調査によると、「大変幸福である」と回答する人の割合は、ずっと人口の3分の1前後で変化していないとのことです。結局、本当の幸せとは、何かを手に入れることではなく、現在の些細なことに満足し、未来を夢みて歩き続けるプロセスに感じるものだと思います。その証拠に、00年世界価値観調査では、日本「非常に幸せ」28%(5年前より△5%)「やや幸せ」59%に対して、メキシコ・フィリピン・ナイジェリア・タンザニア・ベネズエラ・プエルトリコなどでは毎年8~9割が「幸せ」と答えています。その特徴は、幸せ感が「家族が揃っていて元気で御飯が食べられかどうか」という曙覧的な身近なところにあることです。その意味では、物の満ちあふれた今の日本は夢が描きにくく、幸せ感が薄いのもうなずけます。
2010.03.09
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
アメリカの社会心理学者マイケル・アージルは、「幸福度に本当に差をつけるのは、交際、仕事、余暇のあり方である。これらの分野で満足できる状態を確立するうえで、絶対的な意味でも相対的な意味でも、物質的豊かさはあまり関係ない」と言っています。マザー・テレサが来日したときも、「日本では飢えた人はあまり見かけないけれども、街を歩き人の話に耳を傾けてみると、インドの道端に横たわる人以上にたくさんの人が精神的に苦しんでいると感じました。インドではパンを与えれば微笑みを引き出すことができるが、日本では苦しんでいる人から微笑みを引き出すのは易しいことではありません。日本の皆さんの使命は、心の悩みをともに分かち合い、微笑みを取り戻すことではないでしょうか」と言いました。後進国へ旅し、「まあ、可哀想に。見てよ、あの子裸足よ」「気の毒にね、あんなにやせ細って」と言いがちだが、ルカ伝には「幸いなるかな、貧しき者よ」とあるように、貧しいから、裸足だから幸せでないというのは日本人の奢りであり高慢でしかないと思います。ストレス社会の私たちに大切なことは、「心の欠乏感はものでは埋まらない」ということに早く気づくことです。
2010.03.08
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
もの凄い財産があるのだが、好きなこともなく、自分を孤独で不幸の塊のように思いこんでいた未亡人が、ある心理療法の医者を訪ねました。彼女には、たった一つアフリカスミレを育てる趣味がありました。そこで医者は、「アフリカスミレをできるだけたくさん育てて、日曜日に教会に持っていき、誕生日がきた人に一鉢ずつ贈りなさい」とアドバイスしました。未亡人がそれを実行すると、思いがけない喜びの葉書やお礼の手紙が来るようになりました。今までは誰も近づいてこなかったのに、自分の周りに段々と笑顔の人が近づいてきます。そして、未亡人はとても幸せな気分になったということです。物質的なものや相対的なものは、一時の幸せ感をもたらしたとしても長続きしません。麻薬と同じで、次から次へと刺激を強くしていかなければ効かなくなります。そんな「もっと欲しい」という欲望につけ込んで、日本では年間6万件もの詐欺が起き、なけなしの財産を失う人が後を絶ちません。トルストイは「自分の心中に幸福を求めなさい。幸せの泉は外ではなく内にある」と『戦争と平和』の中で書いているが、今、私たちに大切なことは、「心の欠乏感はものでは埋まらない」ということに気づくことだと思います。
2010.03.07
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
ある看護婦さんと話していたら、「死に際がすんなりしているのは貧乏な人です。生きていてもしょうがないからでしょうか? フーテンの寅さんのような人は、あっさりと死んでしまいます。死に際がバタバタして見苦しいのは、決まって財産を持っている人です。財産があるとか名誉があるとかに関係なく、不思議なことに般若心経をやっている人は、すんなりと死んでいきますね」と言います。死んでしまえば、財産が有ろうが無かろうがゼロになってしまいます。それなのに、残していく財産にまで未練が残ってバタバタするのでしょうか?人間とは浅ましいもので、何かを得れば得たで、それにこだわり、それを失うことが恐くなります。そこでジタバタします。老子は「身(健康)と貨(財貨)といずれがまさる。得ると亡うといずれかくるしき。甚だ愛すれば必ず大いに費やし、多く蔵すれば必ず厚く亡う。足るを知れば辱められず、止まるを知ればあやうからず、以て長久なるべし」と言ったが、名誉にも財貨にもこだわらないことが、心安らかに生き、死んでいく秘訣かも知れません。(その点、私は願望通りすんなりと逝けそうです)
2010.03.06
コメント(0)
-
悲しい日本人
いま起業者セミナーの原稿を整理していて、志や倫理観の欠如が公害隠しやリコール隠し、詐欺まがいの商法に繋がるので、強い志を持つことの大切さを説いています。だが、現実はお寒い限り。あのトヨタまでが、リコール隠しのパッシングで右往左往しています。今度はカドミウム被害の調査に自治体が応じないという。お客様あっての企業、住民有っての自治体なのに、みな自分達の目先の保身しか考えない。一時は逃れたとしても、対応が遅れれば遅れるほど結果が悪くなるのに悲しいことです。目先しか考えないのが日本人の特性だが、何とかならないものですかね?愚痴や政治の話は書かないつもりでしたが、つい愚痴が出てしまいます。歳ですね。ところで、春がもうそこまで来ましたね。ここ嵯峨野では、清涼寺のお松明が近づいてくると「春が来るぞ」と感じます。15日は、清涼寺で京都三大火祭りの一つであるお松明が20時過ぎから有ります。同じ日の13:30;15時~;18時からは、京都三大狂言の一つ嵯峨狂言も行われます。月曜日ですが、お暇な方はお出かけ下さい。http://www.thekyoto.net/movie/070316_03/◆百名山NO5大雪山
2010.03.05
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
もう一つは、手に入れたものを失うかも知れないという恐怖です。『正法眼蔵随聞記』は「貧しく欲張らなければ、怒りと辱めの難を逃れて常に安らかで心配のない生活ができる。証拠は目の前に明らかで、仏教の教えを待つまでもない。それなのに道に暗い人は、財宝を蓄えて常に怒りを抱いている」と諭します。財産を沢山持っていると、人がその財産を奪おうとし、すると取られてなるものかとたちまち怒りが生じて、口争いから訴訟になったり、殴り合いになったりして、辱めを受けることにもなります。悪魔が「子ある者は子によりて喜び、牛ある者は牛によりて喜ぶ。まことに頼りは人の喜びなり。頼りなき者は喜ぶことなければなり」と歌うと、お釈迦様が「子ある者は子によりて愁い 牛ある者は牛によりて愁う。まことに頼りは人の愁いなり。頼りなき者は愁うことなければなり」と応えます。私たちは、愛する子供や、財貨や地位、名誉など、何かを得ると嬉しくなります。しかし、得れば得たで、今度はそれを失うまいという苦が生じ、失えば愁いが生じます。ですから、物質的なものや相対的なものを求めるかぎり、決してあなたを平安で心豊かな暮らしには導いてくれません。
2010.03.05
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
日本金地金流通協会が大分前に調査したところ、18歳以上の女性で宝石を持っている人が92%もいて、平均7.6個も持っていました。そして、宝石を6個以上持っている人と、5個以下しか持っていない人に分けて、「今後もっと宝石を購入したいか否か」を聞いたところ、6個以上持っている人の方が購入意向が強かった。また、過去1年間に宝石を購入した女性の方が、購入しなかった女性よりも強い購入意欲を持っていることが分かった。つまり、持てば持つほど欲しくなり、買えば買うほど欲しくなると言う訳です。インドの仏典には、「無財餓鬼・少財餓鬼・多財餓鬼」の三種があると書いたが、欲望というものは財貨の有無に関係なく起きるものです。特に、欲望を充足すればするほど、ますます飢餓感が嵩じてくる傾向があります。宝石を買えば、それにあう高価なドレスや靴、バックなどを様々なものが欲しくなります。同じものばかり身につけられないので、さらに別の高価な物が欲しくなります。一つの欲望は、より以上の欲望を生み出します。人生の苦は、多くは人間なら誰しもが持っている欲望を追求し愛着する心から起きます。少欲こそが、心豊かに暮らすコツのようです。
2010.03.04
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
一つは、もっと欲しいという欲求です。何かを手に入れたとしても、私たちはそれで満足して止まるわけではなく、「もっと、もっと」と膨らんでいきます。ある時、海辺のあばら家に住む漁師が魔法の魚を釣り上げました。その魚は、自分を海に帰してくれるなら、その見返りに、漁師のつましい願いに応えて、丸太小屋と十分な食べ物を与えてあげると約束します。漁師は魚を放し、願いはかなえられました。一週間後、漁師は最早それでは満足できなくなり、また海に行って魔法の魚を捕まえて、より大きな住まいを願い、手に入れました。そんなことが何度も繰り返され、ついに王宮を要求するまでになりました。そのあまりの厚かましさに、魔法の魚は彼を元の海辺のあばら家に戻してしまいました・・・、というポーランドの民話があります。お釈迦様も「ヒマラヤを黄金と化すも、またそれを二倍にしても、それだけでは一人の人を満足させることはできない」と言ったように、際限なく欲望を膨らませていくのが人間の変わらぬ性です。本来、欲望というのは、苦しむためのものではなく、楽しむためのものであるはずなのに、際限なく膨らました欲望が満たされないと言って苦しんでいるのが私たち人間です。
2010.03.03
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
トルストイも「物乞いであろうと百万長者であろうと、自分の境遇に満足している人間がいるだろうか。千人に一人もいないだろう。今日、外套とオーバーシューズを買えば、明日は懐中時計と鎖を買わずにはいられない。明後日は、ソファーとブロンズ製のランプのあるアパートに入らなくてはならない。その次は絨毯とビロードのガウン、そして屋敷、馬と馬車、絵画と装飾品だ。今日の贅沢品は明日の必需品となり、前世代の贅沢品は次の世代には必需品となる」と言っているが、まさにいまだにその通りですね。この欲望の拡大をどこかで止めない限り、どんなに外見的には豊かに見える生活を送っていても、心の貧困から抜け出すことはできず、私たちはいつまでも餓鬼のままです。私たちは、誰もが幸せな生活を望んでいるが、幸せとは何でしょうか?私たちの心は常に目に見える外界の対象物である財貨や地位、権力などを追い求めて止まず、魅力的に映る物を手に入れるために脇目もふらずに邁進しがちです。そして、運良くそれを手に入れることができると、その当座は幸せ感を感じます。だが、それを手に入れた途端に、すでに二つの不幸が芽生えていることには誰もなかなか気がつきません。
2010.03.02
コメント(0)
-
第2章 幸せに生きるための智慧 欲との付き合い方と幸せ感
あなたは餓鬼(ガキ 欲望を御せない子供も同じです)をご存じですか?仏教では、悪行の報いとして餓鬼道に落ちた亡者のことを指します。やせ細って、喉が針の穴のように細くて飲食することができず、常に飢餓に苦しんでいる絵姿を寺などで見た方もみえると思います。インドの仏典には、「無財餓鬼、少財餓鬼、多財餓鬼」の三つがあると書かれています。人間は、財貨が無くても有っても餓鬼になりうるのです。つまり、餓鬼とは財貨の多寡にかかわらず、「現在の状況に満足しない姿」を言います。現在の私たちは物質的には豊かになって、昔の人から見れば極楽のような、何の不自由もない生活をしています。しかし、次から次へと「もっともっと」と欲望が膨らんできて、なかなか現状に満足することができません。ですから、いつまでたっても、安らかで心豊かな暮らしとは程遠い生活をしています。そんな私たちの姿は、まさに餓鬼そのものです。消費は人間に満足を与えないというのは、古くはキリストの生まれる前のローマの哲学者ルクレティウス以来、言われ続けていることです。「人間の欲望には限りがない」と、2千年以上も前にアリストテレスも言っています。
2010.03.01
コメント(0)
全47件 (47件中 1-47件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 2025 Xmas★ウェッジウッド アドベン…
- (2025-11-19 11:35:32)
-
-
-
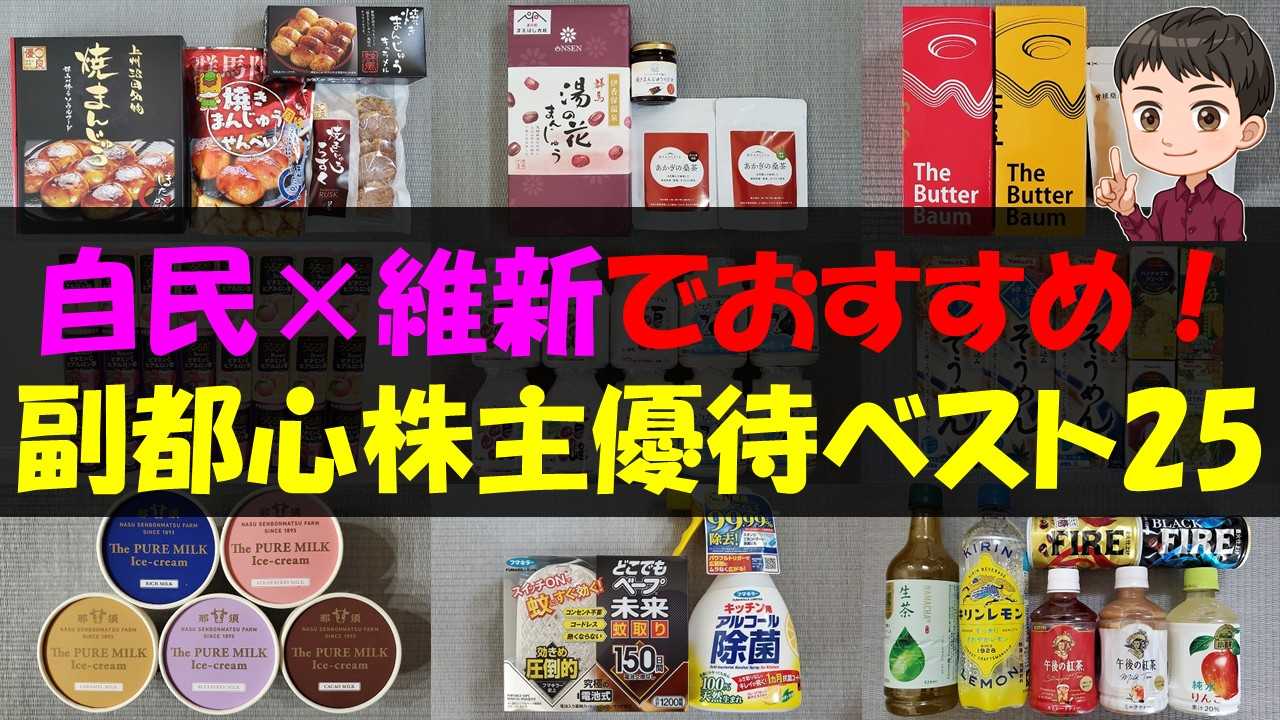
- 株主優待コレクション
- 【大阪】自民×維新でおすすめ!副都…
- (2025-11-19 18:00:06)
-