2010年11月の記事
全51件 (51件中 1-50件目)
-
番外編 釈迦の教えと経営
厳しい時代なって近江商法が見直されています。琵琶湖のアユは外へ出て大きくなるという言葉に象徴されるように、近江商人は行商を通じて商売の勘とコツを身につけ、独自のネットワークを構築し、他国で成功する例が多かった。その基本は、「三方良し」「定宿」「始末して気張る」の三つです。「三方良し」=「売り手に良し、「買い手に良し、世間に良し」と、ともすれば自分の利益だけを考えがちだが、商売地や第三者の利益まで考えて商売をすることを基本とした。商売は仏の心からという考えが根本にあり、暴利を戒め、品質と価格管理を徹底した。それが結果的に、一回の利益は薄くとも信用となり、永続的な取引関係を築いた。「定宿」=近江商人たちはお互いが競争相手ではあったが、郷党意識も強く、他国へ出て泊まるときには定宿に泊まり、互いにそれぞれの土地の商品情報などを交換した。今で言えば、情報ネットワークの活用です。「始末して気張る」=一回の取引で多くの利益を得るのではなく、取引の永続性を追求するために、絶えず倹約と勤勉に努め、良い商品をより安く提供できるように心がける。
2010.11.30
コメント(0)
-
蕪の美味しい季節になりました
散歩の途中で農家直売の蕪を見つけ、買って帰りました。早速、豚肉と蕪の甘辛いためを作ってみました。蕪は柔らかく、甘みもあって冬の味覚として最高です。葉っぱも炒めてみました。蕪の葉にはカルシウムがほうれん草の5倍も含まれているそうです。早速、お酒のアテにして楽しんでいます。今週はもう忘年会に突入で、水・金・土と三つもあります。まあ、飲み食いの友があるということはありがたいことです。来月には、私の70歳の誕生日(討ち入りの日です)に会わせて、京大のポスドクでアメリカで研究生活を送っている女性(私の5女扱い)がビザの書き換えで返ってくるので会いたいとメールがあり、これも楽しみです。また、彼女の先輩でもある甥っ子たちとも食事会が予定されていて師も走るという季節がやってきます。◆写真は真如堂
2010.11.29
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
全国270店舗で自然志向の化粧品を販売している「ハウス オブ ローゼ」(昭和53年設立)は年商120億(現在は150億円)で、6百人近い従業員(99%は23歳から30歳の女性)がいるが、一店一店はちっぽけで、店長と販売スタッフの2人か、せいぜいパート含めて3人しかいません。川原要暢社長は、「会社を始めた20年前は若い女性ばかりで、回りにはいつも笑いがあった。ところが3年ほど前から、うちの女性社員たちが笑わなくなっていることに気づいた。客に接するときにも、自然な笑顔がこぼれる従業員も少なくなった。よく注意してみると、百貨店の店員もガソリンスタンドの従業員も、皆、ブスッとした顔をしている。ウチだけじゃなく、若い人が笑わない時代になっているんです。一店当たりにすれば零細販売業で、販売スタッフの無愛想で一人、二人とお客さまの足が遠のいただけでもすごい痛手となる。現に、ある店の月間売り上げがガクンと半減したので行ってみると、最近配属されたスタッフが飛びっきり無愛想である。急いで笑顔のいいスタッフと入れ替えたら、たちまち売上高が平常の4倍になった」と言う。つまり、笑顔一つで±8倍もの差になります。
2010.11.29
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
戦前には武士道と儒教的なモラルがあったが、戦後は精神的なものがすっかりなくなってしまい、ただ儲ければいいということになってしまった。だが、経済観念だけで突っ走ると暴走してしまうので、宗教的というか精神的なブレーキが必要です。魂のないシステムは成立せず、大阪商人魂に注目しています。そもそも大阪の基盤は、本願寺の寺内町です。道修町も船場も寺内町にあり、御堂の鐘の音が聞こえるところに本店を持ちたいという近江の門徒商人たちが集まり、薬品問屋や繊維問屋が発展してできた街です。だから、御堂筋は信仰に支えられた街だった。大阪商人の気質を表す例として、よく「儲かりまっか?」「まあ、ぼちぼちでんな」などという挨拶が交わされるが、昔は「儲かりまっか?」「お陰さんで」だった。「お陰さんで」と言うのは、神仏の加護によって何とか生きていけることを感じて、そのお陰を感謝する思想です。大阪商人は実は根のところでは非常に精神的、宗教的な心根を持った人たちであり、大阪ビジネスの背後には儒教的な倫理のほかに「お陰」という宗教的なものもあった。お陰思想の衰退と共に、大阪経済の地盤沈下も激しい。
2010.11.28
コメント(0)
-
洛中も紅葉真っ盛り
昨日は、嵯峨野に来るまで住まっていた近くの紅葉を見ながら6時間ばかり散策しました。まず真如堂に出かけましたが、なかなかのものでした。ここは、私が京都に来た頃は人もいない穴場でしたが、近年は人で一杯です。吉田山まで来るとさすがに人は少なくなるが、大文字山を背景にした紅葉も良いものです。吉田山から吉田神社を経て法然院へ。さすがに人で一杯です。茅葺き屋根の門から見る紅葉は好きな一つです。奥の方の紅葉が真っ盛りです。池に映った紅葉も良いですよ。安楽寺・霊観寺もいいですね。哲学の道も綺麗に紅葉しています。人混みを避けたくて、若王子神社から山道を経て南禅寺に出、疎水沿いにインクラインに抜け、日向神社に出る。さすがにここまで来る人は数人だが、彼岸桜が紅葉をバックに咲いていてなかなか良いですよ。昔は、ここから山越えして山科まで出かけたものです。最後に永観堂に寄ったら、人でごった返していたが流石に綺麗な紅葉でした。ここも昔は無料で通り抜けできたのだが、有料になって囲ってしまい、世知辛い世を感じます。平安神宮を経て、夜の会に出るために鴨川沿いに5条まで出て温泉に入り足の疲れを癒す。秋を満喫した1日でした。この週末に出かける人は参考にして下さい。なお、高雄茶屋の主人にあったら、三尾はもうこの週末が最後の名残だそうです。◆永観堂の紅葉
2010.11.27
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
(昨日の続きです)福島で薄皮饅頭を百五十年近く代々作っている柏屋の本間善兵衛さんは、「先代からよく、『お客様の喜びだけを見ていろ』と言われた。お客さんの喜びを見ないで、同業他社ばかり見ていたら、結局は他のコピー商品になってしまうんですね。真似をしない、ということを頑なに守ってきました」と言う。でも、それをやり続けるとなると難しいものです。「こんなことをやっていて儲かるのだろうか」と、疑問に思うときもあるかもしれません。そんなときは、米、コネティカット州にある食品専門スーパー「ステュー・レオナード」の社是を復唱してみると良いでしょう。ルール1 顧客は常に正しいルール2 もし顧客が間違っていると思えるときはルール1を再読せよ店内にはお客様の声を聞くための投書箱がいたる所に置いてあり、クレームを受け付ける電話やファクスが備えられ、どんなことにも24時間以内に対応するようにしています。例えば、夕食用にチキンを買ってきたが焼くのをしくじってしまった奥さんが、「お宅で買ったチキン古かったわよ」と理不尽な苦情を言ってきたとしても、店の側では黙って話を聞き、鄭重にお詫びをしたうえで、新しいチキンとすぐに引き換えてくれます。このような場合、調べればお客様が明らかに嘘をついていることなどすぐに分かるが、どんな理由があるにせよ「お客の言うことは常に正しい」というルールを適用した結果です。お客様と議論して勝っても、客を失えば本も子もありません。ただでチキンを渡す経費など、それによって店が得る利益を長い目で見れば安いものです。徹底したサービスこそが、結局は長続きする顧客をつかむ早道といえます。現に、店は2店しかないのに、他の食品スーパー15店分もの売り上げを誇っています。徹底的にお客様第一を実践すれば、お客様は応えて下さいます。
2010.11.27
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
お客様第一とは慈悲の心の実践であり、自店の提供する商品やサービスによって、「人を楽しませる・楽にしてあげる・苦を和らげたり取り除いてあげる」ことで、お客様を気持ちよくさせることです。その結果、お客様が喜ばれるのを見て自分の喜びとする(喜捨の実践)ことです。そうすれば、自然とお客様からは「なくなってもらっては困る」と言われる存在になるはずです。「大切なことは、お客様に喜んで頂くためにできることは何かを常に自分に問い続けること。会社からではなく、お客様から給与をもらっているんだという感覚でいなければ」と高級車を40年間で6千台売った増田叔久さんは言う。毎日9百人にヤクルトを売るヤクルトレディーの中山よし子さんは、「一番心がけていることは、お客様の名前を呼んであげることですね。『○○さん』って。道端でもどんどん声をかけます。やっぱり、自分の名前を呼ばれると嬉しいんですよ。ある会社の新人社員で、いかにも大人しそうな男の子がいたんです。まだお給料も少なそうだろうから、変に声をかけて買わせちゃったら可哀相と思って最初は声をかけなかった。あるとき、自動販売機でコーヒーを買っていたので、近くの女の子に名前を聞いて、『○○ちゃん、自動販売機なんかで買わないでこっちで買いなよ』と話しかけたら、とても嬉しそうにしましてね。それからは、毎日、私のところから買ってくれるようになったんですよ。いつも考えていることは、お客様が喜ぶことです」と笑顔で言う。お客様に喜んで来ていただくには、相手の気持ちを慮って、相手の喜ぶことを絶えず心がけることです。
2010.11.26
コメント(0)
-
嵯峨野は人で一杯
いま嵯峨野は紅葉が見頃です。この週末も十分にお楽しみ戴けると思います。昨日は多才な方々と秋の一時を過ごすことができ楽しい1日でした。そこで、フッとこんな話しを思い出しました。京都の名刹大徳寺大仙院の名物和尚、尾関宗園氏は、人間の器を植木鉢に例えられます。植木鉢には穴があります。穴がなければ水がたまって根腐れを起こしてしまうからです。人間の器にも、この穴が必要だというのです。たった一つの穴があることによって、器の中の生命は外の大自然と一体になって息づくことができるわけなのだ。石頭がなぜ嫌われるかといえば、外の風が入らずに、腐りはじめているからだ。外の風とは人の意見なり、人の喜びなり、人の悲しみなり己れ以外の人間の生きている姿そのものである。いわば、穴のない器というのは、たとえどんなに大きかろうとも「井の中の蛙」ということなのでしょう。器の大きさとは、その穴を通してどれだけ外の風や水を受け入れられるかということであり、どれだけの循環が行われているのかということなのかもしれません。昨日は穴のある方々ばかりで、それは楽しい一時でした。◆我が家の近く清涼寺の紅葉です
2010.11.25
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
そして、今まで、どうして銭をもうけようか、どうして自分の会社を大きくしようかと焦ってきたが、それは間違っていた。銭儲けなんぞは考えんでもいい。世の中の大勢を喜ばせさえすれば、金は自然に入ってくるのだ。これからは、自分の電器事業を通して、社会の大勢のみなさんに喜んでもらえる会社にならねばならぬ。それが自分の一生の事業だと気付かれたそうです。あくる朝会社に行って、数十人の社員を集めて、「今まで自分はどうして銭を儲けようか、どうしてこの会社を大きくしようかと焦っていたが、今日から考えを変えた。今日からは、どうしたら世の中のみなさんが喜んでくださるか、ということに全力をあげる会社にする。みなさんの欲しがるもの、必要なもの、便利なものを、なるべく安く提供すれば、社会のみなさんが喜んでくださる。社会のみなさんが喜べば、会社に金がはいるのは当たり前だ。銭もうけなどは考えないで、今日から社会に奉仕していくことをこの会社の目的とする。みんな賛成か」といったところ、みんなもこれに賛成した。これが、家内工業から松下電器へと発展する精神的な礎となったことは疑いの余地もありません。 真に成功した企業の根底には、このような慈悲の志が必ずあります。
2010.11.25
コメント(0)
-
飲み食いの友を大切に
昨日は、30代後半から70代後半の人まで入り交じって、3時から8時過ぎまで鮒寿司と鍋で宴会。飲み食いの友は、損得勘定や上下関係もなく楽しいものです。ところで、現在付き合っている人も、最大6代遡ればルーツに行き着くという。私が京都に来てから四半世紀、普段お付き合い願っている人たちで検証してみたら、まさにこの通りでした。それも、仕事がらみではなく、飲み屋や飲み会の友の連鎖です。これは、私が飲み助と言うこともあるが(362日は飲み屋に顔を出していた・3日間だけ断食)、飲み屋がらみでない人脈(仕事や交流会がらみだけのご縁)はルーツまで2代も遡れば終わりで、発展性がありません。(これは私の場合ですが、そんなものでは?)京都の地の人たちが行く店は、紹介、紹介の繋がりで、お店を通したご縁でお付き合い願っている人たちが殆どです。そんなご縁の繋がりだから、いろんな会に初めて顔を出しても、どなたか顔見知りの人がみえるのが常です。こうしてみると、京都では夜、何処でデビューするか(地元の人が行く気安い店)が大切なことが分かります。私のコンサル会社での最後の仕事先になった某社役員(元銀行支店長)に連れて行かれた店は、三姉妹がやっているささやかな店(10名も入れば満席)だったが、学園紛争時に京大総長をされ、文化勲章まで戴いた方も常連でした。旧都ホテルや大垣書店の社長、大学教授方もみえていました。(それまでの1年位は、誰の紹介もなしに飛び込みで開拓した店に行っていたが、そこから人脈が広がることはありませんでした。見知らぬ人とたまに話しが弾むことがあっても、そこで終わり。)当時、私は50歳前だったが、お店では私よりも年配の方々が殆どで、若いと言うことで可愛がられ、紹介で連れられていく店も増えました。そして、常連客の遊び会の幹事役も引き受けてきました。そんなお店で知り合った方々の連鎖のご縁で、いま私は楽しく過ごすことが出来ています。でも、私も70歳、もう今では無くなった店や先輩方も多く、時代の変遷を感じます。そう言えば、「快老力」にメールを転載した彼女も、もう百ケ日を迎えます。百カ日は正式には卒哭忌(そっこくき)といい、「哭=泣く」のを「卒=終わる」ためのおつとめという意味があるそうです。また、四十九日は天国に到着する日で、まずは天国での見習い期間開始であり、百カ日は正式に天国の住人になるという考え方もあるそうです。話はそれたが、若い方々も、リタイヤーした後も楽しく過ごすためには飲み食いの友を大切にすることです。利害関係でつながっている友は利用価値が無くなればそれでお終いだが、飲み食いの友は死ぬまで続く財産です。◆書斎の窓から嵐山の紅葉を望む(電線が目障りですが)
2010.11.24
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
道元は「己を忘れて他を利する。これ慈悲の極みなり」と言っているが、「なくなってもらっては困る」と生活者から言われる店になるには、仏教で言う「慈悲喜捨」=お客様第一の心をどこまで実践できるかに尽きると思います。慈とは、人を楽しませてあげたい、楽にしてあげたいと願う心です。悲とは、人の苦を和らげてあげたい、取り除いてあげたいと願う心です。まさに、商売は慈悲の実践によって成り立っています。そして、お客様が喜ぶ姿を見て、それを喜びとするのが商売人の最大の喜びであるはずです。松下幸之助は、事業を始めて15年ほど経った頃、ある新興宗教の本部に連れて行かれ、素晴らしい本殿が建ち、信徒の宿泊のための建物がずらっと並んでいるのを見てびっくりしたそうです。「大したものを建てたものだ、この新しい宗教がこんなものを建てたが、財源はどこにあったのか、どうして建てられたのだろう」と、そのことが頭を離れなかった。電車の中でも考え、家に帰っても考え抜いて結論が、「あれはなんでもない。その宗教の教えで社会の大勢の人を喜ばせたのだ。喜んだ人が大勢なら、わずかな金を持ち寄ってもあれができるのだ。大勢の人を喜ばせたということ、それだけが資本だ」だった。(明日に続)
2010.11.24
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
私なりに釈迦の教えを解釈し、人間には三つの本性があると思っています。一つは、自分ほど可愛い者はいないという自愛の心です。フランスの箴言作家ラ・ロシュフコーは、「世間の人が友情と呼称するものは、社交・欲望のかけ合い・駆け引き・親切の交換にすぎない。つまり、自愛がつねに何か得をしようとする一種の取引にすぎない」と言ったが、最愛の彼女や子供、他の誰よりも愛しく可愛いのは自分自身です。一つは、自分が先ず幸せになりたいという我欲の心です。隣に蔵が建つほど悔しいことはなく、隣が火事で燃えるほど(密かに心の奥で)嬉しいことはないというのが人間です。誰よりも先ず、自分が幸せになりたいのが私たち人間です。この愛欲の心を「渇愛」と言います。一つは、人との関係で、相手に善いことをすればこちらにも善いことを、相手が嫌がることをすればこちらにも嫌なことを返してくることです。山彦は、「あなた好きよ」と叫べば「あなた好きよ」と、「あなたなんか嫌いよ」と叫べば「あなたなんか嫌いよ」と返ってきます。人間関係も同じで、善いことも悪いことも、自分のなしたことが自分に跳ね返ってくるだけです。
2010.11.23
コメント(0)
-
嵯峨野は紅葉真っ盛り
雨の合間に嵯峨野を散策小倉山に登るが、低木が伸びて見晴らしが悪くなり天龍寺がよく見えなくなりました。絶景だったのですがね。嵐山の眺めは未だ良く今が盛りです。下りで雪駄の鼻緒が切れ、家まで紐でくくって足を引きずって返る。明日辺りは洛中も良いと思います。私は鮒寿司を賞味する会があるが、それまでに以前の住まいだった吉田山から法然院辺りを歩いてみようと思います。
2010.11.22
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
事業も、相手のことを第1に考えれば永遠に栄えます。アメリカの航空機メーカー、ボーイング社が日本で重役会議を開くことになり、京都の清水寺の座敷を借りたことがあります。その時、貫主の森清範師に、「今後50年、100年と会社を続けていくための参考にしたいので、清水寺が1200年の歴史を刻んできた極意はどこにあるのかを話してほしい」ということになりました。森貫主は、「清水寺の御本尊である観音様は、相手の気持ちになって物事を考えられる大我の仏さんです。自分ではなく、相手がどう思っているかということを説いて1200年になる。企業にしても、相手の豊かさや幸せをまず考えることができるなら1200年でも2000年でも続くのです」と話された。「儲けてやろう」とだけ考えていては自滅してしまう。「相手に喜んでもらう」、つまり慈悲の心(慈=相手を楽しませてあげたいと願う心、悲=相手の苦しみを和らげてあげたいと願う心)の実践こそが大切です。総ての欲を捨てることは難しいが、自分の心の中にある三毒(貪欲・怒り・愚痴)を認めて、その逆のことをすれば善いことが返ってきます。
2010.11.22
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
経営の世界では、お客様第一とか共存共栄と言うことが昔から言われるが、これは仏教で言う「忘己利他」と「自利利他」と同じです。最澄は「好事を他に与え、悪事を己れに向え。己れを忘れ他を利するは慈悲の極みなり」と言ったが、人間は自分が一番可愛いから、どうしても自分を第一に考え、自分が得をしよう、 楽をしようという気持ちが先に立ち、相手を気づかう気持ちは二の次三の次になります。商売でも同じで、お客様のことよりも、作り手や売り手の都合が先に立ち、ついついお客様のことを忘れがちです。お役所仕事は最たるものです。すると、お客様からそっぽを向かれ事業も成り立たなくなります。お釈迦様は「四摂事(ししょうじ)=布施・愛語・利行・同事」の四つの実践を説いたが、これはお客様第1の心に通じることです。しかし、これは私たち凡人にはなかなか出来ることではありません。せめて、自利利他のできる人になりたいものです。これは、「自らを生かし、他者を生かす」ということで、「自分のことはさておき、人のためになにかをしなさい」ではなく、自分を生かし他者も生かすことができる人になれと言うことです。
2010.11.21
コメント(0)
-
清滝は見頃
昨日は、快晴にさそわれて、三日間煮込んだおでんと酒を持ってハイキングに出かけました。私の隠れスポットである人通りもない川辺で、紅葉を焚いて独り酒を楽しむのは格別。極楽、極楽です。静かな独り旅を楽しんでいたが、清滝まで来るとさすがに人が多くなりました。清滝(化野の先のトンネルを越えたところ)は今が見頃で、私と同年代と思われる方々が、三々五々と三脚を担いで紅葉を撮って見えます。でも、皆さん写真を撮ることばかりに熱心で、紅葉をゆったりと楽しむ余裕もないように思えました。とらわれるということは余裕を無くします。ご用心、ご用心。リーダーに連れられて、ズラリとカメラを構えている集団もいます。確かに無難なスポットではあるが、私から見たら10メートルも離れないところにもっと良いスポットもあるのに、皆が同じ場所から一斉に写真を撮っているのは何か異常に感じられます。よく見れば、顔も同じに見えて輝きがありませんね。歳を取っても、群を外れるのが怖いのでしょうか?人生も写真も、自分らしさ、人と違った視点が大切なのにと、つい思ってしまいます。私など、獣道のような不確かな道でも見つけようものなら、「何処へ行くのだろう」とつい踏み込んでしまう輩には理解できない行動です。仕事や人生でも同じで、好奇心からつい横道に踏み込むことが多かったが、そのお陰で随分と新しい出会いや発見があり、変化に富んだ楽しい人生を歩んでくることができました。たった一度の短い人生なら、大過ない人生よりも、先の分からない波瀾万丈の人生の方が楽しいと思いませんか?歳をとったから無難に生きるのではなく、残り少ない人生だからこそ自分らしく奔放に生きたいものです。のたれ死にでもいいじゃないですか!
2010.11.20
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
トルストイが「今日、外套とオーバーシューズを買えば、明日は懐中時計と鎖を買わずにはいられない。明後日は、ソファーとブロンズ製のランプのあるアパートに入らなくてはならない。その次は絨毯とビロードのガウン、そして屋敷、馬と馬車、絵画と装飾品だ。今日の贅沢品は明日の必需品となり、前世代の贅沢品は次の世代には必需品となる」と喝破したように、人間は何かを手に入れたとしてもそれで満足することなく次々と欲望を膨らませていきます。ポーランドの民話です。海辺のあばら家に住む漁師が魔法の魚を釣り上げたところ、その魚は「自分を海に帰してくれるなら、その見返りに、漁師のつましい願いに応えて丸太小屋と十分な食べ物を与えてあげる」と約束します。漁師の願いは叶えられたが、やがて漁師はそれでは満足できなくなり、また海に行って魔法の魚を捕まえて、より大きな住まいを願い手に入れます。そんなことが何度も繰り返され、ついに王宮を要求するまでになりました。そのあまりの厚かましさに、魔法の魚は彼を元の海辺のあばら家に戻してしまいました・・・。ですから、次々と新しいモノを提示したり、機能をアップしていき、生活者のフラストレーションを高めることで購買意欲を刺激することが大切なのです。
2010.11.20
コメント(0)
-
今朝は冷え込み紅葉も見頃に
この週末は京都はどこも紅葉が綺麗になってきました。今日はお酒を携えてハイキングに出かけ、紅葉を焚いて一献を楽しもうと思います。嵯峨野も見頃になってきました。祇王寺の手前、壇林寺もいいですよ。化野からトンネル手前の500羅漢で皆さん折り返されると思うが、トンネルをくぐって清滝に出、バス駐車場の横の坂道を下ってみるのもお奨めです。◆写真は壇林寺
2010.11.19
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
お客様の「フカイヨ」を良く知り、生活者のどんな欲求に応える店かが明確になり、具体的な対応策が決まったら、後は欲求を刺激してフラストレーションを高めてやれば、それを解消しようとしてモノやサービスの購買に走ります。お客様のフラストレーションを高めるには、「こんなことで不便を感じていませんか。これを使えばこんなに便利ですよ」「こんな素適な生活ができますよ」などと夢や理想を提案したり、「他の人はこんなことをしていますよ」と他人との比較をさせたり、「こんな危険性がありますよ。でもこの商品を購入した人はこうなりましたよ」などと不安を煽っておいて解消策を示したりすれば良い訳です。人間は「不」に敏感なので、不安を煽るのが一番効果的です。例えば、「肥満の人ほど生活習慣病に罹る確率が高く、糖尿病は正常者の5倍、高血圧は3倍にもなり短命の傾向があります」と訴え、「1食これに代えただけで何キロダイエットできました」などと言われればつい手が出ます。さらに、欲求は満たされれば刺激がなくなるので、例えば携帯電話のように、最初は通話機能だけだったのが、メール、カメラ、電子マネー、ワンセグ、ネット検索などと次々と新機能を付加して欲求を刺激し続ける必要があります。
2010.11.19
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
大切なことは、狙い定めた自店のカテゴリーに対するお客様の「フカイヨ」を正しく知ることです。お客様の意識と会社(店)の意識にはギャップがあるのが普通で、対応はさらに遅れるので、お客様の意識と対応のギャップはさらに大きくなります。図のある商店街のアンケート結果を見れば分かるように、実は、この正しく知ると言うことほど難しいことはありません。お釈迦様も正聞(正しく聞く)を第1に挙げているが、人間は耳で聞き、目で見るのではなく、自分の心で見るので受け取り方にバイヤスがかかります。自分の経験・知識の範囲でしか理解できないし、自分の立場や欲目などが邪魔をして自分の見たいようにしか見えない(解釈を曲げる)ものです。真実は一つなのだが、物事をどちらから見るかで様相は180度違ってきます。例えば、あなたが車に乗っているときは歩いている人が横着でしょうがないと思うが、逆に自分が歩いている側になった途端に車の横暴さに怒りを現すことがあります。それは、どんな場合にも起こることです。物事がどのように見えるかは、心の反映にしかすぎません。つまり、「同じ世界を、それぞれが全く違うものとして見ている」、それが人間なのです。
2010.11.18
コメント(0)
-
教育費も大変だが就職するのも大変な時代
教育費は大変だ日本政策金融金庫が教育ローン利用者に聞きました年収階層 大卒までの経費 教育費/年収200~400万円未満 961.9万円 56.5%400~600万円未満 1041.3万円 37.7%600~800万円未満 1095.4万円 30.0%800万円以上 1228.5万円 27.2%◆教育費の捻出方法1.他の支出を削減 62.4% 削減項目 ・旅行やレジャー 61.3% ・外食費 50.8% ・内食費 50.0% ・衣服費 43.4% ・保護者小遣い 41.1%2.奨学金 53.3%3.子のアルバイト 40.3%4.預貯金取り崩し 27.2%5.残業やパート 19.6%それだけ大変な思いをして大学を卒業させても、就職が大変な時代になっています。この春4年生大学を卒業した学生で、進学も就職もしなかった人が16.1%もいたが、今年の大卒予定者の就職内定率が、調査を始めた96年以降で最低となった。文系57.4% 理系58.3%男子59.5% 女子55.3%関東61.0% 近畿60.5% 北海道東北55.6% 中国四国53% 中部51.9% 九州51.5%◆清水寺のライトアップも始まります(桜で言えば5分咲き程度とか)
2010.11.17
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
経営における唯一の秘訣は、「お客様にとって新鮮な価値を、絶えず提供し続ける」ことです。そして、購買を促すには、お客様の「フカイ」を極限まで高めれば、「直ぐにでも解消したい」という気持ちが起きるので、お客様の「欲しい」という煩悩を刺激すればいいわけです。では、お客様はどんなときに「直ぐにでも欲しい」となるのでしょうか?それは、貴方の会社の商品を使えば「こんな楽しいことがありますよ」「こんなに便利ですよ」「こんなに幸せな気分になりますよ」という購買後のイメージを膨らませてあげればいいのです。それには、お客様をよく知ることが大切です。そして、ただ売るためではなく、心から慈悲(お客様を楽しませてあげたい、お客様の苦を取り除いてあげたい徒願う心)の実践を心掛けることです。そして、「欲しい」と思ったときに、(必ず競合があるはずだから)「なぜ、当社から買うと善いのか」ということを納得させることです。つまり、「何故、この商品なのか」「何故、当社なのか」の二点を説得し、納得してもらうことです。
2010.11.17
コメント(0)
-
いつかどこかで
昨日はあまり天候も良くなく、書斎の窓から見える嵐山の紅葉を眺めながら、酒を片手に本の整理をしていました。ふと手に取ったエドウィンM・ラインゴールドTIME元東京支局長著「菊と棘」(95年刊)を覗いてみたら、冒頭に次のように書かれていた。日本人とはいったい何者なのか。土地とハイテク会社を買いあさり、次から次へとものを売りまくって市場を支配し、突然に世界から注目されるようになったこの人たちーー彼らは経済の救済者なのか、それとも金持ちの食人鬼なのか。教師なのか、それとも略奪者なのか。われわれは日本人の台頭を真剣に受け止め、彼らについて考えてみる必要があるのではないか。気がついてみると、欧米人はこんな問いかけを次々に繰り返しているのだが、答はなかなか返ってこない・・・フッと、これを今の中国に置き換えてもほぼ同じようなことが言えるのではと思った次第。◆清滝川の紅葉
2010.11.16
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
そのような煩悩を満たすために、様々な欲求が生まれます。人間は地球上で最高の本質的に厚かましい「要求する者」であり、金銭を、物品を、栄誉を、特権を、尊敬を、注目を、平穏無事を、興奮や刺激を、支配を、庇護を、親切を、美を、秩序を・・・と、とかく次々と求めてやみません。そんな人間の欲求を大きく分けると、危機回避欲求(身体的な病気や障害、精神的な疾患や苦悩、病気や事故による死亡などを回避したい欲求)・優越欲求(実績・能力・地位等の相対的な優劣の尺度を用いて自分の優位性を確認したい欲求)・屈辱の回避欲求(嘲笑・侮辱・無礼・揶揄・愚弄・無関心などの言動を他者から取られないようにしたいとする欲求)があります。そして、それらが満たされないといって様々なストレスを抱え込んでいます。「常に求めて、たまたま得られても満足はその時だけ」という儚さもストレス、「常に求めて、いつまでも得られない」のも欲求不満のストレス、「内心では求めているのに、ずっと我慢する」のも自己抑制のストレス、どちらに転んでも「一切皆苦」です。一つの山を起こせば次の山をと、常に「山のあなたの空遠く」幸せを求めて、自転車操業をしている哀しい動物が人間といえます。だから、商売の種は尽きないと言えます。
2010.11.16
コメント(0)
-

京都の秋も本番
嵯峨野は紅葉見物の人たちで一杯です。今週末当たりは洛中も見頃になると思います。京都滋賀の紅葉情報 http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/momiji/
2010.11.15
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
会社には、お客様から「無くなってもらっては困る」と言われる会社と、「おたくが無くなっても別に困らない」と言われる会社の二つしかありません。「やめてもらっては困る」と言われる魅力のある店を創るには、まず生活者の「フカイヨ」を良く知って、当社は生活者のどんなフラストレーションを解消するための存在なのかを経営者自身がハッキリと意識する必要があります。そして、生活者のその欲求を最大限に満たしてあげることを考え続ければ、お客様から「なくなってもらっては困る」と言われる会社になります。アメリカの心理学者マズローは、欲求の五段階説を唱えました。1.生理的欲求=生命維持のための食欲・性欲・睡眠欲等の本能的・根源的な欲求です。食料品店や飲食店、ホテルや旅館、寝具店、人類最古の商売と言われる風俗店など、最も根源的なこの欲求を満たす商売は多いですね。2.安全の欲求=安全性・経済的安定性・良い健康状態・良い暮らしの水準など、予測可能で、秩序だった状態を得ようとする欲求です。病気や不慮の事故などに対するセーフティ・ネット(人間ドック、セキュリティ、保険)なども、これを満たす要因に含まれます。 生理的欲求と同じように人間の根源的欲求のため、テレビや新聞、雑誌などの広告はこの関連で溢れています。 3.所属と愛の欲求=他者に受け入れられている、どこかに所属しているという感覚で、この欲求が満たされない時、人は孤独感や社会的不安を感じやすくなり、鬱状態になりやすくなります。この欲求が十分に満たされている場合、生理的欲求や安全の欲求を克服することさえあります。 4.承認(尊重)の欲求=自分が集団から価値ある存在と認められ、尊重されることを求める欲求です。低レベルの尊重欲求は、他者からの尊敬、地位への渇望、名声、利権、注目などを得ることによって満たすことができます。高レベルの尊重欲求は、自己尊重感、技術や能力の習得、自己信頼感、自立性などを得ることで満たされ、他人からの評価よりも自分自身の評価が重視されます。 人間は「認めて欲しい」と生涯叫び続けている動物だと言った人がいるが、子供から大人まで様々な形でこの欲求を満たそうとしています。5.自己実現の欲求=自分の持つ能力や可能性を最大限に発揮し、具現化したいと思う欲求で、すべての行動の動機はこの欲求に帰結するともいえます。 これらの欲求は、1→5の順に高次となり、低次の欲求がある程度満たされないと、それよりも高次の欲求が発現しないと言われています。つまり、低次の欲求が満たされることによって、次の段階の欲求が芽生え、それを満たすためにさらなる行動を起こすと考えられています。1~4の欲求は足りないものを満たすという意味で「欠乏欲求」と呼ばれ、5はそれらとは質が異なり「成長欲求」と呼ばれています。この5つの欲求ではうまく説明できない消費者行動が経済の成熟化に伴って顕著になってきて、マズローが晩年に唱えたのが超自己実現の欲求です。それは、自己超越、つまり他人への奉仕や、知識欲の充足、美の追求といったものです。これらをわかりやすく説明するキーワードとしては、哲学用語の「真・善・美」が適切なような気がします。この頃の若者たちに顕著な、ボランティア活動はこの範疇にはいると思います。欠乏欲求とは、まさに私の言う「フカイ」=欲求と現実のギャップにほかなりません。モノやサービスは、これらの「フカイヨ」からくるフラストレーションを解消するためにあるといえます。
2010.11.15
コメント(0)
-
三尾の紅葉は見頃でした
昨日は、10年ばかり会っていなかった懐かしい人が堺から訪ねてくれました。私が大阪に事務所を開いたときに事務をしていてくれた女性の旦那さんで、彼もときたま営業を支援してくれていました。長男が来年春には卒業すると言う。出産で止めることになったのだから、出会いはもう20年近くも前になります。清滝川沿いの東海自然道を歩いて、高雄へ出かけました。下の方はまだ早い紅葉も、高雄まで来るともう彩りも鮮やかになっていました。知人のやっている高雄茶屋の庭は最高で、うどんすきを楽しみながら話も弾み、つい酒の徳利が並びます。槙尾、栂尾へと足を延ばし、帰りは違う道をまた歩いて帰りました。黄砂が空を覆う、もう一つの天候でしたが、心楽しい秋の1日でした。紅葉したナナカマドの葉にモリアオガエルが座っていました。
2010.11.14
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
そんな人間の本質をお釈迦様は紀元前の昔に見通され、「全ては燃えている。熾然として燃え盛っている。そのことを、汝らは知らねばならない」と釈迦は言われたが、燃え盛っているのは私たちの煩悩の炎です。人間には、「貪(トン)・瞋(シン)・癡(チ)」という根本的な煩悩「三毒」をはじめとした様々な煩悩があります。(詳細は省略)人間というものは、思いが叶ったから「もうこれで良い」と満足することはなく、次々とハードルを上げ、目標も増えてきます。その裏返しとして、「出すことは一切いや、舌を出すのもいや」ということになる、これが貪(欲)です。自分の思い通りにならない、バカにされた、相手にされなかったなどどいってすぐに腹を立てる怒りの心が瞋(恚)です。癡(愚痴)とは、正しい判断が出来ないで、すぐ文句ばっかり言う心です。宝くじやサッカーくじを買って、一等が当たったらなどと都合の良い夢を見ているが、何のことはない外れかせいぜい元返し、でるのは愚痴ばかりです。人間は生きている限り、三毒から脱することは不可能です。何故なら、それは生きている命の証でもあるからです。だから、商売の種は尽きません。
2010.11.14
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
人間には様々な欲求があるが、それらは人間の煩悩から起きます。お釈迦様は苦の原因を自らの煩悩と捉えたが、苦は求めても得られないものを求めようとして思い悩むことから起きます。108の煩悩とか8万4千の煩悩というように、煩悩には限りがありません。私たちは四苦八苦という言葉をよく使うが、これは仏教からきた言葉で四苦とは「生老病死」を指し、それに「愛別離苦(愛しい人とも別れなければならない苦)・怨憎会苦(嫌いな人とも顔を合わせなければならない苦)・求不得苦(求めても得られない苦)・五蘊盛苦(肉体と精神が生み出すあらゆる苦)」を加えて八苦といいます。「死にたくない」というのは人間にとって最大の欲求で、そのために「病気になりたくない、健康でありたい」「歳を取りたくない」という願望が強く、健康関連商品やアンチエイジング商品、保険のコマーシャルが溢れています。例えば、「死にたくない→健康でいたい」という欲求から、太りすぎや体力低下、足腰の衰え、食の安全などへの「フカイ」が起きます。それを解消するために、ダイエットや健康維持、健康促進のための様々な商品があります。
2010.11.13
コメント(0)
-
週末は三尾へどうぞ
冷え込んできて、高雄茶屋から週末から来週には見頃になるとの便りがありました。健脚自慢の方でしたら、清滝から川沿いに高雄まで散歩がてらに歩くのも良いですよ。一時間もあれば大丈夫ですから、秋の一時を楽しんで下さい。高雄茶屋では、知り合いたちが臨時の屋台も出しています。写真は我が家の近くの落柿舎です。
2010.11.12
コメント(0)
-
番外編 釈迦の教えと経営
経営にも釈迦の教えを生かすことができます。その辺りを少しの間書いてみたいと思います。私たちには、痛みから逃れたい、快楽を得たい、時間を短縮したい、様々な不満を解消したい、歳を取りたくないなど、様々な夢や欲求、願望などがあります。それは現状では満たされていないから起きるわけで、夢や欲求、願望を抱くと現状との間には様々な問題点や課題が浮かび上がってきます。私は、その関係を「フカイヨ」と呼んでいます。・ヨ=欲求・夢・願望・ありたい姿・理想などという言葉で表現できます・フ=「不」で不の付く漢字を思い浮かべて下さい。人間は「不」に敏感だから、手元の小さな漢和辞典を開いてみても不安・不満・不便・不快など4ページにわたって掲載されています。・カ=課題(問題解決への方向性を示したモノ) ・イ=イライラすること人間は「不」に敏感なので、「フカイ」が高まるとフラストレーション=欲求不満が高まってきます。すると、それを「解消して早く楽になりたい」という気持が起きます。その解消策として、モノやサービスを購入するのです。ですから、お客様の「フカイヨ」解消策を提案することが仕事の実態です。それは、まさに慈悲の実践に他なりません。
2010.11.12
コメント(0)
-
大型書店ばやりだが
京都の駅を挟んで、大型商業施設が張り合うことになりました。駅には伊勢丹や大型電気店もあり、相乗効果が期待されています。ところで、それぞれの施設には大型書店が出店しているのだが、なかなか目的の本を探すのが大変です。本の検索システムが不十分で、新刊の正しい情報を持っている本しか買えません。しかも、本が多すぎて、なかなか目的の本に巡り会えません。分類棚までは行っても、本に巡り会えなかった経験が何度もあります。これは、大型電気店でも同じようなものですね。コンビニが流行っているように、書店や電気店もおまり大きすぎるのは消費者の使い勝手からみると問題で、パット見て欲しい本が買える本屋の需要はあると思うのだが、昔ながらの街の本屋さんは無くなっていきます。その結果、アマゾンなどのネットで買う人が増えているようです。試みに、調べてみたらこんなデータがありました。普段読む本の入手先(複数回答 ネット経由での調査なので少し偏りがあると思うが)大型書店 54.6%ネット 39.8%図書館 36.2%近所の本屋 26.4%古本屋 26.3%大型商業施設内の本屋 21.7%
2010.11.11
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
願はくは 花のしたにて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃 西行願ひおきし 花のしたにて をはりけり 蓮の上も たがはざるらん 俊成西行と俊成の歌に私の願いを託して、そろそろ終わりにしたいと思います。十四世ダライ・ラマは「人間として生を享けた以上、死は不可避的に訪れる。然らば、死もまた人生の一部として享受する他ない。年老いることには何も特別な意味はない。誰もが年老いる。老後といえども、それも立派に人生の重要な一部である。人間は年老い、やがて死を迎える。その時になれば、従容として死ねばいい。来世があるか否か、再生するか否か、思い迷う必要はない。あるがままの死を迎え、認め、受容すればいい。それが死というものだ」と言う。12人兄弟の末っ子で姉たちに育てられたような私は、今は亡き長姉の顔を見ると何時も仏様を思い出したものです。若い間は随分と苦労した姉の、老年になってからの福よかな笑顔を見るとホッとしました。だから、私の理想は、何時も笑顔を忘れない人生です。一度しかない人生だから、楽しく笑って暮らし、笑って死んでいきたいものです。私の理想とする死に方をされた例を最後に、この原稿を閉じさせて戴きます。62歳で大腸がんの手術をしたものの2年後に再発して、再手術は無理と診断された人がいました。息子さんは、「オヤジは小さい頃から私を連れてよく山歩きをした。山川に親しみ、自然の楽しみ方を教えてくれた。もう、そう長くは生きられないのなら、オヤジを連れて旅行をしたい」と、先生に無理を言って退院させました。そして、勤めを辞めてフリーターになり、ライトバンを買って何時でも寝起きできるように後部座席をベッドに改造し、月に何回か旅行に出かけました。とうとうある日、旅行中の山道で父親の病状が急変しました。息子「すぐ、近くの町にある病院を探すから、しっかりして」父親「いや、もういい。病院には連れて行かないでくれ」死期が近いことが二人にはわかったのです。息子さんは車の窓を開けて、大声で叫びました。「オヤジ、あれが○○山だ。こっちに見えるのは××峠だ」しばらくうなずいていた父親は、やがて静かに息を引き取りましたとさ。
2010.11.11
コメント(0)
-
嵯峨野の紅葉はまだまだ
急に冷え込んできましたが、嵯峨野の紅葉はまだまだです。あちらこちらで色づき始めましたが、色ももう一つです。14日は嵐山もみじ祭があるが、やはり第4週辺りが見頃ですかね?
2010.11.10
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
よい人間関係をつくるには、好意と信頼関係が必要です。信頼関係を作り出す本は、小さな約束、とくに時間とお金の約束を守り続けることだと思います。東北地方に、メキメキと業績を伸ばしている建設会社があります。社長は、朝礼で「必ずお客様との時間の約束を守ってほしい」と言い続けてきました。初めは上の空で聞いていた社員も、時間の約束を必ず守ることによって次第に信用が高まり、「この人に任せたら間違いがない」という理由でお客様が契約してくださったことがわかるにつれて、お客さまとの時間の約束を守る社員が増えてゆき、それにつれて会社全体の業績も伸びを示すようになったそうです。そんな会社だから、建物の引き渡し期日はもちろん、建築材料も指定のものが確実に使われているので、ますます信用が増していったのです。「少しくらいなら」「私的な約束だから」「大事な仕事ができたから」という理由で、小さな約束を疎かにする人がいます。でも、「約束の時間一つ守れない人」と信用を失って、その後に約束されている大きな幸せを逃しているはずです。何故なら、約束を破ることは相手の時間=命を浪費することだからです。「金の切れ目が縁の切れ目」というように、お金の約束はとくに大切です。
2010.11.10
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
慈悲も四摂法も頭では理解できてもなかなか実践できないのが人間だが、R・アクセルロッドが様々な交渉戦略をコンピュータの中で競い合わせ、どれが長い目で見て最適の対処戦略かをシュミレーションしてみました。1.最初から相手を騙そう2.とにかく友好的、平和的に3.最初は攻撃して相手が強かったら次は下手に出ようなどと多様な人間の生き様のような幾通りもの交渉戦略を作り、手当たり次第に相手を変えながら交渉していき、ポイントが稼げたら生き延びて繁殖していけるというルールで競い合わせました。何百回も総当たり戦を繰り返した結果、単純に利己的な小ずるいいき方も、観念的、理想的な平和主義も、長い目で見ると最適ではなく、最も着実に勢力を拡大していけたのは、ある意味では最も常識的な応報戦略、つまり初回は親切に、相手も好意に応じたらまた親切に、しかし相手が裏切ったら必ずしっぺ返しを、ただし前非を悔い改めたら再び親切にという、ある意味では常識的な対処方法だったということです。「与えよ、されば開かれん」ではないが、まずは自分から相手に好意を示し、後は適正なギブ&テイクという互恵関係を結ぶのが現実的なようですね。
2010.11.09
コメント(0)
-
この頃の課長さんは大変だ
産能大が上場企業の「部下のいる課長」に調査したところ、課長の4割が「イキイキ働けず」と答えています。仕事の悩みを相談できる人がいない 50・2%悩みの要因 ・業務量が多すぎて余裕がない 33・6%・部下の人事評価が難しい 32・9%・部下がなかなか育たない 29・7%・上司と考え方や意見が合わない 18・7%・部下が指示通りに動かない 15・4%・部下のメンタルヘルスに不安 13・6%メンタルヘルスに不安を感じたことがある 43・7%悩みの要因 ・上司との人間関係 44・4%・成果へのプレッシャー 44・4%・仕事の内容 43・9%・部下との人間関係 36・9%・仕事の量 36・4%3年前との職場環境の変化・仕事量の増加 54・2%・成果へのプレッシャーの高まり 41・1%・職場の人数が減少 34・1%・人間関係の希薄化 25・5%・仕事の納期の短期化 24・5%・非正社員の増加 10・7%仕事の割に給料が低い 55・1%課長としてイキイキと働いているか・イキイキと働いている 6・8%・どちらかといえばイキイキと働いている 54・9%・どちらかといえばイキイキとしていない 30・4%・イキイキと働いていない 7・9%安い給料でこき使われ、上と下との人間関係でも悩んでいる課長職の悲哀が見えてきます。
2010.11.08
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
成功している人に共通することは、「ありがとう」の言葉が自然に出てきて人の何十倍も使うことです。どんな些細なことでも「ありがとう」と言える人は、仲間に尊敬され平和を創る人ともいえます。逆に成功できない人は、「ありがとう」よりも文句、グチ、不平不満、陰口などが多いようです。ある保険会社の支部長伊藤さんは、優秀営業員でもなく、組織に協力的な人でもなかった。どちらかといえば、上司にとっては扱いにくい部下ともいえた。そんな伊藤さんが、「性格的にも無理かな」と周囲の人が懸念するなか、支部長を引き受けることになった。それから十数年、部下を採用し、育成し、陣容35名を誇る優秀支部長として表彰されることになりました。経緯を知る役員の方が成功の秘訣を聞くと、「ありがとう」の一言ですと答えられた。支部長になった後、すぐにご主人が脳溢血で倒れ、命は助かったが障害が残り、今も入院中という。そのご主人が、看護婦さん、付添婦さん、お見舞いの人、同室の人などに、不自由な言葉で「ありがとう」を繰り返す。その後ろ姿に教えられ、自分の部下に対して「ありがとう」を繰り返したら、組織が伸び始めたそうです。
2010.11.08
コメント(0)
-
京通が勧める紅葉スポット
紅葉シーズンを前に、京通に聞いたところ次のような順位でした。1位 東福寺2位 永観堂3位 銀閣寺・哲学の道4位 大原三千院5位 高雄・嵯峨その他 京都御苑・瑠璃光院・毘沙門堂それぞれに好きな所があると思います。今年は何処へ行きますか?
2010.11.07
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
人間関係は、言葉・挨拶・思いやり・優しい視線・相手のために時間を割くなどといった目には見えないもので成り立っているが、その7,8割はコミュニケーションです。欧米では、「エクスキューズ・ミー」「アイアム・ソーリー」「プリーズ」「パードン」「サンキュウ」の五つの言葉を、言葉の王様と言って、いろいろと使い分ける習慣を子供のときから厳しく仕付けます。なかでも効果的なのは、「ありがとう」という感謝の言葉です。たった一言の「ありがとう」が、人の心を晴れやかにします。店で買い物をしたとき、飲食店でお茶や水を注いでくれたとき、レジでお金を払うとき、同僚や部下に仕事をしてもらったとき、どんな時でも一言「ありがとう」と言うだけで、自分の心も周りの人も心も明るくなってくるから不思議です。「ありがとう」と感謝の気持ちを口に出すことで、相手にも思いやりの優しい心が自然と育ちます。私は「ありがとう」が口癖だが、近くのスーパーではレジで袋詰めをしてくれます。この頃では、「ありがとう」「すみません」という言葉を聞くことが少なくなってきたが、もっと気軽に使ってみませんか。
2010.11.07
コメント(0)
-
少し色づいてきました
昨日は好天に誘われて高雄まで散歩しました。清滝川沿いも少し色づき始めましたが、やはり来週末あたりからが良いかと思われます。川沿いの所々では、イノシシが土を掘り返した跡が見られます。山は食べ物が少ないのでしょうか?また、昨日はご紹介もしたが、TVではユーチューブでの尖閣問題で持ちきりでしたね。
2010.11.06
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
今でいう社会福祉ボランティアの草分けであり、日本版マザーテレサみたいな一面を持った東京山谷のバタヤ部落で「アリの町のマリア」と慕われた北原怜子さんが、子供達に口癖のように話して聞かせた言葉があります。醜いものの中に美しさを 卑しいことの中に尊さを乏しい暮らしの中にも豊かさを まずいもののなかにも美味しさを苦しいことの中にも楽しさを ニッコリ笑って発見しよう和やかな顔や優しい微笑みは、お金や品物がなければできないものではありません。その気になれば、誰でも、いつでも、どこでもできることです。そのことが、とれだけ人の心を和らげ、周囲を明るくすることでしょう。そのことだけで、お世話になった社会の恩に報いる行為になります。楽しいときには自然と笑顔もでるが、「厳しいにもかかわらず」「嫌であるにもかかわらず」「病気であるにもかかわらず」など、「にもかかわらずの笑い」を大切にして下さい。暗く沈んだ顔では、運も友も逃げていきます。
2010.11.06
コメント(0)
-
尖閣ビデオ
尖閣諸島での中国船との衝突ビデオが流出してユーチューブで見られます。http://www.youtube.com/watch?v=PO3icKluj7o先日の公安の情報流出といい、ネット時代の怖さがみえてきます。本当に大切な情報は、アナログでないと守れない時代のようです。効率だけを大切にする社会の危険性を認識することが大切ですね。携帯依存症も同じではないでしょうか?京都の秋の話題はそんな生々しい現代を癒してくれます。大覚寺でもライトアップが始まります。嵯峨野の見頃は23日(休日)以後かなと思いますが。
2010.11.05
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
ある女性が「自分は、会社でも近所でも白眼視されている」と訴えます。私たちは、自分ほど可愛い者はいません。ですから、人が自分に会ったとき、心地よい微笑みや優しい言葉をかけてくれないと心に不満が生じ、「あの人は冷たい」、「私を無視している」「私を嫌っている」などと思いがちです。でも、それは甘えにしか過ぎません。自分に出会ったら、相手から笑顔や親切な言葉をかけてくるものと決めてかかっていませんか?しかし、こちらが微笑や親切な言葉を相手に期待しているのと同じように、相手もまたあなたの微笑みや親切な言葉を期待しているのです。相手が素直でなかったり、冷たいと感じられたり、ときには攻撃的だったりするとき、大抵の場合は自分に原因があります。思い切って、あなたから「お元気ですか」と笑顔で声をかけてみてください。誰もがそれを望んでいるのです。こちらが心を開けば、相手もきっと心を開いてくれるはずです。顔は自分では見えず、人のためにあるもの。菩薩の最後の修行が「和顔(和やかな顔、優しい微笑み)愛語(慈しみの籠もった優しい言葉)」とも言われるように、人の心を和らげ、周囲を明るくし、自分をも幸せにする秘訣です。
2010.11.05
コメント(0)
-
自分を悪人と気づく
散歩の途中、お寺に書いてあった言葉にドキッとしました。「善人になるより 悪人と気づくのは難しい」お釈迦様は「誰にも褒められる人もいなければ、誰にも誹られる人もいない」と言ったが、確かに、私たちの心の中には善人の要素も悪人の要素も同居しています。普段、その悪人の要素に気づくことなく、善人面して生きています。そんな自分を思い知らされた言葉でした。心したいと思います。
2010.11.04
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
ボランティアは現代版の布施だが、ボランティアというのは、決して無理せず、もっと気楽にすることです。「遠くに出かけられなければ、隣の家の前の道を掃除してあげるだけでもいい。無理しなくてもいいのよ。ボランティアだと肩肘張らないで、自分のできる範囲で手伝いましょうよ、そうしないと長続きしない。ボランティア活動のために家族を犠牲にする必要はない」とマザー・テレサの仕事を手伝っている上流社会の婦人であるクマールさんは語る。目の不自由な人がそばにいれば、自分が読んでいる新聞を声を出して読んでやるだけでもいい。それも、自分が読みたい時間で充分です。年取った人のために窓を拭いてやったり洗濯してあげることだって立派な愛の表現です。いや、何をしなくても、苦しんでいる人がいるということを知っているだけでもいいのです、とマザー・テレサも言う。親切で慈しみ深くありなさい。あなたに出会った人が、誰でも前よりももっと気持ち良く明るくなって帰るようになさい。親切があなたの表情に、眼差しに、微笑みに、温かく声をかける言葉に現れるように・・・。何も特別のことをしなくても、普段の何気ない対応の中で布施はできます。
2010.11.04
コメント(0)
-
紅葉には未だ少し早く
久しぶりの快晴です。朝の散歩に化野の方へ出かけたが、まだ紅葉は少し早いようです。(写真「あゆ茶屋」前)でも、先週末に仕事の相談できた知人が「ホテルが取れなくて困った」と言うように、もう京都の秋の観光で見える人が多いようです。高雄茶屋の主人の話では、15日頃が高雄など三尾辺りの見頃ではないかということです。嵐山辺りでは、それよりもう少し後になると思います。いまは、嵯峨菊が綺麗に咲いています。
2010.11.03
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
またまた『少女ポリアンナ』の話です。ポリアンナが孤児のジミーの面倒を見てくれる人がいないかと、教会の婦人会の人たちに一所懸命に話をします。誰もが黙りこんでしまうが、牧師夫人が「毎年インドの子供たちに送っているお金の一部を、その子に回してはどうか」と提案をします。すると活発に意見が出始め、この教会はインドに寄付をすることで有名だったので、今年から減らすのは言語道断ということになりました。教会の名前が報告書のリストのトップに出ていれば、お金がどう使われようが構わない。報告書の名声を保つために、自分たちの街にいる独りぼっちの子供を助けるよりも、インドへ金を送る方選んだのです。そして、ポリアンナに、「あの人たちは遠い所にいる子供たちのことばかり考えていて、身近にいる困った子を救おうとしないのですもの。ジミーの方を大切にすべきじゃないのかしら、報告者なんかよりもさ」と言わせます。私たちにも耳の痛い話です。大地震や海外の災害などのニュースに接すると、沢山の救援物資が集まるが、身近な不幸な人々には見向きもしない傾向があります。近くのお年寄りに声を掛ける、話を聞いてあげるだけでもいいのです。
2010.11.03
コメント(0)
-
第4章 釈迦の智慧で苦を滅する 2 命と心遍
7人掛けの電車のシートに、6人しか座っていないことがよくあります。混んでいるときなど、少し詰めてくれればもう1人座れるのにとイライラすることがありませんか? (大阪のおばちゃんは見逃しませんがね)仏教では布施を教えているが、少し詰めて立っている人を座らせてあげるのも立派な布施です。けれども、あるとき、こんなことを考えたとひろさちやさんは言います。7人掛けのシートに7人が座ると窮屈だが、6人であればゆったりとできます。そうすると、1人が立つことによって、後の6人はゆったりとできます。その意味では、立っている人は、座っている6人に布施をしてあげていることになります。物事は全て相対的なもので、立っている人を座らせ上げるのも、無理すれば座れるのを敢えて座らずにゆっくりと座らせてあげるのも布施です。また、急に雨が降ってきたときに、傘を貸してあげて自分は濡れていくのが布施ではなく、相合い傘で二人共に多少濡れるのを我慢するのが本当の布施です。こうゆう考え方をすれば、世の中の刺々しさも薄れて、もっとゆったりと楽しく生きていけるのではないでしょうか?
2010.11.02
コメント(0)
-
筆の悩み
今回、著書に闘病中のメールを転載したことで、知人たちの間で少なからず波紋を巻き起こしています。主人を亡くした人からは、抗弁もできない残された人には酷だとも言われました。公開を託されたといっても、そこまで許したのだろうかとも言われました。そのような意見が出るだろうと言うことは予想していたので、決断までには私自身も随分と悩みました。加工して当たり障りのない部分だけ載せるという手もあるが、それでは載せる意味もなく、あえて赤裸々な部分まで載せたが、身近な人には酷だったという思いも未だに心の底にはあります。以前、朝ドラの中で、「怒りや悲しみ、人を恨んだり~いろいろな心を持っていて、でもそれを心の奥にしまって、心の闇を抱えてしまった時、それを気づいてあげられるのが家族だと思う」というようなことを主人公が言っていたが、身近な人だからこそ、相手を傷つけるかも知れないと恐れて言えないことがあるのもまた事実です。人には、心の奥底にしまって誰にも言えないことがあります。それが、心に重くのしかかることがあります。それを、利害関係のない赤の他人に聞いてもらうだけで心が軽くなるという面もあります。だから、ただ聴いてあげるだけの傾聴ボランティアがいま脚光を浴びつつあります。(内容を公表しないのが鉄則だが)ある主婦の方は、「女は、小難しいアドバイスが欲しいわけでも、パートナーになんとかして欲しいわけでもなく、ただ、うんうんと耳を傾けて、ギューッとして欲しいだけです。それで十分だと思います」とも言ってみえました。ただ今回の場合は、「身近な人でも分からない心の闇があることを、他の看病している人たちにも知って欲しい」というお寺の奥さんなればこその当人の気持ちもあり(自らの苦を開示することで衆生を救う菩薩の姿をそこにみて)、その意志を汲むことにしました。(闘病の前から、生き方や宗教などについてやりとりもしていたので、その気持ちを理解していたつもりです)その意味で、関係のない方々や介護関係の人からは「大変、参考になった」と言う意見が多く、彼女の気持ちが通じホットしています。例えば◆老老看護の厳しさ 看護者が病気になるか死ぬか、あるいは今よく新聞に載っているように殺してしまうかという究極の場面が、普通の家庭でも起こりうる可能性のあること。◆周りの人は少しでも可能性があると思えば治療を受けさせようとしがちだが、本人は周りを気遣って言い出せず、負担になっていること。看病している人にしたら、自分が悔悟しないためもあると思うが(こんなことを言うとまた物議をかもすが)、ある歳になればインドの「死を待つ家」に書いたように治療をせずに寄り添うだけというのも愛の一つの形だと思います。また、信州の友達のように、一切の治療を拒否しても、自然と治ってしまう不思議もある。◆デイケアー施設などでも、聴いてあげることをもっと取り入れないかということ。人手が大変なので、傾聴ボランティアなどをもっと積極的に受け入れる。◆傾聴は、聞く側にとっては相手の苦をもらうことにもなり、非常にしんどいことです。そこで、メールで受けるサイトを作るのもいいのではないかということ。・・・などなど
2010.11.01
コメント(0)
全51件 (51件中 1-50件目)
-
-
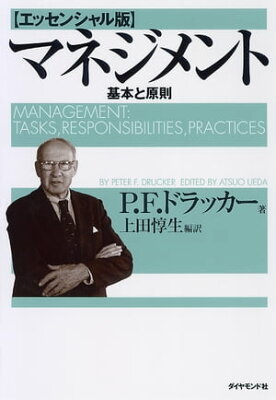
- 今日のこと★☆
- - 19. NOVEMBER * Peter Ferdinand D…
- (2025-11-19 05:25:32)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 内勤です。⛅️(8度)寒い秋模様🍂
- (2025-11-18 17:12:55)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-








