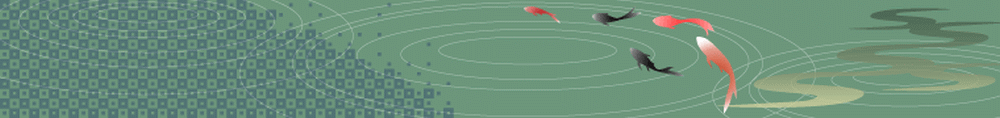カテゴリ: ニュース雑記
実は引越し計画を表明した昨日も、懲りもせずここに日記を書こうとしたのだが、書き上げてアップしようとしたら「メンテナンス中ですよ、またねん」とはじかれ、書いたものも消されてしまった。久々に学問系の話題だったのに。
やはり楽天様に楯突くと怖い?
・・・・・・・
そのまんま東が宮崎県知事に当選だって?すげえな、予想もしてなかったよ。
お笑いタレントというだけでなく色々トラブルあったそうだけど、タレント活動を休んで大学で政治学を勉強していたとか、頑張っていたらしい。これなら親分のビートたけしが選挙に出たら圧勝するんじゃないだろうか?
前任者が談合で辞職に追い込まれた知事選だというのに、あいも変わらず中央官庁出身者を引っ張り出す既成政党に嫌気があり(しかも保守分裂だったようだし)、草の根選挙のこの人に支持がいったのも理解できる。選挙権を持っていたとして、この人に投票したかどうかは分からないが。
まずは横山ノックみたいにならないように気をつけて、改革に頑張って欲しいと思う。
・・・・・・・
上のニュースも一種「テレビの力」のお陰だが(彼の知名度はテレビのお陰なので)、それを思わせるニュースを発見。お気に入りブログを見てると、結構な騒ぎですな。
捏造といえば僕らの専門分野にも以前そういう事件があって、ずいぶんあちこちから叩かれたみたいだが(他人事じゃないですよ、と後輩に叱責されたものだ)、こういう出来事の種は尽きない。
さて小さい頃に見た「川口浩の探検シリーズ」とか矢追純一のUFOシリーズは、「なんだか嘘くせえなあ」と思いつつもわくわくしながら見ていたのだが、あれは娯楽番組である(「この番組はフィクションです」とは出てなかったと思うが)。見るほうには笑い飛ばせる余裕が、見せるほうには「これは娯楽ですから」とごまかせる雰囲気があったと思う。まあ似たような出来事は以前から繰り返し起きていたと思う。
ところが報道あるいは情報番組も娯楽番組と化している昨今、これはまた別の意味を持ってくるんじゃないか。見るほう(納豆を買いに走った人々)も見せるほう(関西テレビ)も余裕がなくて悲惨ですな。テレビや新聞といった既成のメディアは今までの寡占状態をインターネットというアルターナティヴに揺るがされ(とはいえホリエモンも孫さんも口先だけですが)、既存メディア側からのネット(特に「2ちゃんねる」)への批判も最近強まっているようだが(僕は「2ちゃんねる」は見たこと無いけど)、僕からすれば五十歩百歩ですな。
ネット上の情報の9割は情報源の怪しいデマやポエムで(「便所の落書き」)、利用するにはおそろしく慎重でなくてはならないかもしれない(だから学問での利用にはまだ慎重だ)。だが既成メディアのような一方通行のメディアでは得られない情報があり、情報の集約性は個人個人の頭脳を凌駕する(その考えから出来ているのが「ウィキペディア」だが)。テレビが自らネットに擦り寄り、またこういうことをしてるんじゃあ、ネットに負けるでしょう、そりゃあ。といいながら僕はネットのことも全然知らんのだが。
テレビ局の社長が「視聴者の信頼を裏切る云々」っていうけど、今どきテレビを完全に信じちゃダメ、ということを改めて示しただけなんですかね。
この騒ぎを見ていてふと連想したのは、だいぶ前に読んだ中島らも著「ガダラの豚」である。



この作品はあくまで小説で、エロ・グロ・ドタバタ劇もあって(作者は劇団を主宰していた)、娯楽作品の分野に属する。確か発表年のホラー大賞か何かももらっていたような。
しかしそのテーマは「人はいかに騙されるか」という鋭いものである。一応フィクションなんだが、ヴィヴィッド過ぎて笑えない箇所もある。この本読んでから、僕はテレビの奇術番組を一切信じなくなったし(笑)。
場面は四つに分かれている。
主人公は文化人類学者とその一家。気鋭の学者だった彼は今やいわゆる「タレント学者」で、テレビ番組でいじられる身に落ちぶれている。そこで奇術ショーなどテレビ番組での「仕込み」(ヤラセ)やテレビ局の内情を目の当たりにする。
彼の妻はある事件で神経を病み、新興宗教にのめりこむ。その手口がいろいろと書かれているのだが、学歴も高く常識人であるはずの彼女がどんどん騙されていく様など、この本の発表の少し後に明らかになるオウム事件を予見しているかのような内容である。
最後はそのアフリカ呪術と、「現代の呪術」であるテレビとの恐ろしい融合、そして主人公たちの運命が描かれる。最後はクライマックスに向けてのドタバタで、かなりファンタジー色が強まるので、好悪が分かれるかもしれない。
ともあれ、お奨めです。
新興宗教といえば、僕は入ったことは無いが仄聞したことはある。
最初は高校のときで、商店街を歩いているとにこやかな大学生のお兄さんに声を掛けられた。サークルのアンケートだという。興味のあることとかを聞かれ、連絡先を聞かれた。今なら絶対教えないが、当時は皆ウブである。
そうしたらしばらくしてこのお兄さんから「一緒に夏休みのキャンプに行かないか」という誘いの電話がかかってきた。めんどくさいので断ったらもう電話は来なくなったが、今にして思えば行ったらどうなってたかと思うと恐ろしい。
彼らは最初からその正体を現さず、別名のサークル(シティパークとかサンライズとか、よく分からないが爽やかそうな名前)としてにこやかに接近してくる(確かに、寮の部屋にまで個別訪問してきた)。それにのこのこ着いていくと、キャンプや合宿所など隔絶した環境に連れて行かれ、最初は当たり障りの無いビデオとかを見せられて何事もなく帰してもらえる。しかしそれを繰り返すうちだんだんと引き込まれ、ついに洗脳状態になっていくんだという。そうなったら最後、家族を捨てさせられ、他の信者とやや街外れにある「合宿所」で共同生活し、山海の珍味やら怪しい壷やらを近所に売り歩かされ、教団の資金を稼がされるのだという。その前後「合同結婚式」やら脱会騒ぎやらが話題になっていた。
「ガダラの豚」を読んでいると、そういうことを思い出した。
それはともかく、「ガダラの豚」が書かれた当時はまだインターネットは普及していなかった。広告業界に身を置いていた中島らもはテレビにこだわって、その「呪力」をいわば暴露話のようにしてヴィヴィッドに描き出したが、今回の「あるある」の騒ぎは、その「テレビ呪術」の棹尾を飾るものになるかもしれない。
インターネットには間違いなくテレビを超える呪力がある。それはポジティヴなのばかりでなく、ネット上を見回すとほんと怪しげなのが多い(多分僕も誰かに騙されているのだろう)。それは仕方無いでしょう。仕方あるとすれば、中島らもは不慮の死を遂げてしまったが、インターネット隆盛の現在を見て「ガダラの豚」の続編を書いてくれていれば、と思う。
やはり楽天様に楯突くと怖い?
・・・・・・・
そのまんま東が宮崎県知事に当選だって?すげえな、予想もしてなかったよ。
お笑いタレントというだけでなく色々トラブルあったそうだけど、タレント活動を休んで大学で政治学を勉強していたとか、頑張っていたらしい。これなら親分のビートたけしが選挙に出たら圧勝するんじゃないだろうか?
前任者が談合で辞職に追い込まれた知事選だというのに、あいも変わらず中央官庁出身者を引っ張り出す既成政党に嫌気があり(しかも保守分裂だったようだし)、草の根選挙のこの人に支持がいったのも理解できる。選挙権を持っていたとして、この人に投票したかどうかは分からないが。
まずは横山ノックみたいにならないように気をつけて、改革に頑張って欲しいと思う。
・・・・・・・
上のニュースも一種「テレビの力」のお陰だが(彼の知名度はテレビのお陰なので)、それを思わせるニュースを発見。お気に入りブログを見てると、結構な騒ぎですな。
あるある大事典 「納豆ダイエット」はねつ造 関西テレビ
1月21日10時13分配信 毎日新聞
関西テレビ(大阪市北区)は20日、今月7日にフジテレビ系で全国放送したテレビ番組「発掘!あるある大事典2」で、事実とは異なる内容が含まれていたと発表した。「納豆を食べるとダイエットができる」との内容だったが、研究者のコメントや被験者の検査データをねつ造していた。同テレビは社内に調査委員会を設け、原因の究明を行うとともに過去の放送分についても検証を行い、番組を継続するかどうかを含めて検討する。(中略)
同テレビによると、(1)被験者がやせたことを示すのに別人の写真を使用(2)米の大学教授の発言の日本語訳の一部をねつ造(3)被験者の一部の中性脂肪値が正常値になったとしたが、測定せず(4)納豆を朝2パックまとめて食べた場合と、朝晩1パックずつ食べた場合の比較で、被験者の血中イソフラボン濃度の結果をねつ造(5)被験者の血中のDHEA(ホルモンの一種)量検査のデータをねつ造、また、許可を得ずグラフを引用--していたことが分かった。
千草宗一郎社長は「報道機関でもある放送局として、視聴者の信頼を裏切ることになった。誠に申し訳ない」と謝罪した。
同番組は関西テレビの社員2人と番組制作会社「日本テレワーク」の4人がプロデューサーを務め、テレワーク社の取締役1人がコンプライアンス(法令順守)担当者になっていた。実際の取材は孫請けを含む9チームの番組制作スタッフが行っていたが、どのチームが担当していたかについては「調査中」として明らかにしなかった。
今回の問題は、「週刊朝日」の取材をきっかけに同テレビが調査を行い、明らかになった。
健康ブームを背景に健康をテーマにした番組は増える傾向にある。「納豆」の回でも全国の小売店で一時納豆の売り切れが相次ぐなど、社会現象となった。そんな中で起こった今回の不祥事で、改めて放送倫理のあり方が問われそうだ。【北林靖彦】
(引用終了)
捏造といえば僕らの専門分野にも以前そういう事件があって、ずいぶんあちこちから叩かれたみたいだが(他人事じゃないですよ、と後輩に叱責されたものだ)、こういう出来事の種は尽きない。
さて小さい頃に見た「川口浩の探検シリーズ」とか矢追純一のUFOシリーズは、「なんだか嘘くせえなあ」と思いつつもわくわくしながら見ていたのだが、あれは娯楽番組である(「この番組はフィクションです」とは出てなかったと思うが)。見るほうには笑い飛ばせる余裕が、見せるほうには「これは娯楽ですから」とごまかせる雰囲気があったと思う。まあ似たような出来事は以前から繰り返し起きていたと思う。
ところが報道あるいは情報番組も娯楽番組と化している昨今、これはまた別の意味を持ってくるんじゃないか。見るほう(納豆を買いに走った人々)も見せるほう(関西テレビ)も余裕がなくて悲惨ですな。テレビや新聞といった既成のメディアは今までの寡占状態をインターネットというアルターナティヴに揺るがされ(とはいえホリエモンも孫さんも口先だけですが)、既存メディア側からのネット(特に「2ちゃんねる」)への批判も最近強まっているようだが(僕は「2ちゃんねる」は見たこと無いけど)、僕からすれば五十歩百歩ですな。
ネット上の情報の9割は情報源の怪しいデマやポエムで(「便所の落書き」)、利用するにはおそろしく慎重でなくてはならないかもしれない(だから学問での利用にはまだ慎重だ)。だが既成メディアのような一方通行のメディアでは得られない情報があり、情報の集約性は個人個人の頭脳を凌駕する(その考えから出来ているのが「ウィキペディア」だが)。テレビが自らネットに擦り寄り、またこういうことをしてるんじゃあ、ネットに負けるでしょう、そりゃあ。といいながら僕はネットのことも全然知らんのだが。
テレビ局の社長が「視聴者の信頼を裏切る云々」っていうけど、今どきテレビを完全に信じちゃダメ、ということを改めて示しただけなんですかね。
この騒ぎを見ていてふと連想したのは、だいぶ前に読んだ中島らも著「ガダラの豚」である。



この作品はあくまで小説で、エロ・グロ・ドタバタ劇もあって(作者は劇団を主宰していた)、娯楽作品の分野に属する。確か発表年のホラー大賞か何かももらっていたような。
しかしそのテーマは「人はいかに騙されるか」という鋭いものである。一応フィクションなんだが、ヴィヴィッド過ぎて笑えない箇所もある。この本読んでから、僕はテレビの奇術番組を一切信じなくなったし(笑)。
場面は四つに分かれている。
主人公は文化人類学者とその一家。気鋭の学者だった彼は今やいわゆる「タレント学者」で、テレビ番組でいじられる身に落ちぶれている。そこで奇術ショーなどテレビ番組での「仕込み」(ヤラセ)やテレビ局の内情を目の当たりにする。
彼の妻はある事件で神経を病み、新興宗教にのめりこむ。その手口がいろいろと書かれているのだが、学歴も高く常識人であるはずの彼女がどんどん騙されていく様など、この本の発表の少し後に明らかになるオウム事件を予見しているかのような内容である。
最後はそのアフリカ呪術と、「現代の呪術」であるテレビとの恐ろしい融合、そして主人公たちの運命が描かれる。最後はクライマックスに向けてのドタバタで、かなりファンタジー色が強まるので、好悪が分かれるかもしれない。
ともあれ、お奨めです。
新興宗教といえば、僕は入ったことは無いが仄聞したことはある。
最初は高校のときで、商店街を歩いているとにこやかな大学生のお兄さんに声を掛けられた。サークルのアンケートだという。興味のあることとかを聞かれ、連絡先を聞かれた。今なら絶対教えないが、当時は皆ウブである。
そうしたらしばらくしてこのお兄さんから「一緒に夏休みのキャンプに行かないか」という誘いの電話がかかってきた。めんどくさいので断ったらもう電話は来なくなったが、今にして思えば行ったらどうなってたかと思うと恐ろしい。
彼らは最初からその正体を現さず、別名のサークル(シティパークとかサンライズとか、よく分からないが爽やかそうな名前)としてにこやかに接近してくる(確かに、寮の部屋にまで個別訪問してきた)。それにのこのこ着いていくと、キャンプや合宿所など隔絶した環境に連れて行かれ、最初は当たり障りの無いビデオとかを見せられて何事もなく帰してもらえる。しかしそれを繰り返すうちだんだんと引き込まれ、ついに洗脳状態になっていくんだという。そうなったら最後、家族を捨てさせられ、他の信者とやや街外れにある「合宿所」で共同生活し、山海の珍味やら怪しい壷やらを近所に売り歩かされ、教団の資金を稼がされるのだという。その前後「合同結婚式」やら脱会騒ぎやらが話題になっていた。
「ガダラの豚」を読んでいると、そういうことを思い出した。
それはともかく、「ガダラの豚」が書かれた当時はまだインターネットは普及していなかった。広告業界に身を置いていた中島らもはテレビにこだわって、その「呪力」をいわば暴露話のようにしてヴィヴィッドに描き出したが、今回の「あるある」の騒ぎは、その「テレビ呪術」の棹尾を飾るものになるかもしれない。
インターネットには間違いなくテレビを超える呪力がある。それはポジティヴなのばかりでなく、ネット上を見回すとほんと怪しげなのが多い(多分僕も誰かに騙されているのだろう)。それは仕方無いでしょう。仕方あるとすれば、中島らもは不慮の死を遂げてしまったが、インターネット隆盛の現在を見て「ガダラの豚」の続編を書いてくれていれば、と思う。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[ニュース雑記] カテゴリの最新記事
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
Vortrag 18.6.2003

Einfuehrung

Yayoi-Zeit

3/4 Jhdt. n. Chr.

5/6. Jhdt. n.Chr.

7. Jhdt. n. Chr.

日本語版
過去の日記

考古学・歴史日記03年

考古学・歴史日記02年後半

考古学・歴史日記02年中頃

考古学・歴史日記02年前半

考古学・歴史日記01年
各国史

EU-25/2004(南欧)

EU-25/2004(中欧)

EU-25/2004(東欧)

EFTA諸国

ヨーロッパのミニ国家

EU加盟候補国

西アジア

アメリカ史(上) 建国

アメリカ史(中) 大国

アメリカ史(下) 超大国

カフカス諸国

バルカン半島(非EU)

EU加盟国(北欧)

スペイン史(1) 前近代

スペイン史(2) 近現代

EU-27/2007

中央アジア
ヘロドトス「歴史」を読む

その2

その3
「太平記」を読んで…
 New!
七詩さん
New!
七詩さん
復刻記事「韓国記事… alex99さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
北海道2023(その7) Leadcoreさん
Leadcoreさん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
 New!
七詩さん
New!
七詩さん復刻記事「韓国記事… alex99さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
北海道2023(その7)
 Leadcoreさん
Leadcoreさん絨毯屋へようこそ … mihriさん
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.