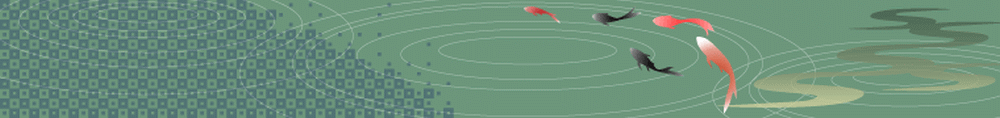カテゴリ: 映画
アイルランドには行ったこともないのだが、昔から僕の好きな国の一つである。
一方でアイルランドは苦難の歴史ももっている。特に700年続いたイギリス支配への抵抗がそれで(北アイルランド=アルスターでは最終的な決着をまだ見ていない一方で、彼らの日常語は今や「支配者の言語」である英語になっている)、映画になったこともあるし、僕も ここ でアイルランド独立派の対英闘争について書いたことがある。
さて昨年のカンヌ映画祭で金椰子賞(最優秀作品賞)を受賞したのはケン・ローチ監督の「The Wind That Shakes the Barley」(邦題:「麦の穂をゆらす風」)だったが、それはアイルランドの独立戦争をテーマにしているというので、見に行った。
ケン・ローチ監督はイギリスでは当代最高の監督ということだが、僕は彼の映画を見たことがない(多分)。出演者も主演のキリアン・マーフィーを除くと、アイルランド以外では無名の俳優が起用されている。このキリアン・マーフィーってなんか見たことある顔だと思ったら、 「真珠の耳飾の少女」 でスカーレット・ヨハンソンの相手役をやっていて、僕が「間抜け面で嫌い」とこきおろした俳優ぢゃ無いか。あと 「コールド・マウンテン」 にも出ているそうだが、思い出せない。
(あらすじ)
しかし彼がロンドンに向けて発とうとする前日、挨拶に訪れた馴染みの家で、ブラック・アンド・タンズ(イギリスの治安部隊。素行の悪さで有名)の捜索に出くわしてしまう。デミアンたちが「ハーリング(アイルランドの伝統球技)をして、集会を禁止する戒厳令に反した」という理由だった。イギリス兵はデミアンたちに服を脱がせ尋問するが、その家の少年ミハール(英語ではマイケル)は英語で自分の名を言うことを拒否したために、家族の目の前でイギリス兵に惨殺された。
憤激したデミアンの兄テディらはアイルランド義勇軍への加入を決めるが、暴力を嫌うデミアンは仲間を振り切ってロンドンに向かおうとする。しかし駅でイギリス兵の暴行を受けながらも無抵抗で乗車を拒否する鉄道員ダンらの姿を見て、一転義勇軍に加盟する。テディは地区の義勇軍の指揮官になる。
テディやデミアンら義勇軍は、イギリス軍の兵舎を襲って脅迫したり、バーで飲むイギリス士官を殺害するなどの都市ゲリラ戦を行う。しかしイギリス軍は保守的な地主らの密告でテディやダミアンを一網打尽にする。テディは拷問されながらも自白を拒んだため、翌日全員処刑ということになったが、イギリス軍にいたアイルランド人兵士の助けで間一髪脱走する。ダミアンらは地主や密告者に非情な報復を行うのだった。
義勇軍の攻撃は続き、移動中のイギリス兵を待ち伏せし全滅させる。一方イギリス軍も村を焼き討ちするなど報復し、抗争はますますエスカレートするかに見えた。しかし1921年12月、イギリスはついにアイルランド独立を要求するシン・フェイン党との交渉に応じ、停戦となった。
しかしアイルランド代表団がイギリスと締結した条約は、デミアンらの理想とはかけ離れたものだった。アイルランドはある程度の内政上の自治(「アイルランド自由国」)を得るもののイギリス連邦内に留まり、議会はイギリス国王に忠誠を誓う、しかもプロテスタント住民の多い北アイルランド6州はアイルランドから分離される、というものだった。批准を巡って賛成・反対双方のアイルランド人同士の対立が深まるが、再戦を辞さないイギリス側の圧力もあり、結局条約は批准された。イギリス軍は撤退した。
しかし首都ダブリンではアイルランドの完全独立を求める条約反対派(共和軍)が蜂起、アイルランド自由国軍はそれを武力で鎮圧する。この対立は地方にも及び、ついに流血の事態となった。今や正規軍である自由国軍の将校となったテディに対し、デミアンやダンは完全独立のため共和軍に投じ、以前イギリス軍に対して行っていたゲリラ攻撃を、今度は自由国軍に行うことになる。
こうしてかつての仲間同士は互いに血を流すことになり、デミアンとテディの兄弟の間にも悲劇が起きることは避けられなかった・・・・。
(感想)
凄惨なアイルランド独立闘争(テロ行為などを中心とした非対称戦であったが、アングロ・アイルランド戦争と呼ばれる)と、それに続くアイルランド内戦の悲劇を正面から描いた作品。思ったより残虐シーンはなかったが、それでも心臓に悪そうな場面もあるにはある。
同じテーマを扱った映画「マイケル・コリンズ」(二ール・ジョーダン監督)はアイルランド義勇軍の英雄コリンズを中心に描いているが、普通の人々が中心のこの作品は、より「英雄度」は低い。ただそのためなのかどうなのか、登場人物はやや型にはまった感じがするし、ストーリー展開もアイルランドの近代史に詳しい人ならばいささか説明的で、通り一遍な印象を免れないのではないだろうか。正統的な描き方といえばそうだが、凡庸といえなくもない。そう古くも無い時代(今からおよそ90年前の話)の歴史映画を作るというのはなかなか難しいところもあるのだろう。ドイツの映画評とかを見ても、ケン・ローチにしては歯切れの悪い作品、あるいは金椰子賞受賞は意外という論調が多いようだ。

「マイケル・コリンズ」では支配者イギリスの暴虐やらアイルランドの民族主義とかが前面に出て分かりやすい話だったが、なぜ団結してイギリスに立ち向かっていたはずのアイルランド人が内戦に陥らねばならなかったのかはなかなか分かりにくかった。
イギリス軍の暴虐ぶりも描かれるが、ケン・ローチ監督はアイルランド人ではなくイギリス人である。「700年の支配」からの脱却を叫ぶアイルランド人の声に比べれば、イギリス側の事情は「俺たちはソンムで命を掛けて戦ったんだぞ」という台詞くらいしかない。 「ソンム」 とはフランスにあるこの映画の少し前に行われた第一次世界大戦の激戦地の一つで、ドイツ軍と対戦したイギリス軍は膨大な損害を蒙った。ドイツはアイルランド独立派に対して武器や資金を供与しようとしたこともあり、イギリス側にもそれなりの理屈はある。
監督は「この映画は反英を意図した映画ではない」とカンヌでのインタビューで述べているのだが、その意図を知ってか知らずか「イラク戦争に加わったイギリスへの批判であり、とても現代的なテーマ」という見当違いの映画評も見られる。ただ彼がイラクで続く暴力の連鎖を意識して作ったことは間違いないようだ。
「マイケル・コリンズ」では独立義勇軍を指揮した英雄的な一人の男の生き様が、この作品では義勇軍に参加した無名の人々の闘争と悲劇が描かれている。しかし実際のところ、アイルランド義勇軍に全てのアイルランド人男性が加わっていたわけではない(仕事としてイギリス軍・警察に属したアイルランド人のほうが多い)。この映画では「背景」となってしまっている、「何もしなかった人々」というのがたくさんいたはずだ。僕は臆病者だから、この時代のアイルランドに生きていれば、おそらく抗争騒ぎをよそに義勇軍に加わらずジャガイモしか作れない畑を掻いていたかもしれない。次はそういう人々の視点でアイルランド独立闘争を描いた映画が見てみたいと思う。
陰惨な映画だが、背景となるアイルランドの自然は美しい。
I sat within the valley green, I sat me with my true love
My sad heart strove the two between, the old love and the new love
The old for her, the new that made me think on Ireland dearly
While soft the wind blew down the glen and shook the golden barley
'Twas hard the woeful words to frame to break the ties that bound us
But harder still to bear the shame of foreign chains around us
And so I said, "The mountain glen I'll seek at morning early
And join the bold united men," while soft winds shake the barley ・・・・
一方でアイルランドは苦難の歴史ももっている。特に700年続いたイギリス支配への抵抗がそれで(北アイルランド=アルスターでは最終的な決着をまだ見ていない一方で、彼らの日常語は今や「支配者の言語」である英語になっている)、映画になったこともあるし、僕も ここ でアイルランド独立派の対英闘争について書いたことがある。
さて昨年のカンヌ映画祭で金椰子賞(最優秀作品賞)を受賞したのはケン・ローチ監督の「The Wind That Shakes the Barley」(邦題:「麦の穂をゆらす風」)だったが、それはアイルランドの独立戦争をテーマにしているというので、見に行った。
ケン・ローチ監督はイギリスでは当代最高の監督ということだが、僕は彼の映画を見たことがない(多分)。出演者も主演のキリアン・マーフィーを除くと、アイルランド以外では無名の俳優が起用されている。このキリアン・マーフィーってなんか見たことある顔だと思ったら、 「真珠の耳飾の少女」 でスカーレット・ヨハンソンの相手役をやっていて、僕が「間抜け面で嫌い」とこきおろした俳優ぢゃ無いか。あと 「コールド・マウンテン」 にも出ているそうだが、思い出せない。
(あらすじ)
しかし彼がロンドンに向けて発とうとする前日、挨拶に訪れた馴染みの家で、ブラック・アンド・タンズ(イギリスの治安部隊。素行の悪さで有名)の捜索に出くわしてしまう。デミアンたちが「ハーリング(アイルランドの伝統球技)をして、集会を禁止する戒厳令に反した」という理由だった。イギリス兵はデミアンたちに服を脱がせ尋問するが、その家の少年ミハール(英語ではマイケル)は英語で自分の名を言うことを拒否したために、家族の目の前でイギリス兵に惨殺された。
憤激したデミアンの兄テディらはアイルランド義勇軍への加入を決めるが、暴力を嫌うデミアンは仲間を振り切ってロンドンに向かおうとする。しかし駅でイギリス兵の暴行を受けながらも無抵抗で乗車を拒否する鉄道員ダンらの姿を見て、一転義勇軍に加盟する。テディは地区の義勇軍の指揮官になる。
テディやデミアンら義勇軍は、イギリス軍の兵舎を襲って脅迫したり、バーで飲むイギリス士官を殺害するなどの都市ゲリラ戦を行う。しかしイギリス軍は保守的な地主らの密告でテディやダミアンを一網打尽にする。テディは拷問されながらも自白を拒んだため、翌日全員処刑ということになったが、イギリス軍にいたアイルランド人兵士の助けで間一髪脱走する。ダミアンらは地主や密告者に非情な報復を行うのだった。
義勇軍の攻撃は続き、移動中のイギリス兵を待ち伏せし全滅させる。一方イギリス軍も村を焼き討ちするなど報復し、抗争はますますエスカレートするかに見えた。しかし1921年12月、イギリスはついにアイルランド独立を要求するシン・フェイン党との交渉に応じ、停戦となった。
しかしアイルランド代表団がイギリスと締結した条約は、デミアンらの理想とはかけ離れたものだった。アイルランドはある程度の内政上の自治(「アイルランド自由国」)を得るもののイギリス連邦内に留まり、議会はイギリス国王に忠誠を誓う、しかもプロテスタント住民の多い北アイルランド6州はアイルランドから分離される、というものだった。批准を巡って賛成・反対双方のアイルランド人同士の対立が深まるが、再戦を辞さないイギリス側の圧力もあり、結局条約は批准された。イギリス軍は撤退した。
しかし首都ダブリンではアイルランドの完全独立を求める条約反対派(共和軍)が蜂起、アイルランド自由国軍はそれを武力で鎮圧する。この対立は地方にも及び、ついに流血の事態となった。今や正規軍である自由国軍の将校となったテディに対し、デミアンやダンは完全独立のため共和軍に投じ、以前イギリス軍に対して行っていたゲリラ攻撃を、今度は自由国軍に行うことになる。
こうしてかつての仲間同士は互いに血を流すことになり、デミアンとテディの兄弟の間にも悲劇が起きることは避けられなかった・・・・。
(感想)
凄惨なアイルランド独立闘争(テロ行為などを中心とした非対称戦であったが、アングロ・アイルランド戦争と呼ばれる)と、それに続くアイルランド内戦の悲劇を正面から描いた作品。思ったより残虐シーンはなかったが、それでも心臓に悪そうな場面もあるにはある。
同じテーマを扱った映画「マイケル・コリンズ」(二ール・ジョーダン監督)はアイルランド義勇軍の英雄コリンズを中心に描いているが、普通の人々が中心のこの作品は、より「英雄度」は低い。ただそのためなのかどうなのか、登場人物はやや型にはまった感じがするし、ストーリー展開もアイルランドの近代史に詳しい人ならばいささか説明的で、通り一遍な印象を免れないのではないだろうか。正統的な描き方といえばそうだが、凡庸といえなくもない。そう古くも無い時代(今からおよそ90年前の話)の歴史映画を作るというのはなかなか難しいところもあるのだろう。ドイツの映画評とかを見ても、ケン・ローチにしては歯切れの悪い作品、あるいは金椰子賞受賞は意外という論調が多いようだ。

「マイケル・コリンズ」では支配者イギリスの暴虐やらアイルランドの民族主義とかが前面に出て分かりやすい話だったが、なぜ団結してイギリスに立ち向かっていたはずのアイルランド人が内戦に陥らねばならなかったのかはなかなか分かりにくかった。
イギリス軍の暴虐ぶりも描かれるが、ケン・ローチ監督はアイルランド人ではなくイギリス人である。「700年の支配」からの脱却を叫ぶアイルランド人の声に比べれば、イギリス側の事情は「俺たちはソンムで命を掛けて戦ったんだぞ」という台詞くらいしかない。 「ソンム」 とはフランスにあるこの映画の少し前に行われた第一次世界大戦の激戦地の一つで、ドイツ軍と対戦したイギリス軍は膨大な損害を蒙った。ドイツはアイルランド独立派に対して武器や資金を供与しようとしたこともあり、イギリス側にもそれなりの理屈はある。
監督は「この映画は反英を意図した映画ではない」とカンヌでのインタビューで述べているのだが、その意図を知ってか知らずか「イラク戦争に加わったイギリスへの批判であり、とても現代的なテーマ」という見当違いの映画評も見られる。ただ彼がイラクで続く暴力の連鎖を意識して作ったことは間違いないようだ。
「マイケル・コリンズ」では独立義勇軍を指揮した英雄的な一人の男の生き様が、この作品では義勇軍に参加した無名の人々の闘争と悲劇が描かれている。しかし実際のところ、アイルランド義勇軍に全てのアイルランド人男性が加わっていたわけではない(仕事としてイギリス軍・警察に属したアイルランド人のほうが多い)。この映画では「背景」となってしまっている、「何もしなかった人々」というのがたくさんいたはずだ。僕は臆病者だから、この時代のアイルランドに生きていれば、おそらく抗争騒ぎをよそに義勇軍に加わらずジャガイモしか作れない畑を掻いていたかもしれない。次はそういう人々の視点でアイルランド独立闘争を描いた映画が見てみたいと思う。
陰惨な映画だが、背景となるアイルランドの自然は美しい。
I sat within the valley green, I sat me with my true love
My sad heart strove the two between, the old love and the new love
The old for her, the new that made me think on Ireland dearly
While soft the wind blew down the glen and shook the golden barley
'Twas hard the woeful words to frame to break the ties that bound us
But harder still to bear the shame of foreign chains around us
And so I said, "The mountain glen I'll seek at morning early
And join the bold united men," while soft winds shake the barley ・・・・
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[映画] カテゴリの最新記事
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
フリーページ
Vortrag 18.6.2003

Einfuehrung

Yayoi-Zeit

3/4 Jhdt. n. Chr.

5/6. Jhdt. n.Chr.

7. Jhdt. n. Chr.

日本語版
過去の日記

考古学・歴史日記03年

考古学・歴史日記02年後半

考古学・歴史日記02年中頃

考古学・歴史日記02年前半

考古学・歴史日記01年
各国史

EU-25/2004(南欧)

EU-25/2004(中欧)

EU-25/2004(東欧)

EFTA諸国

ヨーロッパのミニ国家

EU加盟候補国

西アジア

アメリカ史(上) 建国

アメリカ史(中) 大国

アメリカ史(下) 超大国

カフカス諸国

バルカン半島(非EU)

EU加盟国(北欧)

スペイン史(1) 前近代

スペイン史(2) 近現代

EU-27/2007

中央アジア
ヘロドトス「歴史」を読む

その2

その3
復刻記事「韓国記事…
New!
alex99さん
韓国ドラマ「金持ち… 七詩さん
七詩さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
北海道2023(その7) Leadcoreさん
Leadcoreさん
絨毯屋へようこそ … mihriさん
韓国ドラマ「金持ち…
 七詩さん
七詩さん不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
北海道2023(その7)
 Leadcoreさん
Leadcoreさん絨毯屋へようこそ … mihriさん
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.