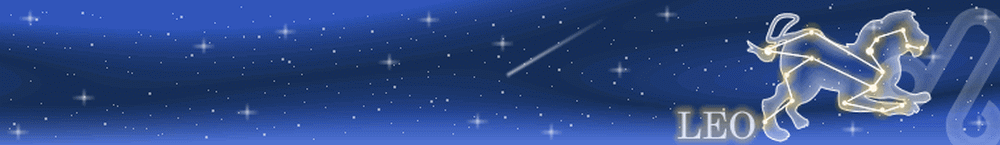2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年09月の記事
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
ロハスな生き方
これからのライフスタイルとしてLOHAS(ロハス)という言葉が注目されています。このロハスの考え方というのは、人がそれぞれ互いに異なった分野で本来生かすべき潜在能力を開花させるということでもあります。この考え方の人を見てみると、自分が得意な分野、好きな分野、自分が楽しめる分野をみんながそれぞれに持っています。最近好きなことを仕事にするということをよく言われますが、このロハスな生き方においては、まさにそれなので、ここには他人との競争という概念はありません。あるのは、ただ自らが自分のソース(根源)と繋がることだと思います。それは、無我夢中という境地で花が自然に開花するように、人の潜在意識というものも自然とと開花する方向に向かっている状態だと思います。努力とか頑張る必要はないのだと思います。しかし、常にこういう境地の人って新しいことに挑戦していると思うのです。成長する人は、けっして順調なところに安住しないからです。すると、そこには困難にも直面するかもしれない。ただ、この困難というのは競争社会での困難とはニュアンスが違います。ここでの、困難とは自分を高めるとかいう意味での困難なので、むしろそれを楽しむ感じの困難です。自分の可能性を広げるための挑戦みたいなものです。それで、努力とか頑張る必要はないのだけれど、何か自分を高める方向へ行きたいというような衝動に駆られます。それが、その人の天命というものなのかもしれません。それは、努力とか頑張るというものではないのですが、はたから見るとそう見えるようなものです。本人は楽しんでいるのですから。そして、そのことは周りのみんなにも喜ばれる事であります。人は、周りの人に喜ばれることで、もっと喜ばせることをしたいと思うからです。そして、こういうロハスな生き方の人が増えれば、競争ではない共生の社会に向かうと思います。これまでの価値観は、変わりつつあります。天国では時間という概念がないといいます。この現実社会でもそれと同じ境地があります。それが、無我夢中です。この境地の時って時間があっという間に過ぎていく感じです。それも充実感と共に。無我夢中になれるほど好きなことをすること。それは、ロハスな生き方に繋がるキーワードだと思います。ワンクリックありがとうございます
2005.09.30
コメント(4)
-
競争しなくても人は生きていける
競争しなくてもいい世界というものが理想としてあるとしても、矛盾するようですが、競争の世界も体験する必要はあります。なぜかというと、競争の世界で生きてきて、そこでの疑問を体感として感じるからこそ競争のない社会でないといけないということが言えるからです。これも、陰と陽の関係でコインの表と裏のように一体なので、表(競争のない社会)を実現したければ、その逆である競争社会も知らないといけないからです。そうでなければ、本当の意味での競争のない社会でないといけないということが心の底からは言えないのではないかと思うのです。そこには、苦しみとか辛さとか負の要因があるからです。そして、そういうことを体験として知った上で感じて気づくのです。そこから戦おうとはせずに、ただ受け入れる。ただ、それだけでいいのです。それを、競争のない社会にしないと・・とプラスに振れさせようとすると、陰と陽のバランスが崩れます。この世は、バランスでできているので、無理にバランスを崩そうとすると失敗するのです。そんな世の中の仕組みがモナリザの絵には封印されています。でも、なぜ今になってその秘密が明かされているのか?これまでにも、いろいろな優秀な方がその暗号を解こうとしました。でも、できなかった?それが、ここにきて「ダ・ヴィンチ・コード」という小説がベストセラーになり注目を浴びています。そして、その暗号を日本人の首藤尚丈氏が解いた。そこに日本人ってすごい何かを持っているような気がします。だから、その日本が変われば世界は変わるではないですが、まず、ここから変わることって起点になると思うのです。そして、そのもっと根源はひとりひとりの個人。そのひとりひとりの個人の心に問う言葉があります。それは、「どんな自分になりたいか?」ということです。別にこの答えに明確なものを出さなくてもいいと思います。ただ、そういう部分に感じる道を進めばいいと思うのです。その言葉に反する方向に行っていたら、自分というものを見失っているのかもしれません。競争しないということは、ただひとりひとりが自分になっていくだけでいいのです。他人の人生を歩むから競争するのだと思います。まずは、ここから。「どんな自分になりたいか?」ワンクリックありがとうございます★そんな事をテーマに一連したイベントです■10月15日(土)首藤尚丈氏講演会「モナリザを解く」詳しくはこちらから■10月22・23日ソース・ワークショップIN奈良詳しくはこちらから■10月30日てんつく祭り詳しくはこちらから
2005.09.29
コメント(0)
-
これからの時代のキーワード「LOHAS」
LOHAS(ロハス)という言葉をご存知ですか?このキワードは、これからのビジネスを考える上で頭に入れておきたい言葉だと思います。なぜそうなのか?を考える前にLOHASという言葉の意味を簡単に説明します。LOHASとは、Lifestyles of Health and Sustainability の頭文字をとった略語で、健康と環境に配慮した生活という意味です。ある雑誌でそのロハスに注目しはじめ、ロハススクールというものが特集されていました。それを読んでいて確かにこれからの時代のキーってこういうところにあると思いました。なぜなら、これまでのように規模の拡大や価格競争をしてばかりいたのでは、そこに携わるすべての人がWIN-WINの関係が保てません。しかし、このロハスを元にした考え方であれば、それができるようなヒントがありそうです。今の時点では、まだまだ知らない人も多いと思いますが、これからに時代を考える上でキーとなる言葉だと思いました。ワンクリックありがとうございます★イベントのお知らせ 10月15日(土) 首藤尚丈氏講演会 「モナリザを解く~上&中の巻」 「モナリザを解く」から生まれた更なる新事実 レオナルド・ダ・ヴィンチが名画に残したミステリー その謎を追う舞台をイタリアへと広げ モナリザミステリーの第二章の幕が開かれます。 建築家でもあり数学者でもある首藤尚丈氏が スライドを交えながら皆様を謎解きの世界へとご案内いたします。 謎には続きがあった・・・ 申込はこちらから
2005.09.28
コメント(5)
-
自分というレールを歩む
経済を拡大するという事は、あらゆる面で自分というものを見失わせるような気がします。19世紀的な考え方が、朝から晩まで身を粉にして働く、つくったものはお上に差し出す、規模の拡大、10年1日のごとく働くとしたら、21世紀的な考え方は、ゆとりを持って脳を活用する、作業の効率化を優先する、時間当たりの生産性を最大にする、市場(マーケット)と直接かかわる、今日の自分は昨日より進化しているというような考え方にシフトしてきていると思います。そういう方向になりつつあるのに、経済拡大にばかり目を取られていると、本当の自分というレールがあるとしたら、いつの間にか別のレールを歩んでいるという感じになるというような錯覚を起こしかねません。そういうような事を伝えている映画として、「キッド」という映画があります。主人公のブルースウイルス演じるラスは、40歳で仕事命のビジネスマンです。そんなラスのもとにある日一人の少年が現れます。その少年とは、8歳の頃の自分だったのでした。ラスはこの少年が現れたことで自分がガイドとなって自分が教えていると思ってました。しかし、本当は間違った方向に行こうとしているあなたに何かを伝えたくてあなたのもとに現れたのではないかとある女性に助言されます。そして、究極の質問をされます。「あなたは、人生で本当に価値のあるものを手に入れた?」「それは、お金には関係ないもの」その質問にラスは即答できませんでした。そして、しばらく考えて閃きました。それは、忘れかけている自分の中にあるということを。そして、どこかで踏み外したレールを探しに8歳の自分といっしょに出かけます。その結果、レールから外れている原因が分かりました。子供の頃のいじめが原因で大人になってもずっと本当の自分が表現できない自分になっている事に気づきました。そのあげく仕事命で人生で何が大切なのかを見失っていたのです。8歳のラスは感じていたのだと思います。人生で本当に大切なものは何かを。それは、自分が自分であるということです。それは、自分のレールを歩むということです。自分でないレールを歩んでいたから「人生で本当に価値のあるものを手に入れた?」という質問に答えられなかったのだと思います。そのレールを歩むということは、輝いているということだと思います。そして、輝く為にあともうひとつのフォースがあります。それは、この映画の最後にもでてくるものです。でも、見てない方の為にここではタネはあかしません。といっても、私がそう感じた部分なのであしからず。でも、こういう部分ってソースのセミナーと重なる部分です。ソースのセミナーも、こういうことを探していくというようなセミナーだからです。自分のワクワクの源泉(ソース)とやりたい事が重なった時、自分が楽しくてやっていることが、周りのみんなも楽しくしている。それは、自分探しとか自分発見とかいうものではなく、あなた自身のソースとつながる事です。そのソースとつながったとき、あなた自身が一番ワクワクしてて輝いている状態になっているのだと思います。ワクワクするということは、外でもなく内でもなく今ここにあるものです。あなたのソース(源泉)とつながることは、今こことつながります。それは、自分というレールを歩むということです。あなたの人生をドライブさせるワクワクの旅に出かけませんか?ソースの旅に。あなたのワクワクの源泉を探す・ソースワークショップ・2DAYS詳しくはこちらからワンクリックありがとうございます
2005.09.27
コメント(0)
-
ジャッジしないということ
ダ・ヴィンチのモナリザの絵は、相対する二つのものが合わさって一つの絵として完成しています。モナリザの絵を真ん中から分けてみると、向かって右側が男の顔。向かって左側は女の顔を示しています。背景の絵も、右側が地上世界(地獄)で左側が天上世界(天国)を示しています。まだまだこの絵には、深い暗号が隠されているのですが、序の段階としてこれだけでもこの世の仕組みを解いている気がします。映画「コンスタンティン」でも天国と地獄の相反することについて画かれていますが、ここにこの3次元の世界を思うように生きるヒントがあると思います。そのキーワードは、あるがままを受け入れるということです。あるがままを受け入れるとは、どちらにも振れすぎずにバランスを保つということです。いい悪い、プラスマイナス、長所短所、戦争平和・・・といろいろありますが、あるがままを受け入れるとは、ジャッジしないということです。例えば、プラス思考について見てみます。プラス思考するということは、すでにプラスに振れています。これでは、バランスが崩れてしまうことになります。プラス思考の元を辿るとマイナスから出発しているのです。そこには、思考が入っています。あるがままという境地では、思考が入りません。思考が入るとこの3次元の世界の迷路にはまってしまうようです。ここの部分って感覚で掴むようなものだと思うので、より具体的な例で見てみます。例えば、自分の仕事が好きになれないとします。まずは、ジャッジせずにあるがままを受け入れます。その上で一生懸命、一心不乱にその仕事に打ち込んでみます。そうすると、苦しみの中から喜びがにじみでるように生まれてくるものです。「好き」と「打ち込む」はここでいうバランスです。このバランスの均衡がとれていれば、好きだから仕事に打ち込め、打ち込めるうちに好きになっていくという循環ができます。ここまでくると、もう仕事に対する見方もおのずと変わってくるものです。さらに、いい循環ができると思います。座禅とかでも空になるとか言いますが、その境地も同じ感覚だと思います。その境地では、思考してない状態だからです。あるがままを受け入れてジャッジしないそのポイントは素直だということです。★モナリザを解く~首藤尚丈氏講演会IN奈良 10月15日 14:00~16:00 モナリザの絵に隠された暗号を解いていきます。 謎には続きがあった・・・詳しくはこちらから人気Blogランキング
2005.09.26
コメント(0)
-
ワクワクの波動
臨死体験とかモンロー研究所に行けば体験できるようですが、私自身は時間があれば体験したいなあという程度です。でも、確かにそういう世界はあるんだなあとは思います。臨死体験をされた事がある方の話を聞くと、あの世では時間の概念が無いくらい思いがすぐに現象となって現れるそうです。例えば、暗いことを思うとすぐに空が曇り始めて暗くなるような感じです。しかし、この世では、嫌な事を思っても時間があるので軌道修正ができるそうです。怒りを持ったとしたら、しまったと思う時間があるので修正がききます。あの世では、この軌道修正ができないので魂の波動が荒いと悪い状況から抜けられないような感じになるそうです。それで、魂はこの世でもっとその修正ができるように訓練したいのでこの世に出てきたがるそうです。宇宙の法則というのがあるとすると、自分がまいたものは自分に帰ってくるそうなのですが、あの世ではそれがすぐに帰ってくるという感じです。荒い波動をまけば荒い波動が帰ってくる。荒い波動とは、怒りとか不平不満、暗いことを考えるというものです。一方、ワクワクの波動をまけば幸せの波動が帰ってくるそうです。ワクワクの波動とは、感謝、笑顔、祈るとかいうものです。しかし、荒い波動でばかりいるとこのワクワクの波動が全く分からなくなるようなのです。解決方法としては、日頃から荒い波動になったとしても、この世では時間があるのですぐにワクワクの波動に転換すればいいようです。でも、これがなかなか簡単そうで難しいのです。何か嫌な事があっても「ありがとう」と感謝の言葉が言えるかどうか。これがひとつの方法とすると、あとひとつ方法があります。それは、常々ワクワクの波動の種をまいておくという事です。要は、自分がワクワクすることをしてれば、自分も楽しいしそれがまた帰ってくるとなると、ダブルで楽しめるので、ワクワクの波動の循環ができます。自分がワクワクするような好きなことをするということは、ひとつのキーですね。ワンクリックありがとうございます。★セミナーのご案内★■10月15日(土) 首藤尚丈氏講演会 詳しくはこちらから■10月22~23日 ワクワクの源泉探し~ソースワクショップ 詳しくはこちらから■10月30日(日) てんつく祭り 詳しくはこちらから
2005.09.25
コメント(0)
-
みんながてんつくマン
今日は、10月30日に開催するてんつく祭りのスタッフミーティングに参加してきました。てんつく祭りとは、てんつくマンの映画上映会やトークライブ、アコーステックライブなどを通して彼のメッセージである動けば変わるというものを体感してもらう趣旨で行うイベントです。我々スタッフもその日に向かってミッションを決めました。それは、みんながてんつくマンです。これは、てんつくマンのようになるという意味ではありません。どういう意味を込めているかというと、てんつくマンの名前の由来が天国をつくる人からきているので、てんつくマンになるということは、ひとりひとりが天国をつくる人になるということを込めています。池に石を投げると波紋が広がるように、このイベントがきっかけでその輪が広がっていく。そんなことをイメージしています。私も昨年このイベントを奈良と京都で主催して実際にこのような現象が起きました。その時、来ていただいた大谷さんが実際にカンボジアの支援状況を視察しに行きました。それで、いかに報道されていることと実際のズレがあることが分かり、その現状の問題点はどこにあるかを伝えたいということで現地で支援されている日本人の奥田氏とその真意を汲み取って活動されている現地のテックナル氏を京都に迎えて講演会を行いました。このように、ひとつのイベントがまた次に繋がりました。その時の日記です。てんつくマンは言います。死んでから天国に行って幸せになってもしょうがない。生きている今を天国にして、死んでもう一回天国というダブルチャンスで行きましょう。人生はやっぱり楽しんでなんぼです。日本から世界を面白くしましょうと。てんつくマンになる。それは・・・ひとりひとりが天国をつくる人になるということ。そのきっかけをここで掴みませんか?動けば変わる
2005.09.24
コメント(5)
-
そこにいたという偶然が・・・
得意先の歯医者さんの隣が空き地になっていて、2ヶ月くらい前からそこに犬が捨てられていたそうです。それでも、この歯医者さんや近所の方たちがエサをあげたりしていたので、その空き地がその犬の家みたいになっていて、その場所に馴染んでいました。散歩とかもこの先生の飼っている犬の後についてきたりして、人なつこい犬だそうです。今日、たまたまその先生の診療室の外でそんな話をしてました。すると、3,4名くらいの役所の職員みたいな人が「こっちにおいで」とか言って捕まえようとしていました。それで、その先生がその犬を捕まえて、どのように保護するのかを聞きました。すると、捕まえた後は、処分するような事を言われたそうです。それで、その先生はそれなら自分が買うからと言ったので、それならいいですよということで役所の人は帰っていきました。たったこれだけの事が数分で終わったのですが・・・もし、その日のその時間にしかも外で先生と会話してなかったら・・その犬は、どこに行ったのか分からなくなる所でした。この犬は先生の娘さんもかわいがっていたそうなのでなおさらどこかへ行かなくて良かったです。それにしても、ペットの飼い主は責任を持って飼ってほしいですね。ほんのちょっとの違いで殺されてたかもしれないのですから。勇気を持って買うと言ってくれた先生にありがとうございますです。10月30日 秋のてんつく祭り開催人気Blogランキング
2005.09.22
コメント(0)
-
遊びをガイドする
今日は、京都の雅幸塾の定例会に行ってきました。幸塾では、毎回ゲストを招いてお話をしていただくのですが、今日のゲストはうぇいくさんでした。うぇいくさんは、子供に遊び方を教えるような「遊び力を育てる」という小冊子を書かれています。その小冊子がどこでどう伝わったのか京都新聞が面白そうだということで取材にきたそうです。そういうこともあってかどうかは、分かりませんが、この小冊子かなりの反響があるそうです。この話を聞いてなるほどと思い当たる方の話を思い出した。その方はアウトドアのライフスタイルを提案している方なのですが、その方の話によると、最近の子供はキャンプ場とかで自由にさせておくと、遊び方を知らないから指示を待っているそうです。この話から遊び方をガイドして大人と子供がお互いに楽しめる教材みたいなものがあったら確かに需要はあるしニッチな部分で面白いと思いました。実際にどういうことかというと、例えばアウトドアでの子供達に指導するワークとして、そこらじゅうに落ちている枝や木でエンピツを作ったりするワークがあります。そこでは、実際にナイフを使って木を削ったりするのですが、そこで手を切ったりする子供もいるそうです。でも、そのミスが実は狙いでここに大きな学びがあるのです。それは、自分が怪我をすることでナイフで切るという事がこんなに痛いということを認識します。認識するとそれを人に対して行ったらどういうことになるかを本能的に学ぶそうです。そんなふうに大人は何もせず子供に考えて行動してもらうような機会を与えます。すると、自分なりに考えて行動して考える力がつくようなのです。ちょっとしたことのようですが、こういうことが実は今忘れられているような感覚としてあるようです。そんなあるようでなかったものを思いつくセンスの良さみたいなものをうぇいくさんの話から感じました。なるほど、という感じでした。ありがとうございます
2005.09.21
コメント(0)
-
感じて、気づくということ
感じて気づくということは、要は「受け取る」ということです。この「受け取る」ということについて例を上げてみます。感覚を掴んでみて下さい。受け取るということは、あなたという花を開花させる方向に運んでくれます。そのポイントは「今この瞬間を楽しんで生きる」ということです。生きてても今を楽しんでなければ、それは死んでいるのと変わりません。それでは、下の例からそのコツを感じてみて下さい。ある勉強会に車イスの方が来ていました。その方は「受け取る」ということに抵抗感がありました。なぜかというと、自分は車イスなので勉強会とかに来ると誰かの力を借りないと階段にも昇れないからだそうです。それで、自分が車イスだということが周りに迷惑をかけていると思いうと嫌な気分になる自分を感じていたそうです。ここでひとつのポイントがあります。それは、嫌な自分を感じるということです。なぜなら、嫌な事と楽しい事はコインの表と裏のようにセットだからです。セットなので、嫌な事を知らないと楽しい事も知り得ないのです。嫌な事に目を伏せて逃げると楽しい事も手に入れる事ができません。それで、ここでは、そんな自分をただあるがまま受け入れる必要があります。「嫌な自分」も認めてあげるということです。このようにして認めてみると実は嫌だと思っていたことにも、いい部分が見えてきたりします。周りに迷惑をかけていたと思っていたことが、実は周りの人を幸せな気分にしていたのです。どういうことかというと、周りで手伝っている人たちは、車イスのその方を手伝うことで「愛」とはどういうものかを体感できているからです。そして、その事に対して素直に心から「ありがとう」と言えるのです。車イスの方も、周りを信頼することで自分も周りの人に愛を与えているのだと感じて心から「ありがとう」と言えるのです。そして、お互いが「ありがとう」と「ありがとう」のいい循環ができます。つまりは、お互いがハッピーな状態になるので、これは今この瞬間を生きている状態と言えます。今この瞬間を生きているエネルギーは、あなたを開花の方向へと運んでくれます。運ぶというと何もしなくてもいいようですが、そうです。何もしなくてもいいのです。何もしなくてもいいのですが、次のサインがあるようです。サインとは、あなただけにしか感じることができないような内からこみ上げてくるようなものです。このサインは衝動というものだと思います。この衝動はあなただけにしか感じることができないものです。この衝動の方向へと行くという事は、あなたの道を歩んでいる。そういうことなんだと思います。他人の人生ではなく自分の人生を歩むということです。そうでないと、自分の人生は楽しめません。答えは外でもなく内でもなく、今ここなのです。クリックありがとうございますイベントの紹介★10月15日「モナリザを解く」首藤尚丈氏講演会IN奈良 弟4回船井オープンワールドでも講演されます。 申込み★10月22・23日 自分発見「ソース」ワークショプIN奈良 申込み★10月30日 大阪KOKOPLAZA てんつくマン・トークライブ&映画上映 申込み
2005.09.20
コメント(0)
-
開花のエネルギー
自分が何者になろうとしているのか?この答えはなかなか出せるものではないと思います。なぜなら、この答えは一生かかって追求していくものだからです。経営という言葉が「真理を一生かけて追求すること」であるならば、私という個人も自分というものの経営者なので、自分というものも「真理を一生かけて追究していく」ということになります。そうして人は、その鍵を探すためにそれが外にあると思い、外を探す。あるいは内にあると思い、内を探す。しかし、探す必要はないのだ。探すのではないのです。なぜなら、その花は今ここに咲いているのだから。では、探さないのであれば、どうしたらいいかというと。感じるということです。感じて気づくこと。「あ、そうか」というような感覚です。あなたという存在が船だとしたら、その船は開花の方向へと運んでくれているのかもしれません。しかし、日常生活で日々忙しくしていたりしていると、この感じて気づくというアンテナが錆びている可能性があります。感じて気づくことが自然とあなたを開花の方向へと運んでくれているとしたら、大切なことは探す事ではなく生きることになります。ただ、この「生きる」ということが問題なのです。生きるということは、今この瞬間を楽しめているかどうか?です。生きてても死んだようになってたら、それは今を生きてないのです。でも、楽しめてないとしても、なぜ自分は楽しめてないのかに気づけばいいのです。気づいて「あ、そうか」というこの感覚が分かれば、それはもう消えているのです。ということは、これができていれば、自然と開花の方向へと運ばれているということです。それで、自然と開花の方向へと向かうのですが、それは無限なので、一生を賭けて真理を追求していくということになるのだと思います。人気Blogランキング
2005.09.19
コメント(0)
-
ホスピタリティーとは、
昨日は、友人が主催しているオーガニックランチパーティに妻と参加してきました。マクロビオテックの食事をしながら豊かな時間を共有しようという趣旨で開催されたのですが、この会に対する友人はじめスタッフの思いが伝わってくるいい食事会でした。主催した友人は、ホスピタリティーを感じてもらいたかったそうです。ホスピタリティーというと横文字で分かりずらいのですが、要は心からのおもてなしということです。以下リッツカールトンが大切にする「サービスを超える瞬間」から抜粋トップ5%の感性を大切にする。トップ5%の方にサービスを提供するというのではなく、トップ5%の方の感性を満足させるようなサービスを提供するということを目標にしている。ホスピタリティーとは心からおもてなしをするということです。お客様に感情を示す事です。リッツカールトンは宿泊産業ではなく、ホスピタリティー産業である。ある自動車メーカーは、私達は車ではなく車を運転しているときのワクワク感や快適さを売っている。ある歯医者は、「歯が痛くなくてもここへ来たいなと思える空間を提供している。引用ここまでなるほど、ホスピタリティーとはこういうものなんだな、と体感できた会でした。この感覚をお客さんに感じてもらいたい。それがまた次へ。そしてまた次へ。形は違うけれどそんな輪がどんどん広がっていくような感覚。何をするにもこの感覚って大切だと思います。人気Blogランキング
2005.09.18
コメント(0)
-
見通すということ
「見る」というのではなく「見通す」。見るというだけでは、分かってないんですね。見通してこそ分かるという領域にくるのです。例えば、低燃費自動車とか環境にいいとされている自動車があります。これを「見る」という観点から見ると、確かに燃費もよくて排気ガスも少なくてすむので環境にいいと見ることができます。しかし、「見通す」という観点から見るとどうでしょう。この電気系統のエンジンを作るために普通の自動車を作る以上のエネルギーがかかっているそうです。ここの細かい所は、専門ではないので詳しくは書けませんが、詳しく調べている方から聞きました。それによると、この車を廃棄する時も、普通の自動車を廃棄する時以上の経費がかかるということです。だから、逆のことをしているのです。コマーシャルとかでは、環境にいいとかうたい文句にしてますが、見る人が見れば逆にそんなこともないという事が見通せるのです。こういったことって、なかなか見通せてないのではないでしょうか?私もこれを聞くまでは勘違いしてました。ジェレミーリフキンが書いた「エントロピーの法則」という本によると、人間が進歩だ進歩だと思っていることのほとんどは退歩しているのだといいます。ひとつ自動車の例を上げてみます。人間は、自動車に乗って高速に移動する事ができるようになった。これは、ものすごい進歩みたいだけれど、それは勘違いですよ。あなたは、車を買う為に何時間働いていますか。車検代、保険料を払うために、燃料を買う為にものすごい時間、何百時間も何千時間も働いた結果、車に乗って移動しているだけだ。アフリカのサン人などはあそこに行きたいと思った瞬間に歩き出すという。皆さんは車を買う為に何千時間か働いてから移動する。実際にはみなさんのほうが遅いよと言っている。しかも、エネルギーを浪費している。みなさんが頑張れば頑張るほど地球は壊れますよと言っています。進歩の逆にあるものをしっかりと見通す目を持ちたいものです。人気Blogランキング
2005.09.17
コメント(0)
-
秋のてんつく祭り
昨年奈良と京都でてんつくマンのイベントを主催したのですが、今年もスタッフとしてイベントの開催にたずさわることになりました。今日はその宣伝をします。日時は、10月30日(日)開場12:00場所は、大阪のKOKOPLAZA今回は3部構成で映画上映にトークライブにライブにと盛りだくさんで行います。第一部は、「107+1~天国はつくるもの~」総指揮・監督 てんつくマンの映画上映会第二部は、てんつくマントークライブ、森源太ライブ、丸山茂樹ライブ そして、3人のコラボによる巨大書き下ろしをします。第三部は、てんつくマンがあなたを見てインスピレーションを感じた言葉を書きます。こちらは、希望者のみで別途費用がかかります。動けば変わるという「てんつくマン」のメッセージを体感てみませんか?申込・問合せはこちらから人気Blogランキング
2005.09.16
コメント(0)
-
アクセスアップさせるタグ
HTMLタグというホームページを表示するための言語がありますが、このHTMLのタグで検索結果を上位表示させるタグがあるのをご存知ですか?上位表示されるということは、アクセスアップにつながります。以下に私のセミナー案内を例に書いてみます。タグはすぐどこで使われているかはすぐに分かると思います。一番はじめのタイトルです。でも、セミナー案内も見ていただきたいので種は最後にあかします。PASONAの法則を基に書いていますので参考にしてみてください。ソース・セミナーのお知らせ天国と地獄の違いが死ぬときにあるという話をご存知ですか?死ぬときに「やったね」と言って死んだ時が天国、「もっとやっておけばよかった」と思うのが地獄。だとすると、この「やったね」は日々の一瞬一瞬が満たされているからこそ言える言葉なのです。満たされている為に必要なのは、「あれがしたい」「これがしたい」と「すること(Do)」でもなく、「あれが欲しい」「これが欲しい」と「所有すること(Have)」でもありません。「なぜそうしたいのですか?」と問われると、そうした体験や所有の結果、得られると信じている「在り方(Be)」なのです。しかし、急ぎ足の日々を過ごしているうちに、本当の自分を見失ったり、ズレが生じている場合があるかもしれません。でも、心配することはありません。あなたはただ自分の中にあるワクワクする種を忘れているだけです。大切なのはあなただけのオンリーワンの種を開花させる事であり、それは、忘れていたものを思いだすということなのです。あなたの心の奥深くから届く声に耳を澄ませてみてください。砂金を拾い集めるように、内なる声を拾い集めてそれがひとつになった時、自分の姿がはっきりと見えてくるようになり「在り方(Be)」もわかってくるでしょう。本当の自分を思い出し、そして進む方向がはっきりして初めて、そこへ到達する事が可能になります。あなたの人生をドライブさせるキーを捜す旅にでましょう。ワクワクを発見する「ソース」の旅です。追伸:「私はなぜ生まれてきたのか」このシンプルな質問に答える事を、人生の後回しにしないで下さい。時間切れにならないうちにという感じですが、この「ソースセミナーのお知らせ」という部分のタグに秘密があります。ここの部分を<h1></h1>でくくってあります。<h1>の数字の部分は1~6まであります。GoogleやYSTでは、<h1>タグに書かれている記述が検索結果に反映されるそうです。ただ、すぐには反映されず1ヶ月くらいはかかるみたいです。だけど、注意しないといけないのはページ全部をくくってしまうとスパム(不正行為)になるので、そこだけは気をつけないといけません。ちょとしたことですが、使えるテクニックとして紹介しました。試してみて下さい。人気Blogランキング
2005.09.15
コメント(0)
-
ふみ越える
ドストエフスキーの小説「罪と罰」の中で「ふみ越える」という言葉がしばしば、それも極めて重要な個所で使われています。最近以前から読みたいと思っていた「罪と罰」をやっと読み終えました。以下、少しだけ感想を書いてみます。「罪と罰」の主人公ラスコリーニコフは、金貸しの老婆を殺害します。犯行後、証拠を隠すために奔走する一方、高熱を出し悪夢にうなされたり、周りの人に奇異に映る言動を繰り返します。やがて彼は家族をささえるためにやむをえず売春婦をしているソーニャという娘に出会う。彼は、ソーニャーに老婆を殺害したのは自分だと言う事を告白します。そんな告白を聞いた彼女は「大地にキスしなさい」と言い、さりげなく自首をすすめます。~以下引用「ぼくが、あのとき、一刻も早く知りたいと思ったのは、自分がみなと同じようにしらみなのか、それとも人間なのか、ということだった。僕はふみ越えることができるのか、それともできないのか!」~ここまで逡巡の末、彼は自ら警察に向かいます。ソーニャーは彼が本当にふみ越えられるかどうか心配でずっとその後を気づかれないように尾行しました。それで、彼は告白しようとしたのだが、告白できずに帰ろうとした所、死人のように真っ青な顔をしたソーニャが立っていて、不気味なばかりのけわしい視線を彼に注いでいた。~以下引用彼は、その前に立ち止まった。何か痛ましい苦痛にあふれたもの、何か必死なものが、彼女の顔にあらわれた。彼女の口もとに、形にならない、途方にくれたような微笑がうかんだ。彼はしばらくその場につっ立っていたが、やがて苦笑をもらし、後ろを向いて、ふたたび警察署にあがって行った。~ここまでこの部分は、ずっと読んでいてここの箇所にくるととても印象深いシーンのひとつでした。それで、ソーニャも彼と共にふみ越えて行きます。ここでのふみ越えるとは、共に罪を背負うという意味です。ラスコリーニコフは、彼女にこう言います。「君もふみ越えた・・・ふみ越えることができたじゃないか」そして、彼への判決は8年間のシベリア徒刑だあったが、ソーニャはその地に赴き、彼をずっと見守り続けます。シベリアでの1年が過ぎようとしていたある日、それまで心を閉ざしていたラスコリーニコフは、突然ソーニャの足元に身を投げ出し、彼女の膝を抱きしめながら泣き出します。そこで、ソーニャはラスコリーニコフが自分を限りなく愛している事を知ります。こうして、ソーニャの愛によって救済され、復活した殺人者の物語は終わります。ドストエフスキーはこのように書いています。「彼らを復活させたのは愛である」と。愛こそが生命の源泉にほかならないと。ラスコリーニコフは、確かに罪を犯しました。でも、そこに受け止めてくれるソーニャがいなかったら獄中で自殺していたかもしれません。ラスコリーニコフがふみ越えられたのは、ソーニャの愛があったからこそです。でも、何事をするにも、ここが基本だと思います。すべての事は、形は違ったとしても、本質は愛を伝えていくことなんだと思います。そこに愛が込められているから感動が伝わるのだと思うからです。その源泉は、パートナーにありですね。人気Blogランキング
2005.09.14
コメント(0)
-
ピラニア
琵琶湖でピラニアが発見されたそうです。ピラニアは人でも食べる獰猛な魚なので、海水浴やボートなどのレジャー客にも影響がでそうです。それにもっと大切な事は生態系が崩れてしまうことです。ピラニアに比べると今までに問題になっていたブラックバスやブルーギルというのは、かわいいものです。誰かのモラルなき行動がここから出て行かざるを得ない誰かをつくるかもしれません。それで、商売が成り立っていた人もいると思いますから。これと似ているのですが、私が仕事で歯科医院を訪問している時もこんな状況に出くわす事があります。それは、今までわきあいあいとスタッフ同士が仕事をしている中にピラニアみたいに場の空気を乱す人が入ってきた場合のことです。すると、いい人がいつのまにか辞めていってさらにまた・・・という現象が起こったりします。そして、そのピラニアは居座ります。一見すると、仕事はできるのかもしれない。だけど、仕事はチームとしてするのであって、その輪が乱れていては単なる個人プレーに過ぎないと思うのです。でも、ここで問題なのは、その変化に鈍感な経営者(院長)なんですけどね。日頃から働いている人の方が、何気ないようにしてますが経営者の人間性というものを鋭く見ています。だから、それを見抜けない経営者に愛想をつかす部分もあると思うからです。こういうケースでも、見通すということの大切さが分かります。ただ単に見ていたのでは分からないかもしれない。でも、鋭く見通す力があればどこに問題があるのかを直感で分かるくらいに場の空気が読めると思うのです。歯科医院の場合は会社でいうと小さな会社みたいなものだから、いいスタッフがいるかどうかは重要なファクターになります。そういういいスタッフが辞めるとき、場の空気が読めない経営者は簡単に辞める事を了承し引きとめもしません。ただ、引き止めても事の本質が分かってないから無理なんですけどね。つまりは、見通せてないんですね。その結果「給料もう少しあげるから」というような火に油を注ぐような事を言ってしまいます。「よく見る」ということは「見通す」だということです。この深さを感じられる感性って何をするにも必要だと思いました。人気Blogランキング
2005.09.13
コメント(0)
-
五事を大切に
経営とは、真理を一生かけて探求すること。こう言われる高木善之さんの経営塾に2日間参加してきました。はじめに塾とは何かから始まり、環境問題の現状を説明されました。最近では、アスベストの問題がありますが、この問題は92年に問題提起されていたのです。しかし、業界が阻止した為に見送られ、今になって表に出てきた事件です。他にも2005年7月7日の毎日新聞でも胸部X線廃止・厚生省有効性に疑問という記事があるのですが、この疑問というのはすでに危険だということなのです。職場の健康診断とかでX線写真とか撮っているとしたら辞めといたほうがいいかもです。私もX線の怖さを知っているので歯の治療をする時も、X線を撮らないようにしています。他にもたくさんの事例を見ましたが、結局いい事をしようとしても、その事が可決されると困る団体があるので、環境によくて本当にいいものがあったとしても、流通しにくい社会構造になっているのが現状です。ただ、こういう環境問題は本質ではなく本質は五事を大切にということを説明する為に例として環境問題を取り上げられました。五事を大切にとは、よく見るよく聴く受け止める分かる変わるということなのですが、この「よく見る」というのは、事の本質を見通すとという意味なのです。だから、先にあげた環境問題なども、その裏まで身通すという意味で例として上げたのでした。その為には命がけで見通さなければなりません。「よく聴く」「受け止める」も同じです。それが本当にできた時、「分かる」ということです。分かるとは、本当に自分が変わる決断をしたときで今までの事から訣別するという事です。それで、「分かる」という段階にくれば、おのずと「変わる」ということです。ただ分かるという意味ではなくそこには、こんなに深い意味があったのでした。経営塾ということで経営の事を勉強するかというと、そうではなくどちらかというと経営者としての考え方に重点を置いた内容になっています。というのも、このままの経済状態でいくと、経営の手法どうこうを言っている場合ではなかもしれないからです。大きな流れとして地球自体は存続すると思いますが、環境破壊で我々が住めなくなる可能性があるからです。でも、そうなったとしても「やったー」と思える人生を生きればいいのです。その為には考え方が大切になってきます。例えば、あなたが今飛行機に乗っていたとします。そしてその飛行機は、30分後に墜落するとします。その状況のとき、日頃からやるべき事をしていて「やったー」と満足して死ねますか?それとも、「ああ、あれもしとけばよかった」と後悔を残しますか?大切なのは、そういう時がいつきてもいいような生き方です。そんなスピリッツを高木さんに五感で感じた二日間でした。人気Blogランキング
2005.09.11
コメント(0)
-
言葉に感謝を添えてみる
感謝の言葉を会話に添えると相手の心に伝わるものがあります。和田裕美さんの本を読んでいたら目にとまる箇所があったので引用してみます。例えば、いつもより早く会社に来て欲しいとき、「明日、七時に来てください」というより、「申し訳ないけど、明日七時にきてください」さらに、「申し訳ないけれど、明日七時に来てくれると嬉しいんだ」と言えば、もっと伝わるものがあります。また、相手が気持ちよく動けるには危機感と可能性をミックスさせた言い方をすると効果的なんだそうです。例えば、「何度言ったらわかるんだー」よりも、「何度言ったらわかるんだーやればできるのに、もったいないだろう」とか、「何度言ったらわかるんだー期待してるからがかりさせないでくれよ」とか、危機感と可能性を同時にみせるといいそうです。この部分、共感するものがありました。「ゴミ捨ててきて」と言われるより、「ゴミ捨ててきてくれると嬉しい」と言われるほうが気持ちよく動ける気がします。ちょっとだけ感謝の言葉を添えるだけで、確かに違うなあと思いました。日常で使えると思うので実践したいものです。人気Blogランキング
2005.09.09
コメント(0)
-
動けば変わる
今日は、中村文昭さんの主宰するRYO-MA倶楽部に行ってきました。話は、竜馬の話からはじまりました。竜馬が勝海舟を暗殺に行った時のことです。その時、竜馬は暗殺するつもりだったのに海舟の話にすっかり虜になり弟子にしてくれと頼むのである。この話に似ているのだが、中村さんがある人物に会ってこんな気分になった人物がいました。その人の噂は以前から聞いていたそうです。そして、すごい奴だなあと思っていて、いつか会いたいと思っていたそうです。それで、先月初めて会ったということです。その人とは、だれかというと・・・てんつくマンです。それから、てんつくマンのお金をかき集めて映画を上映するまでの経緯や映画の感想などを交えて話されました。それで、彼の信条が動けば変わると言う事なので、RYO-MA倶楽部でも何かひとつのものを創ってみようという話になり、各テーブルごとに意見を出し合いアイデアを出したりしてました。このつづきは、また中村さんがまとめて大阪らしいものをつくってまたみんなと話し合いましょうということになりました。てんつくマンのイベントは、10月30日に開催するのに私も関わっているので偶然ですが、いいタイミングでいい宣伝になりました。今後二人でジョイントライブでもしようかという話もあるそうなので、これが実現したら面白いものになりそうです。動けば変わる動けば変わるてんつくマンの映画そのもののメッセージです。見てない方は、ぜひ。10月30日 日曜日 大阪KOKOPLAZAにて「107+1~天国はつくるもの」映画上映てんつくマンをお招きしてのトークライブ、書き下ろしもあります。そして、森源太のライブコンサートも。人気Blogランキング
2005.09.08
コメント(0)
-
アウトドアはビジネスになるか?
アウトドアというと思い浮かべるのは何だと思いますか?多くの方が思い浮かべるのがキャンプだそうです。私もキャンプは、よく行きます。今年から農業を始めたのもアウトドアとの関連もあるので始めている部分もあります。というのも、アウトドアを利用したイベントを考えているからです。今のところ、マクロビオテック、農業、とコラボできそうな方たちがいます。私は、やりたいイベントに対するキャンプ場のセレクトや大人と子供がそれぞれに楽しめる構想などにアイデアがあるので、そういう方々と組んで面白いことができそうなのです。キャンプ場といっても、せっかくいいロケーションにあるのに、うまく活かされてなかったり、休眠状態のキャンプ場って意外と多いのです。要は、ソフトのノウハウがないのとサービスが悪いのでリピートに繋がらないのだと思う。私が考えているのは、そういう休眠状態のキャンプ場を借り切って何か面白いことができそうだというものです。でも、その時に必要な設備があります。それは、コテージかバンガローがあるキャンプ場です。シーズンまっただ中で借りることはしないので、ここは必須条件になります。でも、もしキャンプ場を経営する立場だったら、このコテージとかバンガローがないと経営が成り立っていかないのでは?と思う。キャンプ場のサイトって普通5,000円くらいなので管理する手間とか考えると単価が高い商品つまりキャンプ場でいうとコテージがないと売り上げが上らないからです。それに、コテージがあれば冬でも来るお客さんはいると思います。テントサイトだけでは、冬はキャンプ好きの人しか来ないですから。アウトドアは、ディズニーランドのようにリピートしたいと思わせる仕組みをつくれれば求められている事なのでビジネスとして成り立つと思います。ただ、ディズニーと違う点は、アウトドアは何もないところから自分で楽しさを探すという部分があるので、その部分をどのようにして誘導していくかが鍵ですね。人気Blogランキング
2005.09.07
コメント(0)
-
カゴメ歌の真実
郵政民営化をすると、そのお金を虎視眈々と外資が狙っているという説もありますが、大きな流れからいうとこのことは起こるべきして起こっている出来事らしいのです。大きな流れとは一般論ではなく神がかり的な視点で見てみた場合のことです。それは、どういうことかというと・・・(澤野大樹氏の記事を引用)この歌にヒントがあります。かごめ かごめ かごの中の鳥はいついつ出やる 夜明けの晩に鶴と亀がすべった後ろの正面だーれまず、「かごめ」とは、「ろくぼう星」「ダビデの紋章」とも呼ばれる図形のことです。これは、エネルギーの中心という意味で、つまり「岩戸」のことです。「かごの中の鳥」は、身の自由が束縛されている状態のたとえとすると。閉じ込められた天照大神だそうです。「いついつ出やる」とは、いつになったら外にでられる?「夜明けの晩に」は新しい時代に入る直前だとすると・・。現在で言えば、「9 ・11衆議院選挙」ともいえる。そして、鶴と亀がすべった。この亀はすぐ思いつくと思います。亀井氏のことです。それでは、鶴はというと?マスコミ関係で鶴のタブーというのがあるそうだが、この鶴とは、創価学会についてのタブーを鶴のタブーというそうです。でも今回の選挙では公明党と自民党は連立していて公明党の敗北の可能性は低い。とすると、選挙後に何か起こるのか?で、「後ろの正面はだーれ」ですが、これは、この流れを遂行している人物。つまり、小泉首相のことです。さらに、この大きな流れが成就した時に示される世界の状態もしくは状況のことだそうです。郵貯350兆円を放出するということは、(かごめ)岩戸を開くこと。そう考えると、(かごの中の鳥)天照大神は、お金と考えられます。お金は価値の象徴であり、お金は人が価値を認めて初めて「お金」となる。つまり、お金=人の心なのです。郵貯350兆円は、日本人の心の総体であり、このお金が放出されるということは・・・天照大神が天の岩戸からでてきて、この世に明かりを灯したように、そのお金が放出されることはアセンションに繋がることなのかもしれません。すべては、大きな流れの仕組まれたようなものがあるようですが、それくらい、小泉自民党が勝利することには意味があるそうです。好き嫌いは別にして。もし、敗北したら、地球人類のアセンションも遠のくことになるそうです。でも、そういうことを外資ハゲタカも小泉さんも知らないような、それはまるで計画されたような大きな時の流れみたいなのです。そして、その結果は今週末に・・・果たしてどうなるのか?首藤尚丈氏講演会IN奈良ソース・ワークショップIN奈良人気blogランキング
2005.09.05
コメント(0)
-
臨死体験で見た不思議な世界
昨日、木内鶴彦さんという天文学者の講演を聞きに行って来ました。臨死体験というと怪しそうですが、この方は22歳の時に実際にその体験をしたそうです。本人もどちらかというとそういうものを信じていなかったそうですが、見てしまったからには信じざるを得ないし、実際に現実の形として自分の中では実証されたそうです。それはどういうことかというと、臨死体験をしている中で意識は、はっきりとあったそうなのです。でも、自分はベッドにいる自分を見ている。父親は、先生から自分が死んだと説明を受けている。そんな、状況だったそうです。それで、母親はどこに行ったのかと意識したらすぐ母親の場所に行けたそうです。このことから、自分が意識したらその場所に行けると思ったそうです。こういうことが解かったのでそしたら過去にも行けるんじゃないかと思ったそうです。それで、一番行ってみたい過去を思い出したそうです。すると、子供の頃に、「あ、危ない」という声がしてとっさに姉の背中を押したら上から落ちてくる石から反れて軽い怪我ですんだ出来事があったそうです。でも、その後兄からお前が押したから怪我したんだと散々怒られて悔しい思いをしたのでその時の事をよく憶えていたそうです。それで、あの時の「危ない」と言ってくれた人は誰だったのかを知りたくなって、その過去に行きました。そして、今にも石が転がる寸前になりました。あ、転がると思ったときとっさに「危ない」と叫びました。「あれ、なんだあれは自分だったのか」結局あの声は自分だったことが解かったのでした。それなら・・・未来にも行けるんじゃないか?そう意識すると、10年後の近未来へと行けました。すると、そこは、砂漠のような世界でした。このままでいくと、99,99%の確率でそうなるかもしれないそうです。でも、0,01%は、すばらしい世界になる可能性もあるそうです。その分岐するもののキワードは・・・お金です。どういうことかというと、お金のいらない社会を実現できるかどうか?これを実現すると人間の進化の道となるそうです。でも、もし砂漠のような状況になったとしても、意識体のレベルでは時空がないのです。ということは、死ぬときに「やったー!」と思って死ねれば、それは天国になるのです。「やったー!」という意識はずっと続くのだから。一方「あの時ああしてればよかった」とかいう思いで死ぬと、それが地獄になるのです。意識と身体は別だと考えると、この借り物である身体の能力を自分の意識で最大限に発揮できるように眠っている能力を引き出してやる必要があります。その能力は、ひとりひとりが見出していく必要があります。そういうものを見出すのにソースのセミナーとも繋がるものを感じました。何か最後にくっつけた感じになりましたが、そのソースのセミナーを奈良で開催します。あくせくする人生ではなく豊かな人生を、見出しませんか?10月22・23日 ソース・ワークショップIN奈良人気Blogランキング
2005.09.04
コメント(2)
-
謎には続きがあった・・・
この世は、相対する二つのものから成り立っているという陰陽二相一対という理論があるのですが、モナリザの絵も相対する二つのものが一つになっています。陰と陽は、コインの裏と表のようにきってもきれない関係にあります。右手左手、右脳左脳、戦争平和、健康病気、男女、天国地獄、幸せ不幸、、、、というように、この世は、すべてふたつのものから成り立っています。だから、そのものの本質を知るには、ただそのものを受け入れる必要があるのです。病気を受け入れれば、その後には健康があります。でもそこから、逃げるとその反対にある健康を受取れないのです。短所を直せば長所も消える。だから、短所は短所で必要なのです。ただ、あるがままを受け入れるだけでいいのです。そう考えるとプラス発想というものが間違っているかということが分かるかと思います。プラス発想すると同時にマイナスも引っ張ってくるからです。プラスもマイナスも含めてただあるがままを受け入れる。この感覚でいったほうが、考え方が楽になります。「ダヴィンチ・コード」という小説で、そのへんの事が面白描かれていますが、モナリザの絵には、いつかこの暗号を誰かが解いてくれるのを待つかのようにいろいろなメッセージが封印されています。謎には、まだ続きがあったのです。その謎をこの方の講演を聞いて学びませんか?10月15日(土) 「モナリザの謎を解く~上&中の巻」IN奈良首藤尚丈氏講演会人気Blogランキング
2005.09.03
コメント(0)
-
普段とは違ったものに接する
この前、デビッドバーンのライブビデオを久々に見ていたら、コンサートかミュージカルにとても行きたくなってきました。それで、前々から予約してあったミュージカルに行って来ました。そのミュージカルは、マンマミーヤです。劇団四季のミュージカルは、はじめてでしたが、このミュージカルはとても良かったのでお薦めします。その他にも、行こうと思った理由は、小阪裕司さんの影響があります。今年、小阪さんのセミナーを受講している時、クイーンの曲がセミナーの休憩中などに流れていました。なぜこの曲が流れているのかというと。最近、クイーンの曲を題材としたミュージカルに行ったからだそうでした。それで、いつもと違うものに接する事でそれがビジネスのヒントになったりするということを言われてました。その言葉がけっこう頭に残っていたのです。今日のミュージカルを見てまさしくそうだなあと思いました。このミュージカルは、アバの曲をベースとしているのですが、全部日本語に訳したものを歌っています。それが、うまくセリフとマッチしているし、マイクなしなのに声が会場全体にまで響いていました。人間の声ってここまで響かせられるのかと、そういうところにも感動しました。コンサート、映画、演劇、ミュージカル、漫才その他、普段接することがないようなものに接してみると何か違う視点が持てるような気がします。その中でもライブという部分のものには、特に触れるようにしたいなあと思いました。人気Blogランキング
2005.09.01
コメント(1)
全25件 (25件中 1-25件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ^-^◆ 浪花節(浪曲)の修行<少年時の…
- (2025-11-25 05:00:06)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 駆け引きの上手な人になれ
- (2025-11-24 07:56:07)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- ブラックフライデー1〜3店舗☆タイツ…
- (2025-11-25 06:00:06)
-