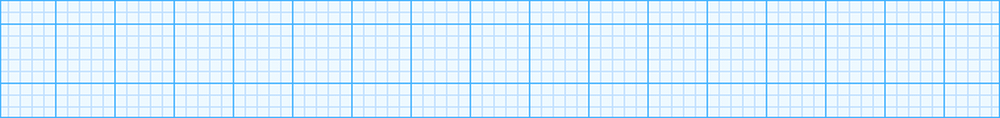全2332件 (2332件中 1-50件目)
-
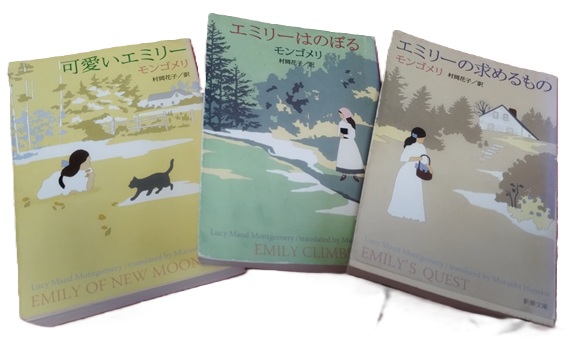
エミリーシリーズ3部作感想ーその2「エミリーはのぼる」+「エミリーの求めるもの」感想 村岡花子訳
エミリーシリーズ3部作感想ーその1 概要+「可愛いエミリー」感想 記事の続きです。エミリーシリーズ3部作感想ーその2「エミリーはのぼる」+「エミリーの求めるもの」感想 村岡花子訳*以下、備忘の為にキャラクター概要、展開の説明をたくさん記載してます。シリーズ全体&各巻について、結末までしっかりネタバレ含みます。スリリングな展開が魅力的なシリーズだと思いますので、未読の方はお気を付けください*『エミリーはのぼる』(Emily Climbs) 1925年著・1967年和訳【新潮文庫・背面あらすじ】威厳正しいエリザベス伯母、優しいローラ伯母、批評家カーペンター先生、イルゼ、テディ…。美しい自然と人々の愛情に恵まれたニュー・ムーンで、エミリーは「ひらめき」に従って創作に励み、雑誌社に送り続ける。「アルプスの道の頂上」にのぼって行こうと努力する彼女の姿には、著者の恐ろしいまでの文学への敬愛とたゆみない勉強がうかがわれる。【主要キャラクター:2作目時点】(マレー家)・エミリー・バード・スター14歳になり、シュルーズベリーの高等学校(3年間)へ進学する。自作の詩等を 何度送り返されようともめげずに出版社に送り続け、やがて少しずつ採用されるようになる。ごくまれに第六感/シャーマン的な能力を発揮し、遠くに居る人への思念伝達や行方不明者の発見等を行う。・ルース・ダットン伯母シュルーズベリーに住むマレー家出身の女性。高等教育期間中 エミリーが下宿する屋敷の主。エミリーとは長く馬が合わなかったが、作品後半 彼女にいわれのない悪評が立った際にはマレー家の権力を駆使して鎮圧を図る。・エリザベス伯母エミリーを引き取ったニュー・ムーン農場を切り盛りする女性。エミリーをシュルーズベリーに進学させる際、3年間は小説を書かない約束を取り付けた。・アンドルー・オリバー・マレーアディー伯母さんの息子。マレー家が一族内でエミリーにあてがった婚約者候補。エミリー評としては、悪い人ではないが “つまらない人”。(学友)・テディ・ケントエミリーのボーイフレンド。シュルーズベリーの高等教育へ進む。エミリーとは度々良い雰囲気になるも、一人息子を溺愛する母親の影がちらつく。・イルゼ・バーンリエミリーの親友の女の子。シュルーズベリーの高等教育へ進む。奔放さは相変わらず。・ペリー・ミラーエミリーが好きで立身出世を目指す男の子。シュルーズベリーの高等教育へ進む。弁論大会等で頭角を現し始める。・イブリン・ブレーク1学年上のエミリーの天敵。エミリーはイブリンから様々な嫌がらせを受ける。(その他)・ミス・ジャネット・ロイアルプリンスエドワード島・シュルーズベリー出身の女性。20年前に単身ニューヨークに出て出世。大きな婦人雑誌の文芸記者であり、小説会社の原稿選定委員も担っている。エミリーの文学的才能に目をつけ、ニューヨーク行きの話を持ちかける。【感想】シリーズ2作目、シュルーズベリーの高等教育期間が描かれます。こちらは、アンシリーズで言うところの「青春」「愛情」で描かれたターンと似た話回しが多数登場しました。ただやはり要素が似ている分、どこまでも「執筆」に向かい、すべての感情を「上へ上へ」昇華していくエミリーちゃんの異質性が際立ちます。エミリーシリーズ3部作は 各巻それぞれ異なる面白さを持っていますが、この2作目は異色の出来栄え…「エミリーシリーズ」として一番描きたかった部分だろうと思いますし、個人的なイチオシは間違いなくこの「のぼる」です。…とにかく1シーン1シーンの描写がキレてる!!どのシーンも絵的に面白く、わくわくしながら読み進めることが出来ました。その上で1作全体通して、エミリーちゃんがラスト、「学校卒業後、都会へは出て行かず、ニュームーンで執筆を続ける」道を選択する心情作りにすごく説得力がありました。【個人的に印象深かったシーン】・第三章 嵐の夜誤って教会に閉じ込められてしまったエミリー。そこには新婚時に奥方を亡くして以降 気が触れたモリソン老人も居り、追いかけまわされるという超恐怖体験を被ることに。絶体絶命のその時、テディが現われ助け出してくれる…。真夜中、超ロマンチックな2人きりのムードは、一人息子を溺愛し嫉妬に狂ったケント夫人の登場で台無しに。…ジェットコースターのように畳みかける展開が爽快な章でした。最後、夫人の登場で興ざめし、すんっとなって、あれだけの恐怖体験をしたにも関わらず 夜道を独りですたすた帰っていくエミリーちゃんの可愛げのなさも印象的でした。・第十章 伯母とのごたごたルース伯母の反対を無視して学校のコンサート出演を強行したエミリーは、家から閉め出されてしまう。4月頭のまだまだ寒い夜、腹を立てたエミリーは二度とここへは戻るまいと誓いつつ、7マイル離れたニュームーン農場まで単身徒歩で帰宅する。ニュームーンに着き、ジミーさんと話すうちに気が晴れたエミリーは、エリザベス伯母たちに気づかれないよう、7マイルの道のりをまた独り歩き出す。エミリーちゃんの片意地の強さと、こんな体験の中においても”夜の帰宅道”を劇的に楽しめる アーティスト感性がよく見て取れるシーンでした。・第十二章 乾草づかの下で”シュルーズベリータイムズ”の特別版予約注文勧誘のため、エミリーちゃんとイルゼちゃんの2人は 2泊3日で近隣の家々を回る勧誘旅を実施。不愉快なことばかりを言う住人も含め、人間観察もしながら楽しく勧誘の旅は続くが、日没近くで道に迷った2人は 雨の心配がないのを良いことに乾草づかの上で一夜を明かす。美しい星空の下におけるエミリーちゃんのモノローグ↓が印象的でした。ー有限の世界は一瞬、無限の世界にかわりーしばし人間が神性をおびー醜いものがすべてかき消えて後には完全な美だけが残る。おおー美ーエミリーはあまりの喚起に身を震わせた。彼女は美を愛したー今夜ほど美に満ち足りたことはなかった。身動きをしたり呼吸をしたらからだを流れている美の流れが途切れるのではないかと恐れた。人生は神の音楽を奏でるための素晴らしい楽器のように思えた。「ああ、神様、わたしをそれにふさわしい者になさってくださいませーああ、わたしをそれにふさわしい者になさってくださいませ」とエミリーは祈った。「アンの青春」でも、アンちゃんとダイアナちゃんの2人が村の改善会の資金集めに村の家々を回ったり、あひる小屋の屋根にはまって身動きが取れなくなったところに雷雨が来て ハイテンションになったり…というシーンが描かれていますが、それらの体験が「文学」に昇華されていく…そこの説得力は圧倒的に「エミリーはのぼる」の描写の方が精度が高く、洗練されていると感じました。・第二十一章 水よりも濃く…ルース伯母さんカッケェえええええ!!・第二十五章 恋の季節次巻、恋愛面を進めていくよ~…という予告的な意味合いも含めているタイトルでしょうか。キレッキレの終章だと思います。周囲の望む一族内の婚約者・アンドルーを超冷静にぶった切った後、テディが自分を求めないことに対するゆらゆらざわざわするエミリーちゃんの心情が綴られています。わたしはもし我慢しなければ、テディ・ケントをいくらでも愛せたのだーもし彼が望めば、明らかに彼はそれを望まないらしい。~略~それでいい、かまやしない。もしテディがわたしを欲しないなら、わたしもテディを欲しない。それがマレー家のやり方である ~云々…言い回しが天才的!我が強すぎて、なんて可愛くなさすぎるエミリーちゃんの思考回路!それでいてラスト、池の水面をふと見たときに、垂れ下がっている枝の影がちょうど木の葉の冠ー月桂冠のように見えて…わたしはそれをいい兆(しるし)として受けとった。そうだ、テディはただ恥ずかしかったのだろうと。…この、最後の最後の一文!なんというキレ!自分の心に言い訳して言い訳して…だけど本当はテディくんに自分を望んで欲しい…エミリーちゃんの深層の心情が顔を見せる瞬間がたまりませんでした。『エミリーはのぼる』…超傑作だと思います!!!『エミリーの求めるもの』(Emily's Quest) 1927年著・1969年和訳【新潮文庫・背面あらすじ】平和で旧時代的なニュー・ムーンの世界から、ボーイフレンドのテディも、親友のイルゼも、都会へと飛びたっていった。孤独に耐えながら、ひたすら創作に没頭するエミリー。野心(アンビッション)に燃える彼女にも、時として眠れぬ「夜中の三時」が訪れる。いわゆる適齢期を迎えた女性の、微妙な乙女心が求めるものは何かー このエミリー・シリーズ完結編は、村岡女史最後の訳業となった。【主要キャラクター:3作目時点】(ニュームーン農場)・エミリー・バード・スター17歳。シュルーズベリーでの3年間の高等教育の後、ニュー・ムーン農場に戻り、ひたすら執筆の道を志す。結婚適齢期が近づきはじめると、彼女の結婚に係り様々な男性が名乗りを挙げ始め、恋愛の噂が絶えない。(幼なじみたち)・テディ・ケントモントリオールのデザイン学院へ進学し、画家として成功をおさめ始める。エミリーを愛している素振りを見せるものの、はっきりとしたことは言わず、遠くに暮らすうちにエミリーとは徐々に心の距離が出来始める。・イルゼ・バーンリモントリオールの“文学と表現の学校”へ進学する。作中、幼い頃よりペリーを愛していたことをエミリーに打ち明けるも、彼を諦め、“習慣のようになった”テディと婚約する。・ペリー・ミラー貧しい生まれながら 高等教育の中で頭角を現し、シャーロットタウンの法律事務所で働く。エミリーに何度もプロポーズするも断られ続け、それでもなお良き友人として付き合っている。(その他)・カーペンター先生エミリーの執筆作品を辛口で批評してくれた先生。本作序盤で病死し、彼の死はエミリーの孤独に拍車をかける。・ディーン・プリースト伝統あるプリースト家の独身中年男性。エミリーの良き理解者だが、彼女の執筆活動にはあまり良い反応を示さない。エミリーへの愛情を自覚しながらもそれを隠してきていたが、大けがをして半年間病床に伏せていた彼女を支え、結婚の約束を取り付ける。その昔花嫁が逃げたという曰くつきの“失望の家”を購入し、新たな住まいにしようと準備するも、テディを愛していることを自覚したエミリーに「あなたを愛していない」と破談を切り出され、承諾する。・ミセス・ケントテディの母親。一人息子を溺愛し エミリーの存在を憎む。都会へ出ている息子に対し エミリーの他の男たちとの恋愛噂を逐一報告し、またテディからエミリーにあてた愛のメッセージの綴られた手紙を隠蔽する等、2人の関係を悪化させる数々の所業を行う。物語終盤、エミリーが彼女の亡き夫(テディの父親)の手紙を見つけたことで心救われ、これまでの自身の行動を反省するようになる。【感想】エミリーシリーズ3部作の最終章。幼馴染カルテット+ディーンさん+そのほかの数多の求婚者たち(+裏でミス・ケントの暗躍)…と、登場人物たち全員自分勝手なため引き起こされる、コロッコロ形成逆転しまくるラブバイオレンス!とにかく、はっきり自分の気持ちを相手に伝えていない状態の上で、誤解や嘘・その他もろもろの各人の環境変化が重なっていき、相当話が詰まった上での婚約破棄や結婚式当日ドタキャンが横行するひどい世界戦でして…なんというか…アンシリーズって本当に優しい世界だったんだな…というか、「エミリーの求めるもの」を読んでいると、全員どっかで人様に迷惑をかけまくらないと自分の根幹にある感情に戻ってこれない、たいがいなキャラクターばかりなんです……が、っっっ超オモシロかった…!!これはここにしかない面白さだ…。エゴイスティック×複数主体でこじれまくってて最高だった!!第1作目から仕掛けてあったキャラ配置/伏線を、余すことなくすべて生かし切ってラストまで突き抜けていて、これだけドタバタして人間関係も焦土と化したんじゃないかというとそうでもなくて、ラストで主役たちが向かうべき未来に踏み出すことが出来ていることがきちんと伝わってきて、爽快感を持って読み切ることができて感動しました。【エミリーちゃんの第3の気質について】エミリーシリーズの特徴として、とにかく”家系・血筋に係る意識”が非常に強調して描かれており、彼女の意識の中で、自分の気質をおそらく下記のように認識しているのだろうと思います。①母方・マレー家の血筋:自然を愛し、代々プリンスエドワード島に住む伝統ある血筋。②父方・スター家の血筋:フリーライターだった父と同様、執筆に情熱を燃やす血筋…エミリーちゃんは2作目「エミリーはのぼる」のラストで、自身の生きる道を上記2つの血筋を混合させたところにある「プリンスエドワード島で目に映るあらゆるものを自身に取り込み、文学にして昇華/表出すること」に見出します。彼女の文学&自然に向かう志向性について「血筋」という確固たるもので裏打ちしてあるので、読者にも伝わり易いですし、何よりもエミリーちゃん自身がこれらの血筋を引き合いに出して「自分の定義」を行っています。エミリーちゃんは「自分の定義」に誇りを持ち、何度挫折があったとしても忠実にその道を進みます。ただ本シリーズを読み進めると、エミリーちゃんの思考回路にもうひとつ…第3の気質があるように思います。幼い頃よりテディくんに口笛の合図で呼ばれればすぐに飛んでいく…テディくんが大好きで、テディくんに求められたい!というロマンチックで乙女チックな側面です。これもしっかり血筋で説明できるように、最初から仕掛けてある…エミリーちゃんが物心つく前に亡くなった「母親の気質」だと受け取っています。③母親・ジュリエットの気質:若くして貧乏なジャーナリスト(エミリー父)と恋に落ち、家族に大反対されるも駆け落ちする。恋に生きた女性。エミリーちゃん自身が、自分のこの気質をしっかり定義できていない。母親の記憶はないですし、周囲の人々からは口をそろえて「母親に似てない」「母親はすごく可愛い娘だった」と言われますので。※父には「お前はあまりお母さんに似てない。でも笑顔が似ている」と言われていた。またこの第3の気質が、もう2つの気質:①自然を愛し②執筆に情熱を燃やす気質と親和性が高くないのも、自身の定義に組み込まれにくい要因だと思います。この第3の”恋愛”気質を貫こうとすると、相手の世界に飛び込んでいく…つまり相手都合に合わせて動く必要が出てきますので、エミリーちゃんのやりたい執筆活動に支障がでる可能性もあるんです。執筆活動だけを自身の使命と認識するのであれば、恋に向かいたい志向性は日陰に置いた方が都合がいい…でもどうしても彼女の深層に存在しますので。本作「求めるもの」においては、エミリーちゃんがこの第3の気質を素直に表に出すことが出来ず、焦燥にかられ苦しむことになります。【カップルについて】・エミリーちゃん/テディくんメインカップルであるエミリーちゃんとテディくん。この2人のキャラ設定は、アンちゃん/ギルバートと相反する形で作り込んであると感じます。アンシリーズは、アンちゃんが思ったよりも臆病な子で、そしたらアンちゃんを幸せにすることを生きがいにする推進力お化け・ヒーローのギルバート氏が暴走を始めました。奴が、あまりに強力過ぎた…。最終的にはアンちゃんが人生を選ぶというよりは、“ギルバートの理想”にアンちゃんが人生を全振りする、作品全体が“ギルバートの理想”実現&ブライス一家万歳!にたどり着く…言ってしまうと完全に“ギルバートが作品を乗っ取る”状態になってました。これがアンシリーズ最大の魅力であることは確かですが、強力過ぎて何もかもが乗っ取られてたと思います。エミリーシリーズで描きたいのは、あくまで“エミリーちゃん自身の主体性、アーティスト性”ですから、ヒーローのテディくんは、第一に“ギルバートにならないようにすること”を大前提に、設定から作り込んであるキャラクターだと思います。この子自身も画家…アーティストであるという点と、何よりも母親の存在ですね。エミリーちゃんとテディくんは2人ともアーティストで、やりたいことが他にきちんとある子たちなので、相手の存在は“唯一の生きがい”ではないんです。だから、相手のことは大好きだしもし相手が自分を望んでくれるなら…!とお互いにずっと思ってるんですが、お互いに絶対にそれを直接には言わない。特にテディくんには、母親・ケント夫人の存在がずっと付きまとっていますので。出逢った頃からテディくんがエミリーちゃんのことを大好きだったので、ケント夫人はエミリーちゃんを目の敵にしていましたし、かといってたった一人の親族を捨てることなどテディくんにはできないし…画家として成功して、母親を引き取って面倒を見て、亡くなるまできちんと見届けて…そこまで来ないと、最終的にテディくんがエミリーちゃんに直接愛を伝えることが出来なかったのもすごく説得力がありましたし、どんなに大どんでん返しを繰り返しても納得できました。エミリーちゃんもね…困ったことに自分よりどうしても母親を優先させてしまうテディくんだから好きなんだろうな、ってのもなんとなく分かるので。自分は強くて、他に執筆という生きがいもあるので、テディくんに求められなくても大丈夫だけど、ケント夫人はテディくんがだけが生きがいなので。…と、エミリーちゃんは言語化できる次元では思っていますが、下線部については先に語った彼女の第3の気質がどうしてもうずいて苦しい…そんなぐるぐるした心もちで10代後半~20代後半を過ごすことになりました。ラスト、テディくんの告白(プロポーズ?)の言い回し↓が、ギルバートと正反対で本当に興味深かったです。「ぼくを愛することができないとは言わないでくれ。できるんだーそうしなけりゃいけないんだーねぇエミリー」ー彼の眼は一瞬間、彼女の月の光のような、明るい眼に合ったー「きみは愛している!」エミリーちゃんの主体的な愛情を、テディくんの方から懇願する…という言い回しですね。根幹のところで言いたいこととしては、「望ましい未来に向かいたい、それをあなたにも望んで欲しい」ということなので、アンちゃん/ギルバートのプロポーズシーンと同じ意なのですが、でも言い回し自体が真逆の形になっているところは、2組のカップルの違いがよく見て取れて面白いところだと思っています。・イルゼちゃん/ペリーくんもう一組の幼馴染カップル。イルゼちゃんはずっとペリーくんのことが好きだったのですが、ペリーくんが幼い頃よりずーっとエミリーちゃんしか見ていなかったことや、立身出世のためにペリー君が別の縁談の話も進めている状況もあり、想いを伝えることもせずになんとか彼を諦めようと、テディくんと婚約/結婚を進めようとします。※イルゼちゃん&ペリーくんは、エミリーちゃん&テディくんの絶妙な両想い関係には気づいていないイルゼちゃん/ペリーくんの2人は、普通小説を書くとしたらこの子たちを主役にした方が明朗な物語になるだろうな…というエミリーちゃん/テディくんよりすごく“主役っぽい設定”を持った子たちだと思っています。イルゼちゃんは、幼い頃より母親がおらず、父親にも長いこと構ってもらえなかった娘で、奔放さの裏に愛情への渇望や不安定さを垣間見せることが度々あり、読者としても「幸せになってほしいなぁ…」と常々思って読み進めてしまう娘でした。クライマックス、テディくんとの結婚式を間近に控えたイルゼちゃんが 妙なハイテンションになって来て、そこから夜通し泣きはらしたり ペリーくんからの結婚祝いを叩き割ったり…とどんどん不安定になっていき、式の直前、ペリーくんが事故にあったとの報を聞いてから忽然と姿を消してしまうシーンは、ある意味爽快な面白いシーンでしたね…!もちろん超絶傍迷惑な行動なんですが…まぁ…幼少期からのあの子の置かれた状況を考えれば、父親だって村の人たちだって 誰もそうも強く文句は言えないよね…タイミングの良し悪しはさておき、誰よりも早く自分の気持ちに従って動いたイルゼちゃんのおかげで、結果、幼馴染カルテットは正常の一番望ましい形に落ち着くことができたよね…と思います。エミリーちゃんとテディくんは…たとえ誤解やすれ違いがなかったとしても、最終的にはケント夫人が存命のうちには、結ばれることはなかっただろうと思いますので。【若くして亡くなった母親の生き方の肯定について】ここまで感想を書いて来て、本作の"恋愛"面には、アンシリーズと同様に”若くして亡くなった母親の生き方の肯定”というテーマがあることをひしひしと感じました。本作は、やたらと”若くして死別した夫婦”が登場します。エミリーちゃんの両親もですし(駆け落ちするも、母が若くして病死、数年後に父も病死)、イルゼちゃんの両親も(母親が誤って井戸に転落、その後12年間不貞を疑われ続けていた)、テディくんの両親も(父が若くして病死、母は一人息子を連れて引きこもりの生活)です。周囲にも、来るはずだった花嫁が来ず未完成のまま放置された”失望の家”や、新婚時に奥様を失い気の触れた老人等、やたらと結婚にまつわる悲劇が蔓延しており、幸せが長続きした夫婦像がほとんど居ない。エミリーちゃん、イルゼちゃん、テディくんが、心から想う本命の相手になかなか面と向かって愛を伝える/結婚を切り出すことが出来なかったのもなんか納得できますし、でも最後は皆”結婚”に向かっていく…。両親のことが心理的なネックになってるとか、両親の生き方の肯定がしたいとか、はっきりそれを言語化できる次元で自覚できているわけではないのですが、めぐりめぐった結果として”両親/母親の生き方の肯定”をしているんだな、と思います。このテーマは、アンシリーズでも思いっきり描かれていました(アンちゃんは、出産直後に亡くなった両親の目指していたであろう”幸せな家庭を築く”道に進んでいく)。モンゴメリさんの結婚観の根底に、”両親(特に母親)の生き方の肯定”…両親の生き方の再生産をしていくという観点があったんだろうな、と感じています。ざざざっと思ったことを書きたくって来ましたが、やっぱりエミリーシリーズも、“心情構成”を念頭においた、練り込んだキャラクター配置・繊細な各種設定の数々が本当に凄まじいですね。特に本シリーズは、狙って仕掛けたものを、きれいに見事に回収し切ってラストを迎えていますので、意図したものをまっすぐ書き通すことが出来た作品として、モンゴメリさんの構成作家としてのずば抜けた手腕がよくよく語れるシリーズだと思います。アンシリーズにひと区切りつけた後、モンゴメリさんがなぜ本シリーズを執筆したくなったのかもよく分かりますし、非常に読み応えがありました。アンシリーズと比較すると、相当バイオレンスで攻撃的な話回しも多いので、アンシリーズよりも読む人を選ぶ作品だろうなぁ…とも思いますが、この書き方でしか描けないぶった切った爽快感もあるな、と感じています。総じて、超面白かったです!!アンシリーズを完読し、もう一段階モンゴメリさんの構成力を深堀り/堪能したい方は、是非!さて…次は「青い城」かな??(1926年著・「エミリーはのぼる」1925年と「エミリーの求めるもの」1927年の間の作品)なるべく時系列順に、ぼちぼちと読み進めていきたいと思っています!【村岡花子さん最後の訳業】最後に、少し話はそれますが…文庫背面の説明文や巻末の寄稿によると、エミリーシリーズ3作目「エミリーの求めるもの」は、村岡花子さんの最後の訳業とのことでした。本作の最後の原稿を出版社に手渡した1968年10月、その月のうちに村岡花子さんは75歳で亡くなられたとのことで…エミリーシリーズ3部作をきちんと翻訳し切れたことは、モンゴメリ作品の訳業という偉業の一貫として本当にやり切れてよかったなぁ…と感じます。『可愛いエミリー』のタイトル一個取ってもいくらでも語れますが、村岡花子さんは天才です。村岡花子さんの他の訳業に手を付けたわけではないので全部想像で言いますが、モンゴメリ作品の訳業を鑑賞する限りにおいては、「英語力」という言葉では言い尽くしきれない…”モンゴメリさんの意図を汲む力”というか、"文脈/物語構成を捉える力” ”フィーリング/テンション/ニュアンス”、そしてそれら捉えたものを”日本語に起こす際の語感センス”…尋常じゃありません。どうしてこんな繊細なものをきちんと掴んで、見事なまでに日本語でアウトプットできるのか…何をどう語ろうとしたって…「天才」としか言えません。国と世代を超えて、こうして私がモンゴメリ作品を堪能できるのも、ひとえに村岡花子さんの偉業あってのことと受け取っています。それを改めて実感する、エミリーシリーズ3部作でした。by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.11.27
コメント(0)
-
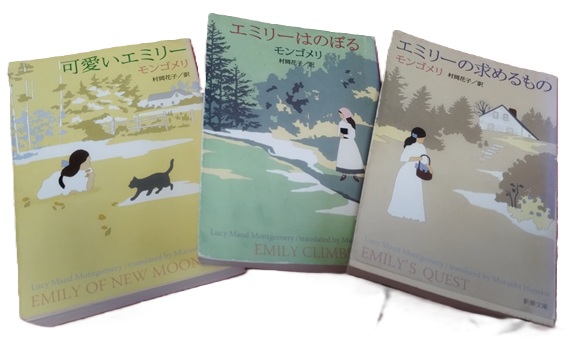
エミリーシリーズ3部作感想ーその1 概要+「可愛いエミリー」感想 村岡花子訳
エミリー3部作(村岡花子訳)を読みました。モンゴメリさんが『アンの娘リラ』(1921年)をもって、一旦アン関連の作品を切り上げた後に展開された3部作シリーズです。エミリーシリーズ3部作感想ーその1 概要+「可愛いエミリー」感想 村岡花子訳ざざざーっと目を通しての概要&各巻感想を簡単に書いていきます。*以下、備忘の為にキャラクター概要・展開の説明をたくさん記載しています。シリーズ全体&各巻について、結末までしっかりネタバレを含みます。スリリングな展開が魅力的なシリーズだと思いますので、未読の方はお気を付けください*■エミリーシリーズ 概要について・アンシリーズ、ストーリーガール+黄金の道とのエピソードの類似エミリーシリーズですが、話の舞台はプリンスエドワード島。10歳前後の親を亡くした少女が農場に引きとられるところから始まる…等、アンシリーズやストーリーガールと非常に似た舞台/出だしで展開します。作中に登場する話回しの要素も、既視感があるものが多いです。幼少期を書いた「可愛いエミリー」は、基本的には「赤毛のアン」を、青年期・高等教育期間を描く「エミリーはのぼる」は「アンの青春」「アンの愛情」を彷彿とさせるエピソードが多い印象です。また、本シリーズのエミリー・イルゼ・テディ・ペリーの幼馴染カルテットの関係性…特にペリーくんのキャラクターは、ストーリーガールのピーターくんが下地にあると考えられます。こういった、ひたすら同じ舞台を使用しながら 異なる設定やテーマでもってどんどん作品を描かれるモンゴメリさんのスタンスは、現代の漫画家だと非常に「あだち充先生っぽいな」と思いながら読み進めています。あだち充先生も、基本的に渾身作は「西東京/高校野球」を舞台にしていて、キャラクター造形も非常に似ているのですが、設定や描くべきテーマ自体はまったく異なる長期連載ヒット作を何作も何作も生み出しています。似てるけど、明確に「描いているテーマ&描いている感情」が違うので、同じような舞台&同じような要素で話を回したとしても、文脈における意義が全く異なり、逆に作品毎に「描いているもの」の違いがよくよく理解できるんです。・エミリーシリーズの特徴エミリーシリーズで特徴的だと感じたのは、特に下記の2点です。エミリーシリーズの特徴①著者モンゴメリさんの「自伝的」な側面について“愛されるための娘”アン・シャーリーと“書くための娘”エミリー・バード・スター本作は、どの説明でも「アンシリーズより自伝的」と書かれており、読んでみて非常に納得する部分がありました。(文学面)アンシリーズは、もちろんモンゴメリさんの生まれ育った背景が下地にある作品であり、主人公のアンちゃんには著者自身の体験や感情が色濃く投影されていると思っています。しかし、やはり特に2作目「青春」以降は、アンちゃんがモンゴメリさんからかなり離れて自由に動きしゃべっているのを感じていました。実母と幼くして死別したモンゴメリさんですが、祖父母宅で育てられたとのことで、アンちゃんの「生後3カ月、周囲にはまったく血縁者/近親者ゼロ」とは全く状況が異なりました。やっぱり走らせていくうちに、アンちゃんはモンゴメリさんご自身よりずっと「安心の上に立てなくて、怖がりで、”求めること”が出来ない娘でしたし、非常に潔癖で守ってあげたくなるタイプの娘だったんだと思います。青春→愛情→夢の家と、物語が進むにつれてどんどんアンちゃんがモンゴメリさん自身から離れて、特に夢の家の頃には、モンゴメリさんが構想した話筋から全然別の動きをしていることを感じます。特に文学執筆面については、モンゴメリさん的にはアンちゃんには”奥さん/お母さんをやりながら著名な作家になる未来”を構想し、物語を進められていたのだと受け取っています。「青春」では有名な女流作家のグリンゲイブルス訪問、「愛情」ではアンちゃんの著作が初めてお金になるシーンがあり、「夢の家」では、そのまま小説の主人公になりそうなジム船長の投入&妊娠期間中に彼の物語を執筆&出版→モンゴメリさんがアンちゃんに出会ったように、アンちゃんも”初出版の小説の主人公・ジム船長”と出逢い、物語の最後に息子・ジェムくんとして生まれてくる…小説執筆と出産を繋げるような形で筋道を構想されていたのではないかと想像しています。ただ、アンちゃんにとって出産は非常にセンシティブなアクションであり、彼女自身の意向として 文学的成功という野心的な面や、小説の主人公として前に出るようなアグレッシブな動きはやりたがらなかったのだろうと受け取っています。彼女は、ひとたび家庭を築く道に進むと決心したからには、どこまでも夫/子どもたちに献身的な女神&聖母でした。エミリーシリーズは、モンゴメリさんが アンシリーズで仕掛けていたけれど書き切れなかったこれら文学面について、アンちゃんとは別の主人公を据えてしっかり描き切ることを念頭に着手された作品と認識しています。エミリーちゃんは父親へあてた手紙/日記/詩や小説…という様々な形で、ひたすら「書くこと」に執着・没頭します。理不尽な出来事も無力さにさいなまれる時も幾度となく訪れるのですが、一般人メンタルで再起不能になりそうな出来事も、ひたすら「書き出す」ことでエミリーちゃんの中で昇華され、血肉になっていく様子がよく見て取れます。(家系への意識/自身の定義)また、上記文学面とも被る部分ではありますが、主人公の「自分の定義」の違いがそのまま作品の違いだなと感じています。エミリーシリーズの特徴として、とにかく“家系・血筋に係る意識”が非常に強調して描かれています。エミリーちゃんの思考回路として、行動言動を考える際の頭文として「マレー家の者として」「スター家の血を引く者として」という言葉を多用します。エミリーちゃんは、特に母方の家系が伝統を重んじる一族であり、出生やルーツがはっきりしているため、とにかく最初から怖いくらい「自分」がある娘です。エミリーちゃんの意識の中で、おそらく自分の気質を下記のように認識しているのだろうと思います。①母方・マレー家の血筋:自然を愛し、代々プリンスエドワード島に住む伝統ある血筋。②父方・スター家の血筋:フリーライターだった父と同様、執筆に情熱を燃やす血筋彼女は自身のルーツも背景もすべて理解したうえで、「ではここにこうして生きるエミリー・バード・スターの使命とは?」の回答を自分自身で見つけ出し、上記2つの血筋を混合させたところにある「プリンスエドワード島で目に映るあらゆるものを自身に取り込み、文学にして昇華/表出すること」に見出していきます。※実は、エミリーちゃんの気質として上記2つとは別にもう1つ、エミリーちゃん自身も自覚できていない第3の気質が仕掛けてあると思っています。これについては「エミリーの求めるもの」感想パートで語ります。反面、アンちゃんは両親の記憶もなく 血縁者が周囲に0という立場なので、そもそも「自分」が何者か分からない…実は「自分」がほぼなくて、 いつまでも不安定なところに立ち続けている娘で、だからこそ「ここにあなたが居てくれて嬉しい」と言ってもらえることが、彼女を定義づけるすべてでした。簡単に言うと、アンちゃんを定義するのは「周囲の人たちの愛情」ですし、「ギルバート(&子どもたち)に人生を全振りする」選択ー“結婚”をして「ブライス家」に属して真の家族を持つことが出来ることこそ彼女の至高の幸せだったのだろうと受け取っています。この2人の意識の違いが、エミリーシリーズの方が著者にとって「より自伝的」と言われる最大の要因だろうな、と感じています。エミリーシリーズの特徴②自由な作品構成/キャラクター配置もう1点、エミリーシリーズを読んで印象的だったのが「構成重視」の物語である点。1冊1冊、解き放たれた鳥のように自由~にのびのび~っと執筆されているのを感じました。モンゴメリさんの作家性として、真っ先に語りたくなるのは「構成」です。小説作品の1冊1冊、短編でも1作1作、「心情作り」を基盤としながら それらを全然違う筋道で形作って来る「構成」に特化された作家様だなと感じています。ただ、アンシリーズはかなりキャラクターがモンゴメリさんの手を離れて自由に動き回っていて、また作品人気に比例して、読者の期待の目線が強力過ぎたのだと思います。読者は、キャラクターたち(特にアンちゃん&ギルバート+子どもたち/ブライス家)が幸せになるのを見たくて読んでいる…その前提を重々承知したうえで、モンゴメリさんの興味関心/描き出したいテーマをどのように折り合わせて形作っていくのか。「夢の家」以降の作品は、複数のキャラクターたち…特に迷いなく自身の理想に作品全体を引き寄せようとしてくるギルバートのような作品掌握型の魔王的キャラクターとディスカッションして、説き伏せて、ちゃんと読者目線で面白い形に演出して整えて出す…というステップを踏まれていると感じます。アンの娘リラ(1921年)に至っては、主役カップルの子どもが6人も居るうえ、牧師館の幼馴染4兄弟もいて、そこに戦争という激重題材をぶつけているので、あっちこっちで激情爆発の凄惨な状況の中を、子ども世代の上の方の子たちとは少し距離のある末娘・リラちゃん主観で、数々の感情の爆心地に突っ込まないようにかいくぐりながら、なんとかかんとかラストシーン(終戦)までたどり着く…という書き方をされていると思っています。普通の考え方で「あの形」にはならない作品ですので、非常~にこじらせながら、苦しみながら形にされたのだろうな…と想像しますし、リラまで書ききったあと、モンゴメリさんが晩年までアンシリーズのキャラクターたちに触ることが出来なかったところからも、あまりに責任が重過ぎて、物語を構想する際の自由さが全くないところまで行き着いていたんだろうな、と感じます。エミリーシリーズは、読者目線/キャラクターの主体性はいったん重要度を下げ、モンゴメリさん主体で、描きたいテーマ/構成の方を優先したつくりで描き切ったシリーズだと認識しています。『可愛いエミリー』(Emily of New Moon) 1923年著・1964年和訳【新潮文庫・背面あらすじ】「勇気を持って生きなさい。世の中は愛でいっぱいだ」。父の遺した言葉を胸に、作家になることを夢みて生きる、みなし子になったエミリーは、ニュー・ムーン農場に引き取られた。孤独で夢みがちな彼女は、伯父伯母から変わった子供だと言われながらも、書くことに熱中し、詩人か小説家になろうと決心する。著者は『赤毛のアン』シリーズで親しまれているが、より自伝的だとされるエミリー・シリーズの第一作。*どうも1959年に別出版社・秋元書房より『風の中のエミリー』や『雨に歌うエミリー(2作目のぼるのこと?)』といったタイトルで一度刊行されていたのかな?ただ、その後新潮社より発刊された際にはこの『可愛いエミリー』というタイトルで発売されているようです。【主要キャラクター:1作目時点】(ニュー・ムーン農場)・エミリー・バード・スター4歳頃に母親と、10歳頃に父親と死別した後、母方の実家であるマレー家・ニュームーン農場に引き取られる。ふいに訪れる“ひらめき”を待ちながら、日々の出来事や想いを亡き父にあてた手紙として綴り続ける。・エリザベス伯母誇り高きマレー家のしきたりを重視し、厳格にニュームーン農場を取り仕切る。可愛がっていた異母妹(エミリーの母)が、フリーライター(エミリーの父)と駆け落ちした後に若死にしてしまったことを悔やんでおり、エミリーがものを書くことを良く思わない。・ローラ伯母ニュームーンに来て以来、エミリーの面倒を見てくれる心優しい伯母。ただ、エミリーの文学的野心への理解は薄い。・ジミーさんマレー家の親類。ニュームーン農場で働き、庭の管理に力を注いでる。幼少期にエリザベス伯母と遊んでいる際に井戸に転落し、脳への後遺症が残る。エミリーの文学的野心を理解し、紙を与える等全面的に強力してくれる。・ペリー・ミラージミーさんの小間使いとしてニュームーン農場にやとわれた貧しい生まれの少年。エミリーのことが好きで、将来の立身出世を志す。(近所の住人)・イルゼ・バーンリドクター・バーンリの一人娘。親が無神論者であり、また放任の元育っているため、周囲にはお転婆との評を受けている。口が悪くエミリーとはしょっちゅう口論を繰り返しながらも、打ち解けた会話のできる大事な親友。・ドクター・バーンリ医師。妻(イルゼの母親)の失踪依頼、無神論者で娘の面倒を見ない。・テディ・ケントよもぎが原に母親と2人で住むハンサムな少年。絵を描くのが上手。エミリー・イルゼ・ペリーたちと遊ぶようになる。・ミセス・ケントテディの母親。家に引きこもり、一人息子を溺愛する。息子が愛情を注ぐ(愛情を注ぎそうな)対象を憎む。(学校の先生/生徒)・ローダ・スチュアートエミリーが最初に仲良くなった女の子。彼女がエミリーを誕生日会に呼ばなかった事件を持って友情関係は終了する。・ミス・ブラウネルエミリーを目の敵にしているいじわるな先生。エミリー作の詩をクラス中で笑いものにするなどの仕打ちをする。・カーペンター先生ミス・ブラウネルの後任の中年男性。昔は大臣を目指すのでは?と言われていたほどの神童だったらしいが、大学の頃道楽におぼれたと噂されている。エミリーの執筆作品を、辛口かつ的確に批評してくれる。(マレー家親類/プリースト家)・ナンシー・プリースト大伯母プリースト・ポンドに住む、マレー家出身で一番お金持ちである90歳の高齢女性。エミリーは一時期彼女の家に滞在する。・ディーン・プリーストマレー家と同様、伝統あるプリースト家の独身中年男性。肩の高さが異なる/脚をひきずる等の身体特性を持つ。小金を貯めており現在は仕事を持たず、世界中を旅している。豊かな知識を持つ。海岸でエミリーの命を救って以来、エミリーは父親以来の気心を許せる相手としてなつく。エミリーとは親子ほど年齢が離れているが、彼女を愛し始める。【感想】原題は「Emily of New Moon」…いかにもファンシーな物語っぽい響きです。これをさらに村岡花子さんが「可愛いエミリー」なんてタイトルに訳すものだから、さぞや可愛らしい、乙女チックな物語かと思うじゃないですか。…多分、「タイトルの印象と本編とのギャップ」は狙って仕掛けたものだと思うのですが、第一の感想がひたすらコレです。↓エミリーちゃんも、物語自体も、全っっ然カワイくねぇえええ!!!いや、モンゴメリさんの「より自伝的な作品」という触れ込みは聞いてたので、なんとなく想像はしていましたが、やはりというかなんというか…エミリーちゃんは最初から自分が出来上がり過ぎてて、引き取られた名家の伯父伯母たちに全く負けずに生意気だし、学校での担任からの仕打ちや女同級生たちの動きもアンシリーズに比べ陰湿性が高い。ただ、どんなことがあっても「書くこと」ですべて昇華し、血肉にして創作に還元していくエミリーちゃんの姿は、モンゴメリさんが思い描く「理想的な作家」の姿なのだろうな と思いますし、どんなに陰湿な出来事が立て続けに起きようと、それほどのネガティブさは感じません。本シリーズは、きちんとエミリーちゃんの主観で読み進めることが出来るんです。嫌なことがいっぱい起こるんですが、エミリーちゃんが読者よりも数段強い鋼メンタルの娘なので、「強い娘だなぁ…」と置いて行かれながらも一緒に進んでいく…そんな印象を持って読み進めました。後半も後半・第29章「神聖冒涜」。エミリーちゃんがこれまでニュームーンに引き取られてからの日々の不平不満のはけ口として書きたくった「亡き父への手紙」の束を、エリザベス伯母が発見し、エミリーちゃんと衝突するシーン!あることないこと自分の悪口もいっぱい書き連ねてあるそれらを目の当たりにしたエリザベス伯母もショックですし、誰にも見せるつもりもなかった 赤裸々でエゴイスティックな手紙群を読まれたエミリーちゃんもショックですし、ぶつかった後 お互いに「読むべきではなかった」「書くべきではなかった、本心ではない」と謝り合うシーンが印象的でした。作品冒頭よりなかなか本音を言い合うことが出来なかった エリザベス伯母との心の交流。ちょっとばかし傷つけ合いが過ぎてるというか、殺伐とはしてますが、愛情を持った関係性だとお互いに認識し合えるシーンになっていて、この流れでこういう風に読ませるのか!すげぇ!!と感動しました。…このシーンがクライマックスだと思うじゃん!第30章 ・「カーテンが揚ったとき」…ここから、まさか…古井戸から、12年前に行方不明になったバーンリの若奥様(イルゼの母)の遺体が発見される怒涛のサスペンス展開が来ると思わないじゃん!!※悪性のはしかにかかり、意識昏倒したエミリーちゃんがシャーマン的な素養を発揮。周囲には「赤ん坊が居るのに、若い他の男と逃げた」と噂されていたイルゼの母親の居場所を叫び、伯母たちが半信半疑で井戸の捜索をすると発見された(事件性はなく、あくまで事故)。いや…ジミーさんの件も含め、やたらと井戸に人が落ちるなとは思って読んで来ていましたが、あまりの衝撃展開故、読後に残ったのが「井戸危険!要注意!」の感情だけだったのは凄かったです。…なにが『可愛いエミリー』だ馬鹿ヤロウ!(※)可愛らし~いタイトルで釣っておいて、赤毛のアンと似てるよ~って出だしで始めておいて、最後におっかなびっくり!ぎょっとさせる展開で読者をビクつかせたい意図が見事に形になっている作品だな、と思いますモンゴメリさんは構成作家なので、基本的にラストで読者をびっくりさせるのが大好きなんだろうと思います。…でも、これはアンシリーズではもう出来ない。本作『可愛いエミリー』は、アンシリーズのファンたちをびっくりさせること、このシリーズはアンシリーズとは違う面白さを目指して執筆していることを打ち付けたかったのだろうな と受け取っています。※村岡花子さんのタイトル付けが、モンゴメリさんの意図を汲むことが出来過ぎてて凄すぎる。「エミリーはのぼる」「エミリーの求めるもの」感想に続く!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.11.27
コメント(0)
-

漫画感想『ちはやふる Plus きみがため』2巻・3巻・4巻・5巻(末次由紀先生)
最近この作品の気分が高まってるときは緑黄色社会 さんの♪恥ずかしいか青春は ※clickリンクをよく聴いてます‼(好きな漫画には、すぐ私的テーマソングを探しちゃうタイプのオタクです)『ちはやふる plus きみがため』2巻~5巻 ちはやふるプラスきみがため(末次由紀先生、講談社、BE LOVE、2023年~以下続刊)累計2800万部突破の青春かるた漫画『ちはやふる』待望の続編ストーリー!舞台は千早たちが卒業したあとの瑞沢かるた部。競技かるたの高校全国大会優勝を目指す長良凛月(ながら りつ)だけど、千早や太一が抜けたあとの瑞沢はA級選手がたった一人で…。ひたむきにかるた、そして人生に向き合う凛月と、仲間の成長物語!読みました!雑多な超簡単感想をば!…読みましたというか、本当に私…この作品が大っっっ好きでして‼講談社の電子サイト「コミックDAYS」でポイントを貯めて、月イチの更新を心待ちにしております。発売日の0時回ったら即購入!ーと、それ位楽しみにしています。※以下、第十九章/単行本5巻までのネタバレ含みます。未読の方はご注意ください!※4巻の中盤から、舞台は滋賀県・全国大会へ!しかし主役の凛月くんが家族都合で急遽東京に帰ったりと、ハプニングが続出!ー苦戦しながらも予選を勝ち抜き、ベスト8に残った瑞沢高校。凛月くんも戻って来て、前作の主役・綾瀬千早をはじめ瑞沢かるた部OBの面々も応援に到着し…いざ、決勝トーナメントへ‼前作主人公たちも登場し、作品のノリも確立して油がノッてきているといいますか…25年夏には実写映画の10年後を描いた「ちはやふるーめぐりー」のオリジナルドラマも放映され、作品としても盛り上がってきているのではないかな?という印象を受けてます!以下、個人的な「ココが見所!」の箇条書きです。◆発光する画面…男の子主人公なのに、めっちゃキラキラ画面!本当に眩いんです「全てが新鮮な青春の目線」が‼ーいや描いてあるものは決して美しいものばかりではないんですけども…かるた部の皆で遊びに行った時の景色とか、初めての近江神宮の鮮やかな景色とか。好きな人とか。本作には「やるせなさ・暗さ・憤り」なんかも描かれている分、余計にキラキラが際立つといいますか。正直…「この漫画画面を体験できる」というだけでも、単行本揃える価値があると思います!◆かるた界隈の人物像の描写について前作の「ちはやふる」でもそうだったんですが、本作には「高校かるた部」だけにとどまらない、取材に基づいた「子供・社会人を含めたかるた界隈」の描写・群像劇が散りばめられています。ただ、前作は「クィーンになる女の子」を描く物語だったため、やはり周囲の大人たちもトップ・オブ・トップのキャラクター造作に寄っていました。彼らの悩みは、全盛期と比べて衰えていく自分とどう向き合うか・どう人生とかるた道を折り合わせながら生きていくか…。意識が高いトップアスリートたちのエピソードは、もちろん見ごたえがありました。ただ…やっぱり、それだけだと「向上心が無い人間はダメ」な世界に見えてしまいますので。1巻の感想でも書きましたが、今作では「トップになるためではなく、趣味として楽しむかるた」「限られた時間の中で頑張るかるた」「楽しい想い出になるかるた」「豊かな人生の糧としてのかるた」もまた、美しく輝かしく描かれています。2巻の初段認定試験の生意気な小学生男児だったり、7年やっても勝てないエンジョイ勢のおばさんだったり…。バリエーションに富んだサブキャラたちが、「ああ居そう‼」という立体感で描かれていて、楽しかったです。◆各キャラクター/他校の描写について・長良凛月(ながら りつ)…本人は無自覚だとは思いますが…しっかり者&陽キャ過ぎて(私には、多分近くに居たら眩しすぎて目が潰れてしまいそうなほど)パワフルな男の子です。〝かるたしか出来なかった子″ではなく、色んなスポーツを経験した上で&妹の面倒を見ながら時間を捻出して〝かるたを選んで頑張ってる子″。彼にとっては「かるたの団体戦で全国大会優勝!に邁進すること」が、亡きお母さんと繋がっていられる方法なんだろうな、と思います。自分にも他人にも厳しいけど、「自分はこうだが!お前はそうなのか‼」という、他人の特質を肯定的に受け入れる視野の広さを持っています。3年前に母親が亡くなってしまった長良家。彼の父親は、小学1年生の妹の世話を高校1年生の息子に丸投げする親です。※休日は引き受けてくれます。もちろん生活がありますので、妻の居ない中でも、稼ぎ頭として仕事に精を出すのは(父親として)立派なことです。ーただ今までも仕事一筋で生きてきたため、基本的に「何よりも〝子供の心を優先する″という発想」が出来ません。でも凛月くんは…仕事に邁進するお父さんのこと、本当に尊敬してて大好きなんですよ。本当に良い息子や…(涙)勉学に部活に育児に大忙しすぎて、とても恋愛なんて出来ない状況の凛月くんですが…想い人の花野菫先輩には、めっちゃ良い所を見せる事が出来てると思います!行けるよ~頑張れ‼私はずっと、凛月くんには是非、近江神宮の階段下で仮告白「全国優勝したら、その時また返事聞かせて」リターンをやっていただきたい…!と思ってるんですが… どうなるかなぁ⁉・秋野千隼(あきのちはや)この子は〝かるたを選んだ″し〝かるたに呼ばれた″子なのかな、と。超初心者ながら驚異の記憶力&集中力で、メキメキと&着実に実力をつけて来ています。1巻を読んだ際は(この子はどんなタイプの競技者になるんだろう?)と見えなかったんですが…記憶力⇒相手をよく観る⇒相手をかく乱させる配置⇒鋭い払いの手さばき… と、あらゆる面でどんどん天才の片鱗を見せてきています。オールラウンダータイプだったか‼また、凛月くん・肉まん君・田丸さん・太一くんといった、瑞沢かるた部(OB含む)の中でも理論的・分析的な視点を持つ面々から「次はコレ」と適切なアドバイスを受け、学習の場にも恵まれています。近江神宮にて現名人・綿谷新を見て「ああなりたい」と言った千隼くん。太一くんは(千早みたい…)と感じ、またフォームに新くんの鋭さを見出し(もしもこの子が…)とその将来性に期待が膨らんで、楽しくなっちゃったみたいです。太一くんと千早ちゃんが立ち上げた瑞沢かるた部から、新くんに挑む名人候補が生まれるかもしれない…いやぁワクワクしますね!千隼くんには、心配性が行きつきすぎて行動制限をかける母親が居ます。普通に見れば「毒親」なんですが、千隼くんも親の事を悪く言われるのは嫌な様子(ええ子や)。高校生になり、自分からも「こうしたい」と主張することが出来るようになれば良いですね!・花野菫(はなのすみれ)菫ちゃん~!! 本当にヒロイン力が凄まじいです!いちいちカワ(・∀・)イイ!!一番グッと来たのは第6首。千早ちゃんへのコンプレックスの根幹にあるは太一君への恋心だと思うけど、そこではなく「かるた部のキャプテンとして」気持ちを吐露してたのが、本当に良かった!話が進むにつれて、太一くんのへの恋心は吹っ切れていってる感じがしてます。菫ちゃんから観ても、凛月くんがどんどんキラキラして見えるようになっているのも印象的。今後に期待してます♡・田丸翠(たまるみどり)この続編では、田丸さんがいちいち良すぎると思うんです‼完全に裏ヒロイン‼ーいや元々ちはやふる無印の頃から、成長主体として非常に魅力的なキャラで大好きだったんですが…プラスではそれがさらに花開いている気がします!自分大好きで褒められたい願望が強い娘だけど、自分を受け入れてくれた瑞沢かるた部の皆が大好きで、少しずつ「周りの子たちの気持ちを考える」娘になっていってるというか。3巻で真っ先に花野先輩に抱きつきにいったり、原ちゃんたちの頑張りを主張したり…なんて可愛いの!それでいて、かるたには非常にシビアで実力主義。凛月くんや千隼くんの入部に一番喜んでるのはこの娘なんじゃないかな。4巻第十五首で描かれた、江別恵尚高校の笹原さんとの一戦が、個人的には現時点での本作ベストバウトなんです!無印の方ではほぼ描かれなかった「対戦相手が怖い」という感情…そうなんです!かるたに精通してない、かつスポーツもほぼしてこなかった私みたいな人間から見ると、かるたってめっちゃ怖い競技です。相手と近距離で向かい合って、相手が狙ってる札を取り合って…いや怖いよ。それこそ「かるたの鬼」じゃないと普通は怖いよ!「怖いのはしつこく揉めてくる人じゃなかったよ本当に怖いのは 本当に強い人 この人に勝てる自分になりたい」田丸さんのストイックなかるたへの熱意が、笹原さんのかるた愛を燃え上がらせる起爆剤になっていて、痺れました!・瑞沢かるた部面々筑波くん…「だめだなぁ」と言われつつ、慕われる部長を頑張っていてとても良いです!これからの戦いでめっちゃ活躍してくれると信じてます!橋立くん…多分この子が次期部長なんじゃないかなぁ。かるたの才能には恵まれてないけど、人を良く見ている&言うべきことはきちんと言う、男気のある子(+漫画家として大成してくれ!)です!原ちゃん…団体戦で勝ち星を上げることが出来る要因として、着実に力をつけ始めている原ちゃん。「〝ちは”は私の札だとも思ってる」は作者様のとっておき台詞だったんじゃないかな。5巻ラストでの輝きは素晴らしかった!橋立くんのこと好きなのかな?と感じさせる描写もちらほら。結構気になってます!・瑞沢かるた部OBたち初代瑞沢かるた部の面々が続々と登場!なんやかんや5人とも近江神宮にかけつけました。めちゃくちゃ応援してるけど、ちゃんと「後輩から呼ばれる&お願いされるまでは介入しないようにしてる」のが良いですね。肉まんくんが浪人中…だと⁉衝撃の事実でしたが… 個人的にはしっくりきているというか。肉まんくんって、本当に頭が良くて視野も広くて、教育的観点もある…真島太一ですら甘えにいく、めちゃくちゃ仕事出来る子なんですよね。…ただ賢い分だけ頭でっかちというか。瞬時に相手の能力と自分の能力を見定めてしまって、早々に諦めちゃう癖があって。ここが真島・机君と比べて非常に弱い部分だと感じていました。お話が進むにつれて粘れる場面も出て来てたんですが、やっぱり「かるたでトップをとる子」ではないので。末次先生的にも、「この受験という踏ん張り所で、みっともなくても粘り続けて、より高みを目指してほしい&成功体験を得てほしい」という想いがあるんじゃないかな~と感じてます。・綾瀬千早&真島太一50巻丸々かけて、最終回の最後の最後でついに恋を実らせたお二方。「運命の恋はこっちでした(バーン)‼あとは読者の想像にお任せします(ドーン)❣」って感じで、強烈なエンドマークがついていたわけですが…続編である本作では、その後のカップルに成りたての初々しいふたりの描写が小出しに小出しに描かれていて、それがシリーズファンの楽しみのひとつになっています♡私は元々(…最初から「幼馴染だよ」と言いながら、あれだけベタベタしてたお二方なんだから…正式に恋人になれば、そりゃぁ…たぶん読者がビックリするレベルでラブラブでしょうよ)と思ってました。4巻ラストでは千早ちゃんが「太一に会いたい」と走り出し、5巻では数か月ぶりの再開で太一くんが顔を真っ赤に染めました。あ~~~今こんな感じなんだぁ~~~ふぅ~~ん?(・∀・)ニヤニヤ❤あれですね。今後も1巻に1回くらいのペースで、2828シーンを入れてくださると良いですね。それだけで読者満足度、爆上がりですから!…しかし2人して「会えてない」「不安だ」「自信ない」とかなんとか弱音を吐いてますが…夏の近江神宮高校選手権(7月下旬)が終われば、大学生には2か月の夏休みが待ち構えているじゃありませんか‼そこんとこどうなんですか‼!?ーと思って見守ってます…うん。語り出したらやっぱり結構長くなってしまった💦これからの展開も楽しみにしてます‼by妹『ちはやふる』感想リンク『ちはやふる』読み始めました!感想-その1 話の骨格について感想-その2 かるた競技への芸術的・創造的アプローチについて感想-その3 千早ちゃん・新くん・太一くんの三角関係について感想-その4 瑞沢かるた部&綾瀬千早ちゃんについて感想-その5 綿谷新くんについて感想-その6 真島太一くんのかるたと、2人の師匠について感想-その7 千早&太一 恋愛とかるたについて-1感想-その8 千早&太一 恋愛とかるたについて-2感想-その9 千早&太一 恋愛とかるたについて-3感想-その10 百人一首と「せをはやみ」の歌について感想-その11 末次先生の過去作とちはやふるのハイブリットなラブストーリー描写について感想-その12 若宮詩暢ちゃんについて感想-その13 「一緒に居るための手段」の整理とサブキャラクターを用いた視点の投入について京都に行ってきました-その①近江神宮初ねんどろいど!ちはやふる「綾瀬千早」+直筆イラスト付サイン本について映画感想『ちはやふる』(上の句、下の句、結び)3部作漫画感想『MA・MA・Match(マ・マ・マッチ)』(末次由紀先生)漫画感想『ちはやふる plus きみがため』1巻(末次由紀先生)漫画感想『ちはやふる plus きみがため』2~5巻(末次由紀先生)
2025.11.23
コメント(0)
-

「アンの幸福」ー赤毛のアン・シリーズ5ー感想 村岡花子訳
「アンの幸福」ー赤毛のアン・シリーズ5ー感想 村岡花子訳(L・M・モンゴメリ・1936年、和訳 村岡花子・1958年)原題は、「Anne of Windy Willows」。Windy Willowsはアンちゃんの下宿先の名前で、日本語では柳風荘と訳されています。大学卒業後・婚約者であるギルバートの医科卒業を待つ3年間…サマーサイド中学校校長として働くアン・シャーリーの日々が、ギルバートへ向けた手紙形式で描かれた作品。シリーズとしては1921年に「アンの娘リラ」が発表され、そこから15年程経ってから、空白期間だった婚約時代の3年間の物語として補完的に発表された作品とのこと。当初は描く予定のなかった部分ですので、アン・ブックスシリーズ内においては(アンちゃんの人生の転機が描かれるような)ポイントとなる重要巻ではなく、本当にどこまでもアンシリーズが大好きで、ワールドに浸り切りたい方だけが読めば良いのかな…という作品だと思っています。端的に言えば…20代前半ながら、大学卒の女性教員として校長職に重用されたアンちゃんは、学校運営や社交的に様々な問題に向き合いながらも、非常にしっかり順調に職務をこなし、サマーサイドで大勢の知人・友人(特に女性)を得て、3年間を過ごします。シリーズ中、こんなに順調ばっかりなのは本作くらいでは?…ってくらい順調です。私のような読者(完全ギルバート感情移入型読者)にとっては、サマーサイドの生活自体がよく分かりませんし、とにかく早く結婚したい一心だけなので、本作で描写される出来事にあまりひっかかりがないというか、言及することがない作品なのですが……それでもちゃんと面白い。モンゴメリさんは、本当にどんなとっかかりからでもいち作品に仕立てることが出来る、物語構成の神だな、と改めて思いました。以下、徒然に感想です。■手紙形式 & アンちゃんによる『ギルバート・ケア』本作の一番の特色は『アンちゃんから婚約者・ギルバートへあてた手紙形式』という点です。そしてまたその書きっぷりが、超熱烈ラブレター風味💌というか…手紙の主な内容は、アンちゃんサイド(サマーサイド)で起こった出来事の説明なのですが、随所に「最愛のギルバート」「私たちの未来」の話題を差し込み、「愛してる」アピールが凄まじいんです。本作の直前… 大学卒業後・夏休みに婚約する(「アンの愛情」のラストシーン)まで、大学生活の4年間はアンちゃんの男嫌い&唐辛子対応に拍車がかかり、プロポーズしてくる男ども(ギルバート含)を全員トラウマ級の返り討ちにした挙句、それでもなおギルバートの存在が怖くて、彼の結婚願望を完膚なきまでに打ち砕こう&周囲にも「友達」と認識してもらおうと、主人公としては禁忌の技(読者に嫌われる)である「他の男とイイ感じ」アピール攻撃まで繰り出して、終いにはガチでギルバートを殺しかけるところまで追いつめていた…(そして本当に死ぬと分かった瞬間、アンちゃん自身も死にたくなっていた)そんな殺伐とした、まさしく殺し合い…ラブバトルを繰り広げていた女性とは到底思えない、驚愕のデレッぷり(ものすごい変わり身)に、読者がまず唖然とさせられるところから始まります。ちなみにギルバート自身は、この熱烈なラブレター群をものすごく喜んで、自然と受け取ると思いますが…ギルバートに感情移入していると思って読んでいた読者(私)ですら、「すごく嬉しいんだけど…アンちゃんはいきなりどうしたんだろう…?なんでこんな嬉しいことばっかり言ってくれるんだろう…?婚約前からの落差が大きすぎて怖い」と思いました。ここで「私はアンちゃんに感情移入して作品を読んでいる」と豪語する妹が、『アンちゃんの心持ち』を色々説明してくれました。↓妹談:そもそも本作は、「アンの愛情」のラスト:ギルバートが死にかけて2か月も経たない所から始まっている。…学生時代はお金がないかもしれないが、将来性抜群&堅実&ハンサムで、結婚相手などより取り見取りであるにも関わらず、「アンちゃんと結婚できないから」という理由で目指すべきビジョンを見失い、死にかけるギルバートの方がおかしい。まず、そこだけははっきり言っておきたい。その上で… アンちゃんも、ギルバートのたちの悪さに本当に懲りたというか。「ギルバートを諦めさせよう」とか…圧倒的に自分の認識が甘かったことを、強烈に突き付けられた。(人生がひっくり返るレベルで )大後悔&大反省した。「本当に死にかけられた」ショックが大き過ぎて、一度世界終末を体感した上で、この先の人生を「ギルバートの目指すビジョンの実現」に捧げることになったというか…「”ギルバートの女神”として生きていく」人生を選んだというか…言ってしまうと『ギルバート・ケア』に全振りすることになったんだと思う。黙示録以降、アンちゃんの人生の命題は『ギルバートがイキイキと働き、充実した日々を過ごす姿を守ること&ギルバートを幸せに晩年まで生かしきる事』になった。アンちゃんは、ギルバートの瞬間的行動力・集中力は尊敬しているが、別に(調子に乗ってor焦って)常に120%フルスロットルで働いてほしいわけではなく、平均80-95%位の、無理のない持続可能な状態で働いてほしい… と思ってる。婚約後、ギルバートの病み上がり直後に遠恋が始まっているので、アンちゃんとしても本当は近くで見張っていたいが、現状ではそれは難しい状況。折角アンちゃんが結婚を承諾してくれたのに、自分都合(大学医科)で3年間待たせてしまう…ギルバート側に、絶対に焦りの感情があるだろうことも、容易に想像できる状況。そこで、アンちゃんとしては唯一のコミュニケーション手段である「手紙」を用いて、出来る限りのギルバート・ケアをしようと、とにかく下記点を強調して手紙を綴っている。①『焦るな』『時を待て』『安心して過ごせ』・私は3年後、貴方と一緒に暮らせるようになる日を非常に楽しみにしており、間違いなくそこに向かって、今の生活を日々過ごしている。・その上で、私は仕事も交友関係も、大変さはあれど非常に充実しており、楽しめている。 ⇒貴方が私の心持ちを心配をしたり、ご機嫌取りに労力を回す必要は全くない。 自分の学問や生活を優先し、3年後、無事に医科を卒業して迎えに来い。②『そちらの状況も報告しろ』 こちらの状況は事細かに報告するため、そちらの状況もつつがなく知らせるように。婚約以前のギルバートは、学業(大学トップレベル)&学費稼ぎに加え、アンちゃんへのアプローチ&機嫌取りに非常に労力を費やしていた。その労力をギルバート自身のセルフケアに回させたい、…とはいえ心配なので状況は細かく報告せよ、ということだろうと思う。遠恋1年目~2年目のクリスマス&夏休み休暇では、ギルバートはアヴォンリーに帰省していたが、2年目~3年目間の最後の夏休みでは、西部の鉄道敷設に出稼ぎに行く選択をした。大学生活7年間、本当に最後の最後までギルバートがじり貧だったことが窺えるが、それと同時に、短期間でより良い給金を求めて遠地の肉体労働に出向いている点から、卒業までの学費のほか、1年後の医科卒業後即結婚に向けて「必要最低限の結婚式/新生活資金を確保したい」という意志を感じる。ここでギルバートに、アンちゃんの機嫌取り&愛を育むことに労力を割かさせず、1年後の為の資金稼ぎに注力する選択をさせられたことこそ、アンちゃんが2年間ひたすら手紙で「焦るな、安心しろ」をきちんと強調してきた賜物。アンちゃんがギルバートに伝えたいことを伝えきれた証拠だと感じた。妹の見解に、なるほど…確かに、と思いました。■様々な女性像、いち社会人女性としての活躍本作には、バリエーション豊かな女性ゲストキャラクターたちが登場します。未亡人、サマーサイドの覇権一族の女性たち、シングルマザー、婚約に関して諸問題を抱える若い女性たち…etc中でも、メインで描かれたゲストが下記の2人。・キャサリン・ブルック…アンの学校の陰気な女性教師。・エリザベス…柳風荘のお隣・常盤木荘に暮らす少女。母を亡くし、愛情を感じられない環境下で祖母に育てられている上記2人については、長期休暇にグリンゲイブルスに招く等、アンちゃん自身が非常に肩入れをし、その結果2人に人生レベルでの大きな変革をもたらします。環境面も含め、2人にはアンちゃんが共感できる部分がたくさんあって、力になりたいと思ったんだろうな、と受け取っています。やはりこの「幸福」の時点では、アンちゃんは「大学卒の女性」…というおそらく島内でも数えるほどしか居ない超貴重人材として重宝される立場のため、マシュウ/マリラや近所の大人たち・ジョセフィンおばさんに支援される側だった「赤毛のアン・青春・愛情」時代とは異なり、支援する側に回っていることが見て取れます。※アンちゃんの立派に成長したこの姿は、子ども時代から彼女を見て来て、支援する立場だった大人たちからしたら本当に嬉しいだろうな…と思います。上述したように、サマーサイドでの生活では、アンちゃんが様々な人々に干渉していきますが、同じようなとっかかりで関わっていったとしても、良い方に転じることもあれば、悪い方に転じることもある。同じことをしても、結果が真逆になる事象が多々発生しています。人に寄っては、全くそんなつもりじゃない受け取り方をされたり、「あ~関わるんじゃなかった!」と思うような出来事も多々起こります。でも人に寄っては、キャサリン&エリザベスのように、アンちゃんとの出会いがその人にとって人生レベルの大きな転換点となる場合もあります。…人との関わり方に正解はない。でも、アンちゃん自身の立場がしっかり確立しているので、他の誰に何を思われようと、アンちゃん自身がスタンスを変えることはないし、人と関わっていくことに悲観的になる必要はない…というモンゴメリさんの価値観もよく見て取れます。※「炉辺荘のアン」でも、これと同様の価値観を感じます。■アンの「幸福」…結婚までの心の準備期間最後に、本作の和訳タイトル『アンの幸福』について。アンちゃんの心持ちはこうだと思う(妹談)↓婚約時代の3年間は、ギルバートにとってはひたすら巻きたい遠恋期間だったかもしれないが、アンちゃんにとっては、落ち着いた心持ちで「結婚後」を想像することができるとても大事な時間だったと思う。「アンの愛情」記事でも書いて来た通り、結婚自体に大きな恐怖心を抱いていたアンちゃんは、婚約の時点で初めて「結婚」に向かう自分が想像できた。この3年間で、結婚するとどうするのかな…あれもできるな…これもできるな…と「家庭を築いていくこと」を夢見ることが出来た。その中で、深層部分でいちばんハードルの高かった「出産」に向かう覚悟も固めていったと思う。※アンちゃんにとっては、ギルバートは「大成すべき人/理想の家庭を築くべき人」。ギルバート自身はそう思ってはいないかもしれないが、アンちゃんの意識としては、こんなに優秀な人は絶対に血をつないでしかるべきであり、「子どもはマスト」。大学時代を描いた「愛情」は、(アンちゃんのトラウマを下地とした)破壊的思考回路に寄り、クライマックスで破滅(世界の終末)にたどり着く物語だったのに対し、本作が描いているのは、建設的な未来を目いっぱい想像しながら、その上で今の日々を大事に過ごすことが出来る…まさにアンちゃんの「幸福の日々」だな、と思います。世界的な名作・アンシリーズは、現実的な…不愉快も理不尽も、抗い切れない時代の大きな流れや悲劇…そういったものもたくさん存在する世界線なんですけど、でもその中で、主人公のアンちゃんは出逢いに恵まれて、彼女自身もいっぱい努力して、大勢の人に認められて、その上で、尊敬できる大好きな人と、愛ある大家族を築いていく……自身の両親が道半ばで倒れ実現出来なかったビジョンに、勇気を持って向かっていくことが出来た、本当に本当に幸せな人生を歩んだ女性だと思っています。後年になってから公表された、本作「アンの幸福」&子育て時代を描いた「炉辺荘のアン」は、モンゴメリさんが、アンちゃんの人生がどれだけ夢心地な幸せなものであるかを噛みしめながら執筆された作品なんだろうな、と感じました。…アンの幸福は、ギルバート的に感想書くことがあまりないかな…と思ってましたが、妹の見解含め、結構書くことが出来ましたね。アンシリーズは、1作1作の意義&構成がしっかりしているので、本当に感想が書きやすいです!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.10.24
コメント(0)
-

長野県飯田市 りんご狩り&名勝・天龍峡に行ってきました。
長野県飯田市 りんご狩り&名勝・天龍峡に行ってきました。写真ログです。経緯↓・アニメ『アン・シャーリー』にハマる⇒・原作 赤毛のアンシリーズ & 他のモンゴメリ作品(果樹園のセレナーデ 等)を一気読み⇒・親の「りんご狩りに行こうと思ってる」という話題に過剰反応⇒・親より先に、林檎の木に囲まれ&もぎたてを食べに行く🍎モンゴメリさんの作品の世界線(というかプリンスエドワード島)では、恋人たちのデートやプロポーズ…ロマンチックなシーン作りは、とにかく果樹園/Orchard(or古い庭)!!絵面の萌えを求めて、家からのアクセスもかなり気軽な距離感なのですが、これまで一度も行ったことのなかったりんご狩りに行ってきました。最高でした!!!こちらは「シナノゴールド」という黄色のリンゴです。大ぶりでみずみずしい印象のリンゴでした。こちらは「シナノピッコロ」。小ぶりで、オレンジっぽい色合いがなんともファンシーでした。もちろんその場でリンゴもたくさんいただきました。もぎたてフレッシュ&ジューシーで最高でした!種類毎に酸味・風味が異なることもよく分かりました。こちらは「秋映え」という種類のリンゴです。名前通り色が濃くて風景の中でよく映えていました。こちらは「シナノスイート」。名前の通り、一番甘味があって、ザ・王道のリンゴ!という味わいでした。ひたすらにたわわに実ったリンゴの樹々が超かわいい!こんなに幸せなものなのか…!とびっくりするような空間でした。脳内がもはやプリンスエドワード島なので、「絶対、あの木陰にアンちゃん(女神)が居る!」「今、キルメニィちゃんの幻影が見えた!」…とか口走るような馬鹿高テンションで散策しました。めっちゃくちゃ楽しかった&おいしかった~~!!是非毎年行きたい!リンゴ農園のすぐ近く、名勝・天龍峡にも寄って来ました。吊り橋…結構揺れました。あまり得意ではないので景色を楽しむ余裕がなかった(勿体ない)。…いや、本当になんで今まで来たことがなかったんだろう…?峡谷が超かっこよかったです。駐車場の近くで手打ち蕎麦も食べてきました。丁寧なお蕎麦&野菜天ぷら&とろろ…至福でした。長野県飯田市…目の前に現れるもののすべてが好み過ぎました。飯田市は、家からのアクセスもすごくいい場所なんですが…いや、本当になんで今まで来たことがなかったんだろう…?また行きたいです!by姉
2025.10.18
コメント(0)
-

暁のヨナ 第269話・第270話・第271話・第272話 感想 (姉編)+ハクヨナイラスト
花とゆめ 21号より、暁のヨナ連載再開!最終章記念!キャラクターコンテストの結果発表もありました。6月に発売した46巻には、第268話「心を縛る秤」まで収録されていましたので、そこから4話のざっくり感想&more を走り書きで記しておきたいと思います。暁のヨナ 第269話・第270話・第271話・第272話 感想 (姉編)+ハクヨナイラスト※以下、単行本47巻収録予定の下記4話分のネタバレを含む感想になります。未読の方はお気をつけください!第269話「天をも恐れぬ者」第270話「堕ちてゆく」第271話「ヒビ割れた楽園」第272話「透明な行き止まり」■キャラクターコンテストはがき&Web投票で受け付けていたキャラコン。1日一人1回、1位=3pt、2位=2pt、3位=1ptで投票できました。投票毎に各キャラクターへの応援コメント記載が必要なので、書くことが無くなって来て、地味にしんどさもありつつ、出来る限り毎日投票しましたよ!寝落ちする日もあったけど…!結果はこちらのHPでも公表されています。ハク様盤石の1位から、トップ3位をハク様・ヨナ姫・スウォン様の幼馴染3人が独占し、そこから四龍&ユン君の腹減り一行が漏れなくランクイン!というあまりに作品バランスに正しい結果過ぎて、観た瞬間に涙ぐみました。※ちなみに、私も妹もだいたいこの結果のようなバランスで投票してました。■46巻までのあらすじ焼け落ちた緋龍城。その地下・緋龍王の廟では、「盃の中」と外で、龍神たちの妄執との闘いが繰り広げられていた。龍神たちは緋龍王(=ヨナ姫)を天界へ連れて還ることを切望し、ハクの命を秤にかけてきた。それだけは…!と揺れるヨナ姫に、ハクは「結婚しますか」と告げる。■47巻収録分~ 展開の整理「血の盃編」に入ってからは、ころっころ様相を変える精神世界の中でドタバタしており、また1話1話の本誌掲載も間隔が空いているので、読者的にはなかなか流れが掴みづらい状況です。47巻収録分に入ってから、ここまでの流れを整理すると、下記の通りです。(第269話)・ヨナ姫・ハク様・三龍(キジャ・シンア・ジェハ)が盃の中から出られない状況・現実世界(緋龍王の廟)で5名の帰還を待つスウォン様&ゼノ →状況打破のため、スウォン様が緋龍王の亡骸を剣で突き刺す →盃の中から龍神三体が怒って現実世界へ →スウォン様に攻撃しようとするところをゼノさんが庇う・龍神がいなくなった隙に、ハクヨナは三龍を探す(第270話)・現実世界では、龍神たちとゼノの攻防が続くが、 これ以上もたないと判断したスウォン様は緋龍王の亡骸の首を落とそうとする →ゼノの中の「黄龍」が自我を失い、スウォン様を攻撃する →ゼノがそれを制止しようとする隙をつき、スウォン様が緋龍王の亡骸の首を突き刺す →龍神たちが苦しみ出す・盃の中では、ハクヨナが三龍と再会 ※ここまで展開の中で、三龍は能力の宿っていた右手・両目・右脚を失い、 人間になった(?)状態・黄龍に攻撃された龍神(白龍)が盃の中に戻り、キジャを吸収して回復を図ろうとする →ハク様がキジャを庇い、食べられそうになる・ヨナ姫は「緋龍王の剣」を使い盃を内側から突き刺し、壊す(第271話)・盃の世界が崩壊 →ヨナ姫は龍神(白龍)を剣で刺し、ハク様を連れ出そうとするが、 ハク様は「俺は後から行きます…必ず行きます」の言葉とともに、白龍に飲み込まれる →ヨナ姫+三龍は現実世界へ。・現実世界・緋龍王の廟では、瀕死のスウォン様&黄龍を制御し切れないゼノと 龍神(青龍・緑龍)が対峙を続けていた →ヨナ姫が「地上に来て一緒に居よう」と語りかけると、龍神は静まる(第272話)・龍神の加護が無くなり、二龍(青龍・緑龍)が消える →それと同時に緋龍王の廟も倒壊 →ヨナ姫は一瞬、死者たちの行き交う世界を垣間見る・ゼノは邪神化した黄龍と一体となっており、身動きが取れない状況 →キジャ・ジェハが付きそうことに・瀕死のスウォン様を外に連れ出そうと、ヨナ姫+シンアは彼を抱えて外を目指すが、 入口が塞がれて出られない →シンアが大声を出して助けを呼ぶ →城の外ではケイシュク・ユン・リリたちが、 スウォン様・ヨナ姫&四龍たちを助けようと懸命に動いている →シンアは「ヨナ姫が許す力を持ってこれまで歩んできたから皆ついて来た、 助けを求めていい」と諭す・ヨナ姫は「ハク様の帰りをここで待つ」と祈りを捧げる・一方、ハク様が目覚めたのは…明るい波打ち際…?■四龍伝説の終焉第269話~第272話までの4話で印象的だったのは、下記2シーンです。①スウォン様が自身の意志&自身の手で、「緋龍王の亡骸(&その首)」を剣で突き刺す緋龍王の亡骸は、建国時代より以降緋龍城の地下に存在し「龍神の加護」を発揮していた。建国以来の高華国の国家体制の大元にある存在であり、四龍伝説が政治基盤として活き続けてきたことの象徴。⇒高華国体制の基盤として存在した、政治面における四龍伝説の効力を、 現国王(=緋龍王の子孫)自らの手で終わらせた。②ヨナ姫が自身の意志&自身の手で、「血の盃」を内側から剣で突き刺し破壊する龍神たちと四龍(元人間)の契約に使用された血の盃は、血の契約の象徴。血を継承してきた四龍たちは、異能の力を得る代償として短命&不死の身体…と常に悲劇性を纏っており、再び「血の認める緋龍王」が迎えに来るまで、「呪い」と形容される状態で今日まで継承され続けてきた。⇒龍神たちの血の契約を、 ヨナ姫(=緋龍王の生まれ変わり)自らの手で終わらせた。いずれのシーンも「王自身が、自らの手で四龍伝説を終わらせた」ことが明確に、印象深く描かれていたと受け取っています。また、2人ともに共通して、もともと各々の側面における「四龍伝説」を終わらせる意志がある前提の上で、最終的に引き金となったのは、「ハク様(※)を守りに行かなければ」という急を要する場面に直面した、というシーン作りになっていたと思います。※厳密には、ハク様だけではなくヨナ姫や他の仲間たちも含めて…ですが、 2人の意識内ではハク様への意識が一番大きいと受け取っています。■残り話数について上述の通り、47巻収録分は既に4話分進んでいます。通常の単行本の場合、1冊の収録話数は6話ですので、もし47(ヨナ)巻完結を目指しているのであれば、残りは2話となります。花とゆめ21号(10/3)に第272話が掲載で、次回第273話は間を置かず花とゆめ22号(10/20)掲載予定とのこと。おそらく2025年中には完結見込で動いているだろうことが予想される状況ですし、クライマックス企画として開催していたキャラコン発表は21号、イラコン発表は次号・22号で消化予定です。本当に残り2話で終了予定なのであれば、22号(10/20)→第273話掲載+イラコン発表、23号(11/5)→休載(ヨナ付録有)、24号(11/30)→最終・第274話掲載 …という感じなのかな?などと考えつつ…でもな…アニメイトの花とゆめ連続複製原画特典フェアは、21号(10/3)から始まり7号連続…22号(10/20)、ザ花とゆめ姫(10/27) 、23号(11/5)、24号(11/20)、1号(12/5)、2号(12/20)まで続くらしいし…流石にヨナが掲載されていない(付録も無)本誌にこの特典は付けないだろうと思うけど、でもコンテスト企画の結果発表も弾がなくなるし、何より47(ヨナ)巻での完結はこだわって来る気がするんだよな…そうすると…花とゆめ1号&2号は、アフターストーリーチラ見せのショート番外編とかそんな感じ?…とかいろいろぐるぐる考えていますが、神(&白泉社・編集部&関連会社の方々)のみぞ知る感じです。いずれにせよ、22号掲載の第273話がどう展開するか…だな、と思っています。■解決課題&第273話以降の展開予想について残り2話なのかはさておき、残り数話であることは間違いないと思います。本編内で解決しなければならない課題・不明瞭点(と思わしきもの)を挙げ連ねると…こんな感じ↓でしょうか?(超緊急課題)・ハク様の安否・スウォン様の安否・スウォン様&メイニャンの緋の病は?・ゼノさん&黄龍の安否、行く末(未だ真相が不明瞭)・スウォン政権最大の矛盾:なんでスウォン様は、 謀反劇を『ハク様を追い出すような』やり方で実行したのか?・親世代の真相:カシ様暗殺はユホン様指示認識で本当にOK?(今後の課題・行く末)・今後の高華国の運営体制・高華国の体制基礎となっていた四龍伝説は完全に終結を迎えそうだけど、 結局ヨナ姫(緋龍王の生まれ変わり)が次期国王になるのか?・単行本46巻末で、ハク様から「結婚」の単語までは引き出したが、 ヨナ姫を本当にちゃんともらってくれるのか?・能力の宿っていた身体の一部を欠損したキジャ・シンア・ジェハはこの状態のまま?・各部族の行く末・各キャラクターの行く末上記項目の中にはもちろん、触れられないものもあるだろうと思いますし、本編中では触れず、番外編/アフターストーリーという形で出すものもあるかもしれませんが、…うん、それにしても多いな。272話で、ひとまずゼノさん&黄龍以外の龍神(白龍/青龍/緑龍)は消滅した?ようで、攻撃されるような余談を許さぬ状況は脱した(?)様子。あとは、目下安否が不安視されるハク様・スウォン様・ゼノさん(黄龍)に焦点が当たるだろうと予想されます。第272話のラストカットは、現世とは異なる世界に居る?ハク様が目覚めたシーンのようです。※ヨナ姫がハク様を思うモノローグからの繋ぎで登場してますし、 この黒髪の男性はハク様でいいんだよね?? 髪の毛が長いので、実は一瞬「誰っっ!?」って思いました。おそらく次回・第273話は…安直に考えれば、現世と死者の世界との間において繰り広げられる、ハク様&スウォン様の対話劇になるのでは!!?…と今のところは思っています。草凪先生の前作「NGライフ」においても、最終回の3回前で主役の敬大くんが頭部負傷&意識不明となり、最終回の2回前~1回前では、敬大くんの意識が前世の世界線に飛び、その目で真相を確かめるとともに、彼の前世であるシリクスと直接対話するシーンが描かれ、心の枷が解消された形で現世に戻って来ます。話の構成としては、暁のヨナのラストも、上記NGライフのクライマックス↑と近い印象になるんじゃないかなぁ…(安直)…っていうか、私がそれを見たい。スウォン様&ハク様…君たちにはまだお互いに確認すべきことが…あるんじゃないのか!?あとは、スウォン様&メイニャンの緋の病等、ぐるぐるした龍神の妄執の最終的な問題は、黄龍に責任持って引き取って天に還ってもらえばいいんじゃね!?(雑)というか、「龍神たちが緋龍を天から呼ぶ」ことが緋の病の原因なのであれば、龍神たちが四散した(?)と思われる状況なら、病自体発症しないのでは??…ってことは、龍神たち(白龍・青龍・緑龍)が木端微塵に消滅して、黄龍も自発的に消滅してくれれば問題解決じゃね!?(雑)諸問題を解決し切って、不明瞭部分の真相もある程度の外観はきちんとはっきりさせた上で(詳細をどこまで語るか分かりませんが)、その上で、どういう形で今後の高華国の体制を形作っていくかは、キャラクター同士で話し合って、国の構成員たちの大多数が納得のいく形を作っていけるといいなぁ、と思っています。…はい。こうやって感想を書いて来てみて思いましたが、もしNGと近しい構成でラストを駆け抜けるとしても、NGではこの段階から最終回まではまるまる3話かけていた上、単行本には、本編では描き切れなかったサイドキャラの心情独白や、主役カップルの後日ラブラブ譚等を、ページ数の許す限り全力で投入されていました。NGライフとは比にならないほど大人数のキャラクター群を抱える暁のヨナで、何をどう考えても、あと2話での完結は…無理だろうな。…うん。10/20にはもう次話・第273話が花とゆめ22号に掲載されますので、取り急ぎで今の考えを書きなぐりましたが、…実際はどんな感じになるのかなぁ…??ドキドキハラハラで待ちたいと思います。21号のクリアファイルが可愛くて、妹が描いたイラスト♪次号22号にも描きおろしイラストのクリアファイル(四龍)が付くそうで…!バックハグがコンセプトかな?楽しみです~!by姉(イラストby妹)
2025.10.13
コメント(0)
-

完全新作アニメ「らんま1/2」 第2期!大歓喜イラスト🍥
完全新作アニメ「らんま1/2」第2期が放送開始しました!第13話&第14話を鑑賞しました🍥もうもう…原作のノリに超忠実で、乱馬くん&あかねちゃん(乱あ)が丁寧に描写されていて、すごく嬉しいです‼OP&EDも超可愛い❤おそらく1期から取り組まれていたであろう「デフォルメへの挑戦」がこなれてきていて、ワンシーンワンシーンの切り替え&情報量の多さがキレてきているなぁ!…と感じました。※らんま1/2は、ギャグ・バトル・ラブの面白味要素てんこ盛り作品です。シーン毎に必要な質感/重量感等が異なるため、今作では1話目からとにかく「シーン毎に必要に応じてテイストを変える」意図=アニメーションのデフォルメへの挑戦心を感じてました。アニメーター様たちも、キャスト様達もすごくノッてきているというか…楽しんで制作されてるんだろうなぁ!と感じることが出来て、それが長年のファンとしては一番嬉しいところです!ムース&右京も登場し、ドタバタラブコメが加速する2期!ますますイキイキと動き回るキャラクター達を楽しみにしてます☀️by 妹
2025.10.12
コメント(0)
-
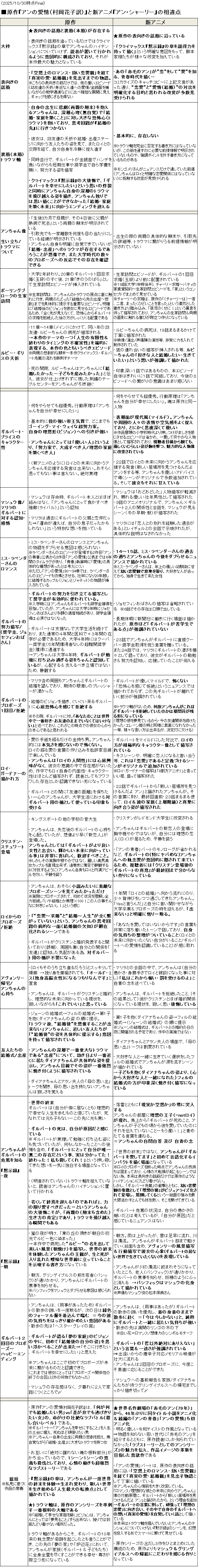
アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
先に、アニメ最終回・24話で感動したところについての感想は別途記事で吐き出していますが、ここでは原作とアニメとの相違点について、まとめを書き記していきたいと思います。アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について以前の感想記事から繰り返し書いて来ている通り、私たちは、特に『アンの愛情』パート(の後半、ギルバート1回目のプロポーズ頃から)は、原作と新アニメは全く異なる筋道を描いているものと認識しています。原作/アニメがそれぞれどのような考え方で筋を通しているのか、超勝手な私見をまとめました。下記相違表の前提↓・原作感想記事:『アンの愛情』感想・アニメ感想記事:第23話 感想+ロイ・ガードナー描写の原作との比較について・参考記事:「果樹園のセレナーデ」感想私は、基本的には原作で描いている「トラウマ軸」は、アンシリーズ…というか、「アンちゃんの人生」を串刺す根幹の大軸だと受け取って、原作シリーズを読み進めました。この「トラウマ軸」があるからこそ、孤児の女の子・アン・シャーリーが、後に結婚してアン・ブライスになり、家族に目いっぱい尽くして、愛し愛されて生きていける…それが彼女にとってどれほど「『夢』をはるかに超えたところにある、幸せな人生」なのかを説明できるんです。『アンの愛情』の1作品として、そして『赤毛のアンシリーズ』として、他の何を差し置いても、この「トラウマ軸」だけは絶対に抑えなければならない最重要軸だと思っています。…ただ一番重要な大筋なのに、このトラウマ軸は、原作中で明確に言葉で説明されていません。モンゴメリさんの「アンの愛情」周辺での公表作を読むと、トラウマ軸と類似した話筋の作品(果樹園のセレナーデ 等)も簡単に見つけられますし、他の作品でも、別の筋をたどっているように見せて、明言しない形で「本筋」を匂わせる手法は多々見受けられます。そのため、私は「アンの愛情」が描いている本筋はトラウマ軸で間違いないと考えていますが、もしこのトラウマ軸を捉えていなかったとしても、作品自体は楽しむことが出来ると思っています。何故なら、ちゃんと「表向きの話筋」が用意されているからです。アンちゃんの結婚観の欠如した思考回路や、『黙示録』シーンの彼女のハイテンションについて行けない等、ところどころに違和感を覚えつつも、最終的には「ギルバートとの結婚」という同一のゴールにたどり着けるんです。今回のアニメ『アン・シャーリー』は、「アンの愛情」の本筋であるトラウマ軸を通した作りにはなっていなかったと思っています。上記表にも書いてありますが、やはり表向きの話筋だけでは「何故アンちゃんが1回目のギルバートのプロポーズを固辞したのか」は説明し切れていないと感じますし…またそもそも論として、「ずっと想ってくれている幼馴染のギルバートを振って、ポッと出の当て馬(金持ち)と付き合うアンちゃん」とか… 何故こんな…読者・視聴者が誰も見たくないような話筋の物語なのか、その意義の説明は難しいと思います。…だけど、本当に本当に超面白かった!!脚本家さまたちが、「表向きの筋道」を極力違和感なく通そう!『黙示録』のアンちゃんのハイテンションに、視聴者がついていけるようにしよう!とギルバートやロイの表層面のキャラ変、恋愛のニュアンス改変、アンちゃんのモチベーション筋作り…と、あらゆる手段を使って、全力で「表向きの筋道」を繊細且つ大胆に盛り、またアニメーションの強みも最大限活かして、ビジュアルの作り込みで視聴者を「納得感」になぎ倒すよう、最終24話を超魅力的に駆け抜けてくださっていたからです。上記比較表を書き出しながら、アニメの脚本家様たちがどこを丁寧に作り込んでいるかも改めて認識できました。原作では、「表向きの話筋では繋がらない」ように、意図的に構成してある部分です。そこを原作の作り込みとは逆張りの形で、「絶対につなげる」意志をもって改変しているのですから、凄くパワフルでした。いや~~…面白かったです。私たちは、今年に入ってからアンシリーズにドはまりした超にわかファンですが、他の誰よりも、新アニメシリーズ鑑賞を楽しんだ自信があります!(言わせとけ案件)今回の新アニメをきっかけにして、(私たちのように)赤毛のアンシリーズ自体に興味を持った視聴者も多かったと思います。アニメ自体、映像も音楽もキャスト様も、皆一様にハイクオリティの本当に素晴らしい意欲作で…新アニメを制作してくださり、ありがとうございました!の気持ちしかありません。原作のアンシリーズ、モンゴメリさんの他の作品、アンシリーズの他の映像作品や、その他もろもろのメディア展開…赤毛のアン沼はまだまだ深く、ただっ広いものですので、今後はぼちぼちと、無理のないペースで鑑賞&感想投下を続けていきたいと思っています。<雑談>◆アン・シャーリー24話(最終回)放送後、X(旧Twitter)に投稿したポスト↓想像以上に多くの方に見てもらえて、嬉しかったですw赤毛のアン 原作ギルバートもおススメです🍎「原作版ギル」と「アン・シャーリーのギル」には「映画版ジャイアン」と「きれいなジャイアン」位の差がありまして!アニメの爽やかギルも超素敵でしたが、原作も女神命の超おもしれー男なので‼是非見比べてほしい‼◆アン・シャーリー熱が高じて作った、自分の自分による自分のためのアン&ギルバートグッズ↓ハート型キャンディアクリル です❤(何をやっているんだ…) 半年間、赤毛のアンシリーズにどっぷりはまって、いろいろ考えて記事もたくさん書くことができて…本当に楽しかったです!by姉(X用ポスト&グッズ作成:妹)アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.10.05
コメント(0)
-
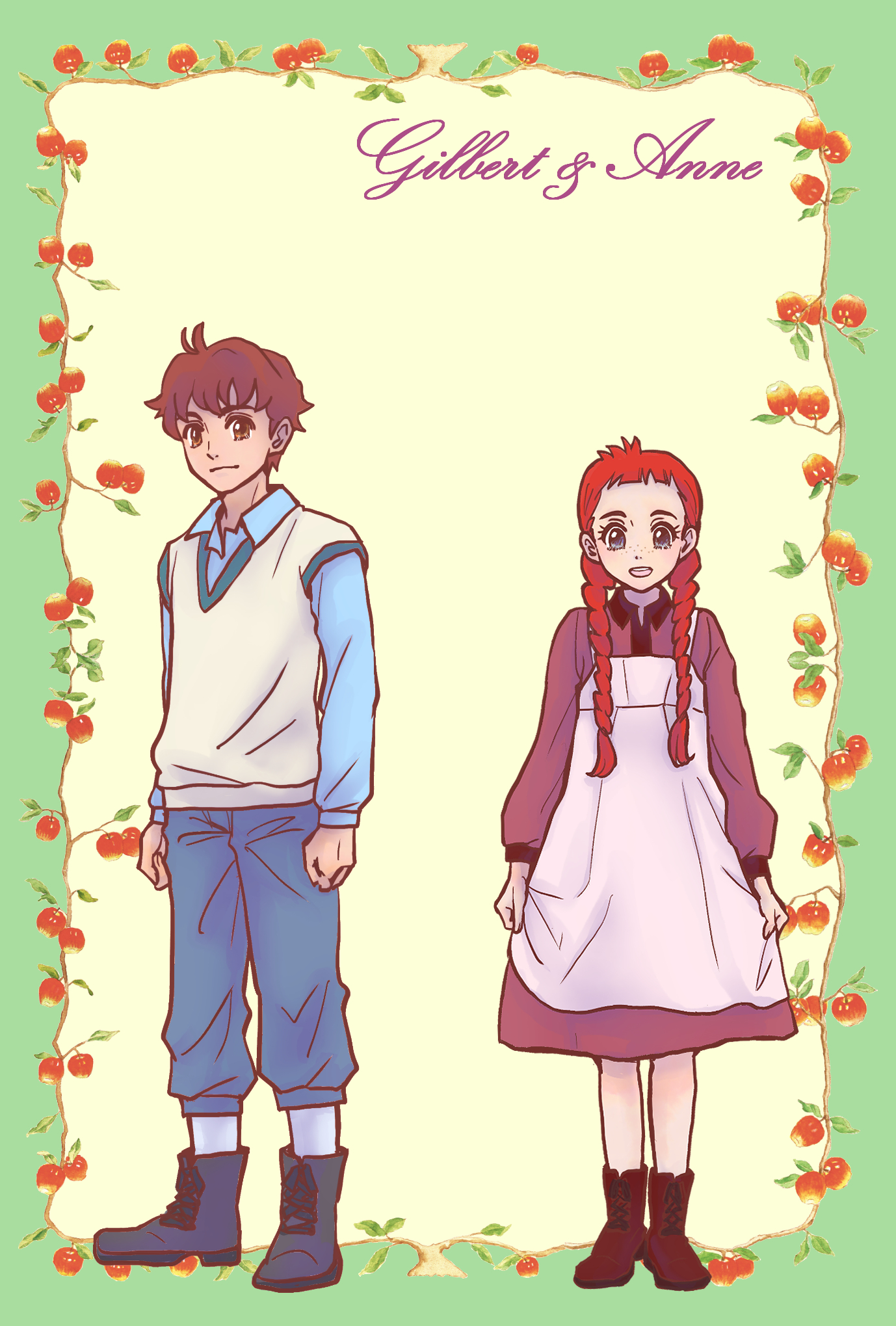
アニメ『アン・シャーリー』最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&after イラスト
アニメ『アン・シャーリー』最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&after イラストアニメ最終回・第24話を鑑賞しました!ひとまず、アニメ本編の中で素晴らしい!と感じたシーン等についてメモ的に書き記したいと思います!*これまでの感想でも書いてきた『原作とアニメの筋立ての違い』は、こちらの記事にまとめました↓アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について*以下、最終回ネタバレを含むため、未鑑賞の方はお気をつけください。*■アニメ最終回・第24話について前回・23話のラストで、ロイからのプロポーズに対しアンちゃんが「結婚できない」と返したところで最終回へ。まだまだやるべきことがもりもりで、ジェットコースター展開になるべく最終回がどのように描写されるのか、ものすごく楽しみにしていました。…鑑賞し、とにかく圧巻!!!!いち視聴者の安易な予想など歯も立たぬ…魅せたいものを暴力的に叩きつけてくる様々なシーンのキレッキレ描写が本当に素晴らしかったです!!ひとつひとつのこだわりに、…なるほど!!やられたぜ!!とノックダウンしながら鑑賞しました。・ロイのプロポーズ→拒絶→フィルと会話→ドロシー(ロイ妹)と会話ギルバートの1回目のプロポーズシーンと被せたシーン作りになっていましたね。アンちゃんが自分自身の感情を整理できた上で、「愛していないから」と言っていることが伝わってきました。ここからフィルやロイの妹との会話をわりとじっくり描写したため、最初はひたすら「尺が…残りの尺が…」とハラハラしながら鑑賞してました。しかし本当にアンちゃんの表情が逐一良い。申し訳ない気持ちはあれど、すごくすっきりしたんだな…と顔つきだけで分かりました。演技のニュアンスが徹底されていて素晴らしかった!・アヴォンリー・グリンゲイブルスへ帰宅アンちゃん、マリラ、リンド夫人3人の会話がほっこりしました。マリラだけでなく、リンド夫人が身内として娘のようにアンちゃんを愛し、可愛く思っていることが伝わって来て好きなシーンです。マリラは、ギルバートの話を振った際の反応を見て、アンちゃんの中にギルバートに対する愛情と後悔の念があることを全部察している表情が素敵でした。子どもを抱くダイアナ&フィルの愛に溢れる結婚式を祝福し、マシュウの墓前で「私も幸せよ…!」と告げる…無理してるんですよ。フィルの結婚式での涙も、友人のためだけのものじゃないんですよ。何も表現が入らなくても、彼女の心の中で「ギルバートへの想い」の存在をすごく感じさせる描写で、素晴らしかったです!そして、アヴォンリーに帰って来てから、テンポが一気に早まります。ここからの流れは圧巻でした!・白い花=ロマンス/想像の世界のモチーフアンちゃんの部屋の目の前にあった大きな桜の木「雪の女王」が大風で倒れてしまい、切られてなくなっていることにショックを受けるアンちゃん。第1話、歓喜の白路に始まり、雪の女王…と、アンちゃんの持つ「想像力」の体現として印象深い「白い花」を、最終回を通して一貫した「ロマンチック/想像力」のモチーフとして、画面作り・小道具に活用していて素晴らしかったです。・黙示録フィルの結婚式(ボーリングブローク)に参列し、アヴォンリーに戻って来たアンちゃん。グリンゲイブルスに帰宅すると…そこでギルバート危篤の報を知らされます。マリラ・リンド夫人・デイビー・ドーラそれぞれがアンちゃんに気を使いながら話しかける姿も印象的でした。嵐の夜、自室の窓辺でギルバートの死に直面するアンちゃん。雷が落ちて家の隣の木を真っ赤に燃やし、ここから一気に「現実か空想か」の境に突入します。彼女の目の前に現れた「白馬に乗った理想の王子(notロイ)」は、悲しげな表情でアンちゃんにギルバートが死ぬこと、アンちゃんが彼に愛していると伝えていないこと、…「もう遅い!」と責めたてる言葉を連ねてきます。このシーン、原作ではアンちゃんがひたすらその心情を独白するシーンなのですが、今回のアニメでは、極力、原作のアンちゃんのセリフをそのまま使いながら、彼女自身がやっと言語化にたどり着いて放つ「ギルバートを愛してます!」の一言を一番際立たせるシーン作りとなっていました。鑑賞者には、きちんとこれが「アンちゃん自身の自問自答及び自責の念」だとが分かります。「後悔~独白」をこうやって…こんな形で映像化するのか!とぶん殴られる衝撃がありました。誰だこんな奇抜な表現方法を考えついたのは!!凄かった!!最高でした!!・朝方、雨上がり…だけど雲は足早に流れ、川は濁流。ギルバート邸に駆け付けるも、ちょうど医師が迎え入れられるところを目撃し、話しかけることが出来ず帰路につくアンちゃん。小学校時代、ギルバートに命を助けられたにも関わらず、意地を張って彼に悲しい顔を指せた場所である川の橋を渡りながら、気持ちが濁流に飲まれそうになるアンちゃん。そこに一人の老人(パシフィック)が通りかかる…ギルバート邸の隣で働くその老人に、ギルバートが今朝方快方に向かったことを聞き、喜びで足元から崩れ落ちるアンちゃん。老人は「白い花のついた小枝」をアンちゃんに手渡しつつ、妖精のようにふっと消えていきます。ギルバートのもとに駆け出すアンちゃん…濁流に飲まれそうになるアンちゃん…これら朝方のシチュエーションづくりは、完全にアニメオリジナルです。※原作では、アンちゃんがグリンゲイブルスの前を通りかかるパシフィックに声を掛けます。アヴォンリーの様々な風景と空気感で、アンちゃんの心象を表現する…アニメーション万歳!!な作り込みで、本当に感動しました。…そしてパシフィック=マシュウの化身!最高な改変ポイント!!前振りなく突然登場し、アンちゃんにギルバートの無事を伝える重要な役割を担うパシフィック。原作では若者であるパシフィックを、わざわざ老男性として描き、姿・体格は異なるけど、「目元がマシュウだ」と感じさせるデザインになっていました。パシフィックの声優様についても、マシュウ役の松本保典さんがあてられており、「自分の仕事の跡継ぎ(?)の若者を駅まで迎えに行く」という言葉も、第1話のマシュウ像と被せて来てます。「なるほど~!これがやりたかったからこそ、第9話にアニメオリジナルで、アンちゃん×ギルバート2人の関係性と会話をマシュウに見せるシーンがわざわざ入ってたのか!」とすごく腑に落ちました。仕込みが凄い!その後、ギルバートの枕元で安心して涙ぐむアンちゃんの姿も描かれましたが、この辺は「現実か、空想か」どちらと捉えてもいいよ、という描き方になっていたと思います。(このシーンが、アンちゃんorギルバートの空想だったとしても、もちろんアンちゃんには「ギルバートのもとに駆け付けて顔を見たい」気持ちがあって、ギルバートもそれを感じてるよ…ということは分かりますので。)・お散歩~2回目のプロポーズラスト!アンちゃんとギルバート2人の2回目のプロポーズシーン。わざわざ原作の「フォーマルな緑服を着込んで場に臨むアンちゃん像」からは外した形で、ギルバートの誘いの機会を逃さず「着の身着のままで散歩に向かうアンちゃん像」にしてありました。ギルバートの明るい髪色もそうですが、わざと「原作とは違うイメージ像だよ」というメッセージを込めて制作されていることを感じました。そして…ここでアニメオリジナルシチュエーションとして、満開のリンゴの木!暗がりの中、真っ白orピンク色に輝く花が幻想的でロマンチックでした!話の流れとして、つまらない意地が邪魔して、ギルバートが差し出した手を取ることが出来なかったアンちゃん…という、第7話・エレーン姫のときと同じ流れをたどっており、だからこそマシュウが言った「ロマンチック」を体現する満開のリンゴの花が本当に映えました。ギルバートの一言一言に反応する、アンちゃんの本当に細かな表情動作!ギルバートの、爽やかさの中に「ここで決める!」という確固たる意志を感じる演技筋!絵・声ともに丁寧に丁寧に詰められていて、本当に見ごたえがありました。ギルバートの言葉:「君が僕の頭に石板をたたきつけたあの日から、ずっと君を愛して続けてきた」から、アンちゃん目線でのギルバートメモリアル~睨みつける・拒絶する・手を振り払う・悲しい表情をさせるという、ろくでもない歴史の数々~アンちゃんの言葉:「不思議だわ こんなお馬鹿さんなあたしをどうして愛し続けて来られたのか」。…ココの流れが最高でした!もともと私と妹の間では『黙示録』のシーンで、優しかったギルバートメモリアル映像が来るのでは!?」と予想していましたが、まさかここで!こんなに可哀想な…ろくでもないメモリアルが来ると思わないじゃないですか!誰だこんな可哀想なシーン編集をノリノリでやったのは!!…最高でした!!その後、ギルバート目線から見る「リンゴの花(想像力)を背負った女神・アンちゃん」が最高に輝いていました!・ハッピーエンディングラスト、3年間の遠距離後の結婚式シーンまで見せるのかな?と安直に思っていましたが、「お似合いのウェディングの絵面」は既に22話(ダイアナの結婚式)で、キスシーンも大盛り上がりで描写した直後ですので、それはありませんでしたね。本当にきっかり、『アンの愛情』終了まで。ただ、マシュウ&家族たち(+ダイアナちゃん家族)が待つグリンゲイブルスに帰結する形での締めシーンとなりました。最後の最後、倒れてしまった「雪の女王」に新たな芽吹きが描写され、新しい大樹が生まれる兆しも感じさせるラストカットが素敵でした!いやぁ~~…本当に渾身の渾身の渾身の最終回・24話でした。第1話より、毎週ウッキウキで鑑賞を続けて来て、こんな素晴らしいラストシーンを拝むことが出来て、観て来て良かった~~~!!と心から思います。『赤毛のアン』時代と『アンの愛情』時代のお二方↓。アンシリーズの映像化作品に精通していないので、想像での発言ですが、モンゴメリさんの原作発表から110年以上…アンシリーズは幾たびも映像化はされてきていても、本アニメーション作品が、『アンの愛情』本編&その強烈なクライマックスシーンの映像化に本気で真正面から取り組んだ、いちばん最初の作品なのではないかな、と思っています。スタッフ・関係者の皆様、キャストの皆様、ギラついた本気がまぶしい、素敵なアニメーション作品をありがとうございました!!この作品を機に、改めて『赤毛のアン』の原作やモンゴメリさんの他作品から履修し、まだまだ道半ばではありますが、完全にその魅力の虜になってる、令和新規ファンは、半年間、全力で楽しませていただきました。X(旧Twitter)懸賞で妹が当選した番組ポスター♪↓あ~~~面白かった~~~!!!by姉、イラストby妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.09.28
コメント(2)
-
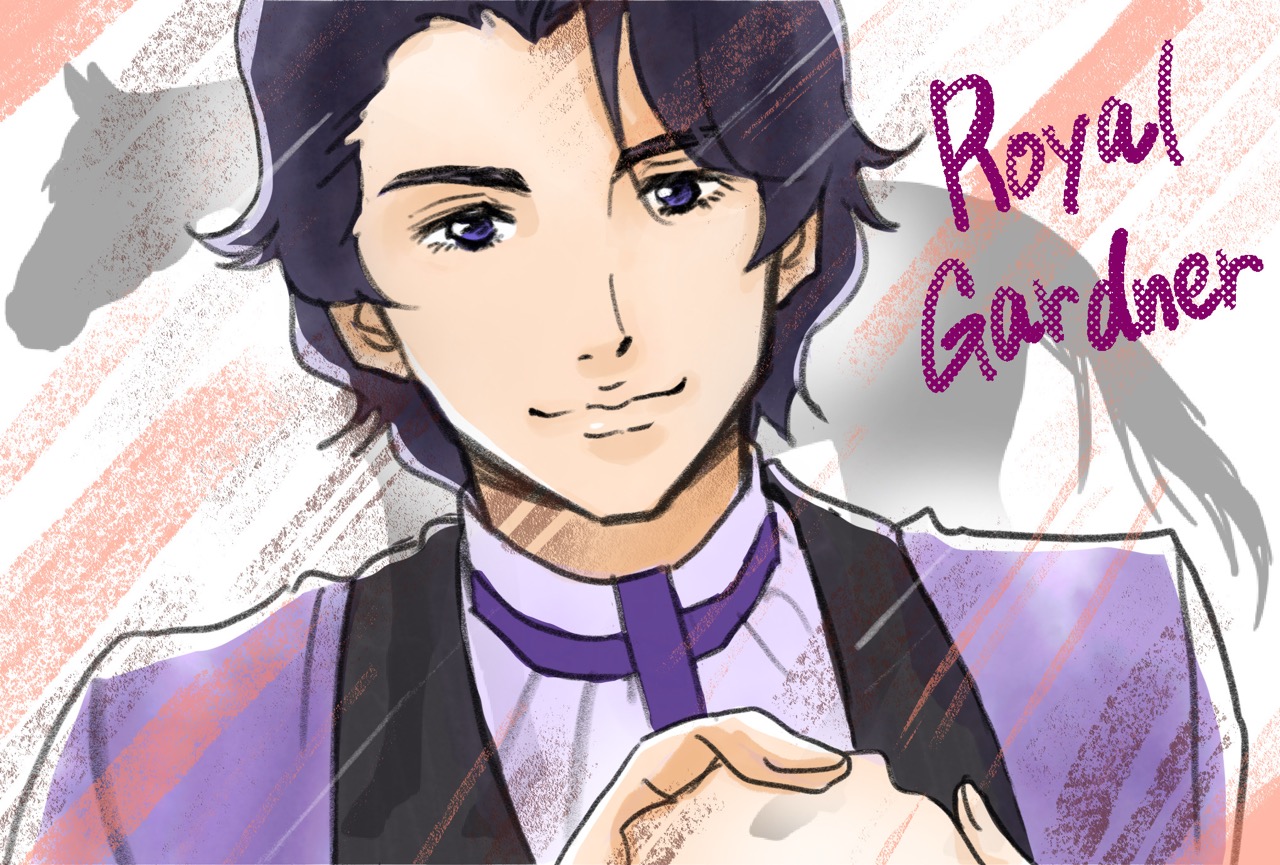
アニメ『アン・シャーリー』第23話 感想+ ロイヤル・ガードナー描写の原作『アンの愛情』との比較について
アニメ『アン・シャーリー』、今週土曜日9月27日が、最終24話の放送です!最後まで鑑賞した後、総括しての感想はしっかり書きたいですが、今の時点で言いたいことを簡単に書き出します。アニメ『アン・シャーリー』第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写の原作『アンの愛情』との比較について前回の記事でも比較表を書き出して語りましたが、私たちは新アニメは、原作とは異なる筋道で、説得力を持ってクライマックス『黙示録』の章にたどりつこうと、脚本家様たちが練りに練って様々な改変を加えているのではないかと受け取っています。23話は、原作とアニメの違いが一番顕著に見て取れる話だと思いました。同じ話筋をたどっているようで、全く描いているものが違っているので、新アニメの脚本家様たちが何をやっているかも本当によく見て取れて…そうするとまた、比較して原作は何をやっているのかも改めて認識できて、…すごく面白いんです‼*以下、全部自分たちの勝手な私見による「原作と新アニメの相違点」の話をしており、また今後のネタバレを含むため、原作未読の方はお気をつけください。*■アニメ「アン・シャーリー」23話22話で、ダイアナの結婚式&彼女が新しい生活に向かう姿を見送り、その帰り際、ギルバートに「新しい居場所を見つけるんだよ アン」と諭されたアンちゃん。ギルバートの隣には既に新しい恋人・クリスチンが居る状態…23話ではギルの言葉に則る形で、アンちゃんが再び小説応募にチャレンジしたり、新しい居場所となる?ガードナー家との交流を深めながら、大学生活残りの1年を過ごします。キラキラで生活感のない王子・ロイも、家族/家が描写され地に足が付いた存在に見え始めつつ…上流階級の人々との交流の中で、アンちゃんが背伸びして立ち振る舞う・取り繕う姿を絶妙に描写しています。そして迎える、ロイからのプロポーズ。「Yesと言うんだ」とアンちゃんは自分に言い聞かせながらその時を迎えますが、本当の本当に決断を迫られたその時に「出来ない」と悟り…断ってしまいます。20話ではロイとキスシーン及び「恋人同士になる」と言い交わすシーンもあり、きちんと「理想から入る恋愛」をして、相手やその背景にも向き合ったうえで、最終的に「この人の世界」に飛び込んで生きていくことは出来ないことが分かる…大なり小なり誰もが一度は体験する苦い体験…「自分を知る瞬間」が丁寧に繊細に描かれていて、とても見ごたえがありました!23話の面白さは、本当にまるまる本作の脚本家様たちの手腕だと思います。…なぜなら、原作『アンの愛情』には、キスシーン&しっかり恋人同士だと確認し合うシーンがないばかりか、ロイというキャラクター自体、描写やセリフがほとんど登場しません。ギルバートの「新しい居場所を見つけるんだよ アン」という言葉からして存在せず、「新しい居場所に無理して向かおうとするアンちゃん」「ロイ&その家族たちと真摯に向き合うアンちゃん」など、まったく描かれていないからです。■改変箇所、原作における描写について今回、なんで脚本家様たちが力を入れて「ロイの描写&アンちゃんの意識筋」を大きく変えて盛ってきたのかは、すごく分かるんです。原作のアンちゃんの意識筋が、あまりにもおかしい からだと思います。アンちゃんは、ロイを極論「人間だと認識してない」くらい…彼の気持ちとか考えない。相手方の親&姉妹まで出て来て、はっきりと結婚がちらついているのに、全然自身にとっての重大事として向き合わず、結婚後の未来について微塵も思い浮かべない。ロイからのプロポーズ直前まで「理想のプロポーズをしてもらえれば、私は『イエス』って言うんだろうな」とか軽く考えてるのに、いざその場が来た瞬間に「無理無理無理無理!×100」ってなって、「結婚できない。好きだと思ってたけど、そうじゃないことが今分かった!」とあまりにもひどい非人道的な振り方をした挙句、アンちゃん自身はその後すぐに「あ~すっきりした!素敵なオールド・ミスの道を歩むぞ♪」と、晴れやかにアヴォンリーに帰って来る……おかしいんですよ。このくだり。だってアンちゃん、普段はこんな娘じゃないですもん。もっとちゃんと、周囲の人たち皆を肯定的に捉える力があって、もちろん、他の人の気持ちもちゃんと考えられる娘なので。今回の新アニメでは、脚本家様たちが、原作のこの「おかしい・不自然に感じるアンちゃんの意識筋」を極力丁寧に詰めて、改変して、きちんと「理想的な恋愛をしてみたけれど、未来にはつながらなかった」筋として頑張って作りこんで来てる…本当に真摯な作りで、感動しています。…でも、じゃあ そもそもなんで原作はこんなおかしな書き方になってるのか?という話なんですが、答えは簡単で、『アンちゃんのおかしさ』を一番顕著に表現する為のシーンだからだと思っています。『アンの愛情』の本筋はトラウマ軸だ!という私見は 『アンの愛情』感想記事 でもさんざん語ってきましたが…要は、アンちゃん本人は無自覚だけど、深層でものすごく「結婚」を怖がってる。理想の「恋愛~求婚」は思い描くけど、思考回路がその先・当たり前にあるはずの「結婚~人生」まで絶対行き着かない。その手前でシャットダウンしちゃう。(結婚というか…一番怖いのは極論「出産」だよね、と妹と話してまして…両親の顛末は、詳細までは明言はされてないけど、おそらく母親が、アンちゃん出産後3カ月…体力が回復し切らない段階で熱病で重症化してしまい、必死に看病してた父親も道連れのような形で2人とも亡くなったんだよね…コレ。出産と両親の悲劇との因果関係ははっきりとは言えないにしても、そうなんだろうな…と想像はしてしまいます。)自分自身の出産にまつわる両親の悲劇を抱え、自身も生後3カ月で身寄りも何もないところに放り出され、引き取り先においても一家離散を何度も目の当たりにしてきたアンちゃん…「この娘には、『結婚・出産』に対して根深く巨大なトラウマがあるよ」って…可哀そうだけど、しっくりくる話だと思うんですよ。ロイや家族、その先に本来は当然思い描くべき結婚のビジョンがあるのですが、それらをあまりにも捉えられないアンちゃん。おそらく「お金持ちの一族に加わると、どんな暮らしになるのかな」という想像すらしなかったのではないかな、と思います。「鈍いとか、幼い恋愛観とか、ひどい女とかいうレベルではなくて、この娘のこの部分(結婚)に対する思考回路、『病気』でしょ⁉」って言いたいのが、モンゴメリさんが書いた原作筋:ロイ・ガードナーのくだりのニュアンスが表現してるものだと思っています。アンちゃんの認知の歪みを表現するためのエピソードなので、「ロイとか、新アニメでは本当に『へのへのもへじ』で表現してくるんじゃないか?」と…アニメが始まった当初は、私と妹内では本気で話していました。■表向きの話筋と本筋「トラウマ軸」幼い「空想上のロマンス」を経て、「真実の愛」を見出すまでの物語。…原作中で明言された言葉だけを拾って、アンの愛情のあらすじを語ろうと思うとこうなると思いますが、私たちはこれを「表向きの話筋」、モンゴメリさんが書いている原作の本筋は「トラウマ軸」だと認識しています。(だってアンちゃんは「空想好きな子」ではあるけど、それはつらい現実世界でだって楽しく日々を過ごしていくために幼少期から培った逃避方法であって…決して「夢と理想を追い求めるあまり、目の前にある大事なものを見失う」なんて娘ではなかったので。)モンゴメリさんの他の作品においても、トラウマ&越えられない心理的ハードルはテーマとして頻繁に登場しますし、作りこんである本筋をあえて隠し、別の視点からの筋を描きながら匂わせていく…という手法もよく使われています。「アンの愛情」(1915年)は、シリーズ2作目「アンの青春」(1909年)から6年間もの間、熱烈なファンを待たせに待たせて繰り出した、皆さんお待たせしました!という超渾身のラブストーリー作品だと思います。アンちゃんが人生の主軸を何に据えて生きていくかを決定づける重要作です。歯に衣着せぬ言い方をすれば、幼い「空想上のロマンス」を経て、「真実の愛」を見出すまでの物語。…だけの筋道をたどるような、そんな…誰も読みたくないような 馬鹿みたいなテーマの作品を、心情構成の神・モンゴメリさんがわざわざここで出してくるわけないよね‼⁉…と思います。…思ってました。だから今回のアニメ『アン・シャーリー』が、本当に真摯に、表向きの話筋を繊細に詰めて描いて来て…ロイに真摯に向き合うアンちゃんとか、最終回直前の23話まるまるかけて描写されて、びっくりして「…おぉおおうっっ!!」と変な声が出ました。…それがちゃんとラブストーリーとして魅力的なんですよ!!もともと、本作のコミカライズのキャッチコピーに「あの「赤毛のアン」が”恋”をして”愛”を知る、青春時代を描くー」と書いてあったので、きっとアニメ本編も、アンの愛情パートは表向きの話筋の方をメインで描いてくるんだろうな、とは思っていました。想像してた通りのはずなのに、まさかここまで頑張って、魅力的に見える形まで作り込んで出してくるとは想像していませんでした。…なんっっって 原作と逆張りのところを渾身で描写して来るアニメなんだ!だが、これもこれですごく面白い!!!妹がノリノリで描いたロイ・ガードナーのイラストです。妹はロイの話をするとき&絵を描くとき、必ず馬モチーフ/馬アイコンをつけて来ます。※刮目!『当て馬』の元祖がここに居るぞ!という主張23話を鑑賞して、「へのへのもへじで描写するのも妥当なキャラクター」とか思ってて悪かったなと、心から思いました。…まぁ、何がどうあっても、原作と違ってアニメのアンちゃんがどれだけ真摯に向き合おうとも、最終的に当て馬であることに変わりはないんですけども。■クライマックスに向けてアニメ『アン・シャーリー』、土曜日の24話はいよいよ最終回です。原作の一番面白い所は…「アンちゃんのトラウマ軸が本筋」とかいろいろ書いて来ましたが、最終的に、「アンちゃんと結婚できない=アンちゃんを自分が幸せに出来ない」故に目指すべきビジョンを見失い、心労&勉強へ打ち込み過ぎでバランスを崩し、感染症に罹患し「死ぬ」をガチで実践してくる…脅威の執念系ラブファイター・ギルバート氏が全部持っていくところ。原作のアンちゃんは、ギルバートがちゃんと他の素敵な女性と婚約するまで見届けて(誤認)、自身は予定通り優秀な成績で大学卒業&ロイとも破談して、これからキャリアウーマンとして生きていく…彼女自身が向かうべき道にちゃんと進んでたんですよ。そのアンちゃんが…もうショック過ぎて…ここまで暗に描写してきた彼女の出生にまつわるトラウマとか、こだわりとか、自我とか、プライドとか…何もかもが全部パーンッって爆発四散する、強烈なクライマックスシーン『黙示録』。「トラウマを乗り越える」というより、「トラウマが爆発四散して消えてなくなる」とか、「それどころではない、新たなトラウマによって強烈に上書きされる」とか、そういった類のシーンですね。これはね。アンちゃんが、ギルバートに自我の強さで完全敗北する瞬間というか、…毒をもって毒を制す。本当に、あの壮絶なバックボーンを抱えるアンちゃんより、なんでお前の方が病気(重症)なんだ、ギルバート‼⁉…だが、分かる。帝王だから、仕方ないよな。アニメの方は、23話までで本当に丁寧にギルバートのいじらしさを描写してて、アンちゃんも普通にもうギルバートのこと好きだよね?と分かる描き方になってて、彼女が既に後悔しているので…黙示録~真実の愛の気づき~ハッピーエンディングの流れは、より素直な話筋に見えるのではないかな、と想像しています。いや~…原作との相違点をあれこれ考えるのも含めて、アニメ『アン・シャーリー』、本当に楽しく鑑賞させていただいてます。…最終回、しっかり見届けさせていただこうと思います!by姉、イラストby妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.09.23
コメント(2)
-
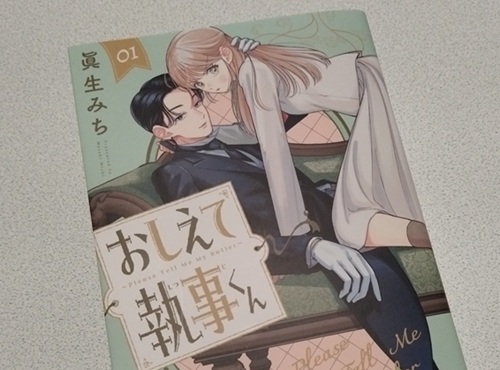
少女漫画感想「おしえて執事くん」1巻 眞生みち先生
久しぶりに新しい少女漫画を購入しました。超簡単ひとこと感想!「おしえて執事くん」1巻(眞生みち先生・講談社・月刊デザート・アプリPalcy)(公式・作品紹介)「わかったら浮気すんな バーカ」ずっと執事の花柳(はなやぎ)に片想いしている綺香(ききょう)。何度もアプローチをしているのに、花柳には全然響いてなさそうで…?片想いお嬢様×クール執事の可愛すぎる主従ラブコメ!講談社の漫画アプリ・コミックDAYSで1話試読し、面白かったので単行本を購入しました。あらすじにもあるように、ごまんとある「お嬢様×年上執事」のラブコメですが、キャラクターの表情や演技動作も可愛く、何より画面の緩急…光…空気感…!!漫画表現が達者過ぎて、読者の視線の流れのコントロールや、情報量の多い1コマ1コマに、少女漫画好きのにやにやが止まらなくなる作品です。あとは、魅せ方として、ヒーロー側は極力表情を動かさず、女の子・綺香ちゃんの可愛らしさに、両想いの説得力の根拠を全振りしているところが徹底的で面白いと思います。私のような、どうしても男目線から入って読み進めてしまうラブコメ好きにはしっくりくる描き方で、たいへん好みです。新しい漫画を購入出来て嬉しいです。続刊も楽しみにしています♪by姉
2025.09.21
コメント(0)
-
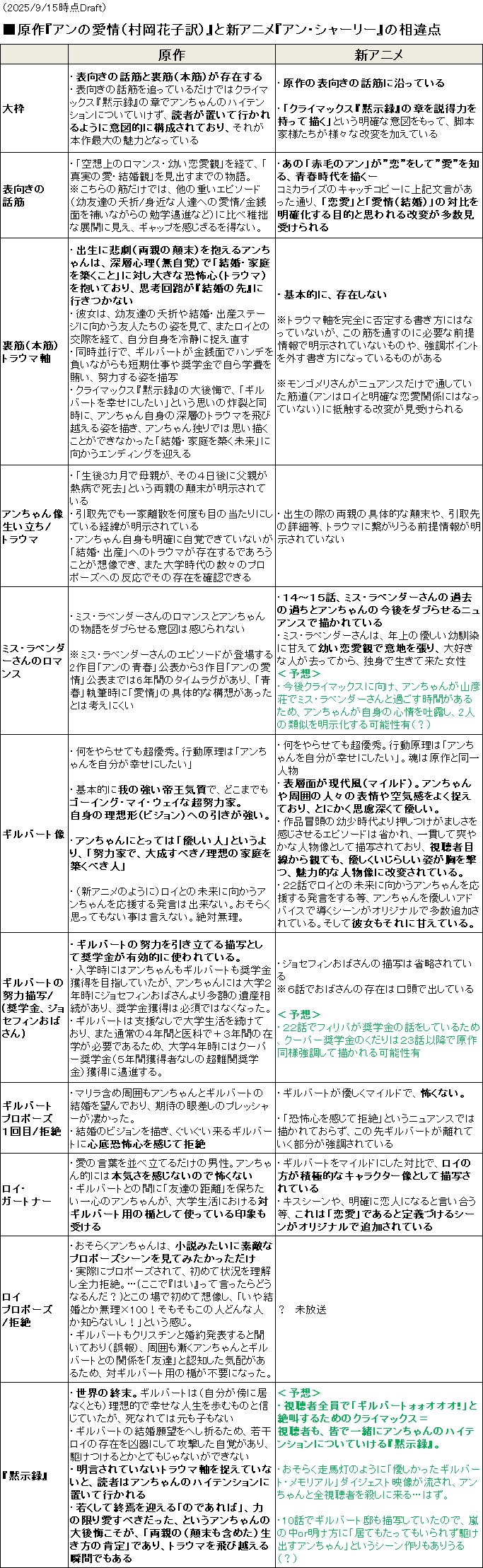
アニメ『アン・シャーリー』第21話・第22話 感想+原作『アンの愛情(村岡花子訳)』との相違点について
アニメ『アン・シャーリー』第21話・第22話 感想+原作『アンの愛情(村岡花子訳)』との相違点についてアニメ『アン・シャーリー』、物語も佳境!毎回妹と大騒ぎしながら鑑賞しています。現時点で「今回のアニメの筋はコレなんじゃないか⁉」「そうだったらこんな場面もありうるのでは‼」と、二人で好き勝手キャーキャー話し合ってる展開予想などを、とりあえずまとめてみました。*以下、全部自分たちの勝手な私見による「原作と新アニメの相違点」の話をしており、また今後のネタバレを含むため、原作未読の方はお気をつけください。*第21話でロイ・ガートナー&クリスチン・スチュワートが登場。第22話までで、ダイアナちゃんの結婚式まで終わったところ。ここまで鑑賞したうえで、私と妹の間では、新アニメは、原作とは異なる筋道で、説得力を持ってクライマックス『黙示録』の章にたどりつこうと、脚本家様たちが練りに練って様々な改変を加えているのではないかと話しています。まだ23話・最終24話が未放送ですが、今のところの情報で、原作と新アニメの相違点についてぐるぐる考え、書き出してみました。下記相違表の前提記事↓・原作感想記事:『アンの愛情』感想・参考記事:「果樹園のセレナーデ」感想新アニメの筋道については、今後の予測も思いつく範囲で書き込みましたが、さてどうなるか…?とにかくアニメ『アン・シャーリー』の脚本筋は、確固たる方向性を持って『黙示録』に向けて作り込まれているのだと思っています。そうでなければ、ギルバートのキャラ変(表層面)なんて思い切った改変はできないと思います。いや~~、本当に面白い!語りがいがある!アニメが最後まで放送されたら、上記相違点の一覧をアップデートして頭の中を整理したいです。アニメクライマックス!超渾身であろう『黙示録』のシーンが、どんな描写・ニュアンスで描かれるのか、本当に楽しみです!余談。原作では「面白味が無い」と評されていたロイ・ガートナーですが…極端な王子ビジュアル&積極性プラスによって、めちゃくちゃ面白キャラになってますねうっかり間違って、コレに嫁入りしちゃう女の奮闘記になったら…それはそれで面白そうかも?by姉、妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.09.14
コメント(0)
-
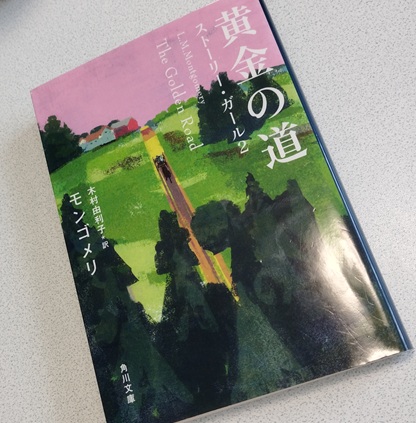
「黄金の道 ストーリー・ガール2」木村由梨子訳 感想+ アンの娘リラについて
「黄金の道 ストーリー・ガール2」木村由梨子訳 感想+ アンの娘リラについて「黄金の道 ストーリー・ガール2」 (1913年 ルーシー・モード・モンゴメリ/著木村由梨子/訳 角川文庫※元は1983年 篠崎書林より刊行)(角川文庫/背面あらすじ)季節は巡り、少年と少女たちはまた少し大人になった。情熱を込めて取り組んだ新聞づくり、魔女と呼ばれる女性との恐怖の一夜、お客を取り違えたおもてなし騒動などなど。プリンス・エドワード島の美しき思い出を胸に、今、彼らは別れと旅立ちの時を迎える。仄かな恋心や秘められた約束、そして周囲の大人たちのロマンチックな愛の物語をからめながら描く、虹のような声色をもつ少女、大人気ストーリー・ガール第2弾!先に感想を書いたストーリー・ガール(2011)の続編の物語。執筆は両作とも、アンシリーズの2作目・アンの青春(1909)~3作目・アンの愛情(1915)の間です。「黄金の道-The Golden Road」とは、モンゴメリさんの定義だと多感な子ども時代の、目に映るものの全てが、そして前途が光り輝いて見える時期…のことなのだと思います。本作を読んで感じたことを…上手く書けるか分かりませんが、備忘の為に吐き出しておきます。*以下、「黄金の道」及びアンシリーズ10「アンの娘リラ」のオチまで含めた内容について触れています。ネタバレを避けたい方はお気をつけください。*「黄金の道」を読んでの印象ですが、まず、第1作目のストーリー・ガールよりもキャラクターたちが生き生きしゃべっていて、キャラクター同士のお互いの認識も深まり、各キャラクターにとても愛着を持って読み進めることが出来ました。前作の感想でも、8人の幼馴染たちを絡ませて自由にさせているところが「虹の谷のアン」っぽい!と書きましたが、本作を読んで、今度は「アンの娘リラ」っぽい!と思いました。一言で言うと…空中戦。本シリーズは、特に最後どこに向かおう!と、大筋を決めて書き始めた作品ではないと思います。少年・少女時代でしか味わえない高揚感とか、スリルとか…そういったものを想起させるであろうものごとを子どもたちにぶつけてみて、キャラクターたちがわちゃわちゃするのを楽しむ。キャラクターたちの自発的な行動・感情の動き重要視して、自然発生したものの中で、このキャラクター同士の関係性は面白いな、とか、この感情は読者の目線筋の中でも活きるな、という部分をモンゴメリさんが拾って、1作の小説として体裁を整えてまとめ上げるような考え方なのだろうと思っています。それでいて本作「黄金の道」については、シリーズとしてまとめにかかっている…これがシリーズ自体の最終巻という認識で執筆されているので、当然読者としては、各キャラクターの行く末を常に気にしながら読んでしまいます。モンゴメリさんが、各キャラクター軸について、自発的な心情筋/他キャラクターとの関係性を的確に分析した上で、作品全体バランスを考慮しながら、「作中ではっきりと明示するorニュアンスだけで悟らせる」を使い分けつつ、読者目線を自在に操る魔女のような手腕で、なんとなく作品全体感として納得のいく形にまとめ上げていきます。本作では、ラスト近辺の第30章「予言」で、ストーリー・ガールが幼馴染たちの将来像について(お遊びっぽく)予言するエピソードがあります。主役のベバリーくんは、本書きになって世界中を回ること…弟のフェリックスくんは、一生太ったままだけど50歳前にはおじいちゃんになること…キング農場の長男・ダンくんは農場を継いで、11人も子どもが出来ること…ピーターくんは牧師さんになること、フェリシティーちゃんは牧師さんの奥さんになって幸せ暮らすこと、セーラちゃんは結婚するが、相手が難ありそう(?)なこと、長生きすること…等。これらの予言は、基本的には「出任せのお遊び」でも「本当」でもどっちと受け取ってもいいよ、という書き方になっています。ただ唯一1点、ストーリー・ガールが口をつぐみ明言を避けたセシリーちゃんの未来について、おそらくこの時点より間もなく…彼女は「黄金の道」を抜けることなく天に召されることが、主役・ベバリーの回想的な語り口に寄って明言されています。キング農場の次女(3兄弟の末っ子)のセシリーちゃんは、仲間内での喧嘩(特に兄・姉間の日常的ないがみ合い)に心を痛めたり、また親戚筋外で過保護な母親付・且つ 本人も少しピントが外れた発言が多く仲間内でも厭われがちなセーラ・レイちゃんに誰よりも親身に接する、徹頭徹尾争いを好まない聖女のような女の子です。この子が、本作途中頃より肺を悪くして咳込んでいる描写が度々挿入されて来ます。仲間内で一人、「黄金の道」を抜けることなく逝く…という本作のバランス構成それ自体が「アンの娘リラ」の全体構成の下地のような印象を受けました。セシリーちゃんの夭折は、もちろん悲劇なんですけど、読み切った時に妙な納得感があるんです。まず、「黄金の道」というパッケージ感として、美しい光輝く世界に少女が一人残るようなイメージ提示に説得力がある点。セシリーちゃんがあんまりいい娘なので、神様がこの姿のままで、この世界に留まって欲しかったのかな~…というふうに納得させられる…というか、飲み込むとしたらそうやって飲み込む、という筋道が見いだせます。また作中、セシリーちゃんのことが大好きで言い寄って来るストーカーまがいのクラスメイトが居まして、それに対してセシリーちゃんがとにかく嫌がって拒絶しまくります。モンゴメリさんの他作品を読んでいると、アグレッシブなヒーロー像はそれはそれとして受け入れられる描写も多く(ギルバートとか)、わざわざ、この男の子自身は将来は成功者になるよ…という書き方までされていたので、セシリーちゃんの全身全霊をかけた嫌がり方は、少し引っかかって読み進める部分でした。これがラスト、セシリーちゃんの夭折が明言されると、納得感につながります。そして何より、妹の夭折に向き合うことになる、ダンくんとフェリシティーちゃんへの影響の大きさ…ですね。ダンくんとフェリシティーちゃん(&セシリーちゃん)は、キング農場…プリンスエドワード島・キング家の「本家の子たち」…なのだと思っていて、読者目線的には、傍家筋であるストーリー・ガールや主役兄弟たちより、今後の行く末が気になる子たちでした。2人にとって、妹夭逝は一生レベルで世界の認知が大きく変革する出来事になるであろうこと、そしてきっと、妹の分まで人生を力強く精一杯生きねばと思うだろうことが想像できます。ダンくんが、農場を継いで11人もお子さんを産んで、立派にキング家を繁栄させていくんだろうな…とか、フェリシティーちゃんが、きっと力の限りでピーターくんを愛し支える人生を歩むんだろうな…とか、ストーリー・ガールの「お遊びの予言」が説得力を持って響いて来ます。(完読時の余韻)「黄金の道」を読んで、「アンの娘リラ」を読んだ際に感じた感動…「なんだこの空中戦は!こんな書き方、観たことがない!」の下地と言うか…明言しないけど点在する情報&ニュアンスで魅せてくる、筋道と納得感!…その片鱗を感じました。あぁ、この作品を書いていたから、「リラ」をあの形でまとめ上げることが出来たんだな、と感じました。モンゴメリさんの天才性の成せる技・空中戦的なお話構成については、今後他作品も読み進める中で、もっと見つけていけるのかな…?見つけていけるよう、他シリーズを読み進めていきたいと思います!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.09.07
コメント(0)
-
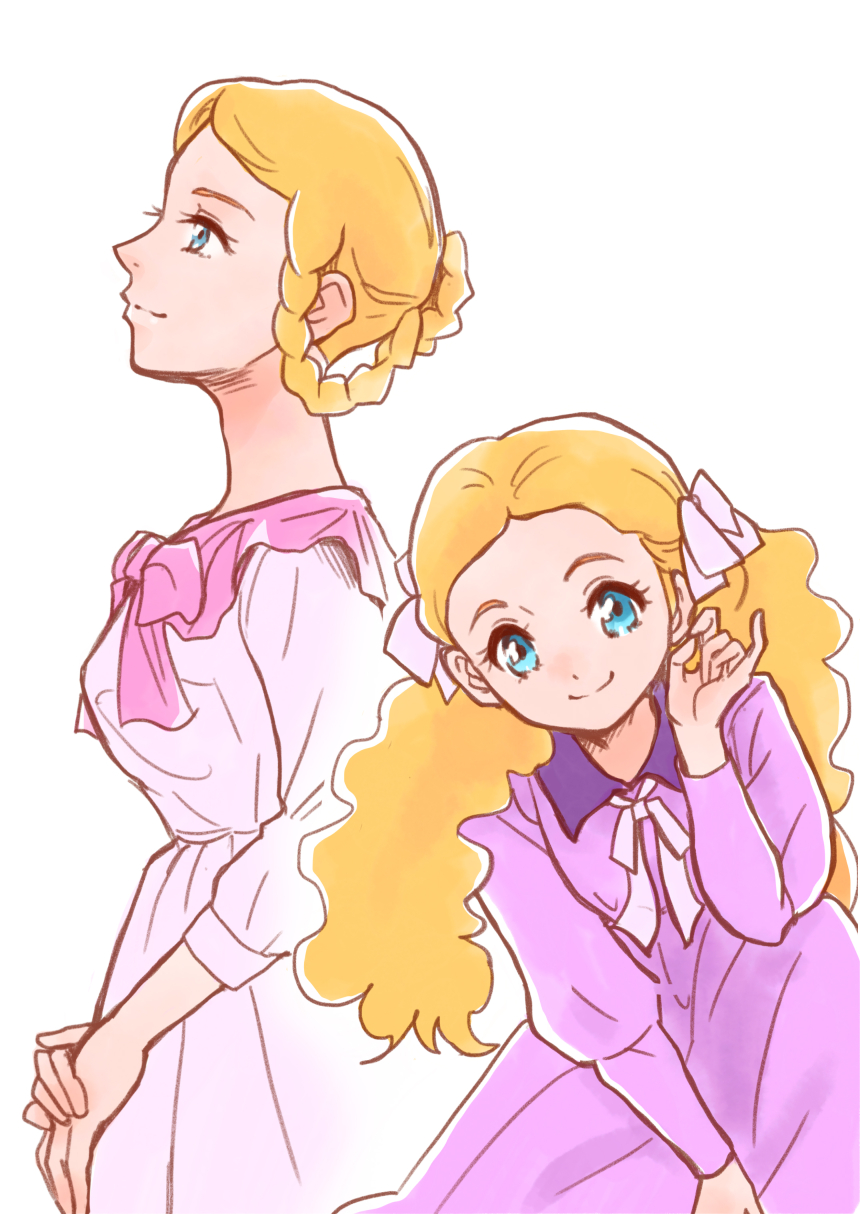
アニメ『アン・シャーリー』第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト
アニメ『アン・シャーリー』第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト最新3話の簡単感想です。※以下、原作シリーズを読んだ上でネタバレ全開で好き勝手語ってます。原作シリーズ未読の方はご注意ください!※■第18話 チャーリーのプロポーズ~パティの家賃貸契約~ボーリングブローク生家訪問小学校時代からの旧友・チャーリーくんのプロポーズを速攻で断るアンちゃん。断られたチャーリーくんが発した「孤児のくせに!」というひどい言葉→大学生活2年目以降に友人たちと暮らす家(パティの家)のあてを見つける→フィリパちゃんの帰省についていき、ボーリングブロークの生家を訪れ、両親の話や母の残した手紙を見つけ、両親の存在を実感する18話は、「家」というコンセプトできゅっとエピソードをまとめていました。今回のアニメシリーズにおいては、第1話より、アンちゃんが幼い頃から記憶にない生家&を両親を想像しながら過ごしてきたよ…という前振りをしっかりしていましたし、ここでTV放送は2週間お休みを挟んでいたこともあり、鑑賞者の頭に収まりのよい形で、且つ 心情的にも穏やかで素直に「良かったね」と思える形でまとめられていたのは、鑑賞者目線の軸で非常に納得のいくものでした。原作では、ボーリングブローク生家訪問エピソードはもっと後…大学2年終わりの夏休み前…第20章「ギルバート口をひらく」でギルバートが1回目のプロポーズをして見事に玉砕するエピソードのすぐ後・第21章「きのうのばら」として挿入されています。原作において、ギルバートを振った直後に挿入される生家訪問エピソードは、確かに鑑賞者目線の軸で見たときに不思議に感じるところなんです。ギルバートに心乱された直後に、フィリパの帰省について行く…とか、アンちゃんあまりギルバート振ったことを気にしてないのかな?と受け取られる可能性もある。ギルバート1回目プロポーズ(玉砕)→アンちゃんの意識内においてギルバートの重要性を強調する という流れを考えても、今回のアニメの構成はスマートだし、納得がいきます。ただ、じゃあなんでわざわざ原作においては、この生家訪問エピソードがギルバート玉砕直後に配置されているのかも、ちゃんと理由があると思っています。…アンちゃんの深層の心情筋(トラウマ)の軸がここに通ってる。以前、「アンの愛情」の原作感想記事で一生懸命語っているところなのですが、アンちゃんがギルバート&結婚から逃げ回るのは、出生直後に両親を亡くした生い立ち故、アンちゃんが深層心理では「結婚・家族を築くこと」に対して大きな恐怖心というかトラウマですかね…を抱いていて、どうしても思考回路が『結婚』の手前で一気にシャットダウンしてしまうからだと受け取っています。アンちゃんは複数人からプロポーズを受けますが、どんな男性から求婚されたとしても「この男性と一緒になったら、どんな未来になるのかな」とは一切…絶対考えないんです。「結婚から先」を自分事として想像することが全くできない。「恋愛~求婚」と「結婚~人生」がつながらない。病的なほどに。生家訪問エピソードは、アンちゃんのトラウマの原点に直に触れに行き、両親のたどった「結婚から先の出産~悲劇」までを具体的に提示する重要なエピソードです。明確に「結婚後のビジョン」を魅せるエピソードになるためアンちゃんの心情筋だけの話をするのであれば、原作通り「全く先が見えなくて、怖くてギルバートのプロポーズを拒絶」した後の方がしっくりくる配置だと思っています。これはもう…今回のTVシリーズ構成として、アンちゃんの深層の心情筋(明確に説明はしない)か、鑑賞者の目線筋か、どちらを優先するのかの話だと思いますが…改めて モンゴメリさんの原作『アンの愛情』は、この「アンちゃんの深層の心情筋」に特化して構成されているんだな、と強く感じました。■第19話 幼友達・ルビーちゃんの病悪化→死、同時並行で、アンちゃんが初めて小説執筆女友達の中でも一際可愛いルビーちゃんのキャラクターデザインを見て、絶対に力を入れて映像化してくださるだろう!と思っていたエピソードです。想像通り、映像は表情/演技動作、背景美術…と力が入っており、声優様たちの演技、取りおろしBGM等、あらゆる面でスタッフ様たちの凄まじい意気込みを感じる回でした。特にルビーちゃんの表情…ルビーちゃんが「天国はアヴォンリーと同じなわけない!」と強く言ってしまいアンちゃんが困って泣いてしまって、それを見たルビーちゃんがしまったと思って…そこから「生きたい、結婚して子供を産みたい」と吐き出してすっきりした表情になって…このあたりの表情筋は練に練られてて渾身で、息をのんで見入ってしまいました。素晴らしかったです!ルビーちゃんの想いを目の当たりにしていたからこそ、絶大に輝く本作クライマックス・アンちゃんの『黙示録』の大後悔&独白なのだと思ってます!■第20話アンちゃんの小説、ベーキングパウダー会社の広告賞を受賞、大学生活2年目、パティの家での同居開始、猫×3、ギルバート1回目のプロポーズ、そして玉砕ダイアナちゃんが勝手にアンちゃんの小説を応募した件…まぁ、アンちゃんの承諾を得てからやるべきでしたよね。残念ながらダイアナちゃんには「アンちゃんの文学に対する美学」が理解できませんでした。ーただ結果的には、アンちゃんの方が自分の視野の狭さを見直すきっかけになり、25ドルも稼ぐことが出来ました。そして何より、初めて小説を認められたという実績になりました。アンちゃんにとっては、凄く良い事だったと思います。「生涯の友で居る」って「ずっと変わらないで居る事」じゃないと思います。お互いが人生を歩む中で、それぞれ絶対変わっていく部分があって、それでも相手を想いやって&相手の価値観を尊重して、ずっと変わらない友情を保っていくことなんだと感じました。すごく好きなエピソードです!ちなみに妹は小説のタイトルを『アルビルの”あ”がない』…ルビル?だと思ってたらしいです。あがない=贖い ですね。そして遂に来ましたギルバートの玉砕シーン!!楽しみにしていましたが、ドストレートに盛大で最高でした!ギルバート役の宮瀬尚也さんの、芯のある声質と攻撃的なまでにまっすぐ心を撃ってくる演技がブラボ―!でした。この玉砕シーンは、原作を読み進める中で、オイッ!こんなことしたら…コイツ(ギルバート)死ぬぞっっ!!と明確に思ったシーンでした。だって、ギルバートほどの超仕事脳人間(※)にとっての目指すべきビジョンの一番根幹にあるもの(※※)を完膚なきまでに破壊する行為ですからね。※目標到達に向けて生活の全てが回るタイプの人※※アンちゃんを自分が幸せにしてあげたい!という感情いや…まぁね…ギルバート自身はまだ大学課程がまるまる5年間(通常2年+医科3年)も残ってますし、婚約なんてこぎつけられるような立場じゃねえだろお前…とは思うのですが、目先の資金難故、夏休み長期休暇は短期仕事に従事せざるをえず、アンちゃんと一緒にアヴォンリーに帰ることすら出来ないため、いつ何時アンちゃんにアプローチする輩が現れるとも限らない焦りもあるし…何より…頑張りたかったんだよな…!!目指すべき目標(ビジョン)をアンちゃんと2人できちんと共有して、確固たるものにして、そこに向かって頑張りたかったんだよな…(泣)結果、地獄の(日々に続く)入場ゲートの竣工セレモニーになってしまいましたが、ギルバートがやりたかったことはすごくわかりますよ…(泣)次回は ロイ・ガートナー登場&クリスチン・スチュワートさんも登場ですかね!?妹は、アンちゃん主観の描写…どれだけロイ&アンちゃんのシーンを軽薄に描いてくるか、どれほどクリスチン・スチュワート登場の衝撃を重く描いてくれるか、勉学に没頭していくギルバート(健気にもアンちゃんの前では気丈に振舞う)をどのように描くのか、ここからが今回のアニメの真骨頂のはず!と非常に楽しみにしています。ますます混とんとして、お互いにわけが分からないことになっていく元祖・爆萌えカップルの行く末から目が離せません!次回も楽しみにしています。by姉・妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.08.31
コメント(0)
-
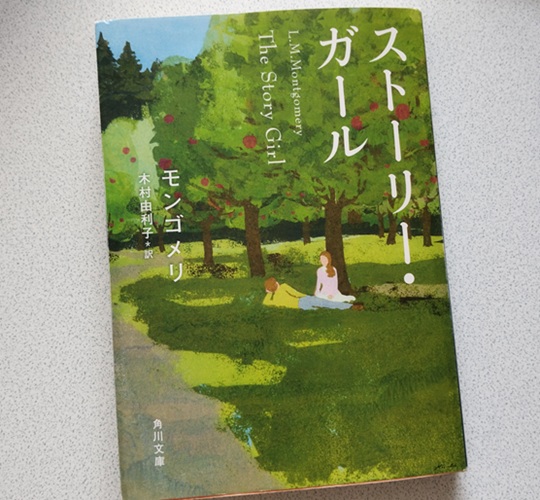
「ストーリー・ガール」木村由梨子訳 感想+ アンの愛情『黙示録』の章について
「ストーリー・ガール」木村由梨子訳 感想+ アンの愛情『黙示録』の章について「ストーリー・ガール」 (1911年 ルーシー・モード・モンゴメリ/著 木村由梨子/訳 角川文庫※元は1980年 篠崎書林より刊行)(角川文庫/背面あらすじ)父の仕事の関係で、トロントからプリンス・エドワード島にやってきたベバリーとフェリックスの兄弟。キング農場で個性豊かないとこたちと一緒に暮らすことになった彼らが出会った、すらりと背の高い大人びた少女。虹のような声色でお話を語る不思議な魅力のストーリー・ガールと過ごした多感な10代の日々を、夢のように美しい島の四季と重ね合わせて描く、もうひとつの『赤毛のアン』と呼ばれ愛されるモンゴメリの傑作。本国・カナダでは1990年代に、本作「ストーリー・ガール」シリーズをベースとして、アンシリーズのエピソードも交えた形で「アボンリーへの道」というテレビドラマ作品が制作されているそうです。全91話とか書いてあるので、超大作ですね…。原題は「The Story Girl」。1911年発表の作品とのことなので、「果樹園のセレナーデ」の1つ後の作品になるのかな?本作は『赤毛のアン』で名声を得たモンゴメリさんが、より自身の幼少期の体験談や聞いてきた物語の引き出しを大きく広げ、お話しの上手な女の子を、今ならこの体裁で描くな、というとっかかりで楽しく執筆された作品なのかな?と受け取りました。本作も、以前感想を書いた「果樹園のセレナーデ」と同様に、この先で紡がれるアン・ブックスの下地と思わしき要素が多数見受けられ、非常に興味深い1冊でした!■8人の幼馴染本作を読んで、真っ先に感じたのが『虹の谷のアン』と似てる!でした。本作は、トロントからベバリー(13歳)とフェリックスという2人の兄弟がプリンスエドワード島を訪れるところから始まります。預けられた父の実家・キング農場には、長男・ダン(13歳)、美人で料理上手な長女・フェリシティー(12歳)、争いを好まない温厚な次女・セシリー(11歳)の3兄弟が居ます。近所にはキング家と親戚筋のセーラ・スタンリー(ストーリー・ガール・14歳)が暮らし、彼女の家ではピーターという少年が雇人として働いています。親戚筋ではないですが近所に住む女の子・セーラ・レイ(11歳)も含め、総勢8人の子どもたちでいつも遊んでいます。『虹の谷のアン』は、アンちゃんとギルバートの子どもたち(6人居るが、特に上の4人)と、近所の牧師館に越してきた一家の4兄弟(長男・長女・次女・次男)を掛け合わせ、走らせる中でキャラクターや関係性の試行錯誤・確立を行っている作品と認識しています。今回「ストーリー・ガール」を読んで、8人の子どもたち(男の子4人:女の子4人)のわちゃわちゃを描いている点が完全に被っており、『虹の谷のアン』は基本的に「ストーリー・ガールの要領で執筆」を念頭において着手した作品なのだろうな、と感じました。また、キャラクターについても色濃く繋がりが見て取れます。『虹の谷のアン』の牧師館の4兄弟(ジュリーくん、フェイスちゃん、ユナちゃん、カールくん)ですが、特に上の3人の配置は「ストーリー~」のキング家3兄弟と印象が似ており、キング農場の3兄弟+主人公の弟(フェリックスくん)のイメージを持って牧師館の兄弟たちを走らせたんではないかな、と感じました。「ストーリー~」を読んでの個人的な印象ですが、本作は当初「ストーリー・ガール」というタイトルの通り、おしゃべり上手なセーラ・スタンリーちゃんを一番魅力的に描き、子どもたち、更に周囲の大人たちの輪の中心として描こうとしたのかな…と思います。ただざっと読んだ限り、あまりストーリー・ガール自体の印象は強く残りませんでした。主役のベバリーくんは「ストーリー・ガールが非常に魅力的である」と繰り返し語るのですが…やっぱりアン・シャーリーほどの惹きは感じないというか…アンちゃんは孤児という立場ながら、明朗快活で聡明…に一瞬見えるけど、本当はすごく繊細&怖がりなところが魅力的な娘だと思うので。※ギルバート的 執着&全力で尽くしたくなるポイント「ストーリー~」をざっと読んで、私はどちらかと言うとフェリシティーちゃん&セシリーちゃん姉妹の方が印象的/魅力的に感じました。フェリシティーちゃんは誰に言わせても美少女。高慢で男の子との言い合いも多いですが、料理上手で、両親たちが不在の間は家を預かりきちんとせねばという責任感を見せますし、セシリーちゃんは姉に比べ派手さはないものの、仲間内での喧嘩を諫めたり、年上の子たちにも臆さない芯の強い子です。先にも語りましたが、この2人が「虹の谷~」でメインとなるフェイスちゃん/ユナちゃん姉妹の原型なんじゃないかな、と受け取って読み進めました。本作を読んで、いちばん興味深かったのが次の2つのトピックです。■『世界の終末』・『近しい幼友達の“死”』いずれも「アンの愛情」の話回しにおいて大きく取り上げられるトピックなのですが、ラブスト―リ-を描くにしてはかなり独特というか、普通の思考回路ではまず出てこないよな、モンゴメリさんは天才だな!と思っていました。これらのトピックが、見事に「ストーリー~」の中でガッツリ取り上げられていて、非常に腑に落ちたというか…ここで一度しっかり形にしてるから、「アンの愛情」でもあれだけ自由に、描くべきものに見事に適合させた形に展開させることができたんだな、と感じました。・第19章 恐怖の予言、第20章 審判の日曜日(ジャッジメント・サンデー)新聞に掲載された「最後のラッパ、明日二時鳴りわたる」という一節…つまり、世界の終末(最後の審判)が訪れるという予言です。これを信じた子どもたちは焦り怖がりまくりますが、結局何もなくその時は訪れ過ぎていく…というエピソード。「最後のラッパ」と言われても聖書に詳しくない私にはピンときませんでしたが、調べると新約聖書の聖典・ヨハネの黙示録において、災害の前触れとなる7つのラッパを吹く7人の天使達が登場、各ラッパの合図とともに恐ろしい災害が起こり、最後の第七のラッパで最終的な世界終末が訪れる(?)…とのことで、このくだりを指しているのだと受け取りました。なんか最近…日本でもありましたね…2025年7月5日の予言的なのが…。私はキリスト教の教えに詳しくないので、終末論の考え方が根付いているわけではないのですが、ただ、終末が身に迫る危機意識を高め、いざというと時の動きをシュミレーションする機会として大事な思想なんじゃないかな、と思っています。本作の子どもたちも、ただ怖がるだけではなく、1週間喧嘩して口をきかなかったストーリー・ガールとフェリシティーちゃんが、それを悔いてすぐに仲直りしたり、子どもたちなりに残りの時間を悔いなく過ごそうと、恐怖にかられながらもあれこれ考えます。『アンの愛情』のクライマックス(最終章の前章)の章題は英語原文だと「A Book of Revelation」…和訳では『黙示録』としており、突如として「世界終末」を迎えたアンちゃんが、自身の内から溢れる後悔の念を大爆発させます。この「世界終末」というトピックですが、モンゴメリさんの興味関心どころとしては、やはり誰しもに想起される「後悔の念」の観点だったのだろうと思います。「世界終末」という強烈なトピックに対し、ここで終わるなら…もっとああしておけばよかった、これをやっておけばよかった…という後悔の感情は、世界中・老若男女問わず少なからずは自然と想起されるものでしょうし、一番重要な心情筋がこうした永久不変の概念で作りこまれているからこそ、アンシリーズは「世代も国も超えた全世界中の人々が、共感し楽しむことができる作品」なのだと思います。・第28章 虹のかけ橋、第29章 恐怖の影、第30章 手紙の花束本作のクライマックスとして、幼友達仲間の一人であるピーターくんが "はしか"にかかり、生死をさ迷うエピソードが大々的に描かれます。つい先日まで笑い合っていた仲間に突如迫る死の影は、子どもたちに大きな衝撃を与えます。私自身も小学校高学年の頃に、同じ学区の子が不幸な事故で亡くなったのを知った時、学年も離れていたし話したことはない子でしたが、「こんなことが本当に身近で起こるんだ…!」と凄く衝撃を受けました。カルチャーショックというか…本当に初めて「死」が自分の近いところにもあることを認識した瞬間ですね。あの時の感情は焼き付いていて、数十年経った今でも鮮明に思い出すことが出来ます。「ストーリー~」の子たちに関しては、いつも一緒に遊んでいた仲間うちで起こった話ですので、その衝撃はさらに大きなものだっただろうと思います。特にこのピーターくんというのが、若いながら一際苦労人で…三つの頃に父親が蒸発し、母の稼ぎでは食べていけない為、六つの頃から働きに出ていて、8人の仲間内の中でも他の子たちと違い、あまり学校にも通えていない様子。ただ、誰に言わせても「躾はないが地頭のいい子」で、本作の中でも事あるごとにその有能さを発揮します。正直、本作を読み進める中で、読者目線でのアイドルは完全にピーターくん一択でした。ピーターくんは幸いにも一命をとりとめ、30章では元気になるまでの間、仲間たちから思いやりいっぱいの手紙を受け取り、大喜びします。「アンの愛情」においては、この「近しい友人の死」について、物語中盤・ルビーちゃん病死のエピソードで具体的/悲劇的に印象深く焼き付けておいた上で、クライマックス・ギルバート瀕死の報がアンちゃんに突き付けられます。■2つのトピック→アンの愛情:『黙示録』の章への転換について上述の通り、「ストーリー~」においては2つのトピック:「世界の終末」と「近しい幼友達の“死”」は、全く別物のエピソードとして描かれていました。これが、アンの愛情では一つの大筋に集約されているというか、イコールのものとして、クライマックス『黙示録』の章に据えられています。<アンの愛情の『黙示録』の章の一節>(和訳)聖書に黙示録の書があるように、だれの生涯にも黙示録がある。アンは嵐と暗黒の中で身も世もなく、寝もやらずすごしたその苦悩の夜、彼女の黙示録を読んだ。(原文)There is a book of Revelation in every one's life, as there is in the Bible.Anne read hers that bitter night, as she kept her agonized vigil through the hours of storm and darkness.ギルバートの"死"が、アンちゃんにとっての『黙示録』…つまり「世界の終末」であると言っている一節と受け取っていますが、かなり独特な言い回しだなぁ~~と感じていました。今回、大元の「ストーリー・ガール」の中では「世界の終末」と「友人の死」を別のトピックとして扱っていて、「世界の終末」は世間一般的な「聖書の黙示録」の内容を示していたことを知り、あぁ…だからわざわざ、「アンの愛情」では「ギルバートの”死”は、アンちゃんにとっての『 黙示録 ≒ 世界の終末 』だよ」と強調する書き方になっていたのか、と非常にしっくり来ました。いやぁ…「ストーリー・ガール」、面白かったです!モンゴメリさんの初期発表作に、ことごとく「アンの愛情」の原型を見いだせるというか、あまりに分かりやすく「すべての道は『黙示録』の章に通じる!」状態で、超楽しいです。「ストーリー・ガール」については、2年後の1913年に発表された続編「黄金の道」という作品があるそうで、そちらも是非チェックしなければ!と思っているところです。by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.08.24
コメント(0)
-

赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて
赤毛のアンシリーズのビジュアライズ化に興味があって、こちらのシリーズにも手を出しました。『赤毛のアンの手作り絵本』(Ⅰ~Ⅲ)(白泉社紹介文より)夢あふれるアンの世界。そこに出てきた素敵なお料理や手作りの小物を丁寧な解説とともに紹介。あなたをグリーン・ゲイブルズへ誘います。もともとは鎌倉書房という出版社より、1980年に刊行されたシリーズのようです。その後、白泉社から復刊されているのかな?世界名作劇場のアニメが1979年放送ですので、放送後の刊行に合わせて準備されていたのかな?と感じます。体裁としては、赤毛のアンに出てきた(もしくは出て来そうな)料理や手芸の紹介本です。シリーズ内の時系列に沿って、プロの方たちがイメージを膨らませて作った料理/小物等を、きれいな写真で紹介&詳しい作成方法が掲載されています。(前々から感じていた所なのですが、やはり「80~90年代の 料理・手芸本 の熱量&完成度はヤバイ」というか…バブル期の時間的余裕がある豊かさ&パソコンが普及する前ということで、本当に「この一冊で夢と憧れを提供しきるぞ!」という名著が多い気がします。)とにかく「こんなに制作に力の籠った本を私は知らない!」と感じるほど、熱量のある『超良質本シリーズ』です。特筆すべきが、超美麗な挿絵イラスト!松浦英亜樹さんという男性のイラストレーター様のワークスだそうですが、とにかく素晴らしいです!見ごたえがあります!1冊目は、『赤毛のアン』パート。挿絵がひたすら美麗且つ芸術的で、「上手過ぎる…」しか言葉が出てこないのですが…2冊目・『アンの青春』『アンの愛情』パートになってくると、明らかに熱量が異なったぶち抜きイラストが多数収録されるようになります。『アンの青春』以降は、そもそも1979年のアニメでは映像化されていないので、アニメーションからのファンの方たちにとっても、本書籍シリーズがビジュアライズの最先端を担っていたのだと思います。特に、2冊目以降は、「本編にこんなシーンはなかったが…?」というギルバートがグリーン・ゲイブルスに足繁く通い、デイビー/ドーラと遊んでる体でアンちゃんにメロメロしているイラストが多い!私はこのイラストを見て思いました。「小説で読んだ印象そのままの、完璧なギルバート像だ…!」巻末の著作者様方のコメント集で、「アンが年頃になり、画面の中から笑いかけるのでついつい見とれてしまった」といった内容が掲載されていましたが…完全に男性目線というか、ギルバート目線なんです。アンちゃんがひたすら女神でギルバートがラブファイターなんです。3冊目は『アンの夢の家』~『炉辺荘のアン』までのパート。イラスト自体の陰影がグッと濃くなって、めちゃくちゃ立体的になります。表紙イラストが既に3冊目のイラストの方向性の全てを体現していますが…もはやイラストというか「幸せなブライス一家写真集(撮影/構成 ギルバート)」みたいになって来ます。もともと、妹が本シリーズを購入したのは、アンシリーズを小説で読み進めるにあたり、「子どもたちをビジュアルで見たい!(ビジュアルで見ないと頭に入らない)」という意向があったからでした。正直なところ、特にこの3冊目に関しては本書のイラストやキャラクタービジュアル(子どもたち/スーザン)が完璧過ぎて、「炉辺荘~」を読みながら、本書のビジュアルでしか想像ができませんでした。ギルバートも必要に応じて映り込んで来ますが、基本的にどのカットも美しく、女神なアンちゃんを激写するためのアングルで撮影されています。『アンちゃん(女神)の美しい横顔』への執念が凄まじいです。子どもたち6人もそれぞれ個性的に、活き活きと描写されています。「炉辺荘~」のラストシーン。本編ではアンちゃんは緑の服は着ていませんが、イラストレーター様の強い要望で(ギルバートが一番好きな)緑の服にしたと巻末のコメントに記載があり、完全にギルバート主観で絵を描かれていることが見て取れて面白かったです。ビジュアライズ化の中でも、圧倒的画力&ずば抜けた熱量で「アンちゃん(フィクション)がいかに美しい女神であるか」を、そして「ブライス一家(フィクション)が幸せに生きた証」を、現代の日本人にもきちんと伝えなくては!…くらいな、すさまじい挿絵画家の意欲を感じるスーパーワークスだと思います。…お料理・手芸本のはずなのに‼アンシリーズのビジュアル化に興味がある方は、是非!松浦英亜樹さんの他のワークスも気になったため、入手できる絵本を探して購入してみました。『ピーター・パン』(前・後編)チャイルド本社、1982年、絵:松浦秀昭 名義平面の重層で立体感を表現した、和風・浮世絵風のピーター・パンでした。特に、ピーターパンとフック船長の1枚は、北斎の白波パロも入れ込んだばっちり決まった浮世絵風になっていてしびれました。こんなもの子どもが観たいものでも何でもないと思いますので、ただただ「画家がやりたかったんだな」と感じる作品でした。なんたるアーティスティック絵本!たいへん面白かったです。松浦英亜樹さんですが、イラストレーターの後に服(?)のデザイナーに転身されてる(?)という情報がちらっと出てきました。とにかく「天才…っっ!」と思わず感嘆するイラストばかりなので、イラスト集/ワークス集が欲しいな…(今更無理だと思うけど…)今後も機会を見つけて、ワークスに手を出して行けたら良いなと思っています。by姉・妹◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.08.17
コメント(0)
-
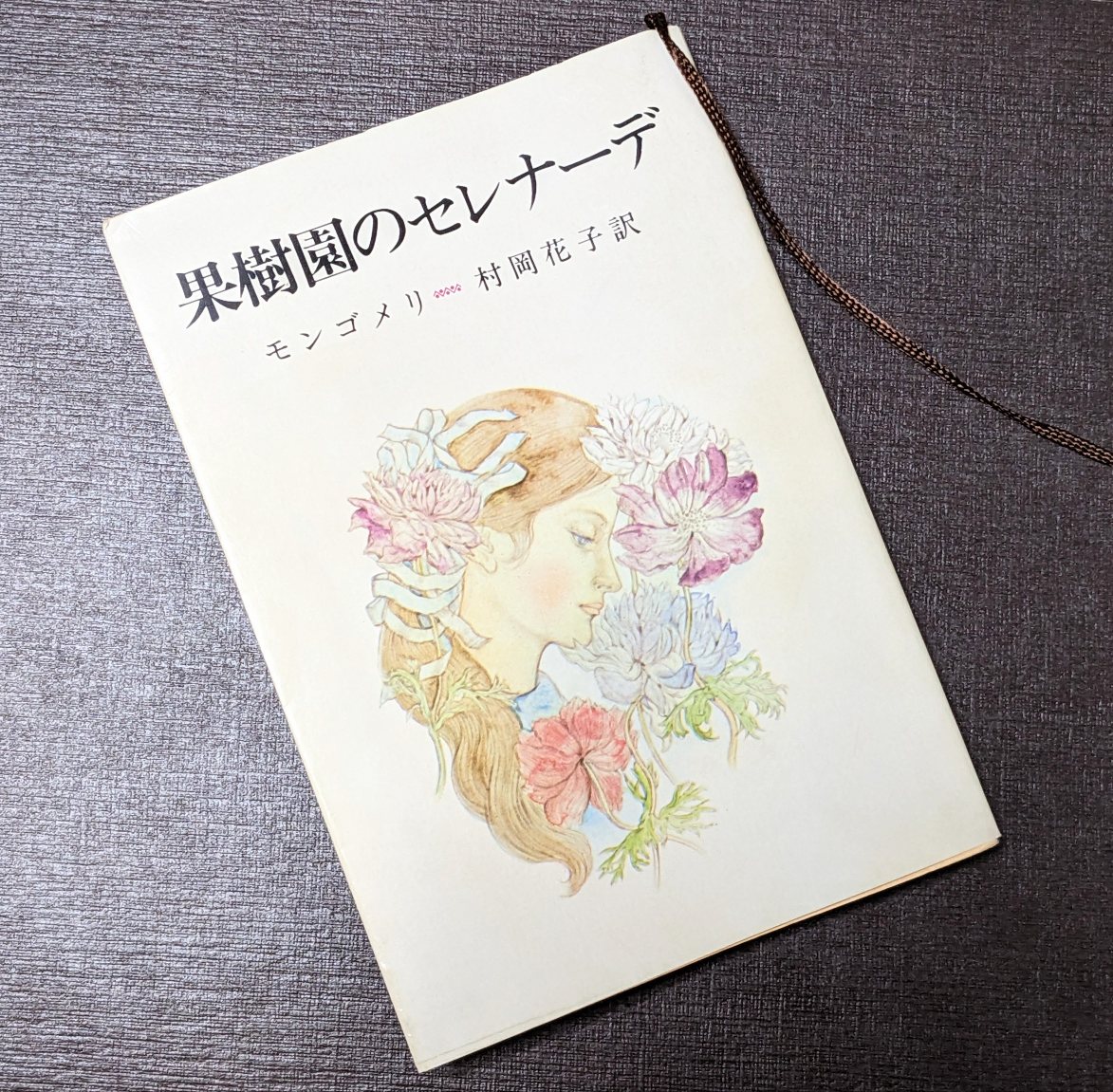
「果樹園のセレナーデ」感想 村岡花子訳
モンゴメリさんのアンシリーズ以外の作品にも手を付け始めました。「果樹園のセレナーデ」(1910年 ルーシー・モード・モンゴメリ/著 1961年 村岡花子/訳)(新潮社説明文)荒廃した果樹園の古びたベンチにすわって、ひとり静かにヴァイオリンを奏でる美少女キルメニイ。悲運の母の偏愛ゆえに世間から隔絶された口のきけない少女に、大学を出て赴任してきた若い臨時教師エリックが真実の愛をそそぎ、奇蹟を起こすこの美しい愛の物語は、『赤毛のアン』で知られ、生涯青春の情熱を失わなかったモンゴメリ女史の実質的処女作。原題は『Kilmeny of the Orchard』。あとがきを読むと、赤毛のアン(1908年)、アンの青春(1909年)に続いて1910年に公表されたモンゴメリさんの3冊目の小説とのことですが、実際の執筆時期は赤毛のアンより数年前の作品とのこと。文庫自体は薄く、果樹園のセレナーデ本編は170ページ弱です。短編作品ではありませんが、「短編集の中に収められた長めの中編作品」と言っても不自然さのない長さの作品です。「果樹園のセレナーデ」…村岡花子さんの和訳タイトルセンスが素晴らしく、モンゴメリさんの著作一覧(アンシリーズ以外)の中でも一番気になっていた作品でした。文庫の裏にあらすじの記載がなく、どんな話か全くまっさらな状態で読み始めました。…はい。まるまる1作、見事なまでに「『アンの愛情』のプロトタイプ」な作品でした。ギルバート・ブライスの前世がここに居た。めっっっちゃくちゃ面白かったです!!■感情面に特化した(恋愛)作家様の特徴以前、他の作品の感想を書く際に、感情面に特化した(恋愛)漫画家様を例として、あだち充先生、「ちはやふる」の末次由紀先生、「暁のヨナ」の草凪みずほ先生等を上げて、下記のような個人的着目点について長々と語りました。(感情面に特化した作家様の特徴)着目点①作品の中で成熟した感情を、次の作品に持ち込んで、更にひねって出してくる。「感情」は、いち作品の中で、キャラクターが行動でそれを体現することで、より強固になっていく…成長というか、成熟していくものだと思っています。特に連載作品です。いち作品としてのまとまりは、当然読み切り作品や1冊で読み切れる作品の方があると思いますが、ただ連載作品の面白さは何より、感情の成熟過程を見て取れることだと思っています。感情に特化された漫画家様の中で、前作で成熟した感情や、キャラクター同士の関係性を、次の作品にどんどん転生させているんだろうな、と思う作家様が居ます。既に成熟しきった感情を持ち込むわけですから、次の作品は最初からキャラクターの行動・言動が飛んでいて、その作品から読み始めた読者は、「なんだコレ、なんだコレ…」と戸惑いながら読むことになります。キャラクターの爆発的な感情と行動が先走り過ぎて、読者は正直ついていけてないんですが…でもなんかすげぇ感情があるのが分かるから、面白くて読む。漫画作品ではありませんが、今回改めて赤毛のアンシリーズを鑑賞する中で、モンゴメリさんも間違いなく上記のような「感情面に特化した(恋愛)作家様」だと思っています。「アンの友達/アンをめぐる人々」の感想を書いた際には下記の感想を書きました。モンゴメリさんの執筆/編纂時期を考えても、個人的に注目してしまうのが、『アンの愛情』の下地になるような感情やお話構成の作品を、たくさん見つけられるところ!『アンの愛情』は…アンシリーズの中でも、アンちゃんの人生軸を決定づける重要な作品だと思っています。すごく強烈な感情が、繊細なエピソードの積み上げで構築されており、モンゴメリさんご自身の一番の興味分野(結婚)について、咀嚼して咀嚼して、アンシリーズのファンたちの期待に応えられるよう、渾身で繰り出された作品なのだろうと感じています。『愛情』を読んだ際に感じた「なんて強烈な感情なんだ!なんて洗練された構成なんだ!」という印象は、こうやって…短編作品として似た題材を繰り返し形にする中で、キャラクターを走らせることで感情自体を成熟させたり、1話としての構成として魅せ方を試行錯誤したりして、高濃度/高品質なものとして洗練・構築していくものなんだな、とひしひしと感じました。感想記事はまだ書いていませんが「アンと想い出の日々」でも、これまでの短編作品の焼き直しと思わしき作品が複数見受けられました。・キャラクターの転生について本作を読んで、いちばん面白かった点がこちら。「ギルバートの前世が居る!!」本作には複数人の青年たちが登場しますが、特に下記3人の要素で錬成されたのがギルバート・ブライスだな、と感じました。【魂/前世】エリック・マーシャル身体を壊し休業を余儀なくされた大学時代の友人の代わりに、プリンスエドワード島・リンゼイ中学校に来た臨時教師。ただ、その実は、大手のマーシャル百貨店等を経営するマーシャル株式会社の御曹司であり、父が一代で築いた事業をより拡大する気満々の跡継ぎ。大学の美学科を首席で卒業する頭脳明晰且つ非常にハンサムな男性。完全に「ギルバートの前世」みたいな男主人公です。ハイスペックさもさることながら、思い込みの激しさ(一途さ)、すっとんだ行動力等々…「同じ魂」というか。アンシリーズを読んで、ギルバートは…本当に自我が強いというか、片田舎の農家生まれのくせに、なんでコイツはこんなに帝王思想なんだと感じていた、その謎が完全に解明されていく爽快感を感じながら、「果樹園~」を読みました。「そっか~、前世は御曹司だったからか~」と思いました。また、2人の違いも面白いところで…本作のエリックさん、全然悪人ではないし、言ってることも行動も間違っていないのですが、落ち度がなさ過ぎる上に自信満々過ぎて、読んでいて非常に鼻につきます。応援したくなる気持ちが一切湧いて来ません。読者に、「自惚れが強いやつだな」「どっかで痛い目にあって欲しいな」という感情すら想起させます。正直、このエリックさんの人物像は全くアンちゃんの好みではないので、もし彼がアンちゃんに求婚したとしても、基本的にはチャーリー扱い、運が良くてロイ・ガートナーコースで終了だったと思います。【職業/将来像】デビット・ベーカーエリックより10歳年上のまたいとこ。背が低く容姿も良くない青年。様々な困難(おそらく家庭環境)を抱えていたが、マーシャル氏(エリックの父親)の寵愛もありクインスリー医科大学を卒業し、のどの医師となる。※マーシャル氏に出してもらった学費は、最後の1セントまで完済作中では、キルメニィちゃんののどの診療のためにプリンスエドワード島を訪問します。【生い立ち】ラリー・ウェストエリックの友人。経済的な理由で大学を2年で辞め、プリンスエドワード島で教師をしながら学費を稼いでいる。※大学における美人な才女・アグネスと婚約同然の間柄らしい身体を壊し、自身が務められなくなったリンゼイ中学校教員職を「エリックに務めて欲しい」と手紙をよこす。エリックの魂が、ラリーの生い立ちを経てデビットの職業を目指し、ギルバート・ブライスが誕生したことがよく見て取れました。・話筋の転生について今回、果樹園のセレナーデを読んで真っ先に感じたのが、コレ。「まったくアンの愛情と同じ(恋愛の)ストーリー筋だ!」強力な推進力を持つヒーローが、薄倖のヒロインにベタ惚れ・熱烈に求婚し、一度はヒロインの遠慮心もあって、思いっきり振られるものの、最終的にはそれらヒロインの心の枷になっていた部分を払拭し、二人は結ばれ、ハッピーエンド!本作では、ヒロイン・キルメニィちゃんが、自身の姿を醜いと誤解していたことと、「唖(おし・口がきけず、言葉が不自由)」であることから、相手(エリック)を愛しているからこそ「結婚できない!」と断固として言い張ります。以前、「アンの愛情」の感想記事で語っているところなのですが、アンちゃんがギルバート&結婚から逃げ回っていたのは、出生直後に両親を亡くした生い立ち故「結婚/出産(家族を築くこと)」にトラウマがあるからだと受け取っています。アンちゃんは、「ギルバートはどこまでも理想の家族を築き、誰よりも幸せで認められた人生を送るべき人」だと思っています。アンちゃんが1度目のギルバートのプロポーズを全力で拒絶した理由は、「ギルバートがアンちゃんの理想通りではないから」ではなく、「ギルバートの理想的な未来に対し、そこに向かう意志のないアンちゃん自身がふさわしくない為、諦めて他の女性とより良い未来を築いて欲しい」からだと思っています。つまり、アンちゃんがギルバートに言いたかったことは「私の相手はお前じゃない」ではなく「お前の相手は私じゃない」だと思っています。「果樹園~」を読んで、「アンの愛情」で描いている本筋は間違いなくこれと同様のものだと思いましたし、「果樹園~」の話筋自体が「アンの愛情」に転生しているとも言えると思います。(感情面に特化した作家様の特徴)着目点②言葉で感情を説明しなくなる。アンの愛情では上記の話筋について、明確に言葉での説明はしていません。以前書いた『アンの愛情』感想記事でも一生懸命語ってますけど「説明してないけど…でも『ある』」んですよ。モンゴメリさんの中では「果樹園~」で作り切っている感情筋であり、「果樹園~」と「アンの愛情」が世に出るタイミングも数年のタイムラグなので、あんまり説明し過ぎるのも無粋だし、アンちゃん自身も、言葉に出来る次元でトラウマの自覚があるわけではないという前提の上で、「言葉にせず、ニュアンスだけで筋道を読ませる」形に挑戦されたのかな?と想像しています。■「果樹園~」と「アンの愛情」の違いについてここまで「果樹園~」と「アンの愛情」の似た作りについて話を続けて来ましたが、あくまで「果樹園~」は「アンの愛情」のプロトタイプの作品と言う認識であり、2作には明確に異なる部分もあります。「果樹園~」は、絵面/ロマンチック性重視…古い果樹園で出会う美男美女、バイオリンを通じての心の会話…という、ロマンチックなイメージ像をとっかかりとし、膨らませた話筋だと思っています。心情筋という面では、アンシリーズの方が格段に繊細で読み応えがあります。「アンの愛情」は心情筋に特化しており、作中、ドラマチックな絵面としての面白さはほぼ皆無と言っていいストイックな作りです。アンちゃんの大学生活(日常生活)の描写が延々と続き、だからこそラストの『黙示録』のシーンの衝撃が際立つ作りになっているのだと思います。2作の最大の違いは、ヒーロー目線かヒロイン目線か かな、と思います。「果樹園~」は終始ヒーロー・エリック目線。彼はひたすら自身の直感(運命)に突き進んでいきます。反面、ヒロインのキルメニィちゃんの心情筋としては、「未来明るいこの人を邪魔してはいけない」という愛情深い遠慮心は感じられるものの、エリックを自分が幸せにしてあげたい、守ってあげたいという主体的な感情はありませんでした。(エリックが最初から恵まれすぎてるため、その感情を想起させるスキがないとも言う)「アンの愛情」は終始アンちゃん目線で描かれ、彼女自身の内から湧き出る「ギルバートを幸せにしたい」という感情…その感情が生まれ、育ち、炸裂する『黙示録』までの心情筋づくりこそ、「アンの愛情」が描いているものだと思っています。「アンの友達」「アンをめぐる人々」には、ヒロイン目線で、主体的に「ヒーローを幸せにしたい」「この人の生活の中に自分の居場所がある」という感情が生まれる物語も数多く見受けられます。やはり、「アンの愛情」は「果樹園~」をプロトタイプとして据えながらも、そこから踏み込んで、ヒーロー/ヒロイン側の心情筋を繊細に詰め、特にヒロイン側の心情筋を劇的に見せる形で改めて構成してある作品だと思います。「果樹園のセレナーデ」…単体でもロマンチックな面白い短編作品ですが、「アンの愛情」との見比べがめっちゃくちゃ面白かったです!「アンの愛情」の副読本として是非!おすすめです!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.08.15
コメント(0)
-
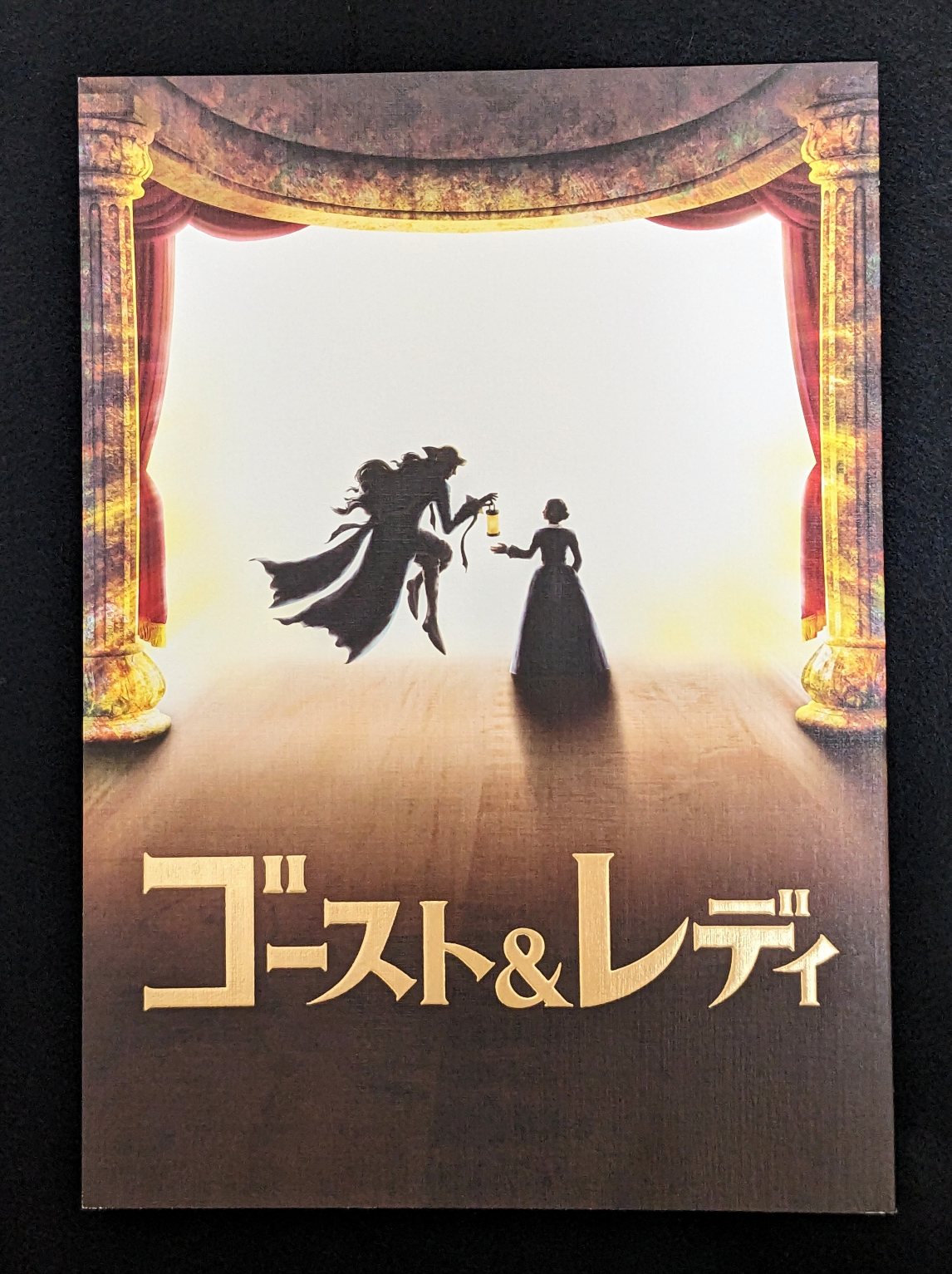
劇団四季オリジナルミュージカル『ゴースト&レディ』感想
劇団四季のオリジナルミュージカルを鑑賞してきました。劇団四季『ゴースト&レディ』感想通称『ゴスレ』『ゴーストアンドレディ』・名古屋公演プロモーションVTR・ゴースト&レディ:ナンバー集■前段・原作漫画について。こちらのミュージカルですが、原作は漫画作品です。週刊少年サンデーや青年誌で活躍され、「うしおととら」「からくりサーカス」等の大長編ヒット作を数多く生み出され、エネルギッシュな画面や壮大な物語で漫画ファンたちの心を掴み続ける藤田和日郎先生が、2014~2015年に週刊モーニング誌上で連載された『黒博物館 ゴーストアンドレディ』(上・下巻)です。私はもともと藤田先生のファンで、本作も単行本発売から間もないタイミングで手を出しました。当時に感動して書いた感想→こちら「銃弾のかち合い弾」という誰もが興味を惹かれるアイテムから、あれよあれよという間にイギリスの古い劇場に連れていかれ、そこからナイチンゲールに導かれて、「淑女病院」や「クリミア戦地」へ…。ナイチンゲールという…名前はもちろん知っていますが、具体的に何を行ったのかまで詳しく知らなかった偉人の、あまりにアグレッシブな仕事ぶりに初めて触れ、それだけで非常に刺激的なものでした。そこに、彼女を守る幽霊ナイトの目線が投入され、偉人の大河物語における「精神の戦い」を、思いっきり少年漫画画面で魅せる…漫画作品としてなんて美味しい!そのうえで、まさかの「クリミアの天使」と「幽霊ナイト」のラブストーリーだったんです。あまりに漫画的・エンタメ的美味しさの欲張りサラダボール過ぎて、時代の激動とキャラクターたちの激情が激流みたいに襲ってくるこの作品を、流されるがままに突き抜けちゃいまして、読み終わった直後は放心状態…「度肝を抜かれた」状態でした。藤田先生のインタビュー等では、本作のとっかかりは元々クリミア戦争時の、銃弾と銃弾が真正面からぶつかった「かち合い弾」で、そこから膨らませた物語であるとのお話があります。原作は、タイトル冒頭に「黒博物館(ブラック・ミュージアム)」と記されている通り、ロンドン警視庁の中にある秘密の博物館…大英帝国で捜査された証拠品が展示されている博物館、そこの展示物をめぐる物語を紹介するシリーズの第2弾として執筆されています。全部想像なのですが、当初はそれほどラブストーリー軸を印象的に描くという想定は、藤田先生の中になかったのではないかな、と感じています。藤田先生の他の作品を読んでいて、もちろんラブ要素は多々出てきますし、特にからくりサーカスでは情熱的な恋愛感情が大きな要素として描かれていると思っています。ただ、藤田先生のどの作品も基本的に「ラブストーリーを描く」ことが目的で作り始めた話だとは感じません。どちらかと言うと、少年漫画的なアクションシーンの絵面の面白さ…大きな獣の妖怪と少年ですとか、大きなからくりを動かす少女ですとか、そういった方向性のとっかかりから作り始める作家様という印象を持っています。「ゴーストアンドレディ」も、基本的には偉人の大河における「精神の闘い」を、妖怪じみた化け物として描くこと、それをやっつける「幽霊ナイト」の着想から出来ている作品と感じています。もう1点、藤田先生が「ゴーストアンドレディ」を執筆される直前(2008~2014年)まで、週刊少年サンデーにて『月光条例』という作品を連載されていました。こちらは、藤田先生が既存の「おとぎ話」の筋道に対し、特にその中に見受けられる「理不尽な点」に本気で喧嘩を挑みに行くような内容の作品でした。私自身、着想が面白い作品だな…と思っていましたが、爽快感を感じるような作りでもなく、正直なところこの作品は「うしおととら」や「からくりサーカス」に比べると、特段メディア化もされず、藤田先生の作品の中では人気がない地味な作品なんだろうな…という印象を持って受け取っています。ただ、「月光条例」執筆直後にこの「ゴーストアンドレディ」が出てきたので、藤田先生が「ナイチンゲールという偉人の物語」をこれほどエンタメ的に曲解して描けたのは、「月光条例」でおとぎ話という既存の筋道と本気で格闘してきたからこそできた、自分の世界に取り込んでの再構築…というか、料理の仕方なんだろうな、と感じています。ラブストーリー軸は、作品を構想していく中で自然発生したものなのかな、と想像しています。ナイチンゲールの偉業について具体的なエピソードを聞くと、改めてその行動力と決断力の凄まじさ、絶対的な結果で体制から強烈に作り変えていくバイタリティに驚愕します。藤田先生が感じた「ナイチンゲールのヒロインとしての魅力/偉業への尊敬」の思いが、生のまま幽霊・グレイの感情に反映されたのだろうな、と受け取っています。そうした「フロレンス・ナイチンゲール」という女性を、藤田先生の中で再構築していくに際し、極限の戦場病院で戦い続ける彼女が自然と、傍に居てくれる幽霊を心の支えにし始めたのかな、と思います。自分のやっていることをずっと見守ってくれて、肯定してくれて、信じて応援してくれる存在を、彼女が欲して、大好きになった…というか。この自然発生的な彼女の恋心が、この物語を読み進める読者が自然と抱く疑問「なんでナイチンゲールはこんなに頑張れるんだろう?」に対する、心情筋として非常に納得のいくアンサーなのだと思います。上述の通り、本作におけるこの「ラブストーリー軸」は、作品の構築の中では後発的なものだったんじゃないかな、と思っていますが2人の感情が自然発生的なものであるからこそ、自然且つ強力に読者を作品の渦に引きずり込む…強力な吸引力・魔力になっているのだと思っています。この濃厚な原作は、おそらく漫画作品としての評価は非常に高いものだったと思うのですが、藤田先生の作風は、どちらかと言うとコアな男性漫画ファン層がメインという印象があります。作品の位置づけとしては、「知る人ぞ知る、名作 中短編漫画作品」というか…青年誌掲載だった点も影響し、本作の持つブラックホール的なラブストーリー軸に一番食いつくべき女性ファン層の多数に届いているとは言えない状況だったと思います。(メディア化も全くされていませんでした。)今回、「ゴースト&レディ」を劇団四季が取り上げて、力を入れてミュージカルにしてくださると聞いて、すごく嬉しかったんです。そうだよね!この作品、凄い作品だよね!と思って。※妹談:今まで 『劇団四季=ディズニー&海外の名作ミュージカルを日本に高品質で届けてくれる団体』という認識で…本作が発表された当初(何故メディア化もしてない全2巻の漫画を?)と驚いたんですが、近年「世界に通じるオリジナルミュージカルを!」と精力的に取り組まれてたんですね。2024年の東京公演には行くことが出来ませんでしたが(チケットの取り方も分かってなかった)2025年に名古屋公演をやってくれるとの情報を聞き、2月の一般発売開始時にチケットを購入しました。ミュージカル自体は全然嫌いな人間ではありませんが、本格的に鑑賞する機会があったわけでも、積極的に見に行こうとするわけでもなく、劇団四季は、小学生の頃に「美女と野獣」と市民会館に来た「冒険者たち(ガンバ)」に連れて行ってもらって以来…20年以上ぶりの鑑賞でした。■四季のミュージカルについてまず、とにかく最高でした!素晴らしかったです!!原作を読んで感じた感動がしっかりと、ラブストーリー軸が引き立つようにスマートに再構成されており、役者様の演技力/歌唱力や練りに練られた演出等、劇団四季でしかできない、エネルギッシュで超ハイクオリティな舞台作品でした。普段ミュージカル慣れしていない私たちのような観客も、音楽と魔法で19世紀のイギリス/クリミア戦争の戦地へ引っ張りこんでくれました。本作は、劇団四季が「世界にも通用するオリジナルミュージカル演目を!」と、独自の人脈を用い、演出家のシュコット・シュワルツ氏をはじめ振付・衣装・イリュージョン・照明分野で世界的に活躍する海外アーティストを起用し、全力で繰り出してきた、超渾身作のようです。しかし、それでいて…本作は、もともと企画の段階から、女性向けのラブストーリーとして構築していく方向性が明確にあったのだろうと受け取っています。上述の通り、演出家様は海外の男性ですが、脚本家(&作詞)様/音楽関係には日本人女性の方々が名を連ねています。「ゴーストアンドレディ」というパッケージ自体、劇団四季の主要演目であろう「美女と野獣」を彷彿とさせるものですし、劇場モチーフも「オペラ座の怪人」に似たものを感じます。藤田和日郎先生の漫画作品の独特のテンポ・描き出す壮大なスケール感を舞台作品に落とし込むことが、劇団四季なら出来る!そして、この重厚なラブストーリーのパッケージは、劇団四季ファンの志向性に合致する!という制作意図だったのではないかな、と受け取っています。■素晴らしかった点、原作との違い等について(概要)途中休憩を挟み、2時間50分くらいのプログラムとの事前情報でしたが、休憩時間が若干延長したこともあり、実際にはまるまる3時間近くでした。私たちは1階のかなり後方、中央から全体を俯瞰するような座席からの鑑賞でした。(役者様)劇団四季は専用劇場をいくつも持ち、年間何千という舞台作品を提供しています。1演目につき、キャスト様は複数人充てられており、定期的/安定した公演を提供されています。今回チケットを購入してから知ったのですが、各公演日の出演者はおおよそ週単位で変更され、その週の始まる直前にHPに公開されるとのこと。※もちろん、諸事情により週の途中や公演日当日のキャスト変更もありうるチケットを購入する時点ではどの公演にどの役者様が出演予定か分かりません。四季は、基本的にあまり役者性を対外的に推していない…1人のアイドル的な役者様に依拠することなく、同様のクオリティで定期的/安定した公演を提供できる点を圧倒的な強みとされているのだろうと感じます。ただ、もちろんスター役者様は誕生しますし、特にゴースト&レディのような心情に重きを置く、キャラクター性が際立った作品は役者さん毎に見比べると同じパッケージで全く異なる印象になるため、見比べを楽しみたい方、特定の役者様のファンの方は、ローテーションを予測してチケット確保を行う(最終的には読み切れない)という…なかなか大変な世界なのだな、と知りました。私は、今回1回の観劇予定ですし、役者様の違いを見比べる気もないので特段気にしていなかったのですが…結構その点を妹は気にしていたようです。先行イメージが付かないように、鑑賞するまではあまりPV動画を見ないようにしていたとのこと。(劇場で鑑賞しながら「なんか違うな」と思いたくなかったそうです)今回、私たちが鑑賞した際のキャスト様一覧です。↓・フロー(フローレンス・ナイチンゲール):町島 智子さん名古屋公演からの新キャスト様のようです。高らかに天に響かせるような美しい歌声が圧巻でした!上に向かう歌声は讃美歌のようで、「クリミアの天使」というキャラクターにもすごくマッチしていました。非常に可憐で守ってあげたくなる雰囲気もありながら、ラストに向けどんどん力強くなり、最後敵キャラと対峙する ♪偽善者と呼ばれても のシーンには圧倒されました!原作を読んでイメージしていたフロー像そのままの姿でびっくりしました。・グレイ:萩原 隆匡さんメインビジュアルや公開されているPV映像等は必ずこの方のグレイです。幽霊という異形の存在であるため、立っているだけで圧倒的な華やかさ&ずっと周囲を観ている達観した存在感が必要で、しゃべり出したら必ず空気感を全部持ってく役どころであり、なかなか誰でも出来るような役ではない…萩原さんの演じるグレイは「超はまり役」なのだと感じました。ディズニーのミュージカル化であれば、観客は皆当然アニメを先に観ていますので、話筋も歌も知ってるし「オリジナル(アニメ)と比べてどうか」という感じ方になりますが…そもそも、本作はメディア化していない作品です。ミュージカル作品としての「グレイというキャラクターのオリジナル」は、この「荻原さんの演じるグレイ」になるんじゃないかな、と感じました。茶化しながらのやり取りの中に、フローを信じたい、彼女の進む道を守ってあげたいという感情が芽生えていく過程も丁寧に感じられて、キュンキュンしながら鑑賞しました。・デオン・ド・ボーモン:岡村 美南さん中世的なキャラクターですが、太く響き渡る声や舞台上での存在感が圧巻でした。非常に有名で固定ファンの方が大勢ついている役者様なのかな?観客の拍手も一際大きかったような気がします…。そのほかのキャスト様も、本当に隅々の方まで歌が非常にお上手で…‼(劇団四季だから当たり前?)いやでも本当に、舞台上に居るすべてのキャラクターたちの動きが端々まで洗練されていて、説明調の台詞もすべて必要なバランスでスッと入ってきて…圧巻でした‼(演出/脚本/シーン)・開園時、ライト消灯までのタイミングを溜めて溜めて…大きな音とともに一気に消灯!いきなりちょっとびっくり演出から始まりましたが、この「うわっ!驚いた!」という感覚自体が、藤田和日郎先生の漫画作品を読んでいる際の感動と近いもので、印象的でした。・舞台装置、美術イギリスの華やかな劇場、フローの実家(お金持ちの家)、クリミアの戦地病院…とコロコロと場面が変わっていきます。基本は劇場の舞台の骨組みを活かし、マッピング/ライティングで色を変え様々な場所を表現する…どの場面転換も非常にスムーズに、魔法のように転換して凄かったです。妹は、劇場の客席の凹凸を利用し、墓石を表現していたところに感動していました。光の演出や音の演出も、それぞれのシーンで魅せたい方向性がはっきり分かるものばかりでした。専用劇場で、何百と続けて公演されるプログラムの洗練の格の違いを見ました。・かちあい弾の設定は省略。その代わり、本舞台作品はグレイが仕立てて、観客に提供しているものであるという筋道の提示。舞台大好きのグレイが、舞台を書き上げるという感慨深さ、ナイチンゲールの功績とその内面を伝えたいという愛情と尊敬の念を感じる、素晴らしい脚色でした!・グレイ、幽霊たちとダンスフロー&グレイの出逢いの後、グレイがシェイクスピアをたくさん引用しながら幽霊の概念について説明するターンがあります。このシーンはかなりの尺を取り、不気味な幽霊姿のダンサーさんたちが現れ一緒に踊るのですが、原作にはないシーンです。原作では、精神世界の戦いは妖怪じみた気持ち悪い怪物が画面いっぱいに描かれ、少年漫画的なアクションシーンが展開しますが、本舞台ではライティング?を用い、影を蹴散らす演出で表現されています。グレイが異形の存在であり、彼が闘うのは気味の悪い精神体である点を、このシーンを盛って強調し、観客に印象付けているのだと思います。ミュージカルはこうやって理知的に考えて、観客に必要な情報を意識付けしているんだな、とよく分かるシーンでした。・淑女病院のくだりを省略原作では、フローは最初「淑女病院」の総婦長に任命され、運営の立て直しに従事します。病院内の設備改善やナースコールシステムの導入等、劇的な変革と大きな成果をもたらす姿は非常にカッコよくて大好きなシーンなのですが、本作では口頭説明にとどめ、すぐにクリミアの戦地に向かっています。原作は週刊モーニング掲載ということで、かなり具体的にナイチンゲールさんの実施した改革の数々を描写しています。基本的に社会人の男性読者を念頭に置いているので、具体的に詳細を書けば書くほど彼女の凄さが伝わり易いのだと思います。今回の舞台では、具体的な施作等はそれほど詳細に描写されてませんでした。しかし感覚的に、どれほどフロー&看護婦団たちの功績が勇敢なものであるかは、セリフの端々や各所の反応によってきちんと観客が受け取れるようになっていたと思います。・ウィリアム・ラッセル戦場の様子をイギリス国内に知らせる「ザ・タイムス」の戦場特派員。話を進める上での状況説明、場面転換に大きく貢献する役どころ。劇の筋回しにうってつけの役ですが、このキャラクターは原作に既に登場しており、藤田先生のそもそもの原作の描き方が、脚本的に洗練されてるんだな~と感じました。・アレックスとエイミー本舞台における完全オリジナルキャラクターの2人。アレックスはフローの婚約者であり、衛生委員会として戦地の病院にも赴く貴族の青年。フローへの求婚シーンでサムシングフォーの概念を丁寧に提示し、またフローのいち女性としての結婚/幸せと言う道筋の可能性を完全に閉ざす役割も担います。エイミーはハーバード戦時大臣の親戚の娘。フローとともにクリミアの戦地へ向かう看護団に参加します。どこまでもまっすぐ理想に突き進むフローの姿に憧れ/尊敬とともに恐れも抱き、その心情を高らかに歌い上げるシーンもあてがわれています。またフローから見ても、エイミーは「一般的な女性の幸せの道」を生きていく、自分とは対照的な女性として描かれます。エイミーの視点は、女性鑑賞者が自然と入っていける「フローを見つめる」視点であり、原作ではこの視点は重点的に描かれていなかったので、本ミュージカルが基本的には女性向けを意識して再構築していることがよく分かりました。この2人のキャラクターは、特に「フローのいち女性としての意識筋」という面で、話回しへの貢献度が非常に大きく、スマートな脚色に感動しました。・クリミアへ向かう女性看護婦団勇敢に戦地に乗り込んでいく女性陣たちが♪走る雲を追いかけてという楽曲を歌い上げるシーン。どんどん力強くなる曲調や振付が素晴らしく、圧巻のお気に入りシーンです!・グレイがフローにランプを手渡す本公演のメインビジュアルにある、グレイがフローにランプを手渡す絵面が作中でもしっかり描写されました。この絵面モチーフ自体、原作には登場しないミュージカルオリジナルです。ラスト、サムシングフォーの中の「借りたもの」も、原作ではかちあい弾でしたが、ランプに変更されています。「ランプの淑女・ナイチンゲール」…孤高で清廉潔白な独りの女性という一般イメージ像に対し、彼女の傍らに、姿は見えないけどランプを手渡す存在が居たこと、彼女にとってそれは、心の拠り所であり、行く先を照らす明かりそのものであり…という美しいほど見事な概念だな!と感動しました。・ランプの淑女本ミュージカルの楽曲は、メロディアス且つ方向性も明確で素晴らしいものばかりでした。その中で個人的に一番好きかも…!と思ったのが、♪ランプを持ったレディという楽曲。戦地の病院の夜、ランプを持って患者の様子を見て回るナイチンゲールの姿を病床の兵士たちが敬いながら歌う楽曲です。非常に絵的というか、暗闇の中に灯りを持って歩く彼女の姿を丁寧に言い表していく楽曲で、絵面のイメージがガツンと頭に入って来て、その上で「レディ」という単語が余韻で残る、素晴らしい楽曲だと思います!・デオンの過去デオンが、女性でありながら男性として育てられた人物となっていました。「女であることは呪いでしかない」といったセリフもありました。これらは原作にはない筋立てです。ナイチンゲールを殺そうとするも、彼女が女性の姿のまま社会へ大きく貢献する雄姿を見て、彼女を守ろうとするグレイに殺される自分自身の最期に満足して散っていく…グッとくるキャラクター筋に脚色してあり、感動しました。・グレイの過去シルエットだけでアニメーション的に魅せていく手法がとても面白かったです。本作は、クリミア戦争の最低限の説明や、ファンタジックな幽霊の要素、主要キャラクター各人のバックボーン等、説明しなければならない前提情報が非常に多い作品です。どのように情報を観客に擦り込んでいくのか、その中でも強調どころはどこか、よくよく練られていることがよく分かりました。・グレイの過去・酒場のシーングレイが劇場の看板女優と恋に落ちるシーン。酒場の楽しい宴会シーンに、楽曲とともにかなり長い尺を取っていました。話筋的には、それほど強調が必要なシーンではないと思うのですが、後半パートに楽しい派手目のシーンが少ないことを考慮して入れられているのかな、ミュージカル作品はこういう部分に気を使うのか、と思いました。・ラストシーン90歳になったナイチンゲールの死の間際、彼女の傍らに現れたグレイ。フロー1人で天に逝くラストは原作と変わらないものの、その後100年以上かけて、グレイは「(今観ている)このミュージカル」を完成させ、本日公開しているという体裁で幕引き。原作ではグレイが「自分は(天国には)行けない」とはっきり明言していましたが、明言は避けているものの、おそらくそうなのだろうな、というニュアンスで描かれていました。その後のアンコールで、フローとグレイの2人が仲良く祝福されて登場しますし、劇中の楽曲♪あなたの物語で、「ハッピーエンディングストーリー」の単語を繰り返し焼き付けた上で迎えるラストですので、鑑賞者としてはなんとなく「ハッピーエンディングを迎えた!」ようないい気分で会場を後に出来ます。劇場公演パンフレット&藤田先生描きおろしイラストグッズをいくつか購入しました。書きたかったことは一通り書けたかな?とにかく、本当に誠意と熱量の籠った素晴らしい舞台作品でした!藤田和日郎先生の漫画作品が、これほどミュージカルと親和性があるとは…!企画の発表段階で謎の納得感があり、実際に鑑賞してみてその出来栄えにスタンディングオベーション!でした。ミュージカル化、本当にありがとうございました!ずっと魔法の中に居るみたいで、本当に面白かったです!!by姉
2025.08.12
コメント(0)
-

原型師・香川雅彦さんの名作ヴィネット!(赤毛のアン)
原型師・香川雅彦さんの名作ヴィネット!(赤毛のアン)以前、原型師・香川雅彦さんのアルプスの少女ハイジ&世界名作劇場シリーズの食玩ヴィネットシリーズについて記事を書いていましたが…世界名作劇場「赤毛のアン」シリーズもあったんです!知ってたんですが…「赤毛のアン」シリーズだけやたらと相場が高くてっ!手を出しあぐねていましたが、今回「赤毛のアン」シリーズにドはまりしたのを機に、思い切って購入しました。やっぱり香川雅彦さんのフィギュアはいいわぁ~~~!どの作品にも絵としての面白さがあって…アンちゃん/ダイアナちゃんの仕草がいちいち可愛くて、素敵です…!!以下、お気に入りの作品。グリンゲイブルスの窓辺で小鳥と戯れるアンちゃん。窓の外の桜の木が表現されていて、室内に居ながら外の空気感/季節感を感じられる、情報量の多い作品です。どの角度から見ても見ごたえがあって素晴らしいです。ラインナップにはグリンゲイブルスも含まれています。素敵。よく見ると、窓辺にアンちゃんらしき人影が居ます。アンちゃん&ダイアナちゃんのピクニックの様子。食べてるのはアイスクリームかな?こちらは2個を並べて組み合わせる形となっています。ダイアナちゃんのフィギュア側から伸びる大きなブドウの木が印象的。香川雅彦さんのフィギュアは、実際のアニメーション画面より空間感というか、魅せたい高さ・凹凸を大胆にデフォルメして、ぎゅっと濃縮して、小さなフィギュアの世界の中で強調している印象です(天才)。香川雅彦さんのフィギュア…特に世界名作劇場シリーズは本当に輝いていますので、これからもポツポツと集めていきたいな!と思ってます。by姉
2025.08.09
コメント(0)
-
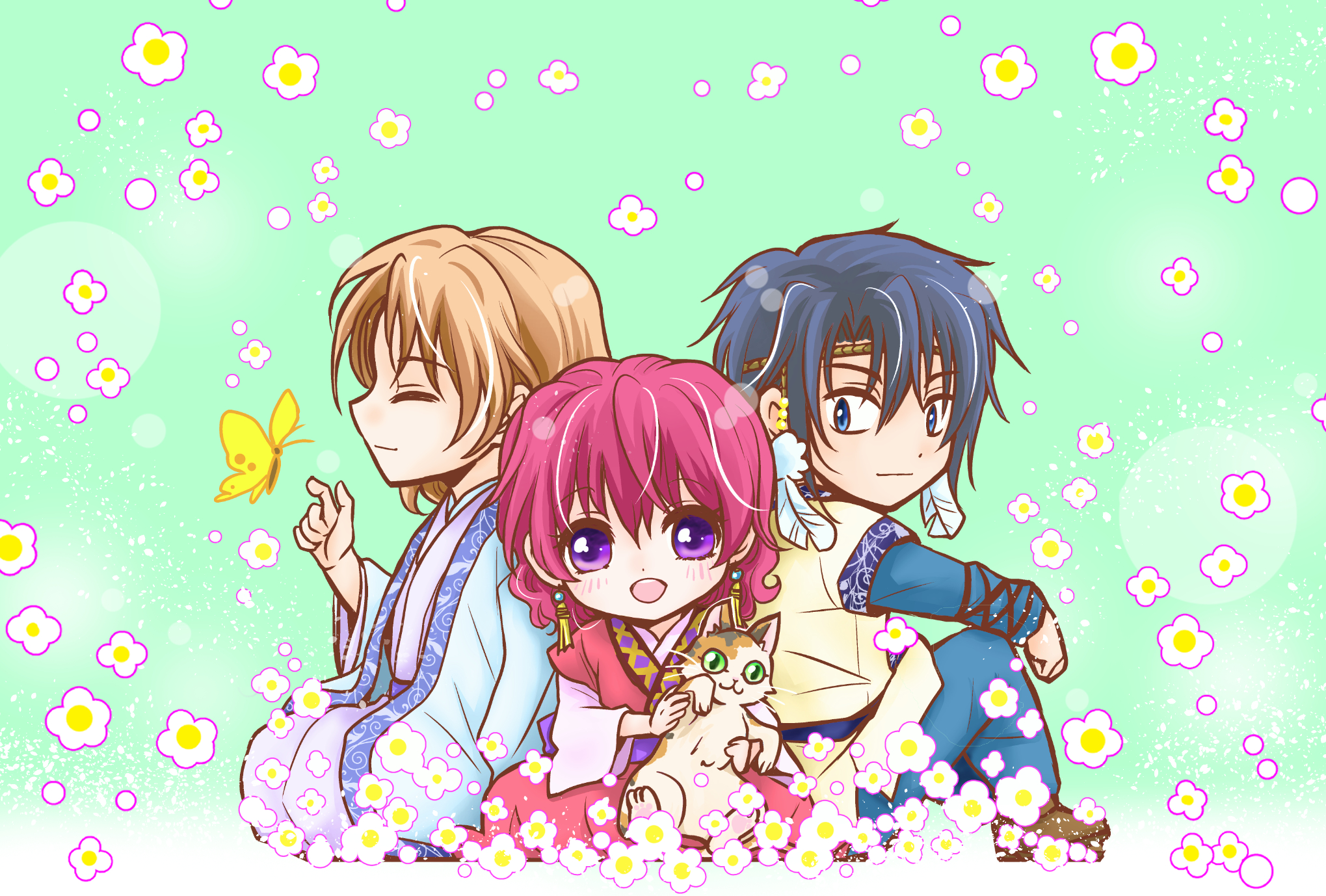
クライマックス直前!「暁のヨナ」イラストコンテスト★
2025年7月4日~8月5日にかけて、花とゆめ本誌でクライマックス直前!『暁のヨナ』最終章記念W企画 が開催されました。特設サイトでのキャラクターコンテスト(人気投票)&郵送orTwitter投稿のイラストコンテスト!キャラコン…毎日参加!…は、ちょっと出来ませんでしたが(寝落ちする日多数;)力の限り参加させていただきました!イラストコンテスト…新しい新規絵を用意することは出来ませんでしたが…描きためていた(私的)渾身絵を再編集したり、加筆したり…何枚も投稿させていただきました!「クライマックス」の文字が感慨深いですが…最後まで全力で追いかけさせていただきます!以下、イラストコンテスト参加イラスト群です~。『在りし日』『あなたのそばに』 第122話(21巻収録)ラストシーンの ハクヨナ でテンション上がりすぎて描いたものです。『旅の始まり』2巻のハクヨナのやり取りを観て「10巻越え…いや欲を言えば20巻越えの大長編少女漫画になってほしい!」と思ってました…!『高華国神話のステンドグラス』 暁のヨナを神話と捉え、上方は天(腹減り一行、四龍)、下方は地(5部族)の要素を詰め込んでみました。拝めば、慈愛に満ちたぷっきゅーがドングリを差し出して救済してくれるイメージです。↑姉に「説明文付けなきゃ、絶対分かってもらえないから解説しろ」と言われ…長々と説明文つけて投稿しました;一番頑張って加筆したイラストになります。個人的には気に入っているファンアートです!『ハート乱舞❤️』『小鳥が無事でよかったわ』 まだ専属護衛になる前のハクヨナ…というイメージで描いたものです。実はこの構図自体は、原作5巻あたりが本誌に掲載されていた頃…ーそう、pixivに暁のヨナ絵が一枚もアップされてなかった頃に、姉に「ハクヨナのラブラブ2次創作絵が観たい!」と言われて描いたものでした。(そのリメイク版になります。)そのため、姉は「この絵には思い入れがある」と気に入ってくれています『15歳の皇女』頑張ってアナログで描きこんだものですが、いまいち気に入らなくて…今までどこにもアップしたことが無かった絵です;久々に見たら「意外と可愛いじゃん…?」と思えたので、投稿しました~。『ヨンヒ様とヨナ姫』 ヨンヒ様、凄く好きなキャラクターでした!『ぎゅっ』ちょっと肌寒い森の中で固まる、腹へりご一行(ポップな感じで)!ーというイメージで背景を加筆したんですが、分かりにくかったですね;;下の2枚は用意したけど、加工が間に合わなかった&なんとなく投稿を見送ったもの。ここに供養いたします。イラストコンテスト、参加出来て良かったです!by妹
2025.08.07
コメント(0)
-
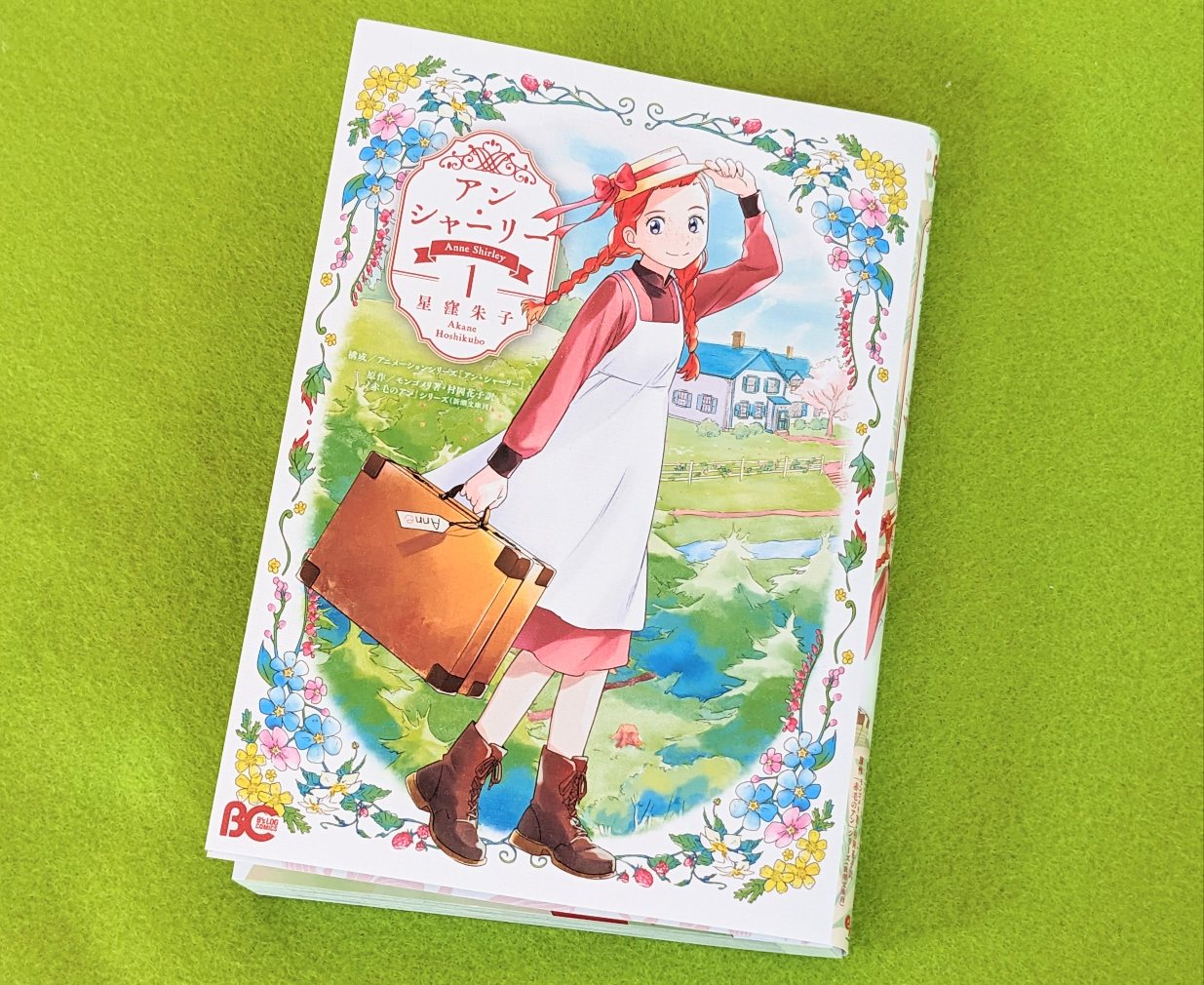
漫画感想『アン・シャーリー①』+赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
漫画感想『アン・シャーリー①』+赤毛のアンシリーズのコミカライズについて毎週楽しみにしているNHKアニメ『アン・シャーリー』のコミカライズを購入しました。『アン・シャーリー』1巻(星窪朱子 先生、KADOKAWA ビーズログコミックス)装丁が可愛らしい!表紙カバーの紙質もキャンバス地風のこだわったものになっていて、高級感があります。基本的には今回のアニメーションのキャラクター造作で、アニメ本編のセリフ/演技筋を漫画画面に落とし込んだものになります。アヴォンリーで暮らし始めたアンちゃんの視界に広がる「光・色彩」を読者も感じ取ることが出来る漫画画面が素晴らしいと思います。また、いきいきとした表情が素敵!特に女の子たち…アンちゃん/ダイアナちゃんの表情が華やかで可愛いので、パラパラとめくるだけで楽しいコミカライズです。今回のNHKのアニメシリーズが、かなり脚本家様主導のつくり方というか、必要な要素やニュアンスを理知的に詰めて映像化している印象があります。星窪先生のコミカライズが、感覚的なところを重視する画面の描き方だな、と感じますので、アニメ本編とのアプローチの違いも面白いところでした。是非、今回のアニメシリーズの最後まで…原作だと「アンの愛情」パートまで、しっかりコミカライズしきって欲しいな…!(…最後まで描き切れるかどうかは、今回のコミック1巻の売上次第かな?)応援してます!今回、赤毛のアンシリーズにドはまりして、様々なビジュアライズ化に非常に興味を持ちました。赤毛のアンシリーズには多岐にわたる魅力が詰め込まれているので、同じ原作小説を取り上げたとしても、メディア展開する主体がどこに着目し魅力を感じて咀嚼しているか、誰を対象とした作品にするのかによって、ガラッと作風が変わり、全く別ものに見える面白さを感じています。赤毛のアンシリーズは、日本においてもサブカル(少女漫画的萌え文化)の基盤的な位置づけと感じていて、様々なメディア化&ビジュアライズ化も、絶対的に力のある作家様たちがリスペクト&誠意をもって取り組まれているのを感じます。下手なメディア化が見受けられないのも、作品の格の高さを非常に感じますし…様々なメディアでどれだけ追いかけても追いかけても、咀嚼し切れない感情の繊細さ・多様さがそれを可能にしているのだと思います。あれよあれよという間に、様々な形式の赤毛のアンシリーズ書籍が増えたくっています。(恐ろしき赤毛のアン沼)以下、現時点で鑑賞したコミカライズ作品に関する簡単感想です。『まんが赤毛のアンシリーズ』全5巻(いがらしゆみこ先生、くもん出版、1997~1998年)赤毛のアンを全3冊、アンの青春/アンの愛情を各1冊ずつでコミカライズしていて、総計5冊に渡る「アンシリーズのコミカライズ決定版を作ろう」という意欲を感じるシリーズです。私が小学生の頃、もし本シリーズが図書館にあれば絶対に手を付けていたと思いますし、ここでしっかり読んでいたら、赤毛のアンシリーズへの印象は全然違うものだっただろうな、と感じます。本作は、アンシリーズを思いっきり少女漫画テイストでコミカライズしている作品で、ある意味で、今回・2025年のNHKアニメシリーズと似た考え方で構築してある作品だな、と思います。日本において、アンシリーズは高畑勲監督のアニメーションのイメージが強く根付いていますので、それとは異なるイメージでのビジュアライズ化は難しい面もあったと思いますが…「いがらしゆみこ先生」という、コミカライズ作家様自身が強力なイメージを纏っているからこそ成立した企画だと思います。「"少女漫画"・"乙女ちっく”は正義だ!」というパワーが本当に凄い。特に赤毛のアンパートは3冊に渡り丁寧にじっくり漫画化されていて、四季折々、時間帯によっても表情を変えるアヴォンリーの美しい風景が焼き付いて、非常に見ごたえがあります。ギルバートが「ここまでやるか」と感じるほど、キラキラ王子様として描かれているのも興味深かったです。第3巻のエレーン姫ごっこのシーンは、少女漫画でしかできないキラッキラ画面が素晴らしかった!あらゆる時間帯で輝きたくる「水面」万歳!『虹の谷のアン』上下巻(原ちえこ先生、講談社、2003年)「虹の谷のアン」…原題は「Rainbow Valley」であり、アンちゃんではなく子どもたち世代…それも、ブライス家ではなくお隣に越してきた牧師館の子どもたち目線を主軸に据えた作品です。リラ執筆の前段階で、子どもたち世代のキャラクター造形を試行錯誤している作品と捉えています。原ちえこ先生はお名前は知っていましたが、しっかり作品を読むのは初めてでした。表紙イラストを見ただけで分かると思いますが、ブライス家及び牧師館の子どもたちも納得のいくデザインで、スマートな漫画表現が超絶達者で、とにかく「素晴らしい!」の一言です。手放しで超おすすめのコミカライズ作品です。特に本作の主だった牧師館の姉妹…フェイスちゃんとユナちゃんの対比的なキャラクター性がスマートに頭に入って来ますので、「アンの娘リラ」を読む前の事前準備としてもおすすめの作品です。世界的名作シリーズはいろんな楽しみ方が出来て面白いですね…!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.08.03
コメント(0)
-
アニメ『アン・シャーリー』第14話・第15話・第16話・第17話 感想
アニメ『アン・シャーリー』第14話・第15話・第16話・第17話 感想2クール目も、毎週楽しみに鑑賞してます!16話からは、いよいよ本シリーズでは最終章となる「アンの愛情」パートの幕開けです。各話一言ずつの簡単感想です。※以下、原作シリーズを読んだ上でネタバレ全開で好き勝手語ってます。原作シリーズ未読の方はご注意ください!※■第14話青春パートのクライマックス、ミスラベンダーさんのラブストーリーエピソード。アンちゃん&ダイアナが道迷いの末訪問した「山彦荘」。そこに暮らすのは、美しくも風変りな独身女性/ミス・ラベンダーとお手伝いの少女・シャーロッタ4世。アンちゃんは、自身の教え子のポール・アービングがラベンダーさんが25年前、けんか別れした元婚約者/ステファン・アービングの息子であることを知っており、ラベンダーさんの意向もあり2人を引き合わせることに…。今回のアニメでは、意図的にラベンダーさんのビジュアルを髪をおろしたアンちゃんに似せて設定されていて、(アンちゃんが年を重ねると、こんな姿になるのかな?)と思わせるようなデザインになっていたと思います。ラベンダーさんの立ち振る舞いも、上品さと明朗さが強調されていて、アンちゃんが自然と憧れることのできる素敵な女性として描写されていました。興味深いなと思ったのが、アンちゃんが、ラベンダーさん×ステファンさんの物語(悲恋+運が良ければ壮年に再成就)に対し、感情移入して涙ぐむシーン。もちろんまだまだ無意識的にだとは思いますが…既に「自分もこうなるんだろうな」とどこかで感じているというか…自分自身とギルバートの将来像を、この悲恋にダブらせてる?ーみたいな、かなり踏み込んだニュアンスまで感じました。次の「アンの愛情」パートに繋がる話ですが、アンちゃんはギルバートのことを本当に信頼してるし、大好きなのですが…まずアンちゃん自身が(深層心理のところで)結婚する気がないのでは、と。…おそらく、自身の両親の顛末の影響もあって、「家庭を築く事」がトラウマになっている、非常に複雑で繊細な娘なんじゃないかな~ と(原作を読んで)認識していますので。ミス・ラベンダーさんの話を聞いて…もちろん明確にではないですが「私もこんな風に意地を張ってしまって、相手が去ってしまった後に後悔を携えて、でも明るく美しいオールド・ミス(独身高齢女性)になるのかな…!」くらいな感慨に浸っているのかな、と感じました。ーしかしまぁ、相手がね…ギルバートもステファン・アービング氏くらい諦め&割り切りが良くて、他の女性と結婚してお子さん産んで…って出来るような奴なら、アンちゃんがふんわり思い描く未来に向かったんでしょうけどね…まぁ…相手が悪かった(想像以上に思い込み激しくてヤベェ奴だった)ですね。ラストシーン、ポールくんの亡き母の墓前での言葉での締めはグッときました!■第15話「アンの青春」ラストエピソード。リンド夫人の旦那さん死去、ラベンダーさんの結婚式、そしてアンちゃんは大学進学の決意を固める…。寂しいけれど、アンちゃんに大学進学を促すマリラ&ダイアナちゃんの愛情が染み入りました。そしてダイアナちゃん、婚約おめでとう!小説本編とは異なり、アンちゃんはフレッド・ライトに寛容的ですが、フレッド・ライト役にあえてゲスト声優様(棒読み)を配置することにより、「…チクショウッ!こんなぼーっとした奴に可愛いダイアナちゃんを奪われるとは!腹立たしい!」という感情を視聴者側に想起させていて、面白い作りですね。■第16話「アンの愛情」編、スタート。16話放映前に、メインビジュアルが大学生編に変更されました。本アニメシリーズで一番描きたかったところが、「愛情」パートだと思っています。スタッフ様たちの「やる気満々!」という意欲を感じる素晴らしい回でした。16話出だし、橋の上で超美しい夕焼けを見つめながら、ギルバートがアンちゃんの手を握ろうとして拒否られるシーンから始まります。…初っ端からぶっ飛ばすな…。次の日、改善会のメンバーたちによる送別会では、アンちゃんに「そういう話(色恋沙汰)はするな」と釘を刺され… ていたにも関わらず、更に次の日(出立前夜)には夜のお散歩デート(リンゴの木)に誘いに来る驚異のおきあがりこぼしメンタルのギルバート氏。Aパートの中だけで、3度もアンちゃんに不自然なアプローチを図る不屈のギルバートの姿に、既に涙を誘われました。お前…頑張るよな…。Bパート、キングスポートの背景美術が本当に素晴らしかったです!アンちゃんと同郷の、自由奔放なお嬢様・フィリパ登場。個人的に、小説で読んでいたイメージに非常に近いな、と思いました。フィリパは、基本的にはアンちゃんをボーリングブロークに誘う役割を持って投入されたキャラクターだと認識しています。そしてもう1点。本作においては、一番大好きなはずのギルバートからひたすら逃げたくるアンちゃんのラブストーリー軸と、出だしは「私は優柔不断~!」と言っておきながら、貧しい牧師さんに恋して「コレーー!私の人生はここに向かうのーー!」と、躊躇なく自分の心が定めた運命に飛び込んで行ける、非常に爽快で、読者受けも良いであろうフィリパのラブストーリー軸の対比が鮮やかに焼き付きます。オールド・セント・ジョン墓地のシーンも丁寧に描かれて嬉しかったです。18歳の少尉候補生のお墓を見て、アンちゃんの意識がタイムスリップするシーンは小説本編よりも意味あり気に描かれていて、これは…若干、ウォルターくんの示唆が含まれているのかな?と感じました。■第17話大学生活、パティの家+クリスマス休暇&初めてのプロポーズ(ジェーンちゃんの兄)キングスポートの街並みは、やっぱり見ごたえありますね~!プリンスエドワード島の面々が、都会での大学生活を謳歌できているようで良きです。(私も、田舎生まれの田舎育ち→大学時代だけ都会→その後はずっと田舎暮らしの人で、基本的に田舎大好き民なのですが…ただやっぱり学生時代の都会生活は貴重な、すごく良い経験だったなぁ…と思います。)クリスマス休暇でアヴォンリーに帰ったアンちゃんですが、周囲がざわざわとして来ました…。ジェーンちゃん伝手で、ジェーンちゃんのお兄さんより結婚の申し出を受けます。驚きつつもしっかりお断りするアンちゃんですが、ジェーンちゃんとは不穏な空気感に…。ジェーンちゃんの物言いから(ああ、アンドリュース家は根本的に「孤児」であるアンちゃんを下に観てるんだな…)と分かってしまう演出が凄かった!アンちゃんの思い描く理想のプロポーズシーン(2連発)が非常に馬鹿っぽく描かれていて、素晴らしかったです。2つ目に至っては、プロポーズ成功してないし…そして謎の花火。アンちゃんの思い描く「恋愛」は、基本的に「プロポーズシーン」限定です。(物語のクライマックスシーンであるため、プロポーズが成功しようが失敗しようが、美しく盛り上がればヨシ!ーという考え方なんだと思います。)そして…またしても不自然にやって来るギルバート!(アニオリシーン)「雪の中をお散歩しましょう」との誘いに、「グリンゲイブルスの皆に会っていって」と2人きりになるのを回避しようとするアンちゃん。アンちゃんの靴紐がほどけているのに気付いたギルバートが、かしづくような態勢でアンちゃんを見上げるシーンですが…ギルバートの意識としては、アンちゃん(女神)には常に下から行ってるというか…「そう、ギルバートの意識はコレ!」と思えるシチュエーションになっていて、素晴らしかったです。ジェーンちゃんの一件のすぐ後なので、このギルバートのアンちゃんをどこまでも大事に扱う態度は、本当に輝いてましたね!そしてアンちゃんの怯えた表情と牽制がまた…ね。冬の朝日の背景美術もとてもきれいで、2人の表情もとても繊細でした!とてもお気に入りシーンになりました。次回・18話は、アンちゃんがボーリングブロークの生家を訪れるエピソードが少し前倒しで入って来る感じかな?上述してきた通り、愛情編に入り、16話・17話が非常に繊細/丁寧に描かれていて素晴らしいので、近々訪れるはずのギルバートが果樹園でものの見事に玉砕するシーン(1回目のプロポーズ)を凄く楽しみにしています♪今時、こんなに…清々しいほど見事に、木端微塵に玉砕するヒーローなかなかお目にかかれません。今から心が痛いですが…貴重なシーンを是非目撃したい…!by姉アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.07.27
コメント(0)
-
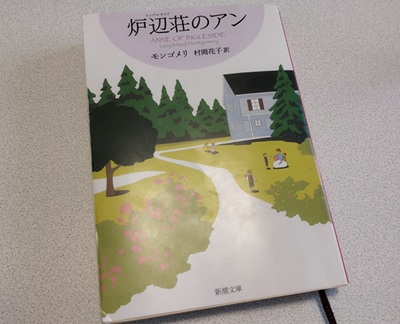
「炉辺荘のアン(ろへんそう/イングルサイドのアン)」ー赤毛のアン・シリーズ7ー感想 村岡花子訳
「炉辺荘のアン(ろへんそう/イングルサイドのアン)」ー赤毛のアン・シリーズ7ー感想(L・M・モンゴメリ・1939年、和訳 村岡花子・1958年)夢の家で長男・ジェムくんを出産した後、ブライス夫妻はグレン村の大きなお屋敷・炉辺荘(イングルサイド)へ移り住んだ。そこで男女2人ずつの子どもが次々と誕生し、5人の子どもたちは元気に育っていた。アヴォンリーにも時折顔を出し、ギルバートの父母の死やギルバートの親戚で気難しいメアリー・マライア叔母さんの炉辺荘長期滞在、末娘・リラの誕生と、子どもたちの巻き起こす騒動・友達問題に向き合う日々…時に苦々しい思いもしながらも、慌ただしく過ぎ去っていく大切な時間。愛しい、幸せなブライス一家の日常&子どもたちの成長の物語。本作は、1921年発表の「アンの娘リラ」より20年弱経って、空白期間だった部分を埋める形で1930年代後半に発表された作品だそうです。「アンの愛の家庭」という題名で出版されていることもあるみたいですね。大きな出来事があるわけではない日常…でも、感情の起伏としては焦ったり不愉快に思ったりがっかりしたり立ち直ったり…がだらだらと重ねて描き出されます。本作はシリーズの中でも、エピソードがとっ散らかっていて洗練されていないというか、「さっきも似たようなの読んだ」みたいな…整理されてないから頭に入って来にくいというか。ネタを詰め込んだ第一草案を、あえてそのまま発表したような、独特な印象を受けました。ただもう、この「慌ただしい日常」を余すことなく描くことこそ、本作の意義というか。この1冊があることで、ブライス医師一家がどのような一家なのか、子どもたち一人ひとりの個性もよく分かるので、おそらくコアなファンが大喜びするような『ネタの宝庫』というか。アン・シリーズとしては非常に大事な1冊だな、と感じています。世界中で愛される名作物語・アンシリーズの主人公:アンちゃんの人生が、最終的にどこにたどり着いたのか、と言ったら、その答えは、まるまるこの「炉辺荘のアン」の1冊であり、本作の締めシーン「ブライス(快活な)!あたしはブライスだわ」の一言に尽きると思います。以下、取り留めなく、本作の見どころについて。・聖母:アンちゃんとにかくアンちゃんは、徹底的に『聖母』!です。家や庭はきちんと清潔に保ち、子どもたちには丹念できれいな服装を、食事もお菓子も手の込んだものを…そして子どもたち一人ひとりとしっかり向き合って話を聞く時間を作って…また社交的にも、ギルバート医師の奥方として地域社会への参画、パーティー等の外交に重きを置き、身なりを整えて挑む理想的な『町のお医者さんの妻』を演じます。ここまでの作品を読んでも少し感じていましたが、本作を読んで改めてはっきりと、アンちゃんは本っっっ当に「やるとなったら徹底的!」ものすごく潔癖な女性だな、と感じました。炉辺荘で描かれている、「ブライス一家=理想の家族」像は、「普通、そこまで頑張るのは難しいよ」と感じるレベルです。(もちろん住み込みの女中さん・スーザンが居るからこそ保てる水準です。)アンちゃん自身は、幼少期に「安心できる暖かい家庭」を享受出来なかったので、実態を知らないからこそ、彼女はどこまでも自身の理想に忠実というか。また、アンちゃんは「夫のギルバートは、どこまでも理想の家族を築き、誰よりも幸せで認められた人生を送るべき人」だと思っている節があると感じますので、そこに自然と追いつこうとしている側面もあると思います(妹談)もともと作者・モンゴメリさん的には、アンちゃんには「妻・母をやりながら、小説家としても名が売れるような未来を…」という構想があったんだろうな… と想像しています。青春ではモーガン夫人という女流作家がグリンゲイブルスを訪れていますし、愛情ではアンちゃんの小説が初めて賞金になるエピソードがあります。夢の家では、ジム船長という小説題材の宝庫のようなキャラクターを投入し、最初はアンちゃんに妊娠期間で小説執筆を促すような作りだったのではないかな…と。ただ、結婚&お子さんの出産に向かうアンちゃんが、とにかく『ギルバートと子どもたち…「家庭」に全力を尽くしたい!』と言ったんだろうな、と受け取っています。この潔癖さこそが、アンちゃんのキャラクター性として一番特徴的で、魅力的なところだと思います。ちなみに、(一生外れぬ女神フィルターで)アンちゃんを観てきたギルバートにとっては、この聖母・アンちゃん像はものすごく「しっくり」来るものだと受け取ってます。ギルバートの理想とアンちゃんの理想(社会面・家族面)は、根本的に合致しています。基盤・資本が無い中で、これほど気高い「理想の家庭」を1から築くためには、夫婦ともにそれに見合う気高さとハイスペックが必要となります。アンちゃんとギルバートは、本当に「運命的 相性の良さ」だったな、と。※どうでもいい情報本作の中だけで判明している、ギルバート→アンちゃんへ贈り物の数々(誕生日/結婚記念日)・エメラルドの指輪・純金の指貫(ゆびぬき)・ダイヤモンドのペンダント +ロンドン医学会ついでのヨーロッパ旅行(夫婦水入らず)そして、 広大な庭付き屋敷の購入+住込の女中さん雇用+子ども6人(高等教育進学可)+子どもたちへの贈り物の数々…ギルバート、一馬力でどんだけ稼ぐんだ…(良かったね)・いらだち、虚構、失望子どもたちのエピソードも含め、本作の個々のエピソードは よく分からない&意地の悪いゲストキャラクターが登場し、気分の良くない話回しをするようなものが多い印象です。ギルバートの親戚のメアリー・マライア叔母さんの滞在…気難しく、周囲を嫌な気分にさせるようなことばかりを言い、子どもたちも委縮してしまい、アンちゃんも鬱憤を溜めていきます。マシュウやマリラ・リンド夫人も含め、アンちゃんを取り巻くグリン・ゲイブルスの大人たちがあまりに皆優しく素敵なので、「身内ってそんないいことばかりじゃないよね」という観点のエピソードだと受け取っています。また子ども達は、友人たちにひどい嘘をつかれ、困惑&失望するエピソードが非常に多いです。皆に頼られる格好良いお父さんと、優しくて聡明なお母さんに恵まれ、大きなお屋敷で大事に愛されながら暮らすブライス家の子どもたちは、一部の同級生たちからは「憧れと妬みの対象」となっているのかな…というニュアンスで描かれています。でも、これらの もやもや感情も全部ひっくるめて「愛しい日々」というか…余すことなくだらだらと描写して、その上で「ブライス!」に行き着いてナンボ!という作品だったと思います。・子どもたちのエピソード、人物配置作中、子どもたちはどんどん成長していき、また個々人に焦点を当てたエピソードが展開していきます。(三男・シャーリーくん以外)リラの感想でも語りましたが、基本的ににブライス家の子どもたちの人物配置は、「アンの娘リラ」の物語を描くために配置されていると受け取っています。全部想像ですが…ブライス家の兄弟配置の考え方の順番としては下記の順なんじゃないかな、と。①第一に、ジェムくん/次男ウォルターくんの2軸で第一次世界大戦を見せていくこと。・ジェムくん軸:夢の家で生まれた待望の第2子/超理想的な光属性の長男が戦争に行く・ウォルターくん軸:若くして戦死するが、詩は後世に残る(詩人として大成する)いずれもドラマチックな筋立てですし、この2軸をいち家族の物語として描き切りたかったのだろうと思います。②そこに、双子の妹・ナンちゃん/ダイちゃんを配置。そもそも絵面の受けの良い双子の設定で、2人並ぶことで容姿/性格面で父母の要素をほぼ充足する形で設定されてます。たぶん…最初はこんな感じ↓で、基本的には双子の視点を主人公として「リラ」の話筋を回す案を考えていたのではないかな、と。・ナンちゃん:容姿は鳶色の髪の毛・瞳とギルバートの系譜を引き継いでおり、外見は母と似ていませんが、本名(アンちゃん)と夢見がちな気質を受け継いでる可愛い女の子。家庭的な面を持つ子(本来は「アンの娘リラ」でリラちゃんの立ち位置だったのでは?)リラ本編にも出てきた「神様と取引」の観点は、もともとはナンちゃんがリラの話筋の中で行う設定だったのではないかな…と思っています。そう考えると、本作「炉辺荘のアン」での「アンちゃんが肺炎になり生死をさまよう、非常に印象的なエピソード」が、ナンちゃんの目線で描かれたのも、納得がいくな、と。・ダイちゃん:ダイちゃんは赤髪で、容姿は母親・アンちゃんの幼い頃とそっくりですが、性格はギルバート似で、現実的/合理的且つ仕事脳の様子。母・アンちゃんが最終的に「家庭に全振りする」道を選んだため、もしそうではなく社会的に仕事を続けていたら、の「Ifを体現する存在」として設定されているのかな、と感じました。…上記の役割分担で考えると、4人兄弟それぞれの役割がかなり明確でしっくりくるため、当初はブライス家の4人兄弟で考えていたのではないかな、と想像しています。(物語上の時系列的には「炉辺荘~」の後になる「虹の谷のアン」では、近所に越してきた牧師館の4人兄弟(長男・長女・次女・次男)と絡ませることで各キャラクターを自由に走らせ、関係性の試行錯誤をしていたのかな、と。そう考えると、ブライス家6名兄弟に対し、何故牧師館兄弟は4名なのかも理解し易いと思います。)③リラちゃん、シャーリーくんの投入上記の通り、子どもたち世代でいちばん作りこんであるのはどう考えても上の4人(×牧師館の4兄弟)のところだと思っています。普通に考えれば。ただ、「アンの娘リラ」の書き方の異常性…というか、いちばん作りこんであるはずの、この年上の方の子たちについて、具体的な描写・本人の主観がまるっと抜け落ちてるんです。これはもう…各キャラクターに自由に会話させて、感情を作って作って、いざ1冊の小説として書こうとしたときに、辛くなり過ぎちゃったのかな…と。前述したとおり、「アンの娘リラ」のとっかかりは、間違いなくジェムくん&ウォルターくんの2軸を描くことだと思っていますが、ただやはり非常に重い題材ですので…この2軸をどういう形でエンタメ作品としてまとめていくのか、ぐるぐるぐるぐる試行錯誤をされていたんだろうな、と感じます。その過程の中で、やっぱりナンちゃん&ダイちゃんの目線からでは、直に上の兄であるウォルターくんの戦死というのはどうしても近過ぎて、1冊のエンタメ小説作品に収まり切らないというか…ウォルターくんの戦死について、両親&スーザン&リラちゃん(主観)以外の家族のリアクションは「リラ」本編では基本的に全く描かれていません。(ラストのラストに、帰還後のジェムくんが思いを語る場面はありますが)読者としては、年の近い姉妹や幼馴染たちの反応というのはすごく気になるところなんです。でも確かに、皆それぞれにもの凄い激情があるはずで…書き始めると収集が付かない。全部想像ですが、上記のようなぐるぐる混沌とした激情群から少し距離を置き、もう少し冷静に、上の世代を皆リスペクトしながら淡々と物語を進める主観として、末娘・リラちゃんが投入されたのかな…?と。また、娘をもう1人据えるとなった際に、男女同数にしたくて三男・シャーリーくんも設定されたのかな? と感じています。シャーリーくんについては、基本的に描写&情報が極端に少ないため、彼がミステリアスであることこそが、「すべて魅せ切っているわけではない」というブライス家の深みになってるんじゃないかな、とも思います。話を「炉辺荘のアン(イングルサイドのアン)」に戻します。・結婚記念日本作のラストは、アンちゃんとギルバート夫妻の微笑ましい(?)すれ違いエピソードで締めとなります。アンちゃんが(イライラして子どもたちに優しくできない…)と落ち込んでいる最中、大学生時代、ギルバートと婚約の噂があった女性・クリスチン・スチュワートが出席するパーティーへのお誘いが届く。当日はブライス夫妻の結婚記念日であり、アンちゃんは断ってほしいと願いつつギルバートに声をかけると… 非常に快い返答。嬉しそう。医師の仕事で激務のギルバートは、15回目の結婚記念日を忘れている様子。アンちゃんは戦闘態勢でパーティーに臨むが、未亡人&事業家として活躍するクリスチンは非常に輝いて見え、また学生時代、ギルバートと彼女がどれほど親密だったかを見せつけられ…意気消沈して帰宅。アンちゃんのネガティブ思考が「ギルバートは私に飽きたのだ」まで行き着いた その時、ギルバートが用意していたダイヤモンドのペンダントをプレゼント。最近ぼんやりしていたのも、患者さんのことを心配していたからだということが分かり、灰色に見えていたアンちゃんの世界は再び金色/バラ色/虹色に輝き出す。「今度ロンドンの学会ついでに2人でヨーロッパ旅行してこよう♪」からのどこまでもハイパーラブラブイチャイチャで突き抜けて、締め。まぁ…アンちゃんを不安にさせたギルバートの過失ですね。…うん、そんなに誤解させるようなことしたかな?と思わんでもないですが、でも結果的にアンちゃんが不安になってましたので、やっぱりギルバートが悪かったんですよ。うん。ギルバート的には、クリスチンさんとは本当に全くその気はなかったわけで、(なんなら、大学時代、アンちゃんに振られてからの2年間は「空虚な!暗黒の日々!」を歯を食いしばりながら生きていた記憶しかないわけで)アンちゃんがクリスチンさんにこれほど拒絶反応を起こすとは思い至りもしないわけです。ただ、妹曰く、「アンちゃんの目線では、1年半ほどかけて、ギルバートとクリスチンさんが順調に理想的な未来に向かって歩みを進めていくのをずっと見ていたわけで。「ギルバートがクリスチンさんに惚れこんでメロメロ!」という初報から、美しく理想的な2人を遠巻きに眺め、最終的に婚約するまで見届けていた(誤報)わけで。多分アンちゃんは、自分の将来像はあんまり想像できていなかったが、ギルバートとクリスチンさんが築く幸せな家庭は、はっきり想像できていたと思う。(当時は、ギルバートには自分ではない他の人と幸せになって欲しかったので、それでいいと思ってたし、ロイ・ガートナーを隠れ蓑にして、静観していた。)ただ、沸き出ずる感情を殺しまくっていたツケが無意識に存在しており、今回自信が無くなっているタイミングで、クリスチンさんの存在を思い出し…ウゲロフォファーッ!(吐き気)ってなったんだと思う。」私:「そうか…アンちゃんが『ギルバート×クリスチンさん』の輝かしい未来を具体的に思い描いてる頃、当のギルバート本人は『空虚な!暗黒の日々!』をさ迷ってただけだったけどな。」いずれにせよ、誤解も解け、結婚15年超・40歳を過ぎてもなお読者に「これでもか!」という致死量のラブラブシーンを力の限りで叩きつけて、本作は幕を閉じます。めでたしめでたし。雑多な作品なので、感想も雑多になりましたが、いろいろひっくるめて、「アンちゃんの人生がどこに向かったのか」のアンサーとなる1冊ですし、人気シリーズだからこその1冊だと思います。「赤毛のアン」本編のアンちゃんがギルバートにツンケンしてたイメージだけを持って本作を読むと、結構面食らうような将来像だと思いますが…この激甘の夫婦感と、アンちゃんの超潔癖な奥さん/聖母像こそが、アンちゃんのキャラクター性が一番見て取れるところだと思ってます。ブライス家、尊い!万歳!!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.07.20
コメント(0)
-
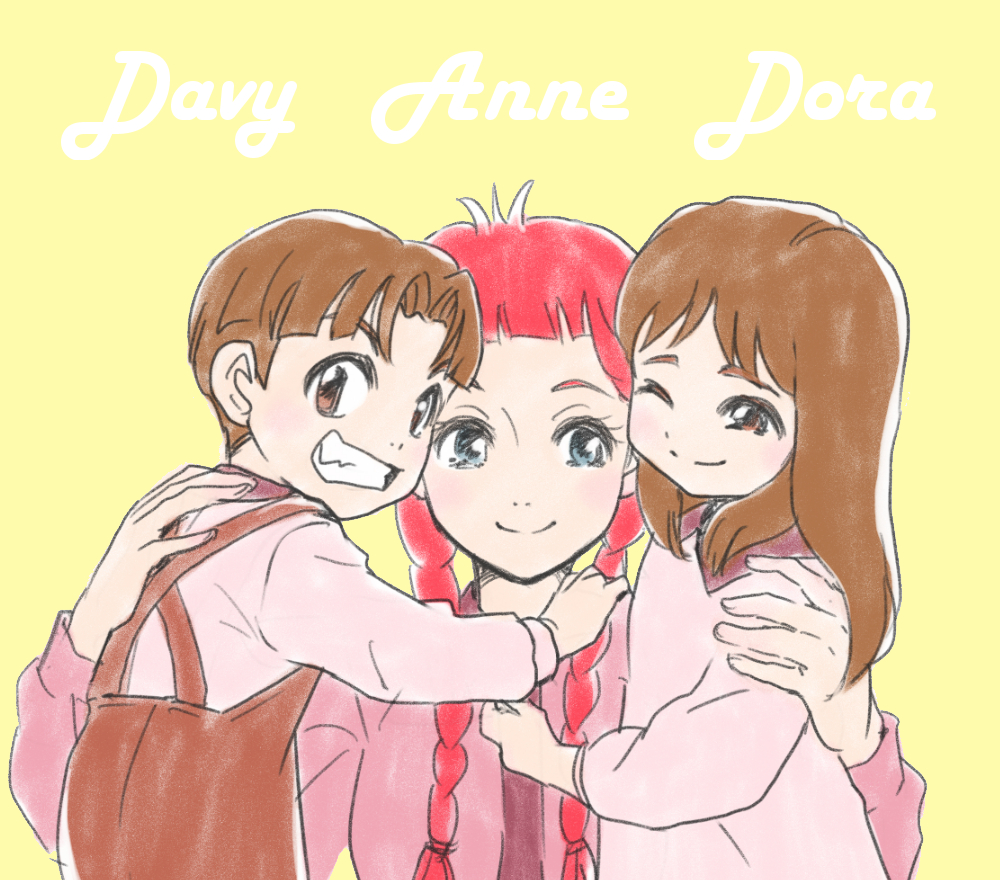
アニメ『アン・シャーリー』第11話・第12話・第13話 感想+アン&デイビー&ドーラ イラスト
アニメ『アン・シャーリー』第11話・第12話・第13話 感想+アン&デイビー&ドーラ イラストシリーズ2作目・「アンの青春」パートに入って3話が経過しました。簡単感想です。※以下、原作シリーズを読んだ上でネタバレ全開で好き勝手語ってます。原作シリーズ未読の方はご注意ください!※原作の感想→「アンの青春」ー赤毛のアン・シリーズ2ー感想 村岡花子訳脚本好きとして、言いたいことはただひとつ!描くべきものの取捨選択が完っっっ璧!!原作全3作を24話のアニメにまとめるとなれば、当然エピソードの取捨選択が必要となります。以前からの感想でも書きたくって来ましたが、とにかく本アニメシリーズは、描写すべきもの…映像として何を優先して作りこむかの選択の判断基準の明確さがずば抜けていると感じます。脚本好きからすると、あまりに気持ちよく鑑賞できます。素晴らしいです!エピソード選定の判断基準に関し、特筆すべきは…下記の点かな、と思っています。・アンちゃんが、自身の人生の軸を何に据えていくのか選んでいくに際し、重要な要素をピックアップして、しっかり映像化している点・毎回ゲストキャラクターを吹っ掛けるつくりに見えて、描いているのはあくまで「アン・シャーリー」であるという確固たる方針「アンの青春」には、絵面的/エピソードとして面白いシーンがたくさんあるんです。冒頭、アンちゃんが誤ってハリソンさんの牛を売ってしまうエピソードや、借りた絵皿を割ってしまって、代替を探そうと奮闘するエピソード等。映像化すれば絶対面白くなる部分ですが、ただシリーズ全体として見た時にアンちゃんの将来像に直接つながるかと言うと、つながる要素ではない。今回のアニメ「アン・シャーリー」においては、短い尺の中でアンシリーズの3作をきちんと筋立てて映像化するために、これらの「筋立てとしては重要度の低い面白味」エピソードは、事実だけをさくっと紹介するにとどめる or説明しないまでも時系列としては原作と齟齬のない形で少しだけ情報として入れ込み、原作を知っていればもっと楽しめる余白の部分として扱っています。反面、アンちゃんとダイアナちゃんが寄付金集めで村内の家を回り、生まれたての赤ちゃんを見て2人が感嘆するシーンや、何より、アンちゃんが幼い双子の面倒を根気強く見るシーン、料理や掃除等の家事/育児に熱心に取り組む姿、お互いを思い合うマリラとの暖かな会話のシーン等、「家庭」ベクトル上にある部分は非常~~に丁寧に、また、ギルバートとのシーンは原作の記載を膨らませた形で描写されています。徹底的です。(過去のアンシリーズの映像化作品には全く精通していないので、あくまで想像ですが…)妹ともよく話すのですが、今回のアニメシリーズはおそらく、モンゴメリさんの作家性が爆発した、渾身の一撃である「アンの愛情」の強烈なクライマックスシーン・『黙示録』の章をきちんと映像化しよう!と本気で取り組んでいる、初めての企画なんじゃないかな、と思っています。『黙示録』の章は、まともな映像化すら前人未到…それくらい強烈&繊細&難解なシーンなんじゃないかな と思っていますし、でもアンシリーズにおいて、アンちゃんの人生軸を決定づける、シリーズ通しての最重要シーンだと思っています。以下、各話の見どころについて、好き勝手語ります。■第11話アヴォンリー小学校新任&村の改善会の活動アンシリーズの世界では、15歳…16歳?から成人扱いなのかな?しっかりお給料を稼ぎつつ、地域社会への貢献にも意識を向けて…皆しっかりしてて偉いですね…!アンちゃんたちが立ち上げた村の改善会は、村内では「求婚クラブ」と揶揄されているようで…いや、同村内の若者たちが意欲的に婚活に取り組む状況とか、何よりの村の活性化だろうが…!ちなみに、ギルバート(会長)の最大の活動目的は「婚活」です。この時の彼にとっては、目指すべき到達点が「アンちゃんと結婚」なんで。ギルバートが不自然にアンちゃんと2人きりになろうとしてて面白かったですね。ラストシーン、アンちゃんがどうやらこの先40年教師をやるつもりだと聞き、唐突に「医者になろうと思うんだ(稼ぐつもりだよアピール)」をし出すギルバートと、やたらと具体的で立派なギルバートの将来ビジョンを聞いて焦ったアンちゃんが、対抗して「私は人生を美しいものにしたいの」とか、具体的に何も考えてないこと丸出しのふわっとした目標(妹談)を口走るところ。イイ雰囲気の会話のようで、お互いの意思が噛み合ってなくて面白いシーンでした。■第12話6歳の双子(デイビー・ドーラ)登場、デイビーのいたずらへの対処マリラの遠縁で、両親を亡くした6歳の双生児(男女)がグリンゲイブルスで暮らし始めます。ドーラ(女の子)は非常に大人しいですが、デイビー(男の子)が度を越えたいたずらを繰り返します。2人とも、とても賢そうな部分を垣間見せつつ、これまで周囲の大人たちにかまってもらえない環境下に居たのかな…と想像させる描かれ方になっていると思います。(父親を早くに亡くし、母親も病気がちだったようなので。)デイビーの表情/演技動作や、いたずらが残酷に映り過ぎないよう配慮を感じるデフォルメになっていて、素晴らしかった!また、双子に対するアンちゃんの接し方…かける言葉や表情、演技動作が輝いてました!逆光気味の部屋の中で、デイビーと向き合い涙を流して思いを語るアンちゃんの姿が非常に印象的でした。アニメーションとして非常に洗練された1話だと感じました。私の脳内では、ギルバートがこの先すぐに来るであろう「恋愛パート」の狼煙を上げる準備をいそいそと進めながら、延々と「女神っ!女神っ!!」って太鼓たたいて喜んでて、すごくうるさかったです。■第13話モーガン夫人訪問、後日談アンちゃんが元々ファンだった有名な女流作家、モーガン夫人。実はクイーン学院の友達(プリシラ)の親戚だったとのことで、グリンゲイブルスを訪問してくれることになります。わくわくとおもてなし準備…料理やおめかしにいそしむアンちゃん&ダイアナちゃん、準備を手伝う双子が可愛らしく、ドタバタが残る回で楽しく鑑賞できました。特筆すべきは後半パートの出だし。アンちゃん&ギルバート&双子で舟遊びをするシーン!原作では、アンちゃんが双子をボートに乗せる話をしている場面でマリラがちらっと「ギルバートの参加」も示唆しているだけでしたが、その部分を思いっきり映像として具現化した形ですね。ギルバート目線で鑑賞しているいち視聴者としましては、「アニオリあざっっっす!素晴らしいですっ!!」に尽きるんですが、それにしても…双子と戯れるギルバートをアンちゃんが優しい眼差しで見つめる描写とか都合が良過ぎて、内心キョドりながら鑑賞しました。…こんなん、すっっっげぇイイ感じじゃん!すぐにでも上手くいきそうじゃん!!これはさ…ギルバートも「行ける!」って勘違いするて!まさかここから、大学時代の…お互いに「殺るか・殺られるか」みたいな、命がけの殺伐とした&傍迷惑なラブ模様を繰り広げるとは思えない2人ですよね最高でした。さてさて、次回はミス・ラベンダーさんの登場のようです。「ここから、ギア切り替えてラブロマンスやります!」って形で出して来るんじゃないかな?と妹と2人で話してます。(…そろそろOP映像の冒頭部分、マシュウの立ち位置をギルバートに譲ってくれませんかね。アップデートを期待してるんですが…そろそろ来ませんかね。)次週も楽しみにしています!by姉・イラストby妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.06.29
コメント(0)
-
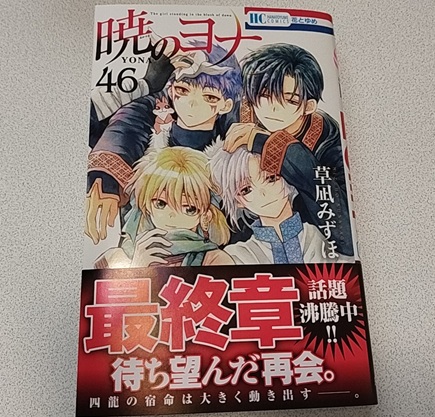
暁のヨナ 46巻感想(姉編)
妹が本誌掲載時に感想を書いていましたが、単行本で改めて読みましたので、簡単に感想です。暁のヨナ 46巻感想(姉編)ここまでの流れをじっくり…42~46巻まで読みました。いやぁ…クライマックスですねぇ…!まだ明言はされていませんが、巻末の次巻・47巻予告が「来春」とかなり遅く、MEMORIALイラスト集付き特装版も発売とのことで、おそらく、花ゆめ本誌では今年中、コミックとしては次巻・47巻(ヨナ巻)での完結を目指して諸々準備を進められているんじゃないかなぁ~…??と感じています。花とゆめ本誌では、既に47巻収録予定分として2話分進んでいますので、多くてあと残り4話か…。四龍の呪いを天に返すことは出来ると思うんですけどね…。あとはもう、どこまでをどういう説明で、いまだふわっとしている部分や、高華国の「この先」を魅せていこうとされているのか…各部族/各キャラクターの行く末ももちろん描く必要があると思いますし…4話…4話か… 全っっっ然、分かりません。ただ、はっきりと「説明」はしていませんが、暁のヨナの目的地は、今巻のラスト・ハク様の「あの一言」だと思っていました。既にたどり着くべき場所にたどりついていますので、本編自体はこのまま一気に〆るつもりなのかな…と想像しています。(本当に47巻中で終わるのなら、の話です。)妹の感想記事でも大騒ぎしていましたが、ハク様の最後の一言について。ヨナ姫の旅の目的は、この一言に尽きると思っていますし、「暁のヨナは、これをハク様に言わせるための物語」と言っても過言ではないと思います。ハク様にとって、この一言にたどり着くのがどれほどハードルの高いことだったか…幼少期より、ハク様本人が絶対に絶対に考えないように、思考回路の奥底に眠らせ切っていたため、ヨナ姫と周囲公認の恋仲状態になっても言おうとしませんでした。なんでかって…「身分違いだから」ではないと思ってます。よくこの↑「俺は従者だし」的な感じでハク様が演出して来ますが、そもそもハク様は、史上最年少将軍/部族長だったエリートなんで。第一話で、イル王が定義している通り、「ヨナ姫の夫となる者は、この国の王となる者」だから…だろうと思います。3巻以降、四龍伝説の話が出て来て、ヨナ姫が緋龍「王」と混同されるのでやたらと彼女自身を「王」職に担ぎ上げようとする風潮がありますが、第一話時点でイル王の提示した「王の定義」は、「ヨナ姫の夫となる者」だったんです。…もしハク様がヨナ姫と結婚したら、スウォン様が立つべき「高華国王職」とバッティングする。本人にその意図がなくても、周囲からは「そう」見える可能性があるじゃないですか。ハク様は、幼少期よりスウォン様と並んで、彼の力になれるように頑張って来て、謀反劇を経てそれが叶わなくなって、国の新体制から外れて一切合切から身を引いて。イル陛下弑逆及びヨナ姫追放について、スウォン様を恨んでる体を装いながら、ハク様が延々とここまでやってきたことは、実は第一話の謀反劇以前と変わってない。「スウォン様と対立図式を作る意図は一切ないことのアピール 及び、可能な限りでスウォン様の描くビジョン実現の手助け」だと思っています。本当は、スウォン様と対立図式を作ったとしても、ハク様がヨナ姫を欲しがる展開が来るのかな?と思って読んでた時期もありましたが、ハク様が徹底的過ぎて…。ことここに至るまで言わないとは思わなかった…。結局、緋龍城が燃え落ち、高華国は闇で覆われ、四龍伝説は終焉を迎えそうな中、スウォン様が王職を辞す意向を明言し、彼の重荷(鎧)を外すのを手伝い、その上、「盃の中」という人知の及ばぬ謎世界に四龍(ぐるぐる)にひっつかまれて、血みどろになりながら連れてこられた状態で、独り天界に行ってしまいそうなヨナ姫に最後のひとこと言えって言われて、それでようやくこの言葉が出てきた…と。ここまで追い詰めないと言わないものなのか、とも思いますが、…まぁ、ハク様にとっては、世界が一度終わらないと言えない、それくらいハードルの高い言葉だったんだな、と受け取っています。独り、天界に去ろうとしているヨナ姫に、ハク様が思わず言った「結婚しますか」。2巻で、風の部族を独り去ろうとしているハク様に、思わずヨナ姫が言った「私にハクをちょうだい」と対になるアンサーシーンとして作ってあったと思います。連載第一話から本誌で追いかけて、2巻第8話「自分で決めた」で巨大感動を覚え、「すごいシーン!長編大作になってほしい!」と思ったところから、15年…16年後に、46巻の巻末として見事なアンサーシーンにたどり着けたことは、しみじみと、万感の思いです…!さてさて…こっからどういう形に収まるんでしょうかね…?「47巻完結(?)」というのも、もちろんただの予想です。ただ、超クライマックスであることは間違いないので、最後まで悔いなく、リアルタイムで長編大作を追いかけることが出来た喜びを噛みしめながら、楽しみたいと思います。by姉
2025.06.23
コメント(2)
-
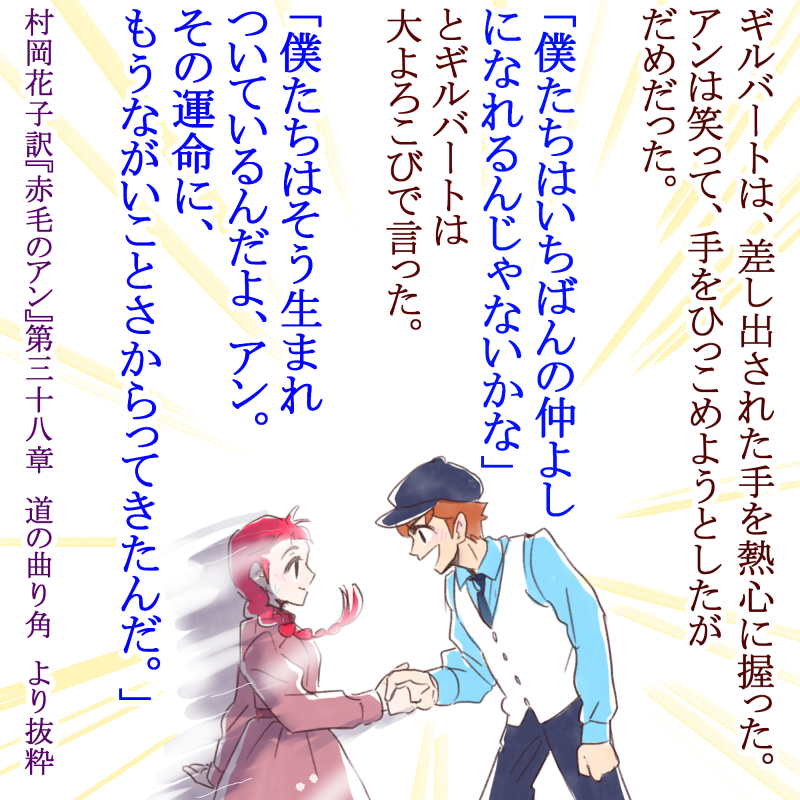
アニメ『アン・シャーリー』第10話 感想+イラスト
アニメ『アン・シャーリー』第10話 感想+イラストシリーズ1作目・「赤毛のアン」パートが堂々の完結。心に響いてくる素晴らしい1話でした!簡単感想です。※以下、原作シリーズを読んだ上で好き勝手語ってます。 今後の展開のネタバレの含みますので、未読の方はご注意ください!※■マシュウ急死アバンパート。ある朝にマシュウが心臓発作で急死してしまいます。急死とは言いますが、発作で倒れるシーン/体調が悪くなってきている描写を重ねて来ていましたので、そのタイミングがここで来た、ということかと思います。7話のラストで、原作にはない「アンちゃんの前で」一度マシュウが倒れるシーンがありましたが、今回初めて「赤毛のアン」を純粋に追いかけている子ども視聴者の目線に配慮して、脚本上で意図的に入れ込んだんだろうな、と受け取っています。アンちゃんに感情移入して鑑賞していた子どもには、すごくショックでトラウマになってしまってもおかしくない展開だと思います。アンちゃんは16歳になってますが、第1話のアンちゃんと同い年(11歳)で見始めた視聴者は、まだ11歳なので。ダイアナちゃんのアンちゃんへの心づかい、突然のことなのに、畑を借りて管理することを申し出てくれるバーリーさん、マリラ&アンちゃんを気遣い、足繁く顔を出すリンド夫人…大人目線では、ご近所さんたち各々が精一杯手を貸そうとしてくれる描写が心に残りました。■大学進学の断念、マリラとともに過ごす道の選択マシュウの死により気落ちしたマリラに、さらに視力悪化&失明の可能性が判明。アンちゃんは奨学金を辞退・大学へは行かず、教師として働きながらマリラの傍に留まる選択をします。この話筋だと、普通はアンちゃんが可哀想に見えると思うんです。せっかく、島で1人しか獲得できない希少な奨学金を獲得したのに、自分を犠牲にして、家に留まらなければならないなんて…勿体ない!と。ただ、このシーンは全然悲劇ではないし、可哀想には見えない。アンちゃんがこの場面で、「家族を何より一番に大事にすること」を選べていることが非常に幸せなシーンだと受け取っています。アンシリーズを読んでいて、今回のシーンのように、筋道だけでは「悲劇」なのに、むしろ主人公たちが幸せに見えるシーンというのは、他にもたくさん思い当たります。もちろん、主役や周囲の人々がそれを望んでいたわけではないのですが、アンちゃんが「曲がり角」と表現した通り、誰の意志や悪意でもなく、時の変遷とともに、どうしても思い通りにならない事態は起こります。その時に選択肢がある…自分で納得して、いちばん大事にしたいものを選べることは、とても幸せなことだと思います。「選択肢」ってなんだろうな?と思うと、私はやはり、意識の中で、周囲の人々/物事への認識の広さ/深さ、何よりリスペクトが重要だと思っていて、ひとつの事象をどれだけ多面的に捉えることができるか、だと思っています。今回のシーンだと、アンちゃんの意識の中でギルバートの存在は非常に大きくて、彼がアヴォンリーに留まり、教員として働きながら進学資金を貯める道を示してくれてるからこそ、負の感情を持つことなく、この選択が出来ているのだと思います。エイブリー奨学金は英文学にくくった選定だったため、アンちゃんが獲得しましたが、クイーン学院で総合一位の成績(金メダル)を修めたのは、ギルバートです。クイーン学院からは、他にも大学進学する子たちが居たと思いますが、「一番進学すべき」ギルバートは、金銭面の事情で今すぐの進学は諦めました。彼の行動を、アンちゃんがとてもリスペクトをもって捉えてる。基本的にアンちゃんは、ギルバートのやることを絶対的に信頼していて、常に自身の行動のお手本にしているので、この局面で「納得して」一旦大学進学を諦める道を選べたんだな、と思います。ギルバートの行く道は、「家族都合の犠牲になり、大学進学を完全に諦める」道では決してなく、「自力で資金を貯めて、大学へ進学する」道なので。■ギルバートとの和解(&ギルバート像について)アンちゃんが学校で働くつもりだという話を聞き、既に決まっていたアヴォンリー小学校の教職枠(近い)を辞退し、アンちゃんに譲るギルバート。いや…もちろん、アンちゃん&マリラのことを思いやっての優しい行動で、なかなかできることではないですし、アンちゃんにも非常に感謝されて、周囲のおばさま方(マリラ・リンド夫人)の信頼もがっちり掴むことになります。ただ、なんだろう…ギルバートが誰にでも優しい聖人みたいな人間かというと違うと思っていて。ギルバートにとって、アンちゃんは心底「女神」に見えてると思っています。彼女の、勉学で上を目指す気高さと、家族に対する愛情深さが、彼にとっては神秘的というか。島で一人しか取れない奨学金を獲得して、とてつもなく高貴な存在となったのに、マシュウが亡くなり、進んでマリラを独りにしない選択をする愛情深いアンちゃん…とか、女神があまりにも見事に女神過ぎて、尊さが天元突破し、スタオベ&感涙しながら「投げ銭した」…みたいなイメージで受け取ってます。資金面での支援をしろと言われても、大して力にはなれなかったと思うんですが、…幸運にも、その時自分が手に持っていたんですよ!女神を今いちばん輝かせることが出来るであろう、女神にとっての最強カードを!アンちゃんに「譲った」というのもおこがましい…「ギルバートは、『女神が使ってくれるなら!』と喜んで奉納した。」感じですかね。もちろん、ギルバートとしては何か見返りを期待した行動ではなかったと思うんですが、女神(&周囲の人々)がめっちゃ喜んでくれて、女神から過去の過ちを流す免罪符を賜り、その上、これから「仲良くできる」…と未来に一気に灯がともり、家に帰りつくころには、一本筋の未来のビジョン(結婚)まで見えてたと思います。和解シーンで、いきなり運命について語り出すギルバートのセリフについて。妹は「あまりに突拍子もなくて、『何言ってんだコイツ』ってなるから、今回のアニメでは変えてくるんじゃない?」と言っていましたが、私は「ギルバートのやばいところは、このセリフを冷静に事実として述べているところ。本気だから。大げさに言ってるわけでもなんでもなく、本気で運命があると思って言ってるから。奴をなめない方がいい。ここは、彼のキャラクター性として残してほしい!」と思ってました。アニメでは、すごく爽やかなイイ感じで、上記のセリフをすらすらと述べていましたね。夕日を映す水面がまぶしく輝いて…まるで世界に祝福されているようでした。(脳内BGM:歓喜の歌 byベートーベン)いやぁ~…アン・シャーリー10話、超良かったです!それにしても…自分でも、なんでこんなに(こじらせた)ギルバート目線でこの物語を鑑賞しているのか、よく分かりません。妹曰く、「ギルバートとかよく分からねぇよ!積み上げてきたエピソードと、奴のテンションが合致してないの。アンちゃん目線で思い返すと、黒板でなぐりつけるわ、謝って来てるのにさんざん無視するわ、(ギルバートの)優秀さを勝手に敵視するわ、命を助けられても仲直りを突っぱねるわ…つくづくひどい唐辛子対応の歴史しかないのに、なんでギルバートがあんなにアンちゃんLOVEなのか、全然分からないの!」…私は、全然普通にギルバートについていける。アンちゃんは、女神だから…!話すことができない時期も、アンちゃんの行動言動を傍目に見ながら「女神…!」って勝手にもだえてたから。たぶん、黒板で殴られたときに打ちどころが悪かったのと、下のアングルからアンちゃんを見上げる形になったときに目線が定まって、そこから許しを請う姿勢で5年間ずっとアンちゃんを見てたから、彼の中では采配を司る「女神」としか言えない存在になっているのだと受け取っています。さてさて、11話からいよいよジャパニメーション未開の地「アンの青春」パートですね。どんな映像になるのか、わくわくです。そして双子の登場を心待ちにしています。by姉(イラストby妹)アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.06.12
コメント(0)
-
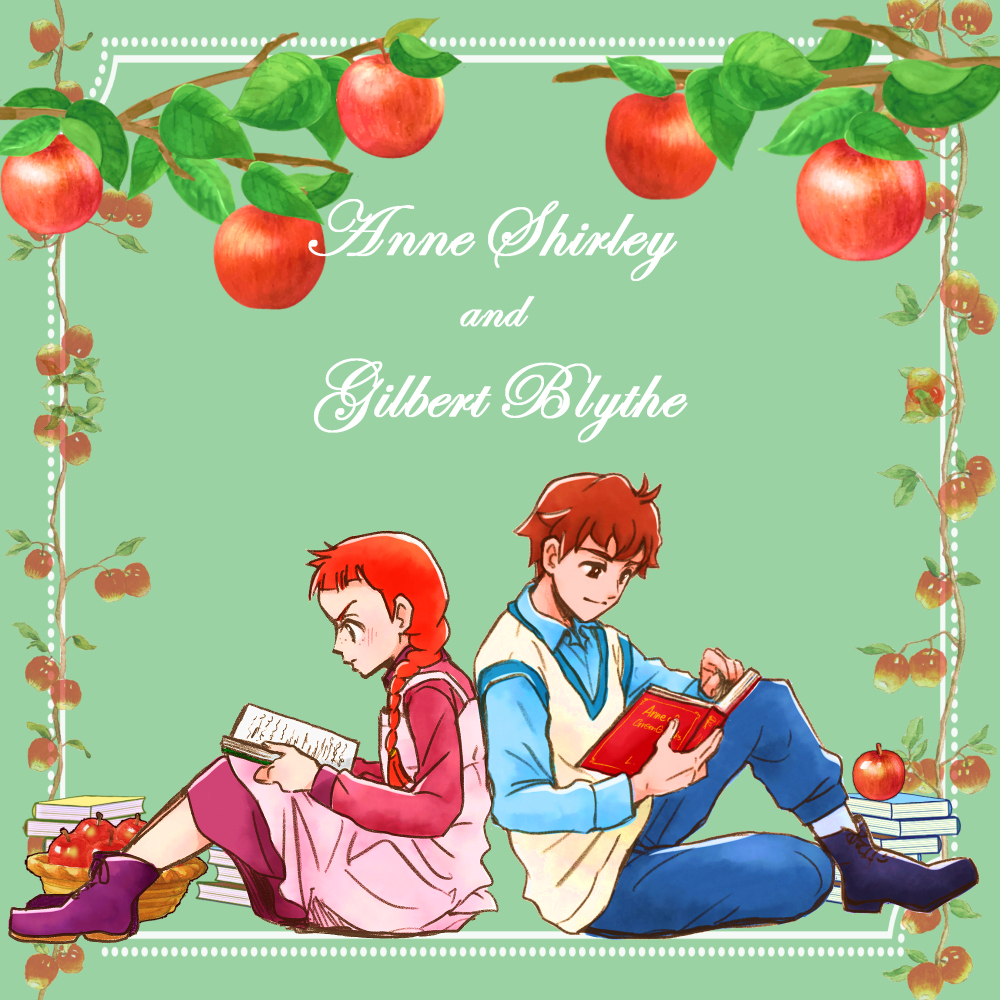
アニメ『アン・シャーリー』第7話・第8話・第9話 感想+アン&ギルバートイラスト
アニメ『アン・シャーリー』第7話・第8話・第9話 感想+アン&ギルバートイラストNHK Eテレアニメ『アン・シャーリー』、毎週(家族で)楽しみに鑑賞しています!各話、語りたい部分に特化した簡単感想!※以下、原作シリーズを読んだ上で好き勝手語ってます。 今後の展開のネタバレの含みますので、未読の方はご注意ください!※第7話前半:エレーン姫(小舟水没エピ)、後半:クィーン学院進学に向けて…アニメーション的に、非常に力の入った1話でした。…特に、前半・エレーン姫のアンちゃん&ギルバートの2人のシーン!もともと原作においても、「赤毛のアン」パートではこの小舟エピ&ラストの仲直りシーンしか、主役カップルがまともに話す絡みのシーンが存在しないという貴重なシーンの1つですし、絵面的にも非常に面白いシーンなので、力を入れてくれるんじゃないかな!とワクワクしていましたが… 期待を遥かに上回る渾身のアニメーションで、度肝を抜かれました。特に、橋の杭にアンちゃんがしがみつくところから、おそらくOP作画を担当されているような、作画界のスーパースターたちが投入されて、OP映像並みの渾身さで制作されているのではないかと思います。ギルバートが手助けしながら、アンちゃんが杭から船に降りるシーン、その後、船上で向き合って会話するシーンの、ぬるっっぬる動く超細かな演技動作!アンちゃんが気まずくて手をもじもじさせてるところに目をやって、多分「指きれいだな~」とかギルバートが見入ってて、アンちゃんが、ギルバートが自分の汚れた服を見てるのかと思って(杭につかまった時に汚れた)持ってたストールでバッと体を隠しながら、ちらちらとギルバートの方に目をやって、「それで、申し訳ないですけど…(船着場まで連れて行って欲しい)」と言うシーン。ギルバート目線で、アンちゃんがスーパー可愛らしく女の子らしーく描写されていました。そこから、船着場まで小舟を漕いでいくシーン。アンちゃんからのアングルで、ギルバートがすごく頼りになる、かっこいい感じで描写されている…のに、アンちゃんは右に向いて「見てないよっっっ!」って態度でアピールしてるんですが、…でも、絶対に左目じりの端でものすっごいギルバートの方見てる!全神経をそこに集中させてる!というのが分かる表情になっていました。こ・れ・で・す・よ!!視聴者として期待していたのは!この「『見てないよ!アピール』しながら、めっちゃ見てる」描写、『アンの愛情』パートでめちゃくちゃ活きるはず…!というか、本アニメーション作品、基本的にそれがやりたくて作ってる…『愛情』パートの映像化をそもそもの念頭に置いて、「言葉で説明しないけど、『主観(映像)』で魅せていく」形で第1話からずっと作ってあると思っていますので。このアニメは…絶対に外さない…!注力してほしいところをここまで見事に盛って描写してくれる…こんなに鑑賞していて心洗われるアニメーション作品にはめったに出逢えないな、と思います。幸せ♪船着き場で、「友達になろう」と伝えるギルバートのセリフがまっすぐ響いて来まして、「声優様のキャスティング、ブラボー!」と思いました。ギルバートはどこまでも真っ当にド直球で来るので、アンちゃんがかわしきれなくて、全力拒絶&逃亡しなくちゃいけなくなる。怖いですよコイツは。でも最終的に絶対に正しいから…アンちゃんは結局勝てないんだよね…(by妹)第8話前半:クイーン学院受験、後半:ホワイトサンドホテルのコンサート(朗読披露)一気にグッと背の伸びるアンちゃん&同級生たち!島中の優秀な学生たちが集い、行われるクイーン学院の受験。新聞で合格者が発表され、アンちゃん&ギルバートが1位タイで掲載されるのも、印象深いシーンですね。私がどうしてもギルバート目線で本シリーズを読んでしまうので、「ギルバート的には、アンちゃんのアウトオブ眼中にならないように必死。一度でもアンちゃんががっかりするような成績を取ろうものなら、その瞬間に、アンちゃんの意識の中で「その他大勢のモブ(男子)たち」と同化してしまう。そうならないように必死に自分も勉強してるんだけど、アンちゃんがマジで頭良過ぎて、島でいちばんの成績レベルで、ようやくアンちゃんと同水準である。常に「女神(=アンちゃん、頭が良過ぎて)、マジキッツい…!」と思いながら必死で勉強してる」と感想をこぼしたら、「この作品は常にアンちゃん目線で描写されていて、特に赤毛のアンパートでは、ギルバート目線なんてどこにもはっきり描かれてない。アンちゃんから見たら、ギルバートはどんなに頑張っても勝つことが出来ない、常に飄々と自分の上を行くスーパーマンだが?」と妹に言われました。えっ…描いてない?? だってそういうシーンでしょ…あれ??クイーン学院編ってギルバート目線で読むもんじゃないの?…あれっっ?(↑自分の偏った読み方を自覚する瞬間)後半のホテルのコンサートシーンは、小学校のクリスマスコンサートとも被る絵面なので、省略するのかな~と思っていましたが、しっかり描写されました。アンコールで「風がわりな、こっけいな」詩(カエルの鳴き声?)を堂々と演じるアンちゃんが、大物感あふれていて素敵でした。ドレスアップして、文化人たちの中でも一際輝くアンちゃんの姿を見ることが出来て…わざわざ遠出して、駆けつけた甲斐がありました。(←やっぱりギルバート目線)第9話全体通して:クイーン学院への入学~卒業、マシュウの「12人の男の子より…」「赤毛のアン」パートもいよいよクライマックス…!全10話構成のようですね。クイーン学院に入り、ホームシックと戦いつつ奨学金の獲得に燃えるアンちゃん。今回のいちばんの見どころ!アニメオリジナルシーンが最高でした!アヴォンリーでのクリスマス休暇を終え、雪の中シャーロットタウン行きの電車に乗れるよう、駅までマシュウがアンちゃんを送ってくれました。一旦は駅前でアンちゃんを降ろしてマシュウは帰ろうとするのですが、やっぱりアンちゃんが寂しそうにしていたのが気になって引き返して…そしたら、駅にギルバートが居まして。寂しくて泣いてるところを見られたのが気まずいアンちゃんに、ギルバートが「独りごと」のように話しかけ…アンちゃんと良いライバル関係を確認するような短い会話をするシーン。…クィーン学院卒業前に会話出来たよ⁉良かったねギルバート‼※原作だと、本当に『赤毛のアン』ラストシーンまで口をきかない↑ギルバートとアンちゃんの細かな表情の変化、しぐさも最高でしたが、これほど思い切った2人のオリジナルシーンは、「マシュウに見せるため」に入れ込まれたんだな、とよく分かって、繊細なところを、よくよく考えて詰めようとしてるんだなぁ~!と感じました。ギルバートほど、アンちゃんの人生にとって重要な存在は居ないわけですが、マシュウは存命時、ギルバート本人とはほぼ絡みはなく、なんなら「アンちゃんにとって負かすべき強敵(ライバル)」という認知のままでした。それが今回、ちゃんとマシュウの「2人はライバル」という原作で描かれている認知は変えないまま、「アンちゃんが独りで寂しがってるかも」と思って引き返したら、ギルバートが居て、2人がすごく信頼し合ってる&お互いを高め合う良いライバル関係なことが分かって、自分の出る幕はなかったな…と、ある意味で「ギルバートにアンちゃんを任せる」形で安心して身を引いて…というオリジナルシーンとして、「優しい感情」且つ「概念的に完璧な形」に補完されていました。なんて優しいっっっ…なんて繊細なところを詰めてくれるんだ!と思いましたし、また第1話の、アンちゃんが駅で1人マシュウを待っていた絵面と今回の、駅で同じ電車を2人で待つ絵面が対比になるようにも作ってあり、見事なオリジナルシーン過ぎて、超感動しました。・・・素晴らしいっっっ!マシュウの名台詞は、「12人の男の子より~」より「わしの自慢の娘」のフレーズが強調されている気がしました。村岡花子さん版の原作に忠実ですね!本作ではクライマックスではなく「物語の通過点」となる場面ですが、松本保典さんのどっしりとした言葉が涙腺にきました…!(by妹)次回はいよいよ…!なシーンがたくさんの回ですね。まぁ、ギルバート的には「いよいよ物語が始まる瞬間を迎える」というか。…こっからですから、こっから。ようやくまともに、アンちゃんと話をして、笑い合うことができるようになるところですから。楽しみに待ってます!(←やっぱりギルバート目線)by姉(イラスト&一部解釈 by妹)アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.06.02
コメント(0)
-

「アンの夢の家」ー赤毛のアン・シリーズ6ー感想 村岡花子訳
「アンの夢の家」ー赤毛のアン・シリーズ6ー感想(L・M・モンゴメリ・1917年、和訳 村岡花子・1958年)原題は「Anne's House of Dreams」。アンちゃん25歳・結婚式~新たな土地での新婚生活、出産等が描かれます。大学の医科を卒業し医師となったギルバート。アンちゃんは3年間務めた校長職を辞して、2人はグリンゲイブルスで結婚式を挙げる。プリンスエドワード島内、アヴォンリーから60マイル離れたフォア・ウィンズ港の小さな「夢の家」での新婚生活(超ラブラブ)をスタートした2人は、さまざまな事情を抱えた個性豊かな隣人たちと出逢い…シリーズの時系列的には、大学時代を描いた「愛情」と本作「夢の家」の間に、婚約時代を描いた「アンの幸福」があります。(アンちゃんの校長職としての日々が、ギルバートへ向けた手紙形式で綴られた作品)ただ「幸福」は1930年代に入り追加で書かれた作品なのだそうで、実際の執筆順序は、「アンの愛情」の次が本作「アンの夢の家」とのこと。非常に独特な感性で執筆された…モンゴメリさんの天才性がよく見て取れる1冊だと感じました。とても興味深く、面白かったです!*以下、いち読者のただの想像(本作構築の際の考え方等について)です。*■アンちゃん&ギルバート軸・結婚式/新婚生活~出産本作執筆のとっかかりとして、やはり一番大きかったのは、読者の熱烈な要望だろうと思います。「アンちゃんとギルバートの結婚式が見たい!新婚生活が見たい!」…etc。本シリーズは、流石さすがの「少女漫画の原点」というか、他のどの魅力を差し置いても語るべきは、主役カップルの吸引力…平たく言うと「カップル萌えパワー!of元祖中の元祖」の凄まじさだと思っています。そしてモンゴメリさんとしても、アンちゃんの人生を描く物語シリーズとして、「妊娠・出産」というステージは形にすべきと考えられたのかな、と受け取っています。前作「愛情」でアンちゃんが結婚に向けた決心…ギルバートの為に生きていく決心を固めることができているので、そこからの流れとしては妥当な、まっすぐに向かうべき(と考えるだろう)ステージだと思うのですが、ただアンちゃんにとって「出産」は非常にセンシティブなアクションだと思います。もちろんアンちゃんのみならず、「出産」はほかの女性にとっても重大且つセンシティブなアクションであることは疑いようのないことですが、アンちゃんにとっては、周囲の人々も含め「特に」気をつかうべき事項だな、と。アンちゃんは若いながら育児経験豊富で、小学校での教職/校長職経験も積んでいて、教育面ではいわゆるプロ(しかもトップエリート)です。本人も子どもが大好きで、絶対にどんな子だって愛し可愛がれる自信があると思いますので、「育児」自体への不安感はない…むしろ得意分野!だと思います。ただ「自身の出産」となると、どうしても「両親の顛末」が思考回路に存在する…産後3カ月で熱病で母親が亡くなり、その4日後に父親が亡くなり…はっきりとは書かれていませんが、まぁ…想像するだに、産後まだ体力の戻っていない段階で、母親が感染症で重症化してしまい、父親も必死に看病してたけど、道連れのような形で2人とも亡くなってしまい…という、言いようによっては「出産起因の悲劇」とも言いうる流れだったんじゃないかな…と。(1作目「赤毛のアン」で、アンちゃんが物語クラブの章で書いていた小説(ラブストーリー)も、川に落ちたジェラルダイン(ヒロイン)を恋人のバートラムが助けに行って、結局2人で亡くなってしまう、という話筋でしたので…。)アンちゃんの立場としては、自身の意に反して「産んだ子どもを育てられない/責任が取れない」状況に陥ってしまう、ギルバートも巻き込んで不幸にしてしまうリスクがある…その恐怖心は確実にあると思ってます。そもそも「愛情」でなぜアンちゃんがあそこまで結婚とギルバートから逃げ回っていたかと言えば、深層心理の根本のところにあったのが、この「出産」への恐怖心・トラウマだと思いますので…。「愛情」のラスト、ギルバートの2度目のプロポーズのこの↓言い回しが印象的だったのですが…「僕はある家庭を夢みているのです。炉には火が燃え、猫や犬がおり、友だちの足音が聞こえ ―そして、君のいる」普通だったら「子供たちの足音が聞こえ…」になりそうな所ですが、ここで「子ども」に言及しないギルバートの賢明さというか…あぁ…ギルバートはやっぱり、アンちゃんの深層のところにあるこの部分への不安感をちゃんと掴んでるんだな、と思って読みました。最初の話に戻りますが、やっぱりアンちゃんにとって「出産」は非常に勇気の要る重要なステージですし、モンゴメリさんご自身が3度の出産(うち1回は流産だったのかな?)を経験された上で、アンちゃんの物語としても「結婚~出産」を軸にした1冊として執筆を構想するに至ったのかな、と想像しています。■強烈なゲストキャラクターの投入、海洋モチーフ本作を読んでまず感じるのが、「なんかゲストキャラたちが強過ぎるくらい強いな」という印象。主には、劇的な航海経験を積んできた老年の灯台守・ジム船長と、とんでも悲劇を背負って生きる美女・レスリーの2人。本作を読み切って、ひたすらドラマチックに描かれていたのは、主役カップル軸よりも、このゲスト2人の物語筋の方です。(もう1人・ミスコーネリアさんは、おそらくリンド夫人的な役割というか、頼んでもないのに様々な情報を提供してくれる「噂好きの女性」かな。)最初、この作品はなんでこんなバランスで描かれてるのかな?と不思議に思いました。…ゲストキャラの存在感が大き過ぎて、1冊としてバランスが悪く見えるんですよ。ただ、アンシリーズ全体を読み進める中で、…あぁ、これはもう…「主人公を演るよりも、出産に集中させて欲しい」というアンちゃんの意向を汲んだ上での構成なんだな、と思い至りました。エンタメ作品ですので、1冊の読み物としての満足感は絶対に必要です。ただ本作に関しては、アンちゃんは作中のほとんどが妊娠期間となりますし、ギルバートは駆け出しの医師として、知り合いのほぼ居ない中、地域の方たちの信頼を勝ち得て、地盤を固めていかなければならない大事な時期です。1・2作目のように、主役たちのドタバタ(失敗)エピソードで話を回す形式は取れない。そこで投入されたのが、このゲストキャラ2人なのだろうな、と思いました。・ジム船長アンちゃんがあまり身体を動かすことのない形をとったうえで、わくわくする昔話を語ることができるジム船長。ブライス夫妻の新居「夢の家」の歴史にくわしく、特に最初の住人だった「若い教師夫婦」の面影をブライス夫妻に投影し、懐かしがる/慈しむ目線も持っています。ジム船長の海洋談は、新聞記者オーエン・フォードが「ジム船長の生活手帳」として小説に起こし、出版されベストセラーとなりました。これも全部想像ですが、初期の構想段階では、この「小説に起こす役割をアンちゃんが担う」案もあったんじゃないかな、と思います。ただこれも、アンちゃんとモンゴメリさんのディスカッションの上で、「妊娠中に、万が一にでも身体に障るようなことはすべきでない」「このタイミングで小説執筆(しかも海洋冒険譚のような大作)に気持ちは向かわない」という結論に至ったのかな、と。・レスリー本作のヒロイン的な立ち位置だと思います。非常に聡明な美女なのですが、家の借金のために若くして結婚し、その旦那もすぐに酔っぱらいの喧嘩(?)の後遺症で赤ん坊のような状態になり、これまでの十数年間、そしてこれからも旦那の面倒を見ることに人生を費やしていかなければならない女性。本作では、薄倖なレスリーさんの人生が大転換する物語、そしてラブストーリーが劇的に描かれています。キャラクター設定の考え方としては、基本的には「近所で暮らし始めた、展望の明るい若い医師夫婦」に対し、誰よりも「羨望」…隠さず言えば「嫉妬」の眼差しを抱く存在であり、またギルバートの医師としての手腕を見せていける要素も入れ込んで、作ってあるのかな、と受け取っています。・海洋イメージ、幻想性アヴォンリーはどちらかと言えば畑や森…牧歌的な印象が強かったのですが、本作の舞台・フォア・ウィンズは「港」であり、新居・夢の家も海に面していますので、非常に「海」の印象が強く描写されています。読者としても、新しい土地に行ったんだな、という印象を強く受けますし、それを一番に形作っているのが、灯台守でもあり海の大冒険を語るジム船長なのだと思います。また、レスリーもよく海岸に居るシーンが描写されています。モンゴメリさんの短編(アンの友達/アンをめぐる人々)を読む限り、基本的にモンゴメリさんにとって、海というモチーフが、幻想的なイメージとして使われることが多いと感じます。「目の前に広がる、人知を超えた世界」…というか。本作「夢の家」の印象も、アヴォンリー時代よりも「足元がしっかりしていない」「ゆらゆらしている」印象を受けます。(主役たちが、新しい土地で地盤を作っていくところの話ですしね)主要ゲストキャラ2人も、かなりとんでいる、浮世離れした「劇的なキャラクター」として描かれていますので。この幻想的なイメージは、アンシリーズでは本作が一番強いのかな…と感じます。ただ、モンゴメリさんの他作品ではおそらく珍しいものではなく、むしろどっちかと言うと、こういった幻想的なストーリーの方がモンゴメリさんが素で書く物語の基本形なんじゃないかな…と感じています。※ちなみに、「愛情」までに登場する土地は、実在する土地をモチーフにしていますが、このフォア・ウィンズ港にあたる土地はプリンスエドワード島内には存在しないそうです。(島以外にモデルはあるのだと思いますが)そういった観点からも本作の持つ「夢モチーフ/幻想性」も納得がいくなと感じています。「アンの夢の家」は、上記のような形で、読者が見たいもの(主役カップルのラブラブシーン)をめっっちゃ描写しつつ、アンちゃんの妊娠・出産ステージを、アンちゃんがそこに最大限注力できるように、強いゲストキャラクターを複数投入した形なら、読みごたえも担保してきちんと書き切れるね、という アンちゃんとモンゴメリさんのディスカッションを経た合意点でもって、書かれた1冊なんだろうな、と受け取っています。■アンちゃん&ギルバート軸についてーその2上記の通り、本作の読み応え/絵面の面白さとしては、ゲストキャラクターの投入により担保してると思う、と書いてきましたが、ただやっぱり読者としていちばん重く受け止めるべきは、主役カップルの軸の方だと思っています。アンちゃん自身もものすごい覚悟を持って、周囲の人々も尽くせる手はすべて尽くしたうえで迎えた第1子の出産でしたが、ひょっとしたら少し早産だったのかな…?(9月に結婚して、翌6月初旬に出産を迎えていますので…)大変な難産で、母体も危険視されるような状況の中で産んだ長女は、丸1日生きることなく亡くなってしまうという、非常に残念な形となってしまいます。妊娠期間中は、アンちゃん自身&周囲の人々も極力母体への負担がないように動いてるんです。クリスマスには、ブライス夫妻はアヴォンリーへは帰らず、グリンゲイブルスの4名(マリラ/リンド夫人/双子)が夢の家へ訪問して来てますし、出産が近くなると、2人暮らしの小さな家にわざわざ女中さん(スーザン)を何週間も前から雇い入れて、アンちゃんの家事/心的負担軽減や、ギルバート不在時の万が一に備えた体制を取っていました。ここまでやった上で、上記のような結果でしたので、読者としてもアンちゃん…これはショックだろうな、もっと怖くなるだろうな…大丈夫かな…?とすごく心配しながら読み進めますが、ただ想像よりずっとずっと、この場面でのアンちゃんが「強い」んです。もちろんお子さんを亡くした直後はショックも大きく、嘆き悲しむ場面もありますが、その後すぐに第2子出産に気持ちを向けて、1年後には長男・ジェムくんを産むことができてますので。このアンちゃんの「強さ」こそ、本作の一番の見どころだと感じました。周囲の人々の温かさや、レスリーが曝け出してくれた強烈な「羨ましい」という感情も全部有り難く丁重に受け取った上で、やっぱりこれは根本的に「ギルバートの為」だからこその強さだな、と受け取っています。「夢の家」で描かれる結婚~新婚生活は、ギルバートにとっても正念場なんです。アンちゃんを幸せにしたい一心でここまでやって来て、念願叶ってこうして結婚することが出来て、医師としての地盤をしっかり作っていかなくては…!と必死に働く傍ら、ずーっと「アンちゃんを幸せにできてるかな…?」って心配して見てるんです。自分が望んで望んでアンちゃんにお嫁に来てもらって、自分はすごく幸せなんですが、やっぱり有能なアンちゃんには、他にも様々な人生の選択肢がありましたので。女性ながら二十代前半で校長という重職を任され、責任持ってこなすことができる、島の教育界にとっても唯一無二の超貴重人材でしたし、ロイ・ガートナーと結婚していれば、上流階級の社交界で活躍できていたでしょうし(アンちゃん的には、教職の道はさておき、「ロイとの未来」など想像したこともなく、選択肢になかったが?という意識だと思いますが…)。それらの様々な栄えある選択肢を捨てて、島の片田舎の、人里離れたぽつんと一軒家に来てもらって、機知に富んだ隣人たちに恵まれたことは幸いでしたが、基本的には、日中はアンちゃんは家で独り過ごしていますので。そうした中で第1子が亡くなり、嘆き悲しむアンちゃんの姿を見てしまうと、この道を選ばせて、アンちゃんを不幸にしてしまったかな…と不安も大きくなったと思います。アンちゃんが、これ↑(ギルバートの不安)を掴んでる。アンちゃんだって、ギルバートを幸せにしたくてこの道を選んで来てるんです。「やっぱり怖い」とか「ショック」とか言ってらんない。何があっても、「絶対にギルバートの子どもを産むんだ!」と覚悟を決め込んでまっすぐ動くアンちゃんを目の当たりにすると、やっぱり彼女にとって、前作「アンの愛情」の『黙示録』の章のインパクトがどれほど大きなものだったのかを改めて思い知らされます。アンちゃんにとって、あれより怖いものは無いので。本作「夢の家」で描かれている「アンちゃんの強さ」は、「アンの愛情(の『黙示録』の章)」における、アンちゃん自身が「死にたい」と思い至るほどの強烈な後悔…それに対するアンサーだな、と思います。言い換えると、『黙示録』以降のアンちゃんは、本当に日々、ギルバート(&子どもたち)に全身全霊を捧げて生きていて、たとえいつ不慮のタイミングで死を迎えたとしても、「精一杯愛に生きた、悔いはない!」と言い切れる人生を遂行しているんだな、と感じています。アンちゃんが勇気をもってもう一度出産に臨み、待望の長男・ジェムくんが誕生しました。「可愛い!可愛い!幸せっっっ!」と大喜びするアンちゃんを見て、ギルバートもようやく「…間違ってなかった、これでよかった」と安心できたんだろうな、と受け取っています。■終幕~それから本作のラスト、レスリー&ミスコーネリアさんは結婚という形で、ジム船長は現世からの船出を迎え、遠い過去に海で亡くなった恋人マーガレットのもとへ…ゲストキャラクターたちはそれぞれに「好きな人」のもとへ向かいます。ブライス夫妻も「夢の家」から、新しい子育て用の大きな屋敷・炉辺荘(イングルサイド)へ…「夢の家」は借家でしたが、炉辺荘は購入するとのことで。ギルバートが大きく出ましたね…医師業が順調にすべり出しているとはいえ、たった2年で、広大な庭付のお屋敷をキャッシュ一括購入できるような蓄財は絶対ないだろうに…(お屋敷の相場感とかよく分かんないけど…)まぁ、何でもできる!いくらでも稼いでみせる!!という、無敵の心持ちなんでしょう。ギルバートが完全に調子に乗っていて、喜ばしい限りです。本作のラストでは、お子さんを無事に産んで、産後3~4カ月経過したところで、ブライス夫妻は、アンちゃんの両親がたどり着くことのなかった「子育て」ステージに進むことが出来ました。本作「夢の家」までで、アンちゃんを主人公とした物語シリーズについて、一旦「やるべきことはすべてやり切った」と言えるな、と感じます。…ただ。本作のラストまで見事に描き切った上で、モンゴメリさんの中に強く渦巻く感情…懸念…不安…があったのかなと。「これだけの両親(&周囲の人々)の思いを受けて生まれてきた、そしてこの先も本当に大事に育てられるであろう、待望の長男・ジェムくん、戦争に行くことになっちゃうんだぜ…!!?」本作「夢の家」の発売された1917年は、既に第一次世界大戦真っ只中です。「アンの娘リラ」でウォルターくんが亡くなるソンムの戦いが1916年の出来事ですので。本作が、実在する土地ではない場所で、少し幻想的なモチーフを入れ込みつつ、浮世離れした登場人物たちを据えて描かれたのも、執筆時のモンゴメリさんの心持ちとして、アンシリーズの大事な主役たちを「戦争が起こる」現実世界から遠ざけてあげたい気持ちもあってのことだったのかもな…と受け取っています。ただ、長期化する戦争、日々増え続ける犠牲を目の当たりにする中で、カナダを舞台にした作品として、戦争を無視することは出来なくなったんだろうな、と感じました。(本作「夢の家」終盤でも選挙の話が登場し、ブライス夫妻の支持する保守党が政権から落ちて…というエピソードも描かれ始めます。)この部分…モンゴメリさん自身が生活の中で感じる大きな不安感をとっかかりにして、アンちゃんの子どもたち世代を主役に据えた物語の構想が始まり、「アンの娘リラ」の執筆に向かっていったんだろうな、と感じました。「アンの夢の家」…もっとあっさり感想書けると思っていましたが、書き始めると想像よりずっと長文になってしまいました。本作を最初ざっと読んだ際は、ゲストキャラの筋が強く、散漫とした印象を受けて、どう捉えていいか若干戸惑いましたが、「なんでこの書き方になってるのかな?」と考えたときに、主役主体(ブライス夫妻)の意志を一番に尊重し、様々な配慮を行ったうえで、ゲストキャラを投入し、いち作品として読み応えのある形にしっかりまとめ上げているんだな、と思い至りました。ゲストキャラ2人の筋道も、お互いにつながって話が回る部分があったり、よくよく熟考してあることが見て取れますし、読者の渇望するもの(主役カップルのラブラブシーン)もお腹一杯大満足!に提供し切った、モンゴメリさんの天才的且つ自由自在な物語構成手腕が一際輝く1冊だな、と思っています。感想を書いてみて、改めて大好きな1冊になりました!by姉(イラストby妹)◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.05.29
コメント(0)
-

暁のヨナ ハクヨナイラスト & 大原画展 名古屋開催!
※感想ではありません。暁のヨナ最新話(269話「天をも恐れぬ者」※47巻収録予定)を読んで、描いたハクヨナです。暁のヨナについて… 今 若干のロス状態に陥っておりまして(早いわ)。ーというか白状すると、花ゆめ本誌を購入後も数日は怖くて開けず…休日に意を決してやっと読む!みたいな。ホント駄目ファン状態なんです🥲 とりあえず、269話ではハクヨナがずっと手をつないでいてくれて嬉しかった…!花ゆめ本誌懸賞用に、アナログでも同構図で仕上げてみました。久々に水彩画具を使いました。ipadも便利だけど、やっぱりアナログは現物の良さがあって楽しいなぁ~♪(一番好きな紙だったストラスモア水彩紙、もう廃盤になってしまってたんですね🥲)ーこのように 暁のヨナに関しては、ファンとして穏やかに…取り乱すことなく 旅の終わりを見届けよう…という心情だったのですが、先日公式様より↓が正式発表されました。◆草凪みずほ 画業20周年記念「#暁のヨナ 大原画展」◆名古屋巡回展決定🎉会場:テレピアホール会期:2025年7月12日(土)~8月3日(日)暁のヨナ大原画展 名古屋開催‼ありがとうございますありがとうございます‼流石に無理だと思ってました…(赤髪の白雪姫の原画展の兼ね合いかな…?)生原画にまた取り囲まれたい…複数回は通いたいです…‼by妹
2025.05.26
コメント(0)
-
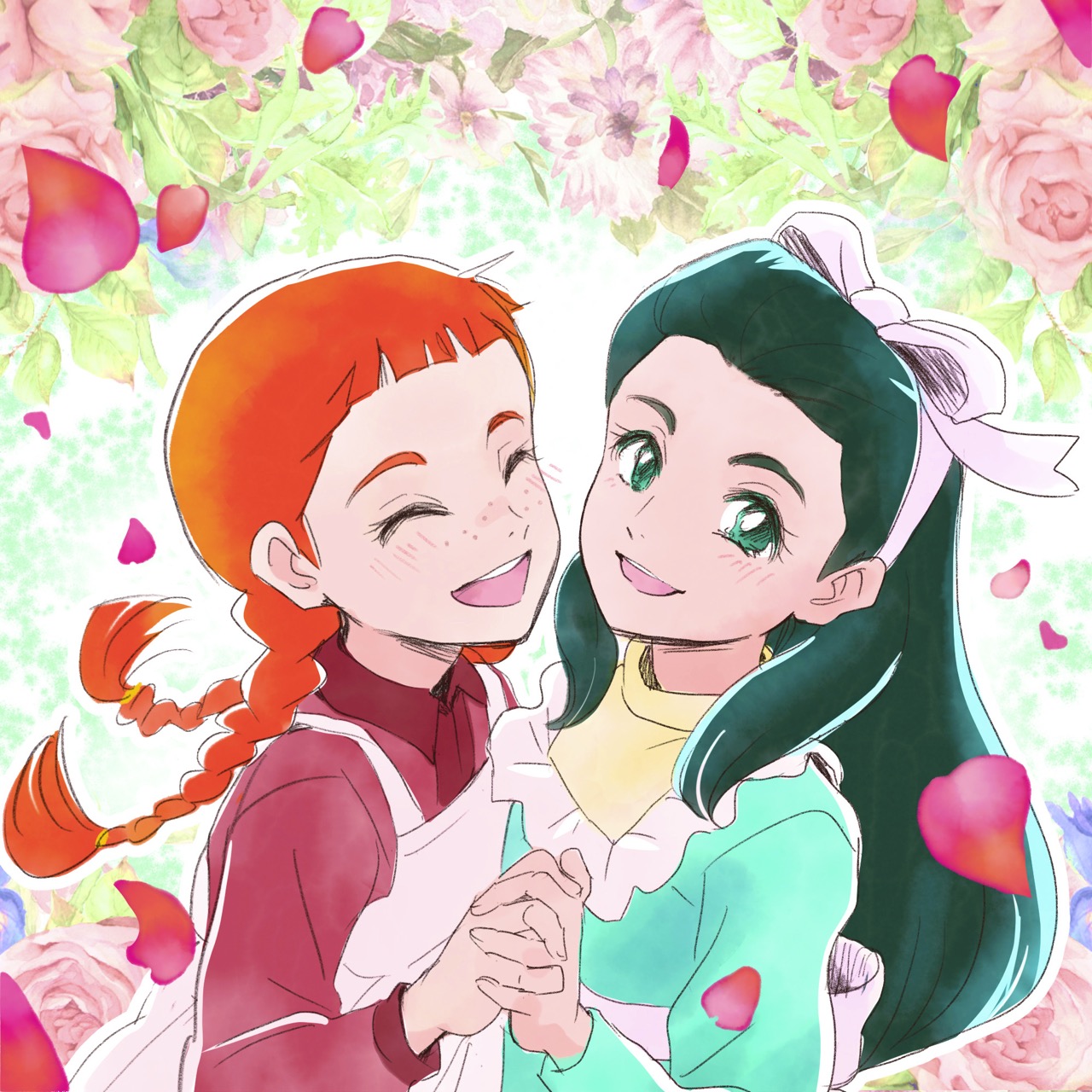
アニメ『アン・シャーリー』第4話・第5話・第6話 感想 まとめ
ダイアナ・バーリー🌼アン・シャーリー🎵赤毛のアン 時代の2人を描いてみました。わちゃわちゃしてる仲良しな2人がとってもかわいいです❤アニメ『アン・シャーリー』感想を毎週ツイートしているものが溜まってきたので、ブログの方にもまとめていきます~。◆アン・シャーリー 4話観ました!アンとダイアナ回。会うことを禁じられてしまった大親友の二人…本気なんだけど、どこか悲劇ごっこ遊びしている感が楽しかったw11~12歳位の女の子たちのリアルさよ…!キャラ造作&ニュアンス等本当によく練りこまれていて、毎回毎回 演出上の取捨選択に唸ります。◆アンシャーリー5話観ました!マシュウ&マリラの愛情回として、綺麗にまとめられていました。基本原作に忠実ですが、毎回脚本構成の工夫が素晴らしいなと。季節が一気に巡り、絵的にも面白味がある回でした。想像以上に派手に屋根から落下しててビックリ!よく足首ですんだなぁ💦新しい服、袖が膨らみすぎ?と思ったけど、成長を見越して大きめのものにした と。成程。今作では、アンが常に赤系の服を着てますね。①アニメ的キャラ立て(イメージカラー)を優先した画作りになっているため②最終話で、緑の服を印象的に登場させるため辺りが理由なのかなぁ。予告でギルバートが可哀そうな顔をしてたけど、小舟シーンではなさそう…アニオリ?飛ばしたキャンディ&林檎エピの補完とか?もしや小舟シーンの「君の髪はとても綺麗~」→アンの怒りぶり返しだけ先に出して、髪染めの動機に繋げるとか⁉色々予想するの楽しいです!◆今のところ、姉と「アン・シャーリー」の話数構成としては 下記のような予想をたててます。■ 赤毛のアン 9話■ アンの青春 6話■ アンの愛情 9話う~ん、どうなるかなぁ。ちょい先ですが、デイビー&ドーラのビジュアル解禁がすごく楽しみだったりします😊◆アン・シャーリー 6話、神過ぎました。いや毎回なんですが、特に今回の表情・演技動作が素晴らしすぎて‼最近原作読んだ勢なので、髪染めエピとか笑い話かと思ってました。そうかこんなに重めに描かれるのか。いやそうだよね13歳の乙女だもんね!でもどんどん成長してるね…(泣)!前半の物語クラブパートは、今後の示唆が山ほど入れ込まれ&強調されていて、コアな原作ファンが手を叩いて喜ぶやつでした😊アンとダイアナの「~は貧乏な青年じゃなかったのね!」「そうよ実は大金持ちだったの!」をギルバートに聞かせるとか…脚本どこまで遊ぶんだ案件。最高!私と姉がキャーキャー騒いでたら、最近は父親も観てくれるようになりましたwOPを絶賛してます。うちの父親は本当に(ホラー系以外は)何でも楽しんで観れる人です。私たちがむず痒くて観れない「少女漫画原作の実写映画」も楽しめるのは、本当に凄いと…!親族総出で楽しみにしているアニメ『アン・シャーリー』!赤毛のアンターンもいよいよ大詰めですね。今後も楽しみです‼by妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.05.17
コメント(0)
-
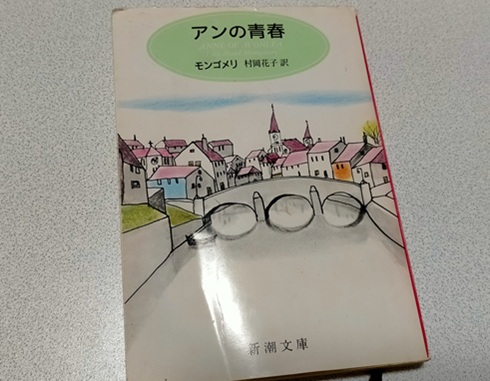
「アンの青春」ー赤毛のアン・シリーズ2ー感想 村岡花子訳
「アンの青春」ー赤毛のアン・シリーズ2ー感想(L・M・モンゴメリ・1909年、和訳 村岡花子・1955年)原題は「Anne of Avonlea」。アンちゃん16~18歳の青春時代が描かれます。クイーン学院卒業時に奨学金を獲得し、レドモンド大学進学準備を進めていたアンちゃんですが、マシュウの急死及びマリラの視力低下を受け、大学進学を断念/奨学金を辞退します。アンちゃんは母校であるアヴォンリー小学校で教師として働き始める傍ら、若者たち有志でアヴォンリー村の「改善委員会」を結成し、村の景観改善等の活動も始めます。またマリラは、母親を亡くした遠縁の幼い男女の双子(デイビー/ドーラ)をグリンゲイブルスで引き取ることになり…。第1作目・赤毛のアン発売から1年で発表された続編小説。第1作目が、発売後短期間で大きな反響を得たことが想像されます。おそらくモンゴメリさん自身の構想/執筆期間も非常に短い作品だと思いますが、一気に注目を集めた新鋭女流作家の鮮やかな筆の滑り(キレキレ)を堪能できる1冊だな、と思いながら読みました。妹ともよく話すのですが、モンゴメリさんのずば抜けた天才性として『アンシリーズの中でも、1冊毎に全然構成の方法が異なるところ』があると思っています。物語構成力の怪物というか。今回は「これ」をやるんだと決め込んで、全然異なるアプローチ方法で1作1作を形にされているので、受け手としても全然違う魅力…美味しさを味わえます。それでいて、シリーズ全体として「アンちゃんの人生」を様々な方法で煮詰めているという 一貫した前提があるため、シリーズとして年数&冊数を重ねる毎に、「アンちゃんの人生・幸せ」の立体感と味わいがどんどん深まるのだと思います。2作目である「青春」のつくり方としては、大きく2つの目的があって構成してあるのかな、と思っています。本作のいちばんの目的としては、アンちゃんがこの先、何を基軸にして生きていくのか、様々な物事を試し試し吹っ掛けてみて、「どうかな?」とアンちゃん本人や周囲の人々とディスカッションしてる作品という認識で受け取っています。・アンちゃんの人生軸の試行錯誤①教育面…小学校教員職亡くなったアンちゃんの両親はどちらも教師だったというバックボーンもありますし、1作目「赤毛のアン」でもステイシー先生という「憧れの教師像」を投入していました。そこからの流れとして、また片田舎における女性の肩書ある生き方として、思い浮かぶいちばん自然&堅実な将来像かな、と思います。②文学面…小説家の投入モンゴメリさん自身、幼い頃より小説家への憧れがあったと思いますし、文学的才能に富むアンちゃんも、小学校時代より女友達たちと「物語クラブ」で遊んでいた経緯がありますので、将来像として「小説家」の道も選択肢としてあったのだろうと思います。本作においては、モーガンさんという人気女流小説家が。グリンゲイブルスを訪問するというイベントとして入れ込まれています。③地域貢献面…政治的側面?幼少時代との差別化もあると思いますが、本作ではより社会的な影響力を持った動きが出来るようになった点を強調するように、村の「改善委員会」の組織/運営という活動も描かれています。モンゴメリさんが、自身の住む村で生きていく中で、地域社会への貢献という側面を非常に重要視していたのだろうと感じます。④家事・育児面…主婦面の能力6歳の双子を引き取ったことで、一気ににぎやかになるグリンゲイブルス。アンちゃんは2人の子どもたちを非常に可愛がります。男の子(デイビー)は度を越えたいたずらを度々繰り返しますが、アンちゃんは時間をとって、根気強く彼と向き合います。また作品全体を通して、家事面…料理や裁縫・掃除といった諸仕事にアンちゃんが誠意取り組む場面がたくさん登場します。総じて、アンちゃんはめっちゃくちゃ良い奥さん&お母さんになる!(断言)アンちゃんが、上記の様々な物事に向き合う姿を見て、やっぱり…「④家事・育児面」に向き合う姿がずば抜けて輝いて見えます。いや、全然ほかの仕事も立派にこなせてるんですよ。アンちゃんはすごく賢い娘ですし、誰からも愛される娘なので。ただ、やっぱりアンちゃんが一番輝くのは『家』だな…!と。第1作目の体裁が「家」にくくっていた影響とも言えますが、やっぱり何を差し置いても、この娘が一番に求めて求めて、全身全霊で尽くしていくもの…と考えたときに、『家/家族』がいちばんしっくりくる。本作のラストで長年独り身だったミスラベンダーさんの結婚式が大々的に描かれますが、『家/家族』に向かうアンちゃんの人生の方向性と、シリーズとして、その前段階で『結婚』に向かって話を進めていく方向性が定まったんだろうな、と受け取って読みました。・グリンゲイブルス及びアヴォンリー村への貢献本作で描くべきものの2つ目として、グリンゲイブルス及びアヴォンリー村への貢献があると思っています。…最終的にアンちゃんの人生が向かう『家』は、グリンゲイブルスではなく、結婚後に新たに築く『家/家族』になります。また、結婚後に人生の大半を過ごすのも、プリンスエドワード島内ではありますが、アヴォンリー村ではありません。結果論ではありますが、アンちゃんがグリンゲイブルスに腰を据えて「住む」のは、本作のラスト、大学入学前の18歳までとなります。(もちろん、その後も長期休暇でアヴォンリー村/グリンゲイブルスに長期滞在はします)本作で描かれる青年期の2年間は、マシュウ亡き後のグリンゲイブルスの切り盛り、アヴォンリー小学校での教鞭、改善委員会での活動、村内の隣人・知人たちとの交流、女友達たちとの遊興…と、孤児の自分を引き取ってくれたマシュウ・マリラの2人&グリンゲイブルス、そして暖かく育ててくれたアヴォンリー村に対して、アンちゃんが生活のすべてで目いっぱい貢献することが出来た、アンちゃんの人生の中でも非常に大切な時間だったな、と思います。この2年間で、「グリンゲイブルス/アヴォンリー村の役に立てた」、「引き取ってよかった/育ててよかったと思ってもらえた」、という実感をもったうえで、ようやくアンちゃんが…「この先、何を軸にして人生を生きていきますか?」という『未来(人生)の話ができるステージに立てた』のだろうな、と感じました。・マリラとギルバートの動きについて上記の通り、本作はアンちゃんの人生軸について試行錯誤している作品と受け取っていますが、アンちゃん本人としては、本作終了時の段階で、向かうべき方向性がはっきり見えているわけではありません。ただ本作のかなり序盤から、アンちゃんの人生軸を想定(予想)して動き出しているのが、マリラとギルバートの2人だと思っています。マリラに関しては、「グリンゲイブルスからアンちゃんを自由に巣立たせてあげる」ための動きですね。マリラとしては、マシュウの急死や自身の体調によって断念させてしまった大学進学、またその後の就職や結婚に関して、アンちゃんに「家(グリンゲイブルス)を背負わせる/家に縛る」ことをしたくないという思いを持っていることがひしひしと伝わって来ました。これも結果論ではありますが、最終的にグリンゲイブルスは、遠縁筋のデイビーくん(双子の男の子の方)が継ぐことになります。マシュウ急死後、アンちゃんがグリンゲイブルスに留まってくれたおかげで、幼い双子を引き取ること、ある程度2人が落ち着くまで育てることができましたし、リンド夫人も含めて、家を切り盛りする新たな体制を準備するところまで持っていくことが出来ました。マリラはもちろん、アンちゃんに家から出ていけと言っているわけではなく、でもアンちゃん自身の将来を見据えたときに、もっと自由に、才能を発揮できる場所や、一緒に居たい人と生きて行っていいんだよ!という強いメッセージを込めた動きをしているな、と思います。マリラはなんて賢くて愛情深い方なんだ…と感心しっぱなしで読み進めました。そして…ギルバート。彼の動きは…おもしろいですよね。アンちゃん自身には、まだ自分の今後の人生ビジョンが見えていない段階で、何故かコイツは勝手に「結婚→アンちゃんの主婦像」ビジョンを描き出して、「アンちゃんをお嫁さんにしたい!」「僕は医者になる!」とか言い出して、「アンちゃんの人生ビジョン(ギルバート脳内の理想)」に向けて誰よりも早くスタートを切ってますので。今回、アンシリーズを読み進める中で、妹が…「赤毛のアンシリーズの中で、何が一番おかしいってコイツ(ギルバート)の異常なハイテンションだからな!」と主張していますが、「まぁ…そうだな、走ったキャラクターだよな」と私も思います。「赤毛のアン」のラストシーンで、ようやくアンちゃんとお話できるようになって、「青春」に入って、笑いかけてもらえるようになって、嬉しくて嬉しくて、調子に乗ったんでしょうね…。この時点での未来へのアグレッシブさのバランスとしては、ギルバート>>>>…>アンちゃん ←こんな感じです。本作・第十九章で、日暮れにアンちゃんとギルバートが会って話をするシーン…アンちゃん:ギルバートはなんて立派で男らしくなったんだろう……まぁ自分の理想の男性のタイプには全然似てないけど…そんなことは友情には差しつかえないことだ。ギルバート:理想の女性は?と聞かれたら、目の前に居るそっくりそのままのアンちゃん!自分の未来を、この清らかで優美な女神にふさわしいものにしなければならない!もう少し素直にときめこうか…という、自身の心の動きにキャップをかけようと頑張るアンちゃんのモノローグに対し、照れることもなく、真顔で女神フィルターフルスロットルなギルバートのモノローグ。この2人のテンション落差が最高に面白いシーンで、大好きです。やはりこの「青春」以降、ギルバートの、アンちゃんに先行したアグレッシブな動き(for 理想のビジョン)の輝きはシリーズ全体を支配していきますし、本シリーズを全世界的な不朽の名作に押し上げたパワーの源泉はコレだな、と認識しています。ギルバートがこれだけ好きに独走を始めているので、ここからは基本的に「アンちゃん/ギルバートのW主人公」だな、と認識して読み進めています。ここまで書いてきたのは、基本的には『アンの青春』の大枠…というか、シリーズ全体の中の位置づけ、骨格・文脈の話になります。最後になりましたが、本作はアンちゃんの反応を引き出すことが目的の「試行錯誤」的な作品ですので、非常に自由度が高いというか…こういう作りの作品は、基本的に漫然とした印象を受けることが多いのですが、でも本作は、読み物としてエピソードの一つ一つがきちんと面白いんです。1作目「赤毛のアン」の体裁を引き継ぎ、様々なアンちゃん(&デイビー)の失敗が愛すべき日々として描き出されますが、失敗の1個1個も、悪気があったわけではないことが分かるものですし、キャラクターたちを愛せます。1作目『赤毛のアン』とは異なる大枠を据えて構成しているにも関わらず、きちんと1作目の面白さを求める読者の満足に耐えうるようなキレのあるエピソードで、本作『アンの青春』は形作られていると思います。改めて、本作「アンの青春」を短期間で一気に書き上げられたモンゴメリさんの作家力に感服します。「アンの青春」は、今回のアニメ『アン・シャーリー』で映像化される部分です。どのような切り取り方で、どのような映像になるのか、今からとても楽しみにしています。by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.05.13
コメント(0)
-
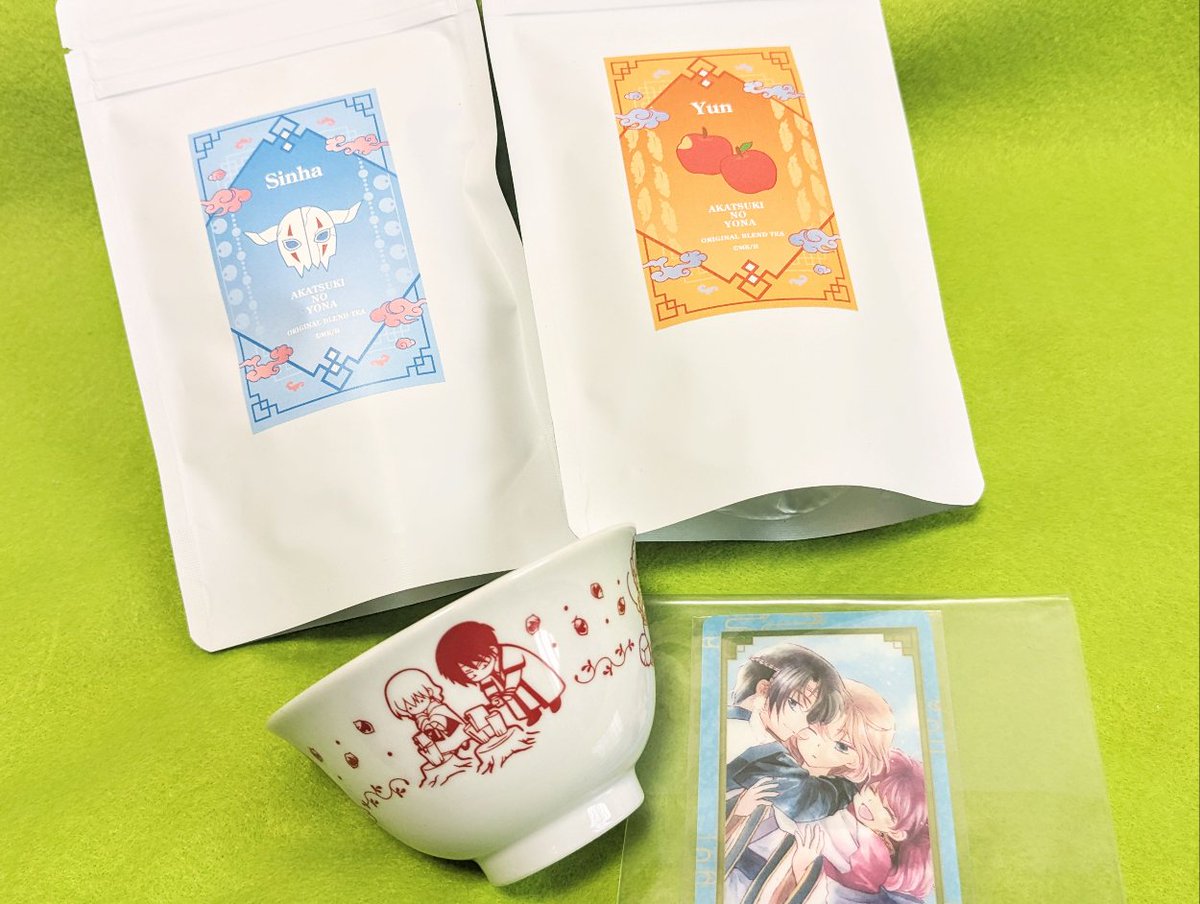
暁のヨナ ブレンドティーを飲んでみました。
暁のヨナ ブレンドティーを飲んでみました。「camos」という五感でたのしむキャラクターアイテムブランドからの発売だそうで。様々なアニメ/漫画作品のブレンドティーやバスソルト等を制作されているのかな?こちらのブランドから、暁のヨナの主要キャラクター8名(腹へり7名+スウォン様)のイメージブレンドティーが発売されました。せっかくの楽しい企画なので、悩んだ末にユンくん/シンアくんのブレンドティー+湯のみを購入しました!(本当は全員分飲んでみたかったのですが…お値段的に全種は厳しかった…!)★ユンくん ブレンドティー(商品説明)ニルギリ紅茶とほうじ茶の落ち着いた味わいの茶葉をベースに、ジンジャーのほっとするスパイスを重ねました。じんわりと林檎の香りがあふれ、やすらぎに包まれるブレンドティーです。<ブレンド内容>ニルギリ紅茶、ほうじ茶、ドライアップル、玄米花、ジンジャー、香料(林檎)商品説明を読んで、いちばん味が好みそうだったためセレクト。予想通り、非常に美味しかったです。アップルティーを想像していましたが、商品説明にある通り結構スパイシーな風味が強く、可愛いだけではなく、切れ者/しっかり者なユンくんのイメージだなぁ~!ととてもしっくりくる味でした。★シンアくん ブレンドティー(商品説明)青い水色を生み出すバタフライピーに、パインやパパイヤの黄金色の素材を加えました。フルーツの優しい甘みとまっすぐなペパーミントの香りが不器用な優しさを思わせる、ハーバルな味わいのブレンドティーです。<ブレンド内容>ドライパパイヤ、ドライパイン、レモンピール、月桃、バタフライピー、ローズマリー、香料(ペパーミント)こちらは色合が面白いだろうな、と思いセレクト。商品説明の通り、水色のきれいなお茶でした。味についてはあまり予想できていなかったのですが、フルーティー&ミントがシンアくんの純朴な目線を表現しているんだな~、とこれまた非常に納得感のある味でした。いやぁ…さすがプロの方が考えてるんだな~…というか、どちらのお茶も、キャラクター性をそれぞれ分析し、要素でもってきちんとお茶(色/味)が構築されていることがよく分かりました。フレーバーティーってこんなに面白いんですね!びっくりしました。★中華湯呑み暁のヨナ大原画展のTシャツ用の描きおろしイラストを使用した湯呑!こちらのイラストカットが可愛くて欲しかったので、嬉しいです。(Tシャツは着ないので未購入)腹へり一行の日常風景がぐるっとプリントされてます。可愛い~!買ってよかった~!既に漫福ガチャ・暁のヨナ第3弾(6/20~)が告知されていますが、花とゆめ本誌の展開も佳境中の佳境で、今後最終回に向けて様々な企画が水面下で動いてるんじゃないかな~と予想しています。(いつになるのかは分かりませんが…)楽しい企画がいっぱいあるといいな。全力で楽しめるようにお金を用意しておかなくては…!(無理のない範囲で)by姉
2025.05.11
コメント(0)
-
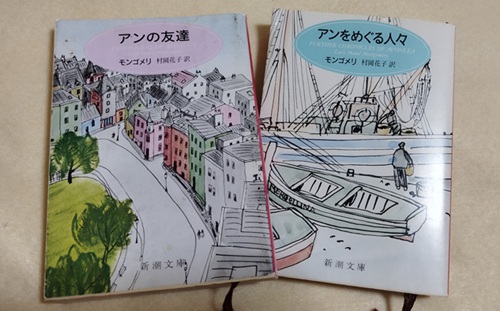
「アンの友達」「アンをめぐる人々」ー赤毛のアン・シリーズ4・8ー 感想 村岡花子訳
赤毛のアンシリーズの感想が続きます。面白いっ…面白いんだ…!!簡単感想です。「アンの友達」ー赤毛のアン・シリーズ4ー「アンをめぐる人々」ー赤毛のアン・シリーズ8ー 感想(L・M・モンゴメリ・1911年,1920年、和訳 村岡花子・1956年,1958年)村岡花子さんのシリーズでは「赤毛のアンシリーズ」として取り扱っていますが、海外では(一般的に)アン・ブックスシリーズには含まれないものみたいです。内容としては、アンちゃんとは縁薄い「アヴォンリーの人々」を主役とする体裁の、モンゴメリさんの短編集です。いやぁ~…面白かったです!!「アンの友達」(Chronicles of Avonlea)モンゴメリさんのワークスとしては、アンの青春/アンの愛情の間に刊行された初期ワークス。アンシリーズの人気を受け、自身の短編小説をアヴォンリーの諸物語として、アンちゃんも少しだけ絡ませるような体裁で取りまとめた作品集と認識しています。モンゴメリさんの一番「素の部分」が楽しめる作品集なのかな、と感じました。まだアンシリーズ+アンシリーズの短編集数作を読んだところですが、モンゴメリさんが繰り返し使うモチーフ(興味分野)として、下記の辺りが挙げられるかなと思っています。1,結婚 ■特に喧嘩別れした後、10~20年越しの壮年/老年になってからの成就 ■相手の生活の中に自分の居場所を見つける女性(相手は、しっかりし過ぎておらず、支えてあげたくなる男性像が多い) ■家族間(特に姉→妹、母→息子)の、結婚への反対(妨害)2,悲恋 ■叶わなかった過去の恋→ 憧憬/恋人の血縁者を通じての思いの昇華3,死に際 ■傍から見たら「何も成しえていない寂しい人生」かもしれないが、本人が生きてきた主観の中で軸にしていたもの/執着していたものを完遂する、強く光り輝く一瞬。総じて、基本的にはほとんど「女性の生き方」が焦点の話という認識です。同じようなモチーフでも、1作1作状況が違って面白いですし、繰り返し描かれる中で『感情』も成熟していって、アンシリーズ本編の中で似たモチーフとしてまた繰り返し描かれたり…。モンゴメリさんの『感情軸を最重要視し、構成するお話のつくり方』がとてもよく見て取れました。・描くべき「感情」を強く想起させるために、練り込まれた人物配置・感情のクレッシェンドを説得力を持って描き出す、絶妙なエピソードの積み重ね・誰の主観から、どのような順番で情報を読者に魅せていくか、様々な選択肢から一番面白い魅せ方を厳選していることが分かる、ひねりのある演出…1作1作、どの作品も非常に面白く、興味深かったです。以下、お気に入り短編について。1,奮い立ったルドヴィック(The Hurrying of Ludovic)5,ルシンダついに語る(The Winning of Lucinda)モンゴメリさんの作品中に何度も何度も(×100)登場する、「プロポーズしない」男性及び何十年も結婚しないカップルの物語。モンゴメリさんご自身が、祖母が亡くなった後に37歳?で結婚され、そこから出産・小説も書きながら家事もやりながら子育てして…という経緯があるそうで。ご自身の体験も含め、「結婚」という人生における一大イベントへの決心に向け、人がどのように心を作っていくのか… その過程に非常に興味があったんだろうな、と思います。2.ロイド老淑女(Old Lady Lloyd)世間への見栄はあるが、実際には困窮生活を送るロイド老婦人。昔の恋人の娘が近くに越してきたことを知り、なんとか彼女を笑わせてあげたいと願い、匿名で様々な贈り物を届けはじめるが…。1番のお気に入り作です。泣いたよ…。自身の寂しい極貧の生活や様々な後悔をもって、尚のこと一層、「若々しく才能のある昔の恋人の娘」への思いを募らせ、献身的に贈り物を届けるロイド婦人…老婦人の献身とか…やめろよ…泣いちゃうじゃんよ…。3.めいめい自分の言葉で(Each in His Own Tongue)4.小さなジョスリン(Little Joscelyn)2作、「音楽×臨終モチーフ」の似た話が並んでいて印象的でした。アンシリーズ本筋では、それほど音楽モチーフが出てきた印象がなかったので、音楽の力を奇跡のものとして描く感性のある方だったんだ…と意外に感じました。7.オリビア叔母さんの求婚者(Aunt Olivia's Beau)8.隔離された家(The Quarantine at Alexander Abraham's)12,争いの果て(The End of a Quarrel)状況は異なりますが、いずれも長きに渡り結婚していなかった女性が結婚する話。モンゴメリさんの価値観というか、結婚観がよく見て取れる3作だと感じました。「オリビア叔母さんの~」の、一度求婚を自分から断っておいてからのラストの大反転は、形としては、「アンの愛情」のお話構成に似たものを感じました。「争いの果て」のラストの会話も、「愛情」のラストシーンを彷彿とさせる言い回しですね。11,カーモディの奇蹟(The Miracle at Carmody)妹の足が不自由になり、様々な手を尽くしたが治らないことに絶望した姉は信仰を捨てる。姉妹は養子の男の子・ライオネルを迎えるが、姉は教会へは通わせず…。日本の感覚とは異なる宗教観/信仰観を見て取れる1作で、興味深かったです。モンゴメリさん自身の宗教観は、なんとなく…ご自身が「信仰してる」と言うより、様々な事態に対し、人が「信仰」を使ってどのように心に収めていくのか、また「教会」組織の社会的機能の側面…地域社会としての共通認識醸成等への興味の方が強い方だったんじゃないかなぁ…と感じています。「アンをめぐる人々」(Further Chronicles of Avonlea)Wikiに寄ると、この短編集は、「アンの友達」をまとめる際に没にしたはずだった原稿を、後年になって出版社が(若干手を加えた形で)勝手に刊行したものだそうで、長期間の裁判沙汰になっていた1作と記されていました。(…本当なら、そら作家は怒るわ…。)読んでみて…確かに、これは世に出す用に体裁を整えてはいないな…モンゴメリさんとしては全く世に出す気はなかっただろうな…と感じる作品もあるので、ご本人的には非常に不本意な作品集だったのかもしれませんが、ただまぁ…洗練していない作品にこそ、モンゴメリさんのお話構築過程を想像させるヒントがたくさん見て取れて、読者的には、めっちゃ面白かったんですよねぇ…。「アンの友達」と比べると、若干狂気じみた…「とんでる/いっちゃってる」系の話が多い印象でした。その分、1作1作の色がはっきりしていますし、どうなるか展開が分からないスリリングさがあって読み応えがありました。1,シンシア叔母さんのペルシャ猫 (Aunt Cynthia's Persian Cat)2,偶然の一致 (The Materializing of Cecil)3,父の娘 (Her Father's Daughter)出だしから、様々な経緯を経た「結婚」物語が続いて興味深かったです。9,セーラの行く道 (Sara's Way)何度も求婚してきた男性が事業に失敗して逆境に立った途端に「結婚する」という女性の物語。これも「独特な結婚観」…なんですが、心情としてきちんとついていけます。「アンの愛情」でも、アンちゃんが「自分の幸せ」ではなくて、「ギルバートの幸せ」の中に自分の生きる場所を見出したところから「結婚」の道が開けていったのだと受け取っていますが、それに近い感性を感じました。5,夢の子供 (The Dream-Child)20カ月で赤ん坊を亡くした妻が、夜になると「子どもの声が聞こえる」と海辺をさ迷い歩く。ラスト…まさかそうなると思わない展開が来てびっくりしました。10,ひとり息子 (The Son of his Mother)11,ベティの教育 (The Education of Betty)12,没我の精神 (In Her Selfless Mood)上記3作はかなりぶっ飛んだ作品で、それぞれ面白かったです。ひとり息子を溺愛するあまり、息子の恋愛相手に憎しみを覚え、傍目に奇行にまで発展する母親…自身を振った女性のひとり娘の後見人となり、親身に教育する男性の、娘への飽くなき愛情…死の床の母親と弟のクリストファーを護ることを約束した少女の生涯…各話、おいおいおいおい…どこまで行くんだコレ…!とハラハラしながら読みました。15,平原の美女タニス (Tannis of the Flats)住民の多数がインディアン血統や混血で構成される、カナダ西部の平原地方の電話局へ赴任した英国系男性の運命。この作品はまた、なかなか当時のカナダにおける価値観を持っていないと出てこないお話というか、他とは趣向の異なる作品で興味深いお話でした。先に書いてきたこととも被りますが、これら2作の短編集を読んで…とにかく、『結婚』をモチーフにした作品が非常に多いです。モンゴメリさんの執筆/編纂時期を考えても、個人的に注目してしまうのが、『アンの愛情』の下地になるような感情やお話構成の作品を、たくさん見つけられるところ!『アンの愛情』は…シリーズの中でも、主人公の人生軸を決定づける重要な作品だと思ってます。すごく強烈な感情が、繊細なエピソードの積み上げで構築されており、モンゴメリさんご自身の一番の興味分野(結婚)について、咀嚼して咀嚼して、アンシリーズのファンたちの期待に応えるよう、渾身で繰り出された作品なのだろうと感じています。『愛情』を読んだ際に感じた「なんて強烈な感情なんだ!なんて洗練された構成なんだ!」という印象は、こうやって…短編作品として似た題材を繰り返し形にする中で、キャラクターを走らせることで感情自体を成熟させたり、1話としての構成として魅せ方を試行錯誤したりして、高濃度/高品質なものとして洗練・構築していくものなんだな、とひしひしと感じました。アンちゃんたちとは縁薄い…と言いつつ、アンシリーズのお話の構築の仕方を鏡のように映す、縁深い作品集だと思うので、特に「『アンの愛情』凄い!やばい!」と感じる方は、これらの短編集も是非!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.05.06
コメント(0)
-

アニメ『アン・シャーリー』第2話・第3話&OP/ED感想 +村岡花子さんについて
アニメ『アン・シャーリー』第2話・第3話&OP/ED感想妹と2人で、キャーキャー騒ぎながら鑑賞してます!※以下、原作シリーズを読んだ上でネタバレ全開で好き勝手語ってます。 原作シリーズ未読の方はご注意ください!※少女漫画ベクトルを至高のものとして、どこまでも詰めて描いてくれる「赤毛のアン」シリーズ・こだわりのハイクオリティアニメーションとか…なんかもう、私たちのためにありがとうございます!!! と叫んでいます。3話まで鑑賞しての簡単感想です。妹とも鑑賞後真っ先に言い合うのが、コレ↓ひとつひとつの演技筋とニュアンスが完っっっっ璧!!!非常に尺の短い中で話を展開させていく必要があり、またナレーションに頼らない、絵と演技で魅せ切ることに徹しているからこそ、一つ一つの表情変化と演技動作が、脚本段階→画としての指定/音としての指定として、間違いなく丹念に詰められているのをひしひしと感じます。また、魅せ方としての重さ…ニュアンスというか、重くするところ、軽くするところの取捨選択が、細かなことろまで熟考してあることがよく分かります。印象的だったのは、2話で日曜学校(教会)へ行ったアンちゃんが帽子に花をつけていき、それをマリラが怒るシーン。マリラが頭痛でイライラしていたこともあり、「私が困るんだよ!」と言ってしまい、それに対するアンちゃんのリアクションが非常に大きく、マリラが逆に慌ててしまいます。「赤毛のアン」冒頭では「癇癪持ち」と言われるほど感情の起伏の大きいアンちゃんですが、礼儀作法を教わっていないという点ももちろんあると思いますが…それよりもこの娘の立場として、まだまだ土壌が不安定な中で、不安な気持ちが大きくなると、感情コントロールが出来なくなってしまうからだろうな、と受け取っています。だって…やっぱり血の繋がりも何もないところで、しかも望んでいた男の子ではなかったのに、ご厚意で家に置いてもらい始めたところで、世間一般の常識がないのも(アンちゃん的には)見ばえが良くないのも、気にしてる所だと思いますし、「捨てたい」と思われてしまったら、全然捨てることが出来る存在だ…という不安が常にありますので。アンちゃんは賢い娘なので、ちゃんとアンちゃんのためを思って言ってくれてる言葉だったら、叱られてもむしろ嬉しいくらいだと思います。相手の勘違いだったり…という場面も、「そういうこともあるよね」と通常のやり取りとして軽く流せる。ただこのシーンのように、マリラが本気で迷惑がっていて、マリラ自身が「自分のいらだち解消」の為に発した言葉をぶつけてしまうと、アンちゃんがそれを全部掴んじゃって、不安感が増大してパニック状態になっちゃう。レイチェル夫人やギルバートの「にんじん」も、もちろん発言者2人の言動が軽率なものだったことは確かなのですが、それにしてもアンちゃんの反応が、常識を遥かに逸脱して&周囲がびっくりするほど「大きい」。この部分も、時が経ちマシュウ/マリラの揺るぎない愛情を実感できてからは落ち着いていく部分なのですが、ただの「癇癪」「感情の起伏が激しい」とは質の違う深い描写だな、と受け取っています。妹が言うには、今作では、アンちゃんの演技筋として、とにかく“笑う娘”というコンセプトがあるのでは。高畑勲監督版との違いとしても意識していると思うけど、今回は嬉しくても悲しくても不安になっても、演技筋は“笑う”方向性に寄せている印象。特にマシュウ&マリラ、女友達など、好かれたい相手に対しては。たった数話の中で、全然違う文脈でバリエーション豊かな“笑顔”が登場して来て、表情が本当に見ごたえがある。そしてこの「つらい時でも笑顔」描写が何を伝えてくるかって、彼女の健気さなんだよね。マリラの方もアンちゃんのリアクション見て、「自分が当たって、こんなにアンちゃんを不安にさせてしまった、やばい!」と思ったのもすごく伝わって来ましたし、映像作品としてものすごい見ごたえがありました。3話では、いよいよもう1人の主人公・ギルバート・ブライスの登場です!115年以上前の小説に登場した、元祖・溺愛系スパダリ(ただし学生時代までは本当に金がない)にして、読者の声援を一身に受ける、めげない努力型片想いラブファイター(ラブコメ主人公)でもある…片田舎の農家(?)生まれのくせに、何故か生まれながらの帝王気質(思想)で、自分のビジョンに作品全体を引き寄せようとしてくる、脅威のアグレッシブキャラクター。いやぁ…このキャラクターはすごいですよ。今回「赤毛のアンシリーズ(村岡花子さん訳)」をまじまじと鑑賞してみて思いましたけど、②青春…特に③愛情以降は、完全に作品を乗っ取ってましたもん。赤毛のアンシリーズ全体を通して、何が描かれていたのかと言われたら…私的には「ギルバートと、彼の築くブライス家が描かれていた」という認識です。今回のアニメ作品、何がやりたいかってそんなもん…アンちゃん軸と両輪で、ギルバートの成長軸をしっっっかり描いて、お互いがお互いをすごく見てる描写をいっぱい入れ込んで、元祖・爆萌えカップルのザ・少女漫画的ラブストーリー(成就まで)を演出及び演技(絵・表情動作・声)で、説得力を持って描き切ることですよね…!旧作アニメは、「①赤毛のアン」までの映像化でしたので。ギルバートも当然出て来てたんですけど、アンちゃんとまともに話すことができるようになったところが最終回だったので。もちろん高畑勲監督版のリアリティのある、じっくりした描写の『①赤毛のアン』は、「アルプスの少女ハイジ」からの流れを汲んだ『世界名作劇場』のアニメーション企画として、まるでプリンスエドワード島に暮らしているかのような体験ができる、完成形の素晴らしい傑作だと思っています。ただ、少女漫画好きな私たちとしては、やはり… えっ…だって…「シリーズの一番美味しい&一番ヤベェところは、ここからじゃん!」というか…、「真の主役(ギルバート)が、まだ主役張り出す前じゃん!」というか……ギルバートはここからですから!本当に!!今回の新作アニメでは、ギルバートのビジュアルを旧作アニメイメージからガラッと大きく変えて来ています。出だしの印象はかなり幼いイメージにしてあり、また髪色がかなり明るめになってます。髪色に関しては、基本的には村岡花子さん訳で度々記される「鳶色(とびいろ)=赤暗い茶褐色」なのだと思いますが、ここまで旧作と乖離した明るめのイメージでわざわざ出しているのは、「ギルバート像は明確に、旧作とは違うことをやるよ」というメッセージだと受け取っています。ギルバートの成長軸は本作の核心とも言える部分だと思いますので、絶っっっ対に描写は渾身のはずです。妹の予想では…おそらく年齢が上がるとともに、アニメーション自体の質感も重めに、画面の色調を抑えめに変化させていって、ギルバートの髪色も落ち着かせていくのではないか、幼い/チャラい印象→しっかり立派な/重めの印象 として描いていくんじゃないか、とあれこれ妄想しています。声優様も明らかに青年編以降を念頭に、しっかり芯のある声質の方が当てこまれていて…アンちゃんの幼め/高めな声質とのバランスもすごく良いし…も~~~、本当にこの先、楽しみしかないっっっ!!!■OP♪予感/ED♪heart山田尚子さんが手がけられたOP/ED…Youtubeに掲載されたものを何度も何度も×100 繰り返し鑑賞して感嘆してます。2楽曲とも、速攻で音源をDLしてエンドレスリピってます。楽曲も映像も渾身ですね!最高です!!OP♪予感一番最初のカット、お花の縁取りのような画面は、おそらく「モンゴメリさんのスクラップ集」イメージかなぁ(妹談)。ぴょんぴょんと飛び跳ねるアンちゃんが可愛らしくて!白抜き画面でお花を抱くスーパー乙女ちっくアンちゃん…あれは間違いなくギルバートの目に映っているアンちゃんです(断言)。…完璧です。彼の目には、本当にあれくらい清楚可憐な「女神/花の妖精/樹木の精霊」に映ってるし、この女神フィルターは死ぬまで一生外れません。本編もそうなんですけど、今回のアニメのアンちゃんは…ギルバート(&マリラ)のテンションが爆上がりするアンちゃん像なので。あらゆるシーンに「ギルバートホイホイ」が仕掛けられていて…1・2話を鑑賞していても、アンちゃんがマリラの手をきゅっと握ったり、ダイアナちゃんに「親友になってほしい」と懇願するシーン等、(私の脳内で)ギルバートが「ハイッ!ハイッ!僕もッ!」って挙手しながら駆け寄ってくる想像がワッと浮かんで来ました。…まだ登場してもいないのに。時計の針を「③」まで進めて、大学生アンちゃんのビジュアルがガツッと印象的に登場するカットは、来た~~っ!って感じでした。妹とも「OP映像は、観れば本作が何をやろうとしてるか分かるように作ってくるはず。旧作では登場していなかった大学生アンちゃん像は、絶対出してくると思う」と話しており、「やっぱり♪」と2人で喜んで鑑賞しました。それにしても、まだまだギルバートの成長軸ビジュアルや、アンちゃんの人生が最終的にどこに向かうかはひた隠しにした映像になってまして、も~~~、本当にこの先、楽しみしかないっっ!!ED♪heartも、これまた本当に素晴らしいです!鉛筆デッサン&印象的な色をほんの少し水彩で乗せたイメージ像。線画や色数は違うけど、昭和~平成にかけて長きに渡り発売されていた(のだと思う)、村岡花子さん訳・赤毛のアンシリーズ(新潮文庫)旧ジャケットのイメージと似てるなぁ…もしかしたらオマージュなのかも。(妹談)印象派に近いような…「心象で画面構築する」「画面バランスで心象構成する」という今回のアニメーション作品の、確固たる方向性を打ち付ける映像だと思います。楽曲自体も、間違いなくそのことを歌っていますので…!今回、村岡花子さん訳の赤毛のアンシリーズを改めてじっくり読んで、何が凄いと思ったかって、やっぱり…ここ。話筋・キャラクター筋をしっかり捉え、それを読者に伝えきるように演出する文章力。子供向けラジオ番組でも活躍されていたという村岡花子さんは、対象とする相手に話を聞かせること・文脈を伝えることに非常に優れていたんだろうな、と。日本語訳の際の語感のセンスというか…読み進める中で、ところどころに輝いて焼き付く単語や一文があるんです。それらは、作品の中の主人公たちの心象においてインパクトの大きな出来事…絵面だったり、言葉だったり…だと思うのですが、その強弱でもって、各キャラクターの行動言動軸、作品全体としてのバランスを構成して、読者に魅せるべき感動を伝えきってくる…。赤毛のアンシリーズが、執筆されたのは110年以上前…村岡花子さんの日本語訳が約70年前…それにも関わらず、時代を超えた世代が感動を受け取れるというのは本当に凄いことだな!と思います。ED映像をまじまじと拝見して、今回のアニメーション作品は、村岡花子さんが和訳…文章でやっていた上記↑「キャラクターの心象構成/作品としてバランス構成」を、今回は映像…演出及び演技(絵・表情動作・声)でやる!という作品なんだな、と受け取っています。映像で構築した様々な要素の強弱で アンちゃんの心象を形づくり、最後に彼女が人生の軸を何に据えて生きていくのか、その選択を説得力を持って描き切る…これは本当に難しいチャレンジだと思います。本当にアーティスティックで、意欲的なアニメーション作品だと思っています!今後も楽しみに、心して鑑賞させていただきます!by姉(イラストby妹)アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.04.21
コメント(0)
-
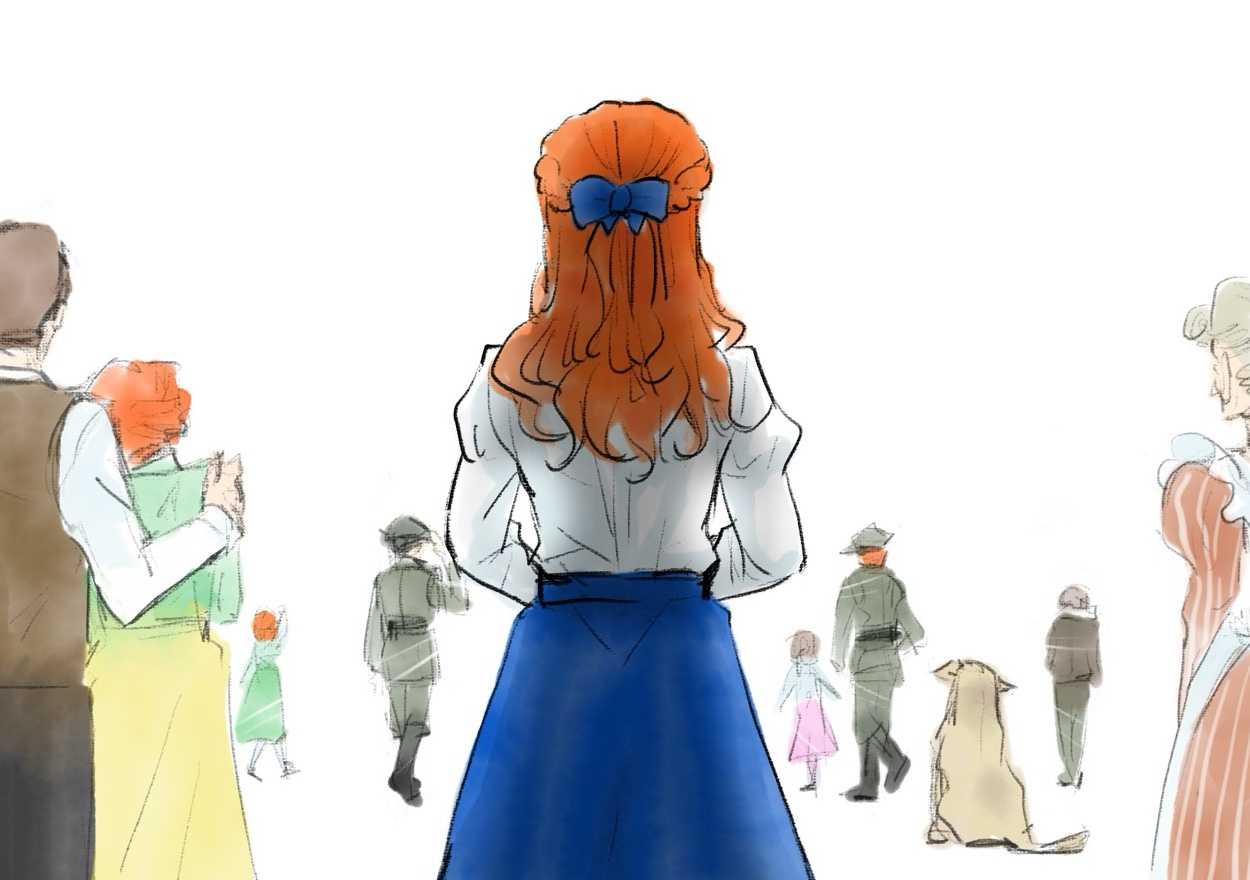
「アンの娘リラ」ー赤毛のアン・シリーズ10ー感想その2 リラちゃん軸/ブライス夫妻について
「アンの娘リラ」ー赤毛のアン・シリーズ10ー(L・M・モンゴメリ・1921年、和訳 村岡花子・1959年)感想その2 リラちゃん軸/ブライス夫妻について感想その1では、ひたすら長兄ジェムくん/次兄ウォルターくんについて語りましたが、その2記事では本作の主観・リラちゃんと、シリーズ通しての主体であるブライス夫妻(アンちゃん/ギルバート)について。*以下、「アンの娘リラ」のラストシーンまでのあらすじ、及び後日譚を含む作品「⑪アンの想い出の日々」のネタバレあり感想です。未読の方はお気をつけください。*・末娘・リラちゃん(本作開始時14歳・すぐに15歳クイーン学院には進学せず、戦争期間を家で過ごす)長兄・次兄とリラちゃんの間に、双子の姉たち(ナンちゃん/ダイちゃん)&三男(シャーリーくん)が居ます。一家における圧倒的末娘であり、家族の中では赤ちゃん扱いされ続けているが、スラッと手足の長い、自他ともに認める美しい女の子。本作開始時には、上の5人に比べ勉学等への志が低く「兄弟の中で唯一野心がない娘」との評を受けていましたが、実際には「組織体としての『家庭』」への意識が非常に高い子で、戦争が始まると、家に唯一残る子どもとして、周囲の感情変化を敏感に察知し、優れたバランス感覚を発揮し始めます。アンシリーズは、原題が「Anne of Green Gables」「Anne's House of Dreams」と、その時々のアンちゃんが、住んでいる土地や家に帰属する体裁で整えられており、本作はシリーズを引き継いでいるからこその「Rilla of Ingleside」というタイトルであり、まさしくこのタイトルに集約していく形で、見事にまとめられた1作だと認識しています。以下、私の受けた印象ですが…リラちゃんが生まれた段階で、ブライス家は既に医師一家としての基盤を整えており、上に5人も兄・姉が居て、女中スーザンも含め総勢9名の大家族であったため、彼女にとってのそもそもの「家庭」の定義が、理想的且つ社会的責任を負ったいち組織体なのだろうと思います。リラちゃんは社会を見るような目線で「家庭」を捉えている…ある意味で非常に仕事脳の娘だな、と思って読みました。リラちゃんは、本作冒頭より「兄の中でウォルターくんが一番好き!」としきりに言いますが、個人感情ももちろんあると思いますが、その背後には「組織体としてのバランスを意識した行動」である側面が見て取れます。長男が圧倒的な光属性なので、それはそれで組織体として非常に幸せなことなのですが、特に下の男の子たちは「自分よりジェムくん」の意識がありますよね、と。もちろん、両親の次男・三男への愛情が希薄というわけでは決してないのですが、家庭の基盤である両親は「次男・三男が一番!」とはもちろん言いません。家庭としてのバランスがありますので。そこ…両親がやるのは適切ではない部分に対して、自然と周囲がフォローに入ってる…スーザンは「三男・シャーリーくんが一番かわいい!」を本人や周囲に向かっても強調しますし、リラちゃんは「ウォルターは美しくて素晴らしい!」を一生懸命アピールします。すごくすごく気づかいな娘です。戦争が始まってからは、「私は責任がないから」「愛情の希薄な人間だから」と言いながら、振ってかかる様々な事態に対し、自分の感情は二の次でひたすら周囲の人たちの気持ちを最優先して働きかけを続けます。兄たちに何かあると、もちろんリラちゃん本人だってショックなんですよ。でもそこですぐに切り替えて、母のアンちゃんや、兄たちに恋する幼馴染たちの心情を推し測ることに心を砕く姿が読み進めながら泣けて仕方がないところでした。なんていい娘なんだ…!ジェムくん出征直後、リラちゃんは赤十字の活動中に行き場のない生後間もない戦争孤児に出くわし、思わずその子を引き取って来てしまいます。「無責任なことはせず、リラ本人が面倒を見るように」と釘をさす父・ギルバートを横目に、リラちゃんは徹底した育児っぷりを、発揮し家族の面々を感心させますが、この思わず現れた成長主体(男の子)に、ジェムくんと同じ「ジェイムズ(通称は差をつけてジムス)」と名付けるあたり、兄・ジェムくん本人への愛情や無事を祈る思い、家族内の大きな不安を少しでも「成長」という希望で慰めたいという彼女の思いが込められているのを感じます。本作が、世界大戦という重い題材を据えながら、それでも尚最終章で愛の幸せな物語として頭にしっかり収まるのは、ジェムくんが長男として間違いなく真っ当な正義を生き抜き、その影で悲劇性を請け負ったウォルターくんの意志と、彼の意志をきちんと汲み取った一家の末娘・リラちゃんがジェムくん帰還までの間、精一杯「ブライス家」を守ろうと心を尽くせたから…各々の役割を目いっぱい遺憾なくやり切り、戦時下で大荒れのブライス家を守り切り、未来を迎えることが出来たからだな、と思います。また、本作はリラちゃん軸として描き切ることで、第1作「赤毛のアン」の要素をリバイバルして昇華するような作りも感じます。男の子が望まれていたのに、孤児院から女の子が来た…という赤毛のアンのとっかかりに対し、状況はかなり異なりますが、望まれるべき跡取り息子(たち)が戦地で命がけの戦いをする中、自分ができる限りでこの家を支えなければと奮闘する末娘の感情は、ある意味で「赤毛のアン」のリバイバルと受け取っています。また生後間もない赤ん坊という、アンちゃんの生い立ちに近しい孤児をリラちゃんが引き取り、時間と心を砕いて愛情をもって世話するという筋道は、本作がシリーズの締めであるという意識を感じます。・ケネス・フォード(ウォルターくんと同い年くらい?首都トロントの一流大学生)通称ケン。「夢の家」で登場したレスリー/オーエン夫妻の長男。両親譲りの美貌の青年。上記、ブライス家の主要トライアングルを「家」主体で魅せながら、物語を少女漫画的ベクトルで串刺すのが、ケンくんとリラちゃんのひそかなラブストーリー軸です。ケンくんは、血縁でないはずなのに何故か一番ギルバートみを感じさせる青年で、ブライス家の中でまだまだ子ども扱いされている15歳になったばかりのリラちゃんの、いち女性としての魅力…美しさ・愛情深さに誰よりも早く気づいて手を出し…アプローチをし始めたところで、大戦が勃発。足のケガで少し遅れたタイミングで、ほどなくケンくんも出征することになります。欧州戦線へ加わる直前、わずかな時間プリンスエドワード島へ立ち寄ったケンくんは、ジムスくんを抱くリラちゃんの姿(マドンナ)を見て、自身の気持ちを確かめるとともに、彼女にキスして「自分が帰るまで誰にもキスさせないで」と約束して去ります。このシーンは、2人の関係性に何も気づかず良かれと思って超邪魔に入るスーザンも含め、シーン作りの上手さに感嘆しました。出征前のウォルターくんと、母(アンちゃん)にひそかに打ち明けた他には、2人の関係には誰も気づいておらず、各々が内に秘めたまま物語は展開します。リラちゃんは、都会のモテモテ一流大学生であるケンくんが本気なのかの確信が持てず弱気になりながらも、出征直前の他の求婚者のキスの求めを、悲痛な思いを持ちながら断る等、彼との約束を守り続けます。そして本作ラスト、戦争が終わり、ジェムくんも帰って来て、4年半育てたジムスくんも親元へ返し、兄/姉/幼馴染たちはあるべき場所へ向かい…ひとり、今後の行く宛てを模索するリラちゃんの目の前にケンくんが現れるところで締めを迎えます。この、リラちゃん軸での爽快なまでの「キュン」締めは唸りました。リラちゃん目線で一瞬誰か分からない…雰囲気の激変したケネスくんが、戦地でさんざん苦労をして、でもリラちゃんを迎えに来ることを心の支えにしてここまで戦い抜いてきたことがきちんと強烈に伝わって来るんです。リラちゃんは、兄弟/幼馴染たちの中でもとりわけ年が離れた末娘で、兄姉や幼馴染たちそれぞれに対してリスペクトを持ちながらも基本フラットで全体バランスを気にする性分だからこそ、本作のような「群像劇」を串刺す主観として最適だったのですが、彼女自身には、取り立てた「腹心の存在」が居ない状態でした。ウォルターくんが、戦争に対する弱音を垣間見せてくれることに喜んだり、自分しか頼れる人が居ない孤児のジムスくんに対する徹底的な責任感・愛情の注ぎ方も、リラちゃんが「誰かのいちばん」になりたい、尽くしたい娘である面が見て取れます。4年半、ひたすら家族のため・ジムスくんのために「自分の感情/欲求は二の次」で尽くしてきたリラちゃんが、ラスト、ケンくんが現れた瞬間に「自分」の感情を一気に開放して、「この人のところに行きたい」と人生の道筋を決められたのがとても自然に感じ取れました。すごいシーンでした!長男・ジェムくんもこれから2年間大学医科が残っているので、フェイスちゃんとの結婚はその後だろう…とのことで、これはまさかの、末娘から「じゃっ!」って遠くの首都・トロントに嫁に行っちゃう…ギルバートぎゃふん案件だろうな、と思って読みました。・ブライス夫妻(アンちゃん/ギルバート)本作では、主役の座を子どもたち世代に譲っている体ではありますが、やはり読者が一番顔色を窺ってしまうのが、この2人。女中・スーザンも含め、可愛い可愛い息子たちを戦地へ送る苦しい役どころでした。本作開始時、ギルバートは50歳を過ぎたところ…だと思います。兵役募集対象が18~45歳(?)とのことで、既にその対象に含まれていなかったわけですが、そもそもこの年齢設定自体ひねってあるところだと受け取っています。モンゴメリさんが1974年生まれとのことなので、1914年の戦争開始時は40歳…つまり、ギルバートとアンちゃんは作者よりも7~10歳ほど年上の設定なのですが、1作目・赤毛のアンは当然自身の幼少期を思い出しながら描き出した物語だと思いますので、本来的には、作者とアンちゃんはほぼ同年代と考えるのが自然だと思うんです。ただ、もしアンちゃん40歳で戦争が始まったとしたら、ギルバートは43歳…村医の重責を負う彼が、戦争開始直後に真っ先に志願兵として出征するのは違和感がある点、子どもたちも、長男ジェムくんがせいぜい13歳くらいである点を考えると、本来的にはギリギリのラインで、ブライス家の男性陣全員出征することはなかったのでは?と。この部分は、戦争開始時に子どもたち世代が兵役の想定年齢ドンピシャになるように、ジェムくんを起点として、シリーズ全キャラクターたちの年齢が7~8歳繰り上がったのかな?と感じました。長男ジェムくんが、兵役に就いたのが21歳…ここの年齢設定も絶妙で、ジェムくん/ウォルターくんに関しては、戦争開始時に20歳を超えていましたし、賢く、きちんと分別のつけられる子たちですので、親としても本人の意志を尊重し、押さえつけるようなことは出来なかったのも納得できます。納得…そう、納得して読み進めている…はずなのですが、本作を読んでいる間中、なぜか私はずーーっと怒っていて。私は、本シリーズは基本的にギルバートになって読んでしまっているのですが…本作は読んでる間ずーーっと、ひたすらに無力感が凄いんですよ。ギルバートは、本当に自我と(自身の)理想形への引きが強くて、作品を作り変えてくる(自分に引き寄せる)パワーを持ったキャラクターだと思っています。しかし、先に書いた通り本作は子どもたち世代が主役で、彼らの意志が一番大事ですので、作者がギルバートが暴れ出さないように「お前は大人しくしてろ!ハウス!」と、様々な設定で黙らせにかかっているな、と感じます。先述の息子たちの年齢設定とかですね。ギルバートはちゃんと大人しくしてましたよ…ですが、やっぱりギヅがっだ!本作の主役主体『ブライス家』は、ギルバートがアテナよろしく女神・アンちゃんを抱き、非常に高い志のもと建国し、一から2人で作り上げた理想の王国です。可愛く賢い子どもたちは、王国でいちばん、何よりも守るべき宝物なわけで、どんなに誇らしい「勇敢な正義」が付随していたとしても、他の「国家」にくれてやれる安いものでは決してない…のに、結局、息子3人全員をなすすべもないまま戦地に送り出し、1人は永久に失われてしまって…。作中ずっと、ブライス家の大黒柱として働き詰めのギルバートですが、作中後半、ウォルターくんの戦死・三男・シャーリーくんの出征が重なってからは …相当ガタが来てる。ジェムくん行方不明の報のあたりでは、表情が薄くなりリアクションが取りづらくなってる様子もうかがえます。この辺の描かれ方が本当に興味深いのですが…本作は基本リラちゃん主観で語られていて、ラストのあたりはリラちゃんの日記に記されている内容として、飛ばし飛ばしでトトトっと情報提示がなされます。リラちゃんは常にお母さんの反応をすごく気にしてるので、(母が繊細な人である点は、家族全員の共通認識)アンちゃんへの言及は非常に多いのですが、ギルバートについてはあまり言及がありません。強くて頼りになり過ぎるお父さんのことは、リラちゃんは心配するまで意識が及んでいない。でも、アンちゃんのリアクションから、間接的にギルバートの状態が想像できるんです。ウォルターくん戦死の報を聞き、ショックで何週間も床に臥せっていたアンちゃんをギルバートはアヴォンリーに連れて行くなど必死に支えようとしますが、シャーリーくんの出征~ジェムくん行方不明の報のあたりになってくると、逆にアンちゃんがシャキーンとし出す。あぁ…戦争に入ってからもずっと気丈に振舞って来たギルバート(やスーザン)に、ガタが来てる…とアンちゃんが認識したんだな、ってところまで想像させるんです。ジェムくんから無事を知らせる電報が入ったシーンの描写も唸りました。電信を受け取ったリラちゃんから、「まるで少女のような」姿でその報を聞いたアンちゃんが、「(仕事で外に出てる)お父さんを電話で呼んで知らせなくてはなりません」と落ち着き払って動くのを見て、リラちゃんが驚くシーン。リラちゃんは「(ジェムくんに)お母さんのために帰って来て…!」と願っていたし、アンちゃんは「ギルバートのために帰って来て…!」と願っていたんだな、と思います。目に浮かぶような緊張感/空気感と、幾人ものキャラクターがどこに一番に意識を向けているのかよく分かる演技/臨場感が凄まじいシーンで、本当に感動しました。私は、本作におけるギルバートのフラストレーションは、最後まで解消されることはなかったな…と思って読み切りました。しかし、ブライス家のその後を垣間見ることが出来る、モンゴメリさんの遺作「アンの想い出の日々」において、孫のギルバート・フォードくん(ケネスくんとリラちゃんの息子)が第二次世界大戦においてトロントの空軍に入隊したのを知って、腑に落ちたというか…「あ、これはギルバートのフラストレーションの昇華だな」と感じました。ギルバート…彼は「正しいこと」を至極真っ当に行うことで、社会的ステイタス/ほぼ一代で大家族を築いた人で、大戦開始時にもし20代だったら、ジェムくん同様真っ先に志願して戦場へ向かった人だと思うんです。でもやっぱり「戦争」は彼にとって未知のもので、「正しさ」が常に揺らぎ時に反転するので上手く立ち回ることも出来ないし、自信も無くなるし…3人の息子のうち、ジェムくんやシャーリーくんは自身の気質と近いところがあるので、もし何かあっても「『正義に殉じた』と納得できる」ところに心を持っていくこともまだできたかもしれませんが…ウォルターくんはもともと自身には似てない、彼独自の文学的芸術的な感性/美学をしっかり持った子でしたので、尚のこと「行かせるべきではなかった」「何もしてやれなかった」というやり切れない思いが強く尾を引くだろうな、と。息子たちを戦地に行かせるくらいなら、代わりに自分が行ってやりたかった、銃弾の楯になれるものなら、なってやりたかった…という思いは当然あるでしょうし、ただ実際には、ギルバートは戦場自体を知らないので、息子たちが何を感じ、何を考えていたかを推し量ることも出来ないし…「想い出の日々」の中で、他の孫たちは存在だけふわっとの示すに留めているのに対し、ギルバート・フォードくんだけやたらと詳細に、トロントで空軍志願したことが描かれている…祖父・ギルバートのやり切れないフラストレーション、戦場に向かいたかった思いの昇華、更にもっと言うと、戦時下のあまりの無力さへの反省を踏まえ、それこそ「真っ当に」、戦争で采配を示せる社会的地位を勝ち取りに行ってるんだろうな、と私は受け取って読みました。※妹 追記※モンゴメリさんの遺作「アンの想い出の日々」においては、アンちゃんが亡き息子・ウォルター君が残した詩を家族に読み聞かせたり、続きを綴ってみたり…という場面が描かれています。戦争で息子を失った哀しみを、アンちゃんの方では「詩の中に息づいている、息子の想いとの対話」で昇華しているというか…やっぱりアンちゃんは、ウォルター君と美的感覚が似ている部分があるので、「あなたがこれを望んだんだよね」と、息子の生涯・顛末を認めてあげなければ…という想いが強かったのだろうな、と感じました。長くなりましたが…とりあえず、一番言及したかったところは言及できたかな?他にも、スーザンの奮闘や犬のマンディの根気とジェムくんへの忠誠…感想を述べなければならないところは山ほどあります。…恐ろしき群像劇です!ただもう…子どもたちも皆、「理想的な、素晴らしいブライス家」が大切で誇らしくて、この理想の一家を守りたいんですよ!それが痛いほど伝わってくるから、泣けます!面白かった…感動しました!号泣でした。繰り返しになりますが…アンシリーズの中で…「『リラ』がマイベスト」です!!by 文章:姉 イラスト:妹◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.04.13
コメント(0)
-
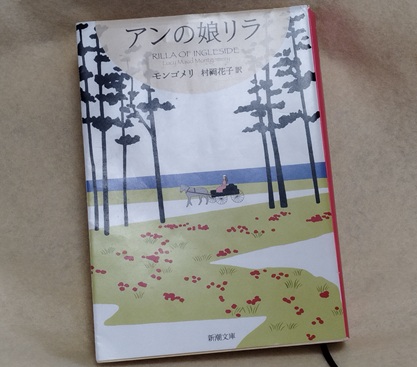
「アンの娘リラ」ー赤毛のアン・シリーズ10ー感想その1 ジェムくん・ウォルターくんの配置について
「アンの娘リラ」ー赤毛のアン・シリーズ10ー(L・M・モンゴメリ・1921年、和訳 村岡花子・1959年)感想その1 ジェムくん・ウォルターくんの配置について原題は、Rilla of Ingleside。イングルサイドは、ブライス一家の住む大きなお屋敷の名前です。1914年、プリンスエドワード島フォア・ウィンズ港・グレン・セントメアリ村。ブライス医師一家の6人の子どもたちも大きく成長した。兄や姉はレドモンド大学/クイーン学院の高等教育に進む中、責任や野心のない末娘リラは、15歳になり、この先10代後半の青春時代を謳歌するつもりでいた…しかしその矢先に第一次世界大戦が勃発。英国参戦にカナダも追随し、志願兵として長兄・ジェムや幼馴染が戦地へ向かうこととなった。当初はすぐ終戦するという楽観的な見方もあったが、諸国参戦により戦争の規模は拡大・長期化。戦況が混沌とする中、カナダ中の若い男性たちが次々と出征していく。詩と美しいものを愛する次兄・ウォルターも出征の意志を固め…。2009年に作者・モンゴメリさんの遺作である『アンの想い出の日々』が公表されるまでは、本作が赤毛のアンシリーズの(本編時系列的な)最終作だったのだと思います。まだシリーズ全作をしっかり読めたわけではないのですが、アンちゃんの人生軸/物語時系列はおおよそ把握したところで…描きたいものが明確で、描写のキレ・読み応えがずば抜けている!と妹と話しているのが、①赤毛のアン、③アンの愛情、⑩アンの娘リラ の3作です。個人的好みという観点においては…⑩リラが、マイベスト!…凄い!名作って本当に凄い!こんな凄まじいものがあったなんて!どうしてこんな…戦争題材で、悲劇もいっぱいあって、だけど「愛」ばっかり読み手の心に焼き付くんだ!?主体数も数えきれないほど登場して来て、そこかしこに様々な関係性や激情があって、…でも、きれいに1つの物語として、最初から存在していたみたいに頭にすっと入って来て度肝を抜かれました。*以下、「アンの娘リラ」のラストシーンまでのあらすじ、及び後日譚を含む作品「⑪アンの想い出の日々」のネタバレあり感想です。未読の方はお気をつけください。*本作の主人公は子供たち世代であり、ブライス家の末娘・リラちゃんの主観で物語が語られます。主人公はリラちゃん…とも言えますが、個人的には本作は「群像劇」という印象が非常に強かったです。群像劇というか…言ってしまうと主役は「ブライス家」という組織体かな、と。ギルバートとアンちゃんが、一代でその土地における圧倒的信頼を勝ち得ながら、個性豊かな6人の子どもたちを、愛情持って堅実に育て上げた一家… 非常に志の高い、意識の高い「理想的な家庭」…いち組織体。頼られまくる立派な医師の父と、美人で聡明で子どもたちに精一杯の時間を費やす愛情深い母、料理上手で家族の一員である女中・スーザンに囲まれ、子どもたちは何不自由なく、周囲から羨まれる環境で育ち、また、両親ともに非常に頭脳明晰なので、一家全員子どもたちも皆優秀。このあまりに真っ当で理想的な「ブライス家」自体、非常に特色のある組織体だと思います。そこに降っかかってくる…第一次世界大戦という、いち個人・いち家族ではどうにも抗いようのない大きな出来事。世界大戦など前代未聞なため、どんなに頭の良い人でも事態の予測は不可能ですし、上手く立ち回ることなど誰もできません。もし「うまく立ち回れた人」が居たとしても、そんなものは全部結果論です。この事態に対して、「ブライス家」が組織体として…というか、組織体の中の個々人が、いかに向き合っていくか…絶妙なキャラクター配置の中で、子どもたち一人ひとりが目いっぱい考えて行動します。6人の子どもたちの配置自体、本作・リラを描くことを念頭に構成されていると感じます。基本的には、長男ジェムくん、次男ウォルターくんの2軸で大戦といち家族の関係性を作り、それを「ずっと家(イングルサイド)に居る」末娘のリラちゃんの主観で切り取って、魅せる。ここのトライアングルが本作を形作る一番の土台だと思っています。以下、各キャラ/関係性について。・長兄・ジェムくん(本作開始時21歳・レドモンド大学で4年の文科卒業後、医科1年目)母親譲りの赤髪且つ父親譲りの圧倒的リーダーシップを兼ね備えた光のスーパー長男。大学の医科在籍中で、誰の目にも明らかな「ブライス家の跡継ぎ」。ブライス夫妻の第1子(女の子)は産後すぐに亡くなってしまい、その悲しみも背負って誕生した待望の第2子であり、実直で、両親や弟・妹たち/周囲の人々にも素直に愛情を示す性分のため、老若男女+犬・近所の幼子までみんな彼にメロメロ。近所の牧師館の幼馴染4兄弟のうち、美人でしっかり者の長女フェイスちゃんと相思相愛の仲。ジェムくんがあまりに「理想的な跡継ぎ」として盤石なため、下の弟・妹たちは興味分野方面を結構好き勝手やってる印象です。本作の大きなとっかかりの一つとして、「この『スーパー跡継ぎ』が戦争に行く」という組織体にとってあまりに葛藤のある状況を描く点があったのだろうと受け取っています・次兄・ウォルターくん(本作開始時20歳・クイーン学院卒業後、2年の教職を経て大学入学)眉目秀麗・文学的才能に富み、詩と美しいものを愛する心優しき青年。勉学に打ち込み過ぎて、父親と同じく腸チフス(重症)にかかった経緯があり、家族に体調面を心配されている。戦争勃発時は病気後で募集対象ではなかったものの、1年後、周囲から兵役忌避者の烙印を押される状況に苦しんだ後に入隊の意志を固める。塹壕で書き記した詩が世界中で脚光を浴びる中、1916年・フランスのソンム戦線で勇敢に戦い、戦死。本作のとっかかりのもう一つとして、大戦中の戦死後に名を馳せた詩人からのインスパイアがあったようです。1917年発表の『アンの夢の家』の冒頭には、ルーパート・ブルーク(~1915)という詩人の詩が引用されており、彼自身や彼の残した詩の与える影響力に感銘を受けたモンゴメリさんが、大きなテーマとしてこの要素を取り扱ったのだと受け取っています。・ジェムくん/ウォルターくんの配置について上記2つのとっかかりは、分解してみると個別のものだと思うのですが、これが、ブライス家の長兄・次兄という配置によってなんとも絶妙に神合わさって…間違えた、噛み合わさっていて、度肝を抜かれました。この2人の配置・作り込みこそ、本作最大の語りポイントだと思っています!ジェムくんとウォルターくんは、表裏一体・光と影の関係性というか…お互いにそれぞれの役割を強烈に認識している「半身」というか…ブライス家というのはどこまでも「理想的な家庭(組織体)」であって、この第一次世界大戦下において、「戦線に出て、国のために勇敢に戦った後に帰還する」も「国のために勇敢に戦い戦死する(詩とともに名は後世に残る)」もどちらも泣けるほど立派な「理想の息子」像なんですよ。1人の人物像として2つの理想像を描き切れないから「2人に分かれた」…。「となりのトトロ」も、初期構想時にはさつきちゃんとメイちゃんが1人の少女でしたが、いち人物像として不整合な面が出てきたため役割を分けた…と聞いたことがありますが、それと似た印象を受けています。ジェムくんは、世間体も含めてブライス家の未来と品格を一身に背負っていますので、どこまでも「正義」に忠実で、戦争が始まると真っ先に志願して出征していきましたし、その上で長期化し混沌とする戦場の中で、なにがなんでも生還しなければならない立場でした。ウォルターくんは、極論、役割として「理想的な息子としての『戦死』」という側面を一身に請け負ったキャラクターだと受け取ってますが、彼自身が「ブライス家で一番大事な息子はジェムくん」って、進んで演出して来るんです。本作を、本作のバランスで読ませ切ったコンダクター/演出家は彼だと思ってます。リラの前作「虹の谷のアン」は、子どもたち世代のキャラクター配置を諸々試行錯誤しているのかな?と感じる作品ですが、この中で、喧嘩を好まないウォルターくんがフェイスちゃんの為に決闘するエピソードがあり、またリラ本編でもさらっと彼女のことを詠った一連の短詩を書いていたことが記されているので、…これ、フェイスちゃん本人は元より、家族/周囲にも悟らせてなかったけど、ウォルターくん、フェイスちゃんのこと好きだったのかな?…と受け取りました。本来、ジュリーくん(牧師館長男)たちと共に大学に行ってても良いウォルターくんが、勉強のし過ぎで死線をさ迷うほどの重病(腸チフス)を患い、進学を延期していたのも、背景に「フェイスちゃん諦めなきゃ」という、彼の中での葛藤があったからでは…?(父・ギルバートと同じこと(by「アンの愛情」)やらかしたんじゃ…?)…切ねぇ!!…でも超イイ子!!上記、憶測&憶測の裏読みでしかないのですが、でも「虹の谷」~からの流れの中で、牧師館の4兄弟との掛け合わせで一番丹念に作りこんでいるのは、ここだと思うんですよ。やっぱり…次兄ウォルターくんの、対・長兄ジェムくんへの感情って、「リラ」で描くべき話筋において一番重要なところだと思いますもん。本作を読んだ際、一番驚いたのが「ハッピーエンドに見えたこと」でした。4年半ほど続く苦しい戦争ですが、途中でウォルターくん戦死の報が届き、そこから18歳になった直後の三男の出征、そして長男・ジェムくんの負傷/行方不明の一報が入ります。最後、読者としても「ジェムくんさえ帰って来てくれたら…!」と祈りながら読んでしまうんです。「次男は戦死したけど、長男は帰って来たからハッピーエンド♪」なんて絶対不謹慎じゃないかと思うのですが、でも「このバランスで正しいんだ!」という大きな意志に押し切られるんです。ひたすらジェムくん帰還を駅で待ち続けるブライス家の飼い犬のマンディや、ジェムくんが大好きで、無事を祈るあまり可愛がっていた飼い猫を供物として神様に捧げるブルースくん(牧師館の幼子)…等、ジェムくん帰還を至宝の出来事に持ち上げる神演出が凄いんです。大けがを負って行方不明になったジェムくん(後に捕虜になっていたことが判明)の帰還が、「神様に感謝したくなる」ほど奇跡的な…言い換えれば「あまりに都合の良い」出来事なのですが、何かしらの意志に導かれるように、「神に感謝しながら」自然と読める。作品に押し切られる。…これはすごいことだな、と感動しまして。作品を司る、これらの演出/印象は何なのかな…と考えると、やっぱり「ウォルターくんの意志」だな、と感じたんです。ジェムくん帰還を誰よりも願っていたのはウォルターくんで、戦場でもずっと、「自分はいいから、病気したとき運よく拾った命だし、何ならあげるから、ジェムは帰してね」って願掛けしてたんじゃないのか…とか、作品全体バランスを見れば、「交換条件をもって神様と取引した」のはブルース坊やじゃなくて、ウォルターくんだったんじゃないのか…とか、あれこれ妄想が広がって…。とにかく本作を読んで一番感動したのは、この力業の「ハッピーエンド」の説得力。はっきりと明確に記されているわけではないし、あくまで「裏読み」の筋道なのですが、でも設定や話筋を俯瞰する限り、一番作り込んである作品の核は間違いなくここ、ジェムくん/ウォルターくん2人の対比だろう、と思って読みました(沼)感想その2に続く!by姉◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.04.13
コメント(0)
-

ふたりのアン・シャーリー🌸アニメ『アン・シャーリー』第1話感想
楽しみにしていたEテレアニメ『アン・シャーリー』第1話観ました🌸画も音楽も、声優さんたちも凄く良かった~‼そしてひとつひとつの演技動作が素晴らしかったです。特にアンちゃんが、喋り倒した後に相手の顔色を伺う描写とか「この娘、会話が続くように喋っちゃう気づかいな所もあるんだな」と感じられて良かったです。1979年の世界名作劇場「赤毛のアン」が50話かけて原作1冊をじっくり映像化したのに対し、今回は全24話で原作3冊分を駆け抜けるそうです。おそらく、最大の見どころは後半の恋愛パート!話はトントン進んで、キャラのビジュアルもどんどん変わっていくんだろうな~と。楽しみです♪新旧アニメ版 2人の アン・シャーリー 🌸じっくり描き比べてみました。いやあらためて、コンセプトの違いが面白いです!高畑勲監督版『赤毛のアン』の方はリアリズム芝居を追求し、モンゴメリの幼少期写真のイメージ等が入れ込まれてるのかなと(想像)新作はラブ描く気満々の少女漫画仕様❤️ギルバートが生涯愛し抜く女性として、健気さや可憐さが強調されてる気がします!今回新アニメ化に際し、原作「赤毛のアン」村岡花子翻訳版シリーズを(とばしとばしではありますが)最後まで読み切りました。一番最初の感想は「なんか…原作のアンちゃんは、名作劇場のイメージとだいぶ違うんだな。こんなに 一見すごく朗らかそうで、でも潔癖で、守ってあげたくなる雰囲気の女性だったんだ… 作中の誰より甲高い声してそう」でした。やっぱり旧1979年版のアニメは、高畑勲監督の天才性が爆発しているというか…いやもちろん原作に忠実なんでしょうが、鼻にかかってぬけない声&訝し気な表情のアンちゃん像とか、命がけで描写してあるおどおどとしたマシュウ像とか、このアニメで確立した(日本における)パブリックイメージなんじゃないかな~と。にわかな人間の超・個人的な意見ですが、原作シリーズのアンちゃんのイメージに近いと感じるのは、今回の新作の方です。原作シリーズ、3巻以降は基本的にアンとギルバートの物語(ロマンス~家庭を築くまで・その後)が主軸に描かれています。ーというか「出版当時、ラブストーリーとして人気だったんだなぁ」と感じる程に、この2人のハイパーラブラブ夫婦っぷりを楽しむ作品になっていきます。(そこに世界大戦が絡んでくるから凄いんですけど)今回の新アニメ『アン・シャーリー』は、もちろん「新たな世代に赤毛のアンを知ってほしい!」というコンセプトも感じますが、それと同時に、「ふわっとしか知らない人たちに(赤毛のアンってこんなにラブストーリーだったんだ!)と言ってほしい」という意気込みも感じています。しかし「アンの愛情」パートの映像化は…すごく難しいと思います。どんな形になるのか、毎週楽しみに鑑賞させていただきます♪by妹アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.04.11
コメント(0)
-
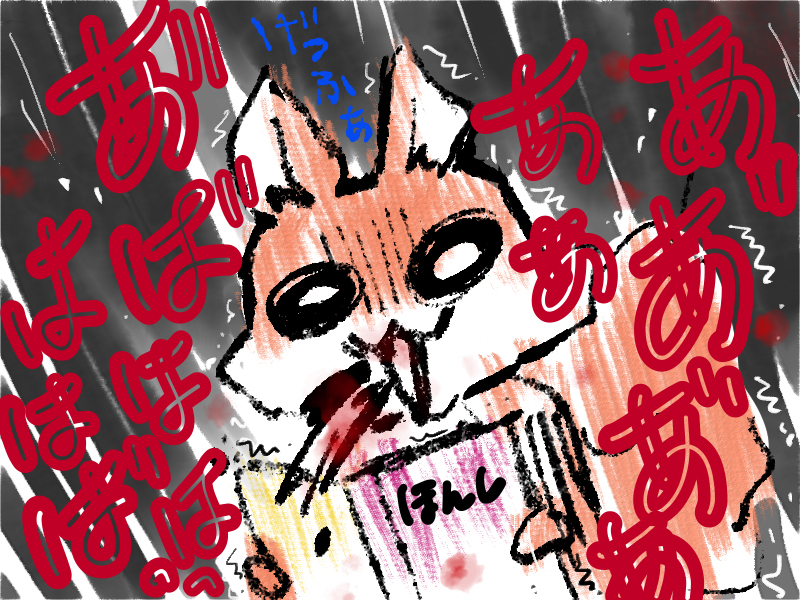
暁のヨナ 46巻 / 第265話・第266話・第267話・第268話 感想 (妹編)
…はぁ。はぁ。なんかもう、どう反応すれば良いのか分からず…簡単な掃き出し感想です。最近は本当に、めちゃくちゃ身構えて&心して花とゆめ本誌を開いております。 しかし毎回毎回「どうしてそうなったぁあ"あ"ああ‼」と絶叫させられてます…草凪みずほ先生の作品を愛読して20年以上の読者がどれだけ展開予想を巡らせてもことごとく驚愕させられる漫画・それが 暁のヨナ…(長文遺言)※以下、単行本46巻収録の下記4話分のネタバレ感想になります。未読の方はお気をつけください‼※第265話「四龍を哀れだと思ってた」第266話「遠い日の景色を追いかけて」第267話「はるかな昔から私の未来へ」第268話「心を縛る秤」◆「緋龍は天界に戻るゆえお前達の役目は終わった」byぐるぐる 「彼女は緋龍王とは違う ヨナ姫として生き抜いてきた」byゼノうぉのれ ぐるぐるぅ…(殺)‼「尊重」ですよ…良い関係を築きたいなら、相手の現状をちゃんと見て尊重しろってんですよ!◆「ゼノの目を見て わかったからいい あとは俺は命の限りヨナを守りに行く」byシンア君 「この時間はご褒美みたいなものさ」byジェハ 「うむ…また会えた」byキジャ会いたかったよ皆ぁあああ‼言いたい放題の龍神(本体)達への怒りで覚醒するとは、なんとも彼ららしいです!そしてシンア君の台詞がさぁ~もうさ~~‼ゼノが皆を盃に誘ったこと、四龍の皆はどう感じてるのかな~と、いやそんな心配はしてなかったんですけども、どんな声をかけるのか気にはなっていまして。…一目ゼノの表情見ただけで、全部理解してくれたんですねシンア君は本当に出来る子優しい子…‼「四龍を哀れだと思ってた」っていうのはゼノの心情かなぁ。でも「思ってた」なので!過去形なので!ほかの皆の力強い言葉が胸に来ました。◆「緋龍はまた地上で愛する者を見つけた 我らのことは忘れてしまった」by黄龍(本体) 「黄龍 お前も来い 緋龍と黄龍のいない天界は寂しい」byぐるぐるえ~~~っと‼はい!つまり… 地上の初代四龍たち(人間)に血を与えた際、他の3龍と違って、黄龍だけは、血と一緒に本体がゼノに宿っていた! と‼ーそう、ちょっと前の描写で変だとは思ってたんです…あれ?龍神様、天界じゃなくてゼノの体の中に居たの…?と。本当です。状況理解するのにちょっと時間かかったけど、本当です‼ゼノの体の中で、腹減り一行と一緒に旅をしてきた黄龍(本体)様…まさかの味方でした‼神様だろうがなんだろうが、求めてばかりで暇してるだけじゃダメってことですね!教訓!◆「神は強大な力で契約を結ぶがそれを反故にすれば強大な力と知性が失われてゆく」by黄龍(本体)痛いトコつかれた途端、歪んで苦しみ始める ぐるぐる三龍+ぷっきゅーもどきたち‼痛ましや。やっぱり無理筋押し通そうとしてる自覚あったんじゃん…。「決まり事を反故し続けると、知性が失われていく」ってあたり、ひやっとしました。これは本当に人間でもそうだと思います。大人になるとまた強く感じる部分です。◆「我が奪った 神に逆らうので罰を与えた… だが緋龍が帰ってくるなら元に戻す」byぐるぐる緑龍 「次々と交換条件を出してくる あなたと契約をしたいのだ 成立すれば力を取り戻せる」by黄龍(本体)完全なる脅迫になって参りました。『緋龍を愛す』とは…?でも皆「体の一部がなくなっても問題ない!」とヨナ姫を励まします。◆「みんな行こう あの闇に向かって飛ぶの いいでしょう? 地獄でも 誰もいない光の世界よりずっといい」byヨナ姫さすが即断即決の我らがヨナ姫!またひとつ、暁のヨナから大名言が誕生してしまった…‼そしてこの辺の疾走感のある漫画表現は素晴らしかったですね~。◆「外を目指すが我も 三龍神の許可なくここを出て どうなるかわからぬ 或いは我が連れ出せるのは ゼノだけ」→振り落とされるヨナ姫&三龍早く言って‼そんな時間なかったのは分かるけど、先に言っておいて黄龍(本体)さん‼◆「ひりゅう… さいごのけいやくだ あれはあなたのあいするもの あなたがてんかいへもどらなければ あれをころす」byぐるぐる緑龍それだけはヤメたげて‼‼う"ぉの"れ ぐるぐるぅ(殺殺殺)‼ヨナ姫は… 自分の手足が無くなろうが、四龍たちの一部が欠落してしまおうが、高華国が闇で覆われようが、全部自分の責任として背負って生きていく覚悟なら出来るんです。ただそれだけはダメッ‼ああぁ嗚呼ああ””‼(イケナイもはや感想ではなくなってきている…)◆「私の「これまで」にあなたがいなかったら 私は存在していない 死なせてたまるか」byヨナ姫ハクヨナの軌跡メモリアル+ヨナ姫アイのハク様メモリアル…‼う”ぁ… 全部のカットに「そうかそこなのか…うんそうだよねそこだよね…うん(泣)」ってなりましたよ…。。◆「私なら ハクを天秤にかけさせます」byスウォン様黄龍(本体)が危惧したように、ゼノだけ地上に帰還。スウォン様とハク様が、ヨナ姫たちの現状を知ることとなりました。キレイな瞳で、さらっと「龍神たちの鬼畜最終手段」を言い当てるスウォン様。さすがです。そして次の瞬間、突如ぐるぐるハンドに連れ去られる我らがハク様ビビったわ‼‼スウォン様がちょっと笑ったのは「こっちが後のこと頼むつもりだったのに、逆に頼まれちゃった」って笑いなのかなぁ?それとも何か打開策でも思いついたのでしょうか…?◆「さいごの慈悲だ ひりゅうに言イ残シたことがあれば 言エ」byぐるぐる三龍 「そうだな… 結婚しますか」byハク様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ちょっと待っこっ心のっ 準備が… ヒェッココでか!ここなのかそうか!こんな…今にもぐるぐるに握りつぶされんばかりで血だらけで…‼でもそうか。「ハクだけは死なせたくない自分が諦めるしかない」って思っちゃってるヨナ姫の気を引くには、確かに効果抜群すぎる「最後の一言」で あるぅ…!ああ遂にこの言葉が来たか…と。待ちわびておりました。いやぁ…万感の想いです。ハク様、ぐるぐるに握りつぶされんばかり&血だらけで死にかけてるけども!こっからどうなるんじゃぁああ‼??最後に…ええっと、私は今回ずっと「感想を書こう…書こう!」と思いながら、1か月何も出来ずに過ごしました。結構このブログでも書いてきたんですが、私は2巻の「ハクを頂戴!」のシーンを読んだときから、ずっとずっと「ハク様がヨナ姫を欲しがってくれるラスト」を心待ちにしてたんですよ!!15年待っていた場面がついに来ました… 嬉しい‼って気持ちももちろん本当なんですが、なんかもう寂しい‼‼本当に終わっちゃうんだなぁ ー寂しい‼って気持ちがじわじわと来てしまって…;なかなか感想を形に出来ませんでした!(馬鹿か)いやいや、まだまだ どんな展開が来るのか分かりませんよね次回も楽しみです♪by妹
2025.04.06
コメント(0)
-

『アンの愛情』感想 ー赤毛のアン・シリーズ3ー 村岡花子訳
まだまだシリーズ全体を読みきれていないですが、思いつくままに感想を。「アンの愛情」ー赤毛のアン・シリーズ3ー感想(L・M・モンゴメリ・1915年、和訳 村岡花子・1955年)私は昔、村岡花子さん訳の「赤毛のアン・青春・愛情」の3冊を読んだところで満足し、その先は放置していました。ずいぶん昔の記憶なので(大学生の頃だったかな?)細かいエピソード/登場人物は覚えておらずただただ「ギルバート、よかったね…!」と強烈に感じた覚えしかなく赤毛のアンとは、副題として~ギルバート、よかったね…!物語~が付いている作品…くらいな大雑把で偏った認識を持ち続けていました。今回妹が読み始めたのにつられて、ポツポツと私も読み直し始めました。基本的にどうも私は(特に恋愛ものは)男性目線で読み進めてしまうことが多く、本シリーズもどうしてもギルバートになって読んでしまうのですが…ただ以前よりずっとずっと、作品全体の構成…それがアンちゃんの主観を軸に作ってあることを拾えるようになってきました。特に…『アンの愛情』。これはすごい。アンの愛情が、赤毛のアン(1908年)・アンの青春(1909年)から間を置き、さらにアヴォンリーの人々を描く短編集(アンの友達・1912年)&他作品の発表を経て、推敲に推敲を重ねた上で1915年に発売された、決定的な渾身作なのだろうと受け取っています。アンちゃんの設定や作中に登場する様々な物事自体、作者・モンゴメリさんご自身の背景や実体験が色濃くにじみ出ていることは明白ですが、特に「愛情」は(祖母を亡くした直後の)1911年に結婚/転居/その後複数回の出産という大きな転機を経る中で形にされているようで、ご自身の実体感した生の感情が生きたまま、しかしアンシリーズのファンたちの声と目線を非常に意識した形で、数年間の推敲を経て繰り出されたものであろうことが想像されます。(少なくとも1・2作目に比べ)『アンの愛情』1冊として、説得力のあるエピソードの積み上げの繊細さがずば抜けていると感じました。もちろんメインで描かれているのは「ラブストーリー」ではあるのですが、その一言でくくるには、あまりに高尚で繊細で深い心理描写がされている。アンちゃんが人生の主軸を何に据えて生きていくのか…何のために生きていくのか、を決定づける重要な1作だと思っています。■『アンの愛情』概要18歳~22歳まで、アンちゃんのレドモンド大学入学~卒業+αが描かれます。大学に入っても、特に文学面では敵なしの好成績を収める優秀なアンちゃんは、一軒家を借りての友達との共同生活も含め、楽しい大学生活を謳歌します。恋愛面でも、聡明で美人なアンちゃんの魅力に惹きつけられ、求婚者が後を絶ちません。(1冊の中で5人?くらいから求婚されてる)結婚せず、貴重な高学歴女性人材としてバリバリ働いていく未来も、誰か良い人(上流階級含)と結婚する未来も、どちらも選べる贅沢なポジションが確立してきます。孤児だった彼女が人生を選択できるポジションに居ること自体、クスバート家が養子として愛情をもって育ててくれた故のものですし、周囲の人々もアンちゃんの幸せを心から願っていて、あとはアンちゃん自身が納得のいく道を選ぶだけなのですが…でも最後の最後まで、なかなか大学卒業後のビジョンが見えてこない。読者も、この娘がどんな人生を歩んでいくのか、なかなかしっくりくるものが見いだせない。それが本作ラスト『黙示録』と題されたアンちゃんの強烈な独白シーンで、そこまで積み上げてきていたエピソードが力強く集約して、アンちゃんが読者おいてけぼりのとんでもないテンションで突き抜けます。■2つの話筋について妹と話し合ったのですが、「アンの愛情」の最大の語りポイントは意図的に、2つの話筋をもって物語が構成されている点だと思います。①言葉で語られる「あらすじ」(恋愛面)「ロマンチックな恋愛」に憧れる「幼い恋愛観」を持つアンちゃんは、様々な形でなされる男友達たちからのプロポーズを全く受け付けない。大学2年の終わり、一番仲の良い&周囲から公認視されていたギルバートに求婚されるも「一番好きだけど愛してない、友達のままでいたい」と言って彼を全力拒絶。理由は「自身の思い描く『理想の恋愛相手像』に当てはまらないから」?大学3年時、自身の「理想」とぴったり一致したロイ・ガードナーと出逢い「これが運命の恋なのかも?」と、彼からのアプローチを断ることなく受け続ける。ーそうこうしている内に「ギルバートに美人な恋人ができた」という噂を聞き、内心めちゃくちゃ動揺しつつも、彼とは少し距離をおいた友人関係を保ち続ける。大学卒業時、ロイ・ガードナーに申し分のない理想的な形で求婚されるが「今 あなたを好きではなかった事が分かった、結婚できない」と断る。酷い。アヴォンリーに帰って来て間もない嵐の夜、ギルバートが過労+感染症で命の危機に瀕していることを知り、強烈に彼を愛していたことに気づく。幸いギルバートは一命をとりとめ、再度アンちゃんにプロポーズ→地に足の着いた&生活に属した「真実の愛」に目覚め、ハッピーエンド本作の概要(恋愛面)を「あらすじ」として説明しようとすると、まず↑こうなります。もちろんこの話筋はきちんとあります。はっきり言葉やエピソードで説明されてますし、アンちゃん自身が後悔・懺悔として上記のような内容を語る一節もありました。また『赤毛のアン』を少女の物語として読み始めた大半の読者にとっても、ロマンチックな恋愛に憧れを抱く「幼い恋愛観」を持つアンちゃん像は非常に分かりやすく、受け入れ易いと思います。だけど…本作はやっぱりこれだけじゃないな、と思います。「アンちゃん、あなたが好きなのはやっぱりギルバートなんだよ!気づいて~!(やきもき)」みたいな読み方をしていた大半の読者が、ラストシーンのアンちゃんの独白のハイテンションに、驚愕させられるというか「完全に置き去りにされる」ように意図的に構成してある。②明言されないながらも、描かれている深層部分の話筋(人生面)口では「理想通りじゃないから」と言って、数々のプロポーズを断り続けるアンちゃん。ただ、彼女の求婚への拒絶の仕方が…特にギルバートからの求婚に対し、心底恐怖を抱いて力の限り拒絶するその態度が明らかに「幼い恋愛観だから」では説明できない次元のものとして描写されています。その①のあらすじで、違和感を感じるのはココだと思います。彼女がギルバートを拒絶した理由は、本当に「彼が『理想の恋愛相手像』に当てはまらないから」なのか?…この理由は、言い換えれば「世の中には、もっと私のロマンスにふさわしい理想の男性が居るはず‼」という、非常に恋愛的野心に満ちたものであるはずなんです。しかしアンちゃんの態度からは、そういったものは感じられません。アンちゃんは、非常にモノローグが多い主人公です。「そこまで赤裸々に言うか」という位、べらべらと雄弁に自分の感じたこと・考えたことを、逐一読者に語ってくれます。それならば… ここまで彼女の頭の中・思考が開示され続ける中で逆に「語られていないこと」の方が重要、という観点から捉えてみるとアンちゃんが、自身の「結婚~結婚生活・その後の人生」を具体的に想い描くことがどうしても出来ない… という一面が見て取れるな、と感じました。ロマンス小説には憧れがあるし「私の理想のプロポーズシーンはこう!」と仰々しく語りますがその先の「結婚式~新婚生活はこうで、そして子供を産んで育てて…」という、ダイアナちゃんや他の女の子たちが「普通に」思い描くであろう結婚後のビジョンを、自分自身のものとして想い描く場面が、全くといっていいほど 無い。「恋愛~求婚」と「結婚~人生」がつながらない。病的なほどに。妹曰く、アンちゃんはそもそも『結婚する気がない』『結婚のビジョンが無い』から、男友達からの求婚はすべて『そこで関係終了』の合図になっちゃってるアンちゃんが結婚したくない理由を考えると、下記の2つが思い浮かびました。A:一つ目は、アンちゃんの「男の子(特にギルバート)と対等で居たい」というプライドのため。アヴォンリーに来てからのアンちゃんのアイデンティティとして「学校で一番優秀な男の子(ギルバート)に、勉強面では張り合うことが出来る」というプライドが自分を支える大きな柱としてあるので、結婚という形で独立性を手放すこと・自身のバランス軸を変えることへの抵抗があるのでは、と。…でもそれにしても、あまりにも『結婚後のビジョン』が無さすぎる。あのギルバートの求婚(1回目)への恐がり方はどこから来ているのかな…と考えると、2つ目の理由として下記にたどり着きました。B:(アンちゃん自身&マリラ達もはっきり気づけていないところだと思いますが)アンちゃんが深層心理では「結婚・家族を築くこと」に対して大きな恐怖心というかトラウマですかね…を抱いていて、どうしても思考回路が『結婚』の手前で一気にシャットダウンしちゃうのでは。やはり結婚・出産直後に悲惨な運命をたどった実の両親の経緯が大きいと思います。アンちゃんは生まれて数か月後に両親を相次いで亡くし、(お呼びでない存在として)肩身の狭い思いをしながら育ち、更には引き取り先においても、一家離散を何度も目の当たりにしてきました。もちろん頭では「結婚してお子さんを産んで育てて、生涯を供にして…」という「幸せな結婚生活~一生幸せな夫婦」が存在することは分かってると思います。ただ、どうしても自分事として想像することができない。でもアンちゃんは、周囲の人が自分に向けてくれた愛情や優しさ・配慮をどんなにささやかな事だって拾っていちいち喜ぶことが出来ますし、どんないたずらな子どもたちだって寛容的に可愛がって、お世話も出来て…絶対アンちゃんは『素敵な奥さん/お母さん』になれるし、この娘が一番願って止まないものこそ、幼い自身にとって全くブランクになってしまった『幸せな家庭』のはずなんです。アンちゃんの深層部分に根付いている「家庭を築くこと」に対する本当に大きなハードル。その部分を、複数人の求婚者たちに対する彼女の反応によってあぶりだしつつそれを飛び越え、幸せに手を伸ばすことができるまでの土壌づくりを、周囲の人物たちの様々なエピソード・観点で積み上げている…『アンの愛情』は、アンちゃんの深層心理まで踏み込んで描写する、本当に繊細で深いラブストーリーだと受け取っています。ここで、今作「アンの愛情」のメインキャラクターであるアンちゃん&ギルバートの2人についての勝手な解釈を語ります。漫画作品でも「想定以上の人気を得た引きの強いキャラクターたちは、自分で勝手に走り出すな」と感じることが多いですが、まさにこの赤毛のアンシリーズはそういった作品だと思います。以前の記事にも書きましたが私は、本当に作り込んであるラブストーリーの読解は、ものすごく難しいことだと思っています。「感情」は、キャラクター周辺環境の設定を繊細なところまでひねり回して、作り込むものなので。現代日本を舞台にしていたとして、持って生まれた能力や性格があって、その上で周辺環境…住んでいるのが都市なのか、田舎なのか、家が家業をやっているのか、サラリーマン家系なのか、またいずれでもないのか、家族構成や兄弟の有無によっても、立ち位置の振り方の意識は大きく変わって来ます。↑これらを、ちゃんと最低2人分描いたうえで、きちんと掛け合わせて、ラブストーリーは成り立つと思っています。ラブストーリーを読む際、私(姉)はだいたい、ひたすら男性目線で読み進めます。一方妹はひたすら女性目線で読み進めるため、いつも見えてるものが違い過ぎて面白いんです。作品鑑賞の後に2人で感想を言い合い、お互いに拾えていなかった部分を補完しながら「作品の全体像の認識」をすり合わせていきます。■ギルバート像(by姉解釈)ギルバートは徹頭徹尾、超優秀且つ判断を誤らない。明確なビジョンを据えて全身全霊で推進していく、目標到達の鬼/超出来る仕事脳人間。バランス感覚もよく、家族都合等で思い通りに行かない場面があっても常に冷静に受け入れ、どんな状況でも目標に向けて最善を尽くすことができる。作品の人気を受け続編を執筆する中で、やっぱりすごく走ったキャラクターだと思っています。コイツの思い描くビジョンが強過ぎる。赤毛のアンシリーズは、最終的に「堅実な医師家庭/女神兼聖母のアンちゃん&大勢の可愛い子ども(天使)たち」という「ギルバートが夢見たビジョン&その延長線上にある大家族像」に行き着いている。ある意味で「ギルバートが夢を叶える話」とも言える。彼の目線からは、不幸な境遇を跳ねのけ、勉学でどこまでも上を目指す気高さ&家族思いの愛情深さを持ったアンちゃんは、心底「女神」に見えている。反面、アンちゃんが「安心」の上に立つことが出来ない娘という側面も掴んでると思う。アヴォンリー中で「優秀な男の子」の代名詞であろうギルバートに終始対抗意識を燃やし、なんとかそれに勝とうとするアンちゃんのモチベーションの根幹にあるのが、マシュウ・マリラの恩に報いたい…プラス面の感情と、その奥底に常に『不安』があるからだと感じる。男の子を所望していたのに、手違いで自分が来てしまったこと、本来目的としていたマシュウの野良仕事の手伝いを、自分は出来ないこと…マシュウ・マリラが全然気にしてないところを、アンちゃん本人はずっと引け目に感じているし、彼女の頑張り方が「そこまでやらなくていい」…2人の想像が及びもしない次元のものなので。ギルバートがアンちゃんにあげたいのは、やっぱり「アンちゃんがここに居ていいんだと『安心』できる幸せな家庭」だと思うし、そのためにしっかり稼げるように、アンちゃんが安心して頼り切れる自分になれるように、絶対にアンちゃんが不安に思うような下手なことはしないし、やることなすこと、どこまでも真っ当且つ清廉潔白で一途だし。ただ、大学2年でアンちゃんに思いっきり求婚を断られて振られ、それだけだったら簡単に諦める奴ではないと思うんですが(彼女が真に欲しているのは『安心できる家庭』だ、という思い込みは依然としてあるため)上流階級の金持ち(ロイ・ガードナー)と付き合われて、アンちゃんがあそこに「安心と幸せ」を見出すよと言うのであれば、自分にはなすすべもない…「人が崩れるのは、『何のために頑張っているのか』分からなくなった時だ」とどこかで聞いたことがありますが、まさしくその「ビジョンの喪失」というか。ギルバートのような仕事脳人間は、勉強や仕事…生活のすべてにおいて、頭を動かすのも身体を動かすのも、まっすぐビジョンに向かって進んでいく構造になっていて、特に彼の場合はまた…14の頃から10年以上に渡り、「頑張る」モチベーションの源にずっとずっとアンちゃん(女神)が居たような、若干信仰心が混ざったスーパー一途な精神構造が確立し切っていたので、いろいろ機能不全に陥ったというか。アンちゃんが大学卒業を迎え、今ころ婚約しちゃったかな~…いやいや自分(医科でまだ3年ある)はそれどころじゃない、死ぬ気で来年の自分の学資稼ぎ(激難奨学金獲得)しなきゃなんだぜ…と夢&ビジョン喪失の気落ちを紛らわそうと、限界を超えるまで勉強に打ち込んでみたら、本当に身体壊して死にかけて(感染症)、たぶん自分でもびっくりした。「アンちゃんを諦めようとする」=「即・死」というものすごく単純明快な(頭の悪い)自分自身のフローチャートを改めて自覚したので、やることは一つだけ。リトライ。■アンちゃん像(by妹解釈)本作をアンちゃん筋で定義づけるとしたら、「世界で一番好きな人から逃げ回る話」かな。アンちゃんは、ギルバートのことを心の底から信頼している。あれだけ目の前の、なんでもないものを慈しんで喜びを見いだせる娘が、誰よりも努力家で真っ当に勤勉なギルバートのやっていることを拾えないわけがない。ずっと見てる。自分には備わっていないリーダーシップも本当に凄いと思ってるし、その反面「地道に学費を稼いで、奨学金もたくさんとって…」と周囲にはひけらかさないけど、裏でたくさん努力しているところも心から尊敬している。ギルバートの努力は絶対に報われるし、どこに行っても当然認められるし、どんな状況が訪れたって「彼は絶対幸せになる」と信じて疑ったことがない。アンちゃんにとってギルバートの存在は、「自分にとっての指標」でもあると思う。16歳の時、学費を稼ぐためにアヴォンリーに留まった時も、2年後に大学進学した時も(もちろん意図的ではないが)アンちゃんが、ギルバートの行く道を追いかける形になっている。「これさえ見失わなければ、絶対に人生に迷うことがない」という、一番信頼出来る指標…灯台の光のような存在 …なのかな、と。そう考えると、果樹園でギルバートを振るときにも、アンちゃんは「世界中であなたが一番好き」とはっきり告げている。この追い詰められた場面で、彼女が叫んだ言葉が真実なんだと思うんですよね。「あたし、そんなふうにはどんな人にだって好意は持てないわーそれだから、あたし、好きなことにかけては世界じゅうのだれよりもあなたがいちばんなのよ、ギルバート。あたしたち、お友達のままでいなければいけないわ、ギルバート」大好きだけど、ギルバートがアンちゃんの望む「対等」な関係を崩そうとしてきているのが分かるし、プロポーズのその先が真っ暗で見えないから、とにかく怖い。周囲の人々の「この2人は結婚するでしょう(半確定)」という生暖かい目線も耐え難かった。だって、そもそもアンちゃんは「結婚したくない娘」なので。ギルバートとの関係破綻から半年後、突然作中に登場して猛アプローチしてきた上流階級の学生 ロイ・ガードナー。アンちゃんとしては、彼の外見が「理想の恋愛相手像・王子様像」と合致していたためときめきを覚えたのは本当だし、ロマンス小説みたいなプロポーズシーンを演出してくれれば自分も「はい」と言えるのかな…?という淡い期待はあったんだと思う。アンちゃん自身には「自分=結婚したくない人間だ」という自覚はないので。ただ…その裏には、↓のような下心(本心)もあったんじゃないかな、と思っている。この人と仲良くしてれば、ギルバート本人にも周囲の皆にも、そして自分自身にも「アン・シャーリーとギルバート・ブライスは、対等な善き友達である!それ以上でもそれ以下でもない!」って、強烈にアピール出来るじゃん‼ ーみたいな。無意識的な打算というか。ロイは、素敵なロマンスごっこを演出できる人なので、彼の作るシチュエーションや言葉の数々の作りこみは素晴らしく、アンちゃんはその出来栄えを批評家目線で冷静に楽しんでいた。ーただまぁ結局堂々巡りで、アンちゃんはそもそも結婚する気がないので、ロイに家族を紹介され始めた時点で、もう完全に逃げ腰になってるし、理想的な演出であったとしても、やっぱりプロポーズの先は真っ暗で何も存在しなかった。(そして本当に酷い話だが、アンちゃんは「ロイの人間性」には心底興味がなかった。彼女の意識の中で存在感がないため、作中でもロイ自身の内面性・キャラクター性はほとんど描写されず、読者としてもフワフワした存在としか認識できない形になっている)ロイを傷つけ、皆からの期待や応援を裏切り続ける形にはなってしまったが、大学卒業時のアンちゃんは、彼女が一番望んでいた「アン・シャーリーとギルバート・ブライスは、善き友達である」という共通認識を獲得することには成功している。やっぱり、この娘が思い描く中での「自身の進むべき最良の未来」は、「学校の先生として働きつつ、物語も紡ぎつつ…独身で過ごしていく人生」だったんだと思う。■人生の有限性と結婚後のビジョン先に書いている通り、本作は「アンちゃんの主観」を軸に据え、様々なエピソードが大きく2つのテーマに沿って積み重ねられていると思っています。①人生の有限性、終わりのタイミングの不確実性大学入学後すぐ、アンちゃんがプリシラと、墓地で何気なしに墓碑を見るシーン。84歳で亡くなった方、43歳で亡くなった方…そしてアンちゃんが物語として知っていた海戦の最中、18歳で亡くなった少尉候補生…と、まだ絵空事の遠い出来事のような描き方で「同い年の死」をちらつかせておいて、そこから間もなく、幼友達・ルビーちゃんの病死の描写が突き付けられます。絵空事としての漠然感じた「人生の有限性」が、現実のものとして身に迫ってくるような書き方になっていて、うなりました。人生は有限であり、その終わりはいつ何時訪れるか分からない。若い方でも、どれだけ明るい未来があるはずの人でも、もちろん自分自身にとっても、すぐ目の前に終焉はあるかもしれない。常に未来が「可能性」として存在した「少女の意識」から、「有限」を生きる…「有限の世界」の中で出来ることは限られていて、では自分は何を一番優先して生きていくのか、という「大人の女性の意識」へ大きく転換するタイミングなのかな、と受け取っています。ルビーちゃんが亡くなる直前、アンちゃんに「結婚したかった、子どもを産みたかった、愛してる人が居た」と語り、彼女が仕上げられず残した刺繍のテーブルセンターをアンちゃんが引き継ぐのも、非常に示唆的な描写だな、と思います。また 物語の中盤、アンちゃんが生まれ故郷を訪れ、初めて実の両親の人となりや結婚生活/自分が生まれた直後の様子に触れるエピソードが挿入されます。両親については、まさしくその終焉は突然で、生まれたばかりの赤子を1人残して逝くという、ご本人たちにとっても非常に不本意で無念なタイミングだったであろうことが想像されます。先にも書いた通り、アンちゃんにとっても「両親の顛末」というのは、無意識下での漠然とした「大きな不安・トラウマ/心の枷」だったのだろうな、と受け取っています。ただ、アンちゃん自身が成長して両親と近しい年齢になったタイミングで実際の場所を訪れ、どんな人たちだったのかを聞いて、手記にも触れることができて、朧げだったところが具体的に肉付いて見えてきたときに、不安も和らいでいくというか…両親たちの行動や顛末も、でもそこにちゃんと幸せがあったことも、「分かる・納得できる」ものとして心に収まって来たのだろうと受け取っています。②結婚後のビジョン先にも書いてきた通り、アンちゃんは自身の結婚後のビジョンがとにかく描けません。大学卒業直後、ロイからのプロポーズも拒絶し、アヴォンリーに戻ってきたアンちゃんは若干自分を軽蔑しつつも「ーさてこれからしっかり(独身で)働いていくぞ!」と、ある意味で一番彼女らしい&非常に落ち着いた心持ちに辿り着いていました。ただそこから、彼女の前に立て続けに「結婚及びその後のビジョン例」がどんどん提示されます。・幼友達・ジェーンの億万長者との結婚・大学時代の友人・フィルの牧師との結婚この2つは、アンちゃんに「結婚」のイメージ像を対比的に見せているのかな、と思います。・お金持ちとの結婚=(暗に)ロイ・ガードナーと結婚イメージ・裕福ではないけど大好きな人と結婚=(暗に)ギルバートと結婚イメージいずれにしてもアンちゃんは、2人の選択を「彼女たちを幸せにするもの」と祝福しています。間髪入れずに目の前に鮮やかに現れる「母となったダイアナちゃん」のインパクト。学業面では「アンちゃんの方が置いて行った」存在だったダイアナちゃん。しかし彼女は、結婚という面で、アンちゃんよりもはるかに先を歩いていました。小説なので、文字でしか書かれてないんですけど…赤ちゃんを抱き、瞳を輝かせている若い女性の神々しい絵面がバッと目の前に浮かんできて、非常に印象深いシーンでした。立て続けに提示されるので、アンちゃんもそれらの情報を咀嚼して、自身の将来像につなげるところまでは全く思い至っていないのですが…でも、同世代の、近しい女友達たちが見せてくれる「『結婚・その後』とは『こういうこと』だぞ‼」という具体的な姿が、アンちゃんが自身の未来を思い描くための土壌を耕し、選択肢の幅を広げる準備してくれているのかな、と思っています。上記①・②のテーマに沿ったエピソードを丁寧に積み重ねて来て、最後の最後のラストシーンを迎えます。■『黙示録』もくしろく(Wikiより抜粋)・『ヨハネの黙示録』とは、『新約聖書』の最後に配された聖典であり、『新約聖書』の中で唯一預言書的性格を持つ書・終末に於いて起こるであろう出来事が記されている。・解釈と正典への受け入れをめぐって多くの論議を呼びおこしてきた書物聖書に詳しくないのでWikiで調べましたが、「世界の終末」の預言が書かれている章とのこと。3週間、知人宅でゆるやかなバカンスを過ごしたアンちゃんは、グリン・ゲイブルスに帰宅後、ギルバートが瀕死の状態であることを知らされます。感染症の重篤な症状が数週間続き「望みはないだろう」と言われ、今夜が峠だと…嵐の夜、自室の窓辺に座り、突如「世界の終末」に直面したアンちゃんが、その胸の内を明かす「独白」シーン。すごいシーンです。文庫の1ページ以上に渡り、強い強い言い回しでアンちゃんが一気に畳みかけて来ます。読者は驚愕&絶句し、圧倒されるしかありません。ここで彼女のハイテンションに置き去りにされてこそ、本作の正しい読み方だと思います。…こんなすごいテンションに、ついていけるわけがない。興味深いのは、この局面において、アンちゃんが「神様、ギルバートを助けてください」と祈っている訳ではない点です。唐突に「ギルバートの死」に直面したアンちゃんは即座にそれを「自分自身の終わり」と定義付けました。自分の終わり…世界の終末を迎えるシーンだから、「彼女の『黙示録』を読んだ」という表現なのかな、と受け取っています。・「自分はずっとギルバートを愛していた」という強烈な自覚・本当はやりたかったこと、本当は居たかった場所の強烈な自覚・ギルバートの居ない世界では、自分も生きていられないという強烈な自覚凄まじいインパクトの語り出しから始まり、そこからどんどん語気がクレッシェンドしていきます。「ギルバートなしでは何も価値はない あたしはギルバートのものであり、ギルバートはあたしのものなのだ」…自分にとってギルバートが「行く道を指し示す光」であったように、「ギルバートにとっての自分も、なくてはならない存在だったんだ」「ギルバートを幸せにできるのは、自分だけだったんだ」「私たちは運命共同体であり半身だったんだ」という強烈な自覚。ギルバートが重篤な状態で苦しんでいた数週間、周囲の人たちは誰も「なにがなんでも一番にアンちゃんに知らせなきゃ!」って動かなかったんですよ。アンちゃんの望んだ関係性:ただの友達 という共通認識が確立していましたから。ここに来て、アンちゃんは自分の身の内から一気に溢れる「後悔の念」の独白をします。世界の終末が今ここで、こんな形で訪れるなら、愛してることを伝えていればよかった。そうすれば、今、臨終に共に居ることが出来たのに…若くして終焉を迎える「のであれば」、力の限り愛すべきだった…というアンちゃんのこの「後悔」こそが、「両親の(顛末も含めた)生き方の肯定」なんだろうな、と感じました。嵐の夜が明け、「東の丘の頂が朝日の初光でルビー色に染まった」という風景描写…本作中で病死した”ルビー”の名を出して美しい風景(朝焼け)を描写し、世界の終末を体験したアンちゃんの主観が「生と死が入り乱れた曖昧な世界線」に立っていることを示唆する描き方になっていて、印象的でした。死の淵に立たされた悪夢の一夜を乗り越え、幸いなことにギルバートは快方に向かいました。動けるようになった途端、彼の方から足繫くグリン・ゲイブルスに顔を出すようになり、再度アンちゃんにプロポーズ! ⇒2人は晴れて婚約します。ーめでたしめでたし。■アンちゃんの生き方について2人は婚約後、3年間の遠距離恋愛を経て&ギルバートの医科卒業を待ち、結婚。(アンちゃんはその間学歴を活かし、島の学校の校長として立派に働いていた)その後のアンちゃんは、医師となったギルバートを支え、6人の子どもたちを育てる…という、非常に『愛と家庭』に振り切った生き方を選んでいます。このアンちゃんの生き方は、1作目『赤毛のアン』の頃の印象から考えると、結構意外性があるというか。もっと文学系・教育系の界隈で、男性顔負けの活躍をするような未来なのかな~と、ふわっと思っていましたが、あ、結構こういう…家庭第一優先の、全力で「奥さん・お母さん」な感じなんだ、と。ただ『アンの愛情』を読むと、彼女がこの生き方を選んだ過程が本当に丁寧に描かれていて、すごくしっくり来ました。アンちゃんにとっては、「独りで立派に働き、生きていく」より、「結婚・幸せな家庭を築いていく」道の方が、心理的ハードルが高かったですし…でも、彼女が本当の本当に望んでいたのは「これ」だよな、とも思います。前述しましたが、アンちゃんはギルバートのことを非常に信頼しています。学生のうちは、たぶん「この人は絶対大丈夫」という意識だったんだと思います。ギルバートは表向きは常に飄々としているというか、弱っている姿・努力している姿を人に見せることを是としないタイプです。アンちゃんも、大学4年時に彼が相当根詰めて勉強しているのをちゃんと見てるのですが、それでも絶対大丈夫だと、過信しすぎていたんじゃないかな、と。「ギルバートに、他の想い人が出来た&婚約した」という噂に胸をかき乱されながらも、「どんな女性と一緒になったとて、ギルバートは絶対間違わない&幸せになる」「灯台の光みたいに、ずっと自分の指標として輝き続けていてくれる」と、アンちゃんは信じて疑わなかったんだろうな、と。それが、いきなり過労&病気で死にかけられて…強烈に「大丈夫じゃなかったんだ」「ギルバートも有限な存在だったんだ」と認識した時に、初めて「自分主体」ではなく「ギルバート主体」の考えに行き着いた、というか。「この人を、自分が幸せにしてあげたかった」と意識が大きく大きく転換したんじゃないかな、と感じました。ここまで来て初めて、アンちゃんがギルバートの思い描く「夢」のビジョン…「2人で築いていく『家庭』」に自然と飛び込んで行けた…「愛と家庭に捧げる生き方」を選べたんだな、と受け取っています。この夢は、アンちゃん一人では到底思い描くことが出来ないものでしたので、やっぱりギルバートが強く強くビジョンを思い描いて、そこに向けて全身全霊で努力したからこそ、たどり着くことが出来たものだと思います。いやぁ~…「アンシリーズ」、心情描写が深いです!それと、1冊1冊の構成パターンが全然違っていて、面白い!ただやっぱりこの『アンの愛情』は飛び抜けて強烈な構成になっていて、脚本好きとしては本当に興味深い1冊だと思いました。少女漫画のお手本中のお手本中のお手本ですね!「名作」って本当にすごい。面白かったです‼by姉(一部解釈&イラスト:妹)◆小説 赤毛のアンシリーズ(村岡花子訳) 感想リンクアンの青春(Anne of Avonlea)1909アンの愛情(Anne of the Island)1915アンの幸福(Anne of Windy Willows)1936アンの夢の家(Anne's House of Dreams)1917炉辺荘のアン(Anne of Ingleside)1939その1:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921その2:アンの娘リラ(Rilla of Ingleside)1921アンの友達(Chronicles of Avonlea)1912アンをめぐる人々(Further Chronicles of Avonle)1920◆モンゴメリ著 小説 感想リンク果樹園のセレナーデ(Kilmeny of the Orchard)1910ストーリー・ガール(The Story Girl)1911黄金の道―ストーリー・ガール(The Golden Road)1913可愛いエミリー(Emily of New Moon) 1923エミリーはのぼる(Emily Climbs)1925エミリーの求めるもの(Emily’s Quest)1927◆赤毛のアン 関連本 感想リンク赤毛のアンの手作り絵本 / 松浦英亜樹 さんのイラストについて赤毛のアンシリーズのコミカライズについて
2025.03.29
コメント(0)
-

旧尾崎テオドラ邸一周年記念展示『不思議な少年 山下和美展』に行ってきました!+α
旧尾崎テオドラ邸は、世田谷区にある非常に古い洋館だそうで、数年前、取り壊しの危機に瀕した際、漫画家の山下和美先生が買い取り・改修&保存に乗り出されて、昨年・2024年に漫画関係のギャラリーやカフェとして運営を開始されたそうです。経緯やプロジェクト自体は、ネット情報などでちらちら見ておりました。今回、別件で東京訪問する予定があり、ちょうど大好きな『不思議な少年』展が開催されていると知って、いそいそと初訪問してきました。旧尾崎テオドラ邸一周年記念展示『不思議な少年 山下和美展』(2025/3/8~2025/4/8)山下和美先生の作品は、ほかの作品もちらちら読んでおりますが(ランドもすごく好き)、やっぱり一番好きなのは『不思議な少年』シリーズ!どこの時代、どんな場所でも自由に行き来する「不思議な少年」が、人間の生きざまを外から見つめたり、時に大きく干渉したりする読み切りシリーズ。単行本は実家に置いてありますが、数年に1度は必ず読み返したくなる傑作シリーズです。1篇1篇、どれもこれもほかでは見たことがないような超名作揃いなんです。突拍子のない自由な着想の世界観でも、風に乗せられるようにすっと流されて入っていけて、その中で、毎話爆発するような強烈な感情やシーンが心に焼きつくんですが、やっぱりすっとまた別の世界に飛んで行けて…。*以下、写真ログです。展示室内も(一部除き)写真撮影可だったため、掲示物多数です。今後訪問予定の方はご注意ください。*旧尾崎テオドラ邸。閑静な住宅街の中に、いきなり現れるライトブルーの洋館は、目立ちました…。そしてとにかく山下和美先生の作風や「不思議な少年」シリーズに“合ってる”!1階は売店&カフェ、2階がギャラリーになっていました。カラー原画(水彩メイン)や白黒原画がいっぱい!カラーイラストは、大胆でとにかく空気感がすごく伝わる絵が多い!と思いました。絵画鑑賞は、妹の解説がないと、自分が何に感動してるのかも上手いこと言葉にできないんですが(鑑賞眼なし)…でもどの原画も風を感じてすごく素敵でした。カラーイラストは、やっぱり青の印象がすごく強かったですね。(経年でも残りやすい色なのもあると思いますが。)ショーケースは引き出しになっていて、こちらにも原画がみっちり。第37話「波多野圭」は全白黒原画が展示されていました。凄い見ごたえ!見開きの少年の語りシーンがグッと来ます!1階で『不思議な少年』の好きなエピソードにシールを貼る人気投票を受け付けていました。私は、第9話「リチャード・ウィルソン卿とグラハム・ベッカー」に1票。購入した図録に、山下和美先生と本作立ち上げ時の担当様との対談が掲載されていまして、担当様が「これは製作段階~出す時までずっと「これでいいの?」と違和感があった作品。でもアンケートはすごく良かった」と紹介されていて、山下先生も「これが一番面白いと言ってくれる親戚も居るが、なんでそう言ってくれてるのか分からない」とおっしゃっていて、興味深かったです。私が本エピソードをイチ推しする理由は、流氷の世界から生還を目指すという極限の状況、そこに置かれた2人の男性…走馬灯のように駆け巡る少年時代の記憶と疑心暗鬼…そして、悲劇のような喜劇のような衝撃のラストシーン。少年の困惑の表情と、相反して安堵と納得・悟りに満ちたウィルソン卿の穏やかな表情…という、形容しがたいウラハラウラハラな人間心理が、まさに「人間って不思議で面白い」という『不思議な少年』シリーズの真骨頂!を感じるから です。第11話「由利香」もとても印象的なエピソードで大好きです。投票では、どちらにしようかとても迷いました…。直筆のカラーイラスト原画やミニサイン色紙も展示・販売されていました。手の出せるお値段ではなかったですが…どのイラストも雰囲気があって素敵でした…!売店では、上述の図録を購入しました。とにかく先生と担当様の対談が読みごたえがあります!読者が、「不思議な少年」の魅力とは「まさしくこれ」だな、と感じている部分について、どのような考え方で生まれてきたのかがよくわかるお話ばかりで、すごくしっくり来ました。旧尾崎テオドラ邸…今後も漫画作品をメインに展覧会が開かれていくのかな?洋館自体も素敵ですし、この空間で鑑賞する原画はより高尚さを感じて素晴らしかったので、また機会があれば、是非訪れたいです。テオドラ邸の予約時間まで周辺散策をしていました。グーグルMAPで位置を確認していたところ、テオドラ邸のすぐ真横、豪徳寺という大きなお寺があるのを見つけて伺いました。(そういえば乗降するのは小田急線の「豪徳寺駅」…これか!と思いました。)井伊家菩提寺 且つ 招き猫の聖地として有名…と気になるワードがたくさんあったもので。招き猫がインスタ映え?で外国人観光客たちに大人気。猫もいっぱいいましたが、それよりも本当に観光客がひっきりなしにいらっしゃってて、そちらの方に驚きました。猫も面白かったですが、個人的には井伊家の大名墓群が興味深かったです。整然と並ぶ歴代藩主たち(&親族+家臣たち)のお墓… 一番奥には、桜田門外の変で有名な第13代井伊直弼のお墓がありました。井伊家のお墓は、ここのほかにも領地・彦根等に2か所ありますが、すべて合わせると歴代藩主は全員揃う、と説明の立て看板がありました。譜代大名筆頭の名門さが垣間見えますね。(ちなみに、彦根城のキャラクター・ひこにゃんはこの寺の招き猫/白猫伝説がモチーフだそうです。なるほど)もう1か所、線路を渡った先にある世田谷八幡宮も見てきました。源義家が~とか解説に書いてありましたので、とても古い神社なのかな?江戸三相撲の名所!と記載があり、神社入り口に、ローマの劇場のような形の相撲場があって驚きました。ザ・江戸!を感じる神社・寺院でした。なかなか知らない名所も訪れることが出来て楽しかったです。by姉
2025.03.23
コメント(0)
-

らんま1/2コラボレーションカフェ「猫飯店」&ポップアップショップに行ってきました。
リアルタイムらんま1/2を満喫中です。同名古屋PARCO内で、らんまイベントが2つも開催されているとのことで、行ってきました。らんま1/2コラボレーションカフェ「猫飯店」&ポップアップショップに行ってきました。■「猫飯店」:2025.2.21~2025.4.7名古屋PARCO 西館8F THE GUEST cafe&dinner作中で、シャンプーちゃん(&おばあちゃん)の営む中華料理屋『猫飯店(ねこはんてん)』をモチーフにしたカフェです。初報が出た時から、是非行きたい!と思っていました。店内、にぎやかで可愛らしい装飾が素敵でした…!イメージとしては、作中の大衆向け店舗イメージより、高級料理店寄りのイメージでしたね。料理は妹と2人で3品注文しました。どれもこれも絵面一発オチ狙い!的な見た目の料理ですが、実際に食べてみると、意外なほどに皆美味しくてびっくりしました。・早乙女玄馬のあんかけオム炒飯卵炒飯の周りに、少し焼いて固めたメレンゲをコーティングしてパンダを表現した、かなり手の込んだ料理です。注文から提供まで、若干時間がかかりました。すごく美味しい…んですが、食べてるとだんだん「黒色(あんかけ)」に精神がやられて来ます。・シャンプーの愛妻弁当 子ぶたの広東風焼きそば人間(良牙くん)と知らず、シャンプーちゃんが乱馬くんのために調理した黒豚料理(風の焼きそば)※幸い生焼けだったようで、良牙くんは一命をとりとめた。よかった店員さんが、作中のシーンにちなんで、銀のカバー(クロッシュっていうのかな?)を開けるところから再現してくれました。お肉や各種野菜に丹念に下味がつけられていて、たいへん美味しかったです。・久能先輩の「おさげの女」に捧げる 花束ジェラートwithフレンチトースト見切れちゃっているんですが、右手にバラのジェラートがあります。料理を頼むと、こちらも作中のシーンにちなんで、店員さんが「おさげの女へ」と書かれた果たし状風の短冊を持って来てくれます。着色料?で黒くしてあるフレンチトーストはどんな味なのか想像できていませんでしたが、バラジェラートとの食べ合わせもばっちりで、すごく美味しかったです。私たちが訪れたのが休日のお昼という、絶対に混む時間帯だったので、AM11:00~の開店より30分前くらいから待機列に並んで、3組程度の第一陣として入店させてもらえました。料理自体凝ったものが多く、調理・提供にはそこそこ時間がかかるようでしたので、間違いなく混み合う日程で訪れるのであれば、なるべく早めに動いた方が良いかな、と感じました。料理も一品一品丁寧で、満足度がすごく高かったです!■ポップアップショップ:2025.3.7~2025.3.23名古屋PARCO 南館10F イベントスペース大きなPOPがたくさん置いてありました。写真を撮りまくり。アニメ制作のMAPPAさん自身で展開されているポップアップショップなのかな?本ポップアップショップの上記メインビジュアルを、妹がとても気に入っていまして、「このショップは絶対に行きたい!」と前々から口にしていました。今回の新アニメの特色を感じさせるように、あかねちゃんを立てて中央に配し、男乱馬くん&女らんまくんどちらと並べてもばっちり決まるデザイン、また、柔らかさを感じ取れる描線が素敵!…とのことです。購入グッズ!(猫飯店分も含む)とにかく乱馬くん&あかねちゃん&女らんまくんを並べたい欲に溢れたセレクトですね。第1期EDアニメーションを担当された北村みなみさんのイラストがとても可愛らしくて、グッズが欲しかったので、購入出来て嬉しかったです!(トレーディングステッカーも、メインカップルの2ショット多という引きの良さでした)いや~、行けてよかったです!楽しかった!リアルタイムらんま1/2!機会があればまた諸々イベントに参加して、幸せを噛みしめたいな、と思っています。by姉
2025.03.16
コメント(0)
-

『 らんま1/2 SSC完全復刻BOX 』購入しました!
2月に入り、自分たちが昨年の夏~冬にかけてやらかした様々な所業を突き付けられていました。訳:夏~冬にかけてポチってしまったグッズ諸々が2月に一気に届いたのでビビってます。ーでも!これはしょーがないでしょう‼(いつも言ってる)らんま1/2 SSC完全復刻BOXが届きました‼はうぁ~ 壮観…‼最初は「欲しい‼欲しい…けどっ 金額が…💦」と様子を見ていたのですが、自宅にあるらんまコミックスを引っ張り出して来たら…20年以上前にブックオフで購入したもの&ボロボロの状態であることに気が付きまして。(中学生が集めたものだしね)(そういえば新装版やワイド版が出た時も「なんか馴染まなさそうで違う」ってスルーしちゃったしね)…買うしかなくない‼⁉結果:買って 良 か っ た…‼こちらは裏面です。コミック本体38冊+2つの収納BOX+得点の複製原画2枚入冊子 +店舗購入特典のキャンバスボード!どれもこれも嬉しい!複製原画は筆致を感じることが出来る位見ごたえのある印刷で、箔押しの装丁も美しいです古いコミックと比較してみました。経年劣化の黄ばんだものも味があって良いのですが…新しい紙に印刷されると、画面が活き活きしているような印象が…する⁉やっぱり名作は何度でも再販されるべきなのですね!またじっくり読み返したいなぁ。「らんま1/2」って パラパラ眺めてるだけでもう…なんか画面のパワーが凄まじいんですよね…!by妹
2025.03.08
コメント(0)
-

「赤毛のアン」シリーズを読み始めました+ TVアニメ「アン・シャーリー」期待してます。
「赤毛のアン」シリーズを読み始めました+TVアニメ「アン・シャーリー」期待してます。新しいTVアニメシリーズ「アン・シャーリー」が2025.4月~放送開始予定とのことで… この機会に!と妹が率先して手を付け始めました。「少女漫画好きを名乗る者の必修科目だろう」と思いつつ、活字読めない人間すぎてふわっとしか触れてこなかったけど、なんか今呼ばれた気がした! とのこと。「アン・シャーリー」公式HP→こちら新アニメへの妹の期待ポイント(現時点)は、下記のあたりだそうです。・背景美術の素晴らしさアニメーションPVを見ただけでも、背景美術が目に付いて素敵!非常に力のある方たちが、光と憧れを詰め込んで形にされているのを感じる!※最近のアニメーションには、写真を若干加工して画面に当て込んだ背景(そして人物たちは画面上で浮いてる)をよく見かけます。勿論作品に合っている手法なら全然良いのですが…そうでないものも多く。「“絵”を作ろうとしてくれ!背景は画面を埋めるために使うものじゃない!効果的でないなら、背景なんてないほうがイイから‼」と妹が嘆いていて、「アン・シャーリー」の背景美術には心洗われる思いだそうです。・主人公/アン・シャーリー役を井上ほのかさん(井上喜久子さんの娘さん)が演じられる点昔から井上喜久子さんの自作楽曲の、独創的/文学的なワールドのファンだったため、その娘さんの活躍も嬉しいし、言葉のパワーを感じる演技が見れるのではないかと期待しているとのこと・新作アニメのメインビジュアル今回のアニメが、24話でシリーズ3作を駆け抜ける構成になるそうで。(「赤毛のアン」「アンの青春」「アンの愛情」)スピーディーな展開になりそうですよね。旧作アニメの一番有名な絵面(駅で大きなトランクとともに少女が待っている絵面)と対比させるような形で、新作アニメのメインビジュアルは、成長したアンちゃんがより広い世界/未来に向かって歩み出すイラストとなっていて、旧作アニメとのコンセプトの違いを明確に打ち出していて、非常に楽しみ!私(姉)は、赤毛のアンシリーズは村岡花子さん訳のものを読んだことがありました。一通りアンブックスシリーズは買い揃えたつもりでいたのですが、「赤毛のアン・青春・愛情」の3冊を読んだところで満足して、その先は読まずに放置していました。いつだったか忘れるほど前の記憶なので(大学生のころだったかな?)、細かいエピソード/登場人物たちは全く覚えていませんでした。今回、妹が読み始めたのにつられて、私も読み直し始めていますが…いや~~~、面白い!以前よりずっとずっと、いろいろ拾えるものがある!気がする!シリーズ自体非常に数も多いので(活字だし)、すべて鑑賞し切る前でも、ポツポツ感想を書いていきたいと思っています。改めて、新アニメシリーズ楽しみにしています!by姉アニメ『アン・シャーリー』2025年 感想リンクTVアニメ「アン・シャーリー」待機中!第1話感想・ふたりのアン・シャーリー第2話・第3話&OP/ED感想第4話・第5話・第6話感想まとめ第7話・第8話・第9話感想+アン&ギルバートイラスト第10話 感想+イラスト第11話・第12話・第13話 感想+カスバート家子供たちイラスト第14話・第15話・第16話・第17話 感想第18話・第19話・第20話 感想+ルビー・ギリス イラスト第21話・第22話 感想+原作との相違点について(予想)第23話 感想+ロイヤル・ガードナー描写について最終回・第24話 感想+アン&ギルバート before&afterイラスト総括:アニメ『アン・シャーリー』と原作『アンの愛情』との相違点について
2025.02.25
コメント(0)
-

日渡早紀原画展 大型キャンバスボード(受注生産)が届きました!
日渡早紀原画展 大型キャンバスボード(受注生産)が届きました!昨年10月の「日渡早紀原画展」名古屋会場(→感想記事リンク)にて注文していた亜梨子ちゃんが地球を抱く、コミック1巻表紙絵の、大型キャンバスボードが届きました。受注生産品/P8号(455×333mm)会場ではまだサンプル品のみの展示だったのですが、大きさが原画原寸に近いんじゃないかな~、と感じたことと、既存で販売している(通常サイズの)キャンバスボードの、特に濃い色がしっかり乗っている感じが素敵だったので、本キャンバスボードも、宇宙の黒が深く印刷されてるとイイな~!と期待していました。実物が届き、宇宙や地球が期待通りの色の深さで、人物(水彩)部分の色もこだわりの淡さというか、元のキャンバス地が生成り色で、全体的に品の良さ・ヴィンテージ感があって、大満足です!大きさは通常単行本と比較してこんな感じ。なかなか気合の入った迫力サイズです。私たちが「ぼく地球」に求めるものが詰め込まれてるというか、「作品愛」が昇華されるようなグッズを購入できて嬉しいです。買ってよかった~!改めて、名古屋会場でも開催してくださり、ありがとうございました!by姉
2025.02.08
コメント(0)
-
ドラマ感想「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」
なかなか鑑賞できていませんでしたが、昨日Tverで最新4話まで追いつきました。簡単感想です。ドラマ感想「日本一の最低男※私の家族はニセモノだった」(フジテレビ・2025年)大森一平(香取慎吾)はTV局で高視聴率の報道番組プロデューサーを務めるやり手だったが、何らかの問題により退社を余儀なくされ、無職となり父の残した実家に戻ってきた。彼は社会再起をかけ、議員秘書を務める幼馴染の伝手を頼りつつ、区議会議員への当選を目指している。区民への生活者目線アピールのため、「ホームドラマ」を演じることを決めた彼は、半年前にがんで亡くなった妹の残した家族…義弟の小原正助(志尊淳)と2人の娘・息子との同居生活を始める。一平は、慣れない家事や子育ての傍ら、票集めのため商店街の有力者や小学校のPTAに潜入しようと画策するが、それぞれ諸問題に直面し…。じわじわじっくり面白くなってくるドラマで、とても気に入りました!タイトルやあらすじ、画面のつくりとしてパッと見の派手さはなく、出だし~2話あたりまでは少々説教くささがあるかな~…と感じながら鑑賞していましたが、3話・4話と話数を重ねていくと、主人公含め主要キャラクターたちの心情というか、家族知人たちへの反応の諸々から、行動の意図が推し量ることができるようになってきて、キャラクター同士の言葉や心情に対するお互いの認識感が増してきているのが分かって、すごく見ごたえがあります。主人公も「超野心家」「家族も全部選挙のために利用してるだけだ」~的に言いながら、様々な物事へのリアクションから、実家を顧みず一心不乱に仕事に打ち込んできた自分への後悔…でもないのですが、居なくなってみて初めて父親や妹が何を考えて過ごしていたかを改めてなぞってみたくなったんだな…という奥底にあるものが見え始めたり。姪・甥にも接していく中で、「お母さん亡くして…ショックだったよね」という…すごくストレートなところなんですけど、推し量っているふりはしてても全然実感できてなかったことを認識するような瞬間があったり。主人公が「日本一の最低男」って(奥底で)自分のこと思いながら、元敏腕プロデューサーの常人ならぬアグレッシブさで諸問題に対する企画書をどんどん書いてぐんぐん推進していく姿が見どころの作品なのかな、と受け取っています。志の高い、良質なドラマ作品だと思います!各話魅せどころがありながら、各キャラクターの心情について大きな流れの軸がしっかりあり、脚本と俳優様たちの絶妙なニュアンスが素晴らしいです。主人公の大森一平は、アイドル・香取慎吾さんのこれまでの経緯と被るところもあり、セリフや表情にも深みを感じてグッと来ます。5話以降、もともとは中山美穂さんが演じられていた保育園の園長さんや、主人公の幼馴染・議員秘書を演じられている安田顕さん等、有名どころキャスティング部分にスポットが当たって話が展開していきそうですね。想像も追いつかないような大変な状況下で、携わられてるスタッフ様、皆さま大きな不安とご苦労を抱えながら、それでも全力で制作を進められているドラマ作品だと思います。この先、心して鑑賞していきたいと思います。by姉
2025.02.02
コメント(0)
-

ヨナ姫のドールヘッドを造ってみました。
暁のヨナファンが、樹脂粘土フィギュア制作動画を観る⇒以前造ろうとして挫折していたドール素体&無地ヘッド&出来合いのドール用チョゴリを発掘⇒100均の樹脂粘土&アクリル絵の具&ミリペンを使ってヨナ姫のヘッドをとりあえず仕上げてみる。←イマココ一応リカちゃん人形風のヨナ姫を目指しました。ウ~ン(もっと髪の毛をこうしたら良かった)は尽きないですが、次に何か作る機会があった場合の糧にしましょう。靴だけは用意してあげたいなぁ。そして毎度のことながら、コレを造ってどうするんだ私は。(どこで保管しよう…)以上、突発的クリエイティブ(⁉)オタ活日記でした~。by妹
2025.02.01
コメント(0)
-

初ねんどろいど!ちはやふる「綾瀬千早」を購入しました。+α
初めてまともに可動式フィギュア(?)を購入しました。グッドスマイルカンパニー社のねんどろいどシリーズ新作・「ちはやふる」の綾瀬千早ちゃんです!ねんどろいどってこんな風に自分でポーズをとらせて遊ぶものだったんですね。(↑よく分かっていなかったが、イメージ画がすごく可愛かったので予約してた)届いてみて、すごく「太一くんの目から見た千早ちゃん」の表情だなぁ~、奥ゆかしくてなんともかわいい~!と思い、早速、コミック10巻の名シーン・vs朋鳴高校の試合で千早ちゃんが太一くんにタオルを差し出す場面イメージで組み立ててみました。かわいい~!めっちゃかわいいよ~!太一くんが本当に求めたかったものが、見事に体現されてるよ~!(↑ちはやふるを完全真島太一目線で読み進めた読者の感想)下半身パーツは2種類、表情パーツは3種類のセットです。下半身パーツを正座verにすると、かるたをとってる凛々しい千早ちゃんになります。台座を畳風にするカバーの紙やかるた札も付属してました。かるた札は、作中の登場人物の名前にちなんだ札+せ札が用意されてました。(千早ちゃん、新くん、太一くん、詩暢ちゃん、瑞沢かるた部面々)作品愛があって素敵でした。もう1種の表情パーツは、少しはにかみ照れ顔千早ちゃんです。この表情もすごく可愛い!小道具・携帯電話(ガラケー)が付属していました。芸が細かい!コミック3巻頃の、新くんからの連絡がないな~と携帯を見ている千早ちゃんイメージかな。どの角度からまじまじと見ても、すごく可愛いんですよ。昨日届いたばかりなのですが、めっちゃ遊び倒しました!面白かった~!ねんどろいど、すごいですね!これは是非…「暁のヨナ」のキャラクターたちでも出していただきたいところです…!!!以下、ちはやふる関連で話は変わりまして…次代の瑞沢高校かるた部を描く「ちはやふるプラスきみがため」の連載を追いかけていますが…画面のキラキラが素晴らし過ぎて…もう!!!2025.1月時点でコミック3巻まで発売されていますが、主人公の長良凛月(りつ)くんたちが、初めて夏の全国高校選手権大会・近江神宮を訪れる+ 恋のキラキラも増量中(菫ちゃんが可愛い過ぎる!)+ 瑞沢かるた部OBたち+新くんも登場!という激アツの展開&ノリノリの漫画画面が堪能できます。マンガ好きの方には、激推します!上の写真は、コミック2~3巻+1巻発売時のX(旧ツイッター)感想投稿キャンペーンで妹が当てたミニ色紙です。旧作の淡い色を重ねる水彩&和風イメージデザインの表紙群に比べ、明るめ&原色系の色合いで、ペタッとした塗りつぶし感のあるデザインになっていますね。3巻のピンクが来ると、一気に「少女漫画感」が映えて素敵です。そしてもうひとつ…旧作の連載時より末次由紀先生発起人の「ちはやふる基金」というかるた振興団体があり、コミック発売の度にサイン本+グッズセット(500~1,000セット)や描きおろしイラストを多数使用したオリジナルカレンダー等のグッズを販売し、活動資金とされています。サイン本の中には直筆でイラストを入れたものもあるよ!という…お忙しい連載漫画家様で普通なかなかそこまでやらない(出来ない)驚愕のサービスを継続実施されており、本当に行動力のある起業家作家様だな、凄いな…!と思いながら見ています。ちはやふる最終50巻の時より、これまでも何回かサイン本セットを頼んで来ていたのですが、「きみがため」3巻のサイン本+2025年のカレンダーセットで…幸運にも直筆イラスト入りサイン本を届けていただきました。荷物開封の瞬間、妹が叫んだ…!作品きっての人気キャラクター・瑞沢かるた部初代部長・爆イケ真島太一くんがいらっしゃいました。*上の画像ではサイン本の通しナンバー消してます。うわぁあああああ!「きみがため」に太一くん初登場の3巻で、これはうれしいぃぃぃいいい!家宝~~!!とりあえず千早ちゃんが喜びそうだったので、カレンダー表紙(の千早ちゃん)の横に並べてみました。うん、とても嬉しそうだ。カレンダーは今年初めて購入したのですが、すべて描きおろしイラストという渾身さで、各キャラクターが生き生きしていて、とても見ごたえがありました。デザイン/配色も超ハイクオリティで素晴らしかったです。来年も欲しいな。ちはやふる、2025年の作品展開も楽しみにしています~!by姉(写真:妹)『ちはやふる』感想リンク『ちはやふる』読み始めました!感想-その1 話の骨格について感想-その2 かるた競技への芸術的・創造的アプローチについて感想-その3 千早ちゃん・新くん・太一くんの三角関係について感想-その4 瑞沢かるた部&綾瀬千早ちゃんについて感想-その5 綿谷新くんについて感想-その6 真島太一くんのかるたと、2人の師匠について感想-その7 千早&太一 恋愛とかるたについて-1感想-その8 千早&太一 恋愛とかるたについて-2感想-その9 千早&太一 恋愛とかるたについて-3感想-その10 百人一首と「せをはやみ」の歌について感想-その11 末次先生の過去作とちはやふるのハイブリットなラブストーリー描写について感想-その12 若宮詩暢ちゃんについて感想-その13 「一緒に居るための手段」の整理とサブキャラクターを用いた視点の投入について京都に行ってきました-その①近江神宮初ねんどろいど!ちはやふる「綾瀬千早」+直筆イラスト付サイン本について映画感想『ちはやふる』(上の句、下の句、結び)3部作漫画感想『MA・MA・Match(マ・マ・マッチ)』(末次由紀先生)漫画感想『ちはやふる plus きみがため』1巻(末次由紀先生)
2025.01.25
コメント(0)
-

ipad proでお絵描き中(喜びの舞2)
先日購入したipad proで、お絵描き楽しんでますAdobe Frescoがもう…楽しくて楽しくて‼以下、描いた順に落描き並べました。by妹
2025.01.19
コメント(0)
-
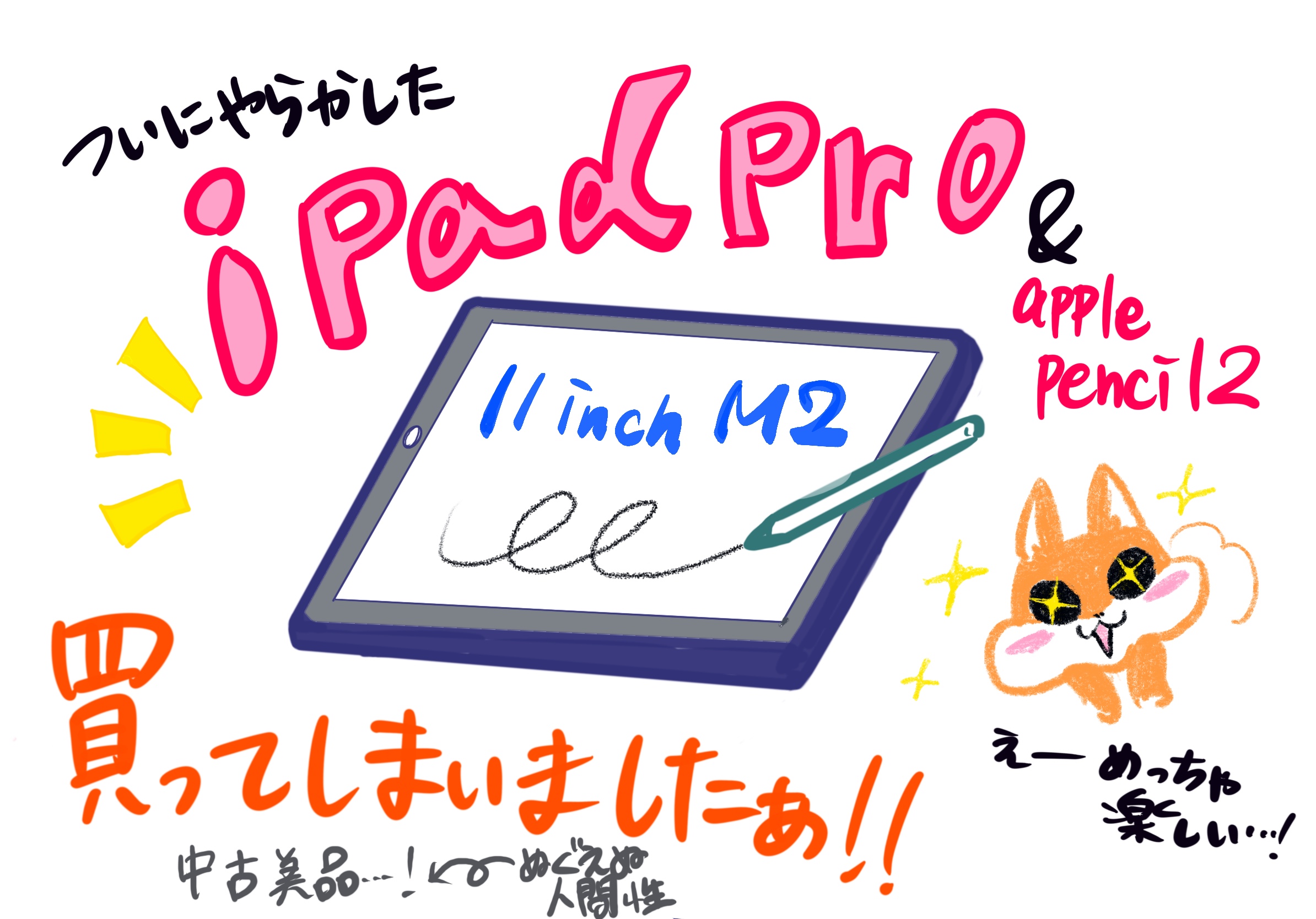
ipad pro 購入しました(喜びの舞)
こんにちは妹です。お絵描き好きが喜んでいるだけの記事です!2010年代末頃から、世のお絵描きトレンドは圧倒的に apple ipad pro ‼分かってました…分かってたんですけど、お財布的にも厳しいし一応安価な液タブを所有するパソコン(windows)ユーザーとしては「まぁパソコンで描けるしね…」となかなか一歩踏み出すにいました。ーそう、使ってみたら最後 絶対欲しくなるのは分かっていましたので…今まで興味がありつつも、一度も機器に触れることなく、2025年を迎えました。しかしここのところ ふと…「欲しいなぁ」と。お正月休みの間中ずーっと ipad動画や旧型~新型の特徴&相場を眺めておりました。大きさに関しては「絵を描くなら一番大きい12.9インチ」という通説もあったのですが…私は ①そんなに大型の大作を描きたい訳ではない ②めちゃくちゃ姿勢を変えながらごろごろ描きたいタイプ という自分の性質を考え、軽量の11インチ選びました。正解だったと思います。あと、最初は(すごく古い型の中古品でも良いかな~)と思ってたんですが…2025年現在のipad中古市場、古くてもそうも安くならないっぽい‼6~7年前の中古美品でも、一式それなりに揃えるには5~6万円以上は必須のようでした。もうそれだったら…と、最新版ではありませんが2022年のM2モデル・バッテリー100%超美品中古(やっぱり中古かい)を購入‼128GBの一番安価なものですが、本体とペンシル、フィルムやお絵描きアプリ「procreate」まで含めて10万円に収めたので、まぁまぁ上手く揃える事が出来たんじゃないかな(自画自賛)!…買ってよかった‼ と思うためにも、これからたくさん活用していきたいです~‼以下、はしゃいで描きなぐった1枚目~4枚目ラクガキです。4枚目は Adobe Fresco なんですが… いやコレめちゃくちゃ楽しいんですが‼このアプリ…無料で良いんですか⁉ スゴイ‼by妹
2025.01.15
コメント(0)
-

国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング2024-2025を見て来ました。
国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング 2024-2025を見て来ました。プロジェクションマッピング自体は、もう4~5年?開催されているのかな?スーパーフォトジェニックな松本城天守がカラフルに彩られるということで、是非見たい!と思っており、松本まで行ってきました。本年は、昨年に引き続き一旗というプロデュース会社さんのワークスとのことです。他にも歴史コンテンツ系・浮世絵関連のデジタルイベントを多く手掛けられている会社様のようで…見応えがありそうだ!会期中、3つのプログラムを楽しめるそうです。私が鑑賞したのは、今週始まった第二期プログラムでした。【日時】 2024年12月14日(土)~2025年2月16日(日)18:00~22:00■第一期:躍動する歴史絵巻 2024年12月14日(土)〜2025年1月8日(水) ■第二期:光で彩る伝統文化 2025年1月9日(木)〜1月29日(水)■第三期:春、咲き誇る花々 2025年1月30日(木)〜2月16日(日)*以下、写真ログ(低スペックスマホ使用)です。*城内の天守以外も光ってました。縁取りが光るだけでめっちゃカッコよかったです。天守のプログラムは、18:00以降、9分間の本編+3分のインターバルを繰り返し投影します。休日ということもあり、松本城といえばココ!というスポットはかなりの観客でにぎわっていました。風も少なく、水鏡にきれいに天守が映り込んでいて、マッピングがなお一層華やかに鑑賞出来ました。豪華絢爛!華やかで綺麗で、とても見応えがありました~!行けて良かった。…真冬の松本の夜、めっちゃ寒かったけど!でも行けて良かった!!実物は、非常にスピーディーにマッピングが展開しますし、上記写真など目じゃないほどのキレイさ/豪華さなので、興味のある方は、防寒対策万全の上で…是非!私もまた機会があれば伺いたいです。by姉
2025.01.12
コメント(0)
全2332件 (2332件中 1-50件目)
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(青木祐子)・・その百六十…
- (2025-11-25 21:14:22)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0942 30代を無駄に生きるな
- (2025-11-28 00:00:15)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…
- (2025-11-26 21:00:05)
-