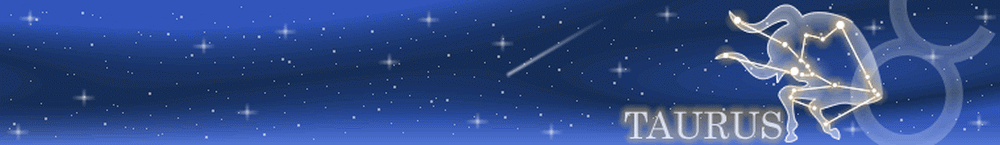2005年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
桟橋釣り
今日も朝釣りに行ってきました、朝6時、島の東海岸、羽伏漁港南西の風、いつもの様にクルクルと呼んでるルアーを引っ張った。南西の風のはずが時々正面(東)から吹いて少しやりにくいが始める事にした、久しぶりの羽伏漁港何か釣れそうな気が?ところが何回投げてもあたり一つ無い、サバは目の前を泳ぎ回っているがルアーに反応しない、こりゃぁ駄目だ何も釣れないで渋々帰る事にした、水温も良さそうだし潮色も明るく良さそうなのだが?
2005.10.31
コメント(0)
-
天皇賞
やった!!取ったど万馬券昨日の予想通り、牝馬が来ました。それも1着に、これってエアグルーブ以来の事か? 掲示板に3頭の牝馬が乗った。やっぱり2000メートルでは、牝馬でも十分通用するという事だろうか?馬連で12340円付けばおんのじ いやぁ嬉しい限りです久しぶりの万馬券だつたからなぁ結果1着 ヘブンリーロマンス2着 ゼンノロブロイ3着 ダンスインザム-ド4着 アサクサデンエン5着 スイ-プトウショウ単勝 1番、7580円 枠連、1-7、2200円 馬連、1-13、12340円馬単 1-13、47290円 三連複、1-12-13、141100円三連単 1-13-12、1226130円
2005.10.30
コメント(1)
-
天皇賞
天皇賞前日売りオッズ(17時30分現在)単勝オッズは、昨年のこのレースの覇者で前走、英インタ-ナショナル(G1)2着に入ったぜンノロブロイが2.5倍で一番人気、以下宝塚記念2着から制覇を目指すハーツクライが6.9倍。3番人気は、一昨年の宝塚記念の勝ち馬で今年の同レース7着から巻き返しを図るタップダンスシチーが7.6倍前走の京都大賞典で1年7ヶ月ぶりの勝利をあげたリンカ-ンが8.9倍ここまで4頭が10倍を切っている、これらの馬を一蹴りし宝塚記念を制した、スイ-プトウショウが10.5倍馬連は、ハーツクライ、ゼンノロブロイが7.4倍馬単は、ゼンノロブロイ、ハーツクライで11.7倍三連複、リンカ-ン、ハーツクライ、ゼンノロブロイが10.8倍三連単、ゼンノロブロイ、ハ-ツクライ、リンカ-ンで35.4倍で1番人気となっている自分もやっぱり、ゼンノロブロイから流してみたい相手は、ハーツクライ、今年も牝馬が絡むと見てスイ-プトウショウへヴンリーロマンス、の2頭あとは、武豊騎乗という事もあり期待もこめてリンカ-ンなど、まぁ最終予想は、当日という事でまた、予想がころっと変わる事もある、それほど難しいレースという事か?また、去年みたいに馬連と三連単的中というようなことは無いと思うが?まぁ、当たればいいが?
2005.10.29
コメント(0)
-
久々の桟橋釣り
久しぶりに朝釣りに行ってきました。久しぶりの釣りなのでどのような物が釣れているかわからなかったのですが、まぁサバは、まだ釣れるだろうと思い島の西海岸、黒根港の桟橋での釣りとなつた。一投目、二投目とサバが釣れたので「これは、いっぱい釣れるのではと思い」二匹とも逃がしてやったが、それっきり一匹もつれなくなった。こうなると、逃がさないで、持ち帰ればよかったなぁ、まぁ後から悔やんでもしょうがない事ですが。
2005.10.28
コメント(0)
-
テレビ水戸黄門の謎 4
黄門一行の移動スピードを測定してみると?かれこれ四半世紀も、旅をしている黄門一行。北は松前(北海道)南は薩摩(鹿児島)、佐渡や隠岐、五島といつた。離島まで足を延ばしており、当時の日本で訪れていないのは流刑地の八丈島ぐらいという徹底ぶりだ。コ-スもさまざまで基本は水戸-目的地-漫遊-水戸という回遊パタ-ンだが九州まで行って(第5部)そこから帰ってくる(第6部)という片道パタ-ンもあつた、踏破距離は、通算5万キロ以上。新幹線の東京-博多間を40回以上往復している勘定だ。さて、ここで気になるのが、一行の移動するスピ-ドである。いかにものんびりしている印象だが、はたしてそうなのだろうか。そこで、回と回の移動距離を7日(一週間)で割り、速度を計算してみた。大ざっぱに言って、一日に8キロというぺ-ス。やはり、のんびりしている。何せ、当時の旅人は1日10里(40キロ)を歩いたのだ。何かと寄り道したり、事件に首を突っ込んだりする癖が祟っているのだろうしかし、これはあくまで平均値であり、時にはとんでもない猛スピードで移動する場合もある、その最たる例が第17部の最後の一週間で大阪から江戸(約560キロ)を移動したもの。一日80キロという常識の2倍のぺ-スだが、以前、黄門は自信たっぷりにこう言っていた。「一里(4キロ)やそこらいそげば四半刻(30分)で着けます」。確かにこの言葉どおり、10時間歩いたとすれば、十分可能なのである。ただし、八兵衛は茶店にも寄れず、つらかろうが一方、遅い例も極端だ、第3部では宮(名古屋)から桑名を一週間で移動した。この区間は、七里の渡しと呼ばれる舟を使えば、わずか4時間の距離なのだ悪天候で舟待ちをしていた可能性もなくはないがじつは第8部でも同じ区間を一週間で移動している。おそらく、熱田参りか、焼きはまぐりか、はたまた有松絞りか例によって名所巡りやグルメに興じていたのではあるまいか。
2005.10.27
コメント(0)
-
テレビ水戸黄門の謎 3
黄門は越後では何となのる?越後のちりめん問屋の隠居光右衛門といえば(視聴者の)誰もが知る黄門の仮の名、しかし、この名が通用しない土地がある。越後だ、最初に第1部で訪れた時、助さんが「俺たちは越後の、いや、越後にはるばるやってきた常陸太田の」としどろもどろになつた教訓を生かしてか、黄門はあらかじめ偽名(もともとそうだが)を考えるようになった。越後を丹後に変えてみたり、八兵衛の進言で江戸の菓子屋を名乗ったり、ただ、布の染め方を聞かれ、町人娘にちりめん問屋であることを怪しまれた事もある、また、第4部ではなんと本物のちりめん問屋の光右衛門に遭遇、これが黄門に瓜二つでしかも評判の守銭奴だつたことから、人違いされさんざんな目に遭った(このときは、ひげを黒く塗ってごまかした)。とまあ、何かと厄介な越後だが、気になるのは道中手形だまさか、越後のとは書かれてわあるまい越後の関所を通る場面は一度も登場していない助さん格さんの持つ荷物の中身は?黄門の荷物は、助さん格さんが分担して持っている。旅日記や矢立(筆記用具)、財布は助さん通行手形や路銀、出納帖、そして印籠はもちろん格さんだ失くしても困らない物を助さんに、取り返しが付かない物を格さんに委ねているあたり、人を見る目の確かさが感じられる。助さんが取りにいく事の多い路銀も堅物の格さんが預かっているわけだ。ちなみに、着替えは各自一着ずつ用意、黄門のあの衣装も、格さんの振り分け荷物の中に入っている。宿では洗濯や火のし(当時のアイロン)かけも行い。おかげで一行はいつも身ぎれいな姿で旅をしているのです。ただ、どうにも不思議なのは、時々れっきとした正装で登場することだ。正体がバレた時にはすかさず、水戸家の家紋の入った着物に着替え大名に面会する黄門と助、格、振り分け荷物の中には入っていないしそんな大それた貸衣装があるとも思えない、ドラマの手品というヤツだろう
2005.10.26
コメント(0)
-
テレビ水戸黄門の謎、2
なぜ最後まで正体がバレないのか?「ご隠居様はいったい、どこのどなたで!?」という問いかけに「ただの旅の隠居ですよ」と、とぼける黄門様ドラマの中盤でよくある場面だ。あまりに沈着冷静な態度に誰しも疑いを持つが、正体がバレることは滅多にない。まれに、大大名や佐渡奉行といった高官に見破られたり、八兵衛がうっかり洩らしたりするくらいである。これも、風呂番をしたりバクチを打ったりという貴人らしからぬ奇抜な行動のたまものだが時として、黄門が来ているらしいとの風説が流れている事があるそんな場合に使われる奥の手が(なぜかタイミングよく現れる)ニセ黄門を利用してカムフラージュする方法だたとえば、第21部の初回「悪鬼が巣喰う岡崎城」では、たまたまニセ黄門が同宿したのをいいことに、農夫に化けて陳情するという挙に出た、そうやって途中まで世直しを代行させてしまったのである、黄門のお忍び旅にはそんな巧妙な演出も隠されている。「控えおろう!」というのが助さんで印籠を出すのが格さんなのはなぜこの謎を解くには、2人の比較から入るのが手っ取り早い。かたや女好き、かたや堅物、得意技も助さんが剣なら、格さんは少林寺拳法と対象的だ。また、当初の設定では、助さんが家老の命で西山荘に遣わされたのに対し、格さんは18歳で黄門に引き取られたいきさつがあった。おそらく印籠を出す役目は絶対に失敗があってはならないだけに、堅物で、素手で戦うことが多く、昔から可愛がっている格さんに任せたと考えるのが、妥当だろう。しかし、この分担が定着するまでには曲折があった。助さんはもちろん、黄門自身が印籠をかざしたり弥七が牢屋の天井裏からほうり投げたり。驚くべきことに、八兵衛が挑戦したこともある(第7部31話)だが台詞のかわりに「お控えなすって」と仁義を切ってしまい格さんのリリ-フを仰ぐというドジを踏んだこうして、今のパターンとなるのは第12部から。以来、格さん役には、よく通る声という条件も加わったという。
2005.10.25
コメント(0)
-
テレビ水戸黄門の謎
自分は、日本の歴史なども好きでよく歴史に関係した本なども読んでいます今回は、架空の事ですがテレビの水戸黄門の謎をいくつか書いてみる事にしました、1、「水戸光圀公なるぞ」の一言で誰もがひれ伏す真の理由とは格さんが印籠を出し、助さんの「控えおろう」で一同平伏す、ご存知8時45分の定番シーンである、今さらながら、黄門の威光を思い知らされる場面だが、厳密にいえば一同が平伏しているのはさきの中納言でも、天下の副将軍でもない、実は、あの印籠に描かれた葵の紋は、水戸徳川家のものではなく徳川本家、すなわち将軍の物なのだ。第22部の冒頭で、黄門が旅立ちにあたり、箱の中から印籠を丁寧に取り出す姿が描かれたように、黄門は将軍の名代として世直し旅に出ているつまり、一同が平伏するのは、印籠の向こうにお上の威光を見るからなのである、同時に、一同の極端な態度の変化には黄門様の演技もものをいつている、自ら牢屋に入ったり風呂番を勤めたり、わざと相手に無礼を働かせているのだ正体を知った彼らがあわてるのも、当然だろうる米つきバッタのように平謝りする姿には、同情さえしてしまう。印籠で本当に身分証明ができるのか?第7部の18話で、一行は印籠を盗まれると言う失態をしでかした。さすがの黄門も青ざめたのは言うまでもない。家紋の入った印籠は当時、身分証明書代わりに使われていたしあの印籠は上様から預かったものなのです。その印籠が身分証明の方法として、初めて使われたのは第1部23話でのこと、かざして見せたのは、黄門自身だつた。「控えおろう!」がまだ定着していなかつた初期には、印籠の使い方もまちまちで、中には、相手の書画骨董を褒めて、ただの隠居ではないことを悟らせ、去り際に腰にぶら下げた印籠を見せると言う手の込んだやり方もあつた。ところで、黄門にはもう一つ身分証明の方法を持っている「梅里」という号だ、最後の仕上げの場面に大名や家老を呼ぶため弥七やお銀に持たせる書状に使われる。一般人にはわからないが、大名クラスならピンとくる効果的コードネームである。
2005.10.24
コメント(0)
-
新島に光を掲げた人々5
天宥法印 羽黒山第50代別当無玉や羽黒にかへす法の月天宥法印が島流しになって新島で死んだ後、本山では天宥法印の霊を弔うために、その墓を探しましたが、どうしても見つかりませんでした幕府の判決文によると、天宥法印は伊豆の大島に流されたことになっていたため、270年もの間、大島の各所を探していたのですそして昭和13年になって、初めて天宥法印が流されたのが大島ではなく新島であることが分かりました。早速、羽黒山から人が派遣されて盛大な供養が行われました。本山から来られた人々は、300年近くにわたる探索の苦心を振り替えり、感激のあまりに涙にむせんだと伝えられています羽黒山より遠山宮司、大川禰宜の一行が来島し大きな自然石に墓名を刻んだ立派な碑を建てて、盛大な墓前祭を行いました当時、大島支庁新島出張所の浅沼重四朗氏、新島本村長、市川仙松氏ほか村内有志がおおぜい集まった席で、遠山宮司は、「270年間の長きにわたって別当の墓を探し訪ね今日ようやくにして探しあてた本山の喜びと感激」を切々たる名調子で読み上げたと伝えられています。友好町村の盟約は、昭和59年に結ばれました。
2005.10.24
コメント(0)
-
菊花賞
やっぱり強かったディープインパクト祝 21年ぶりの無敗の三冠達成、ナリタブライアン以来11年ぶりの三冠馬がついに出た。いゃぁ興奮しましたね、また、ドキドキものでしたなんとか馬券も当たりやれやれです。結果1着 ディ-プインパクト2着 アドマイヤジャパン3着 ローゼンクロイツ4着 シックスセンス5着 フサイチアウステル単勝 7番 100円 枠連 3-4 410円馬連 6-7 1290円 馬単 7-6 1320円三連複 4-6-7 2730円三連単 7-6-4 7090円自分も三連複で買つたので、当てることができた三連単でやっていたら完全にはずれてたあぁ良かった22000円のプラスが出た。来週は、天皇賞(秋)です、競馬をやる人は頑張りましょう去年の20万馬券的中からもう1年たってしまったのか早いなぁ1年経つのも。
2005.10.23
コメント(0)
-
菊花賞&公営競馬の最高配当
菊花賞の前々日売りの過熱ぶりディープインパクトの前々日売りがまたまた1.0倍になったそうだこれは、皐月賞、ダービーの前々日、神戸新聞杯の前日に続く元返しオッズ、単勝支持率93.7%という過熱ぶり大本命に人気が集中した結果、2番人気以下のオッズにも異変が2番人気のシックスセンスでも70.6倍、3番人気のフサイチアウステルでは、94倍という高オッズ、6番人気以下はすべて万馬券だったようだこれなら、馬連でもそこそこ配当が付くのでわ?当日は、多少のオッズの変動があるとは思いますが極端に変わる事はないでしょう。やはり自分もディープ本命には変わりない公営競馬最高の配当10月22日、今日の事、東京12R、3歳上ダート1400メートル16頭立て、小林惇一騎乗の16番人気のゼンノエキスプレス2着12番人気のカネスベネフィツト、3着に3番人気ケイアイカ-ルトンが入り、3連単の配当が18469120円を記録した。これまでの公営競技の最高配当は、今年5月13日に大井2Rで記録された三連単13000390円だつたJRAでの最高配当は今年福島9Rで記録された、三連単10149930円だった。 今日の結果 馬連437390円(120通り中、120番人気馬単1021160円(240通り中、237番人気)三連単(3360通り中、3344番人気)で最高配当が更新された自分もラジオで聞いていて、驚くとともに羨ましくもなった。 ディ-プの単勝は前日売りで、1.1倍だそうです2番人気のシックスセンスが、20.8倍に3番人気がローゼンクロイツで、24.2倍さすがにオッズがどんどん下がりこれでは、馬連では、いくらも付かないなぁ。三連単でやるか?
2005.10.22
コメント(0)
-
新島に光を掲げた人々4
天宥法印 羽黒山弟50代別当流人第1号 天宥法印は出羽の国(山形県)羽黒山の第50代の別当でした。羽黒山といえば、月山、湯殿山とともに出羽三山として古くから信仰が厚く、今でも大いににぎわっています。新島村と羽黒町は現在「友好町村」として深いつながりを持っていますそれは、長い間見つからなかった「天宥法印の墓」が新島で見つかったことがきっかけとなっています。では、天宥法印とはどんな人で新島でどんなことをしてくれたのでしょうか。天宥法印ははじめ「宥誉」(ゆうよ)と言う名前でしたがあとで「天宥」と改めました、それは、そのころ江戸幕府にあって黒幕的な力を持ち、大いに勢いをふるった「天海僧正」の弟子となってその一字をいただいたからです。法印は羽黒山にあって大きな功績をを残しました。その功績の一部を紹介します。(1) 承応3年(1654)年近くを流れる川の水を引いて原野を開拓したこと(2) 本殿を造り替え、参道を改修整備し、杉の木を植え神社の領域を整理したこと、天宥は、本山の再興を図ったので後世になって「羽黒山中興の祖」といわれたのです。あるとき、羽黒では宗教上の争いが起きて、天宥は苦しい立場に立った天宥は天海の力を借りて、出羽三山を統一しょうと考えました。もともと出羽三山は、真言宗でしたが天海の弟子になった天宥はこれを天台宗に統一しょうとしたのです。しかし、賛成と反対の両意見が出て統一することが出来ないばかりかかえって対立してしまい、にらみあう結果になってしまったのですまた、増川山が寺の領地か藩の領地かで、藩主の酒井出羽守との間に土地の境界争いが起こりました。そしてこの争いを解決するために幕府に訴え出てその採決をあおいだところ、羽黒山の不利に終ったのですそれは万治元年(1658)のことです、そのうえ、頼みにしていた師の天海僧正が死んだため、天宥はついに蔭口をいわれて訴えられ有罪になってしまいました。そして寛文8年(1668)4月4日に新島に流されてきたのです。天宥は新島に流された流人の中の第1号です。新島に着いた天宥は、現在の梅田茂兵衛宅で、島の子供たちを集めて読み書き算盤をはじめ農作物の生産技術を教えるなど大きな功績を残しました。そして、流罪となって7年後の延宝2年(1674)10月24日、82歳の高齢でわびしく死にました。遺品となった印鑑1個と書画数点が今でも梅田家の家宝として残っていますその2に続く
2005.10.21
コメント(0)
-
新島に光を掲げた人々3
相馬主計 新選組最後の隊長3硯の海の深き心相馬は明治5年10月13日「足柄県令、柏木忠俊の下知状」によって赦免され出島しましたが、別れにのぞみ、子弟を集めて惜別の言葉を述べて一首の和歌を詠んだのです。さながらに そみしわが身は わかるとも 硯の海の 深きこころぞ「皆さんとせっかく親しくなったわが身でしたが、たとえ別れても学問の道(硯の海)で結ばれた深き心は、いつまでも忘れる事ができません」と言う意味でしょう、こうして多くの子弟や島民の涙に送られて妻マツと一緒に新島を後にしたのです。上京してしばらくして、榎本武揚から「鳥取県令(県知事)に君を推薦する」との連絡を受けました。しかし、流罪を解かれて県知事に推された相馬はこれを断りました。相馬の答えはこうだったのです。「私は、もうすでに世間を離れてしまった一老人です。静かにこれからの世の中を生きたいと思います。私を県知事にしてくれると言うご厚意は身に余る光栄でありがたいことですが、どうぞお許しください」相馬が住む蔵前には元新選組の隊員が大勢住んでいました。罪人あがりのこれらの人々の生活は見るに忍びないほど貧しかったのです。前はこの人々の隊長でありながら今、楽の道を選ぶ事は出来ないと考えたからです。相馬主計は、この年間もなく切腹して自らの命を断ちましたが、その理由は今でも不明です。現在新島勤労福祉会館の西側駐車場入口近くに相馬が詠んだ和歌を書いた石碑が建てられています、この近くに住んでいたらしいです。
2005.10.20
コメント(0)
-
新島に光を掲げた人々2
相馬主計 新選組最後の隊長2新選組隊長に任命相馬は明治元年10月から翌年5月までの函館戦争に参加しました。この函館戦争とは、王政復古と江戸城明け渡しに不平を持っていた榎本武揚を主将とする旧江戸幕府の脱走軍が函館五稜郭で臨時政府を作って官軍に抵抗した戦争のことです。しかし、歴史の流れに逆らう事ができず新選組副隊長の土方歳三ら多くの戦死者を出して降伏してしまいましす相馬主計も明治2年3月25日の宮古湾海戦で軍艦に乗船して司令官をしていましたが、負傷してしまいました。この後、土方歳三が銃弾によって戦死した後を受け相馬は函館奉行の永井尚志によって5月15日新選組隊長に任命されたこのころから相馬主計は「主殿」(とのも)と改名しています時に28歳でした、しかし相馬は新選組隊長を努めたのはわずか1日で戦犯者として政府軍に捕まってしまいました。榎本武揚らは、軍務局の糾問所の牢に入れられて戦犯者として兵部省の取調べを受けました相馬は坂本竜馬が殺害されたことで取り調べを受けるために刑事犯に切り替えられました、刑部省に移されてさらに取調べを受けたのです。判決は「流罪終身刑として伊豆七島の新島に流す。」でした、理由は不明で坂本竜馬の暗殺と新選組は関係なかったようです。新島での生活新島に流された相馬は自ら読書するとともに子弟を集めて読書や習字などを教えました教養が高く親切に分かりやすく教えてくれたので、学びたい人がたくさん集まりました、家に入りきれずに屋外まであふれていたと伝えられています、また手先が器用で建築の技術も身に着けていました仮住まいとして別室を建てるときも、その設計、建築、造作など全部自分でやり、職人や大工の力を借りずに完成したと言われていますこの建築技術を島民にも教えてあげました。新選組の隊長として活躍した相馬は、このようにして教養と特技を島民に広めていったのです相馬は流人の中でも特別に扱われました、帯刀が許された武人であり、島民と親しく交わり、居食をともにしていましたしかし、どんな時でも常につつしみ深く厳格であり扇子を持つて身なりや姿勢をきちんとしていました村民は相馬のこのような威厳のあるようすに敬服していたと言います。その3に続く
2005.10.19
コメント(0)
-
新島に光を掲げた人々
相馬主計 新選組最後の隊長相馬主計は笠間藩士であった船橋平八郎の息子として天保14年(1843)年常陸に生まれ、「肇(はじめ)」と命名されました。文久3年(1863)年の新選組が組織されたころの京都や大阪の記録によると新選組の平隊士として、「主計(かずえ)」の名で記されています。そのときは21歳でした。新選組というのは、1863年に江戸幕府が武芸に優れた浪士を集めて編成した警備隊であり、近藤勇や土方歳三らが入っており京都で反幕府勢力を抑えるために作られた組織です。ところで、この新選組最後の隊長がどうして新島と関わりがあるのか流人帳によると、相馬主計は明治3年(1870)年11月、終身刑として28歳の時に新島に来ています。教養が高く、村の人々に親切な主計を慕って教えを受ける人が後をたたず、相馬主計は新島の人々に学問を教えたのです。その2に続く
2005.10.18
コメント(0)
-
島の伝説
為朝様源為朝は、大島に流刑され、伊豆諸島に勢力を強めたことによつて伊豆介狩野茂光の討伐を受け、自ら大島の館に火を放ち自殺したことに「保元物語」では記されているとすれば為朝は三十一歳で死んだことになり新島の「為朝様」の伝説は生まれてこない。為朝は幾人かの従者とともに、大島から逃れ新島の羽伏浦に上陸した、道に迷ったが、キジが道案内をして村へたどり着いた、当時の名主土屋平左衛門のもてなしを受け同家を宿とした、同家には丹千代という娘がいた。為朝にかしずくうちに、為朝の子を身ごもった。為朝は新島も伊豆に近いため身の危険を感じ八丈島へ渡ることにした、丹千代に神息(かみひろ)の刀を与え「再び京へ上り旗上げしたことを聞いたら、生まれた子供が男であれば、この刀を持って会いいにくるように」と言い残し九月十三日前田権左衛門家の「天神丸」に乗って八丈島へ船出した。天神丸の船主前田家では、為朝のために新しい手編みのござむしろを作り為朝の船中の敷物にした、土屋家は現在青沼と改姓しているが住居の一部に祠を建て「為朝霊社」として祀り九月十三日の船出の日を記念して、為朝が描いたと伝えられる墨絵の自画像と神息と書かれた白鞘の刀とを霊前に供え左右に剥製のキジ二羽が置かれ(これは為朝の道案内したキジに因縁するもので、同家では、キジを食しないこともその一つである)このような儀式のもとで一般の観覧に供している村民はこの日を「為朝様」と呼んで参拝している九月十三日の儀式は、権左衛門家から毎年新しい手編みのござが青沼家へ届けられると式が行われていたが毎年作ることは負担であろうと思い同家に相談して市販のござで汚損するまで使うことに決めた神息(かみひろ)は、為朝以前の九州の有名な刀鍛冶でその作は国宝級の品である「鎮西八郎」の名にふさわしい所持品である。
2005.10.17
コメント(0)
-
秋季ソフトボ-ル&秋華賞
きょうは秋季ソフトボ-ル大会が行われました。前の日から天気が悪く当日出来るか微妙だつたが何とか始めたが、自分としては、あまりやりたくはなかったが仕方なくやることに、他の二人が腰にコルセットを巻いてでもやるのでは、出ない訳にはいかない一試合目が終わり二試合目が自分達の試合だったのですが一チームが出場を取り消し三試合目も自分達になってしまった。二試合目の途中から雨が降ってきて、その後の試合は中止になつた。そうだ、きょうは、競馬がG1秋華賞だ毎年秋季のソフトボ-ル大会の日はG1レースとよく重なることが多いのです早速家に帰り予想を始める、このレースは、人気2頭で固いと思いいつもなら馬連を買うのだが、この2頭で決まれば馬連の配当は2倍も付かないのでは、儲けもないそこで三連複でこの2頭を軸に流す結果1着 エアメサイア2着 ラインクラフト3着 ニシノナ-スコール4着 オリエントチャ-ム5着 ライラプス単250円 複 10番 100円 5番 100円 11番 340円枠連3-5 180円 馬連 5-10 180円馬単10-5 400円三連複 5-10-11 1110円三連単 10-5-11 3580円何とか1110円ですが、当たりました。5000円くらいですがプラスさあ来週は菊花賞21年ぶりの無敗の三冠馬の誕生なるか楽しみです。
2005.10.16
コメント(0)
-
島の不思議9
おんにんさま(御根様)若郷村の東海岸に、淡井浦(あわいうら)という入り江があります。その海岸近くに海中から高く突き出している岩がありますがそれが「おんにんさま」です、これは、「御根様」(おんねさま)のなまつたものです、新島では「ネ」を「二」と発音します。錨の上に白髪の老人昔、ある回船が海が荒れたので、錨を降ろしてこの入り江に避難しました。しばらく休んだ後、やつと海も静かになつたので錨を上げてげて出帆しようとしました、ところが錨がどうしても上がらないそこで一人の青年が海に潜って錨の様子を調べてみました。するとどうでしょう、「おんにんさま」の近くの錨の上に白髪の老人が腰を下ろし、口に麻をくわえて指で麻をつむいでいたのです。驚いたのは青年です、すると老人はこういいました。「わたしを見た事を誰にも言ってはならない、もし他人に話したらおまえの命はないものと思え」。そういうと、老人はどこかへ姿を隠してしまいました、青年はもんもんとした幾日かを過ごしましたがついにこのことを知人に話してしまったのです。すると老人に言われたとおり、間もなくこの青年は死んでしまったのですそして誰言うともなく、白髪の老人の祟りであろうと言い伝えられるようになりました、こうしてこの根を「おんにんさま」と呼び、この根の付近では天草やさざえを取ったり、その他の漁業もしません淡井浦の人魚姫「新島炉ばなし」(武田幸有氏著)では、このおんにんさまは「淡井の人魚」となっています、また、高さ数十メートルの岩が海中にそそり立つこのおんにんさまには神が宿ると伝えられています。この浦を通る船は櫓をこぐ音にもひかえめにし、かたわらを過ぎる時御神酒か水をささげて、岩に宿る神に対してうやまいつつしむ気持ちで渡ると言われています、「新島炉ばなし」では錨に腰をかけていたのは女になっています。青年は「これが噂に聞く人魚か」と驚き、やむなく錨の綱を切り、やっとの思いで脱出したと伝えられています。
2005.10.15
コメント(0)
-
島の不思議8
死者の返礼新島ではむかしから「水死人を弔ってやると豊漁がある」と言い伝えられている、江戸時代と思われるがある朝、浜に一つの水死体が流れ着いた。たぶん、どこかの船が時化にでもあつて遭難したのかも知れないその朝、たまたま漁夫のAが死体を発見したが早朝の浜にはまだ人影も無く、Aは無情にも死体の胴巻きから所持金を抜き取った、そして何食わぬ顔で家に帰った。その後へ、やはり漁夫のBがやってきて死体を見つけた。「ああ気の毒に、どこの誰かは知らないが同じ海の仲間だ自分が葬ろう」そう言ってBは死体を家に運び、手厚く弔ってやった。それからしばらく過ぎたある夜、Bの家の戸を叩く者がある目を覚ますと、「羽伏沖にサバがたくさん集まっている」という声がする誰の声だろうかと確かめるいとまもなく、職業柄はね起きて身支度し直ちに船子をかき集めて船を出したが間もなくピチピチしたサバを満船して帰ってきた。一方、同じ時刻にAの家でも雨戸をトントンと叩く音に起こされた。「アジア沖に魚が沢山いる」と告げられ「ソレ、魚が散らないうちに」とB同様急いで船を出したがそれきりAの船は帰らず、船も人も行方不明となったというこれって、やつぱり水死人の祟りだったのでしょうか?それと、これは、親戚のおじさんから聞いた話ですがその、おじさんが若いときに仕事で、三宅島に行っていた時浜で女性の水死体を見つけたそうです、その中の一人の人がその、女性の水死体をいたずらしようかと言ったそうですおじさんが言うには、その女性は、水死してからそんなに時間が経っておらずとても死んでいる様には見えなかったとそれと、凄い美人だつたとも言っていました。そんなに美人だつたから、一人の奴がいたずらしようと言ったのでしょう。その後、浜でその女性をダビにふす事になり、おじさん達も近くにいたそうです、火が点けられ燃え上がった、その時、先程、いたずらしようかと言った人が火に巻かれて焼け死んだというのですもちろん、風も無く穏やかな日だつたそうですその火に巻かれた時の事を詳しく聞いてみました。風もほとんど無風で炎は真上に燃え上がっていた。それが急に風も無いのに炎が横に伸びて、そいつを一瞬に包みこんだあっという間の出来事に周りに居た人達は、驚き一瞬身を引いたが我に返り、火を消したのだが、そいつは、死んでいたそうですそのおじさんが自分にこのような事も言いました「やっぱりあいつは、女性の霊に祟られて、殺されたにまず間違いないたとえ、死体でも魂はあって身動きできない亡骸を裸にしようなどと言ったその人に怒って霊の力で殺したんだろうと」言ってました、まして相手は女性です、そのおじさんが最後に女は、おっかねえどと言って笑ってましたがもはや、過去のことで笑い飛ばすことも出来ますがその時は何ヶ月か笑う事も出来なかったそうです。おつかねぇ
2005.10.14
コメント(0)
-
島の不思議7
はまなり小僧昔、力自慢の漁師がいました、この漁師が浜にいるといつのまにか小坊主が現れて相撲を取ろうと言い寄ってきました。漁師と小坊主は何回も何回も相撲を取りましたがやがて力の強い漁師もすっかり疲れ果ててしまいました。そして、全身の気が抜けたようなふらふらした姿で家に戻りました。家の人が心配してそのわけを聞くと、「浜で小坊主と相撲を取ったので疲れた。」と、とぎれとぎれに答えましたそこで家の人が急いで浜に行ってみると砂浜には大きな足跡だけが残っていました、誰言うともなく小坊主が力自慢の天狗鼻をへし折ったのだと言い伝えられたというこの小坊主を「はまなり小僧」ともいいます。小さい子供がだだをこねると、よく母親が「ほら、はまなり小僧が見ているよ。」とたしなめたそうです。
2005.10.13
コメント(0)
-
島の不思議6
かんなんぼうし(海難法師)江戸時代、伊豆の島々は天領といつて、幕府が直接治めていました。反射炉で有名な伊豆韮山代官所の支配下にありました。その歴代の代官の中に、島の人々のことを考えてくれない悪代官がいましたあるときその代官は、大島の巡視を終えて、新島に向かう事になりました。しかし大島の人々は、このような悪代官が新島に行けばさぞ困ってしまうに違いないと相談して代官の船が沖に出た時船底の栓を抜いて沈没させてしまったのです。若者たちは泳ぎ帰りましたが、代官は海底に沈んでしまいました。それから毎年その日が来ると代官の亡霊がやって来るという話が新島に伝わっています、この日をカンナンボ-シ(海難法師)とかカンナンボ-様と呼んで物日(祭などの特別の事のある日)として難を避けるための行事をするようになりました。1月24日がカンナンボ-シです。この日には漁を休んで、他の仕事も早く終えます、夕方になるとどこの家でも戸口に「トベラ」の小枝をさして雨戸を固く閉ざしてひっそり夜を迎えます。また、音をたてるとカンナンボ-シに気づかれるので火箸は寝かして音の出るものは縁の下にしまいます。まずカンナンボ-様にお供物をして夕食をすませば早く寝ます。供物は各家庭によつて少しずつ違いますが、共通なものに揚げ餅です。お正月の供餅を乾燥させて油で揚げて、これを神前に供え家族もその揚げ餅を食べて寝ます。これは、水気の多いものを食べるとトイレに行くのが近くなるので。これを防ぐためと言われています、また漁師は出漁の時にこの揚げ餅を持っていけば海難に遭わないとも言われていますもしも海難にあつて船が沈没しても、これを食べて海に飛び込めばカンナンボ-様の御神力によつて助かると言われています。この晩に揚げ餅を供え、また食べることによって祟りを避け、出漁中に海難を避けることが出来るのです。自分の幼少の頃の記憶ではこの日にトベラの小枝を雨戸の節穴に刺して穴をふさぎ、トイレは外にあったので、土間に肥桶を置きそのまま小用をたせば音が出るので藁を中に入れて音が出ないようにして有りました、それと夕食の支度の時に餅も一緒に揚げて食事が終わって直ぐに餅を食わされ、早く眠らされました。もちろん、ここに書いたことは昔のことで今は漁船も大型になり少しぐらいの時化にもつよくなりまた、建物も良くなり、トイレも家の中にあるところが多いそれでも、この行事が今でも続いているのは、昭和になつてからもこの日にいろいろ不思議なことが、あったからなのでしょうか?
2005.10.12
コメント(0)
-
島の不思議5
なぞの榎ある流人が31歳で処刑された時「おれは無実だ。その証拠に法燈塚に榎をはやす。」と言い放ったそうですこの流人は、放火の罪で捕らえられたのです。流人の身で罪を犯すことは、何倍もの重い罪に問われます。まして放火です、彼は死刑を言い渡され、今、縛り首で処刑されるのです。取調べを受けた時にも懸命に自分の潔白を主張し続けましたがどうしても取り上げてくれませんでした。縛り縄が首にかけられ、もうこれまでと言う時に彼は最後の声を振り絞って叫んだのが「俺は無実だ。」でした。いい終わらないうちに縄が食い込み彼は無念の涙を飲みながら、哀れ刑場の露と消えたのです。はたして後になつて、塚から1本の榎が生えてきました。しかも固いい石を割って、その間から伸びてきたのです。そこでその流人の霊を慰めるために、この墓石が建てられたと伝えられています。もう1つの説があります、ある流人がある日、村の豆腐屋に豆腐を買いに行きました、あいにく豆腐屋の店先には誰もいませんそこで彼はお金をそこに置いてから豆腐を自分で取って帰りました。しばらくして、この流人は豆腐を盗んだとされ捕らえられたのです。彼は決して豆腐を盗んだのではないと、何度も何度も訴えました。必死になって無実を主張しましたが、聞き入れてはくれませんでした。ついに無実のまま死刑が決まりました。処刑の直前に彼は前と同じように叫んだと言われています。そして石を割って榎が生えてきたのです。1つの事実から、放火の説と豆腐1丁を盗んだ説ではあまりにも相違があります、豆腐1丁で死罪に問われたとは常識では考えられませんが、犯人が流人であつたため処刑が行われたのかもしれません。この流人の宿をしていた本村北村の農家では、この流人を「榎のおじい」と呼んで今でも法事のあるときやお盆には、お香と花を供えています。「なぞの榎」の呼び名は、罰する人と罰せられる人との立場が考えられ説きにくいなぞとして、村民がいつとはなしに語り継いできたように思われます。このなぞの榎は自分の家と隣接していて、毎日嫌でも目に入ります小さい頃トイレが外にあり、夜、トイレに行くときはこの榎に向かって歩いていかないといけないので、とても怖かったものでした。
2005.10.11
コメント(0)
-
島の不思議4
山にはいってはいけない日その2今から46年前の昭和34年11月14日すなわち前にお話した。「山に入ってはいけない日」である。この日はよく晴れた日で、島の晩秋には珍しいおだやかな日であつた。某氏(当時49)は、この日、自分の分担する工事現場の見回りに出かけた。氏の持ち場は、都道から少し山に入った地点である。氏はいつものように愛用の自転車で出かけたが家を出る時、ふと思い出したように今日は戒目だな、しかし天気もいいし、こんな日には何もあるまいと奥さんに言い、夫婦顔を見合わせて笑った。ところが、氏が工事現場付近に来かかった時。突然、氏は自転車もろとも路上に投げ出された。氏は驚いて見回したが、もちろん人影もなく聞こえるのは遠く右手の羽伏浦の浜に打ち寄せる波の静かな眠くなるような音だけ道路も都道として整備されており、小石一つないほど。加えて、氏は日頃から非常に用心深い性質の人で十分足元にも注意しながら行ったことはもちろんである。「やれやれ、年をとったかな」苦笑いしながら氏は自転車を起こし現場におもむいたが、現場の人たちから「顔に傷がある」と教えられ、急いで帰宅した鏡でみると、言われたとおり、顔に爪で引っかいたような傷跡があり血がにじんでいた、元来、氏は無神論者で、特に迷信の類は気にしない人であつたが、事ここに至り止む無く人を走らせて工事を一日休ませたそうです。確かに自転車で道路に転んでも、顔に爪で引っかいたような傷はできない、それに現場にいた人達には何ともないのになぜこの氏だけがこのような事になったか現場の親方だったからなのか?もちろん調べようもない。
2005.10.10
コメント(0)
-
島の不思議3
ノトウのおきく俗に「ノトウのおきく、ミホラのおじょう」といわれ。両者は併称される事が多い、しかし両者の関係はつまびらかでなく。それぞれに奇談を残している。「ノトウのおきく」については、いつのころか時代は判明しないが、島の南端近くに「ノトウ」。(漢字で書くと能登)と呼ばれる地に「おきく」という女性が住んでいた。現在でもあまり人の行かないところで、往時はさぞかしと思われるところ。おきくはまれに見る美女であったと言う、それがこういう人里離れた。山の中に暮らすという事は、よほどの事情でもあったものか。ところで村内に「Kくや」という屋号の家がある。今は何の商売も営んでいないが、昔は豆腐屋さんであつた。ある夜、更けてから、一人の美しい女性がこの「Kくや」に。豆腐を買いに来た、女は美しい小袖を着、懐剣を差していた。その若い女が「ノトウのおきく」であつた。しかし、夜中何のために豆腐を買いに来たのか。また、はたしてそれが当のおきくであるか、あるいは。おきくの亡霊か誰も知らない、もちろん昔の事なので。調べることも出来ないし、今となっては、この言い伝えすら。知らない人のほうが多くなってしまったのではないでしょうか?。
2005.10.09
コメント(0)
-
島の不思議2
ミホラのおじょう本村の北、宮塚山の西麓に当たるところに「ミホラ」と呼ばれる沢がある。ここに若くて美しい女性が住んでいたと伝えられ、人呼んで。「ミホラのおじょう」という、元来新島では11月14,15の両日は。山にはいらない掟になつている。今から70数年前のこと。屋号を「K」と呼ばれる家の雇い人に「H」さんという女がいた。「H」さんは生まれつきオシであつたが、たまたま禁を忘れて。14日に山に入った、ところがどうしたわけか、常日頃歩きなれた道であるのに迷ってしまい、さまよい歩くうちに。とある泉の湧いてる場所に出た、この泉がいわゆる「おじょうヶ池」で。今は涸れてしまったが地名は残っている。さてさまよい出たHさんが、何気なく目をやると、反対側の。水辺で大島田に髪を結った、若い美しい女が赤ん坊の体を洗っていた。女は顔をあげると、あっけに取られているHさんに言った。「今日は山に入ってはいけない日だ、それなのになぜ来たか。直ぐに山を降りて家に帰れ」、Hさんは生まれつきのオシであつたが。持ち前の感でそれと覚った、しかし、女があまりに美しいのと。山の中という似つかわしくない場所とに驚いて、しばらくとどまつていると女は怒ってHさんの顔を両手の爪で引っかいた。Hさんは顔中血まみれになって、後をも見ずに飛ぶように山を降りた。その後、この日になると、心無き村人がしばしばHさんをからかったが。そのつどHさんは顔色を変えて恐ろしそうにしたという。思うに、Hさんが禁を破って山に入ったため。山神の怒りにふれて戒められたのか、あるいはまた、事実。「ミホラのおじょう」の魂のなせるわざであったのかも知れない。自分も小学生頃、この話を聞いた時、そんなに綺麗な女の人なら。見てみたいと思い、何人かの仲間と11月14日にその場所へ。行こうと相談していた時、近所のおばさんに相談の話を聞かれて。イシラそんなバカな事はよしよ(お前たちそんなバカな事は止めろ)。と怒られた、事もあった、小学校の高学年の頃で、そろそろ。色気づいてきた頃の話です。現在は山に入っては駄目な日のことを知らない人も多く、知っていても11月14、15日であることは。知らないでしょうし、この日も平気で山に入っている。もはや過去話として忘れ去られているのか?また中にはそんな事があるわけない、ただの作り話だという人もいる。そのわりには1月24日のカンナンボーシは信じるようで。その日の晩は飲み屋さんも休み、消防団の冬季夜警も無し。外を出歩く人もいない。カンナンボーシの話は後日書きます。
2005.10.08
コメント(0)
-
島の不思議
死体が追いかけた話今から100年以上前、羽伏浦の「イケノハラ」という所に。水死人が流れ着いた、たまたま漁夫の某が通りかかり、これを発見した。某はあたりに人無きを幸いと、水死人の持っていた。金品をうばって自分の懐に入れた、しばらく歩いて何気なく振り返ると。今の今まで波打ち際にたおれ伏していた死体が。ムックリ起き上がり、目をむいて砂浜を一つ跳びに追いかけてきた。某はビックリ仰天、一目散に家に帰った。某の家は島でも有数の財産家といわれていたが、その後没落した。本当にこのような事があったのかどうかは、確かめ様がないが。もしあったとしたらこの人の家は水死人の祟りで没落したのでしょうか?
2005.10.07
コメント(0)
-
新島の方言2
前回の続きです、 オイ [俺、自分、私] オラア [俺たち、私たち]オイギ- [私の家] イシ [お前、君] イシラ- [お前たち、君たち]ウンダラ {お前ら、相手を軽蔑] ワチョウ [彼]このウンダラという方言は相手を怒る時に使ったのでわないかと思われる。自分も小学生くらいの時、仲間といたずらをした時、お年寄りにみつかり。「ウンダラなにょうやっちゅうだ」とよく怒られたものだった。そのような事から、この方言は、お年寄りが使う言葉のように。小さい時は思った、今の自分もそうであるように。若い人たちの中にはこの言葉自体知らない人もいるのではないでしょうか?今、この言葉に代わって使うのは、 「テメエ」を使うことが多い。その事から、もはやこの言葉も死語になってしまったのでしょうか?そういえば自分より10歳くらい下の奴らが言っていたとことだが。そいつらが小学生の時方言を使う事が禁止になったそうです。ただただ驚くばかりです、自分が中学生の頃、社会科の先生は。方言は島の宝だからおおいに使うようになどといってましたが。10年くらいでそこまで変わるんですね、そのうちまつたく。方言がなくなってしまうのでしようか?さびしいような反面、残念でもあります。
2005.10.06
コメント(0)
-
桟橋釣り7
きようは黒根港で試してみた、きのうが南西の風で暖かつたのに。きようは北東の風で肌寒いしおまけに、雨も降ったりやんだりの。はつきりしない一日だつた、朝6時頃より始めてみた。風を右横から受けるため、少しやりにくいのですが。せっかく来たのですからやつていこうと竿を出す。一投目早速当たりサバが食った、それから何回投げてもサバの入れ食い。しかもサバがみんな小さい、大きければ、持ち帰りもするのだが。何投目かにサバとは違う当たりが来た、やつたカンパチだ。久しぶりのカンパチのひき、さすがにサバとはぜんぜんひきが違う。そうはいつてもカンパチ自体小さいですが、やつぱり。嬉しいものです。
2005.10.05
コメント(0)
-
新島の方言1
島の方言の中には千葉方面の言葉と似通ったもの。伊豆半島や静岡方面から来たと思われるもの。京都の言葉の流れをくむものと思われるもの、流人制度から、生まれたと思われるものなどがあります。長い間島民の間に守り続けられてきた島特有の方言も。教育が広く行き渡ることによって、標準語が使われるようになり。しだいにその姿を潜めています、いつの日にかまつたく忘れ去られてしまうものと思われます。方言のおもなものを書いてみます。男に対する呼び名アカンゴ 「乳児」 ニュ- 「5歳から8歳ぐらいの子供」アンキ 「長兄」 アニキ 「嫁をとるまでの男」 アニイ [妻をめとつた男] トウ [世帯主、戸主}インジイ [隠居者] アンキラ [若者たち]この中で二ューと言う呼び名はまつたくといつていいほど使われていない?女に対する呼び名アカンゴ [乳児] モンモ [子守をする10歳前後の子供]ネンネ [長姉] モイ [嫁にいくまでの娘]アマァニィ [嫁] カア[主婦] ウンバ- [隠居者]オンバ- [嫁に行かないで、出遅れている娘]この中でモイという呼び名も使われていない?。それとオンバ-の意味も今と昔では違うような気がする。昔は二十歳ぐらいまでに結婚するのが当たり前だったようで。二十歳過ぎても嫁に行かない女の人がオンバ-と呼ばれたようだが。今はそんな呼び方をする人はいないと思う。続きはその2に。
2005.10.04
コメント(0)
-
桟橋釣り6
きょうは、黒根港の桟橋で試してみた。南西の風が強く羽伏漁港は無理であろうと諦め黒根港に決めた。風が強く少しやりにくいのですが、羽伏よりましでしょうから。朝6時、早速第一投、食った、やつぱりサバだまたまた。サバの集中攻撃に遭う、しかし何日か何も釣っていなかったから。これはこれでまた楽しい、しかし釣れるサバが小さい。何匹海に返したことか、その中から大きめの物を2匹持ち帰った。そのうちの1匹をお昼にフライにして食べた。久しぶりに食べたのでとても美味かった、もう1匹も明日あたり。またフライにして食べてしまおう。
2005.10.02
コメント(0)
-
桟橋釣り5
きょうは久しぶりに、羽伏漁港に出かけました。朝6時を過ぎてしまいましたが、ルアーを引っ張るには。1時間もやれれば十分、と言っても出かけた時間が遅かったので。場所もいい所が無い、おまけに波も高く先端は波が洗い流した。跡もあり危険と判断し岸よりで試してみた。幸い干潮時で桟橋を波が洗ってくることは無かったが。うねりはあり目の前ではサーフィンを楽しむ若者もいるさすがに当たりも無い、そのうち一人帰り二人帰りで。場所が開いたのでそちらに移動して続けた。一度当たりが来た、サバのようだが食わず。そのまま少し続けたのですが、当たりもないので。諦めて帰りました。
2005.10.01
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1