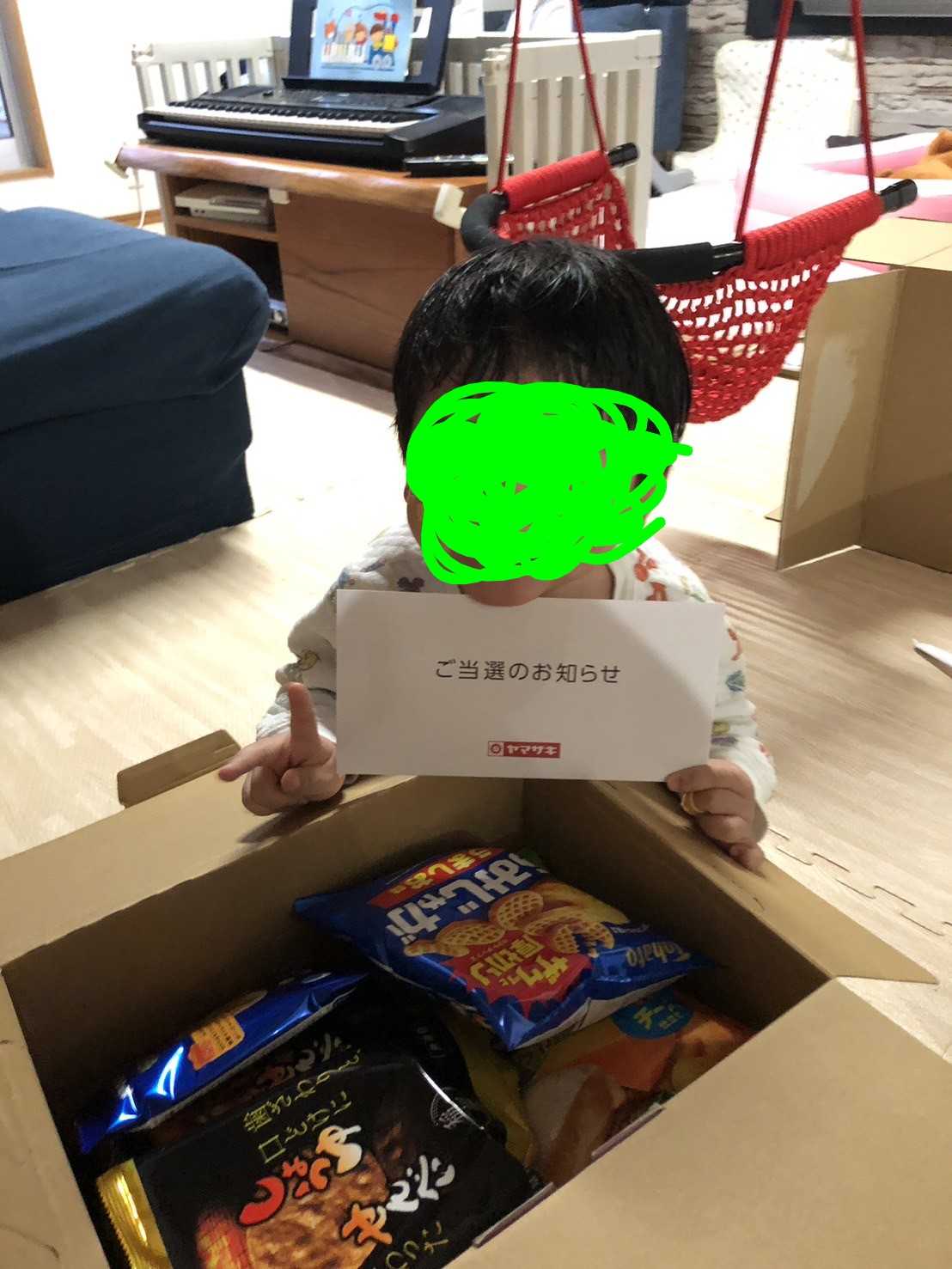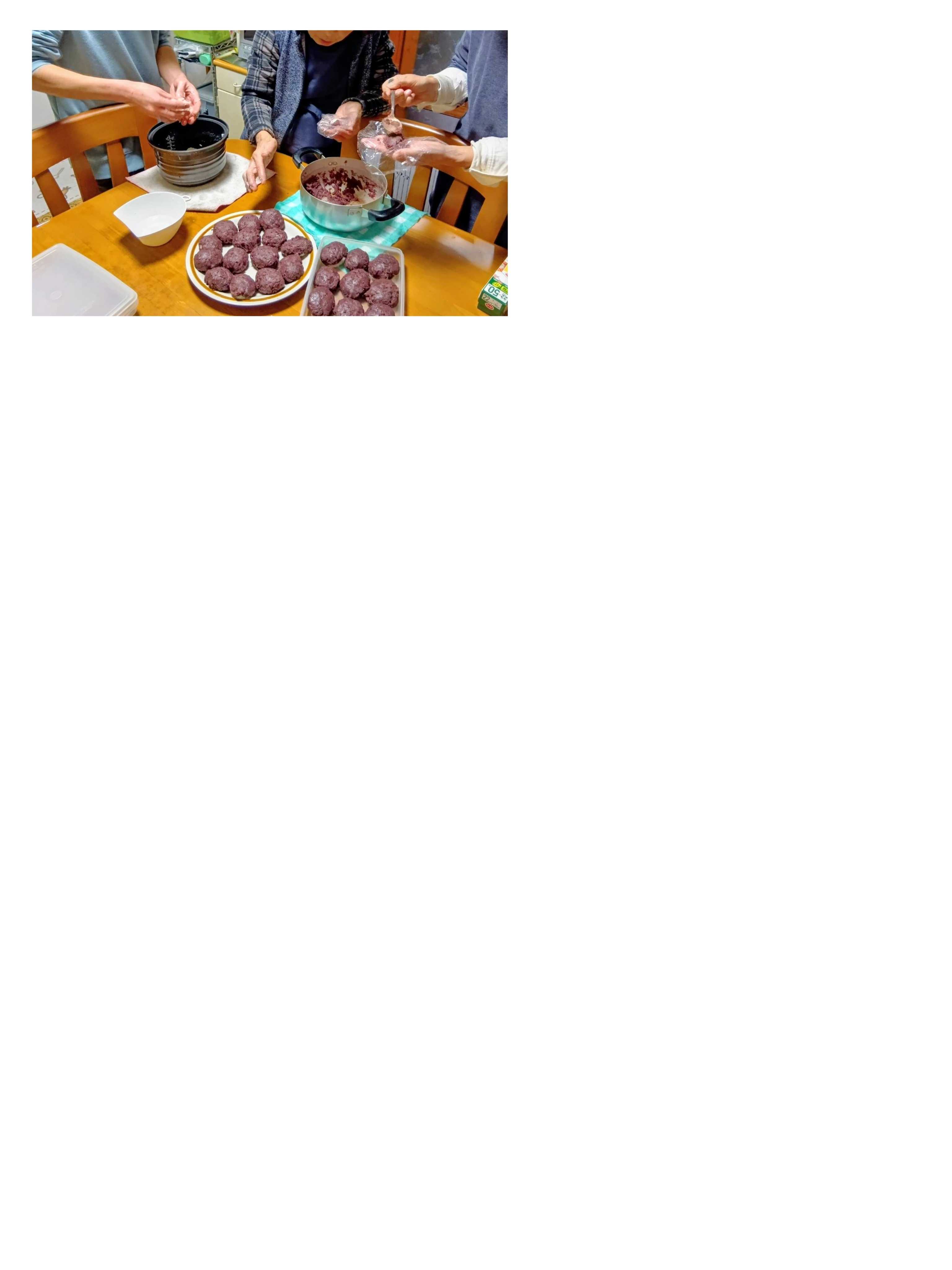2005年01月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
GPLライセンスのソフトをビジネスで使う
GPLライセンスのソフトは、「再配布や改変の自由を妨げる行為を禁じている」ということです。これは、どういうことかというと、例えば、オープンソースのXOOPSのモジュールを自分でカスタマイズした場合に、このソフトは自分のものにはならず、再配布しなければならない、ということです。要は、GPLライセンスのソフトは、それを誰がカスタマイズしようが、無限にGPLライセンスであり続けるということです。誰かが所有することができない、ということですね。ビジネスとしてカスタマイズを行う場合でもこの考え方は同じで、ある事業主の要望にそって、あるプログラマーが有料でカスタマイズを行っても、それは、やはりGPLライセンスソフトであり所有することはできないということです。あと、カスタマイズする場合に使用した「ライブラリ」(元になったプログラムデータ)の著作権表示をしなければならないなどの規定もあります。この「著作権表示」も微妙な問題で、目立つよう適切に掲載するような記述がありますが、どこにどれだけ表示しなければならないか、明記されているわけではありません。まとめますと、ビジネスにおいても、GPLライセンスのソフトでビジネスを行うことはできるけど、所有することはできないということです。このように、規制があるGPLライセンスですが、実際問題として、GPLライセンスに違反して訴えられたり、大きな問題になったことは、今までないようです。オープンであることで、「違反」を厳しく追求していく姿勢が、そもそも弱いという原因はあると思います。だから、何をしてもよいということには、つながりませんが。オープンソースは、ビジネス的にもとてもありがたいものです。私もいろいろ試していますが、完成度が高いソフトも結構あり、作者の方には、頭の下がる思いがします。自分なりに協力できることはしていきたいと思っています。以上のような、GPLライセンスソフトの、規約と可能性を知ることで、オープンソースソフトをより有効に活用できるのではないでしょうか。GPLなどに関して、もう少し詳しく知りたい方は、以下がよいかもしれません。http://pcweb.mycom.co.jp/special/2004/gnu/その他、詳細な情報は、以下にあります。・GNU 一般公衆利用許諾契約書http://www.opensource.jp/gpl/gpl.ja.html・GNU GPLに関して良く聞かれる質問http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2005.01.31
コメント(0)
-
GNU、GPLとは何か?
CMSやブログソフトなどは、有料で使えるものと無料で使えるものにわけられます。もう少し詳しく見ると、・MovableTypeのように個人的に使う以外の商用利用は有料ソフト・個人、商用もすべて無料のいわゆるオープンソースソフトに分けられます。MovableTypeのようなソフトは、基本的には他のパソコンソフトのように購入すればよいわけで、話はそれで済んでしまいます。ところが、オープンソースのソフトを使おうとすると、話はそうはカンタンではありません。オープンソースソフトは、GNUプロジェクトのGPLと呼ばれる規約に従って、配布、使用されることがほとんどだからです。そのため、この「GNU」や「GPL」について、基本的なことを理解しておかないといけません。ところが、これについて、いろいろなところで説明がされているのですが、これが、規約などの特有の言い回しなので、とてもわかりずらいのです。ということで、ここではそれをわかりやすく説明したいと思います。「IT用語辞典 e-Words」の説明がわかりやすいと思います。http://e-words.jp/まず、GNUからhttp://e-words.jp/w/GNU.html「GNU 【グヌー】読み方 : グヌー フルスペル : GNU is Not Unix FSFが進めているUNIX互換ソフトウェア群の開発プロジェクトの総称。フリーソフトウェアの理念に従った修正・再配布自由なUNIX互換システムの構築を目的としている。GNUで開発されたソフトウェアに適用されているGPLは、「あらゆるソフトウェアは自由に利用できるべき」というFSFの理念を体現したライセンスとして知られている。」とあります。いくつか、わからない言葉がまた出てきますが、とりあえずそれはおいておき、GNUとは、フリーソフトウェアの「開発プロジェクト」であり、そこで開発されたソフトにGPLが適用される、という解釈をしておきます。それでは、次はGPLです。http://e-words.jp/w/GPL.html「GPL 【GNU一般公的使用許諾】読み方 : ジーピーエル フルスペル : The GNU General Public License FSFの理念に基づいて明文化されたソフトウェアライセンス体系。主にGNUプロジェクトで開発されたソフトウェアや、その派生物などに適用されている。ソースコードの公開を原則とし、使用者に対してソースコードを含めた再配布や改変の自由を認めている。また、再配布や改変の自由を妨げる行為を禁じている。」とあります。先ほどのGNUのプロジェクトで開発されたソフトウェアを、自由に配布するための規約がGPLである、と解釈するとわかりやすくなると思います。ここで「再配布や改変の自由を妨げる行為を禁じている」ということに注目しておきたいと思います。と、長くなりましたので、次回に、実際にビジネスで、GPLライセンスのソフトを使う上での注意点を説明したいと思います。**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2005.01.28
コメント(3)
-
激安レンタルサーバーXREAはビジネスに使えるか?
ブログソフトやCMSソフトを使う場合、MySQLなどのデータベースがついているレンタルサーバーのほうが、格段に使用できるソフトが多くなってきます。激安サーバーXREAは、MySQLのほか、PostgreSQLも使え、しかも、ファイル設定を行えば、それぞれ5つのデータベースを作成できるようになっています。http://www.xrea.com/価格は、1000MBの容量で1年2,400円。COMのオリジナルドメインを使用しても、プラス990円の合計3,390という激安になっています。この機能、この価格、すごいです。ブログやCMSサイトを10コぐらい平気で作れちゃいます。問題があるとしたら、負荷率や転送量という制限があることです。負荷率とは、詳しいことはサイトを見てもわからないのですが、「CGI負荷率」とあり、それが1000ptを超えると、凍結されてしまうことがあるようです。私は2ドメイン持っているのですが、両方とも0でありゲームやチャットなどのかなり負荷のかかるプログラムを置いていない限り大丈夫そうです。あと、転送量も、1000 M bytes/1日を超えると、アカウントの帯域制限などの措置が行われることになるようです。この「1000 M bytes/1日」という数字は、例えば1000人が、このサイトから1MBのデータを自分のブラウザで読み込んだデータ量ととらえることができます。1MBのデータは、ストリーミングなど動画データなどを置いた場合ならともかく、テキストや多少の画像中心のサイトであれば、1MBはとてもいかないので、1日数千人のアクセスがあっても、耐えられる数字だと思います。ですので、1日に数万ページビューとかあるサイトだと、厳しいかもしれません。#数字についての保証はできませんが・・・このようなXREAサーバーですが、私も2つドメインを持っていますが、実用上、ほとんど問題ありません。個人事業主や中小企業などのサイト展開で、よほどの大規模なビジネスサイトでもなければ、十分に実務的に使えるのではないでしょうか。ただし、運営会社からの細かいサポートはないので、ある程度の知識を持っている方で、問題が起こった場合、自分でいろいろと解決していける方という条件がつくでしょう。サポート掲示板もあり、そこにいるユーザーさんは、親切にいろいろと教えてくれますから、サポートの悪い業者さんよりも、むしろ「サポートはいい」なんていう見方もできるかもしれません。**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2005.01.27
コメント(16)
-
筋肉は使わなければ退化してしまう
今から25年前ぐらいのマンガになるでしょうか。小林まことの「1・2の三四郎」の中で、プロレスラーの桜五郎は、「筋肉というのはな~~つかわなければ退化してしまう・・・がつかいすぎてもおとえてしまう」「そういうわけだからつかいすぎないようにきょうもてきとうにやるぞ~~」と言って、プロレスに入門したばかりの三四郎たちに、8千回、時間にすれば3時間のスクワットをやらせています。8千回のスクワットが「てきとう」かどうかは、はなはだ疑問ですが、この「つかわなければ退化してしまう」というのは、私にとっては、マツケンサンバのリズムのように、頭の中に残る言葉として響いてきます。それは「筋肉」の問題だけではなく、頭の使い方や人とのコミュニケーション、仕事の仕方など、人が行う行為すべてにわたって、言えることだと思うからです。だから、自分が行えること、人として持っている機能をなるべく多く使うことがとても大切なことになってくる、と思います。・体を動かす・頭を動かす・いろいろな人と会うことを意識して行うこと。これらを常に行うによって、新しい発見や楽しさ、感動があったり、ということが起こるのではないでしょうか。
2005.01.26
コメント(0)
-
企業コミュニケーションとブログサイト
2005年最初の投稿になってしまいました。あるクライアントのご担当からは、「最後が2004年12月じゃあ、みっともないよ」なんて、数日前言われてしまいました。(^_^;それは、ともかく、そのご担当の方と話をしたことをヒントに、企業コミュニケーションにおけるブログサイトの位置付けを2005年最初の話題にしたいと思います。結論からいえば、企業コミュニケーションの核にブログサイトがくる、と私は思ってます。企業のコミュニケーションメディアである、マス広告、チラシ、ダイレクトメール、交通・街頭メディアなどもろもろのプロモーション手法、展開の中で、その基本的な方向性を与えるのが、インターネットとそこで活用されるブログの運営方針ではないか、ということです。これは、あらゆるコミュニケーションメディアの中でも、インターネットほど、情報発信ボリューム、頻度の高さなどコミュニケーション性の高いメディアはなく、さらにブログほど、ユーザーとさまざまな視点や切り口で多様なコミュニケーションが行えるツールはない、というのがその根拠です。そうであるがゆえに、他のメディアは、その方針にそって実際の展開を行うべきであり、また、他のメディアでは、最高のコミュニケーションができるレベルであるブログサイトに、ユーザーを誘導することが重要になってくるということです。このように、ブログを使用した「更新頻度の高さ」「本物のメッセージ感」は、その根底に、企業コミュニケーションの他の手法にも影響を与えるような力を持つ、と私は考えているのですが、いかがでしょうか?
2005.01.23
コメント(0)
全5件 (5件中 1-5件目)
1