2006年06月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
登録サイトに関係なく時系列表示ができるRSSリーダー
RSSは業界的に騒がれているし、ビジネスでの取り組みも本格化してきているが、一般の人でRSSリーダーを使っている人はとても少ない。私は、登録サイトに関係なく、記事の時系列表示ができるXOOPSのxhldというRSSモジュールを使っていて、手離せなくなっているが、これができるサーバー型RSSリーダーが出てきている。RSS MARKERhttp://www.rssmarker.jp/feedpathhttp://feedpath.jp/feedreader/両方ともまだベータ版であるからか、表示が見ずらかったり、操作性が少し悪いところもあるが、それでも、RSSリーダーの進化を感じさせるものになっている。時系列表示のほかにも、フィードのインポートができる、「OPML登録」を装備しているので、他のRSSリーダーとフィードの共有もできる。また、「feedpath」では、タグやブックマークレットの機能なども、装備しているし、その他の機能も装備予定のようだ。RSSリーダーをまだ使っていない方や、ほかのリーダーを使ってあきらめた人なら、一度試してみてはいかが?**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.29
コメント(0)
-

『インターネットマーケティング・ハンドブック』杉山勝行、生井俊、武田一也、吉田雅宏著を読む
Webの世界は、とんでもなく早い。この本が3年前よりもっと前に思えてしまう。それでも、インターネットマーケティングのフレームワークとして、「ヴィックスドロップ」(VICSDROP)は興味深く読めた。ちなみに「ヴィックスドロップ」は大正製薬が出しているのど飴の商品名と同じである。この本のヴィックスドロップとは、以下のとおりである。VVisual(視覚)Virtual(仮想)IIndivisual(個人の)Interactive(双方向)International(国際的)CCost(安価)Customize(個別対応)SSpeed(迅速)Sound(音声)DDatabase(データの蓄積)Data Communication(データ交換)Download(データを取り込む)R(L)Retrieval(検索)Link(他のホームページとの連携)OOnline(瞬時につながる)PPerson to Person(個人と個人を結ぶ)確かに1つひとつの要素は合っているし、インターネットの可能性を示す言葉としてとらえることができる。それでは、言葉遊びのついでに、こういった成分(要素)からなる薬としての「ヴィックスドロップ」は、事業のノド元を治してくれる、やさしい薬になってくれるのだろうか?この本全体としては、今読むべきところは、少ないといえるかもしれないが、インターネットマーケティングについて、基本的なことはわかるだろう。2003年にこの本が出てから、Webではいろいろなことが起こりすぎている。★2つ ★★☆☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.28
コメント(0)
-
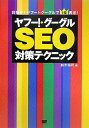
『ヤフー!・グーグルSEO対策テクニック-目指せ!ヤフー・グーグルで1位表示』鈴木将司著を読む
こういうSEO(サーチエンジン最適化)の本を読むと、不思議な感覚がする。それは、何であろうか?SEOとは、一言でいえば、「ミネラルウオーター」とか「フローリング」のような一般的な単語をユーザーがサーチエンジンで検索したときに、自社サイトが上位に表示されることである。売り手も、そして買い手も、この「ミネラルウオーター」や「フローリング」という一般的な単語にとことんこだわることに、この不思議さは存在する。どういうことかというと、ネットにおける買い手の購買行動では、明確に目的とした商品カテゴリーや商品アイテムがある。このとき、商品カテゴリーであれば、「ミネラルウオーター」や「フローリング」という、単語によって、情報や商品を探索するために、自らの購買行動を考えようとする。これは、自分の購買行動において、買いたいものを検索するためには具体的な単語に変換する作業が必要であるということである。検索しなければ、わざわざ考えて最適な結果が表示されるような単語や単語の組み合わせなどを考える必要などない。かくして、売り手は、「ミネラルウオーター」とか「フローリング」などこの一般的な単語をめぐって、1つでも順位を上げるため激しい争いをすることになる。SEO対策以前では、売り手は、自らを売るためには、その商品を訴求するために必死でオリジナルのコピーを作り、メッセージを発信することが、最優先にこだわる言葉だったはずだ。そこでは、一般的な単語は排除され、オリジナルのメッセージ性こそ価値があった。今でも、そのこと自体の価値は変わらないが、インターネットにおいては、コピーとしての言葉よりも、SEOとしての一般的な単語のほうが、はるかに優先するのである。オーバーチュアやアドセンスなどリスティング広告を見てもそれは同じである。冒頭の不思議さとは、あまりにも一般的な単語が、インターネット上でこれほど価値が出るということ、そして、ある単語になると、信じられないような高額で取引されているという事実である。価値とは、人が認めるから価値なのであるが、こちら側としては、何もいじれない、加工しようもない一般的な単語そのものの価値とはいかなるものなのか?これは、その単語そのものの価値ではなく、その単語が関係するビジネスとしての価値であると頭ではわかるが、一般的な単語そのものを売ってしまうビジネスは、やはり不思議としか思えない。それは、コピーライターがさんざん悩んだ言葉とは、あまりにも異質すぎる。一方、SEOから見て一般的な単語にこだわると、それはほとんどテクニックだけの問題になってくるのである。話が少しずれたが、本書は、ヤフー、グーグルで上位表示をねらうには、両サイトを詳細に検証しており、また、具体的な施策が目白押しで、とても参考になる本である。★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.25
コメント(0)
-

『RSSマーケティング・ガイド-動き始めたWeb2.0ビジネス』塚田耕司、滝日伴則他著を読む
RSSはXMLベースのフォーマット規格にすぎない。「すぎない」といってしまえば、この一言で終わってしまうところだが、そこで終わらないところが、RSSのすごさなのだろうか。RSSはXMLフォーマット規格だから、まずRSSリーダーで読むことができる。そして、ソーシャルブックマークで、Web上でRSSが共有され、トラックバックなどによってリンクされたりというフォーマット規格であるがゆえの特性を活かし、トラフィックが拡散していく。そこで起こるのが、ページ単位での情報アクセスである。従来であれば、サイトのトップページから、目的のページに遷移していくが、RSSはページ単位で情報を切り取るので、サイトの中の特定のページへ直接アクセスしていくことになる。ということは、Web上でのユーザー行動が、根本的に変わることになるのである。また、RSSは自分にとっての情報ポータルになるものである。自分にとってのポータルサイトはヤフーなどのサイトではなく、自分のRSSリーダーになるということだ。実際に私にとってのRSSはそうなのであるが、このRSSの使いこなしが、自らの情報武装にとって、とても重要なことになってくるのである。このような状況認識で、RSSマーケティングはどうなるか、というのが本書のテーマである。RSS広告、RSS検索、口コミ、アクセス解析、メルマガとの違い、そしてモバイルRSSという視点からRSSの動向に詳しいRSS関連ビジネスを実際やっている5人からそれぞれ語られることになる。RSSをいろいろな視点から見ていることが、とても参考になる。★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.21
コメント(0)
-

『Webマーケティング-入門eビジネス』多比羅悟、佐藤尚規著を読む
こういう少し前(2000年発行)のWebマーケティングの本を読むと、Webの世界は、いかに進化が早いかがわかる。Webというツールは、いろいろな人がいろいろな視点から、たくさん使っていくことで、その本質が出てくるということだ。例えば今は、Webはユーザーが参加するメディアである。この本では、こういった視点がほとんどない。この本におけるWebマーケティングは、Web以前の流通機構や情報流通の枠組みの中で、Webをとらえているのである。だから、Webは企業が活用するメディア、ツールとなり、その点からのみ、Webが説明される。これは、今だからこそ言えるのだろうが、この本は、Webマーケティングというより、マーケティングにおけるWeb活用の本なのである。そのため、内容的にも、Webがつかないマーケティングの話が多くなる。その中で、いくつかなつかしい話がでてくるのは楽しめる。Web広告の手法のところで、サイト同士でバナーを交換するとか、企業サイトをオープンしたときに、「オープンしました」といって、掲示板に書き込むような話である。確かに、このやり方でアクセスをたくさん集めることができたのは、今だと笑い話のような話である。最初のほうで、Webマーケティングとはの説明に、「インターネットを使ってビジネスを行う企業が、売上を伸ばすための手段」といっているのだが、5年前なので仕方がないのだが、この認識は少し甘い。私が一言で説明するならば、「インターネットならではの技術やしくみを使いながら、企業が顧客とコミュニケーションを行い、顧客と一緒に価値を創造していく手法」のことである。★2つ ★★☆☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.17
コメント(0)
-

『「口コミ」の経済学-人が人を呼ぶ“ブーム”の作られ方』田中義厚著を読む
この本で、ある作家の言葉として、「結局、人生最大の喜びとは、自分と完璧に話の合う人間と出会うことだ」とあるが、「話の合う」とはどういうことだろうか?だれかと話をするとき、この人とは話が弾むとか、話が合うと思うときがある。でもそれは、考え方とか価値観が同じとか似ているというときもあれば、そうでもないのに、そう感じるときもある。だとしたら、それは相性である。でも、相性なんか合わなくても、人は話す、それは話をしたいからであろう。口コミとは、人が話し好き、それも、大変な話し好きだからこそ起こるものなのである。しかも、最近のインターネットという、表現手段を持った人は、今まで以上に、ブログなどのCGMを使って「話す」ように書けるようになった。と考えれば、私もこうやってブログを使った「話」好きとなる。この本の中で、口コミとはどういうものかの説明は、ラーメン屋の話がわかりやすい。ラーメン界には、カリスマ・ラーメン通がいるので、ラーメン屋の店主は、こういった人の評価をとても気にするという。カリスマ・ラーメン通が、「うまい」といえば、店は繁盛し、「まずい」といえば、店の存亡にかかわってくる。だから、店主は、カリスマ・ラーメン通に、アプローチ攻勢をかけるのである。本の後半では、マーケティング的な活用の仕方にも触れ、メッセージを人に話すように作れば、人から人に伝わりやすくなると言っている。その企業側のからの取り組みは、「クチコミはこうしてつくられる-おもしろさが伝染するバズ・マーケティング」という本をわかりやすくした感じか。全体的には、「口コミ」とは何かが、手軽に理解できる本になっている。★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.14
コメント(2)
-

『間違いだらけのWeb戦略-物販サイト、成功の秘訣!』加藤忠宏、杉山啓子著を読む
この本の最大の売りは、SEO対策とキーワード抽出についである。SEOとキーワードについて、著者が実際に手がけているサイトで、その企業の業務内容や経営戦略を見ながら、アクセスログを参照して、Web上のキーワードツールなどを使いながら、検索サイトで実際に試し、ということを入念に行っている。個々の検索エンジンの特徴も、自分で試してよく研究している。Webから売上を上げようと思ったら、Webにアクセスしてもらうために、まず、この部分を特にやらないといけない。ユーザーアンケートのところは、ユーザーがWebサイトに求めている見せ方にもかかわらず、絵がないのがわかりずらい。10コほど紹介されている事例は、部分的に参考にしたい個所がある。著者は、全国で仕事しており、Webに関する地域的な取り組み姿勢が違う、という話はおもしろかった。その姿勢は、戦国時代にまで遡って考えることができ、戦国時代の被支配地域や山間部などは、ネットビジネスが難しいという。人との関係の持ち方は、地域的に継承され、今でもネットビジネスへの姿勢とその運営にまで影響する。あと、最後に著者がよく聞かれる質問集があり、セミナー参加者からサイトが「ダサい」といわれて、ちゃんと説明したあと、最後「余計なお世話です」という言い方をしているのは、著者の人間性が出ている。全体的な読後感としては、Webビジネスはしつこく、ということだ。★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.12
コメント(0)
-

『グーグル Google-既存のビジネスを破壊する』佐々木俊尚著を読む
『ウェブ進化論』にしろ『Web2.0 BOOK』にしろ、インターネットの今を知ろうとして読んだのに、その中心にはグーグルがあった。その延長線で、本書を読んでみた。この本では、ビジネス社会を変えるグーグルと、権力としてのグーグルという、大きく2つの面からグーグルが語られる。ビジネス社会を変えるグーグルは、例えば、羽田の駐車場や北陸のメッキ工場という小さな事業者が、グーグルのアドワーズ広告のサービスを利用することで、いかにビジネスを成功させているかが説明される。つまり、既存のメディア形態、ビジネスにおさまらない、ニッチなビジネスマッチングを可能にしているグーグルという、あのロングテールの話である。一方、権力としてのグーグルは、世界中のすべての情報を集め、(その中には人の行動情報まで含まれる)それを元に、ビジネス展開するという話である。その未来の展開を予想している雑誌の引用をして、例えば、これから始めるグーグルテレビでは、視聴者は、テレビを見る際にIDを入れ、そのIDで視聴者の視聴データを蓄積し、その人に最適な広告が放映される、という、いかにも本当に実現しそうな話を紹介している。著者の経歴を見ると、ジャーナリスト出身なので、最終的に権力論になってしまうのは、いかにもという感じがする。しかし、権力というものを、(この本で使われている「環境管理型権力」「規律訓練型権力」という難しい言葉ではなく、もっとわかりやすく私なりに翻訳すると)上から明らかに強制してくる力と自然に自ら持ってしまうように仕掛けられてしまう力にわけ、グーグルを後者に分類するときに、グーグルという会社の目指すビジネスが見えてくる。そうなってくると、いさかか宗教的な匂いもでてくるわけで、本の後半になってくると、「司祭グーグル」という言い方になってくるのは当然か。とはいえ、あらゆる情報を握るということは、そこまで可能なのか、それはメディアとアルゴリズムの組み合わせによってできるのか、疑問は、やはりそこになってしまうようだ。グーグルについて、少し考え始めると、際限なく難しくなっていきそうだ。★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.09
コメント(0)
-

『ウェブ進化論-本当の大変化はこれから始まる』梅田望夫著を読む
確かヨーロッパ中世に書かれた絵で、外部からのエネルギー補給もなしに、永久に動き続けるのは、完全機関というものでしたっけ?上から水が流れていて、それを水車で受け止めて、そのエネルギーを滑車に伝え、滑車が、水をくみ上げ、その水を、また上から流す。実際には、重力や摩擦の問題があるから、こんなことは不可能であるのだが、それでも、ある種の夢を与えるものになっている。という反面、これを、夢などというべきではないという判断も働く。重力や摩擦は絶対条件であって、それを除外することはできないからだ。この本には、いろいろな要素があって、一言でこういう本であるとは言えないのだが、グーグルの話のところが、一番大きな盛り上がりを見せていると思う。このグーグルのところを読んでいて、私の頭に浮かんできたのが、この完全機関のイメージである。この本を読んでいると、グーグルという会社は、さまざまな視点から見ることができるのだが、その中で、独自の情報収集と処理と表出を行う、アルゴリズムの会社である、という見方ができる。このアルゴリズムで目指すのが、ユーザーが、自分の情報収集と活用についての完全機関ではないか、ということである。しかし、完全機関が機能しないように、アルゴリズムは人にとって完璧にはならない。だが、完全機関が一切機能しないのに対して、アルゴリズムは、限りなく、完全に近づける可能性がある。その辺が、どんなことになるのか、アルゴリズムは、グーグルの社内だけしかないので、その将来性は想像していくしかない世界である。ロングテールは、アマゾンのビジネスにおいて説明されることが多いが、グーグルにおけるロングテールのほうが、アドセンスなどの展開において、世界民主主義を表明している点などにおいて、実際は、興味深いものがある。そして、グーグルビジネスの驚異的な成長と、1人あたりの社員が生み出す利益の莫大さに驚く。大横綱であるマイクロソフトを、きれる頭脳で素早く状況判断しながら、若い力と機敏な運動神経で、ぐいぐい押しまくってくる新大関グーグル。そう、グーグルは、いつのまにか大関なんである。勝負は、時間が決めるような気もする。しかし、そんなマイクロソフトが開いてきた、世界共通言語であるOSを、もっとWebベースで強力に推進することになるグーグル世界構想をわれわれは、どう受け止めればいいのだろうか?その中で、Webの世界を、グーグルとマイクロソフトという対立のみならず、世代間における若い世代の可能性も含めた見方も、興味深く読めた。といっても、この本は、基本的には、全社会的な視点からWebの今を見せてくれている。なので、Webの世界以外の人が読んでも、いろいろな見方を提供してくれ今の自分のポジションについて考えさせられる、啓蒙の書といえるかもしれない。★5つ ★★★★★**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.07
コメント(0)
-
ブランコは、足でこぐのか?
ブランコは、前に進むとき、足を伸ばすことで、後ろにいくときに、足をひっこめることなのであろうか?近くの小学校の校庭で、私が鉄棒を使って軽い筋トレをしていると、その脇のブランコで3歳ぐらいの子どもに、お父さんがそう教えている。前に行くときに「足を伸ばして~」。確かに、ブランコに乗る動作はパッと見るとそうである。でも、この言葉通りのことをいくらやっても子どもは、ブランコをこげるようにはならない。つまり、ブランコをこぐというのは、足の動作の問題だけでないからだ。ブランコをこぐには、手も使えば、肩も使う、腰も使うし、背中の筋肉も使う。カラダ全体を使うのだ。お父さんは、こんなことはわかっているのだろうが、お父さんは、教え方が間違っているのである。しかし、子どもは、この言葉の信憑性とは別に、ブランコの乗り方を覚えていく。自分で、ブランコの乗り方を、ブランコに乗ることで覚えていくからだ。かくして、お父さんは、自分が間違った教え方をしていたことを永久に知ることはない。子どもがブランコに乗れるようになったのは、自分の教え方がよかったからであると、逆にそう思ってしまうだろう。ささいなことかもしれないが、このすれ違いは重要である。ここでは、実は2つの大きなことが起こっている。まず、お父さんのものごとの捉え方である。お父さんは、ブランコに乗るということを単純化しすぎている。ブランコに乗るということは、ブランコを操ることではなく、自らのカラダを振り子現象のなかにおくことの気持ちよさにある。そういった本質をとらえるのではなく、ブランコにうまく乗ることを教えている。これは、処世術なんである。処世術から入ると、モノゴトの魅力がなくなってしまうのである。子どもに処世術を教えてはいけない。教えるとしたらブランコの楽しさである。あと親子関係の問題が早くも起こっている。親は、間違った教え方を平気でしてしまう、ということだ。でも、子どもは、間違ったことに気付くこともあれば、内容によっては、気付かないこともある。そして、子どもが気付いたときに、親子できちんとコミュニケーションがとれるかどうか、ということが大きな問題になる。こういったことが、親子関係のコミュニケーションにおいて、頻繁に起こっている。コミュニケーションがとれる親子関係ならよい。しかし、このコミュニケーションができずに、その状態が続き、ある限界を超えたときに、今起こっているような事件に発展する可能性がでてくる。親子間コミュニケーションは難しいのである。しかし、あきらめてはいけない。そこで求められるのは、きちんとコミュニケーションしようとする、態度と行動なのである。この「きちんと」が、難しいのであるが。**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.05
コメント(0)
-

『Web2.0 BOOK』小川浩、後藤康成著を読む
ITバブル以来の盛り上がり?を見せているWeb2.0。この本は、Web2.0について書かれた最初の本である。Web上でも、Web2.0というテーマの記事をニュースサイトを中心に多く見られるようになっているが、その概念は、Web2.0的だね、というニュアンスで語られることが多い。では、この本は?Web1.0→OS、Web2.0→Web、という説明のしかた、つまり、マイクロソフト対グーグルという図式は理解しやすい。そして、Web2.0的なサービスがAjaxやマッシュアップやら何やら、新しい言葉でいろいろと取り上げられていくのだが、その中で、Web上で動作するワープロソフトなどが出てきているということがWeb2.0的であることへの、理解の早道ではなかろうか?もう少し説明すると、Web2.0は、Web1.0時代のパソコンのプラットフォーム、つまりOSに依存しない、OSが何であっても、ブラウザ上で作業が可能になっていき、そういうやり方がどんどん発展していくという概念のことである。その最先端をいっているのが、グーグルであると。簡単にまとめると、以上になるだろうか?本全体から言えば、最初のほうのWeb2.0までのWebの歴史が、とても興味深く、うまく書けている。それにしてもこの本はすごい。私などは、この本で使われるような言葉には慣れているが、ひらがなの間をカタカナと英数字がみだれとぶ。Webの世界に無縁な人が読めば、チンプンカンプンであろう。これが、ITという世界なのだろうし、Web2.0に関する最初の本なので、そうなるのであろうが、この本の書き方とは裏腹に、ますます、ユーザーにとって簡単になっていくのが、Web2.0の本質であろう。Web2.0の提供する世界がどんなものになるのか、興味はふくらむばかりである。この本は、その期待感を提供してくれていることに成功している。★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.04
コメント(0)
-

『インターネット・ブランディング-成功するマーケティング』赤木稔著を読む
インターネット・ブランディングを私が説明するなら、Web上でのコンテンツとコミュニケーションプロセスを、どう作り、どう演出するかの話である。コンテンツは、その企業なりの理念とコンセプトに立脚したその企業にふさわしい展開をいかに行うかの話であり、コミュニケーションプロセスは、企業と顧客、ならびに顧客とWebサイトのコミュニケーションのプロセスを、いかに構築するかの話になる。(もっと大きく顧客と顧客という視点もある)それを、Webならではの技術やしくみを使って行うことが、インターネット・ブランディングである。インターネット・ブランディングを語るとしたら、どの企業にもあてはまるような方法論としてこのような趣旨で提示すべきである。この本は、ヤフーのビジネスのあり方から、このインターネット・ブランディングの方法を学び、そこから、学ぶべき視点などが示される。それは最後のほうで10点にまとめられるが、ヤフーで学べることと、他の企業で行えるインターネット・ブランディングの関連性が、薄いように感じるのである。確かに、これほどのビジネスに成長したヤフーであり、今でも拡大を続けることから学べることはたくさんある。ただ、この本で提示している点は、ヤフーから学べるものは、今のヤフーだからできるものであると思えてしまう。ヤフービジネスは、そうは、真似することができないことをやっているのであって、だからこそ、ヤフーなのであろう。例えば、ブログやSNSサービスなどは、ヤフーだから一番あとに参入してもビジネスになり得る。つまり、ヤフーの事例からは、われわれのインターネット・ブランディングは、できないということだ。この本は、インターネット・ブランディングというより、サブサブタイトル?にある文を引用して、私がつけるなら「ヤフーに見る・学ぶ!インターネット・トップ企業のビジネスのやり方」というタイトルがふさわしい。★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.06.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1










