2006年08月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

『図解でわかるAjaxのすべて』清野克行著を読む
「Ajax」(エイジャックス)とは、わかりやすくいうと、Webの使い勝手を今まで以上によくする、今注目の技術である。というものの、技術的にはJavaScript+XMLのことであり、目新しい技術を使っているわけではない。操作レベルで考えるほうがわかりやすく、例えば、オンラインパソコンショップでこのAjaxを使っているとしたら、ノートPCというカテゴリーをクリックすると、瞬時に製品ラインナップが表示されるというようなしくみである。これは、ブラウザとサーバー間で、つまり、JavaScriptとXMLの間で必要な情報のみを瞬時にやりとりするというしくみによって成り立つ。これを「非同期」的な通信という。これによって、Webを使う側は、ページごとのWebアクセスから開放され、Webページの使い勝手がよくなるというわけである。ただ、問題はJavaScriptの、ブラウザ間の互換性の問題。いろいろなブラウザを使用している、一般ユーザー向けサイトでは、使用ブラウザを限定するか、多くのブラウザに対応させるために、開発工数やテストなどを多くかけることになる。なので、このAjaxは、一般向けサイトよりも、社内業務用のシステムなどのほうが、ブラウザを限定できるため使いやすくなる。例えば、販売管理や経理システムなど、特に入力数が多いような業務にである。このような業務では、コードを入力することで科目が瞬時に出てくるようなシステムとして使うことができ、入力スピードなどの利便性を高めることができるのである。業務システムのほか、Webアプリケーションの分野で、開発できないものはないのである。(ただ、JavaScriptの問題は現在ではつきまとう)だから、Ajaxは、とても魅力的なものである。この本を読むと、こういうことがわかる。#読書時間 2時間(サンプルコードなどは読み込んでいない)★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.30
コメント(0)
-

『1時間でわかる図解Web2.0』内山幸樹著を読む
この本は、表紙に書いているように、Web2.0を「人の知識を活用する『知識循環』を引き起こし、『インターネットを人にやさしくする仕組み』」とする。そして、その要素として、「利用者の参加」「利用者の知恵の再利用」=集合知「情報の流通性の拡大」とする。それから、その中でブログやグーグルページランク、WikiPedia、ロングテールなどのサービスやしくみを位置付け、マーケティングや技術的なことを説明していく。全体としては、Web2.0の概念や現象や内容など、わかりやすく説明されている。おもしろかったのは、@コスメの吉松氏と著者との対談である。吉松氏は、@コスメサイトを内容的にはWeb2.0技術的にはWeb1.5と位置付ける。内容的には利用者参加ということであり、技術的には、RSSやトラックバックなどの技術が使われていないことである。そして、化粧品のマーケティングデータをビジネスにすることの難しさにふれつつ、そのビジネス展開における、方向性をどうするかが話の焦点になっていく。つまり、これは、Web2.0のビジネス展開の可能性についての話になる。Web2.0になっても、Webビジネス展開の難しさは、相変わらずついて回るのである。ちなみに、@コスメにある膨大なデータは、Webの中で完結するのではなく、リアルの中でどう生かすかという道が模索されているようである。#読書時間 1.5時間(タイトルにある1時間では読めない)★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.28
コメント(0)
-

『Googleマップ+Ajaxで自分の地図をつくる本-Google Maps API徹底活用』米田聡著を読む
Googleマップで、どんなことをどのようにすればできるのかを知るために、本書を読んでみた。まず、Googleマップを使うためには、地図上に位置情報を入れ込むための経度と緯度に関する知識が必要だ。このときに、地球の形の話になる。それは、地球は球ではなく、赤道あたりの円周が長く、北半球よりも南半球のほうが幾分大きく、部分的にあちこちでかなりでごぼこしているという地球全体を頭でイメージすることになる。それは、あまり考えることもない不恰好な地球のイメージであるが、そうであるがゆえに、計算上の経度と緯度は、実際のGoogleマップ上の位置とは、必ずズレが起きるのである。この話は、前提とする知識にすぎないのだが、なんとグーグルっぽい話なのだろうか、と思わずにはいられなかった。それは、世界中の情報をくまなく集めるという、グーグルの姿勢と通じるものがある。地球全体というマクロの視野と、その地球上のあらゆる場所というミクロの視点をともにもちながら情報化ツールとして活用していくのが、Googleマップだからだ。このGoogleマップに、飲食店やら企業やらなんでもいいのだが、あらゆる情報をだれもが好きなように掲載していけるのである。そのやり方を説明しているのが本書ということになる。内容的には、Googleマップ上に、自分で好きな場所を入れこむことを基準に、データベースと連携して複数の場所を登録して、それぞれの地図に場所情報を登録していくやり方などが説明される。地図を表示されるだけならそれほど難しくないが、JavaScriptを基本に、XML、PHPなどさまざざまな技術が使われる上、グーグルが提供しているAPIの仕様への理解が必要になるため、ある程度のことをやるとすると、プログラマー以上のスキルが要求されるだろう。ただ、技術者でない私が読んでも、Googleマップの特長やできることは、理解できるようになっている。あちこちで見ることができるGoogleマップだが、その使い勝手もよく、おもしろいものも見かける。今度は、どのような情報の組み合わせがでてくるか、それを可能にするのは、あなたということか。#読書時間 1.5時間(コードや仕様などは読み込んでいない)★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.27
コメント(0)
-

『本当に役立つ!マーケティング入門』町田和隆著を読む
この本がいうように、中小企業に関するマーケティングの本は、ないような気がする。それは、中小企業の場合、経営術というもっと全体でとらえるか、もしくは営業術という戦術としてとらえる、という両極端の話になりがちだからだろう。そういう点でこの本は、中小企業のマーケティング入門書としての枠組みを提示できている。SWOT分析や4Pなどおなじみのマーケティングの手法や理論を紹介しつつ、大企業に通じるマーケティング理論とは違った、中小企業ならではの視点をおりまぜ、ときには大胆に違った見解を見せる。その中でも著者のやり方の特長を見せるのは、4Pに追加される3Pであろう。3Pというのは、target Profingcommunication Processmarket PositionningのPのことで、中小企業なりのターゲットの探し方、そのコミュニケーションの取り方、そして、商品ポジションのやり方、である。このように、中小企業というポジションならではの、マーケティングの枠組みと実践論が語られるのである。全体的な印象としては、リアルマーケティングが主体になっている。しかし、今ならやはりWeb活用の重要性がもっと高まっている。一部、メルマガやブログなどの記述はあるが、Webには、リスティング広告やアフィリエイト広告など、中小企業が活用できるツールなどは、リアル以上に充実してきており、その辺の取り組み方法が欲しいところだ。あと、こういった本が、ほとんどマーケティングノウハウになってしまうのは仕方のないところなのだが、中小企業ならではの、マーケティングコンセプトの話も欲しい。それは、大企業とは全然違うはずで、中小企業が行うマーケティングの魅力や価値は、どのように創造するのか、できるのか、その辺の説明を読みたい。それでも、中小企業にいる方なら職種や地位に関係なく、読んでおきたい本になっている。#読書時間 2時間★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.25
コメント(1)
-

『「へんな会社」のつくり方-常識にとらわれない「はてな」の超オープン経営術』近藤淳也著を読む
やっている外面だけを見れば、それが「非常識」に見えるが、きちんと説明すれば「へん」でもない。この本を読むと、タイトルとは違って、ネット企業はてなのまっとうさがよくわかる。立って会議をするのは、座って会議をするより効率的にできるし、毎日席を変えるのは、社内のコミュニケーションを最大限活性化するためだし、社内でだれもがみんなのメールを読めるのは、業務のプロセスそのものにみんながかかわることで、業務そのものの生産性、創造性を高めるためだ。そして、それが、はてなが提供するサービスの基本姿勢につながってくる。それは、ソーシャルブッマークなどにそのまま現れているほか、公募したアイデアを社内会議で審査するその様子をネット上にポッドキャストで放映、公開してしまうようなやり方にもなっている。その根本的なところには、妻ときちんとコミュニケーションすることが大切であり、身近な人ときちんとコミュニケーションできない人が、会社や社会できちんとコミュニケーションできるわけがない、というコミュニケーションを大切にする姿勢がある。それは、学生時代に生徒会長などをやりながら、規則などを強制されてきた著者が納得できなかった、規則ができた理由やプロセスそのものが「隠蔽」されていることの実感をした経験に基づいている。だから、「常識」となっているものの背後にある、「隠蔽」されたコミュニケーションプロセスそのものを考え、それを新しい社内のやり方やはてな自身のサービスとして提供し続けるのである。これを理解すると、はてなという会社は「へん」でもなんでもなく、とてもまっとうな会社であることがわかるのである。著書の中で気になることがあるとしたら、著者は世の中は「でたらめ」で成り立っている、と見ている点である。しかし「でたらめ」と言ってしまうと、はてなのやっていること自体が、「でたらめ」であると言われてしまう。このように「常識」そのものを疑い、確かなコミュニケーションを大切にして、ネットを活用して価値あるサービスを提供していることが「でたらめ」なのだろうか?こういうある種自己否定につながる言い方をしてはいけないだろう。あと、気になるのは、毎日すわる席を変えてもあの人の隣の席にはすわりたくないという人はいないというが、そうなると、はてなに今集まっているのは同じような人ばかりになっているのではないだろうか?そこのところをどう考えるか、はてなが抱える問題になるような気がする。最後には「ウェブ進化論」の著者であり、はてなの役員にもなっている梅田望夫の寄稿文も、著者との関係が垣間見えていておもしろい。それは、まず世代間格差を感じるものであるが、実践家(著者)と学者(梅田氏)の違い、つまり実践家が案をだし、学者が解釈するという2人の関係性がよくわかるのである。しかし、この本は、はてなという会社は、ベースとなることをきちんと考えながら、サービスを提供している企業ということがよくわかる本になっている。簡単に読めるが、とてもよい本である。#読書時間 2時間★5つ ★★★★★**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.24
コメント(0)
-

『走って、食べて、ヘルシーライフ!』谷川真理著を読む
へんな人であることはいいことである。テレビなどで見る限り、著者はそれほどへんな人であるとは思えないが、著書を読んでみると、へんさ加減がとてもよく出ている。それは、まず著者が走り始めた頃の話にある。24歳のOLで、いろいろ遊びまくっていた著者は、ある日、会社の昼休みに友人と皇居に行くと、走っている人たちに魅了される。そして、その翌日には皇居1週コースを走り始める。友人と昼食もとらず(そのかわり15時の休み時間に簡単にすませる)、汗をかいたカラダにシャワーも浴びずに、昼休みの1時間を走ることに使い始めるのだ。もともと、学生時代には、中距離選手だったため走ることの基本は知っているが、やらされて走らされていた著者は、さぼることばかり考えていたため、優秀な成績を残すことができなかった。それが、24歳になって自発的に走り始めることで、走ることの楽しさに目覚め、そしてすぐに、男性ランナーよりも、早く走れるような実力がついてくる。そうしているうちに、皇居を走るほかのランナーと知り合いになり、情報交換しながら、目標を定め、市民マラソン大会、そしてついには、東京国際マラソンで、優勝してしまうのだ。前半は、このような著者の経歴が語られるのだが、今までの友人関係や遊びとの関係を大きく変換して、ここまで走ることに固執する理由は、何かを求めていること以上の理由はわからず、まさに「へんな人」としか思えないのである。へんでなければここまでやらないだろう。また、人から命令されたり、やらされたりすることが大嫌いな著者は、自発性の大切さを強調するが、それほど人にやらされることを拒否する姿勢もまた、「へん」なのである。しかし、この「へん」さがあるからこそ、その後の輝かしい実績が生まれたのだろう。そして走ることはへんな著者にとても向いていたのだ。この本は、タイトルとは別にこういう著者のへんさ加減が目立つ本である。もちろん、走ることについて、著者なりのさまざまな情報はあるし、著者が実際料理するランナー向けのヘルシーメニューのレシピまでのっている。しかし、全体としては、ランナー谷川の走る哲学の本であろう。人を強く動機付ける方法として人がどう思おうともへんなことを徹底すればよいのである。●読書時間 2時間★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.23
コメント(0)
-

『ウェブ戦略としての「ユーザーエクスぺリエンス」-5つの段階で考えるユーザー中心デザイン Web designing books』Jesse James Garrett著を読む
企業Web構築においては、ユーザーエクスぺリエンスを元に、表層段階骨格段階構造段階要件段階戦略段階の5つの段階で考えるべきである。この5つの段階は、下から考えていくものだが、1つの段階が完全に終わってから、次の段階に進むものでなく、重なりながら進行するものである。そして最終的には、この5つの各段階に整合性があり、うまくつながることで、よいWebサイトができあがる。この本全体の骨子は以上であり、とても明解である。5つの段階をもう少し説明すると、表層段階→デザイン、見え方骨格段階→ページごとのレイアウト(いわゆるワイヤーフレーム)構造段階→サイトの全体構成(いわゆるツリー図)要件段階→サイトの機能と仕様→求められる情報戦略段階→実現したいビジネス→ユーザーのニーズに対応という話になる。骨格段階においては、ソフトウエアからの見方とハイパーテキストからの見方というように、見るべきポイントなどが示されている。そして、各段階において、ユーザーエクスぺリエンスをどうとらえるかも、調査手法などとからめて述べられる。実際Web構築の作業をしていると、この5つの段階のどこかが、手薄になってしまったり、ユーザーエクスぺリエンスを考慮しなくなってしまうことも多いものだ。そういう意味でも、この本は、Web構築、運営のビジネスを行う人にとって、基本的なとらえ方がわかる、よい入門書になっている。最後にWeb構築における「情報アーキテクチャー」の重要性が述べらているが、わかりずらい。その存在意義は、この5つの段階を、トータルでとらえられる人のことを、言っているのであろう。読書時間 2.5時間★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.22
コメント(0)
-

『カラダ革命ランニング-マッスル補強運動と正しい走り方』金哲彦著を読む
走ることの魅力を十分に伝えている本である。走ることは、「本能」なのである。しかし、本能にもかかわらず、正しい走り方を身につける必要があるのは、いかにも人らしいことであるといえる。正しい走り方における、本書のキーワードとなる言葉は「体幹」(たいかん)である。体幹とは、背中、臀部のこと。この体幹は、立つこと、歩くことにも関係していて、正しく立つこと、正しく歩くことができて、正しく走れるようになる。だから、正しく立ち正しく歩けないと、正しく走ることなどできないのだ。正しく走れないと、すぐに疲れる、故障する、というマイナスの影響がでることになる。体幹をマッスル運動によって補強しつつ、日常的にも意識することで、よい走り方ができるようになるのである。ここまでくると、いささか修行めいてはくるが、語り方としてはできればそこまで意識していきたいという感じである。そのほか、これから走り始める人や、レースに参加しているような本格的な人までのタイプ別の練習方法やストレッチ、マッスル運動などのアドバイスなども紹介している。走ることに関して、自分の状況に合わせて細かい知識を得られながら、走ることは、単に走ることだけでない、健康やダイエットとかも含めて、人を元気にする、悩みを吹き飛ばす、さらにもっと奥深いところでも、人を魅了してやまないものなんである。文章も読みやすく、一気に読める。★5つ ★★★★★**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.19
コメント(0)
-

『入門Wiki-みんなで投稿/編集できるWebの作りかた』竹添直樹著を読む
この本は、ホスティングサービスの「livedoor Wiki」とWikiソフトの「FreeStyle Wiki」について、わかりやすく解説したものである。#livedoor Wikihttp://wiki.livedoor.com/#FreeStyle Wikihttp://fswiki.poi.jp/著者は、FreeStyle Wikiの開発者だけあって、FreeStyle Wikiの基本的な使い方はもちろん、実際のビジネスシーンにおいて、どのように使っていけばいいかがよく理解できるようになっている。グループウェア的な使い方、権限の設定の仕方、掲示板の使い方などである。FreeStyle WikiはPerlで記述されている。PHPで記述されているPukiWikiに比べると、ユーザー数においては少ないと思われるが、PukiWikiにない機能もあり、Wikiに慣れていけば使い分けをしていってもよいだろう。最後のほうでは、Wikiの未来にもふれており、著者のWikiに対する思い入れの深さが伝わってくる。Wikiでどんなことができるかを知りたい人にとって、最適な入門書になっている。★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.18
コメント(0)
-

『世界共和国へ-資本=ネーション=国家を超えて』柄谷行人著を読む
著者の本を読んだのは、15年ぶりぐらいだろうか?読書を習慣にしていると、気になって仕方がない本である。「岩波新書 新赤版」というのも、気になることに拍車をかける。とはいえ、お盆だからこそ、読んだ本か・・・(柄谷先生、ごめんなさいm(_ _)m)読んでみると、「相変わらず」と「さすがに変わったか」、ということを感じる本になっている。「相変わらず」という点は、やはりというかマルクスの資本論の「価値形態論」がベースになっているということ、「さすがに変わったか」というのは、「理念」「人間」という言葉がでてくることや、「ポストモダン」をさめた見方として相対化している点や、「環境問題」「経済格差」など、世界的な問題を解決しようとする姿勢にある。価値形態(貨幣論)をベースにして、「国家」「ネーション」などを論じ、それを、世界的な問題として展開していくこの本は、それ自体、世界の見方として新鮮な見方を提示できている。さすがである。実際「知的関心の高い層」にとって、世界中の哲学者の優れた知見を動員しつつ、それを著者独自に提示し直し、世界観を構築し直すやり方は、知的な関心を刺激する、魅力的な見方を提示できている。しかし、実際は、この「理念」に向けて実現する道のりは、はなはだ遠いような気がしてしまうのである。それは、なぜか?それは、著者が「揚棄」しようとする「国家」や「資本」のとらえ方の問題である。それらは、現実的には、一般人にとって、「揚棄」するものでなく、とても「魅了」させるものだからだ。それも、とてつもなく、「魅了」させられるものだからだ。だから「揚棄」することなど、ほとんどの人が考えることなどないのである。結果的に、ほとんどの人が、「国家」や「資本」に加担する。それは、持てるものと持てないものという「階級」には関係がない。だからそれを成立させている「隠蔽」という「奥深いところ」で考えても理解されないのである。「階級が下」の人にとってこそ、今は「ロングテール」の時代だからこそ、だれもが「自分こそ」「夢」という想いや言葉とともに、魅了されてしまうのである。それは、優れた個人(著者)の思考の範囲を量的なレベルとして軽々と超える「力」をもつ。しかし、これこそが、この本にとっては「問題」なのである。なので、この実際のとてつもない隔たりを、隔たりとしてとらえていないことに、この本の限界を感じるのである。結局、著者は、どういう社会を実現したいのか、ということがわかりずらいのである。(多分、この本のほとんどの読者にとって・・・)そして、65歳?という老年にさしかかった著者は、一番何を大切にしているのか、これからの人にどういうことを伝えたいのかということが、ぜんぜん伝わってこないのである。それでもあえて、この本の意義を私が提示すると「考えること」だと思う。さらに言えば「知的」であることかもしれないが、そんな暢気な価値をもつ時代は終わっている。ならば、本書はもっといろいろな人に読まれるように、「戦略」を考えるべきなのではないだろうか?とは思うものの、現代は、複雑すぎるのである。この複雑すぎる現代を、「資本」「国家」「ネーション」という位相でとらえ直す、そのことだけでも、本書は意義深いといえるのであろうか?しかし、あまりにも知的能力に優れ経済的に安定的な位置にいる著者?だからこそ、展開できる世界観という見方もできる。あと、本の書き方の問題がある。新書という本にもかかわらず引用が多すぎるのである。自分の言葉ですべて語ることはできないのだろうか?引用を減らすだけでも、変わる。それでも「異質な本」として、読んでみる価値はある。その「異質さ」をどうとらえるか・・・読む人に、いろいろ考えさせる本であることは、確かである!わかりずらい書評になってしまったような気がするが、やっぱり、そういう本でしょう。★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.17
コメント(0)
-
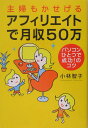
『主婦もかせげるアフィリエイトで月収50万-パソコンひとつで成功!のコツ』小林智子著を読む
主婦を元気にする本である。それは、専業主婦としての制約を乗り越え、アフィリエイトによって成長する著者自らが、きちんと描かれているからである。この本は、単にアフィリエイトで50万円稼ごうとするだけの本ではない。自分の価値観を大切にしながら、家族を尊重し、仕事としてどう取り組むか、そんなきちんとした姿勢と考え方を持ちながら、アフィリエイトへの主婦の取り組み方法が語られる。自分の価値観とは、サイトで情報を提供することやアフィリエイトで紹介するものへのこだわりであり、家族を尊重するとは、アフィリエイトへのめりこみすぎず、家族との関係や時間を大切にすることであり、仕事への取り組みとは、お金を仲介することの責任と、タイムスケジュールで運営することやモノゴトへの関心の持ち方までのことである。そして、著者はアフィリエイトは稼いでくれる「旦那さま」がいる主婦だからこそできたといっている。よって、アフィリエイトで独立することなどは、いましめることになる。ただ、著者のアフィリエイトへの取り組みは、気楽に稼ごうという領域ではないのである。仕事としてショップサイトなどを運営するのと基本的には変わらないのである。これこそが、「カリスマ主婦アフィリエイター」たるゆえんであろう。この本を読んでいると、アフィリエイトとは知識もスキルもない個人のビジネス能力を少しずつ高めてくれる、とてもすごいツールであることがわかる。また、この本は、主婦だけでなく、サラリーマンや学生などが読んでも、アフィリエイトだけでない、ビジネスへの取り組み姿勢を考えさせられる本にもなっているところがいい。さらに、著者はもともと頑張り屋であることは、本を読んでいるとわかるが、アフィリエイトをやることで、ここまでの本を書けるようになったということも、また驚きである。★5つ ★★★★★**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.08
コメント(0)
-

『ウェブコミ!-クチコミとマスコミを同時に実現! 』喜山壮一&(株)ドゥ・ハウス著を読む
ウェブコミは、ウェブ上でのコミュニケーションのことで、これを企業としてどう味方にするかが、この本で説明しようとすることである。全体的には理解しやすい構成になっている。まず、企業からみたターゲットを顧客、アクティブネットユーザー、メンバー、モニター、パートナーにわけ、それぞれがどういう特徴をもち、どのように働きかけるべきかが説明される。また、コミュニケーションの領域を、プロモーション、リサーチ、インバウンド(お問い合わせのこと)、コミュニティ、CMSにわけ、それぞれのやり方を説明する。そして、実践の領域として、コミュニケーションの領域別に、どのターゲットにアプローチしていくかを決めていくことになる。手法としては、ブログ、CMS(XOOPS)、RSSなども使われる。最後には、このターゲットとコミュニケーション領域のマトリックスを基準にして、いくつかの事例が紹介される。私的には、オーソドックスなやり方に思えたが、企業の「ウェブコミ」をトータル概念的にとられるには、理解しやすい本になっている。★3つ ★★★☆☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.07
コメント(0)
-

『ザ・サーチ-グーグルが世界を変えた』ジョン・バッテル著を読む
この本は、グーグルという会社の歴史、考え方、経営などについて、実際の経営者などの取材を通して細かく書いている部分が7割、そして、タイトルにもなっている、「サーチ」、つまり検索についての考察が3割、といったところだろうか?資本主義の歴史上、類をみない驚異的な成長をとげたグーグルに関する興味はつきない。しかし、この本を読むと、そういったグーグルを生み出した、ビジネスの対象でもあるWeb検索というものと、Webを抜きにしても検索という行為そのものがもつ意味には、とても奥深いものがあるという知的な関心を引き起こされる。それは、例えば、おいしいものを食べたいから、おもしろいことをしたいからという通常的な思いに発して、検索エンジンでふさわしい言葉でWeb検索するよりも、もっと根源的なところから考えたほうがいいかもしれないものだ。それは、例えば、母の胎内から生まれ落ちたときに、母という存在やおっぱいを探すであろう行為や、いくばくかの経験や知識を獲得した青年期に、自分とは何ぞやと考え、自分らしさを探すという行為など、人は基本的になにものかを探すものである、という存在論との関連性の元にである。こういったことを考えると、検索する=探すという行為は、話すとか見るとかいう行為より、もっと根源的な行為ではないかと思うのである。ただ、根源的な行為であっても、Web以前では、具体的な言葉にすべて置き換えることはなかった。それが、Webの出現によって、あらゆるコトやモノを自分の感性に従って1つの単語に凝縮させるという思考回路が生まれ、実際、検索できるようになり、その検索対象となる「情報」は、加速度的に増加するばかりになっている。その情報が、グーグルなどの検索エンジンが持っている、ウン十万というサーバーの中にある。このときに、グーグルは、人の探すという行為の本質に対して、どこまで対応できるのだろうか?グーグルは、あくまでもテクノロジーの会社であるが、そこまでのことを考えているのであろうか?自分探しをしている人は、グーグルの検索窓を使って、何かを検索するだろうか?検索するとすれば、なんと言う言葉を入力するのだろうか?★4つ ★★★★☆**********************************有限会社リレーションメイク 羽切 徳行
2006.08.03
コメント(1)
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- ^-^◆ 浪花節(浪曲)の修行<少年時の…
- (2025-11-25 05:00:06)
-
-
-
- ひとり言・・?
- 楽天ポイントアップ等で2~3割安く購…
- (2025-11-22 22:12:52)
-
-
-
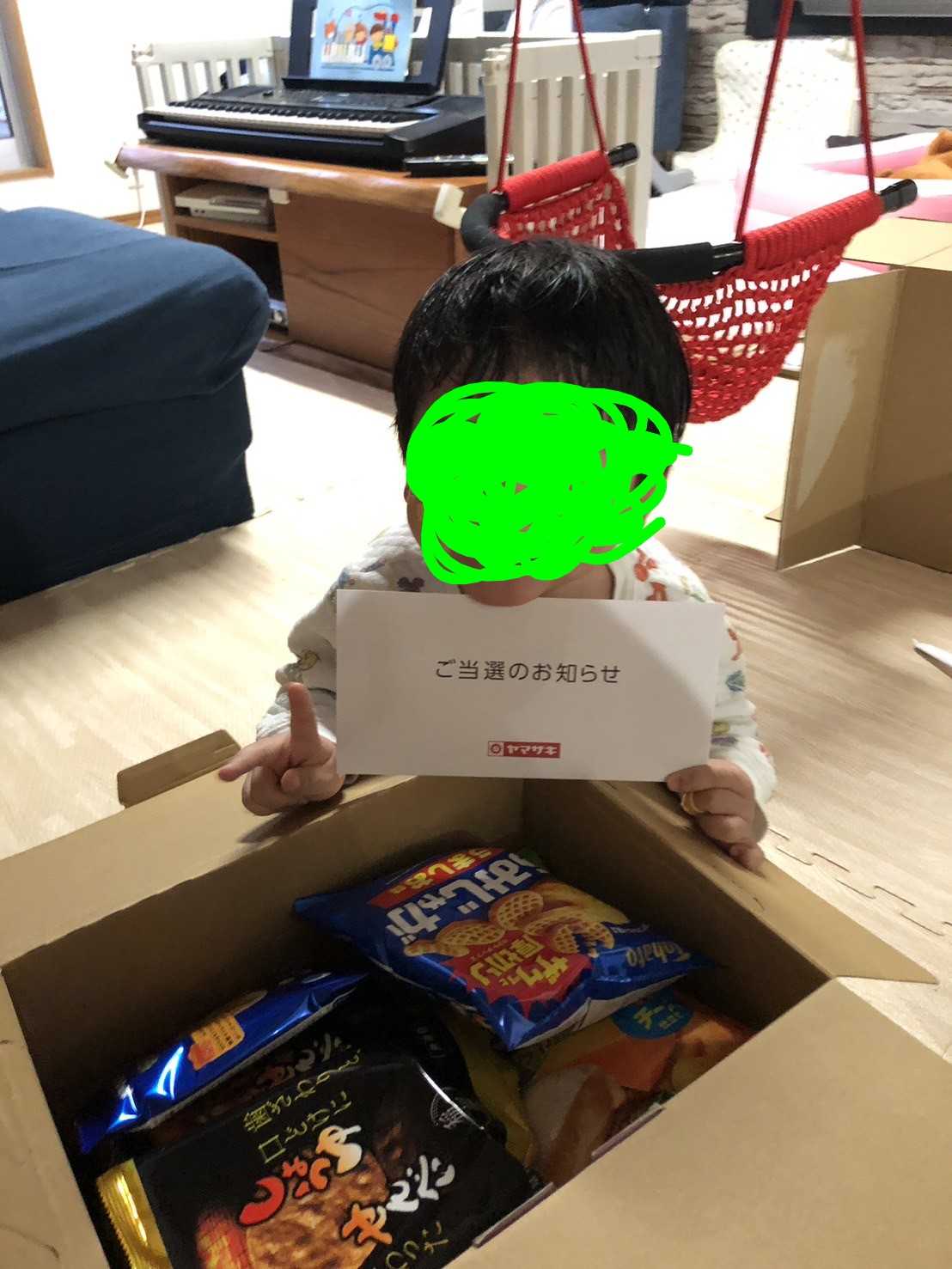
- 懸賞フリーク♪
- お菓子のファンタジーボックス
- (2025-11-25 00:20:41)
-







