2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年09月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
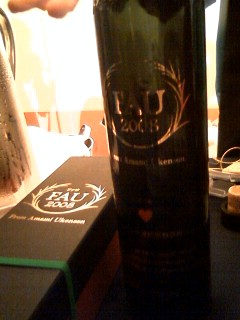
FAU2008(奄美大島開運酒造・黒糖焼酎初垂れ)
FAUで「ファウ」と読みます。From Amami Ukenson(奄美・宇検村から)の頭文字。パッケージングはちょっとエキゾチックです。「初垂れ(はなたれ)」とは初留取りのことで、蒸留の最初に出てくる部分を言います。醸造酒の日本酒で言えば「荒走り(あらばしり)」といったところでしょうか。同じ蒸留酒のウィスキーでも同様に最初に出てくる部分はあるのでしょうが、あちらは樽で寝かせてしまうからあまり関係ないのでしょうか?それともその部分を入れた樽は貴重品なのだろうか?FAUは年1回の限定出荷で、毎年300mlの小さな瓶で1万本以下の造りだそうです。アルコール度44度ということで、お薦めの飲み方は冷凍庫でキンキンに冷やして(凍らないので)、グウィーっといくのがベストと。それって私の夏場のジンの飲み方と一緒じゃないですか! きっと美味いでしょう。このFAUの瓶は黒いので、表面に白い霜がかかって風情がありそう。さて、私が飲んだ時はそんなに冷えていませんでしたが、しっかりとハナタレを堪能しました。贈答品とか、アルコール好き仲間のパーティ向けかな?ここは楽天最安値で、しかも送料込み。↓
2009/09/29
コメント(0)
-

東洋美人・吟醸(山口県萩市・澄川酒造場)
新幹線を東京駅で降り立つと、そのまま山手線に乗り換えればいいものを、地下のグランスタ東京へ行って長谷川酒店を覗いてしまう。新幹線内ではビールだけ飲んで、日本酒は飲まなかった(特定の一種類しか販売していない)反動で、ちょうど手ごろなサイズの酒をゲット。容量240mlは、「1合では少ない、2合では多すぎる」というニーズにピッタリだと思います。(それが購入の決定打でもあったので。)スクリュー式ではない、コルクタイプの栓。なんの米か分かりませんが、精米歩合は50%と表示。アルコール度は14~15度とやや薄め。瓶詰はこの8月。飲むと東洋美人らしい華やかな香りが・・。これは好き嫌いがあるでしょうか。ということで、その時は一杯でやめて、数日後再び飲んだら香りが落ち着いて、わたし好みの酒になっていました。
2009/09/25
コメント(0)
-
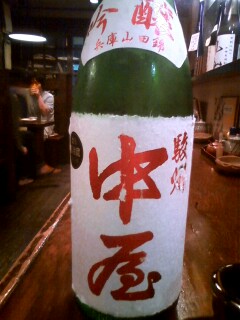
駿州中屋 吟醸 生酒(静岡県富士宮市 富士高砂酒造)
富士高砂酒造のホームページを見ても、「高砂」ばかりで「中屋」は出てこない。この蔵の隠れブランド「中屋」。静岡の酒の中ではカプロン酸が抑えられているのではないでしょうか。飲んだのは前回と同じ焼き鳥屋なんですが、実は一番最初に飲んだのが山形の「楯○川」吟醸。これがちょっと香りがきつ過ぎて「焼き鳥屋には合わないんじゃないの?」と店主に言いたくなった。次が前回の「臥龍梅」の純米で、その次が今回の中屋・吟醸生酒。だんだん臭いが取れて俺好みになってきました。この3つの中では焼き鳥と飲むという前提であれば、中屋がいいなあ。兵庫県産の山田錦を50%まで磨いて、日本酒度+5、酸度1.2、アルコール度15~16度に造られています。この酒蔵は1831年に酒造を開始して、現在2500石ほどの中堅蔵ですが、そのうち中屋は200石未満の構成です。
2009/09/22
コメント(0)
-
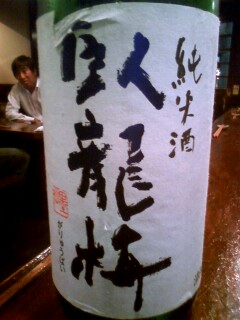
臥龍梅・純米(静岡・清水、三和酒造)
龍が伏せたような形の梅の木から命名した「臥龍梅」。長野の須坂では、松葉屋さんが梅ではなくて近くの山の形から「臥龍山」。今回は静岡の梅のほうです。ふらっと入った近所の焼き鳥屋さんですが、日本酒のラインアップが意外と凝っていたので気に入りました。臥龍梅は生酒や吟醸系のイメージが強く、普通の純米酒は初めてです。スペックが詳しく書いてあるのは好感。使用米は分かりませんが、60%まで精米して、日本酒度をプラマイ0にしているのですねえ。酸度は1.4ですが、アルコール度は16~17度ですから少し高めのセッティングです。飲んでみると甘めという印象はまったくありませんが、やはり静岡の酒らしい香り、静岡酵母でしょうか、そうした特徴がはっきりと出ています。久しぶりの臥龍梅でしたが、わたしは元々吟醸系よりも純米系がどちらかというと好みなので、同じ蔵の純米吟醸よりもこちらの方が合いました。
2009/09/17
コメント(0)
-
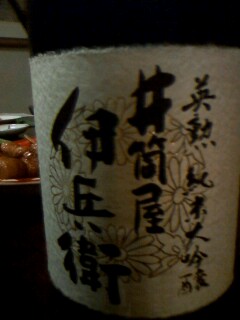
英勲 井筒屋伊兵衛純米大吟醸 三割五分磨き
4合瓶5250円とお高い酒です。京都伏見の斎藤酒造が醸す最上級のランクの品で、精米歩合35%の「三割五分磨き」。酒米は全量京都祝を使用し、日本酒度+2、酸度1.2に仕上がっています。アルコール度は15~16度。さすがに裏ラベルの表示も詳しい。ISC(International SAKE Challenge)の2008年金賞受賞であることも強調してます。飲んでみれば、まるで鑑評会出品酒のような香りと味。いわゆるYK35的な出来上がり。綺麗で美味いですが、乾杯酒向きで、これのみで肴を喰いながら飲んでいたら飽きそう。もっとも高い酒だから、そんなに飲むことは想定していないか。ご馳走様でした。
2009/09/14
コメント(0)
-

七田・純米無濾過生原酒(佐賀県・天山酒造)
日本酒は米から造る酒なので、「田」の付く銘柄が多いですが、今回の「七田」は六代目蔵元さんの名字だそう。その蔵元は、佐賀県小城市で「天山」を醸す大手の天山酒造。蔵元の名字が入るとあれば、杜氏が自分の名前を入れる酒同様、中途半端な酒ではないはずと心して呑みました。香りの出すぎた主張がなくて好感が持てますが、無濾過生ではの麹と米の香りがほのかに漂い、さらには酵母が糖分を充分に喰ったキレの良さを感じさせてくれます。使用米は山田錦2割、麗峰8割で、これらをそれぞれ65%まで精米しています。日本酒度は+2~3ですが、酸度は1.8と高めです。ですが、フレッシュな生酒なので酸度はそんなに感じません。また、アルコール度は18~19度と純米酒として良く醗酵した証しとなっています。一升瓶で2520円、4合瓶で1207円という価格設定は呑み助にとって大変ありがたいことで、雑誌dancyuでコストパフォーマンス賞3つ☆を獲得したこともうなずけます。私は香りのきつい大吟醸よりも、こうしたタイプの酒の方が好きです。
2009/09/08
コメント(0)
-

弥右衛門・大吟醸(福島県喜多方市・大和川酒造)
喜多方と言えばラーメンですが、酒造界では「蔵粋(クラシック)」を醸す小原酒造が有名。文字通りモーツアルトのクラシックを聞かせながら酵母の発酵を促す独特の酒造法です。今回は同じ喜多方でも、寛政二年(西暦1790年)創業という大和川酒造の酒です。主な銘柄は『大和川』『弥右衛門酒』『酒星眼回』『良志久』などですが、 弥右衛門は代々この蔵元の代表が襲名する名前です。地方の大店(おおだな)では良くあることです。今日の酒はその「弥右衛門」の大吟醸・無濾過生原酒。「夢の香」という酒造好適米を50%まで精米し(大吟醸規格ギリギリですね)、アルコール度16~17度に仕上げています。「原酒」というわりにはアルコール度は低いですね。大和川酒造では「江戸蔵」「大正蔵」「昭和蔵」と3つの時代の蔵があって、見学もできるようですから今度喜多方に行ったときには寄ってみたい。清冽な飯豊山の伏流水で仕込む、会津盆地育ちの米の酒です。
2009/09/04
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1










