2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年12月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

黒龍・純吟三十八号(福井県永平寺町・黒龍酒造)
「ゆく年くる年」で除夜の鐘の舞台としてよく放映される越前の永平寺。そんな永平寺町の蔵元「黒龍」の酒を取り上げて今年の最後の記事としたいと思います。その中でも「その年の38番目のタンクが搾られる頃、酒蔵は最盛期を迎えます。その頃搾られたお酒も秋の訪れとともに、一番美味しい季節となりました。今が旬の純米吟醸酒を蔵出しします。」という、純吟三十八号で締めくくります。山田錦を100%使用、麹米50%、掛米55%まで精米し、アルコール度16度に仕上げています。品川区二葉町の飲み屋で女将さんから「希少な酒」と強いお勧めがあったので飲みました。1杯830円。黒龍らしい綺麗で麹の香りの立つ酒。この蔵の酒は洗練されているから人気が高いのもうなずけます。今年も全国各地の美味しいお酒をたくさんいただきました。そして日本に生きている幸せをいっぱい感じました。全国の蔵元・蔵人の皆様、酒販店の皆様、そして料飲店、一緒に飲んだ友人の皆さん、ありがとうございました。良いお年を!
2009/12/31
コメント(0)
-
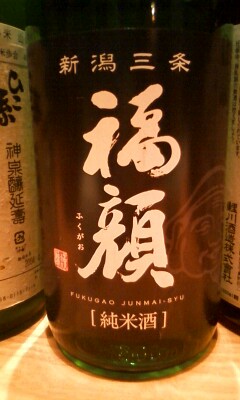
福顔・純米酒(新潟県三条市・福顔酒造)
‘飲んで思わずニコニコする上手い酒’ということで命名された『福顔』。明治30年創業のこの蔵では、酒を量り売りをしていた頃の甕や瓶、代々伝わる屏風にも福顔が描かれていたそうです。お酒のラベルにも「福顔」を描いたらいいのになあと思います。酒どころ新潟においては割りと地味な存在の福顔酒造ですが、時流に流されず旨味のしっかりと載ったお酒に好感が持てます。この秋のはじめには酒造期間である半年間の蔵人求人募集もしていましたよ。
2009/12/28
コメント(0)
-

神亀・小川原専務と酒亭・新八
蔵元の主(あるじ)が居酒屋の主を説得して指導して、うまい酒と肴を提供し、今や東京を代表する居酒屋のひとつにのし上がった事例というのはこの新八を除いてどこかあるのだろうか?それほど、小川原専務と新八の縁は切っても切れないものでしょう。試しに「丸の内・新八」のホームページを覗いて、「お飲み物」をクリックすれば、いきなり神亀酒造の酒ばかり15種類もリストアップされています。酒亭・神田新八・お飲み物もちろんそれ以外の日本酒のメニューも、そして酒に合う料理も、酒好きにはたまりません!(刺身は少し食べたあとですが、とても美味い!)(牡蠣も白子も揚げ物もなにもかもうまい。)新丸ビルに出店している分、料理もやや高めですが、この秋に廉価版の店が有楽町のガード下に新規オープンしました。私は別にこの店の宣伝マンではないので、このくらいにしておきますが、日本酒に対しての愛情豊かな居酒屋が増えてくることが、とても楽しみなのです。最後に小河原専務のご登場。
2009/12/24
コメント(0)
-

神亀ひこ孫・大吟醸(埼玉県蓮田市・神亀酒造)
大吟醸といってもこの蔵の酒は当然「純米大吟醸」。「闘う純米酒 神亀ひこ孫物語」(上野 敏彦著)はこの蔵が主役。今でこそ純米酒を普通に飲む時代になりましたが、40年ほど前の、税務署と、業界と、蔵人と闘う歴史を読んで欲しい。今回は神亀酒造の小川原専務を抜きにしては語れない「阿波山田錦」を、この蔵では最高と思われる40%まで精米した大吟醸です。お値段も1万円を超えますね。そもそも「ひこ孫」って、聞いたような聞かないような言葉で、普通に「ははあ、ひ孫のことか」と思ってしまいがちですが、正確には「ひ孫の子」のことで、通常「やしゃご」と呼んでいるものです。要は熟成させた酒の名前として、「永年末代まで続く」象徴としたのでしょう。ちなみに神亀酒造の酒は熟成がベースで、その中でも「ひこ孫」は3年以上寝かせたもののみに与えられるラベルです。実は神亀酒造における熟成酒は偶然の産物で、純米酒を造ったものの、当時の酒販店からは見向きもされず、蔵の中に売れ残っていた3年前の酒をヤケ飲みしたら旨かったというものです。これこそ「酒の真髄」だと商品化しようとしましたが、そこから税務署との壮絶な闘いがはじまりました。造石税ではなく蔵出税として徴税する日本の酒税制度において、出荷せずに蔵内で貯蔵しておく神亀酒造は、税務署からすれば反逆謀反の敵でした。そのために様々な嫌がらせも受けましたが、そうした逆境に立てば立つほど小川原専務の信念はより強固なものとなっていくのでした。そして彼は今「全量純米蔵を目指す会」の代表幹事として日本酒界をリードしています。話しは長くなりましたが、この純米大吟醸をぬる燗で飲めば、「日本の美と伝統」を五感で実感できると思います。本当にすべりの良い、抵抗感のない酒ですが、なおかつ旨味がしっかりと載っています。ただし、吟醸香プンプンの大吟醸を期待される方にはお薦めしません。(楽天内最安値)
2009/12/21
コメント(0)
-

鯉川・純米酒(山形県庄内町・鯉川酒造)
昭和56年より「亀の尾」の取り組んでいる平均年齢29歳の純米蔵。ちなみに「亀の尾」発祥の地は、庄内地方の余目です。(漫画の影響で新潟のイメージが強いですが。)ですから亀の尾生みの親、『阿部亀治』氏の名前を冠したラベルもこの鯉川酒造で造っています。今回は阿波山田錦を100%使って新境地を開拓しました。精米歩合60%、日本酒度+5、酸度1.7、アルコール度16~17度というスペックです。米の心を知りぬいたこの蔵ならではの造りです。
2009/12/19
コメント(0)
-
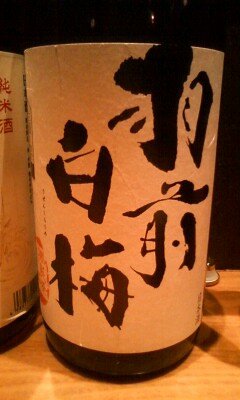
羽前白梅(山形県鶴岡市・羽根田酒造)
羽根田酒造の所在する鶴岡市は、平成17年10月1日の6市町村合併により、総面積で東北一大きな都市となっています。その中で大山町(おおやままち)は、昔は数十軒の造り酒屋が軒を並べ、「東北の小灘」といわれたほどの酒造の町だったらしいです。現在は、羽根田酒造以外に、「大山」を醸す加藤嘉八郎酒造、「栄光富士」を醸す富士酒造、「出羽ノ雪」を醸す渡會本店の4軒になっています。今回の羽根田酒造は1592年(文禄元年)の創業というから、豊臣秀吉が天下統一を果たし、権勢を誇っていた頃のことで、相当な歴史のある蔵だとわかります。現在は300石弱しか造っていない蔵ですが、槽で搾るなど昔ながらの酒造具を使いながら純米酒を中心に丁寧に造っています。このしっかりした味わいの羽前白梅(うぜんしらうめ)を燗酒で美味しくいただきました。
2009/12/17
コメント(0)
-
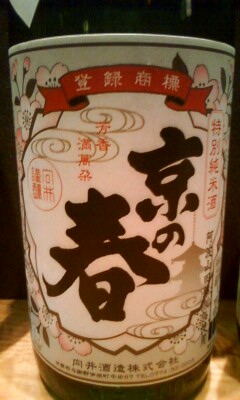
京の春 特別純米(京都府伊根町・向井酒造)
ラベルは春爛漫な桜と東寺の五重塔のシルエットによる古風な雰囲気で「京の春」を演出していますが、この蔵の所在地は京都府とはいえ日本海に突き出た丹後半島の若狭湾側、伊根町にあります。伊根町といえば、BS-TVの「日本原風景」かなにかに出てきた記憶がありますが、伊根湾を囲むように立ち並ぶ「舟屋」が有名です。その数約230軒。これは1階が舟のガレージ・物置で、2階が居住用の空間になっているものです。その風景は以下の伊根町のホームページをご参考ください。FUNAYA 今日の風景「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」に選ばれた舟屋群のある伊根町は人口二千数百人ですが、向井酒造はここで1754年に創業しています。一方、もう一つの話題はこの蔵の杜氏が蔵元の娘さんの向井久仁子さん、通称クニちゃんということ。30代前半の可愛いお嬢様ですが、お父さんの跡を継ぐべく、東京農大の醸造学科を卒業して現在酒造に励んでいます。さて、この向井酒造の蔵の足元も伊根湾の波が洗っていますが、酒の味はどうだろう?スコッチのアイラモルトのように潮風を感じさせるようなフレーバーがあるのだろうか。泥炭で大麦を燻すスコッチと違ってそんなことはないですが、優しいながらも寒風に打ち克ってきたシッカリ感を堪能することができました。
2009/12/14
コメント(0)
-
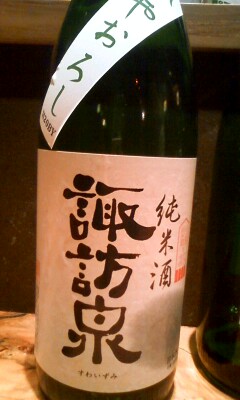
諏訪泉・ひやおろし (鳥取県智頭町・諏訪酒造)
私が純米ファンドを投資している蔵のお酒。勿論全量純米蔵です。山陽側の姫路から山陰の鳥取を結ぶ第三セクターの「智頭急行」。その智頭町は鳥取市の南の山間部にあります。冬場の厳しい冷え込みは、じわりとした醗酵のしっかりとした酒を造り出してくれます。その諏訪酒造の純米ひやおろしには、飲む前から期待感が高まります。旨いです。嫌味(イヤミ)のない旨さです。今日のような寒い日の晩に、燗酒で飲めばそれこそ幸せの極地でしょう。「日本酒って、いいな!」
2009/12/11
コメント(0)
-
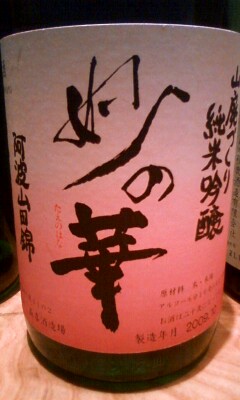
妙の華・山廃づくり純米吟醸(三重県上野市・森喜酒造場)
「夏子の酒」の漫画家、尾瀬あきら氏がラベルを描いた「るみ子の酒」で有名な森喜酒造場。るみ子とは蔵元の専務であり、麹づくりの責任者をしておられる森喜るみ子さんのお名前。この蔵のもともとの銘柄「妙の華(たえのはな)」は、信仰心高く「妙法蓮華経」が由来とのことですが、酒造に不可欠な井戸を掘り当ててくれたのが住職だったということです。森喜酒造場は、製造量200石の全量純米蔵ですが、麹の仕込みは全量麹蓋による文字通り手づくり蔵です。今回はさらに山廃の純米吟醸という、蔵人の汗を感じるような貴重なものです。ここで、講談社漫画文庫「夏子の酒第5巻」のあとがきに、尾瀬あきら氏によって書かれた森喜酒造場、るみ子さんの苦闘・奮闘ぶりを、同社のホームページより転載します。<ここから>「前略 只今、平成三年六月二十二日午前一時です。先だって買ってきた『夏子の酒』を読み終えたところです。なんと書かせていただければよいか… 私も実は、造り酒屋の跡とり娘として生をうけました。大学を卒業し、製薬会社へ勤務しておりましたが、父が脳梗塞で倒れ、急遽主人と結婚し、家業を継ぎました」 こんな書き出しで始まるお手紙を私の元に送ってくれたのは三重県伊賀地方にある、たった二百石足らずの小さな小さな酒蔵、森喜酒造の蔵元、森喜るみ子さん。銘柄は妙乃華(たえのはな)。 『夏子の酒』の執筆中に、私はたくさんのお便りを読者から頂きましたが、その中でも夏子をほうふつとさせる、るみ子さんの一通はひときわ印象的でした。「私も夏子の如く、麹と酒の香りとタンクのもとで育ち、物ごころつかぬうちからお酒の味を覚えました。小学生の時には、すでに槽口からしたたる荒走り (酒槽に積まれた酒袋から圧力をかけずに、自然流出してくる最初の酒) のおいしさを心得ていて、学校から帰ると槽場でこっそり盗み利きをしていました。夏子のように銘柄を当てられる利き酒の達人ではありませんが″おいしいお酒″は解ると思います」 彼女が子供の頃には能登から五人の蔵人が半年間住み込みで来てくれて、活気のあった蔵も今では杜氏と麹づくりの責任者だけ。るみ子さんはお腹に子どもを抱えながらも、朝四時に起きて三十キロの米袋を運び、蒸米をタンクに入れ、上槽を手伝うという。「私は来季も、夏子の様に蔵に閉じこもると主人に宣言しました。やがて生まれてくる三人目の子のためにも、母としてがんばるつもりでおります」 この手紙をきっかけに、私と親しい蔵元や酒屋さんが、「放っておけない」とばかりに伊賀にとび、、蔵仕事を手伝ったり、アドバイスしたりという素敵なつながりが生まれました。『るみ子の洒』はそんな状況の中から生まれた純米酒です。私もラベルの絵を描くお手伝いをしました。『夏子の酒』をもじつたものではないか...という意見もありましたが、これほど的確なネーミングは他に見当りませんでした。現在、るみ子さんは日本酒に携わる女性の全国的なネットワークを作ろうとはり切っています。三重県上野市の森喜酒造は、生き残ってもらいたい蔵のひとつです。<以上>こうした蔵のストーリーを知ってしまうと、飲むほうも思い入れをもって肩に力が入って飲んでしまいます。造る方も思い入れが強いですから、小さな蔵らしい個性的な酒だなあといつも感じています。
2009/12/09
コメント(0)
-
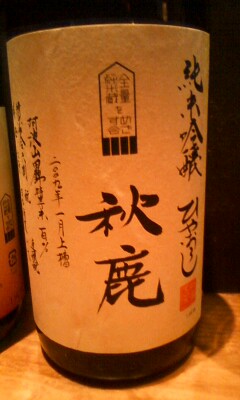
秋鹿 純米吟醸 ひやおろし(大阪府・秋鹿酒造)
米作りから酒造まで、自社で一貫して造りを行うこだわりの酒蔵・秋鹿酒造。大阪の酒蔵といっても、京都府の亀岡に近い大阪府の北端に位置しています。谷間に広がる田園、山の斜面に開かれた棚田、緑の山並み、どれをとっても日本の原風景といった趣きですが、冬の寒さは酒造りに格好の環境を提供してくれます。米作りと酒造りを兼業していた蓄積を生かした、米作・酒造の一貫造りをはじめて20年が経ちましたが、全量純米蔵としても有名です。秋鹿というと無濾過生原酒のラインアップが目に付きますが、冬の搾りのあと貯蔵前に一回火入れし、夏を越した秋にそのまま瓶詰した「ひやおろし」も、ほんのり熟成の香りが沸き立ち、酒飲みのノドをくすぐります。ご覧のように、今年の1月にフネで搾り上げていますが、四国・阿波の山田錦を100%使用し、精米歩合60%、日本酒度+5、酸度1.9、アミノ酸度1.0、アルコール度16.5という、キリッとした仕上がりになっています。まさに北摂の銘酒です。
2009/12/07
コメント(0)
-
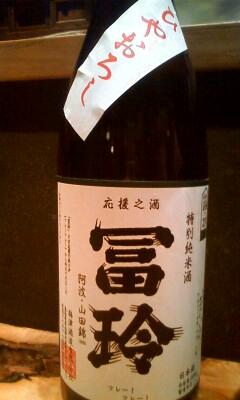
冨玲・特別純米ひやおろし(鳥取県東伯郡・梅津酒造)と梅津社長
ラベルに「応援之酒」と書いてあります。なにかと思ったら、「フレー、フレー、冨玲」なんですって!真面目に蔵のホームページに命名の由来が書いてあります。「三代目の梅津藤蔵(大正時代)は十代から南カリフォルニアに留学してテニスをしていた。そのときに応援される「HURRAH!!」という掛け声がとても印象にのこっていて、帰国後家業を継いだ際に、当時、梅津酒造の最高級酒にHURRAH!と付けたくて、当て字をして「冨玲」と成った。」とのこと。なお、彼は帰国後高等学校の教師として英語を教えながら、テニスも教え、その生徒のひとりに、かつてのデ杯選手の倉光氏がおられたそうです。日本酒の銘柄の名前の語源が英語というは珍しいですし、大正時代に海外留学してテニスをしていたなど、さすが酒造店(だな)は地方の名家だったのですね。梅津酒造は全量純米蔵です。元広島国税局鑑定官の故上原氏の影響もあるのでしょうか、鳥取県は全量純米蔵が多いですよね。この特別純米酒は、最高級の「阿波山田錦」を使用しています。ぬる燗で飲みましたが、とても綺麗な酒の香りと旨味の載った、私好みの酒でした。実はこの蔵元の梅津雅典社長と一緒に飲む機会があったのです。気さくで男前の素晴らしい社長で、いっぺんにファンになってしまいました。
2009/12/02
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1










