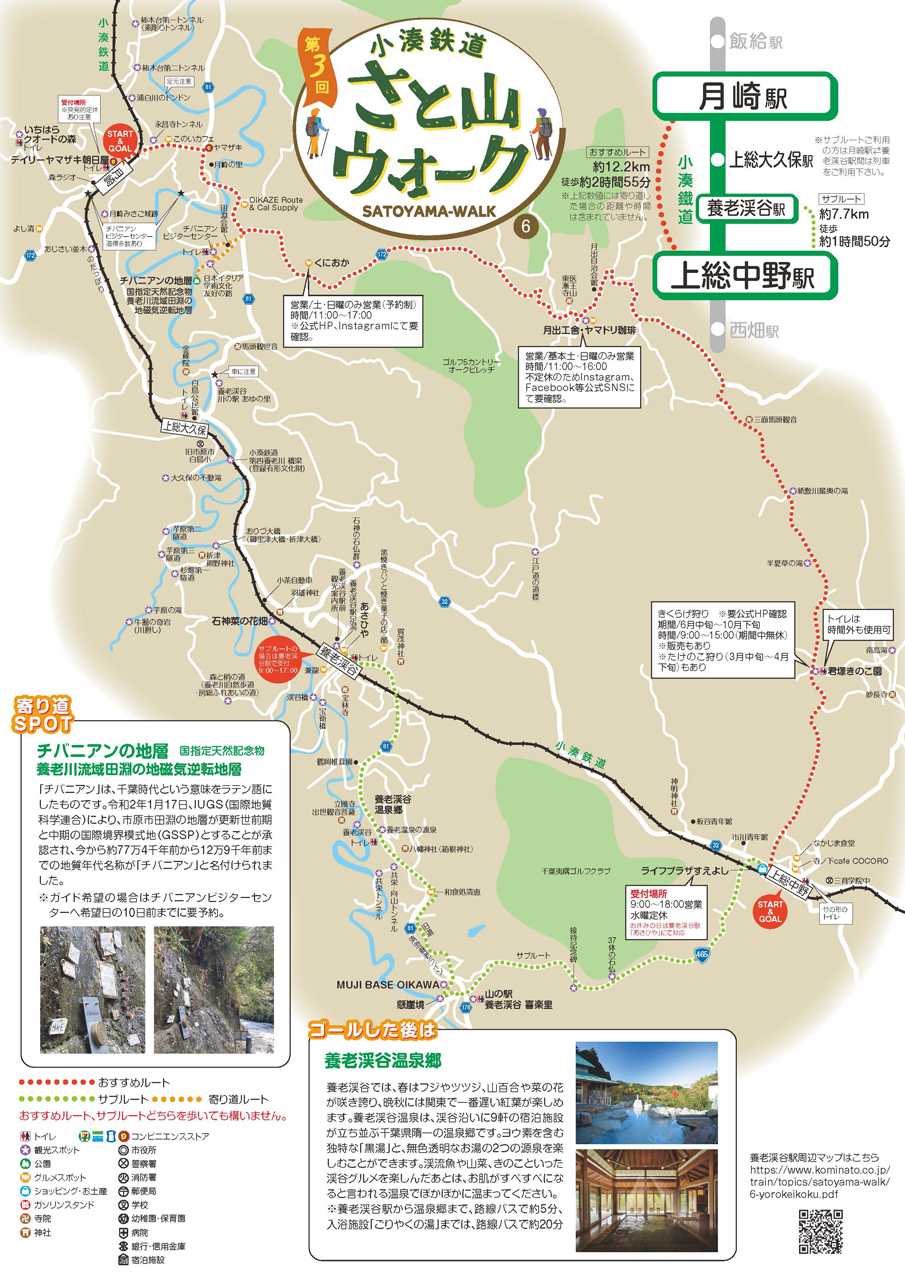2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2006年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
風邪ひいちゃった
実は先週末からのどの調子が変でした。風邪かな、と思っていたら、ヤッパリ風邪。空気が乾燥しているのと、人ごみや会議室に缶詰にされている間に、風邪のウイルスが飛んできたのだろう。何と迷惑な!と思うものの、こればっかりは通常の生活をしている間は避けられないだろう。何とか、引き込んで熱を出したり、寝込んだりすることのないよう、旨く乗り切りたいと願っている。今のところ、この作戦は成功している。今日から会社に行って、この調子を維持できればと、色々工夫しなければ!成果のほどは、後ほど報告します。ではでは
2006.01.30
コメント(4)
-
偉い友達
昨日の新聞に、ファイザー社がアメリカのFDAから口から飲むインシュリン薬の認可を得たと報道されていた。恐らくアメリカの新聞ではその前日に報道されていたのだろう。「ひょっとして」と思って、サンフランシスコのあたり、パロアルトに住む私の友人が手がけていたものじゃないかと、確認のメールをした。すぐに返事が来て、「そう、あれは自分達が手がけてきた技術です。実際に金になるには、あとまだ時間が必要な契約になってるけど・・・」とのこと。思わず、「凄い!」と感心、感激。だって、糖尿病の患者さんは毎日インシュリンを注射している。去年か一昨年、痛くない超極細の針を開発した大田区のメーカーが大きく取り上げられていたが、注射でなく口から飲むようにすればどれだけ楽になり、便利になることか。特に日本では少ないが、第一種糖尿病といわれる、先天性の人、特に子供達にとって、これは生活の質を抜本的に向上させる大きな一歩となる。無論後天性の患者にとっても、QOLの向上は間違いない。自分の友達がこのような大きな貢献をし、そしてそのうち大もうけをして大金持ちになる、というのは素晴らしいことだ。遊びに行っても、ゴルフのラウンド料金くらいはおごってくれるかもしれない。(ラッキー!)彼は、前に日記で紹介したように、時間の半分はスタンフォード大学のビジネススクールで教えている。教えながら時間が経てば、そのうち金が入ってくる。後は好きなゴルフに一層磨きをかけて、なんて考えているのではあるまいか。これは羨ましいこと限りないが、世のため人のためになる技術・商品開発をしたことは立派。大体、画期的な新薬が出にくくなった今日、クスリ本体より、そのデリバリーというか、効果を発揮させる方法論の開発に比重が移っている証拠だろう。これは、これで、将来への示唆に富む話で、色々と考えさせられる。フムフム・・・・
2006.01.29
コメント(4)
-
ホリエモン逮捕
昨日から今日のマスコミは、ホリエモン他計4名の逮捕で持ちきり。いつものマスコミの「熱狂」を地で行く狂騒劇。飽きもせずよくやるなあ、という印象を改めて強める。で、ホリエモンたちの逮捕。M&Aの見せ掛けや利益操作は、無論違法だし、許されない。特に投資家を裏切り、市場への信頼を根本から揺さぶった点で、その行動は決して許されない。まさに、「その罪万死に値する」行いだった。従って、連中が然るべき裁断を受けることは、至極当然である。一片の同情も感じない。ただ、この一連の動きを見ていると、何か日本社会特有の、「出るくいは打たれる」みたいな意図が背景に感じられてならない。やや大袈裟に言えば、日本の保守本流の筋から出た、「国家権力の意図」みたいなものを感じる。これは既に数日前から感じていたことで、何日か前の、同窓会の席でも盛り上がった話題の一つ。その席で、バンカーの友人は、私の「これは久しぶりに国家権力を感じさせる話だね」という感想に同意。役人をしている友人は流石に、「いやー、それは我々レベルでは何とも」などと賛成も否定もしなかったが、実は同じように感じる人は多いのではないか。もしこれが「国家権力」の意志だとすれば、これはこれで面白い。だって、今回の逮捕劇は今の権力者、小泉首相には損な話。彼が指示をしていたのなら、やめさせるか、時期を9月以後に遅らせただろう。そうならなかったのは、彼は「国家権力」なるものからは、必ずしもサポートされていないという結論になる。どこに実体があるのか、私にも分からないし、ひょっとしたら、小泉首相にも分からない話かもしれない。それがどこにあるのか、ひどく興味を覚える。こんなことを感じさせてくれる、一連の逮捕劇ではありました。
2006.01.24
コメント(2)
-
大雪の中
昨日は、大雪の中、某学校で授業。前夜から、雪だ雪だと予報されていたので心配していたら、朝目を覚ますと、一面真っ白の雪の世界。うーーーん、参ったな、とは思うが止むを得ない。講演を聴きに良くのなら、雪だからやめようと決めれば済む。授業をする立場になると、さすがに、そういうわけにもいかず、電車のダイアが乱れているだろうと想定して、早目に出かける。学校に着いたら、ほぼ一時間前。まあ、遅れるよりは良いですがね。定刻になり、教室に行くと、何と予定の定員の9割がたの人がいる。随分と熱心な生徒さん達だなあ、と改めて感心。問題意識が高い人たちの集まりなんだろう。その熱心さに感激すると同時に、その分こちらも熱意を持ってやろうと、即刻決意。中味の濃い議論になって、授業の3時間ほどはアッという間に過ぎて、昼過ぎ。少しのどが痛くなったが、この程度は我慢できる。何か充実感のある午前を過ごせて、むしろこちらが生徒の皆さんにお礼を言いたいくらいでした。こんな問題意識の高い若者達が一杯いるのだ、と安心もした次第。日本もまだまだ捨てたものじゃないんですねえ。
2006.01.22
コメント(0)
-
昨日は同窓会
昨日は、大学のときの同窓会。私は、野暮な会議に缶詰で約一時間半遅れて参加。既にみんなほぼ出来上がっており、遅れてきた私は追いつくのが大変。必死で、ビールを飲み、焼酎の水割りや、お湯割を飲んで、方々、残り物の食べ物を腹に入れながら、少し追いつく。飲みながらも、友人達と最近どうしてるの、とか、こんなしょうも無い話しもあるぜ、なんてな話をして楽しいひと時。この年になると、みんな毒気が抜けて、面白く、達観した話が出来て、とてもいい感じ。今更、俺は偉いんだ、なんていう奴も居ないし、みんなそれぞれに「酸いも甘いも」経験してきたので、理解が早い。それでも、それなりの共通点もあり、結構盛り上がる。遅れた分を、二次会で取り戻す。なぜか、教育の話になり、「教養教育がとても大事だが、最近の若い連中はそれが弱い」と某国立大学で哲学を教える教授の友人が指摘。今時の若者は、倉田百三の「出家とその弟子」なんてな本は読むどころか、聞いたこともないのだろう。可哀そうな事だと、皆で合意。まあ、老眼鏡をかけた時点の遅い・早いを争うぐらいのおじさんたちの言うことだから、詮無いことではあるのですが。それにしても、ハウツー本やノウハウ本じゃなく、ちゃんとした、物を考えさせる教養本を読むように見直すべきときが来ていることは間違いないと思うのですが。
2006.01.19
コメント(2)
-
二度あることは三度ある
証券会社の事務・システムミスが続出しているようだ。昨日の新聞で出ていたのが、大和証券SMBC.その前は日興証券。その前は、ご存知みずほ証券で、これは東証も巻きこみ、社長の辞任にまで発展したのは、皆さんの記憶に新しいはず。それにしても、類似のミスが続出する。よく分からないのは、続出しているのか、あるいは、以前から続出していたが、特にニュースに載らなかっただけなのか。後者の可能性も高そうな気がする。だって、損害が大したこと無ければ、マスコミネタにはならない、そんな程度の話でしかない。みずほの件で、一躍有名になったので、書かれているのかもしれない。思えば、銀行の事務ミスだって、実はかなりあったし、今もかなりあるに違いない。システムミスもかなりある。これは金融機関だけでなく、一般の企業でも多くあるはず。どこにでもあるから構わない、という気はない。これだけの間違いが発生するということを前提にした仕組みを作っておかないと、果ては例の社長辞任みたいな事態に発展する。辞任より、そんな事故・ミスで迷惑を蒙る人をどう減らせるかがより大切だが、それを、フェ―ル・セーフの思想で作りこんでおくことの重要性を、改めて思い知らされた。同時に、個人的感想だが、ミスの程度が以前に比べると、質的に落ちたというか、くだらない間違いが増えているような印象を持つ。これって、日本の国・産業全体にとって、相当問題なのでは、とこれも心配。基本は家庭・学校での教育に戻るのかも。なんて、最後は、極端に飛んだ結論にしたが、でも、これは本音です。
2006.01.15
コメント(2)
-
推薦番組
早起きの人のために、是非推薦の番組があります。NHKのラジオ(AM,FM両方)で、ひそかなヒットとなっている「ラジオ深夜便」。聞けばはじめてから15年になるそうな。これ、結構いけてるんですよね。特に、去年やって、余りの人気で再放送しているのが、朝4時から5時にやっている五木寛之さんの語り。題名は忘れたが、五木氏の若いときからの話を、その時々の流行歌、音楽を聞きながら、徒然に話していかれる。戦前の「カーキ色」一色の時代に、韓国・上海では結構カラフルな音楽が歌われていたり、あるいは新民謡として、日本から出かけた人たちが、現地の山や川になぞらえて民謡を作り、集まって歌っていたとか。若い人にも、「昔」を身近に感じるとてもグッドな機会を提供してくれていると思う。勿論、主たる聴取者は団塊以前の世代の方々。この番組の最初の放送のときに、かなりの反響で、メールやブログでなく、便箋に丁寧な万年筆で書かれた手紙が沢山送られてきたそうな。きっと、そうだろう。同時代を共有する、って言うことの価値は大きいのだ。それにご相伴するのも、これまた楽しいということ。朝目覚めの早い方、一度お試しあれ!!(毎日やってるからそのうち再放送も終わっちゃうよ)
2006.01.10
コメント(0)
-
日本の歌姫
昨日の日曜日、思わず引き込まれたテレビ番組があった。日テレでやってる、朝10時頃からの人生波乱万丈。昨日は都はるみさんがゲスト。番組が、というより、はるみさんの人生が面白いのだろう。始め歌手になって、売れまくり、レコード大賞を始め多くの賞を勝ち取り、ミリオンセラーのレコードを連発していた。「好きになった人」、「北の宿」など、私も大好きな歌だ。その大流行の歌手が、突然、引退。そして、4-5年後、紅白に呼ばれたのが一つの切っ掛けになり歌手に復帰。ここまでのファクトは私も知っていた。その裏に、あんなに示唆に富むことがあったのは、昨日初めて知った。始め歌っていたときは、「仕事」。日々、追われるように、仕事をこなす。売れてなんぼ、という発想でしか歌うことを評価できない。歌うというより、歌わされている感じ。対して、復帰の切っ掛けは、紅白歌合戦への再登場。しかし、本当の切っ掛けは、紅白から5日ほどしてみたエディット・ピアフの人生についてのテレビ番組。その中で、ピアフは歌こそ人生。歌が人生そのもの、と素直に語っていたという。その意味に初めて目覚め、「そうだ、私は歌が好きなのだ。その歌こそを楽しみ、それが私の人生だという気持ちを大事にしよう」と強く、深く確信した。それからは、コンサートも自分流で、楽しくやっているそうな。そういえば、10年ほど前、国技館でのはるみちゃんのコンサートに行ったときも、凄く楽しそうに歌っておられた。野外コンサートの録画を見ても、益々、乗ってやっておられる。こんな人生、みんなも見習うべきだなあ、なんて感心しました。民放もたまに面白い番組を作るのですね。その意味でもちょっと驚き。(なんて、失礼ですねえ。)
2006.01.09
コメント(0)
-
4人組
今日の新聞に中国の文化大革命当時指導者の立場にあった、4人組の最後の生き残りだった妖文元(ヨウブンゲンと日本語では発音している)が死んだとの記事が各紙に載っている。1976年に毛沢東が死んで(周恩来が死んだ直後でしたが)、4人組の追い落としにかかる。そして確か1978年ごろだったと思うが、4人組が断罪され権力から追われた。何百万という人の命を奪い、それに数十倍する人たち、特に若者の夢と将来を奪った、「指導者たち」。あれで中国の歴史の進行が20年は遅れたのではないかと思っていた。その最後の一人の死。個人的には、ひとしおというか、感慨深いものがある。2-3年前だったか、中国に出張していて、中国の若者(というか、会社の部下の若手・・・・一流大学を出た優秀な連中)と話していて、4人組がどうした、こうした、という話は、彼らのほうが全然ピンと来ていなかった。むしろ私が解説してやったくらい。恐らく、情報統制で4人組の歴史や文化大革命などは学校でも、マスコミでも余り触れられないからだろう。本当は、ああいう民族の悲劇こそを言い伝え、二度と繰り返さない教育が必要なのだろうが・・・とまれ、彼等の失権から25年とちょっと。今や中国の発展は目を見張るばかり。でも、これは日本だって、昭和20年の廃墟と昭和45年の姿を比べれば、信じられないくらいの発展だったから、「お互い様」ではあるのだろう。ただ、それを「歴史」として知ってる部分が多い日本と、「同時代人」として、遠くからではありながら、横で見ていた中国とで、個人的には感じ方が違う。面白いものですね。こんなところにも、時の区切りを感じる。同じく、イスラエルのシャロンが、少なくとも政治人間としての生命を終えた。こちらも、過去20-30年間、中東情勢を動かす一方の軸だった人。彼も舞台から去ったのですね。果て、こちらの方は、これからどうなるのやら。
2006.01.07
コメント(0)
-
時の流れと人の流れ
昨日か一昨日のNYタイムスの記事で、時の移り変わりを感じさせるものがあった。人の流れである。去年あたりから、新聞・雑誌の記者、それも政治記者が名前の通ったマスコミ紙・誌を辞め、ブルームバーグ社に移っているという。理由は簡単で、新聞・雑誌は読者からのお金が入らなくなり、加えて広告宣伝も減ってきたので、人減らしをするしかない。他方、ブルームバーグ社はベースの金融機関向けの端末・ニュースサービスの事業が順調で、カバレージを拡げるべく人を採用する。それも、どうやら買い手市場だから、選びに選んで採用しているそうな。ネット社会の一つの断層ともいえる。日本みたいに必ずしも「活字離れ」という訳じゃないだろう。要は、メデイア間のシェアの問題。かねて、Eビジネスやネットのインパクトとして言われていたことに過ぎないが、ヤッパリ徐々に、しかし着実に変化は起こっていたのだと思い知らされる。これって、日本でも類似の現象が起こるはず。楽天とTBSとかという矮小な形でなく、もっと基本から揺るがすようなことが起こるのでしょうね。何時ごろ、どんな形で起こるかです。
2006.01.05
コメント(0)
-
株式投資の方法論
今日はかなり真面目な話。NYタイムスの記事に、ちょっと理論的な話が紹介されている。インディアナ大学の教授とアシスタントの共同論文のテーマは、株式運用の方法論について。それも理論でなく、実績値の検証。(因みにその教授の名前がインド人の名前で、ちょっとどう発音するのか分かり難いので、ここでは紹介しません。それにしても、最近のビジネス・スクールを初め、アメリカの大学でのインド人教授の多いこと。これは凄いトレンドですね。)個別の株の売買を推奨・実行する、「アクティブ運用」と市場全体の指数にあわせて売買する「パッシブ運用」。アナリストが優秀なら、市場全体の動きを反映するインデックス(東証株価などの指数)より、美味しい株を買い、まずい株を売ることでより高い運用実績を残せるはず。アナリストはその優れた分析力と、将来への洞察力によって、たかが指数ごときものに勝たねば、存在価値が疑われる。ただ、実績としては、どんなアナリストでも、彼らが「何とか投信」という形で株の選択をしたものは、市場全体の指数の運用実績を越えるケースは圧倒的に少ないのが現実。だから、機関投資家をはじめ、かなりの投資家がパッシブ投資に比重を置き出した。そのアクティブ運用とパッシブ運用の量的な実績値を推定しようというのが、この論文の意図。この推定は、当然の事ながら、極めて難しい。それを、快刀乱麻を切るがごとき手法で切ったのがこの論文と言う事のようだ。詳細はNYタイムスを見てください。で、結論は、1960年代は市場の80%ほどはアクティブな運用だった。それが最近は24%にまで減ってきているらしい。アメリカ以外の国でも、先進国は同じような傾向。発展途上国ではまだまだ、アクティブな運用が多いとか。因みに中国の株市場は、80%ほどアクティブに運用されているという分析結果らしい。これって、いかにもそうだろうなと思わせる。そして、この「事実」から何を導くのかは、各人の勝手ですから、ご興味のある方は、正月の暇な時に、勝手に考えてみてください。私も考えます。
2006.01.02
コメント(2)
-
やす・きよは別格だ
新年明けましておめでとうございます。なんて、特段変わったことがあるわけじゃ無いですが、まあ、新しい年を迎える感じは良いものです。今年も充実したいい年に出来るよう、頑張ります。さて、昨日はつまらないテレビ番組が並ぶ中、NHKのBSでやすし・きよしの漫才の特集番組をやっていた。一時間強の時間を使った、たっぷりとした番組。昔の漫才を二人がやっているシーンの再放送もあれば、やっさん(ご存知故人)を偲びつつ、笑い飛ばすセグメントもある。その為に林家木久蔵を呼んで、漫談風に一ひねりやらせたり、やす・きよの家族の声を取ってきたり。それにしても、昔の漫才を見ていて、ヤッパリ、圧倒的に面白い。ゲラゲラ大声をあげて、笑ってしまい、暫く笑いが止まらなかった。こんなことは、久しくないこと。腹を抱えて笑うとは、こういうことだったんだ、と思い出させてくれた。やすし・きよしの漫才は、別格だ。あんなおもろいもんは、他のコンビじゃあ出来ないのだろう。そんな思いをしていると、やっさんを太平シロウが演じて、やすきよの漫才をやりだしていると、西川きよし師匠がいう。これも中々の出来で、結構面白かった。せめてもの楽しみになりそうだ。しかし、本家本元の「横山やすし・西川きよし」の漫才は本当におもろい。何でやろうと、考えてしまう。やっさんのキャラがあるから、おもろさが引き立つことは間違いない。日々の常識的な暮らし・言葉の裏に隠されているユーモアを凄く上手に引き出し、笑いの対象にする技術の鋭さと間のとり方。・・・・・色んな分析は出来るのだろうが、そんなことより、見てて。聞いてて、あのおもろさを素直に感じさせてくれる漫才を堪能した。いい年の暮れになりました。新しい年は、どんな興奮を、堪能を齎してくれるのでしょうか。楽しみです。
2006.01.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1