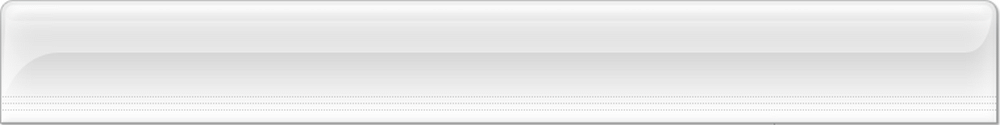2007年04月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
距離感の更新
距離感を壊すのが芸術の仕事かもしれない。すくなくとも真直ぐに整列させるのが芸術の仕事ではない。一番遠くにあるものを前景に持ってきたり、風景の消失点はいくつもあると考えてみたりする。自明と思われている枠組みや価値観を疑ってみる。絵を見る人は絵にとって不可欠なものである。私の絵の前に立つ人が、私の作品を背景にして、レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザの微笑みのような存在になればいい。アトリエからの帰り、修理中の八坂神社の前を通過しながら、こんなことを考えた。出会いとは、距離感の更新である。
2007年04月30日
コメント(2)
-
お気に入りの人
昨日のブログを読んでくれた「お気に入りの人」から、興味深い研究会ですねとメールが入た。今日はお昼からアトリエに出ようかなと思案しているところだった。すぐに電話しようと番号を探したが見つからない。電話をいただいて、はじめましてと挨拶された。わかりますかというので、名前を言って、名字を言った。はっと電話がはじめてだったことに気がついた。お会いしたこともなかった。携帯番号も知らなかった。はじめての電話だったけれど、昔からの知り合いのように会話した。電話を切った後で、さっき言った名字がちがっていたことに気がついた。なぜか中学生の頃にあこがれていた人の名前に重ねて勘違いしたようだ。森に行くことにした。新緑の木々を見てから、アトリエに入った。
2007年04月29日
コメント(2)
-
自分大好きな人
昨夜、ひさしぶりに自分大好きな人から電話が入った。元気そうだ。 「どうやら私はいつもまわりの人から可愛がられる運命にあるようだ」と言う。 「私もそうだな」と答えると「なんで自分の話に持っていくかな」と笑っている。 そして、しばらく「なぜ、自分たちは愛されるのか」というバカすぎる話がつづく。 まず、「理想や夢に共感できる、仕事を尊敬する」 これがなければ、興味は持たない。 (自分大好きの裏返しの自分勝手な大前提である) まず、かっこいいところを見せたり、見せられたりする。そしてかっこよく食事を して、かっこよくアルコールを楽しむ。かっこよいところだけで付き合っている関係 は比較的安全である。 むしろ、落差のある出会いや落差のあるキャラクターの振幅感があぶない。かっこい いところとかっこわるいところを同時に見せられたり、がんばったあとで、気を許し た態度を見せたり見せられたりすると、好きになったり、好きになられたりしやすい。 「無意識だよ」「わざとしてないよ」「してない!してない!」 自分大好き。脳天気過ぎないか?
2007年04月29日
コメント(2)
-
脳のしわしわ
大学時代にお世話になったある先生が、今は美術館の館長をされている。その先生が座長をつとめる研究会の立ち上げに声をおかけいただいて出かけた。子どもの絵の心理判定の研究をされている方など、普段、出会うことのないいろんな経歴をお持ちの方が参加する会だった。今回のテーマは「表現プロセス」についてで、先生の著書をテキストにして、子どものなぐりがきや頭足人、エジプトの庭園図、遠近法についてなどの討論がおこなわれた。その席で先生が私を紹介するときに、彼は論客で私の説になかなかうんと言わない人だったと愉快そうに笑った。昔から、そういう人だったようである。(ちょっとは謙虚にと少しだけ自戒した)随分、頭を働かせたので夕方、2時間熟睡。
2007年04月28日
コメント(0)
-
コーヒーとレーズンと言葉とリンス
夕方、天下一品のラーメンを食べてから、アトリエに入った。 コーヒーを入れて、淡い黄緑色のレーズンを食べた。 集中して描きはじめると、言葉は必要ないような気がしてくる。しかし、本当は作品 をつくるためには言葉も必要だ。 制作の後で筆をまとめてリンスした。筆にリンスすると毛先がそろって描きやすくな る。
2007年04月24日
コメント(0)
-
温故知新
アルバイトで生活していた頃、中古オーディオ屋さんでふと耳にしたスペンドールBC2というスピーカーの音が気に入って無理して買った。壊れたラックスのアンプを拾ってきて、修理してもらって鳴らした。何年かして京都にあるオーディオの木村で流れている音に感動して、木村さんがチューニングしていたラックスの真空管アンプを木村さんが納得するまで半年待って買った。今日は、そのアンプの真空管に積もっていた埃を掃除して、配線もクリーニングして、昨日買ったCDを聴いた。オーディオも手をかけるとよみがえる。午後、額装を頼んでいた作品を取りに行ったついでに十字屋に寄った。今日、買ったのは、JOHN COLTRANE の「STATIN` THE PACE」「LUSH LIFE」「STARDUST」とヴァーシャーリのピアノ「別れの曲/ショパン:ピアノ名曲集」「ラフマニノフ ピアノ協奏曲大2番/パガニーニ狂詩曲」今まで聴いたことのない古い録音の名盤が新譜のように新鮮。勢いで、部屋の掃除をはじめて、今日もアトリエはお休み。
2007年04月23日
コメント(3)
-
派手なシャツを買った
連夜、遅くまでの制作をつづけて疲れると、ピアノの高音域のある音から耳鳴りが始まる。ある音だけが鼓膜を強く揺らせて旋律の調和を曇らせる。昼前に目覚めて、エスニックな輸入雑貨屋で、長い袖がパッチワークになった派手なシャツを買った。2500円。海に行くかパジャマにするかと迷いそうなシャツ。派手なシャツの上にからし色のジャケットを着て外に出た。ジャズのCDを4枚買った。どれも名盤。「ELIC DOLPHY AT THE FIVE SPOT」「SONNY LOLLINS SAXOPHONE COLOSSUS」「SONNY LOLLINS WORK TIME」「MALT-1」高音域の耳鳴りは残っていたけれど、4枚つづけて聴いた。昼も夜も合間合間に眠った。
2007年04月22日
コメント(2)
-
遅くに戻って「プチ家出」かなと笑った夜
「家出」って何だろう。「家出」とは行き先と帰りの予定を告げずに突然いなくなること。そして、そこにはしばらく家にはもどらないという意志がある。まったく何も告げずにいなくなると事故や誘拐と区別がつかないので、手紙くらいは置いてほしい。一家の働き手がいなくなる場合、「家出」よりも「蒸発」というほうがしっくりとくる。異性といっしょにどこかに行ってしまうのも「家出」のイメージからは少しずれる。家族に行き先を伝えて出かけると「家出」ではなく「旅行」になる。そう考えると「家出」の目的は、家や家族から自由になることにあるようだ。朝出かけて、夜にもどる当たり前の一日のなかにも、小さな「家出」がかくされているのかもしれない。
2007年04月21日
コメント(2)
-
ありがとう!
Eちゃんとはずっと家族ぐるみのおつき合いが続いている。Eちゃんは染色体に異常があるらしく言葉は話さないけれど、明るくて心のやさしいお嬢さん。いつだったか、Eちゃんとふたりで家の前のプランターの植え替えをしたことがあった。Eちゃんは土や植物に触れて興味津々。大人になったEちゃんは今はグループホームで働き、週末に家に帰る生活。Eちゃんのまわりでみんなが育った。
2007年04月21日
コメント(0)
-
窓の明かり
誰かが自分のことを本当に必要としているのかと疑う一日は、 どこかに置き忘れてしまいたい。 誰かが自分のことを本当に必要としていると思うことのできる 一日はしあわせだ。
2007年04月20日
コメント(0)
-
虚構と現実
片付きすぎた部屋は人工的な感じで落ち着かない。適当にちらかっている部屋がいい。ものがあふれていてもなんとなく分類できていればいい。床にものを置くのは、ほこりが増えるのでできれば避けたい。部屋の掃除ができていなかったので、午前中、少し片付けた。夜にアトリエで、岩城見一著『感性論』を読みはじめた。第一章は「イメージの力」。あまりにリアルに描かれ過ぎた絵は「だまし絵」やロウ人形のようなものになってしまう。絵の中の立体感が平面の統一感を壊す。それを画家はさけようと地に図と調和する色がおいて平面性を保とうとする。描くときの実感が言葉で語られていると感じた。
2007年04月18日
コメント(2)
-
輪郭
輪郭が閉じると息苦しい。輪郭をなぞるとよい絵にならない。
2007年04月16日
コメント(0)
-
作品の展開
スタイルを変化させることが目的ではないけれど、ひとつのスタイルに安住しないピ カソやピカビアのようなアーティストに惹かれる。 作品の変化にはなんらかの脈絡があるべきなのに、ふっとひらめいてスタイルが変化 してしまう瞬間がある。そのひらめきが今までとは違ったスタイルの作品をつくらせ る。こんな作品をつくってしまったら、自分にはその次の作品がつくれるのだろうか と不安になる。今、描いているのもそんな感じの作品だ。飛躍を肯定しよう。
2007年04月10日
コメント(3)
-
ストレス解消
アトリエに入る前に100円ショップをのぞいた。買ったのは、ピンホールの視力トレー ニング眼鏡とUFOのようなかたちのステンレスソープ。
2007年04月09日
コメント(2)
-
昼夜逆転
昨夜、朝方まで個展の案内状をデザインしネット入稿した。目覚めて、再度、なにげ なく確認したら、アルファベットの「a」が「p」になっているところを1カ所見つけ た。すぐに印刷所に電話したけれど、原稿はもうラインに流れていて、解約料がかか るというのでそのままでがまんすることにした。一日、だらだら過ごして、夕方にお 好み焼きを焼いて、ビールはがまんして、夜にアトリエに入った。 大作に手を入れ出したので、3時過ぎまで制作。ビル・エヴァンスのCDをリピートに して流しつづけた。
2007年04月07日
コメント(4)
-
すべての音を吸い込むような桜の花に触れた
京都国立近代美術館で、夕刻5時から8時にだけ開催されている「ノイズレス」という音の展覧会に出かけた。音のアートというとなにか新しい表現のような印象があるけれども、音も古風でありふれたメディアだということに気付かされる。あるいは、古風でありふれた現代美術のようだ。たとえば、録音されコレクションされた音は集めた本人には楽しい素材であるかもしれないけれど、聞かされる人にとっては特別なものではない。音のコレクションもなんらかのプロセスを経てアートに昇華されなければ、美術の文脈に依存する自己満足でしかないのだろう。むしろ、作品になどしないで音の博物館をつくればよい。美術館を出て、琵琶湖疎水のライティングされた満開の桜を見た。勧業館の対岸の角のベンチまで歩いてコンビニで買った缶ビールを開けた。このあたりは人通りもそんなには多くない。満開であるけれども散る花びらはない。静止した時間がいつまでも流れ続け、疎水の水面下で誘う花に引き込まれそうになる。「死んだらどうなると思う」と耳元で声が聴こえた。「死んだらなにもなくなる」とその声に答えた。「私もそう思う」と答えた声の主が桜の花に触れながら歩き続ける。
2007年04月06日
コメント(4)
-
すべてをネタにしてしまえばいい
直観ギャラリーでオーナーの親友のコンサートがあった。ギター1本とボーカルのシンプルな構成。ときおり歌と演奏に建物の外の救急車や選挙演説カーの音が重なる。歌う人は幾度かの恋に破れて、今も新しい恋のなかにいるのかもしれない。彼女の元パートナーは、私も大好きだったフォークシンガー。後半で、彼女は彼の隠れた名曲を歌った。ふたたび歌いはじめたことで彼女は世界とつながる。味わい深い歌声は悪くない。誰も歌えない心の歌。もっと内面をさらけだしてもいい。
2007年04月01日
コメント(2)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- 花や風景の写真をアップしましょ
- 今朝は久々に・・・天空の城になって…
- (2025-11-14 22:25:06)
-
-
-

- 手作りガーデニング
- 元気なのはサボテンと大葉
- (2025-09-22 05:23:35)
-
-
-

- クリスマスローズについて
- クリロー「ダブルファンタジー」三代…
- (2025-11-10 00:00:07)
-