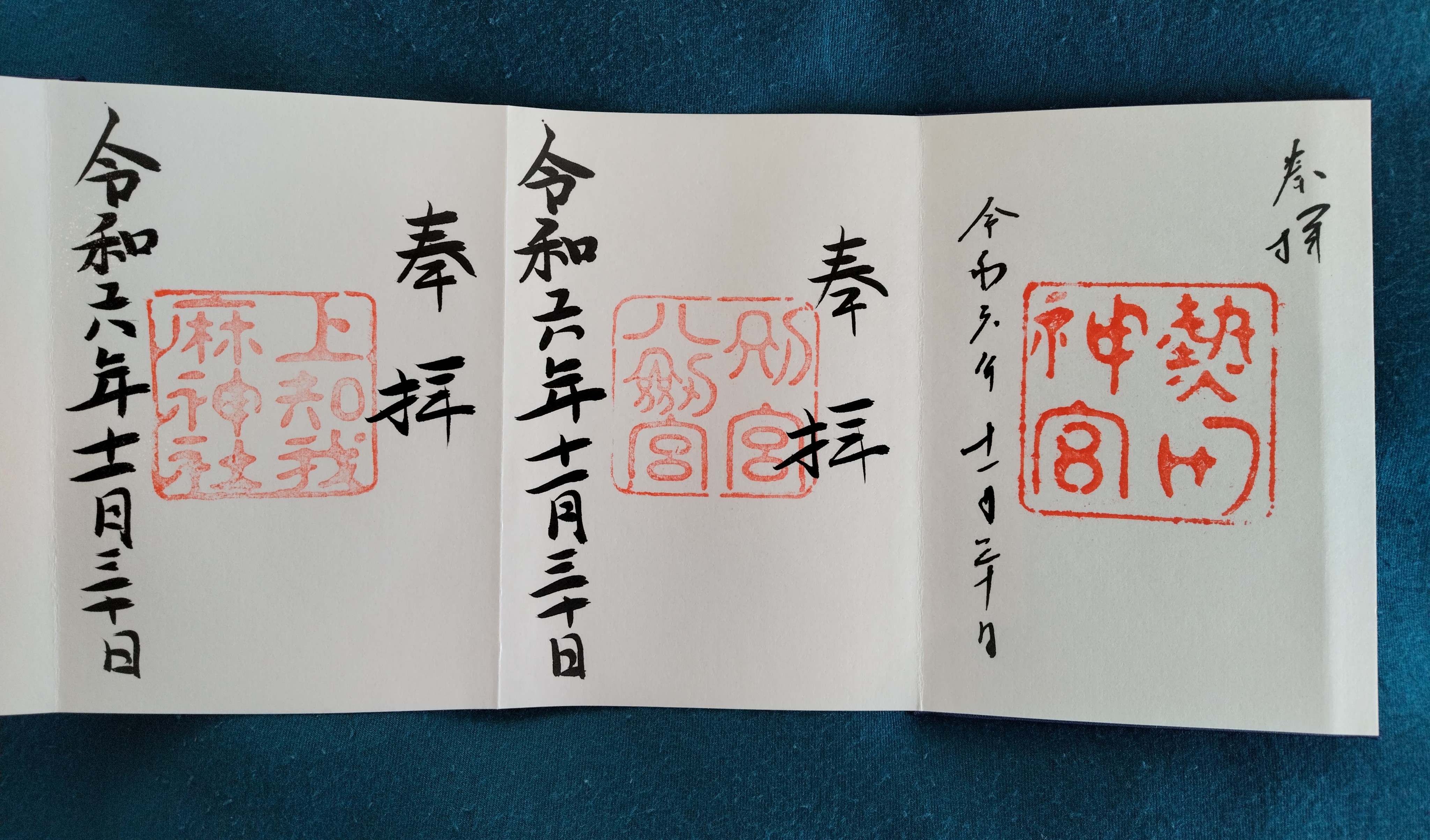2007年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

スパッカナポリを歩く
スパッカナポリは「ナポリを真っ二つに割る」という意味。山から見るとクローチェ通り(おそらく)がナポリの街を文字通り2つに切っているように見えるらしい。残念ながら、「スパッと割ったナポリ」を実感できる眺めを見ることはできなかったのだが、「造形美の坩堝」であるスパッカナポリは、もちろん歩いて堪能した。こちらはジェズ・ヌォーヴォ教会。特異なファサードに思わず足が止まる。異様な力強さで視覚に迫ってくる。そのそばにある広場。建物に囲まれた暗い路地から、いきなり明るく日の当たった広場に出るとき、ちょっとした感動を覚える。トキメキとか、解放感といってもいいかもしれない。陣内秀信はそれを「広場との感動的な出会い」と表現している。ナポリに行くなら同氏の「南イタリアへ!」を読むといい。これはとてもわかりやすく、しかも示唆に富んだ南イタリアの街と建築の解説書になっている。美術史家の著作は過去にもいろいろあったが、特に建築史家としての立場から、ここまでイタリアの街の構造と建築物のおもしろさを日本に紹介した人はいなかったのではないか。南イタリアへ!たとえば、陣内はナポリの街角の広場に立つグーリア(guglia)についても詳しく解説している。グーリアとは「尖塔」「尖頂」のことで、教会の屋根の上にある。上の写真で広場の真ん中に建っている塔がそれだ。一見「オベリスク(obelisco)」の小さいもののように見えるが、グーリアとオベリスクは起源がまったく違う。オベリスクは古代エジプトで権力者の功績などを記念するために作られた方尖柱(塔)のことだ。グーリアはあくまで、教会建築の屋根の頂上を装飾する尖った構造物。陣内によれば、ナポリでは、その尖塔を宗教的祭礼の行事の際に、祝祭のための象徴物として置いたという。それを広場のモニュメントとして恒常的に設置したのが、スパッカナポリの小広場にしばしば見られるグーリアというわけだ。だからオベリスクのような権力者の権威を示すためのものではなく、熱狂的な大衆の祭りの記憶を広場に留めて日常化させたものと解釈できるという。そして陣内は、「この装飾要素は、都市空間に舞台装置的な効果を生むのに大いに貢献している」と指摘する。確かに、庶民が片寄せあって暮らす下町の狭い路地から、ふと明るい広場に出たときに、開けた空間の中にグーリアが屹立し、そこに太陽の光が当たり、周囲に日常品を売る店やちょっとしたものを食べさせる店のパラソルが並んでいるのをみると、何か、ある舞台美術の中に入り込んだような気持ちになる。生活する人々の声が聞こえる。働く声、時間をつぶす声、楽しむ声、怒る声もしているかもしれない。こうした活気は「本番の舞台演劇」で響くセリフそのものだ。スパッカナポリの広場に足を踏み入れる瞬間、それは下町の広場という舞台に、あなたも役者の1人として出て行くということなのだ。ナポリの人はみな、こうした「舞台装置的な空間」の中で自分の人生を演じている。こちらはサンタ・キアーラ教会の中庭。マヨルカ焼きの柱とベンチが整然としつらえてある。この「舞台装置」はよく手入れされた、きわめて静謐な空間の中にある。教会の外の都市的な雑踏とはまったく別世界だ。こうした静寂と喧騒の見事なまでの対比、しかもそれがごくごく隣接して存在していることにナポリの大きな魅力がある。細部まで見ると、マヨルカ焼きの絵付けの技量自体はそれほど高いものではない。だが、それがこうして柱となり、背もたれ付きのベンチとなって大規模に計画的に設置されると見事の一言だ。日本のたとえば有田だったら、スポンサーさえいれば、これ以上の美術的な価値のある空間が作れるだろうに。このベンチはいかにも「座って休みたくなる」ような清潔感がある。だが、ちょっとでも座ろうものなら、あるいは何かを置こうものなら、眼を光らせている係員がやってきて、いちいち注意する。日本だったら看板をそこら中に立てそうだが、ナポリ的美意識ではそうした余計な「舞台装置」は排除すべきものらしい。かわりにナポリ人は、「言葉によるルール伝達」を優先させている。そうした意識はある意味、日本人とは対極にあるかもしれない。
2007.10.31
-

ナポリはホテル・エクセルシオールで満足する
ナポリ2日目もホテルをかえた。海岸沿いの「Hotel Excelsior(ホテル・エクセルシオール)」海の見える部屋を、ということでネットで予約してある。1日目のホテルがとんだ日本人冷遇ホテルだったので、不安な気持ちでチェックイン。ホテルに着くのが早かったせいで、部屋の準備ができていないという。そこで、ホテルの豪華なバールでスプレムータ(生ジュース)を飲みながら部屋が整うのを待った。さすがに、エクセルシオールは歴史のあるホテルだけあって、クラシカルで重厚な内装だった。バールでバリスタのおじさんとおしゃべりしているうちに、部屋の準備ができたといわれて、ポーターについていく。今日の部屋は昨日のホテルとはうってかわって、広々と、天井が高く、ベットやリネン類も高級感がある。窓には重たげなカーテンがさがり、バルコニーに出ると、ナポリ湾が一望できる。バスルームもゆったりとしており、大理石がふんだんに使われている(ただ、シャワーの栓がちょっといかれていて水の止まり具合が悪かった)。バルコニーからみたナポリ湾。遠くにベスビオがかすんで見えた。海は太陽の光をあびてキラキラ光っている。風もおだやかだったせいか、ヨットがたくさん出ていた。右に視線を移すとヨットハーバー。沖では、まるでアリが羽虫を運んでいるみたいにヨットの帆が海面を動いていく。気になる(?)1泊のお値段は当時300ユーロで、そのときのレート換算で3万4800円(カードで払った)。このプライスならむしろ安いと思った。ただし、今はこのホテル、ツインのラックレート(正規の価格)は360ユーロになっている。今のレートで換算すると5万7600円(ひえぇぇ~)。ちなみに、アップルにもエントリーがある。アップルをとおすと4万5000円からとあった。ということは、今は直に個人で予約するより、アップルをとおしたほうが安いということかもしれない。アップルだと基本的に事前に部屋の指定はできない。ただ、現地で空いていれば融通を利かせてくれることもある。もちろん、アップルを通したほうが「いつも安い」とは限らない。直が安いか、アップルを通したほうが安いかは、その都度、自分でリサーチしないといけない。Mizumizuはたいていネットでホテルのホームページにあるラックレートとアップルのレートを調べてから、どう予約するか決める。ただこれ、面倒は面倒なので、人には強くはお薦めしない・笑。朝食もリッチだった。モッツァレッラだけでも、少なくとも3種類は用意されていた。カンパーニャの大地の豊かさを感じる。モッツァレッラはやっぱり南だよな~。昨日の「日本人冷遇ホテル」に2泊しなくてよかった、と心から思ったのだった。
2007.10.30
-
見逃したバロックオペラ
ようやくサンカルロ劇場のボックスオフィスに着き、「メールでオペラ・アマディージのチケットを取っておいてもらっているはずだけど」と告げると、窓口のおじさんが怪訝な顔をした。「アマディージはここではやらない。それにもう始まっているよ」――え?慌てて上演時間をメモした紙を見る。18:00時、と自分で書いていた。しまった! すでに午後7時近い。18時を午後8時と思い込んでいたのだ。しかも劇場はサンカルロの中にある小劇場ではなく、700メートルぐらい歩いた別の場所にある劇場らしい。がーん!このバロックオペラのために、わざわざ日程を調整して、インスブルックから夜行でナポリに着いたのを、いったんソレント半島のアマルフィに行き、そこで2泊してバスで戻ってきたというのに!バロックオペラの中でもヘンデルのオペラは評価が高い。にもかかわらず、日本での上演機会はまだまだ少ない。「リナルド」だって珍しいのに、「アマディージ」を日本で上演してくれるなんてことは当分望めそうにない。日本は世界有数の「オペラ消費都市」だ。有名歌手・有名指揮者・有名オケがこぞって来日する。ただ演目はやはり、お客が集まりそうな無難なものにかたよりがちだ。バロックオペラは体制(つまりは当時の絶対王政)礼賛オペラも多く、今の聴衆には到底受け入れられないような奇異なストーリーが多いというのも、人気がでない理由のうちかもしれないが。いったんは、アマディージが上演されているという劇場の方向に歩き出したが、やはりいくらなんでももう遅すぎる。途中で諦めて引き返した。そのかわり、サンカルロ劇場で翌日のバレエのチケットはしっかり受け取った。歩きつかれて、途中でもうタクシーで帰ろうということになった。ナポリは石畳の道が多く、しかも、その道自体がゆがんでいるので、歩くのが疲れる街だ。道端にタクシーをとめて何やら書き物をしてるにーちゃんがいたので、話しかける。「乗ってもいい?」「ダメダメ。今日の仕事はもう終わったんだ」しかし、ここでせっかく見つけたタクシーを逃したら、また探すのは面倒だ。「でも、すぐ近くなんだけど。それにママがすごく疲れていて…」イタリア男は「ママ」を出されると弱い。運転席から疲れた様子のこちらを見る。「どこまで?」「ホテル・メディテラネオ。すぐ近く」「じゃ、いいよ。乗って」疲れているときは、ボロな(失礼!)タクシーのシートも心地よく感じるもの。タクシーでホテルまでラクに戻った。すぐ近くなのだが、グルグル道を回って走った。ナポリのタクシーはこんなふうに、直線距離だと近いはずの場所もグルグル回っていく。「雲助が値段を吊り上げるためにやっている」とブログに書いている日本人もいたが、実際は街中の道は一方通行が多いから、遠回りしているように見えるだけで、案外最短距離で行っているのかもしれない。まあ、本当のところはわからないが。ホテルに着いて「いくら?」と聞くと、「5ユーロ」と言われた。アマルフィからナポリまで2時間バスに乗って3ユーロちょっとだったのに、数百メートルの距離をタクシーでいくと、これ。だいたいナポリは当時5ユーロが最低料金だった。あのときはレート換算すると600円ぐらいで「日本とだいたい同じだな」と思ったが、今だと800円が最低料金ということになる。ヤレヤレ。
2007.10.29
-
ガレリアの犬
ガレリアを抜けるとすぐにサンカルロ劇場だが、ガレリアを出るときに階段のところで一匹の仔犬が近寄ってきた。仔犬… いや、小型犬で実際には子供ではないのかもしれないが、とにかくそれほど年をとっていないのは確かだ。犬好きのMizumizuは足を止める。首輪はしていないが、尻尾を振って足元をクンクンする人なつっこさからすると、野良犬ではなく捨てられた犬だろう。少し皮膚病にかかっているらしい。あいにくあげられるような食べ物はもっていない。「どうしたの? 捨てられたの?」話しかけると、さらに一生懸命に尻尾を振った。階段をおりるMizumizuの足元にくっついてくる。そのままガレリアから離れ、道をわたって広場のほうへ歩いた。犬はそこまではついてこない。しばらく歩いて振り返った。と――小さな瞳がじっとこちらを見ている。Mizumizuが振り返ったのを認めると、また尻尾を降り始めた。――呼んでおくれよ。そしたらすぐに、ついていくよ仔犬の眼はそう言っているように思えた。イタリアでも捨て犬は問題になっている。長いバカンスに行く前、あるいはバカンス先で、ペットの犬を捨てていくらしい。特に南イタリアでは野良犬をよく見かける。あまり人間がいじめないのか、人通りの多い道でも堂々と寝ている。だが、そういう犬が、また誰かに拾って飼ってもらえるかというと、それはまた別問題らしい。サンカルロ劇場の脇の広場には別の野犬も寝ていた。こちらは大型犬だ。だが、やはり皮膚病にかかっている。実は、サンカルロ劇場の入り口を探していたのだ。どうやら広場のほうにはないとわかり、またガレリアのほうに引き返した。すると、さっきの仔犬は、交通整理をする婦人警官の足元にぴったりよりそって、婦人警官の見つめる先を一心不乱に見つめ、さかんに尻尾を振っている。――この人がボクのご主人さまだよ。ほら、ぼくらはこうして一緒に働いているんだ婦人警官が仕事を終えてその場を去るとき、彼はまたあの訴えかけるような瞳でその姿を追うのだろうか。決してしつこくはしない。しつこくして邪険に追い払われるのはイヤだ。でもいつかきっと、もしかしたら明日、ご主人さまが現れるかもしれない……日本で「崖っぷち犬」が話題になったとき、北は北海道から南は沖縄まで、飼い主希望者が殺到したという。ところが、彼らは一様に、「テレビで有名になったあの犬」だけを欲しがり、施設の職員の呼びかけにもかかわらず、抽選にはずれると他の犬を引き取ろうとはしなかったという。中には選にもれて泣き出す子供もいたそうだ。まったくなんと軽薄でさもしい行動だろう。有名になったお犬様を手にいれ、「これが、あの『崖っぷち犬』」などと自慢したいのだ。そんなみみっちい虚栄心のために労を惜しまず出かけていく。かわいそうな犬は彼らの町にもいくらでもいるというのに。みながそのニュースを忘れた3年後、5年後にはどうするのだろう? もともと野良犬だった犬は人になつきにくい。それでも、もらいに行きたいと考えたときと同じようにかわいがれるのだろうか?子供が「どうしてもあの犬が欲しい」と泣いたら、あの犬は特別ではなく、どの犬にも同じ命があるということを教えるべきなのだ。そして、生き物を飼うにはそれなりの責任がともなうことも。Mizumizuは大の犬好きだが、飼わないでいるのは、今の生活状況と環境では、最後まで責任をもって面倒が見られるかどうかわからないからだ。犬はかわいい。そばにいてくれたら生活も楽しくなりそうだ。あのナポリの「ガレリアの犬」を捨てた飼い主も、おそらく最初はそう思って彼を手に入れたはずだ。きっとかわいがったのだろう、最初のうちは…「ガレリアの犬」は人間のエゴの犠牲者だ。それでも彼は、人間を信じて待っていた。「ガレリアの犬」はナポリだけではない。日本にもたくさんいる。「ガレリアの犬」の飼い主は、彼をかわいがった日々を忘れてしまったかもしれない。だが彼は憶えている。人間に愛され、幸せだった自分を。だから、行きずりの人に愛想を振りまくのだ。ガレリアの周囲には他にも大型の野良犬がいた。小さな彼は、大きな彼らにいじめられることもあるかもしれない。広場のほうに来なかったのも犬同士の縄張りのようなものがあったからかもしれない。そして、守ってくれる者のいない空の下で、不安な気持ちで眠る夜、「ガレリアの犬」が夢見るのは、ご主人さまに寄り添って暮らせた満ち足りた日々かもしれないのだ。
2007.10.28
-

イタリアで感じた日本人と韓国人の違い
理不尽なことをされても抗議もできない日本人もどうかと思うが、韓国人の自己主張の強いふるまいには逆の意味で驚いたことがある。それはローマの空港に遅くついた夜のこと。翌朝からレイルパスを使う予定だったので、ホテルに入る前にテルミニ駅に寄って、夜のうちにパスの使用開始印を押してもらえるかどうか確認しに行った。夜10時をまわっていたと思う。空いている窓口は1つだけ。そこで、なにやら駅員に英語でまくし立てているアジア人の男女がいる。後ろに並んだが、駅員が全然英語を理解しないので、話が進まない。アジア人は英語のアクセントから判断するに韓国人だ。待つのも面倒なので、しゃしゃり出て、「どうしたんですか? イタリア語ができますから、通訳しましょうか?」と英語で話しかけた。韓国人カップルは、これ幸いと説明を始める。「インターシティで来たんだけど、電車が3時間も遅れたんです」「だから、100%返金してもらいたいの」――はあああ?ショージキ驚いたが、まさか私から「そんなことしてくれるわけないじゃないですか。ここはイタリアですよ。3時間遅れ? 別に珍しくもないんじゃ? それに遅れたといっても乗ってここまで来たんでしょう? 難癖つけてタダ乗りするつもりですか?」などとも言えず、「返金ですかぁ?」と確認するに留めた。すると、「100%よ!」と、念押しする女性。若くて美人だが、発想は完全にオバちゃんの領域に足を踏み入れている。仕方ないので、イタリア語で駅員に話す。どう答えるかな? と思ったが、イタリア人駅員のとった作戦(?)は、「たらいまわしの術」だった。「私は、そういうことをする立場にない。明日朝7時にあっちの総合窓口が開くから、そこで話してほしい」なるほど、そうきましたか。面倒なことはたらいまわしネ。返金なんてされないってこと、わかってるのに。顔色も変えず、ぬけぬけと言ってくれるワ。Mizumizuは今度は英語でカップルに話す。一晩たってしまえば返金などされないことぐらい、彼らもわかっているだろう。男性のほうは、「あ~、そう」と、がっかりしながらも納得したようだったが、女性のほうはなおもMizumizuに食い下がる。「どうして彼が返金しないの?」「そういう責任をもってないからだって言ってますよ」こういうときは男性のほうが物分りがいい。男性にうながされて女性も諦めて去っていった。また、ローマの空港から帰国するときも、大迷惑の韓国人ツアー客に遭遇した。彼らは集団で免税ショップを物色し、タバコやらお酒やらをじゃんじゃんカゴに入れてキャッシャーに殺到する。自分の前を歩いている人も押しのけるような勢いで、単純にいえば順番抜かしをしてキャッシャーに並ぶ。ところがいざ、払う段になると、わずかなドル札を出すだけなのだ。それも買った品物に対して、出している金額が全然足りない! 「別の通貨はないの? カードは?」とキャッシャーのお姉さんが聞くのだが、英語も全然通じない。足りないということはわかるらしく、「これとこれを省いたらいくらになる?」などと、今度はキャッシャーで品物をカゴから出している。キレた店員に「ダメ」出しをされても、なおも粘ろうとするが、いよいよ拒否されて、しぶしぶもう一度買い物をやり直しに戻る。それが1人や2人ではないのだ。みんながそのパターン。自分で計算せずに品物を持ってきて、キャッシャーで計算したあとに、全然足りないドル札をぴらぴら出す。そこから品物を引いていこうとしているのだ。要は、余ったドルを使い切って帰りたいということなのだろう。ついに奥から責任者とおぼしきイタリア人のおじさんが出てきて、韓国人観光客の集団に、タバコケースを見せながら、「これはXXドル。ここに値段がある、10ドルでは買えない!」などと大声でレクチャーを始めた。さらに1人ひとりに寄っていって「あなたのもっているのは何ドル?」などとヘルプしている。汗だくで真剣、かつ相当怒った声だ。しかも、彼らは英語を理解しないから大変だ。「彼らは値段がわかっていないのね」とキャッシャーのお姉さんに話しかけると、「わかってやっているんでしょ!」とこちらまで怒られた。藪へび、藪へび(苦笑)。う~ん、「あの」イタリア人をここまでイラつかせる韓国人団体ツアー客パワー、恐るべし。昔日本人の農協ツアーのおじさんが、世界中でご迷惑をかけたやに聞いているが、彼らはそのその再来、韓国版農協ツアーなのかもしれない。日本人と韓国人って違うよな~、でも全然イタリアでは違いが認知されていないけど… 2002年韓国で行われたワールドカップの韓国vsイタリア戦の審判が公正でなかったことは、イタリアの若者の間ではだいぶ尾を引いているらしい。あのあとイタリアで若者に、「ヘイ、韓国!」などと呼ばれて、思わず見るとアッカンベーをされたことがある。トホホ。キミらの国であったワールドカップの審判も、サッカー史に残るぐらい、ずいぶんとイタリアびいきだったって話を聞いたけどね。審判が公正でも不公正でも、自分たちが勝てばいいのよね。そんなところも韓国とイタリアはいい勝負かもしれない。それに公共の場での大声でのおしゃべりも。ああ、そういえば、いい歌手が多いことも共通してる。さて、ナポリの一日目も暮れてきて、いよいよバロックオペラだ。明日のバレエはチケットをカード決済で買っておいたのだが、オペラのほうは小劇場でやるようで、「キープしておくから直接来て」というメールを受け取っていた。パバロッティもお気に入りだったサンカルロ劇場へ向かう。サンカルロに行くためにはガレリアを抜けていく。La galleria a Napoli, qui vite che non si incontrano stanno passandoガレリアは、要するに十字路のアーケードだ。床のモザイクが見事。ここで「ババ」というナポリの有名なお菓子を買って食べてみた。ババとは、お酒と砂糖づけにしたブリオッシュで、言ってみればサバランだ。本場のババはお酒も甘さも強烈だった。最初にかじったときは、「うっ」と思ったが、今となっては懐かしい。日本ではあそこまで強烈なお酒づかいと甘さのババはない。ナポリに行くことがあったら、また食べたいな。このガレリアを抜けたところで、1つの哀しい出会いが待っていた。
2007.10.27
-

ナポリ、Hotel Mediterraneoで大立ち回り
アマルフィからのバスはナポリの街中をとおって、駅に着く。駅と街の中心はかなり離れている。どうせなら、駅で降りずに街中の観光に便利な場所でおりて、バス停の近くで泊まれる適当なホテルを探したほうがよさそうだ。日本で地図と首っぴきで調べたところ、あったあった。バス停からすぐの場所にHotel Mediterraneo。その前の年までは3つ星だったが、改装して4つ星になったらしい。その分値段は1年でぐっと上がった(ツインで181ユーロ)ようだが、まあ快適で便利ならいいだろう。アマルフィからの長距離バスに乗るときに、運転手におりたい停留所の名前を見せて、着いたら教えてもらうように頼む。忘れてしまうこともあるから、到着時間を書いたメモを手に、その時間に近くなってきたら、運ちゃんにさかんにガンを飛ばす。そのかいあって、無事に目指す街中の停留所でおりることができた。荷物を引きずってホテルに入ったのがだいたい午後3時ぐらいだったと思う。Hotel Mediterraneoはロビーはわりあい豪華だった。ポーターについてエレベータにのり、部屋のある階でおりたところで、足がとまった。なんと、エレベータの前の絨毯をとめている金具が床から飛び出している。絨毯をはがす途中のようだ。廊下も暗い。そして外からものすごい工事音が聞こえてくる。「この音は何?」「今外壁を工事してるから」そうか、まだ改装が終わっていないのか。だが、部屋は改装されているものと、このときは信じ込んでいた。通された部屋に入って、言葉を失った。ボロくて暗い。バスルームは蛇口がさびついていて、水が垂れたあとがタイルに残っている。気になるベッドは…? 大丈夫だった。アマルフィのターボラ・ベッドのようなことはなかった。だが部屋は明らかに改装などされていない。とても181ユーロとは思えない。その前の年までは、このホテル、たしかツインで130ユーロか150ユーロぐらいだったはずだ。そのぐらいのプライスなら、まあバスルームはひどくても我慢できたかもしれない。街中で便利な場所にあるホテルなのだ。うんざりしながら、フロントに電話する。「この部屋は好きじゃない。別の部屋を見せてほしい」すると答えたのは中年の男性の声だった。「お客様、今日は予約がいっぱいで…」出た! お決まりの台詞。予約がいっぱいったって、Mizumizuだって予約している。それにまだ午後3時だ。全部の部屋がすでにチェックインすませているはずはないだろう。「まだ空いている部屋があったら、ちょっと見せてほしい」再度粘ると、「ポーターを行かせる」とのこと。さっきのポーターがすぐきて、別の部屋に案内してくれる。ところが!その部屋はさっきの部屋に輪をかけてひどい。バスルームのボロさはさらにグレードがあがっていて、とても足を踏み入れる気になれない。さらに、窓のすぐ外で「キーン」と工事をしている音が響いてくる。こんな部屋、お客を泊められるワケないじゃん!プンプンしながら、元の部屋に戻る。「ま、しょうがないんじゃないの」と連れの母は諦めムードだ。ナポリには2泊するが、明日はホテルを替える予定だ。だから我慢してもいいといえばいいのだが、「改装した」から値段をバーンと上げたのに、その「改装後」の値段で「改装前」の部屋に通すとは、ちょっと… いや、全然、納得いかない。それで、電話ではなく、フロントへ直接談判に出かけることにした。母には、「こちらが文句言っているときに、絶対に笑ってはダメ」だと厳命して。日本人の態度というのは、外国でみるとかなり変だ。クレームしているのに、自信なげで、見ようによっては相手の機嫌をとっているようにさえ見えことがある。あるいは、文句を言っているのか単に意見を表明してるのかわからない。あるいは、相手からかなり失礼なことをされていても、変にニコニコしている。不満があるときは、それがきちんと相手に伝わるように話さなくてはダメだ。そうでなければ、こちらが怒っていることが相手にちゃんと伝わらない。「雰囲気で察してくれる」ということは、ヨーロッパでは相手に期待しないほうがいい。フロントに乗り込んで、電話のおじさんにきつい声で抗議する。「私は改装したということで、このホテルを予約した。去年と比べてプライスは劇的にあがっている。それなのに、私の部屋は古くて汚い。改装した部屋にかえてほしい」フロントのおじさんの容貌は、なんというか、今亀田問題でやたらテレビに出てるボクシングジムの金平会長をナポリターノ(ナポリの人)風に濃くしたような感じ。「改装は1階ずつやっていくから、まだ終わっていない。改装した部屋は少なくて、もう予約がいっぱいで…」「私もずっと前から予約をしている。なぜ改装した部屋でないのか説明してほしい」「彼らはみんな、あなたより早く予約していたので…」(ホント、適当なことを次々言ってくれるよ)「私はインターネットできれいな部屋をみて予約したんだけど、実際の部屋はまったく違う。とても変だと思う。改装した部屋があいているならかえてほしい」「いや、すでに全員チェックインしていて…」手ごわいオッサンだ。改装した部屋がいくつあるのか知らないが、午後3時ですべてチェックインずみとは、ちょっと信じられない。そこに、電話が鳴った。ほかにスタッフがいるのに、ナポリターノ金平のおっさんが、「ちょっと待って」とわざわざ電話に出る。こんどはこちらを待たせてウンザリさせる作戦か?(笑)。「なんなのよ! 話してるのに、もう!」日本語で横の母に話しかけた。そのとき――「どうしたんですか~?」後ろから日本人のおじさんの声。ふりむくと、ビジネスマン風のおじさんが一人で立って心配そうにこちらをのぞきこんでいる。まあ、フロントで身振り手振りよろしく大声でまくしたててるのだから相当目立っていただろう。もちろん、目立つことが重要だ。こうしたホテルはトラブルが起こっている、というのを他人に見られるのを嫌う。誰だってホテルに入ったとたん、フロントでケンカしてる人の姿を見たら、「このホテル、よくないの?」と警戒するだろう。話しかけられたのをこれ幸いと、Mizumizuはホテルの部屋のボロさと値段の不当さを、さらに大声で日本語でまくしたてた。「ひどいホテルですよぉ! 予約してたのに、改装中の階の汚い部屋に通したんですよ。そちらはお部屋、どうでしたぁ?」「う~ん、まあ、きれいじゃないけど、シングルで9000円だから、安いし…」「私たちは、181ユーロも払ったんですよ! 安くないですよ。改装した部屋もあるのに、『いっぱい』とか言うんですよ。差別ですよ、差別! 日本人を差別してるんです! だいたい、こういうことって多いんですよ。日本人はおとなしいから…」フロントデスクの向こうをちらっと見ると、ナポリターノ金平は受話器を耳から少し離して、凍りついたようにこちらを見ている。悪い評判を立てられては困るというような顔だ。そして、ナポリターノ金平は、急に電話をおいて、「すいません」と、私がしゃべっているのをさえぎって、こちらに声をかけてきた。こっちが話してるのをさえぎって勝手に自分で電話に出たくせに、こっちが別の人としゃべりだしたらこの態度だ。「改装した部屋はないけど、眺めのいい部屋が1つ空いている。そこを案内させるから」どうやら、日本人のおじさん相手に、大声で悪口を言いふらしてる姿が相当効いたようだ。いい加減なようでいて、実はけっこう計算高い。イタリア人というのはそういうところがある。たとえば、彼らはよくお釣を間違える。だが、自分たちに不利なような間違え方(つまり、お釣を多くよこすこと)は決してしない。「今の部屋よりよければいい」と、Mizumizu。「じゃ、ポーターを」また同じポーターが呼ばれ、「眺めのいい部屋」に案内してくれた。ポーターがドアを開けてくれて、入ってみると…おお! なかなかいいじゃないの!角部屋だからなのか、明るいし、さっきの部屋より心なしか広い気がする。窓から港とベスビオ火山がバッチリ見える。額縁に入った風景画のようで、美しい。やっぱり、あるんじゃないの。「もっといい部屋」が。それなのに、最初はわざわざ、「さらに汚い部屋」を見せて諦めさせようなんて、敵ながら(敵だっけ?)あっぱれだよ、ナポリターノ金平君。この角部屋は誰のために空けておいたのだろう? Mizumizuたちよりウルサそうな、白人の宿泊客のため? こういうことがあると「ホテルの予約」というのも考えてしまう。ヨーロッパでは、よっぽどのシーズンでないかぎり、空室がないということはない。直接行って泊まるなら、決める前に部屋を見せてもらえる(日本では嫌がられるが、イタリアでは全然オッケーだ)。だから値段と実際の部屋を見比べることもできる。4つ星ぐらいまでだったら、この方法のがハズレがないかもしれない。ネットでみるきれいな部屋を信じて予約をしてしまったら、変な部屋に通されても(それが故意であれ、偶然であれ、仕方がないことであれ)、かえることができないこともある。部屋でちょっと休んだ後、さっそくナポリ見学に出かけた。フロントにはまだナポリターノ金平がいた。「部屋はずっといい。ありがとう」とお礼を述べて、鍵を預ける。「どういたしまして。ありがとう」したたかなナポリターノ金平も何事もなかったかのように、鍵を受け取った。日本に帰ってから「アップル」というホテル業者のサイトで、このホテルのユーザーレビューを開いてみたら、なんと! Mizumizuと同じ目に遭った男性の投稿が載っていた。「改装された部屋のキーはカード式。改装されていない部屋のキーはじゃらじゃら重い古い鍵。古い部屋に通され憤慨した。朝食のときに見たら、白人はほとんどカード式の鍵をもっていて、じゃらじゃら錘のさがった鍵をもっているのは日本人ばかりだった。チェックインのときに渡される鍵に注意」とあった。やっぱりそういうことか。とんだ「日本人冷遇ホテル」だったわけだ。先にこれを読んでおくべきだったなぁ。さらに、その後、「ホテルは改装が終わって全部カード式の鍵になりました。ご安心を」という投稿があった。たった今、このホテルの情報をみたら、ルネッサンスホテルグループに買収されたらしい。さらに値段は269ユーロになっていた(!)。そして、アップルからはエントリーが消えていた。269ユーロねぇ… あのホテルは確かに街中にあって便利だが、駅から行くには遠い。朝食のときは屋上のテラスで食べるので、それなりに雰囲気はある(だが、けっこう道路の音がうるさい)。高層階の角部屋からはベスビオ火山が見えて風光明媚だが、そういう部屋はわずかで、あとはそれほど部屋も広くないし、眺めもない。いくら内装をきれいにしたといっても、269ユーロじゃ、今のレートだと43,000円!。それじゃとても泊まる気にはなれない。ちなみにMizumizuがカード決済で払った日本円は20,996円。あのときは、「こんなホテル、それでも高いよ」と思ったのだが。ナポリではまずはケーブルカーに乗ってヴォメオの丘へ。サン・マルティーノ博物館を訪ねる。広い館内は喧騒の「下界」とは別世界の静寂に包まれていた。ナポリは下町にも見所はいっぱいだ。写真はサンタ・キアーラ教会の回廊。さすがに、フレスコ画の風格は南ドイツの田舎の村のチンケ(失礼!)な壁画とレベルが違う。ヴォールト天井までびっしりと装飾が施されている。さすが、ギリシア時代から2000年の長きにわたり、ヨーロッパ列強のさまざまな権力に愛された街だけのことはある。これまでなんだって、南ドイツのチンケな(失礼!)壁画を一生懸命写真に撮っていたんだろう、とちょっとガックリする。イタリアの文化レベルは、その歴史の長さにおいても、量や質においても、やはりアルプスの北とは違う。
2007.10.26
-

アマルフィからナポリへ
アマルフィで2泊して、いったんナポリへ戻った。なぜインスブルックからナポリに着いたのに、ナポリを素通りしてアマルフィに来たのか、逆に言えばなぜアマルフィに行ってからまたわざわざナポリに戻ったのかといえば、それはバレエとオペラが見たかったからだ。ちょうどアマルフィで2泊して戻れば、2日連続でバロックオペラ「アマディージ(Amadigi)」とモダンバレエ「デューク・エリントン」が見られる日程があった。それでわざわざいったんアマルフィに行き(そこで2日連続で公演がある日にナポリにいけるよう調整し)、それからナポリに戻って、今度はナポリから船でソレントに行き、サンタ・アガタにあるミシュランの星つきリストランテ「ドン・アルフォンゾ」に行くという、ちょっと変則的なスケジュールを組んだ。特にバロックオペラは見たかった。今もそうだが、日本ではバロックオペラの公演機会は非常に少ない。バロックオペラの巨匠ヘンデルの「リナルド」がやっとこさ全幕公演されたのがほんの数年前。バロックの残り香の漂うモーツァルトの初期のオペラ「イドメネオ」をようやく初台の新国立劇場で見ることができたばかりだ。ヘンデルの「リナルド」などといっても、「知らない」と思われるかもしれない。だが、おそらく、「私を泣かせてください」なら聞いたことがあるのではないだろうか?NHKのドラマで使われて、広く認知されるようになった曲だ。サラ・ブライトマンの歌唱が以下。↓http://www.youtube.com/watch?v=6e1mfAGka9E&mode=related&search=(以下、といわれても、どうしていいのかわからない超初心者の方へ説明すると、上に並んでる英数字の羅列をまるごとコピーする。そして、それをグーグルやヤフーなどの検索エンジンの検索する語の欄にペーストする。そしてクリック。するとサラブライトンが歌う場面が出てくるハズ)。聞いてみれば、「ああ、これね」とわかると思う。この「私を泣かせてください」は実はオペラ「リナルド」のアリアなのだ。「アマディージ」は「リナルド」よりさらにマイナーだから、日本での公演はほとんど期待できない。だが、「私を泣かせてください」に勝るとも劣らないアリアがある。↓こちらの7番をクリックして視聴をどうぞ。残念ながらいわゆる「サビ」に入る前に視聴は終わってしまうが、チェンバロとオーボエの美しい響きは垣間見れると思う。http://www.amazon.com/gp/recsradio/radio/B00000JMH2/ref=pd_krex_listen_dp_img/103-3869664-9003006?ie=UTF8&refTagSuffix=dp_imgそれに、バロックオペラは多少現代人には退屈かもしれないが、カストラート役をアルトの女性がこなし、ちょっとした宝塚チックな世界になるし、時代がかったコテコテの舞台衣装も楽しみのひとつだ。アマルフィを12:10に出発してナポリに着くのが14:10。2時間も乗るのに、プルマン(長距離バス)の片道の値段はたったの3.15ユーロ! 例によって狭い半島の道を行き、ベスビオ火山の麓をまわるようにしてナポリに入る。バスの旅も列車とは違う、街中の風景が見られて楽しい。ナポリは都会だった。ごちゃごちゃの街並みは、一見東京のようかもしれない。クルマも多い。だが街中に信号は少ない。一方通行が多く、地元民以外にはわかりにくいルールの中でクルマが動いているようだった。さて、ナポリのホテルでは、またもひと悶着あった。
2007.10.25
-

アマルフィ、Hotel Cappucciniのtavola事件
<きのうから続く>部屋の窓からはエレベータが見える。しばらくすると、分厚い「板」をもったポーターが急いでやってくる姿が見えた。そして、ドアがノックされた。「Tavola、持って来ました」 ――はああ?? ポーターが持っているのは、まるっきりベッドのカタチに合った長方形の厚い「板」だった。たしかに、tavolaには板の意味もある。その板は、なんというか、本当にタダの板だ。ホームセンターに行って、タテ・ヨコのサイズを指定して切ってもらった… みたいな。しかも、マジでベッドにピタリとはまる。要するにここのベッドに合わせて切った板なのだ。 ポーターはベッドのマットレスをいったんとって、tavolaをベッドに置く。そしてまた、マットレスをのせて、「これで、どう?」慣れた手つきだった。相当あきれながらも、ベッドに横になってみる。確かに硬い板が下に入ったから、多少寝心地は硬めになった。だが、よくなったかどうか?「ちょっと、もう一度板(tavola)をとってみて」 ポーターに頼むと、嫌がらずにやってくれた。う~ん…、確かに板があったほうが、多少はいい、ような気がしないでもない。 しかし、いくらなんでも、スプリングがいかれたボロなベッドに、板を敷いてごまかすとは、ひどすぎる。再度フロントのねーちゃんに電話する。「板があっても、快適じゃない。ほかの部屋を見せてほしい」 すると、どうやら、意地でもほかの部屋を見せたくないらしいねーちゃん、言い訳を始める。「お客様、このホテルはすべてがアンティークでございまして…」アンティークぅうう? その一言で、完全にキレた。「このベッドはアンティークじゃない。ただの古すぎるベッドでしょ! ふ・る・す・ぎ・る!! ここはペンションじゃなくて、4つ星ホテルなんじゃないの?」 電話口でまくしたてるMizumizu。ねーちゃんは、オタオタしながら、「ベッドはすべて同じです。ほかの部屋はそこより狭くて、快適じゃないから…」 つまり、これは言ってもムダだということらしい。しかたないので、tavolaを敷いたアンティークベッド(本当はただのボロいベッド)で我慢することにした。 出かけるときに、別の部屋のドアがたまたま開いていた。ちらっと見ると、本当に狭くて暗い! びっくりした。団体客には「古い修道院ですから」なんて言ってあの狭くて暗い部屋に押しこめるのだろう。そのかわりダンピングして。 たしかに、Mizumizuたちの部屋はいい部屋だった。それは間違いない。だが、調度品も「アンティーク」というより「ただ古くてボロな家具」という感じだった。ワードローブはまともにドアが閉まらない(下の写真の向かって左奥の鏡付き)。ネットの写真で見たときはわからなかった。部屋の雰囲気や調度品だってLunaと遜色なく見えたほどだったのに、実際はえらい違いだ。なるほど、同じ4つ星といっても値段が違うのは、こういうことだったのか。 ホテルの中にもホテル内を移動するためのエレベータがあるのだが、これがまた、えらく「アンティーク」。身の危険を感じたのか、多くの客がエレベータを避けて階段を使っていた。あの年代モノのエレベータで事故でも起きたらどうするのだろう。そのうちワイヤーが切れるんじゃいか。 ホテルは幹線道路を通らずにアマルフィの街に行けるようになっている。その通路からアマルフィの中心街を見たところ。そちらから出るとき、業者がやってきて、「Frozen Seafood」と思いっきり書かれた冷たそうなダンボールをバーンと階段に放り出すのを目撃した。なるほど、海沿いのホテルのくせに、こういう冷凍の魚を出して、「新鮮なシーフード」だとか言うワケね。ま、日本だって、「赤福」の例をみるまでもなく、あまりえらそうなことはいえない状況だけれど。 ここのホテルでディナーを予約したのを心底後悔した。夜、レストランの雰囲気はさすが古い修道院を改築しただけあって、よかったのだが、味はダメ。きのうのLunaとはまったくレベルが違う。出されたワインも、スーパーで一番安く売られているテーブルワインだった。 朝食もひどいものだった。ほとんどパンとコーヒーだけ。ウェイターが銀の丸いフタ付きの容器をうやうやしく持って来るので、何かと思ったら、なんと、これもスーパーで10包み1ユーロぐらいで売られているお安いバターだった。こんな銀包みの給食みたいなバターを、銀メッキの容器に入れて、いかにも高級に見せようなんて、愚かにもホドがある。あまりのプアーな朝食に、「もしかして、どこかに何か別の食べ物があるのかな?」と思って、テーブルを立ってみた。なにせ、広さだけは結構あるレストランなのだ。 年取ったウェイターが、寄ってきた。「なにか?」「他に食べるものはないの? フルーツは?」 すると、ウェイターのおじいさんはすまなそうに、「ないんです。フルーツは… あるけど、エキストラになるし…」 こういうホテルの従業員は本当に気の毒だ。あらかじめ「板」があつらえてあるところを見ても、ベッドにクレームする客は珍しくないのだろう。フルーツもヨーグルトも野菜もない朝食に驚く客も1人や2人ではないはずだ。 にもかかわらず、ベッドそのものを新調しようともせず、「板」で押し通し、何もない朝食にバターの入れ物だけフタ付き銀メッキを使ってごまかそうとする。 これで4つ星といえるのだろうか? 本当にひどいオーナーだ。そして、客に怒られて嫌な思いをするのはオーナーではなく、働いている従業員なのだ。海岸沿いの道路に聳え立つ専用のエレベータと、山の中腹にゆったりと広がる雰囲気のある建物と気持ちのよさそうなテラスを外から見ただけでは、この内情は想像もできない。 例のねーちゃんは翌朝もフロントにいたが、Mizumizuの姿を見ると、ぱっと奥に逃げていった。まるでいつもいじめられてばかりいる野良猫が人影を見たときのようにすばやかった。 これは多少古い情報だ。だから今はこのホテルも変わったかもしれない。だが、アマルフィで修道院を改築して作ったホテルに泊まるなら、多少高くてもHotel Lunaをお奨めする。 ちなみに、このHotel Cappucciniのtavola事件は、Mizumizuの海外旅行におけるクレーム史においても、その奇抜さとあきれ具合において、いまだ頂点に君臨している。
2007.10.24
-

Hotel Cappucciniのtavola事件
アマルフィでは2泊した。そして、最初から2泊目にはホテルを替える計画だった。というのは、Hotel Lunaと同じ4つ星で同じように魅力的に見えるホテルがアマルフィにはもう1つあったからだ。そのもう1つのホテルが、Hotel Cappuccini。やはり古い修道院を改築してホテルにしたもので、海岸沿いから垂直のエレベータ(これはホテル専用だ)であがる崖の中腹にあり、規模はこちらのほうが大きい感じだった。宿泊費はLuna が217ユーロ、Cappucciniが198ユーロ。写真で見る限りはどちらも甲乙つけがたいホテルのよう(に見えた)。狭い街で2泊するのにホテルを替えるのも面倒かな、とは思ったが、両方のホテルを味わってみたい気持ちが強く1泊目はLuna、2泊目はCappucciniで日本からネットで予約。LunaからCappucciniまでは荷物もあるのでタクシーを利用した。垂直の専用エレベータであがる。第一印象は悪くはなかった。ただ、Lunaのほうが全体的に手入れが行き届いており、調度品もよりエレガントである気はした。予約してあったので、海のみえる角部屋に通される。部屋は広く眺めもよかった。案内してくれたねーちゃんが引っ込んで、ゆったりしようとベッドに横たわって、驚いた! ギシギシのオンボロベッドだ。安いスプリングマットレスが古くなったときに出る、あの嫌な音。スプリングがいかれているから、体も変に沈み込む。これはひどい。今からなら部屋を替えてもらえるはず。さっそくフロントに電話すると、部屋に案内してくれた彼女が電話に出る。「この部屋のベッドは非常に悪い。変な音がするし、柔らかすぎる。部屋を替えることはできますか?」ねーちゃんは、困ったように、「その部屋が一番いい部屋なんだけど」と言う。「空いてる部屋を見せてもらえますか?」「うーん」と、ねーちゃん。ちょっと変だ。イタリアでは、こういう場合、たいがいは別の部屋も見せてくれる。嫌な顔はされたことがない。ヨーロッパのホテルというのは、本当に部屋によって雰囲気や気分が変わる(しかも値段は変わらないことも多い)から、要注意なのだ。それなのに、妙に口ごもっている。見せたくない理由があるような感じだ。「要するに、ベッドが問題なんですね?」「そう」「ベッドだけ?」「そう、眺めはいいし、部屋は広いから、何も問題なし」「じゃあ、ちょっと待っていて。Tavolaを持っていかせますから」 そういって、電話は切れた。――た、tavola???狐につままれたような気分になった。Tavolaとは普通、「テーブル」のことだ。ベッドの話をしているのに、なんでテーブルを持っていくなどと言うのだろう?<オドロキの真相は明日をお待ちください>
2007.10.23
-

アマルフィの色
アマルフィのドゥーモ付属の回廊、「天国のキオストロ(13世紀)」。入場料は5ユーロだった(今はいくらぐらいだろう?)。シチリアのパレルモ近郊の街、モンレアーレにもドゥオモの隣に僧院の回廊(12世紀)がある。この2つはそっくりといえばそっくりだが、モンレアーレのほうはアマルフィにはない華やかで精緻なモザイクが柱に施されているし、そもそも列柱そのもの美しさが格段に違う。アマルフィはずいぶん質素だ。当然といえば当然かもしれない。モンレアーレは(両)シチリア王国の中心地、国王のお膝元だったのだから。アマルフィの「天国のキオストロ」を実際に見て、(両)シチリア王国の空前絶後の繁栄ぶりをあらためて実感した。Dal Chiostro del Paradisoそれからバスでエメラルドの洞窟へ行った(バス代片道0.93ユーロ)。写真は洞窟の入り口の上で撮ったもの。レモンと唐辛子はこのあたりの店先で大量に売られている。レモンの黄色、唐辛子の赤、そして海の青… アマルフィの色だ。Rosso e giallo, i colori di Amalfiエメラルドの洞窟は、本当に透明な水がエメラルドグリーンに輝いていた。船では芝居っけたっぷりの船頭さんの「語り」に笑った。人面石を指して「あれはガリバルディにそっくり。だがイギリス人はルーズベルトだという」などというので、「じゃ、日本人は?」と聞くと、「ナカ~タ」とおごそかに答えていた。船をおりるときまで、「節」をつけて「ゆぅっくり、ゆぅっくり」と半ば歌いながら、乗客に手を貸す。あれを毎日やっているのかな?カプリの青の洞窟よりこちらのほうがきれいだという人もいるが、どうだろうか。個人的にはカプリのほうがインパクトが強かったが。ただ、どちらもあまりに観光地化しすぎている。金の成る木ならぬ金の成る洞窟だから、これも美しすぎる自然の運命なのかもしれないが。エメラルドの洞窟を見たあとは、山の上にあるラベッロへ行った。行きは適当なバスがなかった(あれば30分で着く)ので、タクシーを利用。20ユーロ。ホントに、バス代とタクシー代の落差には驚く。タクシーはオンボロも多く、たいして快適ではない。逆にバスはそれほど混まないし、超オンボロということもなく案外快適だったりする。ラベッロは標高約350メートル。「この先に本当に町があるの?」というような九十九折の細い山道を行く。見所の1つ「チンブローネ荘(4.5ユーロ)」では藤の花が満開だった(4月中旬)。チンブローネ荘のテラスから見下ろすアマルフィ海岸は絶景そのものだ。Ravello, fra cielo e mare…帰りはあらかじめ確認しておいたバスの時間に合わせて、バスでアマルフィまでおりてきた。この町の眺めのよいホテルで一泊してもよかったかもしれない。夏だったら、海の見えるテラスで、キャンドルの灯りとともに味わう、遅い夕暮れどきのディナーは最高だろう。そういう需要に応える高級ホテルもいくつかある。
2007.10.22
-

アマルフィに吹く風
今、NHKの木曜時代劇(8時オンエア)で藤沢周平の「風の果て」をやっている。これは後に異例の出世を遂げる下級武士の次男が主人公だが、先日放映された第一回で、主人公同様下級武士の次男や三男である道場仲間がさかんに自分の婿入り先を気にする会話が出てきた。家督を継ぐことができない彼らにとっての先の希望と関心は、できるだけよい婿入り先を探すことに集中している。封建的土地所有の方式、すなわち世襲的な保有地の長子相続が固定化した社会では、常に嫡男以外の男子の生計基盤は不安定なものになる。「風の果て」もそうした封建時代の話だが、昨日書いたロベール・ギスカールとルッジェーロ1世兄弟のノルマンディーにおける立場もほとんど同じだった。ノルマンディーでは11世紀にはすでに封建的な領主の長子土地相続が慣行が浸透し、ロベールもルッジェーロも自分の父親の小領地以外に食いブチを探す必要があった。ただ彼らが進んだのは婿としての人生ではなく、傭兵としての人生だった。ノルマンディーだけではない。ヨーロッパ領主貴族層には、こうした次男以下の領主の子弟の「冒険的さすらい」が多く見られる。彼らはやがて十字軍の中に吸収されていくことになる。こうした「冒険的さすらい」はほとんど平凡に終わるか、悲劇に終わるかだった。ただ、ロベールとルッジェーロのオートヴィル家の兄弟の場合は違った。始まりはロベールの異母兄、鉄腕アトム… じゃない鉄腕グリエルモの南イタリアでの成功であり、それからロベールとルッジェーロの南イタリアの実質支配へと続く。そして、その子供の代でついにシチリアを含む南イタリア一帯にノルマン王朝が成立するのだ。オートヴィル家の領地はノルマンディーのさびれた田舎の村だ。その小領主の息子たちがさまざまな小さな勢力が互いに争いあっていた南イタリアに赴き、1つの王国にまとめあげた。それこそ「異例中の超異例」の一大出世物語だといえるだろう。群雄割拠の時代から、より強大な勢力による統一の時代へという歴史の転換期は西洋でも東洋でも見られる。ノルマンディーの青年たちは南イタリアにおけるそうした歴史の転換点に居合わせ、時代の大きな波に乗ったのだ。そして、その歴史の波の中に沈んでいったのが、独立した小勢力のせめぎ合いの時代にうまく立ち回って繁栄を築いた小さな中世都市アマルフィだった。アマルフィの経済の基盤は交易にあり、サラセンやビザンチンなどを含めた地中海の広い範囲の海洋貿易で繁栄する。そのコスモポリタンなアマルフィ繁栄の歴史は、街に残る異国情緒豊かな建築や装飾の中に見ることができる。Il Duomo di Amalfi, ricordo di vento dall'estアマルフィのドゥーモ。ファサードに吹く風は、ビザンチンとサラセンからのものだ。黄金に輝く破風はビザンチン様式、アーチを備えた列柱はサラセン様式にほかならない。今日のホテルは「Hotel Luna」。13世紀に建てられた修道院を改築した名門ホテルで、ワーグナーも滞在したことがあるという。このホテルはシェフも有名だ。La romantica camera dell'Hotel Luna; l'atomosfera arabica青い色調のタイルのひんやりとした床。白い漆喰の壁にアーチ型にくり貫かれたニッチ。窓の外には青い海が広がっている。部屋は広くはないが(アマルフィのように平地の少ない場所では、ある程度仕方がない)サラセン風にロマンチック。サラセンとは、ほぼアラブと同義語だと思っていい。この地域はサラセン人と密接な関係をもっていた時代がある。ロベールがローマに進軍したときにはサラセン人も軍隊に混じっていた。中世の時代、ソレント半島の都市(コムーネ)は他の都市(コムーネ)と対立したときに、しばしば外部勢力であるサラセン人を味方に引き入れて自分たちの政治勢力の維持に利用した。La Torre Saracena, che una volta fu il posto militare per scoprire nemici sul mare.Oggi turisti si divertono a mangiare quiサラセンの塔。昔は海から来る敵を見張るための塔だった。今はレストランに改築されていて観光客が海を眺めながら南イタリア料理に舌鼓をうつ。Mizumizuたちもここでランチ。久々に本場イタリアのパスタを食べた。ドイツ語圏のパスタはたいてい茹ですぎてぐにゃぐにゃなのだが、イタリアはやはり違う。まだ頭がドイツ語からイタリア語に切り替わらず、「どこから来たの?」を聞かれて、思わず「Aus Deutschland」などとドイツ語で答えてしまう。このレストラン、ホテル・ルナの併設のようになっているのだが、あとでディナーをホテル・ルナ内のレストランでとったところ、そっちのシェフのほうがよっぽど腕がいいとわかった。ガーン! 実はランチでしこたま食べ過ぎて、そのおいしいディナーはプリモ(第一の皿)で力尽き、セコンド(第二の皿)まで完食できなかったのだ! ああ、なんとおろかなことをしたのであろうか!! Mizumizuは今でも後悔している(笑)。
2007.10.21
-

ノルマンディーとサレルノの意外な関係?
ブレンネル峠を越えるとイタリアだ。フォルテッツァに着くと、「ああ~、ここで鉄道を乗り換えてドッビアーコに行ったことがあったなぁ」と過去の旅行の記憶がよみがえる。それから夜行列車はボルツァーノに停まる。ここからコルティナまでバスで行ったこともあった。次の停車駅はトレント。トレントからはマドンナ・ディ・カンピーリオにも行ったけ…そんなことを考えながら、ヴェローナに着く前には寝てしまった。眼が覚めると、窓の向こうは暖かな光に満ちていた。ナポリに近づいたころ、車掌が起こしにやってきてドアをノックした。それはいいのだが、ノックのあと、ドアを開けるタイミングが早すぎる。連れが着替え中なのに… あれって、ワザとかも(苦笑)。ナポリ駅で車両からおりる際、車掌はうやうやしく(?)手を貸してくれた。やはり、外は暖かい。 インスブルックとはえらい違いだ。ナポリ駅ですぐに、さらに南下すべく乗り換えた。南の明るい日差しのもと、ナポリからサレルノに向けて電車は進む。サレルノには「カノッサの屈辱(1077年)」で神聖ローマ皇帝ハインリッヒ4世を破門した教皇グレゴリウス7世の墓がある。なぜ皇帝に屈辱を与えるほど強大な権力を誇ったはずのローマ教皇の墓がこんなところにあるかというと、実は「カノッサの屈辱」には後日談があるのだ。教皇に許しを請うという屈辱を味わった皇帝ハインリッヒは、破門をとかれると、祖国で巻き返しを図る。そして大軍を率いて南下、教皇グレゴリウスをローマのサンタンジェロ城に追い詰める。そのときに教皇が保護を求めたのが当時サレルノを含めた南イタリアを実質支配していたロベール・ギスカール(ロベール・ギスカルド)だったのだ。ロベール・ギスカールはイタリアの人間ではない。フランスのノルマンディー(オートヴィル村)出身のいわゆるノルマン人(バイキングの子孫)で、先に南イタリアに傭兵としてやってきて頭角を現し、「鉄腕」と畏れられた異母兄グリエルモを追うように、わずかな部下とともに南イタリアにやってきた。グリエルモの死後、独力でライバルたちを退けたロベールは、やがて南イタリア全域に武力で支配を広げる。ギスカールとはあだ名で「狡猾な」という意味だ。その過程で教皇グレゴリウスの領地を脅かすようになったロベールは、皇帝ハインリッヒ同様に破門されている。神聖ローマ皇帝のハインリッヒは教皇に破門されたことで政治的な打撃をこうむり、わざわざイタリアに出向いて許しを請うハメに陥ったのだが(これが現代の日本人でも一度は聞いたことがあるであろう「カノッサの屈辱」だ)、ロベール・ギスカールは破門されたのちも精力的に南イタリア各地の征服を進める。それは一方では、ノルマン人によるサラセン(アラブ・イスラム教徒)やビザンチン勢力(名目上東ローマ帝国に属する諸侯)の駆逐という側面ももっており、後の南イタリアにおけるノルマン王朝成立の礎ともなっていく。一方、巻き返しを図ってきた北の皇帝ハインリッヒとの確執が再燃した教皇は、南イタリアにおけるロベールの支配地域が広がるにつれ、今度は逆にロベールの軍事力に頼らざるをえなくなる。そして、教皇グレゴリウスが南下してきたハインリッヒの大軍に包囲されると、ロベールはグレゴリウスの援軍としてローマに向かう。いったんはローマを掌握したハンリッヒ軍だったが、ロベール軍の接近を知って撤退。ロベールはグレゴリウスをローマから救出し、ナポリの南、ソレント半島の付け根にある自らの支配地、サレルノに保護するのだ(1084年)。ロベールはその後すぐにビザンチン(ギリシア)に兵を進め、翌年病死。そのほんの2ヶ月前にはグレゴリウスもサレルノで憤死している。サレルノで電車をおりたMizumizuは、ここからバスに乗り、ソレント半島のアマルフィに向かった。所要時間は1時間半ほど(道が狭いから混むとえらく時間がかかることも。ちょうど東京から伊豆へ行く道を想像してほしい)。バス代は1.65ユーロ。イタリアの公共交通機関ってビックリするほど安いなあ。タクシーは高いけど。歴史の視点をサレルノからソレント半島に移すと、この半島の海に面した狭い土地に成立した街は、中世のある時代には、独立した都市(コムーネ、もともとは共同体という意味)として海洋交易で栄えていた。アマルフィに関して言えば、9世紀あたりから繁栄が始まり、アマルフィ共和国が樹立。そして国際的に長く影響力をもつことになる海洋法を成立させ、11世紀に入ると絶頂期をむかえ、一時ベネチアやジェノバと地中海覇権を争うまでになる。だが、11世紀後半のノルマン人ロベールの登場をきっかけに、その独立と繁栄に影がさしはじめる。1073年にロベールがアマルフィを支配下におくが、このときはまだ多くの自治権が認められていた。しかし、1130年に(両)シチリア王国が成立し、1131年に同国に征服されると、さまざまな政治的権利が剥奪されてしまう。その(両)シチリア国王の初代の国王がノルマン人ルッジェーロ2世。ルッジェーロ2世はロベールの弟の子供、つまり甥にあたる人物だった。なぜ(両)シチリア王国の初代の王なのに「2世」なのかといえば、それは単に彼の父親、すなわちローベルの弟も名前がルッジェーロだったからだ。こちらは「王」にはならなかったが、ルッジェーロ1世として南イタリアの歴史にその名を残している。(両)シチリア王国の一部になったアマルフィに共和国時代の輝きをが戻ることはなかった。他国(ピサ)からの侵略と略奪にさらされ、やがて14世紀には大きな自然災害で壊滅的な打撃を受け、歴史の表舞台から姿を消す。つまりアマルフィは、中世に興り、中世に繁栄し、中世が終わる前に終焉を迎えた、純粋なる中世都市なのだ。長く忘れられていた断崖絶壁の海岸沿いにある不便な狭い古い街。そこが今では中世文化のタイプカプセルとして脚光を浴びている。半島の海沿いの狭いバスを大型のバスが行く。カーブに差し掛かると大きくクラクションをならす。2車線しかない道路、そこの対向車線もいっぱいに使わないとバスは曲がれないからだ。運転手はカーブのたびに思い切りハンドルを切っている。一歩間違えば崖から海にまっさかさまだ。神経使うだろうなぁ。でもイタリア人のドライバーってクルマこすっても結構平気(きれいなクルマで来てるのはたいがいドイツ人)だから、日本人とはちょっと感覚は違うかもしれない。グネグネの道を1時間半。ようやくアマルフィが見えてきた!
2007.10.20
-

ミッテンバルトでも壁画
Il villaggio dove vive la gente religiosa信仰の村、オーバーアマガウを17時に出て、ミッテンバルトについたのは19時前。雨が降っている。晴れていれば険しい山に囲まれた慎ましやかな町の雰囲気が堪能できたのだろうけれど、山はまったく見えない。明日はインスブルックへ抜ける。南ドイツの壁画ともこれでさようならだ。Mittenwald - "Museo?" "No, e' la banca."旅したのは4月だったけれど、日本でいうとまだ冬のような天気になってしまった。そのせいか、ミッテンバルトはあまり印象に残っていない。ホテルで一泊して、翌朝12時ちょっと前に電車に乗る。インスブルックには午後1時前に着いた。電車代は2等片道12.4ユーロ。「インスブルックもきれいな街だよ~」と友人に言われてきたのだが、あいにくここでも天気が悪かった。山も見えないし、傘をさして旧市街の見所を見てまわったが、ウィーンやザルツブルクを過去すでに見て、オーストリア風の都市はかなり飽きがきていたのか、またもそれほどの感動がなく終わった。Innsbruck in aprile; ma faceva freddo come inverno!レストランガイド「ゴー・ミヨ」で点数の高かったレストランでディナーをとったのだが、これまた見事にハズレ。魚料理を薦められて、それにしたのがマズかったかな? 日本人は魚好き、という印象がとても強いようだった。ちょっと違うと思う。日本人が好きなのは「おいしい魚」なのだ。日本の魚料理の多彩さは内陸国のオーストリアでは想像つかないかもしれない。はやく食事のウマいイタリアに抜けたい、という気持ちがますます強くなった。冬に逆戻りしたような冷たい雨が降っていてはなおさらだ。インスブルックでは泊まらずに、22:41発の寝台車でナポリへ向かうのだ。ナポリはきっともっとずっと暖かく、天気もいいだろう。ところで、この寝台車、実は日本からネットで予約したのだ。てっきり、カードを見せて現地で切符をもらうのだと思っていたのだが、な、なんと現地から切符が日本まで送られてきた! びっくりしたな~、もう。万が一、着かなかったらどうしてくれたんだろう?夜はホテルのバーで時間をつぶし、22:30にホームへ。電車ははやめに着いた。えらく長~い列車でびっくり。窓から顔を出している乗務員がいたので、チケットを見せて、「車両はどこ?」と聞いたら、後ろのほうを指差す。それを信じて後ろのほうへ車両番号を見ながら歩いていったのだが、全然ない! とうとう最後尾まで行ってようやく、いいかげんなことを教えられたことがはっきりする。あわてて今度は前のほうへ走る。荷物があるから大変だ。連れはかなりアセって、「どこでもいいから、とにかく乗ろうよ」と言う。ヨーロッパの列車が(日本人から見ると)「黙って」発車してしまうのを心配しているのだ。だが、これはアブナイ行為だ。ヨーロッパの列車は、車両から車両に移れないものがある。うっかり違う車両に乗ってしまったら、長い距離を走る国際列車の次の駅までまってまた正しい車両に乗り換えなくてはいけない。夜行の場合は、寝台車両とクシェット車両と普通の座席車両があるから、やはりきちんと自分の車両に乗らないとあとで困ったことになる。長~い列車の端から端まで(つまりは、長~いホームの端から端まで)走った感じだ。ようやく寝台車両を見つけて乗り込んだ。乗り込んで数分後に扉が閉まって出発。電車はわりあい余裕をもって着くから、迷っても案外「乗り遅れる」ということはない。個室に入り、ラクな寝巻きに着替えて寝台に横になるとホームでのあせった気分もすっかり飛んで、くつろいだ気分になった。オレンジに照らされた夜のホームを国際列車は静かに滑り出した。途中でスピードが落ちてきた。ブレンネル峠を越えるのだ。窓からのぞいたら、モミの木は雪をかぶっていた。峠では季節は完全に冬に逆戻りしていた。
2007.10.19
-

オーバーアマガウとリンダーホーフ城
フュッセンを拠点にノイシュバンシュタインを見たあとは、オーバーアマガウとリンダーホーフ城をみて、その日のうちにミッテンバルトへ抜ける計画だった。朝8時に鉄道でフュッセンを出発。1度乗り換えて1時間半ちょっとでオーバーアマガウの駅につく。宗教劇で有名な村だが、思った以上に田舎だ。駅で荷物を預けられるところを探したが、見つからない(本当はホームの入り口にコインロッカーがあったのだが、気づかなかった)。オーバーアマガウからバスでリンダーホーフ城まで行くつもりだったので、ちょっとアセる。個人旅行は「自分で荷物を持って歩かなければいけない」というのが最大のネックなのだ。この日のように、どこかを見学をして別の町のホテルまで移動するという場合が一番困る。泊まるホテルに置いていくということができない。リンダーホーフのあたりに荷物を預ける場所があるとは思えない。城や庭園を見て歩くのに、こんなものを持っていくのは大変すぎる。同じような日本人の男性がいて、「コインロッカーないですね」と話しかけてきた。「ホントに…」と答えて、ふとみると駅のすぐ横にカフェがある。田舎なんで人が親切かも… とアタリ(?)をつけたMizumizuはさっそく、開店直前のカフェにはいって、マスターに交渉開始!「今ここに着いて、リンダーホーフをみて、夕方には戻ってくるんだけど、この荷物を預けられるところが見つからない。よければ預かってもらえませんか? 貴重品は何も入ってないから」床掃除をしていた、素朴で実直そうなマスターは、快く「Ja!」。店舗の裏のスペースを指差して、「そこなら置いていっていいよ」。ラッキー! さすが信仰の村。親切だなぁ。案外こういうことを頼んでくる観光客は珍しくないのかもしれない。さっそく置かせてもらってバス停に行くと、さっきの日本人男性もリンダーホーフ行きのバスを待っている。「あれ? 荷物は?」 と聞くので、「そこのカフェで預かってもらっちゃいました」 こういうとき、日本人のオバチャンだと、あつかましく「私のも頼んでぇ」などと言ってくることが多い。中には「こういうところで荷物って預かってもらえるんだ~」などと勘違いする人もいる。とんでもないことだ。荷物預かり所でないかぎり、交渉してみなければわからない。「ダメ」と言われることも、もちろんある。それに下手に頼んで、荷物がなくなっても文句はいえない。が、さすがシャイな日本男児、「へええ」と感心したようにつぶやいただけで、自分の荷物を預けに行くようなことも、こちらに通訳を頼むようなこともしなかった。リンダーホーフ城行きのバスが来て乗り込む。オーバーアマガウだって相当の田舎だが、そこからまた人里離れた山へ分け入っていく感じ。さすがバイエルンの狂王、ルードヴィッヒ。辺鄙なところに城を作ってくれたこと。「ヴェルサイユ宮殿内のトリアノンを模して作った」リンダーホーフは、こじんまりとまとまっていて、案外よかった。やはり山に囲まれた清涼な空気がすばらしい。ヴィスコンティの映画「ルードヴィッヒ」では、月明かりの夜、雪の積もったリンダーホーフに馬車が到着する冷たくも美しいシーンがあるが、実際のリンダーホーフは白昼の明るい光の中でみると、ハリボテ感が強調されてしまう。この「やっぱりどこか安っぽい城」をあれだけ幻想的に撮れるヴィスコンティはさすがだと思ったりした。ところで、例の日本男児は、バスをおりてからも、コロつきのソフトケースをひきずってリンダーホーフ城まで歩いてきた。城に入ったところで、係員から何事か言われ、別室を指差されている。「あっちの部屋で預かるから」というような話をしてるらしい。ところが、この日本男児、よっぱど警戒してるのか、はたまた迷惑をかけると思ったのか、手を振って断っているではないか。オイオイ、小国バイエルンのヘンな王様の小さな城とはいえ、文化遺産の中をみて歩くのに、コロをひきずって、何かをキズつけたら大変じゃないか。預けなさいよ、と思ったのだが、さすがにそこまでしゃしゃり出るわけにもいかず、成り行きをみていた。案の定、城の最初の居室に入ったところで、再度係員がやってきて、今度は強い調子で荷物を預けるよう指示する。ようやく納得した日本男児が荷物を手ばなしてくれて、Mizumizuとしてもヒヤヒヤせずに見学ができたというワケ。日本男児は城の見学を終えたところで荷物を返されていた。Mizumizuたちは手ぶらなのでゆっくりと庭園を見て歩くことができた。駅の横のカフェのマスター、ありがとう!帰りはバスでオーバーアマガウの町(駅の少し手前)でおり、そこで家屋の壁画などを見ながらぶらぶらと駅まで歩いた。オーバーアマガウもちょっと壁画で有名なのだ。Oberammergau - Il mondo della fantasia sull'esterno muro di casaこれは「赤ずきんちゃん」をモチーフにした壁画。宗教画が多いのだが、たまにこのようにメルヘンチックなモチーフもある。美術品としてどうこうと言うつもりはないが、案外よく描けている。こういうの、日本でも村おこしでやったらどうかな。夕方、駅のそばのカフェに戻り、お礼を言って多少のチップを払い、そのまま鉄道で、ムルナウ乗り換えでミッテンバルトへ向かった。本当はカフェのおじさんにはもっと感謝の念を伝えたかったのだが、とてもシャイなおじさんで、すぐ向こうを向いてしまい、あまり話ができなかった。これがイタリア人相手なら、オーバーにお礼をまくしたてて、向こうもノってニコニコするような場面なのだが… う~ん、やはりつつましくもまじめな信仰の村の村人であった。
2007.10.18
-

ヴィース教会、ロココ教会の最高峰、ではあるけれど・・・
世界遺産にしてロココ教会建築の最高傑作の呼び声も高い「ヴィース教会」。これもまた個人旅行者にはきわめて不便な場所にある。ロココ様式は実はあまり好みではないのだが、ロマンチック街道に来たからには、やはり世界遺産を見ておかねば… という変な義務感に駆られて行ってみた。行きはショーンガウからバスで(3.55ユーロ)。帰りはバス便が不便なので、タクシーを呼んでもらってフュッセンまで(32ユーロ)。ヴィース教会は確かにロココ風な豪華さにあふれていた。白と金の華やかな色づかい、軽やかな天使の舞うフレスコ画。確かにロココ様式の教会としては、すぐれた建築なんだろう。でも、ロココの教会って、そもそもそんなに数あったっけか? 「ワタクシはフランスのじょお~なのです」の宝塚… いや、マリー・アントワネットに代表される少女趣味・貴族趣味の極致がロココ様式というイメージで、あまり教会装飾にはふさわしくない気がする。しかも、パリでもベルサイユでもなく、周りには牛しかいないような、こんな辺鄙な場所になぜここまで豪華絢爛な巡礼教会を建てようと思ったのだろう…?もちろん、それはフランスを中心とした貴族社会のサロン文化への憧憬からだろう。ときに本家に憧れる誰かが本家以上のものを作ってしまうことがある。その典型だろう。Il soffitto affrescato della chiesa di Wies. Puro rococo!確かにヴィース教会は、「ロココの教会」としては白眉なんだろうけれど、はるばる日本から時間をかけて来るほどのものだったのかな? と考えるとなんとも言えない。個人的な好みにもよるのだろうけれど、実際に見てもそれほど大きな感動はなかった。やはり教会芸術はイタリアのほうがスゴイものがたくさんあると素直に思う。大理石をふんだんに使うイタリアは、素材の質感からしてアルプスの北のものとは違うし、フレスコ画の歴史の長さも違う。こういうところに行くと、「世界遺産ってバーゲンしすぎじゃないの?」と思う。いつだったか、マルタ島のヴァレッタ市街が世界遺産に登録されたという話をイタリア人の友人にしたところ、「嘘でしょ? あそこが?」という反応だった。「シチリアのほうがずっと素晴らしいわよ」というのが彼女の意見だった。さもありなん。どうも「よくわらかない世界遺産」が増殖しすぎて、あまりありがたみがなくなっているような気がする。特に西欧に関しては、登録基準がずいぶん甘いと思う。西欧キリスト教文化中心主義という側面があるのは否めない。そうはいっても、近くに「世界遺産」があると聞くと、やっぱり行ってしまうのは、何だかんだいって、UNESCOの思惑にうまくハメられているのかもしれないな。
2007.10.17
-

やはり一度は見る価値あり? ノイシュバンシュタイン城
世界の観光地中の観光地。ノイシュバンシュタイン城。ヨーロッパに何度もバカンスで出かけながら、なかなか足が向かないでいた。それでも、「ルードヴィッヒの異常さが、ガンガン伝わってきてオモシロイ」「一度は見ておくべき」などといった友人の声に押されて(?)、ついに行くことにした。個人旅行で、自動車以外で行くとなると、案外面倒くさい。フュッセンからバスやらお城への馬車やらを使ってたどりつく。実はちょっとしたハプニングがあったのだ。なんと、ホーエンシュバンガウに向かうバスの停留所で、カメラバックを一式全部ベンチに置き忘れてきた!バスを降りたところで気がついた。あわててタクシーで戻った(アホくさ)ところ、バス停のすぐ後ろが観光案内所で、そこで保管されていた。何もなくなっていない。ドイツ人観光客が見つけて届けておいてくれたとのこと。うう~、こんなこともあるもんだと感激。Il Neuschwanstein, castello di sogno per Richard Wagnerお決まりのマリエン橋から撮った写真。澄んだ空気がすばらしい。城の中に入ったときもバルコニーから見える山々のすがすがしさや神々しさに一番感激したかもしれない。しかし、今ですら片田舎のこのロケーション。ルードヴィッヒの治世当時はどれほど人里はなれた寂しい場所だっただろう。城の中はなんというか、コテコテの世界。美術史家からはまったく評価されない理由も、にもかかわらず世界中から見物客を集める理由も、入ってみればワカル。うん、やはり一生に一度ぐらいは行ってみる価値のある場所だ。Arrivederci, Neuschwanstein! Arrivederci Ludwig!帰りのバスの中から振り返ると、中途半端な山腹にあるみょーに新しいそのお姿は、白鳥というよりラブホテルのよう…(苦笑)。ま、日本のラブホが真似をしたワケなんだけど。それでも、こんな寒々しい僻地に「夢の城」を築いたルードヴィッヒ2世の孤独と情熱に思いをはせ、「さようなら、ルードヴィッヒ」とつぶやいてみるのだった。
2007.10.16
-

バロックの影
リンダウ――まるで花の名のように可憐な響きだ。街もこじんまりとして品がいい。そんなリンダウの街を歩き回っていてある広場に出たとき、思いがけない壁画に出会った。Il muro esterno che venne affrescato nello stile barocco.壁画の人物は、重いもので頭をおさえつけつけられ、首が折れる寸前のような苦悶の表情を浮かべている。澄み切った青空の下で営まれている平和な日常とはいかにも不釣合いな世界が壁の中にうごめいている。ここに住む人々は毎日パンを食べるように自然に、この不気味なバロックスタイルの壁画を見ているのだろうか? それはあたかも日々のなにげない暮らしのなかでも、「常に死を思え」と警告しているようだ。"…Qui mangi pane e barocco.Vedi il cielo blu e poi pensa alla morte…""L'ombra di barocco"格子の下部は妊婦の腹のような膨らみ、壁に映った影をみると、不必要に過剰な装飾が施されているのがわかる。格子の造形もまたバロックなのだ。リンダウには、ちょっとこじゃれた商店街もあった。偶然立ち寄った店で買ったブロンズのアクセサリー。ポプラをモチーフにしたと説明されたが、記憶違いかも…。どこがポプラなのかわかるようなわからないような…ペンダント、ブレスレット、イヤリングで159ユーロ。当時の換算では1万9000円弱だったのだが、ユーロ高の今買うとすると2万6000円を超える。2万じゃ買わなかっただろうなぁ。最近のユーロ高は、どう考えても異常だ。
2007.10.15
-

リンダウ
スイスを出てボーデン湖畔の街、リンダウに着く。ドイツ、スイス、オーストリアの国境に近く、古くから交通の要衝として栄えたという。Lindau, situata in un'isola sul lago di Constanza.La facciata del Palazzo Comunale che e' dipinta a fresco con varie istoriette.お行儀よく並んだクルマの向こう。市庁舎の壁画はどこかメルヘンチックだった。Particolare dell'esterno muro affrescato del Palazzo Comunale.Sai quale sono reali cose e quale sono pitture illusionistiche?こちらは市庁舎の下方にあった壁画。だまし絵のレンガの四角とその前に置かれた自転車の輪の現実の丸が、不思議な視覚のマジックを演じていた。ところで、リンダウで泊まったホテルは素晴しかった。「Hotel Villino」。ホームページを見ていただくとわかるように、家族経営で、よく手入れされたこんじまりとした庭が美しい、小さなホテルだった。湖畔ではなく、ちょっと街からはずれた果樹園の中にある。駅からタクシーで12ユーロ。ルレ・エ・シャトーのメンバー。オーナー夫人が迎えてくれる。とてもアットホームな雰囲気。夫人がテキパキと1人でお客の相手をし、旦那さんはだまって庭の手入れをしている(笑)。ここはレストランとしても有名で、夜併設のレストランに行ってみると、宿泊客以外にもたくさん来ていて、ビックリした。便利な場所ではないのだが。みな、わざわざクルマで食事を取りにくるのだろう。テキパキとした若い女の子たちがきちっと給仕してくれた。この中にはホテルのオーナー夫妻のお嬢様もいるよう。朝も彼女がサービスしてくれた。昨日使ったタクシーのおじいさんも感じがよかったので、翌日ホテルを発つときも呼んでくれるようにオーナー夫人に頼んだ。きちんと荷物をもってくれ、エキストラマネーを要求することもなく運んでくれた。渋滞がなかったせいか、前日より安く11.5ユーロで駅まで。タクシーの運ちゃんなんてお釣りをごまかしたり、ワザと遠回りしたり、全然信用できないヤツばっかり…… と思っていたけど、そうでもない。自分の仕事に誠実な人は、見ていてうれしいものだ。
2007.10.14
-

シュタイン・アム・ライン
シュタイン・アム・ライン――ライン川の宝石。スイスでもっとも美しい街といわれている。チューリッヒから40分ほど。壁画で有名な旧市街を訪ねた。Citta' alta a Stein am Rhein, piena di affreschi.赤い牛が描かれているから、「赤牛の家」。Che cosa vuole mangiare, signore?レストランの前で、おじさんが熱心にメニューをのぞきこんでいる。壁画を堪能したあとは、川沿いのホテル「Rheinfels」のレストランでお茶をした。Rheinfelsは古い木造のレストランで、川からの湿気にやられるのか、だいぶ床がきしんでいた。そして、ここで遭遇したのが…Una meringa "esagerata"巨大メレンゲ!前の「普通の」プリンと比べてみるとその巨大さがわかると思う。テーブルにサーブされたときは、「おお~ッ」と素直にどよめいてしまい、給仕さんをビビらせた。Prima; "sara' troppo grande e pesante a noi!"E poi; "inaspettatamente leggera! E' facile mangiare tutta".「食えるか、こんなの~」と言いながらあっさり完食したのだった(笑)。意外と軽くて、もたれない。プリンも上等な味だった。スイスは乳製品がいいから、この手のスイーツは美味しい。
2007.10.13
-
善福寺在住サラリーマン、上荻の路上で寝る
タレントの井ノ原快彦(V6)と瀬戸朝香夫妻が世田谷等々力の路上で倒れた男性を見つけ、119番通報して、救急隊員に搬送されるまで見守っていたという記事を読んだ。 それでちょっと思い出したのが、1週間ほど前のこと。 深夜12時近く、連れと近所を散歩をしていた。自宅からそう離れていない住宅街の四つ角を通りかかったところ、衝撃的な光景が…! 男女2人を乗せたバンが右折の途中…… という感じで路上に停まり、その先の道路の真ん中に、なんと男性が倒れている! 靴も上着も散乱しているではないか。その男性のそばには通行人とおぼしき女性が立ちすくんでいた。「どっ、どうしたんですか? 事故?」 声を上げると、車中の女性が助手席から、こちらに向かって手を横に振ってみせた。「轢いてませ~ん」 ノンビリした声だった。路上の男性のところに近づいてみる。モロに車道の真ん中だ。寝ているのか気を失っているのか、はたまた死んでいるのか、一見したところではわからない。「どうしました?」 かがみ込んで声をかけるも、反応はなし。 おそるおそる口もとに手をやった。息してなかったら、どうしよう? と――「寝てんジャン!」 そう、男性はすやすやと平和な寝息をたてていたのだった。な~んだ。 落ち着いて見渡すと、靴は「やっと家に着いた」ときのように前後に脱いである。そして、上着も「その次に部屋で脱いだ」感じで放り出してある。どうやらこの男性、自身の脳内イマジネーションの中では「家に着いた」らしい。 再度声をかけてみたが、どうもそれでは目を覚ます気配がない。バンも道を通れなくて困っている。運転席の男性のほうがケータイを取り出し、110番通報を始めた。 しょうがないから道の脇に運ぼうか、と通りすがり同士で持ち上げようとしたところ、その男性、やっとただならぬ気配に気づいたらしく、やおら身を起こした。「あれ~?」 けっこう元気そうな声だ。「大丈夫ですか?」 と、Mizumizu。「どうしたんだ? オレ?」「道に寝てますよ」「え?」 周囲を見渡し、「ここ、どこですか?」 と、ハンで押したような反応。「かみおぎ~」 通行人がみなで声をそろえる。「あれぇ、オレ、何でこんなところに寝てんだ?」 出たっ! 酔っ払いのお手本のようなお言葉。期待に応えてくれるなぁ。「靴脱いでますけど?」 最初にいた女性が道端を指差した。最初の緊迫した雰囲気はすっかりとけ、なごやかなムードにつつまれた。 酔った男性は、ヨタヨタと立ち上がり、ノロノロと靴を履く。よく見れば靴も上着もよいものを身につけている。ちゃんとしたカタギのサラリーマンなんだろう。 バンの車中で警察に通報していた男女は、「あ、起きたみたいです。どうも」かなんか言ってケータイを切り、エンジンをかけた。 男性はというと、まだ事態が飲み込めていない様子で、「あのぉ、みなさんは……?」 と、まるで飲み会の仲間と半ば間違えているようにこちらを覗き込む。――もう一軒行くンすかぁ なんて会話をしてる雰囲気だ。「通りがかりですけど」「どちらにお帰りですか?」 口々に尋ねる。 すると、男性は首を振りながら、一瞬黙り込んだ。そして、低い声で、「善福寺……」 と、一言。 どうやら飲み会は終っていることを、ようよう自覚したようだ。 善福寺は上荻から歩くと15分ぐらいはかかる。普段は荻窪駅から頻繁にバスが出ているが、もう深夜でバス便がなく、歩いて帰ろうとしたところ、上荻で「すでに家に着いた」つもりになって靴を脱ぎ、「自宅に上がりこんだつもり」で寝てしまったということだろう。寝てるうちに記憶は楽しかった(?)飲み会までさかのぼっていて、そこで起こされた、ということのようだ。「タクシー呼びましょうか?」 聞いてみたが、「いや」 フラフラしながら青梅街道方向へ歩き出した。「大丈夫ですか?」「善福寺はまだかなりありますよ」 通行人のほうは心配して話しかけるが、男性は恥ずかしそうに首を振りながら、「いや、大丈夫っす。すいません」 と、歩いて行ってしまった。 あれだけ酔っていて、あと10分も20分も歩けるのかな? 少々心配になったが、本人はどんどん歩いているし、青梅街道に出れば、タクシーも拾えるだろうし、だいたいりっぱな大人だし、ということでそのまま見送った。 住宅街とはいえ、あのままずっと車道の真ん中に寝ていたら危なかったかもしれない。だが、路上で泥酔して寝込んでいるにもかかわらず、金品を奪われることもなく、通行人によってたかって起こしてもらえるなんて、まだまだ日本は平和だ。 あの善福寺の男性は翌日ちゃんと会社に行けたのだろうか? 今日の記事を読んで、彼もあの夜のことを思い出しているかもしれないと思った。
2007.10.12
-

4つのチーズのペンネ
忙しくても、材料さえあれば簡単にできる「4つのチーズ(クアトロ・フォルマッジ)のペンネ」デルフト焼き(オランダ)のお皿によそってみた。材料 2人分ペンネ 120~140g塩 水1リットルに対して10g(パスタをゆでるときに使う)ソース生クリーム 130~150ccゴルゴンゾーラ(チーズ) 60gカマンベール(チーズ) 60gマスカルポーネ(チーズ) 大さじ2杯パルミジャーノ・レッジャーノ(なければ緑の容器に入ったパルメザンでも可) すりおろしを大さじ2杯胡椒 少々 (チーズを溶かしてからかける)作り方1) フライパンか鍋にソースの材料を入れ、弱火で全部溶かす。2) その間に鍋にたっぷり湯を沸かし、塩を加え、ペンネをゆでる。3) ペンネが茹で上がったら、水を切り、チーズの溶けた(2)の中に入れ、中火のままよくからめる。ここで胡椒をふる。4) 皿によそい、パルミジャーノ・レッジャーノを上からかける。これだけ!ブルーチーズ系のゴルゴンゾーラはそのままでは食べにくいけれど、こうやって料理に使うとグー! 誰でも美味しく食べられるソースにはやがわり。マスカルポーネはコクを出すために入れる。カマンベールはMUSTではない。フォンティーナチーズなどを使ってもまた違った味わいになってグー!ちょっと辛く感じたら、ゴルゴンゾーラの量を(次回から)減らせばグー!逆に味が薄いと感じたら、ゴルゴンゾーラの量を増やせばグー!というわけで、この料理、材料をそろえるのが一番面倒だったりするけれど、作るのは簡単でウマウマなので、一度お試しあれ。
2007.10.11
-

帝国ホテルの強みは「想い出」、ではペニンシュラは・・・?
これまで銀座エリアである程度の規模のある高級ホテルといえば「帝国ホテル」だったと思う。「西洋銀座」も非常によいホテルでホスピタリティには定評があるが、77室とあまりにキャパが小さいし、中に入れば素晴しい雰囲気だが、周辺環境がよくない。西洋銀座のようなアットホームな高級ホテルを好む客は、いかにゴージャスなつくりとはいえ、大規模ホテルは敬遠する場合が多い。だから、西洋銀座のお客と帝国ホテルのお客は最初からあまり競合しないようにも思う。だが、「ザ・ペニンシュラ東京」は間違いなく帝国ホテルにとっては脅威だろう。ペニンシュラは300室あまりと、帝国ホテルの3分の1ほどのキャパだが、その分お客に目が行き届くだろうし、グレードも高くして顧客層を絞っている。アジアの名ホテルとしてのグローバルなノウハウも帝国ホテルよりありそうだ。これまで帝国ホテルを利用していた海外の富裕層がペニンシュラにある程度取られるのは仕方ないかもしれない。では、日本人はどうかというと、案外ペニンシュラには流れないような気もする。実際に建築を見てそう思ったというのもあるが、帝国ホテルには、ザ・ペニンシュラ東京にはない「銀座エリアのホテルとしての歴史」というものがあるからだ。Mizumizuの亡父も生前、帝国ホテルの「アクアラウンジ」を愛用していた。シングルモルトのウィスキーに目がなく、しかもXX年モノ以上というこだわりがあった亡父にとっては、そうしたお酒を出すことができ、サービスもよく、サイドディッシュもおいしく、夜景も楽しめる帝国ホテルのアクアは嗜好にぴったりだったのだろうと思う。こうしたある程度以上の年代の日本人にとっては「帝国ホテル」ブランドというのはなかなか威力がある。紀宮様の結婚披露宴というのも何だかんだいってブランドイメージを上げたと思う。ペニンシュラは確かにロケーションはいいが、敷地が狭いという印象はぬぐえない。新参者のツライところだろう。ロビーのカフェ「ザ・ロビー」も、香港のそれは東京よりずっとゆったりしている。東京の「ザ・ロビー」はあまりにキチキチしすぎて、優雅な雰囲気がない。帝国ホテルを見上げると、亡父とのアクアでの時間を思い出す。サイドディッシュで特に父とMizumizuが好んだのが、アナゴを使った簡単な料理だった。ところが、アナゴと何を組み合わせていたのか思い出せない。電話をして聞いてみたら、もうそのメニューはないとのことでハッキリとわからなかった。確かアナゴとフォアグラだったような気がするが、違うかもしれない。亡父はこれを「おかわりください」といって追加注文していた。英語もフランス語もできる人だったが、日本語になると突然「おかわり」などと言うのがおかしくもあり、多少恥ずかしくもあった。父が亡くなる直前、アクアからキープしているボトルの期限が迫っていることを知らせるはがきが来た。連絡をもらえれば延ばせるという。父が元気になってアクアにもう一度行く可能性がないことは、そのときすでにわかっていたのだが、電話をして延ばしてもらった。そして、亡くなったあとに家族で亡父の残したグレンへディックのボトルを空け、おいしいサイドディッシュを堪能した。こうしたちょっとした家族の想い出を帝国ホテルにもっている日本人は案外多いような気がする。その土地での歴史というのは、ホテルにとっては大切なことだ。外資のホテルが日本でこうした歴史を作っていくのは並大抵のことではない。だから、やはりペニンシュラは海外の顧客をターゲットにしていくのだと思う。確かオーナーはユダヤ系。その方面の人脈もありそうだ。香港でのブランドイメージはバツグンだから、中国人のお金持ちもペニンシュラを選ぶかもしれない。帝国ホテルのアクアには白人も多かった。ああいった顧客がペニンシュラに流れるのもあるだろうな、と思う。だが、日本人で1泊6万出してもいい、というほどのお金持ちは案外いないのだ。だがしかし、ザ・ペニンシュラ東京の公式ホームページはあまりにシャビーでひどすぎる。もうオープンしたのだから、情報を早く充実させてほしいもの。英語圏ではあの程度のもので許されるのかもしれないが、日本のホテルの百花繚乱の工夫を凝らしたホームページと比べると月とスッポン。あれでは泊まる気になれない。ホームページがあまりにわかりにくいので、ホテルで聞いたところ、2Fに広東料理のヘイフンテラス、上階にバーとフュージョン料理(イタリアンとフレンチを組み合わせた料理だとか)のレストランを併設したPeterがあるそうだ。ランチはそれぞれ4000円台からのよう。広東料理はイイかもしれない。今度はちゃんとバレットにクルマを預けて(笑)、食べに行ってみよう。ところで、スイーツだが昨日ご紹介したマンゴープリン以外はちょっと期待はずれだった。これは「ヤムヤム」というネーミング。yum yumとは英語で「おいしい」という意味。でも、どうみてもサントノーレにしか見えないんですが…(苦笑)。3つのプチシューに違ったクリームを詰めたということだった。サントノーレはとても手のかかる菓子だ。パートシュクレ(土台になるパイ生地)とプチシュー、それにクリームのアンサンブル。プチシューはカラメリゼしてあるのが基本(あくまでMizumizuの中では)だが、ペニンシュラのヤムヤムはチョコレートコーティングとちょっと廉価版(笑)だった。パートシュクレもイマイチ薄いし、クリームもケチくさい量。売り物の味の違うプチシューのクリームも、実はほとんど違いがわからなかった。というわけで、どうも作るのが面倒なサントノーレを全体的に廉価版にした、という感が否めないスイーツだった。これでyum yum(おいしい)とお茶を濁されるより、正統なるサントノーレを買ったほうがいいなぁ。サントノーレでクリームをケチったら、もうそれで高級感がぐっと落ちる。クグログもあったので、思わず買ってしまった。が、実はこれもネームプレートをみて、「え? クグロフ? これが?」と意表をつかれたのだ。クグログはアルザスのお菓子だが、フランスのものというようりドイツ語圏の焼き菓子といったほうが正しい。斜めのうねり模様がはいったドーナツ型がよく見る形だ。小さなクグロフは穴があいてないものもあるが、ペニンシュラのクグロフは砂糖をコーティングしていて、ブリオッシュのうねり模様が見えない。でも、上にのったオレンジの砂糖漬けが美味しそうだったので、試してみた。結果は… あっ、甘い! ブリオッシュ自体はお酒が効いていておいしい「ような気がする」のだけれど、表面の砂糖がメチャ甘くてビックリ。甘みにはかなり強いMizumizuでもかなり衝撃を受けたので、「甘さ控えめ」が好きな人には耐えられないかも… オレンジももう少し苦味や酸味を残してもいいような気がする。とにかく、全体的に甘すぎてブリオッシュの出来具合については詳しい論評が不可能となってしまった。クグロフはやっぱりブリオッシュの焼き方で勝負してほしい。ううむ… 日本以外のアジアではこのレベルで十分高級スイーツなのかもしれないが、東京では、ダメでしょう。
2007.10.10
-

帝国ホテルはもはや、庶民派!? ザ・ペニンシュラ東京
10.8、3連休の最終日は珍しく完全オフだった。9月にも3連休はあった「らしい」が、仕事が多すぎて全然休めなかった。この半年、休日がまったき休日であったためしがない。家から一歩も出ない日も多い。出ないというより出てるヒマがないのだ。今日はまったく仕事がない。ゆっくり寝てお昼近くに起き、クルマでランチを取りに出た。ランチのあと都心までクルマを走らせる。途中で「そういえば、ペニンシュラが9月にオープンしてたはず」だと思いつく。アフタヌーンティーでもしようかと、日比谷へ。ザ・ペニンシュラは地下鉄日比谷駅直結、皇居にも銀座にも近いというロケーションが売り。帝国ホテルの目と鼻の先にあるといったほうがわかりやすいかもしれない。ザ・ペニンシュラの駐車場に近づくと… ゲゲッ、3人もバレットが立っている。田舎のデパートみたいな帝国ホテルの駐車場の入り口とはエライ違いだ。バレット・パーキング=バレット代が高い、と踏んだMizumizuはペニンシュラに駐車するのはやめて、すぐそばの普通の駐車場に停めることにした(我ながら貧乏臭い・笑)。ペニンシュラはホテルの各ドアのところにドアマンが立っている。う~ん、なんだかとってもコロニアルな雰囲気。ドアを開けてもらって中へ。ロビーは香港のペニンシュラと同じく、カフェになっており、しばらくしたらちゃんとペニンシュラのトレードマーク、生演奏も始まった。ロビーのカフェは若い女性でいっぱい。宿泊客が通る埃っぽいようなところだが、ここは「庶民でもペニンシュラの雰囲気が味わえる貴重な場所」なのだ。とはいえ、あまりの混み具合にアフタヌーンティーの気分はすっかり失せた。席を詰め込みすぎていて、「優雅なアフタヌーンティー」をする場所のイメージからは程遠い。しかも、こんなにロビーいっぱいに外部の客を入れているのに、同じ階のトイレが一箇所しかなく、かつ個室は3つだけとはお粗末だと思う。実際、トイレの前は音楽会の休憩時間の劇場のトイレみたいに行列になっていた。内装は… なんというか、「中国人がハリウッドで日本をイメージしたセットをカネかけて組んだ」みたいな感じ。木をふんだんに使ったロビーの内装や、そここに見える「和風」の要素は、いかにもガイジンのイメージするような日本で、なんとなく居心地が悪い。大理石のタイルも惜しみなく使われていてゴージャスなのだが、上品さに欠け、華僑好みの成金趣味という印象になってしまっているといったら、ちょっと意地悪すぎるだろうか。橋本夕紀夫設計というが、どうもガイジンに媚びているのか、日本的な深みのある洗練に欠ける。ちなみに部屋は51平米の部屋で6万円から。帝国ホテルの同クラスの部屋より1万ほど高い設定のよう(帝国ホテルはもっと狭い部屋もある)。ペニンシュラのターゲットは日本人ではない気がする。地方から出てきた日本人が泊まるとは思えない。部屋の広さにこだわる日本人というのはそんなに多くないし、いくらなんでも最低価格が高過ぎるし、ハリウッド映画のセットみたいなエセ和風の建物が日本人の好みに合うとは思えない。とすると外国の金持ち相手かな。海外の富裕層がどのくらい日本に来るのかわからないが、コロニアルで、とりあえずは「モダン・ジャパニーズ」なしつらえの高級ホテルだから、ガイジンには受けるかもしれない。ロールスロイスでのお出迎えなどもあるようだし、海外のお金持ちがジャンジャン来てくれればいいのだが。バレットに駐車料金を聞いたところ、案の定、バレット代が1500円、そのほかに10分ごとに200円かかるという。6000円の食事をすれば1時間無料になるとか。フムフム、さすがに駐車するにも敷居が高いなあ(苦笑)。ちなみにMizumizuの停めた駐車場は10分100円。読みどおり、こちらのが安かった(と、安心するところが、我ながらケチくさい)。地下のベーカリーに行ってみたら、ここもなにやらカフェの前で行列している。テイクアウトなら並ばなくてすむということなので、スイーツを買ってみた。スイーツを買うだけで、こんな(写真右)大仰な紙袋に入れてくれる。まずは、香港といえばコレでしょう。マンゴープリン。値段も600円台と、トウキョウレベルでは、それほど飛び抜けては高くない。Mizumizuがこの南国のムードいっぱいのデザートに出会ったのも90年代の香港だった。当時は日本にはほとんどなかったマンゴープリンだが、今ではとってもポピュラーなスイーツになった。ザ・ペニンシュラのマンゴープリンはさすがにフレッシュで、おいしい。マンゴーの果肉自体はそれほど高級なものではないが、果肉の酸味がプリンの甘みとよく調和する。クコの実がのっているのが、いかにも中華風。香港を思い出して懐かしくなった。普通のマンゴープリンとちがって、白いクリームが中に隠れている。これがまたマンゴーの野性味を上品なデザートに変えるのに一役買っているようだ。マンゴーの果肉のぷるんとした食感とプリンのひたすら滑らかな食感もよいコントラストになっている。まあ、ペニンシュラだしね。このぐらいのものは作ってくれなくては困る。マンゴー好きとしては、もうちょっとマンゴーのクセを残してくれてもよかったかな、という気はするけれど、あのクセを嫌う人もいるし、そういった人にも受け入れられる上品で滑らかな口当たりの仕上がりになっている。トウキョウにあまたあるマンゴープリンの中でも、そうとう高いランクにあることは間違いなし。
2007.10.09
-
荒川選手のコーチ名からタラソワがはずれたワケは?
きのうの書きこみは、設定された文字数をオーバーしてしまったらしく、エラーが出て往生した(笑)。ブログの記事にも文字制限ってあったのね。さて、今日はネットサーフィンをしていて奇妙なことに気づいた。国際スケート連盟(ISU)の2004年世界選手権試合結果のページをみたら、荒川選手の紹介のところで、コーチの名前がモロゾフになっているではないか!↓これがそのページ。http://www.isufs.org/bios/isufs00000324.htm おかしい。昨日さんざん書いたように、モロゾフは当時タラソワ・チームの一員で、タラソワの教え子の振り付けを担当していたのだ。もちろん、高齢で氷の上に立てないタラソワにかわって実際のコーチングをモロゾフが行っていたのは周知の事実だが、それだってあくまでタラソワの意向を伝える補助的な役割であり、コーチは公式にはタラソワだったはずだ。気になったのでYou TUBEで2004年世界選手権の荒川選手の動画を探してみた。Mizumizuはたいがいの世界選手権&オリンピックの有力選手のフィギュア演技を録画しているが、最近ではYou TUBEで捜すほうが速かったりする。これがその画像。http://www.youtube.com/watch?v=6xzGdVragbo演技が終ってキス&クライで得点を見つめる荒川選手とコーチ陣が映っている。その中にモロゾフはいない。タラソワは、もちろんいる。右側でゴージャスな毛皮をまとったロシア人オバサンがタラソワその人だ。2004年当時、ライブで見ていた映像だ。ナレーションでもタラソワがここにいるという事実がうれしいとして、"She has just given up Sasha Cohen"と、この大会の本当に直前に、タラソワがコーエンとの師弟関係を解消した話を紹介している。タラソワがコーエンと別れたと聞いて、素早く荒川選手をねじこんだ(?)のが「あの」城田氏だと聞いている。そしてタラソワがコーチになった数週間後に荒川選手が世界女王の座についたのは、有名な「タラソワ伝説」の1つのエピソードとして語り草になっている。それなのに、ISUの公式ページの記録では、2004年の荒川選手のコーチはモロゾフでタラソワは「前コーチ」になっている。いくら、実際の氷上での指導を行っていたとはいえ、公式にはタラソワ・チームの一員で、試合当日キス&クライにもいなかったモロゾフがなぜ「コーチ」なのだろう? どうも解せない。単なるミス? もちろん、人間のやることだからミスもあるだろう。だが、「単なるミス」というのは一番考えにくい。ISUの公式サイト、しかもオリンピックについで最も格の高い試合である世界選手権のページだ。誰が誰のコーチであるかというのは、非常に重要な問題だ。世界チャンピオンを育てたとなれば、そのコーチの名声は一挙に高まる。高額のマネーが動く、完全にビジネスの世界なのだ。また、各報道機関の記者はISUのホームページで過去の成績やコーチをチェックするはずだから、「モロゾフは2004年当時からトリノの金メダリスト荒川静香のコーチだった」という誤解が生じてしまう。この誤った記載には何か、誰かの政治的な意図が背景にあるのだろうか? もちろん、それもありえるが、憶測をこの場で述べるのはふさわしくない。ただこの記録が正しくないことだけを指摘するに留めよう。
2007.10.08
-
蘇ったタラソワ・ワールド、浅田真央の07-08ショートプログラム
TBSの『日米対抗フィギュア2007』を見た。各選手ともこのイベントに合わせた調整には、まったくといっていいほど力を入れていないと見えてジャンプはひどい出来だった。シーズン初めだし、今後のもっと重要な試合のスケジュールを考えれば、まあ、こんなものかなと思う。安藤選手の転倒は心配だ。試合前日にも転倒して古傷の肩を痛めたというし、怪我が多くなってきている。特に安藤選手の場合は、試合直前にどこかを痛めることが多い。よくない徴候だ。怪我が多くなると引退が近くなる。世界女王になったことでショーも含めてスケジュールもハードになりがちだ。去年よりスリムになって、本人の努力がうかがわれるだけに、うまく試合を選んでいい演技を見せることができるように周囲もバックアップしてあげてほしい。ジャン選手は、やはり14歳とは思えない。だが、現時点では、クワンとコーエンを足して2で割ったような演技にはあまり魅力を感じない。あの特異なスピンがあるにもかかわらず、表現に新鮮さがないのは、トム・ディクソンの振り付け(スパニッシュジプシー)のせいなのか、アメリカでの指導というのが、表現力まで一定の型に当てはめて行うせいなのかはよくわからない。さて、注目の浅田選手だが、演目は今季ショートプログラムの「ヴァイオリンと管弦楽のためのファンタジー 」(映画『ラヴェンダーの咲く庭で』から)だった。振り付けがあの超名コーチ、タチアナ・タラソワということで注目していたが、期待以上に素晴しい作品だった。タラソワが「振り付け」を行うのは珍しい。タラソワはずっとコーチであり、そのタラソワ・チームの一員だったモロゾフが振り付けを行うというのがこれまでのイメージだった。ヤグディンなどはその好例だし、荒川選手が世界選手権で優勝したときも、コーチがタラソワ、振り付けがモロゾフだった。荒川選手がオリンピックで金メダルを獲ったときのコーチはモロゾフだったが、実はこれはモロゾフが直前にタラソワ・チームから独立したことから、荒川選手が「実際に氷の上で教えてくれるコーチにつきたい」という意向でコーチをタラソワからモロゾフに変えたという背景がある(タワソワはモロゾフとの2重のコーチ体制を許さなかったので、荒川選手はどちらかを選ばなければならなくなったのだ)。モロゾフがタラソワ・チームを離れたのは、直接的には高齢だったタラソワが、それまで拠点をおいていたアメリカから健康問題を理由にロシアに帰郷したからだが、裏には、当時のタラソワの教え子のライバルの振り付けをモロゾフがタラソワに黙って引き受け、タラソワの逆鱗に触れたといういきさつもある。モロゾフはコーチとして独立してすぐに結果を出す。荒川選手にはオリンピック金メダル、安藤選手には世界チャンピオン、高橋選手には世界選手権銀メダルをもたらすという快挙をなしとげた。荒川・高橋選手はもともとタラソワが見ていたから、タラソワのまいた種をモロゾフが開花させたという側面も否定はできない。荒川選手のオリンピック直前の曲変更についても、タラソワは「荒川選手は曲を『カルメン』に変えたがったが、彼女にカルメンは合わない。変えるなら『トゥーランドット』にするよう手紙を書いた」と主張している。つまり、トゥーランドットへの曲変更は、タラソワのアイディアだったというのだ。タラソワの主張が本当かどうかはわからないが、確かに「クールビーティ」荒川静香にカルメンは役不足だ。彼女にはやはり、「恋に目覚めて心を開く氷のお姫様」こそふさわしい。そのタラソワが今シーズン、日本女子スケート史上最高の(といって差し支えないだろう)才能のために選んだのは、「ラヴェンダー」という花にまつわる曲の世界だった。このショートプログラムを見るのは今回初めてだったが、「素晴しい」の一言だった。タラソワとモロゾフの氷上の世界は、過去ほとんど一体だった。だからタラソワ対モロゾフの振り付けが見られるなんてことは想像していなかった。浅田タラソワと安藤モロゾフ(あるいは高橋モロゾフ)を見ると、やはりタラソワはモロゾフとは違う。一言でいえば、タラソワは「音と音の透き間」の表現に重きをおいている。こうした叙情性は、やはりモロゾフより高い次元にあるようだ。具体的にいえば、浅田選手の腕の使い方が、これまでになく大きく、かつ繊細になった。タラソワは両腕を広げるときの情感の込め方にひどくこだわる人だが、浅田選手は、まだまだ不完全とはいえ、タラソワの腕のモーションによる情感表現によく取り組んでいた。ショートを通じて表現するのは「強い鳥」だという。だが、浅田選手の表現は、さらに見る者のイメージを刺激し、表現世界の印象を広げてくれる。Mizumizuは、むしろ風にそよぐラヴェンダーの花を浅田選手の演技に見た気がする。出だしのところで、素早い回転のあと、浅田選手が投げキスをするような手のしぐさをみせる。これは花が風に送る愛の挨拶だ。そして、2度めのジャンプ。規定にそっていえば「ステップから直ちに跳ぶ単独ジャンプ」の後で、顎の下で手首を合わせ、それから両腕をぱあっと広げる動作があるが、それはまるで花が開く瞬間のようだ。そして、そのポーズを決めたすぐあとに、素早い回転動作が入る。こうしたポーズは「音と音の透き間」になされ、その後に続く動作は音楽のリズムに乗って行われる。だからまるで、その一瞬の美しい仕草は夢か幻であったかのように次の早いモーションの中に、旋律とともに消えていくのだ。そこにタラソワ独自の叙情的な世界が垣間見える。後半のストレートステップ以降の動作も、実にタラソワらしい。素早くターンし、回転方向を変えてスピンする。そしてその間に、上体を折り曲げたりのばしたり、あるいは腕を閉じたり開いたりといった上体のモーションを混ぜるのだ。こうした一連の身体の使い方は、アイスダンスのグリシュフ&プラトフの動きを彷彿させるようでちょっと懐かしくもあった。ラヴェンダーの花にふさわしく浅田選手は薄いブルーにラヴェンダー色を効かせたコスチュームを着ていた。細くのびた可憐な浅田選手のプロポーションは、スリムなラヴェンダーが風にそよぐさまを演じるのにぴったりだ。タラソワは重厚な感情表現を選手に教えるのを得意としているが、全体的にあまり重くない、こうした「ファンタジー」世界の表出も、浅田選手という素材を得て可能になったのかもしれない。風と花の織りなすファンタジー、今季の浅田選手のショートプログラムのテーマはそこにある。やはり、というべきか、このプログラムの「振り付け」の評価は7点台とダントツだった。浅田選手の大きな上体の動きは、これまでにない進化を感じさせる。だが、同時に欠点も見えたかもしれない。浅田選手は、たとえばキム・ヨナ選手に比べると肩の関節の可動域が広くない。「キム・ヨナの表現力」というとき、それは身体的にはほとんど肩の柔らかさを指しているといっても過言ではないのだが、浅田選手は特に肩の前後の動きが浅いようだ。腕のつけ根である肩の関節が柔らかいからこそ、キム・ヨナ選手は誰にもマネのできないような独特のムードをもつ、前後にも深い腕の動作を行うことができる。浅田選手の場合は、その部分の身体能力に限ってはキム選手には及ばない。だが、一方では、キム選手にない明るさや華やかさ、スケール感ももっているのが浅田選手だ。だから、肩の関節の柔らかさの優劣はあまり大きな問題にはならないと思う。むしろ、浅田選手の懸念は、自他ともに「最大の武器」だと認めるそのジャンプにある。今回の演技では、最初のコンビネーションジャンプが見事に抜けた。セカンドジャンプが入らなかったのだ。というより、やめてしまったように見える。これは非常にマズい。浅田選手のショートプログラムのコンビネーションのセカンドジャンプは、安藤選手と同じくトリプルループだ。ループは足を交差させるようにして跳ぶジャンプで、これを二度目のジャンプで行うためには、一瞬スピードを止めなければならない。スピードを止めた状態からジャンプを跳ぶのだから、難しい。事実、キム選手、ジャン選手など、セカンドジャンプを3回転にする選手の多くは難度の低いトリプルトゥループにしている。トゥループなら多少下りてくるときの姿勢が悪くても、勢いで跳べる(ジャンプの難度は、低い順にトゥループ→サルコウ→ループ→フリップ→ルッツ→アクセルとなる)。今回の浅田選手の最初のジャンプは、やや斜めになって下りてきた。それが迷い、というか不安になってセカンドジャンプを跳ぶことができなかったようにみえる。実は先シーズンから、浅田選手はショートのコンビネーションのセカンドジャンプでしばしば失敗をしている。これはジュニア時代にはあまり見なかった光景だ。トリプルアクセルに関しては、昨シーズンはステップから跳ぶという難しい技にチャレンジしたせいもあって、ほとんど公式試合できれいに決めることができなかった。一見成功したかに見えた世界選手権でのトリプルアクセルも、実はよく見ると着氷が両足だった。163センチという長身の彼女が、トリプルアクセルを跳べること自体が奇跡に近い。浅田選手が出てくる前、トリプルアクセルを女子選手で本当の意味で身につけていたのは、伊藤みどり選手だけだと言っても差し支えないだろうが(ほかの選手は、たとえばハーディング選手にしても、中野選手にしても世界選手権のような大きな試合ではほとんど成功していない)、彼女は140センチ台という小柄な身体だった。ジャンプを跳ぶなら小柄で軽いほうが有利だ。浅田選手は現在17歳。トリプルアクセルも今なら跳べるのかもしれない。だが、20歳近くになったとき、浅田選手が今と同じようにジャンプを跳べるのだろうか? そうした不安を抱かせるのが、最近のショートプログラムでのセカンドジャンプの失敗だ。ジャンプに関しては、浅田選手の周囲が目標とすべきは技のアップよりもむしろ、「20歳になっても今のジャンプのレベルを保つ」ことだ。女子ならばそれで十分だ。最後の世界ジュニア選手権で、浅田選手は自滅してキム選手に敗れたが、あのときも山田コーチによれば「マオは4回転にこだわっていた」という。ヘタに高い技に固執すると、すべての調子を崩す。それがフィギュアのジャンプの怖いところだ。安藤選手がトリノオリンピックで惨敗したのも、すでに調子を崩しているにもかかわらず、4回転に固執しすぎたためだ。浅田選手のジャンプの調子がどうか、現時点では判定するには早すぎる。だが、今季もトリプルアクセルの確率が昨シーズンのように悪いなら、本当にマズい。そのときはアルトゥニアンコーチはさっさと解任すべきだろう。だいたい彼を「クワンを育てたコーチ」などとテレビで紹介するのはやめてほしい。クワンを育てたのは、フランク・キャロルだ。キャロルは10年以上にわたってクワンの指導をし、世界選手権4度優勝というカタリナ・ビットに並ぶ偉業を成し遂げさせた。アルトゥニアンはクワンとキャロルが不仲になって別れた後、つまりクワンが十分成長したあとにコーチの座についたにすぎず、実際、その後クワンはもう一度世界チャンピオンに返り咲いたものの、怪我続きで事実上の引退に追い込まれている。そういえば、読売新聞は、今回のイベントの結果について「浅田はノーミスでまとめたが、合計得点は伸びなかった」などと書いている。ヲイヲイ!! ショートプログラムというのは、要素が決まっているのだ。ジャンプの要素にはコンビネーションが入っている。そのコンビネーションが完全に抜けてしまった。これほど大きなミスはないのに、「ノーミス」ってのはどういう了見なのだろう。セカンドジャンプが入らなかったにも拘わらず、60点台にのせたのだから、得点としては高いほうだ。浅田選手にしては得点がのびなかったのは、このセカンドジャンプが抜けたというミスが響いたからにほかならない。フィギュアに関しては読売新聞ですらこのレベルだ。
2007.10.07
-
パールスピンが日本に初上陸する日
今日、10.6の午後7時からTBS系で「日米対抗フィギュア2007」が放映される。対抗戦とはいっても、こうしたイベントはどちらが勝つか負けるかという勝負に力点はない。浅田真央、安藤美姫(現世界チャンピオン)、高橋大輔など日本の有力選手の今シーズンのプログラムのお披露目の意味が大きいと思う。日本選手の調子やプログラムはもちろん気になるが、この番組でもっとも注目すべきは――ほとんど宣伝されていないが――アメリカの2人の天才少女、キャロライン・ジャンと長洲未来がエントリーしていることだろう。現在隆盛を誇る日本女子フィギュア、そのライバルとしてよく名前が挙がるのは韓国のキム・ヨナだが、「フィギュア王国」アメリカには、次世代の天才が控えている。その筆頭がキャロライン・ジャンだ。浅田選手より3歳若いジャンは、体型はまだまだ子供だし、ジャンプのときに、脚を大きく振り上げて勢いをつけなければ跳べないという欠点もある。だが、彼女の最大の魅力、そして最強の武器は、「パールスピン」と呼ばれるジャンにしかできないスピンだ。それがどのようなものかはいずれ、誰もがテレビで目にするようになると思うので、詳しく書く必要もないと思う。要するにケタはずれの柔軟性を生かしたスピンで、背中が2つに折れているのではないかと思うような深いレイバックスピンから、そのままビールマンスピンに連続して移項する。ビールマンスピンの体勢で回転しているときも頭がお尻にくっつくのではないかと思われるほど身体を曲げてみせる。それが「真珠貝のように見えることから、パールスピンと呼ばれる」と説明されている。だが、ハッキリ言ってこの特異なスピン、「パール(真珠貝)」には全然見えない。以前アメリカのメディアは「オクトバス(タコ)スピン」と言っていたハズだ。そのうほうがぴったりするように思う。まさに中国雑技団のような恐るべき柔軟性。だが、「タコ」という語感が悪いということで、キャロライン・ジャンの側からクレームがついたらしい。「タコ」であろうと「真珠貝」であろうと、このスピンにみるジャンの柔軟性が、現在のフィギュア界一であることは疑いようがない。ジャンは開脚においても、その卓越した身体能力を見せる。スパイラルでは、持ち上げた脚と軸足はほぼ真っ直ぐになっている。これほど開脚できる選手はサーシャ・コーエン以来だろう。片足を上げたウエルバランスの姿勢から回転する動作では手の組み方にご注目。180度に近く頭上に片足をあげ、手を脚の前から外側に回し、背中でもう一方の手と組んでみせる。こんなポジションを取れる選手は見たことがない。加えて、肩の関節も柔らかく、したがって腕の動作にも表情がある。長洲未来は、そのジャンを全米ジュニア選手権で破った選手だ。名前が示すとおり日系(というより、アメリカで生まれた日本人というべきか? 確か二重国籍のはずだ)だが、日本語はかなりブロークン。ほとんど話せないといったほうが正確かもしれない。長洲選手の特長はシャープで切れのいいジャンプだ。だが、日本人選手にとっては、どちらかといえばジャンのほうが脅威だ。ジャンプだけなら、長洲選手より、安藤選手や浅田選手のほうが卓越したものをもっている。長洲にはトリプルアクセルも4回転もない。ジャンには、日本人選手が及ばない柔軟性という武器がある。浅田選手も身体はかなり柔らかい。だから、片手ビールマンなどの難しい技もできる。両手でやっとこビールマンの姿勢をとっているキム・ヨナとは違う。その浅田選手をジャンの柔軟性は明確に凌駕している。だがジャンのスピンは、あまりに身体が柔らかすぎて、美しいというより、むしろ異様に見える。何事も過ぎたるは及ばざるがごとし。長い脚は美しいし、カッコいい。だが長すぎる脚はどうだろう? ジャンの柔軟性は、「凄い」と素直に思う反面、「フィギュアもここまで来たか」という感慨(?)のようなものも抱かせる。ああした特異な技は目を惹くし、印象的ではあるが、フィギュアスケートの本来の魅力である「滑る技術」から人々の目を遠ざけてしまうようで、ちょっと違和感もある。あまりにアクロバティックな技の難度ばかりを追求していくと、ピークを迎える選手の年齢はどんどん低くなるし、それにともなって選手生命も短くなる。フィギュアはそれでなくても、あまりに選手生命が短い競技だ。なににせよ、ジャンの「パールスピン」は見た人を驚かせることは間違いない。メジャーな番組で放映されるという意味で、今夜がパールスピン日本初上陸の日だ。
2007.10.06
-

フシュル湖畔の古城ホテルに泊まる
ザンクトギルゲンからザルツブルクへ行く間に、フシュル湖畔にある古城ホテル「シュロス・フシュル」に泊まった。シュロスは城という意味で、15世紀の大司教の館として建てられた由緒ある建物だ。ホテルのグレードとしても5つ星。なるほど、ロケーションといい建物の雰囲気といい、素晴しい。午後着いてすぐ、ホテルのテラスでお茶をした。ちょうど、天気がよく、午後の日差しを受けてフシュル湖が宝石のように輝いていた。頼んだチョコレートケーキも最高においしい。夜もここで、アスパラ(初夏のドイツ語圏ではこればっかり)と肉料理に舌鼓をうつ。味はよかった。部屋は「グランド・デラックス」という湖の見える部屋にしたのだが、窓をあけると大木が湖の眺望を阻んでいた。部屋もグランドではなかった。ただ、設備はたしかにデラックスだった。ところで、このホテル、ハード面では確かに5つ星にふさわしくゴージャスなのだが、ソフト面、もっといえばホテルの従業員がいただけなかった。まず、ホテルに着いて、エントランスの階段をのぼるとき、ポーターが入り口にいるのだが、見てるだけで何もしない。齢70を超えようという母が自分で荷物を運び上げようとしている姿を見てるのに、だ。そこでMizumizuがポーターに「手伝ってあげて」と英語で話しかけた。すると…!「ハァ~ン?」と言うのだ。つまり、英語が通じてない!英語が分からなくても、こういう場合、何を言ってるかぐらいは想像つきそうなものだ。だが、この手のことには慣れているMizumizuは、すぐにドイツ語に切り替えた。すると…!「Ja!」と、ものすごく感じのよい声音で答えて、さっと母の荷物をもってくれた。5つ星のホテルのポーターが英語ができないなんて、ありえるのだろうか?? いや、もしかしたら、彼はポーターではなくて庭師か何かだったのかも。そういえば、服装がそれっぽくなかった。だったら、ポーターはいったいどこにいたのだろう?また、メイドの態度もいただけないものだった。夕食を終えて部屋に帰ってくると、ベッドメイキングがされていない。何回ベッドメイキングをしてくれるか、それがどの程度丁寧か、というのが、高級ホテルのソフト面を評価するバロメーターだ。たとえば、今度サミットが行われる北海道・洞爺湖の「ザ・ウィンザー・ホテル洞爺」は外出から戻ると常にベットがきちんと整えられていた。シチリアの「サン・ドメニコ」では、ディナーから戻ると脱ぎ散らかした服をちゃんと整えておいてくれた。ところが、シュロス・フシュルではメイドが仕事をした気配がない。そして、なんと午後10時を過ぎてやってきて、ノックをし、ドア越しにワザとらしく優しげな声で「ベッド・メイキングにきました」とのたまうではないか。「普通なら夕食の間にやっておくことでしょう」と、説教を垂れようかと思ったが、疲れていて面倒なので、「もうやってしまった。必要ありません」とだけ言って去ってもらう。こんなわかりやすいサボり方をして、ベッド・メイキング(つまり自分の仕事)を省略して嬉しいのだろうか。ゲストをバカにしている。やはり、きちんと抗議すべきだったと思う。日本人はたいてい、失礼なことをされても、「まあ、いいや」とイイ人になったつもりで何も言わないが、こうした事なかれ主義的な態度の人間は、ヨーロッパでは「都合がいいヤツ」とは思われるかもしれないが、「尊重」はされない。チェックアウトする際にも、「ポーターを部屋によこしてくれ。母が荷物を運べないので」とフロントに伝えたのに、「Yes」といいながら、先に支払いを済まさせようとしている。ジョーダンではない。支払いを済ませたら(つまりフロント係の仕事が終ったら)、さっさと奥に引っ込んでポーターのことなど知らんふりしかねない。そこで、再度、「ポーターを部屋によこしてくれ。母が荷物を運べないので」とオオムのように繰り返した。こういうときに感情的になってはダメなのだ。あくまでこちらの意思をきっちり伝えなくてはいけない。それでフロントのねーちゃんはようやくポーターを呼ぶ。さらに、支払いのときに、明細をみたら、UNICEF 1 Euroとあるではないか。ナンじゃこれ? と思って聞くと、「ユニセフに1ユーロ寄付してもらっている。かまいませんか?」と慌てた様子。別に1ユーロぐらい、いいといえばいいが、寄付をお願いするなら先に言うべきではないのだろうか? あるいは、明細を見せながら自分で説明すべきだろう。明細を突き出しておいて、こちらがチェックして見咎めてから、「かまいませんか」ってのは筋が違う。それに、ホントにユニセフに寄付するかどうか、アヤシイものだと思う。各ゲストから1ユーロずつ勝手に徴収して、それを彼らがただの収入にしていないと、どうやって証明できるだろう?というワケで、この古城ホテル、ソフト面でのサービスは最低レベルに近かった。ちなみに、確かアメリカ資本のホテルグループ傘下に入っていたと思う。宣伝は超一流だ。ネットのホームページを見るとどんな素敵な夢のホテルかと思う。もちろん、その後、改善されたかもしれない。ただ、あくまで一旅行者として宿泊してみての感想は、「サービス業のプロとしての従業員の意識が低い」というのが正直なところだ。ちなみに、ウェイターはまずまずだった。このホテルでは、日本人の団体客10人ちょっとと遭遇した。ちょうど日が落ちかけるころ着いて、バスから降りたご婦人方は、だいぶ疲れているようで、ホテルの入り口の階段に腰を下ろしてしまった。添乗員は、フロントで仕事の遅いオーストリア人相手に必死になっている。せっかく5つ星のホテルに来たのに、エントランスの階段(つまり外)で待たされるなんて、かわいそうだ。そのホテルはエントランスを入っても空間が狭く、フロントデスクしかないが、実は右のほうへいけば、ゆったりとしたサロンがあるのだ。そのサロンは狩猟の館としてのこのホテルの歴史を物語るしつらえで、暗いといえば暗いが、非常に雰囲気がある。ヨーロッパの人間は、こうした空間でくつろぐのが好きだ。本当なら、チェックインまで、こうしたサロンのソファで待つのが当たり前ではないのだろうか? だが、ホテルの従業員は何も言わない。日本人客も、「こんなところじゃなくて中に座って待てる場所はないの?」とも思わない様子で、石の階段にへたりこんでいる。日本人団体客が着いたのは日暮れどきだったから、残念ながらフシュル湖は上の写真のような色ではなかった。光線の具合もあるから、湖や海が本当に美しく見える時間というのは、実は1日のうちでも限られている。団体客は夜のテラスでディナーをとり、翌朝は早く発ってしまったようだ。部屋も湖に面していない別棟のほうを割り当てられていたから、このホテルのロケーションのよさは、それほど味わえなかったのではないかと思う。他人事ながら、ちょっと残念だった。もう3時間早く着けば、宝石のように輝く湖の美しさを堪能できたのに。だが、ツアーを企画する旅行会社としてみれば、午後の早い時間に着いて、天気が悪かったらどうする、というのもあるだろうと思う。湖畔の古城ホテルというのは、孤立した場所にあるから、近くにお土産屋があるわけでもない。ホテルのまわりを散策といっても、それほど時間はつぶせないし、あまり早い時間にホテルに入ってしまっても、クレームのネタになるかもしれない。だが、一方で、バスから降りてすぐ、石の階段にへたりこむほど疲れた様子を見ていると、そんなに引きずりまわすのもどうかな、という気もしてくる。翌朝もずいぶん早かったようだし、あれでは疲れが取れないだろうな、とも。Mizumizuたちはといえば、個人旅行の気楽さで、午後ゆったりお茶をのみ、ちょっと散歩し、寝心地のいいベッドでウダウダし、朝も遅めに起きて、お昼近くになってからザルツブルクへ向かった。名所・旧跡をひたすら精力的に回る旅行も、若いうちはいいが、そればかりでは疲れてしまう。ロケーションのいいホテルで「何もしない」という贅沢も、すでにやめられない快感になっている。
2007.10.05
-

白馬亭に泊まる
オペレッタの舞台にもなったヴォルフガング湖のホテル「白馬亭」。このホテルは日本から、自分でネットで予約を入れた。部屋によって値段が違うということは書いてあるのだが、実際いくらでどの部屋に泊まれるのかがよくわからない。質問したら、季節や混み方によって違うのだという曖昧な理由を書いた返事がメールで送られてきた。殿様商売的でちょっと不安はあったが、まあ由緒正しいホテルだし、一応信頼して、高めの部屋を予約した。割り当てられた部屋はまったく問題なかった。最上階だが、屋根裏部屋的な暗さはない。一応湖に面した部屋で、ベランダも付いていた。ただし、ベランダは湖に面しておらず、外からも見えないので、くつろぐ場所ではなく、洗濯を干す場所となった(笑)。これがその部屋。奥の壁に楕円形の窓があって、ここから湖が見下ろせる。なんとなく船旅をしている気分。船底天井だが、部屋は広く圧迫感はない。カーテンやベットのファブリックは黄色。オーストリアといえば、マリア・テレジア。マリア・テレジアといえばイエロー。黄色は、かの国では高貴な色なのだ。暖色のファブリックを使っているから、窓が少ない部屋でも陰鬱さとは無縁。カーテンのバランス(上飾り)とタッセル、それにベットの天蓋に同じ生地の布。統一感のあるかわいいインテリアだった。写真でいうと右手の窓からベランダに出られるようになっている。ここで一泊してザンクト・ギルゲンまで船で行ったのだが、連れの母の膝の調子が悪くなった。チェックアウトのときもロビーで座っている。片足を引きずるようにして歩く母の姿を見ていたホテルのやや年老いたポーターが、「どこに行くの?」と聞く。「ザンクト・ギルゲンへ」と答えると、「船?」と聞く。そうだと答えると、私たちの荷物を手押し車にのっけて、ガンガン外へ持ち出した。そのまま、船着場まで荷物を運んでくれる。その足の速いこと速いこと。老いたりとはいえ(?)ゲルマン男はすごい。歩幅が違う(笑)。Mizumizuは心底感動した。だいたい高級ホテルでも若いポーターの兄さんなんて、まったく気が利かない役立たずだ。「この荷物を、ここまで運んで。そこに置いて。ありがとう」みたいに、一から十まで指示しないと動かない(いかなボンクラなポーターであろうと、仕事をしてもらったら必ず「ありがとう」といわなければいけない。それがヨーロッパでの礼儀だ)。日本人のように何も言わなくてもいろいろ気を利かせてくれるということはない。声をかけなければ、荷物を運びもしない。「荷物を運びましょうか?」と聞きもしないで突っ立ってるだけ… と、その手のにすっかり慣れていた。でも、さすがは老舗ホテル。こうした職人気質のプロらしいポーターがちゃんといるのだ。なんか古きよき時代のヨーロッパを感じた。船に乗ってザンクト・ヴォルフガングを去る。ホテル白馬亭を湖から見たところ。向かって左側の棟の最上階がMizumizuの泊まった部屋だ。あの老ポーターはもう引退しただろうか。ホテルにお礼のメールを書いたのだが、infoあてだったし、どうもちゃんとオーナーまで伝わっていない気がする。きちんとお礼の手紙をオーナーに出すべきだった。ああいった「よい仕事をしている」人があまり報われなということになると、結局、外見はりっぱでも、突っ立ってるだけのポーターばかりがいるホテルになってしまう。
2007.10.04
-

ドレミの歌の舞台を歩く
「サウンド・オブ・ミュージック」は好きな映画の1つだ。歌と映像が素晴しい。たとえば、ミラベル公園なんて、公園の庭自体はたいしことはない。あれなら、日本人にはあまり知られていないけれど、イタリアの北部マッジョーレ湖のイーゾラ・ベッラやターラント邸のほうが何倍も素晴しい。イーゾラ・ベッラはコテコテのバロックのフランス式庭園、ターラント邸はイギリス式庭園。マッジョーレ湖はまったく赴きの違う庭園がわりあい近い位置で楽しめるという稀有なスポットなのだ。それに比べると、ドイツ語圏の庭園はダサいのばっかり。そのドイツ語圏の「たいしたことない」庭園の代表みたいなミラベル公園に観光客が押しかけるのは、ここが「サウンド・オブ・ミュージック」の撮影で使われたからだ。Mizumizuはエーデルワイス・グッズマニアで、ヨーロッパアルプスに行くとよくエーデルワイスグッズを買っている(ほとんどは中国製なのだろうけど)。たとえば、これは鹿の角にアルミのエーデルワイス装飾を埋め込んだギーホルダー。こうしたエーデルワイス集めも、映画の影響があることは確かと思う。「サウンド・オブ・ミュージック」は名曲のオンパレードだが、なかでも「エーデルワイス」は忘れがたい。Edelweissとはドイツ語で「高貴な白」の意味。映画の中では、2度歌われるが、特にクライマックスで歌われる「エーデイワイス」は感動的だ。まずはトラップ大佐が歌い、感極まって声をつまらせたところで、マリアが、そして子供たちが唱和していく。祖国・オーストリアそのものの象徴であるエーデルワイスに、祖国をいま去ろうとする人間が、「わたしの『くに』を永遠に祝福しておくれ」と歌うのだ。映画自体は、トラップ家の実像とかけ離れているというし、トラップ一家が亡命するまでの筋立てが、あまりに単純な反ナチスのプロパガンダ映画になってしまっているところはある。だが、オーストリアの雄大な自然、マリアと子供たちの心の交流、子供たちの成長、トラップ大佐との愛、そして何より前編をいろどる素晴しい歌が、この映画を、大人は大人として、子供は子供として、誰でもが楽しめ、感動できる名作にしている。そんな映画の中で「ドレミの歌」が歌われるシーンをご記憶だろか。このシーンの撮影に使われたのが、ヴォルフガング湖に面した町、ザンクト・ヴォルフガングにあるシャフベルク鉄道なのだ。赤い可愛いSLが観光客をシャフベルク山へ運んでくれる。眼下に輝いているのがヴォルフガング湖だ。山頂へは、鉄道駅の終点からさらに50メートルほど九十九折りの道を歩く。こちらはヴォルクガング湖とは逆の方向にあるモント湖。あっちもこっちも湖だらけ。まさに「湖水地方」だ。お天気に恵まれてよかった。観光客が山頂から落ちそうだ。
2007.10.03
-

ザルツカンマーグートの拠点にピッタリ、バートイシュル
ザルツカンマーグートめぐりの拠点とするなら、バートイシュルがオススメだ。バートイシュルはオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフとエリザベートゆかりの街。2人はこの街のホテルで初めて出会って婚約した。皇帝の別荘カイザーヴィラもある。ザルツブルクからもバスで簡単に来れる。ヴォルフガング湖とハルシュタット湖の中間にあるから、両方にバスで行ける。ゴーザウ行きのバスもある。ハルシュタットほど田舎ではなく、ザルツブルクほど都会でもない。大きな荷物はホテルにおいておいて、ザルツカンマーグートの山と湖を個人でまわるには便利だ。街はこじんまりとしてわかりやすいが、皇帝の別荘があるくらいだから、いにしえの典雅さの残り香のようなものが感じられる。Badとは温泉のことで、一応温泉保養地でもある。もっとも、飲む温泉が主流のようだが。ここで泊まったホテルはよかった。その名も「テルメンホテル」。「温泉宿」という意味だ。駅(バス停)からも近く、ホテルは木々に囲まれ、窓をあけると庭の鳥が鳴いている。温泉療養が目的だから、とても人にやさしいユニバーサルなつくりになっている。たとえば部屋のベッドは高すぎず低すぎず、マットレスに腰掛けてちょうど、足が床につくぐらいの高さ。部屋も狭すぎず広すぎず、ベットに座ったままチェストの引き出しをあけしめできる感じだ。季節にもよるだろうが、4つ星にしては良心的な価格設定。ロビーには「ハロー」「グッバイ」「チャオ」などと、数ヶ国語をあやつる(笑)オオムがいる。日本語もちょっと伝授してみたが、成果はあったかどうか?スイーツはカフェツァウナーがあまりに有名。ここは日曜日も開いていて、いつも賑わっている。スイーツを食べるときは、ショップで指定して、中の喫茶でお茶と一緒に注文する。ヨーロッパにしては(?)、店員はキビキビ働いている。スイーツ自体の味は… まあ、日本でも名前のほうが有名な老舗店というのがあるが、そういう感じ。ハズレはないと思う。秋にここに行ったとき、栗をチョコレートでコーティングした生菓子を食べた。「栗きんとん」オーストリア版みたいで気に入った。すごくインパクトがある、というわけではないのだが、あまり甘くなくて、栗そのものの風味がはっきりとわかる本物の味とでもいうべきか。店員さんに日もちを聞いたら「せいぜい3日」だという。えっ? そんなに短いの? と思いつつ、日本へのお土産に買ってみた。日本に戻ったのは5日後。ホテルでは冷蔵庫に入れていたし、大丈夫だろうと思っていたのだが、日本についたら、見事に腐っていた。本当に3日しかもたなかったワケね。秋にツァウナーに行った方はお試しを。ケーキより個性的だと思う。日本にはない味だ。おみやげの「塩」も、バートイシュルで買うとよい。ハルシュタットやザルツブルクで買うより同じものが安い。また、ここの塩専門店でピンクの塩をみかけたら、是非買うこと! きれいなピンクではなく、ちょっと不純物が混ざったように見える粗い岩塩で、塩なのに、なんだか甘い。とびきりの味だ。ザルツブルクで似たようなのを買った(こちらは混じりけなしのキレイなピンクだった)のだが、バートイシュルの不純物入り(?)の味にはまったく及ばなかった。ちょっと高いけど、あれを買うためにもう一度バートイシュルに行ってもいいくらいだと思っている。東京でもピンクの岩塩は売っている。だが、バートイシュルで出会ったアレ以上においしいのにはまだ遭遇していない。バートイシュルでは、安くておいしいレストランに入った。Zur Buergerstu'bn というわかりにくい名前で、場所は鐘のある広場の奥。家族経営のこじんまりとした店で、観光客もたくさん来ていた。カードでの支払いを嫌がっていたっけ。夜は有無を言わせず、「今日はスペアリブね」と注文を決められた。美味しかったが、1人分を2人でシェアしても余った(笑)。グラーシュのような普通の家庭料理もおいしかった。ジャンル分けすれば郷土料理の店といったところだろうか。決して高級店ではないが、味は折り紙つき。是非また行ってみたい。さすがにオーストリア皇帝ゆかりの街は、質の高い店が隠れている。明日はシャフベルク鉄道をご紹介します。(←世界の車窓から風に・笑)
2007.10.02
-
不実な美女は本当の美女か?
ちょくちょくお邪魔している蓮池薫さんのブログ。「地震で(自宅から)避難命令が出た」をいう記事が気になって覗いていたのだが、地震についての話はそれで一応完結したらしく、翻訳した本の作者との交流に話が戻っていった。ということは自宅は一応大丈夫だったのだろうと思っている。さて、薫さんの9月27日の記事がまた、あまりにおもしろく示唆に富んでいるので、同じような仕事の現場にいる者として雑感を書きたくなった。薫さんが挙げている米原万里の著書『不実な美女か貞淑な醜女か』。通訳・翻訳の現場を知る人間にとって、これほどの至言はない。ご存知ない方のために簡単に説明すると、外国語を通訳すとき、オリジナルの言語にひたすら「忠実に」訳された言葉はわかりにくく、美しく聞えない。逆に美しく自然に聞える通訳は実はオリジナルからはある意味で「離れている」場合が多い、ということだ。もっと簡単にいえば、米原は直訳を「貞淑な醜女」、意訳を「不実な美女」に譬えたのだ。これは翻訳の世界でも、まったくもって正しい。たとえば英語に、あまりに一途に忠実に訳されると、日本語は和文としての流れを失って硬直してしまう。また意味も非常にわかりにくくなる。言語にはその言語を組み立てるロジックがある。人は無意識のうちに自分の母語のロジックにしたがってモノを見、思考し、そして文章を書いている。その言語を母語としない限り、単語を覚え、文法を習得し、意思疎通ができるようになっても、言語間に横たわるロジックの壁まではなかなか乗り越えられない。「日本語英語」などといわれる文章は、日本語のロジックのまま英語の単語や語順にそって文を書いているからだ。また、バイリンガルといわれる人たちは、ほとんどの場合、どちらかの言語の(あるいはどちらの言語も)語彙が圧倒的に少ない場合が多い。単におしゃべりをしているときはわからないかもしれない。だが、文章を書かせたらそれは如実に明らかになる。書き言葉は話し言葉よりずっと明快に、その人がある言語に対してもっている語彙やロジックの力が露呈するのだ。蓮池さんはブログの中で、「自分の『意見』が通訳の途中に入ってしまう」と書いているが、これもおもしろく読んだ。というのは、よく通訳者の業界で、「女性よりも男性のほうが、自分の意見を入れてしまう傾向がある」というのが言われるからだ。もちろんこれは通訳の技術を磨くことで、克服していくことができる。だが、(あくまで一般的な)傾向として男性は、相手が言っていることを、そのまま「通訳」しなければいけないにもかかわらず、自分の意見や「こうであるはずだ」という一種の思い込みを無意識のうちに混ぜてしまうことが多いというのは本当らしい。それに対して、女性は相手の言わんとすることをまずは必死に理解しようと注力する傾向が高いらしい。翻訳者と通訳者の能力についても、案外世間では誤解されている。だいたいみな、通訳がうまければ翻訳もうまいと考えている。もちろんそういう人もいるが、実はそれは稀有な存在だ。それは英語の通訳業界、翻訳業界を見るとわかる。業界内では「よい通訳者は悪い翻訳者。よい翻訳者は悪い通訳者」と言われることもしばしばで、実際通訳をメインにやる人間と翻訳をメインにする人間はくっきりとわかれている。両方やっている人は実は、どちらの仕事も少ないからだったりする。有能な通訳者は常に通訳の仕事がくるので翻訳をやっている時間はない。有能な翻訳者は常に翻訳を頼まれるから、通訳をやっている時間はない―それが現実だ。英語以外の言語で通訳も翻訳も両方やる人が多いのは、要するに人材が少なく、したがって競争も少なく、通訳者や翻訳者のレベルが英語ほど高くないせいだ。通訳者と翻訳者の能力の違いは、簡単にいえば、しゃべるのが上手な人と書くのが上手な人の違いだ。文章が上手な人が話すのが上手だとは限らない。逆もそうだ。通訳者と翻訳者の向き不向きは、政治家と作家ぐらいの差がある。両方の職種とも「人に何を伝えるか」、すなわちその人のもつ「言葉」の力が非常に大切だろう。双方の素質を兼ね備えた人ももちろんいる。だが、そうした人のほうが少数派であることは納得いただけると思う。だが、米原のいう「不実な美女か貞淑な醜女か」は、通訳にも翻訳にも共通している。「貞淑な醜女」にしかなれないのはヘタな通訳者(翻訳者)だ。それは間違いない。それでは、「不実な美女」になることが、常によい通訳者(翻訳者)になることとイコールなのだろうか? 実はこれには、大きな落とし穴があるとMizumizuは思う。名訳は時として原文には一見、不実に見えるかもしれない。だが、まったく不実であっては、それはいわば「自分勝手な厚化粧で美女だと思い込んでいる」にすぎなくなる。しかも、この思い込みは、翻訳や通訳の技術が未熟な人だけではなく、ときに経験をつみ自信をもったところでひどくなる場合が多いのだ。それはある意味で、「ついつい自分の意見を入れてしまう」ということでもある。たとえ母語であっても、聞き間違えや勘違いはよくある。それはたいがい注意深く再度聞き直せばわかることだ。聞き間違えや勘違いは、純粋に聴力の問題であることもあるが、自分の知識や思い込みで「聞いた」「わかった」と錯覚することから起こるほうが多い。通訳者であれ、翻訳者であれ、ベテランになればなるほど、「自分はこのぐらいはすぐにわかる」と思い込んで相手のいうことをよく聞かなかったり、他人の文章をよく読まなかったりするようになる。なかには「この人(通訳する相手や翻訳する文を書いた人間)は言い方(書き方)がヘタだから、自分がわかりやすく直しておいた」などという人もいる――実のところ、こういうことを言うのはたいていが男性だ。ところが、それは単なる誤訳にしかすぎないことのほうが多い。相手が未熟なのではなく、自分が相手のいうこと(書くこと)を正確に理解できていない、あるいは理解しようと努力していないだけなのだ。「不実な美女」とはときとして、「自分勝手な厚化粧で美女と思い込んでいる」にすぎないというのはそういうことだ。通訳よりも翻訳のほうが、「不実」であってはいけない。通訳はある程度その場その場の勝負だし、人の話すことを伝えるのが仕事だ。人は話すときに、それほど論理的には文章を組み立てない。だから、その場で感じ取った話し手のニュアンスが伝わることが大事になる。だが、「書き言葉」を訳す場合は、じっくりと文章を読み込んで、どの程度のお化粧をすべきか、すべきでないか考えなければいけない。よく未熟な翻訳者が「どの程度意訳していいか判断できなくて…」などと言うことがある。そういう人には「とにかく直訳して」と言うことにしている。翻訳のスキルが未熟なまま「意訳」する癖をつけると、それこそ「不実な醜女」になってしまう。最悪だ。だが、正規のプロセスで構築された「意訳」は実のところそれほど原文に不実にならずに、日本語としても美しく仕上げることができる。適当に読んだところで「こういうことだろう」と書いてしまう意訳は意訳ではなく、ただの誤訳にすぎないのだ。そしてそういう誤訳は、どこか文章の筋がとおっていない。じっくり読み込んでいるときに頭の中で行われているのは、まずはその原語でのロジックで文意を理解する。それから2つの言語間に横たわる壁を乗り越えて、もう1つの言語領域のロジックの中で文章を再構築するという作業だ。これが翻訳における正規のプロセスなのだ。「言っていることはわかるけど、どう訳していいかわかならい」という場合は、言語間の壁に思考がはばまれている状態だといっていい。マニュアルのような決まった言い回しの文書の翻訳ならともかく、書き手独自の意見を起承転結で展開していくような論理性をもった文章の翻訳では、瞬時にある言語から別の言語へ置き換えることは、ほとんど不可能だ「不実な美女か貞淑な醜女か」は名言だし、まさに「言いえて妙」だ。だが、自分は不実だが美女だと思い込む通訳者や翻訳者は、厚化粧で辻褄を合わせたつもりになっている白雪姫の継母にすぎない。
2007.10.01
全31件 (31件中 1-31件目)
1