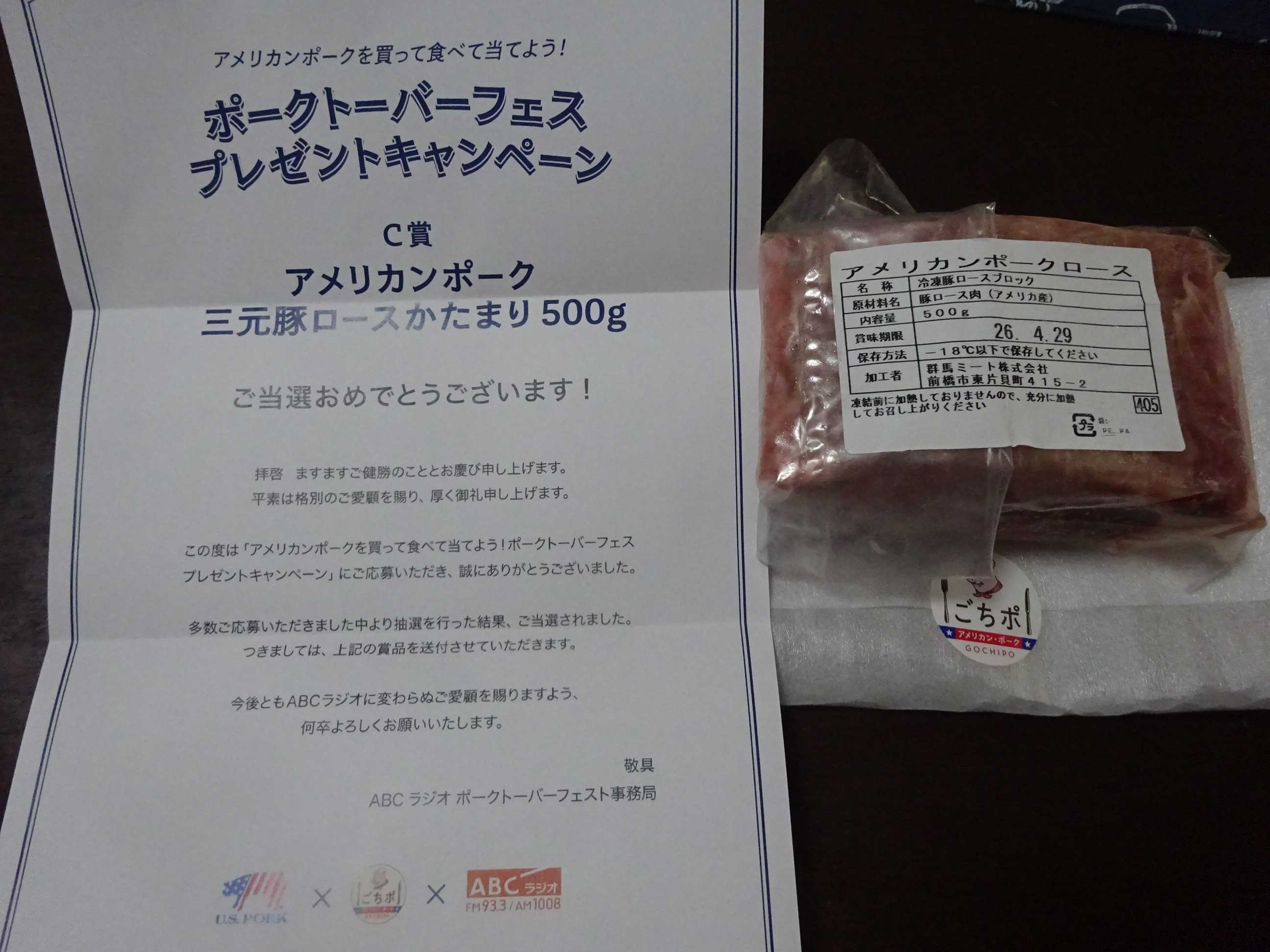2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年09月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

蟻の生活(12日目)
いつの間にか、横穴が二本つながっていた。※ちなみにこの1週間前はこう。蟻は全員元気。っていうか、いつの日記やねんコレ。
2006年09月29日
コメント(6)
-

親の呼び方
東京出張で、白金台あたりを歩いていた。女性雑誌「VERY」が起源という噂だが、巷ではこの付近の高級住宅地に住む婦人のことを俗称「シロガネーゼ」と呼ぶそうなので、てっきり地名の読みは「シロガネダイ」だと思っていたら、駅名の表示を見ると実は「シロカネダイ」であることをはじめて知った。なんで「シロカネーゼ」じゃないのだろうか。ま、それは良いのだが、そのあたりのコンビニで買い物をしていると、ご近所の真性シロガネーゼらしきご婦人が子供(娘)を二人連れて店に入ってきた。子供は幼稚園か小学校低学年ぐらいで、シロガネチルドレンにしては別に着ている服装もいたって普通の庶民の子という感じで、少々安心した。ところが、子供が母親を呼ぶ際に「おかあさま!」と言っているのを聞いて、最初はふざけているのかと思ったのだが、姉妹そろって真顔で「おかあさま、おかあさま」と言っているので、ははぁ見た目は普通でも、やはり白金台のご令嬢は育ちが違うのだなぁと感心したのであった。ワタシ自身の親の呼び方はどうだったかといえば、確か関西にいた幼少期は、父は「とうちゃん」母は「かあちゃん」であった。それが、小学生になり東京に住みはじめた頃に、なぜか父は「パパ」に、母は「おかあさん」となった。その後、母はずっと「おかあさん」であったが、「パパ」はどう考えても父の(波平的)ルックスとの違和感から次第に使用されなくなり、かわりに「あのさ」とか「ちょっと」という呼び名になっていったのであった。そして孫ができた現在は、家族全員が「じいさん」と呼んでいる。なんだかちょっと気の毒な気がしないでもない。ちなみに我が家でムスメは、いまのところワタシを「おとうさん」と呼んでいる。順調に行けば、系譜的には10年後「ちょっとちょっと」さんに昇格の予定である。
2006年09月27日
コメント(6)
-

芦屋ロックガーデン登攀記
この頃ムスメ1号とも出かけていなかったのだが、朝から秋晴れで気候も良いので「芦屋ロックガーデン」に行き、岩登りの実践練習をしてくることにした。「芦屋ロックガーデン」というのは、ロックンロールの新しいイベントなどでは決してなくて、六甲山系にある日本のロッククライミング発祥の地であり、阪神間の地元では結構有名なハイキングコースのひとつにもなっている。一般向けのコースでも普通の山歩きに比べるとかなり急勾配の岩の斜面を両手両足で登っていく少々スリリングな岩場が連続し、また場所によっては上級者向けの本格的なロッククライミングの練習場もある。幼稚園の女子にはまだちょっと難しいかなぁとも思ったが、日頃の様子を見ている限り、まぁなんとかやれるだろうと、「遠足」と称して連れ出したのであった。阪急「芦屋川」駅を降りて、芦屋の高級住宅街の中を、山の方に向かってしばらく歩いていく。駅前には、登山スタイルの老人やおばちゃんなどが何組かたむろしていたのだが、そういう人たちが結構早いペースで次々とワシら親子を追い抜いていく。市街地なので最初は緩やかな勾配ではあるが、30分ほど歩くとかなり登りがきつくなり、リュックサックを背負った背中が汗でベトベトになってきた。しばらく歩いているうちに徐々に住宅は少なくなり、ようやく周囲が緑に覆われた山道に入ってきた。後ろからは、新たなグループがどんどん我々に追いつき追い越していく。ムスメはまだ文句も言わずに、元気に歩いている。さらにしばらく行くと、ようやくロックガーデンの出発点でもある「滝の茶屋」に到着。茶屋の外にはテーブルとイスが出されていて、朝からおでんにビールで一杯やってるおやじさんなどが多数。おそらく、早朝から登っての帰り道であろう。「滝の茶屋」の店の前を通り抜けて先に進むと、すぐ目の前に最初のチェックポイントである「高座の滝」が現れる。水量は少ないが、真下から見上げると水はかなり切り立った崖の上から落ちてきており、ここから急勾配の岩登りの道になっていくことを予想させる。実際、この高座の滝を過ぎると、いきなり直登に近い急斜面が現れ、ここから先は「道」ではなく、ほぼ全面的に岩場である。それでも最初はまだ両足だけでホイホイと歩いていけたのだが、そのうち両手も使って文字通り「よじ登る」斜面ばかりになる。ただし岩場には結構大きな凹凸があるので、しっかり踏ん張れば意外と安心して登っていけるが、さすがにうちのムスメぐらいの幼稚園児で登っているような子供は皆無である。ムスメは日頃のトレーニングのせいか、まったく怖がりもせずにどんどん登っていくのだが、斜面を横から見るとそれでもかなりの急勾配で、ムスメが頭から落ちたらかなりの大怪我だろうと思うと、親の方が少しヒヤリとする。デジカメなんか撮ってる場合ではないのである。途中で、突然目の前をデカいイノシシが横切るので足を踏み外しそうになったりしつつ、登りだして1時間ほど経ったところで、これまでで一番細くて急な斜面を登りきると、突然見晴らしの良い岩場の上に出た。芦屋の市街が一望で、絶景である。ムスメが「やまびこやってよーやまびこやまびこ」とうるさいので、登山者が続々と登ってくる中、恥を忍んで20年ぶりぐらいに山の上でムスメと一緒に「やっほー」と3回叫ぶ。ちなみに、こだませず。さて、その先の行く手にまだまだ続く岩場の先を眺めながら、ふと我に返ったのだが、よく考えると帰りはこの崖を逆戻りで降りていかなければいけないかと思うと、岩場の上に立ったまま一気に全身の汗が引いてサーっと寒くなってきた。ムスメも、ここまでは調子よく登ってきたものの、この斜面をムスメを連れて降りるのは正直言って至難の業である。滑落でもさせたらエライことである。急に冷静になったワシは、本日のロッククライミングはここまでと判断し、ムスメと一緒にそろりそろりと来た道を後戻りするのであった。無事ふもとの茶屋まで戻り、ムスメにとってもさぞかし良い経験になっただろうと思い「楽しかったな、また登ろうか」と聞いてみたころ、ムスメはあっさり「しんどいし、もういかない」とのことであった。ガク。◎芦屋ロックガーデン:参考サイト
2006年09月24日
コメント(4)
-

蟻の生活(夏休み編)
今朝、蟻の巣を見ると、巣の形が大きく変形していて、おまけに蟻の数が異常に増えているぞと思ったら、これは蟻の巣ではなくて高層階のエグゼクティブフロアから見下ろした、ホテルのプールに群がる人間なのであった。今年は、ちょうどお盆の週に3日間だけ夏休みを取ることができたのだが、如何せんムスメ2号が生まれたてなので海外旅行などはもってのほか、国内の遠出もままならないのであった。まぁそれはそれでお金もかからなくて良いのだが、かといってずっと家にいると家事&育児手伝いに埋没してしまい、ただただ疲労度が増すことになるのも避けたい。となると、我が家の逃げ道はいつも安易な「近場の極楽シリーズ」となるわけで、今年は神戸空港の近くにある(学生時代にトイモイがバイトしていた)某ホテルの「エグゼクティブ・スイート」に24時間だけ滞在するという、似非(えせ)エグゼクティブ・ツアーに出かけたのであった。これはその時の写真である。かつて、たまたまホテルの都合で勝手に予約した部屋がアップグレードされていたり、他人のスイートに泊り込んだりしたことはあるが、自腹でスイートルームに泊まるのは初めてである。泊まった部屋も、当然ながら意味無く広かったりするのだが、ずっと部屋意にいてもすぐ飽きてしまうので、ワシらもプールでひたすら泳ぐのであった。はるか上空の神の眼からは、所詮ワシらもみなこのようにアリンコである。
2006年09月23日
コメント(2)
-

蟻の生活(5日目)
昨日に比べて、右上の穴がより一層面的に拡大したが、全体的にはさほど劇的な変化はない。まぁ強いて言えば、蟻の動きがいままでになく活発で、今日は全員忙しげにわっせわっせと動き回っている。特に、昼間見てもせっかく掘った巣穴の中に誰ひとり入っていなかったのだが、今日は1匹中に入っていた。説明書には「時々空気を入れ換えて換気せよ」ということが書かれていたので、上部の蓋を取ってみると、空気の流れを感じ取ったのか、全員一斉にさらに激しく動き出した。いずれにしても、元気そうでなによりである。ハルジが、しきりに「蟻のウンコ」のことを気にしているのでジェルの表面をよく観てみたのだが、どうやら太くてトグロを巻いているようなウンコは見当たらず、チリのような微細な黒い点々が所々に落ちているので、おそらくそれが糞かと思われる。また、オシッコの跡らしきものはまったく見受けられないのだが、そもそもオシッコなんてするのだろうか。屁はどうなんだろう。
2006年09月22日
コメント(4)
-

蟻の生活(4日目)
一晩の間に、右隅から伸びていた横穴が、左から出ていた横穴へとつながった。こうして目の前を横切って巣穴が貫通すると、一気に蟻の巣らしい雰囲気になってきた。しかし掘ったジェルの部分は、エサになっているとはいえ、掘るペースが早すぎて食べるのが追いつかないようで、透明な粒々が地表に散らばっていて少々見苦しい。本日も、一生懸命働いているのは、やはり一匹だけ。他の蟻はどう見てもサボっているようにしか見えないのだが、もしかすると具合が悪くて弱っているのかもしれない。そういえば、蟻の寿命ってどのくらいなんだ?考えていなかったが、こうして観察している間に、そのうち死を迎える蟻もきっと出てくるだろう。そう思うと、たかが蟻とはいえ、急に「生き物」を飼っているという意識が出てきた。しかし、さすがにまだ蟻の見分けはつかないので名前をつけるところまではいかないな。それにしてもこの蟻たち、うまい具合にわざわざ人間に見えやすい正面部分だけに巣を掘ってくれているのは偶然なのだろうか。
2006年09月21日
コメント(2)
-

蟻の生活(3日目)
3日目の朝。おおおお。昨日ちょこっとだけ掘りかけていた右隅の穴が大きく拡大し、左側に向けて横穴が伸びてきた。一方、左隅の縦穴もさらに深くなっている。昨夜も、我々が寝ている間に彼らはせっせと掘っていたようだ。自分では何もしていないのに、こうして日々着実に成果が上がっていく様子を見るのは、なんだか優秀な従業員を抱えた社長にでもなった気分である。しかしよく見ていると、実際のところ熱心に働いているのは主に1匹だけで、時々手伝っているのがもう1匹、他の連中はテキトーに要領かまして、ほとんど一日中グデーと寝ているだけのようである。このあたりの構造も、実際の会社組織に似ている部分があって面白い。
2006年09月20日
コメント(2)
-

蟻の生活(2日目)
昨日、5匹の蟻を投入したところ、いきなり住む世界が変わったことを察知したのか、蟻たちは一ヶ所に集まり互いの触角をつき合わせてミーティング状態に入った。2時間ほどそのままの状態で、まったく動かず。さらにしばらくたって様子をみると、5匹全員がケースの天井部分に張り付いていて、一向に穴を掘り始める気配がないので、この日は観察終了。2日目の朝になって見てみると、向かって左側の隅っこから3cmほど縦穴を掘り始めていた。夜中の間に、活動を開始したらしい。しかも、縦穴の先端から若干右方向に、横穴へと発展する兆候も見られる。さらによく見ると、右隅からもわずかに縦穴を掘り始めているようである。経験者の話によると、「開始してから2週間ほど経ってもまったくなんの進展もないまま蟻は全部死んでしまいました」なんて報告もあるようなので、これはなかなか幸先の良いスタートである。よしよし、この調子で頑張ってくれ。
2006年09月19日
コメント(2)
-

蟻の生活(1日目)
本日より、家で蟻を飼うことにした。仕事が忙しすぎて頭がおかしくなったわけではない。ムスメ1号が、突然「蟻の生活を観察したい」と言い出したので、以前からワタシ自身も少し気になっていた人工の蟻の巣「アントクアリウム」を入手することにしたのである。この「アントクアリウム」は、NASAの科学者たちが「無重力状態での蟻の生態を観察するための研究素材」として開発したものだそうで、2000年に実際にスペースシャトルに搭乗したそうである。まったく、そんな実験を本気でやってどれほどの意味があるのかよくわからないのだが、そういう馬鹿馬鹿しさも含めて気になっていたのである。入手したアントクアリウムは、A5サイズぐらいのクリアケースの中にアクアブルーの固形ジェルが入っている。このジェルが、蟻の巣兼蟻のエサになっていて、エサを食いながら巣を作れるという、蟻にとっては一石二鳥の環境なのである。いかにも人工的というか、極めて無機質でSFチックな雰囲気が、インテリアとしてもなかなか良い感じである。さっそく、ムスメと一緒に近くの公園まで蟻を探しに行き、手頃な大きさの蟻を発見。捕獲するときにヒトの手で触れると弱ってしまうというので、落ち葉などを使ってすくい上げ、フィルムの空きケースに入れようとするのだが、必死で逃げる蟻は意外に動きが素早くてなかなか捕まえられない。20分ほどかけて、やっとのことで5匹捕まえた。自宅に帰って、5匹の蟻をアントクアリウムの中へえいやあと投入。さあ、今日からがんばって巣を掘ってくれい。
2006年09月18日
コメント(4)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- ファジーについて考察します。
- (2025-11-20 07:39:53)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 11/20 20時〜数量限定‼️もち吉『ブラ…
- (2025-11-20 21:59:07)
-