2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年05月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

週末ゴルフ
気がついたら、前の日記からもう2週間も経っている。それまで毎日頑張って日記を書きすぎた反動ということでもないのだが、今月はプレゼンと出張がやたら多くて後半からは週末もほとんど休みがなく、さすがに深夜に日記を書く気力もないまま寝てしまうので一向に日記の更新できなかったのだ。今週末はようやく一段落で、土曜日は社内のゴルフコンペであった。クラブを握るのは半年ぶりなので、内容的にはいつも通りあまりパッとしないスコアではあったが、それはそれとして、久しぶりに外に出て体を動かし、机上のPCより遠くの景色を眺め、仲間と他愛もないことを喋っているだけでも脳がほぐれる感じがして何か少しほっとした週末であった。
2006年05月28日
コメント(4)
-

明日の記憶は何処へ往く
いま巷で話題の映画、『明日の記憶』を観てきた。観ようと思った一番の動機は「若年性アルツハイマー」というテーマ設定に惹かれたこともさることながら、なんといっても主演・渡辺謙の役どころ(主人公・佐伯)が中堅広告代理店の営業部長ということで、同じ業界に身を置く立場として、彼の仕事と生活ぶりがどのように描かれているのかに興味があったからである。で、その点についての感想を言うと、映画なので誇張や単純化している部分はもちろんあるが、それでもかなり内容にリアリティがあって感心してしまった。クライアントの宣伝課長が「○○選手ぅ、しっかりたのむよ~」なんて、あんなクライアントいるいる、とか、主人公・佐伯の「おいおいちょっと待ってくれよ、こんなんで生活者にメッセージが届くのかー?」みたいなセリフなどはホントに我々の日常風景さながらで、思わずニヤリと笑えるシーンが随所にある。さすが、原作者が広告制作会社のコピーライター出身だけのことはある。それにしても、佐伯にアルツハイマーの初期症状が出始めるあたりは、本当に見ているこちらも次第に不安、不安、不安が募ってくる。打合せの時間を忘れるとか、うっかり高速道路の出口を間違えるとか、日用品などで同じ物がまだあるのに何度も買ってくる、そんな些細なミスの積み重ねから症状は次第に深みに入っていくのだが、その程度のことは我々でも日常茶飯事のことであり、ここらでドキッとさせられる人も多いはず。(正直、ワタシはかなり該当する内容があって心配が加速中である。)なかでも極めつけは、もの忘れによるミスの連続の末、ついに訪れた病院で「簡単なテスト」を受けるくだり。「あなたの年齢は?」「今日は何曜日ですか?」などに始まり、「いまから言う3つの言葉を覚えてください、さくら、電車、・・・」といったあたりにくると、なんだかもう主人公と一緒に必死になって覚えようと焦っている自分に気づくのである。実はワタシは2年前の夏頃、原因不明の極度の頭痛と手足の痺れが続いたため、少し恐ろしくなって脳のMRI検査を受けに行ったことがある。幸い、検査結果は「過労による緊張性の頭痛」とのことで大事には至らなかったのだが、その際に見せてもらったのが、自分(健常者)の脳と、脳梗塞患者の脳、そしてアルツハイマー病患者の脳との比較画像である。そこで見たアルツハイマー病患者の脳は、ワタシの脳と比べて前頭葉および側頭葉の部分が明らかに収縮していて、暗黒の空洞部分がまるで悪魔の顔のように見えた。佐伯のアルツハイマーが確定したシーンで同様の脳の写真が出てきたとき、ふとそんなことも思い出した。当然ながら物語は、主人公・佐伯が着実に自分を見失っていく様子を描きながら進んでいく。病状が進行するにつれ、かつて彼にとって、単に仕事上のツールだったポストイットやメモ用紙が、やがて今度は自分の身の回りの家具や電化製品が「何」であるかを認識するための、生きていくうえで不可欠な道しるべに変わっていくさまが皮肉で象徴的である。ラスト近くで、ついに一線を越えたことを示すエピソードが起きるのだが、それを見た瞬間ワタシの中に起こった気持ちは、不思議なことに重いとか暗いとか悲しいとかではなく、なんとも言えないある種の「すがすがしさ」にも似た感覚であった。この病気のように、生きながらにして自分を見失うということは、事実上の死を意味する。しかし本当の死と違うところは、長期に渡って周囲を巻き添えにしていくという点で、一層タチが悪い。残されて介護する側にとっての人生は地獄であるという話も聞く。これをみて「すがすがしい」なんて思っているのはたぶん究極のエゴで、この映画は、「最善の死にざまとは何か?」について考えてみるよい機会でもある。
2006年05月15日
コメント(6)
-
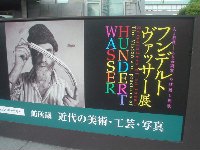
変人が世界を救う
我が敬愛するアーティスト『フンデルトヴァッサー展』を観に、京都まで行ってきた。フリーデンスライヒ・フンデルトヴァッサー(1928-2000) はオーストリア出身の現代美術家で、強烈な色彩感覚を放つ異才の画家であり、「自然との共生」を生涯のテーマにした異端の建築家でもある。フンデルトヴァッサーは、自分自身の皮膚を「第1の皮膚」、衣服を「第2の皮膚」、住居を「第3の皮膚」、社会環境を「第4の皮膚」、地球環境を「第5の皮膚」とし、彼の絵画作品はまさにこの皮膚感覚溢れる世界観によって表現されたものであり、建築作品においては特に大事にしていた「第5の皮膚」=地球環境との共存を具現化している。彼の展覧会に足を運ぶのはこれが3度目だが、今回は特に「建築」に焦点を当てていて、これまで見たことのなかった巨大な建築模型の展示などが充実していて、非常に面白かった。曲がりくねったアウトラインに樹木が絡みつく独特の建築様式は、まったく面白みのない日本のビルやマンション群などを見慣れた眼には極めて新鮮で、何度見ても胸踊らせるものがある。今回は特に、会場の展示に関する解説(岡村多佳夫:東京造形大学教授)が良かったのでご紹介。「フンデルトヴァッサーの宣言のなかでもっとも有名なもののひとつが、『建築における合理主義に反対するカビ宣言』であろう。そこには20世紀の主流として建設され続けた画一的で直線による、乾いた面白みのない合理主義建築が持つ危うさを指摘しつつ、生(なま)の自由な建築を希求した。それはカビという象徴的なものによっていっそう明瞭になる。すなわち、カビはゆっくり増え続け、建物を覆いつくしていき、建造物の直線と、それによる直角交差を破壊するからである。生き物としてのカビ、湿り気のある場所で増殖するカビ、それらは予測不能な形で広がる。それは無味乾燥な都市を人間味ある生活空間と、人間によって破壊された自然を再び取り戻すための暗示的役割を与えられる。そして、人と自然との共生がどのようにしたら可能かを、彼はさまざまな形で求めていった。」また、出口で購入した図録には、フンデルトヴァッサー自身が語る、真のエコロジストとしての強烈なメッセージが載せられていて、再びその指摘にはっとさせられる。「人間はこれまでにこの地球をめちゃくちゃにし、荒廃させたとんでもない疫病であることを理解しなければならない。人間は、この地球が再生することができるように、生態学的境界線の後ろに後退しなければならない。(中略)責任感のない人間の犯罪行為を通して、世界の終末は今までになくその兆しを見せている。私たちは自殺行為を犯している。私たちの都市は癌の腫瘍である。」
2006年05月14日
コメント(7)
-
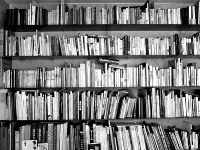
借りパチの構造
私の住む地域では、他人から借りたものをそのまま私物化してしまう行為を(借りる+パチる) =「借りパチ」という。もちろんこれはイケナイことであり、「借りたものは返す」というのは幼稚園の子供でも知っている世の中の基本的ルールである。しかしここだけの話、あらためて自分の本棚のあたりを見回すと、随分以前にヒトに借りてそのまま返せないでいる本(又は映画のDVD)などが、実はいくつかある。考えると、他人からハサミとか傘とかを借りパチしたことはないのだが、本は特に借りパチしやすい傾向があるようである。なぜか?たとえば傘とかハサミなどは、借りたらすぐ使うというのが常で、借りるときももちろん自分から貸してほしいと頼む。対して、本などは自分から頼んでいなくても「これ面白いから」と勝手に貸してくれる場合があり、また、借りてもその場ですぐ読み始めるというものでもないので、借りてから手をつけるまでにタイムラグがある。そもそも自分で身銭を切っていないせいもあって、他に読むべき本のストックがあったりするとさらに優先順位は低くなり、気が付くと平気で1ヶ月ぐらい経ってしまっていたりする。せっかく借りて時間も経ってしまったので今さら読まずに返すわけにもいかないと思い、そのうち読むつもりで手元に置いたままボヤボヤしていると、あっという間にまた1年ぐらい経ってしまう。うわーこりゃいかんなぁと思いつつ、それでもなかなか読む順番は回ってこず、そのうち貸してくれた当人とは次第に疎遠になってしまい、ますます返しにくくなっていくのである。その結果、こうしてある日本棚を眺めていると、借りパチしている本がまたひとつ増えているのに気付き、今さら返せないよなぁと良心の呵責に苛まれるのである。とまあ、ワタシの場合大体がこういう構造になっておるのである。←偉そうに言う事でもなんでもないのである。反省。借りパチをしないための方法は2つしかない。ひとつは、まず「とにかく他人から本は借りない」ということである。どうしても面白いからなどと薦められて自分もそう思ったら、とにかく自分で買うことである。ふたつめは、借りるのではなく、必ず「もらう約束をする」ことである。一旦もらってしまったものは、いつまで読まなくても一向に平気だし、返却も気にしなくて良い。しかし、一旦自分のものになった瞬間、すぐに読んでしまって一刻も早く返してしまいたくなるから不思議である。
2006年05月13日
コメント(6)
-

下り坂
先日のプレゼン結果の報告があり、結局うちの提案は不採用とのことであった。まぁ振り切った提案なので最下位か1位かのどちらかと思っていたのだが、つまり最下位だった可能性が高いわけである。メンバー全員で次のプレゼンの打合せに入っていたので、誰もことさらコメントしなかったが、やはり意気消沈の空気である。夜も更けてきたので近所のワインバーに移動して、食事をしつつ打合せの続きをする。以前贔屓にしていた店から独立した人が最近オープンしたばかりの店だが、開業早々繁盛しているようで、突き出しに凝った「ワンスプーン」が出てきたりしてなかなか料理のレベルも高く、この店の先行きは安泰のようである。閉店の時間になったので、さらに近くの公園の森に面したカフェに移動し、もう少し仕事の話の続きをする(それにしてもうちの連中はホントにいつまでも仕事の話が好きだなぁと、呆れるほどである)。モヒートを頼んだが作れないというので、トマトジュースのレッドアイで健康的に。店の外のテラス席に座っていたのだが、5月とはいえさすがに午前2時過ぎの屋外は肌寒い。しばらくすると頭上から大粒の雨が落ちてきたので、そこで解散となった。 週末は雨らしい。
2006年05月12日
コメント(8)
-

突発的再会の夜
夕方、20年来の友人であるトイモイ氏と、たまたまリアルタイムに近いタイミングでブログの書き込みをしているうちに、急遽そのまま梅田で落ち合ってミーティングを開くことになった。テーマは、特にない。トイモイ氏とは、高校生の時から陸上部の練習で毎日顔を合わせていながら、一方で互いに相手の自宅にせっせと意味不明の手紙を書いては送りつけるという極悪文通仲間であった。時を経て、手段はメールやブログに変わっても、言っている内容やノリは基本的に何も変わらないのが情けなくも誇らしいことであり、このように突発的で意味のないミーティングにも理屈は不要なのである。エグゼクティブな二人にふさわしい場所として、ワタシは「オープンエアの屋台へ」と主張し、トイモイ氏は「典型的な居酒屋へ」ということなので、折衷案としてトイモイ氏が案内してくれたのは、キタでは有名な『新梅田食堂街』という基本的にドブ板的立ち飲み屋が集積する、どこが「新」梅田なのかわからない老朽化著しい飲み屋街の一画にある「オモニ」というコリアン経営の狭い韓国スタンドであった。さすがトイモイ氏の鋭い読みどおり、表の間口が扉全開でワタシの希望に沿って無理やりオープンエアな快適空間でもあった。しかし「いつ来ても、何を頼めばよいのかわからない」と彼が言うとおり、壁に貼られたメニューを一通り眺めてもコレといったものがよくわからず、仕方なくキムチやナムルや韓国のりなどをアテに、ビールやマッコリをひたすら飲むのであった。スーハーエグゼクティブの彼は、ブログでも公表しているとおり莫大な資金にものを言わせて相次ぐ不動産物件の購入やら地上げやら追い込みやらを繰り返し、不動産王として急速にのし上がるという野望と展望を語っていたようであったが、マッコリが進むにつれて記憶の彼方である。その後、話の流れからワタシが最近よく行くBAR「ナチュラリー」へと移動したのだが、念のため電話をするとマスターのMさんはもう夜だというのに意識は寝起きだったようで、店の前に到着してもシャッターは降りたままであった。仕方なくこちらで勝手にシャッターを開けようとしたところ、ちょうど内側から同時に開けてくれたので事なきを得たが、いつもナチュラルハイなMさんは、我々の到着直前までひとりで店にあるギターアンプを引っくり返したりして不可解な行動であった。入店早々トイレに入ると、何やら可愛らしいフィギュアが置いてあったのでよくみると「沼袋民子」という名前がついていて、溺死体をモチーフにした悪趣味ながら不思議と微笑ましいキャラクターであった。カウンターに戻ると、マスターMさんは我々に向かっていきなり来月開催される自らのバンドのライブチケットのセールスを始め、ワタシはともかくトイモイ氏までも2分前に出逢ったばかりのヒトのライブチケットを半ば強引に手渡されていたのであった。その後、この店の常連客のひとりであるインド人が、実はトイモイ氏がかつてインド現地も含めて何度も接触したことのある人物であることが判明し、あらためて世界の狭さを知った夜であった。突然、トイモイ氏が「じゃ、帰ろか」と立ち上がったのでワタシもつられて立ち上がり、一緒に駅まで早足で歩いて戻った。梅田の真ん中で、それぞれの路線に向かいながら「じゃ」と別れたのだが、どうも何か心の忘れ物をしているような気がしてワタシだけひとり、フェイントでもう一度もとの店まで歩いて戻り、再びカウンターに腰を降ろしたことはあまり知られていない事実である。沼袋民子です。
2006年05月11日
コメント(6)
-

ウニかにイクラ争奪戦
「梅田の阪急百貨店で『北海道物産大会』というのをやっているから近日中に指定の品物を確保せよ」、という指令が自宅から飛んできたので、さっそく会社帰りに立ち寄ってみた。営業終了間際に滑り込みで入店し、エスカレーターを急ぎ足で駆け昇り、目指す催し物会場に到着すると、開催初日の現場はエライことになっていた。主婦のおばちゃんたちに加えて、ちょうど通勤帰りのOL様たちが殺到している様子で、催し物会場の通路は押し合いへし合いの超満員電車状態。なかなか前に進めず、ようやく目当ての人気店の前に到達すると、今度は注文待ちの人々が会場の外の階段通路にまで延々と続く長蛇の列である。北海道系の催事はすごい人気なのだと聞いてはいたが、なるほど確かにこりゃすごい。よくは知らないが超人気店の数量限定の弁当などは、「はいこちらのお客さんまでー」と列の途中で切られてしまう一幕もあり、買えなかったお客はまるで死刑宣告されたような悲壮な表情である。おばちゃんたちの中には「カニ弁当をだせ、カニ弁当を」とか「ウニ丼を返せ」などと暴動を起こしそうな勢いで猛烈に抗議するヒトもいたり、順番抜かしをした客を巡ってつかみ合いの事態が起こっていたりして、会場内は修羅場であった。そして、会場を飛び交う「ウニかにイクラ丼」や「さけイクラ弁当」など、空腹どきなのもあってどれを見ても激しく旨そうである。指令を受けた目当ての品物のうち、絶望的に客の列が長いいくつかの店は瞬時に断念し、何もないよりマシだろうと思って比較的人気がなさそうで客の少ない店に、勝手に変更。なんとかパニックに巻き込まれることなく、会場から無事撤退した。家に帰って、さっそく不人気そうな空いてる店で買ったズワイガニの握り寿司など食べてみたが、それでも十分めちゃめちゃ旨かった。ちなみにスウィーツ類も充実しとりました。あなどれない、『北海道物産大会』。
2006年05月10日
コメント(12)
-

自転車の怪(あるいは認知症の兆候)
(前日の続き)自宅に戻ってシャワーをして着替えた後、ソファで20分ほど気を失ったがすぐに起き上がり、再びプレゼンに向けて出発。昼前にはメンバー全員集合して、プレリハをする。そこで、昨晩徹夜でクリエイティブが作っていたCMのビデオコンテの映像を初めて観たのだが、比較的保守的なジャッジをする今日のクライアント様に提案するには結構突き抜けた案で、ちょっとチャレンジ的。たぶんダントツ最下位か1位かのどちらかという潔さで良い。午後からのプレゼンは制限時間キッチリで規定演技をこなし、あっけないほど殆ど質問もなく、無事終了。途中、先方の宣伝担当部長様の様子を観察していると、プレゼンを聞きながら時折下を向いて笑みを浮かべていたのだが、納得の笑みなのか、苦笑なのかは判別し難かった。この日は、メンバー全員不眠不休だったため、夕方早々には解散。ワタシは支社のボスと同僚のMさんとで、まだ空も明るい中、近所の居酒屋でしめやかにお疲れさん会を行う。その後もう一軒近くのバーへ。さほど飲んだわけではないが、さすがに疲れてきたので、その店も早々に撤退して帰る。最寄り駅に着き、駅地下の駐輪場に4日間ほど放置していた自転車を取りに行くと、ワタシの愛車・心斎橋号が見当たらない。広い駐輪場をぐるぐる歩いて全部の自転車を見たが、やはりない。盗られた?しかし鍵はかけたし、手元に持っている。おまけにここは電子キーで契約者しか入れない。寝不足で頭がおかしいのか酔っているのかと思い、もう一度探したが、やはりない。管理事務所で聞こうとしたが閉まっていたので、仕方なく歩いて帰宅。念のためにと思ってマンションの駐輪場を見ると、あれれ、心斎橋号が置いてある。しかも他人のスペースに。自転車が自分で勝手に家まで帰ったのか。しかし鍵はかかったままである。ワタシは夢を見ているのでしょうか。よいしょっと
2006年05月09日
コメント(8)
-

お早い帰宅で
GW最後の日曜日は、昆虫展を見た後、プレゼンの打合せのため午後から休日出社して深夜まで打合せ。そしてGW明けの本日は、翌日のプレゼンの準備で当然夜は遅くなるだろうなぁと思っていたが、企画書は早めに仕上がっていたのでうまくいけば終電で帰れたりして。なんて楽観的なことを考えていたら、クリエイティブの仕上がりが思いのほか時間がかかっているようで、プレゼン用の映像資料を作りに編集スタジオに詰めているワタシ以外のメンバー全員が、一向に帰ってこない。携帯メールを入れると「もうチョイ」とのことなので、とりあえず待つ。しかし2時になり、3時になっても、待てど暮らせど帰ってこない。デスクで寝ているわけにもいかないので、仕方なくブログの日記ネタなどを2本3本と書きながら待つが、全然誰も帰ってこない。おかげでブログは快調にバンバン更新されるのだが、仕事はいつ終わるのかまったく先が見えない。再び携帯メールを送ると、やっぱり「もうチョイ」との返事。結局、全員が戻ってきたのは5時過ぎ。それから資料の出力や製本などを全員の手作業でわっせわっせとやって、ようやく準備が終わったと思ったらもう朝の8時前であった。プレゼンは午後からなので一旦着替えに戻ろうと思いビルの外に出ると、通勤ラッシュの人波に押し戻されそうでつらかった。自宅に到着してドアを開くと、ちょうどムスメが今から幼稚園に出発するところで、ムスメは「おとーさん、もうかえってきたの!?きょうはむちゃくちゃはやいねー!」と驚いた顔で叫んでいた。ちがう、ちがう。12時間ずれとる。
2006年05月08日
コメント(6)
-

電脳昆虫時代
六甲アイランドのショッピングモールで「昆虫展」のようなイベントをやっていたので、買い物がてら寄ってみた。ゲーム「ムシキング」のヒット以降、逆に最近この手のリアルな昆虫にふれあうイベトをよく目にするようになった。アトリウムの限られたスペースに設けられた入場無料の集客イベントにしては、世界の昆虫の標本展示あり、生きた甲虫の観察展示あり、動く巨大昆虫ロボットの展示あり、昆虫と体力を競うゲームあり、といった感じでおそらく低予算の仕込みであろうと想像はつくが、思いがけずそれなりに充実した内容であった。コーナーのひとつに「カブトムシの森」というのがあって、大きなテントの中に入ると100匹の生きたカブトムシに触れることができるのだが、「触れ合い」のしかたが少々驚いた。入口の所に「割り箸」が用意されていて、カブトムシを触る時は素手で触らずに、その箸でつまんでくれ、というのである。まさか箸で食うわけでもないのに、なんじゃそりゃと思ったが、主催者側の思惑としてはどうやら、お客の子供が素手のままカブトムシに噛まれてクレームが来たりするのを回避しようということのようである。バイトの兄ちゃんも「お箸でお願いします!」と力強く言うので、なんだかなぁと思いながらも、ムスメと一緒にそこらにうじゃうじゃ動いているカブトムシを片ッ端から箸でつまみ上げてみるのであった。そうこうしていると、ムスメが突然へんなことを言い出した。「このカブトムシは、キカイでできてるんだよ、ほんものじゃないよ」。ワタシは笑いながら「んなわけないやろ、ほんものです、ホ・ン・モ・ノ」と言うと、ムスメはそれでも真顔のまま「ちがうよ、これはつくったカブトムシなんだよぅ!」と頑として譲らないのである。おいおい、気色悪いこと言うなよなぁしかし。「よく見てみホレ、ホンモノです」「ちがう、きかいでつくったやつ!」「ホンモノ!」「ちがう!」と、その後もムスメはなぜか妙にかたくなで、お互いの主張は平行線のままであった。「こんな、割り箸なんかでカブトムシをつまませるから、ムスメもおかしなこと言いだすんだよなぁ」と思いながら割り箸をバイト君に返してテントを出た。テントの外でふと足元を見ると、小さな金属のネジが一個落ちていた。
2006年05月07日
コメント(6)
-

落ち着くんだ。気を確かに。
また妻がクルマをぶつけてきた。これで3度目である。1度目はもう7年ぐらい前だが、買い物か何かで立ち寄った先の駐車場で、帰り際の発進でアクセルを踏み込みすぎて猛烈に急発進し、駐車場のネットフェンス(中に針金が入ったようなやつ)を突き破ったところで動かなくなり、たまたま近くにいた土木作業員のおニイさんたちに助けてもらったそうである。奇跡的にクルマにはたいした傷はなかったが、破壊したフェンスの修理代で確か数万円の弁償をしたはずである。2度目は5年ほど前、これまたどこかの駐車場からカーブを切りながら出庫するときに、ハンドルと反対側の側面ボディーを建物の角で「ガリガリガリガリ」と思い切りえぐってしまい、これは結構なダメージであった。あまりに痛々しい愛車の姿を見たときは、正直、涙が出そうになった。知り合いの整備士さんにお願いしてディーラーよりも格安の見積もりで直してもらったのだが、それでも修理代に十万円以上かかった。その後、妻がどうしてもクルマが気に入らないというので1年前に買い換えたのだが、新しいクルマになってから初めて、ついに今回の3度目である。乗ったまま路上で停めていたら、後ろからトラックが来て幅を空けろというので無理して路肩に寄せたところ、歩道との境目に立っている車止めの鉄柱でフロントバンパーを「ガガガガーー」とやってしまったようである。見た目のダメージは以前に比べるとまだマシな感じがしたので一瞬ほっとしたのだが、修理屋に持っていくとそれでもやはり数万円もの請求であった。とほほのほ。というわけで、とにかく昼間から飲むしかないのである。とある方からいただいたタヒチのビールを飲みつつ、すべてを忘れて無理やり楽園ムードの中に自分の精神を追い込むのである。らららら~♪あはははははは
2006年05月06日
コメント(8)
-

こどもの日のこと
一応こどもの日なので、ムスメが喜ぶ場所に連れて行ってやろうと思い、2年ぶりにムスメの好きな犬がたくさんいる公園に行った。2年前と同じく、この日も入場料を払って入ったというのに犬たちはまったくやる気のかけらもなく、ただ、ぐでーと地面に寝ているだけである。まぁ、毎日毎日寄ってたかって子供たちに触られたり踏まれたりしている犬の身になってみれば気持ちもわからんではないが、それにしても、あまりにもただひたすら寝ているだけである。気のせいかもしれないが、ときどき微妙に犬以外の生きものも混じっているような気がしないでもない。 いぬ。 いぬ。 いぬ。 やぎ? いぬ。 いぬいぬ。 ひつじ? いぬ。 いぬ。 ほね。おわり
2006年05月05日
コメント(6)
-

大場が撃たれた。
何気なくネットのニュース記事を見ていたら、一瞬意味がわからない見出しが眼にとまった。『本因坊戦第1局1日目終了 右辺の折衝が焦点』どうやら「囲碁」の対戦結果のことらしいのだが、ちょっと読んだだけでは何のことやらさっぱりわからない。まずこの見出しからして、いきなり謎だらけである。「本因坊」とは何だ?坊さんか?お寺か?「右辺の折衝」とは何だ?「どこか右側の方で何か小競り合いが起きています」ということのようだが、よくわからん。わからんが、気になるので内容を読んでみよう。「初防衛を目指す高尾紳路(しんじ) 本因坊(29)か、初挑戦の山田規三生(きみお)九段(33)か、第61期本因坊決定戦七番勝負の第1局は8日、札幌市中央区のホテルオークラ札幌で始まり、午後5時4分、山田が51手目を封じて1日目を終えた。(中略)」なるほど「本因坊決定戦」ね、つうとあれか、「本因坊」というのは、この高尾紳路というヒトが持っている囲碁の段位のようなものであるのだな、きっと。それにしても二人とも名前が渋いが、本名なのか?ま、いいや。で、なになに。「晴れ渡った札幌市の中心部で七番勝負が幕を開けた。対局室に高尾、山田の順に入室し、定刻まで静かに待つ。午前9時になって、立会の石田芳夫九段が声をかけ、 ニギリを行って山田の先番が決まった。」なに!「ニギリを行う」?握るのか?何を? まさか寿司を?「トロ」とか?んなワケないよな。もしかして相手のどこかを!! うわー!いやまてよ、「声をかけ、ニギリを行って」か。そうかわかった、 ニギリッペか!「やあ」とか声をかけて相手が油断した隙にニギリッペか!いやぁ、しかし囲碁の世界も卑怯なことするなぁ。ま、いっか。次いこう。「互いに星と小目を2隅ずつ占め合って布石が始まった。左上黒7、左下黒9のカカリに高尾が両方ハサミ、山田が黒11と打ち込んだことから戦い含みの展開も予想されたが、高尾は41分の長考で白12と穏やかな進行を選び、山田も黒15に43分を投じて連絡、午前中は15手のゆっくりした進行だった。」まてまてまて、これは何がなんだか全然わからんぞ?「カカリ」に「ハサミ」?何か対戦中に「係」があるのか? 掃除係とか?給食係とか? で、「ハサミ」って何だ?凶器?しかも「両方ハサミ」って、 危なすぎるよ。あと、「戦い含みの展開」ってどういうことよ?今まさに対戦中なんじゃないの? しかも「連絡」って、 囲碁の最中にいったい誰に!どこに?! 「午後になって、高尾は白16から左下を封鎖、 黒の実利と白の厚みのワカレになった。」「左下を封鎖」? バリケードか! 「さねとし」と「あつみ」って誰?で、「ワカレ」!いきなりもう別れるの?まだ登場したばっかりなのに。「その後は互いに大場を打ち合ったが、山田は36分の長考で黒31、33と打ち込み、攻めに回った。」「大場を打ち合った」? 撃たれたのか! 大場が撃たれたのか?! 山田が撃ち込んで攻め込んだのか? 大場は関係ないだろう、大場は!可愛そうに!「高尾は白36から隅で生きに回り、黒47に対して白48、50とサバキに出たところで封じ手の時刻になり、 山田が封じた。右辺の折衝がどう進むかが当面の焦点になった。 形勢判断を裏づけにした読みが必要とされる中盤の勝負所だ。<終>」出た、「サバキ」!ついに、高尾が裁きを下すのか!もう我慢も限界ってとこやね。けど、なに? それをまた「山田が封じた」の?山田も抵抗しよるなぁ。しかし結局、 最後まで記事を読んでも、いったいどこらへんで「右辺の折衝」が進んでるのか、さっぱり意味がわからんままなのである。囲碁の世界というのは、ワタシなんかが迂闊に近づいてはいけない世界のようである。
2006年05月04日
コメント(6)
-

祭りの後は
会社の後輩Y君の結婚披露パーティーに行ってきた。場所は大阪ミナミの「いまどきこんな店まだあるの?」という感じのバブリーな匂いがプンプンするパーティー会場なのだが、なぜか当日の演出コンセプトは『祭り』ということで、会場の入り口で会費を払うと全員うちわを手渡され、会社の若手を中心とする幹事連中一同が揃いのハッピ姿で走り回っていた。シックでゴージャスな店の雰囲気とはまったく関係なく、BGMはすべて「ナントカ音頭」であり、会のオープニングからいきなり激しい和太鼓の音とともに「♪ま~つりだぁ、まつりだまつりだぁ~」と北島三郎の唄声が大音響で流れ出し、新郎新婦は神輿(みこし)に乗って登場という、不思議な演出であった。それにしても、この前の送別会もそうだったのだが、最近うちの会社(というか支社)はこういうことにかける時間と費用と労力がだんだんエスカレートしてきている気がする。神輿だってこの日のためだけにわざわざ制作したようだし、この日もまた新郎新婦の馴れ初めから結婚に至るまでの「イメージ映像」をクリエイティブスタッフが作っていたのだが、これがまた爆笑と感動のツボを絶妙に押さえた無茶苦茶クオリティの高いもので、もうこのまんまテレビで流しても問題ないレベルである。最近、毎日毎日社内中が皆忙しそうだと思っていたら、おそらくかなりの人数がこのイベント準備にかかりっきりだったようである。まったく、どいつもこいつもふざけすぎであり、実に素晴らしいことである。しかしながら、映像で公開されたエピソードによると、新郎のY君はかなり自分勝手野郎な性格で、どう見てもワタシと違って無難に家庭生活を乗り切るには不向きなタイプである。祭りの後が「後の祭り」にならぬよう、共同生活を生き抜くためのワタシのモットーである『妥協と諦め』をしっかり肝に銘じて、日々精進してほしいものである。
2006年05月03日
コメント(4)
-

日記燃えつき症候群
この4月は、自分史上初めて1ヶ月間毎日連続で日記を書いた。正確には、3月の後半から40日連続である。まぁホントは後日まとめて埋めたりもしていたので「日記」ではないけれど。それにしても、この飽きっぽい性格のワタシが、自分でも1ヶ月以上も続くとは思わなかった。しかも4月は結構ホントに忙しかったので、実際のところかなり睡眠時間を削り、半ば意地になって書いていたような感じである。最初の10日間ほどは、まぁ意外と大したこともないかな、と思いつつ毎日快調なペースで書いていた。毎日書いていると、うちのような地味なサイトでも日々のアクセス数のベースが以前の5倍~8倍ぐらいに上がってきたのでエライもんやなぁと思い、少しだけ励みになった。しかし月の中盤にさしかかり、仕事の忙しさが激ピークになっていた頃、さすがに毎日書くのがキツくなってきて、頭の中で一瞬「もうやめてもいいんだよ」と悪魔の囁きが聴こえたのだが、その誘惑を振り切ってなんとかピークの数日を乗り切ると、逆に今度は忙しい状態で書くのがなんだか妙に気持ち良くなってきて、どんなにくだらない内容でも、書くのがまったく苦にならなくなってきた。もしかしてこのまま行けるかなと思っていたら、再び最後の1週間がキツかった。むしろ仕事の方は少し沈静化してきているというのに、今度は時間があっても全然書く気が起こらないのである。またも悪魔の囁きが「ほら、無理しなくてもいいんだよ」「そろそろやめて、ラクになろうよ」と耳元で誘惑するのをなんとかこらえて書き続けるのは相当ツラかった。日記のテーマがくだらないのは普段からであるが、最後の1週間はもう「枝豆」だとか「スパイ」だとか本当にどうでもいいことの羅列で、まったく苦し紛れもいいところである。毎日毎日休みなく、同じペースで日記を書き続けられるヒトというのは、ホントにすごいなぁと実感した次第である。どうにかこうにか1ヶ月間完走を果たしたものの、当然ながら誰からの賞賛もなければご褒美もなく、唯一の変化といえば若干のアクセス数の増加と、常連さんとの“書き込みュニケーション”がやや活発化した程度であろうか。というわけで、今後は再び平常運転に戻って、いつもどおりのえーかげんペースで、気が向いた時だけ書くことにしよう。燃えつきて真っ白クマ
2006年05月02日
コメント(6)
-

グラスの中のオアシス
淡路から戻り自宅に家族と荷物を置くと、再びすぐさま大阪のオフィスへ出社。夕方から、どうしても外せない打合せなのである。ほんの3時間前まで淡路島にいたのだが、そんなことは周囲に素振りも見せず、頭を無理やり仕事モードに切り替えて打合せに入る。30分も打合せしていると、まるで朝から会社で仕事をしていたような錯覚に陥ってしまうのだが、我ながら変わり身の速さにあきれる。しかしそこからさらに3時間ほど打合せをすると、さすがに疲労が押し寄せてきて、次第にヘトヘト感が充満。同僚たちとオフィスの近くのたこ焼き屋に寄り、ついでに通り道のバーで今夜もモヒートを一杯飲んで帰る。ふと思ったのだが、ワタシの好きなモヒートの中にはミントの葉というミニチュアの自然が入っていて、ワタシはたぶん潜在的な欲求としてグラスの中のオアシスを飲んでいるのである。
2006年05月01日
コメント(8)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-

- 楽天写真館
- 20 日 ( Thursday ) の日記 リズ…
- (2025-11-20 05:20:01)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- ブラックフライデー2h全品 半額〜…
- (2025-11-19 18:48:00)
-








