2008年04月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
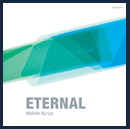
クリヤ・マコトのミニアルバム、エターナル
この前の日曜日に我友クリヤ・マコトが食事をしにきてくれた。 最近彼が出したミニアルバム、エターナルももってきてくれた。いつも新譜が出ると私に一枚プレゼントしてくれるのだ。その代わりというわけではないが、うちの店では彼のCDをいつも何枚か販売している。 このエターナルというアルバムは、CDショップでは販売されていないので、クリヤのライブ会場で買うか、彼のホームページからの通販でしか手に入れられない。 うちの店は、日本で唯一のクリヤ・マコト公認のCD直売場!である。しかも品物は本人が持参する産地直売!?だから鮮度が違います!?? このアルバムは、普段わりとエモーショナルというか熱いイメージのクリヤの音楽とは一転、とても静かで抑制のきいた癒し系の音楽が聴ける。 ¥1900で販売してます。
Apr 29, 2008
-

アイスバインのゼリー寄せテリーヌ、フォアグラ風味
アイスバインのゼリー寄せテリーヌ。 アイスバインというのはドイツ料理名で、豚肉の前足の皮付きスネ肉の塩漬けを柔かく茹でた物に、塩胡椒とマスタードなどを添えて食べる料理だ。 皮付きスネ肉は、コラーゲンの宝庫。茹でてその煮汁とあわせて冷やせば、そのままゼリー寄せになってしまう。このテリーヌには、せっかくだから中心部に火を通したフォアグラも入れてちょっと風味をつけてやる。 ひき肉で作るいつものテリーヌもいいけど、こういうゼリー寄せもなかなか良いもんですよ。評判がよければ、しばらく作っていこうかと思っています。 フレンチでは、こういうゼリー寄せのテリーヌというと、、、Fromage de téte de cochon とか、Fromage de téte de veau などという、豚や仔牛の頭の肉で作る伝統的な料理もある。味や食感は似ているかもしれない。
Apr 25, 2008
-

筍がそろそろ終わりかな?
竹冠に旬と書いて筍という。旬というのは、一月を10日ずつに分けて上旬中旬下旬などというように10日間を表す言葉だから、まさに筍は10日もすれば時期が終了するわけで、名は体をあらわすという事ですね。 一昨日も岳父がどっさりと取り立ての筍を取ってきてくれたのだが、「多分今年はこれで終わりだろう。」とのことだった。 このところもう6~7年も毎シーズン筍を使っているので、だいぶ研究が進み保存法や調理法を確立してきたから、しばらくの間は筍料理を出す事ができるだろう。 そうこうするうちに入梅時になると、真竹の筍も出てくる。 これは去年の画像。真竹の子。これもあくがなくて柔かくて美味しい。 そして、真竹が終われば本格的に夏野菜の季節だ。
Apr 24, 2008
-

4月のシェフお勧めコースの詳細(デザート)
デザートは、ミックスベリー風味のパウンドケーキと南仏産の完熟苺を使ったシャーベットとコアントローというリキュールで和えた生の苺の3種盛り合わせ。 パウンドケーキのレシピは、元三ツ星のジョエル・ロブション氏のものをもとにしている。バターをリッチに使った風味豊かな味わい。生地にはドライクランベリーやラズベリー、チェリー、カシスなどのコンポートを混ぜ込んである。 シャーベットは、南仏産の完熟苺を現地でピュレにして瞬間冷凍した物を使って少しだけ砂糖を加えて仕上げた物。日本の苺より赤みが強く、甘味も香りも強い。 それから、千葉県は美味しい苺の産地でもある。地元産の新鮮な苺をほんの少しのコアントローで和える。コアントローは、ホワイトコニャックベースのオレンジリキュールの事で、いわゆるオレンジキュラソーのトップブランドだ。苺にほんのわずかなリキュールの香りを絡めるだけで、驚くほど美味しくなる。
Apr 17, 2008
-

4月のシェフお勧めコースの詳細(フランス産ウズラのサラダ)
魚料理のリゾットがけっこうボリュームがあるので、メインはウズラのソテーのサラダ仕立て。 サッパリとした自家菜園の有機サラダにフランス産のウズラを丸一羽をさばいて、皮目をカリッと身はしっとりとソテーする。 サラダのヴィネグレット(ドレッシング)は、ワインヴィネガーと上質なオリーヴオイルで作ってある。 ウズラという鳥は、鉄分が多く旨味が濃い上に上手に焼けば、クセがなく柔かくてとても美味しい。複雑な味わいが繊細なブルゴーニュワインによく合うのではないかと思う。 ソースもなく軽い料理なので、この料理には若い当たり年の2005年のブルゴーニュ・ルージュを少し冷やして用意してあります。
Apr 16, 2008
-

4月のシェフお勧めコースの詳細(リゾット)
イカ墨のリゾットです。イカ墨料理の本場は、イタリアやスペイン。この料理にもスペイン産のイカ墨(大きな墨烏賊の墨袋だけを集めて冷凍した物)を使っている。 イカ墨ソースの作り方はいろいろあるのだが、墨の旨味を最大限に生かしながら墨のクセを上手に押さえ込むかが、肝要なところだ。 私のイカ墨ソースは、このようにまーーっ黒なのだが、こう見えてほとんどトマトソースなのだ。 いわゆる、ソースプロヴァンサル。ニンニク、オリーヴオイル、トマトだけで作るソースに重量比にして5パーセントほどのイカ墨を入れ、ミキサーにかけて漉して仕上げる。そこにパプリカをたっぷり加えてさらにイカ墨のクセを押さえ込む。 マリネして下味をつけて温めたホタルイカとソテーした帆立貝柱を添えて、帆立にはボッタルガ(イタリアのサルディニア島産のカラスミの粉)をかけてある。 カラスミというのは、魚卵の生ハムみたいなものですね。つまり、卵を塩漬けにして乾燥熟成するわけです。日本ではボラの卵巣で作る長崎産が有名ですが、元々は中国から入ってきたもののようだ。 カラスミという名前も「唐の墨」(中国産の墨。毛筆で字を書くために硯でするあの墨ですね)にボラの卵巣の形が似ているところから来ているらしい。 塩漬けの魚卵は、地中海沿岸諸国でもよく食されている。南フランスやイタリアの海沿いや、もちろんスペインでも作られているが、中でもイタリアのサルディニア島産が最高級品として有名だ。やはり一番はボラの卵巣で、そのほかにもマグロの卵巣や鯛やスズキなどでも作られている。 姿のままの物は、スライスしてそのまま食べたり、軽くあぶってガーリックトーストに乗せたりサラダに散らしたりして食べる他、おろし金で卸して粉にしてパスタやリゾットに散らして食べると美味しい。 やはり、手間と時間をかけて作るものだからかなり高価な珍味だ。キャビアほど高くないですけどね、、、。 イカ墨リゾットに唐墨を添えるという墨つながりの料理ですね。別にしゃれではありませんが、、。最後の仕上げにサルディニア島産の香りのよいオリーヴ油をかけてある。 イカ墨、トマトの酸味、ニンニクの旨味と香り、カラスミ、パルミジャーノチーズ、パプリカ、オリーヴ油、少しのバターなどの複雑な要素が絡み合ってアルデンテの米の食感を引き立てるという料理です。普段はあまりやりませんが、自慢のスペシャリテです。
Apr 16, 2008
-

4月のシェフお勧めコースの詳細(前菜)
前菜は、イタリアパルマ産の生ハムとスペインのイベリコ豚のチョリソ・ベジョータに定番の自家製もち豚のハムの盛り合わせ。 生ハムは、約7キロあまりの原木物からの切りたてを召し上がっていただきます。 イベリコ豚のチョリソ・ベジョータは、スペインから取り寄せた本物。チョリソというとちょっと辛いウインナーだと思っている方も多いだろうが、本物は生サラミの一種だ。 生サラミというのは、肉の発酵食品のことで、普通はひき肉を使う事が多いが、このイベリコ・チョリソ・ベジョータの場合は、ひき肉にしないで粗く切った肉をパプリカやニンニク塩胡椒などで調味して豚の大腸に詰めて涼しいところに吊るして乾燥発酵熟成させたものだ。製造過程で全く加熱処理はしない。 非加熱なのになぜ悪くなってしまわないかというと、ある種の乳酸菌が繁殖して酸性の環境になり雑菌の繁殖が抑えられるというわけ。だから食べると少し酸っぱいし、乳酸発酵特有のちょっとヨーグルト的というかキムチ的というような風味がある。とても奥行きのある複雑な味わいで、生ハムにしてもこういうサラミ類にしてもヨーロッパの肉食の歴史の奥行きを感じる食品だと思う。 もうひとつ、定番ながら日々進化しているもち豚のスモークハム。これだけは、加熱して火を入れたハムだ。 南房総の養老渓谷で作っている美味しいもち豚の肩ロース肉をフランスのカマルグ産の海塩で4~5日漬け込み、4~5時間かけて低温でゆっくり火を通す。一晩冷蔵庫で落ち着かせ、桜のチップで8時間ほど冷燻にかけてから、氷温庫で1週間ほど低温熟成させて仕上げた物で、これは私の手作り。 やはり何といっても豚肉は脂が美味しいし、また脂が美味しくなければ良い豚肉とはいえないだろう。スペインのイベリコ豚は、秋になると山に連れて行って放牧し森のどんぐりをたっぷり食べさせて脂をのせる。その中でも健康で食欲旺盛な豚で、放牧後に体重が1.5倍以上になった物の中から、霜降り具合などの肉質の基準をクリアした物をベジョータと言って最高ランクの肉とする。つまり放牧前には、100キロほどの豚が150キロ以上の霜降り肉にならなければならないのだ。 豚というのは太りやすい動物だから、ゲージ飼いにして運動させずに高カロリーの餌を与えれば簡単に1.5倍くらいに増えるのだが、イベリコ豚の場合は山で放牧するため、豚は自力で餌を探すから、かなり運動量がある。だから、元気が良くて生命力が強い豚しか規格をクリアできない。体重が足りなかった物は山から下りたあとに肥育して、イベリコ・レセボというワンランク下の肉になり、イベリコ豚の品種ではあるが放牧はしない豚舎飼いの場合はピエンソという規格の肉になるようだ。 イベリコ・ベジョータは、そういうわけで世界でも最高峰の豚肉だから、値段も高い。ベジョータの後ろ足を使って作られた生ハム、ハモン・イベリコ・ベジョータは生ハムの中でも最も値が張る。一本十数万円から二十万円を超えるほどの物もある。 そのイベリコ・ベジョータで作ってあるこのチョリソはやはりかなり美味しいですよ。 今4月のコースの前菜で出してます。
Apr 16, 2008
-

筍の季節
桜が終わるころ、筍が出てくる。わが岳父は筍取りの名人。 サンク・オ・ピエの自家菜園がある成田の竹林から毎年新鮮な筍を取ってきてくれる。 いつも掘ったらすぐ届けてくれるようにお願いしてあるので、湿った土が付いた竹林の香りがたっぷりする新鮮な筍を届けてくれる。 筍は何といっても鮮度が命!掘り出してからいかに早く下茹でしてしまうかが勝負の分かれ目。よく和食屋さんで京都から筍を取り寄せたとか言って自慢する店があるが、どんなに一流の産地だろうが、掘り出して半日も経てばすっかり味は落ちてしまうのだから、じつは何の意味もない。 アスパラガスなどもそうなのだが、、掘り出したり刈り取ったりするとその刺激が発端になって、木質化をはじめる酵素が働きだすのだ。 だから時間が経つほど固くなり不味くなってしまう。 もちろん、きちんと手入れして肥料なども与えた竹林で食用に育てている筍農家の一級品が、掘り出して30分くらいで手に入れられたら言う事はないのだが、、鮮度が落ちた一級品より鮮度がいい野生の筍のほうが、よほど美味しい。 日本のフランス料理店では、この時期フランスから空輸されるホワイトアスパラガスを自慢げに出している店が多いが、いくら空輸とはいえどうしても収穫してから2~3日は経ってしまう。ホワイトアスパラのフランス物はかなり高くて、上物だと1本500円もすることがあるが、それでも私に言わせれば所詮鮮度の落ちたB級品でしかない。 結局、アスパラも筍も取ったらすぐ茹でるのが大原則で、取り寄せ物は本当は意味が無い。 それでも、フランス物のアスパラや京都や広島の一流産地から取り寄せた筍に大枚をはたいて喜ぶ人もいるので、、、まあ、商売としては否定しませんがね、、、。 とにかく、この時期のサンク・オ・ピエは、筍です!フレンチに筍?と思うかもしれませんが、美味しい素材なら何でも使いこなすのがプロというもの。 それに筍の穂先はまるでアーティーチョークの芯のようだし、少し太いところの食感と甘味はまるでホワイトアスパラガスのようだ。さらに日本人なら誰でも感じるはずの、圧倒的な春の季節感!これほど素晴らしい季節の素材が他にあるだろうか? しかも、いつ取れ始めていつ無くなるかは天候しだい。実に儚いところがまた日本的でいいですよね。食べ逃せばまた来年までお預け、、。美味しく口に出来れば、毎年の桜を見るときのようにまた一年歳を重ねてきた実感を感じるような、、。 このようにマリネにした筍をサラダに添えたり、、、 このようにフォアグラのソテーの付け合せにしたり、春野菜と一緒にスープに仕立てたりもするし、もちろんメインディッシュの付け合わせにもなる。 毎年こんなブログを書くと、「筍はいつまで食べられますか?」という問い合わせがよく来るが、、、それは無粋な質問ですな。「そいつぁ、筍に訊いてくれ!」という事です。 フレンチの店に毎年筍を楽しみに来る常連さんがいるんです。お客様に出す以外にも、自分や身内のため作る筍ご飯や若竹の吸い物なども楽しみなのだ。
Apr 13, 2008
-

新レギュラーメニュー、穀物肥育の仔羊のロースト
これは、穀物肥育の仔羊の背肉のクローズアップ。和牛というほどではないが、ちょいと霜降りなのが分かります? 食肉の食味というのに最も影響を与えるのが餌。高カロリーの餌を与えれば、当然太って脂が乗るわけだが、カロリーだけ高くて質の悪い餌を食べさせた肉は臭みが出て美味しくないし脂もしつこい事が多いのだが、質の良い餌を食べさせて適度に運動させた肉は癖がなく旨味が乗って脂もしつこくない。 それから、牛も羊もそうなのだが、、、牧草など草だけで育てると獣臭が強くなる。日本では獣臭が強い肉は人気がない。 かつて、アメリカの牛肉が問題なく自由に輸入されていたころは、アメリカ牛はいち早く日本向けに穀物肥育の牛肉を作っていたので、、、、オーストラリア牛は臭くて安物、アメリカ牛は癖がなくて上物という図式が成り立っていた。 その後オースト物も日本向けに穀物肥育肉をやり始めて、今は出荷前90日ないし120日ほど穀物飼料を与えて日本人に人気がある肉を作っている。 オーストラリアの人たちは、どちらかというと草で育てた少しクセがあるような肉を好む事が多い。 魚が大きらいな人が、普通は感じないような微妙な生臭みを鋭く嗅ぎつけたりするでしょ?日本人ってやはりまだまだ肉がとことん好きではないかもしれないですね。あまりにクセがないとオーストラリアの人たちには物足りないのかもしれません。 仔羊も特有の香りを臭いといって嫌う人は少なくない。 今まで日本に輸入されていた仔羊は、牧草中心の飼育肉だったのでどうしても風味が強い物が多かったのだが、この肉は穀物で育てたので脂の乗りも良いし、クセもない。 この肉を弱火で約1時間かけて低温でゆっくり焼き上げる。生肉より柔かく、臭みがなくジューシー!脂も甘味があってきれいな味。骨までガッツリしゃぶりたくなるはず。
Apr 8, 2008
-

4月のシェフお勧めコース
これは前菜の盛り合わせ。パルマ産の生ハムは手切りの切り立て、チョリソー・イベリコ・ベジョータと私の手作りの養老渓谷産もち豚のスモークハムに黒オリーヴとピクルスとグリーンオリーブのマドリード風マリネを添えてある。 これは、直径40cm近い大きな皿に盛り付けてあるので、けっこうたっぷり!仕上げにはサルディニァ島産の極上のオリーヴオイルを垂らしてある。 豚肉の美味しさは、もちろん赤身の旨味ももあるのだが、、やっぱり脂の美味しさにある。豚肉にオリーヴオイルをかけると異なる脂肪酸の旨味が重なって旨味が格段にあがるのだ。もっとも香りがよい上質なオリーヴオイルじゃなければ駄目ですが、、、。
Apr 6, 2008
-

ホタルイカ
ホタルイカの季節ですね。日本海側で今頃採れる小さなイカですね。小さいけれどこれで大人で、普段は深海にすんでいるのですが、この時期産卵のために海面近くまで浮いてくるので、春はホタルイカ漁が行われるというわけだ。上の画像は下処理を終えた物なのだが、どこをどうしたか分かりますか? 実は、ピンセットを使い軟骨と目玉とクチバシを取り除いてあるのだ。 こういうことです。けっこう細かい仕事でなれないと時間がかかります。私の場合はもうすっかり慣れているので、一匹5秒もかかりません。 こうやって食べてみれば分かりますが、食感が全く違う!実に美味しく感じます。こういうことが、プロの仕事なんですね。 軽く塩をして、少しワインヴィネガーをたらし、パプリカとカイエンヌペッパーそれに少しオレガノを加えて、ガーリックオリーヴオイルをかけて和えておく。これでスペイン風のマリネとしてそのまま食べてもいいが、耐熱の器に入れてオーブンで焼いても美味しい。
Apr 5, 2008
-

パルマ産生ハム到着です!!
1本約7キロあまり、パルマ産の生ハムです。4月のコースにあわせて、今回は4月1日に入荷。これを愛用の刃渡り40cmほどの牛刀でスライスして、切りたてを召し上がっていただくのがうちのやり方。 パルマでは、厳しく法律で規定された伝統的製法が守られていて、豚の品種やその餌や飼育の方法なども細かく規定されているのだが、面白いのはこのパルマ地方のもうひとつの名産物であるパルミジャーノチーズ(パルメザン)を作るときに出るホエーミルクを必ず与える事が義務付けられている事だ。ホエーミルクとは、チーズを作るために、まず牛乳を凝縮酵素で固めるわけだが、そのときにチーズになる固形分と、分離して出てくる液体部分があり、その液体をホエーミルクというのだ。 ホエーには、チーズの主成分たるたんぱく質や脂肪分がほとんど取られてしまっているが、ミネラルやビタミン アミノ酸などがたっぷり含まれているので、むしろ豚にとっては低カロリーなヘルシードリンクという事になる。 世界3大何とか、、と言うのがいろいろあるが、生ハムはこのパルマのハムとスペインのハモンイベリコにフランスのバイヨンヌハムという事になっているようだが、その中でも一番さっぱりしていて赤身の美味しさを味わうタイプの生ハムがこのパルマの生ハムだろう。その赤身のおいしさを高めているのが、このホエーだという人もいるようだ。 まあ、確かにパルミジャーノのような世界でもトップクラスの美味しい高級チーズの副産物を餌にして育つのだから、物凄く特別な豚である事は間違いないだろう。 そのようにして、規定どおりに作られたハムでも最後に1本づつ厳しく検査されてそれをパスしなければパルマのシンボルである王冠の刻印を押してもらえないのだ。
Apr 3, 2008
全12件 (12件中 1-12件目)
1










