2008年03月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

白菜の菜の花
これは、とうが立った白菜の菜の花。春になって急に暖かくなると白菜が縦方向に伸びてしまって、放っておくと花が咲く。一般的に出回っている菜の花は、アブラナの花だが同じアブラナ科の植物である白菜やキャベツ、高菜や野沢菜、蕪やコールラビなどアブラナ科の仲間はみな同じような花が咲くし、もちろん蕾を集めれば、菜の花と同じように食べる事ができる。 これは、サッと茹でて冷水に取り絞ってトレーに並べガーリックオリーヴオイルをかけてオーブンで温めた白菜の花芽。アブラナの花より繊細で軽い味わい。今付け合せに使っている。
Mar 31, 2008
-

ホームページを大改装しました。
この2週間ほど休みをつぶし、寝る間を惜しんで約50時間あまりを費やしてホームページを大改装しました。というか、ほとんど完全に作りなおしました。 というのも、このところ原材料の値上がりが激しく、、フォアグラなどはこの数ヶ月で1.5倍にもなり、その他の材料もユーロ高のせいもあって軒並み高騰してます。 その上、オーストラリアの干ばつが長引き、バターやチーズなどの原料となる原乳の生産が落ち込み世界的に乳製品が高騰しています。他にもコーヒー相場も高騰、牛肉や仔羊なども例外なく、中国産食品の安全性の問題から、国産の野菜や肉の相場も高騰を続けています。 愚痴を言えばきりがないのですが、サンク・オ・ピエとしても値上げをせざるを得ない状況になり、、、値上げに伴いホームページのご案内を書き換えようという事になり、、、、そうなるとどうせなら、一気に作りなおしたほうがいいかもしれないという気になってしまったわけです。 と、いうわけで何とかやりました。ホームページ リニューアルです。 疲れました、、、。で、ストレッチ、、、、、。
Mar 28, 2008
-
桜
敷島の大和心を人問わば 朝日ににほふ 山桜花 たしか こんなうた。 本居宣長だったか、、、
Mar 28, 2008
-

イベリコ豚のベジョータのチョリソ
チョリソーというのは、ただの辛いウインナーのような物だと思っていませんか?本物は、スペインのイベリコ豚の肉をパプリカ(スペインではピメントンと言いますが、、)やニンニク胡椒などで調味して同じくイベリコ豚の大腸に詰める。そうして、乾燥熟成させたものだ。 いわゆるヨーロッパのサラミの類は、このように豚の肉を腸詰にして乾燥熟成して仕上げる物がほとんどだ。このようなサラミの場合乳酸菌が繁殖して酸性傾向になり雑菌の繁殖を抑えるのだ。 だから、サラミの類は食べると少し酸っぱい。日本で普通に売っている日本のメーカーのサラミは、見た目は似ていても大抵火が通っていて、乾燥熟成して乳酸発酵させたこのようなサラミとは全く別物だ。 とにかく、イベリコ豚は脂がうまい。それが少し酸味をもってピメントンの甘い香りと一緒になって、、あーー、マンサリーニャ・パサダ・デ・サンルカールもってこい!!!
Mar 20, 2008
-

秋までお別れ、、自家製スモークサーモン
自家製のスモークサーモンは、だいたい11月から3月ころまでしか作らない。なぜかというとサーモンは冷燻にかけるので煙に当てている間に30度以上になってはならないから、気温の低い季節にしか作ることが出来ない。まあ、大掛かりな設備を使えばもちろん可能なのだが、私の場合は段ボール箱を利用した簡便な仕組みで燻製を作っているので、中に氷を入れたりして温度を下げる努力はするが、どうも肌寒いくらいの季節でないとうまくいかない。魚は火が入りやすいので40度以上にあがると魚が白っぽくなってしまうのだ。 愛用のナイフ、刃渡り35センチあまり、刃幅が2センチ弱の薄刃のサーモンスライサーでこのように横に切っていく。 こんな感じに少しサラダが透けて見えるくらいに切れれば、口解けが良い。昨日今シーズン最後のスモークサーモンを仕込んだ。これが終われば、今年の11月までお別れ。代わりに4月から10月までは毎年イタリアパルマ産の生ハムをお出ししている。 桜の咲くころこのパルマ産の生ハムが届きます。
Mar 20, 2008
-

タコのガリシア風
タコのガリシア風です。スペインの北西部の太西洋沿いの地域がガリシア地方。リアスバイシャスという入り組んだ海岸線があって、これがリアス式海岸の語源だ。 スペインで最も魚介類を好む地域でもある。ヨーロッパではあまりタコは食べる事はない。特にイギリスではデビルフィッシュと呼ばれ、忌み嫌われていたりする。 パイレーツ・オブ・カリビアンなどの海賊映画などを見ても恐ろしいタコのお化けが出てきたりしますね。 イギリス人はまず食べないし、フランス人もあまり食べません。地中海地方の人は食べますが、誰もが食べるわけではありません。南イタリアの人になるとかなり食べますね。 スペイン人はかなり食べますね。特にガリシア地方は世界でも有数の魚介類の宝庫ですから、ムール貝や牡蠣の養殖も盛んで様々の魚介類が取れる。 スペインのタコ料理というと、タコのアリオリソース、アリオリソースというのはオリーヴオイルで作ったマヨネーズにおろしニンニクを混ぜたような物だ。美味しいけどちょっと匂いが強烈ですかね。もうひとつはこのガリシア風のタコ。これはパプリカをたっぷりふりかけ、塩を好みで少々、上質なオリーヴオイルで仕上げるというシンプルな物。 本場では、茹で上げの熱々を食べる事もある。特にタコをゆでるときにガリシアではローリエと玉葱を入れる。香り付けのローリエと玉葱はタコを柔かくする作用があるという。 この画像の料理は、私のアレンジで、スペインの二大タコ料理の折衷のスタイル。普通の茹でタコに薄い味付けのアリオリソースを皿に敷きタコを並べ、カマルグ産の塩を挽きかける。ガーリックオイルを回しかけ、カイエンヌ・ペッパーをほんの少しとパプリカ・パウダーをたっぷり振り掛ける。 ガリシア地方の美味しい白ワイン、リアスバイシャスのアルバリーニョ種の葡萄で作られた辛口白ワインなどあわせたい。もちろん、シェリーの辛口軽口タイプ、フィノやマンサリーニャなども最高だし、スペインのシャンパーニュといわれたカヴァなんかもいいでしょうね。またスペイン人のように若くて軽い赤ワインを飲んでしまっても、パプリカが効いているから不愉快ではないはず。 ちょくちょく定番のメニューでやっています。
Mar 19, 2008
-

ポタージュ・サンジェルマン
これは、ポタージュ・サンジェルマン。グリーンピースのポタージュです。まず、新玉葱をバターで甘味が出るまでゆっくり炒めます。そこに小麦粉をそうですね、豆が1キロなら大匙山盛り1杯くらい入れて玉葱になじませます。そこに豆と薄いブイヨン又は水を入れて強火で一気に火を入れる。 昔はポタージュ・サンジェルマンというとすっかり火が通って緑色がくすんだような食欲をそそらない感じのものが普通だったが、私の場合は一気に沸かして火を入れてミキサーにかけて漉したら、大量の氷水に当てて一気に冷やして色止めをするので鮮やかな緑色が保てる。また、色だけでなくこうしたほうが香りもしっかり残り美味しいのだ。 野菜のポタージュは色々作るが、それぞれの野菜ごとにつなぎに使うリエゾンが違う。リエゾンとは、要するにスープやソースにとろみをつけるもののことだ。 例えば、ジャガイモやカボチャやサツマイモなどの場合は、特につなぎを入れなくてもとろみはつくのだが、芋やカボチャの粉っぽさを抑えるためにコーンスターチなどを使う事もある。 他にはお米!これはニンジンなどによく使うのだが少量で実に上品なとろみが付くし、素材の味を一切邪魔せず綺麗な味が出る。 このグリーンピースの場合は、小麦粉。豆のちょと田舎臭いというか素朴な雰囲気と小麦粉で作るとろみがマッチするのだ。 春はたまに作ります。
Mar 17, 2008
-

ポタージュ・パルマティエ
ポタージュ・パルマンティエ。 パルマンティエというのはフランスの農学者で、確か18世紀頃の人だ。フランスにジャガイモ栽培を広めたという事になっている。 南米アンデス原産のジャガイモは、毒があるなどといわれ(実際」ジャガイモの芽にはソラニンという毒素が含まれている)なかなか人気が出なくて、厳しい環境でも栽培しやすく食べれば高カロリーという救荒作物としては最適な作物なのに一般的に栽培が広まらなかったのだ。 そこで一計を案じた、パルマティエ先生は自分の領地にジャガイモ畑を作り、昼は厳重に兵士に監視させ夜はわざと警備を手薄にしたという。近郊の農家たちの間では、昼の厳重な警備を見てよほど美味しい野菜が植えられているんだろうと噂になり、夜に盗みに来る者がたくさんいたそうだ。それが元になってフランス中にジャガイモが広まったという事になっている。だから、フランス料理ではジャガイモを主として使う料理にパルマンティエ風というように先生に敬意を表することになっている。 このポタージュは、去年の夏に取ったジャガイモで作ったもの。このごろ芽が出てきてしまってもうさすがに終わりなのだが、最後の最期のしなびたジャガイモの凝縮された旨味にはびっくりする。芽を取って皮を厚めにむいて作ったこのポタージュは、ジャガイモに少しの玉葱とほんの少しの牛乳とバターで作るのだが、ブイヨンを使わず水をたっぷり使っているのに旨味がしっかりある。 コロンブスのアメリカ発見以降、新大陸原産の2種類の野菜が後の世界の食文化を変えたのではないかと思う事がある。それはトマトとジャガイモ! 例えば、世界中のファーストフードショップから、フライドポテトとトマトケチャップが消えたらどうですか?それどころか、トマトがないとパスタやピッツァ、ウスターソースやトンカツソース、デミグラスソースやビーフシチューやカレーソースなど、トマト無しでは困る料理は枚挙にいとまがない。 また、ジャガイモは18世紀あたりから、救荒作物として世界に広まり、人々を飢えから救ってきた。 つまりトマトは主として味付けのための調味料的な野菜として確立してきて、ジャガイモは小麦が不作だったり小麦の栽培には向かない土地のための救荒作物として主食的な地位を得た。(そういう意味で、フライドポテトにケチャップというのはアメリカ大陸的食の典型かも?) ヨーロッパで多分一番ジャガイモ好きは、オランダ人かな?日本の家庭に大抵ある炊飯器と同じくらいポテトフライヤーが普及しているらしい。また、ドイツ人やアイルランド人もちろんフランス人もイギリス人もジャガイモは大好き!ふかし芋、ボイル芋、マッシュポテト、フライ、チップス、、、etc いろいろあるけど、ジャガイモは主食になりつまみになり、おやつになり、、ジャガイモ無しの生活なんて想像つかないですよね!でもたった200年もさかのぼれば食物という認識すらなかったんですからね!!
Mar 13, 2008
-

ちょいと古酒、ボルドー入荷
ル・オー・メドック・ド・ジスクール1999年が入荷です。まだリストには載せてませんが、今年は2008年だから9年熟成のワインですね。クラスはただのボルドーより一つ二つ上のクラスのオー・メドッククラス。実際には、マルゴー村の3級格付けのシャトー・ジスクールが近所の別畑で仕込んでいるワインだ。 畑の葡萄の樹齢も20~25年を越えるくらいになってきて味わいも充実しだしたのがちょうどこのころのヴィンテージから、、今どんどん上り調子の作り手である。 ワインコミックの神の雫でもこのワインの2000年が紹介されたらしい。まあ、私の場合2000年と2003年に関しては、実は世間の人気に反してあまり好きではない。どちらの年も夏が暑く、葡萄が完熟して糖度が上がり、果実味が凝縮された感じでとてもインパクトがあるタイプ。一般的にそういう条件はいわゆるワインの当たり年の条件であって本来文句をつけるところではないのだが、、、ちょいと元気がよすぎるきらいがあるのだ。なんというか、ワインが強すぎると感じる事があるのだ。 例えば、いわゆる五大シャトーとかの有名ワインのしかも当たり年などの例えば90年代の物などを味わう機会があるといつも思うのだが、若くて固くてまだまだぜんぜん老けてないことが多く、「アー、まだ開けるの勿体ないなぁ」と思ってしまう事が多い。私の場合どちらかというと力の抜けてきた段階の古酒が好きだから、五大シャトーの当たり年などは私の好みの熟成具合になるのにきっと50年以上かかるだろう。 先日も五大シャトーのひとつであるシャトー・ラツールのセカンドワインのレ・フォール・ド・ラツールの82年を味わう機会があったが、滑らかにタンニンが落ち着いていて、力強い大地の香りとまだしっかり残った果実味もあって実に素晴らしい味だった。これがもし本家のシャトー・ラツールだったら、まだまだ若すぎてこれほど華やかに熟していなかった事だろう。 だから私は一流シャトーよりそのセカンドクラスや別畑のしかもちょいと裏年を選ぶ事が多い。何より価格が安いし、こじんまりした中にも適度の熟成感が楽しめるし、何よりもそういうデリケートなニュアンスを持ったワインのほうが料理にも合わせやすいのだ。 味の強い当たり年のワインは料理の味を吹き飛ばしてしまう事があるので、ワインを単体で楽しむのにはよいのだが、料理とあわせるとなると料理に寄り添ってくれるワインがありがたい。 パッと見地味だけどよくよく付き合ってみるとけっこう味があっていい奴だったりする人っているでしょ?さりげなさの中に光る魅力、、。「なんだー、お前いい奴じゃねえかぁ!」そんな感じのワインですよ。このオー・メドック・ド・ジスクールの99年は、、。 今回入荷のこのワインは、私の親しい輸入元から直にもらっているのでけっこう安価で入ったおかげで6千円くらいで売れるので、ぜひ美味しい熟成酒好きの方は飲んでみてください。
Mar 11, 2008
-

肉の焼き方
これは、和牛のバベットステーキ。 そして、シャラン産窒息鴨の胸肉。 そして、穀物肥育の仔羊ロースの芯の肉。 肉の美味しさを引き出すには、何といっても焼き加減が大切。料理人になってしばらくしてからずっと追求してきたのが、肉の火の通し加減。塩と火加減さえ決まれば料理はほぼ出来たも同然と考えている。もっとも、その火の通し加減が一番難しいのだが、、、。
Mar 4, 2008
-

モワルーショコラ
モワルーショコラ。モワルーというのは骨髄のようにとろりと滑らかというほどの意味。 軽いビターチョコレートのスフレ生地を半生焼けに仕上げてあって、中にはフランボワーズのソースとホワイトチョコレートのガナッシュが忍ばせてある。 熱々のところを召し上がっていただくと、中から解けたビターチョコの生地に混じってほんのり木苺の香りと甘く滑らかなホワイトチョコが出てくるというわけ。 チョコ好きにはたまりませんなぁ!7周年記念コースのデザートです。
Mar 3, 2008
-

穀物肥育の仔羊の芯のロースト
これが、7周年記念コースのメイン、仔羊の芯の肉のロースト。まるで生肉のように見えるかもしれないが、これで約1時間近くかけて弱火でゆっくり焼いてあって、中までちゃんと火が入っているのだ。食感としては生より柔かいという感じ。肉の生臭さはなく、しっとりと肉汁にあふれた焼き上がりだ。 仔羊の背肉の芯というのは、、、 背骨と肋骨がついた1キロちょっとの肉から300グラムくらい取れる芯の肉の事。つまりもとの肉から1/3以下しか取れない贅沢な肉だ。 芯を取った後の骨とくず肉は700グラムあまり。これでダシを取ってソースにする。 つまり、普通のこのような仔羊のローストの黒い線で囲んだところだけを使い、残りはソースになってしまうわけです。 実に贅沢な料理でしょ? 7周年記念コースのメインです。
Mar 1, 2008
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-
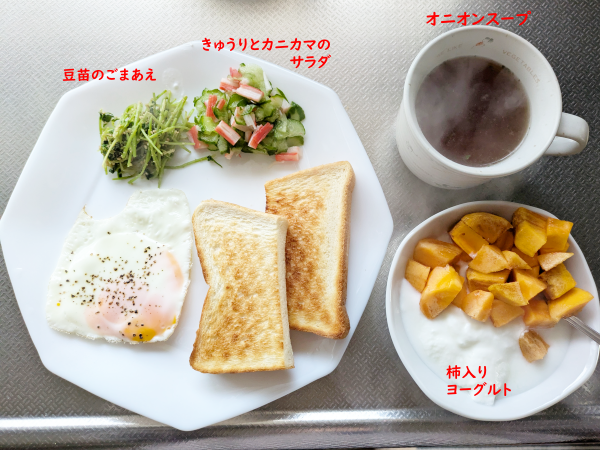
- フルーツ 大好き♪
- 奥州りんごとみかんと柿。
- (2025-11-21 15:07:52)
-
-
-

- パン!ぱん!パン!
- とらおさんのパン「プレーン」(400…
- (2025-11-24 20:10:37)
-
-
-

- スイーツ★スイーツ
- ピーナッツキャラメルサンド、パッシ…
- (2025-11-24 20:41:53)
-







