2007年08月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

QED~ventus~熊野の残照
熊野三山は、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三つの古い神社の総称で、日本を代表する霊場である。古来より、後白河院など、歴代上皇をはじめ、多くの人が参拝し、2004年(平成16)には、「紀伊山地の霊場と参詣道」として、高野山などとともにユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。 しかし、これだけ有名な熊野三山にも色々謎があるという。熊野三山の神の正体は何か。どうして、熊野三山を回る順番が定められているのか。「QED~ventus~熊野の残照」(高田崇史:講談社)これらの謎を解き明かしていこうとするものである。 作品の主人公は、お馴染み桑原崇と棚旗奈々。今回は、学校薬剤師会の親睦会で熊野に来ている。これに、後から、いつものように、奈々の妹の沙織と崇の親友の小松崎が加わる。しかし、今回の作品の中心となるのは、熊野出身の薬剤師神山禮子。何か事情があるらしく、熊野出身ということを表に出さず、どこかはすに構えたところのある女性だ。 いつもは、行った先で殺人事件に巻き込まれるのだが、今回は、熊野の謎を解き明かすのが中心である。もっとも、時折挿入される禮子の過去と思われる出来事のなかで、一つの殺人事件は出てくるのではあるが。ところでこの出来事、矛盾する二つのことが交互に出てくる。どういうわけだと思っていたら、最後で謎解きがあり、ああこういうことだったのかと納得。 そのなかで、禮子の過去に起こった忌まわしい出来事も判明する。でも、さすがに、どんな田舎でも、こんな風習はもう残ってはいないだろうと思うのだが。 「QED~ventus~熊野の残照」(高田崇史:講談社) ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 31, 2007
コメント(0)
-

ガメラ2 レギオン襲来
ずっと前に、地元のテレビ局で深夜に放映していたものをビデオに録画していたのだが、やっと観ることができた。「ガメラ2 レギオン襲来」である。1996年の放映であり、平成ガメラシリーズの第2作目にあたる。 出だしは、いきなり宇宙から隕石が降ってくる。これが実は、未知の宇宙生物の襲来であったというのは、この手の作品には良くあるパターンだが、この作品では、レギオンというとんでもない敵を登場させる。このレギオン、シリコンを食べて育つため、体の組成が、半導体そっくりであり、電磁波でコミュニケーションするため、電波の溢れる都会で繁殖をするというやっかいなやつだ。 レギオンは、でっかいやつが1体と、小さいやつが無数にいる。形はシラミを大きくしたようなものを連想させるが、足がたくさんついていて、不気味だ。私は、足の多いものは苦手なので(10本以内なら大丈夫なのだが)、小さいやつが、ガメラを多い尽くした場面は、まるでフナムシの大群を見ている様で、気持ちが悪かった。 今回は、さすがのガメラも、相当苦戦している。ギャオスを一発で倒す威力のあるプラズマ火球も通用しないのだから。一度は、死んだかと思われたガメラも、子供達の祈りで復活し、レギオンとの最後の戦いに挑む。でも、さすがはガメラ、究極の必殺技を隠し持っていた。この必殺技は、これまで見た覚えがないので、たぶんこの作品で初めて出すのである。もっとも、プラズマ火球も、怪力も通用しなかったと言う設定なので、何か新技を出さざるを得なかったのだろうが。 懐かしさも手伝って、面白く観る事ができた。(監督)・金子修介 (特撮監督)・樋口真嗣(出演)・永島敏行(渡良瀬裕介) ・水野美紀(穂波碧) ・藤谷文子(草薙浅) ほか★「ガメラ 大怪獣空中決戦」の記事はこちら「ガメラ2 レギオン襲来」DVD ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 30, 2007
コメント(2)
-

アインシュタイン丸かじり
「博士が愛した数式」に出てきた博士は、オイラーの公式を美しいと思っていたが、もっと単純で美しい数式があると思う。ただし、数学での話ではなく、物理学でのことである。 それはE=MC^2(^2は2乗を現す)というエネルギーと質量の等価則である。導き出したのは、もちろんアインシュタインだ。 世の中に天才と呼ばれる人はたくさんいる。天才の定義はなかなか難しいと思うが、アインシュタインは、誰もが文句無く認める天才の一人であろう。 そのアインシュタインは、驚いたことに、ある時期までは、ほとんど無名の存在であった。ろくな就職口も無く、やっともぐりこんだスイス特許庁で役人をしていた青年アインシュタインは、1905年、いちやく時の人となる。奇跡の年と呼ばれるこの年、彼は、異なる分野での5つの論文を立て続けに発表する。それは、すべてノーベル賞級のものであった。そのうちの一つが、有名な「特殊相対性理論」である。科学技術を専攻した人なら実感があると思うが、現在の科学技術は細分化しており、大学などでも隣の研究室では何をやっているのか良く分からないのが普通である。異なる複数の分野で、ノーベル賞級の仕事をするということは、いかに彼がスケールの大きな天才だったかが分かるというものだろう。 ちなみに、アインシュタインが1921年にノーベル賞を受賞したのは、「特殊相対性理論」ではなく、この5つの論文の一つ「光の粒子説」に関連してであった。一説には、相対性理論が難解すぎて、ノーベル賞選考委員が、その価値をよく理解できなかったためだと言われている。 現在では、彼の理論は、色々な科学技術に応用され、様々な分野で使われている。 「アインシュタイン丸かじり」(新潮社)は、そのアインシュタインの大ファンを任じる静岡理工科大学教授の志村史夫氏が、その理論について、やさしく解説した本である。 もちろん一般向けの解説書であるこの本だけで、彼の理論が本当に理解できるわけではない。この本の題名のように「丸かじり」などとてもとても。せいぜい薄皮1枚をかじったくらいである。しかしこのような本をきっかけに、物理学に興味を持つ子供達が増えて欲しいものだ。 最近は、高校で、物理を学ばない者が増えているようである。科学立国日本としては、嘆かわしいことだと思う。「アインシュタイン丸かじり」(志村史夫:新潮社) ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 29, 2007
コメント(6)
-

蝉しぐれ
日曜日の夜は、テレビ朝日系の日曜洋画劇場で、「蝉しぐれ」を観ていた。日曜洋画劇場40周年記念企画で、藤沢周平の同名小説を原作にした、2005年の東宝映画である。 舞台は、東北の小藩「海坂藩」。お家争いに巻き込まれて切腹させられた下級武士・牧助左衛門の子・文四郎と幼馴染・ふくとの悲しい恋を描いた作品である。ふくは、やがて殿様の側室となり子供を生む。父を切腹に追いやった主席家老里村左内は、ふくの潜む屋敷に刺客を送り込む。文四郎は、ふくとその子を守るために戦うのであった。 しかし、なぜ、文四郎は、里村を切らなかったのだろう。父の敵であり、ふくの命を狙った男である。それが、彼の士道だったのであろうか。 最後に、ふくが出家する前に文四郎と会う場面で終わっている。時間的には、この事件のすぐ後かと思っていたら、なんと文四郎に二人子供がいることになっている。この間の事情がさっぱりわからないのでとても気になる。文四郎は、身にかかる火の粉を掃っただけとはいえ、何の咎めも受けなかったのだろうか。悪家老の里村は、あの後、何か処分が下されたのか。文四郎に報復はしていないようだが。 (原作)・藤沢周平(監督)・黒土三男 (出演)・市川染五郎(牧文四郎) ・木村佳乃(ふく) ・緒形拳(牧助左衛門)ほか ★「蝉しぐれ」公式サイトはこちら「蝉しぐれ関連グッズ」 ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 28, 2007
コメント(4)
-

ミヨリの森
土曜日の夜は、フジテレビ系の土曜プレミアムで、「ミヨリの森」を観ていた。総制作費2億円と制作期間3年をかけた、特別企画の新作アニメである。予算節約のためか、フジテレビのアナウンサーが声優を務めている役が多い。主題歌を、元ちとせが歌っており、一本桜の精の声でも出演している。原作は、読んだことはないのだが、かって「ミステリーボニータ」(秋田書店)という月刊少女雑誌に連載されていたらしい。 あらすじを簡単に紹介しよう。ミヨリは、小学六年生の、何処かさめた感じで、人に心を開かない少女であった。両親が不仲で、母親が家を出て行ってため、父親の実家に預けられる。そこで、森の不思議な妖精(怪?)達や村の学校の子供達と触れ合うことにより、次第に心を開いていく。そこに、ダム問題が起こり、ミヨリは、妖精や子供達と、ダム計画阻止に乗り出す。一人の少女の、心の成長を通して、自然の大切さを訴えると言った内容かな。 最初、絵柄がちょっと「微妙」かなと思ったが、観ているうちに慣れたようだ。最後の方では、ミヨリもなかなか美少女じゃないかとか、妖精たちも変な顔だけど、なかなかかわいいなんて思うようになったくらいだ。天野ひろゆきが声を演じているカノコ(たぶん河童だと思うが)がなかなかいい味を出している。 かって、田舎の集落には、里山が身近にあった。里山の森は、多くの命を育むと共に子供達の絶好の遊び場でもあった。最近は、山は荒れ放題、妖精たちも去っていってしまった。残念なことだ。(原作)・小田ひで次(監督)・山本二三 (声の出演)・蒼井優(真縞ミヨリ) ・天野ひろゆき(カノコ)・市原悦子(ばあちゃん) ・元ちとせ(一本桜の精) ほか ★「ミヨリの森」の公式サイトはこちら○「ミヨリの森」関連グッズ ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 27, 2007
コメント(2)
-

灼眼のシャナ
とうとう、ライトノベルズにまで、手を染めてしまった。「灼眼のシャナ」(高橋弥七郎:メディアワークス/角川GPメディアワー )である。たまには、普段と違ったものを読もうと思い、本のリサイクルショップで、目立つところにおいてあったこのシリーズの第1巻を買ってきた。元々、SFやファンタジー好きだということもあるのだが、読んでみると、これがなかなか面白い。 高校生坂井悠二は、ある日、怪物に食われそうになっていたとき、炎髪、灼眼の少女に出会う。怪物を倒した少女に、悠二は、自分が「紅世(ぐぜ)の徒(ともがら)」に存在を食われた残りかすで、やがてはこの世界から消えてしまう「トーチ」と呼ばれる「モノ」だと告げられる。 これは辛い。自分は既に死んでおり、存在の残りかすである今の自分もやがては、だんだん影が薄くなり、遂には、最初から存在しなかったことになってしまうのだから。 今回の敵は、「狩人」の真名を持つフリアグネ。人形のマリアンヌを「1個の存在」にするため、存在の力を集め、人々を次々に「トーチ」にしている。悠二が、シャナと呼ぶようになった少女は、彼を守るため、彼の側で暮らすようになる。最初は「モノ」よばわりしていた悠二を、シャナが次第に意識していくところは、この手の作品のお約束といったところか。 このシリーズ、かなりたくさん出ているが、さてさて、続きはどうしようかな。「灼眼のシャナ」(高橋弥七郎/笹倉綾人[コミックス]:メディアワークス/角川GPメディアワー )&シャナグッズ ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 26, 2007
コメント(6)
-

真月譚月姫(5)
おはようさん! ちょっと読書の傾向が偏ってきたかなと自分でも思う風竜胆である。最近は、暑さのせいか、どうも脳みそがくたびれ気味で、あまり、活字を読む気がしない。 こんなときは、コミックでも読むのが一番。と言う訳で、今日は、以前にも記事を書いたことのある、「真月譚月姫」(佐々木少年:メディアワークス/角川GPメディアワー) の第5巻である。4巻までは、子供の買ってきたのを取りあげて読んでいたが、最近金欠だと言うので、仕方がないから自分で買った。 「直視の魔眼」 を持つ志貴と、吸血鬼の「真祖」の姫君アルクェイド、二人は数奇な運命よって出会い、共に吸血鬼のロアを探索する。 この巻では、志貴とアルクェイドは、ほのぼのムード。お互いに大分意識しているようだ。デートの場面が延々と続く。まさか、このまま、デートの場面だけでおしまいか、と思ったら、二人に異変が・・・ この後どうなるんだろう。気になるね。「真月譚月姫」(5)(佐々木少年:メディアワークス/角川GPメディアワー) ★「真月譚月姫」(3)(4)の記事はこちら★「真月譚月姫」(1)(2)の記事はこちら○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 25, 2007
コメント(0)
-

キューティーハニーSEED(2)
ほぼ1年前に「キューティーハニーSEED」(星野小麦/永井豪:秋田書店)の第1巻の記事をこのブログに書いたが、最近、その第2巻をやっと入手した。 星野小麦描くハニーは、ボーイッシュで凛々しいハニーではなく、ホニャニャ~ンとした、萌え萌え系のハニーである。 1巻目は、やっとハニーへ変身したところで終わってしまったが、今回もまだまだ序章と言うところか、エピソード的なものはいくつかあるものの、それほど大きな事件と言うわけでもない。ただ、某国軍隊らしき組織が動いていたので、今後大きく事態が動いていきそうな予感がする。 それにしても、ハニーの居候先の後醍醐裕太はなぜあんなにもてるのだ。別にイケ面という訳でもないのに、ハニーを始め、4人のかわいい女の子にモテモテである。きっと誰かの願望の反映か?★「キューティーハニーSEED」(1)の記事はこちら「キューティーハニーSEED」(1)(2)(星野小麦/永井豪:秋田書店) ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 24, 2007
コメント(6)
-

ちぇんじ123(ひふみ)(1)(2)
最近気に入っている漫画のひとつに「ちぇんじ123(ひふみ)」(岩澤紫麗/坂口いく:秋田書店 )がある。現在、「少年チャンピオンRED」に連載中の漫画であるが、最初の方は読んでいなかった。先日たまたま入ってみた、本のリサイクル店に、この1,2巻があったので買ってきた。 仮面レッダーオタクの高校生・小介川は、ある時、同じクラスの月斗素子がチンピラを叩きのめすのを目撃したことから、彼女と関わることになる。素子は、控えめで目立たない感じの娘だが、彼女は、それぞれ色々な武道の達人である、ひびき、ふじこ、みきり(あわせてひふみ)と言う別人格を持っており、素子が危険な目に遭うと、それらの人格が出てきて大活躍する。 素子を好きな小介川は、なんとか告白しようとしているが、なかなか言い出す勇気がないのが、なんともかわいらしい。ひふみたちは、それぞれが個性的で魅力的であり、健康的なお色気にも溢れている。絵柄も綺麗だし、面白い漫画である。「ちぇんじ123(ひふみ)」(1)(2)(岩澤紫麗/坂口いく:秋田書店 ) ○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 23, 2007
コメント(2)
-

恋人たち
先般帰省したときに、実家の本棚から持ってきた一冊が、「恋人たち」(フィリップ・ホセ・ファーマー/伊藤典夫:ハヤカワ文庫)である。原題は「THE LOVERS」。金城武の出た映画に似たような題名のものがあったが、全く関係はない。 舞台は、古の中国ではなく、核戦争で一旦滅びかけた未来の世界。主人公のハル・ヤロウの住む国は、宗教が支配しており、いつも監視されているような、人間性を喪失した社会である。 その割には、不思議に科学は発達しており、何十光年も離れた惑星に宇宙船を飛ばすこともできるのである。 何かにつけ、教えに従って当局に彼のことを告げ口する妻にうんざりしていたハルは、40光年離れた惑星オザゲンの調査に志願する。オザゲンはバッタから進化した生物ヴォグが支配する惑星であった。バッタから進化しているといっても、別に仮面ライダーではないので念のため。非常に文化的で、ある部分では、人間以上の文明を持っている生物である。 ヒューマノイド型生物がいないはずのこの星で、ハルはジャネットという不思議な美しい娘と恋に落ちる。しかし、彼女の正体を知ったとき、訪れる悲劇と残された希望。 1953年にこの作品が発表されたときには、センセーションを巻き起こしたという。別に直接的なセクシャルな場面があるわけではないのだが、当時は、SFで宗教と性をテーマにすることはタブーに近かったようだ。今の読者だったら、読んでいる途中で結末の見当がついてしまうと思うが、これは、この作品が、類似の作品の雛形となってしまったためということであろうか。 今は絶版になっているようだが、古書店に行けば手に入るかもしれない。SF史に記録されるべき一冊である。○応援してね。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら○関連ブログ記事・ゆっくりと世界が沈む水辺で~きしの字間漫遊記~
August 22, 2007
コメント(2)
-

出口のない海
かって、お国のためという美名の下に、多くの若者達を無為に死の旅路に送り出していた時代があった。今から僅か60年ちょっと前のことである。空は「神風」、海は「回天」。しかし、神風などは吹きはしなかったし、ましてや、天が回りなどしなかった。 先日、テレビ朝日系の「日曜洋画劇場」で放映していた「出口のない海」は、この「回天」に青春を散らした男の物語である。横山秀夫の同名小説を原作にした、2006年の松竹映画だ。 並木浩二は、甲子園の優勝投手であった。しかし、時代は彼らを、容赦なく戦争に駆り立てる。海軍にそして「回天」への搭乗を志願した彼には、国のために死ぬことしか残っていなかった。 この時期、既に戦局は見えていた。日本の復興に貢献すべき若者を、一体何人無為に殺したのであろうか。私は、自虐史観には賛成しないが、それでも、この暴挙は許されるべきではないと思う。 死ぬことが国のためだと信じ込まされた哀しい時代である。なぜ、国のために生きろと教えられなかったのだろうか。 最後のシーンで、回天基地のあった周南市の大津島が出てきた。機会があれば、そこにある「回天記念館」に行ってみて欲しい。きっと彼らが何を思いながら死んでいったか、その一端でも分かるであろう。「大和ミュージアム(呉市)に展示してある回天の実物」 (原作)・横山秀夫(監督)・ 佐々部清 (出演)・市川海老蔵(並木浩二)・上野樹里(鳴海美奈子) ほか ★本の方の感想はこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「出口のない海」(横山秀夫:講談社)&関連グッズ 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 21, 2007
コメント(6)
-

化生の海
「園子はいつか、この町を出て行くことになるだろうな」 余市川を眺めながら、見井所園子の父・剛史は、よく独り言のようにつぶやいていた。園子の東京の大学への進学希望を聞いた時、学費の心配をする母に、剛史は、まかせろと言った。その剛史が、遠く離れた石川県の加賀で、死体で発見された。剛史は、松前に行くと言ったきり、行方が途絶えていたのである。 ところで、北海道の余市と言えば、最近はヤンキー先生で有名になったが、かっては、ニシン漁で栄えた町である。「化生の海」(内田康夫:新潮社)は、その余市に住む、一見どこにでもありそうな、園子の一家に起こった悲劇の原因を解き明かしていくという浅見光彦シリーズの旅情ミステリーである。手がかりとなるのは、卯の刻印のある土人形。光彦の事件を追い求める旅は、北海道や加賀のみならず、福岡、下関と壮大なスケールで展開される。 園子は、父の生い立ちを知らなかった。なぜか父は、自分生い立ちを語らなかったのだ。ある事情により、自分のルーツとはすっぱりと決別して暮らしていた剛史。しかし、園子の進学のため、封印してきた過去にすがろうとした事が悲劇を招く。 剛史が最後に頼った自分のルーツ。しかしそこにたどり着く前に、欲に駆られた魍魎たちに命を奪われてしまう。なんと言う無念。 その無念を晴らすように、光彦が全てを解き明かしたとき、観念した魍魎たちは、この世から、仲間の待つ、「化生の海」へと船出をしていく。いかにも光彦らしい解決の仕方であるが、どこかやりきれない思いが残る作品である。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「化生の海」(内田康夫:新潮社) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 20, 2007
コメント(0)
-

ホーンテッドマンション
ディズニーランドのアトラクションとしてお馴染みの、「ホーンテッドマンション」とは、日本語に直すと「憑かれた家」すなわち「幽霊屋敷」のことである。これを参考に作られたのが、エディ・マーフィ主演のホラーコメディ「ホーンテッドマンション」だ。2003年のアメリカ映画だ。 この映画を、18日の夜、日本テレビ系の金曜ロードショーで放映していたので、観てみた。テレビの前宣伝には、999人の幽霊達が、1000人目の仲間を待っているようなことを言っていたが、内容はちょっと違っていた。もしかするとこれは、ディズニーランドのアトラクションの方の話か? お話の方だが、不動産屋のジムは、商談のため、家族旅行の途中で、古い屋敷に立ち寄る。ところが、この屋敷、豪邸だが、裏庭には墓地があるし、対応した執事がなんとも怪しい。豪雨のため、屋敷から出られなくなったジム一家は恐怖の体験をするというもの。 前半は、だらだらと流れるような感じで、あまり怖くなかった。後半からだんだん本調子になってきたが、やはりそんなに怖くなかった。エディマーフィだからやっぱりコメディタッチの方が強いのか。 それにしても、執事があんなに力を持っているのはなぜ? それに、どうして、水晶玉のおばさんと、歌う銅像カルテットは昇天しないんだ?(監督)・監督:ロブ・ミンコフ (出演)・エディ・マーフィ(ジム・エヴァース)・マーシャ・トマソン(サラ・エヴァース) ほか ○「ホーンテッドマンション」の公式サイトはこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ DVD「ホーンテッドマンション」 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 19, 2007
コメント(4)
-

化石の街美祢市
美祢市は、山口県のほぼ中央部に位置する、人口17000人強の小さな街である。来年の3月には、隣の美祢郡秋芳町および美東町と合併し、新しい美祢市の誕生が決まっている。「JR美祢駅」 大嶺炭田は、無煙炭の産出地として知られ、美祢市は、かっては、炭鉱の街として栄えた。炭鉱の閉山と共に人口は激減し、過疎化が進んでいった。また、美祢市は、石灰石の街でもある。現在でも、良質の石灰石を多く産出しており、国内有数のシェアを誇っている。 ところで、石炭も石灰石も、どちらも太古の生物に起源するものであり、美祢市は、わが国でも有数の化石の産地として知られている。美祢市は、化石の街なのである。 美祢市の化石を語る上で忘れてはならないのが、故岡藤五郎先生である。先生は、地元の大嶺高校の教員を務める一方、多年に渡って化石の研究に打ち込まれ、多くの標本を採取されてきた。この岡藤先生の集められたものを中心に、約10万点もの化石を展示・保管しているのが、「美祢市歴史民族資料館」である。「美祢市歴史民族資料館」 また、「歴史民族資料館」の近くに、もう一つ化石を展示した博物館がある。「美祢市化石館」である。こちらは子供達が興味を持ちやすいよう、「せきつい動物」、「アンモナイト」、「昆虫」の3つにテーマに絞って展示が行われている。「美祢市化石館」「美祢市化石館」のシンボル「アンモナイト」 しかし、昔に比べると本当に寂れてしまった。ぜひ、地域振興のため、誰かこのあたりを舞台にしたミステリーでも書いてくれないものか。 例えば 内田センセなら、「化石の女(ひと)殺人事件」とか 西村京太郎なら、「秋吉台殺人ルート ~秋芳洞に消えた女~」とか 森博嗣なら、「アンモナイトは転んだね」とか 山村美紗なら「小京都山口の近くの街美祢殺人事件」とか書いてくれたら、観光客がもっと増えるんだが。なお、宮部みゆき用や恩田陸用も考えてみたが、どうしても思い浮かばなかった。 この題名は差し上げるので(誰も欲しがらないか)、ぜひよろしく御願いしたいものだ。でも、最後のやつは、いろんな意味で絶対無理か・・・○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ ○楽天ではアンモナイトの化石まで売っていた。 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 18, 2007
コメント(4)
-

クロスファイア(上)
「あたしは、装填された銃だ。」 ちょっと前に、「鳩笛草」(宮部みゆき:光文社)を読んで以来、気になっていたのだが、やっと読むことができた。「クロスファイア」(宮部みゆき:光文社)である。といってもまだ上巻だけだが。読み出すとやめられなくなって、並行して読んでいたほかの本はそっちのけで、一気に上巻を読み通してしまった。 主人公の青木淳子は、念力によって物体を発火させることができる念力放火能力(パイロキネシス)の能力を持っている。この能力を使って、悪人を葬っているのだ。高まる力を抑えるため、力を放出しようと忍び込んだ廃工場で、殺人現場を目撃する。主犯格の男・浅羽に逃げられた淳子は、彼らに拉致された娘を救うため浅羽の居所を探る。 これだけ見ると、まるで必殺仕事人のようだが、大きく異なっていることが一つある。仕事人たちは、自分達が人殺しであると言うことを自覚し、歯止めのために、他人から報酬を受け取って悪を退治するというルールを貫いてきた。自分達の判断で恣意的に人殺しをしないように、恨みを持った依頼人という歯止めをかけているのだ。しかし、青木淳子の場合は、自分の判断だけで悪人を葬ってしまうのである。力は時に暴走し、場合によっては、たまた居合わせた者も巻き添えにしてしまうのである。 例えて言えば、彼女は、自分の中に、竜を飼っているのだ。竜の力は人間には決してコントロールできない。今はコントロールしているつもりでも、やがて竜は本性を現し、主従が逆転する。既にそのような兆候も見える。 この事件を追うのが、警視庁のおばちゃん刑事・石井ちか子巡査長である。そして、淳子にコンタクトするガーディアンと名のる謎の連中。さて、下巻ではどのような展開になるかな。お楽しみである。 なお、この作品は、「鳩笛草」に収録されている「燔祭」と言う作品の続編に当たるので、まずそちらを読んでおいた方が、一層本作品を楽しめるであろう。★「鳩笛草」の記事はこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「クロスファイア」(宮部みゆき:光文社)&DVD 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 17, 2007
コメント(6)
-

笑わない数学者
久しぶりに読んだ森博嗣の本。「笑わない数学者」である。「すべてがFになる」から始まる、S&Mシリーズの3作目のようである。S&Mシリーズといっても、別に女王様が鞭を持って出てくるわけではない。N大学工学部助教授の犀川創平とN大学の学生西之園萌絵の名コンビが、事件に挑むと言う理系ミステリー小説である。 今回のお話をかいつまんで紹介しよう。S&Mコンビが、天才数学者・天王寺構蔵博士の住む三ッ星館に、招かれるのだが、そこで殺人事件が起こる。一方この三ッ星館にはオリオン像が建っているのだが、天王寺博士は、このオリオン像を消してみせていた。S&Mコンビが、このオリオン像の謎と殺人事件の解明に挑むというもの。 話の筋が、なんとなく「すべてがFになる」を連想させる。話の中心となる天才科学者は美女と老人の違いこそあれ、どちらも大金持ちで、人里離れた研究所に長年閉じこもり生活をしている。殺人事件が起きるが、殺されたのは、その天才科学者の近親者である。etc. 森氏好み?の言い方をすれば、二つの話は、互いに、ある数学的変換に対して、等価な構造を持っているというようなことか? それにしても、登場人物の誰もが、何かあると、小道具として煙草を吸うのは、嫌煙者の私としてはただただ、あきれてしまう。他に表現の仕方はないのだろうかね。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「笑わない数学者」(森博嗣:講談社) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 16, 2007
コメント(6)
-

風林火山
「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」 「風林火山」といえば、孫子の書に出てくる言葉だが、武田信玄の旗指物に書かれた言葉としても有名である。現在、NHKの大河ドラマで放映されている。 このドラマの原作となったのが、「風林火山」(井上靖:新潮社)である。主人公は、武田の名軍師として知られた山本堪助。異形の男である。決してNHKの大河ドラマに出てくるような男前ではない。 人から好かれるタイプの男ではない。今川では、9年も飼い殺しにされた。今と違って人生50年の時代である。そして、彼自身も人を好きになるタイプの人間ではない。 行流の達人と噂されているが、実際には剣術は習ったこともない。しかし強い。合戦には一度も出たことはない。しかし城を落とす確固たる自身に満ち溢れている。 武田晴信(後の信玄)は彼を直ちに認めた。彼も凛とした晴信を好きになった。運命の出会いである。 勘助は、武田の滅ぼした諏訪の姫・由布も好きになった。彼は、晴信と由布姫の間にできた子を、武田の後継者にすることを夢見る。 この作品は、武田の中で自分の居場所を見出し、武田のために死んでいった男、そんな男の物語である。 夜寝る前に読み始めたら、すっかり面白くなり止められなくなった。次の日が休日だったのでよかった。★大河ドラマ「風林火山」の公式HPはこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「風林火山」(井上靖:新潮社) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 15, 2007
コメント(6)
-

百人一首の謎
正月に百人一首を楽しむ家は、最近はあまりないかも知れない。しかし、一度くらいはやってみたことのある人も多いだろう。百人一首の面白さの一つは、お手つきをするということである。なぜ、お手つきをするか、それは、同じような語句を使った歌が多いからである。 更に、百人一首には、色々謎があるという。取りあげられている歌人全てが必ずしも著名な歌人と言うわけではなく、選ばれた歌も、必ずしも彼らの代表作というわけでもない。また、なぜ「百人百首」ではなく「百人一首」と呼ぶのか。百人一首を選んだのは藤原定家であるが、彼はどんな意図があって、これらの歌を選んだのであろうか。 これらの疑問について解き明かそうとしたものが、「百人一首の謎」(織田正吉:講談社)である。織田氏によれば、百人一首の歌は、クロスワードのように相互に関係しあっており、隠されたメッセージを含んだ「暗号」である。そして、その目的は後鳥羽上皇と式子内親王の鎮魂であるというのである。 織田氏の説は、高田崇史が、「QED百人一首の呪」を書く際にも参考にしているようで、参考文献のリストにも織田氏の名前を見ることができる。もっとも結論の方は少々異なるのであるが。 百人一首に隠れた法則性に気づき、そこから何らかのメッセージを見つけ出そうとする試みは、画期的あるといえよう。しかし、なぜ百人一首を選ぶことが鎮魂になるのかということについては、この本を読む限りそれほど明確とは言えない。やはり、怨霊信仰だとか言霊信仰などをもっと前面に出さないと説明が難しいのではないかと思う。また呪詛を恐れた後鳥羽上皇と、慕っている式子内親王が、どうして、同じ百人一首により鎮魂されているのかということについても疑問が生じる。「QED 百人一首の呪」の記事はこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「百人一首の謎」(織田正吉:講談社) ●百人一首色々 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 14, 2007
コメント(6)
-

オーシャンズ12
先般、「オーシャンズ13」の試写会に行ってきたが、10日の夜に、その前作に当たる「オーシャンズ12」を日本テレビ系の「金曜ロードショー」でやっていたので観てみた。 簡単なあらすじを紹介すると、そのまた前作の「オーシャンズ11」で、オーシャンズが大金を盗んだカジノのオーナー・ベネディクトに金を返せと脅されて、返済金を稼ぐため、怪盗ナイト・フォックスと泥棒勝負をするというもの。 あちこちのブログなどで見る限り、駄作だと言う評判で、あまり評価は高くない感じだったので、かえって興味を持ったのだが、実際に観て納得。話がだらだらして、どこが山か良く分からない。まあ、このあたりは、大分本人の趣味と主観が入るのではあるが。あれだけの俳優陣を使っているのに残念なことだと感じた。 あらすじ自体も気に食わない。ベネディクトに金を返せと脅されて、はいそうですかと言うことを聞いてどうする。オーシャンズには泥棒スピリッツはないのか。ここは逆にベネディクトと対決して、一泡吹かせてやるくらいの気概がなくては面白くないではないか。 オーシャンズ13と同様、チーム内の人数が多すぎて、13人が12人でも、やっぱり顔が覚えられない。(監督)・スティーブン・ソダーバーグ(出演)・ジョージ・クルーニー(ダニエル・オーシャン)・ブラッド・ピット(ラスティ・ライアン)・ジュリア・ロバーツ(テス・オーシャン)・アンディ・ガルシア(テリー・ベネディクト) ほか・ヴァンサン・カッセル(フランソワ・トゥルアー/ナイト・フォックス) ほか ★「オーシャンズ13」の記事はこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ DVD「オーシャンズ11」、「オーシャンズ12」 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 13, 2007
コメント(2)
-

高千穂伝説殺人事件
宮崎県と言えば、最近は、そのまんま東知事の人気で、良く話題になることが多いが、神話の世界でも重要な位置を占めている。 天照大神の孫に当たるニニギノミコトが降臨したという、天孫降臨伝説の舞台が宮崎県の高千穂の峰とされているのである。しかし、もっと北にある高千穂町を天孫降臨の舞台とする説もあるようだ。 「高千穂伝説殺人事件」(内田康夫:角川書店)はこの高千穂を舞台とした浅見光彦シリーズの旅情ミステリーである。 今回、作品の最初の出だしの部分で、光彦は、天才バイオリニストのものすごい美女、本沢千恵子とうらやましいことにお見合いをしている。その千恵子の父が失踪してしまう。高千穂を暗示する、残された謎のテープ。そして殺人が。 事件のもともとの原因は、終戦時のある出来事。その秘密を守るため、狂信的な犯人が次々と罪を犯していったのであるが、終戦前後の出来事に、事件の原因を求めるのは、内田センセの好きなパターンだ。終戦前後は、日本はまさにカオス状態であり、何があっても不思議ではない。因縁の物語のモチーフにはもってこいなのであろう。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「高千穂伝説殺人事件」(内田康夫:角川書店) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 12, 2007
コメント(0)
-

QED 式の密室
「臨・兵・闘・者・皆・陣・列・在・前!!」 安倍晴明といえば、平安時代に活躍した陰陽師として小説や漫画、映画などでも有名である。十二神将と呼んだ式神を使役し、陰陽師としての名声をほしいままにし、最後は、従四位下まで異例の昇進をしている。 「QED 式の密室」(高田崇史:講談社)は、その陰陽師の家系に起きた密室殺人事件をテーマにした薀蓄系のミステリーである。 この本を最初に手にとった印象は、 「薄っ!!!」というものである。文庫本にして、わずか200ページ余り、このシリーズの他の作品の半分程度しかないのである。このシリーズは、薀蓄を長々と披露しているので、必然的に長編になってしまうところもあるのだが、この作品は、少し薀蓄の材料が少なかったのか? シリーズの他の作品と薀蓄が重なっている箇所も目立つが、一番の特徴は、陰陽師の使役した「式」とは何かについての考えを展開しているところであろう。真偽の程はさておき、なるほどと納得させられてしまう。 このシリーズ、刊行順に読んでいるわけではないので、巻末の解説を読んで始めて気がついたのだが冒頭で、、前作「東照宮の怨」の宿題になっていた「通りゃんせ」の唄の謎解きをして、最後に「竹取物語」への橋渡しをしている。 なお、同じく巻末の解説によれば、この作品は、2002年に講談社ノベルズがメフィスト賞受賞者に、「密室本」というテーマで競作をさせたものであるとのことである。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「QED 式の密室」(高田崇史:講談社) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 11, 2007
コメント(4)
-

ひぐらしのなく頃に解 目明し編1,2
久しぶりに、うちの子が買ってきていたので、例のごとく取り上げて、いや一時拝借して読んでみた。以前にも書いたが、「ひぐらしのなく頃に」とは、同人サークル「07th Expansion」が製作したサウンドノベルとこれに基づいたコミック、アニメなどの一連の作品のことである。 大きく前後編に分かれており、前編で謎を提起し、後半でその謎を解明するという構成である。前編は「鬼隠し編」「綿流し編」「祟殺し編」「暇潰し編」の4編から成っているが、コミックスは、全て刊行済みであり、現在は、後編の物語が進行中のようだ。 今回読んだのは、「目明し編」の1,2巻。前編は大体2巻で終わっているのだが今回は、3巻に続いている。3巻はこの冬に刊行予定とのことだ。 この物語の舞台は昭和58年の、雛見沢村という古い因習に囚われた村である。この村では、オヤシロさまという神様を祭っており、毎年綿流しの日に、村の体制に逆らうものが謎の死を遂げる。それはすべて、オヤシロさまの祟りだということだ。この村はすべて、オヤシロさまの論理で回っている。そして、それを取り仕切っているのが、園崎家なのである。 この物語の主人公は、園崎家次期当主園崎魅音の双子の妹詩音。閉じ込められていた、全寮制の学校を脱走し、戻ってくる。しかし、彼女の周りでは、次々に忌まわしい事件が・・・ 絵柄がきれいなのがいいね。絵に魅力のないコミックスは、初めから読む気がしないからね。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「ひぐらしのなく頃に解 目明し編1,2」(方條ゆとり/竜騎士07:スクエア・エニックス) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 10, 2007
コメント(2)
-

思想なんかいらない生活
常々思うに、いわゆる(文科系)知識人たちの書くものは、どうしてあのような持って回った言い方をしているのか。人に読ませたいと思っているのなら、誰にでも分かりやすい言葉とロジックで書くべきであるが、自己満足や自己顕示欲で書いているとしか思えない文章も多い気がする。 最近、「思想なんかいらない生活」(勢古浩爾:ちくま新書)という本を見つけた。いわゆる知識人達の書いたものを、正に、ちぎって投げ、ちぎっては投げと言う感じで徹底的におちょくって、いや批判している本だ。 この本の中で、引用されている知識人たちの文章がまたすさまじい。いったい誰に読ませようとして書いているのだろうか。そもそも自分でも理解しているのか。これらの文章に対して、作者がいちいちツッコミをいれているのだ。これが結構面白い。自分の言ったことに対して、自己ツッコミをしている箇所も多いのだが、これはちょっと余分で読みにくい。 いわゆる知識人の書いたものなど、読まなくても、人生に何の影響もないということに確信がもたせてくれる本である。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「思想なんかいらない生活」(勢古浩爾:ちくま新書) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 9, 2007
コメント(4)
-

上野谷中殺人事件
「故郷の訛りなつかし停車場の人ごみの中にそを聞きにゆく」(石川啄木) 上野駅は、東京の北の玄関口として、出稼ぎや集団就職で上京した多くの人々を迎えてきた。この上野駅の再開発に関わる殺人事件をテーマにしたミステリー小説が「上野谷中殺人事件」(内田康夫:中公文庫他)である。 開発には必ずといっていいほど、対立が付きまとう。ノスタルジーと発展への思い。そして、そこに様々な利権が絡んでくる。再開発の話さえなければ、このような事件は起こらなかったのだろう。 この事件の発端は、内田センセのところに届いた光彦あての手紙である。東北新幹線の地下工事現場で働いている青年からの、上野の不忍池で起きた殺人事件の犯人にされそうだから助けてくれという内容の手紙であった。しかし、光彦が躊躇している間に、その青年は谷中霊園で死体となって見つかる。 開発問題にゆれる人々の心を背景に、光彦の推理が冴える良作のミステリーである。 ○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 8, 2007
コメント(4)
-

QED 竹取物語
またまた、高田嵩史の作品を読んだ。「QED 竹取物語」(高田嵩史:講談社)である。 ごく簡単にあらすじを紹介しよう。舞台は奥多摩の織部村。ここには、不吉な手毬歌が伝わっており、この歌をなぞったような殺人事件が起こり、桑原崇と棚旗奈々そして小松崎良平のトリオが事件の謎に迫るというもの。 今回繰り延べられる薀蓄は、竹取物語に関してである。さすがに感心させられる薀蓄であるが、このシリーズをいくつか読んだ後では、若干新鮮味に欠ける感がある。初めてこのシリーズを読めばまた違うのだろうが、私の場合は、今回は少しノリが悪かった。 殺人事件のほうであるが、こちらは、このシリーズに共通しているように、平成の世にはちょっとありそうにないような動機であるが、いつものように薀蓄のついでに解決している。 ○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ QED 竹取物語(高田史:講談社) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 7, 2007
コメント(0)
-

悪魔の寵児(横溝正史)
これも、金田一耕介シリーズである。「悪魔の寵児」(横溝正史:角川書店)を読んだ。 多くの愛人を持つ種馬のような実業家・風間欣吾の妻や愛人が次々と連続猟奇殺人事件の犠牲に。そこには、雨男と名乗る謎の人物の影が・・・ こりゃ、ちょっと人前じゃ読みにくいですな。(読んでいたけど) 金田一耕介シリーズということで、あまり人から変な目では見られないだろうが、内容は、猟奇殺人はもちろん、SMあり、性病あり、隠微な蝋人形ありとまさに、横溝ワールド全開である。 横溝作品は、まだ、そんなにたくさん読んでいるわけではないが、誰を犯人にするかについて、ある傾向がありそうだ。今回も、やはりそんな感じで、意外な(横溝正史の小説ではそんなに以外ではないようだが)人物が犯人にされている。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 6, 2007
コメント(4)
-

竹人形殺人事件
福井県といえば、私が思い浮かぶのは、東尋坊、永平寺、越前ガニ、羽二重餅、竹人形くらいであろうか。 ところで、竹人形といえば、水上勉が昭和38年に発表した小説「越前竹人形」も良く知られている。今回紹介する「竹人形殺人事件」(内田康夫:角川書店)は、その竹人形をモチーフにした浅見光彦シリーズの旅情ミステリーである。 浅見光彦の兄陽一郎は、越前大観音堂建立に関係した不正について、地元の有力者・和村から圧力をかけられる。昔、浅見兄弟の父が、なじみの女性に送ったという竹人形を母の雪江に返したいというのである。亡き父親の女性関係に動揺する陽一郎。完全無欠と思えた彼にも、思いもかけぬ弱点があったものである。光彦は、真相を究明するため福井に向う。 この作品中で、竹人形に関する一つの疑問が呈されている。果たして竹人形と言えるものは、水上勉の「越前竹人形」以前からあったのだろうか。もしかすると、「越前竹人形」の小説に触発されて、竹人形が作られるようになったのではないか。浅見兄弟の父親が竹人形を贈ったのは、昭和26、7年頃だという。しかし昭和38年に発表された「越前竹人形」以前に竹人形が無ければ、陽一郎にかけられた圧力は事実無根ということになる。 実は、この答えは、案外簡単にネットで見つかった。越前竹人形協同組合の「越前竹人形の里」というサイトを見ると、竹人形は、昭和27年頃に、師田保隆と弟の三四郎兄弟によって創作されたのが始まりと書いてある。すると年代的には矛盾は無いことになる。竹人形というと、竹を組み合わせた素朴な民芸品のようなものを連想していたが、このサイトに掲載されている写真を見ると、見事な芸術品であることが分かる。 ところで光彦の方は、竹人形のことを聞くために訪ねた野地という男が殺され、例によってその容疑者扱いされたりしているが、次第に事件の真相にせまっていく。 それにしても光彦はあいかわらずよくもてる。今回のヒロインの女性記者・片岡明子に「ああ、この人に愛されたい-」なんて思われているのだから。もっとも、光彦の方は、相変わらず意気地が無いのであるが。 なお、余談ではあるが、この作品は、金曜プレステージの浅見光彦シリーズ第27弾として、中村俊介主演でドラマ化されるということである。○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ DVD「越前竹人形」 ○福井県の名産 「越前ガニ」と「羽二重餅」「ずわいがに(オス)M」【3杯セット】 福井の銘菓★羽二重餅風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 5, 2007
コメント(2)
-

オーシャンズ13
久しぶりに試写会が当たった。応募してもほとんど当たらないので、ポイント交換なんかを利用して行くことが多いのだが、今回は見事懸賞当選である。 当たったのは、今話題の「オーシャンズ13」である。 このシリーズ、残念ながらこれまで一度も観ていないのだが、この作品より前に「オーシャンズ11」、「オーシャンズ12」というのがあったようだ。オーシャンズとは、ダニエル・オーシャンを中心とした犯罪チームのことらしい。犯罪チームと言っても殺人のような陰湿なものではなく、スケールのでっかい窃盗である。観客は、彼らが奇想天外な作戦をいかに遂行し、目的のものを頂戴するかという過程を楽しむという映画のようだ。どこか、その昔、テレビで観ていた「スパイ大作戦」を連想させる。 話の内容を一口で言えば、バンクスにだまされ、丸裸にされたルーベンのリベンジのため、オーシャンズが奇想天外な作戦を遂行するというものである。 「オーシャンズ13」の13はメンバーの人数のようだが、多すぎて誰がメンバーか良く分からない。元々人の顔を覚えるのが苦手なのだが、中心となって動いている数人以外は、正規のメンバーか買収されるなどして一時的に協力している人物かさっぱり分からなかった。まあ、それでもストーリーを楽しむにはあまり影響はないので、それでいいのかもしれないが。 それにしても、やることのスケールがでかすぎる。そんなことをやる金があるんなら、犯罪しなくっても、メンバー全員遊んで暮らせるんじゃないかなと思うのだが。 気の毒だったのは、バンクスのカジノホテルを調査に来た、ホテルの格付け調査員。オーシャンズのために散々な目にあっている。でもオーシャンズも律儀に、最後にちゃんとフォローしていたので目出度し目出度しといったところか。(監督)・スティーブン・ソダーバーグ(出演)・ジョージ・クルーニー(ダニエル・オーシャン)・ブラッド・ピット(ラスティ・ライアン)・アル・パチーノ(ウィリー・バンクス)・エリオット・グールド(ルーベン・ティシュコフ) ほか「オーシャンズ13」の公式HPはこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ DVD「オーシャンズ11」、「オーシャンズ12」 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 4, 2007
コメント(12)
-

鳩笛草(宮部みゆき)
「鳩笛草」(宮部みゆき:光文社)は「朽ちてゆくまで」、「燔祭」、「鳩笛草」という3つの短編作品を収録した本である。 これらの作品の共通テーマは「超能力」。主人公は、それぞれ超能力を持った女性である。 「朽ちてゆくまで」の主人公麻生智子は予知能力者である。いやあったというべきか。8歳のときの事故で、両親をが亡くし、それまでの自分の記憶もを無くしていたのだ。祖母が死んで出てきた、ビデオテープの山。それを観て、彼女は、自分がかって予知能力を持っていたことを知り、両親が死んだのは自分のせいではないかと悩む。 「燔祭」の主人公青木淳子の能力は、すさまじい。彼女は、念力により人や物体を発火させると言う念力放火能力(パイロキネシス)の能力者である。自らを「装填された銃」にたとえ、妹を殺された多田一樹に代わり犯人に報復をすると言うのだ。また、この短編は、後の長編「クロスファイア」の序章とも言える作品である。 「鳩笛草」の主人公、本田貴子は、触れただけで、人の心を読み取ることができる。彼女はその能力を活かして刑事になったが、急激に能力が衰えてきている。 人は、誰でも、自分の才能を発揮して認められたいという欲求がある。これがスポーツの才能や学問の才能だったらよかったのだが、不幸なことに、彼女達の才能とは超能力であった。人は、自分の理解できないものを本能的に恐れ排斥する。超能力を持っていることは、人には知られてはならないのだ。しかしその一方では、力を誇示したいという誘惑がつきまとうのである。その典型が、青木淳子であろう。彼女の能力は、他の二人に比べても、群を抜いて破壊的なものである。ひっそりと目立たないように生きてきたが、ついに、一樹の妹の敵討ちを口実に、自分のすさまじい力をに見せつけるのである。「装填した銃を持っていたなら、誰だっていつかは撃ってみたくなる」という彼女の言葉が端的にそれを現している。 麻生智子は、自分が超能力を持っていたことを忘れて生きてきたのだから、ある意味幸せだったのかもしれない。しかし、その事実を知ったとき、両親の死に対する疑念に悩まされる。 本田貴子は、これまで、超能力をまあまあうまく使ってきた。その反動がでてきたのだろうか。彼女は結局どうなるのか、この作品ではそこまでは書かれていない。 智子と貴子が淳子と一番違うのは、いい人たちに囲まれていると言うことである。いろいろあったが、結局は良い方向に行くという予感がある。しかし、青木淳子の場合は、一番危険な能力を持ちながら、孤独なのである。「クロスファイア」も今手元にあるが、例によって積読がなかなか解消できないため、読むのは大分先になりそうである。果たして、彼女は、どのようになっているのだろうか。 ○ブログの内容が気に入ったら応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「クロスファイア(上)(下)」(宮部みゆき:光文社) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 3, 2007
コメント(6)
-

怪談
映画「怪談」の試写会に行った。出だしは、一龍斎貞水の語りで始まったが、モノクロームの画面とよくマッチし、なかなか期待が持てた。 煙草売りの新吉と、三味線の師匠豊志賀は、出会いそしてひかれ合う。しかし20年前豊志賀の父を殺したのは、新吉の父であった。ここから因縁に彩られた怖い話が始まる。 ストーリーは、まあ標準的な怪談話かな。ところどころ怖いシーンがあったが、それがぶつ切りのように登場して、持続性がなかったのは残念。 疑問に思ったのは、豊志賀の死因。これって、結局、豊志賀の親父の祟りじゃないか。自分の娘に祟ってどうする。そして、死んだ豊志賀も新吉を祟る。なんちゅう親子や! もうひとつ意味が分からなかったのが、新吉の赤ん坊。じっと新吉を見て、確かに不気味なのだが、何をするわけでもなく、登場する必要があったのだろうか。 最後の方で、新吉が大立ち回りをする場面があったが、「新吉強すぎ!!」 元々は武士の子だったかもしれないが、煙草売りとして育っており、どうしてこんなに強いんだろう。まるで荒木又衛門(鍵屋の辻、36人斬り、知ってるかな?)だ。 最後のシーンは、「サロメ」を意識したつもりかな? 新吉の頭がでかすぎて、笑ってしまった。 映画の出来としては、最初の出だしが良かったのと、井上真央がかわいかったので、甘めにつけて70点位かな。(一口コメント) 豊志賀:女は怖いの一言。 新吉 :なぜかハリポタのスネイプ先生を連想。特にザンバラ髪のとき。 お久 :幽霊やるにはかわいすぎ。 お賤 :悪い女や! でも色っぽい。(原作)・ 三遊亭円朝 (監督)・ 中田秀夫 (出演)・尾上菊之助(新吉)・黒木瞳(豊志賀)・井上真央(お久)・瀬戸朝香(お賤) ほか「怪談」の公式HPはこちら○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 「怪談」(行川渉/三遊亭円朝:角川書店) 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 2, 2007
コメント(14)
-

奥津温泉あたりの田舎風景
「奥津温泉」に近いところにあるが、何の変哲もない田舎風景である。ちょっと見ると、どこにでもあるような風景である。奥津温泉の近くであることを示すものは、写りは悪いが、川の向こうに建っている「奥津温泉」の標識位である。 奥津温泉は、美作三湯の一つであり、藤原審爾の小説「秋津温泉」の舞台でもある。足踏み洗濯でも知られたところだ。以前一度行ったことがあるが、今回は通り過ぎただけ。「奥津温泉付近の田舎風」 辺りには、どこにでもあるような野草ガ生えているが、良く見るとかわいい花がついている。写真は、「ヒメジョオン」(たぶん)。ハルジオンと紛らわしいが、ハルジオンの方は、つぼみがうなだれているのが特徴である。「ヒメジョオン」 こちらは、ドクダミの花である。他の雑草に紛れていて、ちょっと分かりにくい。葉は乾かして、お茶代わりに飲むと、色々薬効があると言われている。「ドクダミの花」 さて、この木にも、花が咲いている。私のような田舎者にはすぐに何の木か分かるのだが、あえて書かないでおこう。別に賞品は無いけど、分かった人は、コメントにでも書いてね。「何の花?」○応援してね。 ●「人気ブログランキング」 ⇒ ●「にほんブログ村」 ⇒ 風と雲の郷 別館「文理両道」(gooブログ)はこちら
August 1, 2007
コメント(2)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0941 花まんま
- (2025-11-27 00:00:14)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- レジスタ! 1巻 読了
- (2025-11-24 23:38:36)
-
-
-
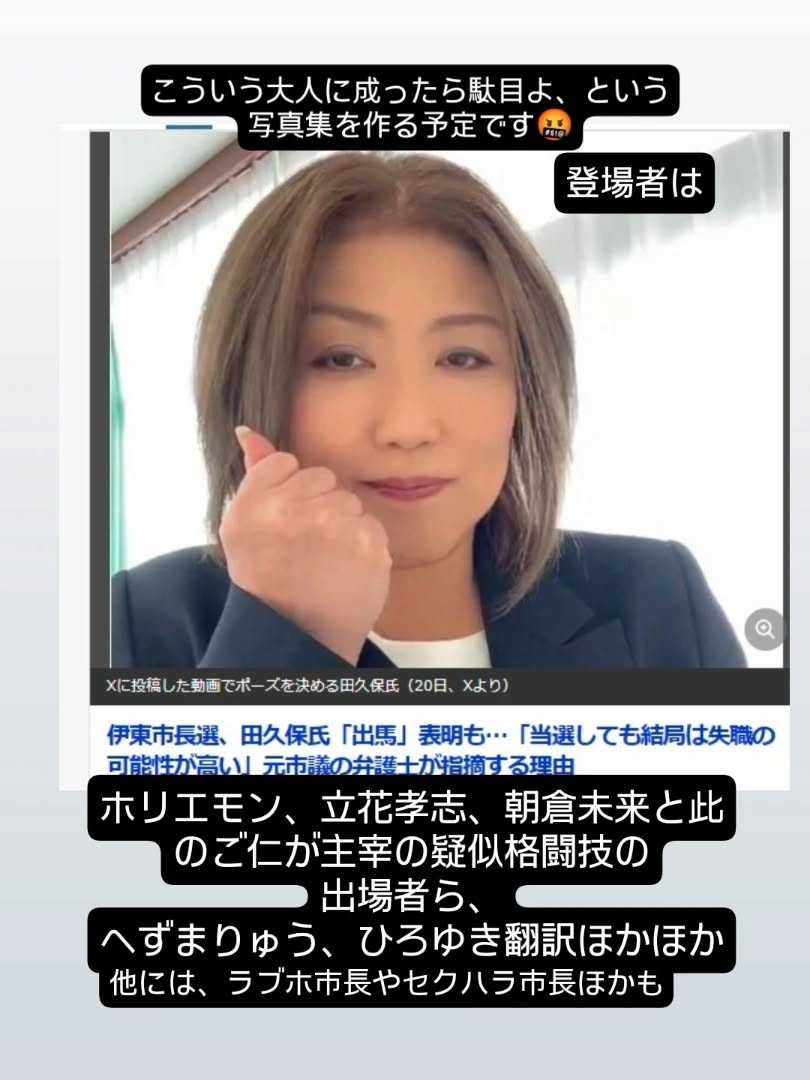
- 人生、生き方についてあれこれ
- Nov.23 田久保前市長・立花孝志氏・…
- (2025-11-23 19:32:35)
-







