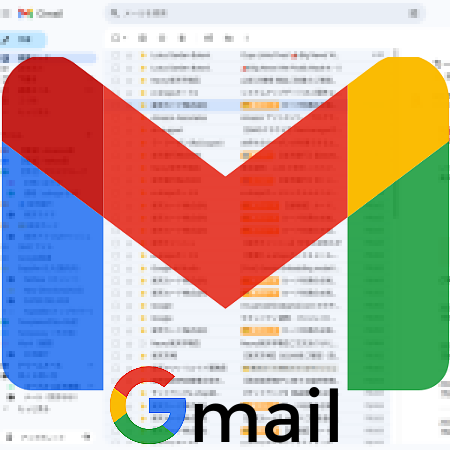2023年02月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
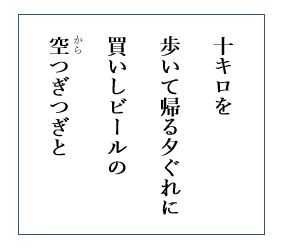
〇〇 異母姉妹、ドラッグストアとコンビニ
♪ 十キロを歩いて帰る夕ぐれに買いしビールの空(から)つぎつぎと 久しぶりに隣の東海市の「茶房じゅん」まで歩いた。午後2時には気温も上がり、いつもより薄着で出たもののけっこう暑かった。 店主の淳さんが、いつも店内に上手に花を活けている。先日(2月20日)のFBには、「いよいよ、春がそこまで来ました。庭の花々たちが、ボチボチと動き始めました。黒椿、白と赤の薮椿、ぼくはん、リュウキンカ、猫柳、クリスマスローズ、元気になります。紅梅、白梅も今年も元気に、咲いてくれました。」とのコメントがあった。 そういうこともあって、トウワタの種2莢分を持参。アブラムシが付くので木酢液で退治すること、切り口から白い汁が出るので、水で洗ってから活けること、種は20℃ほどになってから蒔くことなど、注意すべきことを伝えて、さし上げてきた。 ちょっと変わった個性的な花なので、どんな風に活けて見せてくれるのかに興味があって・・。たくさんあるので欲しい方、差し上げますよ~。 今は大潮→小潮。午後は干潮の時間帯で、河口に近いところはかなり水が引いて底が見えている。引いている状況をみててっきり大潮だと思ってしまった。毎時潮位グラフ 2023年2月13日~2023年2月27日の潮位予測グラフの縦軸は潮位、横軸は日付図中の水色の線は2023年の標高の基準面 27日(小潮) 満潮時刻 9:39 潮位 186 満潮時刻 23:34 潮位 148、干潮時刻 3:29 潮位 104 満潮時刻 16:59 潮位 63 20日(大潮) 満潮時刻 6:37 潮位 238 満潮時刻 8:01 潮位 233、干潮時刻 0:01 潮位 -22 干潮時刻 12:20 潮位 61 干満の差が大きい。 白鷺が小魚を狙っている姿が面白かった。首を、右へくるッ左へくるッと回しているばかりで、なかな狙いが定まらない様子。まだ若い鳥なのかもしれない。 天然温泉・玉ノ湯がコロナ禍で客足が遠のいたせいなのか、いつの間にか廃業してしまっている(2021年11月に閉館)。跡地で新たな工事をしているのは知っていたが、その全貌が現れて、へえ~!と思った。 ドラッグストアらしいものが出来、3月中旬のオープンを前にして広い駐車場の奥にデーンと構えていた。 この辺ではあまり見ない「くすりのアオキ」。石川県にある企業らしい。2003年にイオンと業務提携している。2014年、一宮市に愛知での1号店をオープンしている。当然、この地域では初めての出店となる。昨年10月 なぜ驚いたかというと、わが家から2キロほどの古見駅ちかくに「GENKY(ゲンキー)」が、やはり3月にオープンを控えている。この会社も本社が福井県にある。 ドラッグストアが目白押しの知多市。スギ薬局が、コンビニのごとく1キロ四方に3軒もあるし、他のドラッグストアも何軒かある。この業界は、全国的に進出競争が熾烈になっているようだ。 昔から富山の薬売りは有名で、その明治の創業から脈々と継承されてきた薬業界。日用品と食品まで扱う “ドラッグストアという名のスーパー” に発展してきた。生鮮食料品も扱ってくれるとありがたいが、さすがにそこまでは行かないか。 朝倉駅前にも何らかの商業施設を誘致するらしいが、周りでどんどん先んじられてしまって、この場所に進出するメリットが目減りしていく気がしてならない。
2023.02.28
コメント(0)
-
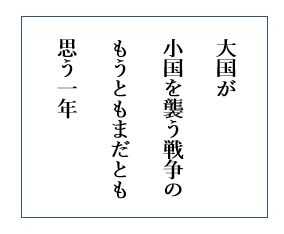
〇〇 春がきて、その先想えば気の重し
♪ 大国が小国を襲う戦争のもうともまだとも思う一年 *ロシアによるウクライナ侵攻から、2月24日でまる1年になる。 3月弥生に合わせるように、気温が上昇して安定した陽気が続くようになってきました。今朝はまだ冷たい風が吹いていますが、これも徐々に収まってくる。日中は14℃ほどまで上昇し、風もないポカポカ陽気になる模様。tenki.jp 朝晩の温度差は相変わらずだ。今年の「佐布里の梅まつり」は、週末が荒れた天気ばかりで散々だったようだ。高いところにあって吹きっさらしなので、ゆっくり花を楽しめるような状況ではなかったでしょう。 我が家の「パキラ」も激しい温度差のせいか、葉がどんどん茶色になっていてみっともない。すでに取り払った葉もあるし、これらも落ちてしまうと樹形も悪くなる。今年は剪定をせず何とか花を咲かせてみたいと思っていたが、このままでいいのかどうか。 1年でこれだけ伸びる。もう1年このままにしておくとかなりの大きさになる。花を諦めて、木肌色になっている幹の10cmほど上から先で、思い切って切ってしまおうか。形が早く整うこと考えると、5~7月の成長期に入り始めた頃がいらしいが・・。ちょっと迷うところ。 まだ植え替えの必要はなさそうだ。☆「キエーロ」は3月からと思っていたが、カミさんがさっそく生ゴミを「今日はこのぐらいあるよー」と見せるので、さっそく入れてやることに。 昨日、水をまいて湿らせておいたのが、ちょっと水気が多すぎたかと気になった。もしそうなら庭土を足してやればいいことだが・・。 大根の皮、コーヒーのかす、出汁を取った削り節とコンブ。大した量じゃないが、取りあえず試しにやってみることに。 スコップで細かくしながら土によく混ぜ、埋め込んで終わり。6ヶ所ほどを順番に入れて、ローテーションしていく。入れたた日を書いて立てておくと良いが、毎日ならその必要もない。 我が家では、2日に1度ぐらいがちょうどいいんじゃないかな。 夏場は3~4日、冬場は10日前後で分解されるらしい。この時期なら1週間というころか。 今週は全国的に見ても、17℃ほどまで上がる日が有ったりして、春が急速に成長していく。5月にはもう夏がやって来そうな予感がする。そうなれば、分解速度も早まるというもの。 真意が分からないまま極端なことを言い、平気で前言を翻す、そんな首相にシンクロしているような今年の気候。どさくさ紛れに独断でとんでもないことを、幾つも決めてしまった。今年の夏は、ゼッタイに猛暑だ。
2023.02.27
コメント(0)
-
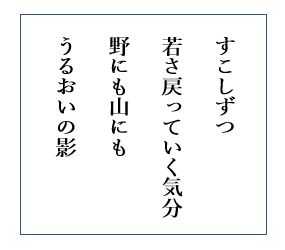
〇〇 最後なる寒風受けて2月尽 キエーロが完成
♪ すこしずつ若さ戻っていく気分野にも山にもうるおいの影 昨日は寒かった。北西の風が吹きまくっていて、とても外へ出る気にはなれなかった。今日も寒いがこれも今日まで。月曜日からは待望の春の陽気がやってくる。「キエーロ」の容器を作る(箱はプランターにしていたものを使う)つもりでいたので、蓋を作る材料を買いにホームセンターへ。 黒土14ℓを2袋、波板クリア(6尺 幅65㎝)1枚、パイン(の集成材(1820×18×18)(91×18×18)各1本、傘釘、丁番。これだけで3,000円ほどかかった。 蓋の造作は家の中で。丁番を取り付けて、土を入れれば完成だ。底板はすき間を開けて付けてあるので良いかと思うが、ネットをも一枚重ねておいた方が良いかと。 生ごみを入れる深さが20㎝は欲しいとのことだが、箱の上まで25㎝しかない。3㎝ほど下がったところまで土を入れる予定で、まあ何とかなるだろう。乾燥しないように注意する必要はある。 土が37ℓ必要だが、黒土は28ℓしかない。9ℓ足りないのは庭土で補充するつもり。 孫をスイミングに迎えにいく日で、ばーばが夕方5時過ぎに連れてきた。最初は新聞に載っていた「間違い探しクイズ」をやらせていたが、終わると、エネルギーが余っているらしく、「ドッジボールしよう」と言いだした。「しょうがない、付き合ってやるか」と外に出る。6~7mの北西の強風が真正面に。身震いしながらちびっこ広場へ。 まったくもって、「子どもは風の子」。寒いなんて言葉は一度も出ない。孫を相手に寒さも忘れ、途中からサッカーに変わって走り回る。 真上に三日月が輝き、蕾も見えない桜の枝に影を作っている。足早に夜の帳が下りてきて、顔もボールも見えなくなった。「帰ろうか~!」─ ☆ ── ☆ ★ ☆ ── ☆ ─そして今日、「キエーロ」を完成させた。 波板の幅が65㎝しかなく、ぎりぎりのサイズ。置く位置がブロック塀の脇なので、吹き降りで雨水でびしょびしょになるのは何とか避けられそうだ。陽はカンカンに当たるので申し分ない。 庭土を篩でふるって余分なものを取り除き、3分の1ほど入れた。ちょっと足りない気もするが、取りあえずこれでやってみよう。購入した黒土も庭土も、サラサラに乾燥してる。適当な湿り気が必要なので如雨露でたっぷり水を含ませる。1時間ほど経って見てみると、これもまあいい塩梅だ。 蓋の持ち手は補強金具があったので、それを転用。長すぎるので、切り込みを入れて折り曲げてある。すごく持ちやすく、指1本でも開けられる。もし、強風で蓋が開くようなら、この部分を何かで固定すればそれで済む。箱ごと移動する場合も考えて、サイドに持ち手も付けた。 気温も上がってくるようなので、3月から始めてみよう。
2023.02.26
コメント(2)
-
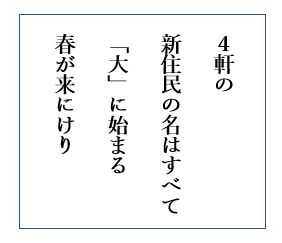
〇〇 輝きて全貌見せる三軒目
♪ 4軒の新住民の名はすべて「大」に始まる春が来にけり 新築中の住宅の全貌が見えてきた。中の大工仕事がようやく終わり、クロス張りとか内装の工事への段階に入るようだ。 大工さんとときどき立ち話をする。いろんな話が聞けて楽しい。近頃はすべて工場の機械でプレカットするので、大工が腕を発揮する機会が無くなってしまっている。細々した手作業の要る場面にしか必要とされないようだ。何とも気の毒なことだとおもうが、時世の変化は誰にも留められない。 棟上げの時に、柱や梁がなんかの理由で折れたりしても、電話で工場に部材の番号を伝えればパパッと作って、作業中に届けてくれるという。小僧の時から身に付けた必須の技術も役に立たたず、鑿を研ぐ必要もない。鋸も切れなくなれば替え刃を使うので目立ての必要もない、など・・・。 白アリはいくら消毒しても、すでに入ってしまったものは上へ上がっていくので、土台だけやっても意味がないという。最近は米松を使うことが多いらしく、白アリの好きな木の一つだという。 この正面のリビングから外を眺めた感じは悪くない。道路より高くなっているし、距離もあるので落ち着いた感じがする。しかし、この前庭も駐車場としてコンクリート固めになってしまうのかもしれない。 端材やさまざまなゴミが分別して篭に入れてある。篭に入らないものがあったので、聞いたら好きなだけ持って行っていいとのこと。使えそうなものを選んでもらっておいた。 今は集成材をよく使う。密度が高く、狂いもないのでかなり丈夫。その代わりかなり重い。1m弱(15×9㎝)のこの端材、2面にウレタン塗装がしてある。鴨居か梁に使ったものだろうか・・ このお宅、4月30日まで工事期間が設けてある。3月中に内装、設備を終え、外周りの工事が4月中頃までかかるのだろう。その工事と入れ替わりに、その隣の工事が始まることになっている。工事期間は3月10日から8月31日。まだまだ落ち着かない日々が続くことになっている。 一つ面白いことがある。すでに入居している2軒と、新しい2軒の苗字の頭文字が、すべて「大」の字。何という偶然。こんなことって、そうそう有るもんじゃない。 最初の2軒はまあ偶然だなぁと思っていた。そして3軒目もそうなって、ほう!という感じ。4軒目が工事のあいさつにみえて、名前を見てビックリ。え~?!また~!! これは「吉」の卦に違いない。このエリアのこの場所で、何かいいことがありそうな・・・「大」は、「両手・両足を伸ばした人」の象形から成り立っている。多くの意味を持つ。①「おおきい」②「おおいに」③「おおきさ(大きいこと。また、大小の程度)」④「根本(物事が成り立っている基礎になる物)」⑤「優れている」、「地位・身分・人格等が高く立派」⑥「尊敬して上に添える言葉」⑦「おおよそ(細かい点を除いた主要な部分)」⑧「強い」、「力・勢い等が強い」⑨「久しい」⑩「遠い」⑪「粗い」⑫「重い」⑬「だいとする(重んじる、尊ぶ、誇る、実際より偉い者だと思い込む)」
2023.02.25
コメント(0)
-
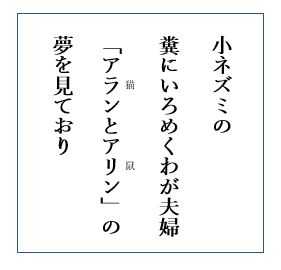
〇〇 小ネズミの可愛い顔がいじらしい
♪ 小ネズミの糞にいろめくわが夫婦「アラン(猫)とアリン(鼠)」の夢を見ており しばらく前から家の中でネズミの糞が見つかるようになっている。あちこちと所かまわず、ある時はまとまって、ある場所ではほんの1つか2つ。 左から去年の10月、12月、今年の1月(電子レンジの置いてある棚の奥にあった糞) たぶんハツカネズミだろうと思う。今までに何度も、我が家の猫たちが咥えてきた、小さくてかわいいネズミだ。まだ元気なやつは猫から救助して、外に逃がしてやったりしていた。 いつぞやはアランが家の中で見失って、どこかに隠れたままになっていたことがあった。そいつが棲みついているのかとも思ったが、よくわからない。 最近は、同じ場所で糞が見つかるようになった。洗面所兼脱衣所の脇に洗濯機が設置してあり、その上の空間に洗濯物を入れる盥が置いてある。その洗濯物の中に時々糞が見つかるのだ。 猫の飲み水が置いてあり、しょっちゅう猫が出入りしているところでもある。どうやら家人が寝静まった夜に出没しているらしい。アランも冬の寒い時期は、2階のベッドに潜り込んで朝まで寝ていることも多い。 どこかに潜んでいて、夜になって出てくるというのが自然な発想だが、違うのかもしれないと思い始めている。外にいるやつが、夜になって猫用の通用門から入って来るんじゃないか? 猫の餌も置いてあるし、外よりもずっと暖かい。洗濯物の上ならなおさらだ。 ネズミはどこでも歩けてしまう。天井だって逆さま状態のまま平気で移動できる。昔、行きつけの喫茶店で、天井から鼠が落ちてきたことがあった。家ネズミの太ったやつで、自分の体重を支えられなかったらしい。 我が家に出没するネズミの顔は、何度か捕まえて逃がしてやったりしているのでよく見ている。何故か水のない浴槽に逃げ込んだことがあった。ある時は、盥の中で立ち上がってバンザイノの姿勢で「たすけて!」とやっていたこともあった。ほんとうに可愛い顔をしている。 その時の鼠騒動は、2020年12月8日。その翌日のブログを見ると「ハツカネズミ」のことが書いてある。「害はクマネズミ属の家ネズミよりもずっと小さい。渇きに強く、コンテナなどの荷物に潜んで移動し、世界の広い地域に分布する。日本でも、史前移入種として、島嶼(とうしょ)部を含むほぼ全地域に生息する」 動物好きのわが夫婦。このかわいいネズミが、夜な夜な家の中を歩きまわっている姿を連想し、「トムとジェリー」を思いうかべてはほくそ笑んでいる。実害はほとんどないので、いっそ、餌付けして手なずけられるものなら仲良くしたいと思う。暗視カメラを設置して、動き回っている姿を観察できたらなぁ、なんてことも思ったりする。「アランとアリン」なんて名前で、だれか漫画にしてくれないか?
2023.02.24
コメント(0)
-
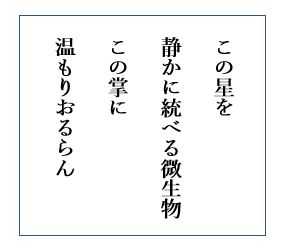
〇〇 キエーロにエコを恃みてキエコーロ
♪ この星を静かに統べる微生物この掌に温もりおるらん 昨年の10月26日のブログに「キエーロ」のことを書いた。それで、いよいよそのための準備に取り掛かっている。木製のプランターがあるのでそれを利用する。しかし、今日は生憎の雨模様で作業はできそうにない。土の量は36ℓぐらい。小食の2人家族なので十分だろう。 これに通気性を考慮し、雨が入らない事、風で蓋が開いたりしないようにして蓋を付けるだけ。 多くの地方自治体で導入しているので、知多市ではどうなっているのか市に問い合わせてみると、環境経済部 ごみ対策課からこんな回答が返って来た。 現在、本市では「キエーロ」の推奨は行っていません。堆肥を利用できる方に対しては、コンポスト等を利用して生ごみの堆肥化に取り組んでいただくよう啓発をしています。 ごみの減量に取り組むうえで、生ごみの減量は重要であると考えています。まずは、3つのキリ「食材の使いキリ、料理の食べキリ、生ごみの水キリ」に努めていただくよう周知を図っていくことが重要であると考えています。「キエーロ」については、堆肥を活用することができない方でも、置場を確保できれば設置することができるため、今後、ホームページなどで活用の周知をすることを検討してまいりますのでよろしくお願いします。 隣の常滑市ではずいぶん前から取り組んでいるらしく、市の女性市会議員の家の処理容器が10年でこんな風になりましたと、FBに写真を載せていた。 このキエーロのお陰でゴミ出しは3ヶ月に1回、小の袋で出すのみだそうです。生ゴミ入れるのでかさが増えていくと思っていたが何故か、土がどんどん減っていくという。これはちょっと理解しがたいが・・。 常滑市では、授産所の子どもたちが作ったものを15,000円で買い上げ、市が10,000円補助して市民は5,000円で買えるんだとか。なかなか普及しないという。やはり5,000円がネックなのだろう。 利用している自治体のサイトではもっと簡単な作りのものを紹介している。プラスチックのプランターを使って、光の透る波トタンで蓋を作ってやるだけのもの。こちらは、横須賀市が紹介している、キエーロの仕組みをそのまま小型・軽量化したミニ・キエーロ。土:14ℓ 費用の目安は2~3千円。 ローテーションしていくので3回分が埋まると分解するまで待たなければならない。「中津市」では3タイプを考案して作り方を指導している。使い方はもちろん、冬の扱い方も丁寧に指導している。内側にウレタンまで入れ込んである。ここまでやると材料費がかなりかかる。土の量に対して箱はかなり大きめになっている。「作り方」●(大サイズ)概ね幅 85 ㎝×奥行 45 ㎝×高さ 80㎝ 土:100ℓ一軒家のファミリー向け。1回につき約 500g の生ごみをほぼ毎日処理可能。●(中サイズ)概ね幅 60 ㎝×奥行 40 ㎝×高さ 60㎝ 土:60ℓ一軒家またはアパート・マンションに住む少人数の家庭向け。1回につき約 500g の生ごみを 2~3 日に1回処理可能。●(小サイズ)概ね幅 60 ㎝×奥行 40 ㎝×高さ 40㎝ 土:40ℓアパート・マンションに住む少人数の家庭向け。1回につき 200~300gの生ごみを週に2回程度処理可能。 汁気のもの(カレーの残り、ラーメン、みそ汁など)、油もの(食用油、バターなど)なんでもござれ。分解にかかる日数は、夏場は3~4日、冬場は 10 日前後。 実際は、どの程度の量をいれられるか、様子を見ながらアレンジしていけばいい。分解しにくいものは避けるという手もある。 微生物は、様々なシーンでわれわれ生物を助けてくれる。この自然にゴミが消えるという現象は、理科の教材にももってこいだろう。目に見えないものが仕事をし、結果を目に見える形で示してくれる。見過ごされている自然の力を、食べ物を介して身近に知ることが出来る。 そして、その食べ物はお腹の中でも、様々な微生物によって消化吸収を助けてもらっている。食べ物の中には、発酵という微生物の力を借りて生み出されるものまである。 21日に書いた「自然還元葬」もまた微生物あってのもの。「地球全体を支配しているのは微生物である」と言っても過言ではないでしょう。頼もしく、可愛くもあり、愛おしい存在でもある微生物。「 微生物に対するリスペクトをもって、「生ゴミよきれいにな~れ」と声を掛ける。
2023.02.23
コメント(1)
-
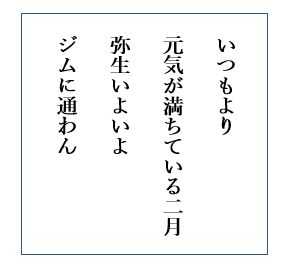
〇〇 遠足の前夜の気分春隣
♪ いつもより元気が満ちている二月弥生いよいよジムに通わん 週2回、1回1時間程度の筋トレ。スクワットさえまともに出来なかった。3、4回だったのが少しずつ増え、15回までできるようになり、15回を3セットの45回が出来るようになったころ、より効果が出るようにと、バーベルを肩に背負ってのスクワットを始める。 10キロのバーベルから始め、20キロに変わり、それからは、20キロのバーベルに2.5キロの軽いおもりを足していって、2年目には30キロの重さのバーベルを肩に背負ってスクワットができるようになった。そして、3年半たったころにはバーベルの重さは40キロにも。大村崑を「筋トレ沼に落とした」20代青年の正体「ぼくの師匠は、60歳年下のスーパーマン」 東洋経済ONLINE こうして、大村崑は86歳からライザップに通いはじめて、あの驚くべき筋肉を身に付けて行ったという。私も最近は基礎的な体力が戻りつつあって、ちょっと余裕がでてきた。しかし、家で好きな時に適当にやっているだけなので、せいぜい30分程度しかできていない。やはりジムに通った方が良いのだろうか。 幸い、歩いて2分のところにある市の体育館にはトレーニングルームがある。そこそこの器具が並んでいる。1回330円で利用できる。使わない手はないだろう。トレーナーがいて、どうしたいかを言えばアドバイスもしてくれるらしい。午前:午前9時00分~午後0時30分、午後:午後1時00分~午後5時00分夜間:午後5時30分~午後9時00分*使用料 1回券:330円、回数券:3,300円(11回分)、定期券:2,300円/月(発行日から1か月間) 暖かくなってきそうなので、3月から通ってみようかな。同級生も長年通っていて誘われたこともある。そいつはボートをやっていて今でも漕ぎに行っているし、化け物のような体をしている。その体を見て、とてもついて行けそうにないと思って尻込みしていた。 先日は、スギ薬局でZABASのホエイタイプを買って来たばかり。15%のクーポンを使って2,000円ほどで買えた。 登山用のリュック(MYSTERY RANCH In & Out Forest 19L 7,480円)も買ったことだし、着々と今年の新生活の準備をしている。 これは、サミットパックとしての機能をしっかりおさえつつ、非常に軽量化(400g)されていて、全体をフロントのメッシュポケットに収納して小さなウォーターボトル程度のサイズに畳めるのがミソ。 リュック旅行、アウトドア、登山、キャンプ、レジャーにオールマイティのsぐれもの。もちろん耐水性。 (参考写真) こんな形で送られてきた。 体重が減っていて、みすぼらしい体になって行くのをみすみす放置しているわけにはいかない。しっかり筋トレすると、いったん減った体重が、逆に増える。筋肉は脂肪よりも重たいので、その分、体重も増えるというのだ。 大村崑は、週2回ジムに通いつづけ、気がつけば筋トレを始めてから3年半で、あれだけの体を作り上げた。「俺を殺す気か~!」と思うほどのきついトレーナーの指導のお陰だ。金をとるということは結果にコミットしているがゆえの、保証金みたいなものだろう。 無料の指導にはそこまでの責任も期待も負ってはいない。でも同じ目標に向かって頑張っている、同じ年代の人たちに刺激を受け、励まされながらやれるので続けられもするのだろう。 講習は受けてある。受講証明書はどこかに行ってしまっているが、再発行してもらえるのかどうか。
2023.02.22
コメント(0)
-

〇〇 自然有機還元葬は大賛成
♪ エコ、エコとエコーはエゴの響きして微生物にも手を借りにゆく 今、アメリカで画期的な遺体の埋葬方法が注目されている。ワシントン州では19年に「Natural Organic Reduction(自然有機還元葬)」と定義し、20年5月に施行した。この葬法を「ヒューマン・コンポスティング(人間の堆肥化、堆肥葬)」とも呼ぶ。 その仕組みはこうだ。(朝日新聞 GLOBEより) 金属製の六角柱の中に「筒型の還元葬を行う装置」が収まっている。その容器中に、最適な比率に計算されたウッドチップやアルファルファ(糸もやし)、わらを敷きつめた棺に遺体を安置し、上からもわらなどで覆って装置に収める。 すぐに微生物が分解を始め、およそ一日で内部の温度は約65度まで上がる。コンピューター制御で内部の空気を循環させ、温度や湿度を管理する。しばらく高温が続き、この間に病原菌は死滅する。 1週間ほどで温度が下がり始めたら、隅々まで酸素が行き渡る様に超低速で数時間、筒型の装置ごと回転させる。 1カ月ほどで柔らかな土と骨だけになり、体積は約3分の1になる。骨は機械で細かくした上で土に戻す。約1立法メートルの容器に移し、2~4週間ほど乾燥させる。「人工的に熱を加えてり、内部をかき混ぜたりはしない。微生物の力だけで、自然な形で土に還る。」のだという。余分なことは一切せず、微生物が完璧に安全で肥沃な土にして大地に還してくれる。 生物はみんな、生きている間は大いに微生物のお世話になり、死んだ後にも微生物のお世話になるわけだ。完璧な処理をして、元の元素の戻してくれる。エネルギーの消費も必要なく環境を汚すこともない。何て理想的な、究極の死後の在り方だこと。一つの遺体からできる堆肥の量は、荷車2台分ほど(遺体の大きさにもよる)らしい。 家族らは一部を手元に残したり、庭で木や花を育てたり、保護林へ寄付することもできる。 北米の従来の土葬は、防腐処理(エンバーミング=土壌汚染のもと)して木や金属の棺に納め、コンクリートや金属で土中を補強して埋葬する。遺体は長い間腐らず、土中には木や金属が埋められて環境にも悪い。火葬にすれば化石燃料を使い、二酸化炭素を放出する。それをなんとか出来ないかと考えて生まれたのが、この「ヒューマン・コンポスティング(人間の堆肥化、堆肥葬)」。 この会社「リコンポーズ(Recompose)」は20年12月以降、2,000件超の埋葬をおこなっている。基本料金7,000ドル(約90万円)350ドル追加すれば装置に収める前の葬儀もできるという。 シアトルにも還元葬を行う会社「リターン・ホーム」があり、装置はもう少しコンパクト。上開きの業務用冷蔵庫のような形で、そのまま棺になる。3段の棚に並びコンピューターで管理する。必要なのは空気を循環させるわずかな電気だけ。 この会社では、装置の中で分解が進む約1カ月の間、家族や友人の訪問を歓迎している。装置のそばに椅子やテーブルを用意して音楽を流し、森をイメージしたパネルを設けたりしている。 還元葬は、コロラド、オレゴン、バーモント、カリフォルニア、ニューヨーク州でも合法化されている。「あらゆるものが急ぎ足の今日の世界で、ゆっくりと土に還るということ。それがただ美しい」「私の望みは土に還ること。その時点で私は無くなる。土を家族や友人がどうしようと、私は幸せ」と、契約者は言う。 リコンポーズの生前契約者1,200人のうち、50歳以下が4分の1を占めるという。貧富に関係なく、リベラルも保守も、カトリックもユダヤ教徒もいる。信仰や信条と「自然に還る」という考え方は共存できる・・。☆ 日本ではどうか。このニュースが流れた後にTwitterなどでも議論が交わされ、「日本には馴染まない」という反対論者が多かったらしい。散骨でさえ禁止をする自治体があるくらいで、遺体が源となった堆肥を農園や菜園に撒くのは抵抗があるだろう。でも、保護林へ寄付するというのなら受け入れられるだろう。 日本人の死生観が変わってきたものの、死者や遺体に対する畏れや穢れというイメージは根深いものがある。しかし、「墓終い」や「散骨」、仏壇を持たない家も増えている。先祖に囚われたくない、血と地に束縛されるのを嫌う人も傾向もある。 日本において「自然還元葬」が合法化される可能性は、あるのかないのか。私は、心情的には大いに有ると思う。ただ、世間体とか常識という呪縛に囚われている人がまだまだ多い。何かのきっかけで、急速に舵を切る可能性はある。 まさにエコ。生態系・生態「ecology」そのもの。SDGsの一端を担うことでもある。 様々な分野、状況で、世界から取り残されている現状がようやく認識され始めている。表面的で口だけ、イメージだけのグローバルが、本当の意味の持つものへ移行していく過渡期にある。 政治、経済、社会、生活の中で、ガラパゴスな世界から脱出する機運が盛り上がる時が必ず来る。団塊世代が生きている間に起こるのが理想だろうが、時期はまったく読めない。
2023.02.21
コメント(0)
-
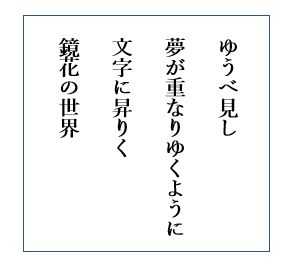
〇〇 観念と想像世界の旅にでる
♪ ゆうべ見し夢が重なりゆくように文字に昇りく鏡花の世界 読むべきものを前にして、そのいずれもが面白そうでウキウキ、わくわくしている。今日も明日も冬型の気圧配置で北西の風が強く、寒い一日。 こんな日は、炬燵にぬくぬくしながら本など読んで過ごすのが、老人の心と身体にとってはモアベターであり、正しい時間の食べ方なのです。「文藝春秋3月号」は、芥川賞受賞の2作品が全文掲載されている。これは昨日買って来たばかりで、他の記事をパラパラとめくって読んでみたりしているところ。 「梶山秀之」についての随筆があって、彼の本は読んだことがなくポルノ作家ぐらいにしか認識していなかったことが恥ずかしくなった。 あの文春砲を当初から打ち続けていた「梶山軍団」のリーダーとして活躍。それだけでなく、自動車業界「黒の試走車」を書き、産業スパイ小説という新分野を開拓。小説誌、週刊誌、新聞を舞台にジャンルも多彩。流行作家にのし上がったて、月に1千枚、最高で月産1千3百枚を記録したというから恐れ入る人。 昭和44年の文壇の所得番付で、松本清張をおさえて一位になっている。そして、「先輩作家の書いた恋愛小説を読破し、そこに欠如しているものが、セックスにおけるノウ・ハウと看破。《同じ書くなら、現代で考えられうる、あらゆる変態性欲の生態を火薬のように詰め込んでやる。世の偽善面したやつらの前で、大爆発を起こしてやれ》と、その分野に切り込んでいったという。 取材先の香港のホテルで突如吐血し、死去したのが享年45歳だった。生前、総計で11万2千6百12枚を書き、死後も120冊以上が文庫化され、累計130万部を超えたという。 こういう話がつづられている巻頭随筆は、いつも最初に読む。今「舞い上がれ」にも出ている「松尾諭」も寄稿していて、自身が忙しい中で小説を2冊出した経緯などが書かれている。 「GLOBE」には、死んだ人の亡骸を文字通り “土にして大地に返す” という、画期的で理想的な手法が紹介されている。埋葬のあるべき姿に、我が意を得たりとばかりに手を打った。いずれ詳しく書きたいと思う。 好きな泉鏡花の今回は、現代語に訳されたもの。その絢爛で幽玄な、鏡花独特の文章は現代語に訳されたからと言って色あせるものではない。古い書物にはかながふってあるのが目障りで、それが無い方がスラスラ読めると思うがしかたがない。 状況描写にうっとりしながら、懐古趣味でもないのにその言葉の操りにつられて面白く読んでいる。もう終盤に差し掛かっていて、貸出期間を延長してもらいもう一度あたまから読み返そうと思っている。
2023.02.20
コメント(0)
-
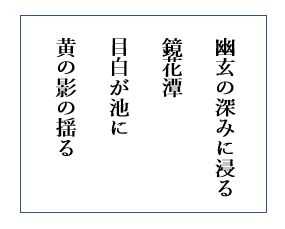
〇〇 変幻の不測に満ちる令和かな
♪ 幽玄の深みに浸る鏡花潭 目白が池に黄の影の揺る 今年の冬は寒暖の変化が大きかった。最低気温がそれほど低かったわけでもないのに、屋内に取り込んだパキラの葉がその変化に対応できず、何枚かの葉が傷んでしまった。 半地植え(塩ビ管に植えてある)した紫宝花は、地上部がすっかり枯れてしまっている。多分、春になれば新芽が出て来るとは思うが、ここの紫宝花にとっても新天地なのでどうなるかは未知数だ。 日本では1年草あつかいの唐綿(アスクレピアス・クラサヴィカ)はメキシコ、南アメリカ原産。世界中の熱帯、亜熱帯地域で帰化状態にあり、中国、台湾、オーストラリアなどでも栽培を逸出したものが野生化しているらしい。 多分この地でも冬越し出来ると思っていたが、地上部は枯れてしまった。辛うじて根元に出ていた新芽は大丈夫そうなので、なんとか冬越し出来たと思いたい。 種がたくさん採取してあるので蒔いて育てればいいわけだが、多年草として育ってくれればその手間を省けるというもの。 シトシトと降る雨は、一気に降る大雨よりの地面によく浸透してくれる。いいお湿りだと思っていたが、窓下は短いながらも庇があるため半分しか雨が当たっていない。油断すると水が足りていない事にもなりかねない。 この浪花茨は成長期に水を欲しがるらしいので、水不足にならないよう注意してやる必要がある。ここに植えて2年目を迎える。大輪の真っ白な花を早く見たいものだ。 エサ台にやって来たヒヨドリ。今年はまだ2度しか目にしていない。先日、ウォーキングで幾つもの群れが南の方へ飛んでいくのを見たが、17日にも同じように飛んでいるのを見た。まだ渡りの戻る時期ではないらしい。 それとも、多くのヒヨドリが留鳥となって南方のどこかに棲みついているのだろうか。ガラス越しに ヒヨが行くと、すぐにメジロがやって来た。「こっちが先客だ」と言わんばかりに・・
2023.02.19
コメント(0)
-
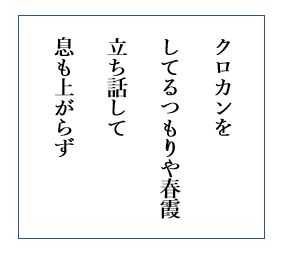
〇〇 体力が気力を追ってザバスかな
♪ クロカンをしてるつもりや春霞立ち話して息も上がらず 昨日は義母の入居していた団地を引き払うため、家財道具を市のリサイクルセンターに回収に来てもらう日だった。午後3時に来るというので、早めに準備しようと、11時頃に行って荷物を外に運び出すことに。2トン車は中まで入っていけないので、40mほで先の道路の所まで運んでくださいと言われていた。 そのことをURの事務所に伝えると「不法投棄になるので困る」と言われ、柵を外して車が入れるようにと、柵のカギを渡された。荷物は階段の下の所に出してくださいとのこと。 カミさんと二人で家財道具を運び出す。幸い2階の部屋なのでわけないこととたかを括っていた。一番大きい洋服ダンス ─ 縦:約180㎝ 、横:約80㎝ ─ が、どうやっても階段につかえて下ろせない。持ち込めたのだから下ろせないはずがないと思っていたのが間違いだった。(多分、業者は屈強な男二人で、階段の手すりの上まで持ち上げて運び出したのだろ。それしか考えれれない。) しょうがないので家に「電ノコ」を取りにいき、胴の真中あたりでカットしてやった(“まだ使えるのでリユースする” などと考えていたらこんなことはできなかった)。あれこれ運び出すと結構な量がある。12時半ごろまでかかってしまった。 私は、リサイクルセンターが回収に来るときはいない方が良いと思い、午後は行かなかった。ちょっと早めに来たらしい。何のことはない、柵を外すこともなく中まで乗り込んできた。一体、「UR事務局」は実態を把握しているのかどうか、疑わしくなってきた。 いざ積み込み始めて、思ったよりも多い荷物に「全部は無理だなぁ」と言い始め、カミさん姉妹を慌てさせたらしい。婆さん二人が「これはどうしても運んでほしい。これはどうですか、これも積んでください。これも、これも」と懇願して、無理やり押し付けた結果、可燃物を入れた大きなビニール袋3袋が残っただけで済んだらしい。 婆さんに頼まれれば、むげに断ることもできないだろう。私が居なかったのは正解だった。☆ この日は、4軒目の建設工事が3月10から始まるにあたって、午後1時過ぎに地鎮祭が行われていた。お払いに加わっている施主はまだ若い夫婦のようだ。 最近の私は体力が回復しているので、午前中の作業など何の影響もない。午後からはウォーキングに、坂をかけ上がるコースを2周するつもりで出かけた。 1周の半分あたりへきたところで、白柴と黒柴を散歩させているご婦人が前からやって来た。近づいていくと、嬉しそうにじゃれ付いてくる。「人間が好きなんですよぉ」「いいですね~!哭かないんですねぇ」「ええ、鳴かないんです」 そんな短い会話をしながら、もっと密着して撫でてやろうとすると、リードを引いて距離を取ろうとする。他所の知らない人に、そこまでは出来ないと思たのだろう。強引に行くのも気が引けるので、ちょっと物足りなかったが引き下がり、「ありがとう。」を言い、犬にも「バイバーイ」と手を振って、別れた。 クロスカントリー的に上りを駆け、再び元の坂の方へ下っての途中からまた駆け上がる。今のところノンストップとはいかず、駆け上がっては歩き、歩いては駆け上がる。1周1.4㎞を約2周して、来た時とは違う道を戻って来た。8,000歩ほどの心地いいウォーク&ランだった。☆ 筋トレには良質のたんぱく質が必要という事もあって、試しに買ってみた。「ホエイ」タイプのSAVAS→ZAVASで、トライアルのもの。1袋は半食分の10.5g。1食分は要らないのでちょうどいい。1袋127円と安いのものいい。毎日飲んでも負担にならない。 夜、牛乳を温めて溶かし込んで飲む。ココア味なのでココアミルクを飲んでいる感じ。安眠にもいい美味しい飲み物だ。*ZAVASをSAVASと書いてサバスと読むという間違いを犯しました。訂正しておきます。
2023.02.18
コメント(2)
-
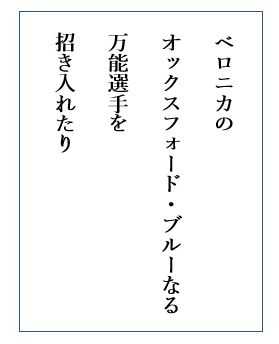
〇〇 宿根のベロニカ属の青き花
♪ ベロニカのオックスフォード・ブルーなる万能選手を招き入れたり Creemaで「ベロニカ・オックスフォードブルー」を購入。 オオバコ科クワガタソウ属(ベロニカ属)の多年草で、約250種あるうちのベロニカ・ペドゥンクラリス種から作出された園芸品種らしい。 “宿根の多年草” でオオイヌノフグリに似た、それよりも少しい大きくて濃い青い花を3~6月に次々と咲かせる。茎はよく分枝して地面を這うように広がり、草丈5~20㎝程度に成長。グランドカバーとしてよく利用されていて、雑草除けにもなるらしい。 ガーデニング初心者でも簡単に増やせるというのが気に入った。 何と言ってもその花の色が美しく、青い花と緑の葉が一面に咲くとそれはなかなか見事だろう。秋には葉が銅葉色になり、とてもシックな姿に変化する。 寒さには強いが真夏の直射日光を嫌うので、午後には日が当たらない場所がいいらしい。しかし、暑さに強いので特別な夏越しの必要はないという解説もある。どっちなんだい!?「草丈は、5~20㎝程度に成長する」とかなり幅があるのは、その環境によって大きく変わるという事だろう。鉢植え 濃いブルーは、“オックスフォード大学のスクールカラーになっている” ということが名前の由来とか。別名の“ジョージアブルー” は、原種がジョージア国(グルジア)に分布していることに由来するらしい。 株分けと差し芽で増やせるので、いくらでも増殖させることが出来る。いろんなところに植えて、様子を見ながら場所を限定していくという手もありそうだ。 株分けは、3年に1度ぐらいに、3月~4月、9月下旬~11月上旬にする。 差し芽は、5月~6月と9月~10月の期間、剪定して切り戻した茎をその都度差してやる(花や葉は取り除き、その後水揚げし、挿し木用の土に挿しておく)。数年後のことになるのだろう。植え方、植える場所、コンビネーションなど工夫次第で色々楽しめそう。 宿根の多年草で、色も良く暑さにも寒さにも強いなんて、まるで大谷翔平みたい。まったくもって、庶民の味方、ガーデニング愛好家の良き伴侶。素晴らしくも頼もしい万能のアイテムだ。 購入したものは2苗セットだったので、場所を変えて2か所に植えておいた。タイミングよく切り戻しすると、2番花を咲かせることが出来るとか。そのタイミングがなかなか難しいという。やっぱりなぁ、大谷翔平には勝てないようだ。
2023.02.17
コメント(0)
-
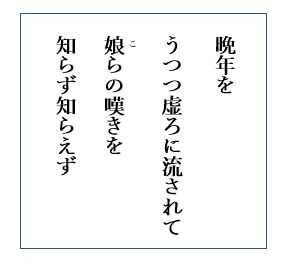
〇〇 成ることと為らざることの見え隠れ
♪ 晩年をうつつ虚ろに流されて娘(こ)らの嘆きを知らず知らえず 去年の10月12日。アクセス数と前日にアクセスのあったページの一覧を掲載した。その翌日から何故か、アクセス数が3分の1になった。それからは500前後で推移していたが、最近になって徐々に数が戻りつつある。それで、ようやく一昨日、大台の3,000,000を超えた。 NETってなんだかわけの分からない世界だ。今、メルカリ相手にすったもんだしている。 同じ品物が二つの値段で出品されることになっていて、一つ売れてもう現物がないのにもう一つの方に買い手が付いた。当然、キャンセルすることになる。しかし、買った人はそのキャンセルの理由を納得しない。 なぜこんなことになったのか。一度、出品したものを価格変更するために「編集」して出品し直した。その元の値段のものもそのまま出品されてしまっていたらしい。そんな馬鹿なことはないと言うこちらの言い分を、事務局が聞き入れず5回も6回もやり取りしているがだめ。 こちらの手続きの間違いとの一点張りだ。まったく同じものが2点出品されていて、マイページの出品一覧にはその一つしか表示されていなかった。「いいね!」ついた時におかしいと思って確認したが無かったので削除できなかった。その事実を認めようとしない。一方的に非はこちらにあると言い張る。いいかげん頭にきた。購入者はキャンセルの承認をしてくれない。 そうこうして一週間がたち、事務局の方でキャンセルの手続きをしてしまった。 せっかく仕事部屋にあった安物のタンス2つを処分し、持ち込んだタンスに整理し直し、部屋も片付いてスッキリしたと思っているところなのに。なんてこった。 義母の入院から後の退院してからの扱い方法で、娘二人の意見が合わずにすったもんだやっている。感情的ですぐ気が変わる長女と冷静でドライな妹。親に対する思いや、全てにおいての価値観が違う。 すんなり話が進まない。一歩進んで後戻り、三歩進んで二歩下がり、ちっとも前に進まない。寝ては覚め起きては苦悩の繰り言を、朝な夕なに聞かされる。 お祖母さん本人の性格や思いを考えているはずなのに、自分の満足を優先しようとする。こっちの言う事なんか頭に入らず、アドバイスなどする余地もない。 なる様にしかならない。紆余曲折のうちに、成るようになっていくのだろう。
2023.02.16
コメント(0)
-
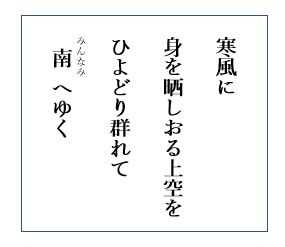
〇〇 戻り寒にあえて逆らウォーキング
♪ 寒風に身を晒しおる上空をひよどり群れて南(みんなみ)へゆく 歯医者に行ったついでに、間が空いてしまったウォーキングへ。強風が吹く寒い中に身をさらして気分転換。いつもとは違う脇道に入って夕日を眺めたり・・。 日没にはまだ少し時間がある。強風に流された雲の間から日が射したり、また曇ったり。日が射して急に暖かくなったり、またすぐに寒くなったりする。 ヒヨドリが次々と群れをなして、上空を乱れ飛ぶようにして南に向かって行く。渡り鳥として北からやって来たものたちだろう。日の長さとか星の位置とかで、戻り寒の中でも帰る時期を察しての行動なのだろう。しかし、まだ北へ戻る時期ではないだろう。どこかにコロニーのようなものがあるのだろうか。 いろんな花木が密集して植えてあったり、こんなところに出るのかとかと驚いたり。高い位置に何も植わっていない畑があり、愛知用水の吐水栓があったりする。元は水田だったことを窺わせせ、諸行無常の世の中の変遷と時代の変化を思い知らされて。 見慣れない風景が目の前に現れて、とても新鮮な気分。坂を駆け上がったりしたので寒さはほとんど苦にならなかった。
2023.02.15
コメント(0)
-
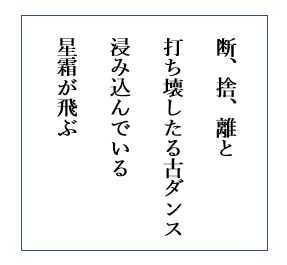
〇〇 古タンス2さお壊し廃棄せり
♪ 断、捨、離と打ち壊したる古ダンス浸み込んでいる星霜が飛ぶ 90歳の義母が入院し、使わなくなった整理ダンスを引き継ぐことになった。それで使っていた古いタンス2つを処分することに。 引き継いだタンスは軽自動車で何とか運んだが、処分する2つを清掃センターに運ぶのはちょっと無理。それで得意の「解体」と相成った。 日曜日に少しうるさかったが、トンカチで抽斗から解体スタート。 1つは安物のタンスなので簡単にバラせたが、もう一つが大変だった。日曜大工が趣味だった義父が手作りしたもので、必要以上に頑丈に作ってある。簡単には解体できなかった。個人の手作り品はコストも無視だし、壊すことなど考えてない。永遠に壊れないものが理想なのだ。 私にとっても頼もしい義父だった。オーディオラックを作ってもらっているし、古民家を買って入居する前の改造で、作り付けの素敵な食器棚も作ってもらっている。知人に依頼されて部屋のリフォームもしたことがあるらしい。とにかく器用な人だった。簡易整理ダンス二つ分がこの程度の廃材となった。使えそうな材があったので、少しだがキープしてある。 月曜日に清掃センターに運び込んだ。 10キログラムにつき、85円(手数料計算後の10円未満の端数は切り捨て)で、480円だった。5キロちょっとあったわけだ。いらない衣装ケースに、布類と一緒に染色に使う助剤とかいろいろ入った容器を突っ込んでいったら、それは見つけられて断られた。「もし、有毒ガスでも出たりすると、業務がストップしてしまって困る」ということらしい。☆ 市では粗大ごみの回収もしてくれる。軽トダンプ車で、1回の収集につき、5,500円。2トンダンプ車だと、1回の収集につき、11,000円。荷台幅、縦2.77m、横1.51m、高さ、0.8mに収まらないものは回収できない。 一般家庭の1軒分ともなれば数回分あるだろうが、団地住まいに変わってからは大した量でもない。整理ダンスは我が家に運んだし、電気製品や金属製のものは他の業者に持って行ってもらってある。2トン車1回で十分だ。 しかし、団地の棟の前の道路は道幅が狭く、2トンダンプは入れないらしい。それで団地横の通路まで出しておいて下さいと言われている。幸い、2階なので運び出すのは問題ないが、出してから洋服ダンスを、40mほどある外の通路まで運ぶのがちょっと大変かも。 入院中の義母は、ほんの少ししか食べないらしい。それまでもそうだった。なのにこんなに長生きしている。コロナのせいで面会出来ないのが可哀そうだ。具体的な様子が分からないので、娘二人はイライラがつのっている。認知症もあるし、骨折からの寝たっきりになる典型の状態にある。痛みが取れれば、病院からは出なければならなくなる。 カミさんは姉と二人で連日、大わらわ。ケアマネに相談しながら、受け入れ先を探してあちこち見に行ったり、相談したり。でも、どこも満室で待機者も多いらしい。退院してすぐに入れないとなると、病院から引き継いで受け入れてくれる施設に入ることになる。そこで最期を迎えることになってしまうのかもしれない。
2023.02.14
コメント(0)
-
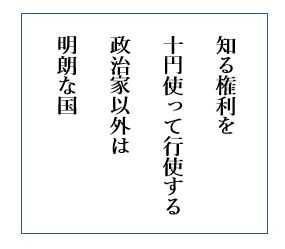
〇〇 レセプトにからくりを見る歯科診療
♪ 知る権利を十円使って行使する政治家以外は明朗な国 以前も書いたかもしれないが、病院からのレセプト(診療報酬明細書)について。受け取らない人は多いのでしょう。私はもらうことにしています。10円掛かりますが、医者が何をどうしているのか、何にいくらかかっているのかが分かる。実際、理解できない項目も多い。知ってどうすると言われても困りますが・・ 「診療報酬」とは、診療に要した費用のことで、診療報酬点数表に基づいて点数で算出される。診療報酬点数から、1点=10円として金額が算出される。4項目に分類されている。 で、今回のレセプトはこれ。 欠けた前歯を直し、部分入れ歯の一カ所をほんの少し削っただけ。 これが市に報告される。治療に4,260円がかかっていて、その2割の850円を患者が負担したというもの。 分からない事ばかり。最初の初診料は分かるが、どんな病気で病院に通うことになっても必ず「再診料」を取られる。その都度カルテを準備する手間賃か? 再診時歯科外来診療環境体制加算1 3点 これ、何? この明細書を受け取るには、「発行体制加算」とかいって、1点=10円かかっている。 歯科衛生士実地指導料1 80点 ─ 実際、衛生士は何も関わってはいない。 歯科疾患管理料 100点 ─ 何を管理した? 文書提供加算(歯科疾患管理料)10点 ─ 何の文書? 歯科口腔リハビリテーション1(義歯困難以外)104点 ─ ? 機械的歯面清掃処置 72点 ─ 欠けた前歯の処置? 部分入れ歯の調整のこと? 欠けた前歯をほんのちょっと削り、プラスチックを取り付けて紫外線を当てる。咬合紙を2度ほど使ってかみ合わせを確認した。そして、部分入れ歯の当たって痛い部分を削った。 “患者が10人いれば歯科医院は成り立つ” と、言われているらしい。ホント、いい商売。しかし、今やコンビニよりも数が多いので、人気商売としての患者の争奪は厳しくなるばかりだろう。
2023.02.13
コメント(0)
-

〇〇 歯は命。便秘まで改善されて・・
♪ 出口にて苦労をするは入り口で横着をした罰だと知りぬ 右側の上と下の歯に部分入れ歯入っている。位置は少しずれているが、これ無いしではものが食べられない。左ばかり使っていると歯茎の部分が疲れてきて具合が悪い。食べ物を左右を交互に移動させながら食べていることが良くわかる分かる。歯は両方にあってちゃんと使えてこそのもの。 その部分入れ歯の下側のものは、一番奥とその隣の2本分を担っている大事なもの。それが歯に引っかける金具が1本折れてしまった。歯茎が後退してゆるくなっていたのを無理して使っていたのが原因だろう。確かに具合が悪かったが、それを無視して使っていた。通っていた歯科医師が文句を言うのを聞きたくなくて、歯医者に行くのを渋っていたという事情もある。 陰険で文句ばかり言う人で、腕がいいのは認めるが人と接する能力に問題がある。歯医者とて接客商売だし、こちの中というデリケートな部分を扱う人気商売でもある。 金具が取れた後の方が噛みやすいような気がして使っていたが、どうにも具合が悪くなってまった。 それで別の歯医者に行くことに。今までも近かったがそれ以上に近い、歩いて2分ほどの所にある。そこの若い常勤の医師の担当となった。前歯が欠けてしまっているのを、先ずCRで治療してもらう。どんなレベルのどういうタイプなのか、最初はお手並み拝見という感じ。 そして、今まで指摘されたことのない小さな虫歯(レントゲンで見つかった)2か所を、次に直した。次回は虫歯の治療後(金属が被せてある部分)が虫歯になっているらしい(これもレントゲンで見つかった)ので、その治療をするという。 その前に入れ歯の方を先に直してほしいと願い出た。最初に入れ歯の修理はできそうだと聞いていたからだ。型を取って、次の週。金具を付け直して歯に装着し、プラスチックを固める。それを外す段になって、かなりきつくてなかなか外れない。ようやく外れたとおもったら、隣の金属部分が割れて取れてしまった。先生も焦ったようだ。気を取り直して、今度はその部分の修理に入る。 何とか形が出来上がった。金属は元の位置とは違うものになり、入れ歯そのものも継ぎ接ぎでぶかっこうになった。かみ合わせなど微調整して、見栄えは悪いが良い具合にできている。 翌週までの間。使っているとどこかが当たっているらしく、痛くなってくる。そしてその間に欠けてしまって直してもらった前歯がまた欠けてしまった。治療の日。先ず前歯を直してもらった。「今回は少し厚めにしておきました」とのこと。次に、入れ歯の痛みの出る部分に印をつけて、削って調整。なんと、スッキリ痛みが取れた。 喜んで使っていると今度は別の所が痛くなってきた。噛み締めが強い私の歯は、歯茎が出っ張っている部分があり、そこに当たってこすれるため痛みが出ているらしい。 1週間後にそこを削ってもらうと、ウソのように痛みがなくなった。完璧だ。これなら何だって食べられる。とはいっても前の歯医者に、「入れ歯の噛む力は通常の6分の1しかない。そして、硬いものを噛むと破骨細胞があごの骨を溶かしてしまうので、くれぐれも硬いものは食べないように」ときつく言われている。 しかし、この先生はそういうことを一切言わない。前の先生は口腔外科出身のため特にそういう事への意識が強いのかもしれない。どっちがいい先生なのか。判断がしずらいところ。 完璧に入れ歯が使えるようになって、安心して食事ができるのは有難い。有名人でなくとも「歯は命」だ。体への影響も大きい。よく噛むことでもたらされるものはたくさんある。 特に実感できたのは、便秘気味で、“出そうで出なかったりで、出てもほんの少しだったりの便” が、ウソのように改善したこと。兎糞便のようにコロコロとして固かったものが、スルッと出るようになった。入れ歯が悪くなる前の状態に戻ったのだ。 よく噛むことの効能は8つほどあるという。 1.胃腸の働きを促進する唾液中の消化酵素の分泌がさかんになり、細かくかみ砕けば胃腸への負担を和らげます。 2.むし歯、歯周病、口臭を予防する唾液の分泌が増え、唾液の分泌が増え、唾液の抗菌作用によって口の中の清掃効果が高まります。 3.肥満を防止するゆっくりたくさん噛むと満腹感が得られ、食べ過ぎを防ぎます。 4.脳の働きを活発にする噛むことで脳への血流が増加し働きを活発にするために、脳の若さを保って老化を防止します。 5.全身の体力の向上よく噛めば全身に活力がみなぎり、体力が向上します。 6.味覚が発達するじっくりと味わうことができ、味覚が発達します。 7.発音がはっきりする口のまわりの筋肉が発達し、言葉の発音もはっきりします。 8.がんを予防する唾液に含まれる酵素には、食品中の発ガン物質の発ガン性を抑制する効果があると言われています。(日本訪問歯科協会より)
2023.02.12
コメント(2)
-
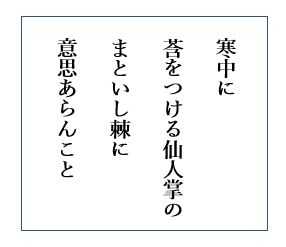
〇〇 防犯に棘の役立つ茨かな
♪ 寒中に莟をつける仙人掌のまといし棘に意思あらんこと 昨日はひさしぶりの雨で、カラカラになっていた大地にはいいお湿りになった。それとなく進めている浪花茨の環境整備。誘引はしたものの何だかごちゃごちゃしていてスッキリしない。風邪を通すためにラチスから浮かしてやる必要があって、そのための支えが見苦しかった。それならいっそ、そんなものは無くしてしまおう。 ステンレスの針金を買ってきて、ラチスから離して水平に2列、引っ張ってやった。そこに麻ひもで固定し、目障りのものが無くなってスッキリした。 ちょっと針金が細い気がする。今のうちに抱き合わせて、もう一本入れておいた方が良さそうだ。 新芽をたくさん出させるために、横に寝かせて誘引している。新芽がたくさん顔を出ているが、これが全部花芽なら嬉しいが・・。そんなわけにはいかないか。 この薔薇は原種に近いので育てるのは楽でいいが、棘がすごく大きくて硬い。大きくなれば窓の下は、難攻不落。防犯にはバッチリの窓になるはず。 ついでに隣にも1本張っておいた。こちらは蝶豆のグリーンカーテンを作る予定。漁網を雨樋の受け金具から垂らして固定する。その漁網を支えるためのライン。これも1本じゃ心もとない。 庇をカットしたおかげで壁面・窓からの距離がない。風が通りにくいのでそれがどう影響するか。やってみないと分からない。サボテンが早々と蕾を付け始めている。
2023.02.11
コメント(0)
-
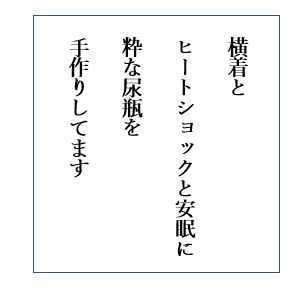
〇〇 コロコロと変わる首相のごときもの
♪ 横着とヒートショックと安眠に粋な尿瓶を手作りしてます 暖かい日から一転して、今日1日は真冬の寒さに逆戻り。そしてすぐにまた暖かくなる。かと思いきや、また15日、16日は真冬の寒さに。10日の予想東京・仙台は日中が極寒で、夜になってから気温が上向くという、昼夜逆転の珍現象。 関東甲信では寒気が残る中、南岸低気圧が通過し広く雪が降るらしい。東京23区など南部の平野部でも積雪となりそうで、内陸部を中心に大雪の恐れ。 どこぞの首相のようにコロコロ変わる。周りに棲息している物たちは振り回されるばかりで、たまったもんじゃない。 14日(火)になると日本列島の東で低気圧が発達し、日本付近は冬型の気圧配置が強まる。15日(水)には非常に強い寒気が北日本の上空まで南下する見込み。 大雪の目安となる上空5000m付近で-36℃以下の寒気が東北北部まで覆い、北海道には-45℃以下という、ひと冬に1度あるかどうかの強い寒気が通過するとみられている。 なんだかんだ言ってもまだ2月だ。 二十四節気(二週間ある)をそれぞれ3つに分けたものが七十二候。立春の候は 初候 2月4日(土)~2月8日(水) 東風解凍(はるかぜこおりをとく) 次候 2月9日(木)~2月13日(月) 黄鶯睍睆(うぐいすなく) 末候 2月14日(火)~2月18日(土) 魚上氷(うおこおりをいずる) 次候に当たり、鶯が鳴くころとなっている。笹鳴きは聞けるかもしれないが、囀りを聞くのはまだまだ先のことだろう。 目白用のみかんは雨に打たれ、水が溜まっている。寒さとひもじさに震える一日になりそうだ。☆ 今朝は朝から炬燵を入れて、パソコンも持ってきてぬくぬくしながら打っている。布団に潜りこんでいた猫もエサを食べたらすぐに炬燵に潜り込んだ。いつもなら、「寒いよ~」って鳴きながらウロウロするのだが、今朝は様子が違っている。私の顔を見ながら、嬉しそうに目を輝かせて潜り込んできた。 トラブルでメルカリとちょっとややこしいことになっている。原因は向こうにあるはずだが、それを探っているところ。スマホで文章を書くのは苦手なので、パソコンでやり取りしている。 膨大な顧客に対応するには時間がかかり、1日1回のやり取りしかできない。時間がかかってしょうがない。
2023.02.10
コメント(0)
-

〇〇 もし囲碁を、藤井聡太がしたらどうなる?
♪ 新しい品種見つかるごとく聞く囲碁と将棋の最年少ニュース 最年少の記録更新が目覚ましい将棋と囲碁界の昨今です。スケボー、スノボーとの共通点はまったく無いけれど、若い気鋭の胎動を聞くのはとてもいい気分だね。 大阪市の小学3年生、藤田怜央君(9)が、2022年9月1日付で囲碁のプロ棋士になると発表した。9歳4カ月でのプロ入りは、仲邑菫二段(13)の10歳0カ月を更新する史上最年少記録。今年、年の差66歳!関西棋院棋士会の会長も務める牛窪義高九段(75)に、3時間余りの戦いの末、202手の白中押し勝ち、初勝利。 仲邑菫三段(当時10歳で初段)が持っていた最年少勝利記録(10歳4カ月)を更新し、9歳9カ月の新記録を打てた。 囲碁の中学生棋士・仲邑菫(なかむら・すみれ)二段(13)が、13歳7か月での三段昇段。女性棋士では最年少。男女合わせても井山裕太名人の14歳0か月を抜き、趙治勲名誉名人の13歳4か月に次いで2番目の年少記録となった。 今年、女流タイトル戦の一つ「女流棋聖戦」を制し、自身初のタイトル獲得。仲邑三段は現在、「13歳11か月」で、これまで「15歳9か月」だった女流タイトル獲得の最年少記録をおよそ9年ぶりに更新。 中学校2年の 鎌田美礼さん(13)が、2022年5月1日付で将棋の女流2級となり、日本将棋連盟で現役最年少のプロの女流棋士になった。 今年2月6日「第26期ドコモ杯女流棋聖戦三番勝負」で初のタイトルを獲得。13歳11カ月のタイトルホルダーは、男女を通して史上最年少。 去年、将棋の八大タイトルの1つ、「王将戦」で挑戦者の藤井聡太四冠(19)が渡辺明三冠(37)に4連勝して5つめのタイトルを獲得し、羽生善治九段(51)が持つ最年少記録を28年5か月ぶりに更新する「19歳6か月」で「五冠(竜王・王位・叡王・王将・棋聖)」を達成。 昨年の昨年の獲得賞金・対局料が、2位の渡辺明名人(7063万円)を抜いて断トツの1億2205万円で初の1位となっている。クリックでYouTubeへ 棋王戦での6冠達成の確率が9割を超え、史上初のグランドスラム(【竜王】【名人】【王位】【王座】【棋王】【王将】【棋聖】の全てを獲得経験が有る棋士は、現役では羽生善治名人と谷川浩司9段だけ)まではあと4勝と迫っているんだとか。 恐ろしくもある怪童の活躍は、進歩あるのみで留まるところを知らない。 プロ棋士は通常、対局中に手を読む際は脳内に将棋盤を思い浮かべ駒を動かして思考するが、藤井は脳内将棋盤を使わず符号が浮かんでくると語り、プロ棋士からも驚きの声が上がったという。 また、将棋ソフトを使用するパソコンを自作していることはパソコン業界などでも注目されていて、「落ち着いたらパソコンを1台、組みたいなと思います」と語っている。 ★ こちらは悪いニュース「梅毒」が急増中 昨年上半期に性感染症の「梅毒」と診断された患者が5000人を超えたことが、国立感染症研究所が7月12日公表した調査結果でわかった。 年間1万人を超える勢いで、現在の調査方法となった1999年以降で最多を記録した昨年(7983人)の1・6倍のペースで増加している。 梅毒は全身の発疹やリンパ節の腫れ、陰部の潰瘍などが表れる。ただ、初期症状は軽く、気づかずに放置すると数年後に心臓や脳に障害が起きることもある。抗菌薬などの薬物治療で完治できる。「自殺者」が増加に転じている 政府の自殺総合対策大綱は5年に1度見直されている。自殺者数はピークだった2003年の3万4427人から減少傾向が続き、19年は最少の2万169人になった。だが、20年には2万1081人(前年比912人増)となり、11年ぶりに増加に転じている。 コロナ禍前の5年間(15~19年)の平均人数と、21年を比べると、男女ともに増加している。 小中高校生の自殺者数も20年に過去最多の499人。21年も473人と過去2番目の水準となっている。
2023.02.09
コメント(0)
-
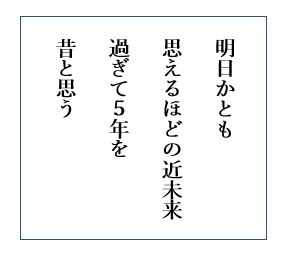
〇〇 5年後の車はいかに?
♪ 明日かとも思えるほどの近未来過ぎて5年を昔と思う 日産が、2月4日から3月1日までおこなわれるイベント「Nissan FUTURES」の一環として、新型スポーツカーのコンセプトモデル「Max-Out」(マックスアウト)の実車を初公開。日産の将来ビジョンを象徴するモデルらしい。 2人乗りオープンカータイプのEVコンセプトモデル。自社による「全固体電池(ASSB)」開発中で、これまでのバッテリーに対しエネルギー密度は2倍で、充電時間は1/3。そして、2028年度には、ガソリン車同等のコストでの量販化を目指すとしている。 従来よりも大幅にコンパクトなため「まるでスケートボードのような形状で床下にすっきりとまとめることが可能になる」らしい。なんか洗練されている感じがしない。とりあえずのアバウト感が気になる。大丈夫かな? 人馬一体ともいえる走りを持つクルマを目指していると言い、マックスアウトはいわば、日産版「ロードスター」という感じらしい。 2030年度までに15のEVを導入するとしている日産の商品計画に、マックスアウトのようなコンパクトオープンスポーツがリスト入りするかどうかはまだはっきりしていないという。見せ消ちけち? 今後5年間で約2兆円を投資し、電動化を加速すると宣言。2030年度までにEV(電気自動車)15車種を含む23車種の新型電動化モデルを投入し、グローバルにおける電動車比率を50%以上へと拡大するという。こんなことで良いんだろうか? 日産はルノーとの関係が大きく変わりつつあり、今は事業規模で日産がルノーを上回り、持ち分法利益や配当金の形で日産がルノーの業績を支えている。22年の段階 ルノーによる日産への出資比率を約43%から15%に引き下げ対等な出資にすること、ルノーが設立する電気自動車(EV)とソフトウエアの新会社(仮称:アンペア)に日産が「戦略的な株主」として出資すること、インド・中南米・欧州で新たな協業プロジェクトを推進することを明らかにしている。 日産自動車株式会社と三菱自動車工業株式会社は、ルノーグループと業務提携していて、拘束力のある枠組み合意を締結し、2023年第1四半期末 までに最終契約の締結を予定している。 日本のEVカーはアメリカや中国に大きく水をあけられていて、トヨタも顔色を変えて首脳陣を若返りさせて巻き返しに舵を切った。今後、何もかもが大きく変わり、5年の間に状況は一変するだろう。当たり前にEVカーが走る姿が目に見えるようだ。「ホンダジェット エリートII」 三菱重工業は7日、国産初の小型ジェット旅客機「スペースジェット」(旧MRJ)の開発を中止。開発を担う子会社の三菱航空機は清算し、「日の丸ジェット」を軸に航空産業を育成する官民の構想は頓挫してしまった。 そんな中、ホンダは子会社が小型ビジネスジェット機を開発中で、「ホンダジェット エリートII」を発表したばかり。航続距離が改善されて2865キロになり、基本価格は695万ドルから。来月納機を始めるという。
2023.02.08
コメント(0)
-

〇〇 クラシックを身近なものにとEテレの
♪ Eテレの茶の間に啓くクラシック露天の風呂に誘うごとし NHK Eテレの「クラシックTV」はとてもいい番組だ。 クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組と銘打って、ピアニストの清塚信也さんと、歌手・モデルの鈴木愛理さんが、ゲストとともに幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」でひもといて見せる。 30分番組なのもいい。伝えたいポイントに絞って、ゲストの魅力とともにうまくかみ合いながら進む。けっこう濃密な30分だと思う。 2月9日(木)PM9:00~9:29 「バーンスタインは問う 君は、音楽が好きか?」レナード・バーンスタインを特集。 大好きなミュージカル「ウェストサイド物語」の作曲者で知られている、あの大御所。世界で愛された巨匠バーンスタインは、音楽家・人間として、そのスケールの大きさは計り知れない。 ▽指揮者・作曲家・教育者・テレビ司会者など多方面に活躍。音楽の魅力を届け続けた人物像に迫る ▽仕事をともにした指揮者・広上淳一が人柄の伝わるエピソードを披露 ▽日本との交流も深かったバーンスタイン ▽熱演もたっぷり!マーラー交響曲第1番「巨人」。亡くなる3か月前に指揮したPMF札幌のシューマン交響曲第2番 ▽ゲストは広上淳一(指揮者)ヤマザキマリ(漫画家・文筆家・画家)。熱量高く濃いめのトークもお楽しみに! 何故か、予告編の動画が見られない。 前回放送(2/2(木) 午後9:00-午後9:29) 打楽器のスーパー奏者・石若駿がゲストの「石若駿と 打楽器の魅力」は「NHK+」で放送中で、9日まで観ることが出来ます。凄いです、この人。 私はそのもうひとつ前の回は観たけれど、この回は見逃してしまった。それで「NHK+」で観ました。 とに角、清塚信也さんのフランクな進行とベストとのコラボレーション。普段は知ることのないエピソードや蘊蓄が、とても楽し気に繰り広げられる。教育番組らしからぬ、肩の凝らない番組構成が音楽ファンなら見落とせない魅力にあふれている。ウェストサイド物語-マリア-の一部 東 賢太郎氏がソナー・メンバーズ・クラブのサイトで、バーンスタインの作曲が如何に素晴らしいか、その技法の妙味を詳しく解説しています。参考までに。
2023.02.07
コメント(0)
-
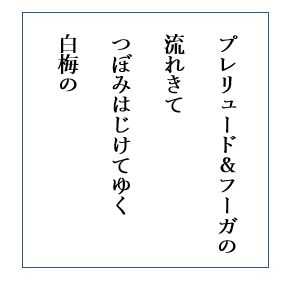
〇〇 穏やかな陽気に庭をうろうろす
♪ プレリュード&フーガの流れきてつぼみはじけてゆく白梅の 今頃になって初めてヒヨドリがやって来た。鳴き声が聞こえたのでもしやと思っていたらやっぱり。意外にメジロよりも用心深く、工事の車が毎日出入りしているので近づけない。 ヒヨドリは留鳥もいるにはいるが、秋に北海道から多数のヒヨドリが本州、四国、九州へ渡ってきて、全国で見られるようになる。至る所に咲いていた山茶花も終わりに近づき、いよいよ蜜柑が頼りの時期になった。草の葉や芽も食べるが、花の蜜は桜が咲くまでおあずけ。 我が家では、つぼみは付けたが、なかなかそれ以上は膨らまなかった山茶花。根の周りに、たい肥と赤玉土をかぶせ肥料をやったら、ようやく花を咲かせてくれるようになった。 メジロはこんな近くに車が停まっていても案外平気で、見張りを立てることなく番の2羽が一緒にみかんを啄んでいる。ヒヨがメジロを追い払うようなシーンはまだ見られない。箱の中のみかんは、ヒヨに食べられないため 山に食べ物が少なくなる冬から春にかけては、野鳥が山から里に下りて来る時期。お庭に野鳥を呼べる絶好のシーズンだ。せっかく買ってある「野鳥の餌」の出番だが、工事車両と人の出入りが気になるところ。☆ いよいよ暖かくなってきた。むずむずと庭いじりの虫が騒ぎ出している。パーゴラの周りと中を整理し、ミニ薔薇を地植えにしてみたり、ネットで買ったクレマチスの苗を植える準備も。 お遊びで、余っているダンポールでパーゴラに曲線を加えてみることに。この園芸用のポールをどうやって固定するか。 押し入れを物色していて、これだ!と閃くものを見つけた。絵の額を吊り下げるための金具。壁にピンを斜めに打ち込んで固定して使うあれだ。 ポールを受けて、針金で固定。なんとまあいい具合だこと。どうせすぐに錆びてしまうだろうが、その時はまた考える。
2023.02.06
コメント(1)
-
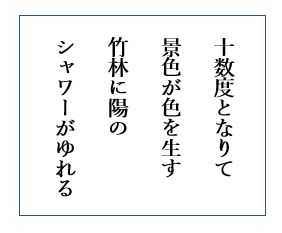
〇〇 斑なる選挙ポスター掲示板
♪ 十数度となりて景色が色を生す竹林に陽のシャワーがゆれる 昨日はお寺に地代(11,000円)を払いに行く日で、住職が歯科医院で私を見たという話から、役員総代らと〇〇の歯医者がどうだとか△△はこはこうだとか、歯科医院の話が盛り上がって面白い情報交換ができた。 家を出たついでにウォーキングに行くことにしていた。通りへ出たところでジョギングをする人に追い抜かれた。柄物のスパッツの上にランニング用の半パンをはき、上半身も長袖に半袖を重ね着して小さなリュックを背負っている。顔は見なかったが、細い体の後姿はいかにも老人。小幅でゆっくり走るその体勢も、少し左に傾いでいるように見えた。 その内にストップするだろうと思っていたが、全くペースが乱れることもなく少しずつ距離が離れて行く。赤信号に捕まることもなく、写真を撮ったりしていたこともあってどんどん離されていく。歩くスピードはかなり早めのはずなのに・・。幾つぐらいの人なのか、どのくらい走るのか興味が湧いてき、追い付こうと走ってみたがついに見失ってしまった。 1キロぐらいの間のできごと。最近は体調が良いので前向きになっている自分にとって、いい刺激になった。歩くスピードを落とすことなく、いつもより多めの距離を歩くことに。いい刺激をもらって歩いた距離は11.5㎞で、大した距離じゃない。16,000歩ほど。ゆっくり歩けば歩数はもっと増えるはず。 翌日に投票日を迎える知事選。歩いていると立候補者の掲示板が目に入る。家の近くのものには一人、写真が貼ってないのがある。愛知県全体の掲示板に貼るのは経費も手間も掛かるので容易じゃないだろからなぁと思って見ていた。家の近く 同じ市内でも場所によって貼ってない写真が違う。候補者によってポスターの分配の仕方が違うのだろう。 選挙にはカネがかかる。ましてや知事選ともなれば、金のない無名の人が立候補するのは至難の業だ。 都道府県知事選挙の供託金は300万円。有効投票総数の10分の1を取らなければ没収されてしまう。 今年は、全国統一地方選挙がある。前半は道府県議、政令市議選(3月31日(金)告示、4月9日(日)投票)、後半は一般市区議選(告示 4月16日(日)~投票4月23日(日))、町村議選(告示4月18日(火)~投票4月23日(日))。 人口減で立候補者のなり手がいない地方の市町村。昨年11月1日時点の現職議員を選出した市区町村議選(補選を除く)で、立候補者が定数以下となり無投票だったと回答したのは271市町村。18年調査(230市町村)の1.2倍に増えている。金や人手不足以前であるこの問題は深刻だ。 ともあれ、金が無くてもやり方次第で選挙に立候補できるようにと、サポートしている民間の組織がある。新人初出馬の立候補をサポートしてくれる。「選挙に出る方法、議員になる方法などの準備や費用の手引き【選挙立候補.com】」京都府城陽市にある「株式会社プットアップ・スタイル」が運営している。(営利事業なので無償でサポートしてくれるわけではない)【選挙立候補.com】 常滑市など、古狸が因習と旧弊にしがみついて何ら改革もしようとせず、新人議員や女性議員を助けるどころか妨害してふんぞり返っている。国政と同じ老害が地方にも蔓延していて、若い革新の芽をつぶして利権をほしいままにしている。 それを打ち破るためにも、若い新しい血を注入しなければならない。 今回の愛知県知事選は、現職がなんの脅威を感じることなくあっさりと当選するのでしょう。結果が想像できてしまうので、どうしても投票率は低くなる。私は今の知事をあまり評価していない。かといって、これはという候補者も見当たらない。しかたなく白票となってしまった。情けない思いで一杯だ。 10年ぐらいに若返った気がしている。ここ数年やっていない30キロほどのロングウォークを、春になったらやってみようと思っている。
2023.02.05
コメント(0)
-
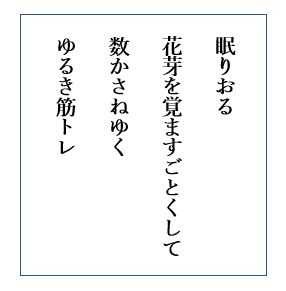
〇〇 ねんごろに目を覚まさせて春を待つ
♪ 眠りおる花芽を覚ますごとくして数かさねゆくゆるき筋トレ 年頭に誓ったあるいは実行し始めたこと。1か月経って、皆さんは続けられていますか? 私はちゃんと続けています。もう少し胸を厚く格好いい上半身にしたいと、昨年の9月から始めている大胸筋の筋トレ。膝をついてやるもので、ハードルは低い。今年は低山登山をしたいと思っているので、その為の準備も兼ねている。 まあ目標は「計画したことの八割はできない」と最初から思って始める人はいないでしょうが、こういう風に言われると気が楽になる。「三日坊主も十年経てば立派な記録」というのは10年間ずっと同じことをしているわけだ。確かにそれはそれで立派なことかもしれない。 大胸筋、膝付き腕立て伏せの筋トレは、ジムで鍛えるのとは違ってゆっくりしたもの。4か月が経過して胸囲が幾つになっているのか、寒いので測り損ねている。まだ見た目に分かるほどのものにはなっていない。やり方が悪いかもしれない。「折々のことば」にある様に、「こなす」ことに目的がすり替わっている気がする。思い直して改めてやり方を再確認。もう少しゆっくり、筋肉を意識しながらやった方が良いようだ。「プランク」についてのアドバイスだが、同じこと。 そう、体幹も鍛える必要があってやってはいる。でも、量が全く足りていない。鍛える手前の現状維持レベル。風呂上がりに、やるようにしているが寒い時期はどうしてもさぼりがち。これから暖かくなってきたらもうすこし頑張ろう。 先日は、試しにがんばってみた。膝付きプッシュアップ60回、スクワット100回、鉄アレイ(両手で10.8㎏)を持っての背筋100回、プランクもやった。そして翌日、御嶽神社の階段を往復駆け上がり、時間を置いてから新知保育園の周囲の坂を駆け上がった。後の方はノンストップとはいかなかったが、かなり余裕があった。筋肉痛になることもなく、疲れも残っていない。この分ならノンストップで一周できるかもしれない。BからAへ駆け上がったり、逆のAからBへ駆け上がったり・・国土地理院断面図 比率1:1 筋トレすれば衰えていた体力がリカバリーできる。それをハッキリと実感できた。そう、効果が分かって来るとさらにモチベーションが上がって、やる気が湧いてくるものだ。 肉体的なことはこうしてハッキリとわかるが、目に見えないものはそうはいかない。それを如何に実感できるようにするか。継続できるか否かはそこに掛かっている。
2023.02.04
コメント(0)
-
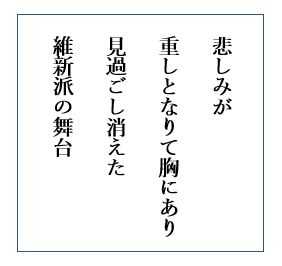
〇〇 維新派と石本由美の名を知りて
♪ 悲しみが重しとなりて胸にあり見過ごし消えた維新派の舞台 ’11年版のベストエッセイ集に掲載されていた、よしもとばななの「人間はすごいな」(本の表題になっている)は、さすがに文章が秀逸で中身の濃い名エッセイだ。その中に、関西に維新派という劇団があり、そこのトップ女優のひとり「石本由美」さんという人について書いている下りがある。その文章を抜き書きしてみます。 関西に維新派という劇団がある。 今はもう少し文化的に暮らしているかもしれないけれど、私が知っていた頃は巨大なセットはもちろん自作で、工事現場と同じ状況、寝泊まりするところも自分たちでさっと一晩くらいで造って、その場で食事を煮炊きして共同生活をしていた。 いずれにしても彼らは、松本雄吉さんという偉大な才能を持つ座長の感覚世界を完璧に体現するために、かなりハードに練習している、とにかく研ぎすまされた演劇集団だ。 そこのトップ女優のひとりに石本由美さんという人がいる。 小さくて、丸くて、ちっとも細くない彼女は、しかしものすごい身体能力の持ち主なのだ。維新派の独特な動きを彼女は体にしっかりとたたきこんでいる。 昔、マイケル・ジャクソンが「カウントしないのがいいダンサーなんだよ。頭の中でカウントしてると、見ているほうには絶対にわかるんだ」とさらっと言っていたとき、やはりこの人は天才だな、と思ったけれど、石本さんの動きはまさにカウントしてない感じとしかいようがない動きなのだ。 維新派の動きとセリフはリズムに乗ったとても複雑なものなので、舞台に出ている人たちがみんなとことん練習して体におぼえさせているから、とにかく大前提としてもともと全員のレベルが高い。 でも、ひとたび石本さんが舞台に出てくると、なぜか他の人たちの欠点が急に見えてきてしまうのである。 あ、この人は頭が動くと体の軸がぶれてしまうんだな、あ、この子は今数を数えて準備した、この人は右側の動きが大きくなっる、この人は今キレのいい動きをしようと頭で一瞬考えてしまったんだな、そんなふうに。 なぜかというと、石本さんだけは完璧に「無」なのである。 動くべきときには一瞬も間違えず動き、止まるべきときは止まろうと考えずに止まり、言葉を発するときは世界にただそれを響かせ、芝居の内容と一体化している。 だから動きのキレがすごいし、他のなんの情報も喚起しない。 ただ、そこには松本さんの世界だけが無慈悲なほどに、数学的といえるくらい、完全に表現されるのである。 石本さんは舞台を降りても異様な存在感があり、立ち姿のどこにも変な力が入っていない。そしてなによりも人をぐうっとひきつける何かを発散している。あまりにその輝きが激しくて、劇団以外の人たちといっしょにいると特に、うまく動けなくなった人間たちの中に美しい獣が一匹だけ混じっているように見える。 そんな石本さんも、初期にはやはり、いろいろ考えてたり大げさな動きをしていたように思う。今の奇跡の動きは長年の修練から生まれた純粋な結晶なのだ。そしてもしも彼女が死んだら、宇宙からなくなってしまう、はかなく美しいものなのだ。 2010年「文學界」新年号 文章に迷いがなく、言葉に過不足もない完璧なセッセイだと思う。そのためか、この劇団のこと、石本由美さんのことが凄く気になって、自分も一度見てみたくなった。一体どこでどんな活動をしているのか、今でもまだ観られるのだろうか。ネットで調べてみた。 Wikipediaによると 維新派(劇団維新派)(げきだん いしんは)はかつて存在した日本の劇団。1970年、松本雄吉(大阪教育大学出身)を中心に日本維新派として旗揚げ。1987年に維新派と改称した。 劇団員総勢50名ほどが自らの手で1.5〜2ヶ月以上かけ巨大な野外劇場を建設し、公演が終れば自ら解体して撤収するという「scrap&build」の劇団として知られている。また公演時には様々なフードやドリンクを提供する屋台村を併設し、巨大劇場と併せ名物となっている。 作品は少年少女の青春群像劇を軸に、退廃的でノスタルジックな世界観を構築。会話によって語られることは少なく、セリフのほとんどを単語に解体し5拍子や7拍子のリズムに乗せて大阪弁で語られる独特の劇形態(「ヂャンヂャン☆オペラ」)を持つ。ヂャンヂャン☆オペラの名は大阪下町「新世界」にあるジャンジャン横丁から取ったものである。 日本以外に海外でも数多くの大規模公演を行っている。大規模公演の新作は基本的に年1回。まれに屋内での公演やプレ公演のような小規模公演を行うこともある。 2017年10月-11月の台湾・高雄『アマハラ』公演を最終公演として解散した。著作権の関係で写真を載せることが出来ない。 高度経済成長の全盛期、学生運動で騒然としている1970年に旗揚げされた。私が全国を放浪し、大阪万博会場で資金稼ぎのバイトをしたりしていた時期と重なっている。 その後の私は自分のことで精いっぱいで周囲のことにまで気が及ばなかった。こんな劇団が生まれたこともその後の活動についても全く耳に入って来なかった。 残念ながら、2017年に解散してしまっている。座長の松本雄吉氏が、2016年6月18日、食道癌のため69歳で逝去したためだ。 ビルのような舞台セットが縦横無尽に動いたり、山間のグラウンドをヒマワリ畑に変えたり、波打ち際を丸ごと劇空間にしたりなど、奇抜なアイディアに満ちた舞台。そこに白塗りの俳優たちが、幾何学的に動き回りながら、単語の羅列のような台詞を、変拍子の音楽に乗せてラップのように発語する。1990年頃に完成した、この「ヂャンヂャン☆オペラ」と呼ばれたスタイルが大きな評判となり、大阪で公演が行われるたびに全国から人が集まるようになっていく。2000年以降は、公演にふさわしい場所を探して各地を漂流するスタンスとなり、日本国内はおろか、ドイツやブラジルやオーストラリアなど、計8ヶ国で公演を行っている。クリックでサイトへ これらの多くがDVD化ないしは映像配信されていて、その中で3本だけを選んで紹介されている。 今になって急に、大事な忘れ物を思い出したかのごとくうろたえている。すでに劇団がないなら、あの石本由美さんはどうしているのか。 松本雄吉の死後、翌年10月に奈良県「平城宮跡地」で野外劇『アマハラ』を上演。これが47年の活動に終止符を打つ最後の舞台になった。最盛期の現場のまかない飯を30年以上も担当していた石本由美さんはその後、大阪市内のカフェスペースでランチの提供したりしていたらしい。 年月は5年飛んで、2022年。 「新進気鋭の7名の劇作家-鏡味富美子/斜田章大(廃墟文藝部)/小林倫子(人魚座)/石丸承暖(しまい倶楽部/優しい劇団)/タチカズナ(群青アパートメント)/カズ祥(劇団あおきりみかん)-が、原作『不思議の国のアリス』を大胆にアレンジし、鹿目由紀(劇団あおきりみかん)が纏め上げる。 それを国内外問わず多数の舞台演出を手掛ける奇才・天野天街(少年王者舘)が”アマノワールド”へと変換する。天野天街×鹿目由紀×劇作家7名×役者総勢40名で創る唯一無二の舞台」というのがあった。 なんと、知多市の勤労文化会館でも公演があったらしいのだ。これに劇団維新派より特別出演として「石本由美さん」も参加していた。名前を見つけてビックリしてしまった。演劇は好きで若い頃はときどき観に行っていたが、「不思議の国のアリス」といった世界にはアンテナが向いていない。 ましてや、最近はそういう世界から遠のいている。劇団「維新派」というものを知ってから、慌てて “走り去った汽車を追いかけている” ようなものだ。 改めて「維新派」のDVDを観てみようと思う。こんなすごい劇団が47年も続けられていたことがすごい。遅まきながら敬意を表したい。
2023.02.03
コメント(0)
-

〇〇 遠足の前夜のごとき梅見月
♪ ドラゴンに襲われている列島が身を反らしおる冬の地上絵 ウォーキングに出るつもりでいた今日は、朝から5~6mの強い北西の風が風が吹いていて、とてもそんなことをしている場合じゃないようだ。日本海側は台風並みの荒れ模様らしい。一時的な冬型の気圧配置で、北海道から太平洋に長く寒冷前線が伸び、発達しながら移動している。まるで竜が身を反らして襲いかかっているようだ。 北海道では低気圧が通過した後、北海道の上空1500メートル付近に、マイナス15℃以下の寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込み。昼過ぎにかけて、オホーツク海側や太平洋側を中心に、台風並みの暴風が吹き荒れ、見通しが全くきかないほどの猛ふぶきとなるおそれ。 東北の日本海側と新潟県では、断続的に雪が降り、吹雪による視界不良で交通機関に影響の出るおそれがある。 しかしこれも一時のことで、季節は確実に春への歩みが本格化。当初、予想されたいた立春の後の寒の戻りはなさそうで、関東以西は10度以上の気温が続くようだ。 9日に限って寒気が入るもののそれが続くことはないようだ。少なくとも、愛知県のここ知多市ではあのくそ寒い日からは完全に開放されるようだ。 雨も降って気温も上がり、湿潤でおだやかな風が大地を撫でていく。そんな空気に包まれて、草木や動物や着ぶくれした人間たちも、ほんわかとこみあげて来る胸のドルチェの高鳴りを聞く。 うきうきとした気持ちが湧き上がって来る、予感と期待の入り混じった2月という月は、金曜日の夜のような、遠足の前の日のようなもの。生きものすべてがこの時を待っている。
2023.02.02
コメント(0)
-
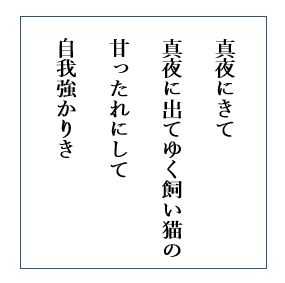
〇〇 剛直の心のなせるへそ曲がり
♪ 真夜にきて真夜に出てゆく飼い猫の甘ったれにして自我強かりき この日の「折々のことば」を読んで、思わず我が意を得たりとばかりに手を打った。人と違うことを言うと嫌われる。違うことをやろうとすると闇雲に反対される。偏屈と言われ、変人扱いされたりもする。 日本という社会は何故にこうも右倣えの同調社会なのだろう。同じことが最も重要で異を唱えることは罪悪でさえある。今の日本が低迷の一途で、世界からどんどん取り残されていくのは、背景にそういうものが大きく影響していると思えてならない。 大企業ほど融通が利かない。変えていくことに抵抗があり、それを阻止しようとする力ばかりが働く。既得権とか自分のポストとかの問題もさることながら、現状に固執してがんじがらめに縛られてて身動きが取れない。部下の意見を聞こうとせず、悪いと思っていてもズルズルと先延ばしし、責任の所在をあいまいにする。 これまで、大企業のトップが、マスコミのカメラの前で頭を下げている姿をどれだけ見せられてきたことか。それらのすべてがこの国の弱点をあからさまに示している。政界も財界とまったく同じ。 かつて「Japan as Number One」と言って、アメリカ国民に「日本に学べ」とおだてられ、高度経済成長に浮かれていた。今はその時の世界状況とはまったく違う。なのにその時の栄光が忘れられず、ぬるま湯にどっぷり浸かったまま出ようとしてこなかった。今や三流の国に成り下がって、発展途上国と見下していた国々にお株を奪われつつある。ハナキリン 自分のことについていえば、偏屈のへそ曲がりそのもの。「他人と同じ」が気に食わない。その上、強制されるのも大嫌いときている。 住んでいる字のある役員に就いた時、今まで通りのやり方に不満があり、「会計」という立場で出来る変革ををどんどんやった。1年限りの役職であるメンバーからの反対はなかったが、翌年の役員がその後どうしたのかは知らない。多分、元に戻してしまっただろうと思う。「因習という常識」を打ち破るのは並み大抵の努力では出来ない。♪ 5月には「マスク外せ」の声上がらん並べてうれすい金太郎あめ
2023.02.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1