2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年06月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
『選挙(想田和弘)』
2005年、小泉改革の中での、川崎市市議会議員補欠選挙のドキュメンタリー。立候補者の山内和彦氏は、自民党の候補者公募に通り、自民党の公認を得て立候補する。政治は勿論、選挙も全くの素人の山内さんが、自民党の人たちの応援を受け叱責を受け選挙戦を戦う姿が記録されている。とはいっても、2時間に収められているわけで、それがすべてではない。監督の想田和弘氏は、学生時代の山内和彦氏の友人であり、その縁がこの監督に、この映画を撮らせたのだろう。記録映画にある、ナレーションも音楽も入っていない。ただただ、目の前の風景を取り続け、それを2時間に編集したものだ。想田監督は「観察映画」と名づけている。メッセージ性を排除したと言うことらしい。しかし、編集も撮影も想田監督による限り、メッセージ性を封印したと言うのは、所詮言葉の彩でしかない。嘗て、「ビデオ掛け軸」というビデオ作品があった。それは、桜の木や滝や竹林や海岸にカメラを据え、一切カメラを動かすことなく、その前の風景を音とともに取り続け、それを作品にしたビデオである。これらの作品は『選挙』以上に、客観的だと思うが、それでも作者からのメッセージは見ているもに伝わる。もし、想田監督が、「観察映画」と称して、メッセージ性を封印したと言うのなら、それは思い違いに他ならない。電柱にもお辞儀とか、そういうことはこの映画をみなくても考えれば、いまの選挙の実態ぐらいは予測がつく。この映画で面白いのは、選挙事務所での手伝いに来ている、叔母ちゃんたち(自民党員か支持者)の会話。例えば、共産党の人に選挙の時、部屋を貸したとか、創価学会の人が公明新聞を取ってくれ、お金は出さなくてもよいから、自分で出すからお願いしますとか・・・、そういう内輪話が面白い。また、山内夫妻の車での会話、家での会話などの本音の部分だ。さて、『選挙』は2時間あった。最初は退屈に感じた。もう少し短く90分くらいにまとめれば、さらに鋭い作品になったと思う。
2007.06.30
コメント(6)
-
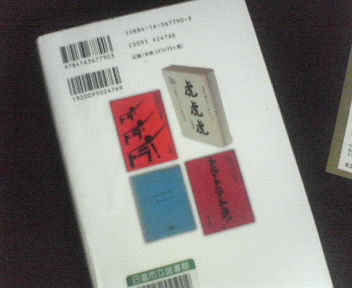
『黒澤明 VS ハリウッド 「トラ・トラ・トラ!」その謎のすべて(田草川弘)』文藝春秋
『黒澤明 VS ハリウッド 「トラ・トラ・トラ!」その謎のすべて』は480ページにも及ぶ大作で労作、そして傑作だ。黒澤明のこともアメリカの映画会社のこともダリル・F・ザナックやエルモ・ウィリアムズなど登場人物もすべてに興味深い。筆者の田草川弘氏は黒澤明の、これも流産した『暴走機関車』のシナリオの英訳が縁で知り合う。そして後、『トラ・トラ・トラ!』が、何故黒澤の手を離れたかの謎に迫る。それも、日本には殆どそれに関する資料がなく、20世紀フォックス社などアメリカにその資料があることを知り、努力の末の末、この書をまとめる。面白い、とても面白い。興奮の一冊。『虎虎虎』『トラ・トラ・トラ!』『トラ・トラ・トラ!』『TORA!RORA!TORA!』のシナリオ。これらも、散逸し米国の図書館などにあった。表紙のイラストは黒澤明の手による絵コンテ黒澤明VSハリウッド『トラ・トラ・トラ!』その謎のすべて田草川弘文藝春秋2006年4月25日 第1刷
2007.06.29
コメント(2)
-

折れた木
何かの力で、へし折れた木です。一瞬、鳥に見えます。場所は名古屋市名東区。
2007.06.27
コメント(6)
-
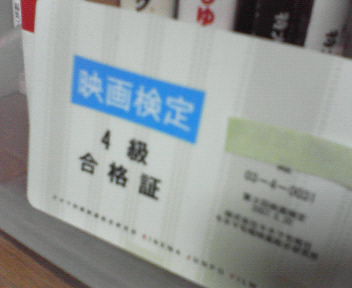
身辺雑記「映画検定」
去る、5月20日受検した、「映画検定」4級の結果が来ました。無事、合格。60点満点の54点でした。思いのほか出来ていました。これで、一安心。写真は合格証です。
2007.06.26
コメント(6)
-
『マダム・グルニエのパリ解放大作戦(ロイ・ポールディング)』
1974年のイギリス映画です。ただし日本未公開作品。DVDで見ました。それも、パソコンのモニターで・・・。だから、ただ見たという程度でしたが、面白い怪作ですね。マダム・グルニエはパリで高級娼館を営む。その時のパリは、ナチスドイツに占領されていた。そこを舞台にした艶笑劇。ピーター・セラーズがヒトラーや日本の皇族「プリンス・キョウト」、はたまたゲシュタポなど7変化の大活躍。嘗て、TVで放送された時、その「プリンス・キョウト」のシーンがまるまる約15分カットされて、98分が、83分になった、という。このDVDは、95分で、3分短い。DVDの解説に、娼婦と野球拳をする云々と書かれてあるが、野球拳のシーンはなかった。ここがカットされたのだろう。不敬罪が今でも生きているのか?冗談の分からぬ人たちがいる限り、こういうことがあるのだろう。スクリーンで観るのは困難だが、DVDでもよいので、カルト的必見作。因みに、原題は【Soft Beds, Hard Battles】
2007.06.24
コメント(2)
-
『大江健三郎 作家自身を語る(大江健三郎 聞き手・構成尾崎真理子)新潮社』
『大江健三郎 作家自身を語る』の続きです。以下、いつものように書き抜きです。保守政党の指導者たちにとって都合のいい、しかも頼りになる理論家として、たとえば江藤淳という評論家がしっかりした足場を得ていた。商業演劇の分野には、やはり日本の指導者が喜んで受け入れる浅利慶太の活動があって、この人は演劇ばかりではなく、中曽根康弘氏がレーガン大統領と会見する場所の演出をするということもした。いうまでもなく石原慎太郎は政治家になって、日本という国家の中心を担う人間の一群として自己実現した。かれらに対して、私や武満(徹)さんは中心に向って進まず、周縁的な場所から、エスタブリッシュメントの社会からは異端視される場所で、批判的な立場の想像力を原動力にする仕事をしてきた。もちろん、音楽の世界でいえば武満さんは中心的な人物ですし、(以下略)私がいま、エドワード・サイードのような、パレスチナの問題に熱中した文学理論家、文化理論家に親近感を持つのは、かれが「エグザイル」と自分を規定しているからです。(中略)私なども、故郷には帰らないエグザイルとして、中心を批判する場所で仕事をしたいという態度を、安保の頃から次第に固めてきた人間です。(p69~70)人間にとって「欲」の制御は難しい。「エグザイル」というのを意識的にでもしない限り、中心からそれた所で行き続けるのは相当の意思の力がいる。普通は、中心にいたくても、それだけの力がなく、たまたますこしはずれた所に立っているに過ぎないと思う。人間は本来、本質的に善良な、いいものだという考え方を私は昔から持ってきましたが、生きて行く上で、そうでないという気持ちを持たざるをえないことが起る。ところが知的に障害を持つ子供が自然に生活していくなかで、美しい音楽を聴いて楽しみ、そのうち自分でも美しい音楽を作る、それを聴いた人たちが「本当にほっとした」といってくださるような音楽を作る。そうした現実に起きた出来事が、私にとって一番神秘的なこと、私らへのgraceの現われだったわけなんです。(p210)テレビや出版物を通じていわゆるスピリチュアルな世界のことと称して、思いつきを情緒的に話しかける、そういう人たちを私は信じない。私はスピリチュアルなものは一般的には人間から離れたところにあって、人間臭くないものだと考えてきたんです、キリスト教や仏教のスピリチュアルな人のことを考えて。ところがいま、テレビなどの出ている人たちはあまりにも人間臭い。(p223)いまの、スピリチュアルと言う人の胡散臭さはどうだ。見るだにしたくないのは自分だけでないと思う。《おれは赤ん坊の怪物から、恥しらずなことを無数につみ重ねて逃れながら、いったいなにを守ろうとしたのか?いったいどのようなおれ自身をまもりぬくべく試みたのか?》『個人的な体験』より自殺した大臣もなにを守ろうとしたのか?嘘をつき続ける会社経営者、他に社会的に偉いと思われている人たち、はなにを恐れるのか?自分でも、同じように大小に拘わらず、守ることがしばしばある。「知的修練/文学修業のどちらにも、ブログの文章をエラボレイトしよう」。ブログに自分で書いたものをプリントアウトして、何度も書き直しを重ねていくのが自分をきたえるのに有効だと思いますよ。ブログという形式の欠点は、まだ生煮えの状態でインターネットに乗せられてしまう、という点じゃないでしょうか。(p279)大江健三郎は、いつもエラボレイトと言う。書き直し、書き直し、推敲し、推敲し、その文章を初めて世に出す。ブログはいかにも生煮えである・・・?このブログもその例に漏れないのだと思いながら・・・。
2007.06.23
コメント(0)
-
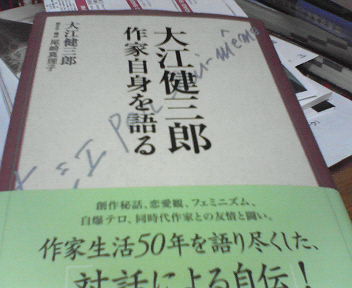
『大江健三郎 作家自身を語る(大江健三郎 聞き手・構成尾崎真理子)新潮社』
『大江健三郎 作家自身を語る(大江健三郎 聞き手・構成尾崎真理子)新潮社』を読みました。作品を読むよりは、読みやすい。最後の、「大江健三郎、106の質問に立ち向かう」が面白い。詳しくは、後日・・・。大江健三郎 作家自身を語る大江健三郎 聞き手・構成尾崎真理子新潮社2007年5月30日発行
2007.06.20
コメント(0)
-
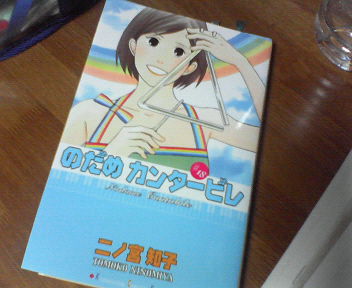
『のだめカンタービレ #18(二ノ宮知子)』
『のだめカンタービレ』18巻読みました。17巻が2月でしたから、4ヶ月経っています。17巻のことは、殆ど覚えていません。17巻の時はそれ以前を殆ど覚えていませんでした。こういう状態で、読み続けています。1巻から16巻までは、一気に読んだので、忘れないで読めましたが・・・。しかし、これ(18巻)だけ読んでもそれなりに、面白かった。19巻はまた4ヵ月後だね。のだめカンタービレ #18二ノ宮知子講談社コミックKiss2007年6月13日 第1刷発行アニメーションは、TV現在も進行中です。
2007.06.17
コメント(0)
-
『あるスキャンダルの覚え書き(リチャード・エア)』
『あるスキャンダルの覚え書き』です。タイトルどおり、スキャンダラスな内容の映画。でも、これは、ホラーです。でも、先が読めてしまうので、そういう意味では平凡な出来。しかし、主演の二人は流石です。ジュディ・デンチとケイト・ブランシェット、やはりプロの役者です。先日の井筒和幸の韓国映画と日本映画の比較を引用しましたが、この『あるスキャンダルの覚え書き』のケイト・ブランシェットのような役を今の日本の女優?思いつきません。しいて言えば、寺島しのぶ?昔は『にっぽん昆虫記』の左幸子など、でしょうけれど。
2007.06.14
コメント(2)
-
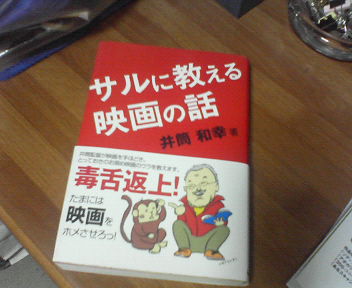
『サルに教える映画の話(井筒和幸)』
この本の帯(通称/腰巻)に、毒舌返上!たまには映画をホメさせろっ!とある。『こちトラ自腹じゃ』では、映画をくさしたり、けなしたりばかりだったそうで、この本では、井筒和幸お薦めの映画が五万と出てくる。それも、殆どが劇場で見ている。浴びるように映画を見た、ということが分かる。やはり、映画監督だから、そのことが説得力をもって迫ってくる。今の映画は、まず撮影したフィルムをデジタル化して、コンピュータのモニターで観ながら編集です。約一ヶ月モニターとにらめっこ!次はデジタルでつないだカット群を、もう一回フィルムに変換してつなぐ。そしてつないだフィルムを、実際にスクリーンで観る。その時初めて、一連の映画として観るわけ。するとモニターで観た時と全く違う、色々なものが見えてくる。(スクリーンとモニターでは)全然違う。スクリーンだと、目の動きとか、手の所作、服の感じ、風景の右端、左端、色んなものが見えてくる。モニターでは上手くいっていたと思った目の芝居でも、スクリーンに映すと実にキョロキョロしていたりとかね。映画のリズムがここで初めて見えてくる。でもVシネマなんかは、そのまま家庭のモニター用の商品になるわけですから、スクリーンでなんか観ていないでしょうナ。映画はスクリーンで観て、初めて雰囲気とか空気感とかが、見えてくるものなんや。やや、長かったが大切な所なので引用した。あとは、井筒監督の言葉を順次引用する。納得するも疑問に思うもそれぞれの自由です。では、例えば、「今夜の深夜テレビで『ET』あるから早めに帰ろう」というサラリーマンいる?絶対、いないよ。『ゴッドファーザー』の撮影に関するところで、だからオモロイ映画を探す場合は、役者、監督、そしてキャメラや音楽にも注目していくと、いい作品に巡り合う確率が高くなる。イギリスの監督ケン・ローチが高松宮殿下世界文化賞を受賞し日本に来て英国大使館のレセプションでスピーチをした。そのスピーチ・・・、「我が国イギリスは最低の国だ。ブッシュの弟分になってイラクに行って、イラク人を沢山殺してしまった。とんでもなく恥ずかしい国家に成り下がった」「最低の大英帝国になりましたが、普通に考えているイギリスの国民がいることを忘れないで下さい」というスピーチだった。こういうことを新聞やテレビがちゃんとインタヴューして報道しないと、日本もどんどん酷い国になってまうデ。ワイド・ショウもくだらんことばっかりやってないで、ちゃんと紹介せい!そんなスピーチがあったことすら報道されない。ケン・ローチは『麦の穂を揺らす風』が昨年公開されました。傑作です。必見です。今みたいに、部屋でDVD見ているノリとちゃうデ。行って観る。その映画は一生覚えている。車の形から、主役がどんなズボンをはいていたとか、全部覚えている。つまり、映画は鑑賞じゃなくて体験だったということです。奴ら(アメリカのハリウッド)の最高の市場は日本なんですよ。だから日本に売っとけと。バカOLとバカガキが観るって、担保みたいなもん。だから、これはアカンいう映画は、日米同時公開。確実にいい映画やと思ったら、まずアメリカで下地を作ってドカン儲けて、そして日本に高く売り付ける。そういうシステム。だいたいコメディアンって反骨精神を持っている、体制の批判者でしょ。シニカルなことも含めて。毒牙を持ってますよね。でも、ニセ・コメディアンは、自分より下をちゃかす。上をちゃかすのがコメディアンよね。イ・ビョンホンとチェ・ジウの韓国映画『誰にでも秘密がある』に触れてながら・・・、ただの艶笑話よ。語るほどの内容やないけど、三姉妹が一人の男と平気でやってる色情三姉妹みたいな話、でも女優はポルノ女優やない。韓国の一流たち。日本じゃ、こんなモンでも作れないナ。長女役なんてチマチョゴリのまま騎乗位でやってたぞ。妹役だって韓国のアイドル系。考えてみぃ。日本の若手人気俳優って?柴咲コウとか、仲間由紀恵とか、妻夫木聡やSMAPかなぁ。柴咲とか、仲間が「ねぇ、後ろ向きでして!」とか、いえるかな?と、かなり厳しい。因みにこの中でホメてる映画を・・・・。『飢餓海峡』『ゴッドファーザー』『ファイブ・イージー・ピーセス』『突破口!』『愛のコリーダ』などです。サルに教える映画の話井筒和幸バジリコ株式会社2006年10月29日 初版第1刷発行
2007.06.12
コメント(2)
-
『パッチギ!LOVE & PEACE(井筒和幸)』
『パッチギ!LOVE & PEACE(井筒和幸)』を見ました。夕方の回でしたからでしょうか?それとも封切って日が経つからでしょうか?客は10人程度。土曜日の夕方、シネコン(MOVIX三好)は混雑していました。前回と同様に、韓国が表に出ている。しはし、そこから読み取れるのは、日本人って?何だ。民族って?今、自分がここのいるということはどういうことの繋がりがあるのか?もっと、真面目に考えよ、たまには・・・、と。読むことが出来る。内容は、前回よりも韓国人中心になっている。中村ゆり、井坂俊哉、今井悠貴の親子兄妹や手塚理美、風間杜夫、そして、日本人役は藤井隆、でんでん、ラサール石井など。その他にも、米倉斉加年、馬渕晴子、愛染恭子などなどその人たちを見るだけでも面白い。物語は、大阪から、子どもの病気筋ジストロフィを治そうと東京に出てきた一家が中心となり、その家族に関わっていく藤井隆。怪しい(?)芸能プロダクション(でも、社長は気骨ある人に描かれる)にスカウトされ、みるみるスターになっていく少女。その少女が、主役の座を掴む、映画『太平洋のさむらい』。やや、図式的過ぎるが、そこには、最近の似たような映画へに対する、井筒監督の批評になっている。最初と最後の乱闘シーンは、前作同様でこれでもか、これでもかとやってくれる。前作よりも、出来が良いと思うのは、メッセージがより普遍的になったからか。
2007.06.09
コメント(0)
-
映画検定プロジェクト
映画検定外伝~映検1級合格者による映画のススメ~を紹介します。今年の5月20日に行われた、第二回映画検定で1級になった人の映画評です。映画検定事務局が企画し、1級合格者に連絡が来て、書きたい人が手を上げて評を書き、事務局に送る方式です。評する映画は、事務局が決めた作品から1作品を選びます。今回、「クィーン」を選んで書きました。それが、掲載されています。映画検定外伝このリンクからアクセスして下さい。映画検定1級の人たちの評が読めます。ブログのデザイン変えました。まだ、しっくり来ませんが・・・。
2007.06.08
コメント(2)
-
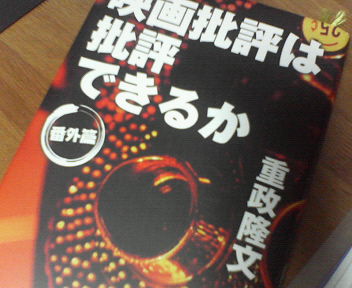
『映画批評は批評できるか 番外篇(重政隆文)』松本工房
読んでいて、余り気分のよい本ではなかった。その訳は、悪口の所を読むと、なんだか気分が・・・、である。しかし、この人の映画は映画館で見るべきだという姿勢の徹底振りは感心する。専門の映画評論家ではない、著者は局外者と呼んでいる。57人を俎上に乗せ批評の批評をしている。著者が認めた局外者を思い出す限り書いてみる。池澤夏樹、橋本治、姫野カオルコ、井筒和幸、久世光彦、手塚治虫、快楽亭ブラック、高田治、内田樹等である。この本の眼目は、狼少年のように、いつも狼が来るぞと言っていると本当に狼が来た時にそう言っても信じてもらえない。だから新聞雑誌で常に好意的な文章を書いたり、番組で常に褒め言葉を使って新作映画を評したりしている人はあまり信用できない。本心から言っているのかあるいは業務上言っていることなのか、読む側、聞く側は冷静に読み取らねばなるまい。p34と、述べている。だから、本来きちんと映画を評価しなければならない、映画評論家と言われる人たちは、映画会社=配給会社と持ちつ持たれつになっているのではないかと、疑問を呈している。勿論すべての映画紹介や批評が、提灯記事的ではないが、それを見極めよと。かえって、局外者の方が映画会社や配給会社とのしがらみがない分、本当の評価をしているのではないかとの期待が、この本を書かせた、と思う。だから、局外者だとは言え、手厳しく批判している。あとがきに、山根貞男と金井美恵子の面白い対談がある。と紹介している。山根 今、試写を見に来ている九割以上の人が、何者か見当がつかない感じなんです。雑誌がいっぱいあって、特に女性の雑誌がすごくたくさんあるので、そういうところにちょっとした紹介を書くために、いっぱいライターが来ているらしい。金井 グラビア系雑誌の、いってみればマッチ箱大の情報紹介記事ね。山根 そういう人がちょっと気のきいたことを一行書きたい。それがプレスシートにちりばめられてあるわけです。極端にいえばマッチ箱大の記事だったら、プレスシートだけで書けますね、映画を見なくても。(山根貞男/金井美恵子「映画と批評の現在」『群像』2003年2月号、講談社、所収)プレスシートが悪いわけではないと思うが、多くの情報紹介記事が似たり寄ったりなのは、書く方がプレスシートに頼っているからだと・・・、あとがきをもう一箇所引用する。私たちマスコミ関係者は、試写で一足早く映画を見た時に、プレスシートと言うパンフレットをもらいます。(中略)一般試写会の前説で、エラそうに映画が語れるのも、このプレスシートがあってこそ。しかも、会場にいる人は入場時にチラシしかもらいませんから、プレスに書かれたネタは極秘中の極秘みたいにしゃべれるのです。(『シネマなお仕事(森川みどり)』2002年11月 青心社 88~9ページ)結論として、映画を見るときに誰の言うことを信頼して見るのか?そういうことは気にせず見るのか?そのあたりを考えさせられる本である。映画批評は批評できるか 番外篇重政隆文松本工房2003年12月1日 初版発行2007年4月1日 第二版発行
2007.06.07
コメント(8)
-
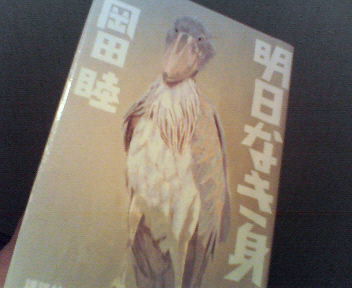
『明日なき身(岡田睦)』講談社
文芸評論家の清水良典氏が、この本の帯で、必読と推薦している。生活保護(セイホ)を受けている作家、岡田睦の『明日なき身』がそれである。まさに、貧困の中での作家活動が綴られている。悲惨、悲愴そういう風だが、どこかあっけらかんとしたものを感じることが、逆によけいに惨めさを醸し出している。「火」から燃える壁、衣類、アルバムより桁違いに深い喪失感があった。阿川(弘之)さん、大久保(房男)さん、大学でただ一人の恩師、水戸(多喜雄)先生各大先輩のお手紙、つき合いかけて別れた美少女、いまでも忘れられないそのスナップ一葉、もう手に入らない書物、例えば江藤(淳)君の署名入り「夏目漱石」(勁草書房)の初版本等々、諦めるにはかなりの年月を要すると思った。これは、著者が暖を取るため、ティッシュペーパーを室内で燃やしたことから起きた火災での記述。セイホを受けてはいても作家だから、本や手紙やを取っているし、はたまた、おもいでの少女の写真もちゃんと取ってある所が、現実的である。全編を通してうじうじした感じは免れないが、その分正直に書いているのだろう。当然物語として、幾分の誇張やデフォルメはあると思うが、そんなことは大したことではないとも思えてくる。こういう作家が居るということだ。岡田睦(おかだぼく)1932年生、東京生まれ。慶応義塾大学卒。家庭教師などを経て文筆業。三人目の妻と別れた後、生活保護と年金で暮らしている。著書に『薔薇の椅子』『ワニの泪』『乳房』等。明日なき身岡田睦講談社2006年12月15日 第1刷発行
2007.06.04
コメント(0)
-

外の仕事。畑と田んぼ。
畑のことや、田んぼのことです。田植えを、今は機械がやります。だから、所々土の状態がゆるく、苗が抜けるます。その抜けた所をあとから手で植えます。それを、今日、やりました。と言っても、主にやったのは家人で、私は苗を運んだりして、植えたのはほんの少しです。また、この田んぼは我が家のものではなく、家人の実家のものです。ただ、うちの隣にあるから、うちで出来る範囲は、面倒を見ています。この景色が、我が家からみえる景色です。今日は、天気もよく、あまり暑くないさわやかな日でしたから、汗もかかずに、外の仕事は快適でした。苗を植えたほか、草刈を少しと、枯れ草や枯れ枝を燃しました。茄子の花が咲きました。
2007.06.03
コメント(2)
-
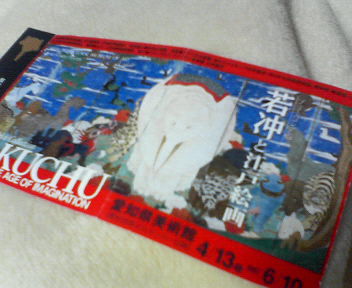
『若沖と江戸絵画』
所用で町へ出たついでに、『若沖と江戸絵画』を見てきました。面白かったです。片付ける時は、たたむという屏風も軸も文化です。先日の『ダリ展』より、よほどよかったです。今、愛知県美術館で開催中。6月10日まで・・・。チケットです。雪中松に兎(部分)葛蛇玉(かつじゃぎょく)作この絵の暗さと雪の感じには魅せられました。これは、六曲屏風。猿猴狙蜂図(部分)森狙仙(もりそせん)作猿が蜂を見上げています。この猿の可愛さは例を見ないものです。これは、掛け軸です。
2007.06.02
コメント(2)
-
『ボラット 栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習(ラリー・チャールズ)』
1000円の日でした。当たり外れを危惧して、1000円の日に『ボラット 栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習(ラリー・チャールズ)』を見ました。どちらかと言えば、当たりです。こういう法螺話は時々ある。カザフスタンのボラットなる男が、アメリカの文化を自国に紹介するためにTVレポーターとしてアメリカに行く。その前に、自国でのこの男の振る舞いが紹介されるから、この米国行きは、はちゃめちゃなものになると分かる。米国のTV局での振る舞い、ロデオ会場でのこと、よそへ招かれた時のことなどすべてが、悪意のある失敗と思われるほどである。確信犯?NYからカリフォルニアへのロードムーヴィー的な部分もある。ここでめぐり合う娼婦が優しい。『世界最速のインディアン』も、ゲイが主人公に優しい。この種の共通点が気になる。何かへの免罪符か?しかし、久々によく笑った。
2007.06.01
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- 今日見た連ドラ。
- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…
- (2022-01-28 23:32:16)
-
-
-

- 華より美しい男~イ・ジュンギ~
- 10月の準彼ンダー&台北公演の画像続…
- (2024-10-01 14:52:47)
-
-
-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…
- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…
- (2025-04-26 15:25:48)
-







