2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年07月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

松岡正剛の「千夜千冊」からの雑感。
『松岡正剛の「千夜千冊」虎の巻』のなかで、小川未明に触れた箇所があり、『小川未明名作選集1 赤いろうそくと人魚(ぎょうせい)』を図書館で借りて、表題の「赤いろうそくと人魚」をまず、読んだ。日本のアンデルセンといわれた小川未明を読むのは初めてのこと。前々から童話=ファンタジー、そして、幻想怪奇であると思っていたので、この話も、そういうことで勝手に納得。ろうそく作りで糊口をしのいでいる年寄夫婦が、神社で拾った、人魚の赤ん坊を育てて云々・・・、という物語。松岡正剛の千夜千冊の第三十七夜にある。ところで、この『松岡正剛の「千夜千冊」虎の巻』は本好きには堪らない面白さである。まだ、初めの部分しか読んでいないが、とても楽しみな一冊。ちょっと本気な 千夜千冊 虎の巻 読書術免許皆伝松岡正剛 求龍堂2007年6月27日小川未明名作選集1 ~赤いろうそくと人魚~小川未明平成5年12月10日発行ぎょうせい
2007.07.29
コメント(0)
-
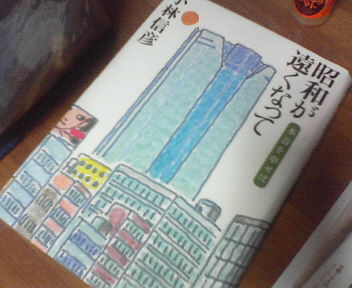
『昭和が遠くなって 本音を申せば(小林信彦)』その2
(承前)『昭和が遠くなって 本音を申せば(小林信彦)』引用を追加します。最近、書店へ行くとアメリカのクラシック映画のDVDが一枚五百円で売られている。ぼくは興味があり、一枚買って、観たことがあるが、画質が悪く、字幕の日本語もよくないので、捨ててしまった。それでも安ければいい、というのか、この〈ゴミまがい〉のDVDは、場所によっては山積みされている。その中に「ローマの休日」もあるわけだ。この『ローマの休日』事件は、パラマウントが仮処分の申請を出し、発売の禁止を求めたが、申請を却下した。映像のクォリティ〈質〉というものが全く無視されている・・・。いわば、海賊版に近いものからの複製ではないかと言うのが小林氏の推測。だが、われらにしてみれば、画質、字幕の日本語の質云々を問う前に、500円は安い。それが、理由でこれらのDVDを買う。私も、『西部戦線異状なし』『グランド・ホテル』『大いなる幻影』など、持っている。今、DVDは2500円から5000円程度だと思う。その他に、690円や1000円、1500円のDVDもある。そのすべては外国映画であり、日本映画のDVDは3000円を超えるものがほとんどで、中々買うことが出来ない。所謂、著作権期限が切れたもの、パブリック・ドメインというものは、正規のメーカーが1000円程度でDVDを出せばいいことだと思う。最後に局と番組関係者と代理店にとって必要なのである。そのころの日本人はまだ、ハズカシサというものを心得ていたので、〈視聴率をこんなにとったぞ!〉と得意になるのはカッコワルい――ぐらいの自覚はあった。あたりまえの話しである。当時のプロデューサーたちは、テレビの第一期生、初代であるから、視聴率と番組の質が一致しないことぐらい、百も承知である。とび抜けたバカ番組だけを手がけるディレクターは、それぞれで、才能を買われていた。世間から叩かれるようなとんでもない番組は、とんでもない視聴率をとったりする。そういう番組があるから、安心して〈有識者向きの番組〉に専念するディレクターが存在できる。昭和が遠くなって 本音を申せば小林信彦装丁 小林康彦2007年4月25日 第1刷発行
2007.07.28
コメント(2)
-
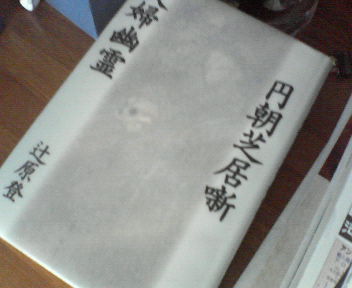
『円朝芝居噺 夫婦幽霊』その2
承前『円朝芝居噺 夫婦幽霊』昨日の続きです。中日新聞のコラム「大波小波」に、辻原登の『円朝芝居噺 夫婦幽霊』は、三遊亭円朝の幻の落語「夫婦幽霊」を記録した速記が発見されたという手の込んだ仕掛けから始まって、みごとに円朝の新作を創り上げてみせた。とある。兎に角、訳者後記に至るまで、手の込んだ創り方であり、噺の面白さも去る事ながら、仕掛け自体を堪能できる。中にある、句を紹介すると、寝てとけば帯ほど長いものはなし入梅やたたみも草のふみ心待宵や汲んで見たきはよどの水足りること知りてもさすがちるさくら以上このコラム、今日(7/27)は河野多恵子と山田詠美の対談、小川洋子と川上弘美の対談のことが出ていたが、これらも読みたくなる。そういう、コラムで、中日新聞の夕刊が手放せない。円朝芝居噺 夫婦幽霊辻原登講談社2007年3月20日 第1刷発行
2007.07.27
コメント(0)
-
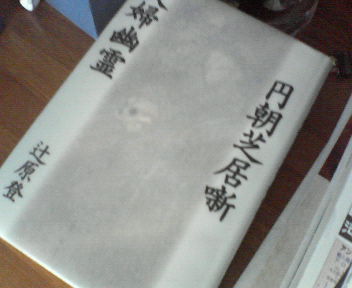
『円朝芝居噺 夫婦幽霊 〈辻原登)』講談社
円朝芝居噺 夫婦幽霊辻原登講談社2007年3月20日 第1刷発行この本を読むきっかけは、「中日新聞 夕刊」のコラム「大波小波」による。このコラムはとても面白く、長続きしている、中日新聞の名物コラムだ。ここで、この『夫婦幽霊 円朝芝居噺』が紹介されていた。
2007.07.26
コメント(0)
-
Second Lifeのこと その2
SL(セカンドライフ)に参加して、1週間。まだ、うろうろしています。PCの環境が合っていないのだと思います。アバターの動きがよくありませんし、服装がなかなか上手き行きません。まあ、気長に・・・。しかし、日本の地域では日本語で会話が出来るので、そこはまあまあです。
2007.07.22
コメント(0)
-
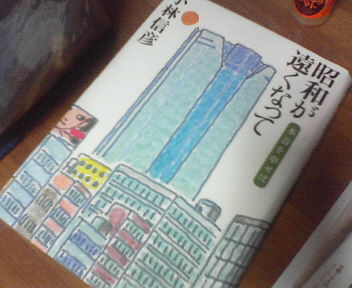
『昭和が遠くなって 本音を申せば(小林信彦)』文藝春秋
週刊文春に連載のエッセイ「本音を申せば」2006年1年分の単行本である。このシリーズは『人生は五十一から』にはじまり9冊になる。と言うことは、9年。小林信彦のエッセイは、映画、本、TVなど軟派が多いが、この週刊文春の連載は、政治のことが結構ある。この『昭和が遠くなって』は、2006年の政治の象徴が書かれているように思う。前原と言う民主党代表の態度が異様な理由もわかった。かねがね、ぼくは民主党の〈若手〉と称する人間の一部は小泉自民党の別働隊ではないか、と推理していたのだが、この代表という人物はどうもそうらしい。(まだまだ続くダイエット 06/3/16)若いと称する永田衆議院議員のあのガンコさ、鈍さは何なのだろうか。ふつう、あれだけ党と国民にメイワクをかければ辞職するものだ。つまり、神経が〈ふつう〉ではないのだ。あの鈍感さを支持するつもりか、永田を守る姿勢をとっている前原代表と言う人物。〈中略)〈責任〉という考えのない男なのですね。〈集団的自衛権行使の容認〉を主張しているそうだが、基本的に野党の発想ではないのだから、代表をやめない限り、民主党は混乱するに決まっている。永田も前原代表も、そういう事態を招いた責任をとってハラキリをするという、ごくふつうの発想がないのだ。〈人間、若けりゃいいのか? 06/4/6)「私はこれを〈コンビニ世代〉と呼んでいるのですがねえ・・・」と、評論家の平野貞夫氏。民主党の若手がふるわない、とうい声に答えたものだった。〈中略)「ボクちゃん、ちゃんと政治、やってんだもーんね」という若手。メダカのように集う〈コンビニ世代〉。民主党にも、自民党にもいるボクちゃんたち。これらを称して、平野氏は、ずばり、〈コンビニ世代〉と呼んだのである。平野氏は数えの七十で政界をしりぞき、後進に道をゆずった。(〈コンビニ世代〉とは――? 06/5/4・11)政治の話題は、こんな感じである。小泉自民党に対しての発言は、もっと厳しく、絶望的である。2006年サッカーワールドカップ。オーストラリア戦の時の話題。日本はオーストラリアに負けた。アナウンサーが「日本、完敗です」と告げた。これは必ず妙な説明が入るぞと思っていたら、コメンテーターが、「向うの身体能力に立ち向うには、日本は精神力しかありません」と神がかってきた。これは典型的な〈戦時中の精神論〉である。翌日の大新聞にはW杯メキシコ大会の日本人審判の言葉として、〈敗戦話し合い 心一つに〉という大きな文字が出ていてギョッとした。全部、あのころのリピートではないか。(ラジオ・デイズ2006 2 06/6/20)と、切り込んでいる。昭和が遠くなって 本音を申せば小林信彦装丁 小林康彦2007年4月25日 第1刷発行
2007.07.20
コメント(0)
-
『それでも生きる子供たちへ』
『タンザ』(メディ・カレフ )は、少年兵の話。『ブルー・ジプシー』(エミール・クストリッツァ)は、盗みを働き、再三再四、刑務所に戻ってくる子供の話。『アンダーグラウンド』『黒猫白猫』のクストリッツァらしい、テンポが私の気に入りだ。『ビールとジョアン』(カティア・ルンド )空き缶や、鉄屑や、ダンボールを集め、暮らしを立てている兄妹。『シティ・オブ・ゴッド』と同じテンションが魅力的。『アメリカのイエスの子ら』(スパイク・リー )は、HIV感染に恐れる少女。仲間が居ることが救いの一つという話。人は救われなくては・・・、希望がなくては・・・。 『ジョナサン』(ジョーダン・スコット&リドリー・スコット )も、戦争が常に世界のどこかにある。子供はいつも巻き込まれる、一番の犠牲者!『チロ』(ステファノ・ヴィネルッソ)これも、盗みを働く少年。イタリアらしい人物描写。孤独な少年の姿がこの映画の本質。『桑桑と子猫』(ジョン・ウー)。ジョン・ウーはアクションのみかと思わせながら、これはしみじみと良い。金持ちの桑桑と孤児の子猫、どちらも明るい少女。その優しさが伝わる。佳作である。『それでも生きる子供たちへ』
2007.07.17
コメント(0)
-
Second Lifeのこと
セカンドライフにログインしました。全く、どうしてよいのか分かりません。アバターの動かし方も、服装の決め方も、着せ方も全く手探り状態以前です。ほとんど、日本語が使えないのです。しかし、面白そう。これからが、楽しみですが・・・。
2007.07.16
コメント(2)
-
DVDで『恐怖のメロディ』クリント・イーストウッド
DVDで見ました。この手のもの(ストーカー映画)はいくらでもあって、その一つ。ジャズフェスティバルや、イーストウッドが恋人と歩くシーンとか長々とあり、何だこれは、である。ドナルド・シーゲルがバーテンダーで出てくることと、ジャズフェスティバルでキャノンボール・アダレーが見られるくらいが、お楽しみ。原題は『Play MISTY for Me』ついでに言うと、「MISTY」はエロール・ガーナー(ピアニスト)の名曲で、この辺が、イーストウッドの趣味で、この映画を取り上げたのかも知れない。恐怖のメロディPlay MISTY for Meクリント・イーストウッド1971
2007.07.16
コメント(2)
-
続『黒澤明VS.ハリウッド 「トラ・トラ・トラ!」その謎のすべて(田草川弘)』
以前に取り上げたましたが、その時にかけなかった部分を追加します。黒澤監督は、自分が惚れ込んだ古典文学に対して、一種の信仰ともいうべき尊敬の念と無条件の信頼感を持っていたように思われる。『虎 虎 虎』が「百年や二百年で古くなるような映画(シャシン)なら要らない」と(以下略)「最も新しい事実とは、いつか必ず古くなる事実のことだ」とは、黒澤の口癖だった。その反対に、昔書かれ今も読み継がれる書物、いつの世にも読まれ人々に愛される古典と呼ばれる文学には古くならない永遠の命がある、というのだ。情報と真実の違いと言い換えてもいいのかも知れない。まさに、不易流行。黒澤の映画がいつ見ても面白いのは、このことにあると改めて知らされました。最近の、映画や文学がつまらないのは、不易がなく流行ばかりだからでしょう。その時は面白いけれど、それもわずか一、二年で古びてしまう・・・。当初『虎 虎 虎』の音楽を担当することになっていたのは、武満徹。武満曰く「最初の台本に、ぼく(武満)は非常に感心したんだ。(中略)(山本五十六が)司令長官として就任してきて、軍艦に乗り移るシーンがあるんだけれど(中略)ほとんど音のことだけがきちんと書いてあるだけなんだよ。舟が艦に接する音とか、縄がぶつかる音とかね。それに【怒涛を超えて】Over the Waveの演奏とかの扱い、そういう音の扱いがすごく上手いんだな。(『黒澤明ドキュメント』)これから軍で起きること、その緊張感の中でワルツの【怒涛を越えて】の使い方こそ、黒澤お得意の、『対位法』という映画の手法に、現代音楽の大家も舌を巻いたのだ。黒澤の音楽の使い方の素晴らしさは『天国と地獄』や『野良犬』などでも実感できる。さて、黒澤明の『羅生門』で助監督だった、加藤泰がいる。その加藤泰は『トラ・トラ・トラ!』が京都東映撮影所で撮影中、あの『緋牡丹博徒 花札勝負』(96年2月1日封切り)を撮影していたという。これも、因縁である。日にちが跨ぎましたが、続きを書きました。
2007.07.14
コメント(0)
-
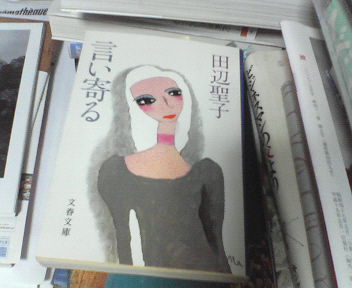
『言い寄る(田辺聖子)』文春文庫
愛してないのに気があう剛。初めての悦楽を教える大人の男、水野。恋、仕事。欲しいものは手にいれた、31歳の乃里子。でも、唯一心から愛した五郎にだけは、どうしても、言い寄れない。女たちに読み継がれ男たちを震撼(?)させた快作、復刊!と、講談社のWebにあります。それに惹かれて読みました。傑作です。古い言葉もふんだんに出てきて(書かれた当時は当たり前かも)、それも興味深いものがあります。一流ホテルへジーパンとTシャツとゴム草履で入って木戸を突かれると、大声をあげてさわぐというような粗野な野蛮人で、・・・木戸を突かれる=興行場で、(無料で、または無断で入ろうとして)入場を拒まれる。「帰るつもり?」「食べ立ちで悪いけど}「僕は帰りたくないなあ・・・」「はじめて来て、はじめての家で泊まるのんいや」この会話は、乃里子が剛の別荘に来た時のもの。タネを明かすと剛「帰るつもり?」乃「食べ立ちで悪いけど}剛「僕は帰りたくないなあ・・・」乃「はじめて来て、はじめての家で泊まるのんいや」です。食べ立ち=広辞苑にはありませんが、食べるだけご馳走してもらって、帰るということでしょうね。博打で言えば勝ち逃げかな。世の中には二種類の人間がある。言い寄れる人と、言い寄れない人である。私にとって五郎は、「言い寄れない」人であった。本当に言い寄れるのは、あんまり愛していない人間の場合である。男の仕事というのは、結局、あとで金を払う、人生すべてこのことに尽きているように思われるのだ。隠しから手帳を出して・・・。隠し=ポケット、のことも知りました。再発売の新刊は講談社。文庫は文春文庫です。自分は、文春文庫をBook Offで購入。言い寄る田辺聖子カバー:灘本唯人文春文庫週刊大衆 1973年(昭和48年)7月15日号~12月27日号1978年8月25日 第1刷1988年7月1日 第22刷
2007.07.13
コメント(2)
-

雨が続きます。
梅雨空で雨が続きます。夕方、少しだけ雲が切れました。泥江町の交差点からです。JRタワーズです。どちらも、夕焼けのかすかな赤みと空の青さが微妙です。
2007.07.11
コメント(2)
-
『ワシントンのうた』続き。
承前『ワシントンのうた』から、少し引用を・・・。外語英語部在学中の大きな出来ごとといえば、生涯の文学の師となる詩人の伊東静雄先生と出合って師事することになったことだろう。とくに、引用することはないが、「師事」という言葉に引っ掛かった。「師事」とは、師としてつかえ、教えを受けること、と広辞苑にある。仕えること、教えを受けることが師事。しかし、今、師事と言うことが余りないように思う。弟子と言う言葉もなくなりつつあるのだろうか。ビジネスの世界でも師事はあるのだが、と思う。最後の章に、長女の話=金時のお夏、やら「大浦みずき」のことやらが書いてあり、これまでの、夫婦二人のシリーズに戻ったような錯覚を起こさせる。しかし、この『ワシントンのうた』もとくに事件らしい事件はないが、面白い。引き込まれるのは、何故か?私は、好きである。
2007.07.10
コメント(0)
-
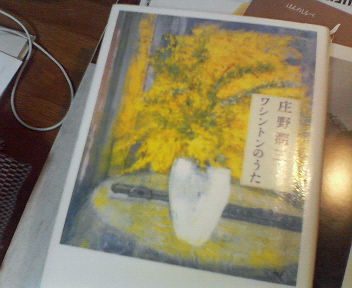
『ワシントンのうた(庄野潤三)』文藝春秋
久し振りの庄野潤三です。昨年2006年1月から12月まで、「文學界」に連載さたものです。ここ何年か、庄野潤三は1年単位で、文芸雑誌に連載をし、それを単行本にしています。これも、その一冊で、最新作です。冒頭を引用する。自伝風のものを書いてみたい。もっとも、私はこれまでその折々の自分の生活を素材とした作品をずっと書いてきた作家だから、いってみればなしくずしに自伝を書いてきたようなもので、特にこの十年はそうであった。子供がみな結婚して、「山の上」の家に二人きり残された夫婦がいったいどんなことをよろこび、どんなことを楽しみに暮らして来たかを書き続けたから、いつも「自伝」を書いて来たようなものだ。『貝がらと海の音』に始まり『けい子ちゃんのゆかた』まで続く十年がそうである。この、十年の自伝風のもの、十冊あるうち少しでも読んでいると、この『ワシントンのうた』が、これら十冊(実は十一冊目『星に願いを』がある)と、同じ線上にあると分かる。読み始めは、何となく退屈だが、読み進めるに従って興味深く面白くなるのが、このシリーズである。特に『ワシントンのうた』は、作家になる頃の話なので、師事した伊東静雄や井伏鱒二、同僚の安岡章太郎、吉行淳之介など作家が出てくるところが面白い。続きは、後日・・・。ワシントンのうた庄野潤三文藝春秋2007年4月25日 第一刷発行
2007.07.09
コメント(4)
-
車の中でCDを聞く
車の中でCDを聞くことが習慣になっています。とくに一人で出かける(といっても用事で出るのでせいぜいが30分くらい)時に、その時の気分でCDを選びます。そして、ここのところ聞いているのが、ベートーベンのピアノソナタです。演奏はヴィルムヘルム・バックハウス、曲は第9番から第12番の4曲入ったものです。今日も郵便局への用事や、久々の墓参りの途上に聞きました。耳を傾けるのではなく、何となく聞くということでですが。それが、中々の贅沢だと思います。その昔、CDは勿論カセットテープすら車で聞けない時代は、せいぜいがラジオです。ラジオでは聞きたいものそのものを聞くことは出来ません。そのことを思うと、いかにも贅沢です。梅雨の鬱陶しい日に綺麗なピアノの音を聞くことが出来ました。
2007.07.07
コメント(2)
-

『臍の緒は妙薬(河野多恵子)』新潮社
『臍の緒は妙薬』は河野多恵子の最新短編集。最新と言っても、「月光の曲(2004/1)」「星辰(2004/6)」「魔(2006/10)」「臍の緒は妙薬(2007/1)」、すべてが新潮に発表されたもの。今から3年前のものから今年1月のものまで収録されている。「月光の曲」は、太平洋戦争が始まる前の、尋常小学校の物語。タイトルの『月光の曲』はベートーベンのソナタのこと。「星辰(2004/6)」は、よく当たると言う占い師に、占いをたのむ女の話。これも一筋縄では行かない女である。奇妙な話。「魔(2006/10)」は、少々気味が悪い。この気味悪さが河野多恵子の面白さ。河野多恵子と比ぶれば、小川洋子の気味悪さ、奇妙さはさっぱりしている。「臍の緒は妙薬(2007/1)」は、自分の臍の緒の包みに穴が開いている風で、子供の頃患った肺炎のとき、自分は臍の緒を薬として2度呑んだのではないか?だから、赤ん坊の時の肺炎も治ったと思う。いろんな人に臍の緒を見せてくれといったりする主人公である。これにしても、気味が悪いといえば気味が悪い。1926年生まれの河野多恵子は、今年芥川賞の選考委員を辞めた。そんなことも話題になる人だ。『秘事』など面白く読んだ。臍の緒は妙薬河野多恵子新潮社2007年4月30日発行本来これは、函に入った本です。函のデザインはいいです。図書館から借りたので、中しかありません。
2007.07.05
コメント(1)
-
『プレステージ(クリストファー・ノーラン)』
『プレステージ(クリストファー・ノーラン)』7月1日、ファーストデーで見ました。日曜日と1日が重なることは稀ですが、今日はそんな日でした。だから劇場は混雑していました。さて、『プレステージ』は、そこで行われる奇術と同時に映画が観客に仕掛けるトリック(伏線)が張り巡らされており、それを見逃すと、分からないということになる。正直、自分も分からない所がある。トリックの映像、舞台や当時の風俗など見所は沢山あるが、地味な映画であることは免れない。その地味さ加減を評価するかしないかも、別れる所だ。いかにも大時代的な作り方。私はこういうのは好きだ。わからない所を埋めるためにも、もう一度見なければ・・・、だが時間と金が許さない。もう一度はDVDで、それも吹き替えで見たいと思っている。
2007.07.01
コメント(2)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-
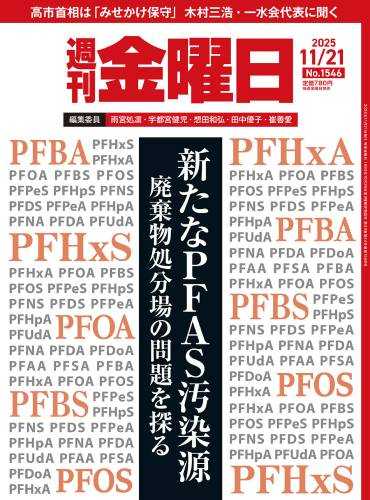
- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…
- 劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとず…
- (2025-11-21 13:22:46)
-
-
-

- おすすめアイドル
- 乃木坂46「熱狂の捌け口」スタジオラ…
- (2025-10-25 17:37:46)
-
-
-

- ドラマ大好き
- 希代の贋作師「ベルトラッキ」とは @…
- (2025-11-24 11:37:30)
-







