2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年09月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
DVDで『オアシス(イ・チャンドン)』
DVDで『オアシス(イ・チャンドン)』を見ました。ひとこと、凄いです。衝撃的です。こういう世界を韓国映画はまだ持っている。この純愛は、背筋が寒くなるほどの、愛です。最近では、『悪い男(キム・グィドク)』を見たとき以来の衝撃です。主演の2人がよい。男がソル・ギョング、女がムン・ソリ。脳性麻痺のムン・ソリの演技は、どういう風に学んだのだろう。実際の脳性麻痺の人とも思える迫真の演技。そして、その演技から、普通の状態に戻る時の、空想での演技への移行の自然さも驚く。白いはとが、部屋の中を飛び回る、幻想的なシーン。光が蝶に変化するシーンなども、目を瞠る。もし、レンタルDVDに、この『オアシス』があれば、是非見て下さい。まだまだ、侮れない韓国映画。
2007.09.30
コメント(2)
-

『陰日向に咲く(劇団ひとり)』
所謂、お笑いの一人。劇団一人の処女作。おぬし、中々できるな、である。『陰日向に咲く(劇団ひとり)』は連作短編集である。「道草」「拝啓、僕のアイドル様」「ピンボケな私」「Overrun」「鳴き砂を歩く犬」の5編からなる。それらが、連環的に繋がっていく。その関連を読みながら、おやおやっと思っているとこの作品に取り込まれている自分に気が付く。そのように、仕組まれた物語の群れである。つながりと言うのが、途中で分かると、どこにそのつながりがあるのか、何処でどういう風にそのつながりが出てくるのかを、探りながら読んでいくことになる。それも、多分計算されて書かれていると思わざるを得ない。そのように、巧みに作られている。最後まで読んで、最初の「道草」に帰ってきて、もう一度「道草」を読んでしまう。「道草」のホームレスが、「拝啓、僕のアイドル様」のボクが、「ピンボケな私」の彼女が、「Overrun」の自己破産者が、そして、「鳴き砂を歩く犬」は、あの巨人の長嶋が新人の時代に一気に遡り、現代に戻る様も見事だ。途中、何度も筒井康隆の初期の短編を思い起こさせるもの(「拝啓、僕のアイドル様」「ピンボケな私」)もあった。ただ、物語の内容は今風で、普通だと思った。陰日向に咲く劇団ひとり2006年1月25日 第1刷発行幻冬舎
2007.09.29
コメント(4)
-

『千年の祈り(イーユン・リー/篠森ゆりこ訳』
著者のイーユン・リーは名前からも分かるように中国の人。アメリカに住み、この『千年の祈り』は英語で書かれた。訳者のあとがきに、なぜ彼女は中国語で書かずに英語で書くのだろうか。「中国語で書くときは自己検閲して」しまい「書けなかった」、だから英語という「新たに使える言語が見つかり、幸運だと思う」とリーは語っている。「自己検閲」とはどういう意味だろう。政治的な意見をはっきり言えない環境、古い価値観にしばられた共同体、そうした二重三重の抑圧を受けているうちに、リーは自分の発言を「自己検閲」するようになってしまったようだ。と、ある。そのことが、以下の文章にストレートに表れている・・・、「英語で話すと話しやすいの。わたし、中国語だとうまく話せないのよ」(「千年の祈り」)「ちゅうごくで、『修百世可同舟』といいます」誰かと同じ舟で川をわたるためには、三百年祈らなくてはならない。〈たがいが会って話すには―――長い年月の深い祈りが必ずあったんです。どんな関係にも理由がある、それがことわざの意味です。愛する人と枕をともにするには、そうしたいと祈って三千年かかる。父と娘なら、おそらく千年でしょう。人間は偶然に父と娘になるんじゃない。〉(「千年の祈り」)「千年の祈り」は中国をでてアメリカに居る娘の所に来た父親とその娘の物語。娘はアメリカで結婚し離婚した。娘を心配して父親はアメリカに来る。だが、娘は余り話をしない。だが、あるとき男友達の電話では饒舌だ。それを、父親が指摘した時の娘のことばが、初めの抜書き。後のは、父親がいつも公園で会う、イランの女性。2人は77歳と75歳。そのイランの女性に、中国語で話したこと。この2人は偶然公園で会い、初めのうちは片言の英語で話をしているが、そのうち彼女はペルシャ語で彼は中国語で話す。言葉は通じていないが、気持ちは通じるのだ。『千年の祈り』は、「あまりもの」から、「千年の祈り」まで、全10編の短編集。新潮社のクレスト・ブックスの一冊。このシリーズでは『停電の夜に(ジュンパ・ラヒリ)』が、忘れられない。千年の祈りイーユン・リー篠森ゆりこ 訳新潮社 2007年7月30日発行
2007.09.28
コメント(4)
-

『陽炎の辻~居眠り磐音 江戸双紙~』
NHK連続時代劇、主演山本耕史を見た。そこに出てくる一人の男の名前が四郎兵衛。吉原の会所の主である。その名前を、今読んでいる『初花~吉原裏同心〈五)~』のなかのもあるので、ピンときた。やはり、作者が同じであった。佐伯泰英(さえきやすひで)、今を時めくベストセラー作家である。この人の得意分野が吉原なのだと、想像する。今までに読んできた本や見てきた映画、TVにはこれ程までに、吉原のディテールを書き込んでいる例を知らない。だが、小生には、この人が面白いとは思えない。普通のレベルの時代小説だ。これまでに面白いと思った時代小説作家は、初期の司馬遼太郎、隆慶一郎と藤沢周平くらいで、最近の時代小説作家に面白いものは不勉強ながら見つからない。それを、少し期待してこの『初花~吉原裏同心〈五)~』の短編を2編ほど読んだ。だが、平凡と言うのが感想。初花~吉原裏同心〈五)~佐伯泰英2005年1月20日 初版1刷発行光文社文庫
2007.09.27
コメント(0)
-
『HERO』と『めがね』
『HERO』と『めがね』を見ました。まずは、『HERO』連続TVドラマであったことを、不覚にも先日まで知らなかった。TV好きを任ずる自分としては、いかにも迂闊であった。そして、昨日(2007/9/23)『HERO』のTV番組を見て、本日、映画『HERO』を見た。亀山千広プロデュース。言うまでもなく、『踊る大走査線』の検事版。昨日のTVを序章とすれば、映画は本編。今回の事件も、最後まで諦めない男、久利生公平は、勝利する。その結果、大政治家は逮捕。物語の骨組みは、何処までも、『踊る大走査線』と同じ。東京地検特捜部と城西支部が、警視庁と湾岸署との関係に匹敵する構図。それが、亀山節と、言ってしまえばそれまでだが、この映画『HERO』は、渋みや苦味に欠け、甘ったるく、歯ごたえもない。木村拓哉も松たか子もお気に入りの大塚寧々も松本幸四郎も好演だ。松本幸四郎は「王様のレストラン」からの常連だからか、先日のTV版『生きる』より生き生きとしている。公平の粘り強さが事件の真相を見極めるが、物語は見る前からどう進むかは分かる。だから一つはこの映画は、TVで培われた役者の連係プレーで見せるものだと思うが、代議士の森田一義は、いかにも不似合いである。鈴木雅之の『世にも奇妙な物語』が縁なのか?こちらの方は失敗だ。彼では、政治家としては小物にしか見えない。むしろ石橋蓮司の方が、大物にに見える。この役をもし選ぶことが出来るなら。民主党の小沢党首か自民党の青木参議院幹事長、森喜郎元首相、くらいである。そうなったらこの映画はもっともっと、力を持ったであろう。『めがね』は、近いうちに。これは『かもめ食堂』が序章なら、本編といえる傑作。必見である。
2007.09.24
コメント(0)
-
『昭和残侠伝 血染の唐獅子(マキノ雅広)』
DVDを借りて、『昭和残侠伝 血染の唐獅子(マキノ雅広)』を見ました。久々に高倉健、池部良コンビの殴りこみシーンなど懐かしく思いました。見ていて、変なのですが、殴りこみのところで、健さんは匕首を持って出て行くのです。健さんは、匕首ではなくいつも日本刀なのです。(鶴田浩二は匕首)そんな所が気になってしまい・・・。予告編も同時に見ることが出来ました。予告編は、本編とは違うことが今回改めて確認できました。予告編は、普通、その映画の助監督が作ります。この時は寺西国光と言う人ですが、よくは知りません。本編とは違うという所を、一つ。健さんの刺青が、本編と予告編では全く違いました。といった具合。これの、見所、2つ。1、火消し・鳶職を扱っている所。だから、この人たちはヤクザではなく堅気。義理や人情や筋を通すことは人として同じ。2、藤純子と高倉健の絡みが、美しい。ちょっとくどいと思うが、綺麗だ。殴りこみの後、初めて唐獅子を見せるところは、いかにもマキノ演出、上手いと思った。久々に、やくざ映画を堪能しました。
2007.09.23
コメント(2)
-
『長江哀歌(ちょうこうエレジー)ジャ・ジャンクー』
2006年ベネチア国際映画祭金獅子賞グランプリ獲得。『長江哀歌(ちょうこうエレジー)ジャ・ジャンクー』チラシには、大河・長江の景勝の地、山峡。そのほとり、二千年の歴史を持ちながら、ダム建設によって、伝統や文化も、記憶や時間も水没していく運命にある古都を舞台に綴られる2人の男女の物語。(後略)と、ある。てっきり誤解をした。この2人のロマンスもある話かと見ていた。全くそうではなかった。だから、この映画の素晴らしさはそこに出てくる人、すべての人へのまなざしで成り立っている。確かに、分かれた人に会いに来た2人が中心にはなっているが、それ以上に、画面に現れるすべての人、現象、風景が見るものをして、感動へ誘う。カラーを抑えた撮影〈現像)も、この静けさをより伝えている。中国は、万博とオリンピックで沸きかえっているのかも知れないが、それらとはへだったった所は、いかにあるのかも、その一部が伝わってくる。ジャ・ジャンクーは、それにじっくりと視線を合わせ、見るものに訴求してくる。あまりにも、時間の流れが緩やかである、それが退屈ではないのは、長江の流れもすべてをゆったりと流しているからかもしれない。マスター・ピースである。
2007.09.22
コメント(0)
-
沖縄行き
一昨日(9/15)、長男の所に子どもが生まれました。お嫁さんの実家が沖縄なので、沖縄の病院で生まれました。だから、急遽、家人と一緒に沖縄に、16日出発。そして、とんぼがえり。今、沖縄から帰ってきました。初めての孫です。
2007.09.17
コメント(10)
-
賞味期限のこと
いつからだろう、食品の賞味期限が取りざたされるようになったのは?そして、その日にちが、食品などに表示されるようになったのは?そのことの、功罪を考えてみたい。1、だから、偽装が行われる。2、まだまだ、充分食べられるのに、破棄される。もったいないこと、しきり。3、腐ったものを食べたことのない人間が出てくる。特に、そういう子どもが・・・。ということは?もし、賞味期限が間違って表示されていたり、偽装されていたら・・・。腐ったものを、腐っているとは知らずに食べる。そういう、子ども達が大きくなる。これは、怖ろしい。前回書いた、安藤忠雄氏設計の保育園のことも、同じ根っこだ。
2007.09.13
コメント(0)
-
安藤忠雄の保育園
9/11の夕刊に『世界の安藤に親「ダメ出し」』の見出し。設計の保育園改修。東京・調布とあった。半年前に完成した、安藤忠雄氏の設計による、調布市立仙川保育園が改修することになったという。理由は、安藤氏の造形に特徴的な、打ちっ放しのコンクリート壁などに対し、保護者から園児のけがを危惧する声が相次いだためと言う。記事によると、今までに、怪我をした園児はいないようだ。これを、読んで驚いている。このことは、この園を建てているとき分かっていたはずだ。怪我をするかしないかは、子どもの問題で、いくら木造の建物でも、壁でも五十歩百歩ではないか。コンクリートの打ちっ放しだから、子ども達は余計に気をつけるかもしれない。これが、知恵を養うことではないのか。子どもの知恵の成長を親が邪魔をしてしまったことにならないか?こういう、過保護な環境は子ども達にとって意味があるのか?疑問は次から次へと出てくる。岐阜県養老町に養老天命反転地という公園があり、そこは、現代美術家荒川修作と、パートナーで詩人のマドリン・ギンズのプロジェクトを実現したテーマパークで、。HPに『園内はすべて斜面で構成されていますので、ゴム底靴など身軽な服装が適しています。』とある。一度訪れたことがあるが、ややもするとうっかり転びそうになる。時々転ぶ人がいて、救急車が呼ばれるらしい。自分が行ったときも救急車のサイレンを聞いた。しかし、ここが危険だから改修し様と言う話は一切ない。当然。ああ、また子どもの情操教育の場が一つ失われた・・・。
2007.09.11
コメント(6)
-
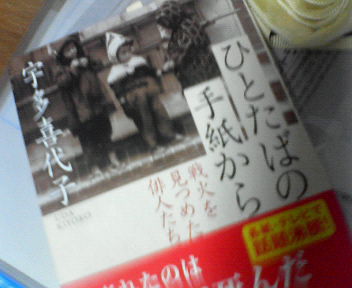
『ひとたばの手紙から―戦火を見つめた俳人たち―(宇多喜代子)』
『ひとたばの手紙から―戦火を見つめた俳人たち―(宇多喜代子)』は今から12年前に発行されたものの、角川文庫版です。「俳句は時代の影響を受けることの最も少ない文学だ」と、虚子の言葉がある。だが、戦争は否が応でも、俳人たちを戦争に行かせ、そして、戦争の句は生まれた。その一部を垣間見せてくれるのが、この本である。勇気こそ地の塩なれや梅真白 草田男この句は、戦争俳句として、本書に紹介されている。私の好きな句である。この勇気とは、今でも十分に通用する勇気だと思う。ひとたばの手紙から―戦火を見つめた俳人たち―宇多喜代子角川文庫平成18年11月25日初版発行平成19年2月10日三版発行
2007.09.10
コメント(0)
-

『生きる』TV版
TVの『生きる』を見ました。癌に侵された男が頑張るというだけの物語だと思っていた(もう40年以上前に映画を見たまま)。しかし、この物語は、人間を様々な角度から描いていると、今回知らされた。名作と言われる所以である。通夜のシーンがそのすべてを語っている。そして、人はそうはたやすく変わるものではないと言うところまで、破綻がない。これは、黒澤明、橋本忍、小國英雄のシナリオの素晴らしさだろう。TVはそのシナリオによって、なんとか見るに耐えるものになっていた。夕方、愛地球博記念公園に行きました。万博以来初めてです。公園から見た西の空です。
2007.09.09
コメント(0)
-
『天国と地獄』TV版
テレビ版『天国と地獄』見ました。ついつい最後まで見ましたが、映画を見直そうかと、思っています。明日は、『生きる』です。
2007.09.08
コメント(2)
-
再び『タタド〈小池昌代)』です。
『タタド〈小池昌代)』50代の男女4人の物語。二人は夫婦。夫はイワモト、妻スズコ、夫の仕事仲間タマヨ、妻の元の仕事仲間オカダ。イワモトの海辺の家に4人が集う。――なんの音。タマヨが聞いた。――夏みかんかな。イワモトが庭を見ないで言った。(庭に)大きな夏みかんの木があった、猿の頭ほどの実が五十も六十も、数えきれないほどぎっしりついている。 すっぱいものの好きなイワモトが、あるときもぎとって食してみたところ、それは都心のスーパーで安売りしているような水気の少ない貧弱なやつでなく、果汁のしたたるみごとな果実だった。ただ、すっぱい。ほんとうにすっぱい。 スズコはこりて、もう食べない。しかし、イワモトは狂ったように食べる。 さて、わが家内の実家の庭にもこれに似たみかんの木がある。夏みかんではない。採れる時期は、冬だからだ。すっぱいということでは、かなりすっぱい。初めのうちは誰もすっぱくて食べなかった。その実でママレードを作った。それが美味であった。だから、毎年ママレードは作られる。みかんは大きなバケツに3杯くらいは採れる。ママレードも大きな壜〈インスタント珈琲の壜〉に詰めたりして、遠方にいる子どもや親類や知り合いに配られる。ある時から、すっぱいとは言うものの、その果実の美味しさは他になく、実を食べることにした。確かにすっぱいが慣れてくれば、そのすっぱさが旨さに変わる。だから、今では直接食べる分と、ママレードになる分が半々になった。そういう、みかんの木が近くの家内の実家にある。それは、贅沢なことだと思う。さて、『タタド』である。風が出てきて、客は泊まることになる。一夜が明ける。その後、4人の決壊が始まる。その時の、音楽がI think it’s gonna rain today,ノルウェイの歌手、シゼル・アンドレセン。水気を含んだ重い歌声が、女たちの暗い子宮を満たすようにひろがる。タマヨがすっと立ち上がり、リビングのまんなかまでいくと、そのまま音楽にあわせて踊りだした。腕をだらりとたらし、脱力している。オカダが夢遊病者のように立ち上がって、タマヨのそばへ寄っていった。ふたりは海藻のように、寄り添って踊っていたが、やがて、ごく自然なかたちで身体を密着させた。スズコも立ち上がって二人のそばへゆく。〈中略〉やがてイワモトも立ち上がって、三人のそばへ寄り添った。〈中略〉何かが決壊したとスズコは思う。それで、『タタド』は終わる。寡聞にして、シゼル・アンドレセンを知らなかった。北欧のJAZZは昔から、ある地位を築いており、アート・ファマーには『スウェーデンに愛をこめて』がある。10年くらい前には、SWEET JAZZ TRIOがある。その北欧のJAZZと、決壊の関係を知りたいと思う。そのためには、シゼル・アンドレセンを聞くことなのか?
2007.09.07
コメント(0)
-
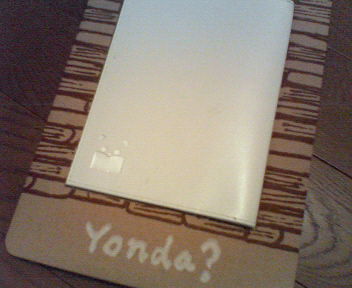
【Yonda?CLUB】
新潮文庫の【Yonda?CLUB】で、ブックカバーを戴きました。20枚集めたらもらえます。
2007.09.06
コメント(2)
-

『黒いユーモア選集 上・下(アンドレ・ブルトン)』国土社
実家の本棚に『黒いユーモア選集 上・下(アンドレ・ブルトン)』があった。勿論、自分がカって読んだ本なので、見付けたと言うのではなく久々に手に取ったということだ。こんな装丁。上は、ブルトンの「避雷針」に続いて、ジョナサン・スイフトに始まり、アルフォンス・アルレーまで、21人・下は、ジャン=ピエール・ブリッセから、ジャン=ピエール・デュプレーまでの24人。錚々たる顔ぶれである。これは、セリ・シュルレアリスムという選書の第1巻に当たるようだ。編集委員=山中散生、窪田般彌、小海永二とある。奥付を見ると、上巻は、1968年10月20日 初版発行定価1200円続いて下巻は1969年1月20日 初版発行定価1200円とあり、今から40年近く前の発行だ。こんな本を、10代で買って読んでいた自分が信じられない。あまりにも、生意気すぎる。嫌な、子どもだったと、思う。
2007.09.02
コメント(2)
-
『遠くの空に消えた〈行定勳)』
今日は、1日。ファーストデー割引で、1,000円。『遠くの空に消えた〈行定勳)』を見てきました。朝の10時50分の回。子供向けの映画と言う認識なのだろう、子供連れが多かった。夏休み最後ということも。結論は、子供たちの友情映画。この手の映画は色々あるので、新鮮味はない。この前の『バッテリー〈滝田洋二郎)』も、そうだ。『バッテリー』を、思い出し、地元唯一の酒場に、日活無国籍アクションを思い出し、女の子のポーズに『天空の城ラピュタ』を思い出し、隕石の動きに『太陽に灼かれて(ニキータ・ミハルコフ)』を思い出した。様々な映画を見てきた行定監督の思いが詰め込まれたのだろう。とはいえ、出来は普通。65点。
2007.09.01
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-
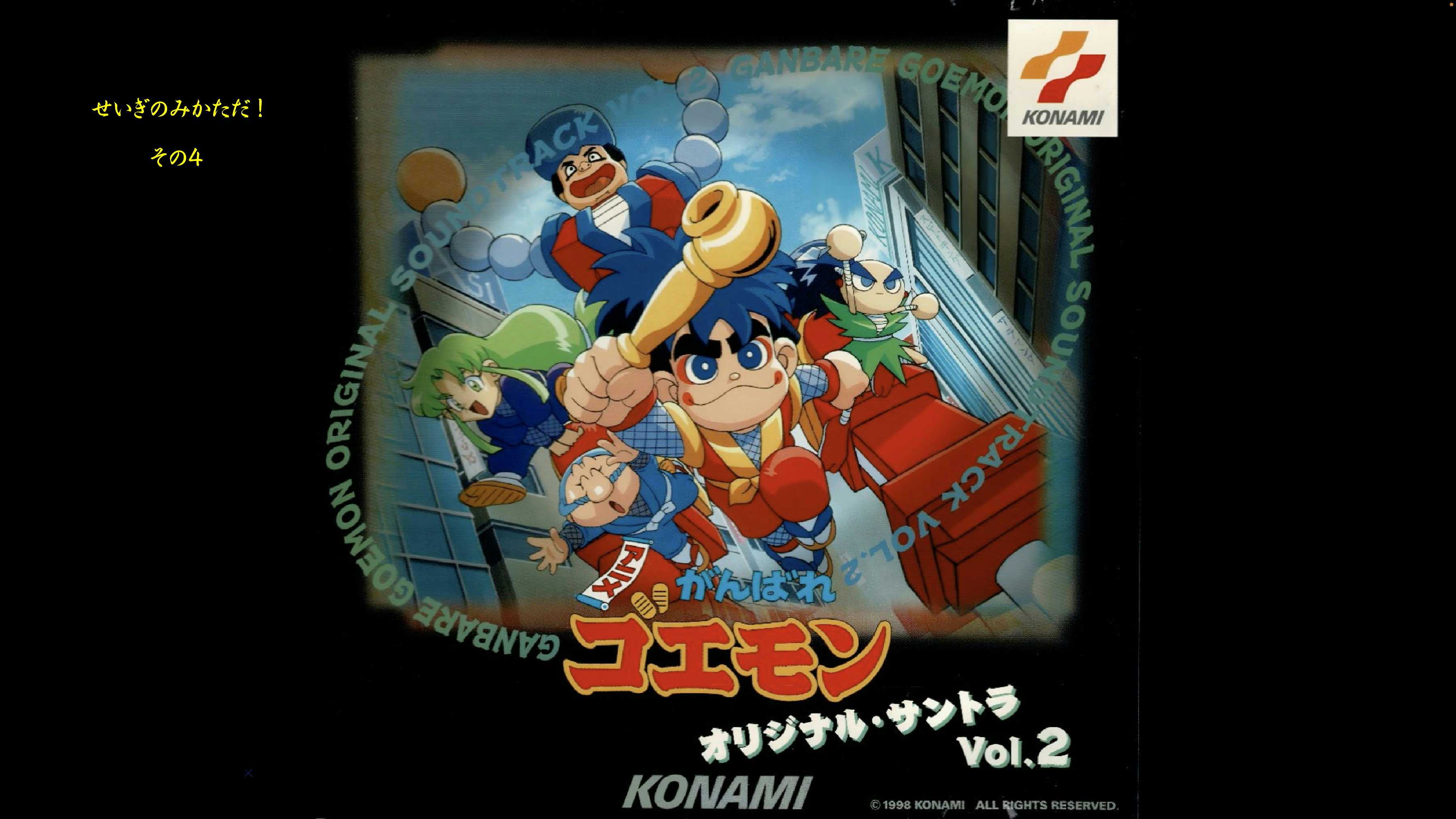
- アニメあれこれ
- お知らせ(今日3):YouTubeに 【ア…
- (2025-11-25 21:16:58)
-
-
-

- 気になるテレビ番組
- 2025.11.22NHK新プロジェクトX:美ら…
- (2025-11-25 01:51:20)
-
-
-

- ドラマ大好き
- 終幕のロンド 第3話を観た 基本路…
- (2025-11-25 21:33:12)
-







