2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年05月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
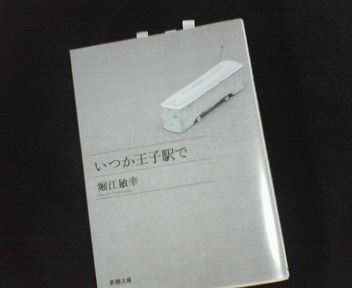
『いつか王子駅で(堀江敏幸)』新潮文庫
堀江敏幸は、この『いつか王子駅で』が2冊目。初めは『雪沼とその周辺』でした。『いつか王子駅で』は新潮文庫で、出たから買ったと、動機は曖昧。昨年の9月、札幌にいる時に、札幌のグランドホテル前の「なにわ書房」が、閉店することを知り、記念に買う本としても、選んだもの。そして、ようやく本日読み終えたと言う次第。それほど期待したわけではないが、面白かった。それで、堀江敏幸はもっと、読みたい作家の一人になった。いまではすっかりさまがわりしてしまった品川駅港南口の、(中略)さらにしばらく歩くと、こじんまりした水産関係の教育施設がある。(中略)構内に鯨の骨格模型が飾られ(後略)この、教育機関は、東京海洋大学のことで、昨年、ここである試験を受けた所で、何となく懐かしく読んだ部分。それからさらに三十分ほどしてできあがった咲ちゃんの「謹製」スープは、あれだけ煮込んだのにきれいに澄んでいて、薄味のバターライスとあわせると口中でほんのりそのバターが溶け出す、繊細でしっかりした味だった。このフレーズを読んで大江健三郎の文体に近いものを感じた。大江より分かり易いが、長いフレーズを最後まで読まないと判明しない形容の仕方が似ていると思わせた。堀江も大江も仏文を専攻したことが共通点と言えば共通点だが。「変わらないでいたことが結果としてえらく前向きだったと後からわかってくるような暮らしを送るのが難しい」この一文がこの『いつか王子駅で』のテーマなのだろう。淡々と生きて尚、それが前向きである暮らし、人生、そういう風に生きられたら・・・、と思う。共感する部分である。リンクを貼ったところに書かれている、タイトルの由来が興味深い。余計なことを言えば、この曲は、ビル・エヴァンスよりもマイルス・ディヴィスなのだと、思うのだ。いつか王子駅で堀江敏幸新潮文庫平成18年9月1日発行なにわ書房のカバー赤のほか色々あった。太字は引用。
2007.05.31
コメント(0)
-
『殯の森』をTVで・・・。
第60回カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した、河瀬直美監督の『殯の森』が、NHKハイビジョンで放映された。まだ、一般に上映されておらず、その上カンヌのような国際映画祭での受賞作がTVで放映、と。こういうことは、稀である。このような地味な映画は、場合によっては上映機会が少なく、多くの人に見てもらえないことがある。それを予測して、早々にTV放映を決めたのだと思われる。その後に受賞が決まった。そういうことだろう。それらの経緯は別にして、映画を録画しながら少し見た。台詞が聞き取りにくい、最悪。TVだからか?それは、不明。しかし、こういうことは基本だと思うが・・・。海外での上映は、字幕なのだろうか?であれば、台詞が聞き取り難いことは、障害にならない。一方で、絵はとても美しい。さすがハイビジョンで見ると、綺麗だ。
2007.05.29
コメント(0)
-
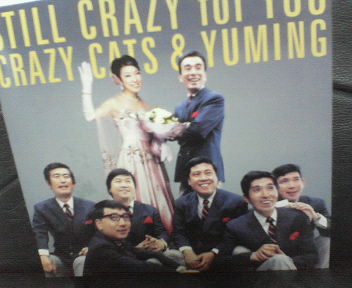
『STILL CRAZY for YOU CRAZY CATS & YUMING』
『STILL CRAZY for YOU CRAZY CATS & YUMING』を借りた。CDとDVDが入っている。DVDを見た。松任谷由美と谷啓のデュエット、「STILL CRAZY for YOU」のプロモーション・ヴィデオと録音風景が入っている。植木等のナレーションも曲中にある。録音には、桜井センリと犬塚弘が加わっており、ハナ肇、安田伸、石橋エータローの映像もある。クレイジーファンには嬉しい企画だ。因みに「STILL CRAZY for YOU」はユーミンのオリジナル。
2007.05.27
コメント(0)
-
『絶対の愛(キム・ギドク)』
話題の監督、キム・ギドクです。初めて見ました。傑作っと、簡単には言えませんし、素晴らしいとも言わせない、ある種のカリスマ性があります。2年程付き合ってきた男女の話です。飽きられたと思った、女は顔を整形します。そして、再び男の前に・・・。男は前の女に心を残しながらも、目の前の女に惹かれます。同じ女と知るのは、女本人と、我等観客です。前の女に手紙をもらい、心が揺れる男。今の女は、自分は何だったのと、男に迫ります。人間(顔や肉体)の存在と、心の存在との間で揺れ動く、やはり肉体と心を持つ人間。その矛盾をすべて抱えもっているのが、我等人間です。『絶対の愛』は、そういう人間の「何か」を描いています。もう一度、見ないと、よくは分からないのです。それと、キム・ギドクの他の作品を・・・、見てみたいと思わせただけでも、これはよい映画体験でした。
2007.05.26
コメント(0)
-

アスパラガス
札幌の知人からアスパラガスが届きました。Lサイズが1kg。早速、お昼にゆでて食べました。マイウです。美味也。
2007.05.26
コメント(2)
-
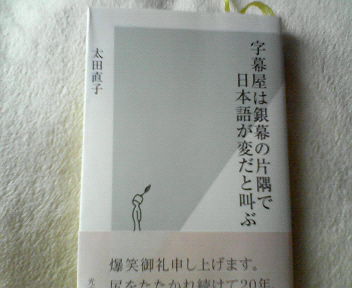
『字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ(太田直子)』光文社新書
一部では、何かと話題の本である。映画に関心のある人が手に取るだろうし、日本語に関心のある人も手に取るだろう。だが、いずれにしろややこしいタイトルだから読者を選ぶと思われる。誰も彼もが読むことはないだろう。筆者には失礼な言い方かもしれないが、誰も彼もに読んで欲しいと、思って書かれた本ではないだろう。映画を見始めて45年以上、字幕のことは余り知らなかった。以前、清水俊二氏の『映画字幕(スーパー)の作り方教えます』を読んだ程度。その時印象に残ったのは、字幕の文字数や『モロッコ』のことくらいで、この本で、1秒4文字と言ったことは初めて知る。それと、映画の元の意味を変えてしまうようなことが、字幕の世界で起きているということも初めて知った。著者は、配給会社との戦い、日本語の乱れ(?)など、縦横無尽に書いている。それでも、ある程度筆をおさえていると分かるので、現状はもっと凄まじいものがあるのだろう。一気に読める興奮の1冊。乱れ飛ぶ「お」と「さん」から、面接や商談で使われているらしい「御社は・・・」という言い方は、あまりに堅苦しく歯が浮きそうなので、一度も口にしたことがない。しかし、「御社」という言葉で先方に心から敬意を表わしているとはどうしても思えない。チラシ掲載のアクセス地図である。自社(自店舗)以外の建物はすべて「さんづけ」という爆笑チラシが、思いのほか多い。「トヨタカローラさん」「ブックオフさん」・・・・。この「御社」は、きっと面接のマニュアルにでもあるのでしょうね。最近商談しているとやたら御社、御社という若者がいる。そんなに恩赦して欲しいのかと、イライラする。チラシのさん付けも、噴飯ものだ。チラシを出している会社のレベルがそれで知れる。くさそうなものには全部ふた~禁止用語をめぐってから言葉そのものに罪はない。それぞれの言葉は、さまざまな音の組み合わせにすぎないからだ。どんな言葉も生まれたてのころは、いかなる色にも染まらず無垢な状態だったろう。差別という、きわめて厄介な手垢がべっとりついてしまうものもある。これはなかなか洗い流せない。(中略)しかたがないので「禁止用語」というラベルをついた容器に入れて、しっかりふたをする。くさくなくてもこっそりふた~禁止用語をめぐって番外編から以下は要約・・・です。1973年製作の英国映画『マダム・グルニエのパリ解放大作戦』。ただし日本未公開作品。ピーター・セラーズが七役をこなす爆笑コメディだ。舞台は、第二次世界大戦中のフランス。マダム・グルニエは高級娼館をナチス・ドイツに占領されたパリで営んでいる。ピーター・セラーズ演じる七役の中に、「プリンス・キョウト」というのがある。この映画を、衛星放送で流すことになり、翻訳字幕の依頼を受ける。このプリンス・キョウトの部分が一切カットされることになった。某放送局の英断に拍手を送ったのだが、やはりということになった。約15分のカットだった。98分が、83分になった、という話。このDVDが出ている。これが、95分である。タブーは存在する。だが、『クィーン』は、よくぞ上映してくれました。売りたい!~復活編からこれも要約。『イカとクジラ(ノア・バームバック)2005年』の公開が決まった。その前に、著者は、とても固有名詞の多い映画だが、一般にその名を知る人が少ないだろうから、固有名詞にある程度の制限をし、普通名詞で字幕を作った。その後、この『イカとクジラ』の公開が決まり、字幕の作り変えをすることになる。これは、いい話で、文学や絵画やいろいろなものの固有名詞が実際に使える字幕になったと言う話。これには、著者も拍手。字幕屋に明日はないから『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズの字幕が原作小説ファンによって激しい非難の嵐にさらされたとき、その配給会社の製作部長は映画フィルムを丸々一本捨てる覚悟で、「原作ファンが求める字幕」を打ち込んでみせたそうだ。勿論、それは字幕としては長すぎて、とても読めるものではなかったらしい。明日に向って打て!から以下、要約。字幕か吹き替えかと、いう命題。昔は字幕が優先。しかし、最近は吹き替えが増えてきた。いずれ、字幕がなくなるかも・・・、という危惧を抱きつつ、本書は終わる。故瀬戸川猛資氏は、複雑なストーリーのミステリは字幕より吹き替えがよいという説を持っていた。実際、『LAコンフィデンシャル』は、吹き替えで見て、その話の面白さがよく分かった。以来、少しは吹き替え派です。字幕屋は銀幕の片隅で日本語が変だと叫ぶ太田直子光文社新書2007年2月20日初版1刷発行
2007.05.25
コメント(1)
-
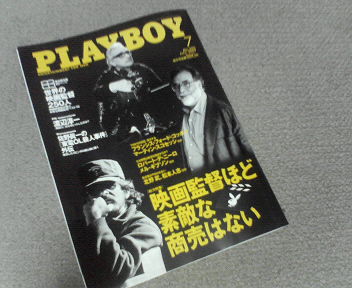
月刊「PLAYBOY」7月号の付録
月刊「PLAYBOY」7月号は映画監督の特集。買ってきました。付録が「250Film Directors of the World 世界の映画監督250人」。外国の監督は、アーサー・ペンからロン・ハワードの210人、日本の監督は、石井聰亙に始まり、若松孝二までの40人。こういう場合に必ずといっていいほど、誰某が入っていない、という議論をしたくなる。切がない。小生の好みから敢えて申し上げれば、外国人にトニー・リチャードソンが日本人に斉藤耕一が入っていない、と言いたい。しかし、日本人監督に勝新太郎が入っているのは解せない。いちゃもんは付けたくなかったが、一つだけ付けさせて戴いた。本誌付録
2007.05.24
コメント(2)
-
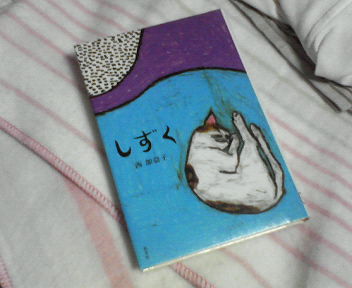
『しずく(西加奈子)』光文社
図書館で借りた本です。借りた理由は単純です。この本を本屋の平積みで見たからです。それなりの話題作なのだろうと、読んでみようと、そういう理由です。発見もありますが、大体は、そんなもんかで終わります。この、『しずく(西加奈子)』も、例外でなく、こんなもんだ、でした。純文学と中間小説(大衆小説)というジャンル分けがかつて存在しました。今は、中間小説と言うジャンルはなくなったようで、ライト・ノベルというジャンルがあるらしい。これも、そのライト・ノベルだ。ライト=軽い、ということだろう。だから、と言うわけではないが、すぐに読めてしまう。2日かからなかった。読んでるうちは面白いが、それだけだ。「映画芸術419号」で寺脇研と宮台真司が対談の中で〈寺脇:泣ける映画という考え方はなんだろう。これはこの数年の日本映画を支配している考え方ですね。宮台:日本映画大バブルが起こっている、・・・。ところが質は下がっています。観客がホメる映画のクォリティが低い。〉幾つかの理由を宮台はあげている。〈宮台:観客が「泣ける」「笑える」と一秒でコメントできる感情的フックだけを要求する「一秒コメント化」が進んだ。皆が観ているから観るという「ネタ化」が進んだ。要は観客に媚びた映画だらけになった。僕らよりも遥かに経験値や知力の劣る監督が撮る映画だらけになった。〉小説の世界も同じことが言えるのではないかと感じている。特に本屋大賞と言う、バカな賞が発足してから、それに拍車がかかったように思う。ほっといても売れる本を選ぶような賞が、本屋大賞だ。本屋はプロとして、売れていないけれど、売りたい本、読んで欲しい本を選ぶのが一つの、使命ではないか。(本屋大賞にはかくれた本を推薦する部分もあるらしいが、表には出てきていない)読者に媚びてはいけないだろう。さて、この『しずく』も、ただただ気分のよいさらっとした本だった。決して悪くはないが・・・、それだけだ。川上弘美や小川洋子もライトな部分があるが、底に流れる、気味悪さみたいな何かが、ある。では、引用します。「影」から〈海は、こっくりと濃い藍色をしている。〉川上弘美のような形容詞の使い方。この一箇所のみだが。〈あの子は、皆に嘘をつくが、自分には決して、嘘をつかないだろう。人の視線に怯えたり、人の評価に阿ることを、彼女は決してしないだろう。〉「シャワー・キャップ」から〈少しばかり悲しいことや、辛いことがあっても、それを我慢すれば「のんちゃんは、賢いね」という言葉をもらえる。それこそが自分のアイデンティティであると、思っていた。〉この本に流れるものは、自分探しだ。本当の自己のアイデンティティって、何処にあるのだろう、それは何なんだろう、というものだ。人に媚びたり、阿ねたりしている「自分って?」ということなのだろうか?むしろ、媚びるのも、阿るのも、すべてが自己であると受け入れることの方が・・・、と思う。勿論、すべてに媚びたり、阿ねたりは、論外だが・・・。宮台の言う、媚びるとは、本質で違う。映画作家が、小説家が媚びてはいけない。だが、個人は個人として、それもありだ。『しずく』は、そういう点では、読者に媚びている、というより改めて小説にしなければならないものでも無かろうに、ということだ。上手な作家だとは思うが。しずく西加奈子(カバーの絵も)光文社2007年4月25日 初版1刷発行
2007.05.22
コメント(4)
-
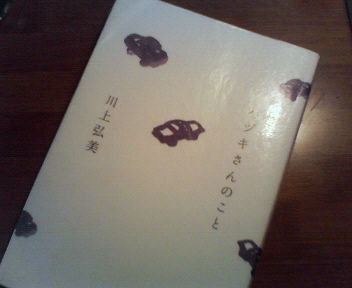
『ハヅキさんのこと(川上弘美)』講談社
この『ハヅキさんのこと』は、原稿用紙にして、10枚足らずの短編集。「琺瑯」から「水かまきり」まで、23篇。3部作の「誤解」が面白かった。他も川上弘美節で、楽しめた。ハヅキさんのこと川上弘美講談社2006年9月29日 第1刷発行
2007.05.20
コメント(0)
-

帽子の話
帽子が好きで、ほぼ毎日被っています。これからは、夏ですので主にはパナマ帽です。パナマは、エクアドル産がよいと聞きます。どこのメーカーの帽子もパナマはエクアドルのようです。パナマ帽もピンキリですが、1万円以下のものから、上は10万円を軽く超えるものまであります。先日、新しく出来た名鉄(名古屋)のメンズ館の帽子売り場で、店の人と話をしました。パナマ帽はとてもデリケートで、帽子を持つ時には気をつけなくてはいけません。正しいもち方は、つば(ひさし)を両手で持つのです。ついつい、王冠のへこんだ所を持って、被ります。でも、自分の帽子ならそれでOKですが、売り場のものは、それでは駄目です。なぜかと言えば、パナマが割れてしまいます。そうなれば商品価値が一気に下がります。とは言え、デパートの場合、四六時中見張っているわけには行かず、季節の終わり頃には、駄目になる帽子が出るとききました。この帽子の扱いは、フェルトのソフト帽も同じです。写真は今年手に入れたパナマです。何故だかバーゲンにありました。普通ではこういう普通のパナマはバーゲンセールには出ません。しかし、これは王冠の一部に割れがあります。それにひさしもスジがあり少々難ありです。割れ(ヒビ)は向って右のはし(手に取りやすい所)にあります。ひさしのスジはこの写真では見えません。もう一つは裏側です。白いリボンがありますが、一応上等の帽子にはこのように内側の汗取りの部分をリボンで止めます。そういう所も、帽子の見分け方の一つです。今年の夏はこの帽子で通勤します。
2007.05.18
コメント(6)
-
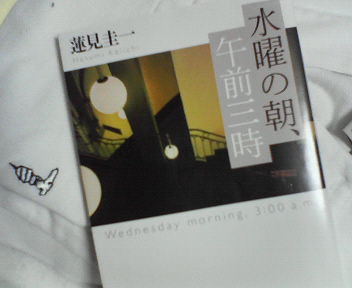
『水曜の朝、午前三時(蓮見圭一)』新潮文庫
前から少しだけ気になっていた本でした。『水曜の朝、午前三時』作者の蓮見圭一のこと、今から6年前の平成13年に単行本でこの本が出たこと、そしてベストセラーになったことも、なにもかも知らない本でした。平成17年に文庫本になり、その平積みで初めて知り、それ以来少しだけ気になっていました。Book Offで105円。それを購入、読み終えました。静かな静かな恋愛小説です。解説で池上冬樹が、作品のいたるところで思索がきらめき、箴言となって、ひとつひとつが心にしみいる。と書いています。そして、“差別する感情の底にあるのは恐怖心に他ならない。”や“私は失敗を楽しめるほどに成長することができたのです。”や“何にもまして重要なのは内心の訴えなのです。あなたは何をしたいのか。何になりたいのか。どういう人間として、どんな人生を送りたいのか。それは一時的な気の迷いなのか、それともやむにやまれぬ本能の訴えなのか。耳を澄まして、じっと自分の声を聞くことです。歩き出すのは、それからでも遅くはないのだから。”などを引用しています。この本の主な舞台は1970年の大阪万博です。当時は大学生でした。例にもれず万博には何度も行きました。殆どのことは忘れました。覚えているのは、夕方から入場料が割引になり、その時間に入り、当時は珍しかった、ジェットコースターに乗ったのを覚えています。だから、この本の万博には親しみを感じます。繰り返しますが、この本は実に静です。燃え上がるような激しい恋愛感情が書かれていますし、女同士の嫉妬心や、差別の問題など熱いテーマを内包してるにも拘らず静なのです。さて、箴言は、多くの場合ひとの心に突き刺さってきます。しかし、この本のそれは知らず知らずに通り過ぎてしまい、あとから振り返ると、そういえばあんなことが書いてあったと思い起こさせるのです。だから、自分はそれに気づかず、解説から孫引きをした次第です。大人の小説と言うとありきたりの言い方ですが、これは近年、人が死に泣き、人が死に泣きの多い小説界で、稀な収穫だと思います。水曜の朝、午前三時蓮見圭一解説:池上冬樹新潮文庫 平成17年12月1日発行 平成18年7月25日 第六刷
2007.05.15
コメント(0)
-
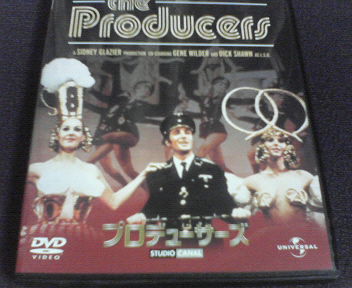
『プロデューサーズ(メル・ブルックス)1968』のDVD
2005年の『プロデューサーズ(スーザン・ストローマン)』は、このメル・ブルックスのリメイクである。某電気店のDVDコーナーで、メル・ブルックス版を見つけて購入。980円でした。2005年は映画館で見ましたが、こちらの1968年版は見ていなっかったし、DVDがあるとも知らなかったので、運良く見つかり嬉しいことでした。近いうちに、見られればと思っています。プロデューサーズthe Producersメル・ブルックス1968
2007.05.13
コメント(0)
-
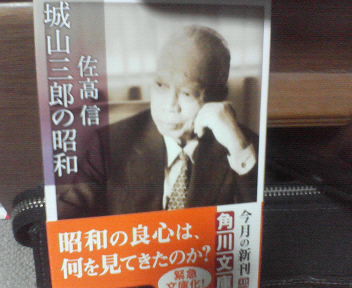
『城山三郎の昭和(佐高信)』角川文庫
所謂腰巻に「昭和の良心は、何を見てきたのか?」「追悼 城山三郎さん」「緊急文庫化」とある。書店でぱらぱらと立ち読み。目次の「三島由紀夫批判」「『仁義なき戦い』との接点」などに惹かれ購入。以下、引用です。「三島由紀夫批判」からボク(城山)が三島さんの『絹と明察』というのを批判した。『朝日ジャーナル』(1964年12月13日号)の書評で。(中略)ぼくはまちがったことを書いたつもりはなくてね。そうしたらすぐに石原(慎太郎)さんから電話がかかってきて、(三島さんが)けしからんと怒っていると伝えろ、と言われたって言うんだね。(その後)奥野健男さんから電話がかかってきて、まったく同じことを言う(笑)。ボクは普通のことを書いただけ。「生涯の師、山田雄三」から城山は、山田ゼミを専攻するが、その山田宛にゼミをやめさせてもらいたい旨の手紙を出す。クール・ヘッドは感じられるが、ウォーム・ハートに欠ける学問だと思ったからだ。それに対して、山田から返事の手紙が来る。城山にとって「いまも読み返す度に、それこそ胸の熱くなる手紙」だった。その手紙の一部、君は自由に君自身の道を選んで進んで下さい。科学のみが人間探求の唯一の途ではありません。真の科学者はこのことを十分認めているはずです。むしろそれぞれの人はそれぞれの職場における実践を通じて、もしその人が事実認識に精進するならば、人間探求をやっているはずです。それが実は私のいう現代人の心のうちにある科学的な態度なのです。お互いにどの途に進むにせよ、より忠実に人間探求をやりましょう。この山田の熱い手紙に城山は、山田ゼミでの勉強を続けることになった。城山は「どんなに詫びても詫びきれぬ思いであった」という。「原基としての父」から「運命は勇者の味方をする」キンスレイ・ウォード『ビジネスマンの父より息子への30通の手紙』に引用された言葉。そんな中山さん(日本興業銀行元会長の中山素平)の見識が光ったのが、湾岸戦争の時の次の発言だろう。「(自衛隊の)派兵はもちろんのこと、派遣も反対です。憲法改正に至っては論外です。第二次世界大戦であれだけの犠牲を払ったのですから、平和憲法は絶対に厳守すべきだ。そう自らを規定すれば、おのずから日本の役割がはっきりしてくる」「横光利一は田舎者です」“小説の神様”と言われた横光利一は、「ヨーロッパの知性とは金銭を見詰めてしまった後の知性」であるのに、「日本の知識階級の知性は利息の計算を知らぬ知性である」と喝破した。など、刺激的で、興味深い内容だ。佐高信は、城山三郎がこの戦争(第二次世界大戦)で日本が得たのは、憲法九条一つである、と言った、ことをあるテレビで紹介していたが、この本で、中山素平も同じ事を思っていたと分かる。今の、経済人がまともなら、中山素平と同じ考えを持つ人がいても良いと思うが・・・。いずれにしろ、きな臭い世の中だ。心してかからねば危ない。いつものように、太字が引用。城山三郎の昭和佐高信角川文庫平成19年4月25日 初版発行
2007.05.11
コメント(0)
-
『清左衛門残日録』 第一回「昏ルルニ未ダ遠シ」
『三屋清左衛門残日録』のTVドラマ化何度と無く再放送されたものを、改めて見る。と言っても、以前所々見た程度であるから、今回初めてのようなもの。出演は仲代達矢, 南果歩, かたせ梨乃,財津一郎ほか。勿論、原作者は藤沢周平。自分は、それ程藤沢作品を読んではいない。『蝉しぐれ』も良いには違いないが、この『三屋清左衛門残日録』が一番好きだ。放送はNHK-BS2で、これから毎週火曜日に放送される。仕事の都合で帰れぬときもあるだろうが、出来る限り見たい。
2007.05.08
コメント(0)
-

『あなたに不利な証拠として(ANYTHING YOU SAY CAN AND WILL BE USED AGAINST YOU)ローリー・リン・ドラモンド 駒月雅子訳』ハヤカワ・ミステリ
やっとのことで読了。ハヤカワ・ミステリの一冊ですが、所謂推理小説でもミステリでもないお話。落語で言えば、人情噺。それも、上等の人情噺。もちろん、普通のミステリ(推理小説も何もかも含み意味で)を、落語に喩えるつもりはありませんが、笑うために聴きに寄席に入ったら人情噺を聴かされたようなものということです。名人の落語は、落語とはいえ人間描写がきちんとしていて、よいミステリも謎解きや殺人のみの面白さ以上に人物がきちんと描かれていて、ちゃんとした小説になっているものです。さて、これは、警察の話とは聞いていましたし、タイトルも「あなたに不利な証拠として」という、いかにもミステリらしき題だし・・・。でも、大変満足した一冊です。登場人物の女性警官がきちんと、しかも等身大の人間として描かれています。それもこの小説を魅力的にしています。久々でした・・・から、こういう小説に出会うことは至福であります。あなたに不利な証拠としてANYTHING YOU SAY CAN AND WILL BE USED AGAINST YOUローリー・リン・ドラモンド 駒月雅子訳ハヤカワ・ミステリ2006年2月10日印刷2006年2月15日発行
2007.05.07
コメント(2)
-
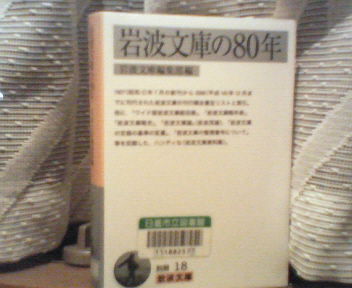
図書館で・・・、借りた本。
手許に、読んでいない本が山積しているにも拘わらず、図書館で本を借りてきます。しょうもない自分だと思います。今日も今日とて、借りてきました。でも、2冊。先回借りて読みきれなかった『あなたに不利な証拠として』と『岩波文庫の80年』。『あなたに不利な証拠として』は読み終えてから書きます。さて、この『岩波文庫の80年』は、表紙に、1927年(昭和2年)7月の創刊から2006年(平成18年)12月までに刊行された岩波文庫の刊行順全書のリストと索引。とあります。目録と索引だけで本になり、しかも1000円+税=1050円するのです。馬鹿な自分は、本当は欲しい本ですが、借りて済ますことにしまました。因みに、最初の1927年は73冊で、この本の最初に出てくるのは、「おらが春・我春集(一茶作・荻原井泉水校訂」です。最後の本は、「酒道楽(村井弦斎作・解説=黒岩比佐子)しかし、こういう本を岩波文庫のみの、特権にするのではなく、新潮文庫も角川文庫も出せばよい、と思う。そして、版元の垣根を越えた、3冊セット1000円ならば・・・。いかがであろうか?そういえば、以前岩波文庫は3冊セットの総目録を出したことがある。ピンボケで済みません岩波文庫の80年岩波文庫編集部編2007年2月16日 第1刷発行
2007.05.06
コメント(2)
-

浜松まつり
大凧で有名な浜松まつりに行きました。100以上の大きな凧が空一面にあるのは見事です。他にも用があったので、2時間ほどしか会場に居ませんでした。それが、やや残念でした。凧の糸の切りあいなど、それぞれの町の競い合いですから、そういうところがきっと面白いのだと思います。また機会があれば、じっくりと見たいものです。
2007.05.05
コメント(5)
-
『クィーン(スティーヴン・フリアーズ)』
いわずと知れた、今年度アカデミー賞主演女優賞、ヘレン・ミレンの見事な演技の話題作です。実は、ヘレン・ミレンが良いだけではなく、フィリップ殿下のジェームズ・クロムェルもトニー・ブレアのマイケル・シーンも演技賞ものです。しかし、まだ10年前の事件(出来事といったほうがよいかも知れません)。女王やブレア首相やその他すべての登場人物の殆どが生きているにも拘らず、これを映画にしてしまうというのは日本では考えられないでしょう。天皇が英国の王室ほど政治的な力はないにしても、皇室を、またそのスキャンダルがあったとして、その事件を映画にしようものなら・・・、何が起きるやら、想像するだに怖ろしいことです。と言うように、『クィーン』は、そういう風にも見られそうです。でも、そうではなく、この映画は、毅然とした作品であり、品格もあり、見事です。
2007.05.04
コメント(0)
-
『その場所に女ありて(鈴木英夫)1962(昭和37年)』
チャンネルNECOで、4月から始まった、監督鈴木英夫の特集。その中の1本。司葉子、宝田明、水野久美、森光子、大塚道子、山崎務、西村晃など。広告会社を舞台にした、営業の戦いの物語。司葉子は西銀広告、宝田明は大通広告。司葉子はコピーライターから連絡(営業のことです)になった優秀な営業。宝田明も一癖も二癖もある営業。この二人が、或る製薬会社の新製品の広告の競争をする。それが、物語の流れになっていて、女性の仕事とその周辺が鮮やかに描かれている。中でも、広告(デザイン・コピーなど)を作る過程や、製薬会社のオリエンテーション、プレゼンテーションは今の様子と大して変わらない。それほどまでに、リアルといえる。この映画の封切りの年1962年は、『椿三十郎(黒澤明)』『切腹(小林正樹)』『キューポラのある街(浦山桐郎)』『私は二歳(市川崑)』などがキネマ旬報の邦画ベスト10。その他ベスト10以外にも『忍びの者(山本薩夫』『座頭市物語(三隅研次)』『鴈の寺(川島雄三)』など、今から思うと佳作、秀作が目白押し。しかし、この『その場所に女ありて(鈴木英夫)』は、1点も入っていません。当時はそういう状況だったのでしょう。その場所に女ありて鈴木英夫東宝1962年1月28日 封切り同時上映 『サラリーマン権三と助十(青柳信雄)』
2007.05.03
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…
- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…
- (2025-04-26 15:25:48)
-
-
-
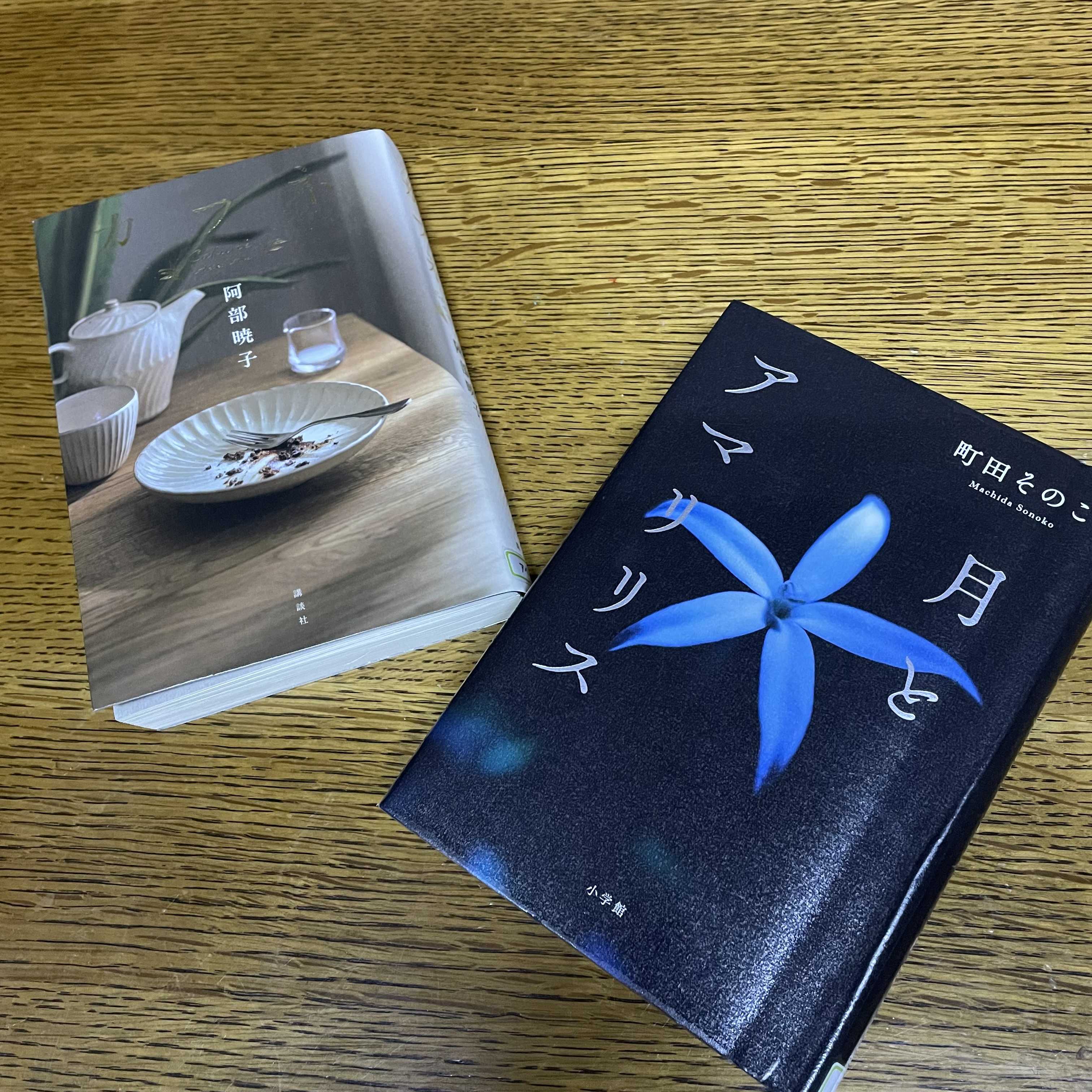
- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-
-
-

- ドラマ大好き
- 終幕のロンド 第3話を観た 基本路…
- (2025-11-25 21:33:12)
-







