2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年08月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
『TOKKO~特攻~(リサ・モリモト)』
叔父が特攻隊員の生き残りだったことを、彼の死後に知った日系アメリカ人監督リサ・モリモト。自爆テロを「カミカゼ攻撃」と呼び「TOKKO」のイメージを重ねるアメリカの風潮に違和感を抱いた監督が、特攻隊だった生存者たちに取材を重ね、彼らの偽らざる心情を映し出した迫真のドキュメンタリー。と、シネマスコーレのWEBにある。身内にカミカゼ特攻隊の生き残り(?)が居たことで、身近になったカミカゼ特攻隊を調べ始める。4人の生き残り(?)にインタヴューする。中でも、印象に残ったのは、この「神風特攻隊」を考えたのは、戦争を終わらせようと考えて行ったのだということ。こんな非道な作戦をするということは、これ以上戦争をしてはいけないことで、当時の天皇〈昭和天皇)に、戦争終結の決断をさせたかった、と。しかし、天皇はもっと頑張れと。原題は、【WINGS OF DEFEAT】である。「敗北の翼」とでも訳せばよいのか。このカミカゼ作戦で、戦争が日本側に好転するとは多くの関係者が思ってはいなかった。資源力に米国より劣る日本が勝てるわけが無い。神風なんて、とんでもない発想だと。しかし、それがヒステリックになった時の人間の行動なのも否定できない。シビリアン・コントロールがない当時にしてみればやむを得ないことだったのだ。証言者の一人はラジオで米国の放送も日本の放送も同時に聞きその差に疑問を持ったという。撃沈された艦船の数の違いなどからの疑問だ。日本のあちらこちらで、戦争に対する疑問がふつふつとわきあがっていたのだと思う。しかし、一方で日本は決して負けないと信じて疑わなかった人たちもいたのだ。それが、世の中であり、地球であり、人類だ。今の地球の危機も同じだと思う。さて、あと6ヶ月早く戦争が終わっていれば、どれほどの命が助かったか?の証言。すべてが、天皇の責任だと。これほどまでに、はっきりとした証言は、稀ではないのか?『ゆきゆきて神軍』の時の衝撃以来だ。今年は、太平洋戦争のドキュメンタリーをこれで3本見た。『蟻の兵隊(池谷薫)』『ヒロシマナガサキ(スティーヴン・オカザキ)WHITE LIGHT/BLACK RAIN』『TOKKO-特攻(リサ・モリモト)=WINGS OF DEFEAT』。うちの2本がアメリカ映画だ。これまで見ることの出来なかった実写フィルムが見られた。これも、今までになかったことだ。さて、今の日本はどこに行くのか?戦争は愚かだ。分かっていても・・・、なんていうのはもっと愚かだ。今の政府は何を考えているのか?戦争に一歩でも近づくようなことをすれば、またまた、国民は皆不幸になる。
2007.08.31
コメント(0)
-

8月最後の空
暑くて暑くて、と言う夏が去ろうとしています。夜は随分涼しくなりました。名古屋の夜空です。
2007.08.31
コメント(0)
-

『雪沼とその周辺〈堀江敏幸)』
川端康成賞・谷崎潤一郎賞・木山捷平賞を受賞した連作短編集。「スタンス・ドット」「イラクサの庭」「河岸段丘」「送り火」「レンガを積む」「ピラニア」「緩斜面」の7編。「スタンス・ドット」は、第29回川端康成賞。閉店する最後の日のボーリング場の話。そこに偶然来た若い男女と店のオーナー。最後のゲームを通じて、オーナーの思い出が色々と蘇る。「イラクサの庭」は、料理教室とレストランを経営していた女性の死と最期の言葉「コリザ」の謎。この短篇の登場人物のそれぞれが、この料理教室に通ったと、書かれてある。また、これに、大江健三郎の『燃え上がる緑の木』を思い出した。「河岸段丘」の、ちょっとした日常の感じ方の違い。そこにある、不安のようなもの・・・。年を取ることの恐さがある。「送り火」は、書道教室を営む夫婦と子供の話。その哀しさは、この連作の白眉。「レンガを積む」の、職人気質。自分にも出来たらいいなあと、思わせる。天職とはこういうことか?石川啄木に「ここちよく我に働く仕事あれそれをし遂げて死なんと思う」だったか?こんなような歌があった。「ピラニア」の、不器用な男の話。女はその不器用に惹かれて行った。「緩斜面」は、幻想的。ここにも、「イラクサの庭」の料理教室、レストランが出てくる。新潮文庫に入ったからだが、今回で、『雪沼とその周辺〈堀江敏幸)』は三度目である。何度読んでも素敵な本だ。雪沼とその周辺堀江敏幸新潮文庫平成19年8月1日発行
2007.08.30
コメント(0)
-
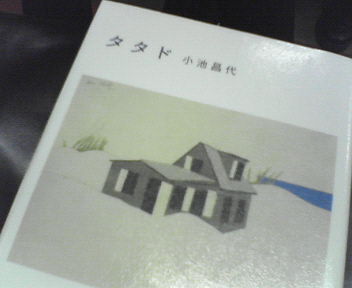
『タタド〈小池昌代)』新潮社
『タタド』です。今年の川端康成賞。「タタド」という表題の意味がわからないことに、読み終わってから気がついた。実は、川端賞受賞の言葉で作者自身が、伊豆・下田の「多々戸浜」をさす旨、種明かししてくれているらしい。(「波」2007年8月号より野崎歓)この本の広告コピーは、二十年連れ添った夫婦と、二人のそれぞれの友人。五十代の男女四人が海辺のセカンドハウスに集まってくる。海草を拾ったり、夏みかんを齧ったり、あどけないような時間の中、各々のあきらめが見え隠れする。倦怠と友情が夜どおし交差して、やがて朝がくると、四人の関係は一気に「決壊」する。である。最後の「決壊」が、正直言って引っかかる。決壊=切り崩される、と言う意味だ。この場合、四人の関係を、決壊と言うのか?むしろ新たな関係と言う見方もあるのではないかと、思う。常識的な倫理観からいうと、やはり決壊か?だが、小説家の想いは・・・?本は再読が必絶という松岡正剛氏にならい、少し間を置いて二度目を。残りの2作品『波を待って』『45文字』も、女の気持ちと男の気持ちが実に旨く描かれている。作者の小池昌代は1959年生まれだから、『タタド』の登場人物より、若い。その辺も考察すると、50代の四人の心の年は40代。タタド小池昌代2007年7月25日発行
2007.08.27
コメント(0)
-
『ブラインドサイト~小さな登山者たち~(ルーシー・ウォーカー)』
ブラインドサイト~小さな登山者たち~「チベットでは、盲目は前世の悪行が原因で悪魔に取り付かれているという言い伝えがあり、盲人の多くは差別的扱いを受けてきた。子供とて例外ではない。」と、チラシにある。そのことを受けて、盲人のドイツ人教育者サブリエ・テンバーケンは、盲人でエベレスト登頂に成功した、アメリカの登山家エリック・ヴァイエンマイヤー〈名前から推測するにドイツ人?〉の協力を得て、子供たちにエベレスト北側、標高7000メートルのクラパリを目指すことになる。その一部始終を記録したのが、『ブラインドサイト~小さな登山者たち~』である。盲人ではない自分には、目が見えない状態で、普通に歩くのさえ困難であると思えるのに、登山を、しかも7000メートルの頂を目指すのはどれほども冒険であるかは、容易に想像できる。しかし、盲人であることは、この映画を見る限りにおいて、関係が無い。と言うより、その登山は、盲人であることを言い訳に出来ないほどのものであると分かる。子供にとっては、目が不自由でなくとも、過酷な挑戦である。国の違いは文化の違いの違いでもある。途中の困難に対しての対応がそれぞれの立場で違う。それらの違いをまとめ、なおかつこの登山は、盲人というハンディを包括して、実行されている。もはや、子供たちを山へ連れて行き、頂を目指そうという大人が子供を連れて行くという図式は無くなってしまった。一人が言う「ここで帰れば、なにもしなかったことに等しい」と。成し遂げることの意味は大きい。しかし、成し遂げられなかったことから学ぶことも大いにある。六人の子供たちが、この登山で学んだことは、かけがえのないものだろう。記録映画だから、あとから編集されたものだ。にも拘らず、見ているとリアル・タイムでその場所にいる錯覚に陥る。山がとても綺麗だ。そして、挿入歌「ハッピー・トゥギャザー」が幸福な気分にさせてくれる。
2007.08.26
コメント(0)
-
シネマコリア2007
「シネマコリア2007」。名古屋では、今日(8/25)と明日、愛知芸術文化センターのアートスペースAで開催される。2日間で4本の映画が上映される。25日は『ラジオ・スター(イ・ジュンイク)』『ホリデー(ヤン・ユノ)』26日は『青燕(ユン・ジョンチャン)』『懐かしの庭(イム・サンス)』そして、26日には映画評論家の寺脇研氏のトークイベントがある。その中の、『ラジオ・スター』を見た。物語は、MBS(放送局)の大賞を取ったほどの、一世を風靡したロックスターが落ちぶれて、地方放送局のDJをすることで、立ち直るもの。特別に珍しい話ではない。ウェル・メイドな作品。だが、この映画で泣けた、笑えた、感動したというものはとは縁遠い無い。確かに、歌手とマネジャーの関係にはほろりとさせられるし、笑わせられるし、感動もするが、今の日本映画にある、人の生き死ににおいての泣ける、感動させられるは一切無い。映画はそもそも、この『ラジオ・スター』でもそうだが、人にある種の感動を与えることは普通だ。作る側にもその狙いはあるだろう。しかし、今どきの映画の感動やらは、どうにも見苦しいものがあり、自然ではない。そこに、面白さがないから、と思うのだ。映画における面白さは、特別なものではない。見て、面白かった。見終えた、その瞬間の反応だ。勿論、面白く感じるか否かは人それぞれだが、その、人それぞれすら存在しない映画が日本映画では、多くなったように思う。ハリウッド作品もそうだ。そのそれぞれは列記しないが、韓国映画には、まだ面白かったが存在する。例えば、『誰にでも秘密ある』や『大統領の理髪師』など。『ラジオスター』を、必見とは言わないが、見て良いとは思わせる。65点の映画だ。会場が、愛知芸術文化センターのアートスペースAで、椅子を並べただけの多目的ホール。今の劇場からしたら見難い場所。前の人の頭で画面が切れる。そういう条件の悪い所であったが、250人ほどの観客。そのほとんどが女性と言うのも、今の映画界の観客の象徴か?
2007.08.25
コメント(0)
-
『ブラインドサイト(ルーシー・ウォーカー)』
『ブラインドサイト(ルーシー・ウォーカー)』見ました。簡単にはまとめられない映画です。ドキュメンタリーですが、撮影したものを編集して見せるというスタンスではなく、同時進行的な見せ方をしています。それが、意図されたものか否かは分かりません。撮影する側もされる側もその存在がそこにあり、そこにあるがままに我々観客の前に出されたという感じです。内容も一言でいえるものではありません。ただ、言えることは、盲目の子供たちのエベレスト〈映画の中で子供たちはチョモランマと言っています)登山の話ですが、盲目であることの特殊性が、そこには無く、子供たちが山登りをする、ということの意義が語られていると思います。改めて、後日まとめて見たいと思います。
2007.08.23
コメント(1)
-

『ちょっと本気な 千夜千冊 虎の巻 読書術免許皆伝(松岡正剛)』
『ちょっと本気な 千夜千冊 虎の巻 読書術免許皆伝』(松岡正剛)求龍堂を読み終えました。兎に角、凄いの一言です。森羅万象、あらゆるものに触れています。勿論本の世界でのことですが。もともとは、WEBで書かれていたものを、全7巻の本にしたのが、『千夜千冊』ですこのWEBが、素晴らしい。いつものように、抜書きを・・・。【序 千夜千冊の誕生 なぜ千冊の本が七巻になったのか】から、そのそも本はリセプタクル〈容器)であって、ヴィークル〈乗物)なんです。本には古代でも宇宙でもシェイクスピアでもラーメンでも何でも入るし、どこにでも行ける。それはいつ行ったっていいんです。乗船自由。p9読書の原則が色々書いてあります。1、できるだけ好きなものを読む。それでいいんです。それが原則です。p182、読書の基本は楽しみです。p203、読書は交際なんです。p204、絶対に再読すること。これは必絶。p215、読書ノートを書いてみるといいですよ。そのばあいは、本の中身についての感想だけじゃなくて、そのときの自分のコンディションや食べたものもメモしておくこと。これが大事です。p24以上が、【序】からの引用です。自分の場合い、再読は余程気に入ったもの以外はしなかった。再々読も、再三再四読もあり得ます。今後の課題です。食べ物のことなど、想定外です。この、原則を映画に当てはめて、今後取り組むようにとの教訓です。【序】だけでも、これほどの抜書きです。今後、続きをいずれまた。ちょっと本気な 千夜千冊 虎の巻 読書術免許皆伝松岡正剛 求龍堂2007年6月27日
2007.08.21
コメント(0)
-
『ダイ・ハード4.0(レン・ワイズマン)』
『ダイ・ハード4.0(レン・ワイズマン)』見ました。期待はしていませんでした、その期待通り。箸にも棒にも・・・でした。ダイ・ハードはアクションとマクレーンと犯人との知恵比べがその面白さの基。しかし、3よりもっとそれがなかった。サイバー・テロというテーマだから、そこが難しいが、ジャスティン・ロング演じるハッカー、マットを上手く使っているが、もう一ひねりあれば、もっと面白いものになっただろう。もう、半分はアクションのみの、それもダイ・ハードという名前の、奇想天外な成り行きだった。ハッカーと言う面では、『踊る大走査線 交渉人真下正義』を思わせる所があった。
2007.08.19
コメント(2)
-
『遠い国から来た男(山田太一)』
先月7月23日の番組です。録画しておいたのを見ました。46年ぶりに南米から帰国した男、その昔、商社の同僚とその妻、その妻は男のフィアンセだった。男は当時赴任先の南米の国の革命に加担し、12年の獄中生活。そのまま、その国に残り、結婚もし、農園を経営している。そして、46年ぶりに日本に来る。そこでの出来事を書いたドラマ。最近の山田太一は、老年の恋を描くことが増えたように思う。この『遠い国から来た男』も、そうだ。だが、生臭くならない所がいい。栗原小巻がすっかり、老けてしまった。その表情や口調に岸田今日子や吉行和子を思い出させるものがあった。
2007.08.18
コメント(0)
-

猛暑=地球は狂っているか?
窓際の寒暖計が摂氏50度を指していた。この寒暖計は50度が限界だから、それ以上あったかもしれない。名古屋のテレビ塔の写真です。
2007.08.17
コメント(3)
-
お盆休み終了です。
暑さはピークでしょうか?明日から、仕事だと思うと、それだけで気が滅入ります。お盆休みは今日で終わりです。何もすることのない、土日含めた5日間でした。
2007.08.15
コメント(2)
-
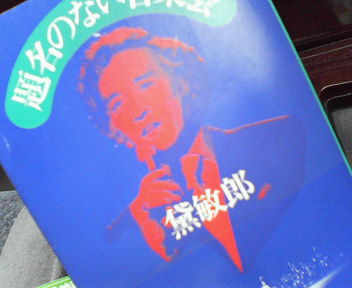
『題名のない音楽会〈黛敏郎)』
題名のない音楽会黛敏郎角川文庫昭和56年4月30日 初版発行という本です。我が日進市にはエコドームという施設があります。エコロジードームのことで、リサイクルできるノモを集めています。ペットボトルや、空き缶、空き瓶、牛乳パックなど持って行きます。そこに本棚があって、不要本を置いておくわけです。欲しい人は原則5冊まで貰っていけます。そこで、今日(8/14)見つけた本です。TV番組で多くの方がご存知だと思います(今も続いていますね)。その司会者でもあった作曲家の黛敏郎のエッセイ集です。この「まえがき」で、この番組のスポンサー【出光興産】にふれて、この会社(出光興産)はいままでテレヴィに番組を提供したことがなかった。独特な社風をもつこの会社は、テレヴィに番組を提供することによって商品の売り上げを少しでもふやそうなどと考えるよりは、企業というものが得た利益は、その何分の一かを必ず社会に意義のあることのために還元しなければならない、という考えをもっていたので、視聴率などは二の次として、社会に貢献する度合いの高い番組をさがしていた。〈後略)そして、このスポンサーはすばらしいスポンサーだった。「金は出すが口は出さない」といった最初の約束は忠実に守られて、以後十六年(中略)私たちは、やりたいことをやりたいように続けることができた。当時でも著者は奇跡であるといっている。今でも、奇跡の中の奇跡であろう。今なら、さしずめ株主のことは、どうだ、ステークホルダーはどうだ、社長の身勝手ではないか・・・、などなどで、このように良心的(あまり使いたくない言葉だ)なスポンサーは、潰されてしまう世の中になったと思う。ある種の、独断と偏見が会社経営者には必要で、その必要性が、こういったTV番組のスポンサー行動に表れる。その好例だと思う。さて、もう一つ。この本は昭和56年=1981年の発行だ。今から、26年前、四半世紀以上前である。もし、BookOffに買取を依頼したら・・・、引き取ってはくれない本だ。しかし、貴重な本であることは間違いがない。リサイクルだとか何とか言ってはいるが、ブクオフは所詮、商売でしかない。綺麗で、新しい本しか興味がない。そういう本屋だと思う。その企業姿勢と、この本にあるスポンサーとの差をついつい、考えてしまう。
2007.08.14
コメント(2)
-

墓参
毎年8月13日は墓参り。我が家の墓は、春日井市勝川の東漸寺(とうぜんじ)にある。高速道路が出来たので、家から車で30分弱。墓参りは年に4回(お正月、春の彼岸、お盆、秋の彼岸)と、家の庭に花が咲いたりすると、それを持って時々。おおよそ年に2回程度。だから、6回程度が我が家の墓参。家人の実家の墓もあるので、そちらにも大体一緒に行く。今回も、家内の母と家内と長女の4人で墓参。写真は、東漸寺の空。
2007.08.13
コメント(0)
-
GHQがつくった日本映画『こども会議』
日本映画専門チャンネルで「GHQがつくった日本映画」と銘打ち、5本の記録映画が放送されている。その中のひとつ、『こども会議(1950)』(1947年に制作されている)を見た。あらすじは、民主主義の精神とルールをある小学校の情景を通して示す教育映画。子供たちが議会を開いて意見を出し合い、ささやかな問題を自分たちの力で解決してゆく。雨具がない生徒が多いため雨の日は登校する生徒が少なく、授業もままならない小学校。子供たちはこども議会"を開いて意見を出し合い、雨具のない生徒が雨の日も登校できるよう自分たちで解決策を考え、実行に移す。演出はドキュメンタリー作家の丸山章治。"以上のように、HPで紹介されている通りだ。中で面白かったのは、子供たちが実に生き生きと話し合いをしていることだ。雨具のない子が雨具のある子と一緒に登校すればよいと言う話し合いのなかで、背の高い子と低い子が一緒にはなれない、とか、意地悪な子が居たらとか、もし、傘のある子が休んだらなど、子供たちは真剣だ。それを見ているだけでも面白い。そして、こども会議が生まれる過程も興味深い。わずか25分程度の作品だが、そこには戦後の希望が大きなものだと、しみじみ分かる。昨日の『ヒロシマナガサキ』とは違う意味で、戦後62年を思うことになった。このシリーズは、今月再放送が何度もあるので、このチャンネルを見ることが出来る方は是非ご覧を。
2007.08.12
コメント(0)
-
『ヒロシマナガサキ(スティーブン・オカザキ)』
25年間かけて被爆者の記録をした。『ヒロシマナガサキ』。嘗て公開寸前まで行ったそうだが、米国内の反対があり、実現しなかったと聞く。今回は、全米のケーブルTVで、1ヶ月放送されるという。すでに放送されているようだ。日本のマスコミはこぞって取り上げている。内容は、アメリカにある、当時のフィルムを使うことで、今までに見たことのない映像が見られる。しかし、そのこと自体はどうと言うこともない。当然の悲劇であることの証言以外何者でもなく新たな発見があるわけではない。かつて、広島にも長崎にも行き、見て感じたこと以上の発見はなかった。しかし、被爆者の方々の証言のすべては、胸に迫るものである。驚くのは、日本のTV番組がこぞってこの映画のことを取り上げていることだ。先日の参院選での安倍自民党の惨敗が各TV局の背中を押したのか?そもそも、憲法改正、第九条の見直しについて、大方のマスコミは積極的に賛成ではなかった・・?だが、支持率の大変高い、安倍政権に真っ向から反対をする姿勢がなかった。しかし、今回の参院選での自民党惨敗で、安倍政権の支持率は急降下し、その勢いで、憲法改正、九条の見直しはやはりまずい、その意味でも映画『ヒロシマナガサキ』が、示している、悲劇を再度考えよう。しかも、米国においてもTV放映され、米国内でも核問題は話題になるはずだから・・と、こういう見方は天邪鬼だろうか。さて、再度繰り返すと、この映画の力は何といっても証言者による。被爆者の方々の言葉は重い。なおかつ、被爆した体を曝しながらの出演は、言葉にいえない重みがある。エノラゲイの乗組員の話も重要だ。落とした側の思いも今回初めて聞くことになった。証言を集めに集めた監督に拍手である。アメリカだけではなく全世界にこの映画を、という声がある。でも、その前に日本の子供や若者に見せるべき・・・。それは、この映画の冒頭を見れば分かる。是非、中学生や高校生に、学校が積極的に見るように活動されんことを、希望します。
2007.08.11
コメント(2)
-
『田辺・弁慶映画祭』の審査員募集
8/6、キネマ旬報名で、映画検定1級合格者の皆さまへ、と書かれた封書が届いた。趣旨は、『田辺・弁慶映画祭』の審査員募集というもの。この映画祭、今年が初めてみたいです。20名募集。映画祭は、10月4,5,6日〈木曜から土曜まで)。平日だから仕事を休んで行くことになる。mixiでの反応は、行きたいけど、遠い、仕事があるなど、行くという人など、それぞれ。南包は、考え中。仕事を休むことになるから。それも、2日だから・・・。気持ちは行きたいのですよ。
2007.08.08
コメント(1)
-
映画芸術420
映画芸術420号で、この雑誌の編集長でもある脚本家の荒井晴彦と映画評論家の寺脇研の対談が載っている。一つだけ、紹介する。「泣ける」「面白い」「安心できる」だけが、今受ける映画の基準だと二人は嘆いている。二人だけでなく、心ある映画好きは嘆いている。だから、『パッチギ!LOVE&PEACE』は、受けなかった。ここには、はっきりと日本への批判にはじまり、世界の国々への批判がある。『リトル・チルドレン』にある、毒も受け入れられやすいものとは思えない。だが、表現には毒がなければ、そんなもん箸にも棒にもかからん、しょうもないものだ。最近の某映画雑誌もそうなってしまった。媚びることと、受け手のことを考えることは違うが、受け入れられようとして媚びてしまうことが多い。先日亡くなった、阿久悠氏の歌は媚びることはなかったように思う。
2007.08.05
コメント(0)
-
『リトル・チルドレン(トッド・フィールド)』
『リトル・チルドレン(トッド・フィールド)』です。アメリカ版「金妻」といわれていますが、「金妻」のような予定調和はありません。それこそがTVではなく映画だという所以。そして、今、NHK地上波で放送中の「デスパレートな妻たち」をも思い出させるが、こちらは、能天気なコメディー。これはこれで、ぞっとさせる面白さがある。さて、物語は、子供にいたずらを働いた受刑者ロニーが仮釈放されて街に戻ってくる。それを、街の人たちは当然の如く反対する。その姿勢は、自分たちの近くに帰ってこなければ良い。よそにいってくれと言う態度。まさに、自己中心。そういう人たちが出てくるから、リトル・チルドレン=小さな子供たちなのか?主人公の主婦サラ(ケイト・ウィンスレット)は、近所の主婦たちと公園で子守。そこに、子守の父親ブラッド(パトリック・ウィルソン)が・・・。主婦たちの関心は、男のこと。主婦たちはサラを嗾(けしか)け、ブラッドの電話番号を聞ければ5ドルと言う。しかし、書くものがないサラは、ブラッドにハグしてもらいその証明としたが、それ以上にその場は発展してしまう。それを見た事なかれ主義の主婦たちはその場を逃げるように去る。そして、この二人が・・・、と言う話なのだが、受刑者ロニーと母親。元警察官の、ラリー(ノア・エメリッヒ)の強さと弱さ。所詮人間は、弱いものそして、捨てたものではない、というのが、この話のテーマ。それを思うと、サラとブラッドの物語より、むしろサイド・ストーリにテーマがある。監督 : トッド・フィールド出演 : ケイト・ウィンスレット / パトリック・ウィルソン / ジェニファー・コネリー / ジャッキー・アール・ヘイリー最後に、『エデンより彼方に』も、この手の映画。やはり、アメリカの普通の主婦たちは、普通に仕合せで、普通に不満で・・・。日本も同じか?
2007.08.04
コメント(2)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 最近観た映画。
- 羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来(羅小…
- (2025-11-24 19:26:41)
-
-
-

- おすすめアイドル
- 乃木坂46「熱狂の捌け口」スタジオラ…
- (2025-10-25 17:37:46)
-
-
-

- あなたが夢中なセレブゴシップ&Kア…
- 天気悪いなあ~ 雨降り心配の小さく…
- (2025-04-26 15:25:48)
-







