2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年02月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
『警官の血』
『警官の血』の前編、後編TV番組を見ました。父子三代の警察官の話。内容は大きく違うが、かつて『 警察署長Chiefs (1981) (スチュアート・ウッズ)』という名の小説を読んだ。これは米国の片田舎のやはり父子三代に渡る警察官の話。米国ではTV化もされ、わが国でも放送されたと思う。私は見ていないが。 リンクは、本の紹介ではないのですが、そこにあるコメントを参考にしていただければ。 しかし、小説は可也昔に読んだので、忘れた。だが、とても面白い小説で当時のミステリベスト10の上位にランクされたと思う。 こんなことを思い出しました。
2009.02.13
コメント(0)
-
『ご縁玉(江口方康)』
『ご縁玉 パリから大分へ Goendama』 乳がんを患った自らの闘病経験を通じ、小・中学生らと命の重みについて話し合う「いのちの授業」を続けた、大分県の元養護教諭、山田泉。さる11月がんの再発で世を去った彼女と、パリで活躍するチェリスト、エリック-マリア・クテュリエとの交流を描いたドキュメンタリー。 生涯最後の海外旅行にパリを選んだ山田は、エリック-マリアと出会う。彼はポンピドゥーセンターを拠点に活動する、世界最高峰のアンサンブルの一員だった。3ヶ月後、エリック-マリアは、山田から渡された5円玉とチェロを手に、大分を訪れる......。人と人との出会いが感動を呼ぶ、必見の72分。 これは、名古屋で上映した館のサイトからの引用。 映画館ではなく、TVでもこれならいいのでは。こういうものはマイナーなので、TVで見せたほうが、より多くの人が見ることが出来る。
2009.02.11
コメント(0)
-
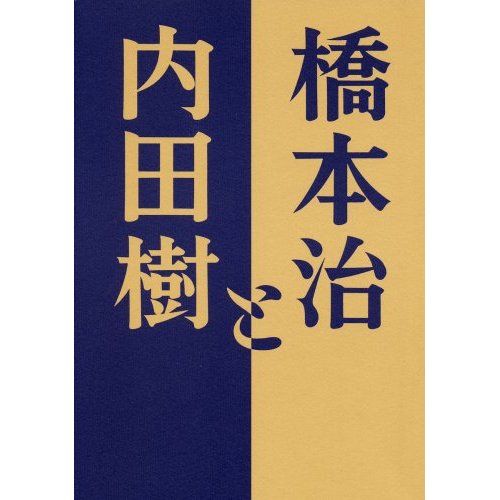
『橋本治と内田樹』『稼げる男のセックステクニック(田辺まりこ)』『芥川賞を取らなかった名作たち(佐伯一麦)』
『橋本治と内田樹』『稼げる男のセックステクニック(田辺まりこ)』『芥川賞を取らなかった名作たち(佐伯一麦)』の3冊。読み終えたものはないが、すべて図書館から借りたのも。 『橋本治と内田樹』は、雑談過ぎて読むには辛い。現場にいて対談を聞くときっととても面白くエキサイティングなものであったと思われる。しかし、改めて『桃尻娘』全作を読みたく思わせてくれた。『稼げる男のセックステクニック(田辺まりこ)』借りた己が馬鹿だが、やはり下らぬもの。しかし、この手と、最近の品格ものは、いくら出版がビジネスとはいえ、堂々とまかり通るのは忸怩たる思いである。 『芥川賞を取らなかった名作たち(佐伯一麦)』巻末の、芥川賞とその候補作の全リストの為に借りた。橋本治と内田樹筑摩書房2008年11月25日 初版第一刷発行稼げる男のセックステクニック田辺まりこベスト新書2009年1月20日 初版第一刷発行芥川賞を取らなかった名作たち佐伯一麦朝日新書2009年1月30日第一刷発行
2009.02.07
コメント(0)
-
『 トウキョウソナタ (黒沢清)』
『トウキョウソナタ』です。先日発表された、『映画芸術』『キネマ旬報』それぞれのベスト10で、4位である。だが、『映画芸術』にはワーストを選び、その得点をマイナスする集計であるから、4位なのであるが、プラス点のみでは、1位である。 それは、さておき。「おくりびと」が日本映画の中では一般に(ということはマスコミにである)受けがよい。それに異議はないが、なぜ「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」「闇の子供たち」が同様な質で話題にならないのか?これらの作品にある政治的なテーマを避けるがごとくに思われる。そこに横たわるのは、マスコミの脆弱さである。マスコミも視聴率(?)欲しさに硬いものではなく柔らかいものにしかライトを当てないのだろうか?せいぜいが「おくりびと」では、若松孝二も坂本順治もこの「トウキョウソナタ」の黒沢清も多くの人が知らぬ間に過ぎてしまう。 『トウキョウソナタ』は傑作だ。リストラされた夫(香川照之はコンスタントに良い)は、なかなか家族にそれを言えない。その妻(小泉今日子=好演)は、何となく知りつつ明るく家族を支える。大学生の長男と小学6年の次男(井之脇海がとてもいい)。長男は大学を中退し米軍に入隊。4人それぞれが屈託を抱えながら生きているのは、現在の日本の家族を象徴しているそれぞれにその屈託と戦いながら、行き着く先まで行くこともできず再び家族を取り戻すまでの物語。こう書くと、なんでもなく見えるが黒沢清はそれをありそうな設定で見せてくれる。父親と次男が家に帰ってくる三叉路が家族のまとまりのメタファーでもある。 ところで、香川がリストラされ、まずその宣告をされる時、「ああたは会社のために何ができますか?」と、そして面接に行った会社でも、若い人事担当者に同じ質問をされます。これは、実際に身近にあることで、身につまされます。質問をしている側の人間が同じ質問にはどう答えるのでしょうか?黒沢清は、かように、ひとつひとつが現実的な面を持つ、寓話を見事に作り上げた。
2009.02.06
コメント(0)
-

『詩の力(吉本隆明)』
『詩の力(吉本隆明)』です。引用・・・、岡井隆の『E/T』より夕餉(ゆふがれひ)をはりたるのち自(し)が部屋にこもりたれども夜更けて逢ひぬ帰りしとき紅潮させてゐた妻に気づかぬふりをしたりせんだりp41 塚本さん、岡井さんほど本格的な仕事をしたといえるのは、詩では荻原朔太郎や宮沢賢治、中原中也、短歌では斎藤茂吉といった名前を挙げられるにすぎない。p37塚本さん=塚本邦雄 岡井さん=岡井隆 ある音声学者が、日本人はメロディー自体を、(音声言語をつかさどる)言語能で聴いたり、(感覚機能をつかさどる)感覚能で聴いたりするために、こういうことが起こるのだといっている。平安期の物語を読めば、日本人が風の音や虫の声を聴いているうちに涙を流す場面がよくある。それは現代にも続いている。風の音や虫の声を言語として聴いてしまい、意味を感じてしまうためだ。p71現代詩についてちょっとは分かった気にさせてくれる。引用されている、詩や短歌を読むにつれ、文芸の厳しさが分かったような気になる。今日(2/4)中日新聞の夕刊に角川短歌賞・俳句賞の発表が出ている。その短歌は・・・、柚子風呂の四辺をさやかにいろどりて湯は溢るれど柚子はあふれずあかねさすGoogle Earthに一切の夜なき世界を巡りて飽かずその俳句は・・・、思ひ切り吹いて草笛かすかな音裸の子「うん」といふなり走りだす短歌も俳句もどちらも緩い。これで賞だってさ。詩の力吉本隆明構成/大井浩一・重里徹也新潮文庫平成21年1月1日発行
2009.02.04
コメント(3)
全5件 (5件中 1-5件目)
1










