2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年07月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

帽子のこと
これは、『1930年代・東京 市の音 濱谷浩 写真集』の写真である。図書館で借りました。浅草 歳の市の風景。可也の人が帽子を被っている。それも、ソフト帽子である。これは、特別の人ではなく、市井の人の服装である。後ろに見える横断幕には「歳の市 羽子板展覧会」とある。右の男性、はっぴを着て自転車、その後ろには商売の箒、はたき、ブラシなどを引いている。帽子はソフト帽。 葛飾八幡宮の「農具市」(9月中旬)。店は傘を売っている。右の男性はお客であろう、買ったものを天秤棒のようなものにぶら下げている。帽子はパナマ帽か? なかなかファッショナブル。白いパンツも決まっている。大八車には「水道道具一式」とあり、ホースを積んでいる。帽子は、パナマ帽。 1930年代・東京 市の音 濱谷浩 写真集初版印刷 2009年5月20日初版発行 2009年5月30日河出書房新社
2009.07.19
コメント(0)
-
『東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・歴史編(菊地成孔+大谷能生)』その2
承前この講義(歴史編)は、前期の講義であり、最後の日はテスト(前期テスト)である。テストは、レコード(曲)を5曲聴き、その批評を書くというもの。講師の、菊地成孔は、テストに入る前に、学生たちにこう言う。インターネットとホームページの普及によって近年この「批評」という行為が爆発的に増えてきております。今や日本人全員がジュースを買っては批評し、映画を観ては批評し、人物を見ては批評して発表するということを日々繰り返していますね。批評という行為には、自分が実際に体験した事柄以外へと開かれていく、外部的な視座・観点というものが必要になってきます。この講義で学習した「歴史」というものも、私たちの外部にあるものです。実際に批評を書こうとするにあたって、個人の嗜好、経験、身体性、心の問題といった個人的なファクターと外部からの批評視座とのあいだには、必ずノイズや軋轢が生じます。自分の身体の反応と、外部から与えられた教育や歴史との相克というものを、記述の中にどうにかして捻じ込む、という行為が批評だと言える。昨今ネット上などで見られる批評の多くは、外部に目を向けるのは苦しいからそういった擦り合わせをまったく放棄して、自分の身体性一辺倒で物事にあたる、といった方向に塗りつぶされつつあるのが現状だ(中略)現在の自分の尺に合ったもの、気に入ったものに関しては「偏愛」する、気に入らなかったものに関しては「滅茶苦茶なクレーム」をつける、といった、ある種の心理的暴力とも言えるような批評ばかりが増加することになります。インターネットが持っている外部遮断能力の高さにも原因があると思うけれど、現在、どの分野においても、いわば「分断して統治する」というシステムが是とされている。こうした状況が招いた事態ですが、そういった現在だからこそ「何かを勉強して何かを批評する」という作業が非常に重要であると思っています。以上長々と引用しました。しかし、この引用も講義の話し言葉などをカットし再構成して引用いたしました。そして、テストの5曲は、Glenn Miller and His Orchestra `Chattanooga Choo Choo`(1941)Bud Powell Trio `Indiana`(1947)The Giuseppi Logan Quartet `Dance of Satan`(1965)George Benson `Affirmatrion`(1976)銀巴里セッション`Green Sleeves`(1963)かく言うこのBlogも日記形式の批評・感想のうちに入るものである。自戒もこめての引用である。菊地の言うとおり、自分の「偏愛」があることは否めないが、自己の気づかぬこと、わが意を得たりと言ったことや新たな発見になど書籍に関しては主に書いている。最近映画について書いていないが、こちらのサイトに「南包」として発表しています。よろしければ、御一読を。東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・歴史編菊地成孔+大谷能生文春文庫2009年.3月10日 第1刷かく言うこのBlogも日記形式の批評・感想のうちに入るものである。自戒もこめての引用である。菊地の言うとおり、自分の「偏愛」があることは否めないが、自己の気づかぬこと、わが意を得たりと言ったことや新たな発見になど書籍に関しては主に書いている。最近映画について書いていないが、こちらのサイトに「南包」として発表しています。よろしければ、御一読を。東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・歴史編菊地成孔+大谷能生文春文庫2009年.3月10日 第1刷
2009.07.18
コメント(0)
-

『東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・歴史編(菊地成孔+大谷能生)』
以前、この本を書店で見たとき、アルバート・アイラーが東大に来て講義をした記録だと単純に思った。そして、そのことをずぅ~っと疑うことは無かった。 しかし、今回、これを手に取り購入し、読み終えて、自分は何と単純なバカ者で早とちりで一人合点であったかを知った。今更ながらである。 読み通して、(キーワード編はこれから読むが)みて、半分以上は理解できなかった。講義中にかけられる音楽のうち知らないものも可也あったからである。しかし、知っているものもそれなりにあったので、分かるところも多くあった。(半分以上理解できなかった・分かるところも多くあったとは、何たる矛盾か?) そういう本だ。 これは、前期の講義であり、最後にテストがある。そこが読み応えがあった。それは、後日。 東京大学のアルバート・アイラー 東大ジャズ講義録・歴史編菊地成孔+大谷能生文春文庫2009年.3月10日 第1刷
2009.07.15
コメント(0)
-
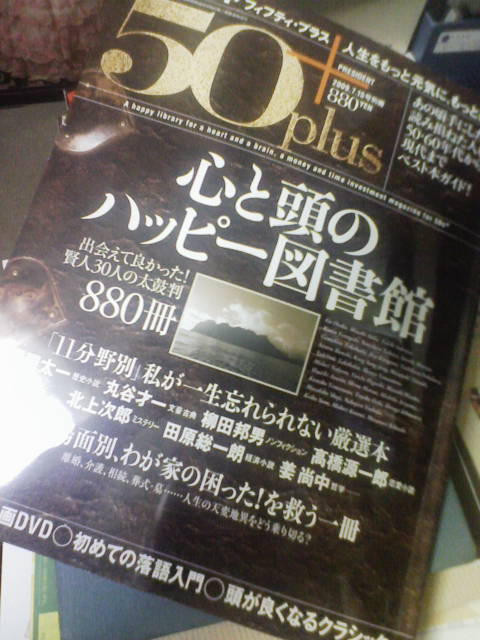
プレジデントフィフティープラス2009.7.15号別冊 「心と頭のハッピー図書館」
そもそも読書とは、私の経験から言えば、何かの役に立てるために読むものではありません。子供の頃から大学時代ぐらいまでに読んだ本というのは、教養として身につく。ところが人格がある程度形成されてから、つまり大人になってから読む本は、知識にこそなれ、身についた教養にはならないわけです。(逢坂剛 プレジデントフィフティープラス2009.7.15号別冊 「心と頭のハッピー図書館」より) この意見には、大いに賛成である。「教養として身につく〈傍点筆者〉」の「教養」といわれると微妙なニュアンスを感じるが・・・。 私は、その人の趣味嗜好は、ティーンエイジャー(即ち13歳から19歳)のときに何に没頭したかで大方が決まるとかねがね思っている。 ティーンエイジャーの時に没頭するということは、お金のない時のことだから、余計に没頭するといえる。音楽だったり絵だったり、将棋や囲碁、またはプラモデルだったり人様々である。先述の剛坂氏は「私の場合、西部劇がそうでした」と書いている。 剛坂氏の西部劇通は夙に知られている。 だからというわけでもないが、最近のビジネス書やハウツー本を、私は本(書籍)とは違うものだと思っている。頑固に頑固に思っている。大いなる偏見を持って乱暴に申し上げれば、読書は何かの役に立ってはならないのである。更に言えば、音楽も映画も絵画もすべては遊びの世界であり、世の中の役に立ってはならない物どもである。 もう一度、同じ剛坂氏を引く・・・、「読書のコツ、極意は、何よりも本屋さんに行くことです。平台に置かれた新刊書を手にとって見るだけでも、世の中の動きが分かるし、自分でも気が付かなかった読みたい本に出合えることもある。それを億劫がっていたら、真の悦びには浸れないと思います」(引用前と同じ) プレジデントフィフティープラス2009.7.15号別冊 「心と頭のハッピー図書館」
2009.07.03
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1










