2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年08月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-

『道楽三昧--遊びつづけて八十年(小沢昭一 聞き手;神崎宣武)』
小沢昭一という人は一筋縄では行かないと、分かっていたが、それ以上である。嘗てここで紹介した2冊「色の道 平身傾聴裏街道戦後史 商売往来」と「平身傾聴 裏街道戦後史 遊びの道巡礼」の時以上の驚きである。 とにかく遣ることが、一通りではない。道楽というのはこういうことだと、妙な言い方になるが勉強させられる。 岩波書店のPR誌「図書」に一年間連載されたもの。虫とりべいごま・めんこ・ビー玉相撲・野球飲む・打つ・買う落語芝居大道芸映画俳句歌競馬食・釣り・写真などと、12章からなる。 相撲・・・から相撲は、江戸の頃、両国の橋のたもとの回向院にかかっていた見世物の一つです。だから、別の言葉で言えば、元は芸能です。(中略)だから、八百長がどうのこうのと騒がれますが、「もっとおおらかに」と言いたいです。この説は、方々で色々な人が説いてはいる云々飲む・打つ・買う・・・から「夢に見るようじゃ、惚れようが薄い。ほんに惚れたら、眠られぬ」競馬・・・から専門家を見極める眼力というか、勘みたいなものを養うべきだと思います。ただ、みんながいいと言っている専門家は、それほどでもない場合が多く、地味な専門家というのに卓越した人がおられるようです。云々食・釣り・写真など・・・から(夏目)漱石先生は、「道楽と職業」という講演で、「仕事」というのは人のためにやるもので、「道楽」というのは自己本位のものなんだという区分けをして、哲学者とか科学者とか芸術家とかいうのは、みんな自己本位に仕事をやっているんだから、それは職業じゃなくて道楽なんだということを力説していました。その講演録を読んで、ぼくの人生は道楽を積み重ねてきたんだなあということの裏づけを漱石先生から頂いたような気がいたしました。神崎宣武の「あとがき」から・・・民俗学はフィールドワークを大事とする学問です。そのフィールドワークでは、また「聞きとり」調査を大事とします。しかし、それは厄介なことなのです。私(神崎)の民俗学の師は、宮本常一です。先生は、こう教えてくれました。「相手が男なら、戦争中の苦労話と息子の自慢話がおわるまで待たないと大事なはなしは聞けない。相手が女なら、嫁の悪口がひととおりすむと、聞きやすくなる」宮本常一は、世間師ともいわれました。いい意味での「たらし」。その宮本先生と同じような世間師のにおいを、私は、小沢昭一さんに感じたのです。 小沢昭一の仕事の中での記録といえるものの量は莫大だと思う。しかし、それも全てが積み重ねによるものであると思う。そのひたむきな態度こそが小沢昭一という人を解く鍵ではないかと思ったりした。 とにかく、この一冊だけでも小沢昭一という人が一筋縄では行かないと分かる。 道楽三昧--遊びつづけて八十年小沢昭一 聞き手;神崎宣武岩波新書(新赤版)11992009年7月22日 第1刷発行
2009.08.27
コメント(0)
-
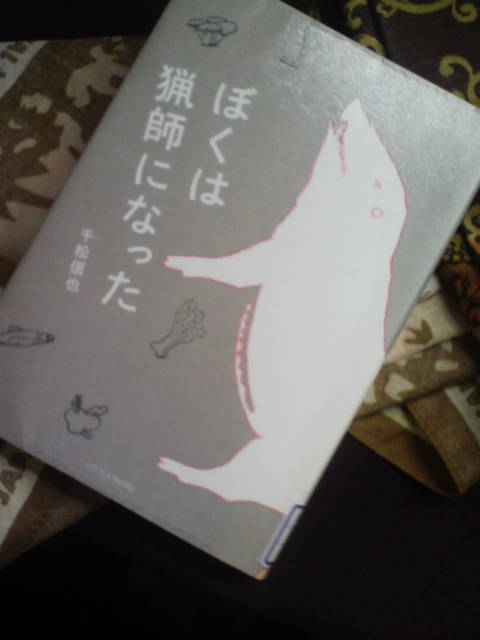
『ぼくは猟師になった(千松信也)』
時々、本屋の中をくるくる廻る。隅々までとは行かないが、店内の8~9割くらい見て廻ると、こういう本が見つかる。それが、『ぼくは猟師になった(千松信也)』である。手にとってぱらぱらと見る。買うまではないが、読みたいなぁ、である。そうなれば、図書館。これも、今回、図書館。 著者が猟師になるまでの話から、新米猟師がどのように猟をして云々、そして獲物の捌き方から食べ方、保存の仕方など、千松信也氏の方法が書かれてある。写真も豊富。 一匹の鹿が、猪がどう捌かれ、著者の食卓に上がるか、それは、今われわれがスーパーの店頭でパック入りの肉を求めるまでに以下に多くの手がかかっているかを逆の方向から見ているようなものだ。 本との出会いとは、様々である。自分の場合、こういう形での出会いが結構多い。ぼくは猟師になった千松信也2008年9月21日 初版第一刷発行リトルモア
2009.08.22
コメント(0)
-
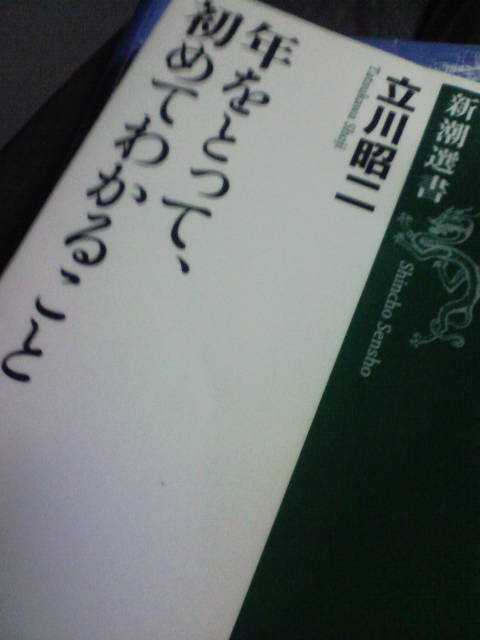
『年をとって、初めてわかること(立川昭二)』
タイトルだけからは、人生訓のようなものが書かれてあるのかと思った。書店で見かけて気になっていた本。図書館で借りた。本書をひらいて初めて、中味を知る。タイトルのみが気になっていたのだということ。中身は、文学に見る、「年をとってからわかること」である。そして、テキストとして取り上げられている作家は、斉藤茂吉、吉井勇、田村隆一、谷崎潤一郎、金子光晴、川端康成、三島由紀夫、幸田文、円地文子、田辺聖子、伊藤整、上田三四二、川上弘美、池波正太郎、水上勉、宮本常一、湯本香樹実、青山七恵、藤沢周平、山本周五郎、瀬戸内寂聴、永田耕衣、齋藤史、伊藤信吉、中堪助、耕治人、青山光二、井上靖、深沢七郎、森敦、村田喜代子という錚々たる顔ぶれ。全10章、それぞれの章は・・・、老いの自覚老いと欲望老いの情念(パトス)女の老い・男の老い老いとエロス老若の共生老いの価値老いの美学老いと看とり老いの聖性全270ページを、一気に読んだ。 年をとって、初めてわかること立川昭二新潮選書発行・・・・・2008年7月25日4刷・・・・・2008年11月30日
2009.08.18
コメント(0)
-
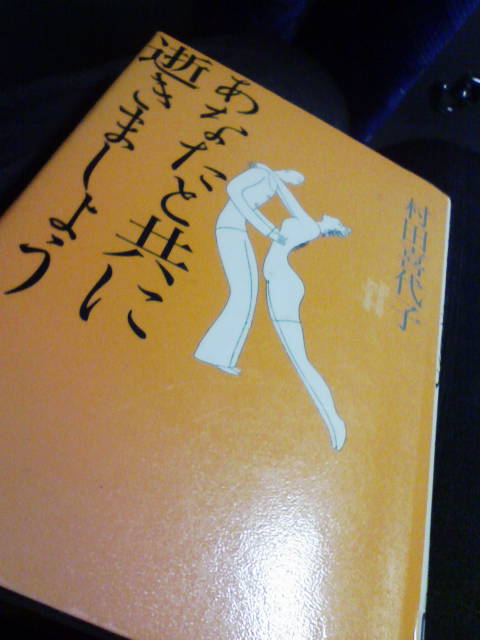
『あなたと共に逝きましょう(村田喜代子)』
『ドンナ・マサヨの悪魔』に続き村田喜代子は5冊目である。『ドンナ・・・・』よりも、こちら『あなたと共に逝きましょう』のほうが、面白く読めた。60歳を過ぎた夫婦の話。夫は機械の設計事務所を持っていて、妻は大学で服装について教えている。娘は結婚して海外に居る。互いに独立した生活を送っている。ある日、夫に弓部大動脈瘤が見つかる。そのまま放っておけば、必ず破裂して死ぬ。早速の検査とその後の手術が求められるが、夫はなんだかんだ言いながら、自然に治らないかと思う。妻は、人から聞いた民間療法に頼ろうとし、夫と共に温泉にいったり食養をする。しかし、瘤は小さくならず、ついには手術・・・。 妻には大学に稲葉梨江という友だちがいる。その梨江とのこと・・・、将来、夫が死んだら、と楽しい夢を語るように言った。私と梨江のそれぞれの夫がちゃんと先に死んで、あの世へ行ったら、それから何をして暮らそうかと。夫が死んだ先にまだ将来というものがあると何となく思っていた。/むろん夫が死んでも明日はある。日にちは続く。しかしその明日は、将来、と呼ばないのだ。将来とは人生の連れ合いが欠けたりするようなことのない、もっと翳りのない、まだ何かいろいろ充実してやることがある、そういう日々のことをいうのだ。/圧力鍋を火にかけながら私は思う。 病院でもらった『患者様の心がけ』。病院の冊子は、穏やかな心を持つことをすすめている。 よく笑うこと。ゆっくりと話すこと。腕時計の針を進めない。他人を許すこと。自分の非を認めること。何が何でもかならず成果を出さねばならないとは思わない。自分の挙げた成果を、必ずしも他人は百パーセント認めるとは限らないことを知る。家族との穏やかな時間を作ること。 さて、『あなたと共に逝きましょう』だが、民間療法のこと、動脈瘤のこと、鯉こくを作るところ、それぞれのディテールは通り一遍ではなく、深く切り込んでいる。それが並大抵のものではないことは読んでいるとひしひしと迫ってくる。 村田喜代子は、黒澤明監督の『八月の狂詩曲(ラプソディー)(1991)』原作『鍋の中』からで、次には10年ほど前『蕨野行』そして、『鯉浄土』と『ドンナ・マサヨの悪魔』。『ドンナ・マサヨの悪魔』は子供が生まれるものだが、常に死が付き纏う。 あなたと共に逝きましょう村田喜代子装画 東郷青児装幀 菊地信義2009年2月28日第一刷発行 朝日新聞出版
2009.08.12
コメント(0)
-

やさいを頂く、庭の樫の木の枝落し
早朝(6:40)の電話。近所の方から、野菜を今から届けます。ということで、電話で起こされる。少し、ピンボケです。これが届いた野菜。冬瓜も2個ありました。そして、樫の木の枝を伐りました。これもピンボケ。約一時間半、はしごに登り新しく伸びた芽を中心に落としました。汗、びっしょり、まるでバケツで水を頭からかぶった様。
2009.08.09
コメント(0)
-
イジー・メンツェルのことなど・・・。
この三月、『英国王 給仕人に乾杯!』を見た。これを見たのもどちらかといえば、偶然。名古屋での公開館「名古屋シネマテーク」が、力を入れてPRしていたことも、私の背中を押した。この監督、イジー・メンツェルが、嘗て『厳重に監視された列車』で米アカデミー賞外国語映画賞を受賞していたことすら、知らなかった。偉そうに、「映画検定1級」とは、いやはやである。 不覚にも、このチェコの監督イジー・メンツェルの存在を知らなかった。新人監督ならまだしも、1938年生まれの、ベテラン監督である。『厳重に監視された列車』は、1966年に出来たものでもあり、『英国王 給仕人に乾杯!』は2007年だから、それまで41年ある。そういう長期間映画監督として活動していた人である。 これを思うと、こういう知られざる監督、映画人はもっといるのではないか、と。では、それらの知らぬ人たちをどのようにマークするか?中々難しい。 一つしか、今は思い浮かばない。それれは、米アカデミー外国映画賞、受賞作品とノミネート作品のマークであると・・・。そこには、知らない監督や作品が目白押しに違いない。他にも、知られざる(私が知らないだけ)監督や映画人を見つける方法があるとは思うが、今は、これで行く。 因みに、手許の『アカデミー・アワード アカデミー賞のすべて(監修:筥見有弘)/キネマ旬報社1995年5月1日発行』各年の米アカデミー外国映画賞、受賞作品とノミネート作品を見ていくと、気が遠くなるほど多量にある。それも、この本は、1994年までのデータしかないのだが・・・。 さて、イジー・メンツェル作品のDVDがまだ出ていないようだ。こういう人のDVDは簡単には売れないのだろうから、出し難いのかも知れない。でも、出たら欲しいと、今は思っている。
2009.08.08
コメント(0)
-

『小川洋子の偏愛短編箱(小川洋子・編著)』
少し前に、「文學界」七月号の『夙川事件――谷崎潤一郎余聞(小林信彦)』を読んだ。その中にたとえば、「過酸化マンガン水の夢」という作品がある。昭和三十年十一月号の「中央公論」にのった時は、「過酸化満俺水の夢」という題だったはずだ。という件があり、この谷崎の小説を延々と説明している部分がある。映画「悪魔のような女」のことや、当時日劇ミュージックホールに出ていた春川ますみのことが小林によって書かれている。 その時には、「過酸化マンガン水の夢」より、「新青年」に載った「武州公秘話」のほうに興味があった。だが、偶然手にした『小川洋子の偏愛短編箱(小川洋子・編著)』に、この「過酸化マンガン水の夢」が、収録されていた。小川洋子は人気作家だけに地元の図書館ですぐには借りることが出来なかったが、予約をして借りた。そこで、早速「過酸化マンガン水の夢」を読んだ。再度、小林信彦を引く・・・、(谷崎の)晩年の作品の中には、小説と随筆とのあわいのようなものがあり、これはその中での逸品と思われる。小林信彦は谷崎が好きである。私は殆ど谷崎を読んでいないので、逸品か否かは判断がつかないが、「過酸化マンガン水の夢」は、面白かった。因みに、『小川洋子の偏愛短編箱(小川洋子・編著)』には、「件(内田百ケン・門構えに月この文字ではアップできない)」「薮塚ヘビセンター(武田百合子)」「みのむし(三浦哲郎)」「雪の降るまで(田辺聖子)}など全16篇が収められている。その16篇全部は読めなかったが、「みのむし」「雪が降るまで」は好きな作品である。 小川洋子の偏愛短編箱小川洋子・編著河出書房新社2009年3月20日 初版印刷2009年3月30日 初版発行
2009.08.07
コメント(0)
-
『厳重に監視された列車(イジー・メンツェル)』
『厳重に監視された列車』の存在すら知らなかった。今年3月『英国王給仕人に乾杯!』を見て、このチェコの監督に初めて出会った。それでも、このイジー・メンツェルを知ろうとはしなかった。何たる怠慢。吾は歳を取ったのか?映画を見はじめたときは、生意気にも監督に焦点を当てるようにしていたのだが。当時は、デヴィッド・リーン、トニー・リチャードソン、ジョン・フランケンハイマーをマークしたのである。 さて、このイジー・メンツェルの特集があり、アカデミー外国語映画賞に惹かれて、『厳重に監視された列車』を見た。ほのぼのとした中の悲しみ、人の哀れさが衝撃的に描かれていた。見事である。1967年第40回のアカデミー賞は、作品賞『夜の大捜査線(ノーマン・ジュイスン)』監督賞は、『卒業』のマイク・ニコルズである。この『厳重に監視された列車』は『Closely Watched Trains』と題されている。だから、日本語のタイトルも、多分原題どおりなのだろう。また、手許にある『アカデミー・アワード アカデミー賞のすべて(監修:筥見有弘)/キネマ旬報社1995年5月1日発行』1967年度の記述に、「外国語映画賞には中村登監督の『知恵子抄』が候補になっていたが、またしてもチェコスロバキアの『厳重に監視された列車』(日本未公開)に持ち去られた」とある。(またしてもとあるには、1965年にも『怪談』が候補になりながらも、チェコの『The Shop on Main Street』が、選ばれたことによるのか?) 何がきっかけでも良いが、このように面白い・優れた未公開の作品が見られることは嬉しい。以下は、名古屋で公開の「名古屋シネマテーク」のHPからの引用である。 今春、『英国王給仕人に乾杯!』で復活を遂げた、チェコの名匠イジー・メンツェル監督(1938~)。『英国王~』のヒットを祝して、その代表作を上映します。●厳重に監視された列車 Ostre Sledovane Vlaky 28歳のデビュー作にして、アカデミー外国語映画賞を受賞した初期の傑作。第二次大戦下のチェコ。青年ミロシュは、村の新人駅員だ。鳩好きの駅長、女と見れば口説く主任など、周囲はどこか憎めない人ばかり。ミロシュも技士の少女と恋仲になった。そんな時、謎めいた美しい訪問者があらわれる。彼女は、ドイツ軍の軍用列車爆破計画をになうレジスタンスの一員だった......。本作で〈プラハの春〉を象徴する監督となったメンツェルだが、ソ連の弾圧によって、以後は"厳重に監視される"存在となる。原作=ボフミル・フラバル。今もみずみずしい、不滅の93分。初公開。
2009.08.03
コメント(0)
-
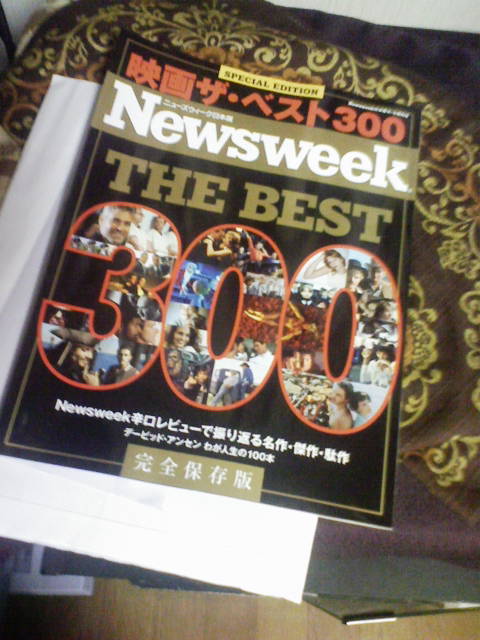
Newsweek日本版9/5増刊号『映画ザ・ベスト300』
Newsweek日本版9/5増刊号『映画ザ・ベスト300』は、ニューズウィークで映画欄担当のデービッド・アンセン個人が選んだベスト300である。まず、この企画に驚き、拍手を送る。しかも、雑誌の増刊号だから、780円と安い。もし、このようなものを単行本で出すとすれば、2500円は下らないのではないか。 デービッド・アンセンは、AFIベスト100の2007年と1998年を比較しながら、駄作は駄作、名作は名作と快刀乱麻である。引用する『スター・ウォーズ』をアメリカ映画史上13番目に偉大な作品と評価する映画通がいるだろうか。確かに面白いし、影響力も大きい。おまけに大ヒットした。だが偉大な映画芸術を評価する尺度は、そんなものではない。独創性、想像力、優れた脚本、素晴らしい技術、際立った映像スタイル、深いテーマ性・・・・・。そうした点で『スター・ウォーズ』はどれも落第だ。 自分は、『スター・ウォーズ』を封切りで観た。その時の感想は、お子様ランチでもお金をかければ美味いものが出来る、というものであった。1978年公開、キネ旬のベスト10で『スター・ウォーズ』は9位、『未知との遭遇』は4位である。1位は『家族の肖像』。 映画を批評するとは・・・、感想ではなく、批評するとは?辛口が批評ではない、しかし自らの立ち位置を自覚し、好き嫌いという尺度だけではなく映画と向き合うことが・・・、と思うのである。今一度、映画を取り上げているブロガーの一人として考えようと思う。
2009.08.01
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
-

- 特撮について喋ろう♪
- (特撮キャラ)黒影豹馬・ブラックジ…
- (2025-11-25 19:00:06)
-
-
-

- おすすめアイドル
- 乃木坂46「熱狂の捌け口」スタジオラ…
- (2025-10-25 17:37:46)
-
-
-

- 懐かしのTV番組
- ブラッシュアップライフ 第3話
- (2025-11-25 16:36:35)
-







