2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年11月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
データベースとしての蔵書
例えば、『山家鳥虫歌 ――近世諸国民謡集――』(岩波文庫・黄242-1)は、その名のとおり、「江戸中期の山家農村の民衆の歌謡398首を集めて成った、民謡の原典」と、腰巻にある。この種を自分はデータベース(資料)として手許に置いている。 この歌集の第一番に「めでためでたの若松様よ 枝も栄える葉も茂る」であり、 九番目にあるのが「こなた思へば千里も一里 逢はず戻れば一里が千里」等々、山家農村の民衆とはいえ、粋なものである。私にとって、こういう本が面白い。それらは、岩波文庫に多い。あとは、講談社学術文庫、ちくま文庫だ。
2009.11.29
コメント(2)
-
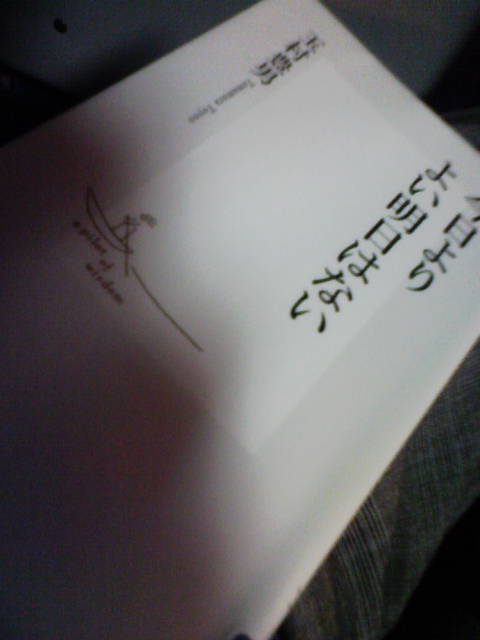
『今日よりよい明日はない(玉村豊男)』
ワイン作りや絵を描く人と言う程度の認識でしかなかった、玉村豊男の本を、知人の紹介で読んだ。まずは、本屋で立ち読み。 冒頭の部分が気に入り、図書館で借りた。 その、冒頭の部分とは、「第一章 なぜ夢を見なければいけないのか インタビューの常套句」 の所、玉村夫妻が信州の山に住み、野菜畑を作り、ブドウ畑の整地をし、それが上手く行った頃、マスコミのインタビューを受け・・・、(記者)「素晴らしい眺めですね」よく、レストランに見えたお客様から声をかけられます。(玉村)「はい、景色だけが自慢で」(記)「それに、こんなにご苦労なさって・・・」(玉)「いえ・・・」(記)「本当に、夢が実現したんですね」(玉)「・・・・・」そういわれると、私は黙って曖昧にうなずきながら、「いや、夢・・・・・ってわけでも、ないんですけど」と、内心でつぶやきます。 この本はこんな会話のやり取りで始まります。玉村夫妻の生活を、玉村氏の夢の実現であるとマスコミは規定したがるのを、玉村氏は、そうではなく、ただ色々やってきた結果でしかないのだと、インタビューアにいうのですが、なかなか話がかみ合いません。この本の、ポイントがこのかみ合わなさだと思います。 これは今更ながら言うことではないのですが、【マスコミ】は往々にして、人(=物事)はこうあるべきだという既成概念、今までの価値観で見ようとします。何故なのか?マスコミの個人個人は、そうではないのでしょうね。 さて、この本の肝心は・・・、カラーテレビで満足していたら、ブラウン管より薄い液晶がいいという。十四インチに慣れていた目には二十インチでも巨大なのに、四十インチだの五十インチだの、狭い家では近過ぎて見にくいから、家の中のテレビを窓の外のベランダから眺める始末。その上こんどは地デジに買い替えろだと?もう、いい加減にしてくれないか。携帯電話もデジカメも、最新機種を買っても一週間で古くなる。もっと新しい機種を。もっと機能が充実したものを。もっと、もっと・・・・・。そうして人が古いものを捨て、新しいものを買うことが、経済の発展・・・・・なのでしょうか。(中略)モノやカネがそれほど動かなくても、それなりに豊かな生活の質を保つ方法はあるはずです。どこかで欲望の輪郭に線を引き、いまの暮らしを肯定して、これが自分のスタイルなのだと、毅然としていうことはできないものでしょうか。p60.61この主張こそが、玉村氏の、この本の主張です。ワイン作りもしている玉山氏は、葡萄の木を例に・・・、ワインをつくるブドウの木も、古いほうがよいのです。ブドウの木は四、五年で成木になり、十五歳から二十歳くらいがもっとも旺盛な生産力を示しますが、三十歳を過ぎるとしだいに実る房の数も少なくなります。が、ワインの味は、それからがおいしくなるのです。五十歳にもなると一本の木につく房の数はせいぜい七つか八つ。全部搾ってもワインが一本できるかできないかという量ですが、そういう老木のブドウからつくったワインこそ最高級品とされています。若い頃の力はないが、知恵と経験を蓄えた人生から搾り出す、珠玉の果汁・・・・・。私は、いつもこの話を引き合いに出して、「人生も五十歳から・・・」といっているのですが、日本の農業では、果樹は三十年を目処に切り倒し、若い苗木に植え替えてしまうのがふつうです。生産量が落ちるから、というのがその理由ですが、やはり若さしか重要視していないことがわかります。p100.101もし、果樹についての指摘が、この通りなら日本の農業行政は滅茶苦茶ですね。先日ここにも書いた、農薬のこともそうでしたが・・・。 いつから、日本は若いこと、新しいことが古いことに勝ると思うようになったのでしょう?戦後(1925年以降)、高度成長期から、それとも明治維新でしょうか?少なくとも、明治以前にはそういう考え方はなかったと思うのですが。 映画も3Dが出てきました。モノクロ・スタンダードの名作群は? 『今日よりよい明日はない(玉村豊男)』2009年6月22日 第一刷発行集英社新書0498B
2009.11.28
コメント(0)
-
『風が強く吹いている(大森寿美男)2009』
箱根駅伝の再現が見事 勿論正月にTV観戦したことがないが、この再現に破綻が無いのは凄いと思った。特にスペクタクルでもなく、CGを使うわけでもなく、主人公たちの熱い思いが箱根駅伝にあるとすれば、その再現こそが必須の条件であったことが分かる。走る一点で思い出されるのが『長距離ランナーの孤独(トニー・リチャードソン)1962』。そして、スポコン物としては、『がんばっていきまっしょい(磯村一路)1998』である。不可能を可能にすることを映画のテーマにする事自体珍しくもないが、この『風が強く吹いている』が、スポコン物としても、不可能を可能にする物としても一日の長があるのは、如何にして素人ランナーが箱根駅伝に出られるかと言う過程。これは、メンバー10人のそれまでの生活と性格による分析による。『長距離ランナーの孤独』にも共通点が見られる。改めて録画してあった『長距離ランナーの孤独』を面白く見た。『バッテリー(滝田洋二郎)2006』でも好演の林遣都がここでも好演。
2009.11.21
コメント(0)
-
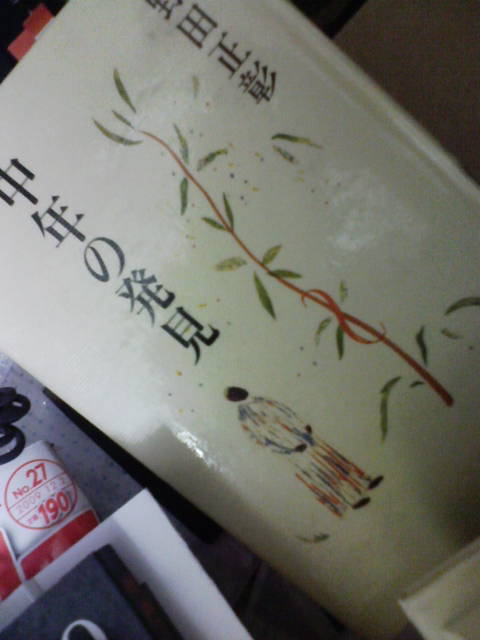
『中年の発見(野田正彰)』
『中年の発見(野田正彰)』は、『もっと、狐の書評(山村修)』(ちくま文庫)で知る。新鮮な「中年」イメージを発見する 野田正彰『人生の秋は美しい(三五館)』による。その書き出しは、こうだ・・・、悪いけど、本欄はこの『人生の秋は美しい』という書名が気に入らない。これには原本があり、その書名は『中年の発見』(新潮社、1994年)であった。と。それを読み、図書館で借りたのがこの新潮社版の『中年の発見(野田正彰)』。著者は、すべてを通して、中年になるまでに捨ててきたもの、あるいは人任せにしてきたものを、自らの手に取り戻すように言っている。儀礼の工夫 では、結婚式は、ホテルやブライダル産業が専門的に取りしきるものになってしまっている。儀礼の商品化はとどまるところを知らず、(中略)この傾向をすぐに変えることができないとしても、私たちは中年の生活を豊かにするために、儀礼や社交をもう少し生活の場に、取りもどしてもいいのではないか。気持ちのよい朝食 では、彼女(主婦)たちはいつも、あわただしく朝食を作り、家族を送り出してきている。外で働いている女性は、お皿を流しに投げ込んで自分も続いて飛び出さなければならない。(中略)子どもの時には朝があった。大人になって一日は日中のもの、夜のものに次第にずれこんできた。中年も終わりになって、朝をとりもどすのだ。 そして、極めつけは、中年心得四カ条 であり、第一に、いきいきと生きるとは、常に楽しく生きるということではない。第二には、将来の課題達成に向けて現在を耐える、あるいは頑張るといった発想から自由になることである。第三には、自分の行動の底辺にある無意識のコンプレックスについて、時々考えてみることであろう。第四に、対人関係において、人を操作的に見ないようにすることである。その他、成熟するということアルコール性管理職夫婦間のギャップ装われた楽天主義中年の遊び方素人にもどる主婦の読書異性との付きあいかたなどなど、どれも含蓄がある。著者の野田正彰氏は、1944年生まれの精神科医である。『中年の発見(野田正彰)』1994年3月15日発行新潮社
2009.11.19
コメント(0)
-
『ローマの休日(ウィリアム・ワイラー)』
NHK-BS2で見ました。途中までのつもりがついつい最後まで見てしまった。2~3度は見ているのだが、細かいところはすっかり忘れている。私服(どうみても制服)の男たちが飛行機から降りて、空港を歩くところなど、コミカルで面白い。そんなところはすっかりであった。やはり、傑作。
2009.11.18
コメント(0)
-
『スペル(サム・ライミ)』
『スペル(サム・ライミ)』の「スペル=spell」は日本でつけた題名。その意味は、呪文、まじない、まじないの文句や魔法、魔力である。原題は「Drag me to Hell」のdragとはマウスをドラッグのドラッグであろう。ということは、「私を地獄に引きずって」というタイトル。それで、思い出したのは「私を野球につれてって(バスビー・バークレイ)1949」であるが、こちらは「TAKE ME OUT TO THE BALL GAME」なので、関連はないと想う。もっとも、1949年にはコンピュータのマウスはなかったから・・・。 しかし、この原題は色々と思いが巡る。 さて、この映画は監督サム・ライミの職人芸であり「ちょいとこんなもん」と、いうところ。面白かった。ストーリなど、ご都合主義はこの手の映画としては織り込み済み、どうしてそうなるのかと問うのは野暮、時間があって何か映画という時にはもってこい。
2009.11.17
コメント(0)
-
最近観たものあれこれ
『未来の食卓』は、有機農法の話。先日書いた、『自然農法を始めました(村田知章)』と同じテーマだが、子どもたちが関わっているある村の取り組み。その記録映画。必見!! 『あの日、欲望の大地で』キム・ベイシンガーとシャリーズ・セロンがいい。乳がんの手術を機に、夫から女性扱いされなくなった(?)女、キム・ベイシンガーの不倫と、その果ての死。その娘のシャリーズ・セロンの生活ぶり、そしてシャリーズ・セロンの娘と、その父のことなど、同時に語り進む。時制が飛ぶが、それが分かりやすく尚かつ、見ていて心地よいのは何故か? 『ATOM』CGはさすがにATOMを生かす。だが、物語などは荒っぽすぎる。『ホースメン』期待しました。チャン・ツィーの悪役に。チャン・ツィーは懸命に演技をしている。気の毒なくらいだ。でも、肩透かし。わが子に無関心な親(子どもから見て)、弟に辛く当たる兄、そんな落ちでは・・・、あれほどのことが出来る?残念。『空気人形』監督の是枝裕和は1962年生まれだから、約一回り違う。私より若い。一回りの差はでかい。この映画に流れる感覚についてゆけない。レンタルビデオ屋での会話など映画好きには興味があるが、それまで。やはり、オタク文化にしか見えない。でもペ・ドゥナはいい。彼女の体がこの作品の価値を作った。今年、30歳とは思えない。同じ是枝裕和は『幻の光』を推す。
2009.11.14
コメント(0)
-

『和泉式部日記(角川ビギナーズクラシック)川村裕子編』
『和泉式部日記』は、まさに王朝のスキャンダルと言うに相応しい。恋多き女と言われている和泉式部であるが、普通に考えて、この日記は色恋の記録。この本の現代文で読む限りにおいては、軽薄なものにしか思えないのだが、原典に当たればそれはそれで格調のあるものなのだと思える。 特に、歌は素晴らしいものが多い。 流石に、和泉式部は手練れである。 こんなやりとり・・・、和泉式部=薫る香によそふるよりは時鳥聞かばや同じ声やした帥の宮=同じ枝に鳴きつゝをりし時鳥声はかはらぬものと知らずや の如くに、連綿と続いてゆく。いかにも、王朝の雅(?)である。だが、それも今から見ればだろうが・・・。原典が理解できないのがもどかしい・・・。 『和泉式部日記(角川ビギナーズクラシック)川村裕子編』平成19年8月25日 初版発行角川ソフィア文庫
2009.11.13
コメント(2)
-

『自然農法を始めました(村田知章)』
『自然農法を始めました(村田知章)』という東京書籍刊行の本です。これを読むと、今われわれが口にしているものの殆ど(100%近くが)何らかの形で薬品(=毒薬)に浸かっている。食糧不足で満足に食べることが出来なかった時代(戦後)から高度成長期にかけて、農業は頑張って沢山米や野菜を獲らなくてはならなかった、そういう時代がかつてあった。 しかし、その後飽食の時代とまで言われる今、肥満を嫌い、痩せているにもかかわらずもっと痩せたいと言う人たちが居る時代にも、食べ物はどんどん作られて、比較的手に入りやすい金額で流通している。もし、もっともっと高価であれば、それほど食べることなく適切な摂取量で人々は過ごすのではないか?といった、変なことも思ってしまう。そんな、本であった。とにかく、食べ物は恐ろしい・・・!?少しだけ、家庭菜園をやっている。農薬の散布はしていないが、化成肥料は使う。消石灰も使う。それすら、問題だとこの本の著者は語る。 だが、この著者の語るところは魅力的である。何とか自然農法でわが家庭菜園もやってみたいと思わせる。 同じ様に菌が働くのだが腐敗と醗酵の違いも納得させられる。生物ピラミッドとは、生産者:植物・・・⇒一次消費者:青虫などの害虫(草食動物)・・・⇒二次消費者:カエルなどの天敵(肉食動物)・・・三次消費者:鳥などの動物これが、自然の形であるが、農薬を使うと、青虫などの害虫が死ぬ、居なくなる。そうなると、二次消費者は生息できない。だったら、三次消費者は勿論そこには居ないことになる。農薬を使うと言うことは、そういうことである。 とにかく、農薬漬けは何とかしなくては・・・、であるが、最早逃れられないのであろうか?村田知章昭和49年東京生まれ平成9年玉川大学農学部卒平成11年自然農法農業士の資格を取得平成12年より農業を始める平成11年3月より8ヶ月間、長野県で自然農法の研修を受ける。研修終了後、茨城県結城市で畑6反(6000平方メートル)借りて農業を始める。翌平成12年に、正式に農業者の資格を県から受けて農家になり、現在にいたる。 『自然農法を始めました(村田知章)』2003年7月5日 第一刷発行2003年12月28日 第二刷発行東京書籍
2009.11.12
コメント(0)
-
『母なる証明(ポン・ジュノ)』
『母なる証明(ポン・ジュノ)』、待望のポン・ジュノ新作。今年の韓国映画は、『チェーサー』『セブンデイズ』と傑作が続く。勿論これも例外ではない。 テーマは母の愛(溺愛?)、どの母も息子への感情は凄い。例外はない。この普遍的なテーマを見事に映像にしたのが、『母なる証明』。監督のポン・ジュノ。だから、ディテールに拘っていくしかないのだが、それも概ね成功している。特に私はロングショットの美しさを評価したい。バス停の母、廃品回収業者の家から出てくる母、ファーストシーンの母などなど・・・。 だが、あざとい面もあることは否めない。それは、水の流れ。 サスペンスも充分。 息子の女子高校生殺し・・・、どうしても、過日容疑者の捕まった現実の世界とダブル。 お金と時間をかけても充分です。是非ご覧下さい。
2009.11.11
コメント(0)
-
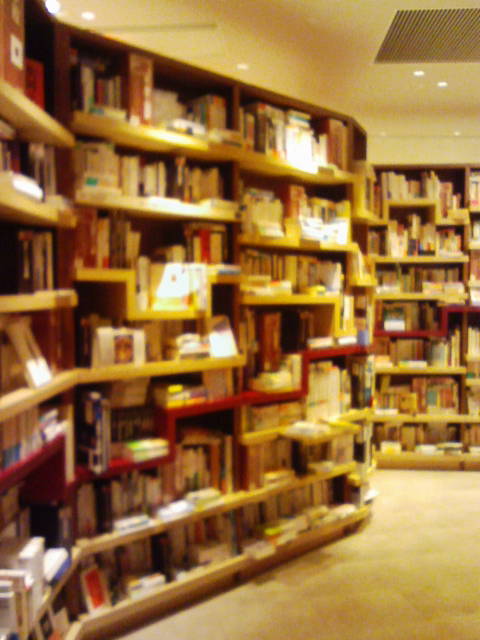
『松丸本舗』 丸善・丸の内本店4階
『松丸本舗』。松岡正剛の「千夜千冊」のサイトで知りました。上京の折に寄って見たいと思い、行って来ました。およそ一時間ほど、本棚を見て廻りましたが、それでは時間がまったく足りません。三時間くらいは居ても退屈しない空間。それも、広くはありません。例えば、ジュンク堂の池袋本店でも三時間では不足かもしれませんが、それは広いということで時間が要るのであって、『松丸本舗』とは本質的に違うもの。 本好きにはたまらない空間です。 手にした本は、「北越雪譜」「一茶七番日記」「王朝百句」「百句燦燦」など、これらは、名古屋でも書店にある。買ったのは2冊『猥褻風俗辞典(宮武骸骨)』『ロマンポルノ女優(早乙女宏美)』いずれも、河出文庫カバーはこれ・・・、
2009.11.10
コメント(2)
-
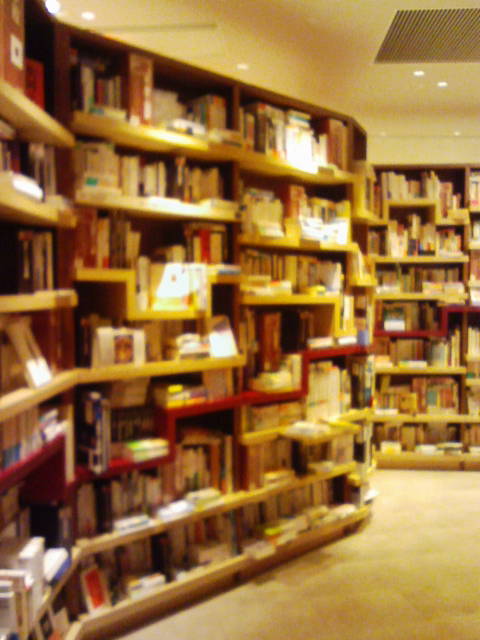
『松丸本舗』 丸善・丸の内本店4階
『松丸本舗』を、松岡正剛「千夜千冊」のサイトで発見。11月9日の状況の際に早速、出かけた。広さこそさ程ではないが約一時間うろうろとした。しかし、全体の20%も見ることが出来なかったと思う。まさに本の塊がそこにはあった。たとえて言うのは、申し訳がないがジュンク堂池袋本店は、広さ(スペース)で圧倒され、3時間は有に過ごすことができる空間であるが、こちら『松丸本舗』も3時間は有に過ごすことができる本の森(群れ)である。 一時間の間で、手に取った本は岩波文庫の「北越雪譜」「一茶六番日記」や塚本邦夫の「王朝百首」「百句燦燦」だった。しかし、これらは名古屋でも書店店頭にある。そこで買った二冊は「猥褻風俗辞典(宮武骸骨)」「ロマンポルノ女優(早乙女宏美)」いずれも河出文庫。これが、カバーです。 ちょうど昼時、その横のレストラン(?)で、丸善の早矢仕ライス、1,000円也を食す。
2009.11.09
コメント(0)
-
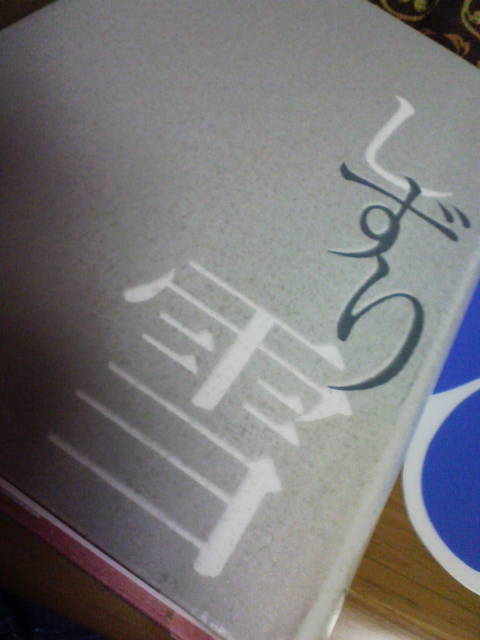
『しずり雪(安住洋子)』
『しずり雪(安住洋子)』の「しずり雪」は、安住洋子が長塚節文学賞短編部門の大賞受賞作品である。市井の人々を描いたものだ。しずり=垂り とは、「木の枝などから雪の落ちること。また、その雪。しずれ。(季:冬)。為忠百首「嵐にたえぬしずりひまなし」(広辞苑)この短編に、しずり雪は、こうある。最後のシーンだ、井戸端の椿の枝に積もった雪が、細くこぼれ落ちていく。花のまま地面に落ちた椿が半ば雪に埋れていた。(中略)一人で死んでいったのか、作次・・・・・。(中略)雪の重みでしなっていた椿の枝が身震いするように跳ね上がり、雪が舞った。孝太の頬に雪がかかる。その冷たさに、昨夜、雪の中で凍えていく作次を感じた。手を伸ばし、枝の雪を掴む。握ると冷たさが掌に切れ込んでくる。そのまま雪の中に膝をつき、雪を掴んでは握りしめていた。その冷たさは骨までしみ入ってくる。(中略)顔を上げると、枝から絶え間なく雪がこぼれ落ちていた。 やや、ありきたりの表現だと思うが、この雪の美しさが伝わってくることに違いは無い。『しずり雪(安住洋子)』しずり雪/寒月冴える/昇り龍/城沼の風(一、虎落笛・二、狭霧)2004年4月10日 初版第一刷発行小学館
2009.11.08
コメント(3)
-
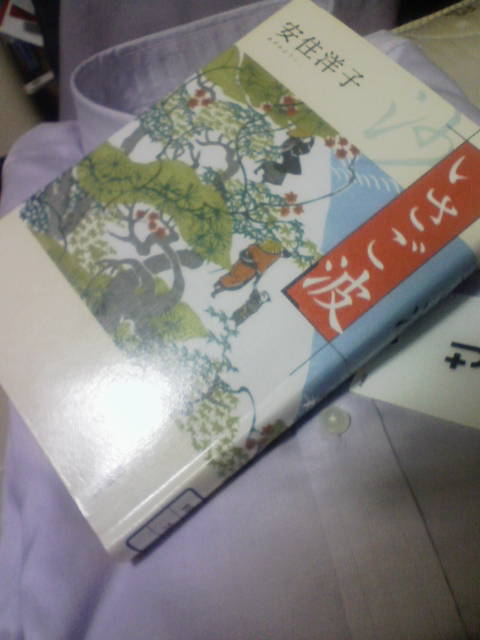
『いさご波(安住洋子)』
新潮社のPR誌「波」11月号の26ページ、評論家生命を懸けて保証する、と銘打って文芸評論家の縄田一男が、安住洋子の『いさご波』を紹介している。それを読んで、読んだ。縄田氏は、現在の出版のやり方が文芸を売る、というより興行を打つようなやり方に変ってしまったことに危惧を感じる、と、書いている。下級武士を描いている点など、藤沢周平を所々思わせる。藤沢ほどの深さは未だ無いが、今後が楽しみである。安住洋子・・・1958年、兵庫県尼崎市生まれ。1999年、「しずり雪」で第三回長塚節文学賞短編小説部門大賞を受賞。もう一冊『しずり雪』も同時に借りたので、これから読もうと思う。『いさご波(安住洋子)』2009年10月20日 発行新潮社
2009.11.04
コメント(0)
-
『ハンナとその姉妹(ウッディ・アレン)1986』
『ハンナとその姉妹(ウッディ・アレン)1986』。双葉十三郎の採点は☆☆☆☆(だんぜん優秀)。「まことにみごとである」との寸評。 こういう大人のドラマは近年記憶に無い。ウッディ・アレンはセックスも何もかも比較的開けっぴろげにするが、一方クリント・イーストウッドはストイックだ。『マディソン郡の橋』にしても例外ではないと思う。ただ、二人の共通なのはJazzであろうか。 家庭劇はすべからくそうなのかもしれないが、この『ハンナとその姉妹』には小津の影が見える。ハンナとその姉妹(1986)HANNAH AND HER SISTERS
2009.11.03
コメント(0)
-
『クヒオ大佐(吉田大八)』
『クヒオ大佐(吉田大八)』予告編の方が、良かった。予告編は、その映画のさわりバカリの連続だが、この「クヒオ大佐」の場合は、落差がありすぎた。 詐欺師の映画に期待する、切れ味が無かった。一方で、このクヒオ大佐の詐欺師としての切れが無かったのはあえてそうしたのかもしれないが、自分は与しない。だまされる女もだます男も、今までのパターンとは違うものである。金のそれほどあるとは思えない女、それほど頭が切れるとは思えない男。その組み合わせでこれを作ることが監督の狙いであったのか?それはそれでOKなのだが・・・、思いの外短かった上映期間も、その期待値との落差が出たのかもしれない。 売り方を間違えた。
2009.11.01
コメント(0)
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-
-
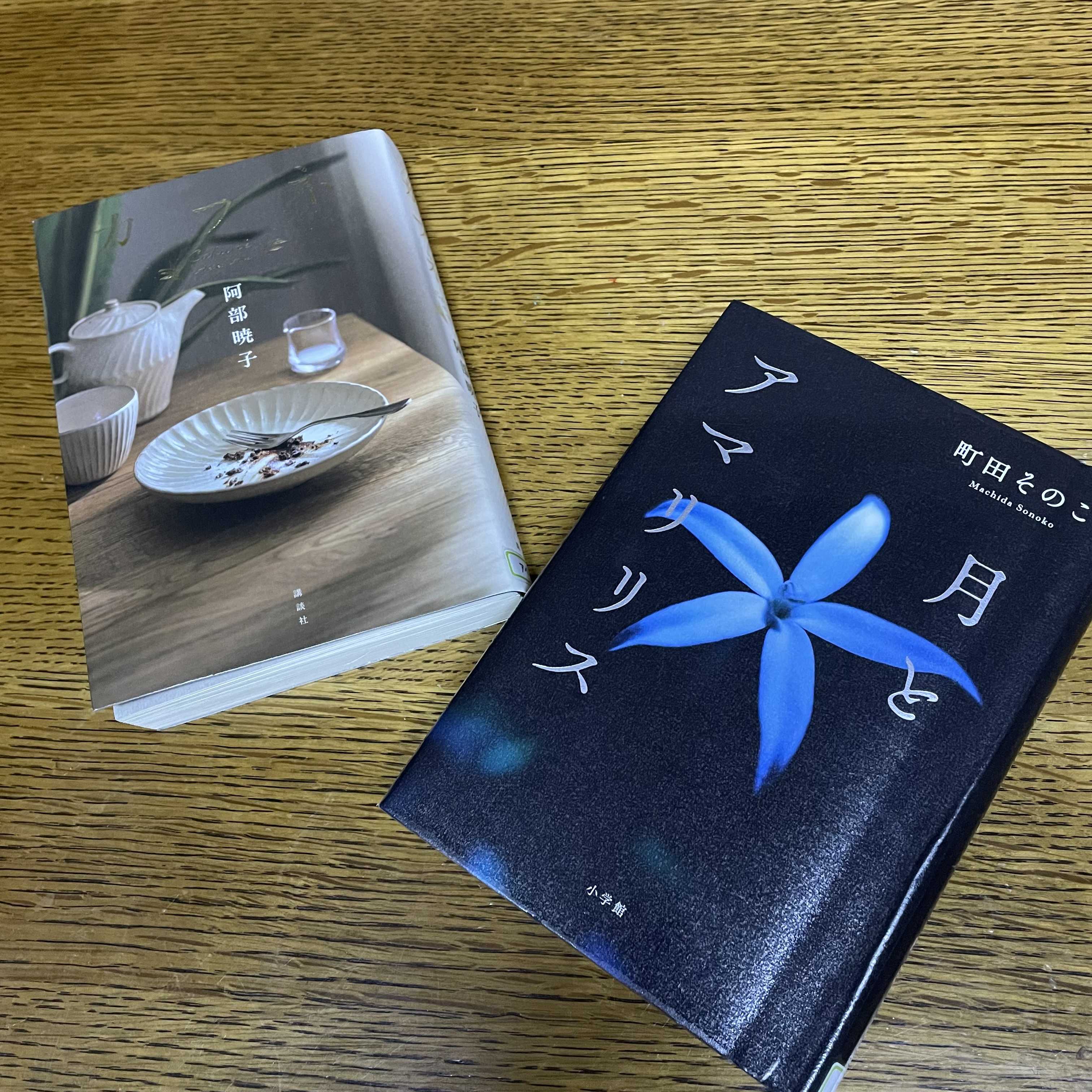
- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-
-
-

- ペ・ヨンジュンさま~♪
- 「ヨン様」の名付け親が初めて語る韓…
- (2023-12-02 17:40:56)
-
-
-

- 今日見た連ドラ。
- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…
- (2022-01-28 23:32:16)
-







