2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年10月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
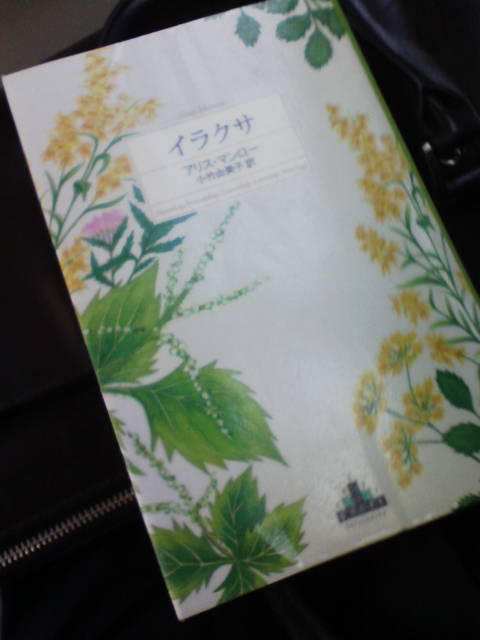
「クマが山を越えてきた(アリス・マンロー)」
短編集『イラクサ(アリス・マンロー)』に収録されている「クマが山を越えてきた」。この短編は映画『 アウェイ・フロム・ハー 君を想う(2006)』の原作である。ある人から、この映画について訊ねられ、寡聞にして知らなかった。探し当てたら、映画は『アウェイ・フロム・ハー 君を想う』であり、原作は「クマが山を越えてきた」だった。 物語は、長年連れ添った妻が認知症になり、施設に入る。そこで、その妻は施設にいる男と仲良くなり、自分の夫のことが分からなくなる。その男が施設を出て自宅に帰った後、その妻は急に元気を無くす。夫は、その男のところに行きその男の妻に、施設にその男に戻ってもらえないかと、依頼しに行く・・・。 そういう物語。映画を観ていないので、何とも言えないが、話をしてくれた人によれば過去と現在が入り乱れた作り方のようで、分かりづらいものであったらしい。原作を読んでも簡単ではない。映画を観てから・・・、この続きはいずれ。イラクサ(アリス・マンロー)小竹由美子 訳2006年3月30日 発行新潮クレストブック
2009.10.29
コメント(0)
-
次世代自動車振興センター
一般社団法人次世代自動車振興センターってご存知でした? 先日、そこからはがきが来ました。何故? それは、エコカー減税と共に実施されている、補助金交付の手続きをしている所。詳しくは、こちらへ。 まったく知らない団体でした。このHPからも分かりますが、次世代自動車振興センターは、平成19年(2007年)2月19日に財団法人日本自動車研究所から独立し、経済産業省からの委託を受けて次世代自動車の購入者に補助金を交付する団体として活動を開始しました。 財団法人日本自動車研究所から独立、だそうです。こうすれば、また天下り先が一つ増えることになるのですよね。これで、そのトップに立つ人が一人増えるわけですよね。もし、この業務を「財団法人日本自動車研究所」がやっていれば、増えないわけですよね。退職金も、給料も・・・。これが、からくりの一つでしょうか? 今回の日記、南包には珍しい内容になりました。
2009.10.28
コメント(0)
-
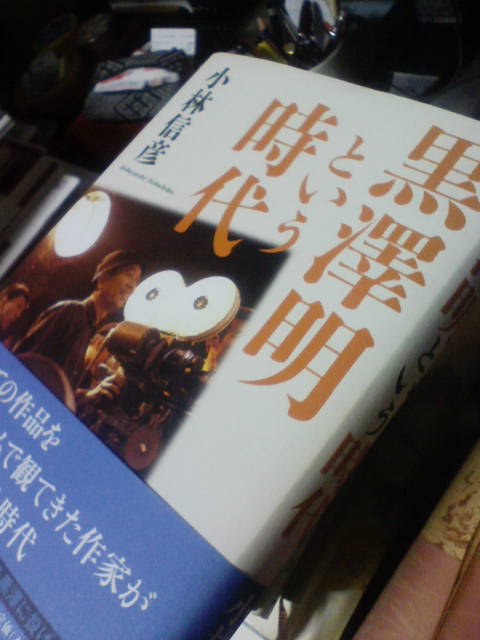
『黒澤明という時代(小林信彦)』
腰巻には、すべての作品をリアルタイムで観てきた作家が読み解く映画と時代第一作の『姿三四郎』から、『まあだだよ』までの全30作を小林信彦流に取り上げてある。いままでの小林信彦の著作以外の視点が多くあるのは読者の一人として有り難い。それと、このような書き方をしている点も小林信彦のストイックさがわかる。ゴミを大量に投入する。こうして、<おそらくは、日本の映画美術史上、屈指の傑作のひとつ>(佐藤忠男氏)である闇市のオープン・セットが出来上がった。『酔いどれ天使』例えば、この佐藤発言は『酔いどれ天使』ではすでに評価の定まったものであったとしても、佐藤氏が最初に言ったということをきちんと出している点について、そう言うのである。日本のジャーナリズムは、アメリカのアカデミー賞は知っていたが、ヴェネチア国際映画祭を知らなかった。だから、九月にグランプリときいても、すぐには、意味がわからなかった。私(小林)は日本のジャーナリズム、特に職業的映画批評家に不信の念を抱いた。その気持ちは、いまだに変わっていない。『羅生門』 奇怪な〈日本側の戦後検閲〉で七年近くおクラ入りしていた不幸な「虎の尾を踏む男達」が、この年(1952年)の四月二十四日に初めて公開されている。好評ではあったが、あまり話題にはならなかったと記憶する。映画はすぐに公開されないと駄目だと思う。この年の黒澤映画は『生きる』である。 「生きる」のシナリオ(時間順に主人公の死までを追ったもの)を読んで怒り、後半を葬式にしてしまえ、と言った戦前からのベテラン脚本家である。その人は、小国英雄と言う。 一九八二年五月、カンヌ国際映画祭三十五周年記念として、黒澤は〈世界の十大監督〉の一人に選ばれている。 特に、戦時中に「姿三四郎」で登場した時の鮮烈なイメージは、ビデオやDVDで〈黒澤明を観た〉世代には想像もできないと思う。これは確信がある。名画座で観た世代とも話は合うまい。黒澤明に限らず、映画は封切られた時に観なければ駄目なのだ。 小林信彦はこう言う。特に〈映画は封切られた時に観なければ駄目なのだ〉と。こればかりはどうしようもない。生まれたときにそれが無ければどうしようもないのだから。しかし、それでよいのだと、小林発言を肯定している自分がいる。映画は時代と共にある。だが、クラシックと言う部類に入った映画には時代を超えた力があるのだと思う。老婆心ながらここで言うクラシックとは、古典と言う意味のみではなく。一流と言う意味も込めている。 この本で最も面白かったのは、野村芳太郎発言の部分である。野村監督が、一九七七年暮に、突然、こう言ったのである。「黒澤さんにとって、橋本忍は会ってはいけない男だったんです」「醜聞(スキャンダル)」「白痴」のニ作で〈名助監督〉と黒澤明が認める男の言葉である。「え?」「そんな男に会い、『羅生門』なんて映画を撮り、外国でそれが戦後初めて賞などを取ったりしたから・・・映画にとって無縁な、思想とか哲学、社会性まで作品へ持ち込むことになり、どれもこれも妙に構え、重い、しんどいものになってしまったんです」ムッとした橋本は言いかえす。「しかし、野村さん、それじゃ、黒澤さんのレパートリーから『羅生門』『生きる』『七人の侍』が?」「それならないほうがよかったんです」以下、野村監督の発言の要約・・・と、小林は書く〈・・・・・それらがなくても、黒澤さんは世界の黒澤になっています。現在のような虚名に近い存在ではなく。僕は黒澤さんにニ本ついたから、どれほどの力があるかを知っています。彼の映像感覚は世界的レベルを超えている。夾雑物がなく、純粋に映画の面白さのみを追求していけば、彼はビリー・ワイルダーにウィリアム・ワイラーを足し、二で割ったような監督になっています。ビリー・ワイルダーよりも巧く、大作にはワイラーよりも足腰が強靭で絵が鋭く切れる。文字通り、世界の映画の王様に・・・・・〉その場で、橋本氏は反論が出来なかった。 ここで、見逃してはいけないのは当然であるが、【映画にとって無縁な、思想とか哲学、社会性まで作品へ持ち込むことになり、どれもこれも妙に構え、重い、しんどいものになってしまったんです】と言う部分。特に【映画にとって無縁な】と、野村監督が言い切っているところだ。これは、『複眼の映像(橋本忍)』からのもので、小林信彦は、この本をこの野村芳太郎さんの言葉に接した瞬間で、云々とあとがきでに書いている。 もう一つ、野村監督の言葉を紹介すると・・・、一九七五年、スピルバーグの「JAWSジョーズ」の試写のあとで、野村監督は橋本忍氏に「橋本さん・・・・・・これからスピルバーグの映画はもう見ることはありませんよと言い、重ねて、「映画の監督を一生やってたって、そんなの(NGカットのない映画)は一本できるかどうかですよ。だから彼には、この『ジョーズ』が最高で・・・・」云々。鋭すぎてついて行けない。『黒澤明という時代(小林信彦)』2009年9月15日 第一刷発行文藝春秋
2009.10.26
コメント(2)
-
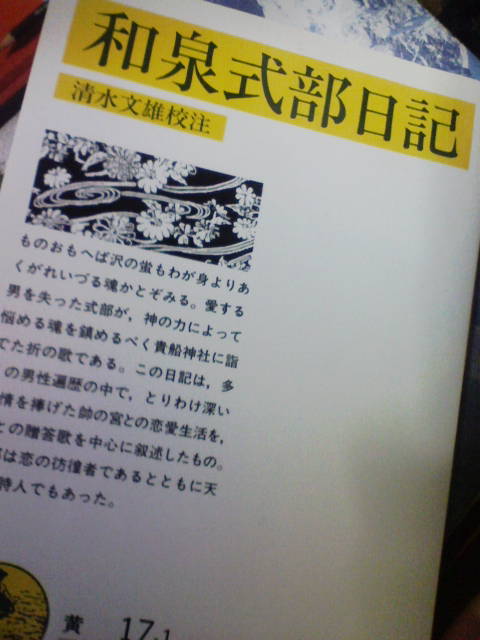
『和泉式部日記』
「和泉式部日記」を入浴しながら読んでいます。原文は流石に難しいので、現代語訳が同時に掲載してある初心者向けの「和泉式部日記」です。勿論、手許には原文の岩波文庫も置いています。まだ、初めの数ページですのでなんとも言うことはないのですが、和泉式部と亡き為尊(ためたか)親王とその弟の敦道(あつみち)親王との物語。主に、歌(短歌)のやりとりで話がすすむ。雅?今から思えば「雅」? しかし、当時はそれが当たり前。読了は先になりそう。岩波文庫版
2009.10.20
コメント(0)
-
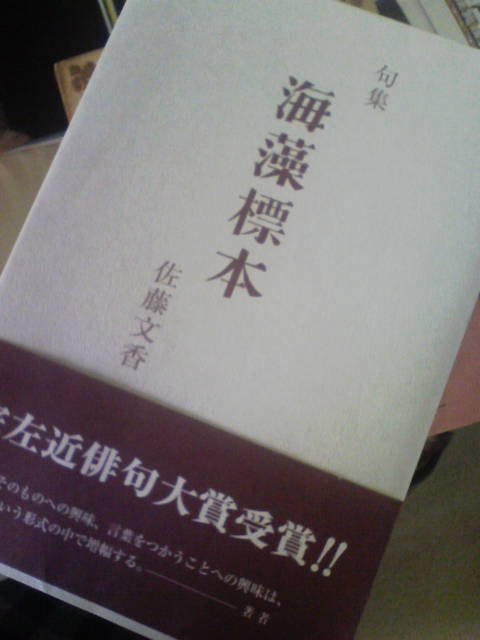
『句集 海藻標本(佐藤文香)』
俳句を読む。自分で作るのではないので、「詠む」ではなく「読む」。佐藤文香の『海藻標本』昭和60年(1985)生まれ、だから現在24歳。この句集が発行されたのが、2008年なので、23歳の時のもの。「序」を池田澄子が寄せている。俳句甲子園で最優秀賞を得た、いわば記念碑的な「夕立の一粒源氏物語」を、文香はこの第一句集を編む時点で捨てた。見事な根性である。そして確かに句集の作はその句を超えている。この健気を以て更に、俳句形式を悦ばせる俳人になっていくだろう。大変なライバルの出現である。では、『海藻標本』から・・・、少女みな紺の水着を絞りけり靴箆の後ハンケチを渡しけり草笛に草の名前のありにけり秋の野にゐてポケットのある不便狂ひ花短き釘を買ひ揃へ青に触れ紫に触れ日記買ふ晩春の買へば臙脂のものばかり国破れて三階で見る大花火などなど『句集 海藻標本(佐藤文香)』2008年6月3日 初版発行 2009年6月3日 第二刷ふらんす堂
2009.10.18
コメント(0)
-
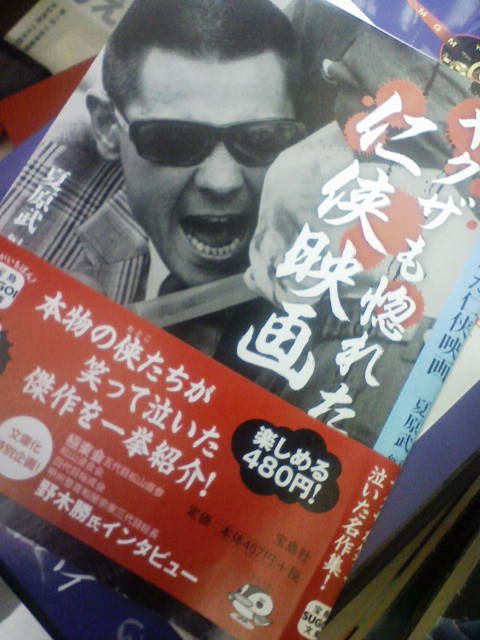
『ヤクザも惚れた任侠映画(夏原武編)』
本物の侠(おとこ)たちが笑って泣いた傑作を一挙紹介!楽しめる480円!これを読まなきゃ仁侠映画は語れない! と、腰巻にある。風呂に入りながら、少しずつ読んだ。熱くない湯に浸かりながら読むのに適した、生ぬるい本だった。 唯一、三池崇史の数々を紹介していたのがいい。こういう独断がないとこの手はつまらない。『ヤクザも惚れた任侠映画(夏原武編)』2009年4月18日 第1刷発行宝島SUGOI文庫
2009.10.17
コメント(0)
-
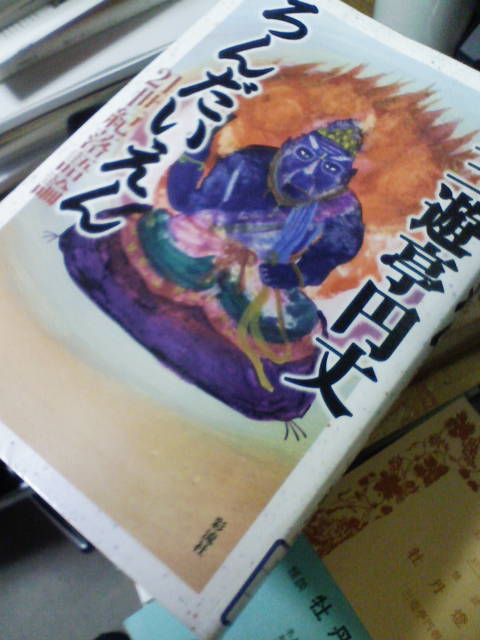
『ろんだいえん 21世紀落語論(三遊亭円丈)』
落語会の異端児、三遊亭円丈である。前の『御乱心』以来。円丈は新作、新作で落語界を生き抜いてきた人。その意気込みや凄まじい。そして、今の落語ブームが円丈の落語とリンクし始めた。もはや、単なる古典落語は受け入れられないようだ。古い言葉遣いや風習、風俗が伝わらないからだ。円丈曰く、昭和50年以降そうなった。江戸の面影が日本全国から消えたと、円丈は言う。そして、新作への想い・・・、いつも「次に作る一作こそ、未だかって見たことがないほど、おもしろい新作になるはず・・・」と作り続けている。これは、チャップリンがネクスト・ワンといっていたことと同じ。風習・習慣としてあった「江戸」 それから春歌は昭和五十年代まであったが、カラオケが登場して春歌を唄う者はいなくなった。やがて生活習慣の中からも「江戸」が知らない間に消えていった。「芸は砂の山」 円丈の師匠、六代目三遊亭円生のことば、「師匠、どうも落語ってネタおろしのときはウケて、二回目のときはあまりウケなかったというのがよくあるんですが、どうしてなんでしょう?」「そりゃ、芸は砂の山だ!芸というのは砂の山。いつも少しずつ崩れている。私の芸はここまで上がったと思っても、なにもしないとずるずる、ずるずると落ちてくる。(略)ネタおろしのときは緊張して全力でその落語をやっているが、二回目になると、前にやったから少し安心して手を抜く。しかもそれから稽古もしてなきゃ、ウケなくて当然なのだ。芸は砂の山だ。何もしないと芸は下がる」最後に・・・、客として見るときのチェックポイント(1)芸人の目が生きていたか?(2)持った湯飲み丼の大きさはいつも一定か?(3)モノの重さや大きさが伝わるか?の、三項目。これは、基本ができている噺家かどうかということ。ろんだいえん 21世紀落語論三遊亭円丈2009年6月10日 初版第1刷彩流社
2009.10.16
コメント(0)
-

『狙われたキツネ(ヘルタ・ミュラー)』
承前 図書館で借りました。今年のノーベル文学賞。『狙われたキツネ』ドイツ文学セレクションの一点として出版されたもの。もしかしたら、ヘルタ・ミュラーの邦訳は是一点かも知れません。因みに、今年のイギリスの賭けでは、この人は第六位で村上春樹と同じだったようです。これから読みます。さてさて最後まで読めますかどうか。狙われたキツネヘルタ・ミュラー山本浩司・訳三修社1997年3月31日 第一刷発行
2009.10.11
コメント(0)
-
2009年ノーベル文学賞と積読
2009年ノーベル文学賞 ドイツのヘルタ・ミュラー氏(58)に決まった。新聞で知る。作品は勿論、名前も知らない作家だ。 新聞によると、邦訳は「狙われたキツネ」がある。1992年に出たものらしい。調べる・・・、図書館にあった。明日借りに行く予定。 昨年の受賞者 ル・クレジオは、学生時代友人が読んでいたので知っていた。だが、読んではいない。 一昨年の受賞者 ドレス・ドレッシングは、知らなかった。1冊借りて途中まで読んだ。1冊、文庫本が出たので買ったが、未だ読んでない。 2006年のオルハン・パムクも、勿論知らなかったが、受賞後作品が書店に並び、「私の名は紅」を買い、読み始めたが、いまだ途中。「雪」は買ったのみ。 さて、さて・・・、米アカデミー賞の外国語映画賞の作品「厳重に監視された列車」を今年見たことは、ここにも書いた。この監督も作品もまったく知らなかった。 事ほど左様に、作家にしても映画監督、画家そのほかあらゆる分野に全世界には面白いもの(素晴らしいもの)を出している人々がいるということである。 賞を出す方の情報量の問題もあるのだろうが、日本のマスコミは今回のヘルタ・ミュラーのことなどこれっぽちも事前には触れていない。というより、日本の誰もが待っているような書き方をしている、村上春樹のこともさほど今回は取り上げなかったようにも思った。
2009.10.10
コメント(0)
-

Sweets Magic
名古屋のスゥーツです。ようやく口に入りました。発売当時は、ネットのみでそれも数ヶ月待ちということのようでした。態々頼む気はなかったのですが、見つけました。1個、630円(税込み)のプリン。名古屋パステルのなめらかプリンの開発者が作ったプリン。 プリント思うと、凄いな~です。でも、この食感や味は、他にもあるような・・・、です。 機会があれば、お試しあれ。美味かったよ。
2009.10.05
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- おすすめ映画
- サマー・ウォーズを観ました
- (2025-11-24 00:18:47)
-
-
-
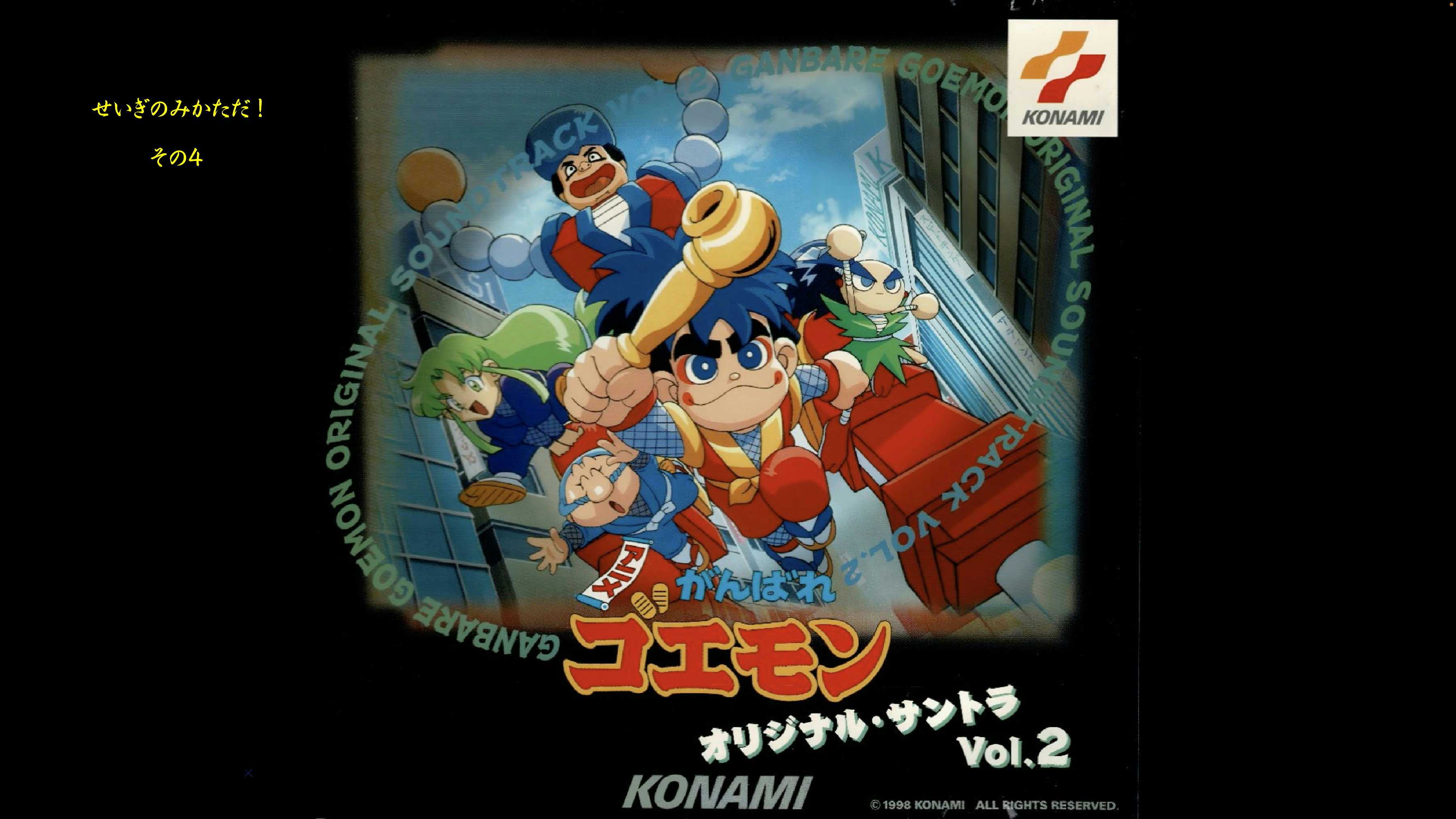
- アニメあれこれ
- お知らせ(今日3):YouTubeに 【ア…
- (2025-11-25 21:16:58)
-
-
-

- 今日見た連ドラ。
- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…
- (2022-01-28 23:32:16)
-







