2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2009年05月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
『定家明月記私抄 続篇(堀田善衛)』その9
建保二年~六年(1214-1218)記 定家五十三歳--五十七歳 有心様だの長高様だとか幽玄様だとか言っても、それはもうどう説明をするにしても、現代日本語にはなじまないものである。それぞれの時代の文化は、それぞれの言葉に託された暗黙の信号を含むが故に文化なのである。文明は説明可能なものによって成る。/たとえば三十七歳のときの仁和寺宮五十首などの完成された歌、大空は梅の匂ひにかすみつゝくもりもはてぬ春の月の夜霜まよふ空にしをれし雁が音(ネ)のかへるつばさに春雨ぞ降る春の夜の夢の浮橋とだえして嶺に別るゝ横雲の空という、絵画的といっても音楽的といっても、到底言い尽すことの出来ない、言葉の解説を一つしたにしてもぶち壊しになる、朦朧たる世界の構築。 かきやりしその黒髪の筋ごとにうち臥す程は面影ぞたつあしの屋に蛍やまがふあまやたく思ひも恋も夜はもえつゝいかにせむ浦のはつ島はつかなるうつゝの後は夢をだに見ず あたかも思い悶える女性の肉体を思わせ、あるいは言葉合せの極限だけで内容皆無かと見せながら、そこに乱れ髪のような官能美・エロティシズムを匂わせる歌。(中略)エロティシズムはマラルメとともに、世界文学の最高の水準に達したものである。そうして、こういう歌が建保三年でまだ三十六歳の壮年にある後鳥羽院に受け入れられないということも、充分に想像出来るのである。 長々と引用したが、ここで気になったのは、『暗黙の信号を含むが故に文化なのである。文明は説明可能なものによって成る。』の部分。この【句】いいよね、凄いね。この【絵】素晴らしいね。この【映画】傑作だよね。などなどその感動を説明すればするほど掬ったものが指の間から乾いた砂が零れ落ちるように感ずることがあるのと同じように思うのである。
2009.05.31
コメント(0)
-
『定家明月記私抄 続篇(堀田善衛)』その8
まだまだ、続きます。引用を続けます。建暦二年(1212)記から 定家五十一歳天皇が、漁労の民、商工業者、諸芸人--すなわち遊女、傀儡、舞女白拍子等の遊芸者集団--などの、「非農業民」の保証者であった可能性は事実として非常に高いのである。しかも、そう理解してはじめて、たとえば多くの勅撰和歌集に、遊女だけではなく傀儡の歌などもが採用されていることが、それとして理解できるのである。多くの遊女や白拍子は、後鳥羽院の宮廷へは、ほとんど木戸御免である。また公卿であって遊女、舞女、白拍子などを母としている人も珍しくも何ともないということ、さらには、これらの女性を母とする皇子もいたことなども、理解出来る筈である。中世にあって彼等、また彼女等は賤民などではなかったのである。 今の戦国武将ブームの中で注目の前田慶次郎などの歌舞伎者(カブキモノ)や出雲の阿国は、前にここで書いた「ホモルーデンス」の代表と思うが、そういう人々がその後の武家の世では「賤民」として身分の低いものになったのか。そして、それを裏付けるように、源実朝のことが実朝は「事ノ外ニ武ノ方ヨリモ文ニ心ヲ入レタリケリ」(吾妻鏡)であったから・・・、実朝は武士でありながら、「武ノ方ヨリモ文ニ心・・・」であった。強引に言えば、文=遊び=ホモルーデンスとうことなのだ。武=真面目なのだ。その武の血を引くのが今の政府=官僚なのだと思う。因みに、今の政府に遊び心はあるのか?その政府がアニメの殿堂などと血迷ったことを考えて本当にいいのか?アニメなんというものは、遊びの最たる物では・・・? 色恋は遊びだと平安人はそう思っていたし、それ以外の色恋はなかった。そこで生きるの死ぬのは論外であった時代である。その血を引いてこその遊びなのだが。 ※特記『塩原多助一代記(三遊亭円朝)』岩波文庫読了。
2009.05.30
コメント(0)
-
『定家明月記私抄 続篇(堀田善衛)』その7
『定家明月記私抄 続篇(堀田善衛)』その7 正編からの続きでその7です。 建暦元年記(1211)定家50歳から・・・、 この年は歌人としての定家はまったく用無しであり、作歌はわずかに四首のみ。/明月記の記する限りにおいては、もっとも時間をとられているのは、後鳥羽院の有職故実(※1)に寄せる情熱、すなわち古儀典の復活とその習礼(シフライ)、すなわち予行演習に関してであった。それは院の興味が次第に政治に移行していることを意味するであろう。礼儀がすなわち政治そのものであるのが宮廷というものなのである。 承久三年記(1221)定家60歳から・・・、 定家の父俊成は、子孫の栄達をねがって、「春日野のおどろの道の埋れ水末だに神のしるしあらはせ」と歌っている。すなわち、「春日野のいばらの生い茂った道の埋れ水のようなわが一族の、せめて子孫だけでも神の御験(シルシ)を顕して世に出させてください」と言っているのである。春日野は氏神である春日明神を暗示し、おどろの道は、棘路、すなわち公卿の意に通じ、埋れ水は、出世の遠い自身を暗に言い、末は子孫であり、道の縁語でもある。/何と面倒な、と言われる方もあるであろうが、元来社交礼儀とは、入り組んだ手続きを踏まなければならぬものであり、その手続きそのものが社交礼儀なのである。 定家50歳と60歳の引用である。10年の間に同じ思いがず~っと定家の心にあったのだろうと想像できる。 即ち、宮仕えとは、元来こう言うことを指し示すのであり、今でも組織で物事を進めるに於いての手続きは、当時となんら変ることがないことが良く分かる。この手続きに様式の美しさを見出す時、やや乱暴に言えば、その見出した人はマゾヒスティックな喜びを感じるのかも知れない。まさに自己犠牲以外何者でもないであろう。 そして、導き出されるものは政治とは手続きである、と言うことだ。 (※1)朝廷や武家の礼式・典故・官職・法令などに関する古来の決まり。
2009.05.24
コメント(0)
-
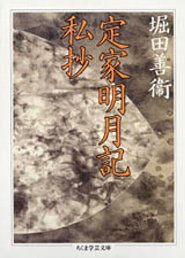
『定家明月記私抄 続篇(堀田善衛)』
去る、3月20日の日記から丁度2ヶ月。『定家明月記私抄(堀田善衛)』『定家明月記私抄 続篇(堀田善衛)』の2冊を読了しました。 これも、読むと素晴らしい。 久しぶりに、興奮した本です。詳細は次回から・・・。定家明月記私抄堀田善衛ちくま学芸文庫1996年6月10日第一刷発行2006年11月30日第三刷発行 定家明月記私抄 続篇堀田善衛ちくま学芸文庫1996年6月10日第一刷発行2008年11月32日第四刷発行
2009.05.20
コメント(0)
-
『子供の情景(ハナ・マフマルバフ)』
「子供の情景」 相変わらず、イラン映画の子供たちは素晴らしい役者である。それも、今回の少女はたかだか6歳である。その少女は学校に行きたいばかりに、ノートと鉛筆を買う多ため片手に2個ずつ卵を持って売り歩く。 小さな手に卵2個、いつ落とすかとはらはらする。だが、周りの大人たちはそういう少女をそのように見ていない。それが彼らの日常なのだろう。 卵を持って歩く所、ノートを持って学校に行く所は、「友だちのうちはどこ?(1987)」を髣髴とさせる。チラシに「6歳の少女の小さな冒険・・・」とあるように、学校に行く途中、少女は様々な目に会う。戦争ごっこの子供たちの妨害や、犬に行く先を阻まれることも。(これは「パンと裏通り(1970)」のオマージュか?) ようやく学校にたどりつくが、そこは男の子の学校、先生は冷たく、「ここは男の子の所だから、女の子の所にいきなさい」と。少女は、再びノートを片手に女の子の所に歩いていく。ようやく辿り着いた学校での鉛筆代わりの口紅による遊びは見事だ。勉強したいという子供が、あれである。 さて、始まりと終わりは、バーミヤンの仏像破戒シーンである。そういう背景の中で、子供たちは無邪気に生きている。特に戦争ごっこをしている男の子たちこそが焦点をあてられて、もっと語られなければならない対象なのだとこの映画は語りかけてくる。だが、この映画は飽くまでも学校に行きたい少女に焦点をあてている。 円の中心は一つ。それが二つになると楕円になる。学校に行きたい少女を一つの中心に、戦争ごっこをする子供たちをもう一つの中心に据えた楕円を描いている。そしてそこには、戦争という現実を抱えながら現実の生活をせざるをえない、どうにもならない大人たち〈現実〉が居る。 学校の帰り、少女は再び戦争ごっこの子供たちに会い玩具の銃で撃たれ倒れる。そこでの「死ねば自由になる」という言葉のみが重い。
2009.05.15
コメント(0)
-
『定家明月記私抄』番外編
『定家明月記私抄』番外編です。過日、『ホモルーデンス』に触れたことがある。それに関連して・・・。それからの連想と余計な勘ぐりと、老婆心から、後白河上皇〈法皇)について書かれているところに遡る。 「後白河法皇死」(建久三年記)の章から、伎芸のことが出て来たからには、後白河の流行歌狂いのことも言及しておく必要があろう。御承知のように、後白河は、『梁塵秘抄』を編輯させた人であり、『梁塵秘抄口伝集』には、「そのかみ十余歳の時より今に至るまで、今様を好みて怠る事無」く、「四季につけて折を嫌はず、昼は終日(ひねもす)謡ひ暮らし、夜は終夜(よもすがら)謡ひ明か」して「六十の春秋」を経た、と述べている。 なおこの法皇に関してもう一つのことを付け加えておこう。後白河は日本の代表的春画の絵巻物『小柴垣草子』というものの、説明文章の筆者と伝えられている。これは、ある皇女と警護の武士との性交物語であり、その二人の男女、また乳母も加わっての、ありとあらゆる性交のかたちが画面に描き出され、後白河はこれに注釈を加えているのである。やりもやったり、とでも言うべきか。 問題の、絵巻物『小柴垣草子』を、橋本治の『ひらがな日本美術史2』が取り上げている。「その三十・・・・・・科学するもの『小柴垣草子絵巻』」である。 《小柴垣草子絵巻》には、《灌頂の巻》という別タイトルもある。”灌頂”というのは、頭のてっぺんに水を注ぐことである。仏道に入るための儀式として、密教の方にはある。(中略)《灌頂の巻》という別タイトルが与えられている《小柴垣草子絵巻》の内容は、だから、”性の洗礼”というようなものなのである。/洗礼を受けてそこに入って行くのは、当然”性の未経験者”である。女なんら当然処女で、その処女は、わざわざ「灌頂」という特殊に宗教的な言葉を与えられるような位置にいた人だということである。/平安時代には、賀茂神社と伊勢神宮という二つの大きな神社の神に仕える、”斎院””斎宮”と呼ばれる特別な未婚の女性がいた。”特別”というのは、この女性たちが内親王をはじめとする皇族の娘たちだったからだ。 このように、興味本位にこれ(『ひらがな日本美術史2』)を取り上げたが、相変わらず良い仕事をしている、橋本治が『芸術新潮』に連載したもので、全7巻ある。機会があれば、是非手にとって見ていただきたい本である。 青文字=定家名月記私抄の引用緑文字=ひらがな日本美術史の引用
2009.05.09
コメント(0)
-
『フロスト×ニクソン(ロン・ハワード)』
『フロスト×ニクソン(ロン・ハワード)』です。4日間、フロストはニクソンにインタヴューをする。本音を引き出そうというのが目的、ニクソンを法廷に引き出すのだと。 3日目までは、フロストの完敗。しかし、最後の日に・・・、奇跡が起きた。そう、奇跡が起きたとしか思えない展開。見ていない方の為にこれ以上は書けない。 さて、ニクソンを演じた、フランク・ランジェラが素晴らしい。最後の、放心したような表情。まさに、完璧な勝利が我手からすり抜け、敗北を喫した男の顔である。そういうことを演技できる見事さに、拍手。 ディテールは別にしても、この話の結末らしきものは分かる。だから、敢えて奇跡が起きたと書いたのも別段不思議でもなんでもない。この手の映画の、予定調和でもあるからだ。だが、しかし、この最後の展開に如何に表現しながら持っていくかが、監督の力量だ。何を描くかではなく、如何に描くかである。如何に役者を表現するディテールとするかでもある。その見本のような一本だ。
2009.05.08
コメント(2)
-
『定家明月記私抄(堀田善衛)』その6
1203年の記録。パルナッス:聖所 (転じて)詩壇,文学界建仁三年〈1203年〉 日本のパルナッス(Parnasse)は連続放火の火に映えていた。一言で言って、これがデカダンスというものである。一つの文化文明がデカダンスにおちいり得るだけの高さに達することが出来るという、歴史的機会もまた滅多には訪れてくれないものである。と、堀田善衛は当時を分析する。 その時定家43歳。4月に後鳥羽上皇に、新古今和歌集のための撰歌を献じている。まさに、歌壇爛熟の時である。 それを、堀田は日本のパルナッス、即ち聖所=詩壇が最高の高みに達したと言っている。だから、それの崩壊をこそ《デカダンスというものである》と、書いた。その18年後、承久3年〈1221年〉、承久の乱で、日本のパルナッスは一つの終焉を迎えるのである。
2009.05.07
コメント(0)
-
寝る前に読む本
眠る前に、布団で本を読む方々は多いと思う。だが、もう何年も1ページも読まないうちに眠りに落ちてしまう。小説やエッセーなどでは毎晩同じ箇所を読むことになる。 これを続けるわけにはいかないので、こうした・・・。俳句や短歌なら、一句ずつ一首ずつなら・・・、である。 それで、最近読み終えたのが、『花神コレクション〔俳句〕有馬朗人』。因みに、有馬朗人は、東大総長から、参議院議員そして文部大臣の経歴がある。その経歴とは関係なく佳句が沢山ある。そのなかで、もっとも惹かれたのが次の一句、街あれば高き塔あり鳥渡る第二句集「知命」(昭和57年 牧羊社)に収められたもの。フランス・ルーアンの前書きがある。この句のように、有馬朗人には、海外詠が多い。多分、それは有馬朗人氏が学者であり、海外の大学で学ぶ機会が多かったからだろう。俳句を通じて海外の風景を読むことで、有馬氏の日本に対する思いを繋げているのだろうか? この、「街あれば高き塔あり鳥渡る」にその望郷の念が感じられる。手前勝手な解釈をすれば、この鳥とは、まさに有馬氏であろう。遥かなる、故国への思いがひしひしと伝わってくる。時に有馬氏五十二歳である。 今も、眠る前には俳句を読んでいる。
2009.05.06
コメント(2)
-
『定家明月記私抄』その5
三躰和歌、「大キニフトキ歌(春夏)。からび(やせすごき由也云々)秋冬。艶躰(恋、旅)」などという、今日の感性ではすでに、到底何がフトキであって、どれがからびであり、艶躰というからには艶ならざるものがどこにあるかどうかをさえ判別しがたいところまで達しえているのである。わかったような顔をしてみても仕方はないであろう。多くの研究書などでその別を論じたものを読んでみても、納得出来たためしがないのである。八百年近くをへだてた京都の狭小な、創作者と鑑賞者とがほとんど零距離の一社会にあった、微妙極まりない美意識の漂流が今日のわれわれに直かに伝わりえないとしても、それは、私は諦めるより仕方はないであろうと思っている。繰りかえす、わかったような顔をしてみてもはじまらないのである。 と、述べ次の2首を、例に挙げる。それは、・・・ 白妙の袖の別れに露落ちて身にしむ色の秋風ぞ吹く 定家面影の霞める月ぞ宿りける春や昔の袖の涙に 俊成卿女 などの、感覚浮遊の極点と言うべく(中略)その定着において彫金のような、金属的な冷たさをもあわせもつ作歌の、その極端な(中略)洗練というものが、如何にもと感得をされればそれで足りるであろうと私は思っている。 続けて、堀田善衛はこう書く、・・・ 言語を駆使しての芸が、かくも過度かつ極度なところにまで達し得ることが出来た例は、他に求めることが出来ない。 とまで、言い切っている。 例えば、この、2首に見られる緊張感は、日本語のもつ独特の緊張感であると思う。ここに見られる文語文独特の切り詰めたまでの短さは、今の日本語では表せないものだが、短歌などの詩の世界にはまだ残っているものかも知れない。 蛇足・・・、短歌は三十一文字(みそひともじ)五七五七七であることから、「白妙の袖の別れに露落ちて身にしむ色の秋風ぞ吹く」を、「白妙の 袖の別れに 露落ちて 身にしむ色の 秋風ぞ吹く」このように五七五七七と分けて書かれたものを見かけることがあるが、作者が意識して(表現上の必然として)分かち書きをしていない限り、分けて書くことは厳禁である。分けて書かれることで、その詩〈歌や句〉の持つ緊張感が全く失われることになる。二つを比べて頂ければ、よく分かるであろう。老婆心ながら、付け加えておく。
2009.05.05
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 海外ドラマ、だいすっき!
- 私立探偵ストライク リーサル・ホワ…
- (2025-11-23 08:00:04)
-
-
-

- アニメ番組視聴録
- 11日のアニメ番組視聴録
- (2025-11-11 19:09:38)
-
-
-

- ペ・ヨンジュンさま~♪
- 「ヨン様」の名付け親が初めて語る韓…
- (2023-12-02 17:40:56)
-







