2005年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
サルビア・ファリナケア>ブルーサルビア
久々に野の花から園芸植物に戻ってきました。長いロードからホームに戻ったみたい。 サルビア・ファリナケアにはピタッとくる和名がありませんね。ブルーサルビアという名札もあったと思うけれど、ほかにも青いサルビア属が多いので、具合が悪い。英名mealy sageは、直訳すれば、「粉だらけセージ」で笑っちゃいそう。 うちのサルビア・ファリナケアは、贈り物の「寄せ植え」から始まって3年半、庭に降り、暑さと乾燥が苦手かも、ということで、今は半日陰の涼しいところへ。秋の訪れとともに、鮮やかなブルーになりました。
2005年09月30日
コメント(1)
-
タウコギ、風に乗ってやってきた「雑草」
風とは限らないのですが、いろんな手段?で「雑草」がうちの庭にやってきます。アカカタバミやチチコグサは増える一方。でも、スミレは保存に努めています。その結果、ツマグロヒョウモンがやってきて、何割かの葉がボロボロ。 さて、見かけない葉っぱの「雑草」が一本生えました。どんな花が咲くかと期待したのですが、ちょっとガッカリ。しかし最接近してよ~く眺めると、面白いじゃありませんか。筒状花ばかりが集まって、キク科の様子。タウコギの結論で、名前のとおり田んぼに多いんだそうで・・
2005年09月29日
コメント(7)
-
適正、太りすぎ、肥満・・・?
「太りすぎ」の認識には美容的、あるいは心理学的なものもあって、それを言い出すと、美意識や文明の問題になってしまう。 客観的な基準は体格指数(BMI)がふつう。キログラムで測った体重を、メートルで測った身長の2乗で割った答えが、BMI。BMIが18.5~25未満が「望ましい」、25~30未満が「太りすぎ」、そして30~が「肥満」である。 世界保健機関(WHO)によれば、今60億人余りである世界人口のうち、10億人以上が太りすぎとか(もちろん肥満も含んでいる)。同時にアフリカ諸国などにおける飢餓が報道されていることを考えると、驚くべき数字としか言いようがない。 さらに、30歳以上の75%以上が太りすぎと推定される国として、女性ではエジプト、マルタ、メキシコ、南アフリカ、トルコ、米国など、男性ではアルゼンチン、ドイツ、ギリシャ、クウェート、ニュージーランド、英国など。日本の名は挙がっていないのは幸いだが、75%というのはものすごい数字。 これらの国を見ると、かって言われたように、所得の豊かな国だけでない。グルメと言えないにしても、甘味に誘惑されての糖質や高エネルギーの脂肪の摂取が、過剰になっていることを思わせる。食料の不足は急速に生命を脅かすが、いっぽう摂取の過剰もゆっくりと生命をむしばんでいく。 しかし、どうしてこんなことになるのか。おそらく動物の進化は、生命を維持するエネルギーを獲得することのみに向けられていたのだろう。運良く余ったエネルギーは、体脂肪にして保存しておくことにしたのか。ここ数十年に起こった大衆の肥満化に、人の進化はまだ対応できていない。 そうなると、「エネルギー管理を自分の体に白紙一任する」のは無謀で、自分の頭脳で(「特効薬」に頼るのではなく)、エネルギー管理の不備を補うしかない。そのさい自分の食糧管理ばかりでなく、世界の食糧分配にも目を向けるべきである。日本の食糧供給については、いろいろの視点がネットでも紹介されているので、参考にできる。
2005年09月28日
コメント(2)
-

ゲンノショウコの花でしょう
写真は一昨日のブログに登場した吉舎町で撮りました。中国山地の山間、小さい川に沿った場所に、1本だけ雑草に埋もれて咲いていました。なぜか花の風情に惹かれたのですが、花の名前を探索するうちに、その理由が見えてきました。ゲンノショウコは、大昔、山で見たハクサンフウロとかアサマフウロに近いのです。 ゲンノショウコでよいとすれば、「薬効」があります。夏に全草を採って乾かしたものを、1日5グラムから7グラム煎じて飲めば、収斂性下痢止めに効果。副作用がないので茶の代用にも使われるとか。しかしです、有毒なキンポウゲ科の植物に葉の形がよく似たものがあるので、要注意!と書いてありました。御岳百草丸
2005年09月27日
コメント(4)
-
こざっぱりしたキツネノマゴ
キツネノマゴはありふれた野草のようですが(当地ではそうでもない)、葉っぱがすんなりとして、グリーンも色よく、そしてバランスがよかったので、写真にしました。 葉っぱに重点を置いたため、パラパラと咲く小さい花が、ますます小さくなってしまいました。原画を拡大すれば、フォーカスは合っているんですけどね。
2005年09月26日
コメント(7)
-
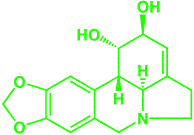
三度目のヒガンバナfrom三次市吉舎町
9月14日、一昨日に続いて三度目のアップ。ヒガンバナに魅入られた(霊界からお誘いがかかった)わけではありませんが・・ きのう、三次(みよし)市吉舎(きさ)町辻にある群生地に行ってきました。写真は一見ふつうですが、背景の木は何でしょうね?栗かと思ったら、果実の形がレモン形。栗のように表面に鋭いトゲはなく、しかしテニスボールのように毛羽立って見えます。 ヒガンバナの球根に含まれる毒素、リコリンが話題になっています。それなら化学構造を調べてやれと思い立ちました。下に示す「構造式」を見て、美しいと思ったら拍手喝采。リングの中に窒素原子(N)が入っているので、アルカロイド。単純に「毒」ではなく、薬理作用もあります。(構造式は自分のソフトでも画けますが、帝京大学薬学部有機化学大講座創薬資源学研究室のHPからお借りしました。ここに記して謝します)
2005年09月25日
コメント(3)
-
季節はずれのノアザミ?
自転車で走っていたら日陰に、薄紫のアザミが鮮明に咲いていました。 秋咲くアザミの区別は難しいそうですが、上向きに咲いていることからもノアザミやノハラアザミが有力候補です。 しかし、です。ノアザミは初夏に咲きますし、ノハラアザミは近畿以西に無いはずです。と言うことで、「季節はずれのノアザミ」にさせてもらいました。
2005年09月24日
コメント(4)
-
ヒガンバナのコンポジション
今日は秋分の日です。それにちなんでヒガンバナをもう一度取り上げました。 ヒガンバナの花の一つ一つは寿命が短い。だから、新鮮な花を撮れるチャンスは、案外少ないのです。写真の花は、色といい、理想的な被写体でした。でも、午後も遅く、おまけに薄曇りでした。そこで仕方なく画像処理のいたずら。成功したとは言えませんね。 この花を改めて眺めると、花は6個、円周を60度ずつきれいに分割しています。1個の花には花被が6枚、そして雄しべと雌しべをあわせて6本(乱れている花もある)。ということで、写真には6X6枚の真紅の「花びら」と、6X6本の「ヒゲ」があります。新鮮さとともに、これが被写体たる所以でしょうか。
2005年09月23日
コメント(6)
-
尾花(ススキ)の写真
今朝の「花おりおり」にも書いてあったけれど、いくら秋の七草でもふつうのススキを庭に植えようという人はいません。荒れ地にも育つしぶとい雑草のイメージが、わざわいしているのでしょうか。 いっぽう、ススキは写真にするのが難しい植物です。ただ、花序にぶら下がる黄色い雄しべには「おかしみ」があるので、よく黒をバックに接写され、1つのモチーフになっていますね。 アップした写真の意図を理解していただければ幸いです。
2005年09月22日
コメント(4)
-
ソバ畑
「焼畑農耕」は、日本では死語になってしまいました。しかし、東アジアのニュースでたまに登場します。ソバは焼畑で重要な作物で、その輪作体系に組み込まれているといいます。 ソバはやせた土地にもよく育ち、短期間で収穫でき、冷涼な気候にもよく適応するという特徴をもっています。今では北海道あたりが大きい産地なのでしょうか。 私の小さい頃、父はソバを、アワなどともに軽蔑していました。「銀シャリ(白米の飯)」があこがれだった時代です。それが今は、米も玄米がいいと言い、「蕎麦道場」が隆盛の世の中です。 これとは別にソバ殻が入った枕が懐かしい!枕に穴が開くと、ソバ殻がポロポロとこぼれて・・そんなこんなでソバ畑を見る目が変わります。
2005年09月21日
コメント(6)
-

史跡‘三ッ城古墳‘@東広島
この古墳は三基の古墳群からなります。その1つは広島県で最も大きいとか。 その1号墳は、全長約92メートルの前方後円墳。墳丘は3段に築かれ、斜面は葺石で覆われています。それぞれの段には円筒埴輪と朝顔形埴輪が、約1800本並べられています。 広島大学が広島市から移転する時期(90年代頃)に合わせて整備が進み、現在は写真のような姿をしています。古墳には疎いので各地の古墳がどんな姿をしているのか知りませんが、ちょっと注目の風景。小さい子供を遊ばせる母親が、「お墓」に上ったり、下りたりする情景は面白いなと思います。むろんお墓を意識していないでしょうが・・
2005年09月20日
コメント(2)
-
ガマズミの実をめでる(訂正:ミヤマガマズミ)
昨夜の名月はこうこうと輝いていましたが、朝起きてみると、曇天でときどき雨が降っています。蒸し暑い。 ガマズミの花は、4月28日にアップしました。それがこんな赤い実に。同じ木です。 ガマズミの実は霜を受けてなお赤く色づき、甘みが増すそうです。果実酒も造れて、見事な朱色の酒になるとか。食欲をそそられますが、まずはそっとしておきましょう。早起きの鳥たちが持っていってしまうかな? 追記:ミヤマガマズミの可能性も残されています。
2005年09月19日
コメント(5)
-
野ばら(ノイバラ)の実
中秋の満月を迎え、いよいよ秋たけなわと言いたいところですが、ちょっと暑いですね。 ヒガンバナに続いて、ススキがいっせいに穂をのばしてきました。この辺の稲の刈り取りももうすぐでしょう。 今日は、野ばらのオレンジ色を帯びた実が愛らしかったので、写真にしてみました。
2005年09月18日
コメント(4)
-
今咲く花、君の名は?(解:ツルボ)
この花は2ヶ所で、野草の間に見つけています。いずれも近くに花壇がないので、花壇から逃げ出したとは思えません。 ○○トラノオとは葉っぱが異なります。葉っぱはムスカリのそれを広げたような感じです。根を掘っていませんが、ユリ科かなと思います。 お分かりの方は、コメントしてください。 追記:自問自答になりましたが、「ツルボ」のようです。サンダイガサとも言い、全国の平地の原野や土手に普通に生えるんだそうです。
2005年09月17日
コメント(4)
-

クズ(葛)の花@東広島
言うまでもなく、秋の七草は萩・尾花・葛・撫子・女郎花・藤袴・朝顔(桔梗)ですが、仙人の周りの自然で豊かに咲くのは、前から三種だけ。撫子は庭に植えてあるので、今ぽつぽつと咲いています。しかし田中澄江の「新・花の百名山」を読むと、野に咲く撫子がめっきり少なくなったと嘆いています。桔梗も家にありますが、今は咲いていません。女郎花は、近くの農家の裏庭で鮮やかな黄色を誇っていました。最後に藤袴ですが、9月13日に載せた仲間のヒヨドリバナ以外を見つけていません。 今日はクズをアップしてみました。写真の個体は、花に個性があるような気がします。ですが、クズに間違いないでしょう。
2005年09月16日
コメント(6)
-
ツリガネニンジンの兄さん、サイヨウシャジン
舗装はされているけれど、車のすれ違いが困難な旧道で、ときどき訪れる場所があります。 そこで見つけたのが写真の野草。ツリガネニンジンによく似ているのですが、花冠の先端部がくびれているとか、花柱が花冠の2倍くらいあるとかの点で、ツリガネニンジンと一致しません。そしてたどり着いたのが、サイヨウシャジン。自生地の記載では中国地方以西となっており、とくに山陽で言えば岡山より西だとか。 ネットを見ると、種から育てている方もあり、忘れずに採種しようかと思っています。
2005年09月15日
コメント(4)
-
彼岸花がスタートにつく@東広島
ヒガンバナは、ある日突然にという感じで花茎が立ち上がって来ます。あらかじめ葉っぱが出ていないから、唐突です。 近所については、用水路沿いとか、ヒガンバナの球根が隠れている場所を覚えています。農家の方もご存知なのか、9月上旬までに観賞に邪魔な雑草を刈ります。 あとは花を待つのですが、数日前には出芽に気がつきませんでした。それが昨日には写真のように!1日何センチ伸びたのでしょう?10センチ以上は間違いありません。お彼岸の当日には、点々と赤い色が連なるでしょう。
2005年09月14日
コメント(8)
-
再びこの花なぁ~んだ?(解:ヒヨドリバナ)
近所にゴルフコースがあるのですが、その周囲の林に野生の花を探してみました。 見つけたのが上の白い花。遠目で見るより、アップした方が可愛いですね。林の中でも日陰に咲いていて、花形が珍しい気がします。蔓性ではなく、すいすいと伸びた花茎の先に、花序が着いていました。 私の知識では同定不可です。ご存じの方、コメントしてください。
2005年09月13日
コメント(5)
-
わたしの天城越え
今では伊豆の天城峠に築かれたトンネルにも新旧の2つがある。ロマンを誘う天城峠越えはむろん旧道のほう。 わたしが天城峠を越えたのは、古いトンネルが開通して今年でちょうど百年というその真ん中あたり。おおざっぱに半世紀前のことである。そしてその越え方はサイクリングでだった。20歳の大学生。 川端康成の「伊豆の踊子」は、トンネルを北から南に抜けた。「伊豆の踊子」の発表が1926年だから、トンネルができて20年ほどのことである。踊り子を追う「私」は、20歳の旧制高等学校の学生。 松本清張が1958年に著した「天城越え」に登場する「私」は、16歳の少年。「私」と酌婦「ハナ」、そして「土工」は峠の近くで出会う。トンネルを南から北に向かった。 わたしは、「旧制高校」の学生のように、一人旅だったわけでない。1つ年下のS君と一緒だった。しかしそのS君は60を前にして、肝臓癌で逝ってしまった。彼は天城峠越えをどう記憶していたのだろう。 われわれの天城峠越えの前日は下田温泉に泊まった。どういう経過だったか覚えていないが、宿の女将と値段の交渉をした。おそらく500円くらいに落ち着いたと思う。女将の顔は想い出せない、しかし穏やかに、外の水道で足を洗えと言った。当時の国道は大部分、砂利道だったのだから、「踊り子」の旅と同じ。 下田温泉でも下田街道でも、「踊り子」にも「ハナ」にも出会わなかった。翌日は海沿いの河津から、ひたすら河津川を詰めていった。湯ヶ野温泉を経て道は傾斜を増す。谷はしだいに下になり、うっそうとした緑が谷を埋めていた。耳を澄ましても河津七滝の音は聞こえない。噴き出す汗と疲労で、風景がボーッとした。 石で造られた天城トンネル。天井から落ちる冷たい水滴が快い。自転車から降り、明るい出口を目指して歩いた。旧制高校生の「私」は下田に向かって、青春のときめきに胸を躍らせ、母親の不義から家出した16歳の「私」は、修善寺に向かって、どろどろした情熱をたぎらせた。サイクリングをするわたしとSはどうだったのか。 急登から解放されたわたしたちは、トンネルの出口に「下りの快感」を想った。小説にはならなくとも、それも青春の一つの形だったのだろう。 4,5年してまた下田に行く機会があった。宿に着くとさっそく湯船へ。男湯なのに、若い女が、手拭いで前を隠しもせず堂々と入ってきた。外はまだ明るかった。わたしの天城越えに、刻をずらせて、「ハナ」が登場したようだった。
2005年09月12日
コメント(4)
-
メキシカンブッシュの花
メキシカンブッシュはサルビア・レウカンタ(サ)とか言いますが、すぐ忘れるのでもっぱらメキシカンブッシュ。頭の中では紫色の花と覚えていますが、よく見ると白い花。萼が紫色なのですね。 メキシコの花なので霜の頃枯れてしまい、生き残った根が翌年芽吹きます。当地では花が咲くのは今頃。
2005年09月11日
コメント(0)
-
過疎地と‘過密地’を襲う地震
過疎地とは、言うまでもなく人口の流失が続いた山間の集落を指す。一方、過密地は住宅を積み重ねたアパート群、とくに高層マンションを指すことにする。それぞれを大地震が襲ったらどうなるのか? 新潟の中越地震で、前者が明らかになった。山古志村を中心として、あちこちに孤立した集落が出現した。そして孤立の理由は道路の寸断。この地域のもろい地質を反映してか、あちこちの山の斜面が崩落して、道路を覆い、果ては谷を埋めつくして池が出現した。水はなんとか自前でまかなえても、食料や燃料の補給、そして医療は車に依存してきたから、孤立して命が脅かされる状態となった。 その状態から徒歩で脱出した人もいるだろう。しかし、老人を中心としておおかたの人はヘリコプターで脱出した。脱出によって救援が可能になったのである。 それでは過密地の高層マンションはどうなるだろう?最近の地震でその初歩が示された。エレベーターが停止して、マンションの高層部が孤立することが明らかになった。最近のエレベーターは最寄りの階に停止して安全だとされてきたが、エレベーターボックスにロープが絡みつく例が出て、脱出に2時間を要したという。停電もなく、周辺の交通も正常だったので2時間ですんだが、大地震なら自動車が土石に埋まった新潟と同じだったのでは? 機械的故障がなくても、停電になればエレベーターは動かない。それどころか水道もやがて止まる。過疎地と同じように、水、食料、燃料(電気)、医療の孤立が起こる。水は過疎地より深刻で、水洗トイレの利用も困難になる。唯一の救いは、脱出のための「徒歩区間」が短くて、気分的に楽なこと。しかし、老人が何十階も非常階段を下り、場合によってまた上るのは不可能。若い人でも10リットルの水を簡単に持ち上げられない。(この問題は台風で2,3日間の停電が起こった広島市の高層マンションで経験ずみ) こう考えれば、過密地と過疎地は生活が全く違っているにもかかわらず、類似点が多い。笑ってすませない問題である。
2005年09月10日
コメント(0)
-

ルコウソウの花、紅白一組
台風に耐えたルコウソウの花は細かい傷だらけだったけれど、その花は枯れて、新しい花が咲いています。そもそもうちのルコウソウは遅れ気味、少雨が続いて発芽が遅れたから。 写真に残していませんが、ルコウソウの双葉はすごく特徴的、一度見たら忘れられません。花と細く切れ込んだ葉の関係も、写真の造形に向いている。紅白一組をアップしたけれど、やっぱり赤の方がいいかなぁ・・
2005年09月09日
コメント(3)
-
三日月、木星、金星を撮る
台風が去った昨日、日没後の西南の空に三日月と木星、金星が目立っていました。調べてみると、正午の月齢が3.3ですから、正真正銘の三日月です。 9月1日のブログでは諦めていた写真ですが、ふと、挑戦してみる気になりました。電柱に寄りかかっての手持ち。まあ、三日月がバナナになりつつも、「光」をとらえることができました。しかしそれだけで感激するのも妙なものです。 三日月は明白と思いますが、その上が金星(ヴィーナス)、そして右へ(西へ)離れているのが木星(ジュピター)です。ネットには、9月7日が三者を観賞するのによい日となっていました。それが写真を撮る気にさせたのかもしれません。
2005年09月08日
コメント(4)
-
台風14号が去った後で
去年は台風の当たり年でした。その中でも1番よく覚えているのは、平和大通りの大木のヒマラヤスギがテレビカメラの前でゆるゆると倒れ、自動車を押しつぶした台風23号です。そのときには宮島の厳島神社も本殿を除いて大被害を受けました。 この台風は、広島市の中心部のすぐ西側を通りました。台風の被害が比較的少ない広島県にとって、アキレス腱のコースです。 今回の14号も同じことになりそうだったのですが、予報円の西、西と北上してくれたので、うちの植物たちの被害も最小限ですみました。東広島では、今日午前9時に晴れ間が見え、11時には風がほとんど止みました。 去年の日記で台風の項を読むと、「またまた台風。植物たちの対策と後始末、うんざりです。‘植木は根が抜け、自然木は幹が折れる’(ある人の説を引用)」なんていうことが書いてあります。 例のヒマラヤスギについては、「広島市内では、平和大通りのヒマラヤスギを含めて、数十本以上の大木が倒れたという。ここで樹木診断士が登場。根の腐った木は早めに取り除く、根が健全でも枝を落として風に対する負担を減らしてやる、とのご診断。最後に市役所の担当者が登場して行政問題に」 そのご行政は、お金を工面して大木の枝を切り落としたようです。今度の台風を前に民放が、枝を切り落とした木のフィルムを見せながら、「今年は枝を落としたので大丈夫でしょう」と言っていました。生き残った大木たちもたいへんですね。
2005年09月07日
コメント(4)
-
日本酒の味の表現
日本酒の味に限らず、食べ物の味を表現することはたいへんに難しい。味を文章で表現できるようになったら、一流の物書きという言い方がある一方、ほとんど味を表現せずにすましている作家もある。テレビの食べ物番組を観ていると、「美味し~い」のワンワードと精一杯の「表情」しかできないレポーターが多い中で、これは本当に味がわかっているな、と思わせる表現ができる人もいる。 日本酒の味を表現するとき、現品に的を絞ってストレートに表現するのが理想的なのだろうが、その表現には業界用語というか、一般に馴染みの少ない言葉が多い。この独特な表現を覚えるには酒造りを経験するか、酒造り経験者と酒を酌み交わしつつ、うまく疑問点を質問するしかない。 それがだめとなれば、道は2つだと思う。1つは日本料理など、料理との組み合わせで表現することである。「酒文化」と言ったとき、料理以外も入ってくるかもしれないが、普通の人にとっては料理が大きい部分を占めるだろう。酒に合わせて料理を選ぶか、料理に合わせて酒を選ぶか。 もう一つは化学に頼る方法である。しかし、これは業界の専門語を覚える以上に壁が高いかもしれない。ただ利点もある。化学が得意な人ならわかりやすいし、分析器械で客観化することもできる。 とはいうものの、日本酒の味を形成する物質は数知れない。そこで化学的知識に基づき、「酸度」や「アミノ酸度」など、味覚物質の取りまとめを行う。「日本酒度」という日本酒の比重を測るやり方もある。しかし、取りまとめたら取りまとめたで、表現がかえって曖昧になる欠点がある。そのため消費者に誤解が生じているのが実情である。 一方で特徴的な風味を持つ一物質を取り上げ、その物質の含有量で日本酒を評価することも行われる。たとえば、酢酸イソアミルはバナナのような香り、カプロン酸エチルはリンゴのような香り。果物のような香りは、吟醸酒の一面を表現する性質である。 これらの積み重ねを経ても、最終判定は、味覚物質と味の関係がわかる、味覚の鋭い人の感覚に頼らざるをえない。化学を使うから科学的なようで結局、表現に感覚的な部分を残している。 しかし、日本酒の味表現とは別に、消費する人の個人差を無視することはできない。われわれは各自が持つ「ベロメーター」(ベロとは舌の意味)に自信を持ち、おのれの酒を選ぶべきだろう。そのとき最も多く消費される日本酒のタイプは、時代により、地域により異なるように思える。
2005年09月06日
コメント(4)
-
アベリア(ツクバネウツギ属)の花
昨日に続いて、ツクバネウツギの花、その2です。古ぼけた名札には「アベリア」とありました。しかし、アベリア(ツクバネウツギ)属のいろいろな性質が入り交じっているように見えるので、園芸品種なのでしょう。 たとえば、ツクバネ(衝羽根)の由来になったがくが2枚しかありませんし、花弁の内側には模様や細い毛(名称を知らない)があります。遠くからでも、近づいても、ハナツクバネウツギとは違った雰囲気を醸します。
2005年09月05日
コメント(7)
-
ハナツクバネウツギの花
ハナツクバネウツギは、公園や道路の中央分離帯に植え込まれ、広く行き渡った花木です。今まで遠く眺めていて、その花を詳しく見ていませんでした。普通はややピンクを帯びていますが、写真のそれは薄く黄色みがありました。星形に開いた赤銅色の萼が目立ちますね。
2005年09月04日
コメント(3)
-

シロバナハギを見~つけた
シロバナハギが、5メートルぐらい連なって咲いているのを見つけました。本当に見事です。日当たりや地味がよい上に、今年は今までに台風もなく、すくすくと目一杯に蕾を着けています。 写真のシロバナハギは、ニシキハギの白花型のようです。ネットにはミヤギノハギの白花型というのも登場しますが、それらとは葉の厚みや枝振りが異なります。 写真の株の1つには、枝先にピンク色の花を咲かせた変異が、2ヶ所ほど見られました。それはネットで見るニシキハギの花というより、3日前に載せたツクシハギのイメージでした。 追記:ピンクの花の写真を追加します。
2005年09月03日
コメント(6)
-
高性アゲラタム(カッコウアザミ)の花
3,4年前でしょうか、どこの園芸店に行っても、矮性のアゲラタムが並んでいました。白とブルー系が代表だったでしょうか。そのころ、それに対する対抗心もあって、背の高いアゲラタムのタネを買いました。2年目からは育苗を止めて、落ちたタネ任せ。今年はずっと少雨傾向なので、アゲラタムの発芽が遅れ、今頃になって花を着けています。霜が降りるまでの運命ですね。
2005年09月02日
コメント(5)
-
ヴィーナスとジュピター
ヴィーナスとは金星の、ジュピターとは木星のことである。 ここのところ日没直後の南西の空をふと眺めると、2つのとても明るい星が見える。最初は、たぶん一つが金星として、もう一つは人工衛星かと思った。しかしそうではない、木星であった。 東京基準で言えば、日の入りが18時9分、金星の入りが19時47分くらい、そして木星の入りが19時53分くらいである。明るさのほうでば、金星の方が明るい。そのヴィーナスを追いかけて、ジュピターが落ちていく。 心に映る2つの惑星の印象を、写真で表すことはとてもできない!
2005年09月01日
コメント(4)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 手作りの庭とガーデニング
- ついにお迎えしてしまった高級ビオパ…
- (2025-11-17 19:52:22)
-
-
-

- いけばな ★彡
- キイチゴとトルコキキョウで ☆ 生…
- (2025-11-17 09:30:04)
-
-
-

- 泣き笑い家庭菜園・・・やっぱり手作…
- とうもろこし🌽栽培の悲劇
- (2023-07-06 12:55:36)
-







