2005年03月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-

野生のボケの開花も遅れている
きのうは他にも時間がつぶれることがあったけれど、サッカーが気になってブログはお休み。 うちの近くには、野生のボケの大群落があります。これが1本の木か、何本かの木が密集しているのかは、中に入れないので分かりません。その様子から近所の庭木から野生化したとは、とても思えません。そうすると、シバボケということになるのでしょう。 こういう自然木を発見すると、心配するのは、誰かに切られてしまうこと。でも、この3年間ずっと安泰で、密かに咲いています。 この春先の寒さは、ボケにも影響しましたね。去年だと今日は満開だったのに、今年は蕾が赤く膨らんだ程度。待ちきれなくなって、去年の写真を載せました。
2005年03月31日
コメント(1)
-
‘循環型社会’へ
NHKスペシャルで「環境革命が始まった~循環型社会への挑戦」が放映されました。その中にコーンやサツマイモから造るプラスチックの話がありました。 プラスチックはポリマーからできています。ポリマーは、1種あるいは少数の種類の化合物が長くつながった物質です。生物自身がポリマーをつくったり、生物由来の原料でポリマーをつくれば、「バイオポリマー」と言われます。 コーンやサツマイモに含まれるデンプンもぶどう糖のバイオポリマーですが、プラスチックに向きません。そこで、まずデンプンを複数の酵素で分解してぶどう糖にします。ある種のバクテリア(乳酸菌)は、ぶどう糖から乳酸を大量に合成します。この乳酸を分離して、化学的にポリマーに合成すると、ポリ乳酸が得られます。これがNHKで話題にしたプラスチックそのものです。 ポリ乳酸は、シート、容器、あるいは自動車の部品などに加工できます。もしこれらの加工品が自然界に放置されることがあっても、土壌の微生物が分解して、「餌」として利用してしまうので、「ポリ乳酸は環境にやさしいプラスチック」と言われます。石油を原料としたプラスチックの多くが、「安定でありすぎて」、環境を汚すこととは対照的です。 微生物がポリ乳酸を分解しても、もちろん二酸化炭素は出ます。しかし、もともとがデンプンだったので、石油のように太古に地底に閉じこめられた二酸化炭素を、現世に開放することはありません。 ところで、ペットボトルを回収したあと、小さな化合物までバラバラにし、再びプラスチックに合成する方法をご存じでしょうか。これだと何回でもリサイクルできます。そして同じことがポリ乳酸にも考えられます。ポリ乳酸を元の乳酸に戻し、再びプラスチックを造るのです。スペシャルではなにも言いませんでしたが、ポリ乳酸の分解に酵素を使うことが注目されます。余録:微生物はときにユニークなポリマーをつくります。たとえば、納豆菌のネバネバは、グルタミン酸のポリマー(ポリグルタミン酸)です。リジンというアミノ酸はヒトの不可欠アミノ酸の一つですが、ある種の放線菌はリジンのポリマー(ポリリジン)を作ります。これには大腸菌の増殖を抑える作用があると言います。
2005年03月29日
コメント(4)
-
野生のアセビの季節
家の近くには「三永水源地」という水道用の貯水池があります。みなが仙人の「みなが」の由来です。 水源地の周りには、地形の凹凸があり、樹木や竹が茂っていて、野鳥がたくさん生息しているようです。その林の中にアセビが混じっていることは、ごく最近まで気がつきませんでした。 アセビはドウダンツツジに近縁で、壷型の花が可愛いのに、猛毒を含んでいるので、鹿が敬遠して、奈良公園にアセビの純林ができたといいます。 写真のアセビは半日陰の場所にあったので、けっこう日陰に強いことを知りました。
2005年03月28日
コメント(2)
-
ミツマタの花に出会う
きのうは自転車に乗ってスミレの様子を見に・・大きな溜め池の堤防にあった群落はどうなっているでしょうか。 見ると、堤防の雑草が焼かれたばかりでした。それはいいのですが、堤防の天井部分が重機でだいぶ荒らされていました。スミレは復活するでしょうが、時間がかかりそうです。前に書いたサンシュユにしても、このスミレにしても、花の運命は意外にもろいです。人の影響もあるのでしょうが、人と同じように来年がどうなるか分かりません。2,3心当たりがあるので、写真はそちらで撮りますが、まだスミレの季節には早いかな? 小さな川に沿って走っていると、ミツマタの黄色が目に入りました。この町にミツマタは多くありません。コウゾ、ガンピとともに、和紙の原料の栽培は、聞いたことがありません。庭木でもないこのミツマタは、どこぞのお婆ちゃんが植えたのかな?全体の花の着き方がたいへん面白かったのですが、ここでは花のクロースアップだけを紹介します。 ミツマタも含めて、写真集「花手帖・早春/春」をネットに載せています。お暇があれば覗いてみてください。
2005年03月27日
コメント(1)
-
30年内に震度6弱以上の地震
23日、地震の未来予測に役立つ日本地図がいろいろ公表されました。ほかを心配しても仕方ないので、自分の住む東広島市を考えるのに良さそうなマップを、1枚ダウンロードしてきました。というのも回線がすごく混んでいて、あれこれ物色していては時間がかかりそうだったからです。そのマップでは、今後30年内に震度6弱以上の強さで地面が揺れる確率が、1キロ四方のマス目で色分けされています。 自分の都合を言えば、今後15年くらいの予測でよかったんですけどね。もっとも地震の起こる周期は、ときに人間の寿命の何十倍にもなるので、30年間でも短かすぎるのかもしれません。 旧東広島市は、ほとんどが黄色く染まっていて、確率が0.1~3%(やや高い)でした。ただ2月に合併した南側の黒瀬町には、3~6%のタイルが線状に並んでいます。これは地盤が弱いと言っているのか、活断層があると言っているのか、嫌な感じです。 仕組みが完全に分からない地震の未来予測が確率論なるのはやむをえませんが、地震発生の確率を知っても、それを日常生活に組み込みこむのはなかなか大変と思います。ちなみに、3~01%は、ひったくりに遭う、すりに遭う、交通事故で死亡の確率に相当するそうです。3~6%は空き巣被害!「交通事故で死亡」が入っているのは注目ですが、地震の場合、地面が強く揺れてもそれで死ぬわけではありません。地震で死ぬ確率は、別に存在します。 ですから、神戸で地震に遭い、新潟で地震にあった不運な方がいるいっぽう、地震のときさえその地にいなければ、物損だけで済みます。物損という観点からすれば、このマップによって地震保険料が変わることがあるのでしょうか。
2005年03月26日
コメント(2)
-
これも沈丁花?
今朝起きたら車の上に2,3センチの雪が積もっていました。春分を過ぎてもこの始末。まあ、とにかく珍しいことです。 さて、写真をご覧いただければ分かりますが、今日の花は沈丁花そっくりです。というより沈丁花そのものです。香りも同じ。しかし、花の位置が違うのです。どの本を見ても、沈丁花の花は枝の端の、葉の上に着いています。ところが、この沈丁花?では花が葉脇に着いています。 近縁でこのような花の着け方をするのはオニシバリですが、どうも見てもオニシバリとは思えません。沈丁花の変種なのでしょうか。とにかく地元では沈丁花と言っています。 沈丁花はよく見かけるので寒さには強いと思っていたのですが、寒地には向かないとか。そう言えば2月の寒さで、うちの別の沈丁花で葉が、蕾を残していっせいに落ちてしまいました。沈丁花は原因不明のまま急に枯れることがあるとかで、ビックリしたのですが、花も咲いたし、新芽が花の下から覗いています。(ヤレヤレ) 余録:沈丁花の香気成分は、120以上報告されているそうです。天然物は1種類だけで構成されることはないと言っても、ずいぶん多いですね。人気のある研究素材で、根ほり葉ほり調べたのでしょうか。リナロール、シトロネロール、ゲラニオールなどは、3月21日の「森林浴」で触れたテルペンの仲間ですね。
2005年03月25日
コメント(1)
-
サンシュユの大木が消えちゃった!
サンシュユは、春黄金花(はるこがねばな)とも言うように、春に目も覚めるような黄色の花をつけます。一つ一つの花は小さくても、それがまとまった姿が愛らしい。アメ玉のようなつぼみが開くと、花弁が反り返り、雄しべを天空に向けて突き出します。 ちょうど1年前に自転車散歩をして、サンシュユの大木を見つけました。道路の法面に当たる場所に生えていました。庭木のサンシュユは見かけるのですが、こんな自然体の大木は珍しいと思いました=写真。 そろそろ花時と思い、1年ぶりに大木に会いに行きました。ところがどうでしょう。確かにここにという場所にないのです!代わって、枯れた木の枝や幹が積んでありました。見回すと、杉の木が倒れた跡が二、三あります。とっさに去年の台風にやられたのかと思いました。広島の平和大通りの大木(ヒマラヤスギ)が倒れたあの時です。 誰かが見切りをつけて切ってしまったのか、あるいはどこかへ移したのか。(涙)
2005年03月24日
コメント(2)
-
青葉アルコールと青葉アルデヒド(緑の香り)
先週のNHK「ためしてガッテン」で、脳のトレーニングの話をしていました。 その中、ごく短い時間ですが、青葉アルコールと青葉アルデヒドが、脳の疲労回復に有効であるという実験が出ました。青葉アルコールと青葉アルデヒドを吸着剤に吸着させ、それをマスクに仕込み、鼻から少しずつ吸い込ませていました。 このような形で画面に登場した青葉アルコールと青葉アルデヒドは、何か特殊な物質に見えるかもしれません。しかし、「青葉」が示唆するように、実は日常生活にありふれている物質です。 青葉アルコールと青葉アルデヒド、そして類縁の化合物は、生鮮野菜や果物の香りを形成しています。新鮮で快い青臭さ(嫌いな人もいますが)、みずみずしさ、エレガントさ、そして新茶や紅茶の新鮮さを演出します。 それにしても、青葉アルコールとか、青葉アルデヒドとか、親しみ?の持てる名前ですね。「スミレ葉」アルデヒド、「キュウリ」アルコールというのもあります。もちろん化学ではきちっとした名称がありますが・・しかし、それを言うと、とたんに「化学アレルギー」が起こってしまうかもしれませんね。 いろいろ考えたのですが、「アルコール」と「アルデヒド」の説明はあきらめました。化学構造から見れば、とても近いんですが・・アルコールというと、お酒とか、消毒に使うエチルアルコール(エタノールとも言う)を連想する方が多いかもしれません。しかし炭素原子の数が違います(多い)。また、エチルアルコールから体内で生ずるアセトアルデヒドをご存じの方があるかもしれませんが、それとも炭素原子の数が違います(多い)。 青葉アルコールや青葉アルデヒド、そしてその仲間は、脂肪酸(脂肪などの構成分)の1種から、酵素の力で作られます。その酵素は加熱で活性を失うので、野菜をおひたしにしては「効果」を期待できません。
2005年03月23日
コメント(2)
-
かき氷に化けたミニ葉ボタン
この季節にかき氷の話をすれば、叱られてしまうかもしれません。でも、上の写真を見て、なるほどと思いません?ソフトクリームでは、いまいちです。 昨シーズン、ミニ葉ボタンは、春になって花を咲かせようと伸び上がりました。ちょっと面白く感じたので、写真に捉えました。作品の出番がなかったのですが、ブログに場所を得ました! 今年の葉ボタンはどうでしょう?寒さのせいか、鳥が増えたのか、葉ボタンの葉っぱは(とくに緑色のところを)さんざんに食べられてしまいました。友人はヒヨドリだろうと言うのですが、残念ながら犯人を目撃していません。ということで写真は貴重なものになりました(笑)。
2005年03月22日
コメント(4)
-
‘森林浴’へ
春分を過ぎました。サクラをさしおいて、緑の芽吹きや新緑を言うのは慌て者かもしれません。 十数年前から、「森林浴」という言葉があります。だれでも経験することなのですが、森林や林の中を登山したり、散歩したりすると、心がすがすがしくなります。この効果には、心理学的側面と化学的側面があるように思います。 葉っぱの緑色そのものは、色素であるクロロフィル類のなせるわざです。しかし、西日本の山の緑がより黄色っぽく、北海道のそれがより青色っぽく見えると思いませんか。おそらくクロロフィル類以外の色素が関わっているからでしょう。 「森林浴」の化学的側面の裏付けとして、「フィトンチッド」が知られています。「フィトンチッド」は、「植物が放出、あるいは分泌し、他の植物、昆虫、時に自分自身に作用する物質」と定義されています。ロシア人が提唱しました。森林植物の葉や幹が放出し、空間に漂っている揮発性の物質が、人の生理によい効果をもたらすと考えます。「フィトンチッド」はあたかも「入浴剤」のようです。 では、その物質は具体的に分かっているのでしょうか。代表的な例はテルペン類だそうです。化学用語で馴染みがないと思いますが、たとえば、ハッカ油に含まれるメントールや樟脳はテルペン類の仲間です。針葉樹林には、別の物質が1ppm(0.0001%)ほど漂っていて、匂いがすると言います。 心理学の方の研究は、触れる機会がありません。興味あるところです。 有名な句、『目には青葉 山ほととぎす 初鰹』(山口素堂)に表された緑は、視覚的に思えますが、「森林浴」と海の幸を結びつけてもいます。 大都会の人が罹りやすい「緑の欠乏症」は、心理学的なものでしょうか、それとも化学的なものでしょうか。
2005年03月21日
コメント(2)
-
ウメの木たち、わたしのなに?
ニュースは東京が中心ですから、世の中、関心はサクラ(ソメイヨシノ)に傾いてしまっているでしょう。でも仕方ありません、当地のウメは今が真っ盛り、と言うより、今年は寒かったので、始まったばかりです。 わたしが一人で楽しんでいるウメの木があります。休日に行けばだれにも会いません。 なぜって、それは大学構内の窪地にあり、おまけに松林に囲まれて人目に付かないのです。「松(ただし赤松)に梅」なんですが、盲点になっているのかもしれません。 ウメは十本ほどあります。ほとんどが白の一重でわたしの好みです。あとはピンクと紅が一本ずつくらい後の方に・・注目点は、木が若くて、バランスが取れている。少女のようです。でも、3年前から見ているんでが、ほんの少し老けたかな?もう1つの注目点は、じつによく咲き揃うことです。理学部の先生が植えたと思うので、遺伝子を揃えたのかな? 昨日現在で、このウメたち、5分咲きくらいでした。去年は1週間前で8分咲きくらい、おととしは20日には満開でした。今年のウメは遅れているようですが、南風でも吹けば、ソメイヨシノが追いすがってきます。
2005年03月20日
コメント(2)
-
シクラメンをこれから鑑賞します
1月29日に、スローガーデニングという副題で、3シーズン目に入ったシクラメンのことを書きました。そのときに1,2番花が咲いたのですが、そのごも進行はスローで(寒さもあったかな?)、ここへ来てやっと鑑賞に堪えられるようになりました。今日はそのご報告。 前述のブログへのコメントで、東京郊外?にお住まいの方から、何回やっても夏越しに失敗するという書き込みを頂きました。私が達人?とはとても思えませんので、あれこれ頭をひねった結果、夏の気温の違いに思い至りました。東広島は東京より南にあって暑そうにみえますが、実は涼しい。200mの標高のお陰で、8月の平均気温が2~3度低いのです。この差が僅かなようでも決定的なのかもしれません。 シクラメンはこれからどれくらい楽しめるでしょうか?気度が急激に上がって傷んでしまうかな?
2005年03月19日
コメント(8)
-
ムスカリの春
雪にもめげず去年から咲き続けているビオラを除くと、「地植え」で、春の訪れを知らせる花たちの順番は、冬知らず、クリスマスローズ、ツバキ(日本海という赤八重咲き)、プリムラ(ピンク八重咲き)。順位判定は難しいが、5位につけたのが紫のムスカリだ。 写真のムスカリはありふれた品種のよう。たぶん和名がブドウムスカリ。球根が安いし、植えてみるとこの地でもどんどん繁殖する。失敗する植物が多い中、とても心強い。これに勇気づけられて、来シーズンは白やバイカラーのムスカリにも挑戦してみよう。
2005年03月18日
コメント(6)
-
庭の片隅でマルバコンロンソウ(丸葉崑崙草)が咲く
うちの庭はアスファルトの道路に面して完全な開放型。ブロックを積んだり、フェンスを立てたりしていないから、野草の出入り自由。3年前の状態では、切り崩した山土が工事の車でカチンカチンになっていた。後で分かったことだが、窒素も、リンも、カリも乏しく、野草にとっても生育するのは容易でなかったようだ。頑張っていたのはスギナ、ヨモギ、ギョウギシバくらい。唯一色物としてマツバウンラン(青)やムシトリナデシコ(ピンク)が、2,30センチの高さに伸びた。 それがだんだん土が豊かになって、野草の進出も多様になった。今年はホトケノザが大挙してやって来た。だがそれより前、北側の庭には写真のような野草が・・最初は気にもとめていなかったが、ごく小さい白い花が日陰で目立った。 牧野の図鑑で調べたところでは、マルバコンロンソウ。ネットの写真も検索したが、中にはとてもマルバコンロンソウとは思えない写真もあった。
2005年03月17日
コメント(0)
-
リーガース・ベゴニア、ホワイトデーの花
今日は朝から春の陽気に戻った。わが庵の空高くヒバリが囀っている。今年初めて。 仙人のホワイトデーは花鉢に決めている。女子学生からチョコレートを貰ったときにも、それが「女子学生の代表」とかでなければ、自分で育てた花鉢を上げるように努めた。だが、これがときに物議をかもした。 今年花屋で選んだ花は写真のとおり。花の形と色合いが仙人の気に入った。 この花の通称はリーガース・ベゴニアだが、エラディオール・ベゴニアの方がまともな名前らしい。同じベゴニアでもセンパーフローレンス種は、タネを蒔いたり、室内で越冬させたりしたけれど、リーガース・ベゴニアは、初めてしげしげ眺めた。 ベゴニアの花言葉は、赤が片思い、公平、白が親切。オレンジはその中間だね。
2005年03月16日
コメント(0)
-
ビスケットの「原材料名」>その解釈
3月5日に「栄養成分表示」のことを書いたけれど、いまいち反応が鈍かった。興味がなかったかもしれないが、この表示があまり役に立っていないとも受け取れた。 そのときのサンプルは、豆もち。そこでも原材料名に触れたが、分かりやすくて問題なかった。だが、すべての場合がそうかと言うと、首をひねることも多い。 今日のサンプルは、B社のビスケット。小麦胚芽入りで、全粉粒ビスケット&バニラクリームが売り。原材料名は、次のように並んでいた。「小麦粉、砂糖、ショートニング、植物油脂、でん粉、小麦全粒粉、ぶどう糖、乳糖、食塩、小麦胚芽、膨張剤、香料、乳化剤(大豆由来)、着色料(カロチン)」この表示の難易度は中くらいか。 まず用語だが、ショートニングは脂肪の1種で、融点が高く、室温で固体状。膨張剤はベーキングパウダーの仲間だから、重曹(炭酸水素ナトリウム)が主成分か。この物質は高温で炭酸ガス(2酸化炭素)を放出する。香料は主にバニラを指しているのだろう。乳化剤は大豆由来の材料を使ったとある。その材料は、おそらく、大豆レシチン。主成分は、用語のとおりレシチンで、リン脂質の1種である。リン脂質は元の大豆細胞で、細胞膜などを構成していた。着色料には生体成分のカロチンを用いている。カロチンは、カロテンと同義で、ビタミンAの前駆物質。 さて、ビスケットの姿に立ち入ってみよう。ビスケットは、全粉粒ビスケットとバニラクリームに分けられる。全粉粒ビスケットは、小麦粉、小麦全粒粉、小麦胚芽、ショートニング、カロチン、膨張剤で焼いたことは間違いないが、甘味は砂糖、ぶどう糖、乳糖のうちどれか、それとも全部?3つの甘味料には、甘味の強度や風味に差があるので、何かノウハウがありそう。 次はバニラクリーム。こちらは油状の植物油脂と香料を乳化剤で乳化したと思われる。とうぜん甘味を付けなければいけないが、3つの甘味料のうちどれを使ったのだろう? 残る原材料で謎が多いのはでん粉である。想像では、クリームにある固さを与えるために使った? こんな具合に、「原材料名」からビスケットの作り方が透けてくる。
2005年03月15日
コメント(0)
-
生化学の専門語、ユビキノン(CoQ10)
ユビキノンは、3月8日のリポ酸と同じように、その名前が日常生活によく登場してきますが、その意味が簡単でない、生化学で重要な物質です。(もっとも、われわれの体を構成している物質はどれも重要で、物質の間に貴賎はないと思っています) ユビキノンの「ユビ」は、最近IT分野でよく使われる「ユビキタス」と同じ意味です。つまり、人を含む動物、そして植物や微生物に広く分布しています。珍しい物質ではありません。「キノン」はある特徴を有する物質を指す名称です。それを理解するためには、化学か生化学を専門的に学ばないといけません。 CoQ10(コエンザイムQテン)の「Co」は、coenzymeの略ですから、「補酵素」です。何らかの酵素を助けていると考えられたわけです。「Q」はquinoneの略ですから、「キノン」です。最後の「10」は、キノンの構造にある繰り返し構造があり、その繰り返し数が10の意です。高等動物の細胞にある「ミトコンドリア」ではこの数字が10ですが、ほかの生物には違う数字があります。 ユビキノンとCoQ10の2つの名前があるのは、最初2カ所で研究をしていて、のちに同じ物質であることが判ったためです。 われわれは、糖質、脂質、タンパク質などから活動に必要なエネルギーを得ていますが、そのエネルギーをATPという物質に担わせて輸送します。そのATPの合成に、ユビキノンは関わっています。たぶんユビキノンの効能の話は、たいていここから始まっていると思います。 ネットを調べていて、ユビキノンは「ユビデカレノン」という医薬品に含まれていることを知りました。心不全の薬です。「東海四県薬剤師会」が出している情報を読むと、忘れても2回分をまとめて飲むことを禁じています。リポ酸でも書いたことですが、過剰摂取は戒めるべきです。
2005年03月14日
コメント(1)
-
八重咲きプリムラ(ピンク)
北極からまた冷たい寒波がやってきた。北極そのものは温暖化が著しいというのだが・・しかし、もともとが冷たいからね。 朝起きたら、雪で一面の薄化粧。ビオラは寒さに強いから去年からずっと咲き続けている。だが、氷点下の5度を割ったときには、さすがに花びらが傷んだ。パンジーは色(品種)によって花が咲く耐寒性が異なるようだ。しかし実際に寒さに当ててみないと、各色の微妙な耐寒性がわからない。 スイートアリッサムも寒さに強い。だが、寒いときは花色がさえないし、一部の枝が枯れてしまう。だから、なんとか寒さに耐えている感じ。 わが家の庭で最初に春の訪れを知らせるのは、ピンクの八重咲きプリムラ。それがやっとポチポチと咲き出した。 このプリムラには長い栽培歴がある。今から12,3年前にはマンションに住んでいた。そのときタキイから「八重咲きプリムラ4色組」を購入した。各色2株計8株。プリムラは多年草だが、夏の暑さに弱い。そこでマンションでは、冬は日当たりに、夏は日陰へ、を繰り返した。3年ほど前、戸建てに引っ越してからは、冬・春は南側の庭、夏・秋は北側の庭にせっせと植え替えた。だが、いつの間にか2色が消えてしまった。たぶん耐暑性が弱かったのだろう。 かくして残ったのが、ピンクと黄色。残るだけでなく、株分けで4倍ほどに増えた。2色のうち先に咲くのはピンク。黄色は20日ほど遅れる。今日は前に撮ったピンク種の最盛時の写真。
2005年03月13日
コメント(2)
-

平均値で語る春
季節を伝えるテレビの原稿には、平均値があふれている。その中で一番多いのが、気温だろうか。「今日の気温は4月中旬並みでした」、あるいは「今日は2月上旬に戻る寒いお天気でした」。次いで雨量、春の話題ではないが、「この台風による総雨量は○○○ミリで、年間雨量の3分の1が降ってしまいました」。以下、平年の霜、積雪、日射が話題になることもある。 ときには、平均値のアナウンスを聞きながらヤキモキするわれわれの心が、滑稽に思えることがある。気温が日に日にばらつくのは自然の摂理。われわれが理解しやすいように、年ごとのバラツキをまとめたのが平均値なのだから。平均値に囚われて、自然に異議を唱えることに可笑しさが伴う。 ところで平均値の計算はとても簡単な算数。データさえあれば、総計を出して、データ数で割ればよい。ところが、平均値が同じでも、バラツキの程度の違いを示す「度数分布」や「標準偏差」になると、とたんに難しい感じになる。それにもかかわらず、それを飛び越えて、天気が「確率」で予報されている。これはどうして? 最近、最低温度とか、最高積雪量とか、夏であれば時間降雨量とかが、観測史上第○位と報ぜられることが多くなったようだ。これは気象のバラツキを表現するというより、気象の「異常性」を強調している。 理科年表を覗くと、春に関わる平均値は、広島市のデータとなっている。3月の気温の平年値は9.0度。それに対して東広島市は6.1度で、2.9度も低い。おそらく高度差200mがなせるわざであろう。それでは東広島に並ぶ気温の場所はどこか。宇都宮(6.2度)、水戸(6.3度)、小名浜(6.2度)、富山(5.7度)。大阪は9.0度、東京は8.9度で、温暖の?地。植物と付き合う者としては、今さらのごとく驚く。 さらに「生物季節観測平年値」を眺めてみた。広島のウメの開花日は、2月6日。ウメはいろいろある上に、満開がどれくらい後か定かでないが、東広島のウメの見頃はたいてい3月中旬である。そうとうの開きがある。 それがなぜかサクラになると、だいぶ差が縮まるようだ。広島におけるソメイヨシノの開花日が3月29日、満開日が4月5日。満開が1週間遅れるのが東広島だと、おととし推定したが、去年はこれが大狂い、たった1日しか遅れなかった! 昨日までの暖かさでホトケノザが咲き出した。同じく春を告げるオオイヌノフグリはすでにいっぱい咲いている。今年はオオイヌノフグリの当たり年なの?休耕田に咲くホトケノザの大群落(昨シーズンの撮影)
2005年03月12日
コメント(0)
-
スローガーデニング3>クリスマスローズ
クリスマスローズがやっと咲いた。02年に3,4百円で買った苗である。冬を3度越したことになる。安い苗はほんとうに気を持たせる。 なにせ初めてだったから、夏は北側へ、冬は南側へと植え替えていた。しかし反応がないので、北側に植えっぱなした。寒さにはめっぽう強い植物である。 安いから花の色はわからない。咲いてみたら薄紫だった。咲いた時期や花の色から考えて、生粋のクリスマスローズではなく、ハルザキクリスマスローズらしい。これはレンテンローズと言うとか(あるいはオリエンタリスとも)。 北に植えてあるせいもあるが、クリスマスローズはなんか憂鬱げ~折からの春雨でなお寂しい。顔を隠す姿は、日本的でもある。むりやり(私の心理)下方から撮影した。だが、どなたかのブログに書いてあったように、力ずくで花を持ち上げなかったので、こちらに負担がかかり息が切れた。 花言葉で、「私を安心させて」は私の想いに近かったが、「スキャンダル・悪評」など、私の想像外もあった。
2005年03月11日
コメント(3)
-
純米酒、「元禄」from澤乃井
このお酒は自分で選んだのではなく、いただき物である。 まずは室温から始めて、湯燗徳利でお酒の温度を上げていった。お燗した方がよいのは間違いない。それにしてもズシンとくる味、何もの? 間を空けて同じように飲んでみた。そのたびに印象が変わる。あっ、飲みやすくなったじゃないか~ちょっと甘すぎるかな?~あれっ、またいい感じ!~私の頭の中がグラグラである。それはどうして? 改めて、瓶のラベルを見た。文章を引用させてもらう。「元禄酒」:元禄は過去の酒/酒蔵の扉の向こうに消えた古(いにしえ)の味がする/洗練を拒否して生まれる存在感/今の酒のなんと優しいことか・・これは現代の日本酒のアンチテーゼだというのか? アルコール表示は15~16度で普通。精米歩合は、麹、掛けとも88%!「日本酒度」はマイナス10! 最初にズシンときた味も、そのごに起こった印象の動揺も「アミノ酸」のなせるわざとは、私の推測。そこで「アミノ酸度」を探したが、表示されていなかった。 米や麹菌に由来するタンパク質を構成するアミノ酸は、20種である。だが、タンパク質が、醸造の過程で完全にアミノ酸に分解するとは思えないので、多種のペプチド(アミノ酸が少数個つながった物質)も同時に生ずる。これらはすべてアミノ酸度として測定される。 実は、アミノ酸やペプチドは、それぞれ、甘み、酸味、苦み、塩からみ、うま味、渋み、曖昧な味などを示す。よく知られているようにL-グルタミン酸ナトリウムだと、うま味(L-はD-に対するが、ふつうには無視してよい)。 お酒に溶けているわけでないが、アスパルテーム(商品名)は太らない甘味料として重宝される。これもペプチドの1種。また、L-オルニチルタウリンというペプチドの仲間には塩からみがあり、減塩物質として重要である。他にもブイヨンには、アミノ酸が8個(?)連なった美味なペプチドがあるという。 話が脱線してしまったが、味とはまことに複雑なもの~
2005年03月10日
コメント(8)
-

サクラの気まぐれ?
「天声人語」子の観察だけれど、ウメの開花は個性が強いというか、気まぐれというか、バラバラである。それに対して、サクラはいっせいに咲きそろう。そう言われてみればそうだが、これには訳があった。 サクラが咲きそろうのは、ソメイヨシノが日本全国に普及した結果だという。このサクラを増やすためには接ぎ木しかないので、否応なく、遺伝子が等しい「クローン」のソメイヨシノが広まった。遺伝子が等しいのだから、咲きそろうのは当然・・なるほど、なるほど。 確かに、いろいろな品種のサクラを集めた公園とか、サクラがポチポチと自然に生えた山とかでは、サクラがいろいろなタイミングで咲いている。 近頃サクラについて、不思議に思っていたことがあった。子どものころに憶えたことでは、サクラは春風とともに南から、だった。暖流の黒潮や対馬海流のように、だんだん北上していく。そして、鹿児島や高知は暖かく、盛岡や弘前や北海道は寒いんだと子供心に思った。 それがどうだろう。最近は九州北部や四国西部、関東南部から花の輪が広がるのだという。東京についてはヒートアイランド現象が、あるいは全国については温暖な気候が影響しているのだろうけれど、どうなっているの? 朝日新聞の科学記事によると、前年の夏にできたサクラの花芽はいったん休眠し、その休眠を破る寒さが必要なのだそうだ。一定の寒ささえ経れば、あとは暖かいほど開花が早い。そして寒さを経ないと、開花は連休頃になってしまう。伊豆諸島や九州では、むしろ、ソメイヨシノの開花が南進する。「春」は北から南へ、それはわかったけれど、困っちゃうなぁ~このサクラはソメイヨシノでないが、品種は不明(昨シーズンに撮影)
2005年03月09日
コメント(1)
-
αリポ酸、どうしてこんな専門語が?
α(あるふぁ)リポ酸が、今年のサプリメントの本命だそうです。テレビは観ていませんが、大変な驚きです。 私は、大学の教養科目や専門の「食品生化学」という講義で、ビタミンや「補酵素」(酵素の働きを助ける物質)の話をしたことがあります。しかし、学生は今さらなんでビタミンの講義をするのかという顔をします。それに気おされて、ビタミンの話を止めました。 だが学生の余裕は本当でしょうか?そこで大学院の入試に、たとえば「水に溶けるビタミンを3つ挙げて、それぞれの役割を書きなさい」を出題してみました。案の定、期待より甘い採点をしないと合格点が出せませんでした。 αリポ酸は「補酵素」に該当します。生化学や栄養学を専攻する者の「専門語」がズバリ世の中に出てきたのです。 リポ酸に付いている「α」はなんでしょうか。「β(べーた)」があるのかと思って調べたのですが、分かりませんでした。だから、「α」は省いても構わないようです。 リポ酸がどんな酵素を助けているのかは、説明が難しすぎます。しかし、ビタミンB1(チアミン)、ニコチン酸、パントテン酸と共同で機能することが、生化学の教科書に書いてありました。このへんから、ダイエットに有効の話が生まれてくるのかもしれません。(すみませんが、ダイエット効果を証明した学術論文が、あるのかどうかなどはわかっていません) またリポ酸には、「活性酸素」を消去できる「化学構造」が含まれています。「活性酸素」は反応性に富んだ酸素の状態で、しなくてもよい悪さをするので嫌われます。しかし「活性酸素」を化学的にちゃんと説明することは、専門課程の学生さんに対しても大変難しいことでした。 「活性酸素」を消去できるという点では、ビタミンCと共通です。ここらへんから、アンチエージングとか、若い肌とかの話が生まれたのでしょうか。(これも、効果を証明した学術論文があるかどうかなどはわかっていません) ところで、リポ酸のサプリメントは、日本の法的な枠組みで言えば、「保険機能食品」のうちの「栄養機能食品」から進化?したものでしょうか。今のところ「栄養機能食品」の中にリポ酸の姿は見えません。 ただ注意しなければいけないのは、生物の特性からして(と私は信じている)、サプリメントの過剰摂取は避けるべきです。生物にとって、多ければ多いほど良いということはありません。実際、「栄養機能食品」の規格を見ていくと、「1日当たりに摂取できる最大限度量」が設定されています。
2005年03月08日
コメント(4)
-

イベリスという花
ぜんぜん知らなかったけれど、イベリスは地中海沿岸に生える植物なのだそうですね。英名はcandytuftで「お菓子のような花のひとかたまり」の意。お菓子好きというわけではないけれど、思わす微笑みます。 写真のイベリスは、イベリス・センペルウィレンスです。園芸品種には、八重咲きや淡紅色のものもあるのだそうです。和名はトキワナズナ。4月くらいから咲くのが普通のようですから、写真の株は促成栽培したのでしょう。 上の写真のように、眺め下ろす角度では気がつかなかったのですが、花は上に伸びながら順番に咲いていくのですね(下の写真)。ナズナ(ペンペン草)ほど花の間隔があいていないけれど、やっぱり仲間です。 アブラナ(菜の花)と同じように、イベリスも花弁が十字形。しかし、内側の2枚が小さい。今日は暖かくなりそうなので、菜の花の開花も近づきます。
2005年03月07日
コメント(5)
-
はてな?加工食品の栄養成分表示
販売に供する食品(一部食品を除く)に新しい「栄養表示基準」が導入されてから、すでに9年が経っています。表示はどれくらい利用されているでしょうか。 市民講座で講義したこともある当人が、改めて(!)眺めて、う~んと唸ってしまいます。おそらく多くの方が、「原材料名」のほうに興味を示すでしょう。 最近「豆もち」を食べました。「原材料名」を見ると、水稲もち米、大豆(遺伝子組み換えでない)、植物油脂(綿実油)、食塩、調味料(アミノ酸等)。強いて言えば、調味料がちょっと曖昧なほかはよく分かります。「遺伝子組み換えでない」は、遺伝子組み換え技術を応用した大豆品種を用いていない、の意でしょう。 さて、「栄養成分表示」です。1袋(20枚)当たり、エネルギー454kcal、たん白質9.0g、脂質16.5g、炭水化物67.4g、ナトリウム523mg。 まず食品化学、栄養学あるいは生化学に使われている専門語ですが、たん白質はまあまあとして、脂質はどうでしょうか?脂質の範囲は専門家でもずれがあり、私も採用されている分析法を見ることにしました。驚いたことに複数の分析法があります。私の経験では、分析法により違った値が出ると思われます。それはそれとして、「表示」の脂質には、脂肪、リン脂質、コレステロールなどが含まれているようです。次ぎに炭水化物、生化学的にはその範囲がはっきりしています。ブドウ糖(グルコース)、果糖、澱粉、セルロールなどを中心とした糖類です。ですが、「表示」では、食品の全重量からたんぱく質、脂質、灰分、水分を引き算して求めます。すべての誤差が炭水化物に集まることになります。 カロリーはふつう計算で出します。上の例では、9.0 x 4 + 16.5 x 9 + 67.4 x 4 = 454.1 (kcal)。カロリーの計算については、ネットでいろいろな議論がなされていますので、ここでは深入りを避けます。 最後にナトリウムです。化学の立場からはこの表現にすごい抵抗があります。食品にしても、われわれの体内にしても、ナトリウムは必ず「ナトリウムイオン」(プラスの電気を持っている)で存在します。もちろん、イオンでない金属のナトリウムも世の中には存在しますが、これはとても危険な物質です。大昔、グランドで洗面器に水を入れ、少量の金属ナトリウムを投げ込んだことがあります。ナトリウムはバチバチと水と激しく反応し、火がつきました。水素と水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)が出来たのです。 ところでナトリウムイオンを表示する理由は、言わずとしれた食塩摂取の目安。ただナトリウムイオンは、食塩(塩化ナトリウム)の重量の39.3%。したがって食塩に換算するためは、2.5倍しないといけません。ご注意を!
2005年03月05日
コメント(0)
-
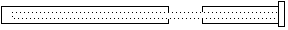
危険な?「杉鉄砲」
皮肉なことに、杉花粉の襲来で春の訪れを知る、今日この頃である。 小学生時代で記憶は曖昧だが、わたしの住んでいた田舎には「杉鉄砲」と呼ぶ、男の子が自分で作る飛び道具があった。この鉄砲では、杉の実を弾丸に使う。そうとう精巧な代物で、上級生がうまく作るのが羨ましかった。 (「シニアの腕まくり」さんのブログ(http://pinetree.air-nifty.com/blog/2005/02/post_1.html#more)では、「杉玉鉄砲」となっているが、わたしの方では確かに「杉鉄砲」と言っていた。もう1つ、「紙鉄砲」があって、こちらは薄い紙をちぎって濡らし、丸めて弾にした) 「杉鉄砲」の作り方と発射法は、「シニアの腕まくり」さんのブログにも書かれているが、まずは杉の実のサイズにあった篠(しの)竹探しに始まる(下図参照)。穴の直経が大きすぎれば飛ばないし、小さすぎれば杉の実がつぶれてしまう。ここで上級生と実力の差が出たようだ。 篠竹の節の上から次の節の上まで1節切り取り、それを2つに切る。節のある方が持ち手になり、他方が発射筒(砲身)になる。持ち手の方には、竹ひごを挿す。とうぜん、竹ひごに既製品がなかったので、竹の穴にピッタリで、まん丸いひごを別の竹から削り出すのが難しかった。 さて、試射!まず1つの「弾」を「砲身」の先まで押す。次ぎにもう1つ「弾」を詰めて、ひごを押す。うまくいけば、ピシッ・・出来が悪ければ、先端の「弾」がポロンと落ちる・・ 当時、杉花粉症という言葉は存在しなかった。私の母もなにも言わなかった。しかし、今、杉の実を飛ばす「杉鉄砲」は、「生物化学兵器」のようである。「杉鉄砲」
2005年03月04日
コメント(2)
-
脂肪分解酵素リパーゼ、よもやま話
リパーゼは脂肪を脂肪酸とグリセリンに加水分解する酵素。ヒトでは、消化のために膵臓から十二指腸に出されるが、ほかの組織にも別のリパーゼがある。 脂肪は、中性脂肪(医学界)、油脂(化学工業界)、トリグリセリド(化学界)、トリアシルグリセロール(生化学界)などといろいろ呼ばれるが、どれも同じ物質。しかし、名称を統一する話は聞かない。 リパーゼは、われわれの日常生活に大いに役立っている。まず「消化薬」に添加して、脂肪の消化を助ける。使うリパーゼには、豚の膵臓リパーゼや酵母のリパーゼがある。酵母と聞くと意外と思う人があるかもしれないが、脂肪が生物にとってありふれた物質である以上、酵母にもリパーゼは必要。酵母のリパーゼを発見したのは、私たちの研究グループだった。 次ぎに医療に必要な検査で使われる。おなじみ、中性脂肪の分析である。これも微生物の酵素を利用している。 洗濯洗剤に加えられるリパーゼも重要だ。タンパク質を加水分解するプロテアーゼなどといっしょに、皮脂や血の汚れを除去する。 食品関係であれば、牛乳を弱く分解して、チーズのような香りをつくること、あるいはチョコレートに使う特殊な油脂をつくること、など。チョコレートの油脂は、人の体温付近で溶ける特徴がある。そしてそれが美味しい。 最後に環境問題に関係したお話。日本人は魚をたくさん食べているわけだが、それに伴って骨や内臓がゴミとして出てくる(魚さいまたは魚腸骨という)。これを埋め立てれば悪臭を発し、燃すには石油が必要になる。 そこで魚さいを新しいうちに回収して、粉砕、蒸煮して、魚油と魚粉に分ける。魚粉はカルシウムに富んでいて、飼料になった。魚油は重油の代わりに使えたが、それはもったいないので、これも飼料にすることを考えた。そこで、酵母飼料をつくるために、魚油で生長できる酵母を探した。今日は選ばれた酵母の顕微鏡写真を紹介しよう。酵母の直径は、10マイクロメータ(0.01ミリメータ)程度である。
2005年03月03日
コメント(4)
-
‘ソーラーウォール’で感ずる春の足音
「ソーラーウォール」というものをご存じだろうか。ソーラーは「太陽の」だから、太陽の壁である。 ソーラーと言うと、最近は太陽電池(solar cell)を指すことが多い。だが、ソーラーウォールは発電に関わっていない。 ソーラーウォールを簡単に説明しよう。下の写真で黒い壁がそれである。普通の家の壁の上に、間を空けて、小さい穴の開いたアルミ板(カナダ製)を張る。アルミ板が黒く塗ってあるのは、太陽光線の吸収を良くするため。 朝、太陽がウォールに当たると、背面の空間にある空気が暖められて、空間を上昇していく。空間の上部には空気の取り入れ口があり、設定温度以上になると、暖められた空気がパイプに吸い込まれていく。パイプは天井から床下まで直行している。家全体の床下は、周囲をコンクリートで固められた空間になっていて、まずここが暖められる。そのご空気は、床の隅にあるグリッドからゆっくりと吹き出す。そして取り込んだ外気により、室内の清浄さは保たれ、結露もまず起こらない。 欠点と言えば、全くのお天気任せ。冬は日差しが弱いし、ましてや雲が出れば、補助暖房は必須。補助暖房には、LPG(プロパン)や電気を使っている。だが、ソーラーウォールによってこれらが節約できたのは確か。 外に出れば10℃以下の天候が続く今日この頃でも、暦の春は着実に進んでいて、太陽の力がいや増していることを肌身に感ずる。 ご参考に:夏はソーラーウォールを止めるから、家の中を熱くすることはない。この地ではクーラー無しで過ごせるが、夜、温度が下がってから冷気をソーラーウォールで取り込むこともある。
2005年03月02日
コメント(0)
-
雄町純米、竹鶴酒造in竹原
広島県の瀬戸内海に面して、竹原という街がある。広島県には大竹という街もあるけれど、こちらは山口県に接している。竹原からは、四国の波方へフェリーが出ている。島の間を縫って70分ほど。 「町並み保存地区」は、本川という川の東側。去年秋、保存地区にある竹鶴酒造に立ち寄った。他に人もなく、お客はわれわれ二人だけ。対するは、ご当主の奥様とお見受けした。 入口の戸を開けて入ると、右側に分厚い木でできた、丸いテーブルがどんと置いてある。その上に4合ビン(720ml)が5本ほど並ぶ。試飲自由。決意?を固めて椅子に座る。相方はニコニコしているだけで、われ関せず。額に汗が滲む。 遠慮して?試飲量は少しずつ。何かかんか言いながら、「値段の順番なら当てられますよ」と、ビンを並べ直した。アタリ!これで奥様の信用を得た様子。奥から、テーブルになかった「雄町純米」を出してきた。 実はこの時点では、竹鶴酒造の「雄町純米」について、何も知らなかった。懐具合も考えながら、「雄町純米」と1,2年醸造年度の古い純米酒を比較。これは迷った・・結局、「雄町純米」に柔軟さと未知を感じて、これを選んだ。 帰ってきて調べてみると、上原浩門下?による「雄町純米」の評判は高い。開栓後の味の変化をみるために間を空けて飲んだり、湯燗徳利で最適温度を調べたり。いやぁ~、驚きました。長い人生、これほど真剣に飲んだことはなかったのだが、すっかり感心してしまう。開栓して何日か後には、すごい個性を発揮した!いい意味で舌がしびれた。 ということで、竹原にまた出かけたいと思っている。
2005年03月01日
コメント(5)
全29件 (29件中 1-29件目)
1










