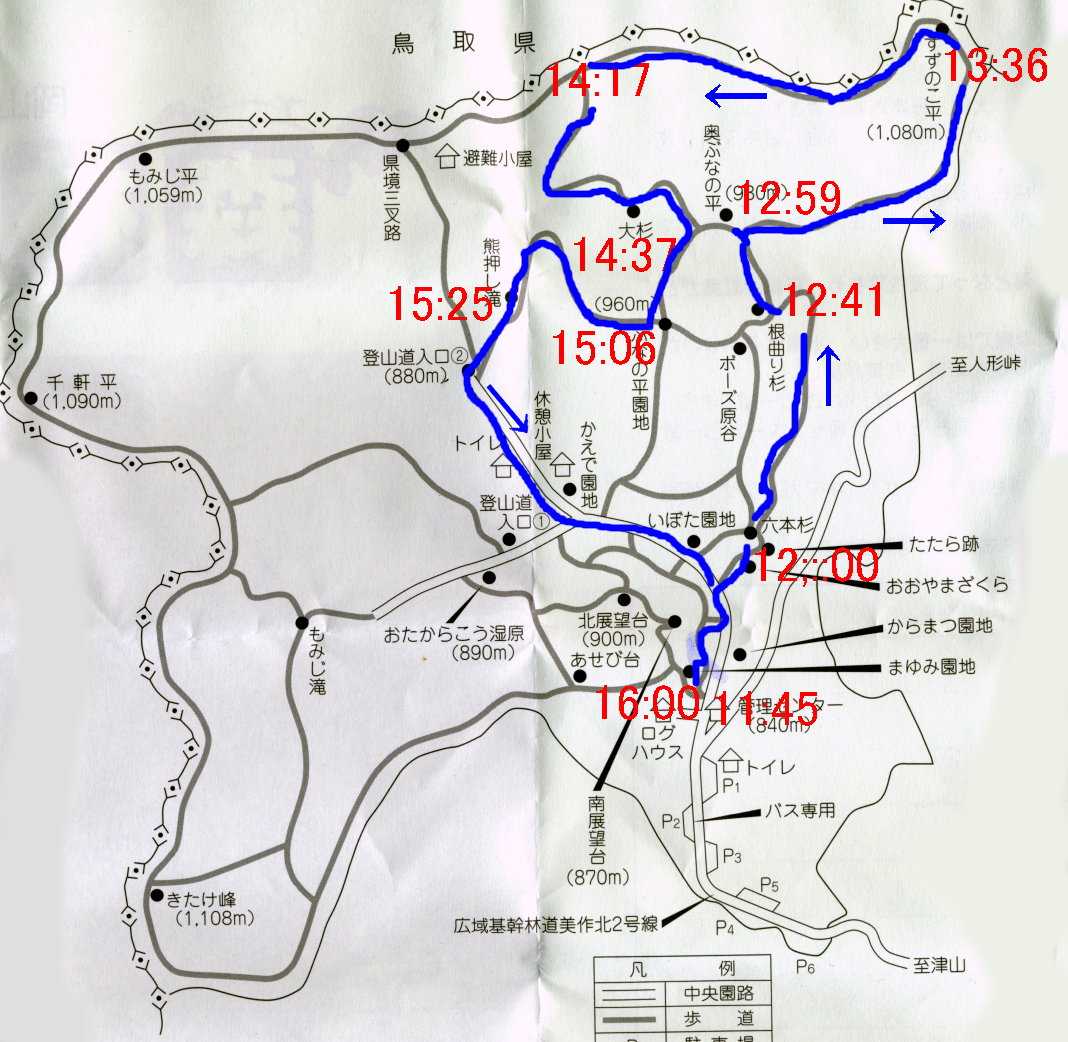2008年06月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
うちのムクゲ開花~ツユムシの雨宿り
ムクゲが雨の中、昨日開花した。1日花だが、これから次々と咲いていくだろう。 ツユムシが(と思うが)、その花の内側に収まっていたので、写真にした。
2008年06月30日
コメント(0)
-
ガクアジサイの「両性花」がこんなに魅力的とは!
アジサイの花序に「装飾花」と「両性花」があることは、周知のとおり。ただアジサイの種類により、両方の割合はさまざま。 このガクアジサイは、さし木から始まりやっと一人前になった。大きい「両性花」が花序の中心を占め、近づくと、それが次々と咲くのが楽しめる。開花のいろいろな段階が分かり、花びらの透明な感覚が夢を誘う。
2008年06月29日
コメント(4)
-
庭に生えた雑草?名前は?(ツタバウンランの突然変異?)
この「雑草」は去年くらいから現れたように思う。花の大きさは数ミリ程度。だから小さい草なのだが、葉っぱがモミジのような形をしているから、目立つ。花の中心にある黄身のような色が、キャラクターの目に見えなくもない。 これだけ特徴があれば、すぐ判ると思った名前、まだ判っていない。ご存知の方はお教えください。
2008年06月27日
コメント(9)
-
お久しぶり>カラー「ブレード」の花
このカラーの特徴は、赤系の花と葉っぱに点々と並ぶ白い「斑」。この斑が面白くて、4年ほど前に球根を買った。 もちろん、最初の年にはいくつかの花を咲かせた。当地の気候では球根が凍死するかと思い、1年目は掘り上げて室内に保存。2年目以降は面倒になって、そのまま放置。しかし凍死することもなく、毎年、春遅くには芽吹く。 いずれにしても問題なのは、以後さっぱり花が咲かないこと。ところが今年は、一輪だけど開花。今年違っていたのは、バラなどのついでに寒肥を与えたこと。ご利益があったの?
2008年06月26日
コメント(0)
-
これもフラワーロードfor自転車散歩
前に、田んぼのあぜ道に除草シートを張り、それに切れ目を入れてシバザクラを植える話を書いた(こちら)。そのアイデアマンの農家は、今度は夏用にマツバギクを植えた。 ここを自転車で通過すると、アッという間だけど、低地から吹き上げる風を受けて快適。(ただし冬は季節風が冷たい) 遠くに見える山際の道路は、できたばかりの東広島・呉道路。こちらは自転車に縁のない自動車専用道である。
2008年06月25日
コメント(0)
-
コチョウランの「寄せ集め」
コチョウランの寄せ植えならぬ「寄せ集め」。 三色のコチョウランの由来といえば、「人から預かったもの(実質頂いたもの)」、「父の日のプレゼント」、「某お祝いの贈りもの」と多様。だから、わが家での滞在年数もいろいろである。 1つの鉢にきれいに寄せられていたものをばらして、改めて1株ずつ鉢に植え、あとは勝手放題にした。厳冬期には数度まで温度が下がる場所だから、開花までの速度が遅々たる上に、花がなかなか揃わない。白いコチョウランなどは一度出たつぼみが枯れ、再度のつぼみが咲いた。
2008年06月24日
コメント(4)
-
アカメガシワの雄花
「アカメガシワ」という木に関心を持ったことはなかった。気がついてみたら、当地のあちこちの道路際に、小さい木がたくさん生えていた。 その一本が花を着けた。調べてみると、この植物は雌雄異株で、写真は雄株だった。それでは雌株は?と思うけれど、まだ見つけていない。 ことの発端のブログはこちら。あまりにも赤い葉っぱが見事なので、コメントを頂いても、にわかにアカメガシワと信じられなかった。その後見に行ったら、葉が緑に変わっていた。やはりアカメガシワかと思ったが、樹形は通常と大いに異なっている。
2008年06月23日
コメント(0)
-
野ばらとアイビーが絡んだ巨大ネックレス
野ばら(ノイバラ)の花はもう終わりだが、ここのノイバラはまだ咲いていた。 そもそもノイバラがこのように懸垂しているのは珍しい。そこへなぜかアイビーが、寄り添って懸垂し、風の悪戯もあって、「お隣」と絡み合い、ついには「ネックレス」になってしまったようだ。近づいてみても、お互いうまく融合している。 アイビーの葉の形はアサガオそっくりで、高校野球で知られたツタではないと思う。
2008年06月22日
コメント(2)
-
シロタエギクは梅雨の花?
シロタエギクにもいろいろ品種があるのかもしれない。他の株はみな枯れてしまったのに、どういう運命か、この株に限って同じ場所で、数年間「常白」を保っている。 このシロタエギクは、梅雨の始まる頃、鮮やかに黄色い花を着ける。それまでは目立たない存在だったのが、曇天のもと急に生き生きとしてくる。 (画面にあるオレンジ色の「物体」は、半分散ったスカシユリです)
2008年06月20日
コメント(4)
-
スパティフィラムの花
スパティフィラムはわが家の新顔。「父の日」の、娘たちからのプレゼントである。 スパティフィラムという名称は、サトイモ科スパティフィラム属に由来するから、生物学の呼称。そして「属」と言うことになれば、多様な仲間がいる気がするが、ネットでは専ら写真のような白い「花」。 白い「仏炎苞」は、水芭蕉を連想させる。それゆえに山野への憧憬を感じるのは、仙人だけだろうか。
2008年06月19日
コメント(2)
-
オゼコウホネ?@広島大生態実験園
コウホネの仲間に間違いないが、葉が水面から抜き出ない点で、オゼコウホネやネムロコウホネに近い。 オゼコウホネは花の中の「柱頭盤」が赤いという。しかし写真では判らない。いずれにしても、広島県では自生しない植物と思うが・・
2008年06月18日
コメント(0)
-
梅雨に濡れるシャスタデージーの1品種
今では野生化した感のある早咲きのシャスタデージーは、残念ながら「安かろう悪かろう」のイメージ。雨が降るとぐちゃぐちゃに倒れるし、ちょっと触れば花茎が折れる。庭の花としては、扱いにくい。 ところが写真のシャスタデージー(と思うが)は、花茎がしっかりしていて見栄えがよい。花の大きさも直径8.5~10cmに達し、花弁数も多く、微妙によれている。 今日は薄日の天気だが、前回の雨の姿をアップしてみた。
2008年06月17日
コメント(0)
-
キキョウソウの花
キキョウソウの花に久しぶりに出会った。すごく珍しい花ではないと思うが、かといってしょっちゅう見るわけでもない。道路脇にしても、川の土手にしても、エンジン草刈機で雑草が刈られてしまうので、咲く前にあえなく「命」を落としてしまうのかもしれない。 この花の紫は、薄色で微妙な色合いである。平安時代にタイムスリップしたわけではないが、高貴な色をしている。
2008年06月16日
コメント(6)
-
宿根カスミソウの花、クローズアップ
12日に宿根カスミソウのことを書いた。その時小さな花の「マツゲ」(雄しべ)について触れたが、どうも気になってしょうがない。 新しいカメラの能力を知るためにも、クローズアップに挑戦。しかし微風でも、風が最大の敵だった。
2008年06月15日
コメント(0)
-
バンドネオン奏者、佐川峯氏の近影
旧聞に属するが、5月25日、広島県立美術館に出かけた。本来の目的は、広島大学名誉教授、難波平人先生が主宰する、「波の会」の絵画展を見ることだった。ただ「ギャラリーコンサート」というアトラクションに惹かれていたのも事実。 展示された絵の前で、バンドネオンをお一人で演奏されたのは佐川峯氏。89才の高齢にもかかわらず、顔の艶だけでなく、眼力も、聴力も全く衰えていないらしい。最初の2,3分で会場の音の反響も、聴衆の心も読んでしまったらしい。まさに「魂のバンドネオン奏者」という賛辞がふさわしい。 年の功か、淡々とされていて、ネットには「非公式ファン・サイト」しかない。CDもないと言ってよい。 写真をアップするについては、「肖像権」のこともあり、躊躇した。しかし昨日、Googleしていたら、私の前で撮影していた方がアップしていたので、同調することにした。「非公式ファン・サイト」では、自分で作曲し、自分で演奏した曲なら自由に聞けるから、たぶんおとがめは受けないと思った。
2008年06月14日
コメント(2)
-
ほふく性のマツヨイグサ、コマツヨイグサ?
マツヨイグサにもいろいろ種類があるようだが、仙人がこれまでに見たのはどれも直立している。ところが、これは地面に張りついていて、斜上すらしない。 「ほふく性」に適合するのはコマツヨイグサ。しかし花の大きさが、ある本に書いてあった1センチほどではなく、3センチはあったと思う。夕方に咲き出すと、目立って美しい。 今のところ、ある区画だけに生えていて、今年初めて登場したように思う。何にくっついてやってきたのだろうか?
2008年06月13日
コメント(2)
-
種から育てた宿根カスミソウ
去年の秋に種蒔きした宿根カスミソウ、「スノーフレーク」。11月9日の様子はこちら。育てるのはけっこう難しいとのコメントを頂いたが、振り返って、最大の敵は幼苗をかじったナメクジだった。心配した耐寒性に問題はなく、マイナス数度の寒さに耐えた。最近ホームセンターで宿根カスミソウの苗を見たけれど、結構なお値段の上に、自分のほうが形がよかったので、大いに自己満足。 4本になったカスミソウが今咲いている(人にあげた苗があったかどうかは忘れた)。フラワーアレンジメントに組み込まれるカスミソウより花弁が小さめで(そう感じた)、全体にきゃしゃに見える。写真では分からないが、「マツゲ」がこんなに目立ったっけ?
2008年06月12日
コメント(4)
-
バイカウツギもそろそろ終わりかな?
うちのバイカウツギも雄しべが黄ばみ、花びらが散り始めている。新たに咲く花もあるから、新旧入り混じった状態。 写真は6日ほど前で、もっともフレッシュに盛り上がった姿。今でも盛んに香りを発散しているが、いっせい開花した栗の花の匂いに一脈通じている。
2008年06月11日
コメント(0)
-
「どくだみ邸」のドクダミは今年も花盛り
このブログで「どくだみ邸」のドクダミを取り上げるのは、3度目(前回はこちら)。季節は巡るである。 「どくだみ邸」とは、普段は人のいない、さいたま市の家のこと。去年、ヤブ蚊と強い匂いを我慢しておおかたを抜いたのだが、そんなことは大勢に影響しなかった。むしろドクダミ以外の雑草が駆逐されてしまった。 JR南浦和駅の線路脇にも生えているこの植物、日向と日陰の中間に最適条件があるようですね。
2008年06月10日
コメント(5)
-
大江戸神楽@浜離宮
テレビで見たことはあるけれど、こういうのを「大江戸神楽」と呼ぶことは知らなかった。かって東京に通学・通勤していても、下町の歴史には疎かった。 広島県で「神楽」と聞くと、広島市の北部山間に点在する神楽団を連想してしまう。こんど、ブラジル・サンパウロで催される「日本文化週間」に招かれて、安芸高田市の神楽混成チームが出演するという。 この催しは、日本からの移民100周年を記念したもの。演目は、「紅葉狩(もみじがり)」、「滝夜叉姫(たきやしゃひめ)」、「八岐大蛇(やまたのおろち)」とか。 「大江戸神楽」は、このイメージからは大いに離れている。しかし写真の彼女もブラジルに行くそうで、英語のトークを練習しなくちゃとか言いながら、10人余のお客さんを笑わせた。そのとたん、通行中の外人さんが振り返ったよ。 このブログを書くに当たって検索したら、ミノル太さんのブログにぶつかった。彼女は去年の年末にも、全く同じ場所で芸を披露したようだ。 もう一つ、陶片木さんのブログを読むと、柴又帝釈天では、芸の最中、ヤジを飛ばし続ける悪ガキがいたようだ。しかし浜離宮ではそんなことはなく、老若男女が一体となって、彼女の「呼吸」がこちらに伝わる芸を楽しんだ。 30分を超える演技を見ていたら、次の約束には遅れてしまった。
2008年06月09日
コメント(6)
-
ユリノキの花@浜離宮
浜離宮の花も関心事だったのだが、6月上旬の「花木園」にはたぶん、ヤマボウシの白い花だけ。「ボタン園」も終わり。 快晴の日だっただけに、光を反射するビル街に挟まれて盛り上がる濃い緑が、むしろ暑苦しい。日陰を作る建屋には昼寝をする人も。 しかしハナショウブはこれから。全体の流れからすれば遅い気がして、違和感も。自分の住む東広島とは、「植物の進行表」が違う気がした。 写真は、ユリノキの花。色が地味なだけに誰も気がつかない。十メートルを超える高木が3,4本も並んでいた。
2008年06月08日
コメント(0)
-
浜離宮恩賜庭園・内堀
浦和(現さいたま市)にはずいぶん長い間住んでいた。特に都心の高校に通っていた頃には、友達がよく浜離宮のことを口にした。 しかし「灯台もと暗し」というか、この歳までついぞ訪れたことがなかった。このたびの上京で、発奮して出かけることにした。すでに「前期高齢者」なので、入場料が150円と安い。 そもそもJR松町駅の近くの緑がそれと思っていたのが大間違いで、重い荷物を引っ張って、15分以上も歩くことになった。暑い日だったし、スイスイと走るサイクリストが羨ましかったこと! 結局、見物できたのは、出入口である中の御門と大手門の周辺だけで、ほんのさわりに終わってしまった。(写真は大手門に近い内堀)
2008年06月07日
コメント(4)
-
白バラと白いカーネーション@結婚式
結婚式の写真。とはいえ、花にフォーカスしている。 うちの白バラは、オーナーとアイスバーグ、そしてマーガレットメリルだけど、いずれとも違うようだ。 カーネーションは八重で、花が巨大。いろいろな品種があるね。
2008年06月06日
コメント(0)
-
枝垂れウメの実が印象的
6日ぶりのブログ。身体をこわしたわけでもなく、デジカメがまた故障したわけでもない。新発売、Nikkon COOLPIX P80は快調である。 食用のウメを梅干しや梅酒にするのは当然だが、枝垂れウメとなると、なんかもったいない気もする。写真の品種は「藤牡丹」で、実は花をよく知らない(汗)。ただ数少ない果実が、貴重で美しく見えた。
2008年06月05日
コメント(2)
全24件 (24件中 1-24件目)
1