2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年11月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
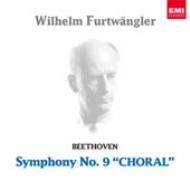
フルトヴェングラー没後50年(追記あり)
『今日のクラシック音楽』 ベートーベン作曲 交響曲第9番ニ短調 作品98「合唱付き」1954年11月30日は、大指揮者ウイルヘルム・フルトヴェングラーの命日で、今年は没後50年という年にあたります。 そこで彼の遺した膨大な演奏記録やスタジオ録音などの中から1951年の戦後復興に立ち上がったドイツ国民が、待ちに待った「バイロイト音楽祭」の再開時のオープニングコンサートでのフルトヴェングラー指揮の演奏会ライブ録音盤を採り上げることにしました。1960年(中学2年生)にクリスマスプレゼントに買ってもらったトスカニーニの52年録音盤のLPが「第9」との初めてのめぐり合いでした。 それを高校2年生まで聴いていたのですが、「第9」そのものへの感動でした。その後、雑誌「レコード藝術」でフルトヴェングラーのこのバイロイト音楽祭のLP盤を知り、聴きたくてうずうずしていたのですが、当時このLPはトスカニーニのLP1枚に較べて、カートンボックス入り2枚組みで売り出されており4千円でしたので、高嶺の花でした。 高校2年生の修学旅行で親戚や親から貰って旅行の小遣いを遣わずに、念願のこの2枚組みLPを買いました。演奏を聴いた時の感動は今でも覚えています。 トスカニーニのきびきびした運びと対照的な、遅めのテンポで変幻自在とも表現できるフルトヴェングラーの演奏にすっかり魅せられて、その後彼のほかのレコード(ワーグナー、ブラームス、その他の音楽)を数多く聴くきっかけになったLPでした。テンポを自在に操り、曲の新しい側面を随分と見せられてきました。 休止符でさえ音楽を物語っているのです。 このバイロイト祭ライブはその典型で、のちに色々な指揮者の演奏を聴いていますが、これほどに強烈なインパクトを与えてくれた演奏は後にも先にもなく、彼の真骨頂の即席性が遺憾なく発揮され、深遠、荘厳さを深く滲ませ、テンポを自在に動かしながら聴かせていく、まさに第9演奏における最高の形で残されている演奏だと思います。 それが一発勝負のライブ録音というところに彼の偉大さ、この録音の貴重さを物語っています。たった1枚だけ第9の演奏を選べと言われると、躊躇なくこのバイロイト祭ライブ盤を選ぶでしょう。 不滅の演奏、名盤とはこういうものだと思えてならない「人類の遺産」だと思います。この時の演奏会を客席で聴いていた日本人がいます(フィクションとありますから、そうでないかも知れません)。 雑誌「レコード藝術」の今月号(12月号)にそのことを投稿されています。 雑誌社(音楽の友社)及びご本人に無断で転載致しますことをどうかご容赦下さい。 それほどにこの演奏を的確に表現している言葉だと思います。『1951年7月29日早朝、私はフランクフルトからバイロイトに向かう列車に乗り込んだ。 この日、フルトヴェングラーがベートーベンの「第9交響曲」を指揮するだ。 途中、ニュルンベルグで乗り換えての4時間。 私ははやり立つ心を抑えるのに必死になっていた。 ハイデルベルグ留学中の、生涯忘れ得ない思い出である。 (中略) バイロイトの祝祭歌劇場は木造。 1800人を収容する格好の大きさだ。 ホワイエは、世界各国かた集まった聴衆でいっぱいだ。 なかに日本人らしき聴衆も何人かいた。いよいよ開演。 固唾を呑んで見守る私たちの前に、フルトヴェングラーがついに姿を現した。 かつかつと驚くほど高い足音だ。 拍手の鳴り終わるのを待って、フルトヴェングラーの右手が、ゆらゆらと動くや、交響曲は荘重に始まった。 それは初め、はるか遠くに稲妻の走るかと見えたが、たちまち急接近し、突如として頭上に、巨大な雷鳴が炸裂するかのような衝撃である。 その冒頭からして、これまでいくつも聴いてきた「第9」とはまったく次元が違う。 私たちは一気に、忘我、興奮のるつぼの中に投げ込まれた。彼の音楽は常に前傾姿勢。 しかもテンポは悠然としているのに、リズムが鮮烈だ。 緊張感が失われることは一瞬たりともない。 そして極大のクレッシェンドと、恐るべき長い間に、私は思わず大声で叫び出したい衝動に駆られた。そうだ。 これは演奏会であるが、同時に敬虔な信仰の世界だ。 聴衆全てが、目の前に現出される"音の奇跡と啓示"に陶酔しきっているのだ。 いやいやその陶酔は聴衆だけではない。 歌手は歌いながら、自らの名唱に聴き惚れている。 また奏者は演奏しながら、彼ら自身の名演奏に感動しきっているのがはっきりわかる。そして最後の疾風怒濤のクライマックス。 私たちは立ち上がって、涙を流しながら猛烈な拍手を送った。 ベートーベンは交響曲を9番目まで作っていてくれた。 フルトヴェングラーはよくぞ空前絶後の名演奏を聴かせてくれた。 私たちは永遠に消えることのない幸福感で、胸がいっぱいだった。 万来の拍手はいつまでも止もうとしない。 そうだ、この拍手は、この半世紀、一度たりとも鳴り止んだことがなかった』 京都市 某男性 70歳永遠の名盤 (東芝EMI TOCE3725 1951年バイロイト音楽祭ライブ録音)フルトヴェングラー指揮 バイロイト祝祭管弦楽団・合唱団 エリザベート・シュワルツコップ(ソプラノ)、ハンス・ポップ(テノール)、エリザベー・ヘンゲン(コントラルト)、オットー・エーデルマン(バス)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月30日
コメント(7)
-
プッチーニ 「マノン・レスコー」 / 台所で倒れる
『今日のクラシック音楽』 ジャコモ・プッチーニ作曲 オペラ「マノン・レスコー」今日はヴェルディと並んで現代でも最も舞台上演回数の多い、イタリアのオペラ作曲家ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)の命日です。 1924年の今日(11月29日)、彼は生涯最後のオペラ「トゥーランドット」を完成しないまま、ベルギーのブリュッセルで亡くなっています。「マノン・レスコー」はプッチーニの3曲目のオペラで、このオペラが大成功したことによって彼のオペラ作曲家としての地位が確立されたと言われています。 命日にちなんでこの記念すべきオペラを聴いてみようと思います。原作はフランスの作家アヴェ・プレヴォーの「騎士デ・グリューとマノン・レスコーの物語」という有名な小説で、美しい女性マノンと運命の邂逅で恋に落ちた青年デ・グリューが、彼女と愛し合って駆け落ちをするのですが、奔放な彼女にふりまわされて、自分の約束されていた将来を棒に振るのですが、刑事罰を受けたマノンがアメリカの流刑先へと流される時に、自分も一緒にと過酷な道を選ぶのですが、最後にはマノンが倒れてしまい、デ・グリューも力尽きて彼女の亡骸に重なって倒れてしまうという物語です。劇中のアリアでは、デ・グリューの「なんと素晴らしい美人」やマノンのアリア「柔らかなレースの中で」、「ひとり寂しく捨てられて」があり、リサイタルなどでも単独で採り上げられることの多いアリアです。この原作小説は映画や演劇、バレエなどに採り上げられており、オペラでもマスネーが書いています。 1948年に製作されましたアンリ・クルーゾー監督の映画「情婦マノン」を学生時代にリヴァィヴァル上映で観ましたが、死んだマノンを逆さまに背負って砂漠をさまよい歩くデ・グリューの絶望的なラストシーンが忘れられません。愛聴盤 キリ・テ・カナワ(ソプラノ) プラッシード・ドミンゴ(テノール) シノーポリ指揮 コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団・合唱団CDではなくて、1983年にイギリス・コヴェントガーデンのオペラハウスで上演された舞台のビデオで、これをNHKが放映したのを録画しており、それを楽しんで観ています。マノン役は美人ですと舞台映えして、いっそうこのオペラを楽しませ、最後には落涙させるのですが、キリ・テ・カナワの美貌・容姿と歌唱力、ドミンゴの最盛期と思われる演技と歌唱力に圧倒される舞台です。 何度観ても涙なしに観ることのできない名舞台です。CDでは、レナータ・テバルディ(ソプラノ) マリオ・デル・モナコ(テノール) モリナーリ・プラデッリ指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管・合唱団とにかくテバルディに尽きる録音盤です。 1954年の録音ですから彼女は当時32歳。 この年で全幕を歌いきり、魅了するとは! 清楚、奔放、熟成、諦観の境地を見事に歌い分けています。 どこか一本調子のモナコを圧倒するほどの歌唱。 やはり稀代の大ソプラノであったことを改めて痛感させられる歌唱・演技です。 この人のこのオペラの立ち居姿を舞台上で観たかったと思うのは私一人ではないでしょう。1962年の「トスカ」「アンドレア・シェニエ」を観れただけでも幸せかな?(ロンドンレーベル POCL3832 1954年ローマ録音 ステレオ最初期の名録音がデジタルリマスターの最新技術で蘇りました)『その他今日のカレンダー』1643年 逝去 クラウディオ・モンテヴェルディ (作曲家)1797年 誕生 ガエタノ・ドニゼッティ (作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『台所で倒れる』昨日の夕方の話ですが、使った大鍋を台所の天井近くに備え付けの戸棚にしまいこむ時のことです。 この戸棚は食卓の椅子の上にまで張り出している代物で、この大鍋を両手で頭の上に持ち上げて、椅子の上に上がってしまいこむ時に、戸棚の張り出しのために体全体が両手で鍋を持ち上げた状態で、少し後に反るような体勢になってしまい、バランスを少し崩しました。 頭の上近くに鍋を支えているものですから、そのバランスの崩れで一気に食卓の上に仰向けに倒れこんで、そのまま食卓から床に転げ落ちてしまいました。幸い怪我はなく、今朝起きても打ち身の痛さもなく良かったのですが、ひとつ間違えば食卓の向かい側にある食器棚のガラス戸に頭ごと突っ込んでいたかも知れず、ぞ~とする思いでした。これはきっと神さまが守ってくれたのだと思います。 食卓にはパックのままの玉子や、食材入りのガラス瓶などがあったのですが怪我もなく、玉子も割れずにいたことは奇跡に近いことなので、きっと神さまのご加護だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月29日
コメント(8)
-
ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番 / 今日も競馬で・・・・
『今日のクラシック音楽』 セルゲイ・ラフマニノフ作曲 ピアノ協奏曲第3番 二短調 作品30 1909年11月28日は、セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)が書きましたピアノ協奏曲第3番がアメリカ・ニューヨークで初演された日です。彼はロシア出身でピアニストとしても卓越した技巧の持ち主で(作曲もピアノ曲が多く遺されています)、コンサートピアニストとしても有名で、アメリカコンサート協会からの招きで1909年にアメリカに演奏旅行を行なっています。その2年前から構想を持っていたピアノ協奏曲をアメリカで初演すべく書き上げて、1909年の今日、11月28日に初演されました。 その翌年1910年1月16日には、当時アメリカに滞在していました作曲家・指揮者のグスタフ・マーラーの指揮、ニューヨーク交響楽団、ラフマニノフのピアノ独奏でこの曲が演奏されて大成功をおさめたそうです。その後1917年に「ロシア革命」が起こり、ラフマニノフはアメリカに亡命して1943年にカリファルニア・ビヴァリーヒルズで亡くなるまで住むことになり、亡くなる前にアメリカの市民権を得たそうです。曲は形式通りの3楽章で、第1楽章は哀愁を漂わせた旋律と、のびやかな歌の2つの主題で展開し、第2楽章は狂詩曲風の主題が変奏されて華麗さを帯びていき、切れ目なく第3楽章に続いていきます。 フィナーレの第3楽章は、マーチ風の主題とロシア情緒あふれる主題で繰り広げられ、スケール豊かな終結部へと進んでいきます。以前の彼の作品に較べてシンフォニックに書かれており、スケールの大きな作品で、演奏時間に約40分を要する大曲です。愛聴盤 マルタ・アルゲリッチ(ピアノ) リッカルド・シャイー指揮 ベルリン交響楽団(フィリップス PHCP20017 1982年12月 ベルリン演奏会ライブ録音)アルゲリッチ43歳の時の録音で、コンサートのためか他のピアニストに較べると奔放さ、大胆、華麗さ、熱気そして繊細さが感じられる演奏で、数多く録音されているこの曲のデイスクの中でも第1級品の盤としてお薦めできる録音盤です。『その他今日のカレンダー』1811年 初演 ベートーベン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日も競馬で・・・』今朝もいつもの珈琲ショップへ行くと、大勢の中高年男女だ来ており、話題は今日の「競馬」。 どの馬が入るとか、園馬はダメだとか賑やかな競馬談義をしていました。それぞれが思い、思いに馬券購入考えていると、馬券を買いに行く人がやってきた。 各自が書いた予想メモを受け取り馬券購入用紙に書き込んでいる。 もうそれも終わり頃になると素っ頓狂な声をあげた。 「何や、これ! 殺生やで!」 何と100円で50組を買う人がいたらしい。 一人で買い行く人の身になってあげればこういう買い方はできないだろう。 50枚の用紙に書き込んで持って行かねばならない。 それに買った馬券が当たり券でもあとの49枚は外れだから、何のために馬券を買うのかわからなくなる。珈琲ショップのマスターがメモに記載の人に電話して、すぐ来るように言ったのでやってきた。 50歳くらいの主婦で、すぐに組み合わせを変えて買っていた。今日も競馬で賑やかな珈琲ショップでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月28日
コメント(4)
-
R.シュトラス 交響詩「トゥラトウストラはかく語りき」 / 贈り物の習慣の意味
『今日のクラシック音楽』 R.シュトラウス作曲 交響詩「トゥラトルストラはかく語りき』SF映画の古典とされているスタンリー・キューブリック作品「2001年宇宙の旅」に流れていた音楽で、クラシック音楽を知らない人たちはこの曲の冒頭の音楽が映画用に作曲されたと思っていたほど、このSF映画にぴったりとマッチしており、映画で使われた部分は、曲の冒頭の部分でオルガンの重低音の鳴る中をトランペットが高らかに鳴り響き、テインパニーが轟き渡るという、まさに「宇宙の創造」のような音楽がこの映画に実にうまく融合していました。実はこの音楽はR.シュトラウス(1864-1949)が書いて、1896年11月27日にドイツのフランクフルトで作曲者自身の指揮で初演されています。曲の題材はドイツの哲学者ニーチェの同名書から採られています。 ニーチェはこの本で書こうとしていたのは、キリスト教を否定した「超人」の思想なのですが、シュトラウスは忠実にこの哲学書を音楽にしたのではなく、作曲者自身がこの本を読んで感じたことを自由に、詩的気分で書かれているそうです。曲冒頭の部分は、オルガンの響きがまるで地底から湧き上がってくるような導入部から始まり、トランペットがいっそう興奮を呼ぶような、精神を鼓舞するように、「旭日昇天」といった旋律が奏されたあと、弦による敬虔な主題や、ホルンなどの荘厳な旋律に溢れており、シュトラウスの美しく、華麗なオーケストレーションが繰り広げられていく様は、シュトラウス音楽の真骨頂です。愛聴盤 アンドレ・プレビン指揮 ウイーンフィルハーモニー (USAテラーク CD-80167 1987年11月26-28日 ウイーン録音)ウイーンフィルのアンサンブルが極上の音で魅了します。 しなやか、艶のある弦楽器、決して硬くならない柔らかいホルンの音色、こぼれるような優雅さを湛えた木管楽器の響き。 これらをプレビンは極上のブレンドに仕上げたまさに名演奏で、テラーク特有の超優秀録音によりこれらの音を楽しめます。『今日のその他のカレンダー』1926年 初演 バルトーク バレエ音楽「中国の不思議な役人」1931年 初演 ラヴェル 「ピアノ協奏曲第3番」1955年 逝去 アルテュール・オネゲル(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『贈り物の習慣の意味』これまで私は、お中元、お歳暮といった贈り物をする習慣とその意味をきちんと知らなかった。 だが、百貨店のお菓子売り場のアルバイトをしたことで、その本来の意味を知った。例えば贈り物をする際には、用途に応じたさまざまな熨斗紙がある。 水引にもちゃんと意味があるのを知った。 花結び、結びきり、この二つでは大きな違いだ。 包装の仕方も香典返し、入院見舞いといった物には、品物の上下を逆にして包装する。 「悲しみを流す」という意味があるらそうだ。売り場の店員のほんのわずかな間違いでも、致命的なミスとなってしまうかも知れない。 こういって贈り物をする機会のない私には、なんて面倒なことなんだろうと感じた。 でも、こういう細かい心遣いがあってこそ、貰う側にとってはうれしいのだろう。私が季節の贈り物をするような年齢になったら、この経験を生かして喜ばれる贈り物をしたい。 産経新聞2004年11月26日朝刊「談話室」 茨城県 大学生 20歳女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月27日
コメント(10)
-
ケテルビー 「ペルシャの市場にて~ケテルビー管弦楽曲集 / ダイエット
『ダイエット』2年前の4月に病院の医師から糖尿病予備軍と言われて、病院の栄養士と1800Kcal/日の摂取を守る食事メニューを相談して決めた時に、なるべく緑色野菜を摂るように言われました。それから間食を一切やめて、ご飯をお茶碗に一杯だけに減らして、野菜を主にメニューを考えて食事療法を行いました。 そして、妹からゴーヤ茶を勧められ飲むようになってから体重が減っていき、3ヶ月で10kg減りました。買ったゴーヤを2mm-4mmくらいに輪切りして、天日干しでからからに乾燥させた後、フライパンで油なしで少し色がつくまで空炒めしたのを、ペットボトル1リットルにゴーヤ輪切り3-4枚でゴーヤ茶を作り、それを毎日1本飲むことを励行したお陰です。 勿論、食事療法で1800kcalは今でも守っていますし、間食もできるだけ避けています。それをもう2年と半年励行しています。 そのお陰で太ることはなくなりました。 最近はゴーヤ茶の摂取を怠ることが多くて、少し自分を戒めています。私のダイエット方法です。人それぞれの療法でダイエットを無理なくすればいいと思いながら、今日は療法の一つをご紹介しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 アルバート・ケテルビー作曲 「ペルシャの市場にて~管弦楽曲集」1875年11月26日は、イギリスの作曲家アルバート・ケテルビ(1875-1959)が亡くなった日です。 彼は管弦楽曲の小品で異国情緒たっぷりの作品を書残しています。 標題の「ペルシャの市場にて」、「中国寺院の庭にて」、「修道院の庭にて」、「エジプトの秘境にて」などの有名曲があります。この「ペルシャの市場にて」はその中でも最も有名な曲で、今のイランの市場の情景をエキゾチックな東洋風の旋律で色彩豊かに、市場の賑わいを描いた音楽で、とても親しみやすい曲です。その他にも、例えば「中国寺院の庭にて」などは「東洋風の幻想曲」とサブタイトルがつけられているように、曲は東洋風の異国情緒に彩られている、とても魅力的な曲もあります。愛聴盤 アレクサンダー・フェイリス指揮 ロンドン・プロムナードオーケストラケテルビーの管弦楽曲集で、上記4曲の他に6曲の標題音楽が収録されており、これ1枚でケテルビーのオーケストラ作品を知るのに充分なCDです。 録音も超優秀盤です。(フィリップス 400011 1981年ロンドン録音 輸入盤)2005年11月26日に「サボテンさん」のコメントをいただくまで、ケテルビーの命日と誕生日を間違えておりました。ここにお詫び申し上げますと共に、訂正させていただきます。(2005年11月27日 記)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月26日
コメント(8)
-
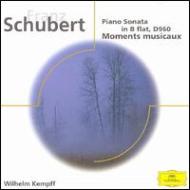
シューベルト 「楽興の時」 D780 / 信濃路へ
『今日のクラシック音楽』 フランツ・シューベルト作曲 「楽興の時」D780 (作品94)フランツ・シューベルト(1797-1828)は多くのピアノ作品を書き遺しています。 21曲のソナタ、3つの即興曲集、幻想曲風ソナタ「さすらい人」、それにこの「楽興の時」などです。彼の前の作曲家ベートーベンのピアノ曲は総てではありませんが、古典的な様式を曲のなかに深く滲ませていましたが、ベートーベンが亡くなった翌年(1828)に短い生涯を終えたシューベルトのピアノ作品には、ベートーベンの「ソナタ形式」を保持したのと違い、もっと感興の趣くままに書かれた作品が多くあります。 この「楽興の時」D780もその例外ではありません。 ただロマン派の曲としては、幻想風に書かれているのではなく、彼自身の中に感興のままに楽想が湧き出るような形で書かれています。 この曲の中でも「第3番」として有名な3曲目の「ヘ短調」は子供の頃から聴き親しんだメロデイーで、誰もが一度はどこかで耳にしている有名曲です。愛聴盤(1) ウイルヘルム・ケンプ(P)(グラモフォンレーベル 469668 1967年ドイツ録音 輸入盤)1895年の今日(11月25日)生まれました不出世のドイツのピアニスト、ウイルヘルム・ケンプの誕生日にちなんで、今日はこのシューベルトの「楽興の時 D780」を聴くことにします。(2) もう1枚 アルフレード・ブレンデル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCP7042 1972録音)ブレンデルの深い叙情性をたたえたピアノの音色に魅せられます。 紹介盤はお求めやすい1000円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『信濃路へ』2日間(11月23日ー24日)はこれ以上ないと思われるような素晴らしい秋晴れに恵まれて、阪和道/近畿道/名神高速/中央道を走りながら、バスの車窓の両側にパノラマのようにどこまでも続く山々の紅葉を愛でながらの旅となりました。中央道恵那山トンネルを過ぎていくと空の色も、いっそう深みを帯びた青となり、道路脇の土手のススキと紅葉の紅や黄色に色づいた木々と美しいコントラストをなしていて、しばらくバスを停めて美しい自然の織り成すパノラマを観ていたいと思うほどでした。23日の目的地は諏訪大社参詣。 そこへ行くまでに日本アルプスの赤石岳や乗鞍岳を遠くに臨み、そのアルプスの峰の頂には早くも白い雪が太陽に映えており、これも深い空の青い色とくっきりとしたコントラストを成していて、サービスエリアではバスの出発ギリギリまで観ていました。 望遠レンズ装着カメラでなく、デジカメコンパクトなので写真を撮ることは出来ず、みなさんに観ていただけないのが残念です。「御柱」で有名な諏訪大社へ午後2時半頃に参詣したあと、翌日訪ねて行きます国宝「松本城」を見ながらその日の宿泊地、松本市内にある浅間温泉に4時半に到着。ここの温泉は「単純アルカリ温泉」ですが、市内20軒ほどある旅館、ホテルへ流すために「源泉かけ流し」でなく「循環」ですが、やはり肌にぬめっとする湯心地は格別で朝7時半の早朝出発という少し疲れた体を休めるのに充分でした。総勢32名の参加となり、宴会場での夕食には名物「野沢菜」それに川魚料理が供されて、地酒「松本城」で一献傾けながらの嬉しい、楽しい宴会となりました。宴会後も翌朝6時までに2回目を覚まして、そのたびにお湯につかる「温泉三昧」を楽しんで気ました。次の朝は、さすがに盆地の松本だけあって空気は冷たく、冷え冷えとした朝でしたが、雲ひとつない深い青空で「情念岳」などアルプスの稜線がくっきりと朝焼けに映えていました。8時半にホテルを出発して国宝「松本城」を訪れて、うちの町の出身で初代松本中学校長をされた山村有也先生が、このお城の保存運動に立ち上がって今日の保存の礎になった史実を観てきました。 城のお堀にも温泉が湧いているのでしょうか、堀の一角にはぼこぼこと湧き上がるところがあり、湯煙が立ち込めていました。城そのものは非常に規模が小さく、お庭も狭い、小さな庭園でまるで箱庭の中に小さなお城が建っているといる趣きでしたが、木造建築のまま残されており現在は国宝となっています。城をあとに長野市にある「牛に引かれて善光寺」へ向かいました。 バスで約1時間。 残念ながら木造の三門(ここは山門でなくてこう呼んでいます)は全面改築中で、その勇姿を観ることが出来ませんでした。ざっと1400年の歴史を持つ日本最古の、御仏を祀るこのお寺は檀家を持たず、現在は天台宗と臨済宗が代表で管理しています。 7年に一度本堂(1707年建立の木造檜皮葺き)の本尊が開帳されますが、これも昨年の5月に開帳されたばかりでした。善光寺参りを終えて、やって来た路をたどって帰る途中にも好天に恵まれて、諏訪湖をとりまく丘や山の紅葉などを車掌から愛でながら無事夜の9時ごろに大阪泉州に戻ってきました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月25日
コメント(5)
-
ギューして
娘は10才ギューして・・・・は抱きしめての意味小柄な私に似ず背丈は負けそうだギューして・・・・のリクエストに応えて思いっきり抱きしめてやる哀しいこと・・嬉しいこと・・悔しいこと・・何があったのだろう何も聴かずにギューしてあげるそしたら また笑顔で離れていく 産経新聞2004年11月22日付け朝刊 朝の詩 大阪泉南市 44歳女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」は休みます。信濃路「旅日記」は明日掲載します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月24日
コメント(2)
-
ファリャ 「三角帽子」 / 信州路へ
『信州路へ』今朝7時半に出発して信州路へ神社役員たちと旅行に出かけます。 泊まる先は浅間温泉です。 松本城、上諏訪神社、善光寺と巡ってきます。 松本城にはこの町の古文書が保管されているそうで、それを見てきます。帰阪後に「旅日記」を書いて掲載致します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 マヌエル・デ・ファリャ 作曲 バレオ音楽「三角帽子」1876年11月23日は、スペインの作曲家マヌエル・デ・ファリャ(1876-1946)が誕生した日です。 ファリャは2曲のバレエ音楽「恋は魔術師」「三角帽子」で一躍有名になった作曲家で、今日は彼の誕生日にちなんでバレオ音楽「三角帽子」を聴いてみましょう。スペイン音楽と言えばすぐ名前が出てくるのがアルベニスとグラナドスという二人の作曲家です。 その二人の後の世代にあたるのがこのファリャです。 二人の先駆者同様に、ファリャも自国の音楽を取り入れて民族性豊かな曲を残しました。この「三角帽子」は、前作のバレエ音楽「恋は魔術師」の成功により、1900年代初頭にバレエ界に君臨していた「ロシアバレエ団」の主宰者セルゲイ・ディアギレフの依頼で書かれています。曲は第1部、第2部とに分かれていて、それぞれにソプラノとメゾ・ソプラノの歌入りというバレエ音楽にしては珍しい構成の音楽で、この女声がいっそう官能的に盛り上げてスペインらしさを演出している音楽です。冒頭にはいきなりテインパニーの音が鳴り響いて、それに続くカスタネットの響きと「オーレ!、オーレ!」の勇ましい掛け声に続いてメゾ・ソプラノの実に悩ましげな、官能的な歌によって、いきなり聴く人をスペインへ運んでくれます。物語はスペインの同名小説を題材にしており、好色代官が美しい粉屋の妻を我が物にしたいが、粉屋と妻にひどい目に遭わされるという筋書きです。全編がスペイン色に塗りつぶされた楽しい音楽です。 第2部の「粉屋の踊り」はコンサートやレコード名曲集などに単独で演奏・録音されています。 演奏時間 約38分愛聴盤 シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団(LONDON レーベル ユニバーサルミュージック発売 POCL 5086 1981年モントリオール録音)『その他今日のカレンダー』1834年 初演 ベルリオーズ 交響曲「イタリアのハロルド」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月23日
コメント(10)
-
ラヴェル 「ボレロ」
『今日のクラシック音楽』 モーリス・ラヴェル作曲 「ボレロ」1928年11月22日は、音楽史上になかった、また後世にも書かれることのなかった、同じ主題だけが延々と演奏され続けるという画期的な音楽が初演された日です。 フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)が書きました管弦楽作品の「ボレロ」です。 もともとフランスのバレエ団の舞台上演用として書かれた音楽ですが、この日演奏会用としてコンサートで初演されたそうです。とにかく音楽常識からしますと完全に常軌を逸脱した音楽なのです。 曲の始まりは小太鼓。 CDで聴いていても思わず音量つまみを上げてしまうほど小さな小太鼓の音が「タン・タタタタン、タン・タタタタン・・・・」と単調なリズムを刻んで始まります。 そうしているうちにフルートがどこかエキゾチックなメロデイーを吹き始めます。 続くクラリネットが後半の旋律を引き継いで吹き始め、この同じ(全く同じ)旋律を別の楽器が延々と引き継いでいくのです。その間小太鼓で、相変わらずあの始まりの単調なリズムが間断なく刻まれており、しかも執拗に繰り返される同じ旋律が延々と楽器を変えて演奏され続け、やがて音量を増していき、フルオーケストラでリズム、同一メロデイー、響きが一体となって音楽はそのままクライマックスを迎えて、まるで爆発するかのように転調した瞬間に音楽が終るという曲なのです。 音楽の終焉はまるで階段から人が転げ落ちたかのような終り方です。演奏時間 約15分の曲です。一つの旋律、主題とリズムだけが楽器を替えることだけで始まりから最後まで繰り返される音楽はこの1曲だけではないでしょうか。ラヴェルは旧ロシアの作曲家ムソルグスキーが書きましたピアノ曲「展覧会の絵」を華麗な管弦楽作品に編曲して、現代でもオーケストラ作品としては最もポピュラーな曲に仕立てあげているように、「オーケストレーションの魔術師」と呼ばれた人でした。 この「ボレロ」でも同じ主題を演奏させる楽器の音色、彩りなど計算し尽して書かれているように思えます。 ストラビンスキー(作曲家)がラヴェルを評して「スイスの時計師」と呼んだそうですが、オーケストラを知り尽くした正確無比な音楽設計を評してのことでしょう。 この「ボレロ」はそれほど人を喰ったような音楽であり、興奮させる音楽、そして最後には感動させる音楽です。ラヴェルはその後交通事故に遭い、脳が少しずつ縮小していく残酷な脳障害に冒されました。 彼の頭の中では新しい音楽が鳴り響いていても、それを楽譜にして音楽にすることができなくなっていったのです。 亡くなる直前まで脳は理性を保ち、音楽を鳴らせているかのような残酷な運命を与えられたそうです。そして、あたかもこの「ボレロ」の終結が突然転調して爆発的に曲を閉じたのと同じように、彼自身も頭の中で音楽を響かせながら悲劇的にその生涯を閉じたのです。この曲を聴くたびに、私は彼の生涯の終焉でのわずかな期間の、階段から転げ落ちたような、悲劇的な人生に思いを馳せるのです。お薦め盤 ケント・ナガノ指揮 ロンドン交響楽団 (ワーナークラシック WPCS-21213 1992-1997年録音)この曲は名盤が目白押しで、一番好きなのがエルネスト・アンセルメ/スイスロマンド管弦弦楽団の録音ですが、このナガノ盤はカップリングも良く(ラ・ヴァルスほかラヴェル管弦楽曲)廉価(\1,000)ですので採り上げました。『その他今日のカレンダー』1901年 誕生 ホアキン・ロドリーゴ (スペインの作曲家 「アランフェス協奏曲」で有名)1913年 誕生 ベンジャミン・ブリテン(イギリスの作曲家 「青少年のための管弦楽入門」で有名)1931年 初演 グローフェ作曲 組曲「グランド・キャニオン」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月22日
コメント(14)
-
ショスタコービチ 交響曲第5番 / 冬の花
『冬の花』今日も「山茶花」を掲載しました。花のアップ画像です。 晩秋から冬にかけては花が少ないのでこの山茶花は重宝します。 もうそろそろ椿も咲くころですね。 椿科で似た花ですが、やはり咲いてくると嬉しいですね。 冬の花は何かクリスマスで見る花といった感じで、花屋さんにはシクラメンやポインセチアなどが並んできました。そんな時期に近所の庭の「合歓」が紅く染まってまだ咲いています。 夏の花というイメージが濃い花ですから季節八ズレでしょうか? あんな紅い合歓は初めて見ました。花の少ない冬は植物園の温室にでも行って花を撮ろうかな?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ショスタコービチ作曲 交響曲第5番 ニ短調 作品571937年11月21日は、旧ソ連の大作曲家ドミトリー・ショスタコービチ(1906-1975)が書きました交響曲第5番が初演された日です。 スターリンの「恐怖政治」下で、「ソビエト革命20周年記念日」にあたる日だったそうです。彼は、生涯で15曲の交響曲を書き残しました。 それらの中で最もポピュラーで録音の数、演奏回数の多いのがこの第5番です。当時のソ連はスターリンというソ連共産党の実力No.1の党首が国を牛耳っており、彼の政策に異を唱える者、或いはそう見える者は容赦なく粛清(殺されるか僻地への流刑)され、殺された人々の数は膨大な数字に達した、所謂「スターリンの恐怖政治」の時代でした。芸術家とてもその例外でなく、社会主義リアリズム体制に迎合しない文学、絵画、音楽も容赦なく糾弾される時代でした。 ショスタコービチも1936年、彼が36歳の時にソ連政府から批判される立場に追い込まれ、一時は自殺まで考えたほど悩んだそうですが、誰が聴いても非難されることのない音楽作品を書くことで、自分の名誉を挽回しようと努めました。 そして発表されたのがこの第5番の交響曲でした。曲は苦悩から立ち上がって、困難を克服して歓喜へと爆発するというスタイルで、同じ5番ということもあってよくベートーベンの第5番シンフォニー「運命」と同スタイルと指摘されています。 苦悩ー克服ー歓喜という図式をベートーベンの交響曲を手本として、巧みに体制に迎合するかのように書き、しかもそれが普遍の命を保つ音楽に仕立て上げたショスタコービチの「したたかさ」が如実に表れているように思います。しかし、そういう時代背景と作曲家の立場を知ることがなくとも、この曲は人々に大きな感動を与えてくれる20世紀最高の音楽であり、いつまでも普遍的な美しさを保っている曲です。 最終楽章の音楽が高揚していく様は圧巻で、オーケストラ音楽の醍醐味とはこういう曲なんだと納得させられる偉大な交響曲です。愛聴盤 エフゲニー・ムラビンスキー指揮 レニングラードフィルハーモニー管弦楽団(Altusレーベル ALT 002 1973年5月26日 東京文化会館演奏会ライブ録音 NHK放送音源による)この演奏会の模様はNHK教育TVで放映されましたのを観ました。 観終わったあとは茫然自失の状態でした。 こんな演奏が実際に行なわれたことが信じ難いほど、完璧なアンサンブル、神がかり的なフィナーレの高揚とコーダの緊張感を保ちながらのクライマックスへと遅いテンポで、じっくりと昇りつめる様は、もうオーケストラの合奏が破綻するのではないかと思わせるギリギリのところまで引っ張っていく鬼のような形相のムラビンスキー。まさに「空前絶後」の演奏と言うほかに言葉の出ない夜でした。 それが30年の時空を超えて蘇って来たのがこのCDです。 あの73年の初夏の夜に観た演奏が戻ってきたのです。1958年の正月(中学2年生でした)、お年玉で買った中古レコードが1枚ありました。 ビクターレコードレーベルで、ハワード・ミッチェル指揮 ナショナル交響楽団の演奏でした。 それがこの第5番のシンフォニーでした。 初めて聴いた時の感動は今尚鮮烈に残って覚えていますが、このムラビンスキーの演奏はそのとき以上の感動で、我が家に戻ってきた、あの夜の演奏会をまた聴いて感動しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月21日
コメント(10)
-
マーラー 交響曲「大地の歌」 / 神木の扱い
『神木の扱い』神社境内に入ると左手に大きな楠の大木が1本植えられています。 樹齢はおよそ200年と推定される木ですが、今までこの木は顧みられずに立っていました。 この木は神社の神木として現在まで崇められてきました。 神社の入り口には大きな石の鳥居があり、そこには「しめ縄」が着けられています。 しかし楠には何もありません。 そこで私がこの木にも「しめ縄」を着けて神社の神木として、誰が見ても判るようにすれば、お参りしてくれる皆さんにもっと大事に扱ってくれる筈だからと提案しました。今年は鳥居の「しめ縄」を替えなければいけないので、その新しい「しめ縄」に「魂」を入れる必要があるので、神木にも「しめ縄」を施してお払いをしてもらい、魂を入れてもらうことを提案しています。12月5日(日)が「冬宮祭」なのでその時に役員で協議決定することになりました。 ただ楠の枝葉の剪定を植木職人にやってもらっていますので、その時に毎度、毎度「しめ縄」のお払いをしなければならないのかという問題があって、それを確認してからの決定になります。神事には色々と約束ごとがあってわからないことが多いです。 しかし、神木に「しめ縄」をかけると相当見栄えが良くなるはずで、是非そうしたいと願っているともさんです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 グスタフ・マーラー作曲 交響曲「大地の歌」1911年11月20日は、グスタフ・マーラー(1860-1911)が作曲しました「アルト(またはバリトン)とテノールと管弦楽のための交響曲 大地の歌」が、弟子の指揮者ブルーノ・ワルター(1876-1962 20世紀を代表する大指揮者の一人)によって、マーラーの死後ほぼ半年を経てドイツのミュンヘンで初演された日です。この曲を書いた数年前に彼の長女が3歳で亡くなり、彼自身も心臓疾患により「死」ということに神経質になってきた頃でした。 そうした折に、彼の手元に1冊の詩集がありました。 漢詩のドイツ語訳で「中国の笛」という詩集でした。 中国の唐の時代に書かれた「厭世詩人」たちの詩集で、厭世感や酒、自然への愛、憧れや青春への回帰などに溢れるこの詩集から選んだ7つの詩に音楽をつけて6楽章の声楽付き交響曲としました(終楽章では2つの詩を使っています)。人生の諦め、人生からの逃避や嫌になった厭世感から、酒をこよなく愛して過ごす人、若い青春を思い出す人、そしていずれは大地に帰っていくという無常観などを色濃く表している詩ですから、音楽も必定暗くなっていますが、東洋的な旋律、和声などに彩られて美しいマーラー音楽の世界を作りだしている傑作です。「生は暗く、死もまた暗い」と始まる第1楽章から厭世観が滲み、酒と春への陶酔と、青春の謳歌に酔う楽章(第3、4,5楽章)と孤独感や死への諦観に近づく第2、第6(終楽章)の対比も見事です。第1楽章 大地の哀愁を歌う酒の歌(テノール) 李太白の詩第2楽章 秋に寂しき者(アルト) 銭起の詩第3楽章 青春について(テノール)李太白の詩第4楽章 美について(アルト) 李太白の詩第5楽章 春に酔える者(テノール) 李太白の詩第6楽章 告別 (アルト) 猛浩然と王維の詩 (最も長い楽章ー約30分) この曲の白眉となる楽章で、「友よ、この世の中に私の幸福は無かった。 疲れ果てた孤独の心に永遠の救いを求めて、私は今こそ故郷へ帰ってゆく・・・・」その心とは裏腹に最後はこう結ばれています。「・・・・春になれば愛する大地は、また至るところに花が咲き、樹木は緑に覆われて、永遠に、世界の遠き果てまでも青々と輝き渡るだろう・・・・、永遠に、永遠に・・・・・」そして印象的なド・ミ・ソ・ラの和音と共に消えていく、感動的な音楽の終焉となります。演奏時間約65分ー70分の大曲です。(追記)この曲は9番目の交響曲として書かれましたが、ベートーベン、シューベルト、ドボルザーク、ブルックナーなどが9曲を書いて(未完もありますが)亡くなっていることから、マーラーはこれを第9番として残さず、番号なしの交響曲とした後に、別の曲として新しく第9番を書き終えてから、やはり10番を書いているときに亡くなりました。初演日にちなんで、今日はこの曲を聴こうと思います。愛聴盤 レナード・バーンスタイン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団 ジェームス・キング(テノール) デイートリッヒ・フィッシャー=ディスカウ(バリトン)(LONDONレーベル KICC 8215 1966年4月ウイーン録音)インバル指揮フランクフルト放送響、コリン・デイビス指揮 ロンドン響、 オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管など名盤が多くありますが、バーンスタインがニューヨークフィルを離れてヨーロッパに渡って、初めてウイーンフィルと1966年に録音をしたこの演奏は、私にとって初めて「大地の歌」を聴いたLP盤でした。 ディースカウの名唱と併せて(珍しいバリトン録音です)この盤をあえて取り上げました。 後に色々な演奏を聴きましたが、燃焼度、生命力ある音の凄さでは、やはりバーンスタインに魅力を覚えます。『その他今日のカレンダー』1805年 初演 ベートーベン 歌劇「フィデリオ」1895年 初演 マーラー 交響曲第1番「巨人」1937年 誕生 ルネ・コロ(テノール)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月20日
コメント(7)
-
シューベルト 「未完成」交響曲 / お父さんへ
『お父さんへ』お手紙ありがとう。 先日、四十九日の法要が終りました。一ヶ月余りの入院生活。 微熱はあるものの、「すごく気分がええんや。 食事もおいしい。 特に昼食はごちそうや」とうれしそうにいっていたのに、容態が悪くなって一週間。 眠るように逝ってしまいましたね。昔、教師をしていたあなたは几帳面な人で、悪くなる前日まで毎日毎日、日記を付けていました。 家の大学ノートには、亡くなった時の連絡先、お葬式の手順、残された皆が困らないようにと細かく書いてあり、とても助かりました。お葬式の後、お仏壇の引き出しを片付けていた姉が、母、私たち兄弟への手紙を見つけました。 これは天国から届いた手紙だと胸が熱くなりました。法要の日、一人ずつ自分あての手紙を開けましたが、涙で字がぼやけて困りました。 それぞれの生い立ちに触れ、「ありがとう」と感謝の言葉で結んでありました。お父さん、お礼を言うのはこちらの方です。 限りない愛をたくさんもらいました。 本当にありがとう。 これからも寝たきりのお母さんを見守ってあげてね。 返事、遅くなってごめんね。 産経新聞2004年11月18日朝刊「きのうきょう」 兵庫県 52歳女性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 フランツ・シューベルト作曲 交響曲第8番 ロ短調「未完成」「わが恋の終わらざるごとく、この曲もまた終わらざれ」古い映画ですが「未完成交響楽」というシューベルトを主人公にした映画の中で、シューベルトが実ることのない伯爵令嬢のために書いたシンフォニーにまつわる悲恋物語で、失恋したシューベルトが叫んだ映画の中の有名な言葉で、これが「未完成交響曲」であるという美しい映画でした。 勿論完全なフィクションですが。1828年11月19日、フランツ・シューベルト(1797-1828)はわずか31歳の若さでこの世を去りました。 ベートーベンの棺を泣きながら担いだ翌年のことでした。シューベルトはその短い生涯で数多くの美しい曲を残しました。 9曲の交響曲、21曲のピアノ・ソナタ、15曲の弦楽四重奏曲や弦楽三重奏曲、弦楽五重奏曲、ピアノ三重奏曲、オペラ、ミサ曲、合唱曲、それに最も彼を有名にしている「美しき水車小屋の娘」「冬の旅」「白鳥の歌」などに代表される600曲を超える歌曲など、美しい旋律に満ちた珠玉の音楽を書いています。それらの作品の中でも最も有名なのがこの8番目の交響曲「未完成」でしょう。 普通、交響曲は4つの楽章からなる形式ですが、この曲は第1、第2楽章だけが書かれており、第3楽章はわずか数小節のみ残されており、「未完成」という名前を冠命されています。この曲は彼の死後、37年後に初演されるまで彼の机に眠っていたそうです。1900年代初頭の名指揮者ワインガルトナーが語った言葉「あたかも地下の世界から湧き上がるようような・・・」第1楽章の神秘的な美しさ、ロマンテイックな極みのような天国的な美しさに溢れた第2楽章。 1956年以来、この曲を聴いていますが、聴くたびにその美しさの新しい発見を覚える曲で、わずか31歳で散ってしまった彼の音楽的天分を象徴するかのような曲です。 あと10年生きておればどんな美しい曲を新たに残してくれていただろうかという思いになる曲です。 シューベルトの天分が存分に開花することなく生涯を終えたことが、この「未完成交響曲」に暗示されていると思うのは私一人だけでしょうか?愛聴盤 ブルーノ・ワルター指揮 ニューヨークフィルハーモニー (SONY SMK 64487 1958年録音 輸入盤)この曲のCDは目白押しの名盤が多いのですが、温かさに溢れ、旋律をたっぷりと歌わせ、ロマンテイックな表情を纏綿と描いていて、もうこういう演奏スタイルの指揮者がいなくなってしまったという観点から、あえてここに掲載致します。 カップリングはシューベルトの交響曲第5番です。 尚、ジャケット写真は最晩年のコロムビア響との録音盤のものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月19日
コメント(4)
-
10,000アクセスを超えました! / 古賀メロデイーの素晴らしさ
今朝このページも10,000のアクセスを超えました。 日記リンクを張っていただいています皆様、ご訪問いただきました方々に感謝申し上げます。 ありがとうございました。これからも日記更新、よりいっそう頑張りますのでご訪問いただくようお願い致します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 古賀政男を偲ぶ1904年11月18日は、日本の流行歌に多大の足跡を残した作曲家古賀政男が生まれた日で、今年が生誕100年となります。貧しく苦労した学生時代に書かれた「影を慕いて」から亡くなるまでの間に書かれた4,000曲とも言われている膨大な歌の数々は、理屈抜きに日本人の心を揺さぶる魅力に満ちた歌ばかりです。 人生の寂しさ、悲しさ、楽しさを端的に表現して、しかも親しみやすい旋律が日本人の心にす~と入ってくるという魅力ある歌ばかりです。彼が学生時代に書いた「影を慕いて」を歌い、古賀メロデイーの重要な歌手の一人である藤山一郎は、ある時古賀を評して「他の作曲家との比較ということになれば、古賀政男は作曲家ではなくて、メロデイーメーカーでしょう」と言ったことがあるそうです。手元にソプラノ歌手藍川由美がチェンバロ奏者中野振一郎と組んで録音した「古賀政男作品集」というCDがあります。 古賀メロデイーの魅力の真髄に迫る珠玉の16曲が収められています。 「赤い靴のタンゴ」「芸者ワルツ」「誰か故郷を想わざる」「サーカスの唄」「影を慕いて」「丘を越えて」「酒は涙かため息か」「東京ラプソデイー」「白虎隊」「男の純情」「人生の並木路」「青春日記」「人生劇場」「湯の町エレジー」「無法松の一生~度胸千両」「悲しい酒」の16曲です。古賀メロデイーを語るに充分な選曲だと思います。 これらの曲をクラシック音楽の声楽家(ソプラノ)藍川由美がチェンバロの伴奏だけで歌っていますので、古賀メロデイーの美しさ(素晴らしさが演歌歌手が歌うのと違って)が見事に浮き彫りにされています。 「赤い靴・・・」「サーカスの唄」「誰か・・・・」「白虎隊」「湯の町・・・」「人生の並木路」「無法松・・・」などにそれが顕著に表れており、古賀政男はまさに旋律を泉の湧くがごとくに創り出して、人の心を捉えて離さない歌を書いていたことがよくわかり、古賀の世界に惹きこまれます。 「湯の町エレジー」などは前奏のギターがつまびくメロデイーを聴いただけで、湯の香りが漂ってくるような感さえあります。ただ「影を慕いて」「悲しい酒」などは、やはり美空ひばりや森 進一の「情念」を深く表現した歌唱に魅かれます。 このあたりはクラシック音楽の声楽とのクロスオーバーがマイナスになるのかなと思います。今日は古賀政男生誕100年に因んでこのCDで古賀メロデイーにどっぷりと浸ろうかと思っています。(日本コロムビア COCQ-83152 1991年1月録音)『その他今日のカレンダー』1786年 誕生 カール・マリア・フォン・ウエーバー(作曲家 代表作 歌劇「魔弾の射手」)1889年 誕生 ユージン・オーマンデイ(フィラデルフィア管弦楽団常任指揮者として有名)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月18日
コメント(12)
-
チャイコフスキー 交響曲第5番 / 恥ずかしい!
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 交響曲第5番 ホ短調 作品641888年11月17日は、チャイコフスキーが書いた交響曲第5番が初演された日です。「運命」というものにこだわって書かれた第4番の完成から10年後にこの曲が書かれているのですが、彼はその前1868年(明治維新の年です)にヨーロッパに演奏旅行に出かけて、オーケストラの指揮を行なったそうです。 彼は内気な性格で、指揮について酷評されたあとは指揮棒をとることがなかったそうですが、この演奏旅行で好評を博したことで創作意欲をかきたてられてこの曲が書かれたと言われています。曲は「チャイコフスキー節」で全編彩られているのは、いつもの彼の作品の特徴で、第1楽章から重く暗い主題が哀愁の響きを覆いつくし、終楽章までこの気分が漂い、やがて金管の燃えるような咆哮と共に曲のクライマックスを迎えるあたりは、彼の本領発揮の曲と言えそうです。第2楽章のオーボエの哀切極まる美しい旋律や、第3楽章で『ワルツ』を用いているところなど、工夫のあとがうかがえます。ロシアの憂愁を漂わせる気分は人生の峠にさしかかったチャイコフスキーの心情を吐露したものなのでしょうか? 憂愁とわびしさ、寂しさと劇的に爆発する気分にそういうことを感じる曲です。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団(EMI原盤 DISKYレーベル発売 1971年録音)まるで演奏会のライブ録音のような、カラヤンにしては珍しく気分を高潮させた燃焼度の高い演奏で、ベルリンフィルの驚異の合奏能力はカラヤンの長年の薫陶と磨き上げた現代オーケストラの美しさの極致のようです。 LP3枚で4番、5番、6番と録音、発売された名盤が廃盤となっていたのですが、HMVが音源を発掘して5番と6番『悲愴』の2枚組でリリースされたCDです。チャイコフスキーのシンフォニーの美しさを、凄絶な演奏を繰り広げて表現する「カラヤン美学」の典型的な美演で、後世にも長く語り継がれる記念碑的な演奏、録音のCDだと思います。『その他今日のカレンダー』1876年 初演 チャイコフスキー 「スラブ行進曲」1959年 逝去 エイトール・ヴィラ=ロボス(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『恥ずかしい!』小説輪違屋糸里(浅田次郎著 文藝春秋刊)を駅のホームで夢中になって読んでいると電車が入って来た。 小説を読みながら開いたドアーから車内に入り、入り口近くに立って相変わらず読み耽っていた。 視線を感じるので目をあげると、複数の女性が私を凝視するように見つめている。 「うふっ、俺もまんざらではないな」と思いながらまたページに目を走らせる。 15分ほど乗って下車駅のアナウンスがあったので、扉の方に移動しようと本をカバンに入れて、目をあげるとまだ女性たちが私を見つめている。「うん?」何かおかしないなと思って四方を眺め回すと、何と乗客は全員女性。 頭に血が上るとはあのことでしょうか、顔中が火照って真っ赤。女性専用車両に乗っていたともさんでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月17日
コメント(4)
-
ヒンデミット 「画家マチス」 / 七五三のお参り(花画像差し替えました)
『七五三のお参り』ここの神社には宮司が常駐していないからかでしょうか、今年の七五三は雨に降られたこともあって、午前中は誰もお参りする人はなく、糠雨を見ながらの社務所での役員だけの雑談に終ってしまう日でした。午後の担当と交代する頃には雨が上がり、薄日が射してきたせいか午後4時ごろに閉める頃に行くと、2組の参拝があったそうです。 最近は七五三の参拝が少なくなってきたとTVニュースでも報道していましたが、段々と伝統行事がすたれていくのは寂しい気がしてなりません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 パウル・ヒンデミット作曲 交響曲「画家マチス」1895年11月16日は、ドイツの作曲家パウル・ヒンデミットが生まれた日です。 オーケストラ奏者を務めたあと20代後半からロマン主義を離れて、無調的な音楽や新古典主義などの作品を書いて、ロシアのストラビンスキーや、ハンガリーのバルトークなど20世紀の作曲家に大きな影響を与えた作曲家といわれています。 管楽器の協奏曲や室内楽曲など多くの作品を残しています。その彼の作品に、交響曲「画家マチス」が残されています。 彼の代表作で、今でもレコード、CDへの録音やオーケストラ演奏会でも採り上げられています。16世紀ドイツの農民指導者マチス・グリューネバルトの描いた教会画から、ヒンデミットが着想したといわれており、「天使の合唱」「埋葬」「聖アントニウスの試練」というサブタイトルが付けられています。 新古典主義音楽の代表的な曲で、20世紀音楽を語るに欠かせない曲です。愛聴盤 クラウディオ・アッバード指揮 ベルリンフィルハーモニー(独グラモフォン 447389)『その他今日のカレンダー』1940年 初演 ハチャトリアン ヴァイオリン協奏曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月16日
コメント(8)
-
シューマン 「子供の情景」(追記あり) / 今日は七五三
『今日は七五三』七五三にはお宮参りをします。 この村の神社でもこの日のためにお宮を開けてお参りする方をお迎えします。 役員は交代で社務所詰めです。「七五三」の由来昔は乳幼児の死亡率が高く、子供の成長を神さまに祈願することから始まっています。 武家制度の発達した頃、それまでの「霜月祭」(家業に関係する神々を祭る)に因んで行なわれ、子に晴れ着を着せて神社参りをして祝の宴を開いたそうです。3歳は「髪直」(髪をのばす)5歳は「袴着」(男子)7歳は「帯解」(本仕立ての着物と丸帯)という正装で神社にお参りをするのが正式な儀式だそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ロベルト・シューマン作曲 「子供の情景」作品15今日は七五三。 今日の音楽カレンダーとは関係がないのですが、七五三に因んで何か子供に関係ある曲をと考えてこのロベルト・シューマン(1810-1856)が書きましたピアノ曲集「子供の情景」を採り上げました。この曲は13曲から成るピアノ小品集で、最も有名なのが第七曲の「トロイメライ(夢)」です。 独立してCDなどのピアノ名曲集やリサイタルなどのプログラムに採り上げられています。 過ぎ去った子供時代の思い出に残る場所、場面などをピアノ音楽で回想しています。 「見知らぬ国と人々」「不思議な話」「鬼ごっこ」「おねだりする子供」「満足」「重大事件」「トロイメライ」「炉端で」「木馬の騎士」「むきになって」「こわがらせる」「眠っている子供」「詩人の話」の計13曲から成り、まるで一つ、一つの曲が遠い昔の子供の時代に連れて行ってくれような詩的な、そして不思議な空間の現れる音楽です。愛聴盤 マルタ・アルへリッチ(ピアノ)(独グラモフォン 410 653-2 1984年録音)ピアノ音楽としての超優秀録音盤でシューマンの「クライスレリーナ」がカップリングされています。 現在では日本グラモフォンのプレスで廉価となってリリースされています(UCCG 7076)。その他、子供にちなんだピアノ作品集としてはイディル・ビレットの弾くアルバムがあります。チャイコフスキーの「子供のためのアルバム」シューマン「子供の情景」ドビッシー「子供の領分」が収録されています。 \1,000の廉価盤です。『その他今日のカレンダー』1787年 逝去 クリストフ・グルック(作曲家)1832年 初演 メンデルスゾーン 交響曲第5番「宗教改革」1920年 初演 ホルスト 組曲「惑星」1942年 誕生 ダニエル・バレンボイム(ピアニスト・指揮者)1949年 初演 ショスタコービチ オラトリオ「森の歌」
2004年11月15日
コメント(5)
-

映画「禁じられた遊び」の音楽 / 不思議な体 / 今日の簡単料理
昨日私の叔父さんから聞いた話。 この叔父さんとは, 以前にこの日記で紹介しました90歳でパソコン生活を楽しんでいる人です。太平洋戦争中にすでに軍籍にあった叔父が実際に体験したそうですが、ご存知のように戦前は召集令状1枚で軍隊に入ることになっていました。 そして召集されると体格、健康検査が行なわれていました。ある日、軍医が下士官を医務室に呼びました。 軍医曰く「さっき検査した兵隊の中に実に不思議な体をしているのがおる。 最初で最後だと思うから皆に見ておいてもらいたい」と言って、一人の兵隊に衣服を脱ぐように命じて上半身裸にさせると、何とその兵隊には乳首が6つ胸の両側に並んでいたそうです。軍医曰く「大昔まだ人類が完全な人間になる前は、こういう風にまるで犬などの動物のような体をしていた時代があった。 この兵隊は何故こういう体をしているからわからないが、その大昔の人間の体の名残りを残している」と解説してもらったそうだ。不思議な体を持つ人間もいたものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 スペイン民謡「ロマンス」1927年11月14日は、スペインのナリシソ・イエペス(1927-1997)が生まれた日です。 彼は同じスペインの、ギター演奏の神さまのようなアンドレ・セゴビアという後継者として世に出た、世界的な一流のギタリストで、ギター1本で世界中を飛びまわるギタリストでした。第一次世界大戦後に、アメリカ、ドイツ、フランス、イタリア、スペインなどの欧米から数多くの映画が作られており、今でも繰り返しアンコール上映されたり、ビデオ、DVDなどで人気の衰えを知らない映画があります。それらの映画の中でも、映画そのものの優秀さと共に今尚、光を失わない映画音楽が数多くあり、聴き継がれている曲も多くありますが、一般的に誰もが知っている音楽に「禁じられた遊び」に使われていましたスペイン民謡「ロマンス」があります。長調と短調の二部に分かれたように書かれているこの曲は、ギターの3連音符の奏法に乗って流れる哀愁漂う美しい旋律で、今でもギター曲といえばこの曲が真っ先に思い浮かぶほどの名曲で、この「禁じられた遊び」で一躍脚光を浴びて世界に広がり、愛されている曲です。この「ロマンス」は戦後の名画「血と砂」(タイロン・パワー主演)にも使われていました。この映画でギターを弾いていたのが、1927年の今日生まれたナルシソ・イエペスです。 彼の誕生日に因んでこの曲を採り上げました。 (グラモフォン UCCG-3393/4 1970-1989年録音)イエペス没後5年企画として過去の彼の名演を2枚組に編集した\2,000というお買い得盤で、「アランフェス協奏曲」「アルハンブラの思い出」「ある貴神のための幻想曲」それに数々のスペインギター曲などがカップリングされており、この「ロマンス」も彼の忘れ難い演奏としてカップリングされています。『その他今日のカレンダー』1900年 誕生 アーロン・コープランド(アメリカの作曲家)1924年 誕生 レオニード・コーガン(ソ連のヴァイオリニスト)1946年 逝去 マヌエル・デ・ファリャ(スペインの作曲家)
2004年11月14日
コメント(12)
-

ロッシーニ 「弦楽のためのソナタ」 / 人助け
『人助けーマザー・テレサを見習いたい』私は先日朝日新聞社に出向いて新潟中越地震被災地への義援金を渡してきました。 そして、この、新聞に投稿した小学生の言葉を読んで考えさせられています。 以下はその小学生の言葉です。「小学校の授業で、インドのマザー・テレサについて勉強しました。 マザー・テレサはインドで人助けに一生を捧げた人です。 私は今まで、人助けなら募金をたくさんすればいいんだと思っていました。 けれどもマザー・テレサは、周りの人がくれた食べ物を、自分は食べないで飢えに苦しんでいる人にあげたり、道ばたに倒れている人を近くの病院に運んで命を助けたり、言葉も話せない子供たちのために学校を開いたりしました。その中で私が一番すごいと思ったのは、マザー・テレサがノーベル平和賞を受賞した時、「この晩餐会のお金は貧しい人たちに寄付してください」と言ったことです。 それほど「貧しい人たちを救いたい」と思っていたのでしょう。私はこのことを知って、自分が恥ずかしくなりました。 募金で人助けをしたと勘違いしていたからです。 私はこれからマザー・テレサのように優しく、困っている人がいたら助けられる人間になりたいです。」 産経新聞 2004年11月11日付け朝刊「10代の声」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ロッシーニ作曲 弦楽のためのソナタ1868年11月13日は、イタリアの作曲家ジョアッキーノ・ロッシーニ(1792-1868)が亡くなった日です。 ロッシーニといえばオペラ。 彼の書き残した傑作オペラの数々がすぐに思い浮かびます。 「セビリアの理髪師」「ウイリアム・テル」「アルジェのイタリア女」「シンデレラ」等々。両親は音楽で生計を立てていましたが、ジプシーのように色々な土地を転々とした生活だったそうで、息子ロッシーニは充分な音楽教育を受けていなかったそうです。 彼自身はチェンバロを演奏したり、教会で歌ったり、合唱の指揮を行なったりして生計を助けていたそうです。「弦楽のためのソナタ」が作曲されたのは、彼が12歳の時です。 このソナタは事実上ロッシーニの最初のまとまった曲で、オペラはそれから5年近く経って書き始めたそうです。 W.A.モーツアルトが、父レオポルドによって幼いころから音楽の英才教育を受けて、「神童」と呼ばれていたの対して、ろくな教育も受けていないロッシーニが12歳で書いたこの曲は、とても12歳の子供が書いたとは思えない美しいソナタ集です。弦楽4部編成の曲で(ヴィオラ部がありません)、 ソナタは1番から6番まで6曲書かれています。 少年ロッシーニの瑞々しい才気と明るさと美しい旋律に溢れた名品です。朝のクラシック音楽として、或いは午後のテイータイム音楽として、はたまた夜のおやすみ前のセレナードとして聴くのもいい、一日中どの時間帯にでもぴったりと合う普遍的な美しさの曲です。愛聴盤 イタリア合奏団 (DENON レーベル COCO70512 1987年 イタリア録音)レナート・ファザーノ主宰の「ローマ合奏団」が解散後に同メンバー有志で出来た「イタリア合奏団」の演奏はファザーノ時代の、豊穣で美しい響きと、まさに「磨き上げられた」カンタービレの美しさを継承しており、学生の頃に聴いていたあの「ローマ合奏団」が帰ってきたかに思える旋律の美しさを堪能できる演奏で、DENONチームがイタリアで行なったPCM録音の超優秀さと兼ね合せ、しかも発売当時2枚組み\6,000だったのが、CREST1000シリーズで\1,500という廉価盤になっているのが魅力です。その他『今日のカレンダー』1893年 初演 シベリウス 「カレリア」組曲
2004年11月13日
コメント(6)
-

ボロデイン 「ダッタン人の踊りと合唱」 / 命の大切さーカブトムシ
『命の大切さーカブトムシ』小さな生き物が与えてくれた感動と命の大切さを短い言葉の中に散りばめている投稿記事に出会いました。 この子供は小さな命の大切さを身をもって感じてくれて、これからの生きていく上での大切なものを得てくれたと思います。 そして母親が何よりもそれを思って子供を見守っていくでしょう。 その記事を紹介します。「家の庭には二匹のカブト虫が眠っている。 夏に小学2年生の息子が電器屋さんからもらってきた、我が家の最初のペット「オストちゃん」と「メストちゃん」だ。 虫嫌いの私が一緒にいたら「見るだけね」と念を押していたのに、別の場所にいたため、息子はこれ幸いと主人に頼んで貰ってきたのだ。 膝の上に虫かごをのせ、嬉しそうに眺めている息子。 男の子だから、いつかこんな日が来るだろうと覚悟はしていたものの、つい文句のひとつも言いたくなる。 「ちょっと何これ?」「お姉さんが『どうぞ』って。 最後の一組だったんだよ」「何でもらっちゃうわけ?」「いいじゃないの、喜んでいるんだし」「喜んじゃえば何でもあり?」。 おさまらない感情にひとり、ブツブツ言ってしまう。 ところが五日後、別れは突然やってきた。 仕事から帰るとオストちゃんが動かない。 メスとちゃんもここ二日、姿を見せない。 まさか・・・・・。 主人が虫かごの中の土を掘ると、メストちゃんも死んでいた。肩を震わせ、泣きじゃくる息子。 いっそ別のカブト虫を買おうかとまで考えたがやめた。 辛くても、悲しくてもオストちゃんとメストちゃんはこの二匹だけ。 代わりはない。 だからこそ「命」って大切なんだ。翌日、息子とお墓を作った。 触れなかったけど、我が家に来てくれてありがとう。」 京都府 主婦 40歳 産経新聞 2004年11月11日付け朝刊「きのうきょう」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ボロデイン作曲 歌劇「イーゴリ公」から「ダッタン人の踊り」1833年11月12日、ロシアの作曲家アレクサンドル・ボロデイン(1833-1887)が生まれた日です。 彼は「ロシア国民学派」としてその音楽をロシアの大地に根をおろしたかのような、民族的な音楽を書いた人ですが、作品は数多くはありません。 中でも有名で、今日演奏されているの「弦楽四重奏曲第2番ニ長調」、交響曲第2番(未完の3番を含めて3曲書いています)、歌劇「イーゴリ公」です。その「イーゴリ公」も未完に終っていて、彼の死後リムスキー=コルサコフとグラズノフによって完成されて、1890年に全曲初演されています。 彼は着手から18年かけて書き続けましたが、生来作曲のスピードが遅く、リムスキー=コルサコフが「彼が倍のスピードで書いていれば、もっと素晴らしい音楽が世にでたのに」と歎いたそうです。物語は、「イーゴリ軍の物語」として残されているロシアの叙事詩を題材としており、舞台は12世紀の初め頃で『ダッタン人』(旧満州あたりの中国北方民族)のロシア侵攻に対して戦ったキエフの大公「イーゴリ公」の物語です。この「ダッタン人の踊り」は、オペラ第2幕でダッタン人の将軍に捕らわれたイーゴリ公を慰めるために将軍の開いた宴会でのバレエ音楽です。 エキゾチックな東洋的な旋律に彩られた曲で、「イーゴリ公」といえばこの曲が真っ先に浮かぶくらい「代名詞」のような音楽です。 ポピュラー界でも「ストレンジャー・イン・パラダイス」として合唱部分をアレンジした、ムード音楽として一世を風靡した曲です。今では「ダッタン人の踊り」のバレエ音楽が演奏会でも取り上げられています。愛聴盤 ユージン・オーマンデイ指揮 フィラデルフィア管弦楽団(ビクターBMGレーベル BVCC38054 1971年フィラデルフィア録音 リムスキー=コルサコフの「シェラザード」とカップリング)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 小菊 ピンポン 白 撮影地 大阪和泉 2004年11月
2004年11月12日
コメント(2)
-
R. シュトラス 「ドン・ファン」 / 「古代へのロマン」
『古代へのロマン』「弥生集落のイメージを一新する発見」として俄かに注目されている「池上曽根遺跡」(国史跡、大阪府和泉市、泉大津市)の建物跡。 またまた古代へのロマンが膨らみます。自宅から自転車で坂道を5分ばかり下り降りた先に大阪府立弥生文化博物館があります。 そのミュージアム前には広大な「池上曽根遺跡公園」があり、その弥生式時代の遺跡の建物跡に見られる「規格性」によって「ミニ都城」があったと推定されることが最近の調査でわかったそうです。今は、日本最古の「都城」は藤原京(694-710)が最初であると定説づけられていますが、これを覆す新しい発見になるかもしれないと地元教育委員会は色めきたっています。この遺跡からは紀元前52年と推定される「神殿」の柱材がすでに見つかっており、今回の発見では4棟の建物の整然とした方位性から、「ミニ都城」の可能性を秘めているそうなんです。これが裏づけられますと、弥生式時代にすでに小さな「都城」が出来上がっていることになり、「卑弥呼」の存在以前の国の成り立ちを探ることのできる第一級の発見となります。また、古代へのロマンに新しいページが加えられそうです。 これからの調査の行方が楽しみです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 R. シュトラウス作曲 交響詩「ドン・ファン」1889年11月11日は、R.シュトラスが書いた交響詩「ドン・ファン」がワイマールで初演されています。彼は数多くの交響詩を書いていますが、第1作「マクベス」に続く第2作目がこの「ドン・ファン」です。 初演はこの2作目の方が先に行なわれていて、世に出された曲としては第1作目になります。「ドン・ファン」は後世の「プレイボーイ」のような伝説的な数多くの女性遍歴を経験した人物で、多くの作家や音楽家によって劇や小説、詩の題材として採り上げられてきました。 先日10月29日にこの日記でも採り上げましたW.A.モーツアルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」もこのドンファン(イタリア語)を題材にしたものです。R.シュトラウスは、ここでは詩人ニコラス・レーナウの詩に基づいて書いています。 この詩は「ドン・ファン」を単なる「女たらし」として描かずに、理想の女性像を追い求める姿を書いているそうです。R.シュトラウスはこの詩を忠実に描く手法ではなくて、詩の持っている情感を膨らませるように抽象的に描いています。曲は颯爽とした美男子「ドン・ファン」を表すテーマと、理想の女性像を表す気品と繊細な美しさを表す旋律が織り成す、官能的な響きの、R.シュトラウス特有の精緻な管弦楽の魅力いっぱいの名品です。 約20分足らずの曲です。愛聴盤 アンドレ・プレヴィン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団プレヴィンは、ウイーンフィルと組んでR.シュトラスの交響詩を4枚のCDに計6曲を録音していますが、このCDはそのうちの1枚で、官能的な表現の響き、音色と香をウイーンフィルの極上の美しいアンサンブルから引き出しています。 昔からこの曲では数多くの名録音盤を色々な指揮者が残していますので、選択に困るほどなんですが、今日はこのアンドレ・プレヴィンの演奏とテラーク レーベルの超優秀録音技術のCDを採り上げました。 カップリングは同じくR.シュトラスの交響詩「ドン・キホーテ」です。(USA テラーク レーベル CD-80262 1990年ウイーン録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月11日
コメント(8)
-
ヴェルデイ オペラ「運命の力」 / 夫から届いたお祝い電報
夫婦の情愛はいくつになっても変わらないものだと思いました新聞の投稿記事を紹介します。 この高齢でこれだけの「愛」を表現できる人に敬意を表して。『夫から届いたお祝い電報』「ピンポ~ン」というチャイムの音がした。 庭掃除の手を止めて玄関に出てみると、女性が一人立っていた。 またセールスかなと後悔した矢先、「お祝い電報です」 慌てて印鑑を取りに行き単行本くらいの大きさの荷物を受け取った。見ると美しいランの花の模様が描かれた七宝焼きのお祝い電報。 宛名の書かれた小さい丸文字は二女の字に似ているなと思いながら、メッセージを開けてみるとそこには夫の名前が・・・・・・。 でも夫は入院中。 昨日病院に行った時、何も言ってなかったのに。 今日が私の誕生日だとちゃんと覚えてくれていたのだ。夕方、夫から電話があった。 病院の電話帳を見ていたらクレジットカードでもお祝い電報を贈ってもらえると知り、やってみたらうまくいったと話してくれた。パソコンもやらない、携帯電話も持たない夫が老眼鏡を頼りに、小さな字を読みながら面倒な操作をやってくれたなんて。 さぞ大変だったことでしょう。 本当にありがとうと感謝の気持ちでいっぱいの誕生日でした。 神戸市 主婦 72歳 読売新聞 2004年11月6日 朝刊より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ヴェルデイ作曲 オペラ「運命の力」1862年11月10日は、イタリアの作曲家ジュゼッペ・ヴェルデイ(1813-1901)が書きましたオペラ「運命の力」が旧ロシア帝国のペテルブルグで初演された日です。前作のオペラ「仮面舞踏会」での性格描写がよりいっそう劇的に描かれるようになった作品で、彼のオペラ作曲家としての中期を飾る傑作オペラです。(あらすじ)時代はスペインとイタリアの18世紀中頃。 スペインの侯爵の娘レオノーラは、インカ王家の子孫であるドン・アルヴァーロと恋仲で、駆け落ちしようとした矢先に父の侯爵に見つかり、その時のアルヴァーロのピストルが暴発して侯爵は死んでいまいます。二人はそのまま逃げ去りますが、侯爵の息子ドン・カルロは復讐を誓って妹レオノーラとアルヴァーロを追跡する旅に出ます。 逃げた二人は途中ではぐれてしまい、レオノーラは修道院に入って信仰の道へと進みます。 一方、アルヴァーロは彼女が死んでしまったと思い、イタリア戦線で仕官となり、レオノーラの兄ドン・カルロと事情を知らぬまま親交を深めます。ある日、ドン・カルロはアルヴァーロの持っている小箱の中に妹の肖像を見つけて仇と知り、決闘をするが邪魔が入って決着がつかず、その後運命の呪いを知ってアルヴァーロは修道院に入るも、ドン・カルロの発見するところなとなって、アルヴァーロは彼を刺してしまいます。血で濡れた剣を持って洞窟に入り、そこでレオノーラと再会しますが、迫ってきたドン・カルロは妹を刺して自分も絶命します。 アルヴァーロに看取られながら彼女は息絶えて幕が降ります。美しいアリアに散りばめられたヴェルデイオペラの真髄を味わえる、音楽も見事なドラマテイックなオペラです。愛聴盤 マリオ・デル・モナコ、レナータ・テバルデイ、エットーレ・バステイアニーニ、ジュリエッタ・シミオナート、 モリナーリ=プラデルリ指揮 ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団・合唱団1950-60年代のイタリアオペラ黄金期の絶頂とも言える、歌手たちの最盛期に録音された盤でステレオ最初期の録音ですが、録音の古さを感じさせない歌手たちの凄さに魅入られてしまいます。まさに「空前絶後」の声の競演を聴かせてくれる、これこそ「人類の遺産」と呼ぶにふさわしい名盤です。 (LONDONレーベル POCL-3947/9 1955年録音 )『その他 今日のカレンダー』1868年 誕生 フランソワ・プーランク(作曲家)1872年 初演 ビゼー 「アルルの女」第1組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月10日
コメント(8)
-

ロドリーゴ 「アランフェス協奏曲」 / 菊花展
『菊花展』昨日は見事な秋晴れと真夏日に近い陽気に誘われて、近所の同窓生と一緒に市内にある国華園に菊を愛でに行ってきました。 折からの好天気で観光バスが30台ほど、近隣からのマイカーでのお客でごっだ返すほどの盛況ぶりでした。 今年は規模の小さな展示会になっていたのでがっかりしましたが、なかなかの力作が展示されていました。 大作や小さな盆栽仕立ての鉢植えにいい物がありましたが、撮影モードの設定のミスでこういう画像だけがかろうじて掲載可能となったのが残念です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ホアキン・ロドリーゴ作曲 「アランフェス協奏曲」1840年11月9日は、スペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴ(1901-1999)が作曲しましたギターとオーケストラのための協奏曲「アランフェス協奏曲」が、スペインのバルセロナで初演された日です。アメリカの作家アーネスト・ヘミングウエーは、1930年代の「スペイン革命」に参加して、スペインに長く滞在しており、パエリアに代表されるスペイン料理やビーノ(地酒ワイン)、それに美しいセニョリータの笑顔、人の心に情熱をかきたたせるフラメンコダンスとスパニッシュギターの音色や、生と死の境に立つ闘牛をこよなく愛した作家で、長編小説「誰がために鐘は鳴る」「日はまた昇る」、ノンフィクション「午後に死す」などを書き残しています。その同じ時代に、盲目のスペイン生まれのホアキン・ロドリーゴがいました。 3歳で目の障害を患って以後盲目に近い状態が、亡くなるまで続きました。「アランフェス」は首都マドリードから南へ50kmほど離れたところにあり、スペイン黄金時代に200年かけて建てられた壮麗な離宮やスペイン随一と言われる美しい庭園があります。 私は若い頃に欧州出張の際にこのアランフェスを訪れたことがありますが、乾燥地帯の多いスペインには珍しく、豊かな水と深い緑の森に囲まれた小さい、しかし、美しい町を見て感動した思い出があります。その「アランフェス」にトルコ人で生涯ロドリーゴを支えていた夫人と、彼は訪れています。 そして頬を撫でる風、木々を吹きそよぐ微風、鳥たちのさえずりや鳴き声、川のせせらぎの音などを、目にすることが出来なくてもその空気に触れた感じを音楽で表現したのです。 そこに立ったときにこの「アランフェス協奏曲」の構想を練っていたと語っていたそうです。曲は3つの楽章から成り、第1楽章冒頭のギターがかき鳴らす音楽からもう私たちはスペイン情緒に包まれています。第2楽章は、オーボエのソロと哀切の旋律を奏でるギター、それをバックアップするオーケストラの豊穣で寂しげな音楽は、後に「恋のアランフェス」と呼ばれるほど有名な、筆舌に尽くし難い美しい旋律が私たちを魅了してやみません。「秋の夜長」をこの「アランフェス協奏曲」の「ギターの音色」で、過ごされるのはいかがでしょうか。 そして、最も大切な人の傍で。愛聴盤 村治香織(ギター) 山下一史指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団(ビクター レーベル VICC-60154 1999年12月 東京録音)イエペスや、ぺぺ・ロメロ、ジュリアン・ブリームなどの素晴らしいギター演奏もありますが、あえて若い村治香織の演奏を採り上げました。 超優秀録音の美しい仕上がりの録音です。その他の『今日のカレンダー』1881年 初演 ブラームス ピアノ協奏曲第2番1901年 初演 ラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番1929年 誕生 ピエロ・カップッチッリ(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月09日
コメント(4)
-
フランク ヴァイオリンソナタ イ長調 / 「楽しむことを学んだ部活」
『楽しむことを学んだ部活』最近の新聞記事は暗いニュースや、やりきれない気持ちになるニュースが多い。 子供への虐待、教師の生徒への性犯罪、警察の署ぐるみの裏金作りなどなど。そんな日常の中でホッとする記事もあります。 読者の投稿記事です。 毎日この投稿記事に癒されています。 そうした記事をここでも紹介していこうと思っています。 今日採り上げた記事などは、中学生でもこうしたしっかりとした考えを持った生徒がいるんだと、ホッとして嬉しくなりました。「長いような短いような最高の3年間から僕は多くのことを学びました。 1年生、 ボール拾いしかできなかった間の「我慢」。 2年生、 やっと普通の練習に参加できるようになり、練習試合に選ばれたいと、一生懸命した「努力」。 初めて試合に出ることが出来た時の、緊張して体が思うように動かなかったが、「勇気」と勝利の「喜び」。 3年生の時、僕たちが後輩を引っ張っていかなければと、背負った「責任感」。 試合で負けている時もあきらめずに最後まで頑張ったのに、敗れた時の「悔しさ」。色々なことがありましたが、部活動がくれた大切なものが二つあります。 一つは「楽しむ」ということです。 僕は野球が楽しかったのです。 だから、辛いことも無理なことも一生懸命乗り越えたのです。将来の仕事も、自分自身が「楽しむ」ものを選びたいと思います。もう一つは「チームワーク」です。 仲間がいるから頑張ったと言える「仲間」ができたことです。さらに、高校生活から何かを学びながら将来の道程を考えたいと思います」 ーーーー広島県福山市 中学生 14歳 毎日新聞2004年11月6日付け朝刊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 セザール・フランク作曲 ヴァイオリンソナタ イ長調1890年11月8日は、フランスの作曲家セザール・フランク(1822-1890)が亡くなった日です。彼は信仰深いクリスチャンであり、オルガンの名手でもあったそうですが、名声を確立したのは高齢になってからで、「大器晩成型」の作曲家でした。彼はその生涯にヴァイオリンソナタはこの1曲しか書いていないのですが、それがヴァイオリンの名曲として現代でも世界中で愛されている名品です。 彼の書いた「交響曲ニ短調」と同じように「循環形式(一つの主題がそれぞれの楽章に現れて、有機的に結びつける手法)」が用いられており、新鮮さに溢れ、聴く人に親しみを覚えさせる「調和」と「詩的な」雰囲気の漂う曲です。この曲の初演当時(1886年の冬)は夕方になって楽譜が見えないほど暗くなってくると、演奏が中止されて次の機会までお預けと言う時代だったそうです。 この曲の初演時も楽譜が見えないほど暗くなったのですが、ヴァイオリニスト(有名な作曲家、ヴァイオリニストのユージェーヌ・イザイ)もピアノ伴奏者も、禁止されていたローソクの火を灯さずに暗譜で最後まで演奏したそうです。 それだけこの曲が美しさに溢れていて二人の演奏者が初演までに暗譜していたことを物語るエピソードです。愛聴盤 西崎崇子(Vn) イエーネ・ヤンドー(P)(NAXOSレーベル 8.550417 1990年 チェコスロヴァキア録音)無個性の個性とも言える非常に素直な音色と演奏解釈は、どっぷりとフランス音楽の詩的な情緒にひたれる録音盤です。 ある、町のヴァイオリンの先生にベートーベンの「スプリングソナタ」を西崎のヴァイオリンで聴いてもらった私の友人の話ですが、聴き終わったあと「こんなのやったら、私でも弾けるやん」それほど素直な演奏なのです。 だからフランクにはとても合う演奏だと思います。 カップリングはグリーグのVnソナタ第3番です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月08日
コメント(8)
-
わが町の交響楽団 / ラフマニノフ 「パガニーニの主題による狂詩曲」
『わが町の交響楽団』私が住んでいる町にはアマチュア交響楽団があります。 毎年11月に年1回の定期演奏会が行われています。 今年は創立25年目にあたり、今日は午後から新しく建てられましたホールでその記念演奏会が行なわれます。 私と同じくこの町の神社役員を担当してくれています一人が創立以来チェロで参加しています。 プログラムはチャイコフスキーの「1812年」序曲、グラズノフのバレエ音楽「四季}、エルガーのチェロ協奏曲です。今日午後2時から開演しました。演奏の良否は書きません。 彼らはスコアを見ながら指揮者のタクトについて行こうと必死になって演奏していました。 音楽を創る喜びに浸りながら。 私は羨ましいと思いました。 自分も何か楽器を演奏出来たらいいのにと今更ながら後悔しています。ホールを出るとすでにお日さまは釣瓶落しの夕陽に変わろうとしていました。 いいコンサートを聴けたと満足してコスモスが風に揺れる小道を自転車で家路に急ぎました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 セルゲイ・ラフマニノフ作曲 「パガニーニの主題による狂詩曲」 作品431934年11月7日は、セルゲイ・ラフマニノフ(1837-1943)の作曲しました「パガニーニの主題による狂詩曲」がアメリカのボルテイモアで、作曲者自身のピアノ独奏、レポルド・ストコフスキーの指揮 フィラデルフィア管弦楽団の演奏で初演された日です。映画「逢びき」(トレバー・ハワード主演)の全編に流れていましたロマンテイックな情緒濃厚な『ピアノ協奏曲第2番」や、ロシアの哀愁を感じさせる「前奏曲 嬰ハ短調」などのピアノ音楽で有名なラフマニノフはロシアで生まれましたが、ロシア革命の勃発のよって貴族の血をひく彼はアメリカに亡命して、それ以後祖国に帰ることのなかった作曲家で、アメリカを舞台に活躍した人でした。作曲家には音楽を書くことと、器楽演奏で有名になった人が多くいます。 モーツアルト、ベートーベン、リストのピアノ演奏や、パガニーニ、サラサーテ、クライスラーのようなヴァイオリン演奏などが挙げられます。 ラフマニノフもそのうちの一人で卓越したピアノ技巧を持っていて、アメリカではコンサートピアニストとして人気があったそうです。そのかたわら、彼は多くのピアノ音楽を書いています。 この「パガニーニの主題による狂詩曲」は、パガニーニが書いた「無伴奏ヴァイオリンのための24の奇想曲」という曲の中から24番イ短調を主題にした、ピアノとオーケストラによる華麗な24の変奏曲です。 最も有名なのが第18番の変奏曲で、ロマンテイックな美しい旋律で、映画にもよく取り入れられていて、誰もが一度は耳にしたポピュラーな変奏曲です。愛聴盤 アシュケナージ(ピアノ) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(LONDON レーベル 486386 1970年ロンドン録音)メインのピアノ協奏曲第2番、3番にカップリングされており、前奏曲や練習曲からも収録されています価格は\2,500という2枚組輸入盤です。『その他今日のカレンダー』1825年 初演 ベートーベン 弦楽四重奏曲第15番1857年 初演 フランツ・リスト 「ダンテ交響曲」1875年 初演 チャイコフスキー 交響曲第3番「ポーランド」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月07日
コメント(6)
-
ブラームス 交響曲第1番 / 奇跡が起こった!
『奇跡が起こった!』今まで奇跡というのは、私の身の上におきるとは思っていなかった。 先日、3ヶ月の入院生活後に奇跡的に退院して、治療を続けている。 「余命1ヶ月、長くて数ヶ月」と医師から宣告されたあの日がまるで嘘のよう。 肺ガンの末期で手術ができず、数ヶ所の転移も告げられていた。 自分のこととして受け止めることができなかった。信頼できる医師、手厚い看護をして下さった看護師さんと出会った。 遠くは関東から新幹線で、岡山や大阪からも顔を見せて励ましてくれた友。 毎日のように絵手紙をくれた義妹。 いとこは仕事や自分のコンサートで忙しい合間を縫ってご主人と病室に足を運んでくれた。 そして毎日、自分で作った弁当を持参して、一緒に食べてくれただんな様ー。大勢の人たちの真心と祈りが一つになった時、奇跡が起こり私を助けてくれた。 良い医療というのは、決して薬だけではないとつくづく思った。 めぐり合った人たちのおかげで今こうして自分の足で立ち、自宅で過ごせる幸せをかみしめている。 (読売新聞 2004年11月3日 兵庫県明石 主婦65歳の投稿記事)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 交響曲第1番 ハ短調 作品68中学2年生だったある朝、登校準備で忙しい時に毎朝聴いていましたNHKのクラシック音楽番組(確か『朝の名曲』だっと思います)から、激しいティンパニーの刻む音が流れてきました。 朝食の箸が止まり、しばらく耳を澄ませて聴いていました。 親から、早く食べないと遅刻するよと言われるまで耳を澄まして聴き惚れていました。それがヨハネス・ブラームス(1833-1897)の交響曲と出逢った最初の瞬間でした。 劇的緊張感に包まれて開始するこのシンフォニーの凄まじさは、ベートーベンやシューベルト、チャイコフスキー(悲愴)やドボルザーク(新世界より)のそれとは異質の音楽に聴こえてきました。 それまでブラームスと言えば「ハンガリー舞曲のおじさん」くらいにしか認識していなかった私には衝撃的な出逢いでした。勿論、登校前でしたから第1楽章のみを聴いただけでしたが、その後すぐにレコードショップで出来るだけ廉いLP盤を探して、エドゥアルト・ヴァン・ベイヌム指揮のアムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団の演奏を長年に亘って聴いていました。ブラームスはこの曲を書き上げるのに21年という歳月をかけて完成しています。 先人のベートーベンの九曲の交響曲があまりにも完成度が高く、これらを凌駕する曲を書くには相当な努力と新しい息吹による音楽を作る必要性を要求されると思っていたようです。 親交を結んでいたロベルト・シューマン(1810-1856)の影響で多分にロマン的な音楽を書いていましたが、この曲によってドイツの伝統的な古典的スタイルの音楽を取り戻して、そこにロマン的な情緒を濃厚にブレンドした「新古典主義音楽」を確立したのです。第1楽章は、上述のようにティンパニーが激しい、緊張感を伴った音を刻むなかで序奏が進み、その劇的緊張感を保ったままま主部に入り、悲劇的な情緒に包みこまれてこの楽章全体を支配します。第2楽章は、ロマンの香りを撒き散らすかのような、ゆったりとしたテンポで、管楽器と弦楽が織り成す、成熟したロマン情緒いっぱいの音楽で満たされ、尚且つ北ドイツ風のわびしさを醸し出しながら進み、終結部の独奏ヴァイオリンのため息のような旋律は美しさの極みです。第3楽章は、間奏曲風の短い音楽ですが、ここでもブラームスは典雅さを表すと同時に、北ドイツのわびしさを感じさせる濃厚なロマンを描いて、激しい終楽章へと流れて行きます。第4楽章は、アルプスを想わせるような金管楽器でのコラール風の旋律が吹かれたあと、ベートーベンが書いたかと思わせるような重厚な主題旋律が弦楽器によって示されて、熱狂的な音楽へと昇華して行きます。終結部は激しく、熱狂に包まれて劇的にこの曲を閉じています。1968年11月6日は、ドイツ系フランス人の今では伝説的指揮者となりましたシャルル・ミュンシュ(1891-1968)が亡くなった日です。ボストン交響楽団を13年間、その後パリ管弦楽団(パリ音楽院管弦楽団の発展的解消したオーケストラ)の初代監督を務め、ドイツ音楽にもフランス音楽にも、激しい情熱を注ぎ込む演奏で、率直で直截的な演奏スタイルは独特のものでした。ボストン交響楽団と50年代に来日した後、1962年に当時の日本フィルハーモニーの招きで来日して名演奏を聴かせてくれました。 それがこのブラームスの1番シンフォニーでした。私は高校生で、62年12月20日のこのミュンシュと日フィルの演奏会でこのシンフォニーを客席で聴くことが出来ました。他の指揮者よりは長い指揮棒をぐるぐる振り回すような、指揮棒が竹のようにしなるような激しい指揮振りで、このブラームスの第1交響曲を熱く、激しく、劇的な緊張を保ちながら、熱狂的な終楽章コーダへ突き進む様にただただ圧倒されました。 数少ない体験ですが、あれほど熱い1番のシンフォニーを聴いたのはこのミュンシュとバーンスタインのシンフォニーホールのステージだけでした。その時の演奏会の記録がDVDとして発売されています。 伝説の域に入ってしまったミュンシュを偲ぶ格好の映像であり、こんな熱い演奏が40年以上前に日本で行なわれていたという貴重な記録です。(フジテレビ製作 エクストン レーベル OBVC-00017 1962年12月20日 東京文化会館演奏会)11月6日 他のカレンダー1893年 逝去 ピョートル・チャイコフスキー1913年 初演 サン=サーンス 「序奏とロンドカプリチオーソ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月06日
コメント(7)
-
スメタナ 「モルダウ」 / 高値のキャベツも・・・・・・
『高値のキャベツも・・・・』今日スーパーでキャベツを買った時のこと。 1個580円の高値に驚きながら、焼きそばを作るのにどうしても必要だから仕方なしに重そうなのを選らんでいると、「あら、半分売りのキャベツが売り切れてるわ。 どうしよう、1個じゃ高いし・・・・。 あの~、失礼ですがそのキャベツを私と半分ずつにして買ってもらえないでしょうか?」と40歳代くらいの女性から声をかけられました。こちらとしても「わたりに船」。 レジで半分に切ってもらって買いました。 私ならああいうことは他人には言いそびれてしまうのですが、賢い買い方をするものだと感心しました。 これも高値へのささやかな抵抗?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 スメタナ作曲 交響詩「モルダウ」1882年11月5日は、旧チェコの偉大な作曲家スメタナ(1824-1884)が書きました連作交響詩「わが祖国」全曲(6曲)がプラハで初演された日です。この6曲から成る「わが祖国」は、スメタナの熱い祖国への愛を音楽で表した曲で、歴史的人物や出来事、祖国の自然への愛着が滲みでている傑作です。 建国の象徴のような第1曲「高い城」、歴史を描いた第4曲「ターヴォル」第5曲「ブラニーク」の間に挟まった第2曲「モルダウ」第3曲「ボヘミアの草原と森」でのボヘミア地方の美しい自然と人々の生活を描いた曲集です。スメタナの時代はまだチェコスロバキアとしての独立国家でなく政治的自由は奪われていました。 スメタンは聴力を失った作曲家でした。 どんどんと幻聴のような病に冒され、貧困生活の中から、こうした連作交響詩を書き上げたのは祖国への誇りと自由を取り戻して、「ユートピア」としての理想の国を思い描き、人々を鼓舞する曲を書いたのだろうと思います。 彼の死後30年経ってチェコスロバキアとしてようやく独立国家となり、チェコに自由がもたらされたのです。チェコの人たちはこの「わが祖国」を大切に守り、愛し、今でもチェコ人の大切な「財産」として敬愛されており、「プラの春」という1946年から始まった音楽祭では毎年この「わが祖国」の演奏でオープニングされています。梅毒にかかり当時の「不治の病」と闘いながら祖国独立の願いを込めて書き上げたスメタナは、最後は精神病院でその生涯を閉じるという悲惨な人生でした。 それだけにこの曲はチェコの人たちには彼の「遺産」としての尊敬の念が深いのでしょう。この6曲の中で最も有名なのが第2曲「モルダウ」です。 「モルダウ」はボヘミアの中心を南北に流れる河の名前で、オーストリア人にとっての「ドナウ川」、ドイツ人にとっての「ライン河」のように祖国を代表する、象徴する川です。曲はモルダウ川の源流を表現したようなチョロチョロと湧いてくる水を想わせる描写から始まり、やがてとうとうと流れ行く様を描いたもので、スメタナがまるで独立国家の誕生を願い、達成することの喜び、賛歌のようにクライマックスを迎えて曲は終ります。 スメタナの祖国への熱い想いと愛に溢れた曲です。美しい旋律に溢れた、これら6曲中で最も親しみのある音楽です。 「わが祖国」といえば「モルダウ」と名前が出るくらいにこの連作交響詩の代名詞のような曲です。 尚、この連作は第1曲「高い城」から順次発表、初演されてこの『モルダウ』の初演は1875年4月4日に行なわれており、6曲全ての連作交響詩「わが祖国」としての初演が1882年の今日(11月5日)です。愛聴盤 ヴァツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団( DENON レーベル COCO70604 198211月5日 東京文化会館演奏会ライブ録音)この録音は1982年秋に来日したノイマンとチェコフィルが、『わが祖国』初演100年を記念して、初演日と同じ11月5日に東京で全曲演奏会が開かれた時のライブ録音で、現在では\1,000盤として再リリースされている盤を紹介しておきます。 民族色豊かな表現で、淀みのない美しい演奏が繰り広げられている名演奏です。 他にはラフェル・クーベリックとチェコフィルの感動的な演奏会ライブ録音もありますが、11月5日にこだわってこの盤を採り上げました。その他今日のカレンダー1846年 初演 シューマン 交響曲第2番1895年 誕生 ワルター・ギーゼキング(ピアニスト)1938年 初演 バーバー 「弦楽のためのアダージョ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月05日
コメント(6)
-
メンデルスゾーン 「スコットランド」交響曲 / 生来の慌て者
『生来の慌て者』仕事の帰りに駅近くの市場の魚屋に立ち寄りました。 この市場は今日が恒例の半額セール。 山かけ用マグロ100g198円が今日は98円だったので、今夜はこのメニューと決めていました。 まず八百屋で長芋を買い求めて、魚屋へ。 もう一つ「銀サケ」が特価。 1枚100円。 これも買っておきましょう。 肉屋も安い。 牛肉細切れを買っておこう。 肉ジャガを作れる。帰宅してさあ作ろうとすると、マグロがない。 銀サケに目を奪われて肝心のマグロを買うのを忘れている。よくあることなのです。 財布忘れて買い物に。 買い物リストを書いて、それを持たずに買い物へ。韓国でのこと。 入国して3日経過。 代理店から明日はパスポート持参ですよ、と言われて「あいよ」と返事したものの、どこを探しても見つからない。 よくよく考えたら入国時に税関検査で荷物チェックの時に税関吏に見せたあと、返してもらってから再度梱包した際に検査台に置き忘れ。 慌てて税関に電話してもらうと「いつ取りに来るのかと待っていた」と言われる始末。最大の忘れ物は、長女3歳の時に徒歩5分のスーパーへ一緒に買いものに連れていってトイレに入る間、出口で待たしておいて長女をスーパーに残したまま別の出口から帰り、途中で気が付いて慌てて迎えに行ったこと。こんな慌て者です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 メンデルスゾーン作曲 交響曲第3番 イ短調作品56 「スコットランド」1847年11月4日は、フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)が亡くなった日です。 メンデルスゾーンと言えば「結婚行進曲」(真夏の夜の夢の音楽)やヴァイオリン協奏曲や「イタリア」交響曲などの有名曲で知られる作曲家ですが、彼が20歳の時にイギリスを訪問してスコットランドにも旅をしています。 そのスコットランドのエデインバラという町の郊外にホールリード城という古城があり、そこへも彼は足をのばしています。 このホールリード城にまつわる悲しい出来事がありました。 それは16世紀のことですが、スコットランド王家の王女メアリー・ステュアートの数奇な悲劇の生涯です。 政略結婚で5歳でフランス皇太子に嫁がされ、18歳で夫と死別。 その後スコットランド貴族と結婚するも、自分の愛人が夫の策謀で殺されたのを恨み、他のスコットランド貴族と共謀して夫を暗殺しました。 そしてその貴族と結婚しました。しかし、結果はスコットランドを追われてイングランドに亡命するも斬首刑でその生涯を終えました。 彼女がスコットランド王女時代に居城としていたのが、このエディンバラ郊外のホールリード城でした。 メンデルスゾーンは1829年英国訪問時にこの古城に佇みました。 そしてこのメアリー王女の悲劇の生涯を想うことから、この曲の序奏のインスピレーションが湧いてきたそうです。このときメンデルスゾーンは20歳でしたが、実際にこの曲が書き上げられたのはそれから13年後の1842年、33歳の時でした。私は1994年4月に何度目かの英国訪問時にスコットランドのエディンバラに仕事で訪れて、その機会にこのホールリード城に足を向け、古城の隣に建っている壊れた教会の床にあったプレートで、そこがメアリー王女の部屋であることがわかりました。 プレートにそう刻まれていました。おそらくメンデルスゾーンもそこに佇み、16世紀に想いを馳せていたのでしょう。 そこから生まれたこの「スコットランド」交響曲は、私にとって特別な曲となりました。豊かで幻想的な、哀愁あふれる第1楽章冒頭からメンデルスゾーン特有の旋律美に満ちており、舞曲風の第2楽章、そして輝かしい終曲の第4楽章まで音楽の流れは淀みなく、ほのかな暗さを醸し出した旋律の美しさは、メンデルスゾーンの最高傑作の一つです。愛聴盤 オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団(東芝EMI TOCE59009 1960年ロンドン録音 カップリングは交響曲第4番 「イタリア」です)その他のカレンダー1783年 初演 モーツアルト 交響曲第36番「リンツ」1876年 初演 ブラームス 交響曲第1番1924年 逝去 ガブリエル・フォーレ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月04日
コメント(8)
-
シベリウス 交響詩「フィンランディア」 / 年賀状予約忘れていた!
『年賀状予約忘れていた!』今年はすっかり年賀状購入予約をするのを忘れていました。 それでも郵便局に電話をかけると「あ、いつもご予約いただいています枚数はお取りおきしていますよ」の返答。 小さな特定郵便局のいいところなのかなと思いました。明日(4日)に取りに行って早速年賀デザインを考えなければ。 疎遠になっている学友たちとの唯一の交友だから、一人一人へのメッセージも考えなければ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『楽天 プロ野球参入決定!』2日正式に楽天のプロ野球参加が決まりました。 おめでとうございます。これから「新しい風」としてプロ野球人気の回復のために頑張って欲しいと願っています。
2004年11月03日
コメント(10)
-
ささやかなギャンブルを楽しむ人たち / ブラームス 「ハイドンの主題による変奏曲」
『ささやかなギャンブルを楽しむ人たち』うちの近所に住む、神社役員が経営する小さな珈琲ショップには毎日町の何らかの活動をしている人たちや、中高年主婦たちが集まってきます。 ここでの会話の話題は種々雑多。 プロ野球の話、殺人事件、イラク戦争、台風や地震被害への同情、はたまた友人や近隣に住む人たちのゴシップと、毎日話題にこと欠かない。私もそこへ出入りしているのですが、こういう雰囲気はまるで広沢虎造の浪曲「石松三十石船」の町人旅人の世間話のようでおもしろい。 口に泡を飛ばして論議する老人や、ゴシップに夢中になる主婦連中。 誰も彼も他愛のない話題で賑わっている。そんな連中も競馬の大きなレースが近づくと、その話題一つになって、いっぱしの競馬評論家になる。 中年主婦がどこで仕入れてくるのかレースに出る馬の状態をとうとうと話している。 それに対して、これまたどこから仕入れてくるのか反対のことを喋り出す男性。 その議論をじっとみんなは聞いている。レース前日になればもっと過熱してくる。 予想を立ててどの馬を当てるか決めなければならない。 ああでもない、こうでもないとうるさいくらいに予想を話し合って自分の買う枠予想を決める。この買い方がおもしろい。 あれだけ過熱して論じ合って、馬券を買うのは一人で最高が3,000円。 ほとんどが600円。 1枚100円の馬券を6通りの予想をして6枚買う。 これで当たれば大変だ。 あくる日の賑やかなこと。 「あ~、この馬券買って当てたけど10万円買っておけば良かった」ささやかなギャンブルを楽しみ、そのために大怪我もしない。 宝くじを当てるより確率がいいと言って楽しんでいる。 このときのここの空間は幸せそのものに見える。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 「ハイドンの主題による変奏曲」1873年11月2日は、ヨネス・ブラームス(1833-1897)が作曲しました「ハイドンの主題による変奏曲」が初演された日です。ブラームスは友人のハイドン研究家のフェルデイナンド・ポールによって教えられたハイドン作曲の野外用管楽合奏曲の中から「聖アントーニのコラール」という楽章に興味を持ち、この旋律を主題とした大きな規模の変奏曲を書いています。 これが「ハイドン変奏曲」と呼ばれています、主題と8つの変奏および終曲とから構成された曲です。 ブラームスはピアノ曲などにも多くの変奏曲を遺しているように「変奏曲の名人」と呼ばれるほどに、立派な変奏曲を書いています。 そうした彼の才能を示す、古今の管弦楽用に書かれた変奏曲の中でも名作の一つといわれるように、一つ、一つの変奏が為される姿は、例えようもない美しさに溢れた音楽です。愛聴盤 クルト・ザンデルリンク指揮 ドレスデン国立歌劇場管弦楽団ザンデルリンクはこの曲をよほど好きだったのか、この1972年録音の他に、1990年に手兵のベルリン交響楽団との録音、それに同楽団との2002年5月の引退記念サヨナラコンサートでも取り上げてライブ録音をしています。 これら3種の演奏はどれも堅牢な構成と重厚な響きに加えて、ロマンあふれる情緒を醸し出していますが、このDENONレーベルの録音はドレスデンの「いぶし銀」のようなアンサンブルが聴けるのと、他の2組はいづれもBOXセットになっていますので、今日はこの\1,000という廉価盤を採り上げました。 ブラームスの交響曲第3番にカップリングされています。 ジャケットはLP盤のオリジナルデザインです。(DENON レーベル COCO70492 1972年ドレスデン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月02日
コメント(4)
-
スギヒラタケ 謎深まるばかり / モーツアルト フルートとハープの為の協奏曲
『スギヒラタケ 謎深まるばかり』秋の味覚の野生キノコ「スギヒラタケ」を食べた人たちが、原因不明の急性脳炎・脳症にかかる例が相次いで起こっているそうです。10月30日までの発症者は、新潟県、秋田県など8県で計48人、うち死者は13人だそうです。 この「犯人」はキノコそのものか、付着物なのか、はたまた未知の病原体なのか? これがわからずに謎が深まるばかりだそうです。発症者の大半は腎臓機能障害を患う50代以上の中高年者だそうです。 脳炎・脳症を起すウイルスやばい菌(細菌)が見つかっていないが、これら発症者のほとんどの人がスギヒラタケを食べているそうです。スギヒラタケは北海道から九州まで広く分布しており、みそ汁の具として食べられています。 秋の味覚の一つです。 食べても発症しない人もいるので、何故一部の人だけが発症するのか腎臓学会では原因を調査中だそうです。 また何故今年に限って発症しているのかも不明。原因がわかるまで食べないようにと学会では呼びかけるそうです。 みなさん、おいしい秋の味覚ですが、今年はスギヒラタケは食べないようにしましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 「フルートとハープのための協奏曲 ハ長調 KV299」1984年11月1日は、フランスのフルート奏者でありフルート教育者であったマルセル・モイーズ(1889~1894)が亡くなった日です。 彼はフランスのオーケストラでのフルート奏者でしたが、後世ではフルート奏者育成にその足跡を残したことで有名な人で、彼の弟子には高名なオーレル・ニコレというフルート奏者がいます。今日はそのモイーズの命日に因んで、華やかなフルートの音を楽しめるW.Aモーツアルト(1756-1791)作曲の「フルートとハープの為の協奏曲」を紹介しましょう。この曲はモーツアルトが27歳の時に書かれています。 1778年にパリ滞在中に、フルートを愛するある貴族とハープを演奏するその娘のために作曲されたそうです。音楽はとても平易ですが、フルートは明るく旋律美に富み、ハープはそれに寄り添うように互いを強調しながら独奏部を受け持っています。曲全体はモーツアルトの特徴である、「ロココ風」の輝くような明るさ、優雅さを備えており、典雅そのものといった音楽で、彼の作品の中でも最も美しい音楽の一つです。愛聴盤 アンドラーシュ・アドリアン(フルート) スザンナ・ミルドニアン(ハープ) ハンス・シュタットルマイヤー指揮 ミュンヘン室内管弦楽団(DENONレーベル COCO70620 1979年録音)1,000円の廉価盤となって再リリースされています・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年11月01日
コメント(9)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-







