2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
90歳でパソコンに / ガーシュイン オペラ「ポーギーとベス」
私の叔父(母の兄)は今年90歳になった。 少しずつ体力は衰えてきてはいるが、毎日犬を散歩に連れて歩いている。 数年前は2kmくらいの高低のある道を歩いていたが、さすがにこの頃は家の近所の公園を散歩するに留めている。この叔父が7年くらい前だったと思うが、パソコンを購入してパソコン生活を始めた。 「ボケ防止にええからなあ」と言いながらPCに向かっていた。 OSはWindows95だったと記憶している。 ExcelやWord教則本を買って、スクールにも行かずにひたすら独力でパソコンの勉強を始めていた。入力もままならぬレベルから始めて、今では私がWordやExcelについて尋ねることがあるくらいに上達している。 今年の春には阪神タイガースの全日程表をWordで作成した。 市のコミュニテイバスの時刻表をイラスト入りで作成したり、24節気一覧表を作ったりしている。今は毎日Wordに日記を書き、そこに政治、経済、社会の出来事を新聞記事からピックアップして書き込んでいる。 それとは別に自分の生き様を記すべく「自分史」を書いている。この町の町内史を背景に書きたいと言って、私が持っている市編纂の町内史を借りに来たこともある。時々とんでもない誤操作をしてPCが動かなくなったとか、保存していたデーターがどこかに隠れてしまって2日も3日も根気良く探していたこともあった。今は新しいパソコンを購入して快適にXPを楽しんでいる。私が撮った花の写真をデイスクトップの壁紙にしてくれている。 数日前は、難聴でもよく聞こえる電話をインターネットで探して購入しようかと、プリントアウトした三洋の電話機のリーフレットを見せてくれた。私が叔父の年になるまでにまだ30年かかる。 脱帽。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第2次小泉改革実現内閣カ 改革なくして成長なしと イ 言い張り続けて3年有半カ 改造の道いまだになかばク 口先だけかと揶揄されるジ 自画自賛は得意だけれどツ ついつい気になる世間の評判ゲン 言行一致の理想は遠くナ 泣くも笑うもあともう2年イ いったい実現するのかしらカ 改革、改革、声のみ高くク 苦闘は必死の郵政一本勝負 9月28日朝日新聞夕刊「素粒子」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ガーシュイン オペラ「ポーギーとベス」1935年9月30日にアメリカの作曲家ジョージ・ガーシュインのオペラ「ポーギーとベス」がボストンで初演されました。 今日はこのオペラを聴こうと思います。「ポーギーとベス」の登場人物はほとんど黒人で、彼らの社会を題材にしたユニークなオペラです。 1920年代のサウスカロライナのチャールストンを舞台にして貧困な黒人社会の恋と犯罪を扱っていて、黒人の庶民生活と人間をジャズやブルースなどのアメリカ的音楽を使って生き生きと描写しています。 「サマータイム」「ベスよお前は俺のもの」「くたびれもうけ」などは独立したナンバーとしても愛されています。とものお薦め盤サイモン・ラトル指揮 ロンドンフイルハーモニー ウイラード・ホワイト(ポーギー) グレッグ・ベイカー(ベス)(1988年 録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月30日
コメント(8)
-
堀江貴文氏(ライブドア社長)の教育改革論について / 乙女の祈り
毎日新聞2004年9月27日付け朝刊に現在プロ野球への新規参入で話題になっている、ライブドア社長の堀江貴文氏の教育改革論が談話として掲載されていました。彼のこの改革論を読むと今までのマスメデイアを通しての、氏のイメージが多少違って見えてきました。主旨は以下の通りです。今の教育には無駄が多い。 学校に拘束される時間が長い。 教育に時間をかけ過ぎる。 小学校から大学まで16年あるが7~8年で充分だと言い切っています。彼自身は協調性のない生徒だったらしい。 小学生の頃はダントツの成績で先生の話はおもしろくない。 テストは5分間で終ってしまうので、あとは苦痛の時間として座っていた。掃除当番にあたってもやらなかった。 雑巾掛けに意味がなかった。 家でもやらないことを学校でする気はなく、先生に雑巾掛けの意味を聞いても納得する答えはなかった。中学、高校の6年間で、5年間は遊んで1年だけ勉強して東大に入学したが、大学の講義は教授が本を読むだけだから自分で読んだほうがいい。 毎週大学に行く意味がなかった。 それで中退した。パソコン、ワープロの発達で「読み書きソロバン」は不要だ。 漢字も書けなくてもパソコンがあればそれでいい。それよりも、子供には必ず何か長所がある。 走る、絵を描くなどの才能を持つ人材の能力を伸ばすことが大事だ。 「人」は国の財産だからそれを生かすためには、制度を変えて国が負担して無駄を失くす改革をやるべきだ。私は彼のこうした教育についての考え方に違和感を覚えると共に、奢りのようなものを感じます。 仙台で性急に楽天社長を追っかけて待ちうけの形で話し合いをしようと試みた、彼のやり方がうなづけるようです。雑巾掛けに意味がないというところにひっかかります。 教師がいくら説明しても、電車内の床に座る生徒と同じように、言葉を尽くしても考え方が違うのだから納得はできないでしょう。 「何故あなたは正しいの?」と問われた答えが「相手が悪いから」の図式と同じだろうと思います。彼の論理を全て否定はしません。 学ぶべきポイントはあります。 経済的な理由から夢を断念せざるを得ない優秀な人材に、開くべき道を国は考えるべきだと思います。しかし、こういう論に達するまでの、基本的な人間育成のための教育に、「協調性がない」視点で観ているところに疑問を生じます。彼のプロ野球への新規参入、新球団設立への情熱をメデイアで観ていた私は何か水を差されたような思いがしました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 バダジェフスカ 「乙女の祈り」1861年の9月29日にテクラ・バダジェフスカ(1833-1861)が亡くなっています。 ピアノ曲「乙女の祈り」を作曲した彼女は、わずか27歳でこの世を去っています。 この有名な曲は18歳ごろに作曲されて1854年にパリで出版されたそうです。 私は彼女の作曲した音楽はこれしか知りません。 この1曲で後世に名前を残しているのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月29日
コメント(8)
-
秋祭りの準備と仲秋の名月(加筆) / MJQ
仲秋の名月(加筆)今日は「仲秋の名月」 しかし大阪はあいにくと雨の予報で名月を愛でる空模様ではありません。 朝からどんよりと曇り空。 夕方にも雨がやって来そうな、そんな名月の夜です。 京都栂尾の高山寺の明恵上人(鎌倉時代初期、高山寺開祖)の名句の月が観られるのは東北、北海道だけらしいです。あかあかや あかあかあかや あかあかや あかあかあかや あかあかや月・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・秋祭りの準備町は日に日に秋祭り(だんじり祭り)に染まってきています。 町内は2つのブロックに別れてそれぞれが1台のだんじりを持っていて、神社の祭りとして五穀豊穣を祝う行事として長い間、毎年この時期に町中をねり歩いてきました。最近は岸和田のだんじり祭りに刺激されて、いっそう過熱するさまは近隣の町と変わりません。すでに町中には飾り提灯が高く吊るされており、毎日夕方になるとだんじりの囃子の音が聞こえてきます。 笛、太鼓のお囃子の練習が2週間前から始まり、「花」といって町内の人々から寄贈される「ご祝儀」の金額と寄贈者の名前を書いた紙を張り出す板が神社や本部の前に立てられています。今年の秋祭りは10月9日、10日の2日間です。 市全体で20台ほどあるだんじりが駅前に一堂に会して、駅前周辺の目抜き通りを走りぬけます。この2日間は、朝7時から夜10時まで市のどの町もだんじりで燃える秋となります。 秋祭りの様子は画像入りでそのころに紹介いたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日の音楽 MJQ(モダン・ジャズクワルテット)今日は趣を変えてモダン・ジャズからMJQを採り上げました。 このクワルテットは1952年に結成されて、その数年前からの「クール・ジャズ」と呼ばれる流れを継承するかのような爽やかな「クールネス」と、当時流行った白人ジャズの「ウエストコースト・ジャズ」のグループ・サウンドの過熱するスタイルの両面を持ち合わせて登場してきました。後年になってバッハの曲を積極的に採り上げて、MJQ独特の「クールネス」な響きで一世を風靡しました。 ヨーロッパのクラシック音楽をジャズの響きに融合させた成功例がMJQです。 フランスのジャック・ルーシェトリオとは、全く趣の違うクラシック音楽とジャズの融合であり、アメリカのジャズ音楽が底辺に脈々と流れているMJQとフランス・ジャズの洒落た音楽・響きとの違いだと思います。私がMJQに魅かれる一番の理由は、メンバーであるミルト・ジャクソンのヴァイブ(ヴィブラフォン)です。 彼のヴァイブはどの曲を聴いても、この楽団の核となっており「クールネス」と「白人ジャズ」の過熱さを楽しませてくれます。 またリーダーのジョン・ルイス(ピアノ)はバッハの音楽をジャズにアレンジして、クールなジャズ・ピアノを楽しませてくれます。お薦めは「プレステイッジ」に1955年に録音された「コンコルド」というCDです。 「ガーシュイン・メドレー」としてジョージ・ガーシュインの曲が4曲録音されているのが貴重です。このときのメンバーは、ジョン・ルイス(ピアノ)ミルト・ジャクソン(ヴァイブ)パーシー・ヒース(ベース)コニー・ケイ(ドラム)となっています。初期のアルバムですがMJQを語るには欠かせない録音です。(プレステイッジ盤 VICJ-2043)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月28日
コメント(8)
-
孫の退院 / オペラ 「ヘンゼルとグレーテル」
孫が昨日退院しました。 産まれた時は2400gで小さい赤ちゃんでした。 授乳時には1回に20ccくらいのお乳の出だったので、なかなか退院できる2500gにならずにいたのですが、私が会いに行ったときにはそれをクリアーしていました。ところが赤ちゃん特有の黄疸症状の数値が退院できる数値にならずにいて、一足先に娘が退院して授乳に通っていたのですが、昨日数値検査でやっとクリアーできて退院しました。自宅では授乳で80cc出るようになり、満腹になって眠ると次の授乳時に起さないといけないそうです。 入院しているときは、お乳での出があまりよくないので、少し飲んでは眠り、すぐに目が覚めて泣くという繰り返しで娘が眠れない状態でイライラもあったのですが、今は少し落着いたようです。これから育児が始まる娘は店の経営と二足のわらじなので、大変だと思いますが、今まで一人で何でもやってきた人ですから、「わたし流」で頑張ると思います。 近くに家内が住んでいるので安心です。孫の退院にホッとするともさんでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 フンパーデインク オペラ「ヘンゼルとグレーテル」1921年の9月27日にドイツの作曲家エンゲルベルト・フンパーデインク(1854-1921)が亡くなりました。 今日はその彼の遺した傑作オペラ「ヘンゼルとグレーテル」を聴きます。ワグナーの重苦しい楽劇の反動として、素朴な民話・童話を題材にして、「森」の好きなドイツ民族の心を捉える民謡などの親しめる楽しい旋律を使って作曲されるようになった「メルヘン・オペラ」の代表作のこのオペラは、有名なグリム童話を題材にしています。わかりやすい、親しみのもてる素朴な民謡風の音楽を基調にしているので、楽しめるオペラになっています。とものお薦め盤 ショルテイ指揮 ウイーンフィル ファスベンダー(Ms) エディタ・グルベローヴァ’S) ヘルマン・プライ(Br) 上記一流の歌手を揃えており、メルヘンの世界を楽しめる極上のオペラ映画(VHS)です。(LONDON POVL-2005 1981年ウイーン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月27日
コメント(9)
-
プロ野球機構の大罪 / バルトーク 管弦楽のための協奏曲
日本ハムがプレーオフ進出を決めた。 但し、ストによる代替試合がないという条件付きだ。この「条件付き」がせっかく選手、ファンが盛り上がっていた熱気に水を差した。 この進出を決める試合の日程は予め決められていたのだから、機構側が代替試合をやるか、やらないかを早急に決めておくべきで、これは機構の責任を全うする義務を怠ったもので、断罪されるべき由々しき問題だと思う。 当日はダイエー松中選手の三冠王も「条件付き」で確定している。明確に結論を出しておけば日本ハムの選手、ファンも手放しで盛り上がり喜んでいたはずだ。 当初プレーオフは初めてのケースなのでパ・リーグも手探りの状態だったのが、ここにきて俄かにとも思えるほど熱気をはらみ、リーグに注目度が増した。それをもっと盛り上げる結論を機構側は考えなかったのか?選手会によるストライキは、代替試合を行なわないとするのが普通の考え方だと思うが、このことにすら結論を先延ばしする機構側の考え方に、これからのプロ野球を考えてもらうことに大いに疑問を感じ、まだまだファン商売の何たるかを知ってもらう必要があると思う。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 バルトーク 「管弦楽の為の協奏曲」1945年の今日、ハンガリー出身の作曲家ベラ・バルトーク(1881-1945)が亡くなった日です。第二次世界大戦でナチ・ドイツに追われてとるものもとらずにアメリカに渡った彼の生活は厳しいものであったらしい。自作の曲がアメリカで評価されず、貧困生活を送っていたのを同じハンガリー系の指揮者フリッツ・ライナーやヴァイオリンのヨゼフ・シゲテイなどが援助の手を差し伸べて、当時の大指揮者クーゼビッキーの音楽財団の委嘱作品として依頼して作曲されたのがこの「管弦楽の為の協奏曲」です。バルトークは、アメリカにわたる前に2つのピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、「弦とチェレスタのための音楽」オペラ「青ひげ公の城」バレエ音楽「木製のかかし」「中国の役人」それにハンガリー民俗音楽を基にした数多くのピアノ曲を作曲していました。この「管弦楽の為の協奏曲」は、まるでオーケストラの各パートの妙技を試すかのような曲で、バロック音楽時代の合奏協奏曲風に書かれており、ハンガリー・マジャール風の音楽が盛りこまれ、しかも厳しい精神性を描いた現代音楽の傑作中の傑作です。ブタベスト音楽院の教授をつとめるかたわら、上述のような名曲を数多く残していたバルトーク。 戦争がなければアメリカに渡ることもなく、貧困にあえぐこともなく、順風満帆の生活からもっと素晴らしい音楽を我々に遺してくれたはずですが、ここにも「戦争」という人類の悲劇があります。とものお薦めCD フリッツ・ライナー指揮/シカゴ響、ゲオルグ・ショルテイ指揮/シカゴ響、アンタル・ドラテイ指揮/アムステルダム・コンセルトヘボー、などのハンガリー系指揮者の演奏はマジャール色、ハンガリー色の濃い音楽を繰り広げています。 これらの指揮者の演奏をお薦めします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月26日
コメント(2)
-
プロ野球の行方 / J.シュトラス 「ラデッキー行進曲」
9月22日に球団側と選手会との話し合いの結果、スト回避の結論が出ました。 球団側の譲歩と見られる合意書に双方が署名して妥結されました。近鉄・オリックス合併の1年間凍結を要求した選手会の最初の要望とは違う図式になったものの、楽天やライブドアの新規参入について球団側の前向きな姿勢により、どうやら来季もセ6・パ6というチーム数で行なわれる可能性が出てきました。これはあくまでも第一歩であって、これから先の改革に突いては選手会も交えて球界全体が、見直し作業にかかり赤字経営をなくすような努力を期待します。選手年棒高騰への歯止め、TV放映権料の見直し、それに解消されてしまう2チームの選手の割り当てなど、色々と山積してるポイントを整理して、真摯に取り組んでもらいたいと願うものです。近鉄・オリックスの選手の痛みが無駄にならないようにやって欲しいと願います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 J・シュトラウス一世 「ラデッキー行進曲」1849年の今日「ワルツ王」と呼ばれた「ウインナ・ワルツ」が代名詞のようなJ・シュトラウスIIの父、一世が亡くなった日です。 この一世の有名曲は「ラデッキー行進曲」です。 元旦のウイーンフィル ニューイヤーコンサートの最後に演奏されて、聴衆も演奏といっしょになって手拍子を打つことで有名な曲です。 彼の命日に因んで、今日はこの曲を聴くことにします、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月25日
コメント(6)
-
凛々しい孫娘 / バスティアニーニ 誕生日
浜名湖国際花博会場は想像した以上に広く、昨日は真夏のような陽射しが照りつけて暑い一日でした。 花の時期が悪くていい花が少ないという印象でしたが、それでもガーベラが庭いっぱいに咲いていたり、館の中では色々な庭を造ってそこへ季節の花を咲かせていて、楽しむことができました。一日であれだけの花を楽しめるのは幸せだな思いながら見ていました。夜になって次女が入院している病院で孫娘と会ってきました。 まだ6日目ですがもっと皺くちゃな顔をしているのかと思っていましたが、凛々しい顔つきをしているのに驚きました。 手や足の指が長く、しっかりとしているのも驚きです。 生命の誕生の神秘を目の当たりにしてきました。家内が言ってました。 「この子、今が王様よ。 我儘放題なんだから」 たしかにお腹が空けば泣きじゃくる。真夜中であろうが、夜明け時であろうが「お~い、お腹空いたぞ!」って威張っているんですから。 「今、せいぜい我儘にしてるといいわ。 これから出来なくなるんだから」と家内。花と孫娘。 幸せな一日でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 バステイアニーニ、イタリアを歌う~ラストレコーデイング今日は1922年イタリアのバリトン歌手エットーレ・バステイアニーニ(1922-1967)が生まれた日です。バステイアニーニは、テノールのマリオ・デル・モナコ、ソプラノのレナータ・テバルデイ、メゾ・ソプラノのジュリエッタ・シミオナートなどと共に1960年代のイタリアオペラ黄金期を支えたバリトンで、明るい、豊かな響きを持った声で世界のオペラファンを唸らせた歌手でした。 学生時代にわずかにTVで舞台を観ただけで、モナコのように実際に舞台姿を観れなかったのが悔やまれます。彼の誕生日にこのCDで美声を偲ぼうと思います。 このCDは日本で録音されたもので、彼の生涯で最後の録音となったものです。 イタリア民謡、歌曲16曲を見事に歌いきっており、今でもどこからか、あの長い、素晴らしい脚線美の足で気品溢れる姿を現してくれるかのようなアルバムです。(キングレコード NKCD 3816 1965年6月東京録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月24日
コメント(8)
-
浜松花博
今日は朝早く起きて(6時)静岡の浜松へ行き、花博を見物してそのあと娘が入院している病院へ孫を見に行きます。初孫でもないのに、やはり日本で生まれた孫にはいつでも会えるという気軽さがあるのか、まるで初孫が生まれたようなウキウキした気分です(ちょっとアメリカにいる孫には悪いですが)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽は休みます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月23日
コメント(10)
-
朝の詩 髪 / シューベルト 「ソナチネ」
「やわらかな髪の子は 心がやさしいのよ」小さな私の髪を梳きながら母は言う猫毛の私の髪を洗い最後のすすぎ湯に椿油を二、三滴入れてくれた母秋海堂の零れ咲く庭で五歳の孫のサラサラのやわらかな髪を梳きながら「やわらかな髪の子は 心がやさしいのよ」母と同じことを私は言っている・・・。 産経新聞朝刊2004年9月21日付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 シューベルト 「ソナチネ」1918年の今日、大ヴァイオリニスト ヘンリク・シェリング(1918-1988)が生まれました。 ポーランドに生まれ、メキシコの市民権を得た彼の演奏スタイルは「厳しさ」「知性」が前面に出て、およそ情緒面に溺れない厳格な演奏様式を貫いた演奏家でした。 1976年の日本でのバッハの「無伴奏ソナタ」「パルテイータ」はあたりを払うかのような威厳に満ちた、ピーンと張りつめた緊張感が最後までホールを支配していました。その彼の演奏を今日は優雅さと叙情性豊かな演奏が持ち味のイングリッド・ヘブラーというピアニストと繰り広げたシューベルトの「ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ」が3曲収められたCDで楽しもうと思います。まるで家庭のサロンで弾かれるために書かれたような3曲のソナチネは、シューベルト独特の流れるような、淀みのない情感に溢れた音楽で、これを知的なスタイルのシェリングと温かさ溢れるヘブラーの見事な音楽世界の融合を楽しんでみようと思います。(Philips レーベル PHCP-9041 1974年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月22日
コメント(5)
-
敬老の日(2) / ホルスト 組曲「惑星」
昨日は「敬老の日」。 先週出産した次女からも母に贈り物が届けられた。 喜ぶ母。 夫に頼んでおいたのか一昨日の日付の宅急便が昨日届いた。 「入院、出産でも覚えていてくれていたんだね、嬉しいね」と涙を浮かべて語っていた。 買い物に行く暇がなかったのか、カタログだけでその中から好きな物を選ぶ、昨今流行のプレゼントスタイルだ。 「どれにしようかな?」品物を選ぶ母は嬉しそうだった。昨夜のTVで元気なお年寄りたちの紹介番組があった。68歳で庭に据えた鉄棒で毎日大車輪を行なうおじいさん(TVCMで有名な人)80歳でハングライダーを楽しむおじいさん。 80歳の卓球世界大会の金メダリストのおばあちゃん。90歳でまだ漁に出ているおじいさん。 流行歌に合わせて鍋、釜叩いてパーカッションアンサンブルを演奏する老人グループ。「人生の夕映え」を美しく輝かせている人たちだった。 そういう老人たちから、「元気」をもらったのは私だった。 どんな老いを迎えるかではなく、今から何をしようかと探して見つけたものを一生懸命にやらねばと、改めて思う番組だった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ホルスト 組曲「惑星」1874年の今日、イギリスの作曲家グスターブ・ホルスト(1874-1934)が生まれました。 彼の作曲家としての名前が有名なのは、作品番号32の組曲「惑星」に他なりません。「惑星」は太陽系の7つの惑星を題材にして占星術からヒントを得て、「火星」(戦争)金星(平和)水星(翼)木星(快楽)「土星」(老年)天王星(魔術師)「海王星」(神秘)に( )の中に書いたような性格づけをして、色彩豊かに、時には静謐な宇宙空間を、時にはダイナミックな空間を描いた現代音楽の傑作です。 「スターウオーズ」の先取りのような音楽です。ではどうして「冥王星」がないの? 1916年にこの曲が完成した時は「冥王星」はまだ未知の惑星で、彼が亡くなる4年前の1930年になってやっと発見された「惑星」なので、この組曲には当然入っていません。とものお薦めCD カラヤン指揮 ウインーフィルハーモニー1961年録音だから相当古いのですが、カラヤンとウイーンフィルが繰り広げる天体のファンタジー音楽は、ウイーンフィルの極上のアンサンブルと響きで包み込んでくれる演奏です。 ベルリンフィルと88年にも再録音していますが、このLPがステレオ録音の進化と共に、「惑星」の録音ラッシュを促すきっかけになったものなので、ここに敢えてお薦めとします。(ロンドン レーベル UCCD7129 1961年ウイーン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月21日
コメント(10)
-
超、超激安! これでいいの? / サラサーテ 「カルメン幻想曲」
先月8月にHMVのHPで古楽器チェロのアンナー・ビルスマの70歳を祝う記念CD11枚組が\3,290での発売が目にとまりました。 バッハ無伴奏チェロ組曲(全曲)、ベートーベン チェロソナタ(全曲) ブラームス チェロソナタ(全曲)ボッケリーニ チェロ作品集、 メンデルスゾーン 八重奏曲、シューベルト 弦楽五重奏曲、モーツアルト デイヴェルトメント集、ヴォヴァルデイ チェロ協奏曲集、弦楽合奏曲選集、プロシャ王とチェロ(デユポー、ベートーベン、ロンバーグ、ボッケリーニのチェロ音楽選集)など、バッハの1979年録音以外は全て1990年代録音です。私は生来、ピリオド楽器による演奏は好きではありません。 どうしても音の厚みに欠けてしまうきらいがあるからです。 特に古楽器オーケストラは避けています。 評判のラトルなどの現代楽器によるピリオド奏法などにも聴くのに抵抗があります。インマーゼルのベートーベンのVnソナタくらいでしょうか、楽しめたのは(コープマンや、ホグウッドのデイスクは例外です)。ですから、ビルスマについてもリリース当時から興味がなく1枚も聴いていなかったのですが、今回のヨーロッパ盤11枚組¥3,290に魅かれて予約しておいて、一昨日HMV阿部野店に取りに行きました。たまたまHMVのポイントカードがあったので、それを使い、さらに10%OFFカードを使って買うと、なんと¥461なんです。 11枚組CDが\461! これでいいのかなと思いながら買ってきて、早速ベートーベンの3番のチェロソナタを聴いたのですが、インマーゼル同様にガット弦の響きが自然に心の琴線に触れてくる、素晴らしい音楽空間が展けてくるのです。 これから聴くのが楽しみな、\461の11枚組です。(Sony Classical ドイツプレス盤 1979-1995年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 サラサーテ 「カルメン幻想曲」1908年の今日、スペインの作曲家で名ヴァイオリニストのパブロ・サラサーテ(1844-1908)が亡くなった日です。彼はヴァイオリンの名手だったそうで、作曲にもヴァイオリンの曲が多く、今日でもコンサート、レコード録音などにも数多く採り上げられています。 「ツゴイネルワイゼン」「スペイン舞曲集」「カルメン幻想曲」などがとりわけ有名です。今日はそのサラサーテの命日にちなんで、「カルメン幻想曲」を聴こうと思います。 この曲はフランスのビゼーが作曲した有名なオペラ「カルメン」の音楽から題材を得て、ヴァイオリンと管弦楽、もしくはピアノと演奏される、非常に親しみ深い、それでいて随所にヴァイオリンの妙技と美しい音を楽しめる曲です。とものお薦めCDイッツァーク・パールマン(Vn) ズービン・メータ指揮 ニューヨークフィルハーモニーこのCDには他にショーソンの「詩曲」サン=サーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」「ハバネラ」ラヴェル「ツィガーヌ」などのヴァイオリンの美しい音楽を楽しめる曲がカップリングされています。 パールマンの多彩で、甘美で情感豊かな技巧を随所に聴くことのできるCDです。尚、今日はフィンランドの大作曲家ヤン・シベリウスが1957年に亡くなった命日でもあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月20日
コメント(11)
-
プロ野球のこれからの行方 / ベートーベン ピアノ協奏曲第5番「皇帝」
選手会側と球団側に埋められない溝があるために、ストライキが決行されました。 来週も引き続き交渉のテーブルが用意されて、更なる話し合いが続けられてその結果によってはまた第二波のストライキの可能性もあるらしい。近鉄・オリックス合併の1年間凍結を訴える選手会が、今度は「ライブドア」「楽天」の2社の新たに参入したいという問題も議論されて、合意点を見出せなかった結果のスト決行であると新聞、TVは報じており、選手会長古田選手はフジTV系列スポーツ番組に出演して、今回のストについて涙を流した場面もありました。次回の折衝も難航が予想されます。この大変な時期に唖然とするニュースが飛び込んできました。 根来コミッショナーの辞任報道。彼の提案した問題が擦り合わせどころか、俎上にも上らなかったとの報道もありますが、それを踏まえての辞任発言らしいのです。球団と選手会の溝を埋める努力を、仲裁のような形で行なうべきコミッショナーが、書類で提出した案がないがしろに近い形になったからといって辞任とは何事かと思います。 両者をまとめるのがコミッショナーで、一度出した提案が没になったといって、在任期間わずか7ヶ月で放り出すのはあまりにも無責任だと思います。あの案に自信があるなら、何故自ら出席して両者を説得しないのか? ちょうどいい「潮時」を見つけて辞任するとうがった見方をされても仕方がないと思います。プロ野球コミッショナーの仕事、責任、義務を今ほどに問われている時期はないはずです。 このまま放置すれば泥沼の確執が生まれてしまい、取り返しのつかないことが起こるかもしれません。根来コミッショナー、今こそあなたの出馬する時ではありませんか? そして強いリーダーシップを発揮するのがコミッショナーの仕事ではありませんか?辞任したあと、誰が責任もって事態収拾を図るのですか?球団と選手会の溝を埋めて、強権を発動する時期なんですぞ、コミッショナー!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ベートーベン ピアノ協奏曲第五番 変ホ長調「皇帝」1972年の今日、フランスのピアニスト ロベール・カザドシュ(1899-1972)が亡くなりました。 その命日にちなんで、彼の遺したデイスクからこの曲を選びました。 私が小遣いで買った2枚目のLPがこの録音盤でした。 中学2年生でした。 そのLPで存分に「皇帝」を毎日、毎日聴いていました。 買って初めて聴いた曲でもありました。 第1楽章の冒頭のピアノのカデンツアにすっかりはまってしまい、初めて聴き終わったあとも3度も連続して聴いていた思い出があります。勿論、その当時は演奏などについての長短などわかるはずもなく、曲の美しさ、偉大さに酔って聴いていました。華麗なピアノのカデンツアから始まり、掛け合いのようにピアノとオーケストラの音楽が流れていくさまは、まるでピアノ付き交響曲といった趣で、あたりを払うかのような威風堂々とした、雄渾なピアノ協奏曲です。年月が流れて、あれは確か1967年だと思いますが、このカサドシュが読売日本交響楽団と共演して、この「皇帝」を新宿厚生年金会館で演奏しました。 指揮は最後の来日となったハンガリーの名指揮者イシュトバン・ケルテスでした。客席に座って冒頭のカデンツアが演奏された時に、「あ、あの音!」と思いました。 あのLPのままのピアノの音が流れ出したのです。 目頭が熱くなりました。ピアノは福よかに、豊穣に響き渡り、しかもフランス人らしい色彩感あふれる音でした。 その演奏会の時にはこのLPはもう聴くに耐えないほどの傷が出来ていて、ただレコード棚に置いてあるだけでした。それが2年ほど前にCDに復刻されてリリースされました。この曲の指揮者はデイミトリ・ミトロプーロス/ニューヨークフィルです。カザドシュよりも、もっといいピアニストの素晴らしい演奏があります。 ルービンシュタイン/バレンボイム指揮、バックハウス/イッセルシュテット指揮、シュナーベル/フルトヴェングラー指揮など数え上げたら10枚以上あるでしょう。しかし今日は、あの少年の頃に戻り、青年時代に接した彼の生演奏を思いだしながら、この「皇帝」を聴こうと思います。ロベール・カザドシュ(ピアノ) ミトロプーロス指揮 ニューヨークフィルハーモニー(ソニークラシカルレーベル フランス盤 1955年9月モノラル録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月19日
コメント(6)
-
カタカナの氾濫・ プロ野球ストライキ決行(加筆)
IT時代、IT世代と呼ばれる昨今。 気が付いてみれば自分のまわりの街中はカタカナで溢れている。 商店の看板が漢字、平仮名表示が減って、カタカナ、アルファベットが目につくようになった。 英語を扱う仕事をしているせいか、その表示の間違いによく気が付く。一番目に付くのが「美容院」の看板や表示。Beauty Salon もしくはBeauty Parlorが正しい英語なのだが、Saloonだったり、Perarだったりする店がある。 さらにパーマがParmaだったり。 パーマはPermanent Waveから来た、今ではどこでも通じる言葉で、これには私も異論はないが、看板表示に何故アルファベットで書くのかが解せない。「・・・建設」と言う会社名。 これを「・・・Kensetsu」だとか、散髪屋がBerber shopとかの表示。 うちの町では外人居住は数人なのに、何故こういう表示にするのかと思う。おもしろいのはスーパーマーケット。 英語ででっかくSuperと書いてある。 日本語で「スーパーマーケット」にすればいいのにと思うのだが。それに車の会社名表示。 巴商店がTomoe Shouten, 外人相手のビジネスではないから、漢字で書けばいいと思うのだが。「ドットコムどこが混むのと訊く上司」 笑い話でなくなってきた。 かく言う私のこのページのタイトルは「プレリュード」だが。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ところで昨日、静岡に住んでいる私の次女に女の子が生まれました。 30歳を過ぎての結婚で高年出産だったので心配していましたが無事出産を終えたとの連絡がありほっとしています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・昨夜プロ野球のストライキ決行が決まった。 この是非については様々な意見があると思います。 おそらくどれも正しいかも知れません。 私は「決行」に賛成です。 いままでに「混迷のプロ野球を憂う」で書いてきましたから、ここに加筆することはありません。ただ今朝のNTV番組で同局専属の野球解説者で元巨人投手の宮本氏がコメントを求められて、「自分の出身地山口で子供たちに野球を教え、全国大会規模の少年野球に力を入れてきているが、あの子たちの目は輝いて・・・・」そこで声を詰まらせてしまった。 彼の言いたいことは5年後、10年後のプロ野球の将来を憂えているのです。古田選手会長が一番スト決行に苦しんでいると思います。新規参入に門戸を開き、せめて1年間はなんとか近鉄・オリックス合併を凍結して、球団、選手会が将来のプロ野球を見据えた青写真を作り上げて欲しいと願うばかりです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月18日
コメント(9)
-
敬老の日 / シューベルト 弦楽五重奏曲 ハ長調
今までは敬老の日は9月15日と決まっていましたが、今は土日の連休を考慮して毎年日が変わっていて、今年は9月20日となっています。老人となっていくと、人それぞれ「老いの生き方」を想い、考えるようになると思います。 私は還暦を迎えましたがまだまだ現役と思いつつ、毎日を過ごしていますが高齢になると「老いる」ことへの想いがよぎってくるだろうと思います。9月15日付け朝日新聞朝刊の「声」欄にこんな投稿をされている女性のご老人がおられます。(前略・・・「年を重ねても自分の生活のすべてを賄い、その上、主人の介護にも通えることが生きがいになっている身をありがたいことと思っております。(中略)次の世代のために、住みやすくなるように願う日です。 文明が進んで心が留守になっています。 お年寄りのための施設やボランテイアなど、随分充実してきましたが、若い方の子育てにも微力を尽くしたいと思います」(福岡 87歳 女性)私もいつか『老い』を迎えて「人生の秋」「人生の黄昏」のときを「美しい夕映え・残照」にしたいと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 シューベルト 「弦楽五重奏曲ハ長調 D956」1850年の今日(9月17日)この曲が初演されました。 15曲の弦楽四重奏曲を遺しているシューベルト(1797-1828)ですが、チェロを2台にしたこの五重奏曲は彼の最後の室内楽曲です。四重奏にチェロを加えているために、交響楽的な色彩と深みが加わり、数多くの歌曲で知られるように、美しい旋律に満ちた室内楽の傑作です。 初演日にちなんで今日はこの曲を採り上げました。とものお薦めCD ハーゲン弦楽四重奏団、ハインリッヒ・シフ(チェロ)(独グラモフォン 439 7742-2 1991年6-7月録音)ハーゲンと息の合ったシフのチェロ。 流れるようなアンサンブルの美しさは例えようのないほど美しく、歌心に溢れた演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月17日
コメント(2)
-
今更・・・・・・・ / マリア・カラス オペラアリア集
アメリカ合衆国パウエル国務長官が議会の聴聞会で、初めてイラクの大量破壊兵器が存在しないことを公式に認めた。「いかなる備蓄も発見されておらず、今後も見つかることはないだろう」「やっぱり」「とうとう・・・」という思いがある。 ブッシュが掲げたイラク戦争が、間違った事実を根拠に始められたことをこれでアメリカ政府が公式に認めたことになる。この戦争で死んでいった人たちの無念さが聞こえてくるようだ、報道では何万人ともいわれる死者。 市民をも巻き込んで起こった戦争。 戦争は人を殺すことだ。 いくら大義名分があっても、人が死んでいく戦争の愚かさをいつになれば終わらせることができるのか?今なおイラク、関係国家でテロのために死んでいくひとが、あとを絶たない。 この事実を、「誤りであった」と認めるアメリカ政府を誰が裁くのか?私は初めからこの戦争を「ヤクザの抗争」の図式として捕えており、国際情勢にうとい母に説明してきた。山口組(アメリカ)が関東一和会(イラク)のシマにある石油利権を獲りたいが為に、縄張りを奪うためにイチャモン、難ぐせをつけて「果たし状」を突きつけた。 兄弟分のイギリスの親分は兄弟の杯という仁義から参加した。 他の組連中(同盟国)もヤクザの仁義・義理から加わった。 小泉組もそのひとつ。唯一、救いは欧州ヤクザ同盟のドイツ・フランス・ロシアの「おじき」衆の反対だった。アメリカはこのパウエル発言からどういう対処をするのか、この発言によって今秋行なわれるアメリカ大統領選挙でブッシュは自分から候補者として取り下げるべきだ。 そうすれば彼の名前は傷深いものにはならないかもしれない。国際社会から裁かれても文句の言えない立場になり、そのアメリカを支えてきた小泉組親分にも、それを問いたい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 「マリア・カラス オペラアリア集」1977年の今日ソプラノ歌手として不世出といわれているマリア・カラスがパリで亡くなった日です。 カリスマ的な魔力ともいうべく歌唱力は、今尚燦然と輝いている存在です。彼女が歌えばまるで音符が息づいているのかのように、他のソプラノ歌手には望めないほどの劇的な表現力で聴く者を圧倒する歌手でした。彼女の声は決して美声とは言えない(同時代に人気を二分したレナータ・テバルデイの美声とは程遠い)、耳障りと思えるときもあるのですが、実に見事に声を操って迫真ともいえる表現、豊かな感情の描写は聴く人を魅了します。彼女の命日にちなんで「ザ・ベスト・オブ・マリア・カラス」というオペラアリアのCDを選びました。「カルメン」「トスカ」「蝶々夫人」「椿姫」「リゴレット」「ボエーム」などの全曲盤からの有名なアリアを抜粋した一枚です。(東芝EMIレーベル TOCE-7998 1954年ー1964年録音)全曲盤のお薦めCD プッチーニ「トスカ」ジュゼッペ・デイ・ステファーノ(テノール)、ティト・ゴッビ(バリトン)、 ヴィクトル・ディ・サーパタ指揮 ミラノ・スカラ座管弦楽楽団(NAXOS レーベル 8.110256-7 1953年録音 既発売の東芝EMIと同じ音源で2枚組\2,000です。 音も改善されています)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月16日
コメント(10)
-
開設して30日 (加筆・修正しました) / ベートーベン 交響曲第6番「田園」
このページを開設してもう30日目となりました。 「スカイミュー」のミューさんからメールで教えていただいて、立ち上げました時はコンセプトも定まらずにいて、ただ毎日のページでクラシック音楽を一曲、その日の何かにちなんで紹介して、あとは自分の撮った花の写真をアップして四季折々の花を楽しんでいただければいいと、単純な思いから出発したのですが、たくさんの方々にご訪問いただき、また同じ趣味をお持ちの方々とお知り合いになり、これまでの邂逅の機会とは異なる、素晴らしい出会いにめぐり会えました。毎日アップしております話題も、今までは心の深層に埋もれていたものや、そんなに深く掘り下げずに素通りしていたことなどにも、知らず知らずのうちに光をあてるようになっている自分に気付きました。 そして思ったこと、感じたことをアップすることにより、みなさんとの出会い、思いの交換などをこのページを通じてできる喜びに浸っています。これからも音楽の紹介や花の紹介などを続けてまいります。 そしてその時の「時の話題」「趣味」「世相」などについて、独断と偏見のコメントを書いてまいります。これまでにご訪問くださった方々に心よりお礼申し上げます。 またリンクを貼っていただいてます、『会長さん』「れもん」さん、「ももんが」さん、「いちき」さん、「ルルさん」「ケイおばさん」、「モルデント」さん、「オケイさん」、「クラシカルさん」それに大先輩のミューさん、そしてご訪問いただきました「ゲスト」の皆さん、画像の転載をご快諾くださった東京のとん平さん、書き込みをいただいておりますyuujiさん、北海道の「もこ」さん、その他書き込みをいただきました方々に、この場をお借りして改めてお礼を申し上げますと共に、今後も引き続きお付き合いいただけるようよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ベートーベン 交響曲第6番「田園」1867年の今日(9月15日)は大指揮者ブルーノ・ワルター(1867-1962)が生まれた日です。 有名なカラヤンの一世代前の人ですが、モーツアルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームス、マーラー演奏にはSP時代から高く評価されて、LPモノラル、ステレオ録音の時代を経験して数多くの名演をデイスクに残してくれています。またグスタフ・マーラーの直弟子としても有名で、彼の遺したマーラー作品は現代でも名演として若い世代にも愛聴されています。今日はそれらの数々の名演の中からベートーベンの「田園」交響曲を選びました。 曲自体が美しい旋律に溢れる名曲ですが、これを数多くの指揮者が演奏・録音しています。 それらの中でも、私はこのワルターの演奏が大好きです。 歌心に溢れ、この人の演奏の特徴となっています温かさに満ちた潤いがいっぱいの名演です。ベートーベンはこの曲に対して「絵画的でなく、感情の表現」と記しているそうですが、このワルターの演奏はそれを見事に表現している感動的な音楽です。 「田園」を聴くのには一度は聴いてほしい名演・録音です。 古いステレオ録音ですが、最新のデジタル・リマスタリングによって、鮮明な音が蘇っています。とものお薦めCD ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 (カップリングは「運命」交響曲)(ソニー・ミュージックエンターテイメント SRCR2696 1958年1月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月15日
コメント(14)
-
ある妻の甘え
知人の33歳の専業主婦から聞いた話。結婚して10年、3人の子供を授かり子育ても問題がなく、夫はサラリーマンで家事や家の用事も協力的にこなしてくれている。 たまに休日出勤することはあるがほぼ理想的な夫らしい。 この話は彼女の友人の話だとことわって切り出した。彼女の目下の悩みは、夫が2日に一度夜の「夫婦の行為」を強要することなんだそうだ。 家事で疲れている奥さんにとって、セックスはすごく嫌で、面倒くさい行為らしい。 外に好きな男性がいるわけでもなく、ただただ面倒なだけらしい。夫が求めることは、彼には「当たり前」というか「権利」のような言い方をするので、口論になるらしい。 二人は大恋愛の末に結婚して、3人の子宝に恵まれた。しかし、彼女は今では夫には「愛情」を感じなくなっているらしい。 それは強要される前から感じていたことらしい。同居人としての夫らしい。かと言って彼女は離婚して自立するだけの経済力がないから、3人の子供を抱えて離婚はしたくない。 彼女の考え方は間違っているだろうかという相談だった。夫は妻に2日に一度求めるくらいだから、愛しているのだろう。 妻には愛情が色褪せて、今は感じられない。 だから性への興味もない。 面倒だ。 離婚すれば生きて行くのが大変だ。私はご主人が可哀想だと思った。 色々な面倒な職場、仕事のストレスを抱えて、毎日仕事に精をだして家族を養っている。 それは家族への愛情だろうと思う。離婚なんてことは論外にして、二人の共通の趣味、例えば花作り、園芸とか、手軽に出来るスポーツとか、何か二人で興味を持てることに一生懸命になってみれば、と言った。性については夫の理解を得る為に説得する、そして自分でもう一度夫を失った時のメンタルな面を想像してみる。 それでも愛情を感じないなら離婚ということを考えて、そのときの為に何をするべきか探し求める気持ちがなければ、何をやってもだめでしょう。夫に性の処理をする相手ができても、文句を言わない覚悟があるのかどうか?正面から向き合って話合うことがまづ大事だと言ってみたが、考え方の甘さに少々気分を悪くしたのは事実です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 休みます 私の音楽メモには記載がありません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月14日
コメント(6)
-
だんじり祭り / バッハ 「トッカータとフーガ ニ短調」
明日(14日)から2日間大阪泉州岸和田でだんじり祭りが行なわれる。 岸和田市20町・20台のだんじりが岸和田市内の目抜き通りを駆け巡る勇壮な祭りで、全国でも唯一だんじり祭りのメッカとして有名です。約300年前に岸和田城主が五穀豊穣を祈願して始まったとされている、由緒ある古い歴史のある祭りで、学校は休み、会社員、公務員もこの行事に携わる人たちは職場を休んで参加します。 この祭りに参加するために休みを貰う申請を出して、却下された人が退職してまで参加するほどの熱の入れようで、この2日間の為だけに青春している人たちが数え切れないほどいます。20町・20台のだんじりが宮入、やりまわし(全速で走り、曲がり角を曲がっていく離れ業)を集まった観衆(5万人)前で披露するのがクライマックスです。このだんじり祭りが始まると、泉州の他の市町村も10月9日・10日のだんじり祭りに向けて準備が始まり、道路には提灯が張り並べられて盛り上がってきます。 私の住んでいる町ももう提灯が電線に吊られて、祭りムードが盛り上がっており、夕方になるとだんじり小屋が開けられて、お囃子・太鼓の練習が始まっています。泉州全体が「だんじり」で燃える秋がやってきました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 J.S.バッハ 「トッカータとフーガ ニ短調」1977年の今日(9月13日)偉大な指揮者レポルド・ストコフスキー(1882-1977)が95歳の生涯を閉じました。 94歳まで現役だった指揮者で日本の指揮者故朝比奈 隆はこのストコフスキーの世界記録まで指揮台に立つことを念じていましたが、93歳で亡くなり未だにストコフスキーのこの記録は残されています。私がストコフスキーの名前を知ったのは、中学生の頃に観ました映画「ファンタジア」でした。 ウオルト・デイズニーのアニメに合わせてクラシック音楽の数々が演奏されていました。 交響詩「魔法使いの弟子」(デユカス)ベートーベンの「田園」交響曲、バレエ音楽「春の祭典」(ストラビンスキー)などで、その演奏がこのストコフスキー指揮のフィラデルフィア管弦楽団でした。この映画の冒頭に演奏されるのが大バッハの「トッカータとフーガ 二短調」でした。 オリジナルはオルガンで演奏される曲でうが、これをストコフスキーは管弦楽用に編曲してオーケストラの様々な楽器で演奏されて、分厚い、重厚なハーモニーを作りだして、美しい原曲の旋律を見事に華麗に変身させています。その後、彼は色々なオーケストラを指揮してこの曲をLPに録音を残しています。 今日はそれらの録音から弦楽器の美しさを誇るチェコフィルハーモニーを指揮した演奏を聴きます。 この録音は「バッハ・トランスクリプション」というタイトルで大バッハのオルガン曲やコラールなどを自ら編曲して演奏しています。とものお薦めCD 「バッハ・トランスクリプション」 レオポルド・ストコフスキー指揮 チェコフィルハーモニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月13日
コメント(8)
-
神社の寄進集め / マーラー 交響曲第8番「千人の交響曲」
今朝9時半から午後4時まで神社への寄進集めに村を廻り、へとへとです。 2500世帯を4つの班に分けて廻るのですが600軒担当するという計算になります。 今週いっぱいかかるでしょう。高齢のご夫婦だけの住まい、若い新婚カップルの家など種々雑多ですが、各世帯を廻って直接話ができることがいいことですね。普段は疎遠になっている世帯とコミュニケーションを図れることが一番嬉しいです。 全戸が寄進してくれるとは限りませんが、話ができることが素晴らしいことだと思いました。中には神社への希望、要望、苦情などをコメントしてくれる方もいて、こういうときでないとできないので今日はいい経験でした。明日も頑張るぞ!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ きょうのクラシック音楽 マーラー 交響曲第8番「千人の交響曲」この曲は1910年の今日マーラーの指揮でドイツ・ミュンヘンで初演されました。マーラーの音楽の集大成と呼べる曲で、大編成のオーケストラと合唱、独唱による壮大な曲で、初演時には1030人に及ぶ編成だったそうです。第一部と第二部に分かれており、一部はラテン語による賛歌、第二部はゲーテの「ファウスト」第二部を使って、魂の救済と天国での平安を壮大に歌い上げています。 80分近く要する大作です。マーラーはこの曲を「大宇宙が鳴り響く」と言ったそうです。 クラシック音楽入門者にはきつい曲かもしれませんが一度は聴いてもらいたい名曲です。とものお薦めCD エリアフ・インバル指揮 フランクフルト放送交響楽団部屋を揺るがすような優秀録音で、インバルが緻密に積み上げていく演奏は時間の経つのも忘れるほどでした。 現在ではDENONレーベルからクレスト1000シリーズで1,000円で発売されています。(デンオン レーベル COCOー70401 1986年10月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月12日
コメント(6)
-
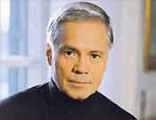
川柳のおもしろさ (掲示板に書き込みをしてあります) / シューマン 歌曲集「ミルテの花」
最近どの新聞、どの週刊誌にも川柳というコラムがあり、男女を問わず投稿の数が増えており選者は優秀作品の選考に追われているらしい。川柳のおもしろさは、まず作者の時代に起こっていることを即座に、時機よく歌われることだろう。 発表するタイミングを失ってはならない。 勿論、作者の家庭、学校、職場などを皮肉ったものは別だが、その時の政治、経済、社会をテーマにした歌は、タイミングが命になる。また使われる言葉が平明で簡略なので、和歌や俳句などに較べて誰もが理解できる。江戸時代には狂歌というのがあって、世相を詠んだおもしろい歌がたくさん残っている。 歌は江戸の目抜き通りに張られたりして、それが当時の政治などを皮肉っておればやんやの喝采を浴びたらしい。 封建制度のもと抑圧された庶民の憂さ晴らしであったのだろう。それが現代にも脈々と受け継がれているのが川柳だ。江戸幕末から明治へと激動の時代変化を遂げたときに謳われた名川柳がある。 明治になって生活様式が変わり、帯刀がなくなり、チョンマゲもなくなり現代のような頭髪スタイルに変わっていった。 その変わった頭髪を「散切り頭」と呼んでいた。ざんぎり頭を叩いてみれば文明開化の音がするこれだけの言葉で当時の世相が目に浮かぶような表現力、言葉の使い方だ。昨年の川柳コンテストの第1位は、課長いる かえった答えが いりませんこれは「課長いる?」返った答えが「いりません」夫婦のことを詠んだおもしろいのもある。(1) 粗大ゴミ 朝出しても 夜帰る(2) 妻の背にテレビのリモコン押してみる(1)は夫のこと、(2)は夫がリモコンの電源スイッチを押して消えてくれということだろう。本屋で川柳選集でも買って珈琲ブレイクにでも読んでみようかなと思っている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 シューマン作曲 歌曲集「ミルテの花」ドイツの作曲家ロベルト・シューマン(1810-1856)と妻クララ・シューマンは、クララの父ヴィークの猛反対を押し切って1840年9月12日に結婚式を挙げて夫婦となった。 その結婚式前夜にシューマンがクララに贈ったのが26曲から成る歌曲集「ミルテの花」で、今日9月11日とされています。全曲が「愛」の歌で、バイロン、ゲーテ、ハイネ、リュッケルトなどの詩に旋律をつけています。この歌曲集の中でも、特に有名なのが第1曲「献呈」と第3曲「くるみの木」です。 タイトルの「ミルテの花」は欧州で花嫁の冠に使われる白い香り高い花で、純潔を表しているそうです。今日はその日にちなんでこの歌曲集を聴いてみます。とものお薦めCD 「シューマン歌曲集」 デイートリッヒ・フィッシャ=デイスカウ(Br) クリストフ・エッシェンバッハ(ピアノ)美声に加えて彫の深い表現力でオペラ、歌曲に活躍した戦後ドイツの大歌手。 ここでも「愛」を嬉々として、また切々と歌い上げている。 ドイツリートでは、彼の他にヘルマン・プライというバリトンがいるが、この二人のどちらかのCDが素晴らしい歌曲の世界へと導いてくれます。(独グラモフォン 474466 1974年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月11日
コメント(6)
-
公共のマナー / テレマン 「リコーダーとフルートのための協奏曲」
今日の話題は、昨夜いただきましたある方からのメールに書かれていましたことがきっかけで、書くことになりました。先日の午後のまだ早い時間にJR電車に乗りました。どの車両も空いている状態で、私が乗りました車両には男子高校生ばかりで12-3人のみが乗っていました。7人掛け横に並んで座る長いすの座席です。 そこへ通路を挟んで向かい合って座席に2-3人ずつ座り、それぞれ座っている生徒の前に(通路に)大きな野球道具を入れたバッグを置いてあり、体面で置いていましたから通るにも歩ける隙間がほとんどない状態で、しかも向かい合っている生徒たちが対面している者へ話しかけるのに、大きなわめくような声で話していました。次の駅で乗車してきた乗客がいても、彼らの座っている状態、荷物の置く場所の移動もしないので、他の乗客は車両を移ろうとして歩くのに走る電車に、その通路の荷物ですから非常に歩きにくいのです。私は一人の生徒に「付き添いの先生は誰か?」と問うと、隣の車両の隅の座席に座っている30代とみられる男性を教えてくれました。その男性のところに行くと、怒りで気持ちが昂ぶっていて、怒鳴りつけるような口調で言った。 「君が隣の車両の生徒たちの付き添いなら、あの子らの態度を改めさせろ!」。その先生が訊き返してきた。「あの子たちが何かしましたか?」私はこれが今の学校教育の一端なのかと、暗鬱な気分になりこの先生に言わずに、直接生徒たちに言えばよかったと思ったものです。結果は先生が生徒たちに言って、整然とした座り方、荷物の置き方になったのですが、この先生と生徒たちにどんな違いがあるのかと思うと電車が下車駅に着いて、友人に会うまで嫌な気分の30分を過ごしたものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 テレマン作曲 「リコーダーとフルートの為の協奏曲 ホ短調」今日は古楽器演奏に一つの光をあてたような、そのジャンルでは有名な指揮者・チェンバロ奏者のクルストファー・ホグウッド(1941~)が生まれた日です。 それにちなんで彼の残している録音から「テレマン 二重、三重協奏曲集」(アルヒーブ原盤 ポリグラム発売 1981年録音 POCL-5221)というCDに収められている、有名なこの曲を聴きことにします。テレマン(1681ー1767)はバロック時代後期の作曲家で、非常に多くの曲を作曲していますが、現在ではそれらの中の一部しか残されていません。 一番有名なのが「ターフェルムジーク(食卓の音楽)」ですが、ここに収められている協奏曲もロココ風の趣きがあって典雅で、愉悦感に満ちた曲です。バロック時代の音楽は、国ごとに都市ごとに異なっていて、同じ時代でも多様性のある音楽でしたが、その多彩なスタイルを形式的な枠組で美しくまとめ上げたのがJ.S.バッハ(1685-1750)ですが、テレマンは自分の手法を駆使して作曲するスタイルを通しています。この「リコーダーとフルートの為の協奏曲」は縦笛(リコーダー)と横笛(フルート)の音色の違う2種のフルートが使われており、音色の対比と絡みの面白さを楽しめる、愉悦感溢れる楽しい音楽です。 私はこういう曲をよく朝の目覚めに聴くのですが、爽やかさ、愉しさがいい朝を迎えさせてくれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月10日
コメント(9)
-
オセチャの9月 (その2) / モーツアルト 「レクイエム」
まるで地獄絵図のようだ。 助かった子供たち、教師、父兄たちの談話が報じられるたびに、詳しい占拠された学校の中でテロリストたちが何をやっていたのかが、人倫に背く冷酷非道さが明らかになっていく。 死者・行方不明者が500人を超す惨状が明らかにされていく。今回のテロリストたちの目的は、学童たちと教師や父母を殺害することにあったと報じられている。 幼い子供たちや女性を殺戮する非道さは、この現代にヨーロッパの暗黒の中世時代が蘇ったかのような錯覚を覚えさせる。 昔、中世の時代に公然と行なわれていた「黒ミサ」の儀式だ。 テロリスト達が子供を壁際に立たせて弾除けにしていた、水も食料も与えずにいたというのだ。 トイレさえ行かせなかった。 喉の渇きにガマンできすに尿を飲んだ子供がTV画面で話していた。逃亡を試みた子供は背中から銃弾を浴びせられて殺された。ハッサン・ルバエフ 13歳の少年。この子は立ち上がって真正面からテロリストたちに向かって叫んだ。 「あなた方の要求には誰も応じない。 僕たちを殺しても何の役にも立たない!」テロリストは訊いた。「お前はそう確信しているのか?」ルバエフは答えた。「はい」と。その直後に銃弾がルバエフに浴びせられて、突然に幸福な、短いルバエフ少年の人生が閉じられてしまった。「正義」を守るために、熱い血のたぎりを抑えられなくて、勇気ある行動、言葉をテロリストたちに発した少年の命はあっけなく奪われてしまった。 日常生活でも弱者を見ると助ける、虐められている子供を見れば相手が年上でも、その理不尽さにガマンできずに闘ってくれたと助け出された子供が語っていた。 それゆえに正義を踏みにじり、弱者を虐待する理不尽なテロに立ち向かったのであろう。 勇気ある、堂々とした訴えが命と引き換えになってしまった。 散ってしまった人生があまりに哀れだ。このニュースをTVで知り、新聞で読んで、私の目からハラハラと涙が流れ落ち、嗚咽まで洩らしていた。さぞ無念であったろう、ルバエフ! そう思うとしばらくの間、涙が止まらなかった。神さまはこの少年に対して、何というむごい舞台を準備していたのかと思う。犠牲者の埋葬日に村の老女は言った。「この墓地はもう何十年もこの広さで十分だった。 だのにたった数日で墓地が倍以上の広さになってしまった。 私たちはこれからどう生きていけばいいのさ?」生き残った子どもたちが、ルバエフ少年の勇気を受け継いで、正義に、平和に反することに対して敢然と立ち向かい、世界の平和の安定を導く人生を送ってもらいたいと思うし、この地獄絵を経験した子供たちのショックは計り知れないものがあるが、ルバエフ少年の魂を引き継いでいってもらいたいと願わずにはおれない。「オセチャの9月」を決して忘れてはならない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・朝の詩 生きる 宇都宮市 柴田 トヨ(93)九十を越えた今一日一日がとてもいとおしい頬をなでる風友からの電話訪れてくれる人たちそれぞれが私に生きる力を与えてくれる 2004年9月9日 産経新聞朝刊より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 W.A.モーツアルト 「レクイエム(鎮魂歌)」ルバエフ少年、そしてまだなお行方不明になっている子供たちや大人たちの死を悼んで、今日はモーツアルトの「レクイエム」を聴いています。「レクイエム」は死者を悼むキリスト教会の儀式の音楽ですが、この曲はモーツアルトの絶筆となったもので、亡くなる直前まで彼は弟子のジェスマイヤーに細かい指示をしていたそうである。 まさに彼の死のために、彼の死を悼むために書かれた「レクイエム」と言えるでしょう。とものお薦めCD トン・コープマン指揮 オランダ・バロック管弦楽団 オランダ・バッハ協会合唱団合唱、独唱の歌唱が素晴らしく美しく、オーケストラも美しく鳴り響く、まさに天国への音楽を満喫できる演奏だと思います。(エラート原盤 ワーナー・ミュージック発売 1989年 オランダライブ録音 WPCS-11102)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月09日
コメント(2)
-

混迷のプロ野球を憂うーその2 スポーツ新聞にもの申す / ドボルザーク「新世界より」
関西のスポーツ新聞(デイリー、サンケイ、ニッカン、スポーツニッポン)のプロ野球記事は、あまりに偏りすぎた記事編成に私は嫌悪感さえ覚えることがある。私は阪神タイガースのファンで、このチームが好きです。 それでもあまりにタイガース記事に偏重されたどの新聞にも嫌悪感を感じる。タイガースがペナントレースがほぼ絶望、あるいは最下位決定でも、勝てば一面、2面、多いときは3面と3枚続けて色々な記事が書かれている。 いっぽうパリーグの扱いはどうだろう。 近鉄の大西がサヨナラホームランを打っても、記事は小さい。 西武、ハム、それに地元神戸のオリックスもそうだ。 記事になることはほとんどない。 ましてや一面トップなんて年にあるかないかという偏重ぶりだ。 パリーグに人気が出ないのは当然だと思う。 選手の名前を知らない、どんな野球をしているか知らないというファンが多い。売れることを想定していることはわかる。 しかし、球界人気を書く前に、各新聞の球団への記事の扱いを考えてもらいたい。野球人気を支える一端にスポーツ新聞がある。 球界人気を盛り上げるために、その日にあった試合でほんとに感動する試合記事を、セリーグ、パリーグの区別無く報じて幾野が新聞の義務だと思うが、どうだろう?スポーチ報知、中日新聞は論外だ。 彼らの親会社が球団経営をしているのだから、偏重になっても仕方あるまい。阪神ファンが敢えて提言します。 もっと公正にプロ野球記事を編集、掲載してもらいたい。そして野球人気を盛り上げる一助として存在してもらいたい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ドボルザーク 交響曲第9番「新世界より」1841年の今日はチェコの偉大な作曲家アントニン・ドボルザーク(1841-1904)が生まれた日です。 彼の名前の代名詞のようになっています「新世界交響曲」を聴こうと思います。ドボルザークは1892にアメリカに渡り、ナショナル音楽院の学長として2年半アメリカに滞在しました。 その間にもいくつかの後世に残る名曲を書いています。 そのうちの1曲がこの「新世界より」です。新世界というアメリカを描写した音楽ではなく、故郷チェコから遠く離れたアメリカから故郷に送ったまるで望郷の手紙のような曲で、チェコの素朴な民謡というか民族音楽のような旋律が全編に溢れています。特に有名なのは第2楽章「ラルゴ」で、後に「家路」というタイトルと歌詞をつけて歌われています。 小学校の下校時間になるとこのラルゴを校内放送で流している学校が少なくありません。とものお薦めCD ヴァツラフ・ノイマン指揮 チェコフィルハーモニー管弦楽団ノイマン(1920-1995)は戦後チェコ音楽界、いや世界中から愛された名指揮者で、日本にも手兵のチェコフィルと訪れて名演奏を何度も聴かせてくれました。 今日は彼の遺した録音から、亡くなる(95年9月2日)二ヶ月まえに録音された演奏でドボルザークと共に偲びたいと思います。 (キャニオンクラシックス PCCL-00305 1995年8月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月08日
コメント(9)
-
混迷のプロ野球を憂う
9月8日開催のプロ野球オーナー会議で近鉄・オリックスの合併を承認される見通しだ。 昨日の東京高裁は、地裁判決を支持して選手会の抗告を却下した。それに伴って1リーグ制への移行が現実味を帯びてくる。 プロ野球選手会はそれに対抗して9月の土日の試合を、ストライキ権行使によるボイコットを全会一致で決議したと昨夜のニュースで報道された。 選手会の決議は、もはやストライキ以外にないという結論を出した。 それに対して球団側は損害賠償をも視野に入れているという。これまでの経緯から浮き彫りにされているのは、球団側/オーナー側の一方的な合併と1リーグ制への移行の話の進め方だ。選手会が求めているー性急な進め方に対して、選手会と話し合いに応じて欲しいーことに対して、選手会との話し合いの場を用意しないことだ。経営者側は赤字経営を理由に合併を進め、その波紋が1リーグ制への移行という問題が浮上、しかもそれを来季から行なおうとする性急な進め方だ。選手会は言う。 「せめて1年間は、この合併を凍結してどうするべきかの問題点に議論を尽くして欲しい」 やみくもに反対しているわけではない。 あまりに唐突に出てきて、性急に野球界の機構を変えようとする(2リーグから1リーグへの移行)ことに反対して、もっと話し合いの場を設けることを要求してきた。 変更への青写真、具体案も迷走している経営者の足並みの揃わないことに危惧を抱いている。当然のことだと思う。 今回のこの問題は全国から反対の署名が70万人に達したという。 球団経営はファンあってのもので、成り立つものだが、ファン不在のような話の進め方である。 商売の相手はファンであることを忘れているのではないかと思う。 ファンの70%が性急な合併と1リーグへの移行への反対(TV朝日調べ)している。球団経営者はこれまでどんな努力をしてきたのか? ファンが満足するサービスを昂じてきたのか? 渡邊前ジャイアンツオーナー率いるジャイアンツ人気に乗っかることばかり考えてきたのではないか? TV放映権料の莫大な収入を逃したくないという考えが強すぎたのではないかと、うがった見方もしてみたくなる。昨日近鉄球団の談話「近い将来球団経営から撤退することも考えている」プロ野球は今やもう、一つの文化になっている。 経営者側の好むと好まざるに関らず、社会的責任を背負い込んでいるのだ。 経営に興味がなくなれば買いたい会社と話し合いをすることもしない。 ファン軽視と言われても仕方がないだろう。古田選手会長は言う。「ファンの気持ちに配慮して(無期限ではなく)こうした形になった。 我々にできることは、最後にはこれ(土日のストライキ)しかなかった。 ファンから観戦してもらう楽しみを奪う時期を作ってしまうことは心苦しいが・・・・」不思議な存在なのはコミッショナーだ。 これだけ球界を揺るがす激震とも言うべき問題が起こってもだんまりを続けていることだ。 何のためのコミッショナーか? ここに至るまでに手を打てなかったのか? 球団経営者側と選手会の主張がどこまでも平行線をたどるなら、根来コミッショナーが仲裁のための出馬が必要ではないか? 指導力の弱さを指摘されている人でも、今回はもうこれ以上沈黙するわけにはいかないだろう。 混迷を続ける球界を整理するために、両者の妥協点を見出すべき指導力を発揮するべき時だと思う。 それがコミッショナーの義務と責任ではないか? そして妥協のための「厳命」をくだせる権限があるのはコミッショナーだけなんだから。 過去にも「黒い霧事件」「江川事件」を収拾してきたのだから、今回も早急の出馬を望んでやまない。今こそ、コミッショナーの決断、裁断が望まれる時だと思う。優勝争いの渦中にあるダイエー選手会長の松中選手は言う。「今後のプロ野球や将来の子供たちの夢を考えると、今が大事です。 優勝争いも大事でが、これからの球界のことの方はもっと大事です」オーナー、球団経営者のみなさん、これが球界を憂い、良くしようとする「たかが選手」の言葉、叫びなんですぞ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽は休みます。 私の音楽メモにはこの日には記載がなく、音楽行事がなかったのでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月07日
コメント(3)
-
昨夜の地震 / リムスキー・コルサコフ 「シェラザード」
2度も地震があって、2度目は強く、長く揺れていました。 震度3と震度4。 2度目はM7.3とか。 相当大きい地震だったのですね。 こちら関西の人は阪神大震災を思い起していると思います。横揺れで長かったので治まったあとも身体が揺れているような感じがしばらく続いていました。1度目は夕食時、2度目は2階で音楽を聴いていたのですが、まず最初にステレオ装置を停めてゆらゆら揺れる階段を降りて、不安がる母を安心させてから玄関の施錠を解いて扉を開けておき、台所に行ってガス栓が閉めてあるか確認をして玄関先で座っている母の傍で私も座っていました。 それでもこの時はまだ揺れていましたから、相当長く揺れていたんですね。 階段を降りる時は、家が軋しんでいる音がしていました。 横揺れ特有の揺れ方とわかっていても、気味の悪い軋み音でした。浅間の突然の噴火、昨夜の東海沖の地震、何かがやって来る前兆でなければいいのですが。母は午前4時までまんじりともできなかったそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 リムスキー・コルサコフ 交響組曲「シェラザード」この曲はアラビアの「千夜一夜物語」を題材としており、絶世の美女「シェラザード」王妃が毎夜シャハリアール王に、冒険談、好色談、怪奇談などを寝物語として一編ずつ話して聞かせるという説話文学の世界を描いています。 「海とシンドバッドの船」「カランダール王子の物語」「若い王子と王女」「バクダッドの祭りー海ー青銅の騎士の立つ岩での難破ー終曲」という4楽章形式の組曲です。シャリアール王の登場を表す荒々しい冒頭の音楽に続いて、「むかし、むかし・・・」と語り始めるシェラザードの旋律は独奏ヴァイオリンで、エキゾチックな東洋風の艶麗な旋律で始まります。 このシェラザードの主題が全ての楽章で表され、彼女の物語が始まることを表しています。 ヴェールを顔にかけ、シースルーの薄物をまとったシェラザードが目の前に表れるかのような魅惑的なメロデイーです。曲全体に東洋風のメロデイーが色濃く溢れており、色彩豊かに繰り広げられ、あなたをアラビアン・ナイトの世界に導いてくれます。 45分間をシェラザードと共に過ごされては。とものお薦めCD エフゲニー・スベトラーノフ指揮 ソヴィエト国立交響楽団(BBCレジェンド レーベル 1978年録音)今日はスベトラーノフが1929年に生まれた日なので、彼の誕生日にちなんでこの演奏を聴こうと思います。 全編強烈なロシア色に染め上げ、まさに万華鏡を見るような、目のくらむような演奏です。 人によっては好き嫌いが分かれると思いますが、誕生日にちなんで紹介致しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月06日
コメント(6)
-
脳梗塞 / バッハ 「シャコンヌ」
一昨年、昨年と脳梗塞による言語障害になりました。 幸いにも身体の麻痺がなくて、呂律がまわらなくなったときのような障害だけでしたので、どちらもリハビリで治りました。 その時に感じたのはいかに医師を信ずるかということでした。 自分の病気を治す指針を作ってくれるのは医者。 その指針通りにやれば良い。 言葉を今までのように話していた自分がどんなに幸せだったかを思い知り、早くあの時に戻りたい、戻れるのかと不安と期待で医者の指示に従いました。「君は治る! それを片時も疑ってはならない。 私の言う通りにやれば治る!」この言葉が頼りでした。 それと愛する人に支えられる、信頼というものにすがって闘った数ヶ月でした。おかげさまで今では何不自由なく話せるようになっています。 職を離れることになりましたが、何とか生計を立てていけるようにもなりました。あの時の医者の言葉と愛する人の言葉「今度こんなことになれば家に連れて行って世話をするから」という言葉でした。今は感謝、感謝の気持ちです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 J.S バッハ 「シャコンヌ」1892年の今日、不世出のヴァイオリニスト、ヨゼフ・シゲテイ(1892年ー1973)が生まれた日です。 シゲテイのヴァイオリンは決して美音ではりませんが、また同じ時代に活躍したハイフェッツの技巧に較べて劣りますが、常に張りつめたような厳しさを伝える演奏家でした。 深い精神性とも言うのでしょうか、彼の弾くこのバッハの「シャコンヌ」(無伴奏ヴァイオリンのためのパルテイータ第2番の第5曲)はぴ~んと張りつめた1本のタイトロープのような趣のする演奏です。シャコンヌはコンサートや録音などで独立して弾かれる15分くらいの曲で、主題と30の変奏からなっています。変化に富む変奏曲で、劇的な起伏と高揚が深い精神性を感じます。今日はその「シャコンヌ」をシゲテイの演奏で聴いてみようと思います。とものお薦めCD 「バッハ 無伴奏ヴァイオリンソナタとパルテイータ全曲」(ヴァンガード原盤 キングレコード発売 KICC8991/2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月05日
コメント(13)
-
「オセチャの9月」 / ヴェルディ 「レクイエム」
「銀(しろがね)も金(くがね)も玉も何せむに まされる宝 子にしかめやも」 山上憶良ロシア・オセチャでのテロ武装集団による学校占拠の解決は最悪の結果となってしまった。 1500人ほどの人たちが人質となり、そのうちの7割が子供たちだと報道されていた。 学校の体育館のような狭い空間に3日間人質とされて食料、水の補給も充分になされずに監禁状態に置かれた挙句に、爆弾の爆発、銃撃戦で今日の朝刊によれば100人を超す死者が出ていて、まだその数が正確には不詳でこれからも増えていくだろうと報じられている。何故子供たちが? これから世界をよりよい住みやすい世の中に導いていってくれるであろう、子供たちがどうしてこうしたテロ、政治戦争の犠牲になるのか?終戦直前の「対馬丸」が爆撃され海に消えていった疎開学童たち、朝鮮戦争で同じ民族が殺しあった朝鮮半島、化学兵器の犠牲になったベトナム戦争、民族浄化という民族間同士のウガンダの殺戮、イスラエル/パキスタンの対立によるテロ行為、イラク戦争等、数え上げればキリがないくらいに世界の子供たちが大人によって殺されてきた。万葉歌人の山上憶良が上に書いた和歌を1000年以上も前に遺している。 この世の中でどんな宝に較べても、子供にまさる宝はないと。オセチャで殺された子供たちの親、家族の悲痛な叫びが聞こえてくる。 理不尽な殺し。 神さまによってこの世に生を受けた子供たちは、こんな形で生の終焉を迎えていいものか。 狂った殺人集団を押さえ込む手段には、「目には目を」だけが残された方法なのか?オセチャで生き残った子供たちが、自分たちの目に焼付けられた阿鼻叫喚の凄まじい光景を、成長したあとに平和への道しるべにしてもらいたいと願わずにはおれない。私個人がこうした歪んだ世相にどんなことをできるのかと自問している。 殺された子供たちは無念であろう。 親、家族も無念であろう。 犠牲になった子供たちへの供養のためにも、もうこれ以上の罪の無い人たちへの殺戮をやめて欲しい。そして私たちは「オセチャの9月」を決して忘れてはいけない。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ヴェルデイ「レクイエム」オーストラリアの作曲家で最近とみに人気のあるアントン・ブルックナー(1824-1896)が今日9月4日に生まれていて、今日はその生誕に因んで彼の遺した9曲の交響曲のうちの1曲を聴こうかと思っていましたが、その機会はまたに譲って今日は「オセチャの悲劇」に対して追悼の意味で「レクイエム}(鎮魂歌)を聴くことにします。 色々な作曲家が書いていますが、もっとも有名な、旋律美に溢れたヴェルデイを選びました。この曲を聴いて亡くなった方、子供たちの霊を慰めてあげたいと思います。お薦めCDは休みます。 改めてこの曲にちなむ日に書きます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月04日
コメント(9)
-

酔芙蓉の一日
午前8時半 おはよう、ともさん、今日はお出かけでっか? ちょっとわしに酒を付きおてくれまへんか? え、仕事? ええがな、ちょっとだけや、な、ええやろ? あかんのか、ほな何時に帰るんや? 昼の12時ごろ? ほな、待ってるでえ~!午前10時 う~、うまいなあ~、やっぱり酒はうまいわ! あの奥さん、わしの顔見てわろてるわ。 なに? 顔が赤いてか? そら酒呑んだら、顔もちょっとぐらいあこなるわ。 もうあっち行ってんかあ~、酒がまずなるわ、綺麗な若いべっぴんやったらええけど。 ともさん、はよ帰ってえなあ~。午後12時 ともさん、遅いなあ~、どないしてんるねん? 一人で呑んでも面白無いわ。 みんな、わしの顔を見てわろとるわ。 そないに顔が赤いか? せやけど、ちょっと酒もまわってきたなあ。 これが酔うちゅうやっちゃなあ? せやけど気持ちええわあ! うん? 何やしらん、重たいなあ。 こらあ~! 子蛙! わしの肩に載るな! 重たいわ! なに? 朝から見てたら白い顔が段々あこなってきて、こら面白いと思て見にきたあ~? 何? うちの親戚のカメレオンみたいに色が変わるさかいに、よ~お見に来たて? あほ! 早よ~、どかんかい、第一カメレオンはお前の親戚やて、ほんまか? 何? 酔っ払いとはそういう学術的なことは議論しません?何ぬかす、この子ガエルが! 何、ほなもうカエル? お前,洒落を言うて、大人をバカにするのか? 午後4時 うい~、酔うたあ~、せやけど独り酒はおいしないわ~。 ともさん、いつになったら帰るんや? もう酔いつぶれるでえ~、うい~。午後6時 うい~、わしは酔っ払ったあ~! うい~、あかん、もう眠たいわ、もう寝るでえ~、 おい、右上にいてる、息子! あとはお前に頼むでえ~。 まだ蕾やけど、開いたらともさんに「薄情者!」てゆうといてやあ! あ、それからな、酒呑んでも、子ガエルにバカにされたらあかんど~。 ええな~。 ほな、お父ちゃん、もうねるでえ~。 おやすみ。かくして酔芙蓉の一日は終わりました。酔芙蓉 アオイ科 フヨウ(ハイビスカス)属一日花で朝開花した時は白いが、夕方になるピンクもしくは赤みがかった色に変わり、花を閉じる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月03日
コメント(11)
-
こぬか雨 / ブラームス 交響曲第4番
昨夜から雨が時折瓦やベランダの屋根を叩いていました。もうすっかり秋かなと感じるほどに涼しい夜で、雨が止むと虫の音が涼しげに、清澄に響いていました。朝になっても「こぬか雨」は止まず、時折思い出したように落ちてきています。 家の外に出ると、まるで体にまとわりついてくるような、しとしと雨です。今日は家の前も静かで、雨が時折ベランダを叩くように降る音以外は聞こえてきません。 それもそのはず、2日前までは夏休みの子供たちの元気な声が終日行き交っていたのに、昨日から新学期を迎えて朝から登校。 お兄ちゃん、お姉ちゃんが学校に行ってしまったので、未就学児童はこの雨で家で遊んでいるのでしょう。 時折通る車の音が、いっそう静けさを惹きたてています。まるで秋が一足飛びでやって来たような静かな一日です。心になにも重いもの引きずってはいないのに、まるで心の中にまで雨が降って濡らしているような日です。こんな日は思い切り秋のたたずまいを味わってみようかな。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ブラームス 交響曲第4番この曲は9月2日に何の関係もない曲ですが、上述のように今日はこぬか雨のせいでしょうか、なんとなく秋の憂鬱さを感じる日ですので、それなら思い切りこの曲で秋を味わってみようと思います。 この曲は季節の秋を表現したのではなく、「心の秋」「人生の秋」を表現しているように私は感じます。ブラームス52歳の時に作曲されたこの曲は冒頭から彼の「ため息」が聞こえてくるような哀愁を帯びた、何かを訴えてくるような旋律で始まり、曲全体が「渋い」トーンで書かれており、第2楽章のチェロの主題はまるでブラームスの嘆きのような哀愁美に溢れた美しい音楽です。 シューマンの妻であるクララ・シューマンへの実らぬ愛を、彼はここで思い存分に嘆いて、死に近づいていく自らの「人生の秋」を謳っているのではないかと、この曲を聴くといつも同じことを感じます。今日はブラームスの「人生の秋」をじっくりと味わってみます。とものお薦めCDクルト・ザンテルリンク指揮 ベルリン交響楽団(カプリッチオ原盤 日本コロンビア発売 1990年 録音)重厚で、どっしりと落着いた構えで、旋律を遅めのテンポでじっくりと歌わせ、弦楽器の響きが古色ががった、いくぶんくすんだような響きで、その上にまるでほどよくブレンドされたような管楽器が柔らかくかぶさり、ブラームス特有のロマンテイックな美しさを味わえる演奏・録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月02日
コメント(14)
-
色盲 / パッヘルベルの「カノン」
私は赤緑の色盲(正確には色弱)です。 赤、緑、黄色の色の3原色の明度が変わると(淡くなると)色がわからなくなります。 私の目にはクレパスでも水彩絵具でも市販の12色の色は識別されていますが、それらの中から任意に2本、3本と取り出して混ぜ合わせると、もう色の名前がわかりません。赤系統とか黄色系統とか水色系統とかの識別しかできません。 一番困るのはピンク系統で、健常者から見てピンク色はグレーに見えるし、反対にグレーが正しいのにピンク色に見えます。私自身が赤鉛筆で極太に線を引き、その横に同じ鉛筆でうっすらと線を引くと、赤鉛筆を使っているのがわかっていても、薄っすらと引いた線は緑にしか見えないのです。小学生の頃、写生で近くの山を描きましたが、私だけが茶色を塗っていました。 しかし、目で見た山の色とクレパスは同じ色なのです。 これは60歳になる今も変わっていません。紅葉の時期に写真を撮りますが、いい紅葉だと見えて撮っても人は何でこんな写真を撮るのかと不思議に思うそうです。先日も妹が携帯電話のカメラで夕焼けを撮ってメールで送ってきましたが、私にはグレーの変な色の夕焼けにしか見えないのです。 他人に見せると「わあ~、きれい!」と喜んでいますが、何がきれいなのかわかりません。私が色盲だと言うと、必ず「これは何色?」と訊かれます。もう慣れていますから面倒だとも思わないのですが、色の名前がわからないから答えようがない時があります。極端な例ですが、相手が自分の顔を指して「私の顔は何色?」と訊くと、「リトマス試験紙を水溶液に浸すとどうなる?」と訊かれたガッツ石松が「濡れる」と答えたのと同じように「顔色」という答えになります。私が花の写真を撮るのは、ほとんどの花の色がわかる(健常者と同じように見える)からなんです。 とても美しい、しかも普通に、正しい色に見える人とあまり変わらない花が多いからです。これからも美しい花、表情のある花を撮っていきたいと思っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 パッヘルベルのカノンドイツの作曲家ヨハン・パッヘルベルは1653年の今日生まれました。 彼の作曲した曲でずば抜けて有名なのが「三声のカノンとジーグ ニ長調」で、通常「パッヘルベルのカノン」として知られているバロック音楽の超有名曲です。非常に親しみやすい旋律で、「どこかで聴いたことのある曲」の一つだろうと思います。 彼の生誕に因んで、今日はこの曲を聴くことにします。 (1653年の日本は江戸時代で3代将軍家光から家綱に代わった頃です)とものお薦めCD 「ヨーロッパのバロック音楽」パウムガルトナー指揮 ルツエルン祝祭弦楽合奏団(グラモフォン レーベル 1966年、1967年録音)その他今日の音楽メモ1) 1935年 小澤征爾(指揮者)誕生2) 1953年 ジャック・テイボー(ヴァイオリニスト)死亡3) 1957年 デニス・ブレイン(ウイーンフィルの不世出のホルン奏者)死亡4) 1878年 トリオ・セラフィン(イタリアオペラの名指揮者)誕生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年09月01日
コメント(8)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- The Beatles(ビートルズ) 『アン…
- (2025-11-20 11:02:10)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-







