2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2004年10月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
拘束された日本人殺害される! / リムスキー=コルサコフ 「スペイン奇想曲」
『拘束された日本人殺害される!』イラクの武装勢力に拉致されて拘束されていた香田さんが、バグダッド市内で遺体となって発見された。 日本大使館医務官によって香田さんと確認されたらしい。昨日のアメリカ軍による日本人らしい遺体発見の誤認情報からまだそんなに時間が経っていなかったので、昨日の午後から今朝にかけてはぬか喜びとなってしまった。武装勢力の残忍さに憤りを感じると共に、イラク国民も同じようにアメリカ軍とその同盟軍によって殺されている事実を考えると、こんな戦争状態を早く終わらせるようにどうにかできないのかと憤りを覚える。最近は外国の民間団体の女性も拉致されて拘束されている。すでに拉致された人たちのうち34人が殺されているとの報道だ。 トラック運転手だったり、民間企業の従業員だったり、とにかく民間人が殺されることが増えている。香田さんの死が無駄にならないように、こういう危険地帯に用事もないのに立ち入る人たちがないようにして欲しいのと、こういう危険地帯を一日も早く安全な平和地帯になるように国連その他の関係国が最優先の、最高の努力をして欲しいと願うばかりです。やられたらやり返す、というまるで「ヤクザ戦争」のような図式を早く解消して、テーブルについて何を平和のためにやるべきかを国のリーダーたちが考えて欲しいと切に願うばかりです。殺された香田さんのご両親の悲痛はいかばかりと推察いたします。 私の息子が20歳で亡くなっています。香田さんの息子さんを亡くされたお気持ちは痛いほどわかります。もう二度とこういう無謀な行動を取る日本人が現れないことを願い、殺されてしまった香田さんのご冥福をお祈り申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 リムスキー=コルサコフ作曲 「スペイン奇想曲」1887年10月31には、旧ロシアの作曲家リムスキー=コルサコフ(1844-1908)が書いた「スペイン奇想曲」がロシアのサンクト・ペテルブルグで初演されています。リムスキー=コルサコフと言えば、管弦楽曲の華麗で、極彩色のような、彩り豊かな音楽を書いた人で、このページでも彼の交響組曲「シェラザード」を紹介しています。この「スペイン奇想曲」もスペインを題材にして、きらめくような色彩豊かな音楽で風景や風物を紹介しています。曲は5つの部分から構成されていますが、全曲を切れ目なしに一つの楽章のように演奏されます。 約15分ほどの短い曲ですが強烈なスペイン情緒に溢れた音楽を楽しめます。<アルボラーダ(朝の歌)> 曲の開始からオーケストラの全合奏で強烈なスペイン風の音楽が奏されます。 これで聴く者をすでにスペインへ誘っています。 管楽器に発展した音楽が最後はテインパニーの音と共に静かに終ります。<変奏曲>主題と5つの変奏で出来ています。 ホルン四重奏で晴れやかな主題が明るく演奏されたあと、管楽器や弦楽器に受け継がれて5つの変奏がなされて最後はヴァイオリンが変奏を受け持って静かに終ります。<アルボラーダ>第1曲の繰り返しですが、ハープが加わることによっていっそう華やかな雰囲気になります。<情景とジプシーの歌>小太鼓が鳴り、ホルンとトランペットが情熱的な、明るい音楽を鳴らし、次に独奏楽器が技巧を示すかのように、ヴァイオリン、クラリネット、フルート、オーボエ、ハープの順にカデンツアを奏します。 最後に「ジプシーの歌」がオーケストラの全合奏で熱狂的な音楽となって奏されます。<ファンタンゴ>3拍子のスペインのテンポの速いダンスで、<アルボラーダ>の音楽が主となって演奏され、情熱のファンタンゴとなります。 この曲の最後を飾る熱狂的な音楽す。愛聴盤 レオポルド・ストコフスキー指揮 ニューフィルハーモニア管弦楽団この色彩豊かな曲を聴くのに、ストコフスキーの演奏が素晴らしい。 彼はこういうオーケストレーションの派手な曲を得意とし、音楽を楽しむ喜びを与えてくれる指揮者、音楽家でした。 時にはあまりの曲いじりのためにひんしゅくを買うことがありましたが、94歳まで指揮台に立って演奏した大指揮者で、「人生を楽しみ、自然を楽しみ、そして美味しいお酒を呑む」ことが「青年のように若さを保つ」ことだと豪語して、63歳で19歳の乙女と3度目の結婚をして2児をもうけた超怪物で、その道でも「達人」ぶりを発揮した音楽家でした。(LONDONレーベル キングインターナショナル発売 UCCD7034 1973年ロンドン録音 \1,000の廉価盤で1964年のロンドン交響楽団との演奏による「シェラザード」とのカップリングです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月31日
コメント(6)
-
賽銭泥棒が! / チャイコフスキー 弦楽セレナード
『賽銭泥棒が!』今日は午後から市の教育委員会が町の神社にやって来る日でした。 神社に保管されている古書類、古物類を観て市にある神社の歴史をまとめる資料にしたいというのが、今日の神社への訪問目的でした。それで私たち神社役員が立ち会うことになり、午後1時から神社神殿、書庫、倉庫などを開けて観てもらっている最中に一人の役員が素っ頓狂な声を張り上げました。「あれ~、賽銭が盗まれてる~!」社務所内通路に置いてあった賽銭箱(高さ1m強、幅1mほど)にあるはずのお金の入っている引き出しが鍵ごとなくなっていました。 すぐにこの引き出しの所在がわかりましたが(神殿横に捨てられていました)、お金は全部持って行かれており、引き出しを開けるとセンサーが作動してアラーム音がなる装置の、センサー自体も取り外されてありません。神社の周囲を見回すと神殿の真後ろの壁に張りめぐらせてある、有刺鉄線がカッターで切られていました。 そこから塀を乗り越えて、社務所に入ったようです。 しかし社務所に入ると、ここもセンサーが作動して警報が鳴る仕組みですが、何か特殊なことをして感知範囲外となるように細工したのでしょう。 空き巣狙いのプロの仕業だと思います。被害額は推定で3万円くらいです。 10月24日の境内の清掃時には鍵がかかっていたのを複数の役員が見ていますから、24日から今朝までの犯行と推測。すぐに警察署に連絡して、警官3名に来てもらい現場を観てもらい、被害届けを出しましたが犯人は捕まるかどうか。役員は教育委員会の人たちと警察への対応に分かれて、それぞれの人たちに協力をした午後でした。 それにしても神社の賽銭を盗むなんて、天罰が下りますよ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 「弦楽セレナード」1881年の10月30日は、チャイコフスキーの「弦楽セレナード」が旧ロシアのペテルスブルグで初演されたそうです。セレナードは本来は恋人の家に忍び寄り、彼女の窓の下で囁くように歌う「恋歌」でしたが、この曲は演奏会用として書かれた規模の大きな曲です。4楽章構成で弦楽五部(第1、第2ヴァイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス)で演奏され、この曲は第2楽章に「ワルツ」が入っているものの、全編にロシアの哀愁のような、チャイコフスキー独特の哀切で、美しく華麗な旋律美に溢れた弦楽合奏の名作です。 第3楽章などはエレジーとして暗く、哀愁に満ちた、チャイコフスキーの甘美な旋律を堪能できます。愛聴盤 ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ベルリンフルハーモニー管弦楽団カラヤン独特の美麗さと彼によって鍛え上げられたベルリンフィルの流麗な、極上のアンサンブルがいっそうこの曲を哀愁の世界に招いてくれる演奏です。 カップリングはドヴォルザークの「弦楽セレナード」。 これも素晴らしい旋律で音楽の楽しみを満喫できる曲です。(グラモフォン UCCG7033 1880年ベルリン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月30日
コメント(4)
-
今夜は満月! / モーツアルト 歌劇「ドン・ジョバンニ」
『今夜は満月!』昨日に比べますと28日は大阪では暖かい一日でした。 朝から柔らかい陽射しが戻ってきて、起きるとすぐに布団を天日干しにしました。 夜はお日様の匂いのする布団で寝られます。陽だまりは暖かく、風も微風。 その微風に吹かれて、家々や公園の小さなところに植わっている色取り取りのコスモスが日向ぼっこをしていました。 風に揺れながらお互いがご近所の噂話をするかのように囁いているのでしょう。 「今日はあったかくていいわね。 昨日の寒さとは大違いよ。 存分にお日さまの陽射しを浴びましょうね。 もうすぐ蜂さんが来てくれるかしら? ちょっとお化粧直しをしないとね」近所の鉢植えのピンポンという、まるでピンポン玉みたいな丸い小さな菊が背伸びをしていました。 「あ、あ~、今日はいいなあ。 お日さまの柔らかい陽射しがいっぱいだあ! ちょっと背伸びでもしようぜ。 昨日は寒くて、こちとらは縮こまってばかりいたからなあ。 どうでえ、この陽射し。 この空。 雲ひとつないや。 天高くってこのことだ。 英語ではDep Skyってやつだなあ。 今夜は満月だってよ。 この分だときれいなお月さまをおがめるってもんだ」菊の独り言のように、夕方になると大きなまん丸お月さまが空に顔を出してきました。 見事な満月。 一点の雲もない夜空を煌々と照らしています。夜の散歩には、普段のコースでなくて丘へ登り林を通って歩くと、木々の間に冴えた月の光が射しこんでいます。 白っぽく浮かび上がる林の情景が幻想世界のようでした。水害や地震の被災地の人々がこの満月を楽しめるのはいつのことでしょうか? これから寒さが増すことを思うと可哀想でなりません。 一日も早く復旧しますことを祈っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 モーツアルト 歌劇「ドン・ジョバンニ」1787年10月29日にはウイーンでモーツアルトの歌劇「ドン・ジョバンニ」が初演されました。 前作「フィガロの結婚」上演の大成功のあとをうけてのオペラでした。物語は、スペインの町が舞台で好色なドン・ジョバンニが数々の女性遍歴の果てに、自分が殺した騎士長によって地獄に落とされるという筋書きで、「フィガロの結婚」などに較べると全体的にドラマテイックに書かれています。モーツアルトのオペラブッファ(喜歌劇)という形式なんですが、この音楽は人間の業の深さを抉り出しているので、喜劇という思いがしないオペラです。 女性遍歴と殺人という奇行や、ドン・ジョバンニのふてぶてしい言葉など人間が持つ生々しい心のひだを描いているからでしょうか。裏切られてもまだドン・ジョバンニに心を寄せるドンナ・エルヴィラは心の襞を歌いつくすさまなどはその典型だと思います。これは「ドン・ファン」というタイトルでも有名な話で、音楽ではR. シュトラウスが交響詩「ドン・ファン」を書いています。愛聴盤 カール・ベーム指揮 ウイーンフィル(ザルツブルグ音楽祭 1977年公演のライブ録音)シェリル・ミルンズ(Br) アンナ・トモワ=シントウ(S) ペーター・シュライアー(T) エデイット・マチス(S) ワルター・ベリーなど最盛期の豪華歌手陣による舞台の録音で、USA輸入盤で¥3,700(3枚組)というお買い得盤です。(グラモフォン レーベル 469 743-2 1977年ザルツブルグ音楽祭ライブ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月29日
コメント(8)
-
また日本人拘束される(イラク) / チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」
『また日本人拘束される(イラク)』新潟地震のその後の報道の間に入ってきたニュース。 イラク武装勢力に拘束された日本人。 彼は何のためにヨルダンからイラクに入ったのか、明確な目的がわからないと報道されている。 ホテルやたまたまヨルダンで彼に会った日本人たちから「ただイラクを見にいくだけなら、やめた方がいい」と言われていたのに入国して拘束された。日本の自衛隊のイラクからの撤退を条件としての人質として拘束されている。 このイラク武装勢力の卑怯なやり方に憤りを覚えるが、この若者にも軽率のそしりは免れないだろう。 イラクの何を見に行ったのか、見たかったのか?今、京都府豊岡市で、新潟の多くの町で台風23号の水害と地震の被災で苦しんでいる人々が6桁の数にのぼっている日本国内。 一人でもボランテイアの手を借りたい人たちです。何故そういうところに目を向けて、援助の手を差し伸べたいと思わないのか? 何故この時期にイラクという危険な国を見たいと思うのか? 理解に苦しむ若者です。この若者の救出に日本政府は国民を守る義務から、また多額の税金を使って救出作業にあたるでしょう。 こういう税金を被災地にまわせばどんなに被災民が助かるか。昔、黒柳徹子さんが故マリア・テレサにユネスコの義援に参加したい意思を表明して、どうすれば出来るかと問うたことがあったそうです。その時のテレサの答えは「まづあなたの家の隣の人から、助ける手を差し伸べてあげなさい」と言われたそうだ。もうこういう暴挙に出る日本人が現れないことを願うばかりです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『♪今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー 交響曲第6番「悲愴」1893年10月28日は、旧ロシアの大作曲家ピョートル・I. チャイコフスキー(1840-1893)の最後の曲となりました交響曲第6番ロ短調作品74 「悲愴」が作曲者自身の指揮で、ペテルスブルグで初演された日です。3つのバレエ音楽、ピアノ協奏曲、ヴァイオリン協奏曲、それに室内楽ではピアノ三重奏曲や弦楽四重奏曲、歌曲、ピアノ作品、オペラなど発表していますチャイコフスキーは、その生涯で7つの交響曲を書きました。 第1番~第6番と番号なしの「マンフレッド交響曲」です。こうした作品群の特徴はロシアを歌い上げた民族色の強い旋律、感傷的で甘く切なく、哀愁あふれる音楽を数多く書き残していることです。その集大成とでも言えるのがこの「悲愴」です。現存する彼の手紙の中にこの曲への思い入れが語られており、生涯で最高の曲を書く意欲に燃えていたようです。この交響曲は、人生への絶望感、恐怖、悲しみや苦悩、といった暗い響きが全編を覆い尽くしている作品です。 それは人間の心の内に存在する悲しみや苦悩の感情が、高度に昇華された普遍性を伴って、極めて美しい表情で描き出された音楽で、チャイコフスキーが書き残した作品の中でも、雄大さとドラマテイックな容貌が際立った音楽です。彼の生きた時代は帝政ロシアの末期の時代で、人々は貧困にあえぎ、民衆の救いようのない怒りが渦巻き、重苦しい気分の中での生活を強いられていた時代でした。彼がこれほどに悲しい、絶望的な感情のあふれる音楽をダイナミックに、雄大に描いたのはこの時代背景があるのかなと私自身は思っています。「悲愴」という副題は初演後に自分の弟に相談して、チャイコフスキー自らが付けたもので、その後の楽譜の出版にはこの「悲愴」という副題が付けられていたそうです。彼はこの曲の5日後(一説には9日後)に不帰の人となり、この悲しくも美しいドラマテイックな「悲愴」交響曲が、チャイコフスキーの「白鳥の歌」となりました。彼の死因は色々と取り沙汰されていますが、同性愛者であった彼がかなり政府から圧力をかけられていた(ロシアキリスト正教ですから)ことに苦悩しての自殺説が、最近では有力視されていますが、依然として謎のままです。愛聴盤フェレンツ・フリッチャイ指揮 ベルリン放送交響楽団1963年に49歳という若さで不帰の人となったハンガリーの指揮者フリッチャイは、遅いテンポでどのフレーズも粘りのある、深く抉ったような演奏スタイルがどの楽章にも表現されており、絶望と苦悩にのた打ち回る人間の姿が克明に表現されており、「悲愴」にもっともふさわしい録音だと感じています。ステレオ録音最初期の盤ですが、デジタル処理により美しい音質となって蘇っています。(グラモフォン POCG1957 1959年9月ベルリン録音)初めてこの曲をお聴きになる方には、生涯でこの曲を7回録音したカラヤンが最後の録音として極上のアンサンブルの、ウイーンフィルと1984年に遺したこの盤をお薦めします。 これ以上ないと思われる美しい「悲愴」の姿が描かれています。(グラモフォン UCCG7021 1984年 ウイーン録音)またチャイコフスキーの後期3大交響曲(4番、5番、6番)を一括して廉価盤として(1,400円)求められる、クルト・ザンテルリング指揮ベルリン交響楽団の演奏もお薦めです。(DENON レーベル COCO70494)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月28日
コメント(6)
-
傘の先が目に! / ドビッシー 「夜想曲」
『傘の先が目に!』昨日大阪市内に出かけるときにJRの駅で起こったことです。昨日は大阪は雨でした。 誰もが傘を持っていました。 駅の階段の昇降にはこの傘が危険なことは、今までの出勤での経験でわかっていました。私は階段の昇り降りには必ず傘の先を自分の体の前にしています。 先を後にすると私の背後の人にその先があたることがあり、子供なら顔や目にあたってしまうことがあり得るからです。そのあり得ることが、最寄の駅の階段で起こりました。 私の前に30歳代くらいの母親と4~5歳くらいの男の子、母親の友人らしい女性が昇っていました。 その前に20歳代の女性。 傘の先が後でした。「あ、危ないな!」と思っていると、男の子が階段で跳んだりしながら昇っていて、とうとう前の女性の持つ傘の先が男の目のあたりにあたって、その子が目のあたりを押さえて泣き叫びました。 母親は何が起こったのかわからない風でした。 傘のご本人はちらっと後を見ただけで、そのまま昇って行ったので私は階段を登りきったところで、その若い女性に言いました。「君、あの子に謝りなさい。 その傘の不用意な持ち方で目に当たっているかも知れない。 様子を見なければ」と言うと、初めてことのいきさつが判ったようで、母親と子供のところに駆け寄って謝りながら話し合っていました。幸いにも目の中には入らなかったようですが、このグループは病院にでも行くのか、階段を降りて改札口の方に出ていきました。 階段を降りるときに、その若い女性が軽く私に頭を下げてくれました。やはり傘の持ち方は気をつけなければいけません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ドビッシー作曲 「夜想曲」1901年10月27日はクロード・ドビッシー(1862-1918)が作曲しました「夜想曲」が初演された日です。ドビッシーの音楽はフランス印象派たちの絵画と同じように「印象主義音楽」と呼ばれています。 この「夜想曲」では作曲者自身がこう語ったと言われています。「この『夜想曲』という曲名は、一般的に言われるものと違ってより広い、ある意味では装飾的な意味合いを持っている。 夜想曲という曲の形式が問題ではなくて、その言葉の中に含まれている独特の印象と光が重要なのです」この曲は「雲」「祭り」「シレーヌ(海の精)」という副題がつけられた3つの曲からできています。 ドビッシー自身が雲や祭りや夜から受けた印象を音楽で表現しており、物語性は何一つありません。 また情景描写でもありません。第1曲 「雲」 弱音器をつけた弦楽器と管楽の調べが淡い音楽を醸し出してパステル画のような雰囲気で、雲が薄闇に溶け込んでいくような情景を感じます。第2曲 「祭り」 賑やかな祭りの騒がしさを思い起こす音楽です。第3曲 「シレーヌ」 ソプラノとメゾソプラノの合唱が加わり、光と影の交錯のような音楽表現です。全曲で22-23分かかる曲です。愛聴盤 「アンセルメ~ドビッシー名演集」エルネスト・アンセルメ指揮 スイスロマンド管弦楽団アンセルメ(1883-1969)は、1964年にNHKの招きで初来日してN響定期演奏会で指揮、1968年には手兵のスイス・ロマンド管弦楽団と2度目の来日をして、フランス近代やロシア音楽の魅力をたっぷりと堪能させてくれました。 客席では聴くことができませんでしたが、当時NHK-FMや教育TVで放映されました。この演奏もパステル画を思わせるような淡い色調の雰囲気で包まれた、いかにもドビッシーと親交を深めていたアンセルメの「魔術師」としての音楽を楽しめる1枚です。カップリングも交響詩「海」「牧神の午後への前奏曲」などドビッシーの代表的な曲となっており、1000円盤というのも魅力です。 1957年という古い録音ですがリマスター技術によって最新録音と遜色のない音質です。 私が持っていますCDは3枚組の「アンセルメ~フランス音楽名演集」という99年に発売された限定盤で、今は廃盤となっています。 音源は同じですのでこの盤を紹介いたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月27日
コメント(14)
-
新潟中越地震 / エルガー チェロ協奏曲
今日は大阪市内に商用があって出ました。 その途中に些少の金額でしたが被災者支援の一助にと思い、朝日新聞社の義援金受付窓口に寄って来ました。 被災者の方々と10万人を超す避難者の方々の健康と心のケアが心配です。 それに今日も震度4の余震があったそうです。 地盤が緩んでいるだろうと推測されるところに無常の雨ですから、皆さんの心中察するに余りあります。 村の名産の錦鯉がほぼ全滅状態で死んでいるのがTV画面に写し出されていました。 全村民あげて避難された村に残って復興の手はずを整えようとしている村役場の方が、インタビューの最後には泣き伏していました。 さぞ口惜しい想いでしょう。一日も早く普段の生活に戻られることをお祈り致します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 エルガー作曲 「チェロ協奏曲」1919年10月26日はイギリスの作曲家サー・エドワード・エルガーの「チェロ協奏曲」が初演された日です。エルガーと言えば最も有名なのは、ヴァイオリンの名曲『愛の挨拶』があります。 今ではヴァイオリンのリサイタルのプログラム、アンコールピースとしてもよく採り上げられるヴァイオリンの名花のような曲です。そのエルガーが、古くはボッケリーニ、ハイドンやシューマン、ラロ、ドヴォルザークなどの作曲しました、チェロと管弦楽のための協奏曲を書きました。 「チェロ協奏曲」です。曲は簡潔な構成ですが、全編に流れるロマンの香りはチェロの魅力いっぱいで、シューマンを想起させるようなロマンチシズムに溢れた名品です。 全体は4楽章形式で書かれていますが、第1、第2楽章は続けて演奏されます。愛聴盤ジャクリーヌ・デュプレ(チェロ) サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団不治の病に冒されて若くして亡くなった不世出のイギリスの女性チェリスト、デュプレの豪快な音色とマイルドなビロードのような「バルビローリサウンド」と呼ばれたサー・ジョン・バルビローリ指揮による濃厚なロマン溢れるこの演奏が一番好きな録音です。(東芝EMI TOCE59053 1965年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月26日
コメント(4)
-

小説「新撰組藤堂平助] / ビゼー 交響曲ハ長調
『小説 新撰組藤堂平助』この小説は今年の1月に読んだのですが、今尚心に残る本なのでここに紹介いたします。私は歴史が好きで、特に江戸時代幕末がもっとも好きな時代です。 日本の世界への夜明けの黎明期とも言える時代で多くの有能な青年武士がその命を散らせていった、日本歴史上もっとも激動の時代でした。その時代の流れの中に忽然と現れて旧幕府体制の中で、最後まで新政府(天皇制勤皇派)に抵抗して死んでいった「新撰組」には尽きせぬ想いがあります。今までにたくさんの「幕末物」小説を読みましたが、いつまでも心に残るのは司馬遼太郎の「新撰組血風録」「燃えよ剣」、浅田次郎の「壬生義士伝」でした。 特に「燃えよ剣」は副長土方歳三の最後まで描いていて、まるで秋のつるべ落としのような残照を思わせる歳三の激しい生き方に「哀れ」を重ね合わせ、それでも凛として五稜郭の地に散っていった歳三の生き様には涙をさそうものがあり、この新撰組を描いて30年間この小説を凌駕するものはないだろうと思っていました。ところが女流作家秋山香乃氏が書いた「新撰組藤堂平助」を読んで深い感動を覚えました。 氏は歴史、とくに幕末を研究されていて、その深く、広い知識を縦横に織り込んで、若くして京都「油小路の決闘」で命を落すまでを、彼の隊士としての心の奥深くに迫り、滅び行く、死に行く者たちへの挽歌のごとく、ひたむきに信念に生きた平助像を見事に現代に蘇らせており、まるで夕陽の残照のように紅く燃えながら沈んでいく姿のごとく描いた秀作です。氏は1968年生まれですから、まだ35歳。 この作品の前には土方歳三を描いた「歳三 往きてまた」を発表しており、この小説も傑作の一つです。「敗者」を描いた文学の中でも秀逸です。出版社は「文芸社」です。 「秋山香乃の館」 秋山氏のHPです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽」 ビゼー作曲 交響曲ハ長調1838年10月25日はフランスの作曲家ジョルジョ・ビゼー(1838-1875)が生まれています。 ビゼーと言えば歌劇「カルメン」があまりにも有名で今でも世界のオペラ劇場で上演されている彼の代名詞のようなオペラですが、今日は彼が17歳のころに書かれたと言われている「交響曲ハ長調」を取り上げました。17歳の頃に習作して書かれたこの曲はおそらく1855年ごろに書かれたと推測されており、完成後も忘れられたままであったのが、1935年にパリ音楽院の図書館で発見されて、その年にオーストリアの大指揮者ワインガルトナーによって80年の眠りからさめて初演され、その翌年に故国フランスでシャルル・ミュンシュによってフランス初演が行なわれています。若々しい、竹を割ったような率直な美しさで、全編を覆う南フランス風のラテン的な情緒いっぱいの曲で、ドイツやオーストリアの作風とは格別に違った明るい作風に溢れた名品です。愛聴盤 小澤征爾指揮 フランス国立管弦楽団1982年の若き小澤が熱狂的にパリに迎えられ、フランス国立管と息の合った演奏で彼の情熱が迸る素晴らしい演奏です。(東芝EMI TOCE-7108 1982年フランス録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月25日
コメント(2)
-
日記を書く / オペレッタの楽しさ 「メリー・ウイドウ」(フランツ・レハール)
また天災が起こりました。 今度は地震です。 新潟中越地震。 マグニチュード6.8 余震の大きさが震度6弱が3度も起こったそうです。 亡くなられた方々や、被災地の方々に心よりのお悔やみと、お見舞いを申し上げます。 やっと水害の傷が癒えてこれからという時にこの地震です。 これ以上の被害が拡大していないことをお祈り致しております。 そして一日も早く復興されんことを願っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『日記を書く』1995年から一日も欠かさずに日記を書いています。 自分の生活を言葉にして書きとめておこう、と思って書き始めたことですが今でも続いています。最初は大判のいわゆる大学ノートと呼ばれているものに、一日一ページのペースで書いていました。 生来「書くこと」を好きな私には苦にならない「作業」でした。 生活日記とでも呼べる物で「仕事」における愚痴・腹のたつこと、成功してうれしかったこと、「趣味」でいい時間を過ごしたこと、いい小説にめぐり合えたこと、「近所の噂話」「交遊録」など話題は多彩。 TV、新聞で扱う大きな出来事、事件、政治、経済、文化についてもその折々に書き添えてきました。2002年から贈り物でもらった3年日記を使っています。 その一番上に「音楽メモ」をその日にちなんだ話題で書いています。 例えば今日ならフランツ・レハール D1948 これは彼が1948年に逝去した意味。 それを見ながら「今日のクラシック音楽」記事を書いています。長期出張もありました。 2度インドに2ヶ月滞在したことがありました。 出張ー例え1泊でも日記帳は持参してその日に書くようにしています。今までに書いた日記を読み返すと、過去の自分が蘇り、世の中のことも蘇ってきます。 パソコンで書いてもいいのですが、私は書くことが好きなので、万年筆で手書きにしています。 これだと漢字を忘れなくて助かります。「書記欲」旺盛のともさんです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 フランツ・レハール作曲 オペレッタ「メリーウイドウ」1948年10月24日にはオーストリアの作曲家フランツ・レハール(1870-1948)が亡くなっています。 彼はオペレッタ(喜歌劇)を多く作曲したことで有名で、特に「メリー・ウイドウ」(陽気な未亡人)は彼の名を世界的に有名にした、ヨハン・シュトラスのオペレッタ「こうもり」「ジプシー男爵」などの一連の名作以来の傑作です。オペラといってもウイーン情緒あふれる楽しい旋律、ウインナワルツのような曲がふんだんに使われているコミックオペラです。物語は、作曲当時(1905年頃)のパリの社交界を舞台にした3幕のオペラで、架空の国の設定の富豪と結婚したが若くして未亡人となった美貌のハンナが、昔の恋人の伯爵と再会して、初めはお互いに素直にならずに意地の張り合いをしているが、やがて愛し合うようになり最後には結ばれるというストーリーです。オペラの音楽は終始レハールの流麗な美しい旋律に彩られており、「メリーウイドウワルツ」やハンナのアリア「ヴィリアの歌」など、単独でコンサートを飾る美しく、楽しい音楽にあふれています。愛聴盤 ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 ウイーンフィルハーモニー、チェリル・ステューダー(ソプラノ) バーバラ・ボニー(ソプラノ) ボイエ・スコウス(バリトン)ウイーンフィルの極上のアンサンブルが楽しめて、名盤の誉れ高いシュワルツコップの古典的魅惑の上品な甘さの歌唱と一味違う、ステューダー、ボニーの現代感覚での美しい歌唱が楽しめて、CD1枚に3幕全曲が収まっているのも魅力の1枚です。優秀録音盤です。(グラモフォン POCG-1840 1994年1月ウイーン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月24日
コメント(10)
-
ヒマラヤの青いケシ
今から2年前、ヒマラヤに咲く「青いケシ」の花の絵を見て感激した人が、実際にその花を見たくなり高山植物園などを巡ってその花を見たが、栽培された花に満足せずに絵で見た自生の花をヒマラヤで見たくなった。 登山経験はゼロだった。そのうちに「青いケシ」の写真を撮り続けている写真家と出会い、ヒマラヤに連れて行ってもらうことになり、その写真家から毎日10,000歩いて体力を付けるように言われた。運動嫌いのこの人は、ヒマラヤの野生のケシを見たい執念に燃えて、毎日ウオーキングに励んだ。 そして近隣の山々で登山の練習を重ね、体力を付けるのにスポーツジムにも通った。今年7月念願のヒマラヤ登山に参加することが出来た。 ネパールに到着後、標高3,351mの町で高度調節をして3日後に4,110mの地点で念願の野生の「青いケシ」に出会った。動物から身を守るために葉や茎や蕾に鋭いトゲをつけた野生の姿と、神秘的な花の青い美しさに声も出なかった。孤高に凛として咲くその姿に、それまでの苦労が癒され、心地よい達成感を感じたそうだ。(産経新聞2004年10月22日付け朝刊 談話室より)この人、登山経験のなかった75歳の主婦。 ただただ頭が下がる思いです。
2004年10月23日
コメント(8)
-

バッハ 無伴奏チェロ組曲 / 気分が良かった(追記)
今回の台風23号で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共に、病床におられる方々、被害を受けられた方々の一日も早い快復と復旧がなされることを願ってやみません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日は愛知県刈谷に出張ですので日記は帰宅後追記しますが、『今日のクラシック音楽』のみ書いておきます。(追記) 『気分が良かった』私は買い物や駅に行くときにはほとんど自転車を使っています。 今日も駅に向かって自転車で走っていると、前から自動車が少しスピードを上げてやってきました。 そのうしろに20歳くらいの若い男の子が自転車で走っていました。自動車が通り過ぎたときに、私が少しグラッと傾いて体勢を整えようとした時に、その若者が自転車にしては凄いスピードで私の脇を走り抜けました。それで私は自転車ごと倒れてしまいました。 すると彼は転倒した音で後を振り返り、私の方に戻って来て「お怪我はありませんか? 大丈夫ですか?」と声をかけてくれました。これまではコンビニのドアを開けて、後を振り返ることもせずに手を離す若者のおかげで、何度もドアーに当たった経験があったので、この自転車の若者の態度に好感が持てました。このごく当たり前の彼の行動と言葉が、私の気分を良くしてくれています。 こういう支え合う気持ちをいつも持っていたいと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 J. S. バッハ作曲 「チェロのための無伴奏組曲」1973年10月22日偉大なチェリストのパブロ・カザルス(1876-1973)が亡くなっています。 96歳でした。 晩年は高齢にもかかわらずマルボロ音楽祭などでオーケストラの指揮もされてチェロにとどまらずに音楽家として活躍した人でした。カザルスと言えばすぐに思い出すのはJ.S.バッハ(1685-1750)の偉大なチェロ作品集「無伴奏チェロ組曲」です。 この曲集を現代に蘇らせたのがこのカザルスです。 かれはスペインのバルセロナにある小さな楽器店に置かれていたこれらの楽譜を偶然発見して、精彩にこの文献を研究してこの曲の真価を世に問うことで、この偉大な曲集に光があてられたからです。組曲は第1番から第6番まで全部で6曲あり、いずれも素晴らしい作品です。 バッハには繊細なヴァイオリンの美音を極めたヴァイオリンのための無伴奏の曲がありますが、分厚い低音の男性的な音色のチェロによって完成された多様性のある音楽世界を切り開いています。各曲の構成は同じでバッハ時代の「舞曲」が使われていて、第1曲が「プレリュード(前奏曲)」以降が「アルマンド」「クーラント」「サラバンド」と並びその後に各組曲で1曲が変化をつけられており、最後は「ジーグ」で終るという規則正しい構成です。チェロという楽器の魅力を最大限に引き出した「人類の遺産」です。 この曲集が書かれて(1720年頃と推測されています)からおよそ100年後にベートーベンが、5曲の「チェロとピアノの為のソナタ」を5曲書いています。 バッハの「無伴奏」をチェロ音楽の「旧約聖書」、ベートーベンのそれを「新約聖書」と呼ばれており、チェロ音楽の完成を物語る呼称です。愛聴盤は、ムスティスラフ・ロストロポービチ(チェロ)演奏の東芝EMI TOCE 8641~42 1992年録音盤です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの「今日の一花」 コスモス 撮影 大阪和泉 2004年10月
2004年10月22日
コメント(6)
-
転落したひな ・ ゲオルグ・ショルテイ(指揮者)誕生日
悲惨なニュースをここに書くのは気分が暗鬱とするので、削除しました。 下記の記事は私も似たようなケースを目撃したことがあって、とても清々しい気分になりましたので掲載することにしました。「転落したひなを助けてみたら」 大阪府 66歳無職男性 先月、我が家の居間から見える児童公園のクスノキに、ヒヨドリが巣を作っていた。 鳴き声が聞こえると、ついその方向を見るのが習慣になっていった。ある日、一羽のひなが地面に落ちるのをたまたま見た。 親鳥はしばらく近くを飛んでいたが、どこかに行ってしまった。 すでに夕暮れ時。 捜しに行くと、巣立ち前と思われる大きなひながバタバタしていた。巣を見たが空である。 元に戻しても落ちそうなのでバケツに保護した。 猫などに襲われないよう厚紙で覆い、うちの庭で一夜を明かした。翌朝、ヒヨドリの鳴き声を聞いた。 バケツのすぐ近くに親鳥と思われるつがいが来ていた。 親鳥とひなは互いに姿は見えないのに盛んに鳴き合っているではないか。 その姿に私は感動した。 厚紙に出入り口を設け、巣のあった木にバケツを固定してみた。 親鳥が来たので安堵した。その5日後、親鳥の姿が見えないのでバケツの中を覗くとひなはおらず、無事に巣立ったと思った。 このことがあって私はヒヨドリが好きになった。(朝日新聞2004年10月21日付け朝刊「声」欄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」 ドボルザーク 交響曲第9番「新世界より」1912年10月21日にはハンガリー生まれの偉大な20世紀の指揮者の一人、ゲオルグ・ショルテイが生まれています。ショルテイは現代の録音技術の進化と共に歩いた指揮者で、数多くの曲をLPステレオ録音時代からディジタルCD録音まで残しています。 1960年代にはイギリスのコヴェント・ガーデン王立歌劇場の音楽監督として就任、名声を確立して「ナイト」の称号を与えられていますから、正式にはサー・ゲオルグ・ショルテイと呼ばれています。1969年にフランスのジャン・マルティノンの後を受け継いでシカゴ交響楽団の音楽監督に就任して、1991年にバレンボイムにその地位を譲るまで指揮を執り、シカゴ市民から絶大の信頼を得た指揮者でした。あれは1990年だったか、彼が退任前にシカゴ響と来日した折に、大阪のシンフォニーホールで鳴り響いたブルックナーの8番の名演が目に、耳に焼きついています。どの曲の演奏も、明晰な表現とダイナミックな推進力でパワフルにオーケストラを鳴らす指揮者でした。 オーケストラコンサートだけでなく、オペラ指揮者としても非凡な才能を発揮してプッチーニ、ヴェルデイなどのイタリアオペラ、ベートーベン、ワーグナー、R.シュトラウスなどのドイツ・オーストリアのオペラなどを数多く上演、録音を行なっています。とりわけ1958年ー1965年にウイーンフィルを指揮して当時の世界の一流歌手を揃えたワーグナーの4部作「ニーベルングの指環」は、今も尚、ワーグナー音楽の聖書のように讃えられている録音です。私が大学生時代にワーグナー音楽を聴くようになったのもこの録音でした。それにミサ曲、オラトリオなどの教会音楽などにも素晴らしい演奏があり、ヴェルデイの「レクイエム」などの名演奏を遺してくれています。今日は彼の誕生日に因んで、名演の一つであるドボルザークの交響曲第9番「新世界より」を紹介しておきます。いかにもショルテイらしい、明晰でダイナミックな音楽表現と、切り込み鋭く、パワフルなシカゴ交響楽団との演奏で、素晴らしい録音がいっそうの迫力を添えており、テインパニーを叩く音などは怖さを覚えるほどの迫力です。(DECCAレーベル 410 116-2 1983年1月シカゴ録音)現在入手可能なCDは(DECCAレーベル ユニバーサルミュージック発売 UCCD5018)のようです。 カップリングはシューベルトの「未完成」交響曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月21日
コメント(4)
-
23号「トカゲ」がやって来る!(追記あり) ・ ブラームス 弦楽六重奏曲 第1番
「23号(トカゲ)がやって来る!」また23号台風が本土上陸確実なコースで進んでいます。 午前11時には四国足摺岬(高知県)が暴風域に入っており、15m以上の強風圏に大阪も入っています。 この強風圏が1600kmというとてつもない超大型台風だそうです。 北海道から九州まですっぽりとはいる広域台風だそうです。九州南部、西部、四国全域、関西、和歌山、三重、東海地方の方々に大きな被害が出ないことを祈っています。 大雨の予想も出ていますので、くれぐれもご注意下さい。(追記)こちら大阪は泉佐野市に上陸して北東に進みましたから、私の済んでいるところは、15kmほど上陸地点から離れたところですごい風が吹くと思いきや、風も雨もなく静かに去って行きました。拍子抜けする思いでしたが、被害に会われた地区の方々にはお見舞い申し上げて、一日も早い復旧、復興を願ってやみません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ブラームス作曲 「弦楽六重奏曲第一番」1860年の10月20日はブラームスが作曲した「弦楽六重奏曲第一番」が初演された日です。弦楽だけの室内楽では、ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ各1という編成の四重奏が一番バランスが良いのでしょう、多くの作曲家がこの編成で「弦楽四重奏曲」を書いています。 ブラームスはこれに更にヴィオラとチェロを加えて六重奏曲を2曲書いています。中音、低音を2つ増やすことは音のバランスの点で扱いにくいところがあったのでしょうか、ベートーベンでさえ手をつけなかったこの編成に意欲を燃やして書いた、これらの2曲はいずれも美しい室内楽曲として遺されています。ブラームスは室内楽では、「ピアノ五重奏曲」「ヴァイオリンソナタ」「チェロソナタ」「ピアノ三重奏曲」「ピアノ四重奏曲」「クラリネット五重奏曲」「クラリネットソナタ」など渋い音色ですが、美しい曲を遺しています。この「弦楽六重奏曲」の2曲もブラームスらしい、深い、渋みのある音色ながら美しさに溢れた名品です。今日が初演日の「第一番」は昔フランスの大女優ジャンヌ・モローが主演した映画「恋人たち」で、その第2楽章が使われて、この曲がいっそう有名になりました。 映画音楽として使われたように、じつに哀愁の美しさに溢れた名品です。この第2楽章だけでも立派な一つの名曲となっています。分厚い低音の響きを見事に活かした、全編に哀愁のただよう室内楽作品です。ともの愛聴盤「メニューイン ブラームス弦楽六重奏曲」(EMI レーベル TOCE-3080 1963-1964年録音)モーリス・ジャンドロン(チェロ)などのメニューイン(ヴァイオリン)の仲間たちで演奏されている盤です。今日のその他の音楽カレンダー1920年 マックス・ブルッフ(作曲家)逝去1958年 イーヴォ・ポゴレリチ(ピアニスト)誕生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月20日
コメント(7)
-

「男女間の壁を飛び越える娘」 ・ ワーグナー オペラ「タンホイザー」
「男女間の壁を飛び越える娘」 大阪府児童構成員 女性40歳 2学期が始まってまもなく、「運動会で応援団長に決まった」と小学6年生の娘が張り切って帰ってきた。 当日、娘は学ランに鉢巻、たすきがけ姿で声を張り上げた。「男の子かと思ったら女の子やわ」「しっかりしてるわ」周囲から聞こえてきた。 娘を見ながら、私の小学6年生の運動会の出来事を思い出した。 担任の先生から「入場行進の時の鼓笛隊の指揮者をやらないか」と言われた。 少しはやってみたいと思ったけれど、結局はクラスの男の子に頼んだ。 大勢の前に立つ恥ずかしさもあったが、「女だてらに何をすると思われるだろう」とか、「男子を差し置いて女子が指揮をするのはまずいのでは」と子供なりに考えていたのだと思う。 娘は「一度学ランを着てみたかった」というだけの理由で母の越えられなかった壁を、いとも簡単に乗り越えてしまった。 大人たちが男女共同参画社会の実現を目指して勝ち取ってきたものを、こどもたちは「同じ人間として世界の中心は私たちです」と主張しているように感じた。 私も「この子たちの未来を守ってやらねば」と誇らしく眺めた。(朝日新聞2004年10月19日 朝刊 『声』欄より)新聞の情報はTVやラジオに較べると遅いのですが、じっくりと読んでみますとその日一日を幸せな気分にしてくれる投稿記事や、豊かな気分にさせてくれる記事が必ずあるものですね。 私は朝日新聞を購読しているのですが、毎朝6時ごろにポストから取り出すのを楽しみにしています。 今日はどんな記事が掲載されているか期待して待っています。勿論、暗鬱な気分にさせられる凶悪事件、殺人事件、子供への虐待事件なども毎日出ていますが、そんな中でも幸せな気分にしてくれる記事を探すのが楽しみです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「今日のクラシック音楽」 ワーグナー オペラ「タンホイザー」1845年10月19日はワーグナーが作曲しましたオペラ「タンホイザー」がドイツのドレスデンで初演された日です。ワーグナーはこの「タンホイザー」がドレスデンで初演される前には、ロシアやパリで作曲の筆をとっていましたが彼の作品が舞台に上がることはなく、ベルリオーズなどとパリ時代に親交を深めていたものの、友だちとしての上演への協力もなく不遇の時代を過ごしており、オペラ「リエンツェ」がドレスデンで上演されたのは1842年の10月20日。 1843年の1月にオペラ「さまよえるオランダ人」が同じくドレスデンで初演され、この成功によってドレスデン宮廷歌劇場の指揮者に就任してのちに構想を持っていた「タンホイザー」の作曲に取り掛かり、1845年10月19日に初演されたそうです。パリ時代の不遇に負けずに不屈の闘志と精神で粘り強く生きてきたワーグナーがようやくこの「タンホイザー」によって自信を深め、次の「ローエングリン」へと進んでその「ローエングリン」作曲後に「歌劇」から「楽劇」へと総合舞台芸術への道を歩んでいきました。「タンホイザー」は3幕から成るオペラで舞台は13世紀初頭のドイツ、今では観光地となっていますアイゼナハのワルトブルグ城です。女性の力によって魂が救済されるというワーグナーの好みのテーマで貫かれている物語です。 ワルトブルグ城主の姪エリザベート姫と吟遊詩人タンホイザーの悲恋を描いています。吟遊詩人タンホイザーは、愛欲の神ヴェーヌスの誘惑の虜となり歓楽に耽るさまから幕が上がります。 しかしエリザベート姫のいる城が恋しくなりやがて城に戻り、おりからの「歌合戦」に参加したのはいいのですが、友だちのヴォルフラムの清らかな愛の歌への反発から歓楽と愛欲の神ヴェーヌスを賛美する歌を歌い追放されます。ローマ法王の許しを得ようと巡礼の旅にでますが許されずに戻ってきたタンホイザーを、エリザベート姫は自分の命と引き換えに彼の魂を救うという悲恋物語です。「序曲」はコンサートプログラムでもよく取り上げられる曲で、劇中に演奏される「巡礼の合唱」の旋律などが使われており、崇高な佇まいの音楽です。「ヴェヌスブルグの音楽」は第1幕が上がると歓楽の場面のバッカナールという音楽で、これもよく演奏されます。 序曲にも取り入れられています。「夕星の歌」は吟遊詩人ヴォルフラムが、夕星たちよ姫が天国に上るときに歩んでいく道を照らしてやってくれと歌う第3幕のアリアで、これも有名な、美しいバリトンのアリアです。「巡礼の合唱」はこのオペラの代名詞のような曲で崇高な雰囲気の合唱曲です。ともの愛聴盤 エリザベート・グリュンマー(ソプラノ)、ハンス・ホップ(テノール) フランツ・コンビチュニー指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団・合唱団(EMIレーベル TOCE-9452/54 1960年10月 ベルリン録音)もうこういう演奏は二度と聴けないのではないかと思えるほどの深い、重厚なドイツ音楽の響きのする演奏をとても気に入っています。 40年以上前の録音ですが音質は良好です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 撮影 大阪和泉 2004年10月
2004年10月19日
コメント(8)
-
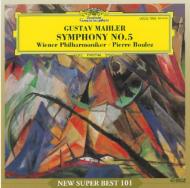
タバコの弊害 / マーラー 交響曲第5番
数年前のこと、通勤途上の自宅から駅へ続くなだらかな坂道の1本道をを歩いていると男性の老人が、路上や溝に落ちているタバコの吸殻を拾ってくれていました。 数日後にわかったことなのですが、この老人は毎朝この道約1kmの距離を歩いて溝や路上に捨てられている吸殻を拾ってくれているそうです。 勿論、私はこの老人を見て教えられて「歩行喫煙」をやめました。歩行喫煙は、例えば幼児が歩いている時には非常に危険です。 1000度近いタバコの火が幼児の顔に焼けどを負わす危険があります。 道路は汚され、こうした危険を引き起こすことにもあります。今朝もこの老人は吸殻拾いをやってくれていました。 この人の年齢は86歳。 この老人の背中が「ポイ捨てはやめてくれや!」と言ってます。喫煙者はお互いにマナーを守りましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 マーラー作曲 交響曲第5番嬰ハ短調今から100年前の1904年10月18日は、グスタフ・マーラー(1860-1911)が自らの指揮でこの交響曲第5番を初演した日です。第2番、第3番、第4番は声楽とオーケストラとの共演という形の交響曲が続いていましたが、第1番「巨人」以来、純粋な器楽合奏だけとなりましたこの曲は、冒頭の第1楽章から「葬送行進曲」という型破りの構成で、マーラー特有の暗い面と悲痛さ、物憂い影を色濃く漂わせている曲です。第4楽章の「アダージェット」は耽美な甘さ、美しさを湛えていて、映画「ベニスに死す」(トーマス・マン原作 ルキノ・ビスコンティ脚本・監督 ダーク・ボガード主演 1971年作品)の挿入音楽として使われて、画像とうまくマッチしたクラシック音楽使用の成功例で、この映画によってマーラーのこの第5番は一躍有名になりました。秋の夜にじっくりと聴くのもいかも知れません。愛聴盤ピエール・ブーレーズ指揮 ウイーンフィルの1996年3月のウイーン録音です。 複雑な音楽を明晰に表現しており、ウイーンフィルの素晴らしさを優秀録音が捉えた優れたCDだと思います。 (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCG7015 1996年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月18日
コメント(2)
-
また新しい命の誕生 / ショパン 「夜想曲」
妹の息子夫婦に第一子が授かりました。 男の子です。相当の難産だったようで嫁も病院始まって以来の騒ぎようで、しばらくは語り継がれるエピソードになりそうな話らしいです。 陣痛というか、痛みを訴えて病院に駆け込んだのが夜の10時。 空き室がなくて分娩室に入ってから、生まれたのが翌日の午後3時半。 その間嫁はず~と痛みを訴えており、最後には「殺せ! 子供はいらん!」とまで泣き続けたそうで、医者は麻酔を使い、それでもダメなら帝王切開をと考えていたそうですが、どうにか自然分娩で生まれました。今日は妹の誕生日。 嫁と赤ちゃんを見舞ってから妹夫婦と誕生日の夕食をパスタ屋で祝いながら、ことの顛末を妹とから聞きながら最後には吹き出してしまいました。 それほど半狂乱に乱れた嫁だったらしい。まあ、生まれてめでたし、めでたしです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ショパン 「夜想曲」1838年の今日(10月17日)フレデリック・ショパン(1810-1849)が亡くなっています。 その命日にちなんで今日は彼の数多くのピアノ曲の中から「夜想曲」を採り上げました。「夜想曲」は、夜に想う、夜の静けさの中に瞑想するような音楽です。 この「夜想曲」という形式はイギリスの作曲家ジョン・フィールド(1787-1832)が創ったもので、ショパンはこのフィールドの影響を受けて夜想曲集を作曲したと言われています。 しかし、ショパンの曲がはるかにポピュラーなのはやはりその卓越した曲の素晴らしさからくるのでしょう。 現代ではフィールドの名をあまり聞かなくなりました。 テラークレーベルでオコーナーというピアニストが最新録音で吹き込んでいて、それを聴いていますが曲自身はやはりショパンの方が遥かに魅かれます。特に有名なのは作品9の第1番、第2番です。 2番は映画「愛情物語」で一躍有名になりました。 夜想曲の代表的名曲です。秋の夜長を夜想曲で楽しんでみませんか。お薦めCD マリア・ジョアン・ピリス 「夜想曲」全曲(2CD)そんなに数多くのピアニストの演奏を聴いているわけではありませんが、このピリスの演奏は甘美だけに陥らずに、造型をしっかりと捉えた格調の高い演奏を繰り広げています。 有名な第1番、第2番なども落ち着きのある奥深い抒情をかもし出している演奏だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月17日
コメント(5)
-
言葉
人の心、感情を写すものに「言葉」があります。 言葉はコミュニケーションに欠かせないものです。 人を幸せにする言葉、楽しくする言葉、哀しくさせる言葉、悲しくさせる言葉、惨めにする言葉、怒らせる言葉など色々な言葉があり、同じ意味でもその場の状況を救う言葉もあります。「吐いた唾は戻らない」と同じで口から出た言葉で暗転することもあります。 逆に幸せ気分にもさせるものです。「口は災いのもと、舌は災いの根」これを私は最近念じています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「四は幸せのし」 大阪府 32歳 看護士 先日勤務している病院のエレベーターに乗っていると、小学高学年くらいの女の子2人が入ってきた。 二人は階数ボタンを見て何やら話していました。 「このエレベーター、4階がないんですけど、どうでしてですか?」ひとりの女の子が私に尋ねました。「死ぬの『し』って聞いたことない? 四は不吉な数字だから病院には4階も4号室もないのよ」と私が答えると、女の子は「え~!」少し驚いた顔になって言いました。 「四は幸せの『し』だよ」そうだ、そうだ。 ドレミの歌でも♪シ~は幸せの~、と歌っていた。 「幸せの『し』の方がいいよね」と二人で話しているうちにエレベーターは目的の階に止まり、彼女たちはにっこり笑いながら手を振って降りて行きました。不吉な数字というのはよく言われることですが、吉にするのも不吉にするのも自分次第。 心の中に幸せいっぱいの一日でした。あれ以来、私のラッキーナンバーは、もちろん「四」です。 読売新聞2004年10月16日付け朝刊投稿記事から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月16日
コメント(6)
-
マリオ・デル・モナコ (今日のクラシック音楽) 特別な日 (お詫びと訂正)
私自身何を勘違いしたのか大変な間違いがありますことがわかりました。 マリオ・デル・モナコの命日は10月15日ではなくて10月16日です。 ここに誤った情報を掲載いたしましたことをお詫び致しますと共に訂正させていただきます。 日記はこのまま掲載させていただきます。 1月27日と10月16日は、私にとっては特別な日です。 イタリアのテノール歌手、マリオ・デル・モナコの誕生日と命日です。 今日は命日にあたります。 1年に二度、私はモナコが遺した名演奏、名録音をこの2日で楽しんでいます。 1961年、私がまだ高校2年生だった年ですが、NHKの招きでイタリア歌劇団が来日して東京、大阪でオペラやリサイタル公演を行ないました。 そのときの歌手がソプラノのレナータ・テバルデイであり、メゾ・ソプラノのジュリエッタ・シミオナートであり、そしてマリオ・デル・モナコでした。この来日時の大阪公演で私はモナコの「道化師」とシミオナートの「カヴァレリア・ルステイカーナ」の舞台を観ました。 フェステイバルホールの1階最前列オーケストラピットに立つ指揮者の斜め後でした。モナコの道化師にただただ圧倒された夜でした。 シミオナートのサントッツアの舞台の興奮冷めやらぬうちに「道化師」が始まり、終ったあとはシミオナートのことが頭から消えてしまうくらいにモナコの白熱の名唱に酔いしれて、秋の夜の中之島をぼ~と歩いていたのを覚えています。モナコはテノール歌手としては、ドラマテイック・テノールでその声はまるで「鋼」のように強靭で、突き刺さる剣のような高い声は「黄金のトランペット」と形容される歌手でした。彼の得意とする「道化師」のカニオは、いまだもってこの人の名唱を凌駕するテノールはいません。 客席で観ていて、劇中の白眉のアリア「衣装をつけろ」では、私の真ん前にモナコが座り、白粉を塗りながら目を大きく開けて、私をぎょろっと睨みながら歌い始めたときには、鳥肌が立つ思いで引き込まれていきました。「空前絶後」という言葉がありますが、まるでモナコのためにあるような、まさに「空前絶後」のテノールです。 この人の名唱を聴くときには襟を正して正座するほどの姿勢になってしまいます。今日もその10月15日がやってきました。 今日は何を聴こうかな、カラヤンとウイーンフィル、テバルデイとの共演の「オテロ」? それともテバルデイ、バステイアニーニとの「アンドレア・シェニエ」か同じオペラの唯一テバルデイとの日本共演舞台の映像? いや、やっぱり1961年の来日公演の映像から「道化師」?今は真夜中の2時を過ぎたばかりです。 朝起きたときに題目を決めよう。 そして40年前にタイプスリップする楽しみを思いながらぐっすりと寝ることにします。 おやすみなさい。お薦めCD マリオ・デル・モナコ オペラアリア集 モナコの魅力満載のアリア集で、「衣装をつけろ」「星は光りぬ」「誰も寝てはならぬ」「オテロ」幕切れのアリアなどがカップリングされています。 この中にマイアベーアの「アフリカの女」から「おおパラダイス」が入っていますが、これこそ劇的な表現に満ちた、「黄金のトランペット」を満喫できる「空前絶後」のアリアです。(LONDON POCL-2431 1955年ー1964年 録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月15日
コメント(6)
-
1300年前の日本人留学生 (追記あり) / ベートーベン 「月光」ソナタ
遣唐使に随行した日本人留学生についての墓誌が中国で発見されました。 中国名が「井真成」。 1300年の時を超えて現代に帰ってきた留学生の望郷の想いに胸を打たれました。彼は西暦717年に阿倍仲麻呂や吉備真備などの有名な遣唐使と共に当時世界の中心だった唐に渡った留学生で、学問を習得したのちに玄宗皇帝に仕えたらしい。 そして734年1月彼は急病によって36歳の生涯を唐の国で閉じてしまった。 その年の秋に日本に帰る船が唐を発ったとあります。 玄宗皇帝から死後異例の官位を追贈されたと書かれていますから、よほどの優秀な人であったのでしょう。室生犀星は「よしや うらぶれても異土の乞食(かたい)となるとても 帰るところにあるまじや」と残していますが、遠き万葉の人は望郷の念をこう歌っています。「天の原ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」 唐に渡って望郷に駆られた阿倍仲麻呂の歌です。 万葉人には月は「月の鏡」と例えており秋の季語にもなっています。墓誌には「遺体は異国の地に横たえども、心は故郷に帰るだろう」と書かれているそうです。 異国で逝ったその留学生も、幾度となく両親の面影やふるさとの風景を「月の鏡」に写していたことでしょう。1300年の時空を超えた望郷の想いが、美しく輝く日本の秋の「月の鏡」の季節に届いたことがいっそうの哀しさを伝えてくる物語です。(追記)この墓誌発見の記事を読んだあとに昼食を食べました。 それが『鍋焼きうどん』でした。 うどんを食べながらもう一度詳細に記事を読みました。 この「うどん」を中国からもたらしたのが、これら遣唐使だったからです。 何気なく食べていました「うどん」への箸の動きが止まりました。 この人たちのお陰で今はこうして改良された「うどん」を日本の食材文化みたいに食べられるのだなと思いながら。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ベートーベン ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 作品27の2 「月光」1985年の今日(10月14日)旧ソ連の大ピアニストのエミール・ギレリス(1917-1985)が亡くなっています。ギレリスは「鋼鉄のピアノ」とも呼ばれるほどの強靭なピアノタッチと冴え渡る技巧の持ち主で、旧ソ連からヨーロッパにデビュー後は亡くなるまで世界を駆け巡った大ピアニストで、同じ旧ソ連出身のスビヤトスラフ・リヒテルと共に20世紀を代表するピアニストと讃えられています。そのギレリスが得意としたベートーベンのピアノソナタから、今日は「月の鏡」から連想して「月光ソナタ」を聴くことにします。3連音符が一貫して流れる特徴的、幻想的な音楽は「月の光」に例えられて付けられた標題で、ベートーベン自身のつけた副題ではありません。 彼は「幻想曲風ソナタ」と副題をつけており、あそらくハイドンやモーツアルトなどの古典様式から脱皮する意図で作られた曲だろうと言われています。それにしても「月光」という標題にふさわしい曲です。 これを今日が命日のギレリスの演奏で聴いてみることにします。(グラモフォン 「ベートーベン 6大ピアノソナタ集POCG9845/6 2枚組 1980年9月録音(月光)」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月14日
コメント(4)
-
集団自殺
昨日のニュースで男女7人が集団自殺をした(?)ことが報じられていました。 レンタカーの中に練炭を持ち込んで一酸化中毒死による死因らしい。 車の窓ガラスにはビニールテープが目張りとして張られていたそうです。まだ確実なことはわかりませんが、全国から集まってきた男女7人であることはわかっているらしい。 それらの7人の接点を警察がこれから解き明かしていくのだそうですが、今のところインターネットで知り合って共通の願望の「死(心中)」ということで一致して自殺をした、所謂「自殺サイト」で知り合ったのではないかと推測されているようです。同じように神奈川県でも2人の女性も練炭を車に持ち込んで死んでいたのが発見されています。自分を理解できる人を求めてインターネットで知り合い、同じ悩みを持つ同士のような結びつきを感じるという系図はどうしても理解できません。インターネットで知り合って自分を良く理解できるとか、本音で語れるとかという言葉、感想をよく聞きますが、ネット上で本音を語っているということがどうして判るのか、それが私には理解できません。仮想空間のように感じるネットを100%信じていることから生まれるのでしょう。 それが「死への願望」という同じ望みを持った人たちが集まり、死へと旅立って行く。 一種のノイローゼのような気分の人たち。 この日本で34万人の自殺者がいる現実とはちょっと違うような気がする「集団自殺」。 世の中が複雑になっていることについて行けなくなっている私かなとも思うニュースでした。皆さんはこの「集団自殺」をどう思うのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メモには何も記述がありませんので「今日のクラシック音楽」は休みます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月13日
コメント(6)
-
携帯電話が水の入ったバケツの中に / グリーンスリーブスによる幻想曲
今日は亡父の月命日。 朝からの秋晴れに誘われて1時ごろから花と線香と真新しいタオル地の布巾を持ってお墓へ歩いて行ってきました。道ですれ違う顔見知りの奥さん、おばあさん、地域の関係者、婦人会の人などと祭りのお世話のお礼を言ったり、神社のお世話で礼を言われたり、気持ちよく歩きながらお墓に着いて、プラスチックのバケツに水をいっぱいに張って墓前に進みました。布巾をバケツの水で絞り、墓石を丁寧に拭く。 以前は墓石の頭から水をかけていましたが、今は新しい布で拭くことにしています。 真っ黒になった布をもう一度水につけようと屈むとシャツの胸ポケットに入れてあった携帯電話がバケツの中にぽろっと滑るように落ちてチャポン!実はこの携帯電話、昨日の夕方から町の喫茶店に置き忘れていたのを昼食後に取りに行って、そのあとお墓にやって来た。 携帯電話は水に浸かると機能は全てダメになるらしい。 自宅でならすぐに電池を抜いて、ドライヤーで乾かせばひょっとしてまだ使えるかもしれませんが、外では無理。お墓参りのあとに喫茶店に取りに行けば良かったと思っても、後悔は先に立たず。 墓前に線香と花を供えてからすぐに隣町にあるドコモショップへ行ったが、時すでに遅しで電源が入らない状態になっており、機種変更で新機購入せざるを得ない。 ポイントを使って8,000円余りで買う羽目になりました。みなさん、水を使うときートイレの水洗を流す時など携帯電話には充分気をつけて下さい。 ドコモショップで言ってました。 この事故の多い3例は、浴槽の洗い、バケツを使った雑巾がけ、トイレの水洗使用時だそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ヴォーン・ウイリアムズ 「グリンースリーブスによる幻想曲」1872年の今日(10月12日)は、イギリスの作曲家ヴォーン・ウイリアムズが生まれた日です。彼はイギリス国民から敬愛された人で、イギリスの古い民謡や古謡を題材にして多くの作品を書いています。 それらの中で最も有名なのは「グリーンスリーブスによる幻想曲」「タリスの主題による幻想曲」「イギリス民謡組曲」などです。標題に挙げましたこの曲はイギリス民謡「グリンースリーブス」を主題にして、フルートとハープを使った弦楽合奏で演奏される牧歌的なメロデイの曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月12日
コメント(4)
-
祭りだ! (最終回) / ショパン ピアノ協奏曲 第1番
2日間の秋祭りを終えて、今朝から町会役員や婦人会、ボランテイアなどで町内、神社の清掃、テントや小屋・椅子の撤収・後片付けを8時半から行って、清掃業者にトラックでゴミを収集してもらい町中は元の静かな通りに戻りました。午後からは青年団や曳航責任者、だんじり保存会などで町内に吊るした秋祭りの提灯を取り払うだけとなり、これが終ると祭りの名残りが消えてしまい、また1年後の「燃える秋」まで待つことになります。このページでの町の祭りの紹介もこれで終わりとします。お立ち寄りありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ショパン ピアノ協奏曲第1番 ホ短調 作品11今日はフレデリック・ショパン(1810-1849)が遺したピアノ協奏曲第1番が1830年にワルシャワで初演された日です。39歳という短い生涯で彼が書いたピアノ協奏曲は2曲で、この1曲目はワルシャワを去る前夜に「ワルシャワへの告別」として行なわれたようで、ショパン自身が弾いたそうです。 そして彼の初恋の人とも呼ばれているコンスタンツィア・グワドコフスカもステージに立ち、華を添えたとも言われています。初恋の人への想いから書かれたとも言われているこの曲は美しい抒情的な旋律に溢れており、激情と甘美な情緒の入り混じった、古今のピアノ協奏曲でも筆頭に挙げられる美しい曲です。 愛聴盤 ジーナ・バッカウアー(ピアノ) アンタル・ドラテイ指揮ロンドン交響楽団(マーキュリーレコード原盤 フィリップス発売 1963年7月ロンドン 35mm磁気フィルムレコーデイング PHCP-1093)情緒的に溺れることのない、まるでクリスタルのような味わいの音で、激しく燃える情熱を表現した「巨匠風」の大きさを感じる演奏です。 USAで「ジーナ・バッカウアー国際ピアノコンクール」が行なわれています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月11日
コメント(11)
-

祭りだ! (2) / ヴェルディ オペラ「リゴレット」
朝から朝日がまぶしく射し込んでくる。 空は一点の曇りもない青空。 秋特有のDeep Sky(天高く)が広がっている。祭り好きをかき立てるような台風一過の素晴らしい天気になった。さあ、今日も祭りだ! (あとは帰宅後追記しますー夜10時ごろの帰宅)(追記)今日は汗ばむほどの午後の強い陽射しを浴びて14町村の18台のダンジリが駅前目指して進む。 5千人のギャラリーの前で走り抜ける「やりまわし」を披露する晴れ舞台にふさわしい空の底まで透けて見えるような好天気。 次々とダンジリが走り抜けていくたびにギャラリーから歓声があがる。 勇壮なダンジリの姿を披露する祭りのクライマックスだ。3時間のパレードが終ってそれぞれの町に帰るダンジリ。 太鼓の音が「お前よくやったなあ!」に響いてくる。 凱旋してホームタウンに帰ると夜の化粧に早変わり。 提灯で化粧を済ませるとゆっくりと町内を曳航するダンジリがすれ違った。そのあと一直線に伸びた緩やかな坂道を走り抜けるダンジリ。 ダンジリに燃えた泉州はつるべ落としの夕陽のように2日間の短い秋祭りを終えた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ヴェルデイ オペラ「リゴレット」1813年の今日(10月10日)はイタリアのオペラ大作曲家ヴェルデイが生まれています。彼は26曲のオペラを残しており、「椿姫」「アイーダ」「運命の力」「オテロ」「仮面舞踏会」「リゴレット」や「ファルスタッフ」などの名作があり、全作品の半数は今でも世界のオペラ劇場で上演されています。今日は彼のそれらの作品から「リゴレット」を採り上げました。フランスの作家ヴィクトル・ユゴーの戯曲「逸楽の王」を題材にして書かれており、北部イタリアのマントヴァ公爵に仕える道化師のリゴレットが、娘ジルダが好色家の公爵に誘惑されたことを知り、公爵暗殺を計画するがジルダは公爵を愛するばかりに身代わりに殺されるという物語で、オペラは音楽と物語が劇的緊張感に包まれており、ドラマテイックな迫力に溢れたものに仕上がっています。タイトルロール(主役)「リゴレット」はバリトンです。 ヴェルデイはバリトンを使う名手で、このほかにも「オテロ」や「ドン・カルロ」などでバリトンを重要な役どころで使い、見事に緊張感溢れる、ドラマテイックなオペラを書くことに成功しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月10日
コメント(18)
-

祭りだ! (追記あり) / サン=サーンス 「序奏とロンドカプリオーソ」
9日午前4時半です。 今は風も、雨も止んで静かな朝を迎えています。 このままの天気で済んでくれたらいいのですが、そういう訳にはいかないでしょう。 午前4時のNHKニュースでは、こちらはこれから200-250mmの激しい雨が降るらしいのです。気持ちだけは元気。 祭りを盛り上げる手助けをしましょう。 これから神社へ行ってきます。帰宅(夜10時ごろ)に追記します。心配しました台風の影響による風も雨もたいした事がなく、朝10時ごろには普通の秋の雨に変わり、午後からは雨も止んで曳航は順調に進んだようです。社務所に座って曳航の安全祈願のお守りを販売していました。 曳航には参加しなかったので、神社前を通りすぎるだんじりを撮っただけの初日でした。明日は曳航に参加して撮ろうと思っています。明日は朝8時から夜10時まで曳航の予定です。 夜の化粧のだんじり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 サン=サーンス 「序奏とロンドカプリチオーソ」1835年の今日(10月9日)はフランスの作曲家サン=サーンス(1835-1921)が生まれた日です。 交響曲第3番、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲、オペラ「サムソンとデリラ」など多彩な音楽を書いた人でした。今日は彼の音楽の中からヴァイオリンの名曲「序奏とロンドカプリチオーソ」を聴きます。 この曲は当時の不世出と言われたヴァイオリニスト・作曲家のサラサーテに捧げられていて、歌心いっぱいの旋律やダンス風なメロデイ、多分にメランコリーな旋律が自由な形式で書かれており、まさに「カプリチオーソ(気のむくままに)」です。お薦めCDイツァーク・パールマン(Vn) ズービン・メータ指揮 ニューヨークフィルハーモニック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月09日
コメント(6)
-
台風がやってくる( 補筆あり) / インフルエンザ(加筆) / ポワルデュー 「ハープ協奏曲」
「台風がやってくる」今日は朝から風まじりの強い雨。 明日は台風22号が接近。 何でこの時期にと思うけれど仕方ないと諦めの境地。 だんじり曳航は曳航委員に任せて神社詰めは予定通り台風接近でも行なうと今朝役員と話し合った。 秋祭りは神社の祭りだから閉めるわけにはいかない。今日午後4時からもう一度役員が神社に集まって台風情報を聞きながら最終的に決めることになるだろう。大阪直撃のコースで風速20mとかになればその時に決めることにした。 もっと太平洋寄りに海を通過してくれることを祈るばかりです。(補筆)メル友の「あきら」さんがこんな画像を送ってくれました。 ありがたいことです。 少しでもいい天気になることを「テルテル坊主」と一緒に祈ります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「風邪・インフルエンザの予防効果」今日のTV番組「おもいっきりテレビ」(日本テレビ系列)で食事による風邪・インフルエンザの予防効果となる食事の摂り方が紹介されていました。キノコ(舞茸など)100g、コンブ30g、醤油10g、トマト30gを1回の食事で一緒に摂るといいらしい。 これを週3回摂ることを推奨していました。料理方法の紹介はなく、これらを一緒に摂れる食べ方を考えればいいらしい。 どんな料理を考えようか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 ボワエルデュー 「ハープ協奏曲」フランスの作曲家 フランソア=アドリアン・ボワエルデュー(1775-1834)が、1834年の今日(10月8日)に亡くなっています。 彼はあまり知名度はありませんが、フランスのコミック・オペラで有名な人でオペラ「バクダッドの太守」は、今では序曲のみがコンサートやデイスクで聴かれ一度はどこかで聴いたことのあるクラシック音楽の一つに挙げられる有名曲です。今日は彼の曲の中で「ハープ協奏曲 ハ長調」を聴いて見たいと思います。 ヘンデル、モーツアルトなどのハープ協奏曲と並んで演奏機会の多い曲です。美しく気品の溢れるメロデイーがとても魅力的な曲です。クラウディア・アントネリ(ハープ) ルードヴィッヒ・イリッシュ指揮 インスブルッグ室内管弦楽団(USA Artsレーベル 472852 1983年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月08日
コメント(4)
-
雨が心配 / ビゼー 組曲「アルルの女」
明後日から2日間(9-10日)秋祭りだ。 8日は神社役員総出で準備に入る。 社務所の掃除、提灯吊り、幕張り、それにお札、お守り、祭りの安全祈願の木札など販売する物の準備などがある。天気予報では9日から雨。 10日も雨。 順延のできない祭りだから雨だけは勘弁してもらいたい。 朝7時から夜10時まで曳航しておれば、子供たち、青年団の若い衆たちが風邪を引くかも知れぬ。 曇り空でもいいから雨だけは降らないで欲しいと願っている。「とも」さんは社務所詰めでだんじり曳航には参加しないが、実は祭りを一番心待ちにしているのは「とも」さんかも?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」 ビゼー 組曲「アルルの女」実は、この曲と今日(10月7日)は何の関係もありません。 今日はスイス生まれの名指揮者シャルル・デュトワ(1936~)が生まれた日です。 その誕生日にちなんで彼の残している数多くの録音から「アルルの女」を採り上げました。シャルル・デュトワはオーケストラトレイナーとして抜群の能力があるのでしょう、カナダのモントリオール交響楽団の常任指揮者として1978年に就任して以来、このオーケストラはめざましい進歩を遂げたのか、それまでにほとんどレコードに録音が残されていなかったのにデユトワとのコンビ以来数多くのデイスクがリリースされました。 特にフランス音楽には素晴らしいアンサンブル、精緻と繊細な音楽表現でドビッシー、ラヴェル、サン=サーンス、フランク、ベルリオーズなどの管弦楽曲に味わい深い演奏を残しています。この曲は第1、第2組曲があり、フランス自然主義派の作家アルフォンヌ・ドーデ(1840-1897)の戯曲「アルルの女」の芝居上演に付帯された劇音楽で、後にビゼー自身が演奏会用に27曲ある音楽から4曲を選んで組曲としたもので、それが第1組曲。 その後ビゼーが亡くなったあとに親友のギローという人が残りの23曲とビゼーのオペラ「美しきパースの娘」の音楽から選んで出来上がったのが第2組曲です。第1組曲の「前奏曲」はプロヴァンス地方の民謡が力強く演奏されていて、まるでこの曲の代名詞的な旋律で誰もが何処かで一度は耳にしている有名な曲です。 第2組曲の「メヌエット」は「美しきパースの娘」の音楽から使われたハープとフルートで奏でる南フランス情緒いっぱいの名旋律で、フルートのリサイタルや録音には必ずと言っていいほどプログラムされる定番曲です。デュトワは、このビゼー(1838-1875)の「アルルの女」組曲を少し速めのテンポにしながら、じっくりと歌い込み、南フランスの情緒と香りをふんだんに表出しており、私の大好きなこの曲のデイスクです。 カップリングは同じくビゼーの組曲「カルメン」で、これもスペインの熱い血潮がたぎるような情熱的な表現の演奏です。(デッカレーベル UCCD5053 1986年10月 カナダ録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月07日
コメント(8)
-
タクシーのサービス / シマノフスキー 「アルトューズの泉」
昨日隣の駅から自宅までタクシーに乗った。 びっくりした。 「ありがとうございます、どちらまで?」タクシー運転手の言葉だった。いつもは乗車しても礼は言わない、着いて料金を払う。 お釣りを貰う。 降りる。 その間一言も発しない運転手ばかりで、とっくに文句を言う気力もなくなっていたからこの言葉は凄く新鮮に聞こえてきた。客を宅急便の荷物と同じように思っているのかと言いたくなる運転手ばかりにあたってきたから、こういう礼を言うことが当たり前なのに新鮮に聞こえる異常さに驚いた。感謝の気持ちがかけらもないコンビニストアの「いらっしゃいませ! おはようございます」の機械的な客への言葉にもうんざりするが、終始だんまりでサービスの何たるかを全く心得ない運転手には憤りさえ覚えることがあったが、この運転手の言葉には心がこもっていて、当たり前のことなんだが今どきこういう運転手もいるものなんだと思った。久しぶりに清々しい気分になった。私の妹は何をしてもらっても、例えば机の上にある新聞を渡してやっても、「ありがとう」の言葉がかえってくる。 家内もそうだ。 必ず「ありがとう」という言葉がかえってきた。「おはようございます」「こんにちわ」「こんばんわ」「ありがとう」「ごめんなさい」は人の輪を作り、人の「和」を創造する言葉だ。私も今日からもう一度これらの言葉を大きな声で口に出すことを心がけよう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日のクラシック音楽」 シマノフスキ ヴァイオリンとピアノのための「アルトューザの泉」(「神話」から)今日はポーランドの作曲家カルロ・シマノフスキ(1882-1937)が生まれた日です。 近代のポーランド音楽の先駆者で、現代音楽のような響きを持つ作品は魅力がある作曲家です。彼が遺した作品で「神話」という3曲から成るヴァイオリンとピアノのための音楽があり、その第1曲目が「アルトューザの泉」です。 これはギリシャ神話に出てくる水の精アルトューザを題材にしており、フランス印象派風のような作風でヴァイオリンの神秘的な響きがとても美しい曲です。今日は彼の誕生日に因んでこの曲を聴こうと思います。ムーリャ・グラフ(Vn) ナタリア・ゴウス(ピアノ)(ハルモニアムンデイ HMC901769 フランス輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月06日
コメント(8)
-
新聞で読んだ育児主婦の悩み / モーエンス・ヴェルデイケのハイドン「軍隊」と「時計」
「新聞で読んだ育児主婦の悩み」今朝の朝刊を珈琲ショップで読んでいてこんな記事が目に付いた。30代主婦。 5歳の子供と夫の家庭生活。 子供を産んだのが世間体と親を喜ばすためと思うようになった。 子供が嫌いでもなく、虐待もしていない。 しかし、育児がまったく楽しくない。 子供と遊ぶことに喜びを見出せない。 夫は子煩悩でそれを見るにつけて、自分ひとりで生活したいと思っている。 母親失格だろうか?こんな記事だった。 ノイローゼ一歩手前かもしれない。 あるいはほんとに子供を可愛いと感じない主婦かもしれない。 そこのところは短い文章では図りかねる。 しかし、ひょっとして母親像なるものを鋳型にはめ込んで、そこへ行けない自分を責めているのかもしれない。 子供は、特に自分の子供がまだ5歳なら毎日の変化していく様が楽しくてしょうがない時期だと思うが、ちょっとした子供への目線を変えてやればいいのにと思う。 このくらいの子供は敏感だから、母親のこうした態度に抵抗や淋しさを覚えて子煩悩なお父さんに傾いてしまい、いっそう家庭の中で孤立しているように覚えるのかもしれない。趣味とかを書いていなかったが、何か自分が好きなことをやるのもいいかもしれない。 四六時中育児という世界から抜け出るし、それがかえって育児の励みになると思う。いい子育てー少なくとも子供と一緒にいることが楽しい、嬉しい、幸せだと思うことができるようになって欲しいと願わずにおれない記事だった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・モーエンス・ヴェルデイケのハイドン「軍隊」「時計」交響曲先月からコロンビアミュージックエンターテイメントが嬉しい復刻盤をリリースしてくれている。 1950年代ー60年代にかけての「ヴァンガード」レーベルで発売されていたLP盤をCDにデジタルリマスターして廉価盤(\1,260)として売り出している。 先月の目玉は以前にこのページの「今日のクラシック音楽」で紹介したヨゼフ・シゲテイのバッハ「無伴奏ヴァイオリンソナタ」「パルテイータ」全曲盤だった。 (但し、紹介した盤は同じ原盤でもキングインターナショナルの発売)今月のリリースにも素晴らしいのがある。 チャイコフスキー 交響曲第4番 ストコフスキー指揮アメリカ交響楽団ベートーベン・ヴァイオリンソナタ全集 シゲテイ(Vn)アラウ(ピアノ)バッハ 平均率クラヴィーア曲集第1巻 ホルショフスキー(ピアノ)など。その中で目に止まったのはハイドンの「軍隊」と「時計」交響曲。 演奏はモーエンス・ヴェルデイケ指揮ウイーン国立歌劇場管弦楽団。実に懐かしい録音。 USA盤では出ていたがなかなか入手できなかった盤だったので、これが復刻されたことがほんとに嬉しい。1956年というほぼ半世紀前の録音だが、試聴して音の良さにまづ驚いた。 鑑賞にはなんの支障もない。演奏 これが凄い! この盤がLPとして初めてリリースされたときに雑誌「レコード藝術」で交響曲評論を書いておられた故村田武雄氏が好意的な批評を掲載されていたので、興味があったがまだ中学1年生の私には当時\3,800というステレオLPは高嶺の花だった。 その後朝日新聞の「試聴室」欄でも音楽評論家の故志鳥栄八郎氏も絶賛の記事を掲載していた。その後、20年ほど経ってLP廉価盤(\1,000)として再発売されてやっと購入できた1枚だった。 それまでに数多くの指揮者・オーケストラで聴いていた演奏と一線を画す素晴らしい録音を聴いて、両氏が絶賛したわけがわかった。 しかし、CD時代に移って行ったので手持ちのLPプレーヤーが故障、メーカーに部品がなくLP盤を全部処分したのでこの盤も知人宅へ貰われて行き、私の記憶から消えていった盤となってしまった。そこへ突然に「ヴァンガード名盤」シリーズとして復刻された。ヴェルデイケのこのハイドンは、まさに「優雅」「典雅」を絵に描いたような演奏で、カラヤン、トスカニーニ、ワルター、バーンスタイン、コリン・デイビス、プレビンなどの今日のハイドン演奏の名盤とは全く趣きが違っている。「軍隊」の開始楽章の序奏が流れた時には、「これだ! これこそハイドン!」と心が躍ったものであった。 オーケストラがウイーンフィル(国立歌劇場となっているが実質はウイーンフィル)で、コンサートマスターがウイリー・ボスコフスキー時代。 言葉で形容できないような、弦のしなやかさ、管楽器の柔らかさをうまく生かしたヴェルデイケの指揮は、ひと昔前の「良きウイーン」の薫を引き出した典雅そのもののハイドン。EMIからイギリスの大指揮者サー・トーマス・ビーチャムが指揮した2枚組みが再発売された名盤も、ハイドンのスペシャリストらしい柔和さに富んだ,エレガントで明るい響きの演奏だったが、このヴェルデイケの演奏は比較にならないほど「優雅」なハイドンを聴かせてくれる。あのLPに刻まれていた演奏が我が家に戻ってきた。(ヴァンガード原盤 コロンビアミュージックエンターテイメント発売 COCQ-83832 1956年ウイーン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 オッフェンバック 「パリの喜び」1880年の今日(10月5日)はフランスの作曲家ジャック・オッフェンバック(1819-1880)が亡くなった日です。 彼は「ホフマン物語」「天国と地獄」など多くのオペレッタ(喜歌劇)を残しています。 これらのオペレッタの旋律を集めてマヌエル・ローゼンタールが編曲したバレエ音楽「パリの喜び」があります。 原曲のオペレッタのメロデイーを使い、パリのカフェの悲喜こもごもを描いたバレエ音楽です。今日はこの「パリの喜び」を聴いてみようと思います。 全曲で40分ほどの、オッフェンバックの有名なオペレッタの音楽が実に効果的に編曲構成されている楽しいバレエ音楽です。お薦め盤 (フリップス レーベル PHCP-9338 1982年10月アメリカ録音)19歳からジャズピアノ録音を始め、ピエール・モントーに指揮法を学んだプレビンは、映画音楽、ミュージカルも手がけてアカデミー賞を4回も受賞している。 その後セントルイスやロンドン交響楽団などの指揮を歴任したあと、ウイーンフィル、ベルリンフィルの客演、録音などを残しており今やクラシック音楽界の重鎮的存在で、女優のミア・ファローとの離婚後、現在はヴァイオリニストのムターと幸せな結婚生活を送り、今月もチャイコフスキーのVn協奏曲をグラモフォンからリリースしています。この「パリの喜び」はピッツバーグ交響楽団の常任指揮者時代に録音されたもので、抜群のリズム感覚でパリのカフェの気分をたくみに描いた名盤だと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月05日
コメント(4)
-

静かな午後の秋 / バッハ ゴールドベルグ変奏曲
この道や行く人なしに秋の暮れ 芭蕉昨日は秋祭り(だんじり祭り)のだんじりの試験曳きが行なわれて、朝から町全体がざわざわとした何となく落着かない趣で、早くからお母さんに1年ぶりに袖を通してもらった子供たちが揃いの祭りのハッピを着て、町内を行きかって活気を呈しており、午後からだんじりの曳航が始まり、どこの町でも同じように試験曳きを行なっていたので、この市全体がお祭りムードに包まれた一日だった。それと打って変わって今日は静かな秋の一日が戻ってきた。 朝から登校する児童、生徒の声が路地を響き渡り、昨日の試験曳きを楽しんだ話題でもちきりの声が聞こえてきた。それが終るとまるで音がしない静かな町となり、深い秋の陽射しがいっそう秋彩、秋色を染めている。 このあたりは高齢者世帯が多くて、普段からあまり往来を行き交う人たちが少ないのだが、秋深くともなるとちょっとした音がいっそう静けさの響きを運んでくる。車やバイクが通るたびにいっそうの静けさを引き立てている。 部屋ではブラームスのピアノ三重奏曲が鳴っており、渋い音の響きが秋色にぴったりだ。こういう秋の午後もいいものだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 J.S. バッハ 「ゴールドベルク変奏曲BMW.988」1982年の今日(10月4日)今世紀の偉大なピアニストであったグレン・グールドが亡くなった日です。 常に斬新な曲への解釈、奏法でステージ、録音で話題を振りまいたピアニスト。 奇人としても有名でステージで30分近くピアノの前の椅子の高低を調整していたとかエピソードの枚挙のいとまがないほどの天才ピアニストでした。 ピアノ演奏を語るときに絶対に欠かせないピアニストの一人です。人によっては好悪の分かれる演奏家ですが、後世のピアノ演奏に大きな影響を残した人に間違いはなく、その早死にを惜しまれてなりません。 もっとも彼は1964年にステージ活動を辞めるという宣言をしてもっぱら録音活動に絞っていました。今日は彼の命日に因んで、遺されている録音から1981年4月から82年5月にかけて録音された彼の「白鳥の歌」とも言うべきバッハの「ゴールドベルク変奏曲」を採り上げました。この曲は主題の「アリア」から30の変奏を経て「アリア」に戻る大曲で、もともとカイザーリンク伯爵の不眠症を治すために作曲されて、それを伯爵のお抱え音楽家のゴールドベルクが演奏したと伝えられています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月04日
コメント(4)
-

孫娘 (お薦めCD盤に修正記事あり) / レスピーギ 「ローマの松」
2日前に静岡から孫の写真がPCに届きました。 身内の贔屓で可愛い。 妹がまだ孫娘を見ていないので写真を待ち焦がれていたので、早速携帯電話に転送してあげた。すぐに返信があり、「メチャ可愛い! 家族で絶賛!」。今が王様の孫娘よ、君はこの日本に命を授けられて幸せだね。 だれからも祝福されて、周りを幸せな気分にさせてくれて、「宝物」だ。 これからもお母さんやお父さんを不眠症にするくらいに夜中にお腹を空かして泣くんだね。 現に君の写真を撮って送ってくれたお父さんはすでに不眠症らしいよ。 幸せ気分を与えてくれる反面、お母さん、お父さんを困らせているんだね。 今のうちだ。 大いに困らせてやればいい。イラクや、アフリカなんかで生まれた赤ちゃんは悲惨な時代を迎えているよ。 それに較べると何て幸せなんだろうってお爺ちゃんは思うし、この先健やかに育って、大きくなれば平和な世の中になるように頑張っておくれ。近いうちにまた会いに行くからね。 そのときはお爺ちゃんの顔を見て泣かないでおくれ。可愛い孫、希空(みそら)へ 大阪のお爺ちゃんより ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 レスピーギ 交響詩「ローマの松」1967年の今日(10月3日)はイギリスの指揮者サー・マルコム・サージェント(1865-1967)が亡くなった日です。 イギリスは辛口のクラシック音楽ファンの多いところですが、国粋的な面があり、自国の音楽家には熱狂的に支持するところがあります。サー・マルコム・サージェントもイギリス国民に根強い支持をされていた指揮者です。 『典雅』という言葉がぴったりの演奏スタイルで、時には中庸すぎて無個性といった趣きがある人ですが、古典音楽の典雅さでは一級の指揮者でした。 遺されている録音はほとんどが有名ソリストとの協奏曲ですが、今日は命日に因んで彼の遺した唯一のレスピーギ(1879-1936)の音楽を聴いてみます。交響詩「ローマの松」 レスピーギの代表作で、イタリア人の彼がローマの有名な「松」の並木などを描写した音楽で、「静」と「動」を上手く描き分けた音楽で、終曲の「アッピア街道の松」はハリウッドの大歴史劇映画を思い起こさせるほどの迫力で、目の前を古えの「ローマ帝国軍団」が行進していく情景を覚えさせるほどです。マルコム・サージェントはこれをUSAの「エヴェレスト」レーベルに録音して「ヴァンガード」がリリースした1960年の35mmフィルム磁気テープに録音したアナログ時代の屈指の名録音で聴いてみます。現在このCDは廃盤となっているようですが、最近コロンビアミュージックエンターテイメントから「ヴァンガード名盤」シリーズが復刻されましたから、いずれこの名盤も再リリースされと思います。お薦め盤 サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン交響楽団(エヴェレスト原盤 EVC9018 USA輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月03日
コメント(17)
-

イチローの偉業・最多安打新記録達成(加筆) / 春はじめてのカッコーを聞いて
アメリカ人だ、日本人だということを超えて人間として、一人の大リーガーとしてのイチローを尊敬の眼差しで見つめる野球ファン。 連日イチローの世界記録到達への道がマスメデイアを席捲しています。 アメリカ大手新聞も一面トップで取り扱う野球好きアメリカ人を魅了してやまないイチロー。報道記事、ニュース画面を通して伝わってくるイチローに「極める人間」共通のオーラが感じられます。 小学校3年生で「こんなに野球の練習をしえいるから、プロ野球選手になれると思います」と文集に刻んだ凄さ。 小学生の頃から走る行く車のプレートナンバーの数字を見て、足し算をする訓練をしていたとか、彼のこれまでの日々のトレーニングの厳しさが連日のように報道されるたびに、私にはイチローと宮本武蔵が重なり合う。 勿論武蔵像は小説(吉川英次著 「宮本武蔵」)を通じてですが、「剣の道」を究めた武蔵と「野球」を極めようとするイチローが重なり合います。オリックス時代のイチローのバットスイングと今のイチローのそれとは明らかに違いがあります。 今のイチローは、まるでテニスラケットで野球の球を打っているかのような、しなやかさを感じます。 体、腰の回転がボールを野手のいないところに運ぶ理想のフォームになってきているのでしょう。 オリックス時代のフォームはまだそこまで感じませんでした。まるで「求道士」のような姿です。 そこには「たかが野球」と言わせない厳しい姿があり、「藝術」「芸術家」のオーラのようなものを感じます。257安打という記録保持者シスラーの孫が言う。「今まで大記録者であった祖父の名前は半ば消え去ってしまいかねないものでした。 しかし、イチローのお陰で祖父の名は82年経って、光をあてられました。 イチローに感謝しています」あと1本。 82年間封印され続けた257安打記録に到達、そしてその記録が破られようとしている。それから数時間後の第一打席で257安打目を放ち、続く第二打席で新記録を達成! 凄い!という言葉以外見つからない。どんな言葉を言ってもこの男を賞賛するに一番ふさわしい言葉がないかも知れない。 ただ、ただ、凄い!左打者と内野安打約60本を考えると、この記録を破れないかも知れません。 破る選手がいれば、それはイチロー本人でしょう。イチロー選手、おめでとう! そして、大きな夢のプレゼントをありがとう! ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 デイーリアス 「春はじめてのカッコーを聞いて」イギリスの作曲家フレデリック・デイーリアス(1862-1934)は自国の風情を描写した音楽を多く書いています。 それらの作品の中で、最も有名なのが「春はじめてカッコーを聞いて」という小管弦楽のための作品で、1913年10月2日に初演された曲です。カッコーの鳴き声が交わされる様を描写しながら、春の訪れの風情をしっとりとした情感で表現されています。お薦め盤「デイーリアス 管弦楽曲集」 サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 (EMI TOCE-7211 1969-1970年録音)デイーリアスの主だった管弦楽曲がカップリングされたCDです。 バルビローリ・サウンドと呼ばれる極上のワインのような、まろやかなオーケストラサウンドが楽しめます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(
2004年10月02日
コメント(10)
-
読売新聞「第4回高校生フォーラム 17歳からのメッセージ」グランプリ / 魔法使いの弟子
テーマ 「今までの自分、これからの自分」 グランプリ山口県徳山工校 中村未来さんの作品 部屋の掃除をしていた時にふと青色の丁寧に二つに折られた画用紙を見つけた。 開いてみると中には、原稿用紙。 タイトルは年頭所感。 思い出した! 小学6年の時のものだ。 3月生まれの私は年女ということもあって3学期の始業式に全校生徒の前でこれを読んだのだ。 読みかえしていると文の終わりに「強い風が吹いてもキレイに咲く花のように、今年は今まで以上に頑張りたいと思います」と書いてあった。 ドキッとした。 こんな言葉を書いていた時があったのか。 とても小学生が、ましてや自分が書いたものとは思えない言葉だった。 あれから中学・高校と「強い風が吹いてもキレイに咲く花」になれたか。 人から何か言われるたびにうるさいな、とか思っている私。 ささいな一言でケンカしてすぐ周りにあたる私。 決して風に身をまかせて揺れている花ではない。 今思えばこの言葉を書いていたあの頃が一番美しい花を咲かせていたと思う。 しかし今からでもできる。 今から枯れかけている自分に水をやろう。 相手のことも考えればケンカも起きず、自分の心の花に栄養をやれる。 心の太陽で「強い風が吹いてもキレイに咲く花」をもう一度咲かせよう。 過去の自分に会うのもたまにはいいもんだ。(終)読売新聞 2004年9月30日付け朝刊より17歳の高校生に教えられたともさんでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・今日のクラシック音楽 デユカス 交響詩「魔法使いの弟子」1865年の10月1日にフランスの作曲家ポール・デユカス(1865-1935)が生まれています。 デユカスといえばこの「魔法使いの弟子」がすぐに出てくるくらいに有名な一曲です。 ちょうどベートーベンといえば「運命」のようなものです。「ゲーテのバラードによるスケルツオ」という副題がついており、序奏とコーダ付きのスケルツオ形式をとっています。内容は魔法使いの弟子が先生の留守に、与えられた水汲みの仕事をさぼるために箒に呪文をかけて水を汲ませて桶に入れ、それを運ばせるのですが水が一杯になっても、箒は水汲みをやめません。 怒った弟子は箒を折ると2本になってますます水汲みをするので水があふれてきます。 「止めろ」の呪文を忘れたからです。 困っているところに魔法使いが帰ってきて呪文を唱えて治まります。これを管弦楽で箒が桶を運ぶところは3本のバスーンで描くなどユーモラスに描いています。ウオルト・デイズニーの戦前の映画で「ファンタジー」という音楽映画がありました。 すべてアニメで、クラシック音楽にあわせて絵が動く映画で、ベートーベンの「田園」 バッハの「トッカータとフーガニ短調」 ストラビンスキーの「春の祭典」などと共にこの曲が全曲演奏されていました。 このときの指揮者がレオポルド・ストコフスキーでした。この映画を私は中学1年(1957年)の時に映画館で観ましたが、その映画のなかでミッキーマウスが弟子になっていました。 この曲を聴くといつもあの映画のミッキーマウスを思い出します。お薦め盤 「魔法使いの弟子~デュトワ・フレンチコンサート」 シャルル・デュトワ指揮 モントリオール交響楽団(LONDONレーベル F00L-2301 1987年10月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2004年10月01日
コメント(12)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-

- 吹奏楽
- ちくたくミュージッククラブ7thコ…
- (2025-11-22 23:43:42)
-







