2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年04月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

春日大社の藤
「春日大社の藤」今年の藤の花は奈良公園に在る春日大社・神苑内の藤を撮ろうと決めていましたので、もうそろそろ見頃だろうと思って行ってきましたが、まだ少し早いようでした。勿論開花はしていますが垂れ下った房一面の花が開花しておらず、満開までまだ数日かかるかなという感じでした。 5月1日にもう一度訪れる予定にしています。写真の掲載はそのあとにしたいと思っています。 JR奈良駅からは徒歩で2.5km、約25分くらいのところです。JR奈良駅前からバスがありますからそれに乗ればいいのですが、興福寺境内を抜けて奈良公園を散策しながら歩いて大社へと向かいました。 公園には鹿が群れており観光客が通ると餌の「鹿せんべい」をねだったり、何か食べ物を呉れるものと思って近づいてきます。 道には屋台の「煎餅売り」が店を出しており150円で売っていました。カメラ機種 Pentax K10Dプログラム AE 露出補正なしTv 1/250 焦点距離 250mmISO 200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro天気 薄日公園には大木が数多くありそのうちの何本かには説明の看板が掲げられていますが、この大木には説明がありません。樹齢がわかりませんが大きな樹でした。カメラ・レンズは上の画像と同じプログラム AE 露出補正なしTv 1/90 焦点距離 34mmISO 200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス天気 薄日またこんな風にまるで「オブジェ」のように造られたかのような老木もありました。カメラ・レンズ共に上記に同じプログラム AE 露出補正なしTv 1/90 焦点距離 28mmISO 200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス天気 薄日さて肝心の藤の花ですが神苑に行ってみるとまだ満開ではなくて少しさびしい程の咲き具合でした。 撮ってみましたがここに掲載するほどの写真ではなく、後日改めて出直そうと思いました。明日(5月1日)もう一度行ってみようと思います。神苑は植物園のようなところで様々な花(木になる花)が植えられていますが、写真になったのは下の山吹だけでした。 ほろほろと山吹散るか滝の音 芭蕉 プログラム AE 露出補正 -0.5Tv 1/90 焦点距離 250mmISO 200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス天気 薄日撮影地 奈良公園 2008年4月28日
2008年04月30日
コメント(0)
-

小手毬~春の長居植物園
「春の長居植物園」 小手毬小さな花を毬(まり)のようにして丸く盛り上がった白い花。 枝ぶりによって咲いている感じが変わる花。 今では家の庭の垣根から長い枝にぶら下がっているのをよく見かけます。近所でも撮れる花ですが、可憐に咲いているので撮ってきました。ばら科の花でシモツケ属。 4月から5月中旬まで咲いています。 中国から渡ってきたと伝えられています。蹴鞠のように咲いており「小さな手鞠」から「小手毬」と命名されているようです。枝が弓状に垂れ下がるところに情緒があります。 カメラ Pentax K10Dプログラム AE 露出補正なしTv 1/250 焦点距離 180mmISO 200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス三脚使用レンズ Tamron Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro天気 曇りプログラム AE 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 158mmISO200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス三脚使用レンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro天気 晴天撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月23日
2008年04月29日
コメント(0)
-

牡丹~春の長居植物園
「春の長居植物園」 牡丹この日も午後からの仕事でした。朝からあまり風もなく良く晴れた日でしたから、午前9時半の開園に間に合うようにカメラ・三脚持参で大阪市立長居植物園に出かけ、その後で仕事に出ました。長居へ行ったのはひょっとして牡丹がもう咲いているのではと思ったからなんですが、見事に開花して見頃を迎えていました。 定年退職したらしい男女のカメラ好きがたくさん植物園を目指して歩いていましたから、期待していましたがその通りでした。 陽射しが少しきついかなと感じながらも、できるだけ逆光で撮れるポジションを探して歩き、柔らかい牡丹の感じを出そうと努めました。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月23日
2008年04月28日
コメント(2)
-

シャガ~春の長居植物園
「春の長居植物園」 シャガこの花は先日も掲載しましたが花の咲き具合と撮り方に不満が残っていたので、長居植物園を訪れた際に群生で見事な花が咲いていたのと、この花が好きなのでもう一度掲載します。カメラ Pentax K10Dプログラム AE 露出補正なしTv 1/350 焦点距離 158mmISO 200 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス三脚使用レンズ TAMRON Aspherical 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro 撮影条件は上記に同じ 天候 晴れ撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月23日
2008年04月27日
コメント(2)
-
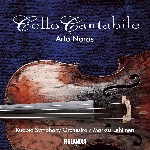
火鉢に切り花/チェロ名曲集
「珈琲ブレイクの音楽」 チェロ名曲集久しぶりに音楽の話題です。このところカメラ熱にうなされていてすっかり音楽への愛着がどこかへ飛んで行ったような感じでしたが、毎日好きな音楽を聴きながら過ごしていました。 今日はチェロの話題です。チェロは、最初はヴィオラ・ダ・ガンバという名前でバロックに時代に通奏低音楽器として使われていましたが、徐々に市民権を得るようになりバロック時代でも、チェロ協奏曲としてデビューしました。 その頃の有名曲ではボッケリーニの協奏曲、そして古典派時代にはハイドンの協奏曲などで脚光を浴びるようになりました。ベートーベンはチェロ協奏曲を書いていませんが、5つのチェロ・ソナタによってこの楽器の地位を確立しています。 そして1889年パブロ・カザルス(チェロ奏者・指揮者)によってあの大バッハの無伴奏チェロ組曲が発見されて、バッハがベートーベンの前に偉大なチェロ作品を書き残していることがわかりました。チェロは、女性を想像させるような体形でありながら、そのしとやかな弧線から逞しいタッチで、時には豪快に、時には優美な音楽を奏でる楽器として親しまれています。チェロが朗々と旋律を歌う美しさ、音を出した途端に惹きつけられる色彩豊かな音色、まるで人間の古老の持つ、酸いも甘いも渋さも兼ね備えたような色合い、明るい輝きもあれば、ほの暗い憂愁の美しさもたたえた彩り、聴く者の心を落ち着かせる不思議な楽器・チェロ。そのチェロに魅せられて数多くの作曲家が小品として残した作品が数多くあります。 またオリジナルがピアノ曲やヴァイオリン曲、フルート曲でも後世の人がチェロ演奏用に編曲したものもあります。私はブログの原稿を書き終えてコーヒーブレイクなどの時間に取出して聴くディスクがあります。フィンランドの名チェリスト アルト・ノラスが演奏した「アンダンテ・カンタービレ」というチェロの小品ばかりを演奏したCDです。ノラスが弾くチェロからは例え小品と言えども曲の隅々まで光を照らしたような神々しいまでに輝く音色、雄大な音楽性、深々とした低音の響き、伸びやかな高音、しっとりとした情緒などまさにチェロの響きの美しさを存分に歌い上げた至高の演奏が聴けるディスクです。どこか哀愁ただよう晩秋に似合いますが、春の艶めかしい情緒に包まれた夜の珈琲ブレイクに聴くにもぴったりのディスクです。愛聴盤 アルト・ノラス(チェロ) マルクス・レヒティネン指揮 クオピオ交響楽団(Finlandia原盤 ワーナー・ミュージック WPCS11761 2003年4月録音)収録曲1. チャイコフスキー:アンダンテ・カンタービレ2. 同:奇想的小品3. 同:夜想曲4. グラズノフ:吟遊詩人の歌5. シベリウス:讃歌「わが心の喜び」6. 同:祈り「わが心からの」7. サン=サーンス:アレグロ・アパッショナート ロ短調8. ドヴォルザーク:森の静けさ9. フォーレ:エレジー10. ブルッフ:コル・ニドライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 火鉢に切り花京都・祇園の狭い路地を歩いていますとこんな風景に出会いました。 昔懐かしい火鉢を花瓶に見立ててその中に春の花たちを切り花にして活けているのです。 奥深く感じられる小路がいきなりパッと明るくなったような雰囲気で、思わずカメラを向けてシャッターを切っていました。 この火鉢への投げいれが祇園の街並みと静謐な小路の雰囲気にぴったりと合う情景でした。 撮影地 京都・祇園花見小路 路地裏
2008年04月26日
コメント(4)
-

京都・祇園を歩く
「京都・祇園小路を歩く」嵯峨野嵐山からJRと地下鉄を乗り継いで京阪三条へ。そこから祇園まで徒歩10分で四条通りと花見小路に出ます。 花見小路と四条通りの交差点を右折すると、そこはもう祇園。折から「都おどり」が開催されていて、どの家の軒先にも「都おどり」の赤い提灯がぶら下がっています。平日にも関わらず好天気に誘われたのかここを訪れる人の絶えない日でした。そんな観光客に混じって私も撮影をスポットを探し歩いていました。 この街並みを歩いてすぐにわかるのが小路が多いこと。 スポットはこれだと決めて絵になる小路を探しながらの撮影でした。約1時間半の探訪でした。祇園の街並みも碁盤状に近い作りで上の写真のような小路が無数と思えるほどにあります。格子戸をカラカラと開けていきなり和服の色あでやかな姿が出てきます。 都おどりにふさわしい光景でした。残念ながらそのスナップを撮ることが出来ませんでした。祇園の街に入ってすぐ目に入るのがこの赤い提灯です。「都おどり」の期間中はどの家、どの店の軒先にもこれが掲げられており、祇園あげての催し物とすぐにわかります。もう一つ京都の初夏・夏の風物なのが「簾(すだれ)」。 京都特有のこの簾がどの家にもかけられています。 祇園では早々とこの簾が掛けられていました。今回の撮影旅行で撮りたかったところをほぼ撮れたので満足でした。ただ残念なのは桜満開の時期を外してしまったことですが、 それは来年きっと訪れようと思っています。 次回は紅葉の時期にもう一度嵯峨野に行こうと思っています。
2008年04月25日
コメント(4)
-

京都嵯峨野の散策
「京都 嵯峨野を散策」友人の美帆さんとお互いにカメラを持って京都 嵯峨野を散策しながら、印象に残った風景を撮ってきました。 今回の嵯峨野では25枚程度撮っただけでしたが、同行の美帆さんは何と500枚を超える写真を撮っていたのに驚きました。 天龍寺~竹林~嵯峨野嵐山(トロッコ列車)~常寂光寺~落柿舎~化野念仏寺~愛宕念仏寺とJR嵯峨嵐山駅から約3kmの道程を歩いてきました。 しかし写真は気に入った風景だけを選んで撮ったのでそれほどありません。 嵯峨野のあとは祇園へ行って祇園小路を撮って今回の京都の旅は終わりました。祇園の街の様子は明日にでも掲載します。天龍寺足利尊氏が後醍醐天皇の崩御の際に建立したとされる臨済宗のお寺。庭園には見事な大きなしだれ桜がありますが、すでに葉桜になっていました。化野念仏寺9世紀の初めに空海によって開山されたと言われているお寺。 野ざらしになっていた遺骨を弔い無縁仏として供養されています。愛宕念仏寺真言宗のお寺として七堂伽藍を備えた立派なお寺だったそうですが、現在は天台宗の寺として本堂だけが残されています。釈迦の弟子として仏教を広めたお坊さんのことを阿羅漢と呼ぶそうですが、昭和56年から一般参拝者が自ら石仏を掘って境内に安置しており、当初は五百羅漢と呼ばれていたのが、今では千二百体もあるそうです。 私の今回の嵯峨野巡りはまさにこの「羅漢さん」の撮影にありました。一体として同じ石仏(羅漢)はなく、個性あふれる表情が参拝客を和ませてくれます。
2008年04月23日
コメント(2)
-

花水木~春の花
「春の花」 花水木これも桜が散ったあとに開花する春の代表花の一つ。 街路樹としても植えられており手入れさえ怠らなければびっしりと木に花をつけています。 家の庭・公園などにもよく見かける花です。この花が開いてしまう前の姿をとても好きで、毎年蕾の状態の時に撮っています。今年も知人宅の庭でたくさんの花をつけていました。その中から開く前の花を探して撮ってきました。 撮影地 大阪府和泉市 2008年4月20日
2008年04月21日
コメント(2)
-

ドウダンツツジ~春の花
「春の花」 ドウダンツツジ門扉の前の植え込みや庭で咲く白い小さな花がびっしりと咲くドウダンツツジ。 これも春を代表する花の一つです。撮影地 大阪府和泉市 2008年4月8日
2008年04月20日
コメント(4)
-

ハナニラ~春の花
「春の花」 ハナニラ清楚な感じの春の花の代表の一つ、ハナニラ。 長居植物園を訪れた時は満開でした。ゆり科南アメリカ原産。 葉っぱがニラの匂いがします。葉が韮に似ているので「ハナニラ」と呼ばれているそうです。 カメラ機種 Pentax K10Dプログラム AE F4.5 露出補正なしTv 1/250 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス 分割測光ISO 400 三脚使用 天気 曇天レンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm Macro撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月8日
2008年04月19日
コメント(4)
-

ソラマメ~春の花
「春の花」 ソラマメ豌豆の花を掲載すればこちらも載せなくてはと思ってアップしました。 空豆(ソラマメ)、これも色の種類がありますね。花の色によって出来る豆がどう違うのか知らないのですが、種類が違うのでしょうか。この空豆を湯がいて塩味で食べるとおいしいですね。初夏や夏のビールの肴にぴったりですね。 撮影地 大阪府和泉市 2008年4月13日
2008年04月18日
コメント(2)
-

豌豆の花~春の花
「春の花」 豌豆の花この花が咲き出すといっそう春らしさを感じます。今では畑で満開の花です。白い花と紫の2種類の花が咲いています。 カメラ機種 Pentax K10DSv モード F6.3 露出補正 -0.5Tv 1/60 焦点距離 300mmISO 100 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル フォーカス三脚使用 天気 曇天レンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年 4月4日
2008年04月17日
コメント(4)
-

白タンポポ~春の野草花/聖火リレー
「春の野草花」 白タンポポ今は黄色いタンポポが我が世の春を謳歌しています。 道端・公園・野原・空き地・畑や田圃の畔に咲き誇っています。 それら黄色のタンポポに混じって異彩を放っているのが「白タンポポ」。西日本限定で咲いている変わり種タンポポ。関東では咲かないそうです。友人宅の庭では毎年花を咲かせる春到来を知らせる野草花の一つです。 カメラ機種 Pentax K10DSv モード F6.7 露出補正 -0.5Tv 1/350 焦点距離 100mmISO 100 分割測光ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス三脚使用 天候 晴れレンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年4月13日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「聖火リレーに思う」今世界の五大陸をオリンピックの聖火リレーが行われています。 しかし、どうみても中国の国家威信をかけたリレーとしか映りません。中国から派遣された「聖火警備隊」なる正体不明のチームがランナーを取り囲み妨害する(これ自体を私は容認しませんが)姿は醜悪です。アメリカではリレーコースを変更して市民が祝う気分を壊してまで、市民から歓迎されないままに続行する姿に、聖火リレーの存在価値そのものに大いなる疑問が湧きます。長野だってイヴェント中止決定をしています。ならばリレーそのものを辞退すればいいのにと思います。 チベット問題を起こしてリレーが始まり、中国政府の人権問題に抗議する世界中のチベット系人民の姿、それを支援するヴォランティア。 しかしその姿は時には醜悪を見せています。こんなリレーなら中止すればいいのにと思います。 ただただ中国国家の威信だけにこだわっているようにしか見えません。オリンピックの精神が政治に左右される、またモスクワ五輪のときのような様相を呈しています。 これでは世界中の代表選手、オリンピックを観戦したい人々の純粋なスポーツを楽しみたい心を傷つけるだけです。大いに疑問に思う聖火リレーです。
2008年04月16日
コメント(4)
-

大犬のふぐり~春の野草花
「春の野草花」 大犬のふぐりいつからだろうかとても小さな花~野草花を撮りたいと思うようになったのは。定かではにけれどやはりインターネットで観た感動が「それなら私も」となったのかも知れません。2年前にマクロレンズを買って撮りだしてから病みつきになりました。しかし私の住んでいるところは開発の波でどんどん田圃や畑、丘陵が破壊されて住宅地に変わっているので、撮りたいと思う野草花を見つけることが難しくなりました。もっと山深いところに行けば撮れると思うのですが、時間的な制約もあり難しい。私は強度の色弱のため若い時の3度の運転免許取得試験で「色弱」のために免許を取れず、以後諦めて今日に至っています。車の運転さえ出来たら活動範囲も広がり時間的制約から解放されますが、どこへ行くのもバスか電車利用を余儀なくされるので、活動範囲にも制約があります。そんな私に癒しを与えてくれるのが「仏の座」・「姫踊り子草」・「烏野豌豆」・「スミレ」などです。 そんな中でも毎年挑戦しているのが「大犬のふぐり」です。あまりに小さく背が低い花ですから、撮影位置がポイントになる花の一つです。 いつもは出来るだけ道具を全て持って撮影に行くようにしていますが、やはり持たない時に限っていいポイントを見つけることがあります。今日は大好きな「大犬のふぐり」です。カメラ機種 Pentax K10DSv モード F3.5 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 100mmISO 100ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス測候方式 分割測光三脚使用レンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm MacroSvモードにしたのは当日は強い風が吹いていて、この小さな花も右に左に大きく揺れていたからですが、やはり無理があったようです。 低台を使って撮りましたが(2枚目)これが限度でした。あと2~3cm高い位置から撮ることが出来たら良かったのですが、また出直して撮ってみたいと思っています。撮影地 いずれも大阪府和泉市 2008年4月13日
2008年04月15日
コメント(4)
-

長居植物園の春~紫花菜とチューリップ
「長居植物園の春」 紫花菜とチューリップ4月8日に駆け足で訪れた長居植物園。春本番を思わせるかのように花たちが咲いていました。あいにくの曇天でしたが、写真撮影には良かった天候でした。 ただチューリップなどの華やかな花たちを捉えるのにはちょっと暗い天気でした。それでも薄日が射してくるのを根気強く待つこともありました。今日は「紫花菜」と「チューリップ」を掲載しておきます。紫花菜カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F6.3 露出補正 +0.5Tv 1/180 焦点距離 300mm分割測光 ISO 200ホワイトバランス オートマニュアル フォーカス三脚使用レンズ TAMRON Aspherical XR Di 1:3.5-6.3 28-300mm Macroチューリップ 絞り優先 F5.6 露出補正 +0.5Tv 1/500 焦点距離 180mm分割測光 ISO 400ホワイト バランス オートマニュアル フォーカス三脚使用レンズ TAMRON Aspherical XR Di 1:3.5-6.3 28-300mm Macroプログラム AE F6.7 露出補正 +0.5Tv 1/250 焦点距離 158mm分割測光 ISO400ホワイト バランス オート三脚使用レンズ TAMRON Aspherical XR Di 1:3.5-6.3 28-300mm Macro撮影地 いずれも大阪市立長居植物園 2008年4月8日
2008年04月14日
コメント(2)
-

若葉~長居植物園の春
「長居植物園の春」 若葉~花水木花が咲き始めて瑞々しい気分に包まれ、春を謳歌するのははなだけではありません。新芽を噴き出して新緑の魅力を伝えてくれるものに「若葉」があります。 花と同時に萌えるような黄緑色の若葉を撮るのもおもしろいですね。花水木の若葉~調和の世界カメラ機種 Pentax K10Dプログラム AE 露出補正 +0.5Tv 1/125 焦点距離 300mmISO200ホワイト・バランス オートマニュアル フォーカス三脚使用レンズ Tamron Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro天気 曇天 絞り優先 F6.3 露出補正 +0.5Tv 1/125 焦点距離 300mmISO 200ホワイト・バランス オートマニュアル フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3天気 曇天撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月8日アオキの若葉~「萌え」プログラム AE F8.0 露出補正なしTv 1/500 焦点距離 100mmISO 200レンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm Macro天気 わずかな陽射し撮影地 大阪府和泉市 2008年4月11日
2008年04月13日
コメント(4)
-

牡丹が咲いた!
「春の花」 早咲き牡丹今日は長居植物園シリーズのお休みをいただいて近所で咲いた花の紹介です。うちの斜め前のおうちの庭で牡丹が咲きました。 毎年桜の散る頃に咲く「早咲き牡丹」です。昨日の早朝出かける前に覗いてみると咲いているではありませんか。出かけるのを一時中断して早速撮影に取り掛かりました。このご主人はもう80歳なんですが毎日庭の花たちに丹精込めて育ておられます。庭が終わる徒歩5分のところにある畑で四季の野菜を育てておられます。今年も見事に咲きました。カメラ機種 Pentax K10Dプログラム AE 露出補正なしTv 1/500 焦点距離 100mmISO 400ホワイト・バランス オートマニュアル フォーカスレンズ Pentax smc DFA 2.8 100mm Macro天気 曇天 プログラム AE 露出補正なしTv 1/350 焦点距離 100mmISO 400ホワイト・バランス オートマニュアル フォーカス機種・レンズ・天気とも1枚目と同じ撮影地 大阪府和泉市 2008年4月11日
2008年04月12日
コメント(6)
-

花水木~長居植物園の春
「長居植物園の春」 花水木時間がなくて植物園全体を歩いたわけでないので、まだまだ花がたくさん咲いているはずですが、4月8日(火)は半分もあるかずに園を出て行きました。また今度改めて一日でもかけて訪れてみようと思っています。ムスカリの群生に迎えられて入った植物園。 その群生が終わったところに花水木が開花していました。いつもここで花水木の花を撮っているのですが、今年はちょっと変わった形と色の花水木が咲いていました。枝ぶりの面白いのを探してこれを見つけました。カメラ機種 Pentax K10Dプログラム AE F4.5 露出補正 +0.5Tv 1/250 焦点距離 73mmISO 200ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月8日
2008年04月11日
コメント(4)
-

長居植物園の春
「長居植物園の春」 ムスカリ私の画像のネタ元となる大阪・長居植物園にも春が来たようです。それほど多くの種類の花たちが咲いているわけではありませんが、自宅から電車(JR各駅停車)で30分ほどで行けるので四季折々に訪ねています。昨年は体調を崩してほとんどカメラを持つこともなかったのですが、今年は元気になって毎日でも撮影したい意欲に駆られています。長居植物園の春の花はどうかしらと思いながら、4月8日(火)の午前に訪れました。午後から仕事が入っていたので、長い時間の滞在はできませんでしたが前回よりもいっそう春らしい佇まいを見せていました。 今日から数日は撮ってきました「春の花」を掲載しようと思っています。植物園の正面入り口を入るとまづ「ムスカリ」の群生が迎えてくれました。 毎年同じところに咲いているのですが、これほどに咲いている時期に来たのは初めてなんでしょう。びっしりと遊歩道脇に咲き乱れていました。カメラ機種 Pentax K10DプログラムAE F4.5 露出補正+0.5Tv 1/250 焦点距離 100mmISO 400ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm Macro天気 極めて曇天撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月8日
2008年04月10日
コメント(10)
-

散る桜
「散る桜」祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす。 驕れる者久しからず、ただ春の夜の夢の如し。 猛き人もついに滅びぬ、ひとへに風の前の塵に同じ有名な「平家物語」の冒頭の文章です。散る桜 残る桜も 散る桜 良寛良寛和尚の辞世の歌とも言われている桜を詠んだ有名な句。 良寛作とは定かでなく未だに定説として誰の句かはっきりしませんが、この句もまた「平家物語」冒頭文に通じる「生きる者・物」への哀れさを歌っています。 生あるものは必ず死ぬか消滅する、という理を表した句とも読める俳句。花の色は移りにけりな いたずらに 我が身世にふるながめせしまに 小野小町これも有名な小野小町の詠んだ歌。桜(花)の命が短いのも我が人生にも似たるよな、と桜が散って行くのを自分の人生に例えた歌。一週間前はあれほどに人の心を浮き立たせた桜も、花びらは水の中。 蓮の残骸と一緒に栄枯盛衰を物語る一風景です。長居植物園の蓮池に蓮の残骸と共に浮かぶ桜の花びらが妙に胸にこたえました。水辺に浮かぶ桜の花びらは人の命のはかなさを教えているようでした。一回きりの人生、その人生にも「黄昏」が訪れた年になり、せめてこれからの余生を悔いのなきように過ごそうと改めて思いました。今日は午後から仕事なので朝の開園時間(午前9時半)と同時に長居植物園に撮影に出かけ、「春の花」たちを撮ってきました。 桜のように短い命を散らした花もあれば、花水木のように若葉を出しながら開花している木、チューリップやムスカリのように「我が世の春」を楽しむ花たちもありました。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F5.6 露出補正なしTv 1/350 焦点距離 63mmISO 200ホワイト・バランス オートマニュアル フォーカス三脚使用レンズ TAMRON Aspherical 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro天気 曇天撮影地 大阪市立長居植物園 2008年4月8日
2008年04月09日
コメント(8)
-

大和郡山城址の桜
「春の花」 大和郡山城址の桜4月3日に奈良県・大和郡山の城址公園の桜を撮影に出かけてきました。天候は晴れたり曇ったり。 陽が射してくるのをしばし待ちながらの撮影でした。公園の見事な桜並木にはすでにブーシートが敷かれて、花見客が弁当・酒などを拡げて思い思いに桜を楽しみ姿があって、撮影を目的に行った者には迷惑となりましたが、それも季節の風物かと諦めて人のいないスポットを探して歩いて撮ってきました。本丸に立てば二の丸花の中 上村占魚ここは城址ですから本丸もないただ門のある建物が復刻で残っているだけでした。その建物の石垣に堀が残されていて、桜がその堀に覆いかぶさるように咲いていました。堀を囲む塀の後ろに回るとこういう風景でした。ここはさすがに桜の木の背が高くて人が映りません。 撮影データーお城の桜カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F8.0 露出補正 +0.5Tv 1/180 焦点距離210mmホワイト・バランス オートマニュアル フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro2枚目はカメラ同じ絞り優先 F8.0 露出補正+0.5Tv 1/180 焦点距離 100mmホワイト バランス オートマニュアル フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm Macro撮影地 大和郡山城址公園 2008年4月3日
2008年04月07日
コメント(4)
-
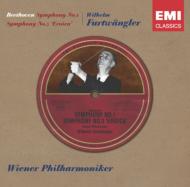
「英雄」交響曲/クリスマスローズ
「珈琲ブレイクの音楽」 ベートーベン作曲 交響曲第3番変ホ長調 「英雄」ルードヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)の伝記を読みますと、必ずと言っていいほど出てくるエピソードがあります。 ベートーベンの友人が尋ねた質問。 「あなたはこれまでに(まだ第九が書かれていない時期)書いた作品で、どの曲が一番好きでしょうか?」 ベートーベンは躊躇なく答えたそうです。 「そりゃあ、第3番の交響曲です」当時のベートーベンの交響曲で絶大な人気を誇っていた第5番「運命」ではなく、不評であった第3番を挙げたことにこの友人は「どうして?」と訝ったそうです。この第3番が発表されるまでは、交響曲の演奏時間はせいぜい30分間くらいの長さでした。 ところが第3番は50分を超す長大な曲なので、長さ故に評判は芳しくなかったそうです。 それに強烈な人間の「個」を表現している音楽で、それまでの「古典派サロン風」音楽とかなり違ったものなので、当時はそれも不評の理由だったかも知れません。第1番・第2番とは表現されている音楽が変わっています。 彼の9曲の交響曲を発表順に聴いていけばよくわかります。 第3番から劇的に音楽世界が変わっています。 貴族の「サロン」から脱出した人間の尊厳まで表現した、それもかなり激しく主張されています。この第3番をきっかけに、のちに「傑作の森」と呼ばれる真のベートーベン音楽の「強い主張」の表れと言っても過言でない、それまでの作品と決別するかのような交響曲となっています。ベートーベンはあの有名な「ハイリゲンシュタットの遺書」を1802年に書いています。 第3番「英雄」の完成が1804年です。この第3番が書かれる少なくとも2年前にはベートーベンは、自分の耳の病(難聴)に気が付いていて音楽家としての致命的な病に苦悩していたのでしょう。 それを苦にしての「遺書」でした。 一度は書いた絶望の淵の「遺書」からベートーベンは不屈の耐えしのぶ・逆境に打ち勝つ精神力で不死鳥のように蘇ったのです。与えられた運命に負けず、その運命を打ち破る最大限の努力をすることの大切さ・そこから抜け出た時の苦悩から歓喜へという強い精神力を音楽で表現する、ベートーベン特有の「人間性」を表現した音楽の最初の曲がこの第3番ではないでしょうか。それゆえに友人の質問に「第3番です!」と答えたのだと思います。この第3番以降、彼は150曲ほどの音楽を書いていますが、前述のように「苦悩から歓喜へ」の図式は変わることはありませんでした。 ベートーベンの音楽表現の根幹を成す思想として表現され続けています。 まさにこの「英雄」交響曲がその出発点であったのかも知れません。第1楽章冒頭の主和音の2度の叩きつけるような音が、ベートーベン自身が「遺書」と決別する明確な意思の表れであり、前向きに「耳の病」と闘う決意の表れであり、古典派の「サロン風」音楽から強烈な「主張」の表れで、その強烈さが芸術作品へと高めていくという「ロマン派音楽」への橋渡しで、まさにドイツロマン派音楽への扉を開ける主和音であると、昨日何度も聴いているうちに感じたことでした。その主和音によって扉が叩かれ、続いて現れる雄大な旋律の第1主題によってベートーベンの強固な尊厳さえ感じられる意思を感じます。 この旋律の情感は以後のベートーベン音楽の雄渾・壮大なスケール、どっしりとした、びくともしない安定感のある、そこに身を寄せてもしっかりと支えてくれる、旋律の始まりではないでしょうか。約15分間の長さの雄大・壮大なスケールの第1楽章が全曲の白眉だと感じています。 昔からこの楽章だけをよく聴いていました。続く第2楽章は前例のない「アダージョ・アッサイ」の葬送行進曲となっています。 ここにもベートーベンの天才的な技法の巧みを感じます。 連綿と嘆き悲しむような曲想が主題を奏するオーボエによって見事に表現されています。 しかしこの主旋律にはのちのチャイコフスキー音楽のような寂寥感をあまり感じません。 深い沈みこむような旋律と曲想なのにとても「心静かな」情感を感じます。 うがった感じ方ですが、ベートーベン自身が「耳の病」と立ち向かう前の「心の静けさ」ではないかと思えます。第3楽章「スケルツォ」で特筆すべきは3本のホルンによる3重奏は圧巻です。 楽器の晴朗性を見事に活かした「スケルツォ」の名品です。第4楽章の「変奏」は灼熱化したフル・オーケストラによる全奏で始まります。 バレエ音樂「プロメテウスの創造物」というベートーベンの作品から主題を採り、それを7つの変装でつないだ圧倒的な音楽で、ここにきてベートーベンがどんな困難にも負けずに立ち向かうという強い精神力の表れが具体化した音楽表現だと思います。この曲はフランスのナポレオンに捧げるつもりで書かれていたのが、彼が皇帝に就いたと知って「俗物ナポレオン」を罵って、楽譜表紙に「ある英雄の思い出のために」と書き直したという有名なエピソードから離れて聴いてみた感想を綴ってみました。1805年の今日(4月7日)、交響曲第3番「英雄」がベートーベン自身の指揮でウイーンで初演されています。愛聴盤(1) フルトヴェングラー指揮 ウイーンフィルハーモニー(EMIレーベル 5858212 1952年録音 海外盤)まさに「不滅の名盤」「人類の遺産」とも大げさに表現できる輝きに満ちた生命力と熱気に満ちた音楽を隅々まで感じられる演奏です。(2) ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮 ウイーフィルハーモニー (DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD7053 1965年録音)ウイーンフィル最初のベートーベンの交響曲ステレオ録音。 まろやかな・柔和な・温かい・しなやかなサウンドを十全に引き出した、イッセルシュテットの至芸が冴える、フルトヴェンングラー盤と対極をなす、晴朗な実に柔らかい演奏が魅力のディスク。(3) ブルーノ・ワルター指揮 コロンビア交響楽団 (SONYレーベル SRCR2308 1959年録音)これほど「歌心」にあふれたベートーベン演奏を聴いたことがありません。 どのフレーズにも「歌」があって、厳しい音楽の中に温かい熱気を盛り込むワルター特有の表現に脱帽。(4) シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 (RCA原盤 BMGジャパン JMCXR0019 1957年録音)ミュンシュ特有の直截的な表現が見事に表現されていて、熱気のこもった灼熱の「英雄」が聴ける演奏。 高度のリマスターでよみがえった優秀録音で50年前の名演奏を味わえるディスク。 欠点は3,450円という高価。 廉価盤でもリリースされていますが、音質は多少落ちます。(5) ピエール・モントー指揮 アムステルダム・コンセルトヘボー管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3379 1962年録音)フランスの指揮者でありながら、ドイツ音楽、ロシア音楽でも出色の演奏を残しているモントー。 このベートーベンでも骨太で熱気にあふれた直截的な表現でベートーベンの音楽を熱く語った演奏。(6) 朝比奈 隆指揮 大阪フィルハーモニー交響楽団(日本ビクター VDC5528 1977年東京ライブ録音)1977年10月6日東京文化会館に於ける演奏会でのライブ録音。 朝比奈の骨太・朴訥で重厚でテンポの遅い表現がドイツ風音楽の極みのように伝わってくる、どこを切り取っても生命力あふれる表現の素晴らしい演奏。 どっしりと腰を落ち着けた安定感のある音楽運びが絶妙に生きている、まさにベートーベン音楽表現の極みのような演奏。 これが30年前にすでに日本で演奏されていたとは信じられないくらいの、この曲の最もドイツ的名演奏。 初版LPがリリースされて聴いたあとはまるで虚脱状態になった録音による朝比奈 隆との初めての出会いでした。 オーケストラの技巧はお世辞にもいいとは言えませんが、それを凌駕する朝比奈の気迫が上回る演奏で、このコンビで何度も実演を大阪で聴きましたが、残念ながらこの時の演奏のすごさを超える生舞台を経験していません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1786年 初演 モーツアルト ピアノ協奏曲第24番1805年 初演 ベートーベン 交響曲第3番「英雄」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 クリスマスローズ金鳳花科 ヨーロッパ原産春に咲く園芸種。 クリスマスの時期に咲くバラに似ていることから命名されたそうです。しかし日本では3月~5月にかけて咲く花ですから、この名前は適しないのですが実にいい名前ですね。花は下向きに咲くために撮影には一苦労する花の一つです。 カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F6.3 露出補正なしTv 1/60 焦点距離 210mmホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ TAMRON Aspehrical 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年4月6日
2008年04月07日
コメント(0)
-

蓮華(れんげ)
「春の花」 蓮華(れんげ)子供のころはこの季節になるとどの田圃にも蓮華の花が満開で田圃一面に咲き乱れていました。今は私の住んでいるところが田圃が極端に少なくなり開発の嵐といった感があります。そんな少ない田圃にまだ少しばかり蓮華が咲いています。 色がいいですね。 咲いている辺りにスポットが当たったように華やかな感じに彩られています。今年は群生の中の花を取らずに1本だけぽつんと咲いている蓮華を撮ってみました。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F2.8 露出補正なしTv 1/1000 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートマニュアル フォーカスレンズ Pentax smc DFA f2.8 100mm Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年3月26日
2008年04月06日
コメント(4)
-

烏野豌豆(カラスノエンドウ)
「春の野草花」 烏野豌豆(からすのえんどう)道端・空き地・野原・公園の植え込みなどいたるところに咲いている春の野草花の代表。 豆科ソラマメ属の花。 これと似た花に「雀野豌豆(すずめのえんどう)」というこれよりまだ小さいのがあって、それと区別するために付けられた名前と言われています。カメラ機種 Pentax 10D絞り優先 F2.8 露出補正 +0.5Tv 1/350 焦点距離 100mmISO 100ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスPモード 絞り F4.5Tv 1/250 露出補正なし焦点距離 100mmISO 100ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス2枚ともレンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年3月26日
2008年04月05日
コメント(2)
-

シャガ
「春の花」 シャガ私の好きな花の一つです。神社の薄暗い境内や竹林の鬱蒼とした所を好んで植わっています。驚きはこの花は種子がないことです。それで原産地の中国から古代に伝来して来たとされていることです。種がなく球根でもない植物なのにどうやって中国から我が国に伝来したのでしょうか? 鉢植えで運ばれたのでしょうか? 謎の花ですね。 こういうロマンを感じる花の一つです。アヤメ科らしい風情のある花で、寒あやめやイリスの風貌を備えています。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F6.3 露出補正なしTv 1/60 焦点距離 210mmISO 100マニュアル・フォーカスホワイト・バランス オートレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro撮らせていただいた庭は小学校の同級生の家で、お母さんが存命中には手入れが行き届いて毎年綺麗な花を咲かせていましたが、今はその友達の弟が庭全体の手入れをしていますが、彼の毎日の努力には頭が下がる思いです。 それでもお母さんとの違いがあるようです。 花は正直ですね。まるで「子育て」を見る思いです。撮影地 大阪府和泉市 2008年3月26日
2008年04月04日
コメント(0)
-

スノーフレーク~春の花
「春の花」 スノーフレーク彼岸花科の鈴蘭に似た白い花。 すべて下向きで咲く花。 植わっている場所によりますがとても撮りにくい花の一つです。 和名は「鈴蘭水仙」、「スノーフレーク」は雪のようなイメージの実にいい名前です。しかし、真ん中斜めの茎が構図としては大失敗でした。もう一度撮り直して掲載することにします。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F6.3 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 300mmISO 100ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3撮影地 大阪府和泉市 2008年3月26日
2008年04月03日
コメント(2)
-

ナズナ~春の野草花
「春の野草花」 薺(ナズナ)よく見れば薺(なずな)花咲く垣根かな 松尾芭蕉この芭蕉の句のようによく見ないと花が開いているのか、あるいは花自体があるのかわからないアブラナ科の俗称「ペンペン草」という雑草。 それでもマクロレンズを通して覗いてみるとこんなに可愛い花びらをつけています。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F2.8 露出補正なしTv 1/500 焦点距離 100mmISO 100ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ Pentax smc DFA F2.8 100mm Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年3月23日天候 曇天 微風
2008年04月02日
コメント(4)
-

開花した染井吉野
「春の花」 桜~ソメイヨシノさきいづるやさくらさくらとさきつらなり 萩原井泉水これも天王寺公園を散歩中に見かけた桜~ソメイヨシノです。ようやく開花してこの日は2分咲き程度の桜が散策する人たちを楽しませていました。風さそふ 花よりもなほ 我はまた 春の名残を 如何にとやせん 浅野内匠頭有名な忠臣蔵ー浅野内匠頭の辞世の歌です。 和歌の世界では花と言えば桜となっています。これが定着したのが「古今和歌集」の時代と言われています。その頃の桜は「山桜」のことで、現代の「染井吉野」は江戸時代まで待たねばなりません。 江戸の中期に駒込染井という植木職人が交配で作ったのが「染井吉野」です。 以来桜と言えば「染井吉野」が代表格となっています。その「ソメイヨシノ」が関西でも開花して今週末が見ごろとなる所が多いようです。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F6.7 露出補正なしTv 1/250 焦点距離 300mmISO 100ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro撮影地 大阪市天王寺公園 2008年3月26日
2008年04月01日
コメント(2)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- オーディオ機器について
- 試作スピーカー31.9(アルマイト処理…
- (2025-11-24 21:13:19)
-
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-







