2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年03月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-

ボロニア
「春の花」 ボロニア天王寺公園を歩いていると見慣れない花が長方形のコンクリートの鉢に植わっていました。小さなピンク色の花びらがとても可愛らしくて、持っていたカメラを取り出して撮ってみました。レンズがあいにくと300mmズームでしかも三脚を持っていなくて、撮りにくいのを我慢して何とか撮りましたがやはり液晶画面はあてになりません。ピントが甘い画像になってしまいました。自宅で調べてみますと「ボロニア」という名前であることがわかりました。みかん科 ボロニア属 オーストラリアが原産地で葉が少し細い線形をしており、星形のピンク色の花がでした。 春になると咲く花だそうです。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F5.6 露出補正 +0.5Tv 1/250 焦点距離 135mmISO 100ホワイト・バランス オートレンズ TAMRON Aspherical XR Di 28-300 1:3.5-6.3 Macro天候 やや曇り 微風撮影地 大阪市天王寺公園 2008年3月26日
2008年03月31日
コメント(4)
-

仏の座
「春の野草花」 仏の座これも春の野草花の代表格の一つで、道端・空き地・公園・畑などでひっそりと、あるいは群生して咲いています。紫蘇(しそ)科 オドリコソウ属 半円形の葉が茎を取り囲んでつくようすを蓮華座(れんげざ)に似ていることから命名されています。 ただし春の七草のひとつの「ほとけのざ」はこの花ではありません。カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F8.0 露出補正なしTv 1/125 焦点距離 115mmホワイト・バランス オートISO 100レンズ TAMRON Aspehrical XR Di 28-300mm 1:3.5-6.3 Macro天候 やや晴れ 風強し カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F2.8 露出補正なしTv 1/750 焦点距離 100mmISO 100ホワイト・バランス オートレンズ Pentax smc DFA 1:2.8 100mm Macro天候 晴れ 風なし撮影地 大阪府和泉市 2008年3月22日
2008年03月30日
コメント(2)
-

姫踊子草
「春の野草花」 姫踊子草萌える大地。春になると大地から次々と小さな野草花が顔を出してきます。初夏から冬にかけてじっと大地の中で眠るように静かに鳴りを潜めて待っていたかのように。この小さな「姫踊子草」もまるで我が世の春といった風情で、空き地・道端・畑・公園などに明るい陽光を浴びながら春を謳歌しています。紫蘇(しそ)科 オドリコソウ属撮影地 大阪府和泉市 2008年3月22日
2008年03月29日
コメント(6)
-

はこべ
「春の野草花」 はこべカナリヤの 餌に束ねたる はこべかな 正岡子規 春になると大地が萌え出るように様々な野草や花を吐き出してくれます。この花「はこべ」もその中の一つ。 肉眼ではあまりに小さいために目を凝らしてみない限りこのようには見えません。 道端・空き地・畑の畔・公園など、どこにでも咲いている「はこべ」。けなげに春を謳歌しているようです。なでしこ科 ハコベ属 カメラ機種 Pentax K10D絞り優先 F2.8 露出補正なしTv 1/750 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートISO 100マニュアル・フォーカスレンズ Pentax smc DFA 1:2.8 100mm Macro撮影地 大阪府和泉市 2008年3月22日
2008年03月28日
コメント(6)
-

馬酔木~長居植物園の春の花
「長居植物園の春の花」 馬酔木(アセビ)花ふさの雨となりたり馬酔木かな 大谷碧雲居つつじ科 アセビ属の花で、3月中旬から4月中旬に咲きます。「アセビ」とも「アシビ」とも呼ばれています。 俳句では「馬酔木(アシビ)」と呼んでいます。 白色の小型壺状の花を咲かせています。葉や茎に有毒性分が含まれているようで、馬やう牛が食べると麻痺が起こるので、「馬酔木」と名付けられたそうです。 カメラ機種名 Pentax K10D絞り優先 F8.0 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートマニュアル・ファーカスISO 100レンズ Pentax smc DFA 1:2.8 100mm Macro天候 快晴 微風 撮影条件は上記に同じ撮影地 大阪市立長居植物園 2,008年3月18日
2008年03月27日
コメント(4)
-

ネモフィラ~長居植物園の春の花
「長居植物園の春の花」 ネモフィラはぜりそう科 ネモフィラ属 北アメリカ西部原産の花で非常に背丈が低く撮りにくい花の一つです。3月~5月に紫、青、白などの色の花を咲かせます。 春が来たという感じのする花の一つです。 上記2枚の画像ともカメラ機種名 Pentax K10D絞り優先 F8.0 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ Pentax smc-DFA 1:2.8 100mm Macro天候 快晴 微風撮影地 大阪市立長居植物園 2008年3月18日
2008年03月26日
コメント(2)
-

サンシュユ~長居植物園の春の花
「長居植物園の春の花」 サンシュユ水木(みずき)科 ミズキ属 開花時期は2月下旬~4月上旬中国と朝鮮半島が原産地だそうで、日本に伝えられたのは江戸時代中期だそうです。 面白い名前が付けられているので調べてみると、中国の漢字をそのまま音読みをしているそうです。 私はこの花木が大好きで、梅の香りが匂う頃になると、ソメイヨシノなどの桜と同じで葉がでてくる前に黄色の小さな花を付けています。いかにも中国・朝鮮半島から渡ってきたような、どことなく和風の感じのする花木です。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年3月18日
2008年03月25日
コメント(4)
-

ジャノメエリカ~長居植物園の春の花
「長居植物園の春の花」 ジャノメエリカ無数の花びらがついた「ジャノメエリカ」。つつじ科の花で冬から春にかけて咲く花ですが、今年やっと撮ることができました。 ピンク色の小さな可愛い花が葡萄の房のようにびっしりと詰まっています。真中に黒い眼玉のような模様があるのがとても愛らしい花です。 この黒い目玉を「蛇」の「目」に見立てて「蛇の目」と命名されたそうです。 開花時期は12月~4月初め頃まで。 機種 Pentax K10D絞り優先 F5.6 露出補正 +0.5Tv 1/180 焦点距離 100mmISO 200ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカスレンズ SMC Pentax-DFA 1:2.8 100mm Macro 絞り優先 F5.6 露出補正 +0.5Tv 1/125 焦点距離 100mmISO 200他上記に同じ撮影地 大阪市立長居植物園 2008年3月18日
2008年03月24日
コメント(2)
-

オオヤマザクラ
「黒鳥山公園の桜」 オオヤマザクラ昨日晴れた朝早く徒歩で15分くらいのところにある黒鳥山公園にカメラ持参で行ってきました。 目的は早咲きの桜の開花状況を見るためでしたが、「オオヤマザクラ」はすでに満開でした。 ソメイヨシノが有名なこの公園で一番先に咲いてくれる花ですが、今年は寒い日が続いたので開花は昨年よりは遅いだろうと思っていたのですが満開とは。「けふもまたさくらさくらの噂かな」 小林一茶広辞苑によると、「本州中部以北の山地に自生する桜でヤマザクラに似ており、葉の裏は青みを帯び、枝は丈夫で暗紫色。花はヤマザクラより赤みが濃い」と書かれています。この画像の桜の木に「オオヤマザクラ」の銘板が貼ってありました。機種 Pentax K10D絞り優先 F8.0 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートISO 100レンズ SMC PENTAX-DFA 1:2.8 100mm Macro機種は上記に同じ絞り優先 F8.0 露出補正 +0.5Tv 1/250 焦点距離 100mmホワイト・バランス オートISO 100レンズ SMC PENTAX-DFA 1:2.8 100mm Macro撮影地 大阪府和泉市黒鳥山公園 2008年3月22日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「朝青竜 優勝」大相撲春場所は朝青竜の優勝で決着。 2場所連続で横綱同士の相星決戦。 年六場所制になって北の湖ー輪島、千代の富士ー隆の里、曙ー貴乃花に次ぐ2場所連続の相星決戦。 やはりジンクスは生きていました。 過去の上記の決戦で連続で優勝した横綱はいませんでした。今場所こそ白鵬がそのジンクスを破るか、朝青竜が好きな大阪場所で復帰を果たすか、大いに注目された千秋楽の取組でしたが、結果は意外にあっさりと決着がついてしまいました。 それにしても今場所も大関の不振。3大関そろって8勝7敗は寂し過ぎます。大関ならせめて11勝はしてほしいものです。また未来の大関を目指す琴奨菊、希勢乃里も停滞状態、大阪出身の豪栄道も引き技が目立つ消極的な取り口が目立ち、やっと千秋楽で勝ち越し。 相撲人気を盛り上げるためにも次世代の若手の伸びが欲しいことは、いつも場所ごとに言われていること。相撲好きの私には何とも物足りない場所が続いています。両横綱を脅かす大関が欲しいし、若手が欲しいですね。話は下世話になりますが、この場所の初日以来西の花道の横、砂かぶり席で毎日座っていた30-32歳のくらいの和服の美人女性が今日は少なくともTV画面では映っていなかったので、とても気になりました。髪の結い方、選ぶ和服の図柄・色などから推して玄人筋のご婦人と見えたのですが、あれだけ14日間同じ席に通いつめて毎日画面に映っていましたので、今日は何故同じ席に居ないのかととても気になりました。朝青竜ー白鵬戦と同じくらいに気になりました。
2008年03月23日
コメント(10)
-

長居植物園の春の花~花菜(菜の花)
「春の長居植物園」 花菜(菜の花)菜の花のはるかに黄なり筑後川 夏目漱石私が小学生の頃国鉄電車(現在のJR)-阪和線に乗ると右も左も春は菜の花ばかりでした。びっしりと植えられた菜の花で黄色の世界となっていました。 大阪市と堺市を隔てる大和川。 その大和川の堤防から南は泉南郡(現在の泉南市)までこの菜の花で埋まった時期もありました。 畑や田圃の裏作として植えられていたからです。自然の生態系もじつに摂理に飛んでおり、黄色の菜の花と田圃の虫をついばむ白鷺という白い鳥の白さが好対照でした。春「弥生」となればこの風景が現われ、家の周りの畑や田圃も黄色一色に染まる春でした。蝶々が舞い、蜂が舞い、鳥たちの天国のような光景がどこにでも見られました。食卓に出てくるのが「菜種の漬物」「菜種のおひたし」が常食でした。今ではその面影もありません。 猫の額のようなせまい農地でわずかに見られるのみと変わってしまいました。そういう風景を見たこともない人たちには漱石の句は「絵」として浮かんでこないと思います。 筑後川に映る黄色の菜の花。それが川の色まで染めてしまうような見事な菜の花畑が続いていたのでしょう。 これも私のような熟年者のノスタルジアなんでしょうね。 撮影地 大阪市立長居植物園 2008年3月18日
2008年03月22日
コメント(2)
-

長居植物園の春の花~シクラメン
「長居植物園の春の花」 シクラメン咲き余る弁のよじれやシクラメン 林原耒井シクラメンの花は上向きに花びらが咲き、色も紫、紅、白、紫紅など多種にわたる色彩で、最近は改良種も増えて「絞り」の花びらも見られます。この花は冬の花とばかり思っていましたが(クリスマス時期に店頭で見かけますから)、俳句の季語では春となっています。 花は12月初め~4月下旬頃まで咲いています。サクラソウ科シクラメン属で地中海沿岸が原産地だそうです。日本には明治24~5年頃に伝わったと言われています。画像のシクラメンは小ぶりの小さな花で寄せ植えに飾られることの多い種類です。最近ではマンションのベランダや戸建ちの庭の垣根・フェンスなどに、鉢植えとして飾られているのをよく見かけます。長居植物園の花壇に植えられていました。 色は鮮やかですが、どこか寂しい風情のある花のように感じます。地中海では豚がよく食べたそうで「豚の饅頭」とも呼ばれているそうです。いかにも無粋な名前です。その点、日本人は美しい別名を付けています。 「篝火花」(カガリビバナ)。 そういう目線で見ると、炎がメラメラと燃え上がるような風情のある花です。 機種 Pentax K10D絞り優先 F8.0 露出補正なしTv 1/180 焦点距離 100mmISO 100 ホワイト・バランス オートマニュアル・フォーカス天候 快晴 風なし撮影地 大阪市立長居植物園 2008年3月18日
2008年03月21日
コメント(4)
-

長居植物園の春の花~椿
「長居植物園の春の花」 椿籠り飛ぶ小鳥あるらし大椿 松本たかし葉の込み合う常緑樹の椿。 びっしりと花をつけるとこんもりと茂ったようになります。大きな椿の木になるとほの暗く小鳥が外敵から身を守るのに安全な場所です。椿は暖かい場所で生息する植物だそうです。 日本でもっとも北で観られる所は青森県で自生する椿らしいです。 「椿」という漢字は日本で作られたもので、中国では山茶(シャンチャ)らしいのです。和名は「アツバキ」(厚葉木)のアが取れて「ツバキ」となったらしいもです。「古事記」や「日本書記」にも椿のことが書かれているそうで、古来から生息する木なんでしょう。現在では世界に分布するようになり1万種あると言われています。長居植物園には「つばき園」があり山茶花と一緒に数多くの椿が植えられています。私が訪れた日は快晴で気温も4月下旬並みの陽気。園内の椿のほとんどの木がびっしりと花を付けていました。今が見頃の時期でした。機種 Pentax K10D絞り優先 F8.O 露出補正なしTv 1/30 焦点距離 100mmISO 200ホワイトバランス オートマニュアル・フォーカスレンズ Pentax DA 1:2.8 100mm MACRO以下の画像も機種・レンズは同じ絞り優先 F8.0 露出補正なしTv 1/125 焦点距離 100mmISO 200 ホワイトバランス オートマニュアル・フォーカス上記2枚とも撮影地 大阪市立長居植物園 2008年3月18日
2008年03月20日
コメント(2)
-

長居植物園の早春の花~河津桜
「長居植物園の早春の花」 河津桜久しぶりにカメラを持って長居植物園を訪れました。 前回は2月19日の訪問でそれから1か月。様子はすっかり変わっていました。やはりこの暖かさに浮かれて花たちもまるで冬眠から覚めたように花びら開き、春の陽射しをいっぱいに受けて喜びを謳歌しているようでした。この公園では折からの春の陽気に誘われて、お母さんに連れられて幼児たちが元気に走り回り、また遊器具などで遊びまわっていました。 最高気温が21度を超えて4月下旬並みの暖かさで、それに風も無く絶好の春の日和でした。植物園に入るまえに広大な長居公園があります。その遊歩道・散歩道に10本ほどの背丈が4メートルほどの桜の木が植えられています。目を引くのが静岡県伊東の「河津桜」。 早咲きの桜で濃いピンクの大きな花びらが特徴です。開花日数も長く春の訪れを楽しめる桜です。その「河津桜」3本が植物園に入る前に出迎えてくれました。 やはり桜はいいですね。撮影地 大阪長居公園 2008年3月19日機種 Pentax K10Dシャッター速度 1/500AV優先 F8.0 露出補正 -0.5焦点距離 158mmISO 100ホワイトバランス オートレンズ TAMRON AF ASPHERICAL XR Di 28-300mm 1.35-6.3 MACRO天気 快晴 風なし昔から俳人が桜を詠んでいます。なかでも好きなのが松尾芭蕉。四方より花吹き入れて鳰(にお)の海 芭蕉「鳰の海」とは滋賀県・琵琶湖を指す言葉です。 「鳰」は和名 「カイツブリ」と呼ばれる水鳥のことです。 「鳰」
2008年03月19日
コメント(2)
-
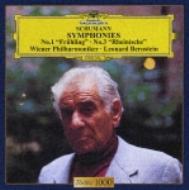
シューマン 交響曲第1番「春」
「今日のクラシック音楽」 シューマン作曲 交響曲第1番「春」ロマン派音楽の代名詞のような作曲家ロベルト・シューマン(1810-1856)は、紆余曲折、困難を乗り越えてクララ・ヴィークと結婚をしたのが1840年でした。 この1840年は、シューマンにとって「歌の年」と言われるほどに歌曲を数多く書いた年でもあり、2年後の1842年にはピアノ四重奏曲などの室内楽の名作を多く書いています。その「歌の年」と「室内楽の年」の間の1841年に書かれた曲に交響曲第1番「春」があります。 シューマンの功績は勿論自作の美しい音楽を遺していることなのですが、もう一つ、シューベルトの交響曲第9番を発見したことも挙げられます。 シューマンによって陽の目を見たこの曲は、彼自身に交響曲を書く意欲を与えたと言われています。そして、ドイツの詩人アドルフ・ベッツガーの「谷間に春が燃え立っている」という詩を読んで「春」というインスピレーションを得て、シューマンは交響曲第1番を書き、自ら「春」というタイトルを付けたと言われています。各楽章には春への想いを込めて、それぞれに「たそがれ」「楽しい遊び」「春たけなわ」などの楽想の言葉を書いていたそうです。第1楽章の序奏でホルンとトランペットがまるで「春の到来」を告げるようで、続いて春の暖かな空気を思わせる第1主題によって「春の気分」を漂わせており、この雰囲気が全曲を支配しています。シューマンの交響曲はベートーベンやブラームス、シューベルトなどに比べるとオーケストレーションに見劣りしていることは、聴いていても感じられることですが、シューマンのほとばしる情熱は楽想として感じられ、若々しい気分を湛えている佳品です。私が高校2年生の頃(1962年)にはハイドン、モーツアルト、ベートーベン、シューベルト、ブラームス、チャイコフスキー、ドヴォルザークやショスタコービチなどの交響曲を聴いており、シューマンのそれはこれら交響曲作曲家の曲に比べて劣るものと先輩から聴かされていましたので、聴きたいとは思っていてもLP盤の購入までに至らずに時間が経過して、1970年頃にやっとカラヤン/ベルリンフィルのLP盤を買うことによってシューマン体験をすることになりました。ロマンいっぱいの音楽に惹きこまれていきました。 この曲はヨーロッパの人たちが待ち焦がれる春の到来を想わせるような、憧れと希望に満ちた旋律。音楽が全編に溢れており、しかも少し渋みのある、影さえ感じられる情緒は独特の雰囲気をたたえています。「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ」 嵐雪厳しい冬の寒さから暖かさへ向かう時間の経過を言いえて妙なる句です。「水ぬるむ 主婦のよろこび 口に出て」 山口波津女使う水が段々とぬるんで来ることに春への予感の喜びの句。日本はこうして徐々に暖かさを実感しながら春到来を喜んでいますが、ヨーロッパの春は違います。 ある朝目が覚めて窓を開けると、もうそこは春の草花が眼前に広がっているような、唐突に春の訪れを告げるかのようです。シューマンのこの音楽を聴いていると、ヨーロッパの人たちの春の突然の来訪・春の喜びを弾けるように喜んでいるような、そんな感じを受ける音楽です。もう「寒の戻り」もないでしょう、昨日から「彼岸の入り」。 とうとう「暑さ寒さも彼岸まで」にやってきました。 シューマンの交響曲第1番「春」を聴いて、また新たな季節の移り変わりを喜びましょう。愛聴盤 (1)デビィッド・ジンマン指揮 トーンハレ管弦楽団 (Arte Nova 82876.57743 2003年10月録音 海外盤)鋭く情感豊かなフレージングと、躍動する生命力のある弾力的なリズムの扱い、平面的な部分がまったくなく、非常にテンションの高い演奏で、聴いていて実に爽快な気分になります。 最近のシューマンの交響曲のディスクでは、ジョージ・セルとベルリンフィルの2番のシンフォニーと共に特筆すべき秀演だと思います。 2枚組CDでシューマンの4曲が全部収録されていて1000円のお買い得盤です。(2)レナード・バーンスタイン指揮 ウイーンフィルハーモニー管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサルミュージック UCCG5098 1984年録音)ジャケットは第3番「ライン」とのカップリングに変わった音盤です。バーンスタイン特有の生命力にあふれた熱演で、どのフレーズにも生き生きとした爆発するような生命が宿る名演。 このディスクによってシューマンの素晴らしさを教えられた記念すべき録音盤です。 現在ではこの紹介盤が1000円で求められる廉価盤となっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1844年 生誕 リムスキー=コルサコフ(作曲家) 1902年 初演 シェーンベルグ 「浄められた夜」
2008年03月18日
コメント(2)
-
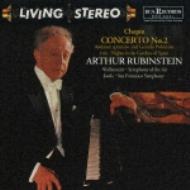
ショパン ピアノ協奏曲第2番
『珈琲ブレイクの一曲』 ショパン作曲 ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調フレデリック・ショパン(1810-1849)は39歳の短い生涯に2曲のピアノ協奏曲を書き残しています。 これら2曲は1829-1830年に書かれていますから、非常に若い間に書かれていることになります。この第2番は、もうすでに有名なエピソードのように、第1番より先に書かれています。 これは楽譜出版が1番と2番が逆になったことから発生しています。ショパンがこの曲を書いた当時に片想いの恋をした女性(ワルシャワ音楽院卒業のコンスタンティア・グラドコフスカ)への思慕から、第2楽章「アダージョ」を書いたことで有名です。音楽は典型的なロマン派ピアノ協奏曲のスタイルで書かれており、ショパンのロマンティックな資質が泉のように湧き出た、甘く美しい旋律が全編に包まれています。 ショパンのピアノ協奏曲は、オーケストレーションのまずさとか下手だとか指摘されていますが、その下手くそと言われる管弦楽伴奏が、よりいっそうピアノ旋律・音楽の魅力を引き立てているようです。この曲の白眉は第2楽章「アダージョ」だと思います。まるで片想いへの恋しい女性に「恋文」でも書いているかのように、熱い想いが甘く美しい旋律で書き連ねられた、豊かな抒情的な雰囲気いっぱいの、ショパンの「青春の息吹」のような音楽に溢れています。グラドコフスカは幸せな人だと思います。 これほどの名曲を書くきっかけが彼女にあって、その想いが第2楽章に込められているのですから。しかし、この曲は片想いの当の本人にではなくて、後にパリで親交のあったデルフィナ・ポトッカ伯爵夫人に贈呈されたそうです。1830年の今日(3月17日)、このピアノ協奏曲第2番がショパン自身のピアノで初演されています。愛聴盤(1) ルービンシュティン(P) アルフレッド・ウオーレンシュタイン指揮 シンフォニーオブジエアー(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37173 1958年録音)ほんとに古い、ステレオ初期の録音ですが、風格豊かに堂々と弾いているピアノだと思います。ピアノタッチの腰が強く、スケールが大きくて、明るく健康的で、情緒豊かに歌う演奏は今でも色あせない魅力です。愛聴盤(2) クリスティアン・ツィマーマン(Pと指揮) ポーランド祝祭管弦楽団(ドイツ・グラモフォン 459584 1992年録音)あらゆる機会に論じられた稀有の演奏。ツィマーマンの弾き振り。オーケストラまで新編成して自分のやりたいこと徹底的に語っています。 第1番とのカップリング、1番から順番に聴いたのですが、冒頭のオーケストラでの演奏から「ちょっと待ってよ!」と思い、使用楽譜に新版が出たのかと想ったほど、従来の演奏スタイルとは全く異なる濃厚なロマン情緒がどこを切っても表れる素晴らしい演奏です。 強弱の対比が鮮明で、強靭なピアノタッチ、蕩けるような甘さ、豊かな艶のある表現、もう無類の音色の変化にただただ呆然と聴いていたものです。しかし、この曲を初めて聴く方には是非この盤以外で聴いて欲しいと思います。 そのあとにこのツィマーマン盤を聴かれたほうがより凄さを理解できると思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1830年 初演 ショパン ピアノ協奏曲第2番1846年 初演 ヴェルディ オペラ「アッティラ」2005年 没 ガリー・ベルティーニ(指揮者)
2008年03月17日
コメント(4)
-
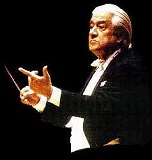
幻想的序曲「ロメオとジュリエット」
「珈琲ブレイクに一曲」 チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」チャイコフスキー(1840-1893)は非常に文学が好きな作曲家であったそうです。 その中でも特にイギリスのシェイクスピアを好んで読んでいたそうです。 彼の書いた作品にもシェイクピア文学を基にした音楽があります。 幻想曲「テンペスト」、劇付随音楽「ハムレット」、それに今日の話題曲で最も有名な幻想的序曲「ロメオとジュリエット」です。この曲はチャイコフスキーの比較的初期に書かれた作品で、完成が1869年、初演が翌1870年3月16日に行われています。 この曲の書かれた経緯がおもしろいのです。ロシアの先輩作曲家バラキレフの勧めで書かれたと言われています。パラギレフ自身が作曲する意思があったのですが、チャイコフスキーの能力を高く評価して託したそうです。 かなり具体的に音楽の構想を練っていたのか、チャイコフスキーには細かいプランも授けていたそうです。 チャイコフスキーが書き上げたこの作品がどの程度バラギレフの意図を織り込んでいるのかは、今ではわからないと思います。曲はもちろんシェイクスピアの悲劇「ロメオとジュリエット」の物語を音楽にした作品で、かなり長い序奏部があり、両家の暗い悲劇的な、また二人の若い男女の悲劇を嘆いているかのように始まります。この序奏部は重々しく荘重な雰囲気が漂っており、宗教的ともいえる気分が息づいています。主部に入ると両家(モンターギュ家とキャピュレット家)の争いの模様が激しく描かれています。 これが第1主題と言えるのかも知れません。 やがて雰囲気が若い愛し合うロメオとジュリエットの優美、甘美なロマンティックな旋律が表れます。 この曲で最も有名な旋律です。ここではまるでチャイコフスキー節満開といった、一度聴くと忘れられない優美な旋律が支配します。この2つの主題旋律で音楽が進み、やがて悲劇的に盛り上がったあと、平安で清らかに静かに曲を閉じています。尚、チャイコフスキーはその後2度初稿に手を加えているそうです。1870年の今日(3月16日)、幻想的序曲「ロメオとジュリエット」(初稿版)が初演されています。初演日にちなんで今日の珈琲ブレイクに聴こうと思います。愛聴盤(1)セルジュ・チェリビダッケ指揮 ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団 (EMI原盤 東芝EMI TOCE9580 1992年録音 廃盤)組曲「展覧会の絵」との収録でチェリビダッケ独特の遅いテンポで見事に悲劇的物語を表現しています。 実演でも聴きましたが今までに聴いた同曲中最も感銘の深い演奏。これが何故廃盤なのか理由がわかりません。後世に語り継ぎたい人類の遺産とも呼ぶべき演奏だと思うのですが。(2)ゲンナジー・ロジェストヴェンスキー指揮 ソ連国立文化省交響楽団(エラート原盤 ワーナー・クラシックス WPCS4016-6 1990年録音 廃盤)チャイコフスキーの第4交響曲や「スラブ行進曲」「弦楽セレナード」等のチャイコフスキー管弦楽曲集の2枚組で、ロジェストヴェンスキー独特の爆演と呼んでいいのか、脂っこい明暗の激しい表現でシェイクスピアの世界を描いています。 交響曲第4番も目の眩むような演奏です。 廃盤理由がわかりません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1736年 逝去 ジョバンニ・ペルゴレージ(作曲家)1870年 初演 チャイコフスキー 幻想的序曲「ロメオとジュリエット」1886年 初演 マーラー 歌曲集「さすらう若人の歌」1924年 生誕 クリスタ・ルードヴィヒ(メゾ・ソプラノ)1935年 生誕 テレサ・ベルガンサ(メゾ・ソプラノ)
2008年03月16日
コメント(2)
-

シューベルト 歌曲集「美しき水車小屋の娘」/大相撲春場所
「大相撲春場所」昔から春場所は荒れる場所と言われています。番狂わせの一番の多い場所で横綱・大関が負ける相撲の多い場所というジンクスのある場所です。 初日から数日はそんな場所でしたが、最近の大関の弱さがまる当たり前のようになっていて、このジンクスはもう存在しないかのような不甲斐なさです。 今日の結果でどうやら千代大海と魁皇が元気を取り戻しています。平幕でも二人7戦全勝(豊真将と栃おう山)で横綱朝青龍を追っています。 白鵬が4日目に不覚を取ってますます優勝争いが面白い。千代大海の腕の故障が良くなってきているのか突っ張りにも威力が出てきたし、魁皇の今日の相撲などは押し相撲。安馬の気迫の突っ込みを一蹴。 人気関取高見盛も6勝1敗と元気。10日目くらいまではこのままで推移して欲しいですね。それにしても琴欧州、琴光喜の二所が関の大関の不信は目を覆うばかりです。何とか奮起してほしいものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 シューベルト作曲 歌曲集「美しき水車小屋の娘」今日は久しぶりに歌曲を聴いてみようと思います。 歌曲と言えば一番先に思い出すのがシューベルトです。 シューベルトの歌曲を採り上げました。フランツ・シューベルト(1797-1828)はわずか31歳でこの世を去っています。その31年という短い生涯で書き遺した歌曲は600を超えるそうです。 それらの歌曲はシューベルトの青春の喜びや悲しみ、寂しさ、怒りなどを綴ったのでしょう。シューベルトのすべての歌曲を聴いたわけではありませんが、こうした感情が瑞々しく書かれた優れた歌曲が残っています。交響曲、ピアノ曲、ヴァイオリン曲、室内楽作品・オペラ。劇音楽などのまるで泉の湧き出るごとく美しい旋律を書き残したシューベルト。 神さまは我々に平等を与えてはくれませんでした。 美しい音楽を書いた彼にモーツアルト、メンデルスゾーン、ウエーバーなどと同じように若い命を散らせてしまったのです。600を超える歌曲の中でも燦然と輝いているのが3代歌曲集です。「美しき水車小屋の娘」「冬の旅」「白鳥の歌」、これが3大歌曲集と呼ばれている作品です。 今日はその中から「美しき水車小屋の娘」を選びました。芸術作品は作者の心で温め続けてようやく開花するがごとき世に出る作品もあれば、ひょんなことから生まれる作品もあります。 この「水車小屋の娘」は後者の方に入る作品です。作曲はシューベルト26歳の1823年で、ある日シューベルトは友人宅を訪れましたが散歩にでも行ったのか不在でした。 テーブルに座って友人の帰りを待っていたシューベルトの眼にとまった一冊の本。 シューベルトとあまり年の変わらないミュラーという詩人の詩集が読みかけて机の上に置いてありました。それを読んだシューベルトは大いに感銘を受けて友人が帰るまでにこっそりと家に持ち帰り、楽想の思いつくままに詩に音楽をつけて書いたのでした。 それが「美しき水車小屋の娘」です。20の詩を選んで音楽を付けています。 この歌曲は独立したものでなく連作とか連編歌曲集と呼ばれていて、同じようにミュラーの詩に音楽を付けた「冬の旅」があります。 シューマンにも「女の愛と生涯」が連作歌曲集として残されています。音楽の物語は、粉屋の若者が職を探して旅に出ます。 水車小屋で働いているうちにそこの娘を恋するようになるのですがライバル出現。 結末は娘に振られ絶望した若者。 やがて失意のまま川に身を投げると物語です。悲劇的な結末ですが、のちの「冬の旅」と違って暗い憂鬱な気分がなく、恋の喜び、あこがれ、甘く若い感傷などが曲を覆いつくしています。 こんこんと湧き出る泉のごとくシューベルト特有の美しい旋律が、影と光を光彩豊かに交錯して、若者の細やかな心情が見事に歌いこまれています。もう10年近くこの曲を聴いていません。響は久しぶりにシューベルトの歌曲の世界に浸ろうと思います。愛聴盤 ヘルマン・プライ(バリトン)(DENON CREST1000 COCO70937 1985年録音)CREST1000シリーズの1枚で1000円盤。 明朗で素直な歌声で若者の心情を見事に歌い上げた演奏。 思わず物語の世界に引き込まれる演奏。 初出と同時に3300円で買ったディスクですが、今では1000円盤と買い易くなっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1807年 初演 ベートーベン 交響曲第4番1865年 初演 リスト 「死の舞踊」1908年 初演 ラヴェル スペイン狂詩曲1929年 生誕 アントニエッタ・ステルラ(ソプラノ)
2008年03月15日
コメント(2)
-
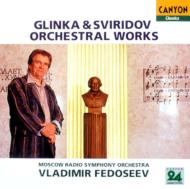
スヴィリドフ 「吹雪」
昨年秋からクラシック音楽(時にはモダンジャズ、ときには花の画像を掲載していましたが)中心にブログで何か趣向を変えてと考えていたのですが、なかなか見つかりません。美帆さんのレシピにも期待しましたが、それもなしのつぶて。 当分は好きな曲を選んで従来通りに書くことにします。 あしかず後了承を下さい、今日は居酒屋で少し呑んで来たためもあり、頭も朦朧としていますので。いづれ書き直します。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 スヴィリドフ作曲 「吹雪」ゲオルギー・スヴィリドフ(1915~1998)は現代ロシアの代表的な作曲家だそうです。私はこのCDを購入するまで名前すら知らない作曲家でした。 13年前の1995年に新譜としてCANYONレコードからリリースされるのを、雑誌「レコード芸術」の広告で魅かれて購入したCDです。演奏も私の好きなウラジーミル・フェドセーエフ指揮のモスクワ放送交響楽団で、1980年代の彼らの来日公演で聴いたムスルグスキーの組曲「展覧会の絵」の演奏が鮮烈な印象で残っており(ちなみにこの「展覧会の絵」は私が今まで聴いた同曲の演奏で最高の名演奏で、コンサート・CDの両方であれほどの演奏を凌駕するものを知りません)、以来彼らの新譜には常に興味を抱いていました。聞き慣れない名前の作曲家ですが、カップリングはグリンカのオペラからの管弦楽曲でしたので迷わず購入したCDです。この「吹雪」はCDの解説書によればこの作品は、ロシアの詩人プーシキンを題材にした1964年の映画の音楽として書かれており、スヴィリドフはこの映画音楽を管弦楽組曲に編曲を行い、さらに1974年に「音楽的イラストレーション」として改編しているそうです。 このCDで演奏されているのはその「音楽的イラストレーション 吹雪」です。 曲は9曲から構成されており、1.トロイカ2.ワルツ3.春と秋4.ロマンス5.田園6.ミリタリー・マーチ7.結婚式8.ワルツの響き9.冬の路というタイトルが付けられています。約30分弱の演奏時間を要する作品です。音楽は全編にロシアの情緒濃厚な音楽で、叙情に溢れた旋律映画の背景に流される甘美なもので、第1曲からロシアの大地に放り出された感じで、それが終曲まで続きます。 そこにはチャイコフスキー以来のロシアの作曲家の伝統的な民族的音楽が展開しています。 チャイコフスキーのピアノ曲「四季」の世界にも通じるような音楽です。と書けばロシアの代表料理ボルシチのような脂っこい感触の音楽を想像されるかも知れません。 ところがそうでないのです。さら~とした透明度の高い、絵で言えば油絵でなくて「水彩画」のようあっさりとした情緒を楽しめる音楽です。 この作品は国民楽派の音楽やロシア音楽を好きな人には、こたえられない音楽だと思います。この作品は現在このフェドセーエフのものしか発売されていないと思います。今日の珈琲ブレイクに聴いてみようと思っています。「追記」嫌好法師さんのコメント書き込みでわかったのですが、作曲家スヴィリドフは亡くなっていました。あちこちで調べますと命日はわからないのですが、1998年に亡くなっています。愛聴盤 フェドセーエフ指揮 モスクワ放送交響楽団(CANYON CLASSICS PCCL00582 1995年5月録音)グリンカのオペラ「ルスランとリュドミーラ」序曲、オペラ「イワン・スサーニン」序曲などが収録されています。 名プロデューサー江崎氏による収録で超優秀録音盤としてもお薦めできる盤です。 現在は上記商品番号で1500円盤として廉価で再発売されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1681年 誕生 ゲオルグ・テレマン(作曲家)1821年 初演 シューベルト 弦楽四重奏曲第13番「ロザムンデ」1847年 初演 ヴェルディ オペラ「マクベス」1852年 初演 シューマン 「マンフレッド」序曲
2008年03月14日
コメント(4)
-

グリーグ ピアノ協奏曲/橋下知事の失言
「府民不在の府議会」大阪府議会の醜態。橋下新知事就任後まだわずかな日数の府議会。それで知事の発言が不適切と知事が認めて議事録から発言を削除すること3度。知事が就任前に「タレント弁護士」としてTVに出演して、過激発言とも言えるコメントを繰り返していた頃を思い出させる事態。 しかし内容は低レベルの質疑応答による答弁・発言削除。「大阪を何とかしなければ」の意気で府庁に乗り込んだ知事。でっかい目標があります。ここ1週間の府議会の質疑応答での答弁削除・謝罪は知事の勘違いもありますが、もうTVで発言していた頃とは違います。 知事の肩には180万人の「願い」と「祈り」がかぶさっています。もう少し府民不在とならないように冷静に答弁を願いたい。 野党ももっと府民のためを考えて質問して欲しい。 知事の過去の著作に書かれたことを問い質すのではなくて、知事の考え・行政の進路をしっかりと捕えて質問をして欲しい。今はとにかく低レベルの質疑応答と言われても仕方がないほどに「府民不在の議会」になっているように感じます。府の30歳以下の職員を前に朝礼をした時の知事の発言。 「始業15分前の朝礼が超過勤務にあたるなる、今後煙草の時間・私語も認めない」なんて発言は、TVタレント時代の橋下弁護士の発言。 知事の発言ではないでしょう。視察に行った時に小学生から言われたコメント。「テレビに出てたから知事になれたんやで」とこれからも言われないようにしっかりと行政の将来を見つめて発言して欲しいものです。そうでないと森を見ずに木ばかりをつつき回されますよ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに一曲」 グリーグ作曲 ピアノ協奏曲イ短調ドヴォルザークが「メロディー・メーカー」ならエドワルド・グリーグ(1843-1907)はさしずめ「北欧のメロディー・メーカー」と呼ぶにふさわしい作曲家ではないでしょうか。 「ペール・ギュント」「ホルベア組曲」などの数々の管弦楽作品、「抒情小品集」などのピアノ作品、ヴァイオリンやチェロ・ソナタなどの室内楽作品、また歌曲集など、どれもこれも美しい旋律に彩られており、親しみの持てる音楽ばかりです。それらのグリーグの作品の中でもひときわ美しいのが「ピアノ協奏曲イ短調 作品16」です。グリーグはドイツのライプチッヒ音楽院(メンデルスゾーンが創設)で作曲を学び、ドイツ・ロマン派の音楽から色濃く影響を受けて祖国ノルウエーに帰り、ノルウエーの民族音楽を作品の中に取り入れて、しかもロマン派の音楽を継承して美しい作品を数多く書き残しています。この作品16のピアノ協奏曲は、愛妻ニーナと結婚した翌年の1868年にコペンハーゲン(デンマーク)で作曲されています。 新婚時代に書かれたこの曲は、まさに夢と希望に溢れた瑞々しい音楽が全編を流れています。シューマンとクララの音楽史に残るほどの夫婦と比肩されるほどの愛妻ニーナとのその後の生活は仲睦まじかったそうです。 ニーナはソプラノ歌手で、夫グリーグの歌曲の作曲に大いに貢献したと伝えられています。ピアノ協奏曲イ短調は前述のように夢・希望にあふれた音楽は、祖国ノルウエーの美しい風景をそのまま映したかのようで、冒頭の激しいピアノと管弦楽の開始は、まるでノルウエーのフィヨルドの海岸に打ち寄せる波の激しさのようです。曲全体は叙情的で憂愁に包まれた北欧の美しい自然を想い起すような旋律に満ちています。特に第2楽章はまるでショパンの夜想曲を想起させるような、ロマンの香りがいっぱいの音楽にむせています。在職中にノルウエー・ベルゲンに行ったこことがあるのですが、そこはグリーグが愛してやまなかったニーナとの平和な生活を共にした町で、彼の墓もそこにありフィヨルドの海を見下ろしているそうです。 このベルゲンにはいつも1月の寒い時期で、私は一度もグリーグが見て暮らした丘からフィヨルドを見下ろすことが出来なかったのが残念です。愛聴盤(1)ラド・ルプー(P) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCAレーベル 466383 1973録音 海外盤)LP時代から聴いているルプーの名演。 「千人に一人のリリシスト」と言われたルプーのピアノはしなやかに旋律を歌わせており、実に瑞々しい音楽に包まれています。(2)スヴィアトスラフ・リヒテル(P) マタチッチ指揮 モンテカルロ歌劇場管(EMI原盤 東芝EMI TOCE14058 1974年録音)この人のピアノの音色には強い意志が感じられて、それが技巧の確かさで裏打ちされて叙情的・詩的な世界を見事に表現しており、生命力にあふれた音楽を聴かせています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1845年 初演 メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲1860年 誕生 フーゴー・ヴォルフ(作曲家)1883年 誕生 エンリコ・トセリ(作曲家)1944年 初演 ヴィラ=ロボス 「ブラジル風のバッハ第7番」1985年 没 ユージン・オーマンディ(指揮者)
2008年03月13日
コメント(6)
-
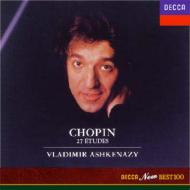
ショパン 練習曲集/春だぁ~
「春だぁ~」ここ大阪はすっかり春めきました。 昨日は快晴に恵まれて気温も17度近くまで上昇。 ほほを時折撫でていく微風にも春の香りが漂ってきます。 沈丁花の花の香りが鼻をつくようになりました。まだ咲き誇るまでいきませんが、白い花びらが可愛らしく顔を覗かせています。土の香りもするようになりました。野草たちもおそるおそる顔を出して来ています。 ハコベや耳菜草、仏の座まども「もういいかな?」と言わんばかりに顔を出してきています。 オオイヌノフグリも点在して咲くようになりました。春の息吹が感じられるこの頃です。 やはり春はいいですね。 1年を通して一番活発な時期です。花も草も命いっぱいに生きていく芽生えを感じます。これからはカメラを持って花を求めて歩き回るいい時期になりました。 奈良のお水取りも明後日で終わります。 すぐに「暑さ寒さも彼岸まで」がやってきます。 楽しい時期です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの音楽」 フレデリック・ショパン作曲 「練習曲」ピアノを習う人、練習する人ならチェルニーやハノンといった指使いのための「練習曲」で音階練習をしていますが、今日採り上げますショパンの「練習曲」(エチュード)はそうした教則本の類ではなくて、曲自体に風情や情緒、感情が盛り込まれている曲で、情感豊かな「練習曲」です。 練習曲で実用的な題材ながらも深い芸術性を湛えていて、ショパンの偉大さを表している曲集です。「練習曲集」は作品10と25に、それぞれ12曲ずつ作曲されており、他に作品番号の付されていない3曲があるので、計27曲からなる曲集です。 39歳という若死にですから、これらの曲は19歳から26歳に間に作曲されており、この二つの曲集には副題が付けられているのが多くあります。作品10の第3番「別れの曲」、 第5番「黒鍵」、 第12番「革命」などや、作品25の第1番「エオリアン・ハープ」、 第9番「蝶々」、第11番「木枯らし」などがあります。 特にポーランドを離れてパリに行き(1830年20歳)、祖国がロシアに占領されてしまい、二度と祖国の土を踏むことのなかったショパンのふつふつとした情念が噴き上げてくるような「革命」(1832年作曲22歳)には、嘆き、悲しみ、怒りのような情感が伝わってくるようです。また「別れの曲」は有名なピアノ協奏曲(2曲)とほぼ同時期に書かれていますので、当時彼が想いを馳せていた女性コンスタンチア・グラドコフスカへの惜情の想いでしょうか。深い精神性と豊かな情感の溢れるこれらのエチュードを今日は全曲盤で聴いてみたいと思います。愛聴盤 (1)ウラジミール・アシュケナージ(ピアノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシックス UCCD5085 1971-72年録音)(2)マウリッツオ・ポリーニ(ピアノ) (グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG9714 1972年録音)新素材を使用したCDで透明度が抜群に向上した驚異のCD。 2800円盤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1857年 初演 ヴェルディ オペラ「シモン・ボッカネグラ」1888年 誕生 ハンス・クナッパーツブッシュ(指揮者)1954年 初演 シェーンベルグ オペラ「モーゼとアロン」1954年 初演 ブリテン チェロ交響曲
2008年03月12日
コメント(2)
-
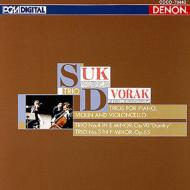
ドヴォルザーク ピアノ三重奏曲第3番
「珈琲ブレイクの一曲」 ドヴォルザーク作曲 ピアノ三重奏曲第3番アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)はチェコの生んだ大作曲家。 9つの交響曲、ヴァイオリン協奏曲、ピアノ協奏曲、チェロ協奏曲、オペラ、15曲の弦楽四重奏曲などの室内楽作品、「スラブ舞曲集」や交響詩などを書き残しています。ドヴォルザークと言えば交響曲第9番「新世界より」が彼の代名詞となっているほどの有名曲ですが、室内楽作品にも珠玉のような美しい旋律にあふれた作品があります。 ピアノ五重奏曲などがその例ですが、今日はひとまわり編成の小さいピアノ三重奏曲を聴いてみようと思います。ドヴォルザークはピアノ三重奏曲を4曲書いており、最後の第4番は「ドウムキー」という副題を付けられたウクライナ地方の民謡を表したタイトルで、彼の三重奏曲の中でも人気の高い曲ですが、その第4番の前の第3番を今日は聴いてみようと思います。彼のピアノ三重奏曲は4曲残されており、民族音楽的な旋律を用いて親しみが感じられ、また多様な音色が魅力の作品ばかりです。その中でも第3番は彼の母が1882年12月に亡くなったことから書かれた作品で、いつものドヴォルザーク調(明るく優しい温かさやのどかな田園調)が影を潜め悲しみに沈むドヴォルザークの心情を吐露したような音楽が書かれています。生々しさや辛い感情や激しい音楽が強く表現された珍しい曲です。チェロの長いしかも深い悲しみをたたえた緊張感の漲った第1楽章。民族舞踊風の旋律が印象的な第2楽章。深い哀愁を帯びたチェロの旋律が印象的に残る繊細な哀調に包まれた第3楽章。フリアント(チェコの古典的舞踊音楽)によるロンド形式で、激しさが前面に出た第4楽章。ドヴォルザークの残した激しい心情の吐露を聴くような音楽です。 やはり私はドヴォルザークが好きですね。何よりも旋律がすごく親しみやすく、わかりやすい。「メロディー・メーカー」というニックネームがあるほど旋律が表情豊かでいいですね。飽きもこない。いつまでも聴いていられる音楽です。愛聴盤 スーク・トリオ(DENON CREST1000 COCO70443 1977年録音)DENON CREST1000シリーズの一枚。 1000円盤でカップリングは第4番「ドウムキー」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1791年 初演 ハイドン 交響曲第96番「奇蹟」1830年 初演 ベッリーニ オペラ「カプレーティとモンテッキ」1867年 初演 ヴェリディ オペラ「ドン・カルロ」1917年 初演 レスピーギ 交響詩「ローマの泉」1976年 逝去 ジュラデイン・ファーラー(ソプラノ)
2008年03月11日
コメント(4)
-
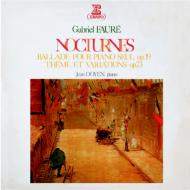
フォーレ 夜想曲集/炎上するピアノ
「炎上するピアノで演奏」先日3月8日ジャズ・ピアニストの山下洋輔がグランドピアノ1台を燃やして、そのピアノを演奏するというイヴェントが新聞で写真入りで報じられていました。私はこの記事を読んで「何故こんなことをするのか?」という疑問が湧いてきました。 高価なグランド・ピアノにガソリンをかけて発火させると同時に、消防服(防火服)に身を包んだ山下洋輔がピアノを弾き出す。 弾ける限界まで弾いていたそうですが、その演奏に何の効果、何の目的があったのかと大いに疑問が残ります。 一体何のためのパーフォーマンスなのかと問いたいですね。燃えていくピアノを演奏することにどんな価値があるのでしょうか? グランドピアノ1台を燃やすのであれば、「ピアノ売ってちょう~だ~い!」へ売ってその代金をどこかへ寄付した方がよっぽど貢献できるのにと思いました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 フォーレ作曲 夜想曲集「ノクターン(夜想曲)」は静かな情感をたたえた音楽で、やはり夜に聴くのにふさわしい音楽と言えるでしょう。 一日の出来事に想いを馳せながら振り返る音楽としてもいいし、若い人なら恋人を想い、二人きりになった熟年夫婦ならこれまで歩いてきた道程を振り返ったり、これからの老後に想いを馳せたりと、聴きながら想いを巡らせる恰好の音楽でしょう。イギリスの作曲家フィールドが創ったスタイルの夜想曲。 そしてショパンが芸術性豊かに21曲の作品を完成させており、「夜想曲」と言えばショパンと言えるほど有名です。ショパンの後の夜想曲は多くの人が作っています。ドビュッシーとかサティも書いています。シューマンにも数曲の作品が残されています。その多くの作曲家の中でもフォーレが書いた夜想曲は13あります。 私が聴いています音盤は全曲集ではなくて第1番、第2番、第6番、第10番の4曲のみ収録されており、あとはフォーレの「舟歌」や「前奏曲集」などのピアノ独奏作品集です。 いつかは全曲を聴いてみたいと思っています。これら4曲の中でも特に気に入っているのは第1番と第6番です。 抒情的でしっとりとした情感をたたえ、夜の中に音楽が溶け込んでいきそうな雰囲気と佇まいの趣きのある音楽です。まさに夜の珈琲ブレイクにぴったりの音楽です。 愛聴盤 ジャン・ドワイアン(ピアノ)(エラート原盤 ワーナーミュージック 1970-1972年録音)エラート・アニヴァーサリー・シリーズとして再発売されています。 2枚組で2940円の廉価盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1785年 初演 モーツアルト ピアノ協奏曲第21番1844年 誕生 パブロ・デ・サラサーテ(作曲家・ヴァイオリニスト)1892年 誕生 アルテュール・オネゲル(作曲家)2006年 没 アンナ・モッフォ(ソプラノ)
2008年03月10日
コメント(12)
-
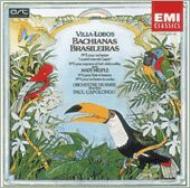
ブラジル風バッハ/喫茶店のモーニング・サービス
「喫茶店のモーニング・サービス」最近はどの喫茶店でもモーニング・サービスとして飲み物のほかにトースト1枚、ゆで卵とかを飲み物とおなじ値段で提供しています。 そのサービスは店によって異なります。 ミニ・サンドイッチを付ける店、トーストだけの店、値段アップしてハムは目玉焼きなどを出す店と様々です。この朝のお客さんと言うと大概は男女共に熟年層が多いですね。 これは私が住んでいる町の喫茶店の話ですから、大阪市内のターミナルなどの珈琲ショップや喫茶店とは違います。 そういうところは若年層も多いのですが。さて、わが町の喫茶店では熟年層が朝8時半~9時半頃までに決まった店に顔を出します。 そこで他愛のない四方山話だとか、シーズンであればプロ野球の話題、競馬・競輪、どこのパチンコ屋がよく出るとか、昨日はウン万円買ったとか話題も様々です。通う店は大概決まっているようです。 その決まった店で「常連」となり、同じように毎日通って来る他の客と親しくなりというパターンのようです。 一つの社交場なんでしょうね。 町の噂話なども語られます。そこに親近感が生まれて益々仲良くなっていくようです。 団塊の世代の人のように定年退職して仕事の一線から退いた人たちが地域のヴォランティア活動するにも便利な場所です。 ここから生まれるヴォランティアへの参加もあります。 情報が豊富ですから。これを呼んで「地域デビュー」と言います。 これまで仕事一本で会社に貢いできたのをこれからは自分の住んでいる町に貢献したいという願望なんでしょうね。私は複数のこういう人たちを見てきました。「たかがモーニング・サービス、されどモーニング・サービス」今日もわが町の喫茶店は朝からモーニング・サービスで賑わっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの音楽」 ヴィラ=ロボス作曲 ブラジル風バッハ第5番ブラジル出身のエイトル・ヴィラ=ロボス(1887-1959)はラテン・アメリカ最大の音楽家でギターを弾く演奏家でもあり、作曲家でもありました。 音楽史上では演奏家としてよりも作曲家としてその名を留めています。作曲した作品は正確な数を残されていないませんが、少なくと1000曲は確認されているそうです。 交響曲、ピアノ曲、ギター曲、室内楽、管弦楽曲とど多才な人であったようです。彼の紡ぎ出す音楽はブラジルの民族音楽に根ざしているようです。 ブラジルの民謡の定義を訊かれると「民謡? それは私だ」というエピソードが残っているほどに、彼はブラジルの民族音楽に自負を持っていたのでしょう。作曲はほぼ独学で習得したと言われています。 それに20歳代でブラジルの奥地に出かけて民謡や地場音楽を採譜したことが、後の彼の音楽の方向性を決めたようです。36歳(1923年)でヨーロッパに渡り、その後アメリカにも出かけて行き認められるようになったと言われています。そのヴィラ=ロボスの残した作品でも群を抜いて現代でも演奏される機会の多いのが「ブラジル風バッハ」です。 J.S.バッハを熱愛していたそうです。 全部で9曲から成る作品ですが、曲ごとの関連性はありません。 チェロだけの合奏であったり、ピアノと管弦楽、管弦楽だけ、合唱と弦楽合奏、フルートとバスーン、ソプラノ独唱と8台のチェロであったりと、編成楽器はまちまちです。その「ブラジル風バッハ」の中でも特に有名なのが第5番です。 ソプラノ独唱と8台のチェロで演奏されるこの作品は、2部に分かれていて1.アリア 2.踊りと呼ばれる部分から構成されています。チェロのピッチカートによって歌い出されており、非常に有名な旋律です。 歌詞がないヴォカリーズと例えられる旋律で、いかにもブラジル風といえる美しい旋律です。ソプラノで歌われる部分はやはりブラジルの詩人による詩だそうです。「踊り」では土俗的な民族舞踊のようで、サンバなどで有名なブラジルの熱い祭りを想い出させます。 奥地での採譜の際に聞いた野鳥の声がモチーフとして使われているそうです。ヨーロッパのクラシック音楽とは性格や音楽と一線を画す作品ですが、とても親近感が持てる曲です。題名の「ブラジル風バッハ」ですがバロック様式で書かれているわけでもなく、聴いていてどこが「バッハ」なのかわかりません。 初めて聴いた時は拍子抜けするほどブラジル風に聴こえ、今でもその感じは抜けません。まあ、そういうことに拘らずに聴いています。愛聴盤 ポール・カポロンゴ指揮 パリ管弦楽団 マディ・メスプレ(S)(EMI原盤 東芝EMI TOCE59148 1973年録音)第2番、第5番、第6番、第9番の4曲が収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1842年 初演 ヴェルディ オペラ「ナブッコ」1849年 初演 ニコライ オペラ「ウインザーの陽気な女房たち」1877年 初演 チャイコフスキー 幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」1910年 誕生 サミュエル・バーバー(作曲家)
2008年03月09日
コメント(8)
-

オスカー・ピーターソン
「珈琲ブレイクの音楽」 オスカー・ピーターソン トリオオスカー・ピーターソン(1925ー2007)はカナダ・モントリオール出身のジャズ・ピアニストで戦後ジャズ音楽を引っ張った偉大なジャズマンの一人でした。 ジャズ・ピアノと言えばこの人の名前が挙がるほどの、まさしく「巨人」と呼ぶにふさわしいピアニストでした。 デビューしてからはメンバーにも変遷がりましたが、トリオとしてはエド・シグペンのドラム、レイ・ブラウンのベースに落ち着き、ピーターソン・トリオと言えばこのメンバーでしょう。一時はギターも入ったことがありますが、トリオと言えばこのピアノ、ドラム、ベースという標準的な組み合わせで長い間ファンを魅了していました。スイング時代のようなピアノ奏法に和声感覚がとてもモダンなスタイルで、スイング調のピアノが聴いている者を浮き浮きとさせる魔力があり、超絶技巧を誇る彼のピアノはジャズ界きってのもので、目の回るようなピアノタッチ、ダイナミックな演奏と流麗なアドリブが部屋を瞬時にジャズ・カフェにするような雰囲気があります。そのあたりを人は「鍵盤の皇帝」というニックネームで呼んだのでしょう。強靭なタッチはミス・タッチが無いと言われ、明快でハッピーな演奏が身上のピアニストでした。 それを支えるエド・シグペンの軽快なドラムがレイ・ブラウンのベースと共にきっちりとリズムを刻んでおり、ジャズ音楽の醍醐味を味わえます。オスカー・ピーターソンは昨年(2007年)12月23日に82歳で亡くなっています。 彼のもう一つの功績は日本人ジャズ・ピアニスト秋吉敏子を見出したことでしょう。 ピーターソンのピアノ演奏の流れを汲む秋吉はその後ニューヨークを中心に活躍して、日本人ジャズ演奏家の草分けのような存在として君臨したのです。このトリオには録音も数多く残されていますが、何と言っても「We Get Request」が素晴らしい演奏を繰り広げています。 聴衆からリクエストを募りそれを即興で演奏するジャズの醍醐味を味わえる演奏・録音でした。今夜は珈琲を味わいながらオスカー・ピーターソンのピアノに酔いたいと思っています。愛聴盤 (1) We Get Requests (ヴァーヴ・レーベル ポリドール POCJ1801 60年代録音)収録曲コルヴァード酒とバラの日々マイ・ワン・アンド・オンリー・ラブピープルジョーンス嬢に会ったかい?ユ・ルック・グッド・トゥーミーイパネマの娘D & Eタイム・アンド・アゲイングッドバイJ.D(2) Best of Oskar Peterson (ヴァーヴ・レーベル POCJ1651 ポリドール)ジャズナンバーのスタンダードばかりを演奏した、まるでモダン・ジャズ入門用のようなCDです。収録曲酒とバラの日々Cジャム・ブルースサテン・ドールフライ・ミー・トゥ・ザ・ムーントゥナイトジャスト・イン・タイムアイ・ゲット・ア・キック・アウト・ユーオール・オブ・ミーサマータイムラブ・フォー・セールアイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン夜も昼もA列車で行こうイエスタデイズブルームーンマイ・ファニー・ヴァレンタイン虹の彼方に一晩中踊れたら
2008年03月08日
コメント(0)
-
インドのジョーク
「珈琲ブレイクのジョーク」インド人はジョーク好きです。 ビジネスランチやディナーの席が設けられるとジョークの披露合戦が始まります。 それで席が盛り上がるという寸法です。 会社や友人同士のパーティなどでも深夜まで延々とジョークが続きます。 ちなみにインドのパーティでは始まる時間は大概9時ごろです。 それもまだ食事は始りません。 フィンガースナックをつまみながらウイスキーやブランデーを呑みながら話が延々と続き、12時頃になって来るとこちらのお尻が椅子から浮いてくるのですが、彼らはそれからやっと「さあ、食事にしようか」という按配です。そんなジョークが好きなインド人のジョークの一例です。昔インドのある村に「賢人」と呼ばれる一人の長老がいました。 彼は村の揉め事や隣村との諍い事を知恵と頓知でうまく丸く収めることのできる老人でした。 それで村人からは「賢人」と呼ばれて敬われていました。その村に貧農の息子がいました。 お父さんが過労で亡くなり、多くの兄弟と父の持ち物を分配しましたが、末っ子の彼には若い山羊一頭が与えられただけでした。その年、村では山羊の競争コンテストが企画されました。 優勝した山羊の持ち主には賞金と褒美の品物が贈られます。 彼も自分の山羊を出すことに決めて参加を申し込みました。 しかし彼の山羊は少しノロマなので不安でした。そこで思いついたのが長老に相談して優勝する方法を教えてもらうことでした。 さっそく彼は長老に家に行って尋ねました。 長老曰く「そんなことは簡単なことじゃ。 飛びっきり辛いチリソース(唐辛子ソース)を用意しなさい。 スタートの号砲が鳴ればそのチリソースを山羊の肛門に塗りこむのじゃ。 山羊はびっくりして物凄いスピードで走るじゃろう。 それで優勝間違いなしじゃ」レース当日少年はガニ股歩きで山羊を連れてやってきました。 号砲が鳴ってすぐに山羊の肛門にチリソースを塗ると、山羊は一目散に走っていき見事優勝を果たしました。それから1週間後、長老はぼやいています。 「あの恩知らずめ。 優勝してもお礼のあいさつにも来ない。 礼儀の知らん奴じゃ」と。10日後にやっと少年が長老の家にやってきました。 長老は彼を思いっきり叱りました。 「この恩知らず! 優勝したあくる日にでも挨拶に来るのが礼儀じゃ。何と心得ておるのじゃ!」「それはよくわかっています、長老。 でも来たくても来れなかったのです。 長老から秘策を教えてもらって、練習のためにチリソースを塗ると山羊はびっくりして飛び出しました。 その山羊を捕まえるのに、私もチリソースをお尻に塗らないと捕まらなかったのです。 それからは歩くのにも痛くて痛くて!」お後がよろしいようで。
2008年03月07日
コメント(0)
-
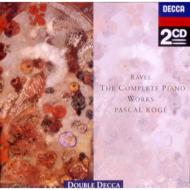
ラヴェル 「夜のガスパール」/青春とは
「青春時代はいつまで?」よく訊かれる質問であり、訊く質問です。 「青春時代」って中学生の頃なのか、高校生の頃なのか、はたまた大学生の頃なのか、それともフレッシュ社会人の頃なのか?私は若い時には「青春時代」とは勉学に励む学生時代だと思っていました。 恐れを知らず社会のことも知らない純粋無垢の時代のことを「青春時代」だと思い込んでいました。それが40歳を過ぎた頃に気がつきました。 仕事で未知の世界に飛び込んだ頃でした。 「仕事」であれば家庭を持っていると、普通の通念では男が家庭・家族の屋台骨を背負っていると自負します。 「仕事世界」があるから家族が食べていけると。「不惑の年」40歳を過ぎて今まで扱ったことのないジャンルへ飛び込んで行きました。 製品はこれまで扱ったことのない物ばかり未知の世界でした。 そこで育つためにはそのジャンルの物をマスターして海外に売る、これが至上目標でした。そのためにはその製品を好きにならなければいけない。 自分は顧客から好かれなければなりません。 それを成し遂げるためには「情熱」と「興味・好奇心」が必要です。その時に思ったのです。 人間幾つになっても「情熱」と「興味・好奇心」を失わなければ、その人はたとえ80歳になっていても、「青春」を謳歌しているんだと。 ある物に滾るような、沸き立つような情熱を燃やして常に興味を抱いている時があれば、年齢に関わりなくその時が「青春時代」を過ごしていると言えないでしょうか?そして自分の心の中に「青春」があれば健康でいられるんだと。幾つになっても「情熱」と「興味・好奇心」を失いたくはありませんね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 ラヴェル作曲 「夜のガスパール」フランスの作曲家で「オーケストラの魔術師」「スイスの時計師」とか呼ばれた精緻で、華麗な音楽を書残したモーリス・ラヴェル(1875-1937)。 今日は彼が数多く遺した名曲の中からピアノ独奏曲「夜のガスパール」を聴いてみようかという気になっています。最近はどうもピアノ曲に魅かれているようで、取り出すCDがピアノ音楽が多いようです。 珈琲タイムに聴いていると落ち着くのかな? いや、そうならチェロでもいいはずだしヴィオラでもいい。 でも何故かピアノの音色に魅かれるこの頃です。この曲はラヴェル33歳の1908年に書かれており、この時期はラヴェルにとって充実した頃であったようです。 ピアノ曲では「ソナチネ」「鏡」「マ・メール・ロワ」、オーケストラ曲では「スペイン狂詩曲」などが書かれた時期です。「夜のガスパール」は「アロイジス・ベルトランの3つの詩による」と副題が付けられているのですが、19世紀初めのフランスの詩人ベルトランの散文詩集「夜のガスパール」から3篇を選んで、そこから得たイメージとかインスピレーションで書いているようです。ほかのピアノ曲と同じように非常に精緻で透明度の高い、澄んだ音色が魅力の「夜のガスパール」。 部屋の空間に瑞々しいピアノの音色が広がるような作品です。第1曲「水の精」人間に恋をしたオンデーヌ(水の精)が、恋に破れて雨の中に消えていく物語ですが、水音のさざ波のような開始音楽と水の精を表す美しい旋律に魅了される曲です。第2曲「絞首台」絞首台の「死」の様相を音楽にしており、引導を渡すかのような鐘の音が不気味に響く、鬼気さえかんじられ、ピアノ音楽をとことん追求したようなラヴェルの面目躍如といった曲です。第3曲「スカルボ」スカルボとは悪戯好きの小妖精のことで、幻想的にスケルツオで書かれており、暗い陰惨なイメージの「絞首台」のあとだけに、この軽妙さが活きています。 3曲中一番長い曲で、技巧に富んだ、ラヴェル独特の精緻なピアノ音楽の魅力を味わえる曲です。愛聴盤 (1)ラヴェル・ピアノ独奏曲全集 パスカル・ロジェ(ピアノ) (DECCA原盤 UCCD3224 1974-75年録音 ユニヴァーサル・ミュージック)「ソナチネ」「高貴で優雅なワルツ」「クープランの墓」「プレリュード」「マ・メール・ロワ」「亡き王女のためのパヴァーヌ」「夜のガスパール」「道化師の朝の踊り」などラヴェルのピアノ作品を収めた2枚組CDです。(2)マルタ・アルゲリッチ(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5116 1974年録音)ラヴェルのピアノ協奏曲とのカップリングで1000円盤。(3)ウラジミール・アシュケナージ(ピアノ) (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCL5167 1982年録音)「亡き王女のためのパヴァーヌ」「感傷的なワルツ」などのラヴェル作品、「喜びの島」(ドビッシーなどのピアノ作品が収録されたアルバム。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音樂カレンダー」1831年 初演 ベッリーニ オペラ「夢遊病の女」1853年 初演 ベルディ オペラ「椿姫」1914年 生誕 キリル・コンドラシン(指揮者)1930年 生誕 ロリン・マゼール(指揮者)1933年 逝去 ジョン・フィリップ・スーザ(作曲者)1944年 生誕 キリ・テ・カナワ(ソプラノ)
2008年03月06日
コメント(4)
-
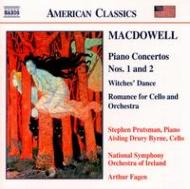
マクダウエル ピアノ協奏曲第2番/アメリカの国土の大きさ
「アメリカ国土の大きさ」在職中には様々な国を訪問したり日本に居ても外国人と接触する機会が多くありました。 そうした体験でもアメリカ人との珈琲ブレイクやランチ、ディナーなどで時々話題になるのが日本の国土とアメリカ国土の大きさ・広さの違いでした。日本から見ると桁はずれに広い・大きい国がアメリカです。 私の娘がアメリカ人に嫁ぎ今はノースカロライナ州で親子4人で住んでいます。 その家の敷地が700坪なんです。 また日本人商社マンの駐在する家も300坪とか400坪とかの規模がざらにあります。 土地が広いから地代も日本と比べ物にならないくらい安いのです。サン・フランシスコ(西海岸)からニューヨーク(東海岸)まで飛行機の直行便で6時間半かかる国土の広さ。 6時間半と言えば大阪からシンガポールまでの飛行時間です。 札幌から沖縄までが2時間半ですから、アメリカの国土の広さ・大きさが測り知れます。もう一つの例ですが、日本の人口は1億2千万。 その総人口が住んでいる日本の面積(宅地)はわずか4%です。 あとは山林・農地・工業地帯です。 わずか4%の土地に1億2千万人が住んでいるのです。この日本の国土はアメリカ・カリフォルニア州のそれとほぼ同じです。 と言うことはカリフォルニア州の4%に1億2千万人が住んでいることになります。 アメリカの人口のほぼ半分です。 いかにアメリカの国土が大きい・広いかがわかる例です。この話をアメリカ人にすると、いかに自国が大きいか、日本が小さいかを即座に理解してくれます。東海岸に移住したイギリス人やフランス人などの「ヨーロッパ人」が西海岸を目指して開拓していった「フロンティア・スピリッツ」の偉大さも同時に理解出来る例です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 マクダウエル作曲 ピアノ協奏曲第2番エドワード・アレグザンダー・マクダウェル(1860ー1908)はアメリカを代表するロマン主義音楽の作曲家・ピアニストでした。 数多くののピアノ曲や2つのピアノ協奏曲を書き残しています。マクダウェルは少年の頃からピアノの音楽教育を学んでおり、17歳でフランスに渡ってパリ音楽院に入学するほどの秀才だったそうです。 その音楽院の同級生にはクロード・ドビッシーがいたり、また音楽院在学中にはリストにも面会しているそうです。 リストが音楽院訪問の際には、リストが作曲した交響詩のピアノ版を演奏したというエピソードも残っています。パリ音楽院では作曲も勉強しており、少しずつ曲を書いていきました。28歳になった1888年にアメリカに戻り、ボストンで音楽教師やピアニストとして活動を続けています。 忙しい学校での生活のかたわら作曲を続けていたようです。マクダウェルの少年期から青年期にかけてのヨーロッパ生活と受けた文化が、彼の作風に何らかの影響を与えているように思えます。 精神的には新天地アメリカの風土を基盤とした心象・文化でなくて、ヨーロッパ文化・精神文化が影を落としているように思えます。例えば彼のピアノ協奏曲第1番は、ノルウエーのエドアルト・グリーグ(1834-1907)が書いたピアノ協奏曲の影響が多分に見られます。 作曲家名を知らずに聴いていると、グリーグの曲なのかなと思うほどです。またピアノ作品だけでなく歌曲にも多くの作品を残しており、最も有名なのが「野ばらに寄す」で昔から日本でもポピュラーな歌曲の一つです。今日の話題曲、ピアノ協奏曲第2番は、華麗なピアノの技巧と紡ぎ出されるような、こぼれるような詩情にあふれており、私のようにロマンティックな音楽を好きな者にはたまらない魅力に満ちた協奏曲です。 この曲がどうしてもっと演奏会でとりあげられないのか、録音ではマイナーな曲の扱いを受けているのか不思議なくらいです。抒情的で哀感を滲み出した本格派ロマン音楽としてのピアノ協奏曲。 是非一聴をお薦めします。このマクダウェルのピアノ協奏曲第2番が1889年の今日(3月5日)、アメリカで初演されています。愛聴盤スティーヴン・プルッツマン(p)/ アーサー・フェイゲン指揮/アイルランド国立交響楽団(Naxosレーベル 8.559049 1999年11月録音)代表作の2曲のピアノ協奏曲が収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1867年 初演 ボーイト オペラ「メフィストーフェレ」1887年 誕生 エイトール・ヴィラ=ロボス(作曲家)1889年 初演 マクダウェル ピアノ協奏曲第2番1953年 没 セルゲイ・プロコフィエフ(作曲家)
2008年03月05日
コメント(2)
-
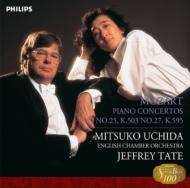
モーツアルト ピアノ協奏曲第27番/川柳
「珈琲ブレイクの川柳」これも喫茶店への原稿の一つです。 以前このブログでも紹介しました川柳を軸に書き直したものです。最近「サラリーマン川柳」など川柳が注目を集めています。世相風俗を痛快に斬り、家族内の面白くないことや、ときに自分をも笑いのめす川柳は庶民の武器でピリッとスパイスの効いた社会へのメッセージとなっています。川柳の起源は江戸時代と言われています。封建制度の中で鬱積したやり切れない気分を風刺という姿で表した庶民の鬱憤晴らしだったのでしょうか。 そう言えば現代でも似た世相です。こんな一句があります。課長いる?返った答えがいりません「居る」と「要る」では大違いですね。 その課長さんが自宅に帰ると粗大ゴミ朝出しても夜帰る いやはや会社で要らないと言われて家に帰れば粗大ゴミ。そんなお父さんが妻に対して反撃に出ましたが、何とも侘しいですね。妻の背にテレビのリモコン押してみるリモコンスイッチの電源を押して「消えてくれ」と言いたいんでしょうね。いやあ~、川柳は面白いですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 モーツアルト作曲 ピアノ協奏曲第27番変ホ長調ヴォルフガング・アマデウス・モーツアルト(1756-1791)がわずか35歳という生涯で、ピアノ協奏曲を全部で27曲書き残しています。 その最後の協奏曲がこの第27番です。モーツアルトは、残されている彼に関する記述では、底抜けに明るく天真爛漫な性格の持ち主であったようです。 いつも上機嫌で、楽しいことも悲しいことも臨機応変に応える性格だったそうです。数多くの手紙が今でも保存されているそうですが(この功績は、悪妻と言われているモーツアルトの妻コンスタンツェが彼の死後にまとめたことによると言われています)、32歳頃からお金に苦労し始めたそうで、借金の申し込みの手紙が増えているそうです。 昔、雑誌「レコード芸術」だったと記憶していますが、この第27番を書き上げた1791年の1月の寒い日に暖房用の薪さえ買うお金に窮しており、妻と寒さをしのぐために二人でダンスをしながら体を温めあったというエピソードを読んだことを覚えています。第27番はこうした悲惨な貧乏生活の中で1791年の1月5日に書き上げられています。しかし、この曲にはそうした暗い生活の翳りが微塵も感じられません。 あくまでも明るさを湛えた音楽が紡ぎ出されています。 そうした明るい情緒の中でも、曲全体に「諦観」に境地が達しているように感じられます。 言葉で表現することが難しいほどに「澄み切った諦観」というものを感じます。明るさはありますが、第26番「戴冠式」のような華麗な気分は全くなくて、まるでモーツアルトが「瞑想」に耽るような楽想は、その年の12月5日にこの世を去ることを予感していたような想いになってしまいます。第2楽章「ラルゲット」で、ピアノとオーケストラが淡々と演奏される音楽は、まるで「対話」のようで「協奏的な詩」のように感じます。 貧乏に追い立てられているモーツアルトが「死」を予感したかのような「諦め」の境地のような感さえあります。ハイドンがモーツアルトの死の前年にロンドンに旅行をする時に、モーツアルトは「先生と二度とお会いできないかもしれません」と言ったエピソードが残っているそうです。 こうしたエピソードを聞くと、余計にこの曲全体に滲んでいる「澄み切った美しさ」が「死」を予感していたのかなと思ってしまいます。第3楽章「ロンド」は、この第27番の書かれたすぐあとに作曲された、有名な歌曲「春へのあこがれ」がそのまま転用されていて、春が訪れるのを待ち望む気分を歌った「春へのあこがれ」。 モーツアルトには、もう二度と「春が来る」こと叶わずに彼岸に旅立ったことを思わずにおれない想いでいつもこの曲を聴いています。ピアノ協奏曲第27番は1791年の今日(3月4日)、初演されています。愛聴盤(1) 内田光子(P) ジェフリー・テイト指揮 イギリス室内管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7053 1987年録音)何よりもピアノの音色がとても美しく響いています。ドラマティクな強い音と豊かでありながら孤独さを感じさせる柔和な弱音の響きがとても美しく感じられるピアノです。 1000円盤としての再発売となっています。第25番とのカップリングです。↓内田光子 愛聴盤(2) クリフォード・カーゾン(P) ベンジャミン・ブリティン指揮 イギリス室内管弦楽団(DECCAレーベル 4677092 1970年録音 海外盤)以前POCL9417としてリリースされていた盤で聴いていますが、この曲の内面的な哀感を見事に表現しています。第20番とのカップリングです。↓カーゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1678年 誕生 アントン・ヴィヴァルディ(作曲家)1791年 初演 モーツアルト ピアノ協奏曲第27番1929年 誕生 ベルナルト・ハインティンク(指揮者)
2008年03月04日
コメント(2)
-

犬矢来/
「犬矢来」これは喫茶・レストランから依頼された件の原稿の一つです。京都には今でも江戸風情を残す情緒ある建物や風物の残る所が随所に見られます。 その代表的な街並みはやはり「祇園」でしょう。 舞妓さんの置屋・倹番などの玄関には塩を盛って置いてあったり、提灯が飾られていたり、「駒寄せ」と呼ばれる板塀の前に格子のガードのような木製の、人の腰くらいの背の防御柵などが見られます。 それらはまるで時空を超えた由緒ある歴史的情緒を思わせるものがあります。そうした風情の中でも今では一般の民家ではほとんど見ることが出来ない「犬矢来」があります。「イヌヤライ」と読みます。 江戸時代に出来た柵の一つですが、これは板壁を道から跳ね上がる泥水や犬の小便から守るために作られた柵ですが、竹で作られており掃除をするときはそのまま外して洗えるようになっています。 今では料亭や料理屋の板塀に沿って置かれています。板壁の防御・保護の目的で考えられた柵ですが、もう一つ目的があったそうです。江戸時代の家の造りは現代と比べて壁が薄かったそうです。 家・料理屋などで内密の話をしていると外壁に耳を寄せますと中の内密の話が聞こえたそうです。 この犬矢来を立てておくと板壁に耳を寄せることができません。 その盗み聞きを防止する目的からもこの「犬矢来」を立て掛けたそうです。犬矢来
2008年03月03日
コメント(6)
-
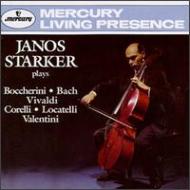
ヴィヴァルディ チェロ・ソナタ第5番/レストランからの依頼
「レストランからの依頼」 2月27日に駅前の喫茶・レストランで珈琲を味わっていると、マスターが私に一つの依頼を打診してきました。 「店のテーブルにくだけた話をエッセイ風に書いたものを置きたいと考えているけれど、その原稿をA4一枚ほどに書いてくれませんか?」という打診でした。 テーマは選ばない、旅行、衣・食・住、スポーツ、絵画、建築、趣味の話、何でもいいからお客さんが珈琲一杯を味わって「あ~、今日はここへ来てこんな話を仕入れることが出来た!」と思って帰ってもらうことが目的なんです、と説明するマスター。この依頼を聞いた時に思ったのが「何で私なの?」でした。 それを尋ねると「ともさんがぴったりだからですよ、このアイデアを考えた時にともさん以外に思い当たる人はいなかったんです」。私にはエッセイ風の肩の凝らない洒脱な文章なんて書いたこともないし、10卓あるテーブル全部に同じ文章を置くわけにはいかないし、週刊単位で差し替えするとなると1か月に40枚書く計算になります。40枚も話題を変えたエッセイ風の、それも肩の凝らない話なんて書きようがない、目がくらみそうな話です。 「それはちょっと・・・・」と断り始めると「いいえ、ともさんなら書けますよ。 自分の体験でなくてもいいのです。 書物をたくさん読んでいなさるから話題は豊富だし、話題に困れば図書館で借りた本の内容を書いてもらえばいいのですから」と強硬に頼んで来られて困っています。「まあ、できるだけ書いてはみますが期待しないで下さいね」と答えるしかなかったのですが、横にいた美帆さんがくすくす笑っている。 「ともさんに肩の凝らない話なんて考えられないわ、あのブログ記事を読んでいると」と冷やかされました。さあ、これから大変だなと困りながら話題を考えています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに一曲」 ヴィヴァルディ作曲 チェロ・ソナタ第5番ホ短調今日はバロック時代に遡ってチェロ・ソナタを聴いてみようと思います。 紹介のCDは「バロック・チェロ・ソナタ集」というヤーノシュ・シュタルケルが弾いているバロック時代に書かれたチェロ・ソナタばかりを収録したディスクです。 J.S.バッハ、ヴォヴァルディ、ボッケリーニ、コレッリ、ロカテッリなどが書いたチェロ・ソナタばかりが収められており、その時の気分で1~2曲聴いています。今日はその中からヴィヴァルディが書いた6曲のチェロ・ソナタから第5番を採り上げました。ヴィヴァルディと言えば「ピエタ養育院」。 ヴェネチアの身寄りのない少女たちを収容して音楽教育を施した有名な施設ですが、彼は弦楽器や管楽器などの多様な音色とその表現を試すために、養育院に作られたアンサンブルを使って試演しながら作品の音色や表現の可能性を追求していたそうです。この曲は4楽章形式で書かれており、第1楽章の甘くも美しい旋律、第3楽章のシチリアーナのリズム、メヌエットのような第4楽章などが素晴らしい音楽空間を創り上げており、深々としたチェロの音色が部屋を満たす時、そこに訪れるのは至福の音楽空間と時間です。今日も大好きな珈琲を味わいながらそうした時空をさまよってみたいと思います。愛聴盤 ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ) スティーブン・スエーディッシ(ピアノ)(マーキュリー原盤 Philipsレーベル 434344 1966年録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1759年 初演 ハイドン 交響曲第103番「太鼓連打」1824年 逝去 ベドルジーハ・スメタナ(作曲家)1873年 初演 ビゼー 小組曲「子供の遊び」1900年 生誕 クルト・ヴァイル(作曲家)
2008年03月02日
コメント(6)
-
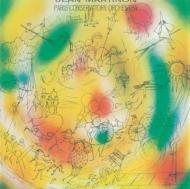
「死の舞踏」/春遠からじ・蕗の薹
「もうすぐ春だ!」今日から3月。 「3月」という言葉の響きには春を感じさせます。 眠っていた生命が目を覚まして土からも木々からも躍動するエネルギーを予感させる響きを感じます。奈良・二月堂の「お水取り」が始まります。 3月14日に終わります。 関西ではこの「お水取り」が終われば「春が来た」と信じています。 すぐに「暑さ、寒さも彼岸まで」の「彼岸の入り」です。 この「彼岸」が終われば桜がぼちぼちと蕾を開き始めるでしょう。 鶯が鳴き、他の野鳥も春を謳歌する季節になります。私のPentaxもほぼ冬眠状態でしたが、春になれば「今日はこっち、明日はあちら」へ連れて行けとおねだりが始まります。 やはり「命の息吹」を感じる春はいいですね。 「3月」は実に響きのこもった希望のようなものを与えてくれる言葉です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに一曲」 サン=サンーンス作曲 交響詩「死の舞踏」カミュ・サン=サーンス(1835-1921)の書いた交響詩の中でも最も有名な曲で、これはフランスの詩人アンリ・カザリスの詩に基づいて書いているそうです。 詩人の名前も詩も知りませんが、どうやらムスルグスキーの交響詩「はげ山の一夜」に似た内容で、音楽もそういう感じで進行しています。真夜中の12時になると「死神」が墓場に現れて来る(ハープの音で表現されています)ところを描いていたり、独奏ヴァイオリンが墓場でのワルツを描くように書かれていたり、骸骨が踊るカチャカチャという音を木琴で表現されていたり、グレゴリア聖歌の「怒りの日」の旋律が奏でられクライマックスへと導かれています。やがて日の出が始まると踊りも終焉を迎え、ヴァイオリンが消え入るように音楽を閉じていきます。まるで「はげ山の一夜」の音楽にも似た構成と内容の、伝奇的なホラーまがいの内容と音楽です。もう20年近くこの曲を聴いていません。 今日は珈琲を味わいながら久しぶりに聴いてみようと思います。今日はフランスの名指揮者ジャン・マルティノンが1976年に亡くなった命日です。 管楽器が素晴らしい音色だったパリ音楽院管弦楽団(現在のパリ管弦楽団の前身)を振った1957年の古い録音盤で聴いてみようと思っています。愛聴盤 ジャン・マルティノン指揮 パリ音楽院管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD9207 1957年録音)あ私の持っている盤は以前ポリドールがリリースしていましたが、今はユニヴァーサルからリリースされた再発売盤となっています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1810年 生誕 フレデリック・ショパン(作曲家)1896年 生誕 ディミイトリ・ミトロプーロス(指揮者)1924年 初演 ショスタコービチ 交響曲第7番「レニングラード」1976年 没 ジャン・マルティノン(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「春遠からじ」 蕗の薹(フキノトウ)地面から這い出たかの感じの「蕗の薹」。 これを見つけ出すと「春遠からじ」の感をうかがえます。
2008年03月01日
コメント(6)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-
-
-

- 楽器について♪
- 2025年冬のハープコンサートのお知ら…
- (2025-11-23 00:18:07)
-







