2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年10月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
ブログの暫定休止
「ブログの休止」突然ですがしばらくの間ブログ記事の掲載を休止致します。理由は先月半ば以来非常に不愉快な事に巻き込まれており、精神的に非常に落ち込んでおります。これまでは何とかそれを抑えながら書いてきましたが、そろそろそれにも限界が来たようで、しばらく休止することにいたしました。こういう精神状態では記事もうまく書く自信がありませんので、思い切って休むことにしました。どれほどの休止期間で元に戻ることが出来るかは推測しかねますが、なるべく早く再開できる日が来ることを私自身も願っております。自分を精神的に鍛え直して再出発したいと思います。新たに再開出来ましたならば、より一層のご愛顧を賜りたいと願っております。尚、リンクさせていただいた方のブログや、リンクしていただいた方のページには、これまでと変わりなく訪問させていただきますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
2008年10月03日
コメント(32)
-
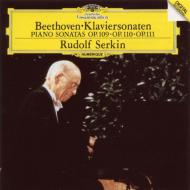
ベートーベン ピアノ・ソナタ第31番/貴船川 渓流
「今日のクラシック音楽」 ベートーベン作曲 ピアノソナタ 第31番ルードビッヒ・ヴァン・ベートーベン(1770-1827)は耳の障害に悩まされながらも100数十曲の音楽を書き残していますが、耳だけではなくてリュウマチや内臓疾患に悩まされ続けた作曲家だと言われています。50歳を過ぎた頃には病気も慢性化して彼の体を蝕んでおり、しかも確実に進行していたそうです。 そんな状態の51歳の頃(1821年)には「荘厳ミサ曲」の作曲をしながら、2曲のピアノ・ソナタを書いています。第31番と32番のソナタがそれです。 ベートーベンは32曲のピアノソナタを書き残していますから、この32番が彼のソナタとしての絶筆となった曲です。しかもこれら2曲が上述のように、病気との闘いの中で書かれています。特に31番は闘病の苦しい中で書かれている曲だけに、音楽には悲哀とか悲壮感のような情緒が散りばめられており、聴く者を感動へ誘う音楽です。ある意味、病を得た人であればより鮮明にわかる情緒の音楽だと思います。ピアノから紡ぎ出される第1楽章の叙情溢れる楽想は、聴く者の胸をしめつけてくるようです。しかし、何と言っても見事な音楽を表出している終楽章は深い感動を与えてくれます。 ベートーベン自筆の言葉で書かれた「嘆きの歌」が、泣き叫ぶかのように悲痛に訴えてきます。その後に「フーガ」の楽想となってもう一度「嘆きの歌」が戻り、最後にまた「フーガ」によって曲が結ばれています。ベートーベンの音楽の根底を成している「人生観」「人生哲学」- 不幸な苦しい境遇であっても耐え忍ぶことが優れた人間であり、成長する - が感じられる楽章で、聴いていて最後には大きな勇気が与えられるように感じる曲です。私事になりますが、2度の脳梗塞を患い、言語障害と闘って治さねばならない立場になってこの曲を改めて聴きました時に、私はベートーベンがこの曲に込めた・秘めたメッセージを初めて理解できたように思ったものです。「諦めるな!」。 ベートーベンが人間の可能性を信じて、勇気を自らに与えようとして書いたこの音楽が、人類への発信でもあったのかとリハビリを続ける私を励ましてくれた一曲でした。涼しい風が吹き渡る秋の夜に、もう一度ベートーベンに感謝しながら今夜はこの曲を聴こうと思います。愛聴盤 ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG2043 1987年録音) 後期の3大ソナタ第30番、31番、32番を収録しており、当時ゼルキンはすでに80歳を超えていたのですが、純粋で高雅で緊張感をも漂わせる演奏が、より一層私を勇気付けてくれました。上記商品番号で再発売されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1913年 初演 ディーリアス 2つの管弦楽小品(春カッコーを聞いて、河上の夏の夜)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「貴船川・渓流」撮影地 京都・貴船 2008年9月25日
2008年10月02日
コメント(2)
-
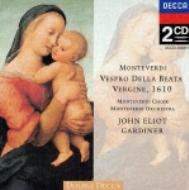
聖母マリアの夕べの祈り」/彼岸花(白)
「今日のクラシック音楽」 モンテヴェルディ作曲 「聖母マリアの夕べの祈り」まづ題名からして美しい! 私はキリスト教徒でなくて仏教徒ですが、そういうことに関係なくこの題名の美しさにまづ魅かれます。 この曲を知ったのは一冊の本からでした。 「神の歌、人の歌」(帰徳書房刊)で、書いた人が音楽評論家の菅野浩和氏。 大阪市内の図書館で偶然見つけて館内で読んだ本ですが、その一節にこういう文章がありました。これほどまでに一つの作品に心を傾けることが出来るのだろうか? 私はそのページを館内でコピーしていました。ーこんなに深い味をもった、滋味尽きない音楽を私はそれまで知らなかった。ずいぶん色々な音楽を聴いたつもりだったが、これほど感動的な名曲があるのかと、私はこの日からこの曲に夢中になった。それ以来、しばらくの間は、寝ても覚めてもこの曲のどこかの部分が耳に鳴り、この曲以外のどんな音楽も虚ろにしか響かない日々が来る日も来る日も続いた。まさに中毒症状である。(中略) 全部の曲を通すと3時間近くもかかるこの大曲の、終末に置かれている2曲の「マニフィカート」の壮麗さ、深遠さはどうだろう。 「マニフィカート」は古典派時代に至るまで、何人もの作曲家によっていくつもの名曲が書かれてきた。 しかし、この2曲の「マニフィカート」の前には、他の総てが色褪せてしまう。(後略)この文章を読んで私はショックでした。あの有名な評論家がここまで書ける、この曲とは一体どんな音楽なんだろうと思い、帰宅途中でCDショップに立ち寄りこの曲のCDを探して買い求めました。凄い! 美しい! 壮麗だ! 全曲を聴き通して感じたのがこの3つの感想でした。さすがに菅野氏ほどの入れ込みはありませんが、純粋無垢、天使が歌うような美しい旋律、そして悲しみ、慈悲と思いやり、キリストを信じていない私でさえ、この音楽の美しさに暫しの間、心を体を包み込まれるような幸福感で満たされていました。管弦楽楽団、8人の独唱者、合唱団、少年聖歌隊、ブラスアンサンブル、リコーダーアンサンブル、通奏低音からなる、カソリック宗教音楽の頂点に立つような音楽。菅野氏が書いているように終末の2つの「マニフィカート」だけでも聴かれるとわかります。私のリスニング・ルームがまるでカソリックの教会に変わったかのように、純粋無垢の音楽が私を浄福感にすっぽりと包んでくれるのです。「マニフィカート」とは「崇める」ことで聖母賛という意味だそうです。この世にこんな美しい音楽があるのか、と思えるほどの心の幸せを与えてくれている音楽です。菅野氏の著作に巡り合わなければ、あの日あの時、図書館に足を運ばなければ、私はこの「聖母マリアの夕べの祈り」に巡り合うことが出来なかったかも知れません。 亀井勝一郎氏の随筆にあった「人生は邂逅の機会である」という言葉の重さを改めて知った作品です。愛聴盤 エリオット・ガーディナー指揮 モンテヴェルディ管弦楽団(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD3384 74年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1865年 誕生 ポール・デュカス(作曲家)1904年 誕生 ウラジミール・ホロヴィッツ(ピアニスト)1930年 没 リッカルド・ドリゴ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 彼岸花(白)撮影地 大阪市立長居植物園 2008年9月23日
2008年10月01日
コメント(6)
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-
-
-

- 好きなクラシック
- ベートーヴェン交響曲第6番「田園」。
- (2025-11-19 17:55:25)
-
-
-

- きょう買ったCDやLPなど
- The Beatles(ビートルズ) 『アン…
- (2025-11-20 11:02:10)
-







